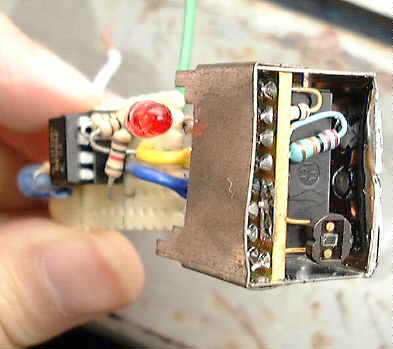 �ǂ����A�ŋ߂͕����ł��郊���R��������j�b�g�������悤�ł��̂ŁA
���R�g���l���܂��B
�ǂ����A�ŋ߂͕����ł��郊���R��������j�b�g�������悤�ł��̂ŁA
���R�g���l���܂��B
 �̐S�̔{���ł����A
AGC�F�I�[�g�Q�C���R���g���[����H�ɂȂ��Ă郂�m������܂����A
�������̎�����W���[���̋K�i�\�������Ƃ���50�`80dB�Ƃ������ƂŁA�������ɐv���Ă���܂��B
�Q�C�����K�v�ł����A
�ʐς̍L��PIN�t�H�gDi�ɋt�o�C�A�X�d���������Ďg�p���邱�Ƃł��҂����Ƃ��o���܂��B
�t�H�g�_�C�I�[�h�ɋt�o�C�A�X����������
PN�ڍ��ʂɎ��R�d�q�̖���������R�w���L����܂��B
���傤�ǁA�R���f���T�[�̋ɔԋ������L����̂Ɠ����ł��̂ŁA
�ڍ��ʂ̗e�ʂ�����A����������������I�ɏオ��܂��B
�܂��A�M�U������d�q�����Ȃ��Ȃ�̂Ńm�C�Y���}�����邩�Ǝv���܂��B
��H�́A����(�S�����z)�ň�_�A�[�X�̃V�[���h����K�v������܂��B
�o����Ό��w�t�B���^�����邩�A
�ԊO�p�̃t�H�gDi�Ɣ��������ł���悤�Ƀ\�P�b�g�ɂ��Ă����ƕ֗��ł��B
�����́A50�{�ɏグ�Ă���A���[�m�C�Y��BPF��ʂ��A1500�{��
�ŏ���Pre-AMP�����́A���܂�グ������ƁA�ʂ̍����g���ɂĐM�����O�a���Ă��܂��܂��B
���g�pDi�́A1N60�Ƃ����Q���}�j�E���_�C�I�[�h(�M�Ɏア�̂ň����ɒ���)���A
���d���p(PN�ڍ��ʂ̗e�ʂ��Ⴂ)�ŏ������d���̒Ⴂ�V���b�g�L�o���ADi���ǂ����ȂƎv���܂��B
1SS99�ƌ����̂��A���̂ł��ꂪ�x�X�g�ł����A�p�łł��āA�ǂ��ɂ����B���邩�A���̑�֕i���L���ł��B
���F������H�̐ݒ肪�ɂ��悤�Ȃ̂ŁA
C3�F56�`100pF
C4�AC8�F1500�`3000pF
�ɂ���Ɨǂ��ł��B
BPF��Q�l���A�����Ƌ��߂ėǂ��Ǝv���܂��B
U4�̃Q�C�����傫�߂ł��̂ŁA
�̐S�̔{���ł����A
AGC�F�I�[�g�Q�C���R���g���[����H�ɂȂ��Ă郂�m������܂����A
�������̎�����W���[���̋K�i�\�������Ƃ���50�`80dB�Ƃ������ƂŁA�������ɐv���Ă���܂��B
�Q�C�����K�v�ł����A
�ʐς̍L��PIN�t�H�gDi�ɋt�o�C�A�X�d���������Ďg�p���邱�Ƃł��҂����Ƃ��o���܂��B
�t�H�g�_�C�I�[�h�ɋt�o�C�A�X����������
PN�ڍ��ʂɎ��R�d�q�̖���������R�w���L����܂��B
���傤�ǁA�R���f���T�[�̋ɔԋ������L����̂Ɠ����ł��̂ŁA
�ڍ��ʂ̗e�ʂ�����A����������������I�ɏオ��܂��B
�܂��A�M�U������d�q�����Ȃ��Ȃ�̂Ńm�C�Y���}�����邩�Ǝv���܂��B
��H�́A����(�S�����z)�ň�_�A�[�X�̃V�[���h����K�v������܂��B
�o����Ό��w�t�B���^�����邩�A
�ԊO�p�̃t�H�gDi�Ɣ��������ł���悤�Ƀ\�P�b�g�ɂ��Ă����ƕ֗��ł��B
�����́A50�{�ɏグ�Ă���A���[�m�C�Y��BPF��ʂ��A1500�{��
�ŏ���Pre-AMP�����́A���܂�グ������ƁA�ʂ̍����g���ɂĐM�����O�a���Ă��܂��܂��B
���g�pDi�́A1N60�Ƃ����Q���}�j�E���_�C�I�[�h(�M�Ɏア�̂ň����ɒ���)���A
���d���p(PN�ڍ��ʂ̗e�ʂ��Ⴂ)�ŏ������d���̒Ⴂ�V���b�g�L�o���ADi���ǂ����ȂƎv���܂��B
1SS99�ƌ����̂��A���̂ł��ꂪ�x�X�g�ł����A�p�łł��āA�ǂ��ɂ����B���邩�A���̑�֕i���L���ł��B
���F������H�̐ݒ肪�ɂ��悤�Ȃ̂ŁA
C3�F56�`100pF
C4�AC8�F1500�`3000pF
�ɂ���Ɨǂ��ł��B
BPF��Q�l���A�����Ƌ��߂ėǂ��Ǝv���܂��B
U4�̃Q�C�����傫�߂ł��̂ŁA
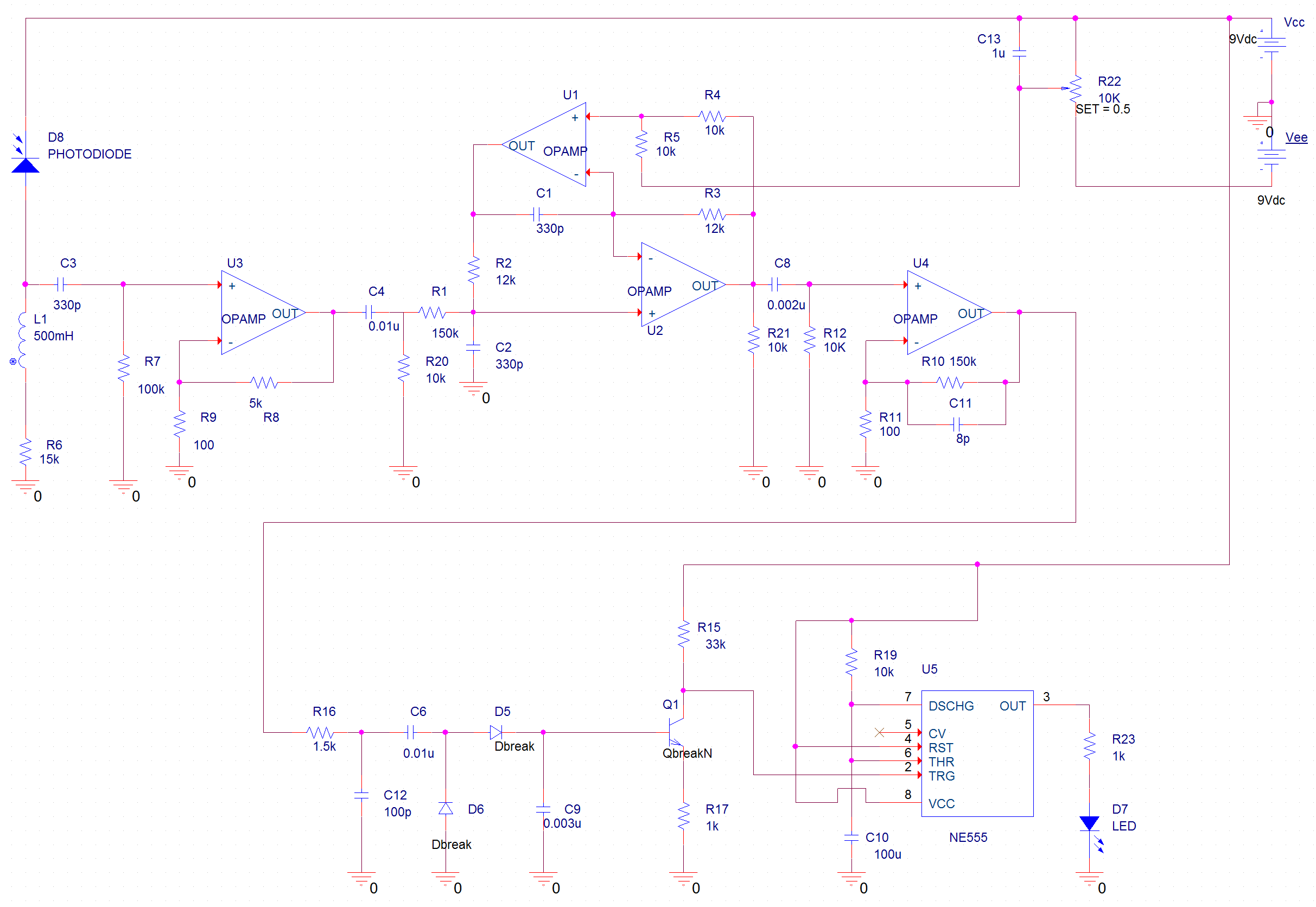
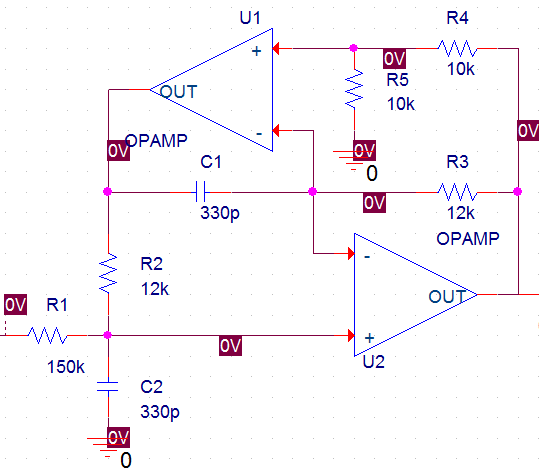
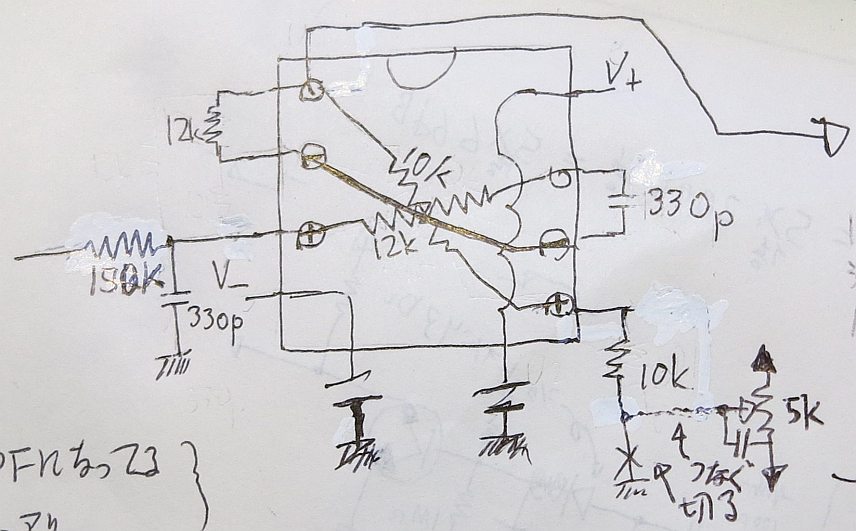
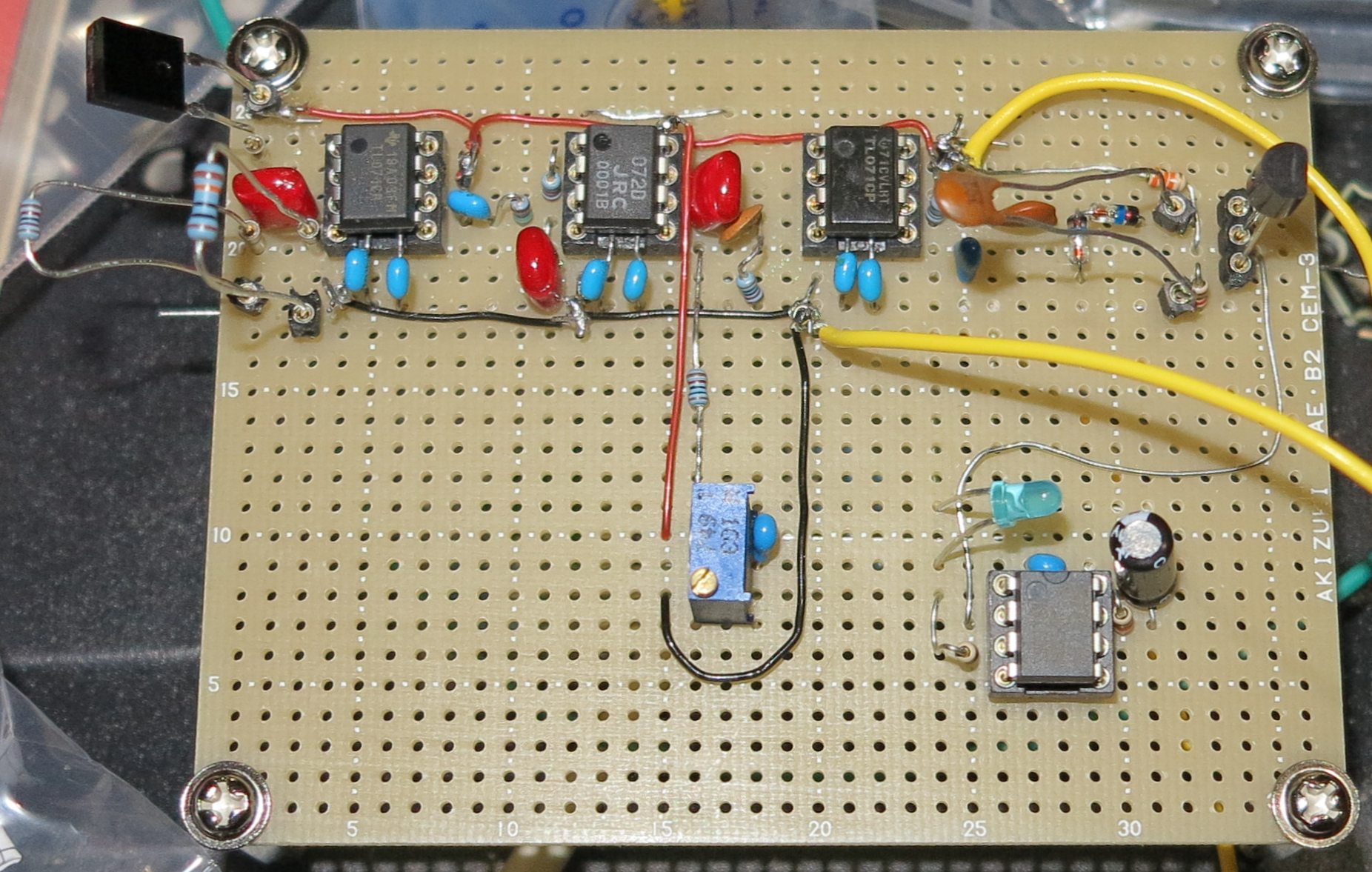
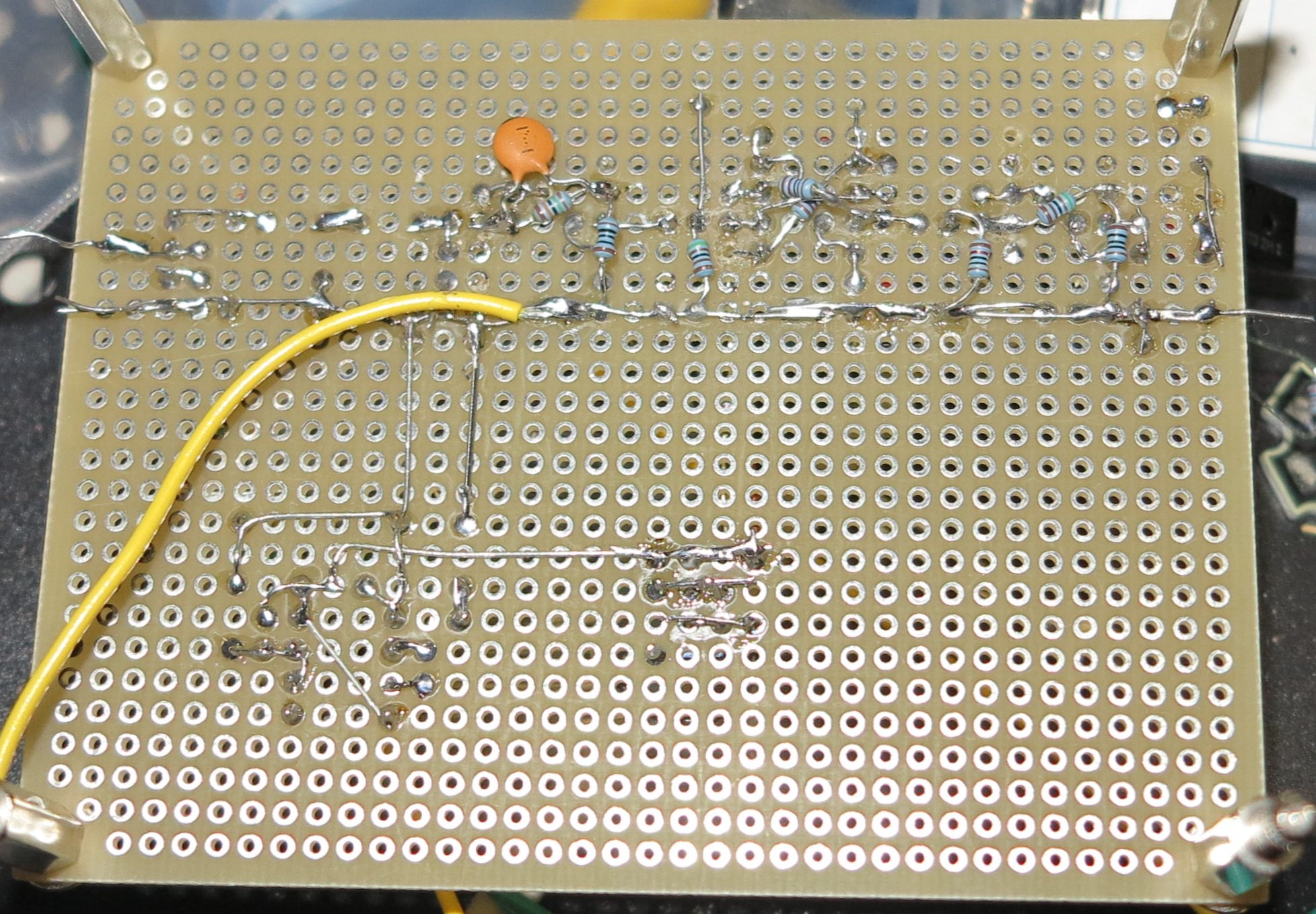
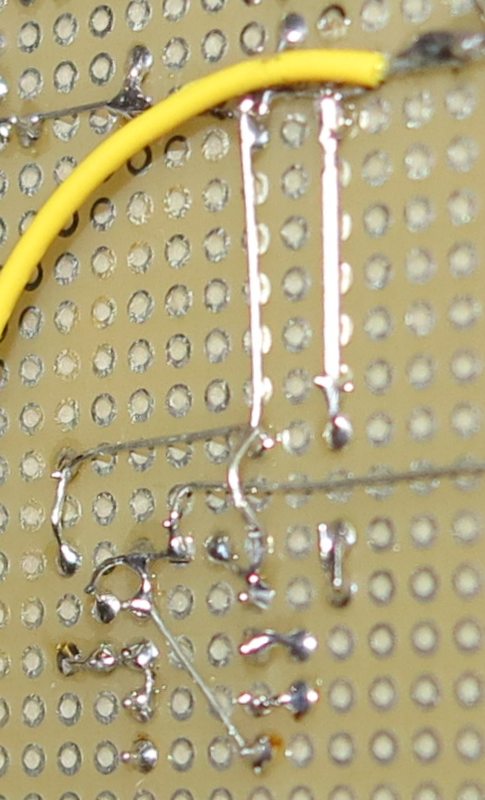
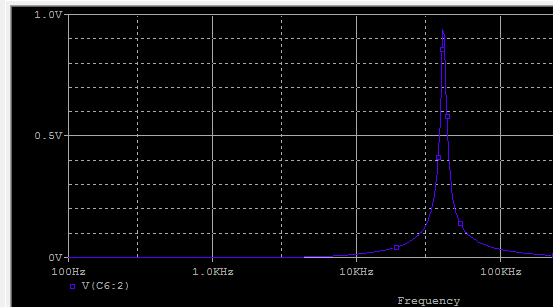 �~�������Y�Ő����ʂ̎��E�⊴�x���グ����A
����ʂւ̒��˓����悯
���w�t�B���^�[
����ʐ�
�����P�[�X�ł̃V�[���h�{��_�A�[�X
�t�H�gDi �FTPS703(�ԊO�̏ꍇ(��))�A
S6775(�����̏ꍇ(�H))���ԃt�B���^�[���炢�͕K�v
�o�C�A�X��R�͎���ʐςɂ���čœK������Ă܂��B
500mH�̓I�v�V�������V�[���h�d�v�@�@(��)
��R�͋����疌�B(��)
BPF�Ɏg��330pF�̃R���f���T�[�̓|���G�`�������|���v���s����(��)
���̃R���f���T�̓Z���~�b�N���邢�͐ϑw�Z���~�b�N(�H)(��)
OP-AMP�FTL071��TL072(NJM072)��TL071(��)(�H)
�g�����W�X�^�F2SC1815(��)
Di�F1N60(�M�ɒ���)��1SS99�݊��i�B(�H)
�Q�C����R11�ł������\�B
��쓮����ꍇ��R11��傫���AC9��傫��(��{���炢�����E)
NE555�̏o�͂́ATr�ő������\�B
��F��Γd���F
�H�F�H���d�q�F
���F�����G���V���b�v�F
�����[���������ꍇ�Ƃ��Ńg�����W�X�^���g�������ꍇ��2SA1815���荠�ŁA���^�Ŕ�r�I��d���ň����ƂȂ��BC337(�H��)�Ȃ��ǂ����Ǝv���܂��B
���[�^�[�Ȃǂ��_�C���N�g�ɓ����������ꍇ�APNP�œd�����傫�����̂��A�p���[FET�Ȃǂ��ǂ��ł����A�m�C�Y���߂��Ă��Ȃ��悤�ɁB
�l�Ԃ́A700nm�����͋ɓx�Ɍ����Ȃ��Ȃ�܂��B
���A�����Ə����������肵�܂��B
���O�ŁA
850nm�p���[LED�Ƃ�
650�Ƃ��ߐԊO��780nm���[�U�[�Ȃǂ��g���ȊO�́A
�ԊO��������W���[���{940nm(�����Ȃ�)���炢�̍��o�͂ȐԊO�p���[LED���ȒP�ł͂���܂��B
���̂Ƃ��A���w�t�B���^�[��A�ő�Q�C���ȂǓ����͌��\�Ⴂ�܂��̂ŁA
���w�t�B���^�͋����A940nm�t�߂������߂��Ȃ��̂�����܂��B
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
�NjL(����)��
�Ƃ肠�����A���~�P�[�X�ɂ������V�[���h�ƈ�_�A�[�X��������A
�������m�C�Y������܂����B
C9��0.001��F�܂ʼn�������A���x������Ȃ�ɏオ��܂����B
�܂��]�T������܂��̂ŁA
�I�v�V�����Ŗ]�ݔ�������500mH�̃`���[�N�R�C�������܂��Ă݂���A
���Ȃ芴�x���オ��܂����B
����āA�����R�����W���[�������Ȃ���銴�x�ɂȂ�܂����B
500mH���A�����Ƒ傫�ȃ`���[�N�R�C������������ƃC�P�����ł��ˁB
�~�������Y�Ő����ʂ̎��E�⊴�x���グ����A
����ʂւ̒��˓����悯
���w�t�B���^�[
����ʐ�
�����P�[�X�ł̃V�[���h�{��_�A�[�X
�t�H�gDi �FTPS703(�ԊO�̏ꍇ(��))�A
S6775(�����̏ꍇ(�H))���ԃt�B���^�[���炢�͕K�v
�o�C�A�X��R�͎���ʐςɂ���čœK������Ă܂��B
500mH�̓I�v�V�������V�[���h�d�v�@�@(��)
��R�͋����疌�B(��)
BPF�Ɏg��330pF�̃R���f���T�[�̓|���G�`�������|���v���s����(��)
���̃R���f���T�̓Z���~�b�N���邢�͐ϑw�Z���~�b�N(�H)(��)
OP-AMP�FTL071��TL072(NJM072)��TL071(��)(�H)
�g�����W�X�^�F2SC1815(��)
Di�F1N60(�M�ɒ���)��1SS99�݊��i�B(�H)
�Q�C����R11�ł������\�B
��쓮����ꍇ��R11��傫���AC9��傫��(��{���炢�����E)
NE555�̏o�͂́ATr�ő������\�B
��F��Γd���F
�H�F�H���d�q�F
���F�����G���V���b�v�F
�����[���������ꍇ�Ƃ��Ńg�����W�X�^���g�������ꍇ��2SA1815���荠�ŁA���^�Ŕ�r�I��d���ň����ƂȂ��BC337(�H��)�Ȃ��ǂ����Ǝv���܂��B
���[�^�[�Ȃǂ��_�C���N�g�ɓ����������ꍇ�APNP�œd�����傫�����̂��A�p���[FET�Ȃǂ��ǂ��ł����A�m�C�Y���߂��Ă��Ȃ��悤�ɁB
�l�Ԃ́A700nm�����͋ɓx�Ɍ����Ȃ��Ȃ�܂��B
���A�����Ə����������肵�܂��B
���O�ŁA
850nm�p���[LED�Ƃ�
650�Ƃ��ߐԊO��780nm���[�U�[�Ȃǂ��g���ȊO�́A
�ԊO��������W���[���{940nm(�����Ȃ�)���炢�̍��o�͂ȐԊO�p���[LED���ȒP�ł͂���܂��B
���̂Ƃ��A���w�t�B���^�[��A�ő�Q�C���ȂǓ����͌��\�Ⴂ�܂��̂ŁA
���w�t�B���^�͋����A940nm�t�߂������߂��Ȃ��̂�����܂��B
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
�NjL(����)��
�Ƃ肠�����A���~�P�[�X�ɂ������V�[���h�ƈ�_�A�[�X��������A
�������m�C�Y������܂����B
C9��0.001��F�܂ʼn�������A���x������Ȃ�ɏオ��܂����B
�܂��]�T������܂��̂ŁA
�I�v�V�����Ŗ]�ݔ�������500mH�̃`���[�N�R�C�������܂��Ă݂���A
���Ȃ芴�x���オ��܂����B
����āA�����R�����W���[�������Ȃ���銴�x�ɂȂ�܂����B
500mH���A�����Ƒ傫�ȃ`���[�N�R�C������������ƃC�P�����ł��ˁB
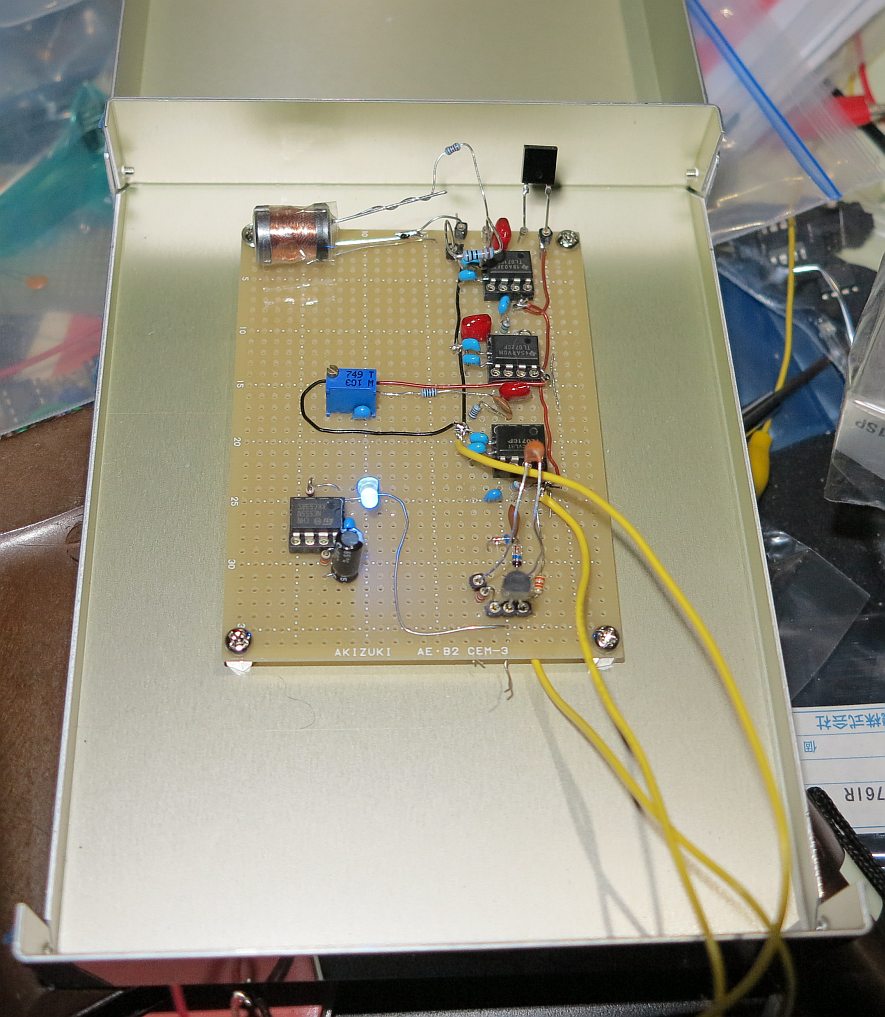 ����p��LED�ł����A
�������Ƃ���ɔ������Ă��܂������m��܂���B
����āA��OR�̐ԃt�B���^�[�Ȃ̂ł����A
����ɃR���f���T�[���q�����Ƃ�ON-OFF���ɂ₩�ɂ��Ă��܂��Ηǂ��ł��B
20mA�̏ꍇ�A���[�h��R300����22��F�ł��Ȃ藎���܂����B
�܂��A���g��̐ϕ����ăR���p���[�^�[�I�Q�[�g��ʂ��Đϕ����Ă��̐ϕ����ɂ₩�ɂ��Ă܂��R���p���[�Ƃ��邱�Ƃɂ��A
�����Ԃ��600��Sec���Z�����Ԃ̓��̓p���X���Ȃ�ׂ��Ȃ��悤�ɂ���Ƃ����\�ł��ˁB
�܂��A������́A�f�W�^���Ȃ�}�C�R���ɓ���Ă��܂��č폜���Ă��ǂ����Ǝv���܂��B
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
���U��H�̐v�}�ł��B�����̔z���}�I
���ۂ́A�d���A�g�����W�X�^��LED�����ɕ����܂����B
����p��LED�ł����A
�������Ƃ���ɔ������Ă��܂������m��܂���B
����āA��OR�̐ԃt�B���^�[�Ȃ̂ł����A
����ɃR���f���T�[���q�����Ƃ�ON-OFF���ɂ₩�ɂ��Ă��܂��Ηǂ��ł��B
20mA�̏ꍇ�A���[�h��R300����22��F�ł��Ȃ藎���܂����B
�܂��A���g��̐ϕ����ăR���p���[�^�[�I�Q�[�g��ʂ��Đϕ����Ă��̐ϕ����ɂ₩�ɂ��Ă܂��R���p���[�Ƃ��邱�Ƃɂ��A
�����Ԃ��600��Sec���Z�����Ԃ̓��̓p���X���Ȃ�ׂ��Ȃ��悤�ɂ���Ƃ����\�ł��ˁB
�܂��A������́A�f�W�^���Ȃ�}�C�R���ɓ���Ă��܂��č폜���Ă��ǂ����Ǝv���܂��B
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
���U��H�̐v�}�ł��B�����̔z���}�I
���ۂ́A�d���A�g�����W�X�^��LED�����ɕ����܂����B
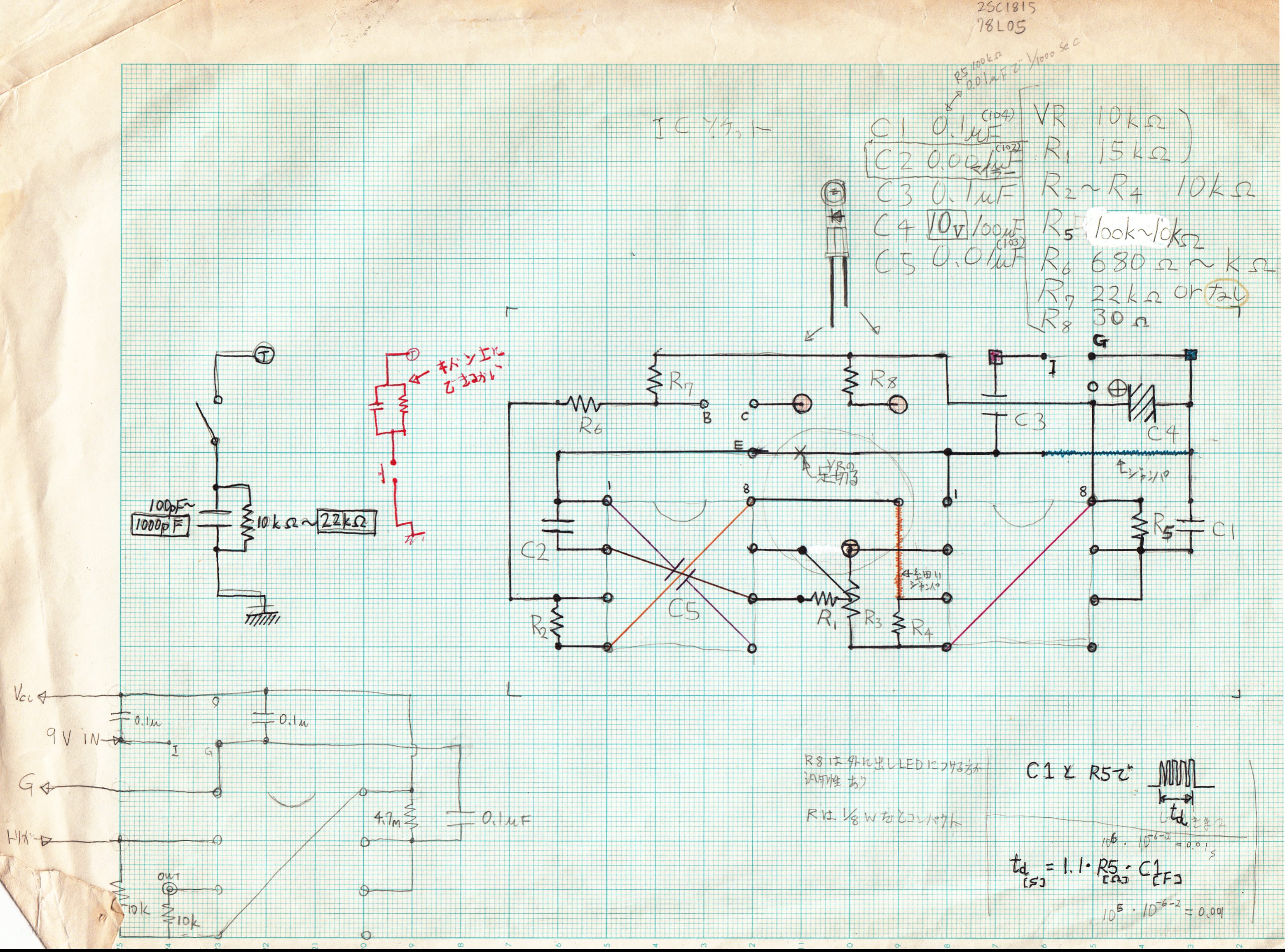 (���̕��ɁAVR��������P������H������܂��̂ŁB��������Q�ƁB)
�����ɌÂ���������ł܂����A���i�͌��݂����Ȃ����낢�܂��B
IC��NE555���g���Ă���܂��B
�g���K�[��100pF��22K���I���ł��B���g���K�𗣂����Ƃ��ɂ���������̂�0.1��F��330K���ɂ�����Ȃ���܂����B
VR�̈�̑��͐��Ė��ڑ�(NC)��Ԃɂ��Ă���܂��B
(���̕��ɁAVR��������P������H������܂��̂ŁB��������Q�ƁB)
�����ɌÂ���������ł܂����A���i�͌��݂����Ȃ����낢�܂��B
IC��NE555���g���Ă���܂��B
�g���K�[��100pF��22K���I���ł��B���g���K�𗣂����Ƃ��ɂ���������̂�0.1��F��330K���ɂ�����Ȃ���܂����B
VR�̈�̑��͐��Ė��ڑ�(NC)��Ԃɂ��Ă���܂��B
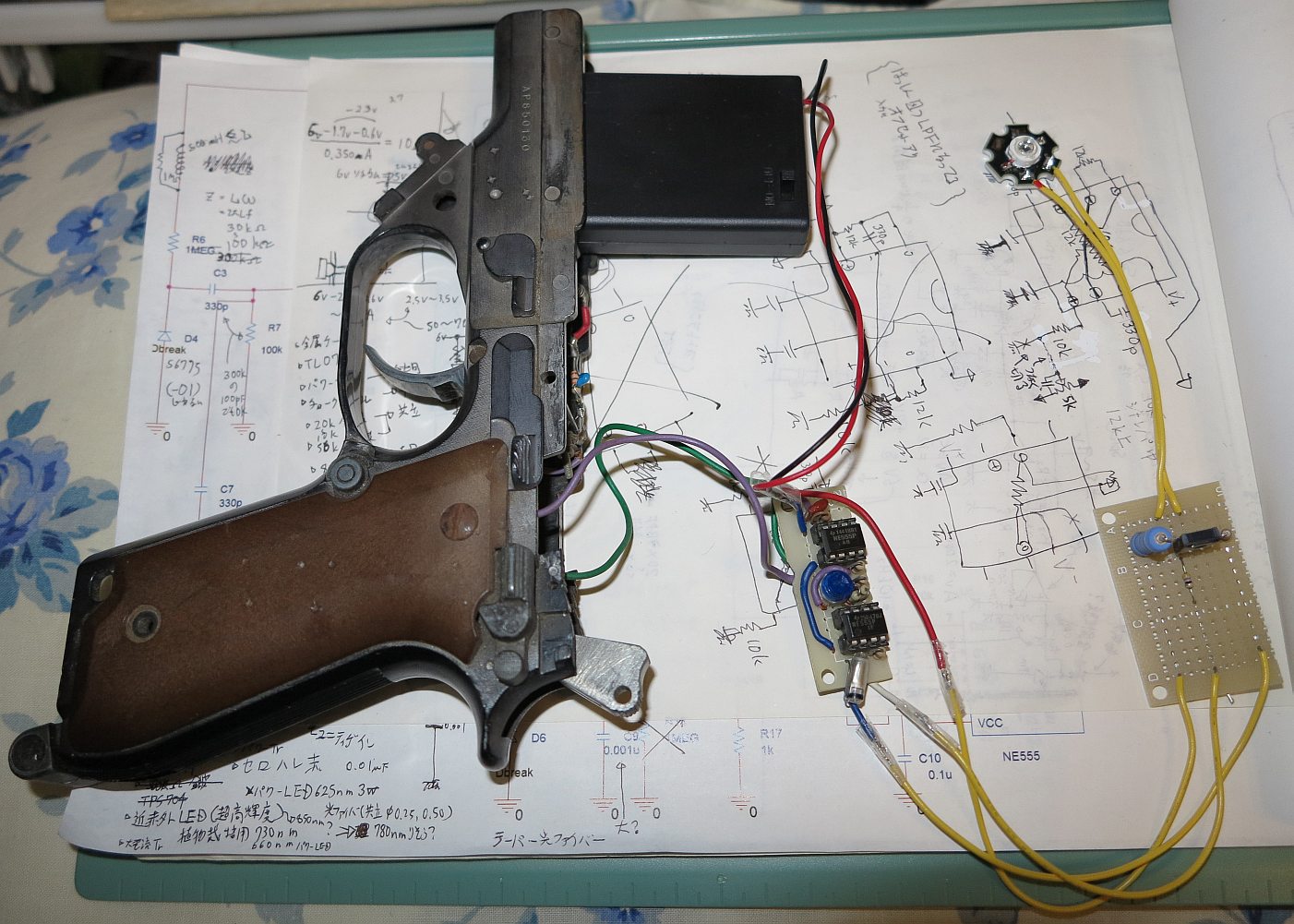 LED�́A940nm�ԊO�̃t���b�g�w�b�h��LED�������̂ł����A
���ݏH���̃`�b�v���i���炢�������݂��Ă��Ȃ����߁B
LED�́A940nm�ԊO�̃t���b�g�w�b�h��LED�������̂ł����A
���ݏH���̃`�b�v���i���炢�������݂��Ă��Ȃ����߁B
 850nm�̐ԊO�������p�̃p���[LED�g�p�ł��B
���̂܂܂ł��˒������\���[�g���ɂ͂Ȃ�Ǝv���܂��B
850nm�̐ԊO�������p�̃p���[LED�g�p�ł��B
���̂܂܂ł��˒������\���[�g���ɂ͂Ȃ�Ǝv���܂��B
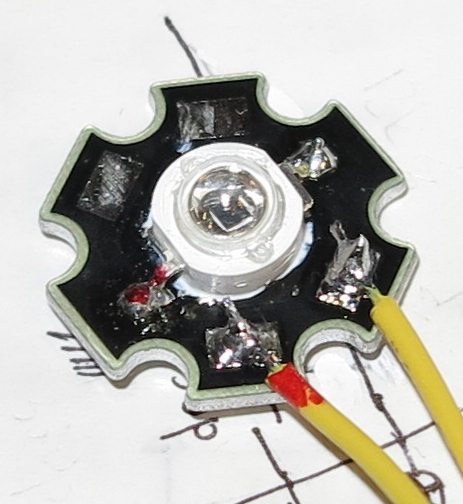 �����Y��t�����LED���͂��߂̃s���z�[�������ł��A���B������100m������̂ł͖������Ǝv���A
�n���h�K���Ȃ炱��Ȋ����̂������葁���Ǝv���܂��B
�O�[�q���M�����^�[���g���Ă��̂ł����A�u�ԓI�ɃI�[�o�[�V���[�g�̉\�������邽�߁A
LD���g�p�����Ƃ��j�����邱�Ƃ�����悤�Ȃ̂ŁA6V�̓d�r�̕������S���Ǝv���܂����B
�u�Ԃ�������Ȃ��ł��̂�LED�̕��M�͗v��Ȃ��̂ł����A
�����̒������Ƃ��A�O�̂��߁A�����ȉ~�������ɕt����X�}�[�g�ŕ��M�͖��Ȃ��ł��傤�B
���ƁA
�����H�́A���Ȃ荂���x�ɂ��Ă邽�߁A
�t�߂œd���h���������ƃu���V�����̃X�p�[�N�̃m�C�Y�Ŕ������܂����B
���ɁA
�ԓ��̐�LED���_������Ƃ��̌��Ȃǂ́A���Ԃɂ���Ă̔��W���������������Ă��܂��\��������܂��B
����́A�����R�����W���[���ł����邱�Ƃ��Ǝv���܂����A
�A�`���́A���p���X���ŃR�[�h�������쓮�������������Ǝv���܂��B
���̏ꍇ�A�����Ɣ��U�𑬂��A�p���X���Ԃ�Z������̂��e���Ǝv���܂����A
����ł��̂ł���ŗǂ��̂ł͂Ǝv���Ă���܂��B
���̃����R���݊��^���U���j�b�g�ł����A
NE555�������d�͂̏��Ȃ�LMC555�ɕύX���܂����B
�����炭�A�Ⴂ����d���ł������A�o�͓d���ʂ������悤�ł��B
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
����LD��p����������H���l���܂��B
�����̃��[�U�[Di�́A���Ƀf���P�[�g�ŁA
�Ód�C�ƌ��o�͂̒�i���b�e�[�W�I�[�o�[�A�ɂ���ĉ��邱�Ƃ������ł��B
�܂��A�t�ڑ��ɂ����Ɏア�ł��B��2V���x�B
�l�Ԃ͋���ȓ��̂ł�����P�ɂ̃R���f���T�[�Ƃ��ēd�ׂ�~�ς��邱�Ƃ��o���܂��B
�n�ʂɂ������Ă郂�m�͂ق�0V�ŁA�����Ɠ��d�ʂɂ��邱�ƂŔ������܂��B
��i�́A�M���ł͂Ȃ����̃G�l���M���ꎩ�̂��f�q�Ƀ_���[�W��^���܂��̂ŁA��u�ł������Ă͂Ȃ�܂���B
(�_���[�W�̏u�Ԃɉ���̂ł͖����������������ꂽ�Ƃ�������������܂��B�����Z�����I)
���[�U�[�ƌ�����Ƌ��������o���Ƃ����C���[�W�ł����A
����̓����Y�ň�_�Ɏ��������ꍇ�ł��āA
LD�̌��̑������ʂ�LED��肩�Ȃ�ア�ł��B
����āA�����Y�Ŏ���������̂������ƂȂ�܂��B
�Ƃ͂����A���ꂪ���Ɏ�Ԃ̂����邱�ƂŁA
�������ԊO�ł͌������킹�����Ȃ荢��ł��B
�������A���܂����������ƁA���e�̔��肪�V�r�A�����邱�ƂɂȂ�܂��B
����āA�g�p���@�̓��C�t���Ȃǂ̐����ˌ��Ɍ����邩���m��܂���B
�{���̋쓮��APC��H�����z�Ȃ̂ł����A����͂܂��A��ɂ��āA
���̂������ȈՔł�ACC��H�ɂ��܂��B
�ȑO��006P����O�[�q���M�����^�[��ʂ��Ďg���Ă��̂ł����A
�d���������Ȃǂ̃I�[�o�[�V���[�g�������A���J���̒P�l�l�{�̋쓮�ɂ��܂��B
(�v�Z�l���ς��܂���006P�_�C���N�g�ł��ǂ������m��܂���B�����[�����ǂ��ł���)
�����Y��t�����LED���͂��߂̃s���z�[�������ł��A���B������100m������̂ł͖������Ǝv���A
�n���h�K���Ȃ炱��Ȋ����̂������葁���Ǝv���܂��B
�O�[�q���M�����^�[���g���Ă��̂ł����A�u�ԓI�ɃI�[�o�[�V���[�g�̉\�������邽�߁A
LD���g�p�����Ƃ��j�����邱�Ƃ�����悤�Ȃ̂ŁA6V�̓d�r�̕������S���Ǝv���܂����B
�u�Ԃ�������Ȃ��ł��̂�LED�̕��M�͗v��Ȃ��̂ł����A
�����̒������Ƃ��A�O�̂��߁A�����ȉ~�������ɕt����X�}�[�g�ŕ��M�͖��Ȃ��ł��傤�B
���ƁA
�����H�́A���Ȃ荂���x�ɂ��Ă邽�߁A
�t�߂œd���h���������ƃu���V�����̃X�p�[�N�̃m�C�Y�Ŕ������܂����B
���ɁA
�ԓ��̐�LED���_������Ƃ��̌��Ȃǂ́A���Ԃɂ���Ă̔��W���������������Ă��܂��\��������܂��B
����́A�����R�����W���[���ł����邱�Ƃ��Ǝv���܂����A
�A�`���́A���p���X���ŃR�[�h�������쓮�������������Ǝv���܂��B
���̏ꍇ�A�����Ɣ��U�𑬂��A�p���X���Ԃ�Z������̂��e���Ǝv���܂����A
����ł��̂ł���ŗǂ��̂ł͂Ǝv���Ă���܂��B
���̃����R���݊��^���U���j�b�g�ł����A
NE555�������d�͂̏��Ȃ�LMC555�ɕύX���܂����B
�����炭�A�Ⴂ����d���ł������A�o�͓d���ʂ������悤�ł��B
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
����LD��p����������H���l���܂��B
�����̃��[�U�[Di�́A���Ƀf���P�[�g�ŁA
�Ód�C�ƌ��o�͂̒�i���b�e�[�W�I�[�o�[�A�ɂ���ĉ��邱�Ƃ������ł��B
�܂��A�t�ڑ��ɂ����Ɏア�ł��B��2V���x�B
�l�Ԃ͋���ȓ��̂ł�����P�ɂ̃R���f���T�[�Ƃ��ēd�ׂ�~�ς��邱�Ƃ��o���܂��B
�n�ʂɂ������Ă郂�m�͂ق�0V�ŁA�����Ɠ��d�ʂɂ��邱�ƂŔ������܂��B
��i�́A�M���ł͂Ȃ����̃G�l���M���ꎩ�̂��f�q�Ƀ_���[�W��^���܂��̂ŁA��u�ł������Ă͂Ȃ�܂���B
(�_���[�W�̏u�Ԃɉ���̂ł͖����������������ꂽ�Ƃ�������������܂��B�����Z�����I)
���[�U�[�ƌ�����Ƌ��������o���Ƃ����C���[�W�ł����A
����̓����Y�ň�_�Ɏ��������ꍇ�ł��āA
LD�̌��̑������ʂ�LED��肩�Ȃ�ア�ł��B
����āA�����Y�Ŏ���������̂������ƂȂ�܂��B
�Ƃ͂����A���ꂪ���Ɏ�Ԃ̂����邱�ƂŁA
�������ԊO�ł͌������킹�����Ȃ荢��ł��B
�������A���܂����������ƁA���e�̔��肪�V�r�A�����邱�ƂɂȂ�܂��B
����āA�g�p���@�̓��C�t���Ȃǂ̐����ˌ��Ɍ����邩���m��܂���B
�{���̋쓮��APC��H�����z�Ȃ̂ł����A����͂܂��A��ɂ��āA
���̂������ȈՔł�ACC��H�ɂ��܂��B
�ȑO��006P����O�[�q���M�����^�[��ʂ��Ďg���Ă��̂ł����A
�d���������Ȃǂ̃I�[�o�[�V���[�g�������A���J���̒P�l�l�{�̋쓮�ɂ��܂��B
(�v�Z�l���ς��܂���006P�_�C���N�g�ł��ǂ������m��܂���B�����[�����ǂ��ł���)
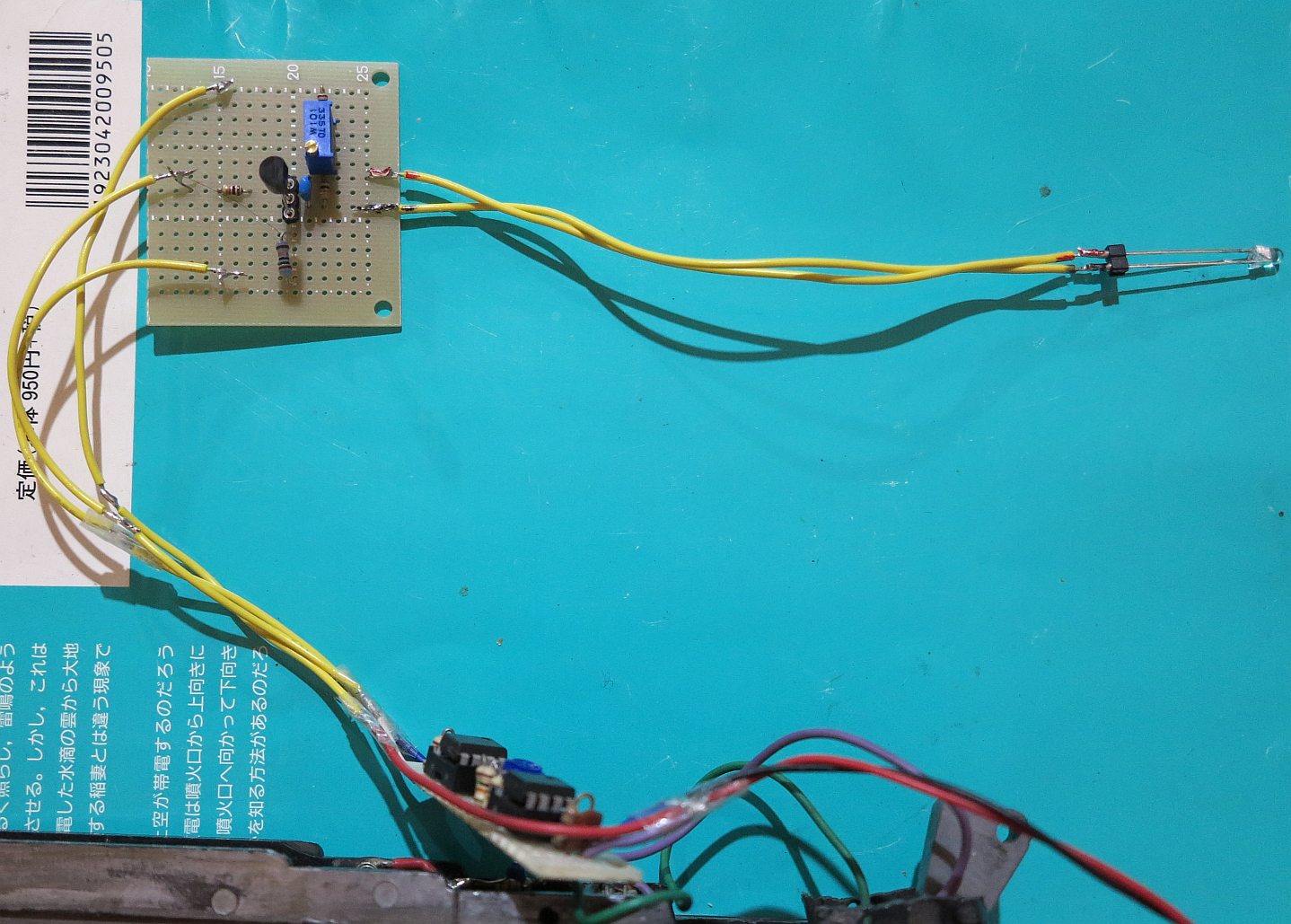 (�摜�ł�LED���͂܂��Ă܂����AIf��20mA�Ȃ̂ŁALD�ƌ��p�ł��B)
LD�͉��x�ȂǂɃV�r�A�Ȃ̂ł����A�K�i�\�͏��X�����������Ă��邾���ŁA
�����̃e�X�g�͂��ĂȂ��ł����A�Ƃ肠�����A
����ŁALD�����U���āA���������Ȃ��悤�Ȃ̂ŁA���p���Ǝv���܂��B
(�摜�ł�LED���͂܂��Ă܂����AIf��20mA�Ȃ̂ŁALD�ƌ��p�ł��B)
LD�͉��x�ȂǂɃV�r�A�Ȃ̂ł����A�K�i�\�͏��X�����������Ă��邾���ŁA
�����̃e�X�g�͂��ĂȂ��ł����A�Ƃ肠�����A
����ŁALD�����U���āA���������Ȃ��悤�Ȃ̂ŁA���p���Ǝv���܂��B
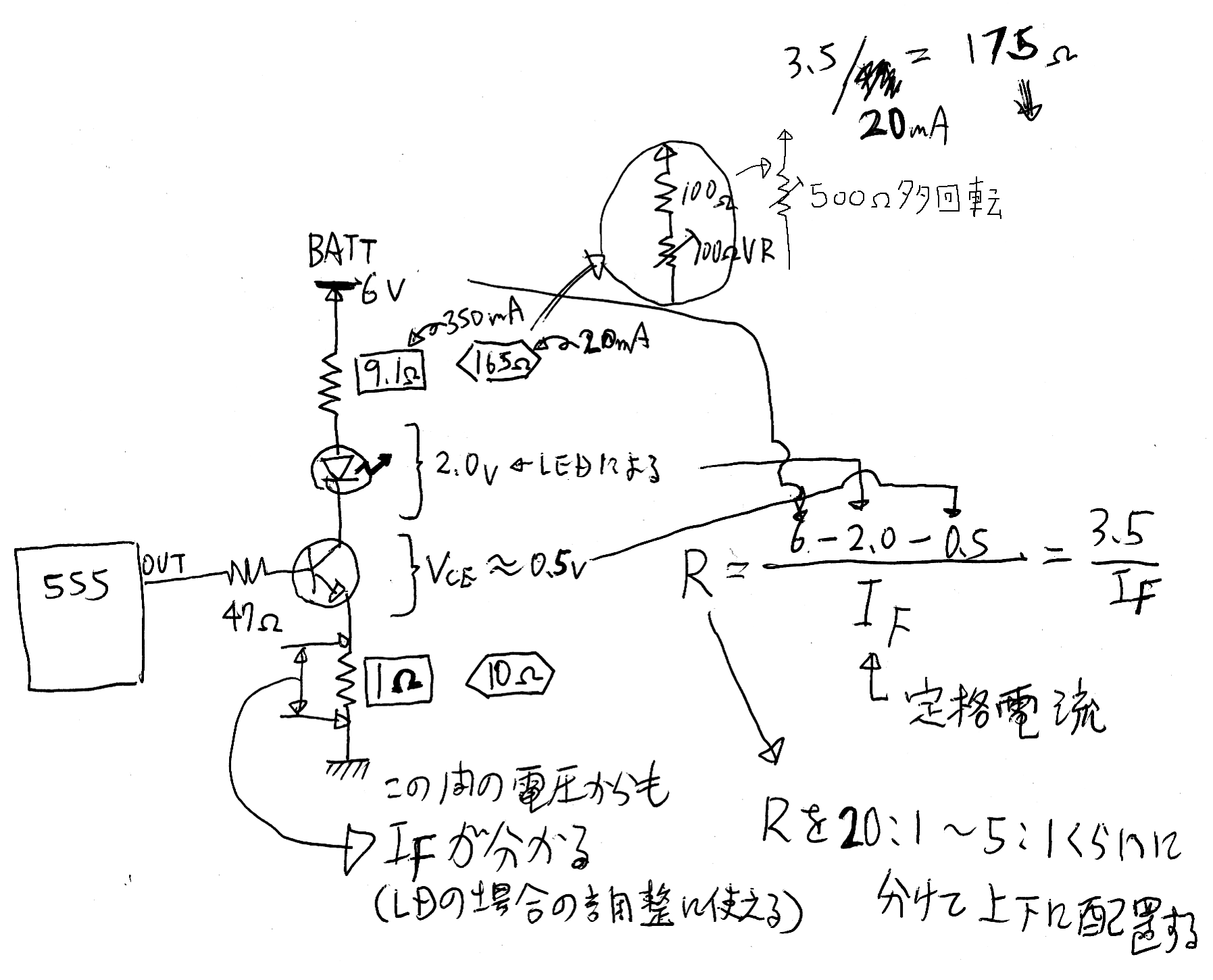 Vce��0.5V�ƍ��߂ɂƂ��Ă���܂������̏ꍇ�́A�����ƒႭ�A
0V�Ōv�Z���Ă�OK�̂悤�ł��B
�܂��A�K�i�ł̓��[�U�[���U��臒l�̓d���͍��߂ɏ����Ă���܂����A
���\�Ⴂ�l�ł����U���܂��B
�܂��A�t�d�����K�i�قnj������͖����ł����A�ɐ����ԈႦ��̂͋֕��ł��B
�G�~�b�^�ɕt������R�͓d������p�Ɠd�������p�Ƃ��l���Ă��̂ł����A
��(�R���N�^��)�ɕt���Ă��A�������v�ł��B
LD��
650nm5mW30�A�����A10�͏H���Ŕ̔�����Ă��郂�m�B
780nm10mW(RLD78NZM1)10�����܂����B
���ҁA���100�~���x�������ł��B
Vce��0.5V�ƍ��߂ɂƂ��Ă���܂������̏ꍇ�́A�����ƒႭ�A
0V�Ōv�Z���Ă�OK�̂悤�ł��B
�܂��A�K�i�ł̓��[�U�[���U��臒l�̓d���͍��߂ɏ����Ă���܂����A
���\�Ⴂ�l�ł����U���܂��B
�܂��A�t�d�����K�i�قnj������͖����ł����A�ɐ����ԈႦ��̂͋֕��ł��B
�G�~�b�^�ɕt������R�͓d������p�Ɠd�������p�Ƃ��l���Ă��̂ł����A
��(�R���N�^��)�ɕt���Ă��A�������v�ł��B
LD��
650nm5mW30�A�����A10�͏H���Ŕ̔�����Ă��郂�m�B
780nm10mW(RLD78NZM1)10�����܂����B
���ҁA���100�~���x�������ł��B
 ********************************************************************************************************************************************
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
�ȈՔŌ����e�̐���B
��H�S�̂��A
�����ƃ��N�ɂ���ƁA��Ɏ����ł̓I���ėp�ł���
�}�C�N���X�C�b�`�Ȃǂŋ��͂Ȍ�(�p���[LED��A���[�U�[�Ȃ�)��������ON-OFF�Ƃ������ɑ����ω��̐M�����o�����̂ŁA
�����H�͔�����H�ō����Ȍ��ω���ǂނ����̃��m������܂��B
�܂��A������ɂ́A�Ђ�����A�����Y�A�ԐF�̃Z���n���Ȃǂ̊ȈՂȌ��w�t�B���^���g�����Ƃ��o���܂��B
�l�I�ɂ́A5�`7m��ׂΗǂ����Ǝv���܂��B
********************************************************************************************************************************************
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
�ȈՔŌ����e�̐���B
��H�S�̂��A
�����ƃ��N�ɂ���ƁA��Ɏ����ł̓I���ėp�ł���
�}�C�N���X�C�b�`�Ȃǂŋ��͂Ȍ�(�p���[LED��A���[�U�[�Ȃ�)��������ON-OFF�Ƃ������ɑ����ω��̐M�����o�����̂ŁA
�����H�͔�����H�ō����Ȍ��ω���ǂނ����̃��m������܂��B
�܂��A������ɂ́A�Ђ�����A�����Y�A�ԐF�̃Z���n���Ȃǂ̊ȈՂȌ��w�t�B���^���g�����Ƃ��o���܂��B
�l�I�ɂ́A5�`7m��ׂΗǂ����Ǝv���܂��B
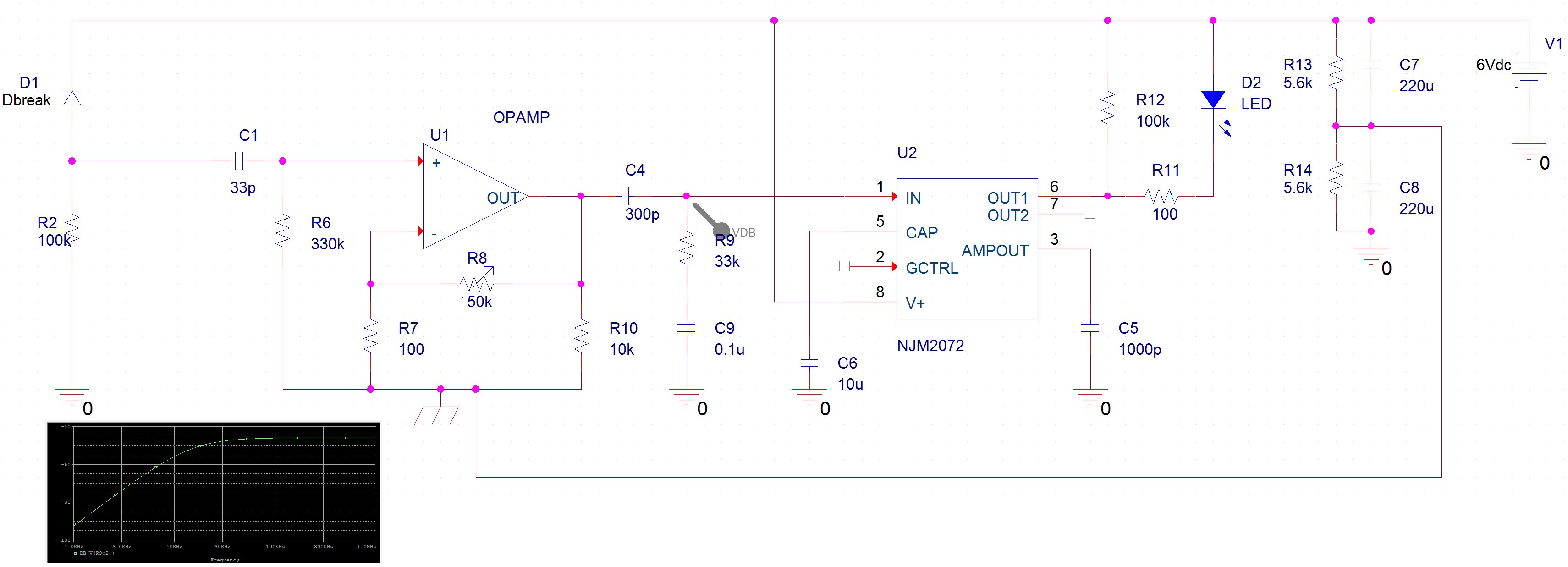 R8�̓Q�C���R���g���[���ł��B���Q�C�����グ������ƁA���͂̃I�t�Z�b�g�d���ŖO�a���Ă��܂��܂��B
D1�̓t�H�g�_�C�I�[�h�ł��B
2072��4�ԃs����GND�ɐڑ����܂��B
�����[���������ꍇ�Ƃ��Ńg�����W�X�^���g�������ꍇ��2SA1015���荠�ŏ��^�Ŕ�r�I��d���ň����ƂȂ��BC327(�H��)�Ȃ��ǂ����Ǝv���܂��B
���[�^�[�Ȃǂ��_�C���N�g�ɓ����������ꍇ�APNP�œd�����傫�����̂��A�p���[FET�Ȃǂ��ǂ��ł����A�m�C�Y���߂��Ă��Ȃ��悤�ɁB
R8�̓Q�C���R���g���[���ł��B���Q�C�����グ������ƁA���͂̃I�t�Z�b�g�d���ŖO�a���Ă��܂��܂��B
D1�̓t�H�g�_�C�I�[�h�ł��B
2072��4�ԃs����GND�ɐڑ����܂��B
�����[���������ꍇ�Ƃ��Ńg�����W�X�^���g�������ꍇ��2SA1015���荠�ŏ��^�Ŕ�r�I��d���ň����ƂȂ��BC327(�H��)�Ȃ��ǂ����Ǝv���܂��B
���[�^�[�Ȃǂ��_�C���N�g�ɓ����������ꍇ�APNP�œd�����傫�����̂��A�p���[FET�Ȃǂ��ǂ��ł����A�m�C�Y���߂��Ă��Ȃ��悤�ɁB
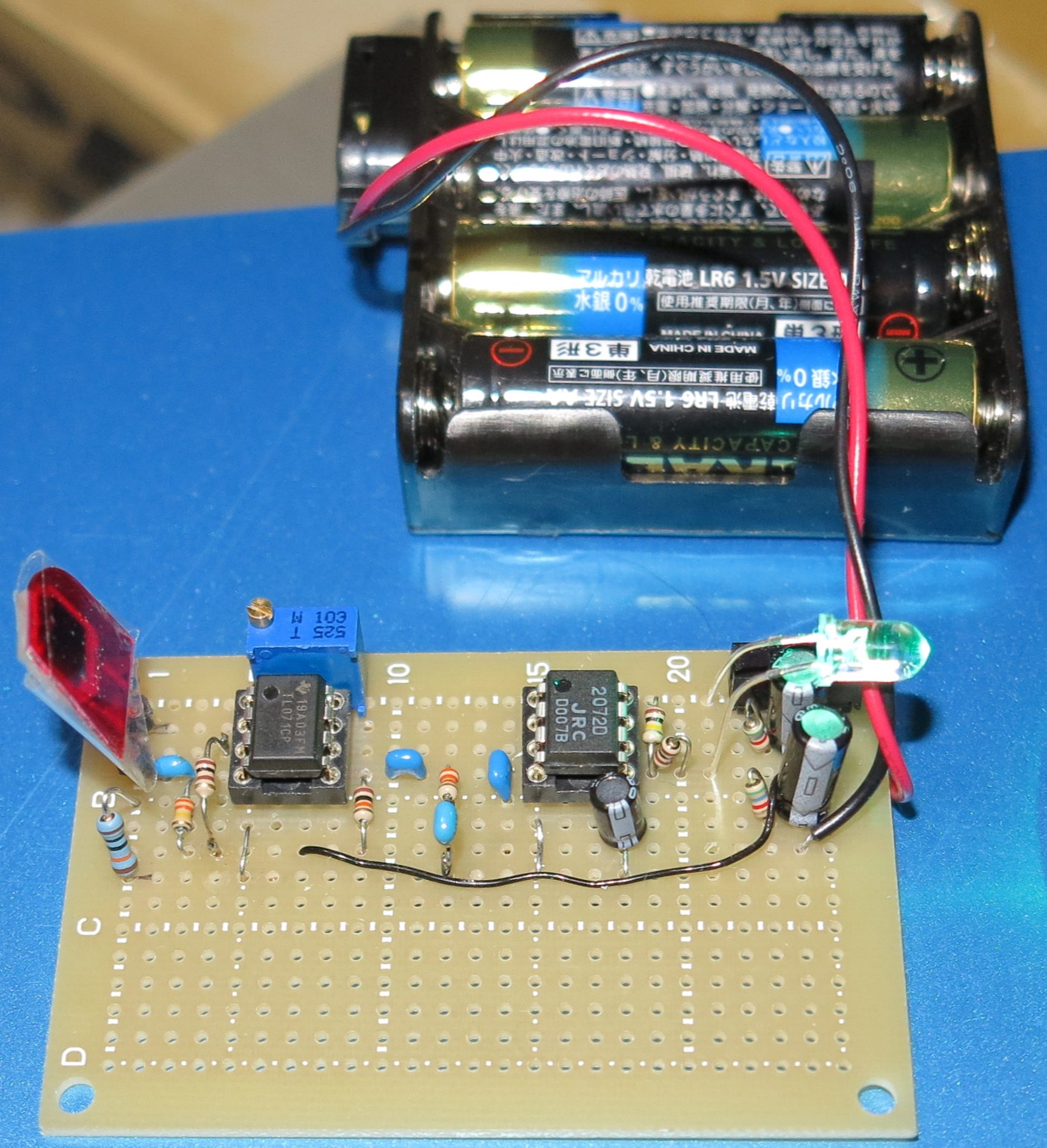
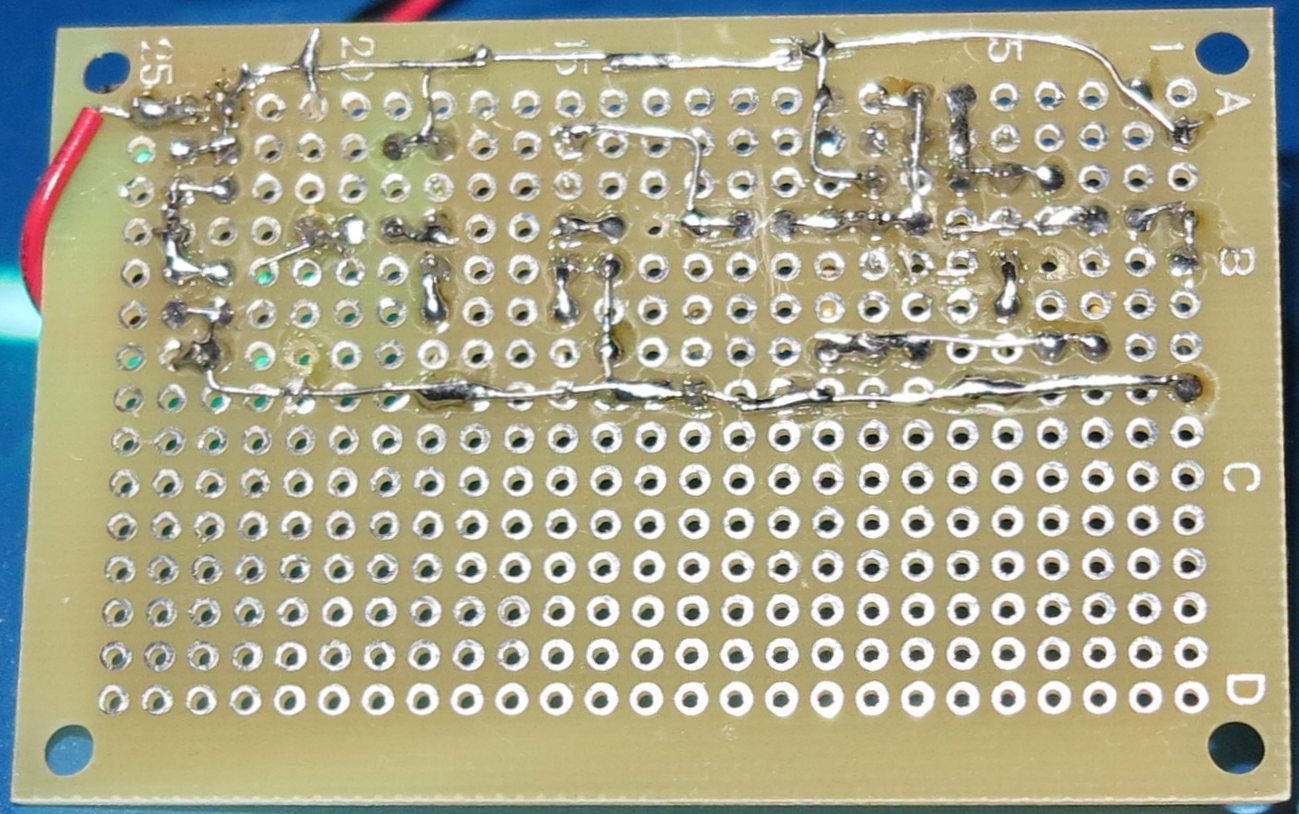
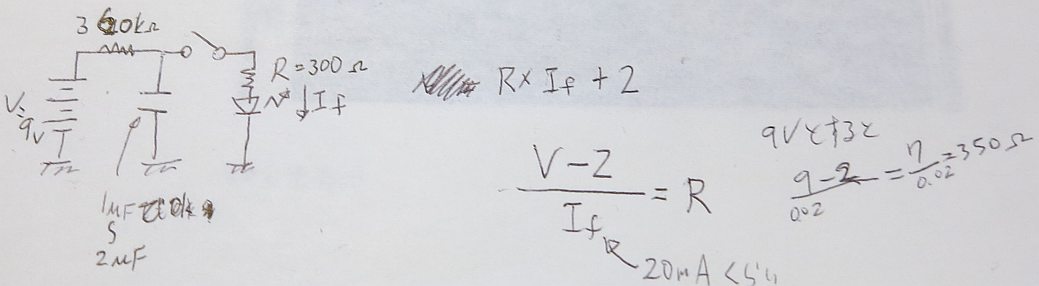 �ȈՂȔ������j�b�g�ł��B
�R���f���T�[�ɏ[�d���āA��u���点�܂��B
�[�d�p�̒�R��50K�����炢�����x�ǂ��悤�ł����B
�ȈՂȔ������j�b�g�ł��B
�R���f���T�[�ɏ[�d���āA��u���点�܂��B
�[�d�p�̒�R��50K�����炢�����x�ǂ��悤�ł����B
 ������LED(50000mcd���ˊp15��)�Ń����Y�Ȃ���8m�ȏ��Ԃ̂ŁA
�����Y��t������X�ɔ�т܂��ˁB
��쓮�������̂ł܂��A���x���グ���܂��B
�ԊO�ł��Ȃ�L�т܂����A�X�ɐԊO�p���[LED�ɂ���X�ɔ���I�ɒ������ɂ��B
�܂��A�I���Ăɂ͏\��������悤�Ɏv���܂��B
���x�A
������������ďe�ɑg�ݍ���ł݂܂��B
�ȈՌ^�����e02
�O��̊ȈՌ^�̂��G�A�R�b�L���O���̏e�̃V�����_�����̃m�Y����O�����ɑg�ݍ���ł݂܂����B
������LED(50000mcd���ˊp15��)�Ń����Y�Ȃ���8m�ȏ��Ԃ̂ŁA
�����Y��t������X�ɔ�т܂��ˁB
��쓮�������̂ł܂��A���x���グ���܂��B
�ԊO�ł��Ȃ�L�т܂����A�X�ɐԊO�p���[LED�ɂ���X�ɔ���I�ɒ������ɂ��B
�܂��A�I���Ăɂ͏\��������悤�Ɏv���܂��B
���x�A
������������ďe�ɑg�ݍ���ł݂܂��B
�ȈՌ^�����e02
�O��̊ȈՌ^�̂��G�A�R�b�L���O���̏e�̃V�����_�����̃m�Y����O�����ɑg�ݍ���ł݂܂����B
 ���͋C�Ƃ��ẮA�����Y���g��Ȃ��A��Ԏ����葁���^�̐}�̕����ł��B
�o���������Ɏ���\��A���ɓh�����Ă���܂����A�ȈՂȃ��m�ł��āA
������ōi�肪��������������ǂ��ł��B
LED�̕��ˊp��15���̋��p�Ȃ̂�����A�����̓o���������猩�Ĕ����̂����S�ɗ���悤�ɍ��킹�Ă��܂��B
�����Y���g���ꍇ�͓��Ƀ�5mm����3mm�Ȃق������x�I�ɂ͗ǂ����Ǝv���܂��B
(�p���[LED�̋��͂��́A�����ʐςɋN�����Ă镔�������X����܂��̂ŁA
���w�I�ɗL���Ȏg�����̍\�z���l���Ȃ��ƁA�L�����p�ł��܂���B)
���f���K���ɕt����ꍇ�A�d���ޕ������]�T�������̂ŁA
�V���[�^�[�����̂悤�ɉΖ�̔��̌������̂��e�ł����A���}�Y���t���b�V���̏o�߂����C�ɂȂ�܂����A
�T�C�����T�[�^�A�X�R�[�v�^�A���[�U�[�T�C�g�^�Ȃǂ���Ǝv���܂��B
���͋C�Ƃ��ẮA�����Y���g��Ȃ��A��Ԏ����葁���^�̐}�̕����ł��B
�o���������Ɏ���\��A���ɓh�����Ă���܂����A�ȈՂȃ��m�ł��āA
������ōi�肪��������������ǂ��ł��B
LED�̕��ˊp��15���̋��p�Ȃ̂�����A�����̓o���������猩�Ĕ����̂����S�ɗ���悤�ɍ��킹�Ă��܂��B
�����Y���g���ꍇ�͓��Ƀ�5mm����3mm�Ȃق������x�I�ɂ͗ǂ����Ǝv���܂��B
(�p���[LED�̋��͂��́A�����ʐςɋN�����Ă镔�������X����܂��̂ŁA
���w�I�ɗL���Ȏg�����̍\�z���l���Ȃ��ƁA�L�����p�ł��܂���B)
���f���K���ɕt����ꍇ�A�d���ޕ������]�T�������̂ŁA
�V���[�^�[�����̂悤�ɉΖ�̔��̌������̂��e�ł����A���}�Y���t���b�V���̏o�߂����C�ɂȂ�܂����A
�T�C�����T�[�^�A�X�R�[�v�^�A���[�U�[�T�C�g�^�Ȃǂ���Ǝv���܂��B
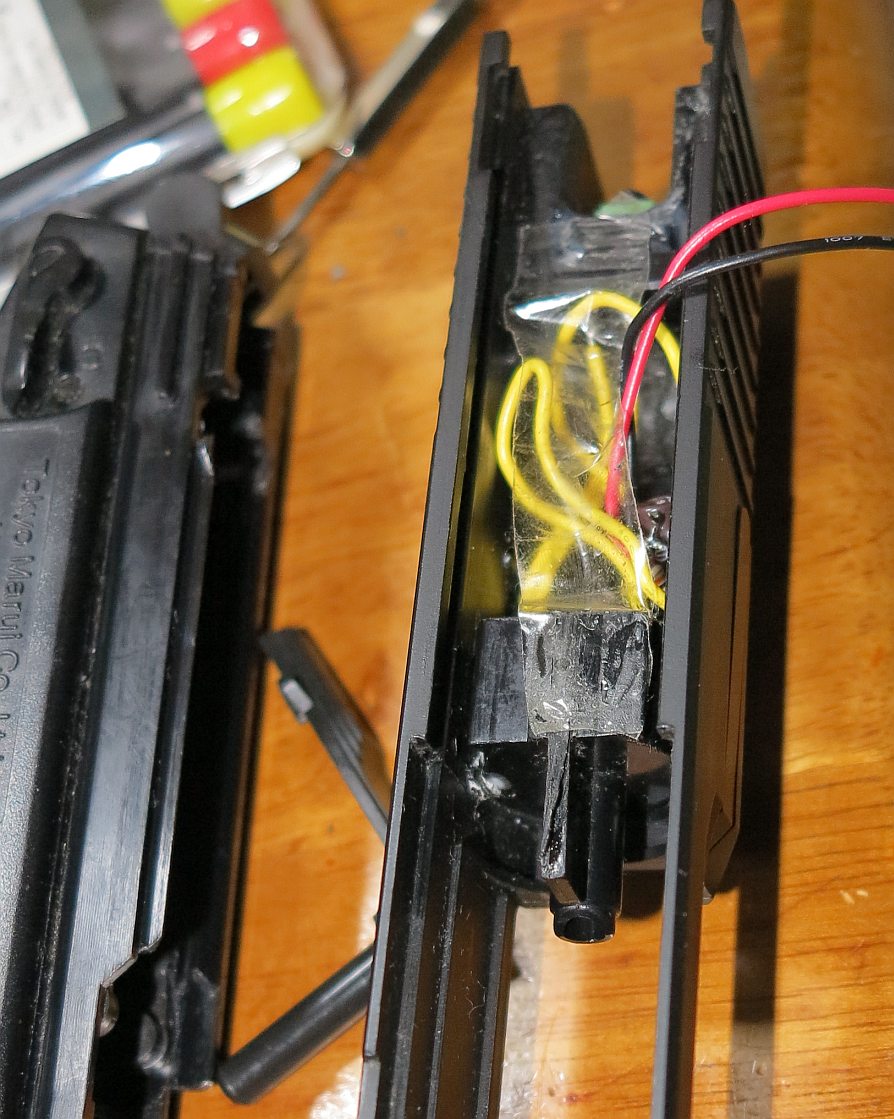
 �X�C�b�`�̓��J�j�J���L�[�{�[�h�̃L�[�ł�����x�̑ϋv�����L��Ǝv���܂��B
(�d���ɂł͖����A�ړ_�͉��ɓ����̂ŏՌ����ɂ���ɎȂ��B)
�X�ɁA�n���}�[���A�X�C�b�`�ډ�����ON�ɂ���킯�ł͖����A
�n���}�[���X�C�b�`�{�^����@���A���̊����ŃX�C�b�`�̃{�^�����O�i���Đړ_��ON�ɂȂ�܂��B
�Ȃ̂ŁA��{�I�ɓd���X�C�b�`�͗v�炸�d�r�͓�����ςȂ��ł������܂��B
�_�����Ȃ̂ł����A���A�T�C�g���A���̊ԂɌ�����t�����g�T�C�g��W�I�ɍ��킹�邱�Ƃ�D�悵�܂��B
�T�u�}�V���K����A�T���g���C�t���Ȃǒ����m�قǂ��̉e���������ł��B
�܂�A�t�����g�T�C�g�ɐ_�o���W�������A�T�C�g�͒P�Ȃ�̂��������x�ł�����x�����܂��B
�X�C�b�`�̓��J�j�J���L�[�{�[�h�̃L�[�ł�����x�̑ϋv�����L��Ǝv���܂��B
(�d���ɂł͖����A�ړ_�͉��ɓ����̂ŏՌ����ɂ���ɎȂ��B)
�X�ɁA�n���}�[���A�X�C�b�`�ډ�����ON�ɂ���킯�ł͖����A
�n���}�[���X�C�b�`�{�^����@���A���̊����ŃX�C�b�`�̃{�^�����O�i���Đړ_��ON�ɂȂ�܂��B
�Ȃ̂ŁA��{�I�ɓd���X�C�b�`�͗v�炸�d�r�͓�����ςȂ��ł������܂��B
�_�����Ȃ̂ł����A���A�T�C�g���A���̊ԂɌ�����t�����g�T�C�g��W�I�ɍ��킹�邱�Ƃ�D�悵�܂��B
�T�u�}�V���K����A�T���g���C�t���Ȃǒ����m�قǂ��̉e���������ł��B
�܂�A�t�����g�T�C�g�ɐ_�o���W�������A�T�C�g�͒P�Ȃ�̂��������x�ł�����x�����܂��B
 �Ƃ���ŁA��������TL071��2�j�������̂ł����B
�����炭�Ód�C�ł����A
�V���b�N��^���Ă���A����܂ł��Ȃ莞�Ԃ�������܂����B
���̗�����ԂŁA����LED�ł͒����P�x�ł��w�ǔ��������ł������A
�Ɩ��p�����R���̐ԊO���p��LED�͂��̂����������������邱�Ƃ��������܂����B
�܂�ԊOLED�́A���������������A�t�H�g�_�C�I�[�h�ɂ��������x�ɂ���Ƃ������Ƃł��B
940nm���ƌ����܂��A
850nm��LED���ƌ����Ă�̂��������Ɍ����܂��̂ŁA��H�̓���`�F�b�N���ڎ��ŏo���܂��B
�ŁATL071���Ǝ�I�t�Z�b�g�������̂ŁALF411�Ƃ���CMOS�Ȃ��̂ɂ��܂����B
����������Ɗ��x�����߂āA
�����P�[�X�ɂł����ꂽ���ł����A
�Œ�̓y�e�b�g���}�W�b�N�e�[�v�ɂ������ł��B
����\���pLED���Ȃ̂͐Ԃ̕�F������ł��B
�܂��A���ʂɌ���LPF�ȋ@�\�Ȃ�A���ʂ��Ȃ��ł��傤���ǁA��肭�����Ȃ������Ƃ�������܂����́B
�����ɂ́A006P�A���J���d�r���g�p���Ă��܂������A���`�E���R�C���d�r�Ȃǂ����x�ǂ��C�����܂����B���t�R�ꌜ�O�ŁB
���[���Ȃ�A
�ŋߏo����Ă鏬�^��12V�̃A���J���d�r�A23S����x�X�g�Ɏv���܂��B
�NjL��
�X�C�b�`�́A����σQ�[���X�C�b�`���C�C���Ǝv���܂����B
�Ƃ����̂��A
�p���[LED�����Ă���A�L�[�{�[�h�̃X�C�b�`���d���̂������A�ڐG�����������Ȃ�܂����B
���̓_�A�Q�[���X�C�b�`�͂܂��ϋv�������肻���ł��B
�X�C�b�`�͒E���A�������o����悤�ɂȂ��Ă�Ɨǂ��ł��B
�Ƃ肠�����A�|���J�[�{�l�[�g�ȓ��ꕨ�ɓ���܂����B
�Ƃ���ŁA��������TL071��2�j�������̂ł����B
�����炭�Ód�C�ł����A
�V���b�N��^���Ă���A����܂ł��Ȃ莞�Ԃ�������܂����B
���̗�����ԂŁA����LED�ł͒����P�x�ł��w�ǔ��������ł������A
�Ɩ��p�����R���̐ԊO���p��LED�͂��̂����������������邱�Ƃ��������܂����B
�܂�ԊOLED�́A���������������A�t�H�g�_�C�I�[�h�ɂ��������x�ɂ���Ƃ������Ƃł��B
940nm���ƌ����܂��A
850nm��LED���ƌ����Ă�̂��������Ɍ����܂��̂ŁA��H�̓���`�F�b�N���ڎ��ŏo���܂��B
�ŁATL071���Ǝ�I�t�Z�b�g�������̂ŁALF411�Ƃ���CMOS�Ȃ��̂ɂ��܂����B
����������Ɗ��x�����߂āA
�����P�[�X�ɂł����ꂽ���ł����A
�Œ�̓y�e�b�g���}�W�b�N�e�[�v�ɂ������ł��B
����\���pLED���Ȃ̂͐Ԃ̕�F������ł��B
�܂��A���ʂɌ���LPF�ȋ@�\�Ȃ�A���ʂ��Ȃ��ł��傤���ǁA��肭�����Ȃ������Ƃ�������܂����́B
�����ɂ́A006P�A���J���d�r���g�p���Ă��܂������A���`�E���R�C���d�r�Ȃǂ����x�ǂ��C�����܂����B���t�R�ꌜ�O�ŁB
���[���Ȃ�A
�ŋߏo����Ă鏬�^��12V�̃A���J���d�r�A23S����x�X�g�Ɏv���܂��B
�NjL��
�X�C�b�`�́A����σQ�[���X�C�b�`���C�C���Ǝv���܂����B
�Ƃ����̂��A
�p���[LED�����Ă���A�L�[�{�[�h�̃X�C�b�`���d���̂������A�ڐG�����������Ȃ�܂����B
���̓_�A�Q�[���X�C�b�`�͂܂��ϋv�������肻���ł��B
�X�C�b�`�͒E���A�������o����悤�ɂȂ��Ă�Ɨǂ��ł��B
�Ƃ肠�����A�|���J�[�{�l�[�g�ȓ��ꕨ�ɓ���܂����B
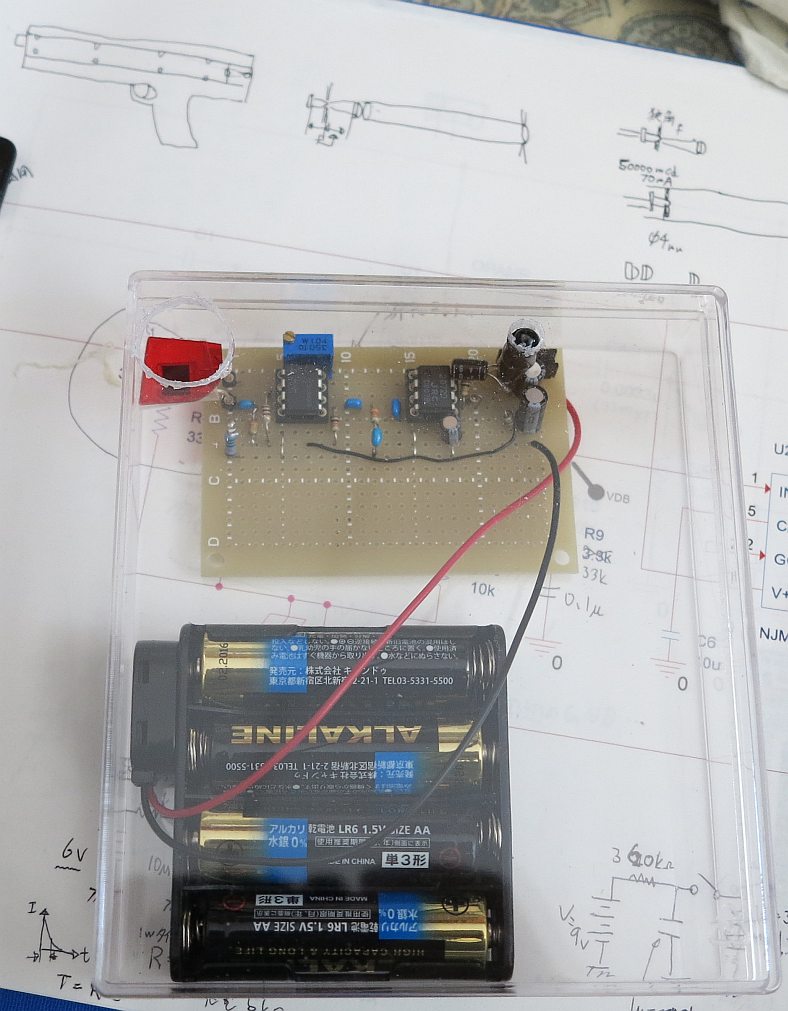 -------
LED�͔M���̖�肪������A
���Ȃ�I�[�o�[�h���C�u�o����悤�ł��B���O�{���炢�̓d���͗]�T�ʼn\�H�B
�����R���̃����V���b�g��
�ȈՔł̏ꍇ�͌��\�I�[�o�[�h���C�u�\�ł��B
-------
LED�͔M���̖�肪������A
���Ȃ�I�[�o�[�h���C�u�o����悤�ł��B���O�{���炢�̓d���͗]�T�ʼn\�H�B
�����R���̃����V���b�g��
�ȈՔł̏ꍇ�͌��\�I�[�o�[�h���C�u�\�ł��B
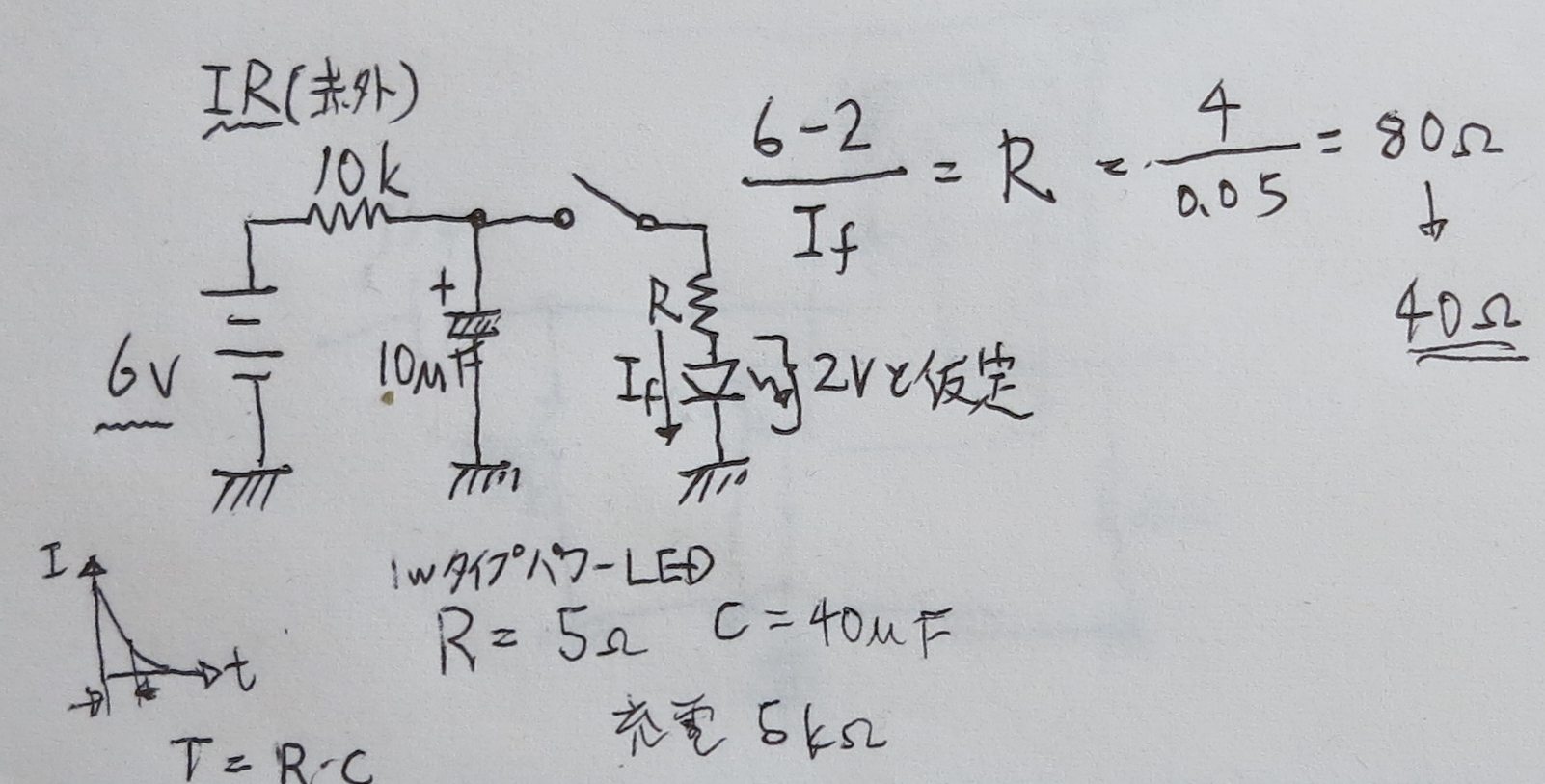 ���ˊp15���̒����P�x��120���̃p���[LED���ׂ�ƁA
�����Y���g��Ȃ���A����܂荷���o�܂���ł����B
�t�Ƀ����Y���g���A�_�����ŃV�r�A�ȃ��m�����܂��B
�s���z�[���˃����Y
�Ƃ��������ƁA
�����Ȃ�ׂ����s���ɂ��镔���ł��B
LD�̏ꍇ�̓r�[��������ƈ��S�ł��ˁB
�����Y�ł����A
��ʂ��ł�������a���œ_�������K�x�ň�Ԏ荠�ł����A
�V�O�}���@�ł����[�Y�i�u���ȃm�[�R�[�g�̃����Y���ʂ������ł��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�ŁA�X�C�b�`�Ȃ̂ł����A
�Q�[���X�C�b�`�ƌ����A�̂͒��Ń{�[�������ɓ]���郂�m�����C���Ɏv�����̂ł������A
�w�������̂́AOMRON��B2R�Ƃ������ƃ��[�h�X�C�b�`�ȍ\���ł��B
���ˊp15���̒����P�x��120���̃p���[LED���ׂ�ƁA
�����Y���g��Ȃ���A����܂荷���o�܂���ł����B
�t�Ƀ����Y���g���A�_�����ŃV�r�A�ȃ��m�����܂��B
�s���z�[���˃����Y
�Ƃ��������ƁA
�����Ȃ�ׂ����s���ɂ��镔���ł��B
LD�̏ꍇ�̓r�[��������ƈ��S�ł��ˁB
�����Y�ł����A
��ʂ��ł�������a���œ_�������K�x�ň�Ԏ荠�ł����A
�V�O�}���@�ł����[�Y�i�u���ȃm�[�R�[�g�̃����Y���ʂ������ł��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�ŁA�X�C�b�`�Ȃ̂ł����A
�Q�[���X�C�b�`�ƌ����A�̂͒��Ń{�[�������ɓ]���郂�m�����C���Ɏv�����̂ł������A
�w�������̂́AOMRON��B2R�Ƃ������ƃ��[�h�X�C�b�`�ȍ\���ł��B

 �n���}�[�Ɏ���t����C�P�����ł��ˁB
�܂��A�}�C�N���X�C�b�`�̕����d���l�͑傫���ł����B
�����ŊȈՂŎg����Ǝv�������̂��A
�X���C�h�Ɏ��A�t���[���Ƀ��[�h�X�C�b�`�Ƃ����l�����ł��B
�����̏u�ԂƂ����킯�ł͖����ł����A
�������i���͂��̂Ŏ����Č��悤�Ǝv���܂��B
�̗p�����A�}�C�N���X�C�b�`�ŁA�u�ԓI�ɓd�����������A���ł��B
�n���}�[�Ɏ���t����C�P�����ł��ˁB
�܂��A�}�C�N���X�C�b�`�̕����d���l�͑傫���ł����B
�����ŊȈՂŎg����Ǝv�������̂��A
�X���C�h�Ɏ��A�t���[���Ƀ��[�h�X�C�b�`�Ƃ����l�����ł��B
�����̏u�ԂƂ����킯�ł͖����ł����A
�������i���͂��̂Ŏ����Č��悤�Ǝv���܂��B
�̗p�����A�}�C�N���X�C�b�`�ŁA�u�ԓI�ɓd�����������A���ł��B
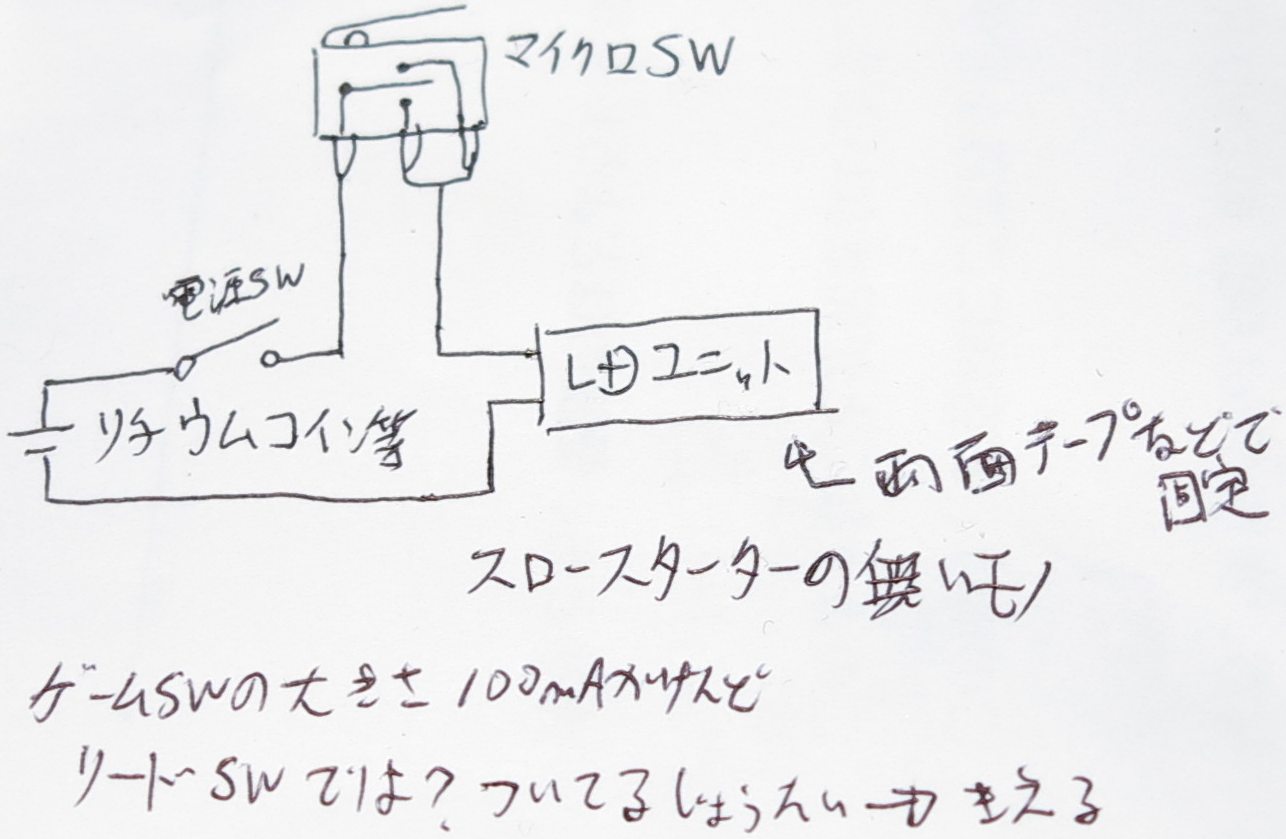 �����A���[�hSW�œ������Ƃ́A3�[�q�̃��[�h�X�C�b�`�͊�̂悤�ł�
�����ɂ́A�n���}�[���A
�G�A�K���̏ꍇ�́A�g���K�����O�́A
���g�A���́A�Ռ��A
���f���K���ł́A�M��
���̕��@���L��܂����A�ȈՂƂ͌����Ȃ��ł��̂ŁA
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�NjL�F04/13��
�Q�[���X�C�b�`�����t���Ă݂܂����B
���[�h�X�C�b�`�̑傫�����炵�āA200�`400mA������Ηǂ����x�Ɏv���̂ł����A
�p���[LED�Ȃ̂ŁA�ق�̈�u�ł����s�[�N700mA����܂��B
�ł��A�����������Ȃ��Ƃ͎v���܂��B
�����A���[�hSW�œ������Ƃ́A3�[�q�̃��[�h�X�C�b�`�͊�̂悤�ł�
�����ɂ́A�n���}�[���A
�G�A�K���̏ꍇ�́A�g���K�����O�́A
���g�A���́A�Ռ��A
���f���K���ł́A�M��
���̕��@���L��܂����A�ȈՂƂ͌����Ȃ��ł��̂ŁA
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�NjL�F04/13��
�Q�[���X�C�b�`�����t���Ă݂܂����B
���[�h�X�C�b�`�̑傫�����炵�āA200�`400mA������Ηǂ����x�Ɏv���̂ł����A
�p���[LED�Ȃ̂ŁA�ق�̈�u�ł����s�[�N700mA����܂��B
�ł��A�����������Ȃ��Ƃ͎v���܂��B

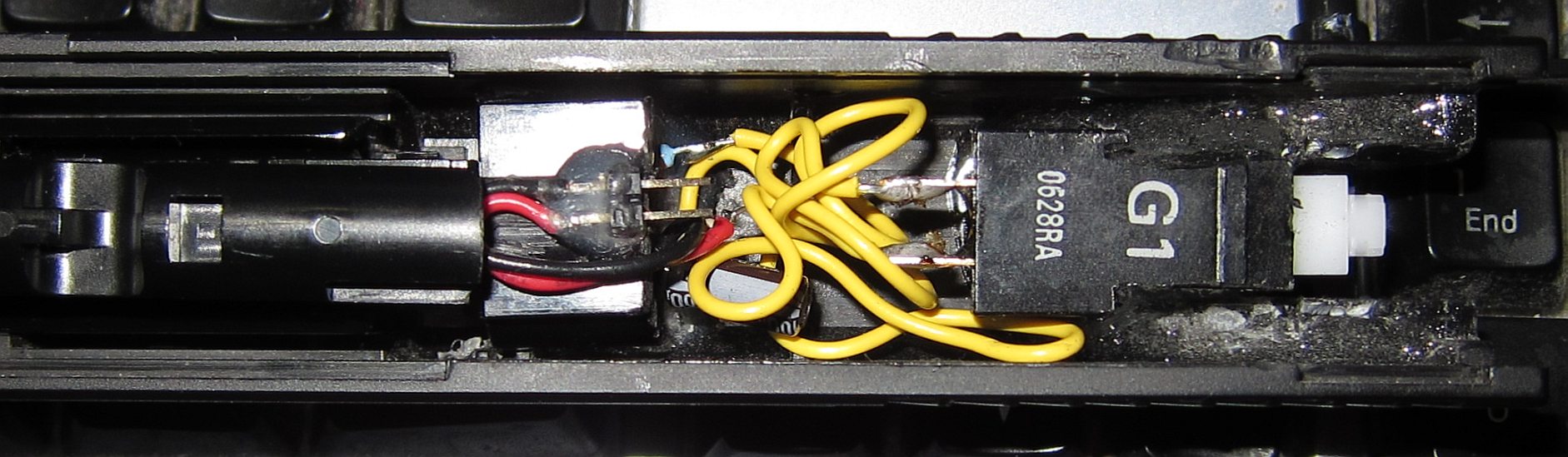 ���͊ȈՔŃp���X�����Ƃ͂����A�����Y�Ȃ���10m�͔�ԂƎv���܂��B
���˗p�Ƃ��Ă͏\�������邩�ƁB
-------------------------------------------------------------------------------------
��H�́A�O��݂����Ȃ̂ŁA���H�ł��B
�����ˌ��Ɍ��肵�܂����A
���[�U�[�͔��U��H�ƃ����Y���ʓ|�Ƃ����l�Ɂc�A
�g���K�����O�́A
���g�A���́A�Ռ��A
�M��
���L��܂����A
�}�C�N���X�C�b�`�ň�u�������Ւf��������B
�O��A���[�h�X�C�b�`�ŃX���C�h�≽���̓����ɘA��������������v�����܂����̂ŁA
�H����LD�������W���[���̊p�`���g�p���܂����B
���W���[�����猋�\�߂Ɍ����o�Ă܂��̂Łc�A
�t�H�[�J�X���o����ی`�̕����ǂ������o��܂���B
�X���[�X�^�[�g��H�t����A�L���̈���LD�������W���[���͌����܂���B
(���̏ꍇ�A
�@LD���W���[���́A�d���ɕ�����H���w�ǖ������̂��g�p�ł��Ă��������B
�@�����ȃ��[�U�[�T�C�g�Ȃǂ́A�ی��H���t���Ă�\�����傫�����Ǝv���܂��B
�@���ɁA
�@���W���[���I��̔��f�́A
�@�d���d�����V�r�A�ŁA�m�C�Y�A�Ód�C�Ɏア�A�Ƃ������ӏ����̃A�����m���ǂ��ł���)
�H����650nm�̓��ނ�OK�̂悤�ł��B
���[�h�X�C�b�`�̓K���X�ǂɐړ_�������Ă邿�����Ⴂ�̂��炠��܂��̂ŁA
�R���p�N�g�ɂ������ꍇ���\�ł��B
���ꂪ�������ė����K�v������܂����B
�X���C�h��1.5cm�قnj�ނ���ƃ��[�U�[���������܂��B
���[�h�X�C�b�`�p�̎��́A
�������ア���̕�������ϓ����������̂ŁA�ǂ��ł��B
��������A�d���u���[�o�b�N�Ȃǂɂ��B������́A�����ł������ł����A
���͊ȈՔŃp���X�����Ƃ͂����A�����Y�Ȃ���10m�͔�ԂƎv���܂��B
���˗p�Ƃ��Ă͏\�������邩�ƁB
-------------------------------------------------------------------------------------
��H�́A�O��݂����Ȃ̂ŁA���H�ł��B
�����ˌ��Ɍ��肵�܂����A
���[�U�[�͔��U��H�ƃ����Y���ʓ|�Ƃ����l�Ɂc�A
�g���K�����O�́A
���g�A���́A�Ռ��A
�M��
���L��܂����A
�}�C�N���X�C�b�`�ň�u�������Ւf��������B
�O��A���[�h�X�C�b�`�ŃX���C�h�≽���̓����ɘA��������������v�����܂����̂ŁA
�H����LD�������W���[���̊p�`���g�p���܂����B
���W���[�����猋�\�߂Ɍ����o�Ă܂��̂Łc�A
�t�H�[�J�X���o����ی`�̕����ǂ������o��܂���B
�X���[�X�^�[�g��H�t����A�L���̈���LD�������W���[���͌����܂���B
(���̏ꍇ�A
�@LD���W���[���́A�d���ɕ�����H���w�ǖ������̂��g�p�ł��Ă��������B
�@�����ȃ��[�U�[�T�C�g�Ȃǂ́A�ی��H���t���Ă�\�����傫�����Ǝv���܂��B
�@���ɁA
�@���W���[���I��̔��f�́A
�@�d���d�����V�r�A�ŁA�m�C�Y�A�Ód�C�Ɏア�A�Ƃ������ӏ����̃A�����m���ǂ��ł���)
�H����650nm�̓��ނ�OK�̂悤�ł��B
���[�h�X�C�b�`�̓K���X�ǂɐړ_�������Ă邿�����Ⴂ�̂��炠��܂��̂ŁA
�R���p�N�g�ɂ������ꍇ���\�ł��B
���ꂪ�������ė����K�v������܂����B
�X���C�h��1.5cm�قnj�ނ���ƃ��[�U�[���������܂��B
���[�h�X�C�b�`�p�̎��́A
�������ア���̕�������ϓ����������̂ŁA�ǂ��ł��B
��������A�d���u���[�o�b�N�Ȃǂɂ��B������́A�����ł������ł����A
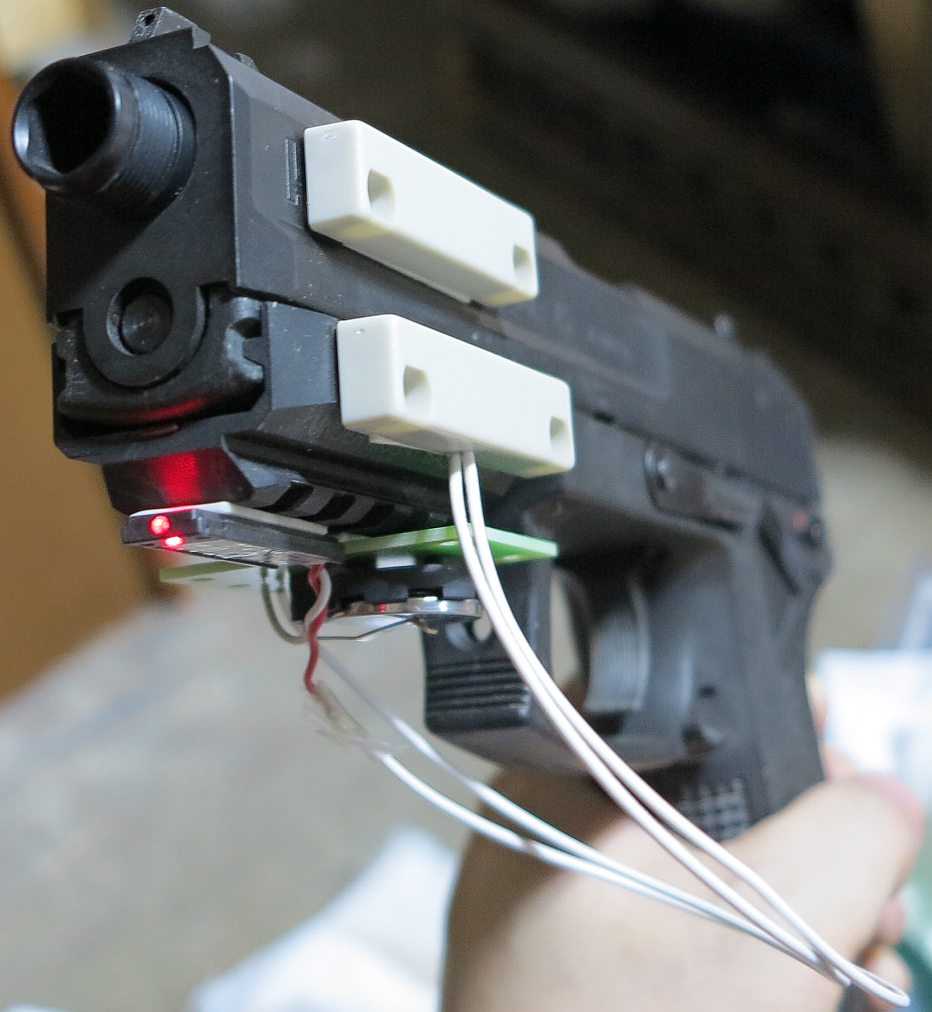
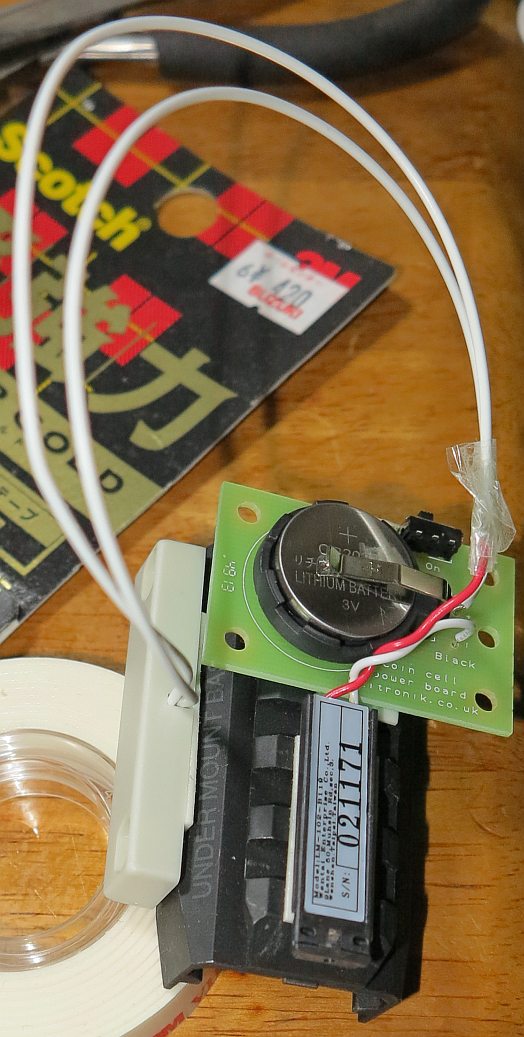
 G18C���g���\��ł������A���[���}�E���g�����i�Œx���炵���ASOCOM��MK23�ł��B
�X���C�h���߂��Ă����Ƃ��ɂ��p���X���o��̂�������ƃA���ł����A�A
������̊g�U�p�́A
�ʐ^�ł̃|���G�`�����t�B�����ł͎シ���܂����̂ŁA�v�����^�p���ɂ��܂����B
G18C���g���\��ł������A���[���}�E���g�����i�Œx���炵���ASOCOM��MK23�ł��B
�X���C�h���߂��Ă����Ƃ��ɂ��p���X���o��̂�������ƃA���ł����A�A
������̊g�U�p�́A
�ʐ^�ł̃|���G�`�����t�B�����ł͎シ���܂����̂ŁA�v�����^�p���ɂ��܂����B
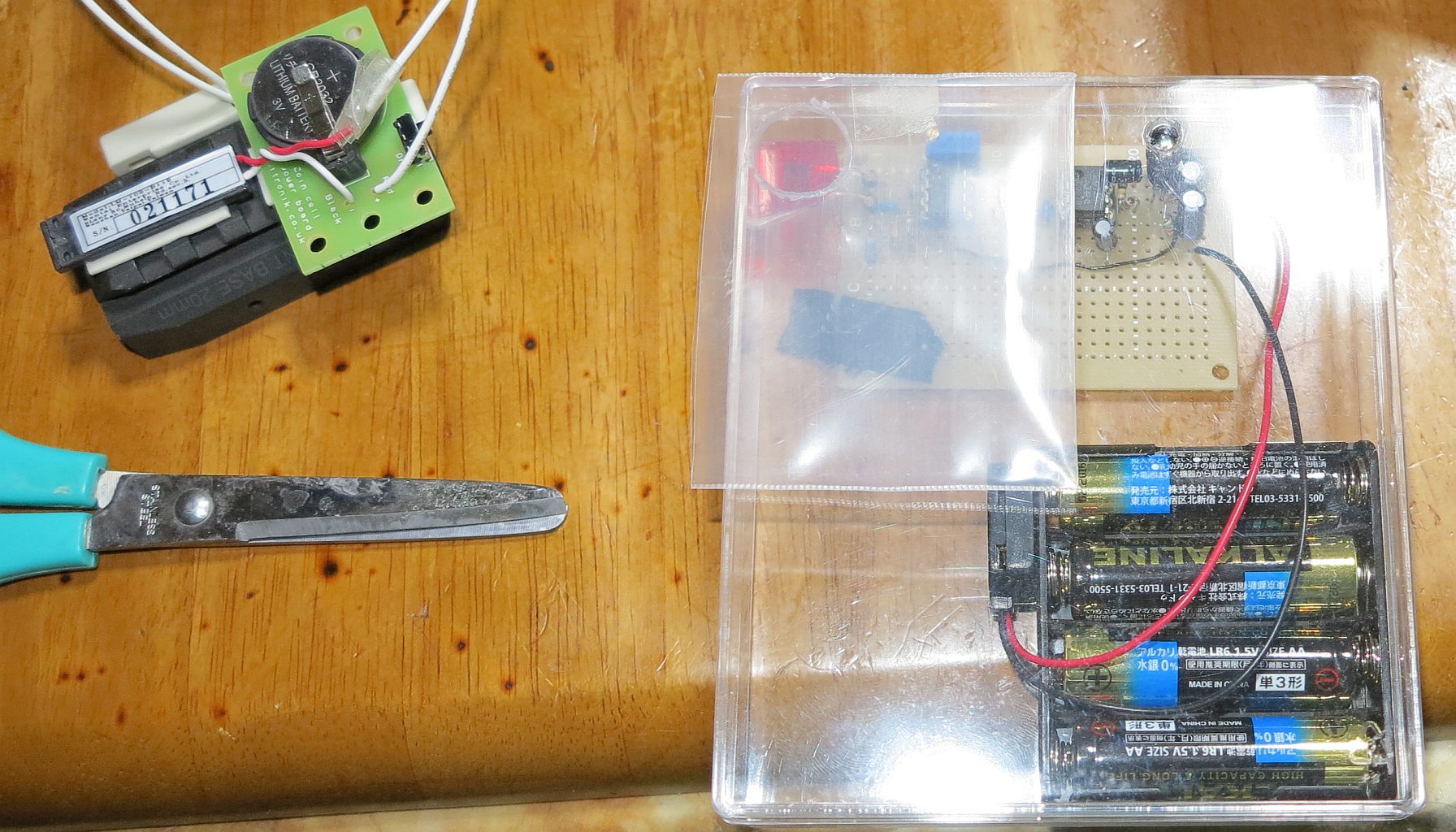 �ł����āA
SOCOM-Mk23�Ƀ��[�h�X�C�b�`�̃��[�U�[���j�b�g��t������A
��H�̃g���K�����O�́A�����ɂ���āA���\�A���ɂԂ��悤�ł��B
�܂��AHW�Ńn�[�h�L�b�N���f���ł����̂ˁB
�����������̂Ɍ������āA���܂ł̋�����Z�����A
�X���C�h���A�y���ďr�q�ȃK�X�K�����A�d���u���[�o�b�N�ɕt�����
���Ȃ�ɘa����Ƃ͎v���܂��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
20�N�ȏ�́A���H�����摜�������܂����B
�N���X2���[�U�[���j�b�g��t������ł��B
�ł����āA
SOCOM-Mk23�Ƀ��[�h�X�C�b�`�̃��[�U�[���j�b�g��t������A
��H�̃g���K�����O�́A�����ɂ���āA���\�A���ɂԂ��悤�ł��B
�܂��AHW�Ńn�[�h�L�b�N���f���ł����̂ˁB
�����������̂Ɍ������āA���܂ł̋�����Z�����A
�X���C�h���A�y���ďr�q�ȃK�X�K�����A�d���u���[�o�b�N�ɕt�����
���Ȃ�ɘa����Ƃ͎v���܂��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
20�N�ȏ�́A���H�����摜�������܂����B
�N���X2���[�U�[���j�b�g��t������ł��B
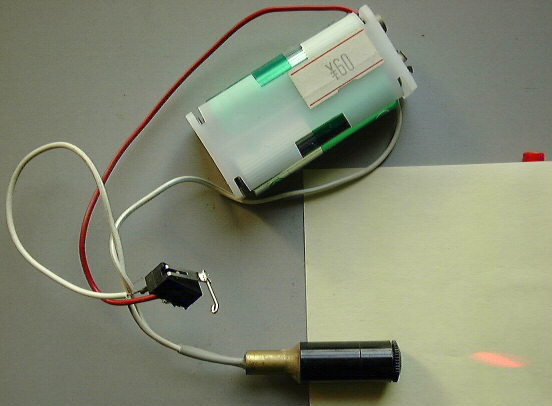

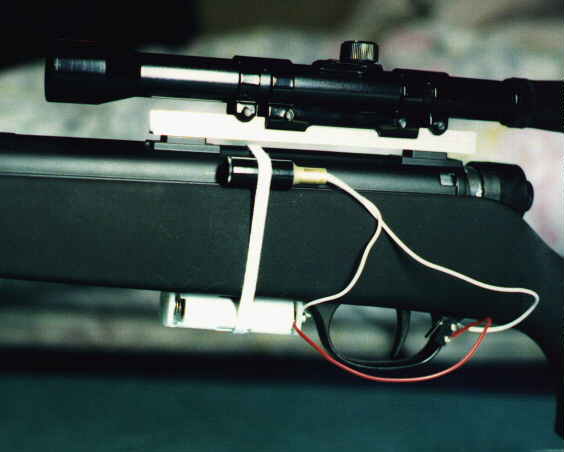 �|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
5mW�̃��[�U�[���j�b�g�ɁA����̑�^�R�����[�^�[��t����
1.2km��̉��˂ɏƎ˂��܂����B
�����ԘI���Ńr�[���������Ă܂����A���ۂ�15cm���炢�̍L����ŁA����ł͏��������Č����Ȃ��ł�
(�R�����[�^�[��������A2�`3m���炢�ɍL�����Ă��܂��܂��B)
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
5mW�̃��[�U�[���j�b�g�ɁA����̑�^�R�����[�^�[��t����
1.2km��̉��˂ɏƎ˂��܂����B
�����ԘI���Ńr�[���������Ă܂����A���ۂ�15cm���炢�̍L����ŁA����ł͏��������Č����Ȃ��ł�
(�R�����[�^�[��������A2�`3m���炢�ɍL�����Ă��܂��܂��B)

 ���Ȃ�650�A�ԊO�Ȃ�780nm��
�N���X2�Ŕ��������A
�f���[�e�B�[��50���Ȃ�A�o�͔͂����Ŗڂɑ��邠����m�ہA
�R�����[�^�ʼn����Ŏ����C���ŁA�o���̃r�[������
�˒���1Km�ȏ�͔�Ԏd�l�B(�����R���K�i�̔��U��H�Ȃ琔�L��)
�P���R�[�̃N���[�Y�A�b�v�����Y���g���Ă܂��B
�V�O�}���@�̂��ƗZ�ʂ������Ǝv���܂��B
�J�����̃����Y���g���A�Z���Ȃ�܂��B
�N���X2�ł́ABPF�ł��ʂ��Ă݂Ȃ�����A�����͌����܂���B
�����ȂǁA���˂�������������A
�}�C�N���v���Y�����ʂ̔��˔�u���Ɨǂ��ł��B
++++++++++++++++++++++++
�d���u���[�o�b�N�ɂ��Ă݂܂����B
5mm��ނ����LD���W���[���̌������悤�ɃZ�b�g�ł��B
���[�hSW�̓R���̔������炢�̑傫��������܂��B
���Ȃ�650�A�ԊO�Ȃ�780nm��
�N���X2�Ŕ��������A
�f���[�e�B�[��50���Ȃ�A�o�͔͂����Ŗڂɑ��邠����m�ہA
�R�����[�^�ʼn����Ŏ����C���ŁA�o���̃r�[������
�˒���1Km�ȏ�͔�Ԏd�l�B(�����R���K�i�̔��U��H�Ȃ琔�L��)
�P���R�[�̃N���[�Y�A�b�v�����Y���g���Ă܂��B
�V�O�}���@�̂��ƗZ�ʂ������Ǝv���܂��B
�J�����̃����Y���g���A�Z���Ȃ�܂��B
�N���X2�ł́ABPF�ł��ʂ��Ă݂Ȃ�����A�����͌����܂���B
�����ȂǁA���˂�������������A
�}�C�N���v���Y�����ʂ̔��˔�u���Ɨǂ��ł��B
++++++++++++++++++++++++
�d���u���[�o�b�N�ɂ��Ă݂܂����B
5mm��ނ����LD���W���[���̌������悤�ɃZ�b�g�ł��B
���[�hSW�̓R���̔������炢�̑傫��������܂��B


 �ŁA�g���Ă݂����ʁB
10m�ł����̋O�Ղ��ő吔cm���Ԃ�Ȃ��ł��̂ŁB
������Aꡂ��ɏ������u�����Ǝv���܂��B
�܂��܂����p�I�ł��B
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
�����R���݊��^�ɖ߂�܂��B
���[�U�[�_�C�I�[�h(LD)�̋쓮�ɂ́B
�I�[�g�p���[�R���g���[��APC��H
�I�[�g�J�����g�R���g���[��ACC��H
������܂��B
��d����H�ł́A
5mw���x�̏��d�͂�LD���ƁA-30���Ɓ{30���̍��Ŕ��U���Ȃ����������U�������ĉ��Ă��܂����ʂ̍����o�Ă��܂��܂��B(�K�i�\�͂��Ȃ茵���߂ɏ����Ă���܂����A���������_�o���ƊȒP�ɉ��܂��B)
����āAACC��H�̓n�C�p���[��LD���\���ɕ��M���Ď�߂ɔ���������ꍇ�Ɏg����Ǝv���܂���
�E�`�ɂ���500mW�̃O���[�����[�U�[��ACC�Ə����Ă����āA30�b�̐������t���Ă܂��B�B
�܂��A�����̃n�C�p���[��LD�ɂ͎Q�Əo�͂��������Ƃ���������������g�������o����̂��Ǝv���܂��B
5mW�̈���LD�́A100�~���x�ŊO�����H���Ȃǂɂ���܂��B
�����Ȃ�650nm�A�ԊO�Ȃ�780nm�����荠�ł����B
�ł����āA
APC��H�̖��ȂƂ���́A�s����3�{�ŁA���i�ɂ���Ă��ꂼ��̋ɐ����Ⴂ�܂��B
�܂��A�}�̂悤��3�ʂ肠��̂ŁA�R���ɍ��킹�Ă��ꂼ��v���Ȃ���Ȃ�܂���B
�Ȃ̂ŁA���܂���ꍞ��Ő�������̂��Ȃȁ[�Ǝv���܂��B
�ŁA�g���Ă݂����ʁB
10m�ł����̋O�Ղ��ő吔cm���Ԃ�Ȃ��ł��̂ŁB
������Aꡂ��ɏ������u�����Ǝv���܂��B
�܂��܂����p�I�ł��B
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
�����R���݊��^�ɖ߂�܂��B
���[�U�[�_�C�I�[�h(LD)�̋쓮�ɂ́B
�I�[�g�p���[�R���g���[��APC��H
�I�[�g�J�����g�R���g���[��ACC��H
������܂��B
��d����H�ł́A
5mw���x�̏��d�͂�LD���ƁA-30���Ɓ{30���̍��Ŕ��U���Ȃ����������U�������ĉ��Ă��܂����ʂ̍����o�Ă��܂��܂��B(�K�i�\�͂��Ȃ茵���߂ɏ����Ă���܂����A���������_�o���ƊȒP�ɉ��܂��B)
����āAACC��H�̓n�C�p���[��LD���\���ɕ��M���Ď�߂ɔ���������ꍇ�Ɏg����Ǝv���܂���
�E�`�ɂ���500mW�̃O���[�����[�U�[��ACC�Ə����Ă����āA30�b�̐������t���Ă܂��B�B
�܂��A�����̃n�C�p���[��LD�ɂ͎Q�Əo�͂��������Ƃ���������������g�������o����̂��Ǝv���܂��B
5mW�̈���LD�́A100�~���x�ŊO�����H���Ȃǂɂ���܂��B
�����Ȃ�650nm�A�ԊO�Ȃ�780nm�����荠�ł����B
�ł����āA
APC��H�̖��ȂƂ���́A�s����3�{�ŁA���i�ɂ���Ă��ꂼ��̋ɐ����Ⴂ�܂��B
�܂��A�}�̂悤��3�ʂ肠��̂ŁA�R���ɍ��킹�Ă��ꂼ��v���Ȃ���Ȃ�܂���B
�Ȃ̂ŁA���܂���ꍞ��Ő�������̂��Ȃȁ[�Ǝv���܂��B
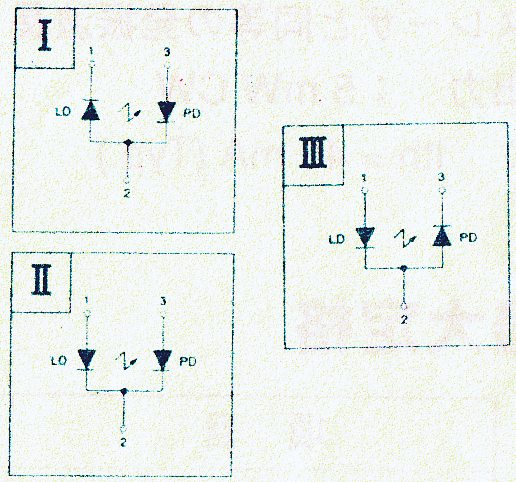 �����͎����ĊȒP�ł��B
��H1�ɂ��āA��Ɏ���Ă݂܂��B
�����͎����ĊȒP�ł��B
��H1�ɂ��āA��Ɏ���Ă݂܂��B
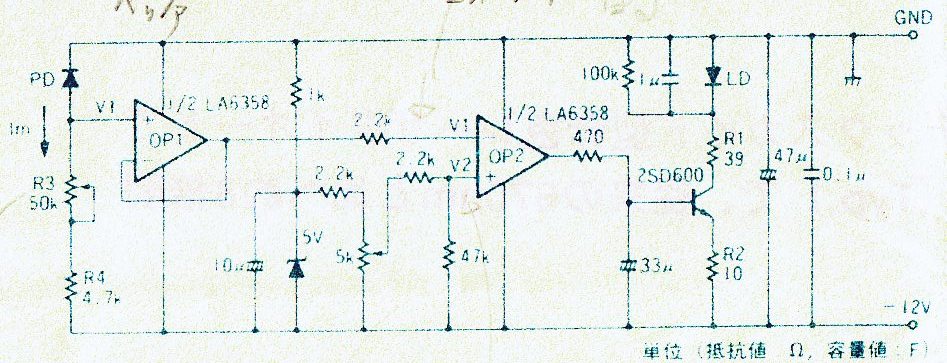 5V�̃c�F�i�[Di����Ȃ��d����VR�ŕ����������̂���A
LD�ɕt���Ă�t�H�gDi�̎Q�Əo�͂����������m(OP-AMP�ň��������Z���܂��B)
OP-AMP�̔{���͗��_�㖳����ɂȂ�̂ŁA
��d�����͂ƃt�H�gDi�̓d���������ɒނ荇���悤��LD�̌��o�͕͂ۂ���܂��B
�܂�A���������ԐړI�ȕ��A��(NFB:�l�K�e�B�u�t�B�[�h�o�b�N)�ɂ���Đ��䂪�Ȃ���܂��B
�Ȃ̂ŁALD�쓮�p�̃g�����W�X�^�̓����Ȃǂ͂��܂�C�ɂ��Ȃ��Ă��ǂ��ł��B
OP-AMP���ėp�̃��j�e�B�Q�C���Ή��ŒP�d���\�^�C�v�̂�OK���Ǝv���܂��B
�ł����āA����ɐM�����悹��Ηǂ��̂ł����A
������AOP-AMP���g�p���������͂ȉ����Z��H���l����Ηǂ��킯�ł��B�����y�̃~�L�T�[�̉�H�Ȃǂł悭�g����B
5V�̃c�F�i�[Di����Ȃ��d����VR�ŕ����������̂���A
LD�ɕt���Ă�t�H�gDi�̎Q�Əo�͂����������m(OP-AMP�ň��������Z���܂��B)
OP-AMP�̔{���͗��_�㖳����ɂȂ�̂ŁA
��d�����͂ƃt�H�gDi�̓d���������ɒނ荇���悤��LD�̌��o�͕͂ۂ���܂��B
�܂�A���������ԐړI�ȕ��A��(NFB:�l�K�e�B�u�t�B�[�h�o�b�N)�ɂ���Đ��䂪�Ȃ���܂��B
�Ȃ̂ŁALD�쓮�p�̃g�����W�X�^�̓����Ȃǂ͂��܂�C�ɂ��Ȃ��Ă��ǂ��ł��B
OP-AMP���ėp�̃��j�e�B�Q�C���Ή��ŒP�d���\�^�C�v�̂�OK���Ǝv���܂��B
�ł����āA����ɐM�����悹��Ηǂ��̂ł����A
������AOP-AMP���g�p���������͂ȉ����Z��H���l����Ηǂ��킯�ł��B�����y�̃~�L�T�[�̉�H�Ȃǂł悭�g����B
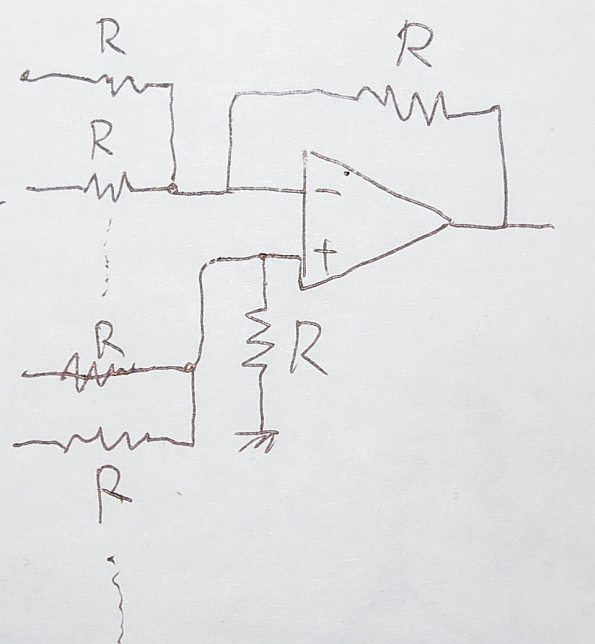 ���ۂ́A�o�̓I�[�o�[�������Ȃ����߁A�}�C�i�X���ɐM��������������ǂ��ł��傤�B
�܂�AOP-AMP�̃}�C�i�X���͑��̓d���ɓd�������Z�����悤�ɍ��Ηǂ��ł��B
�R���p���[�^�[�I�ȕ����ł��B�|���͂�47K���͓��ɗv��Ȃ��Ǝv���܂����A
���ۂ́A�o�̓I�[�o�[�������Ȃ����߁A�}�C�i�X���ɐM��������������ǂ��ł��傤�B
�܂�AOP-AMP�̃}�C�i�X���͑��̓d���ɓd�������Z�����悤�ɍ��Ηǂ��ł��B
�R���p���[�^�[�I�ȕ����ł��B�|���͂�47K���͓��ɗv��Ȃ��Ǝv���܂����A
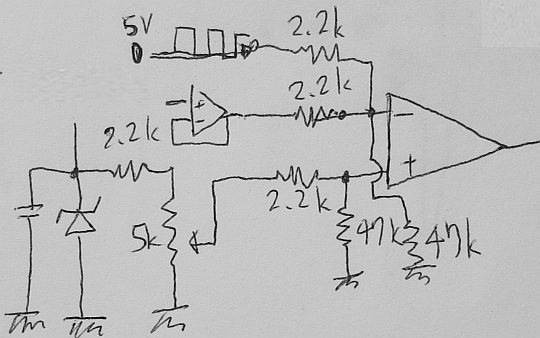 ����
����
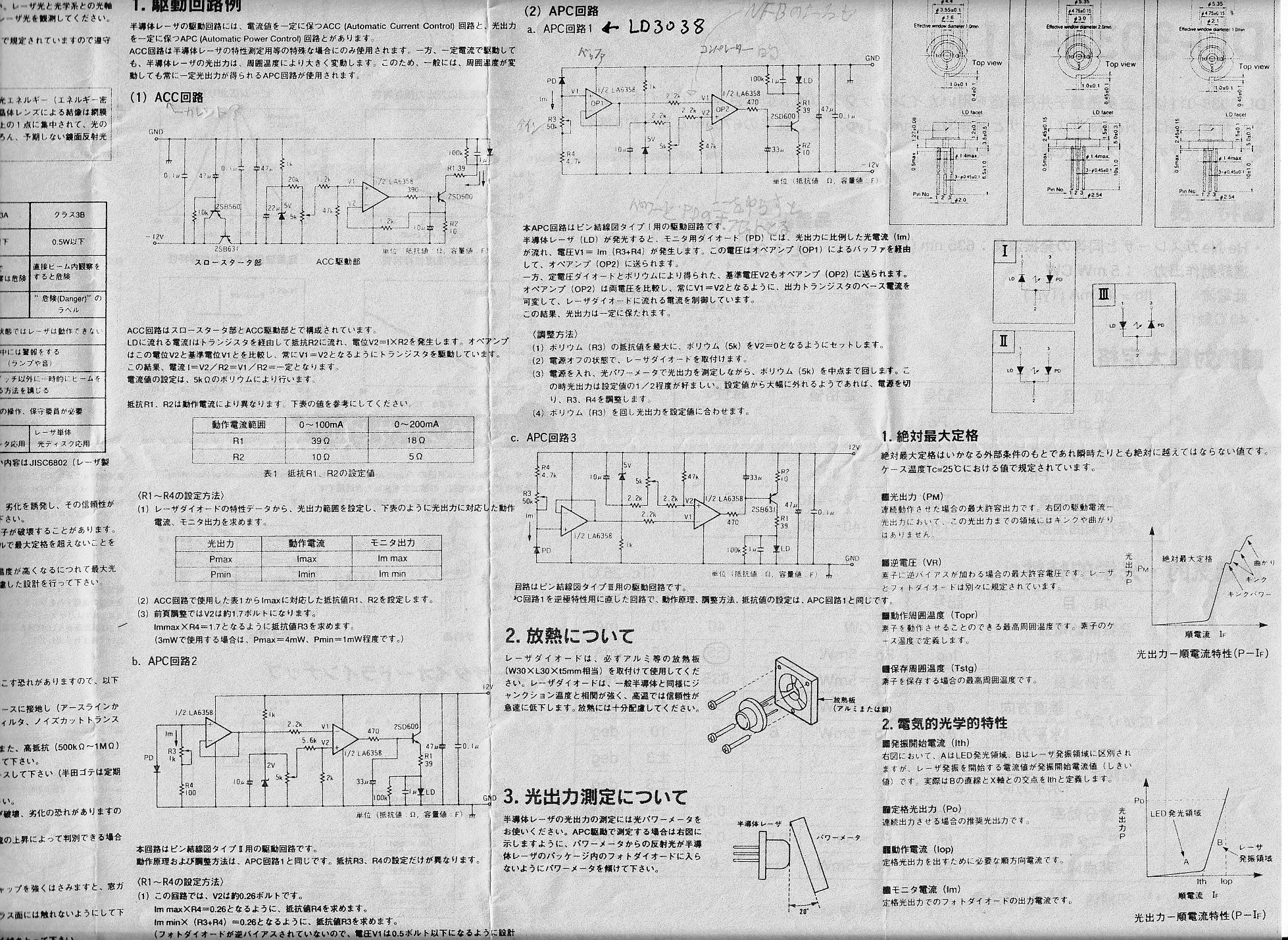 �|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�Ŏ��ۂɍ���OP-AMP�ŁAC��r������
�M�������Ă݂�ƁA(20�N�ȏ�O�Ȃ̂ŏڂ������Ƃ͖Y��Ă܂��B)
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�Ŏ��ۂɍ���OP-AMP�ŁAC��r������
�M�������Ă݂�ƁA(20�N�ȏ�O�Ȃ̂ŏڂ������Ƃ͖Y��Ă܂��B)
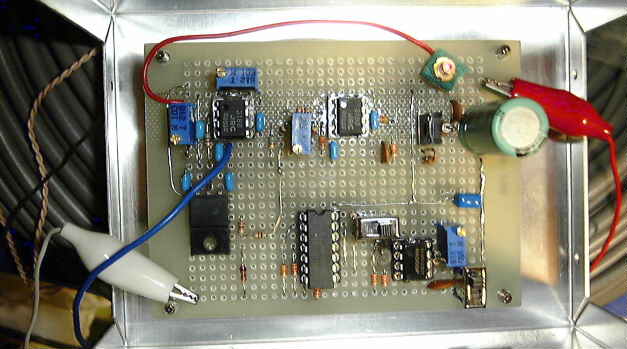 30KHz�Ŕ��U�����ꍇ�Ȃ̂ł����A�S�̉s���p���X�� �Ӑ}���Ȃ����U�ł��B
�ꉞ�A���o�͋��x�ɔ��̐M���ł��B
30KHz�Ŕ��U�����ꍇ�Ȃ̂ł����A�S�̉s���p���X�� �Ӑ}���Ȃ����U�ł��B
�ꉞ�A���o�͋��x�ɔ��̐M���ł��B
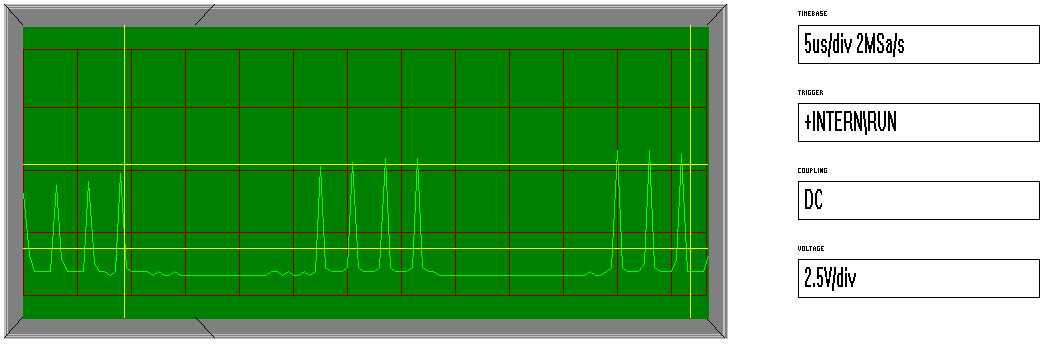 �ȈՓI�ȕ����������݂܂������A�I�i�̔�r�pAMP�Ȍ��Tr�h���C�u���s�\���ŁA�����x���A1/20�ʂɗ����܂����B(���� �ϕ��l��)
�ȈՓI�ȕ����������݂܂������A�I�i�̔�r�pAMP�Ȍ��Tr�h���C�u���s�\���ŁA�����x���A1/20�ʂɗ����܂����B(���� �ϕ��l��)
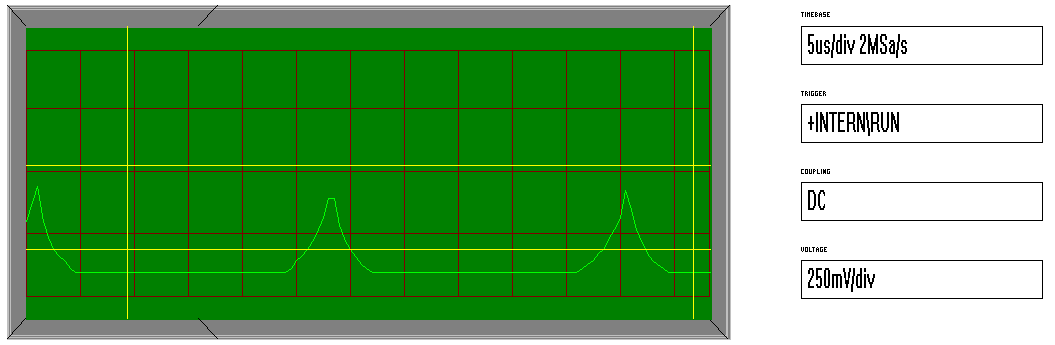 ����n�̔��U�����́A�ʑ��x��ɂ�郂�m�̂悤�ł����A
�ʑ����x���Ȃ�A�i�߂Ă��܂��Ηǂ��Ƃ������ƂŁA
���̂悤�ȉ�H���l���܂����B ������H�ƃX���[�̕���ȍ\���̃��m�ł��B
�������ALD�͂��̏��(���x�A�d���A�o��)�̕ω��� �ʑ����ւ���̂ŁA���萔�̐ݒ肪��������A
�ʂ̉�H�ő傫���x�点�āALD�̕ϓ��̗��������A�Ӑ}�����N���X�|�C���g���������
�ł���H
�ŁA����ȉ�H��g�ݍ��݂܂����B
�܂��́A�Ǝv���A�ʑ���i�߂�݂̂̉�H�ł��B(�ꕔ��x�点���肹�� �ł��B)
����n�̔��U�����́A�ʑ��x��ɂ�郂�m�̂悤�ł����A
�ʑ����x���Ȃ�A�i�߂Ă��܂��Ηǂ��Ƃ������ƂŁA
���̂悤�ȉ�H���l���܂����B ������H�ƃX���[�̕���ȍ\���̃��m�ł��B
�������ALD�͂��̏��(���x�A�d���A�o��)�̕ω��� �ʑ����ւ���̂ŁA���萔�̐ݒ肪��������A
�ʂ̉�H�ő傫���x�点�āALD�̕ϓ��̗��������A�Ӑ}�����N���X�|�C���g���������
�ł���H
�ŁA����ȉ�H��g�ݍ��݂܂����B
�܂��́A�Ǝv���A�ʑ���i�߂�݂̂̉�H�ł��B(�ꕔ��x�点���肹�� �ł��B)
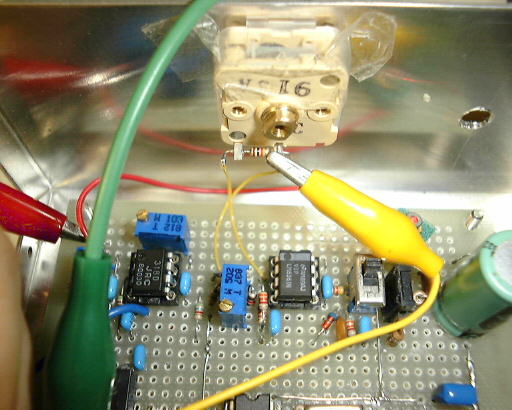 ���ʂȂ̂ł����A�����Ői�ގ��萔�́A�K���ȊT�Z�Ŏ��s���Ă݂��̂ł����A
�o���A�u���R���f���T�[�͈͓̔��ŁA���܂��s���܂����B
���o�͂̐M���ł��B
(�t�H�gDi����� ���j�^�[�d���o�͂��������_�ł̐M���ł��B)
��30KHz�̔��U�ł��BLD�͈��S�̗]�T�����ς����āA��߂̏o�͂ł��B
�����Ȃǂ̐ڑ��ɂ���āA�m�C�Y������ĒW�����Ɍ����܂����A����Ȋ����ł��B
���ɁA�ʑ���H�̎��萔���A�������ꂽ�|�C���g���炸�炵���ꍇ�Ȃ̂ł����A
����Ȋ����ł��B
�オ�����̃J�b�g�I�t���g���������Ƃ����ꍇ�B(C���������ꍇ)
�����A�Ⴍ�Ƃ����ꍇ�A(C���傫���ꍇ)
���ʂȂ̂ł����A�����Ői�ގ��萔�́A�K���ȊT�Z�Ŏ��s���Ă݂��̂ł����A
�o���A�u���R���f���T�[�͈͓̔��ŁA���܂��s���܂����B
���o�͂̐M���ł��B
(�t�H�gDi����� ���j�^�[�d���o�͂��������_�ł̐M���ł��B)
��30KHz�̔��U�ł��BLD�͈��S�̗]�T�����ς����āA��߂̏o�͂ł��B
�����Ȃǂ̐ڑ��ɂ���āA�m�C�Y������ĒW�����Ɍ����܂����A����Ȋ����ł��B
���ɁA�ʑ���H�̎��萔���A�������ꂽ�|�C���g���炸�炵���ꍇ�Ȃ̂ł����A
����Ȋ����ł��B
�オ�����̃J�b�g�I�t���g���������Ƃ����ꍇ�B(C���������ꍇ)
�����A�Ⴍ�Ƃ����ꍇ�A(C���傫���ꍇ)
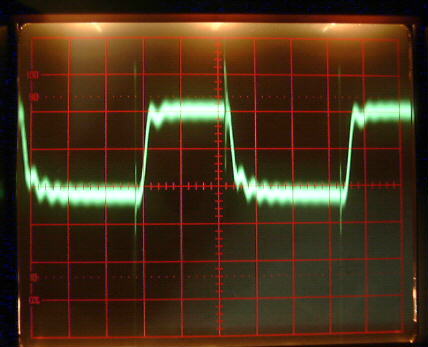
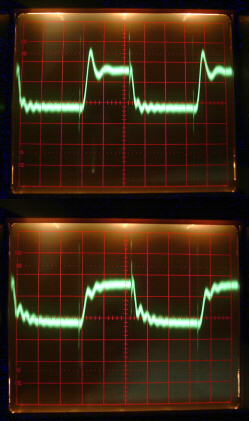 �ϕ��łȂ܂�x�����̈Ⴂ�Ƃ��A
�I�[�o�[�V���[�g�̈Ⴂ�Ȋ����ł��ˁB
�ϕ��łȂ܂�x�����̈Ⴂ�Ƃ��A
�I�[�o�[�V���[�g�̈Ⴂ�Ȋ����ł��ˁB
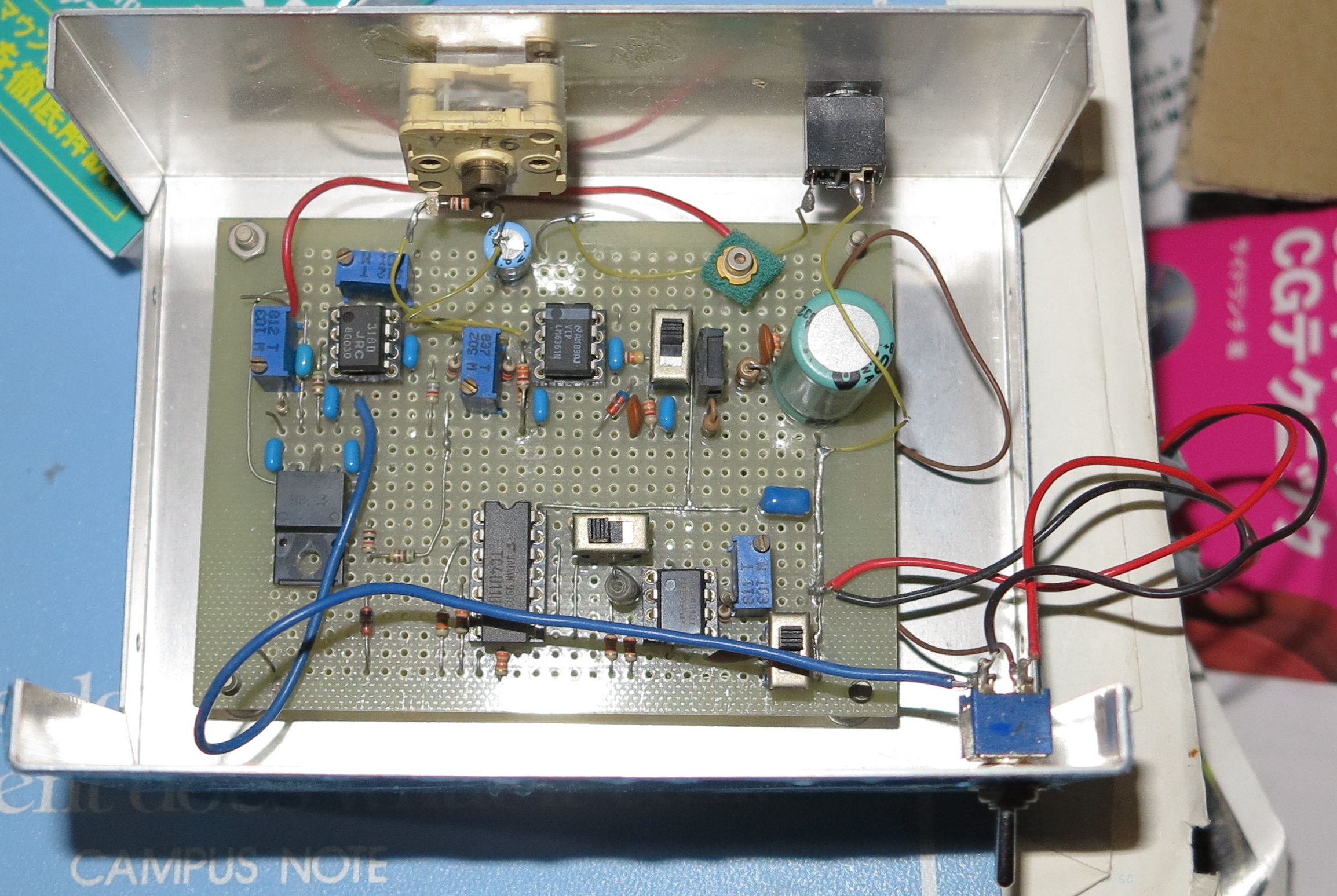 ------------------------------------------------------------------------------------------------
�����e�̌��w�n�B
���\�Ĕz���������ł��B
------------------------------------------------------------------------------------------------
�����e�̌��w�n�B
���\�Ĕz���������ł��B
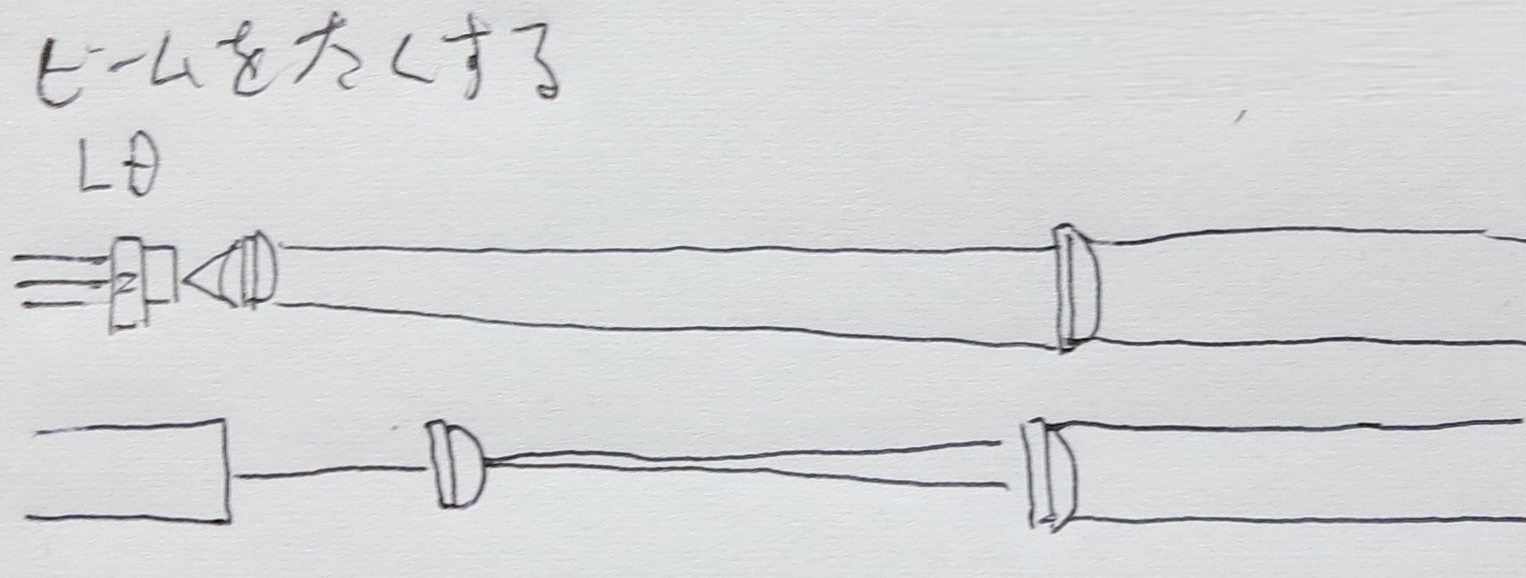 ���[�U�[�ŁA���C�t���Ȃ�A
1�ڂ̃����Y�Ō�������I�ɋ��߂Ĕ���ē�ڂ̃����Y�ɑ���A
��ڂŕ��s���Ɏ���������Ƃ��������B(�}��)
���̕��̐}�́A�قڕ��s���ŏo�Ă��郌���Y�t�����j�b�g�̏ꍇ�A
�����Y�ɏœ_���ߏo�������ōL���点�Ă��ǂ��̂ł����A
�@�\�������ꍇ�A��ڂ̃����Y�ōL���点�ē�ڂ̃����Y�ŕ��s�Ƃ������A
�������ŏœ_������
(���ɂ͉�܂�����܂��̂ŋɗ͂܂Ƃ߂銴����)
�ʐ^�̃R�����[�^�[���j�b�g�́A
��O��f=15cm�ʂ̃����Y�ōL���点�āA330mm�̃����Y�Ŗ������ɏW��
���̂悤�ɁA��U�L�����œ_�Ŏ�����������������ł͗ǂ��W�����A
�܂��A�߂��ł̓r�[���������Ȃ�ڂɓ����Ă����S�Ƃ������@�ł��B
���͉t�ł��̂ŁA�]�����̋t�̃��[�g�����ǂ銴����
���œ_���ƁA�ڕW���ɏ������������܂��B
���[�U�[�ŁA���C�t���Ȃ�A
1�ڂ̃����Y�Ō�������I�ɋ��߂Ĕ���ē�ڂ̃����Y�ɑ���A
��ڂŕ��s���Ɏ���������Ƃ��������B(�}��)
���̕��̐}�́A�قڕ��s���ŏo�Ă��郌���Y�t�����j�b�g�̏ꍇ�A
�����Y�ɏœ_���ߏo�������ōL���点�Ă��ǂ��̂ł����A
�@�\�������ꍇ�A��ڂ̃����Y�ōL���点�ē�ڂ̃����Y�ŕ��s�Ƃ������A
�������ŏœ_������
(���ɂ͉�܂�����܂��̂ŋɗ͂܂Ƃ߂銴����)
�ʐ^�̃R�����[�^�[���j�b�g�́A
��O��f=15cm�ʂ̃����Y�ōL���点�āA330mm�̃����Y�Ŗ������ɏW��
���̂悤�ɁA��U�L�����œ_�Ŏ�����������������ł͗ǂ��W�����A
�܂��A�߂��ł̓r�[���������Ȃ�ڂɓ����Ă����S�Ƃ������@�ł��B
���͉t�ł��̂ŁA�]�����̋t�̃��[�g�����ǂ銴����
���œ_���ƁA�ڕW���ɏ������������܂��B
 330mm�̂̓P���R�[�̃N���[�Y�A�b�v�����Y�ł����A
��O�̃����Y�́A�W�����N�ł��āc�A
�V�O�}���@�ȂǂŃm���R�[�g�̃��[�Y�i�u���̂��A���ł��B
���������ėǂ��Ȃ�A�������Y�̒��ዾ��V�ዾ���g���邩���B
330mm�̂̓P���R�[�̃N���[�Y�A�b�v�����Y�ł����A
��O�̃����Y�́A�W�����N�ł��āc�A
�V�O�}���@�ȂǂŃm���R�[�g�̃��[�Y�i�u���̂��A���ł��B
���������ėǂ��Ȃ�A�������Y�̒��ዾ��V�ዾ���g���邩���B
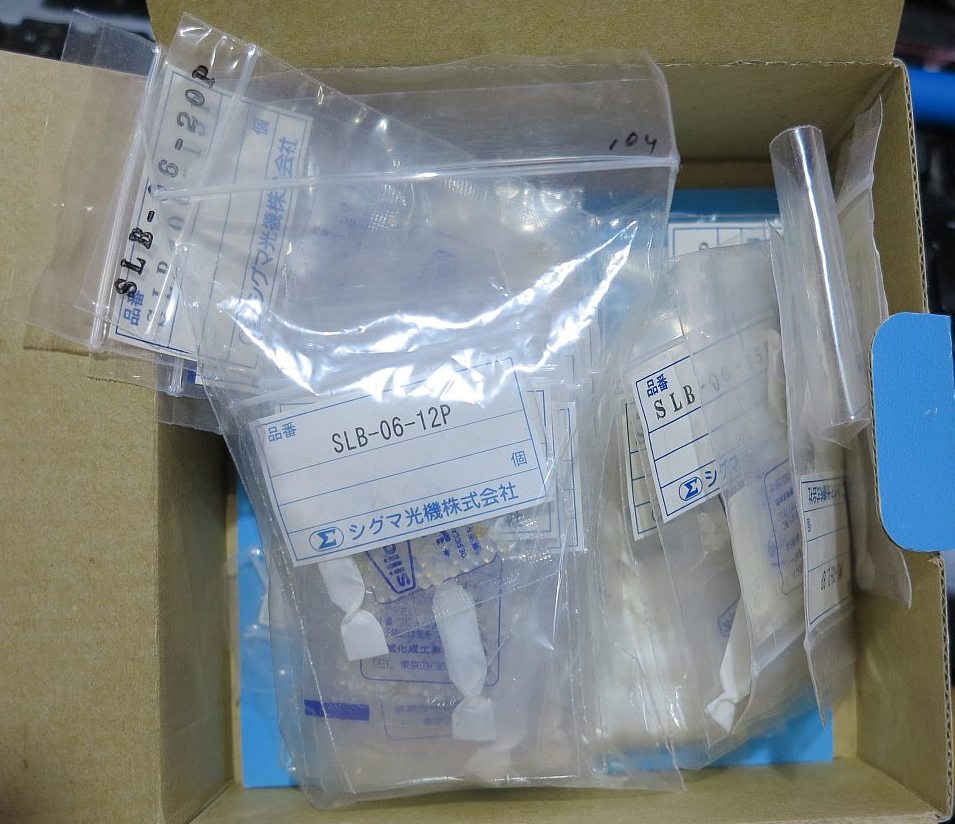 �����_�C�I�[�h�FLED�̏ꍇ�́A������̕������Ȃ��������ł��B
������x�̔����~�����ł����A
�����ł��܂�V�r�A�ɂȂ炸�A�߂��ōL�͈͂ɂȂ肷�����A�Ƃ������ł��B
�œ_���������Ȃ�ׂ��_�����ɋ߂����Ȃ��ƍL����ł��ˁB
�a��3mm�Ƃ��������Ė��邢LED��A
�s���z�[���A�ׂ����t�@�C�o�[�Ȃǂ��g����Ǝv���܂��B
�����Y�́A
�ʂ��ł��Ƃ��荠�����B
�n���h�K��
SMG
�A�T���g���C�t��
�X�i�C�p�[���C�t��
�݂ȓ������Ⴂ�܂��̂ŁA
�����ǂ��̂ł��傤�ˁB
���i�Ƃ��Ĕ����Ă�������e�́A�����Y��ʎY���Ă�̂ŁA���������v����������
�R�R���傫���R�X�g�_�E���ł��镔���Ȃ̂ł���ˁB
�Z�ʂ������܂����B
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
�ȈՔł����������o���オ��܂����̂ŁA
���ꂩ��́A
�o�[�`�������b�N�I���̂悤�ɁA
�����������悤�ȁA���������̃Q�[���̎d�l�ƂȂ�ƁA
�ŏ��ɐv���������R���݊��̐M�����A�����葬���ŗL�U����ǂރ^�C�v�ƂȂ�܂����A
HPF��BPF���g���Ă��A���x���グ��ɁA
����LED�Ɩ��ɂ���쓮��A���˓����ɂ����d���̔{���Ƌt�o�C�A�X�̌��E������܂��B
��҂̓R�C���łǂ��ɂ����悤�ƍl���܂������A�V�[���h��˂��j���ăm�C�Y����邩���m��܂���B
�Ƃ������ƂŁA���x���グ�邱�Ƃ́A���E���A���Ƃ������܂��B
���������A�E�}�����K�v������܂����A
�Ȃ̂ŁA900nm�ȏ�̒����ԊO�̂ݒʂ�������W���[���Ƃ���K�v�����邩���ł����A
(900�`960�͑��z������Ⴂ���ۂ���900�̓t�B���^�A960�̓t�H�gDi���̌��E)
�Ƃ肠�����A�����₷�������ł���Ă������Ǝv���܂��B
���Ƃ́A����Ȃ�H�v���K�v�����ł��ˁB
�����_�C�I�[�h�FLED�̏ꍇ�́A������̕������Ȃ��������ł��B
������x�̔����~�����ł����A
�����ł��܂�V�r�A�ɂȂ炸�A�߂��ōL�͈͂ɂȂ肷�����A�Ƃ������ł��B
�œ_���������Ȃ�ׂ��_�����ɋ߂����Ȃ��ƍL����ł��ˁB
�a��3mm�Ƃ��������Ė��邢LED��A
�s���z�[���A�ׂ����t�@�C�o�[�Ȃǂ��g����Ǝv���܂��B
�����Y�́A
�ʂ��ł��Ƃ��荠�����B
�n���h�K��
SMG
�A�T���g���C�t��
�X�i�C�p�[���C�t��
�݂ȓ������Ⴂ�܂��̂ŁA
�����ǂ��̂ł��傤�ˁB
���i�Ƃ��Ĕ����Ă�������e�́A�����Y��ʎY���Ă�̂ŁA���������v����������
�R�R���傫���R�X�g�_�E���ł��镔���Ȃ̂ł���ˁB
�Z�ʂ������܂����B
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
�ȈՔł����������o���オ��܂����̂ŁA
���ꂩ��́A
�o�[�`�������b�N�I���̂悤�ɁA
�����������悤�ȁA���������̃Q�[���̎d�l�ƂȂ�ƁA
�ŏ��ɐv���������R���݊��̐M�����A�����葬���ŗL�U����ǂރ^�C�v�ƂȂ�܂����A
HPF��BPF���g���Ă��A���x���グ��ɁA
����LED�Ɩ��ɂ���쓮��A���˓����ɂ����d���̔{���Ƌt�o�C�A�X�̌��E������܂��B
��҂̓R�C���łǂ��ɂ����悤�ƍl���܂������A�V�[���h��˂��j���ăm�C�Y����邩���m��܂���B
�Ƃ������ƂŁA���x���グ�邱�Ƃ́A���E���A���Ƃ������܂��B
���������A�E�}�����K�v������܂����A
�Ȃ̂ŁA900nm�ȏ�̒����ԊO�̂ݒʂ�������W���[���Ƃ���K�v�����邩���ł����A
(900�`960�͑��z������Ⴂ���ۂ���900�̓t�B���^�A960�̓t�H�gDi���̌��E)
�Ƃ肠�����A�����₷�������ł���Ă������Ǝv���܂��B
���Ƃ́A����Ȃ�H�v���K�v�����ł��ˁB
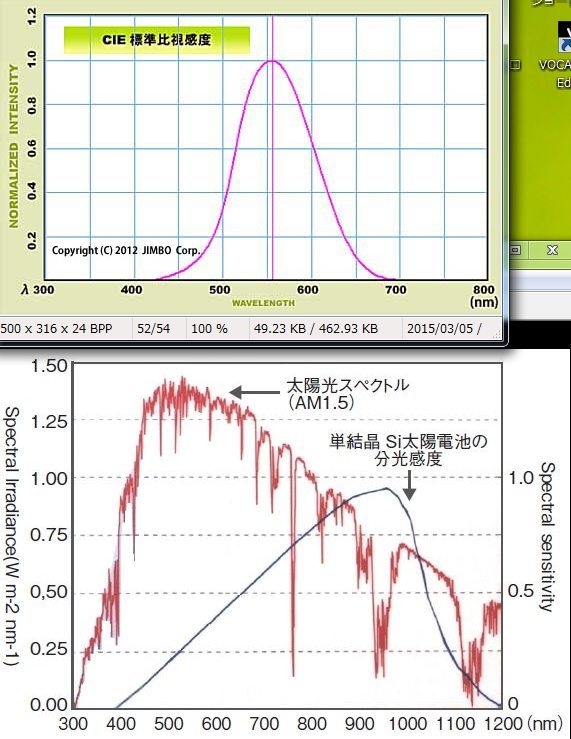 �ł����āALD�͍ēxAPC��H�����̂������ȁ[�A�Ƃ������܂��̂ŁA
��H�����ǂ��āA�l���Ă݂邱�Ƃɂ��āA
�ȈՔ�ACC��H�ɂ��쓮�ŁA�]���������o���邩�ȁ[�A�Ǝv���Ă���܂��B
LED�����́A�Ĕz������̂ł����A
�������Ȃ���l���Ă�����c�A
-------------------------------------------------------------------------------------------------
15/04/14
�o�[�`�����V���[�e�B���O���b�N�I�����A
�I�[�N�V������3100�~�ōw���B������5000�~��Ȃ̂ŁA���߁B
�ł����āALD�͍ēxAPC��H�����̂������ȁ[�A�Ƃ������܂��̂ŁA
��H�����ǂ��āA�l���Ă݂邱�Ƃɂ��āA
�ȈՔ�ACC��H�ɂ��쓮�ŁA�]���������o���邩�ȁ[�A�Ǝv���Ă���܂��B
LED�����́A�Ĕz������̂ł����A
�������Ȃ���l���Ă�����c�A
-------------------------------------------------------------------------------------------------
15/04/14
�o�[�`�����V���[�e�B���O���b�N�I�����A
�I�[�N�V������3100�~�ōw���B������5000�~��Ȃ̂ŁA���߁B
 ������Ƃ������U�����郌���Y�̂悤�ȃ��m�̒��ɁB
�ԊO�������R�����W���[�����X���ē���Ă܂����B
�^��납��̍U���͕s�ł��ˁB
������Ƃ������U�����郌���Y�̂悤�ȃ��m�̒��ɁB
�ԊO�������R�����W���[�����X���ē���Ă܂����B
�^��납��̍U���͕s�ł��ˁB
 �����ł����A�l�W�����̂����������ł��B
�O���b�v�́A����₷���ł����A�X�������Ă�̂ŁA���ʂ�_���Ƃ��ł��������Ƌꂵ���ł��B
�Ȃ����A�����Y��ɂ������ȍi�肪
���͉���LED�B���������͋@�\�͖����^�_�̏���̂悤�ł��B
�����ł����A�l�W�����̂����������ł��B
�O���b�v�́A����₷���ł����A�X�������Ă�̂ŁA���ʂ�_���Ƃ��ł��������Ƌꂵ���ł��B
�Ȃ����A�����Y��ɂ������ȍi�肪
���͉���LED�B���������͋@�\�͖����^�_�̏���̂悤�ł��B
 ���͂���Ȋ����ł��B
�����`�b�v�ł��ˁB��������A���ʉ����o����f�W�^���ȋ@�\���g�ݍ��܂�Ă���܂��B
SEGA�͔����̐v���o����Ǝv���܂��̂Ń\�R�͋��݂ł��ˁB
���͂���Ȋ����ł��B
�����`�b�v�ł��ˁB��������A���ʉ����o����f�W�^���ȋ@�\���g�ݍ��܂�Ă���܂��B
SEGA�͔����̐v���o����Ǝv���܂��̂Ń\�R�͋��݂ł��ˁB
 ��5mm�ԊOLED�ˍ��̃R�[���˃����Y�ˍi��
�œ_����4cm���x�A
��5mm�ԊOLED�ˍ��̃R�[���˃����Y�ˍi��
�œ_����4cm���x�A
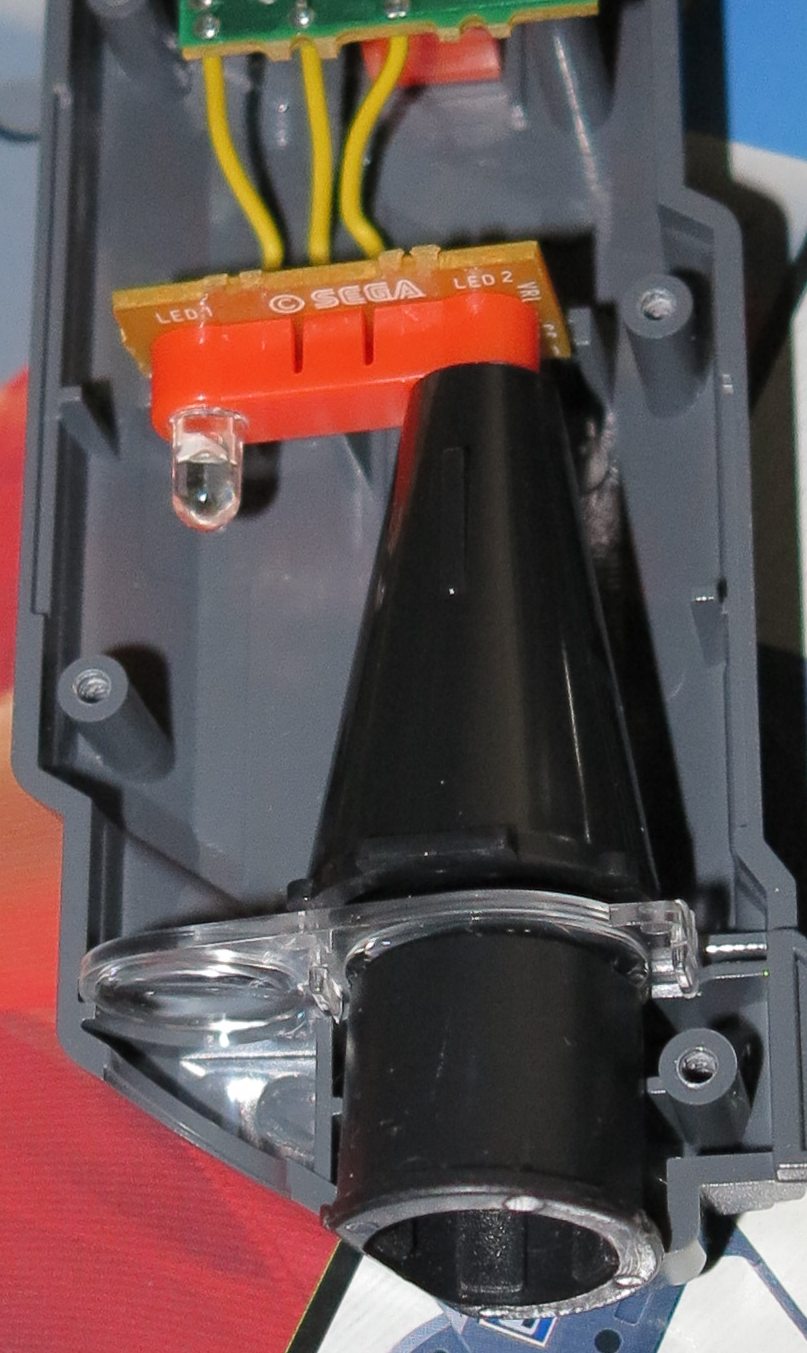
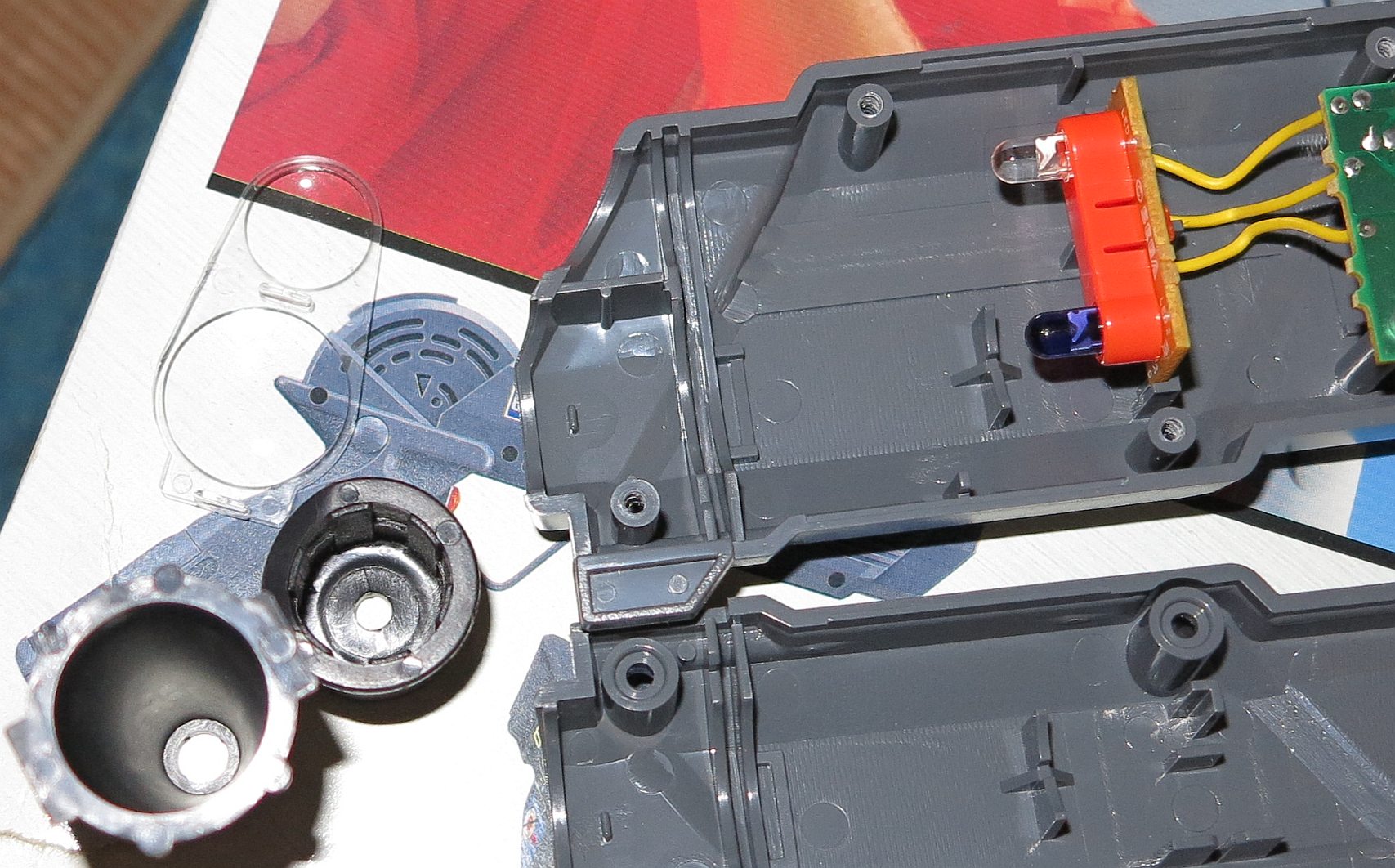 3m�ʂ̋����Ō����Ă݂܂������A����͗\�z�O�ɑ����ɊÂ��ł��B
�����Ȃ�Ες��ł��傤���A�Ȃɂ��A5mmLED�ŏœ_����4cm������w�I�ɂ��Â��ł���ˁB
�ˌ��̘r�������̂ł͖����A�Q�[���헪���y���ލ��̂悤�ł��B
���̉~�����������ɂ͐���Ȃ��Ǝv���܂��B
������ŁA�֕��̂悤�ȕ\�ʂ��A�i�������ׂ������ɂ��āA
�܂��A
���j�b�g�����ɕt���āA�}�Y���܂ł̋������Ƃ�Ƃ悢�C�����܂����B
���肶�Ⴝ���ւ�ł����A�v���X�`�b�N���`�p�[�c�Ȃ���Ȃ��ł��ˁB
����������ƒ��ׂĂ݂����ł��B
���ɁA
�^�J���@�T�o�C�o�[�V���b�g�@���{���u
�Ƃ����̂�����܂����A
�œ_�����͔{�߂��ł��B
�������A�˒������͂��Ȃ�Z���悤�ł��B
���Ł@�s�k�m�Q�R�R�ƌ������āA
LED�����P�x�����Ĕ��̓Z�K���b�N�I���̂��傢��Ƃ������炢�ł��܂�ς�炸�B
�����A�����e�́A
���P�x�ł��邱�ƂƁA���p�ł��邱�ƁA�I�[�o�[�h���C�u�����邱�ƁA
�����Y�ł��܂��܂Ƃ߂邱�ƁB��{�I�Ɍa�͑傫�������L���B
�����āA�������E�}���폜���邱�ƁB
���d�v���Ǝv���܂��B
����LED�n���ɂ����ꡂ��ɂ��̂��Ռ��̎������I�H
------------------------------------------------------------------------------------------------------
SMG��A�T���g���C�t���ւ�
���w�n���l���Ă݂܂����B
3m�ʂ̋����Ō����Ă݂܂������A����͗\�z�O�ɑ����ɊÂ��ł��B
�����Ȃ�Ες��ł��傤���A�Ȃɂ��A5mmLED�ŏœ_����4cm������w�I�ɂ��Â��ł���ˁB
�ˌ��̘r�������̂ł͖����A�Q�[���헪���y���ލ��̂悤�ł��B
���̉~�����������ɂ͐���Ȃ��Ǝv���܂��B
������ŁA�֕��̂悤�ȕ\�ʂ��A�i�������ׂ������ɂ��āA
�܂��A
���j�b�g�����ɕt���āA�}�Y���܂ł̋������Ƃ�Ƃ悢�C�����܂����B
���肶�Ⴝ���ւ�ł����A�v���X�`�b�N���`�p�[�c�Ȃ���Ȃ��ł��ˁB
����������ƒ��ׂĂ݂����ł��B
���ɁA
�^�J���@�T�o�C�o�[�V���b�g�@���{���u
�Ƃ����̂�����܂����A
�œ_�����͔{�߂��ł��B
�������A�˒������͂��Ȃ�Z���悤�ł��B
���Ł@�s�k�m�Q�R�R�ƌ������āA
LED�����P�x�����Ĕ��̓Z�K���b�N�I���̂��傢��Ƃ������炢�ł��܂�ς�炸�B
�����A�����e�́A
���P�x�ł��邱�ƂƁA���p�ł��邱�ƁA�I�[�o�[�h���C�u�����邱�ƁA
�����Y�ł��܂��܂Ƃ߂邱�ƁB��{�I�Ɍa�͑傫�������L���B
�����āA�������E�}���폜���邱�ƁB
���d�v���Ǝv���܂��B
����LED�n���ɂ����ꡂ��ɂ��̂��Ռ��̎������I�H
------------------------------------------------------------------------------------------------------
SMG��A�T���g���C�t���ւ�
���w�n���l���Ă݂܂����B
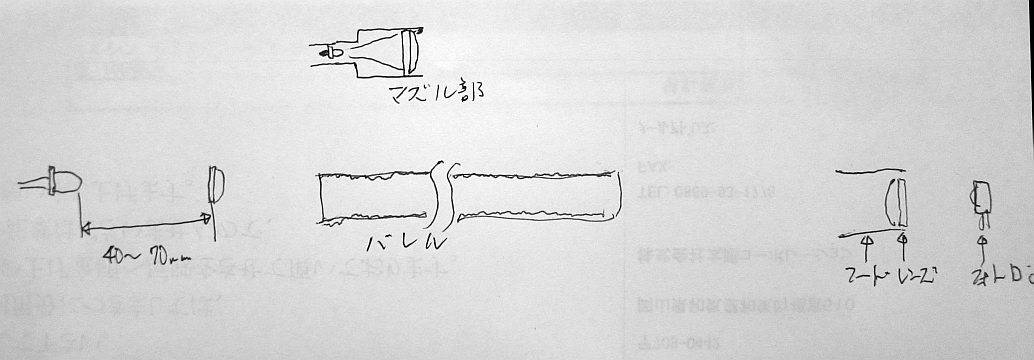 ��̐}�́A�e�̐�[�����ɐݒu�B
�˒������͒����Ȃ肻���ł����A�i���t���Ă�����͊Â��Ȃ肻���ł��B
�Ȃ�ׂ��_�����ŃT�C�����T�[�Ȃ�}�V�����B
���͖̂���Ǝv���܂��B
�����A�˒��́A�C���C���H�v���Ă�100m�s��������܂���B
�P���ɖ]�����̌��H�Ƌt�ƍl����Ƃ����Ȃ�܂��B
��̐}�́A�e�̐�[�����ɐݒu�B
�˒������͒����Ȃ肻���ł����A�i���t���Ă�����͊Â��Ȃ肻���ł��B
�Ȃ�ׂ��_�����ŃT�C�����T�[�Ȃ�}�V�����B
���͖̂���Ǝv���܂��B
�����A�˒��́A�C���C���H�v���Ă�100m�s��������܂���B
�P���ɖ]�����̌��H�Ƌt�ƍl����Ƃ����Ȃ�܂��B
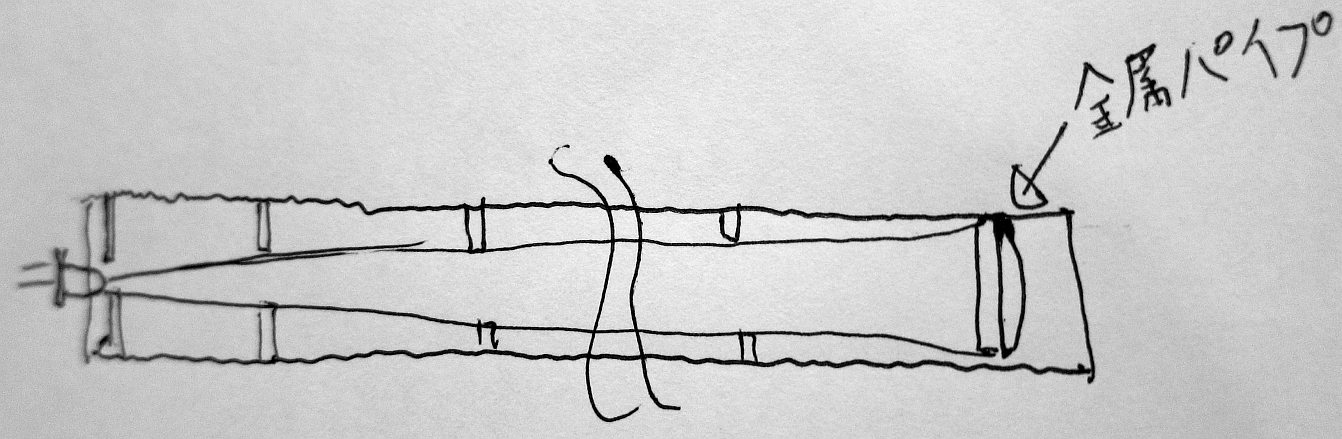 �o����������������ŁA�i����t���܂��B
�o�����́A���a��傫�����������̂ɋ������]�܂����ł��ˁB
�p���[LED���g�����́A�L���肷���Ȃ̂ŁA����Ɍa6mm���炢�̒P�œ_���g���Č��������p�x�Ɏ���������ƃC�C�ł��傤�B
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
�Ɩ��p�̐ԊO�����R���̋����ׂ��o��
�O��A���B�����͍ō��Ǝv����
�u�o�[�`�����V���[�e�B���O���b�N�I���v
�����Ă݂��̂ł����A
���ɁANEC�̃����R���Ȃ̂ł����A
�o����������������ŁA�i����t���܂��B
�o�����́A���a��傫�����������̂ɋ������]�܂����ł��ˁB
�p���[LED���g�����́A�L���肷���Ȃ̂ŁA����Ɍa6mm���炢�̒P�œ_���g���Č��������p�x�Ɏ���������ƃC�C�ł��傤�B
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
�Ɩ��p�̐ԊO�����R���̋����ׂ��o��
�O��A���B�����͍ō��Ǝv����
�u�o�[�`�����V���[�e�B���O���b�N�I���v
�����Ă݂��̂ł����A
���ɁANEC�̃����R���Ȃ̂ł����A
 ���ꂪ�A
�ُ�ɋ����M�����o���̂ŁA�������Ă݂���A
850nm��LED�Ɍ������Ă݂āA���Ԃł������Ă�̂��n�b�L������̂ł��B
�Ȃ�ƁA���g��LED�ł������Ɍ����Ă���̂�940nm�̂悤�������̂ł��B
940nm�̓p���[LED�ł�����̈�Ȃ̂ł����c�B
���ꂪ������قǂ̃h���C�u�Ȃ̂ł��B
�o�[�`�����V���[�e�B���O���b�N�I���Ɣ�ׂāA
50cm���炢�����ă����Y�Ȃ��ł��A�o�͂͌y��10�{�ȏ�͂���܂��B
������������Ȃ̂ɂ��āA
�����Y���g���ALED�ł�1Km�����邩���ł��B���t�ɕt�߂ł͖����ɋ�J�������ł��B
�X�i�C�p�[���C�t���Ƃ���ƁA�����Y�a��2cm�ȉ��ŁA���œ_���]�܂����ł��ˁB
�V�O�}���@�ɂ́A2cm��200mm�����E�̂悤�ł����B
���o�͂̃�5mm��IR��LED�́A��i100mW/Sr���܂����A
(TLN233�@100mW/Sr�@@50mA)
3mm�̂ł����̔����キ�炢�̏o�͂̂�����܂��B
10mSec�ȉ��Ńf���[�e�B�[��1����10�{�̓d����������Ƃ�����̂ł����A
�f���[�e�B�[��������ėL�Ӌ`�Ɏ������ɂ́A
臒l�ȉ��̊O�����J�b�g���Ă���łȂ��ƈӖ��������ł��ˁB
�������A
�f���[�e�B�[��50���ł��A
6�{�Ƃ�OK�Ȃ̂́A�A���I�Ƀp���X���o���Ă���̂ł͖����A
600��Sec�Ƃ����Z�����Ԃ��Ƃ������Ƃ�����悤�ł��B
������������
�ł����āA������H��v���Ȃ����܂����B
���ꂪ�A
�ُ�ɋ����M�����o���̂ŁA�������Ă݂���A
850nm��LED�Ɍ������Ă݂āA���Ԃł������Ă�̂��n�b�L������̂ł��B
�Ȃ�ƁA���g��LED�ł������Ɍ����Ă���̂�940nm�̂悤�������̂ł��B
940nm�̓p���[LED�ł�����̈�Ȃ̂ł����c�B
���ꂪ������قǂ̃h���C�u�Ȃ̂ł��B
�o�[�`�����V���[�e�B���O���b�N�I���Ɣ�ׂāA
50cm���炢�����ă����Y�Ȃ��ł��A�o�͂͌y��10�{�ȏ�͂���܂��B
������������Ȃ̂ɂ��āA
�����Y���g���ALED�ł�1Km�����邩���ł��B���t�ɕt�߂ł͖����ɋ�J�������ł��B
�X�i�C�p�[���C�t���Ƃ���ƁA�����Y�a��2cm�ȉ��ŁA���œ_���]�܂����ł��ˁB
�V�O�}���@�ɂ́A2cm��200mm�����E�̂悤�ł����B
���o�͂̃�5mm��IR��LED�́A��i100mW/Sr���܂����A
(TLN233�@100mW/Sr�@@50mA)
3mm�̂ł����̔����キ�炢�̏o�͂̂�����܂��B
10mSec�ȉ��Ńf���[�e�B�[��1����10�{�̓d����������Ƃ�����̂ł����A
�f���[�e�B�[��������ėL�Ӌ`�Ɏ������ɂ́A
臒l�ȉ��̊O�����J�b�g���Ă���łȂ��ƈӖ��������ł��ˁB
�������A
�f���[�e�B�[��50���ł��A
6�{�Ƃ�OK�Ȃ̂́A�A���I�Ƀp���X���o���Ă���̂ł͖����A
600��Sec�Ƃ����Z�����Ԃ��Ƃ������Ƃ�����悤�ł��B
������������
�ł����āA������H��v���Ȃ����܂����B
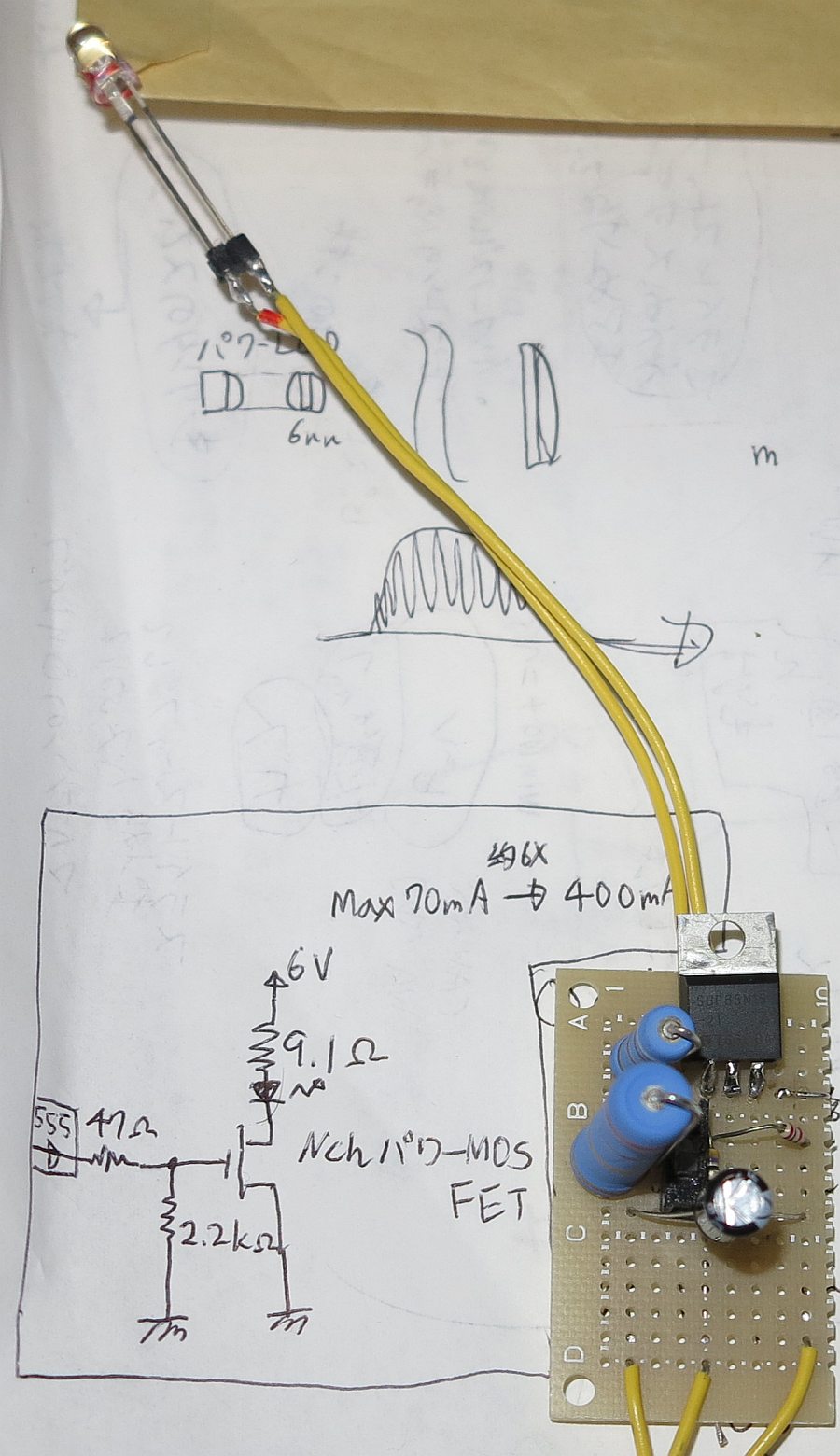 �ʏ��NPN�g�����W�X�^�����ƁA�h���C�u�s���ɂȂ肩�˂Ȃ��̈�ł��̂ŁA
�p���[MOS-FET���g�p���Ă���܂��B
����ŁA�Ɩ��p�����R���Ɠ����ʂ̏o�͂ɂȂ�܂��B
��R�̓����V���b�g�̃p���X���U�Ȃ�A1/4W�^�C�v�ł����Ȃ������ł��B
FET��ON-OFF�ł��̂ŁA�w�ǔ��M���܂���B
�Ȃ̂ɁA
��R��FET����e�ʂȘA�������d�l�Ȃ̂́A
��R�́A�����P�i�ōw���ł���̂�����ȃT�C�Y�������̂Łc�A
FET�͂��荇�킹�������̂����R�Ȃ̂ł����A
�܂��A�����܂ł͂��Ȃ����Ă��A���i����Ȃ����S���ɂ͒u���Ă����������ǂ��ł��B
47���̓o�C�|�[���[Tr�̂Ƃ��̖��c�ł��̂ŗv��Ȃ��Ǝv���܂��B
��ւ�SW�ɂāA�p���[LED�ɂ��ꉞ�̑Ή��ł��B
3W�^�p���[LED�̏ꍇ�A6A�Ƃ��K�v�ł��̂ŁA
�����ƒ�R��Ⴍ���āA�d���R���f���T�[�̗e�ʂ����₳�˂ł��B
LED�ւ̃P�[�u�����������肵�����m�ɁB
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
���܂ŁA����̎�����j�b�g���g���Ă܂������A
�ꉞ�A�����i���`�F�b�N�ł��B
�蓖���莟��W�߂Ă݂܂����B
����ɍX�Ƀt�[�h����Y��t����A�����Ɗ��xUP���_���܂��B
�ʏ��NPN�g�����W�X�^�����ƁA�h���C�u�s���ɂȂ肩�˂Ȃ��̈�ł��̂ŁA
�p���[MOS-FET���g�p���Ă���܂��B
����ŁA�Ɩ��p�����R���Ɠ����ʂ̏o�͂ɂȂ�܂��B
��R�̓����V���b�g�̃p���X���U�Ȃ�A1/4W�^�C�v�ł����Ȃ������ł��B
FET��ON-OFF�ł��̂ŁA�w�ǔ��M���܂���B
�Ȃ̂ɁA
��R��FET����e�ʂȘA�������d�l�Ȃ̂́A
��R�́A�����P�i�ōw���ł���̂�����ȃT�C�Y�������̂Łc�A
FET�͂��荇�킹�������̂����R�Ȃ̂ł����A
�܂��A�����܂ł͂��Ȃ����Ă��A���i����Ȃ����S���ɂ͒u���Ă����������ǂ��ł��B
47���̓o�C�|�[���[Tr�̂Ƃ��̖��c�ł��̂ŗv��Ȃ��Ǝv���܂��B
��ւ�SW�ɂāA�p���[LED�ɂ��ꉞ�̑Ή��ł��B
3W�^�p���[LED�̏ꍇ�A6A�Ƃ��K�v�ł��̂ŁA
�����ƒ�R��Ⴍ���āA�d���R���f���T�[�̗e�ʂ����₳�˂ł��B
LED�ւ̃P�[�u�����������肵�����m�ɁB
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
���܂ŁA����̎�����j�b�g���g���Ă܂������A
�ꉞ�A�����i���`�F�b�N�ł��B
�蓖���莟��W�߂Ă݂܂����B
����ɍX�Ƀt�[�h����Y��t����A�����Ɗ��xUP���_���܂��B
 �ŁA�摜�̂���Ԋ��x�����������i�Ǝv���A
�����Y���܂��C�C�����ł��A
�ŁA�摜�̂���Ԋ��x�����������i�Ǝv���A
�����Y���܂��C�C�����ł��A
 �̏W�߂������̎�����j�b�g�ł��B
��H���t���Ă�̂́A�����̃t�H�g�_�C�I�[�h�Ɍ������Ă���܂��B
�̏W�߂������̎�����j�b�g�ł��B
��H���t���Ă�̂́A�����̃t�H�g�_�C�I�[�h�Ɍ������Ă���܂��B
 �Ƃ肠�����A��쓮�͋N����܂���B
AGC��H���t���Ă�͕̂ʂƂ��Ă��A
600��Sec�̎��Ԃ̒��������Ă��邱�Ƃ�A���U��H��Q�l�AHPF�����ǂ���Ă�Ǝv���܂��B
����ASNS�ɂā��̂悤�ȃR�~���j�e�B�[�����邱�Ƃ��Љ��܂����B
�ꉞ�Q�����Ă݂܂����ł��B
�ŁA�Љ�ꂽ���悪������j�b�g�̐��삾�����̂ŁA������Q�l�ɁA
�܂��A
������j�b�g����̐M�����R���f���T�[�Őϕ����āA
�g�����W�X�^�ő�������̂ŁA���ɊȒP�ȉ�H�ŁA�ʔ������肩��������悤�ł��B
15/04/23
�ŁA
����Č��܂����B
�Ƃ肠�����A��쓮�͋N����܂���B
AGC��H���t���Ă�͕̂ʂƂ��Ă��A
600��Sec�̎��Ԃ̒��������Ă��邱�Ƃ�A���U��H��Q�l�AHPF�����ǂ���Ă�Ǝv���܂��B
����ASNS�ɂā��̂悤�ȃR�~���j�e�B�[�����邱�Ƃ��Љ��܂����B
�ꉞ�Q�����Ă݂܂����ł��B
�ŁA�Љ�ꂽ���悪������j�b�g�̐��삾�����̂ŁA������Q�l�ɁA
�܂��A
������j�b�g����̐M�����R���f���T�[�Őϕ����āA
�g�����W�X�^�ő�������̂ŁA���ɊȒP�ȉ�H�ŁA�ʔ������肩��������悤�ł��B
15/04/23
�ŁA
����Č��܂����B
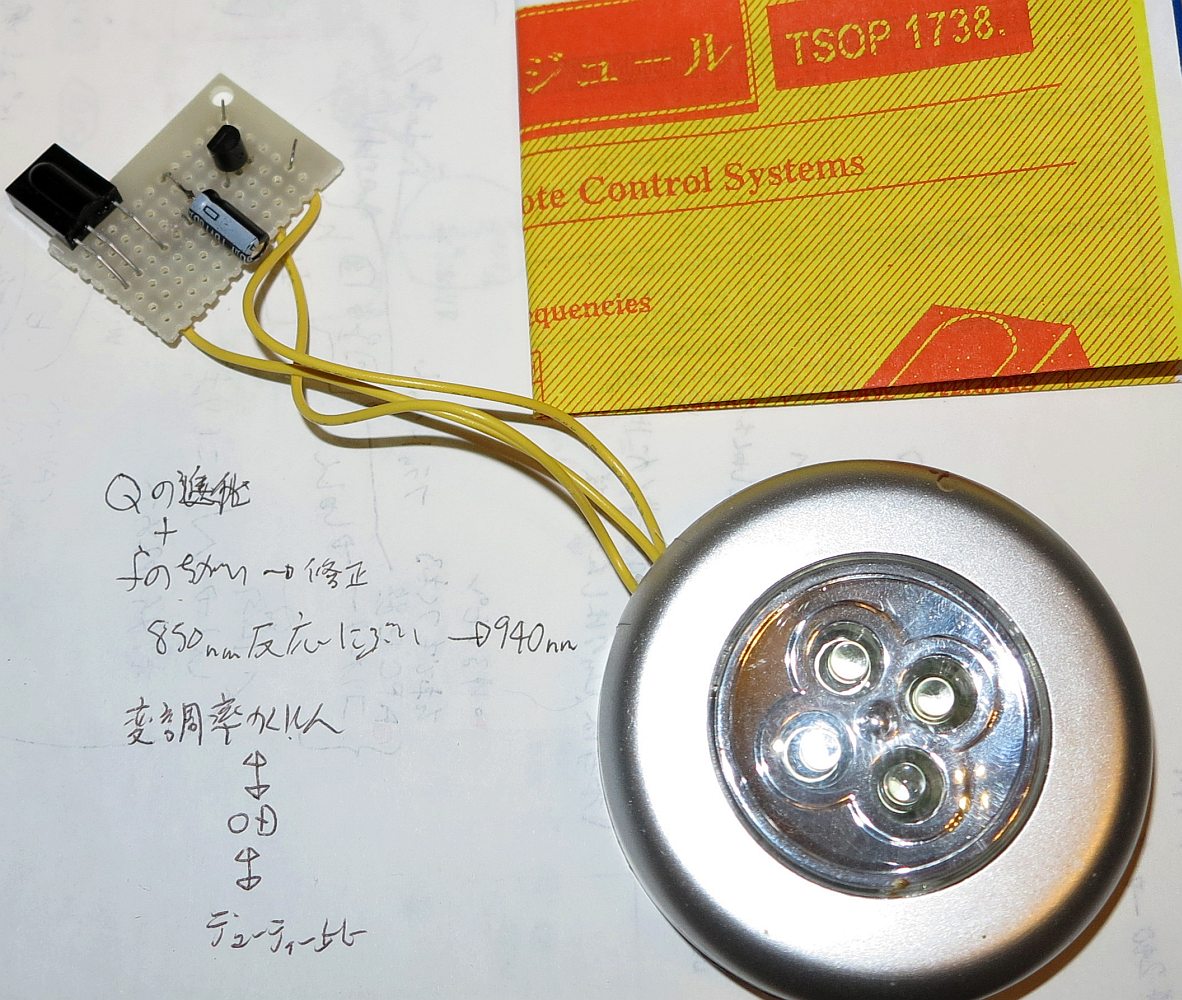 ���i�͂��ׂĂ��荇�킹�Ȃ̂ŁA
Tr��2SA1015�ł��B���C�g�͒n��������Ƃ��Ă��܂����B
���Ȃ�܂Ԃ����ł��B
��̎ʐ^�ł́ATSOP1738��t���Ă�̂ł����A
TSOP38238�̕������x������(�Œ���ˌ����x�FMinimum irradiance���Ⴂ)�ł��B
������LED�ł�45m�Ƃ������ƂŁA�������Ƀ����Y��t������Ȃ�̃��m�Ǝv���܂��B
��҂̕������Ȃ�ʏ������̂ɍ����x�ł��B
���R�́A�����炭�A��������Y���ȁ[�Ǝv���Ă���܂��B
����Ȃ�A������̃����Y��ς����(�lj������)OK�ł��ˁB
�ŁA
�ꉞ�������܂����B
���i�͂��ׂĂ��荇�킹�Ȃ̂ŁA
Tr��2SA1015�ł��B���C�g�͒n��������Ƃ��Ă��܂����B
���Ȃ�܂Ԃ����ł��B
��̎ʐ^�ł́ATSOP1738��t���Ă�̂ł����A
TSOP38238�̕������x������(�Œ���ˌ����x�FMinimum irradiance���Ⴂ)�ł��B
������LED�ł�45m�Ƃ������ƂŁA�������Ƀ����Y��t������Ȃ�̃��m�Ǝv���܂��B
��҂̕������Ȃ�ʏ������̂ɍ����x�ł��B
���R�́A�����炭�A��������Y���ȁ[�Ǝv���Ă���܂��B
����Ȃ�A������̃����Y��ς����(�lj������)OK�ł��ˁB
�ŁA
�ꉞ�������܂����B
 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
���܂ŁA�n���h�K���ɓ���邽�߁A�������Ⴍ�Ƃ��l���Ă��̂ł����A
SMG��C�t���Ȃ�]�T���o�Ă��܂��ˁA
�E�`�ɃA��
M4-RIS���h�L��1980�~�̒����C�t���Ƃ��ɑg�ݍ��߂�c�A
���i�J�^�C�v�́A����͂���ł߂�ǂ��Ƃ�������܂��ˁB
���C�t���ˌ��̗��������̓o�C�|�b�h�̂悤�ɏe�̊p�x�����ł͖����ł��B
�����Ȑ���͊p�x�ł͖����d�S�̕��s�ړ��ōs���Ɣ������ɂ͗ǂ��̂ł��B
�o�����́A�\�[�R���T�C�����T�[���h�L���t���Ă���������܂�Ă��̂ł����A
�S�ɃX�e�����XSUS304�������t�����|�[�����o�����Ƃ��܂����B
���ɍi����������A�����Y�̓T�C�����T�[��[�ɕt���܂��B
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
���܂ŁA�n���h�K���ɓ���邽�߁A�������Ⴍ�Ƃ��l���Ă��̂ł����A
SMG��C�t���Ȃ�]�T���o�Ă��܂��ˁA
�E�`�ɃA��
M4-RIS���h�L��1980�~�̒����C�t���Ƃ��ɑg�ݍ��߂�c�A
���i�J�^�C�v�́A����͂���ł߂�ǂ��Ƃ�������܂��ˁB
���C�t���ˌ��̗��������̓o�C�|�b�h�̂悤�ɏe�̊p�x�����ł͖����ł��B
�����Ȑ���͊p�x�ł͖����d�S�̕��s�ړ��ōs���Ɣ������ɂ͗ǂ��̂ł��B
�o�����́A�\�[�R���T�C�����T�[���h�L���t���Ă���������܂�Ă��̂ł����A
�S�ɃX�e�����XSUS304�������t�����|�[�����o�����Ƃ��܂����B
���ɍi����������A�����Y�̓T�C�����T�[��[�ɕt���܂��B
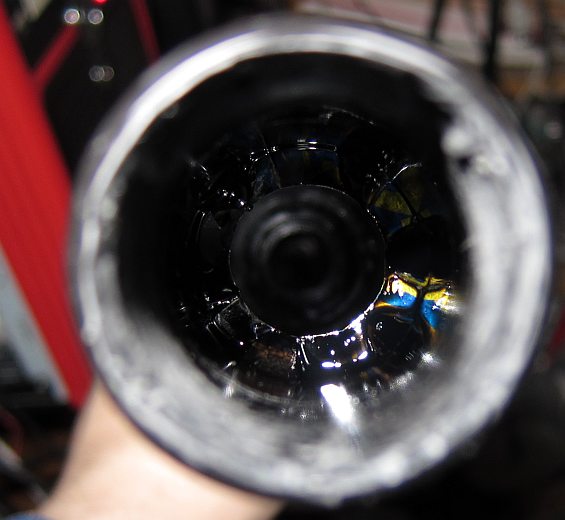 �������āA��������ʂ��A�ڒ��܂ŌŒ�B
�X�R�[�v�p�̃��[�������S�~���������ƁA
�������āA��������ʂ��A�ڒ��܂ŌŒ�B
�X�R�[�v�p�̃��[�������S�~���������ƁA

 �{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{
4-16x�Y�[���X�R�[�v�ƃo�C�|�b�h�ɂ��Ă݂܂����B
�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{
4-16x�Y�[���X�R�[�v�ƃo�C�|�b�h�ɂ��Ă݂܂����B

 ���i�́A�������̊ϓ_����A
�Ȃ�ׂ��O�t���ł��B
������H�ւ̔z���́A�P�[�u�����G�W�F�N�V�����|�[�g����o���\��ł��B
���i�́A�������̊ϓ_����A
�Ȃ�ׂ��O�t���ł��B
������H�ւ̔z���́A�P�[�u�����G�W�F�N�V�����|�[�g����o���\��ł��B
 ���Ƃ́A
LED�Ƃ��̃h���C�u���������t���銴���ł��B
�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{
�����Y���͂��܂����B
���Ƃ́A
LED�Ƃ��̃h���C�u���������t���銴���ł��B
�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{
�����Y���͂��܂����B
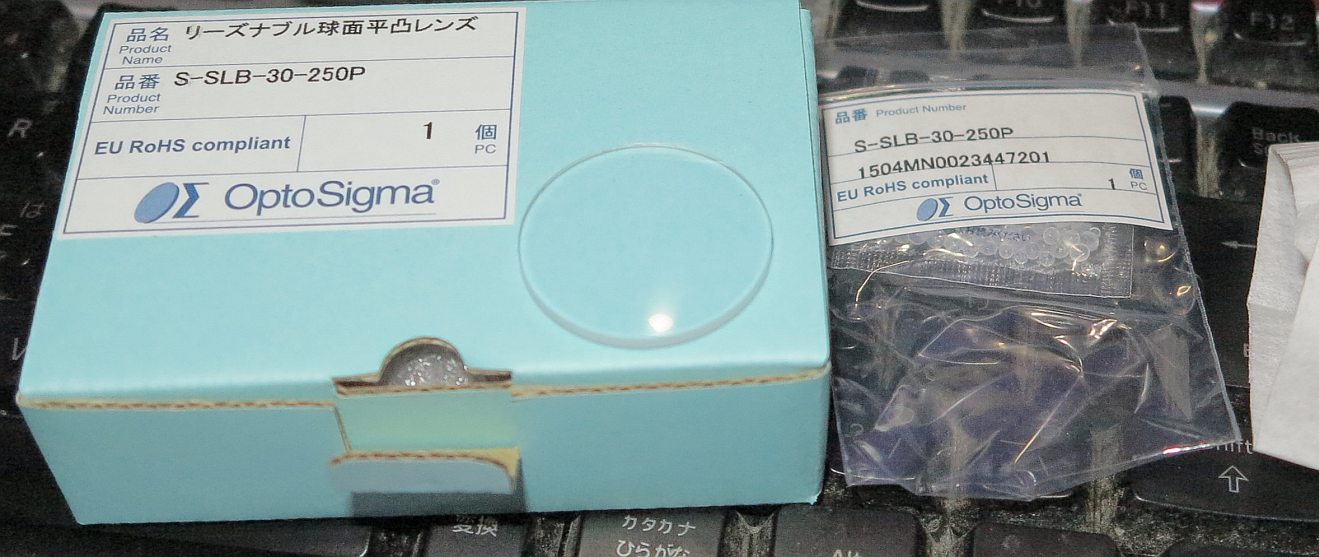 �p�C�v�����ɓ���锭�������̃}�E���g�ł��B
POM�ނŁA���Ղō���č��܂����B
�p�C�v�����ɓ���锭�������̃}�E���g�ł��B
POM�ނŁA���Ղō���č��܂����B
 �ʐ^�ł�3mm��LED���͂߂Ă܂������A5mm�ɕύX���܂����B
�ʐ^�ł�3mm��LED���͂߂Ă܂������A5mm�ɕύX���܂����B
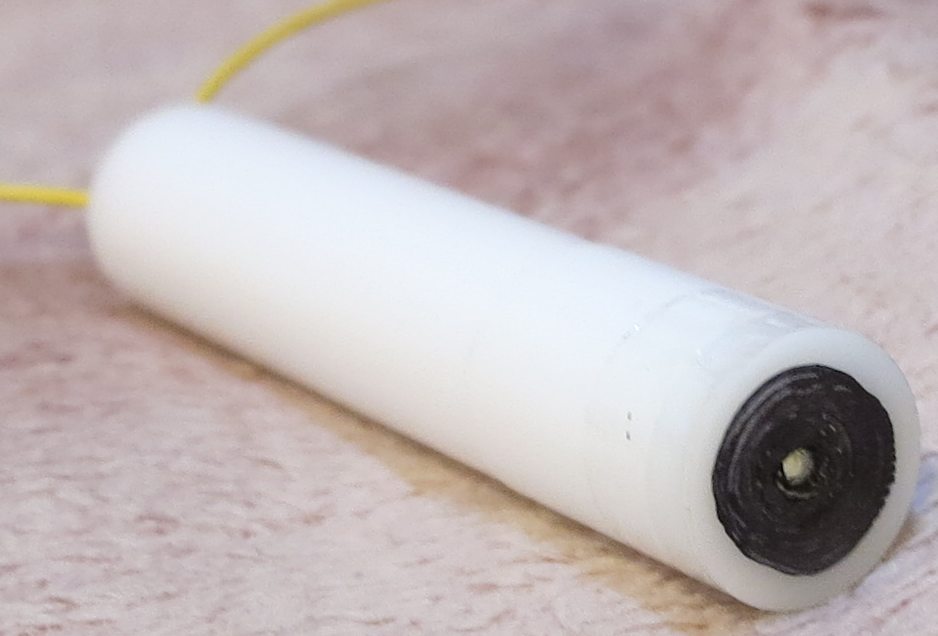 �����Y�͂���Ȋ����ŁA�z�b�g�{���h�ŌŒ肵�܂����B
�����Y�͂���Ȋ����ŁA�z�b�g�{���h�ŌŒ肵�܂����B
 �ŁA�g�ݏオ��܂����B
�ŁA�g�ݏオ��܂����B
 �ŁA�����e�̕��́A�����ɏ\���Ȃ̂͑�̏o�����̂ł����A
���́A�������e�X�g������ꏊ���Ȃ��ł��B
����������Ă����Ȃ��ƁA�X�R�[�v�̒��߂Ƃ�����ς����ł��B
���ƁALED�̃����Y�����������˂��Ă܂��̂ŁA�s���z�[����t����K�v�����肻���ł��B
����ɂ̓K�^�͖w�ǖ����ł����A������Ə�����ɕt���Ă邽�߁A
�L�������O�n���h���ƃX�R�[�v���[���}�E���g�̑O���ɔ�̃��m�����݂܂������B
�C�ɂȂ邽�߁A�擪�̃��[���Ƀ��[�U�[�T�C�g��t���܂����B
�ŁA�����e�̕��́A�����ɏ\���Ȃ̂͑�̏o�����̂ł����A
���́A�������e�X�g������ꏊ���Ȃ��ł��B
����������Ă����Ȃ��ƁA�X�R�[�v�̒��߂Ƃ�����ς����ł��B
���ƁALED�̃����Y�����������˂��Ă܂��̂ŁA�s���z�[����t����K�v�����肻���ł��B
����ɂ̓K�^�͖w�ǖ����ł����A������Ə�����ɕt���Ă邽�߁A
�L�������O�n���h���ƃX�R�[�v���[���}�E���g�̑O���ɔ�̃��m�����݂܂������B
�C�ɂȂ邽�߁A�擪�̃��[���Ƀ��[�U�[�T�C�g��t���܂����B

 ���Ƃ̓s���z�[���c�A
��
3mm�l�W�̃��b�V���[���s���z�[���ɂ��Ă݂���A���x�ǂ��悤�ł����B
�e�X�g����ɂ́A���x�ǂ��ꏊ��������Ȃ��̂ƁA
�����K���P�[�X���K�v�����ł��B
-------------------------------------------------------------------------------------
���H�ɂĊO�ϓ�ӏ��ύX�B
(�g���K�[�[�q�̃v���O���A���[�U�[�T�C�g�̐ڐG�s�ǂ������B)
���Ƃ̓s���z�[���c�A
��
3mm�l�W�̃��b�V���[���s���z�[���ɂ��Ă݂���A���x�ǂ��悤�ł����B
�e�X�g����ɂ́A���x�ǂ��ꏊ��������Ȃ��̂ƁA
�����K���P�[�X���K�v�����ł��B
-------------------------------------------------------------------------------------
���H�ɂĊO�ϓ�ӏ��ύX�B
(�g���K�[�[�q�̃v���O���A���[�U�[�T�C�g�̐ڐG�s�ǂ������B)
 -------------------------------------------------------------------------------------
����܂ł́A�����Y���傫���̂Łc�A
�����I�ɂ́A�����Y���ėL���ʐς��i���Ă��ǂ��̂ł����A
���h���ǂ���������ɂ́A
-------------------------------------------------------------------------------------
����܂ł́A�����Y���傫���̂Łc�A
�����I�ɂ́A�����Y���ėL���ʐς��i���Ă��ǂ��̂ł����A
���h���ǂ���������ɂ́A
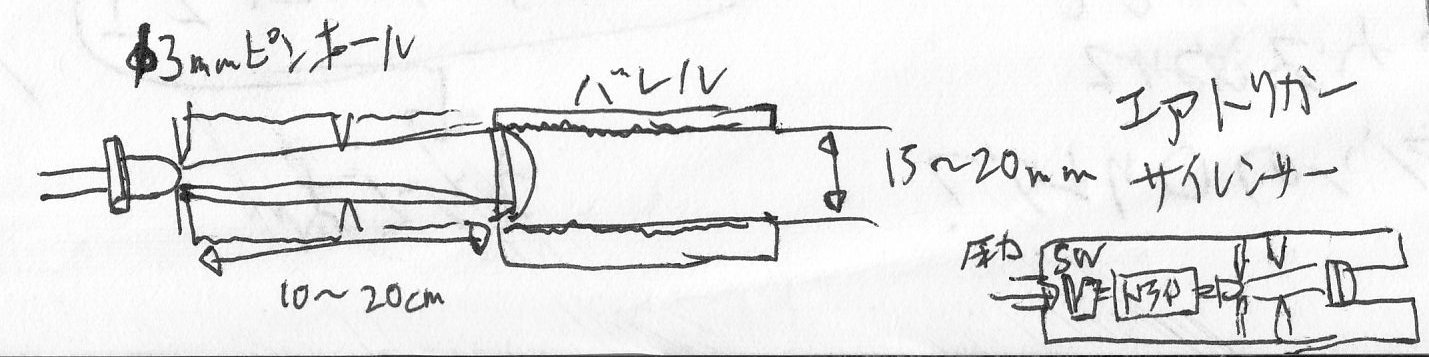 �����}
➑̓����ɓ����Ȃ�A�����Y�͏��X�傫���Ă�OK�˃�25mm�Ƃ��B
���E�}
�o������T�C�����T�[�^�C�v�́A
��20mm�ȉ��ɍi��B
�G�A�K������������ꍇ�́A����SW�݂����Ȃ̂�t���ăg���K�����O����Ƃ��C�y�B
---------------------------------
�ł����āA���܂ł́A
�e�̌`�����Ă��̂ŊO�Ńe�X�g����Ƀ��m���m���������ŁA���ꂪ�ǂ����Ă����ł������A
���ꂪ�A�^�_�̃p�C�v�ɁA�h���C�u��H�A�X�R�[�v�Ƃ����[�U�[�T�C�g���t���āA
�O�r��t���銴���Ȃ疳��Ɏv���܂����B
�����}
➑̓����ɓ����Ȃ�A�����Y�͏��X�傫���Ă�OK�˃�25mm�Ƃ��B
���E�}
�o������T�C�����T�[�^�C�v�́A
��20mm�ȉ��ɍi��B
�G�A�K������������ꍇ�́A����SW�݂����Ȃ̂�t���ăg���K�����O����Ƃ��C�y�B
---------------------------------
�ł����āA���܂ł́A
�e�̌`�����Ă��̂ŊO�Ńe�X�g����Ƀ��m���m���������ŁA���ꂪ�ǂ����Ă����ł������A
���ꂪ�A�^�_�̃p�C�v�ɁA�h���C�u��H�A�X�R�[�v�Ƃ����[�U�[�T�C�g���t���āA
�O�r��t���銴���Ȃ疳��Ɏv���܂����B
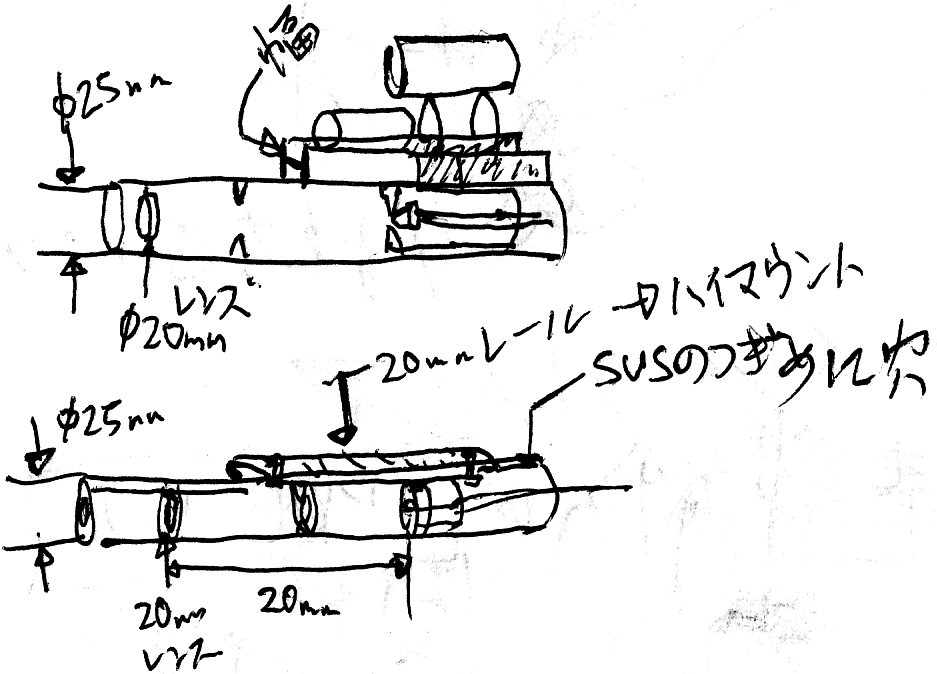 �O�����\�h�ɁA
�^�[�Q�b�g�̎�����j�b�g�́A
�X�s�[�J�[�̃G���N���[�W���[�̂悤�ȁA
���Ɋۂ������J�������m�ɓ��ꂽ�����ǂ������ł��ˁB
�ELED���̂�ǂ����m�ɁB
�E�����āA���܂��I�[�o�[�h���C�u�B
�E�����̗ǂ����w�n�B
�Ɠ˂��l�߂Ă����A�o�͂ɗ]�T�����܂�A
���̗]�T��p���ăR���p�N�g�ɂ�����A�K�x�Ɋɂ�����ɂ���āA
���������ȃQ�[���ɂ����ʓI�ɗL�Ӌ`�ɏo����悤�ɔ��W�ł���Ǝv���܂��B
�]�T������A
�����ˌ��Ȃ�A���[�U�[���A�Ƃ���������������Ǝv���܂����A
LD�̃s���̃^�C�v���C�ɂȂ�܂��̂ŁA�ǂ��������m���ł��B
������������A�O�t���̃t�H�gDi�̐ݒu�̕����ǂ������ł��ˁB
*************************************************************************************************************
�[��ŒN�����Ȃ��g�R�Ń`�F�b�N���悤�Ƃ���ɁA
�������������K���P�[�X�͍w�������̂ł����A
��͂�A�Ă̒�A�Ƒ����畨���ȃ��m�����������ȂƂ����㒅�����܂����B
��X�A�������̔������j�b�g�Ń`�F�b�N���\�肵�Ă���܂����A
�����Y�̔[����15���ȍ~�ł��̂ŁA���Ԃ������肷����̂ŁA
�Ƃ肠�����A�����ő��肷�邽�߂ɁA
�s�{�ӂȂ���A���\������ND-100��ND-500�̌����t�B���^�[�𒍕��v���܂����B��6000�~����
�ŁA�ڕ��ʂƂ��ẮA������2�敪��1�Ō�����܂�Ƃ��������ł��B
�t�H�[�J�X�Ȃǂ̖�肪����덷�ɂȂ���R�g�����邩���A�Ƃ��v���܂����A���p���t�H�[�J�X�̈�I�ɂ͖������Ƃ��Ǝv���܂��B
�_�����Â��Ȃ邩������Ȃ��ł��̂ŁA�X�R�[�v�̐ݒ肪�y�ɂȂ邩���m��܂���B���l���Ă݂�Ίp�x�ˑ��Ȃ̂ł����������Ƃ͂Ȃ������ł��ˁB
�ł����A�Ƃ肠��������ōs���čs�����Ǝv���܂��B
*********
�ŁA��Ԃ̑���́A�X�R�[�v�̃��e�B�N��������Ȃ��Ɓc
�ƁA�����X�R�[�v���w�������̂ł����A�����̓��
����ρA�l�i�̊��ɂ̓}�V�Ƃ��Ă��A
�������m�͎g�����肪���܂�ǂ��Ȃ��ł��B
�O�����\�h�ɁA
�^�[�Q�b�g�̎�����j�b�g�́A
�X�s�[�J�[�̃G���N���[�W���[�̂悤�ȁA
���Ɋۂ������J�������m�ɓ��ꂽ�����ǂ������ł��ˁB
�ELED���̂�ǂ����m�ɁB
�E�����āA���܂��I�[�o�[�h���C�u�B
�E�����̗ǂ����w�n�B
�Ɠ˂��l�߂Ă����A�o�͂ɗ]�T�����܂�A
���̗]�T��p���ăR���p�N�g�ɂ�����A�K�x�Ɋɂ�����ɂ���āA
���������ȃQ�[���ɂ����ʓI�ɗL�Ӌ`�ɏo����悤�ɔ��W�ł���Ǝv���܂��B
�]�T������A
�����ˌ��Ȃ�A���[�U�[���A�Ƃ���������������Ǝv���܂����A
LD�̃s���̃^�C�v���C�ɂȂ�܂��̂ŁA�ǂ��������m���ł��B
������������A�O�t���̃t�H�gDi�̐ݒu�̕����ǂ������ł��ˁB
*************************************************************************************************************
�[��ŒN�����Ȃ��g�R�Ń`�F�b�N���悤�Ƃ���ɁA
�������������K���P�[�X�͍w�������̂ł����A
��͂�A�Ă̒�A�Ƒ����畨���ȃ��m�����������ȂƂ����㒅�����܂����B
��X�A�������̔������j�b�g�Ń`�F�b�N���\�肵�Ă���܂����A
�����Y�̔[����15���ȍ~�ł��̂ŁA���Ԃ������肷����̂ŁA
�Ƃ肠�����A�����ő��肷�邽�߂ɁA
�s�{�ӂȂ���A���\������ND-100��ND-500�̌����t�B���^�[�𒍕��v���܂����B��6000�~����
�ŁA�ڕ��ʂƂ��ẮA������2�敪��1�Ō�����܂�Ƃ��������ł��B
�t�H�[�J�X�Ȃǂ̖�肪����덷�ɂȂ���R�g�����邩���A�Ƃ��v���܂����A���p���t�H�[�J�X�̈�I�ɂ͖������Ƃ��Ǝv���܂��B
�_�����Â��Ȃ邩������Ȃ��ł��̂ŁA�X�R�[�v�̐ݒ肪�y�ɂȂ邩���m��܂���B���l���Ă݂�Ίp�x�ˑ��Ȃ̂ł����������Ƃ͂Ȃ������ł��ˁB
�ł����A�Ƃ肠��������ōs���čs�����Ǝv���܂��B
*********
�ŁA��Ԃ̑���́A�X�R�[�v�̃��e�B�N��������Ȃ��Ɓc
�ƁA�����X�R�[�v���w�������̂ł����A�����̓��
����ρA�l�i�̊��ɂ̓}�V�Ƃ��Ă��A
�������m�͎g�����肪���܂�ǂ��Ȃ��ł��B
 ���ɕt���郌�[���}�E���g�x�[�X�������ł��B��VSR10�p
�������₷���A�z�b�g�{���h�ł���������Ɨǂ��ł����c�A
ND(�j���[�g�����f���V�e�B�[)�t�B���^�[���͂��܂����B
���ɕt���郌�[���}�E���g�x�[�X�������ł��B��VSR10�p
�������₷���A�z�b�g�{���h�ł���������Ɨǂ��ł����c�A
ND(�j���[�g�����f���V�e�B�[)�t�B���^�[���͂��܂����B
 ��������e���ɂ�������ق��������R��ɋ����Ǝv���܂��āA���̂悤�ɂ��܂����B
��������e���ɂ�������ق��������R��ɋ����Ǝv���܂��āA���̂悤�ɂ��܂����B
 �[���̓��A�ɂāA
�O��10m�̒����̃x�����_�ŁA9m�̋����ő��肵�܂����B���e�̒���������̂ŁB
�ˌ����肪�A���̂������V�r�A�ł����A
9�~500��1/2�恁201m�Ƃ��������ł��ˁB
�܂��A200m�͔�ԂƂ����v�Z�ɂȂ�܂����B
�����R�����W���[���͊��x�̍��߂̃��m��I����ł������A
����̉����p�̎�����j�b�g�̕��������x�ł����B
���̏e��3cm�̃����Y���g���Ă���܂����A�i����i���Ă�̂ŁA����2.3�`2.6cm�ȉ��̌��a�ƂȂ�܂��B
�����Y�ɂ͐ԊO�͏œ_�����������Ȃ�v�f������A���̃s���g�̓e�L�g�[�ɍ��킹�Ă���܂��B
�܂��A
�����ƍ��o�͂̏o����(�{���炢)LED������܂��B������940nm�Ȃ�X�Ɏ�����x���A�b�v���܂��B
�܂��A�m���R�[�g�̃����Y�ł��̂�10���قǃ��X������܂��B
ND�t�B���^�[�̓R�[�e�B���O����Ă���܂����A�ԊO�p�ł͂Ȃ��ł��̂ŁA��̓��X���A�������ł��B
�œ_������Z������A�W���ʂ������肻�̕��^�[�Q�b�g�ւ̌����L����Ƃ͎v���܂����c�A���͊W����̂��ł��ˁ`
�Ƃ������ƂŁA�����I�ɂ͂܂��˒������͐L����悤�ł��B
���A�\�R�ɂǂ�قLjӖ�������̂��͕s���ł��ˁB
�܂��A����ȏ�̓��[�U�[���g���������L�������m��܂���B
�ł����āA
�����ň�U�����e�͂܂Ƃ܂������������܂��B
�~���p�C�v�̔������j�b�g�̕]�������ƁA
���[�U�[��APC��H�̏ڍׂ��c���Ă܂����A
�NjL��
���́A250mm�����Y���ƁA10m��2�`3cm�̍L����̂悤�ł����A
�������ɂȂ�ƍX�ɋ��܂��āA100m�ł�10cm���s���Ȃ��悤�ȋC�����܂��B�������Č����Ȃ��ᓖ����Ȃ��B
�������A���Ԃ̓��A�ł́A�o�C�A�X�d���s���̊W�Ŋ��x��������X�ɃV�r�A�ɂȂ�܂��B
�����Y�̏œ_�����͏��Ȃ��Ƃ��A7�`8cm���炢�ɂ�����������ȋC�����܂����B
�܂��A��������A�t�[�h��t���āA�M���M����6V�쓮���ǂ��Ǝv���܂��B
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1
���x�̓�20mm��F=100mm�̃����Y�Ń`�F�b�N�ł��B
�[���̓��A�ɂāA
�O��10m�̒����̃x�����_�ŁA9m�̋����ő��肵�܂����B���e�̒���������̂ŁB
�ˌ����肪�A���̂������V�r�A�ł����A
9�~500��1/2�恁201m�Ƃ��������ł��ˁB
�܂��A200m�͔�ԂƂ����v�Z�ɂȂ�܂����B
�����R�����W���[���͊��x�̍��߂̃��m��I����ł������A
����̉����p�̎�����j�b�g�̕��������x�ł����B
���̏e��3cm�̃����Y���g���Ă���܂����A�i����i���Ă�̂ŁA����2.3�`2.6cm�ȉ��̌��a�ƂȂ�܂��B
�����Y�ɂ͐ԊO�͏œ_�����������Ȃ�v�f������A���̃s���g�̓e�L�g�[�ɍ��킹�Ă���܂��B
�܂��A
�����ƍ��o�͂̏o����(�{���炢)LED������܂��B������940nm�Ȃ�X�Ɏ�����x���A�b�v���܂��B
�܂��A�m���R�[�g�̃����Y�ł��̂�10���قǃ��X������܂��B
ND�t�B���^�[�̓R�[�e�B���O����Ă���܂����A�ԊO�p�ł͂Ȃ��ł��̂ŁA��̓��X���A�������ł��B
�œ_������Z������A�W���ʂ������肻�̕��^�[�Q�b�g�ւ̌����L����Ƃ͎v���܂����c�A���͊W����̂��ł��ˁ`
�Ƃ������ƂŁA�����I�ɂ͂܂��˒������͐L����悤�ł��B
���A�\�R�ɂǂ�قLjӖ�������̂��͕s���ł��ˁB
�܂��A����ȏ�̓��[�U�[���g���������L�������m��܂���B
�ł����āA
�����ň�U�����e�͂܂Ƃ܂������������܂��B
�~���p�C�v�̔������j�b�g�̕]�������ƁA
���[�U�[��APC��H�̏ڍׂ��c���Ă܂����A
�NjL��
���́A250mm�����Y���ƁA10m��2�`3cm�̍L����̂悤�ł����A
�������ɂȂ�ƍX�ɋ��܂��āA100m�ł�10cm���s���Ȃ��悤�ȋC�����܂��B�������Č����Ȃ��ᓖ����Ȃ��B
�������A���Ԃ̓��A�ł́A�o�C�A�X�d���s���̊W�Ŋ��x��������X�ɃV�r�A�ɂȂ�܂��B
�����Y�̏œ_�����͏��Ȃ��Ƃ��A7�`8cm���炢�ɂ�����������ȋC�����܂����B
�܂��A��������A�t�[�h��t���āA�M���M����6V�쓮���ǂ��Ǝv���܂��B
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1
���x�̓�20mm��F=100mm�̃����Y�Ń`�F�b�N�ł��B

 �}�Y�������ɕt���Ă�e�[�v�́A�t�B���^�[�ʂɏ����t���Ȃ��悤�ی삷�邽�߂ł��B
�����ŋC���t�����̂ł����A
���������j�b�g�̕������Ȃ荂���x�Ȃ��Ƃ��������܂����B
����������Ă��Ȃ��̂ŁA�߂��ł͂��̂������L�͈͂ɔ������܂��B
���Ƃ̓s���z�[���]�X���B
�ŁAND500�t�B���^�[��t���Ă݂āA�e�X�g�ł��B
10cm�̏œ_�������Ɣ��肪���\�Â�����C�����܂����B
�����́A��20mm��10cm���ƏW���\�͂��������Ƃ�����̂ł����B
100mm�����Y�Ńs���z�[��2mm�Ɛݒ肷��ƁA
10m��0.2m�Ɍ������銴���ł��B
���ۂ̔��������Ȋ����ł��̂ŁA������ƊÂ��悤�ł��ˁB
�ŁA�����͂Ƃ����ƁAND500�g�p�Ńi�[��4m���炢�ɂȂ��Ă��܂��܂����B
�ł��A��Ԃ�8m���炢�s���܂����B�������E�}�������ĂȂ��̂����肻���ł��B
���Ⴀ�A��20mm�ŁA�W���\�͂������ă��C�t���Ő��x�̗ǂ��œ_�����́H
�Ƃ����ƁA15cm����20cm�ʂ����ł��B
������Ƀt�[�h��t����ƃt�H�gDi�̃o�C�A�X�̖�肩��A���x��UP����Ǝv���܂��B
���ƁA�ŋ߂̎�����j�b�g�͂ǂ��Ȃ̂��킩��Ȃ��ł����A
�f���[�e�B�[��������āA�d���𑝂₷�ƁA�C�P�邩���H
���Ƃ�LED���̂̍��P�x���ł��ˁB
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1
��20mm��F=200mm�̃����Y���Z�b�g�ł��B
�o������2cm�����Ȃ�܂����B
�i��݂͐����Ƀp�C�v�̓����ɂ��������h��܂����B
���X���˂���̂ŁA����ρA�i�肪�����������ǂ��ł��B
�}�Y�������ɕt���Ă�e�[�v�́A�t�B���^�[�ʂɏ����t���Ȃ��悤�ی삷�邽�߂ł��B
�����ŋC���t�����̂ł����A
���������j�b�g�̕������Ȃ荂���x�Ȃ��Ƃ��������܂����B
����������Ă��Ȃ��̂ŁA�߂��ł͂��̂������L�͈͂ɔ������܂��B
���Ƃ̓s���z�[���]�X���B
�ŁAND500�t�B���^�[��t���Ă݂āA�e�X�g�ł��B
10cm�̏œ_�������Ɣ��肪���\�Â�����C�����܂����B
�����́A��20mm��10cm���ƏW���\�͂��������Ƃ�����̂ł����B
100mm�����Y�Ńs���z�[��2mm�Ɛݒ肷��ƁA
10m��0.2m�Ɍ������銴���ł��B
���ۂ̔��������Ȋ����ł��̂ŁA������ƊÂ��悤�ł��ˁB
�ŁA�����͂Ƃ����ƁAND500�g�p�Ńi�[��4m���炢�ɂȂ��Ă��܂��܂����B
�ł��A��Ԃ�8m���炢�s���܂����B�������E�}�������ĂȂ��̂����肻���ł��B
���Ⴀ�A��20mm�ŁA�W���\�͂������ă��C�t���Ő��x�̗ǂ��œ_�����́H
�Ƃ����ƁA15cm����20cm�ʂ����ł��B
������Ƀt�[�h��t����ƃt�H�gDi�̃o�C�A�X�̖�肩��A���x��UP����Ǝv���܂��B
���ƁA�ŋ߂̎�����j�b�g�͂ǂ��Ȃ̂��킩��Ȃ��ł����A
�f���[�e�B�[��������āA�d���𑝂₷�ƁA�C�P�邩���H
���Ƃ�LED���̂̍��P�x���ł��ˁB
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1
��20mm��F=200mm�̃����Y���Z�b�g�ł��B
�o������2cm�����Ȃ�܂����B
�i��݂͐����Ƀp�C�v�̓����ɂ��������h��܂����B
���X���˂���̂ŁA����ρA�i�肪�����������ǂ��ł��B

 �ŁAND500�t�B���^�[���g�p�����Ƃ���A
�܂�̗[���A9m�ł͌��\�]�T������܂����B
�Ə�����Â��̂̓s���z�[�������߂�B
�Ƃ������ƂŁA�����炪�����₷���A��т��ǂ��悤�ł��B
������Ȃ̂ł����A���z����h���A�p�x���L����낤�Ƃ���ƁA�����������]���ɂ��܂����A
�T���E���hSP�̂悤�ɉ~����̔��˔����z�I�ŁA�K�R���Ǝv���Ă͂��܂������A
����ρA�l���邱�Ƃ͓����ŁA�������o�Ă܂��悤�ł��ˁB
http://astamuse.com/ja/published/JP/No/2005349086
http://www.ekouhou.net/disp-fterm-2C014CA05.html
http://www.ekouhou.net/disp-fterm-2C014CA10.html
https://sites.google.com/site/kaimunantai/home/hardwares/avr-micro-controller/ir-shooting-tiny26-861
----�g�������e�ɂ��U���͂̍�-----------------------------------
�n���h�K����C�t���ɂ���čU���͂̈Ⴂ���o��Ǝv���܂��̂ŁA
���̍���t���Ă݂����ł��ˁB
����́A�����R����12�p���X�̃R�[�h�ōs���Ă��ǂ��̂ł����A
�f�W�^���Ȓm�����K�v�ł��ˁB
���ƒ��X�ƌ����o���Ă�R�g�Ȃ��Ă��܂��Ǝv���܂��̂ŁA
(�P�ʎ��Ԃɗ���)600��Sec�̃p���X�̉ŃJ�E���g��ώZ���Ă��܂��A�ȒP�����B
�ł��B
���Ƃ��A�n���h�K���́A���̔��C�ŁA1�p���X�B
���C�t���Ȃ���̔��C�ŁA3�p���X�ȂǁB
�}�̓����R����12Bit��PPM�K�i�B
�ŁAND500�t�B���^�[���g�p�����Ƃ���A
�܂�̗[���A9m�ł͌��\�]�T������܂����B
�Ə�����Â��̂̓s���z�[�������߂�B
�Ƃ������ƂŁA�����炪�����₷���A��т��ǂ��悤�ł��B
������Ȃ̂ł����A���z����h���A�p�x���L����낤�Ƃ���ƁA�����������]���ɂ��܂����A
�T���E���hSP�̂悤�ɉ~����̔��˔����z�I�ŁA�K�R���Ǝv���Ă͂��܂������A
����ρA�l���邱�Ƃ͓����ŁA�������o�Ă܂��悤�ł��ˁB
http://astamuse.com/ja/published/JP/No/2005349086
http://www.ekouhou.net/disp-fterm-2C014CA05.html
http://www.ekouhou.net/disp-fterm-2C014CA10.html
https://sites.google.com/site/kaimunantai/home/hardwares/avr-micro-controller/ir-shooting-tiny26-861
----�g�������e�ɂ��U���͂̍�-----------------------------------
�n���h�K����C�t���ɂ���čU���͂̈Ⴂ���o��Ǝv���܂��̂ŁA
���̍���t���Ă݂����ł��ˁB
����́A�����R����12�p���X�̃R�[�h�ōs���Ă��ǂ��̂ł����A
�f�W�^���Ȓm�����K�v�ł��ˁB
���ƒ��X�ƌ����o���Ă�R�g�Ȃ��Ă��܂��Ǝv���܂��̂ŁA
(�P�ʎ��Ԃɗ���)600��Sec�̃p���X�̉ŃJ�E���g��ώZ���Ă��܂��A�ȒP�����B
�ł��B
���Ƃ��A�n���h�K���́A���̔��C�ŁA1�p���X�B
���C�t���Ȃ���̔��C�ŁA3�p���X�ȂǁB
�}�̓����R����12Bit��PPM�K�i�B
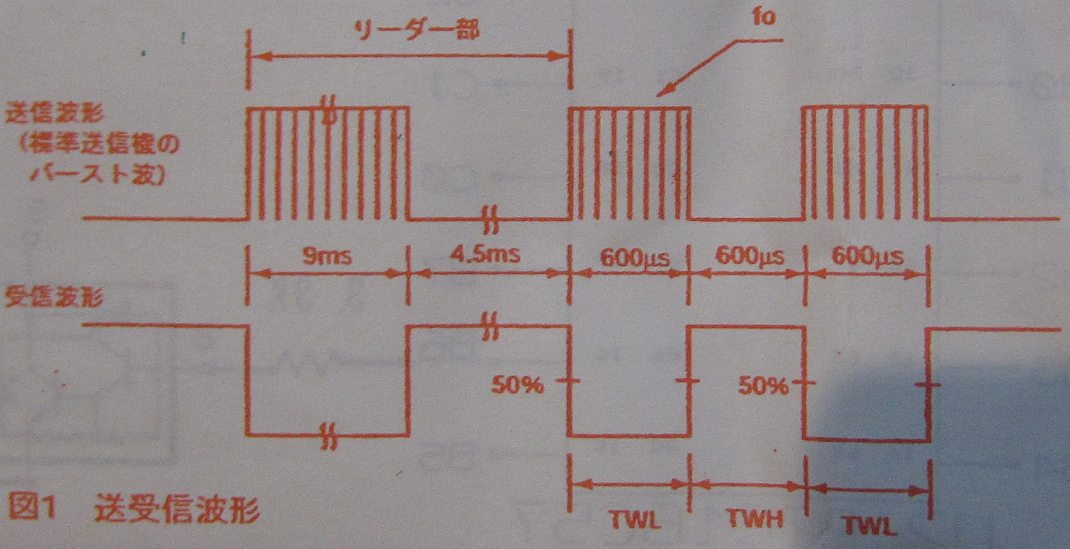
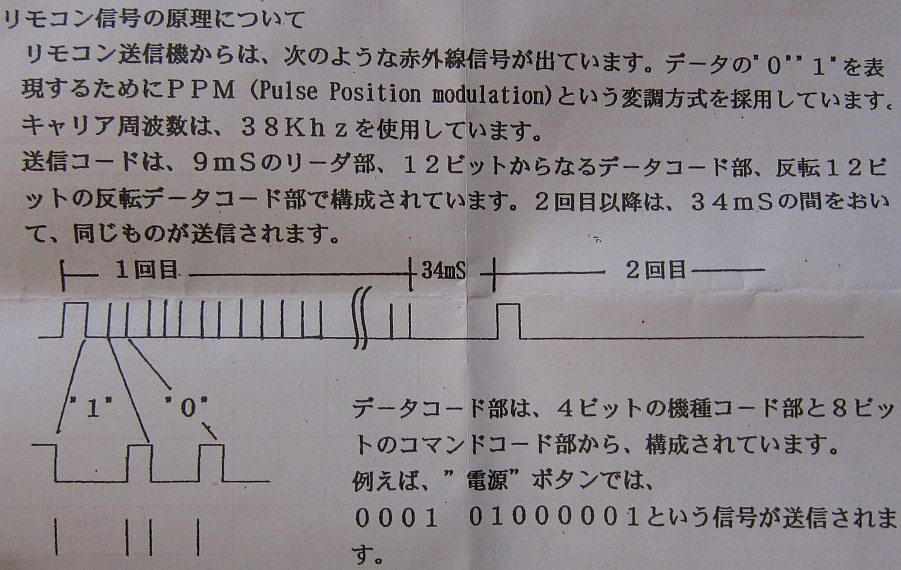 ������}�W���ɂ���Ă��܂��ƁA1/36�b(0.028Sec)�ʂ�����̂ł��B
�R�[�h���M���̎�Ԃ�̖�肪�o�Ă��܂��B
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
�V���Ɏ��g�ނ��ƂȂ̂ł����A
�ENE555����LMC555��p�ɂ��āA���U�A����n��1MHz�A30��Sec�̃p���X�ɂ���B
�E���[�U�[����p����B
�ł��B
�E�����b�g
�������Ԃ��Z���B
�O�����Ȃǂ̃m�C�Y�ɋ����Ȃ�B
���U���̉�H�͂Ƃ肠�����B
����ł��B
��H�̐��l�����Ŗ����AVR�₻�̎���̔z�����ς���Ă���܂��B
(38KHz�̏ꍇ�ł��AVR����͂������������ǂ��ł��B)
������}�W���ɂ���Ă��܂��ƁA1/36�b(0.028Sec)�ʂ�����̂ł��B
�R�[�h���M���̎�Ԃ�̖�肪�o�Ă��܂��B
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
�V���Ɏ��g�ނ��ƂȂ̂ł����A
�ENE555����LMC555��p�ɂ��āA���U�A����n��1MHz�A30��Sec�̃p���X�ɂ���B
�E���[�U�[����p����B
�ł��B
�E�����b�g
�������Ԃ��Z���B
�O�����Ȃǂ̃m�C�Y�ɋ����Ȃ�B
���U���̉�H�͂Ƃ肠�����B
����ł��B
��H�̐��l�����Ŗ����AVR�₻�̎���̔z�����ς���Ă���܂��B
(38KHz�̏ꍇ�ł��AVR����͂������������ǂ��ł��B)
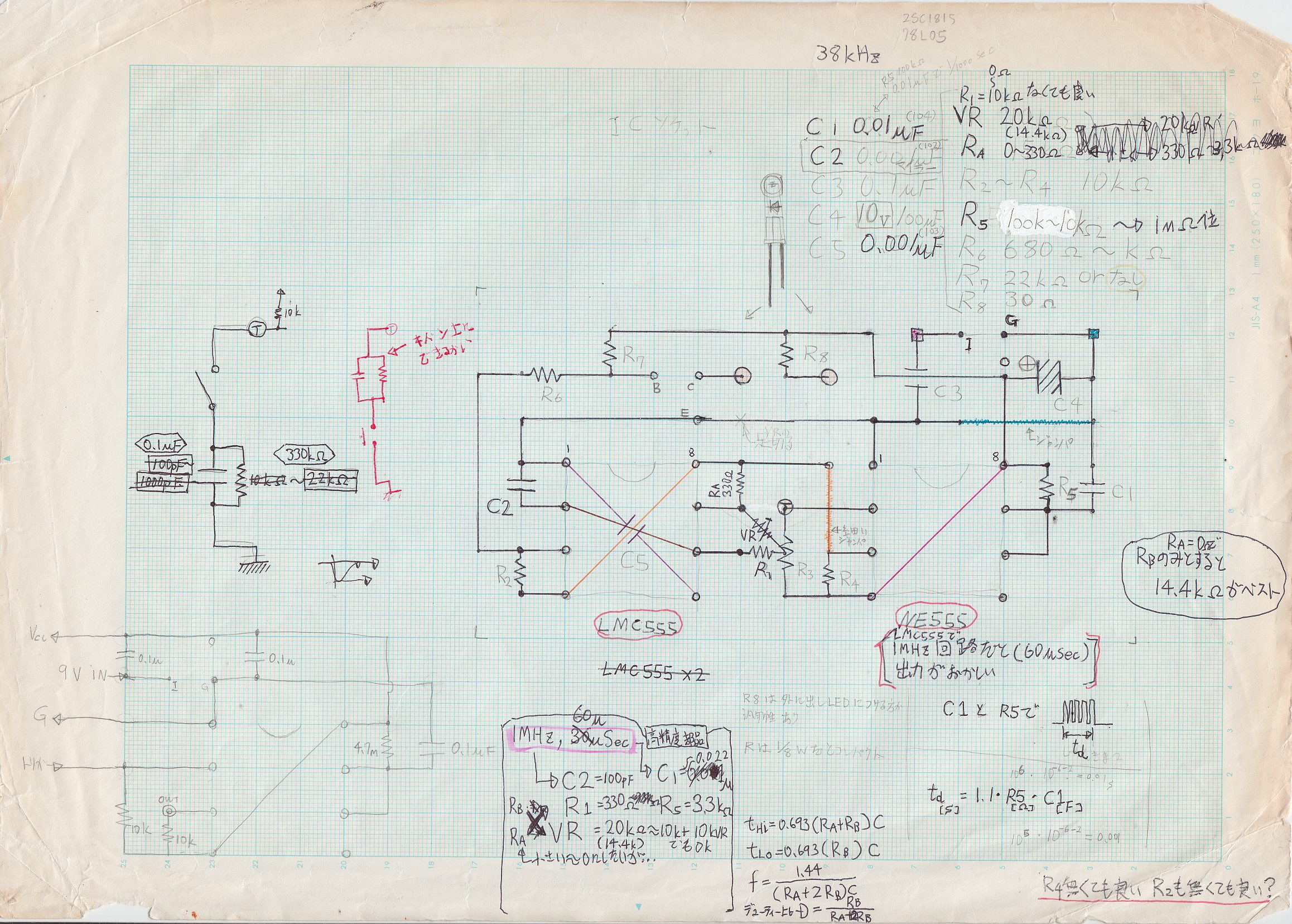 ���i��NE555�œ�i�ڂ̂�LMC555�ɂ���ƈ��蓮�삷��悤�ł��B
�p���[Tr�͂��̎��g���ɂȂ��MOSFET�͓��͗e�ʂ��傫�����Ė���������܂��̂ŁA��1000pF�ʂ���̂ŁA�Q�[�g�̓��͒�R��10���ȉ��ɂ��Ȃ��ƃ_���Ȃ悤�ȁB
����ɁA2SC1815�Ȃǂ��g���܂��B
LMC555�Ȃ�ATr�����ł����[�U�[Di���h���C�u�o����Ǝv���܂����A
�d���ȂǂɃV�r�A�Ȃ̂ŁATr��p���������ǂ��ł��傤�B
���i��NE555�œ�i�ڂ̂�LMC555�ɂ���ƈ��蓮�삷��悤�ł��B
�p���[Tr�͂��̎��g���ɂȂ��MOSFET�͓��͗e�ʂ��傫�����Ė���������܂��̂ŁA��1000pF�ʂ���̂ŁA�Q�[�g�̓��͒�R��10���ȉ��ɂ��Ȃ��ƃ_���Ȃ悤�ȁB
����ɁA2SC1815�Ȃǂ��g���܂��B
LMC555�Ȃ�ATr�����ł����[�U�[Di���h���C�u�o����Ǝv���܂����A
�d���ȂǂɃV�r�A�Ȃ̂ŁATr��p���������ǂ��ł��傤�B
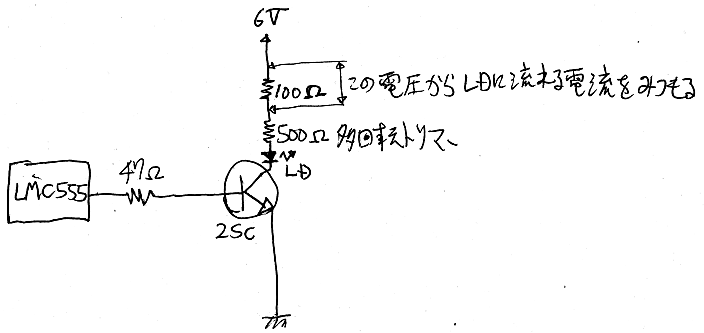 47���͗v��Ȃ��Ǝv�����̂ł����A�^�C�}�[�̎��萔�������̂ŁA510���`2K�����x���K�v�̂悤�ł��B
�O�̐������l�ł���LD��2V�t�߁AVce��0V�ƌ��āA��̂̊T�Z���o����Ǝv���܂��B
����n�͂���Ȋ����ł����A
47���͗v��Ȃ��Ǝv�����̂ł����A�^�C�}�[�̎��萔�������̂ŁA510���`2K�����x���K�v�̂悤�ł��B
�O�̐������l�ł���LD��2V�t�߁AVce��0V�ƌ��āA��̂̊T�Z���o����Ǝv���܂��B
����n�͂���Ȋ����ł����A
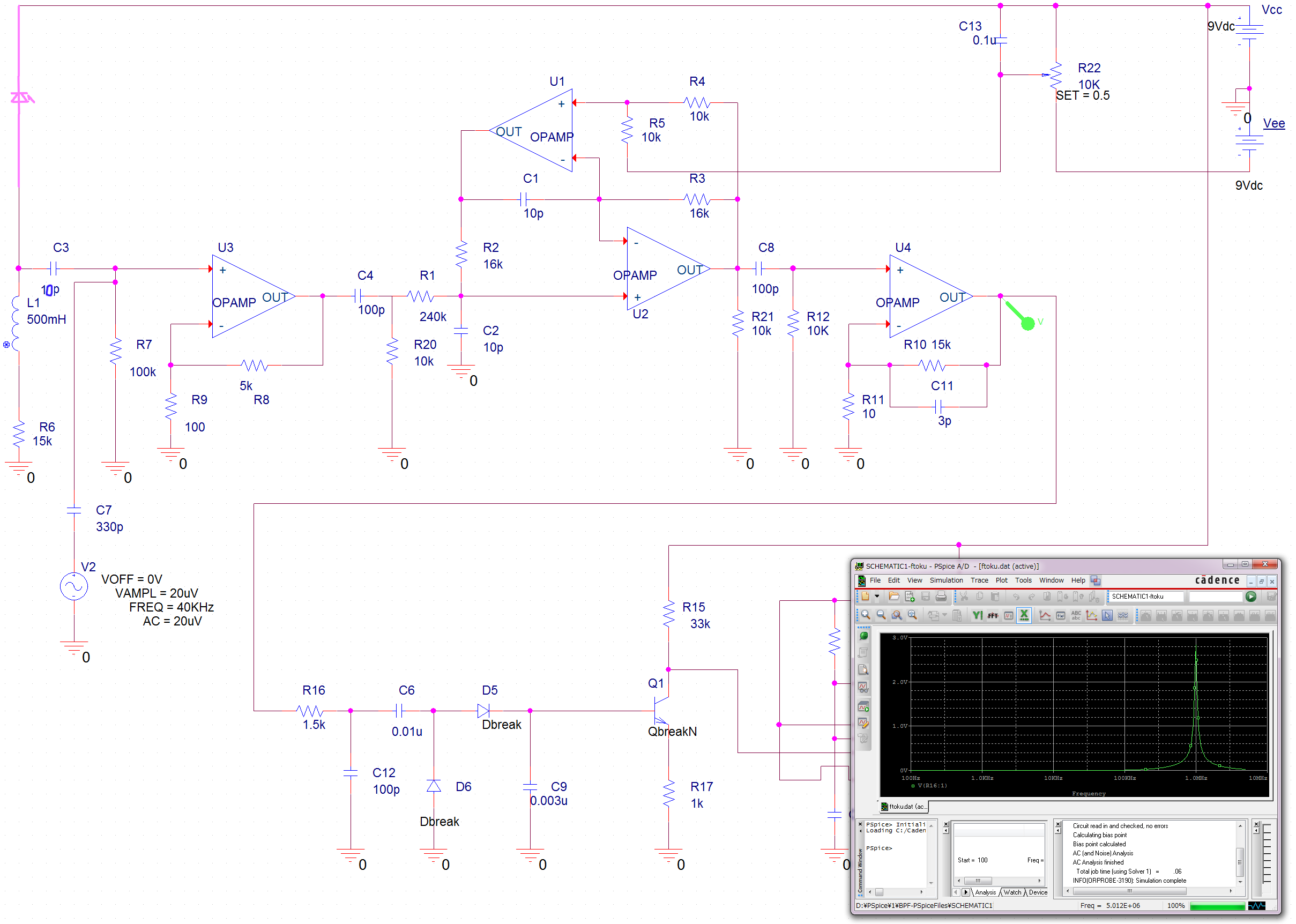 ���g��O�̃g�R�܂ł������l��ς��Ă���܂���B
�ŁA
C12=5p
C6=0.001u
C9=150p
R17�̕���ɃR���f���T�[��t���邩���B
���g��O�̃g�R�܂ł������l��ς��Ă���܂���B
�ŁA
C12=5p
C6=0.001u
C9=150p
R17�̕���ɃR���f���T�[��t���邩���B
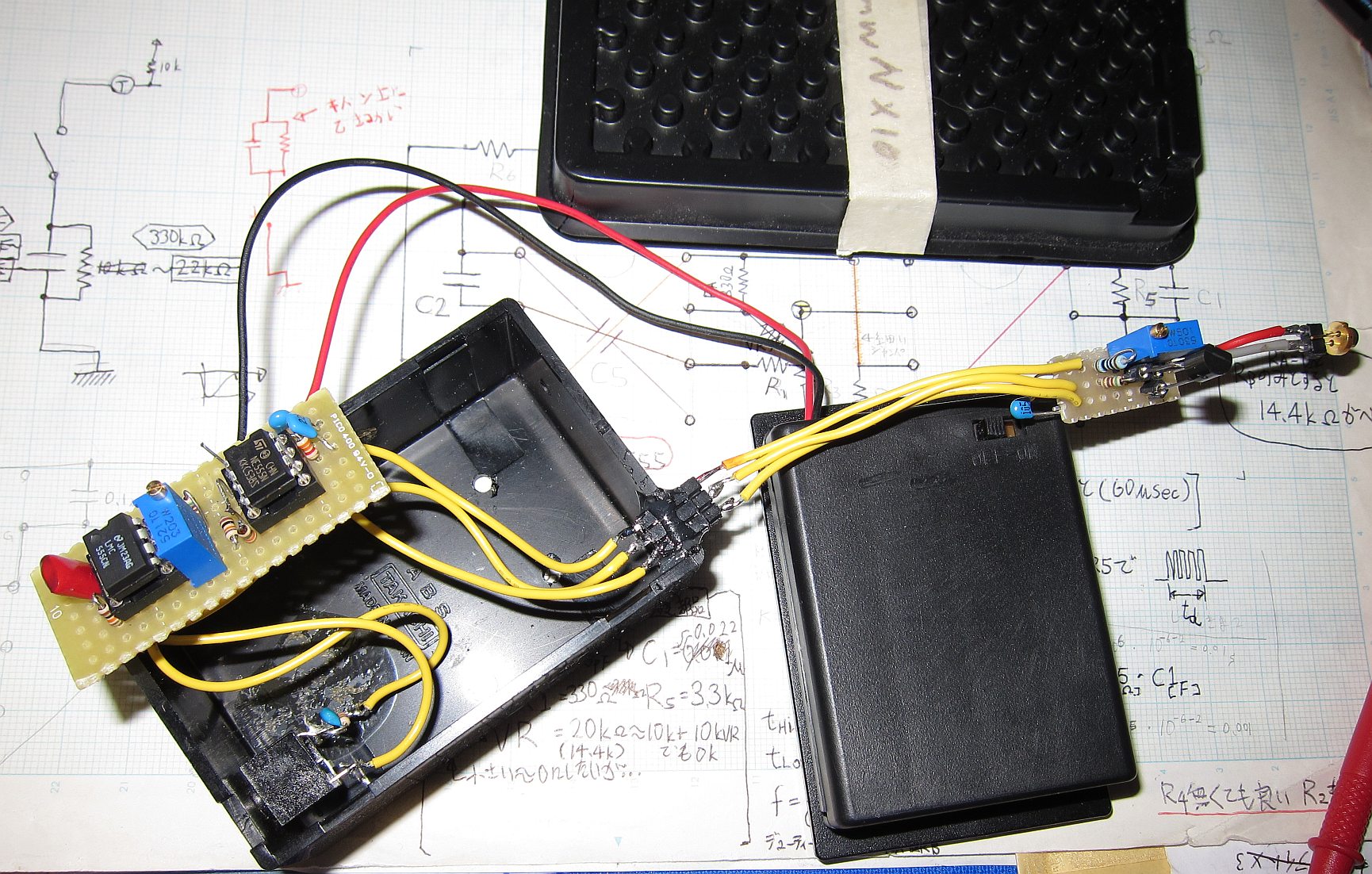
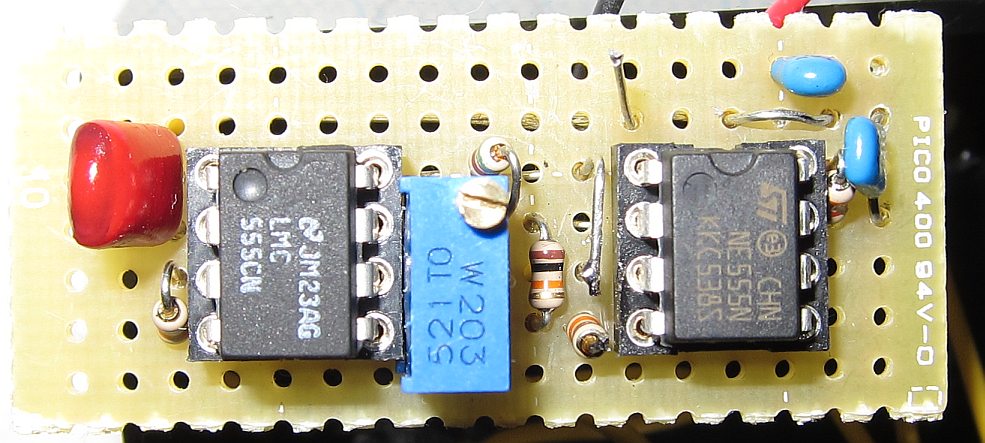 ���́A���[�U�[���̃����Y�ł��ˁB
�T�C�Y�́A�a���������A�œ_������Z���o���܂����A
��20mm��F100mm�̃����Y��U�߂��p�C�v�����܂��Ă܂��̂ŁA������g�������ƁB���܂���������̂͂��������̂ŁB
���S�̂���5mW�ȉ��ŁA�r�[�������銴���ł��B
���[�U�[�R�����[�g�ɕK�v�ȃ����Y��������܂����B
f=8.5mm�̔ʃ����Y�ł��B
���ƁA�����Ə������̂�����܂����B
����n�Ȃ̂ł����A
�Ȃ�����250KHz�ӂ��BPF���������������U���܂��B
OP-AMP��ς��Ă����܂�ς��܂���B
��肭�����Ȃ��ꍇ�A
Q�������邩�A�����g���������邩�A�������H
�Ƃ肠�����A���U���g����1/2�ɂ��Ă����ʂ͖����A�����U�������炵�ē��R���ۂ��B
C2��10pF�ɐG���Ǝ~�܂邱�Ƃ���A
Q���L�c������̂������̂悤�ł��B
����10p�ɒ�R�݂���Ɣ{�����ς��܂��B
�����g�ɑς������H�ŁAQ�����S�܂Őݒ�ł���悤�ł���
���ۖ��ƂȂ�ƁA�ǂ��܂ō����g���H�Ƃ����͉̂���Ȃ��ł����A
Q�������邩�{���������邩�̑Ώ����K�v�����ł��B
�Ƃ��Ă�������OP-AMP���g���Ă݂čl���悤���ƁB
�ŁA�X���[���[�g�͂��܂葬���Ȃ��ł����A���g���͍���
�L�ш�OP-AMP�ɕς��Ă݂��Ƃ���A830KHz�Ŕ��U���܂����B
�ǂ����AOP-AMP�̓����Ɉˑ����Ă���悤�ł��B
�Ȃ̂ŁA���̂܂܂ŁA200�`500KHz�Őv���Ă݂�̂��ǂ��悤�ł��̂ŁA
�����200�`250���炢�ɂ����Ă����Ă݂����Ƃ������܂��B
�Ƃ��������̂ł����A
C2��240K���݂���ƁA���̔��U�͎~�܂�܂����B
���A�ア7MHz�̔��U���N�����Ă���̂ŁA������ǂ��ɂ�����K�v������܂��B
�ア�ł��̂ŁA�t�B���^�ŏ����o���邩���ł����A
���̌���OP-AMP�̔{���͔��ɍ����ł��̂ŁA�M�����O�a���Ȃ��悤�ɒ��ӂł��ˁB
�܂��ALED���A���[�U�[�̕��������g�����������ǂ����߁A
�ア���˂ł������M�����o�Ă��邱�Ƃ���������܂����B�B
���R�́A�ڍ��ԗe�ʂƁALED�̈�ƃ��[�U�[���U�̈�̌��ʍ����n�b�L�����Ă邱�Ƃ���L���̗ǂ��M�����o�ė���̂��Ǝv���܂��B
�O��͌��g���Đϕ����āA�^�C�}�[��LED�����点�Ă܂������A������s�����A
�V�O�i�����m�pIC���g�����ǂ������l���˂ł��ˁB���̏ꍇ�AIC�̑ς�����d���ɉ����Ȃ��Ɓc�A
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�ł����āA
���g���ɒʂ��f�J�b�v�����O�R���f���T�[�̗e�ʂ�38KHz�ł̐v�ł����g���g�����������悤�ŁA
�����傫������ƁA�X�Ɋ��x���������Ǝv���܂��B
���̑��A�e�i�ɂɂ�������HPF�I�ȕ����́A�Ⴂ�̂�ʂ�������̂ŁA
�����𐳂��A�듮������Ȃ��Ȃ肻���ł��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�܂��A�O�i�ڂ�OP-AMP�������ɂ��������ǂ��̂ł����A
�m�C�Y�Ƃ̌��ˍ��������邩���f�X�B
�O�i�ڂ������ȃ��m�ɂ��Ă݂��̂ł����A
1500�{�Ƃ����{���̂��߁A���̓I�t�Z�b�g�ɂăI�[�o�[�t���[���Ă��܂��܂����B
�ł����āA��i�ɕ����邩�A�g�����W�X�^���ǂ��Ǝv���̂ł����A
�����܂Ŏ�Ԃ�������ׂ����m�Ȃ̂��^��ɂ��B
�ł��A�ԊO�����R�����A�ꌅ�߂��͏グ�������m�ł��B
�ŁA
���݂���l���A
AM���W�I�̗̈�ł��̂ŁA
����H�́ALC�ŁA�g�����W�X�^�ɂ���Έ��オ��B
�����I�ɂ�AM�pIC�Ń`�F�b�N�ł���Ɠ��̂ł����A
UTC��IC�ł͂ȁA���������U���Ă��܂��܂����B
-----------------------------------------------------------------------
���݃��[�U�[�̌��w�n���l���Ă�̂ł����A
���g���g������LD�̔����́A�c���Ȃ̂ŁA
��[�ׂ����s���ɂ��āA�r�[�����L���点�Ă���A��^�̃����Y�ő������s���ɏo����A�Ǝv���̂ł����A
���̐v�ƁA�v���g�^�C�v�������z�����ł��ˁB
�܂��A�l�Ԃ͏c���ł�����A������x�c���̃r�[���ł��ǂ��悤�ȋC�����܂��B���Q�[����́A�e���c�ɂ��܂��Ȃ��Ɣ������Ȃ��l�ɂ���Ƃ��B
�Ƃ肠�����A���s���ɁB
���́A���[�U�[���̃����Y�ł��ˁB
�T�C�Y�́A�a���������A�œ_������Z���o���܂����A
��20mm��F100mm�̃����Y��U�߂��p�C�v�����܂��Ă܂��̂ŁA������g�������ƁB���܂���������̂͂��������̂ŁB
���S�̂���5mW�ȉ��ŁA�r�[�������銴���ł��B
���[�U�[�R�����[�g�ɕK�v�ȃ����Y��������܂����B
f=8.5mm�̔ʃ����Y�ł��B
���ƁA�����Ə������̂�����܂����B
����n�Ȃ̂ł����A
�Ȃ�����250KHz�ӂ��BPF���������������U���܂��B
OP-AMP��ς��Ă����܂�ς��܂���B
��肭�����Ȃ��ꍇ�A
Q�������邩�A�����g���������邩�A�������H
�Ƃ肠�����A���U���g����1/2�ɂ��Ă����ʂ͖����A�����U�������炵�ē��R���ۂ��B
C2��10pF�ɐG���Ǝ~�܂邱�Ƃ���A
Q���L�c������̂������̂悤�ł��B
����10p�ɒ�R�݂���Ɣ{�����ς��܂��B
�����g�ɑς������H�ŁAQ�����S�܂Őݒ�ł���悤�ł���
���ۖ��ƂȂ�ƁA�ǂ��܂ō����g���H�Ƃ����͉̂���Ȃ��ł����A
Q�������邩�{���������邩�̑Ώ����K�v�����ł��B
�Ƃ��Ă�������OP-AMP���g���Ă݂čl���悤���ƁB
�ŁA�X���[���[�g�͂��܂葬���Ȃ��ł����A���g���͍���
�L�ш�OP-AMP�ɕς��Ă݂��Ƃ���A830KHz�Ŕ��U���܂����B
�ǂ����AOP-AMP�̓����Ɉˑ����Ă���悤�ł��B
�Ȃ̂ŁA���̂܂܂ŁA200�`500KHz�Őv���Ă݂�̂��ǂ��悤�ł��̂ŁA
�����200�`250���炢�ɂ����Ă����Ă݂����Ƃ������܂��B
�Ƃ��������̂ł����A
C2��240K���݂���ƁA���̔��U�͎~�܂�܂����B
���A�ア7MHz�̔��U���N�����Ă���̂ŁA������ǂ��ɂ�����K�v������܂��B
�ア�ł��̂ŁA�t�B���^�ŏ����o���邩���ł����A
���̌���OP-AMP�̔{���͔��ɍ����ł��̂ŁA�M�����O�a���Ȃ��悤�ɒ��ӂł��ˁB
�܂��ALED���A���[�U�[�̕��������g�����������ǂ����߁A
�ア���˂ł������M�����o�Ă��邱�Ƃ���������܂����B�B
���R�́A�ڍ��ԗe�ʂƁALED�̈�ƃ��[�U�[���U�̈�̌��ʍ����n�b�L�����Ă邱�Ƃ���L���̗ǂ��M�����o�ė���̂��Ǝv���܂��B
�O��͌��g���Đϕ����āA�^�C�}�[��LED�����点�Ă܂������A������s�����A
�V�O�i�����m�pIC���g�����ǂ������l���˂ł��ˁB���̏ꍇ�AIC�̑ς�����d���ɉ����Ȃ��Ɓc�A
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�ł����āA
���g���ɒʂ��f�J�b�v�����O�R���f���T�[�̗e�ʂ�38KHz�ł̐v�ł����g���g�����������悤�ŁA
�����傫������ƁA�X�Ɋ��x���������Ǝv���܂��B
���̑��A�e�i�ɂɂ�������HPF�I�ȕ����́A�Ⴂ�̂�ʂ�������̂ŁA
�����𐳂��A�듮������Ȃ��Ȃ肻���ł��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�܂��A�O�i�ڂ�OP-AMP�������ɂ��������ǂ��̂ł����A
�m�C�Y�Ƃ̌��ˍ��������邩���f�X�B
�O�i�ڂ������ȃ��m�ɂ��Ă݂��̂ł����A
1500�{�Ƃ����{���̂��߁A���̓I�t�Z�b�g�ɂăI�[�o�[�t���[���Ă��܂��܂����B
�ł����āA��i�ɕ����邩�A�g�����W�X�^���ǂ��Ǝv���̂ł����A
�����܂Ŏ�Ԃ�������ׂ����m�Ȃ̂��^��ɂ��B
�ł��A�ԊO�����R�����A�ꌅ�߂��͏グ�������m�ł��B
�ŁA
���݂���l���A
AM���W�I�̗̈�ł��̂ŁA
����H�́ALC�ŁA�g�����W�X�^�ɂ���Έ��オ��B
�����I�ɂ�AM�pIC�Ń`�F�b�N�ł���Ɠ��̂ł����A
UTC��IC�ł͂ȁA���������U���Ă��܂��܂����B
-----------------------------------------------------------------------
���݃��[�U�[�̌��w�n���l���Ă�̂ł����A
���g���g������LD�̔����́A�c���Ȃ̂ŁA
��[�ׂ����s���ɂ��āA�r�[�����L���点�Ă���A��^�̃����Y�ő������s���ɏo����A�Ǝv���̂ł����A
���̐v�ƁA�v���g�^�C�v�������z�����ł��ˁB
�܂��A�l�Ԃ͏c���ł�����A������x�c���̃r�[���ł��ǂ��悤�ȋC�����܂��B���Q�[����́A�e���c�ɂ��܂��Ȃ��Ɣ������Ȃ��l�ɂ���Ƃ��B
�Ƃ肠�����A���s���ɁB
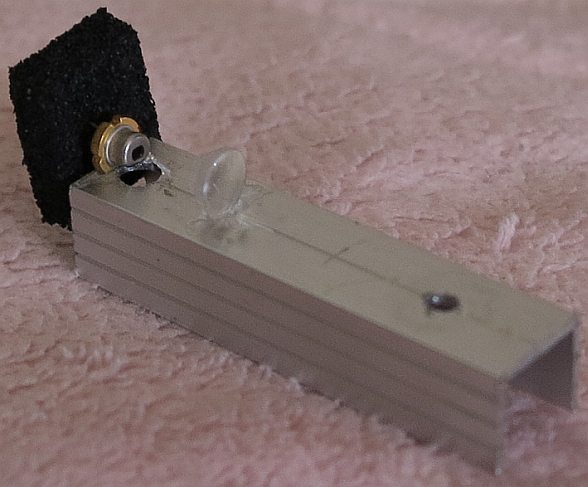
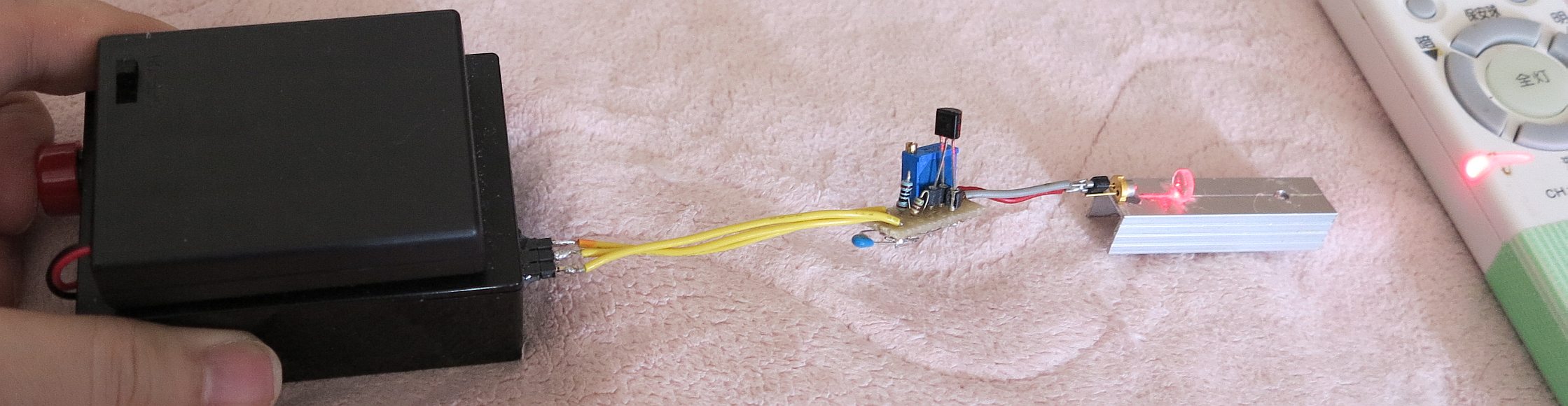 �A�����U������{�^����t���܂����B(�Ԃ����c)
���ƁA���g���Ă��������W���[��TSOP38238��780nm��LD�̌��ɂ��܂蔽�����Ȃ��̂Œ��ׂĂ݂���A
850nm�ł����\�݂����Ƃ������B
�A�����U������{�^����t���܂����B(�Ԃ����c)
���ƁA���g���Ă��������W���[��TSOP38238��780nm��LD�̌��ɂ��܂蔽�����Ȃ��̂Œ��ׂĂ݂���A
850nm�ł����\�݂����Ƃ������B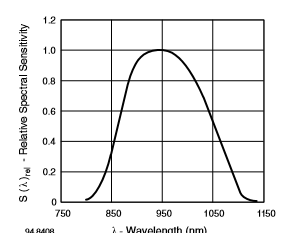 ����āA940�`960nm�t�ߗp�Ɍ��肳��Ă���A���̂悤�Ȕ����̂�p����X�ɔ����L�т邱�Ƃ��\�z����܂��B
LED��300m�����邩���H
�Ƃ肠�����A980nm��LD������(AL980T50@300�~)
�y�K�i�z
�^�C�v Symbol Unit AL980T50
�g�� ��P ��m 980�}10
����p���[ POP mW ��50
�d�� ITH mA ��40
����d�� IOP mA ��150
����d�� VOP V ��2.2
�\�� �� mW/mA ��0.8
�r�[���Y�� B �Ƅ��~��// 40�~12
��R RS �� ��3
�����^�C�v TO-18(��5.6mm)
�f�[�^�V�[�g�������ɐ�������Ȃ��̂ŁA
�������āAPD�ALD�̔��ʁA
�e�X�^�[��Di���胂�[�h�ŁA�A�m�[�h�J�\�[�h�̔��ʂł��ˁB
�����͑��z���Ȃǂ���˂����Ē[�q�̓d�ʂŋɐ��̔��ʏo���邩���B
(LED�Ɍ��Ă�ƁA�t�H�gDi�̂悤�ɓd�ʂ�������)
����LD��100mA���W���I�d���̂悤�ł��B���ő��i150mA
�t�����̑ϓd����1V�ƁA���������Ⴂ�̂Œ��ӂł��B
��r�I�p���[���傫���̂ŁA�X���b�V�����h(30mA)���瑀��d���̕������邽�߁A
�V�r�A�ȃR�g�͖����悤�ł��ˁB
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
940nm��LED(�n�r�h�T�k�`�T�P�P�R�`)�ƃ�20mm��f200mm�����Y��
������ƃ`�F�b�N���Ă݂��Ƃ���A
ND100��ND500�t�B���^�[��ɂȂ��āA175cm�Ŕ������܂����B
����������Ɨ]�T������̂����ł����A�莝���Ō������킹���V�r�A�Ȃ̂ŁA������ŁB
�����P���ɍL�����Ă����Ɗ��Z����ƁA
��50000��223�ł��̂ŁA
223*1.75��391m
�Ƃ������ƂŁA400m���炢��ԉ\��������܂��B
�����Y�̌��a���グ���肷������ƍs���ł��傤�B
�ڂ����́A�ԊO�̋��܂��Â炢���Ƃ�A
�ߋ����Ń����Y�̃t�H�[�J�X���ǂ��Ȃ��Ă�̂��H
�ƌ������Ƃ��A���A�P���ɕ��U���Ă����Ƃ͌���Ȃ��ł����A
���x�O���t�̔�ł�2.5�{���炢�H
����ŁA940nm��LED�̕�������d�����Ⴍ�p���[���o��Ƃ���ƁA�{�ʍs���Ă����������Ȃ������ł��ˁB
����āA940�`960nm�t�ߗp�Ɍ��肳��Ă���A���̂悤�Ȕ����̂�p����X�ɔ����L�т邱�Ƃ��\�z����܂��B
LED��300m�����邩���H
�Ƃ肠�����A980nm��LD������(AL980T50@300�~)
�y�K�i�z
�^�C�v Symbol Unit AL980T50
�g�� ��P ��m 980�}10
����p���[ POP mW ��50
�d�� ITH mA ��40
����d�� IOP mA ��150
����d�� VOP V ��2.2
�\�� �� mW/mA ��0.8
�r�[���Y�� B �Ƅ��~��// 40�~12
��R RS �� ��3
�����^�C�v TO-18(��5.6mm)
�f�[�^�V�[�g�������ɐ�������Ȃ��̂ŁA
�������āAPD�ALD�̔��ʁA
�e�X�^�[��Di���胂�[�h�ŁA�A�m�[�h�J�\�[�h�̔��ʂł��ˁB
�����͑��z���Ȃǂ���˂����Ē[�q�̓d�ʂŋɐ��̔��ʏo���邩���B
(LED�Ɍ��Ă�ƁA�t�H�gDi�̂悤�ɓd�ʂ�������)
����LD��100mA���W���I�d���̂悤�ł��B���ő��i150mA
�t�����̑ϓd����1V�ƁA���������Ⴂ�̂Œ��ӂł��B
��r�I�p���[���傫���̂ŁA�X���b�V�����h(30mA)���瑀��d���̕������邽�߁A
�V�r�A�ȃR�g�͖����悤�ł��ˁB
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
940nm��LED(�n�r�h�T�k�`�T�P�P�R�`)�ƃ�20mm��f200mm�����Y��
������ƃ`�F�b�N���Ă݂��Ƃ���A
ND100��ND500�t�B���^�[��ɂȂ��āA175cm�Ŕ������܂����B
����������Ɨ]�T������̂����ł����A�莝���Ō������킹���V�r�A�Ȃ̂ŁA������ŁB
�����P���ɍL�����Ă����Ɗ��Z����ƁA
��50000��223�ł��̂ŁA
223*1.75��391m
�Ƃ������ƂŁA400m���炢��ԉ\��������܂��B
�����Y�̌��a���グ���肷������ƍs���ł��傤�B
�ڂ����́A�ԊO�̋��܂��Â炢���Ƃ�A
�ߋ����Ń����Y�̃t�H�[�J�X���ǂ��Ȃ��Ă�̂��H
�ƌ������Ƃ��A���A�P���ɕ��U���Ă����Ƃ͌���Ȃ��ł����A
���x�O���t�̔�ł�2.5�{���炢�H
����ŁA940nm��LED�̕�������d�����Ⴍ�p���[���o��Ƃ���ƁA�{�ʍs���Ă����������Ȃ������ł��ˁB
 ������̘A�����U�{�^���́A�I�[�o�[�h���C�u�Ŏg���ꍇ�Ɍ���ĉ����Ă��܂�Ȃ��悤�ɁA
�����ɁA�{�^���L��/�����X�C�b�`��t���Ă���܂��B
���ˌ����x�̂����Ƌ���LED�ɂ���ƍX�ɐL���܂��B
�p���X���̂�ǂރ��m�Ȃ�A
�f���[�e�B�[���������Ώu�Ԃ̌��͋����o���܂��B���A�����ƃC���e���W�F���X�ȉ�H���K�v�ɂȂ�܂��ˁB
�m�C�Y�Q�[�g�݂����Ȃ̂Ƃ��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
LD���U�̎���n��250KHz�ɂ��悤�Ɨ\�肵�Ă���܂��B
�R�i�ڂ́A
�g�����W�X�^�[���g�������m��܂���B
�P�i�ڂ��AFET��NPN�g�����W�X�^�ɕύX����Ɨǂ������ł��ˁB
������̘A�����U�{�^���́A�I�[�o�[�h���C�u�Ŏg���ꍇ�Ɍ���ĉ����Ă��܂�Ȃ��悤�ɁA
�����ɁA�{�^���L��/�����X�C�b�`��t���Ă���܂��B
���ˌ����x�̂����Ƌ���LED�ɂ���ƍX�ɐL���܂��B
�p���X���̂�ǂރ��m�Ȃ�A
�f���[�e�B�[���������Ώu�Ԃ̌��͋����o���܂��B���A�����ƃC���e���W�F���X�ȉ�H���K�v�ɂȂ�܂��ˁB
�m�C�Y�Q�[�g�݂����Ȃ̂Ƃ��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
LD���U�̎���n��250KHz�ɂ��悤�Ɨ\�肵�Ă���܂��B
�R�i�ڂ́A
�g�����W�X�^�[���g�������m��܂���B
�P�i�ڂ��AFET��NPN�g�����W�X�^�ɕύX����Ɨǂ������ł��ˁB
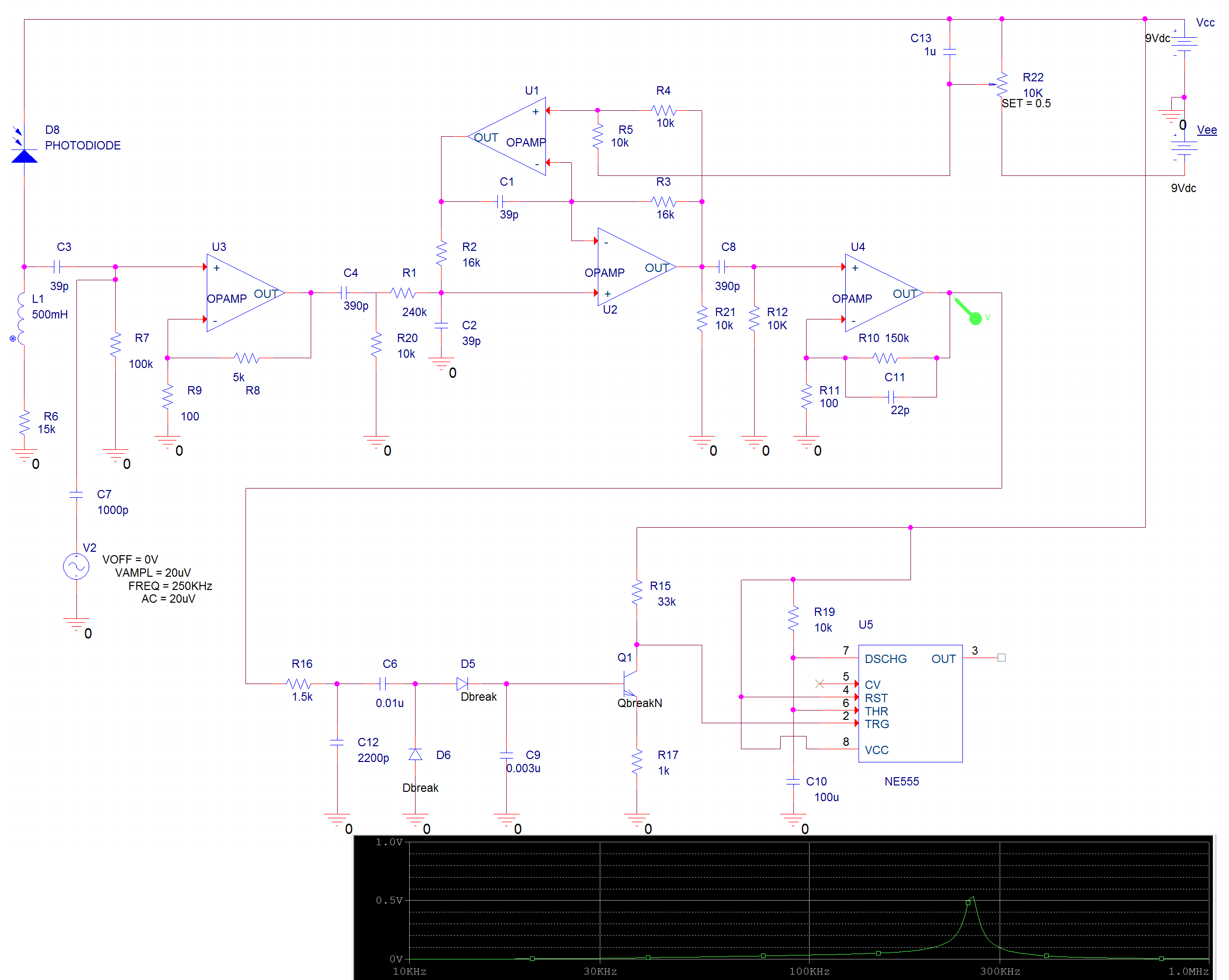 3�i�ڈȍ~�̐�����H��C�̒l�͌��肵�Ă���܂���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���݁A
250KHz�ɂ���ɂ������āA
�܂��A�������́A250KHz���Y��ɔg�`�ɃL���悭���U����̂͌��\�L�c���A
LED�̌�����L���̗ǂ�LD�̌���̕����������ǂ��ł��B
���ALD�̂̓���̈�������ƈӎ����Ȃ��ƁA�g�`�����������Ȃ�܂��B
NPN�g�����W�X�^���p���[MOS-FET���L�������ł����A
�Q�[�g�̐Ód�e�ʂ���6V�d����555�����250KHz���U�̓M���M�����ۂ��ł��B
���̍ہA�Q�[�g�\�[�X�Ԃ�500�����q���œd�ׂ����č������������Ă���܂��B
�f�W�^���g�����W�X�^�@�q�m�P�Q�O�P�@�o�C�A�X��R�����^
�́A�ǂ����낤���ȁ[�Ǝv���Ă݂���ł��B
���ɁA�������250KHz�ɂ��Ă݂܂����B
Di�̋t�o�C�A�X��H�̃��W�X�^���X�₻��ɂ���i�ڂ�AMP�̃Q�C���̍œK�l�̕ω����A���A
������ƁA�������B
�����_�`���[�N�R�C���͏Ȃ��āA�t�o�C�A�X��R�l���A���Ȃ�Ⴍ���Ă���܂��B
�Ƃ肠�����A
BPF�̔��U�ɔY�܂����Ă܂��BQ=15�ł���قljs�����P�ł��Ȃ��A
���U���g����BPF�̌ŗL�U�����ł͖���OP-AMP�Ɉˑ����Ă���܂��B
LPF�ŏ�������ƐM���͂���̂ł����ABPF�Ƃ��ē����Ă�̂����s���ŁA�����Ȃ���ԁB
�Ƃ肠�����A����ȏ�Ԃł��B
�O�i��(���g��H�O/�v���[�u�ʒu)�܂ł������삷��悤�ɂ��Ă܂���B
���F�̃A���_�[���C���̂��镔�����ύX�_�B
3�i�ڈȍ~�̐�����H��C�̒l�͌��肵�Ă���܂���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���݁A
250KHz�ɂ���ɂ������āA
�܂��A�������́A250KHz���Y��ɔg�`�ɃL���悭���U����̂͌��\�L�c���A
LED�̌�����L���̗ǂ�LD�̌���̕����������ǂ��ł��B
���ALD�̂̓���̈�������ƈӎ����Ȃ��ƁA�g�`�����������Ȃ�܂��B
NPN�g�����W�X�^���p���[MOS-FET���L�������ł����A
�Q�[�g�̐Ód�e�ʂ���6V�d����555�����250KHz���U�̓M���M�����ۂ��ł��B
���̍ہA�Q�[�g�\�[�X�Ԃ�500�����q���œd�ׂ����č������������Ă���܂��B
�f�W�^���g�����W�X�^�@�q�m�P�Q�O�P�@�o�C�A�X��R�����^
�́A�ǂ����낤���ȁ[�Ǝv���Ă݂���ł��B
���ɁA�������250KHz�ɂ��Ă݂܂����B
Di�̋t�o�C�A�X��H�̃��W�X�^���X�₻��ɂ���i�ڂ�AMP�̃Q�C���̍œK�l�̕ω����A���A
������ƁA�������B
�����_�`���[�N�R�C���͏Ȃ��āA�t�o�C�A�X��R�l���A���Ȃ�Ⴍ���Ă���܂��B
�Ƃ肠�����A
BPF�̔��U�ɔY�܂����Ă܂��BQ=15�ł���قljs�����P�ł��Ȃ��A
���U���g����BPF�̌ŗL�U�����ł͖���OP-AMP�Ɉˑ����Ă���܂��B
LPF�ŏ�������ƐM���͂���̂ł����ABPF�Ƃ��ē����Ă�̂����s���ŁA�����Ȃ���ԁB
�Ƃ肠�����A����ȏ�Ԃł��B
�O�i��(���g��H�O/�v���[�u�ʒu)�܂ł������삷��悤�ɂ��Ă܂���B
���F�̃A���_�[���C���̂��镔�����ύX�_�B
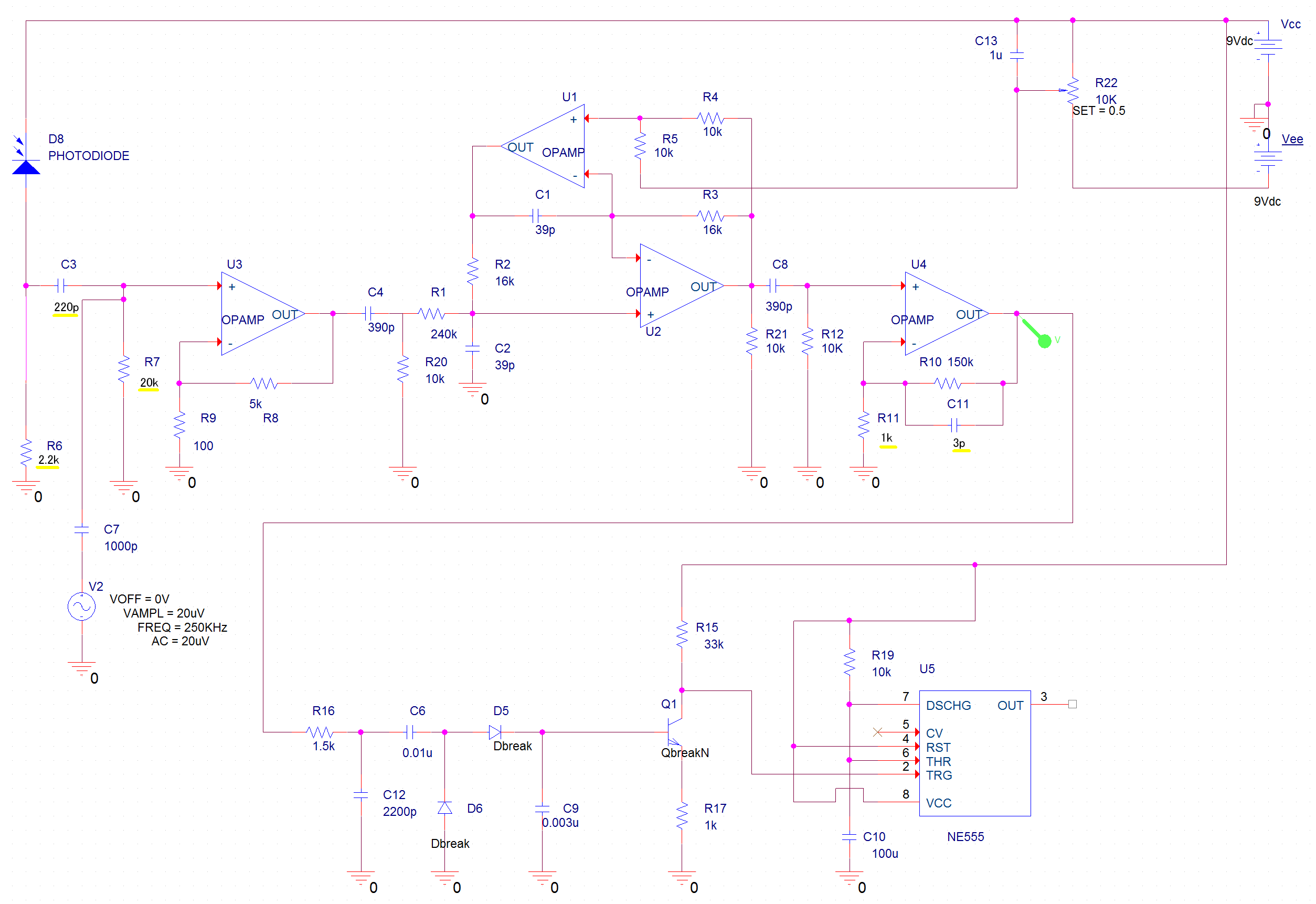
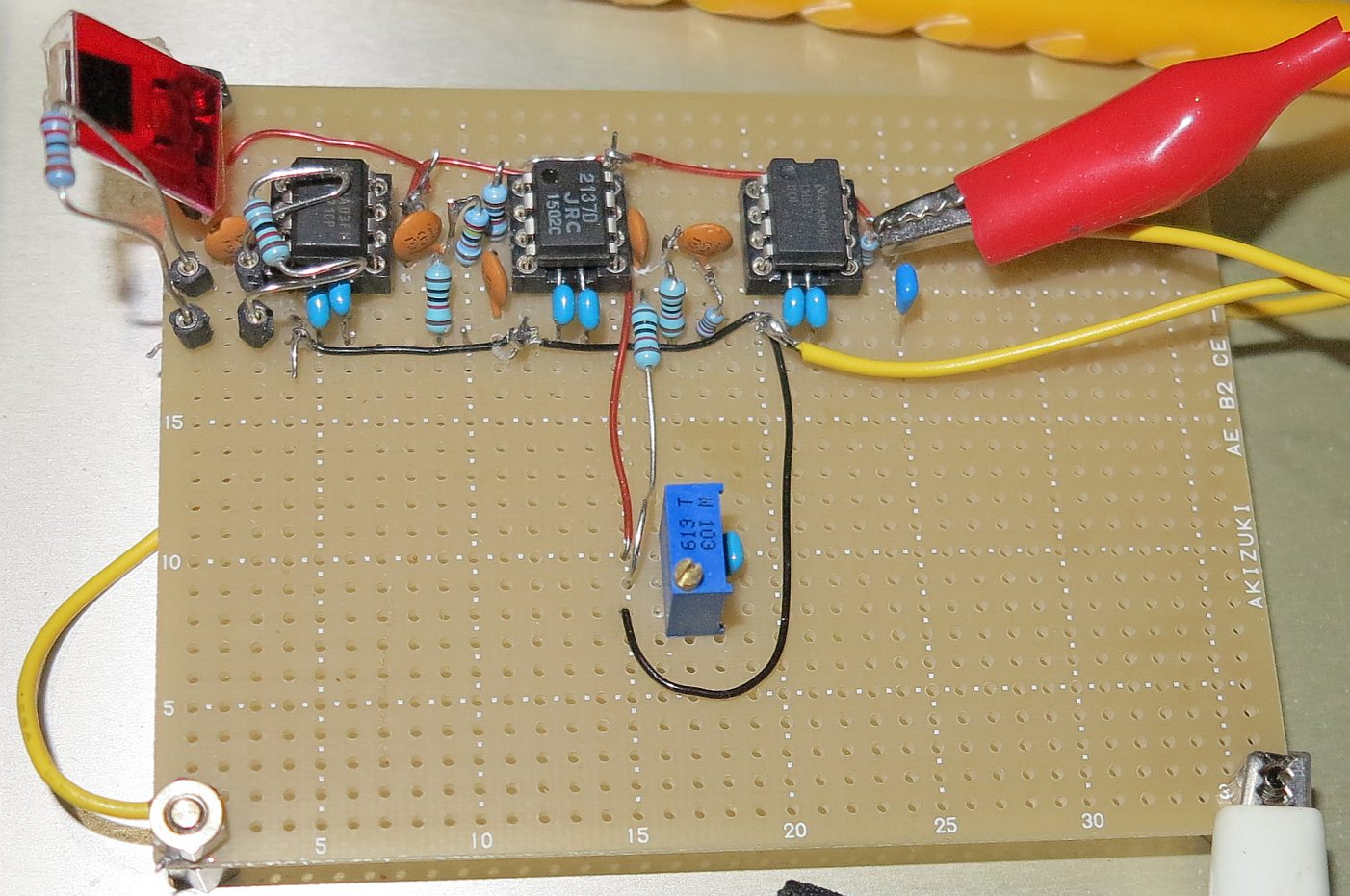 �Q�C���͂����ƕK�v�ŁA�҂��܂��̂ŁA���ꂪ����̉ۑ�ł��B
R8,R9�����R11��ύX�ŏ\�{���炢�̓C�P��͂��B
���ƁA�t�o�C�A�X��R��R6��������Əグ�邱�Ƃ��\�B
����ɁA
�ER8��20k����
�ER11��500����
�ER6��5.6K����
����ł�������P�����܂����B
�ł����āA
�Ȃ�ׂ��g�����W�X�^�őg��ł݂���A����ȕ��͋C���ȁ[�c�A�ƁB�����l�̓e�L�g�[�B
�Q�C���͂����ƕK�v�ŁA�҂��܂��̂ŁA���ꂪ����̉ۑ�ł��B
R8,R9�����R11��ύX�ŏ\�{���炢�̓C�P��͂��B
���ƁA�t�o�C�A�X��R��R6��������Əグ�邱�Ƃ��\�B
����ɁA
�ER8��20k����
�ER11��500����
�ER6��5.6K����
����ł�������P�����܂����B
�ł����āA
�Ȃ�ׂ��g�����W�X�^�őg��ł݂���A����ȕ��͋C���ȁ[�c�A�ƁB�����l�̓e�L�g�[�B
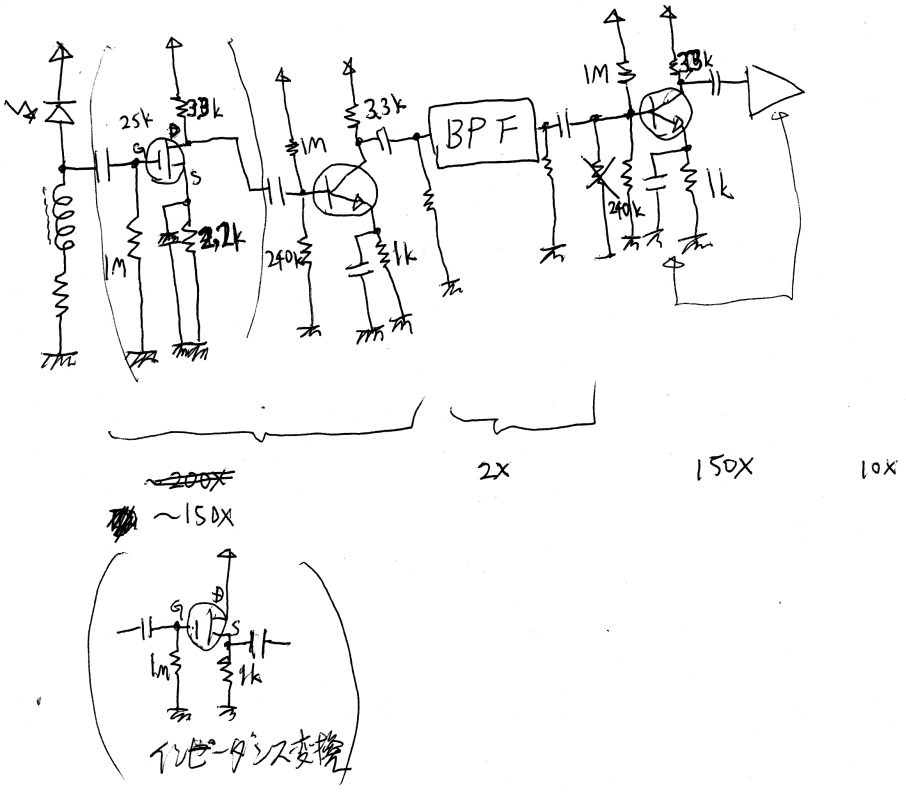 ���i��OP-AMP����Tr�Ɍ���������A
����̏I�i���S�i�ڂƂ��đ��݂��Ă����������B
�}�C�i�X���ɐU���U�����l���Ă݂�A
���̒i�̃g�����W�X�^�قǁA�o�C�A�X���R�����������ǂ��ł��ˁB
-------------------
�ŏI�i��OP-AMP�̌���
�g�����W�X�^������H��t���܂����B��2SC1815BL
�g�����W�X�^�̖��́A�d���d����Tr�̎�ނɂ���āA
�K���ȃo�C�A�X���Ƃ�鐔�l���Ⴄ�̂ŁA�ėp�����R�����Ƃ��������ł��B
(BPF�����U���Ȃ���A�ŏI�i��OP-AMP�̎�O�ɑ}�����������ǂ���H���Ǝv���܂��B)
���i��OP-AMP����Tr�Ɍ���������A
����̏I�i���S�i�ڂƂ��đ��݂��Ă����������B
�}�C�i�X���ɐU���U�����l���Ă݂�A
���̒i�̃g�����W�X�^�قǁA�o�C�A�X���R�����������ǂ��ł��ˁB
-------------------
�ŏI�i��OP-AMP�̌���
�g�����W�X�^������H��t���܂����B��2SC1815BL
�g�����W�X�^�̖��́A�d���d����Tr�̎�ނɂ���āA
�K���ȃo�C�A�X���Ƃ�鐔�l���Ⴄ�̂ŁA�ėp�����R�����Ƃ��������ł��B
(BPF�����U���Ȃ���A�ŏI�i��OP-AMP�̎�O�ɑ}�����������ǂ���H���Ǝv���܂��B)
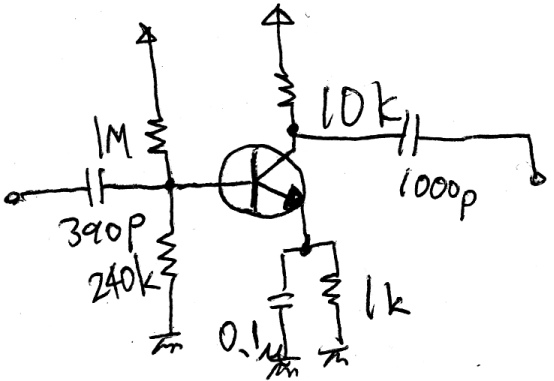 �}�̒ʂ�A�G�~�b�^��0.1��F���t���Ă邽�߁A250KHz������̍����g�M���ɂ�hfe�ő�������銴���ł��B
���ʂ́ABPF���痈��Ǝv����m�C�Y�����߂ł��B
���U��14MHz�t�߂͂ǂ��ɂ��Ȃ肻���ł����A
BPF�̌ŗL�U���炵���A��S�E���\KHz���o�Ă܂��B
���ꂪ�ATr�o�͂̎��_�ŁA2V�ȏ�ƂȂ�A�������Ă��������Ă��܂��܂��B
�Ȃ̂ŁABPF�̎�O�̑�������������x�グ�Ă݂����ł����A
�y��HPF�ȊO�t�B���^�Ȃ��̒i�K�ő傫����������̂�
�O������̊����m�C�Y�ŖO�a�����˂Ȃ��̂ŁA�������ȃ��m���ȁ[�Ǝv���܂��B�����܂�Ȃ������H
�Ƃ͂����A���ƁA5�{���炢�͑����ł������ł��ˁB
���̒��x����OP-AMP������Ȃ�̍������[�m�C�Y��I�t�Z�b�g��v�����܂��B
����ȊO���ƁAhfe�̍����g�����W�X�^�ł��ˁB
����ł��A�����R��������j�b�g�̃Q�C���ɂ͂���Ȃ������ł��B
�܂��A�ԊO�����g���A���{������x���オ�邩�ȁH�Ƃ͎v���܂����A�ȈՂ̂��߂̉������[�U�[�ł�����܂��̂ŁB
�σA�b�e�l�[�^�[��ʂ��A
�������ēK�x�Ȏ��Ԑϕ�����NJM2072�Ƃ������x�����o�pIC���g���̂��e�ł����A����IC��9V�쓮�ł͍�������̂Łc�A���g���Ă݂�����v�����ł����A
+-6V�d���ɂ��āA�o�C�A�X���{�d���Ɓ|�d���̊ԂŎ�邩�ł����邩���B
�ڕW�́A1mW�������[�U�[��3Km��ׂΗǂ��ł��ˁB
�Ƃ͂����A�l���Ă݂�ɁA�^�[�Q�b�g�������܂ʼn����ɂ���Q�[������
�t�B�[���h���L�����ĈӖ�����̂��͕s���ł����B
����ɁA���e�͒����Ō����Ŕ��ł��킯�ł������ł��̂ŁA���A�����Ƃ����ƑS�R�B
�����A��Ԃɂ́A5mW�̃��[�U�[��1200m��̏ċp���ɓ������Ă�̂��m�F�o����̂ł�����A
1Km�ʂ͏\���ɉ\�ɂ������ł��ˁB
38KHz�ł́A�������g���Ȃ��Ƃ����̂�����܂��̂ŁB
���ƂŋC�������̂ł����A�s�̂̐ԊO�����R�����W���[���ł����A
���o�͂̐ԊOLED�����ߋ�������_�������邾���Ō�쓮����Ƃ�������܂��B
����āA�R�����C���e���W�F���g�ȉ�H�ł͖����AAMP��BPF�ƃ��x���Z���T�[����{�̂悤�ł��ˁB
�ԊO�������R��������W���[���́A
�����Y��������x�������A�h�������܂ȂǂŐԊO�t�B���^�[����菜����Ή����Ŏg�����ɂȂ邩���B
���ɂ������ł����A�U�d�̑��w���̌��w�IBPF�ŖړI�̉������[�U�[�݂̂�ʂ��A��쓮���܂����蓾�Ȃ��ł��B
�U�d�̑��w�����w�t�B���^�͔��ɂ������Ƃ͌����A
�P�i��30����30����Ă����z30���Ƃ����悤�ɁA
�����ď������̂�ʎY����A�Ƃ�ł��Ȃ������Ȃ�܂��B
�\�ʐ��x��A
�����ȃK���X���g�킸�A�ėp�i�̂悤�ɗʎY����A���S�~�����Ȃ��Ǝv���܂��B
---------------------------------------------------------------------
�C�ɂ͂Ȃ��Ă��̂ł����A���U�̌����ɁA
�����`�A�i�q�^�ɉ�H��g�ނƔ��U���₷���̂����邩���ł��B
�x�^GND�ƌ����̂��ǂ��̂ł����A
���j�o�[�T����̎�����H�ł́A���Â炭�A����Â炭�A�ł��B
�����A����͐��SKHz�ŋN���錻�ۂƂ��v�����c�A
�܂��A
BPF�ɐV���Ȍ`���������܂����B
�E�B�[���u���b�W���Ƃ������ƂȂ̂ŁA���U���₷�������H
�}�̒ʂ�A�G�~�b�^��0.1��F���t���Ă邽�߁A250KHz������̍����g�M���ɂ�hfe�ő�������銴���ł��B
���ʂ́ABPF���痈��Ǝv����m�C�Y�����߂ł��B
���U��14MHz�t�߂͂ǂ��ɂ��Ȃ肻���ł����A
BPF�̌ŗL�U���炵���A��S�E���\KHz���o�Ă܂��B
���ꂪ�ATr�o�͂̎��_�ŁA2V�ȏ�ƂȂ�A�������Ă��������Ă��܂��܂��B
�Ȃ̂ŁABPF�̎�O�̑�������������x�グ�Ă݂����ł����A
�y��HPF�ȊO�t�B���^�Ȃ��̒i�K�ő傫����������̂�
�O������̊����m�C�Y�ŖO�a�����˂Ȃ��̂ŁA�������ȃ��m���ȁ[�Ǝv���܂��B�����܂�Ȃ������H
�Ƃ͂����A���ƁA5�{���炢�͑����ł������ł��ˁB
���̒��x����OP-AMP������Ȃ�̍������[�m�C�Y��I�t�Z�b�g��v�����܂��B
����ȊO���ƁAhfe�̍����g�����W�X�^�ł��ˁB
����ł��A�����R��������j�b�g�̃Q�C���ɂ͂���Ȃ������ł��B
�܂��A�ԊO�����g���A���{������x���オ�邩�ȁH�Ƃ͎v���܂����A�ȈՂ̂��߂̉������[�U�[�ł�����܂��̂ŁB
�σA�b�e�l�[�^�[��ʂ��A
�������ēK�x�Ȏ��Ԑϕ�����NJM2072�Ƃ������x�����o�pIC���g���̂��e�ł����A����IC��9V�쓮�ł͍�������̂Łc�A���g���Ă݂�����v�����ł����A
+-6V�d���ɂ��āA�o�C�A�X���{�d���Ɓ|�d���̊ԂŎ�邩�ł����邩���B
�ڕW�́A1mW�������[�U�[��3Km��ׂΗǂ��ł��ˁB
�Ƃ͂����A�l���Ă݂�ɁA�^�[�Q�b�g�������܂ʼn����ɂ���Q�[������
�t�B�[���h���L�����ĈӖ�����̂��͕s���ł����B
����ɁA���e�͒����Ō����Ŕ��ł��킯�ł������ł��̂ŁA���A�����Ƃ����ƑS�R�B
�����A��Ԃɂ́A5mW�̃��[�U�[��1200m��̏ċp���ɓ������Ă�̂��m�F�o����̂ł�����A
1Km�ʂ͏\���ɉ\�ɂ������ł��ˁB
38KHz�ł́A�������g���Ȃ��Ƃ����̂�����܂��̂ŁB
���ƂŋC�������̂ł����A�s�̂̐ԊO�����R�����W���[���ł����A
���o�͂̐ԊOLED�����ߋ�������_�������邾���Ō�쓮����Ƃ�������܂��B
����āA�R�����C���e���W�F���g�ȉ�H�ł͖����AAMP��BPF�ƃ��x���Z���T�[����{�̂悤�ł��ˁB
�ԊO�������R��������W���[���́A
�����Y��������x�������A�h�������܂ȂǂŐԊO�t�B���^�[����菜����Ή����Ŏg�����ɂȂ邩���B
���ɂ������ł����A�U�d�̑��w���̌��w�IBPF�ŖړI�̉������[�U�[�݂̂�ʂ��A��쓮���܂����蓾�Ȃ��ł��B
�U�d�̑��w�����w�t�B���^�͔��ɂ������Ƃ͌����A
�P�i��30����30����Ă����z30���Ƃ����悤�ɁA
�����ď������̂�ʎY����A�Ƃ�ł��Ȃ������Ȃ�܂��B
�\�ʐ��x��A
�����ȃK���X���g�킸�A�ėp�i�̂悤�ɗʎY����A���S�~�����Ȃ��Ǝv���܂��B
---------------------------------------------------------------------
�C�ɂ͂Ȃ��Ă��̂ł����A���U�̌����ɁA
�����`�A�i�q�^�ɉ�H��g�ނƔ��U���₷���̂����邩���ł��B
�x�^GND�ƌ����̂��ǂ��̂ł����A
���j�o�[�T����̎�����H�ł́A���Â炭�A����Â炭�A�ł��B
�����A����͐��SKHz�ŋN���錻�ۂƂ��v�����c�A
�܂��A
BPF�ɐV���Ȍ`���������܂����B
�E�B�[���u���b�W���Ƃ������ƂȂ̂ŁA���U���₷�������H
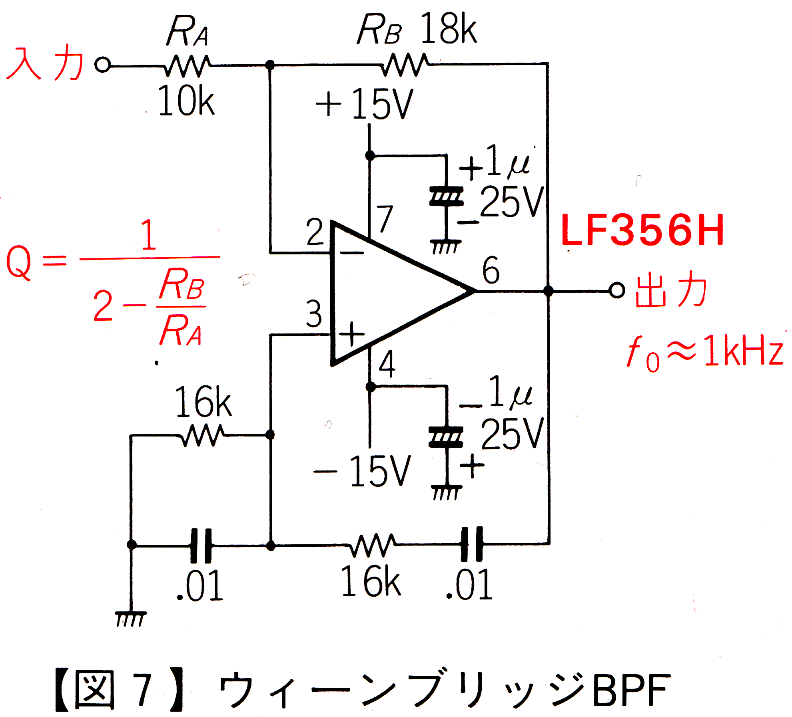 �ǂ����Ă��_���Ȃ炱��������Č��悤���ƁB
----------------------------------------------------------------------
�ł����āA
�V�O�i���W�F�l���[�^�[�Ȕ��M�킩����𑗂��Ă݂�ƁA
DABP��BPF�́A�����Ɠ��삵�Ă��邱�Ƃ�����܂����B
����ɂ��ւ�炸�A
�����R���̔g�`���傫���o�Ă��܂�������́A
�I�[�o�[�h���C�u���Ă�̂ɉ����āA
�t�H�g�_�C�I�[�h�̊��x�������̈�́A
�ԊO���Ƃ����A�h�o���e�[�W�����Ȃ肠��悤�ł��B
250KHz������̔��U�C���ȕ������A
BPF��OP-AMP�Ɏ��G���Ə����܂��B
���d�r���ڂ����Ă����Ȃ��܂�܂��B�����͍��̂Ƃ��H�ł��B
���Ƃ�14MHz���x�̔��U���J�b�g���邱�ƂƁA
20�`100�{���炢�Q�C�����҂����Ƃ��o������Ȃ���p�ɋ߂��Ȃ邩�Ǝv���܂��B
-----------------------------------------
�l���Ă݂��̂ł����A
���x(������)���̂́A���̏�ԂŁA�\���ԊO�����R���ɋ߂��Ǝv���܂��B
�ł��A�����ł����AS/N�̖�肩�����������Ɨ~���������ł��ˁB
--------------------------------------------------------------------
��Ԉ���50�~�̃����R��������W���[���̃��[���h��h�������܂ŗn�����Ă݂܂����B
�ꃖ�����炢�����܂����B
�ǂ����Ă��_���Ȃ炱��������Č��悤���ƁB
----------------------------------------------------------------------
�ł����āA
�V�O�i���W�F�l���[�^�[�Ȕ��M�킩����𑗂��Ă݂�ƁA
DABP��BPF�́A�����Ɠ��삵�Ă��邱�Ƃ�����܂����B
����ɂ��ւ�炸�A
�����R���̔g�`���傫���o�Ă��܂�������́A
�I�[�o�[�h���C�u���Ă�̂ɉ����āA
�t�H�g�_�C�I�[�h�̊��x�������̈�́A
�ԊO���Ƃ����A�h�o���e�[�W�����Ȃ肠��悤�ł��B
250KHz������̔��U�C���ȕ������A
BPF��OP-AMP�Ɏ��G���Ə����܂��B
���d�r���ڂ����Ă����Ȃ��܂�܂��B�����͍��̂Ƃ��H�ł��B
���Ƃ�14MHz���x�̔��U���J�b�g���邱�ƂƁA
20�`100�{���炢�Q�C�����҂����Ƃ��o������Ȃ���p�ɋ߂��Ȃ邩�Ǝv���܂��B
-----------------------------------------
�l���Ă݂��̂ł����A
���x(������)���̂́A���̏�ԂŁA�\���ԊO�����R���ɋ߂��Ǝv���܂��B
�ł��A�����ł����AS/N�̖�肩�����������Ɨ~���������ł��ˁB
--------------------------------------------------------------------
��Ԉ���50�~�̃����R��������W���[���̃��[���h��h�������܂ŗn�����Ă݂܂����B
�ꃖ�����炢�����܂����B
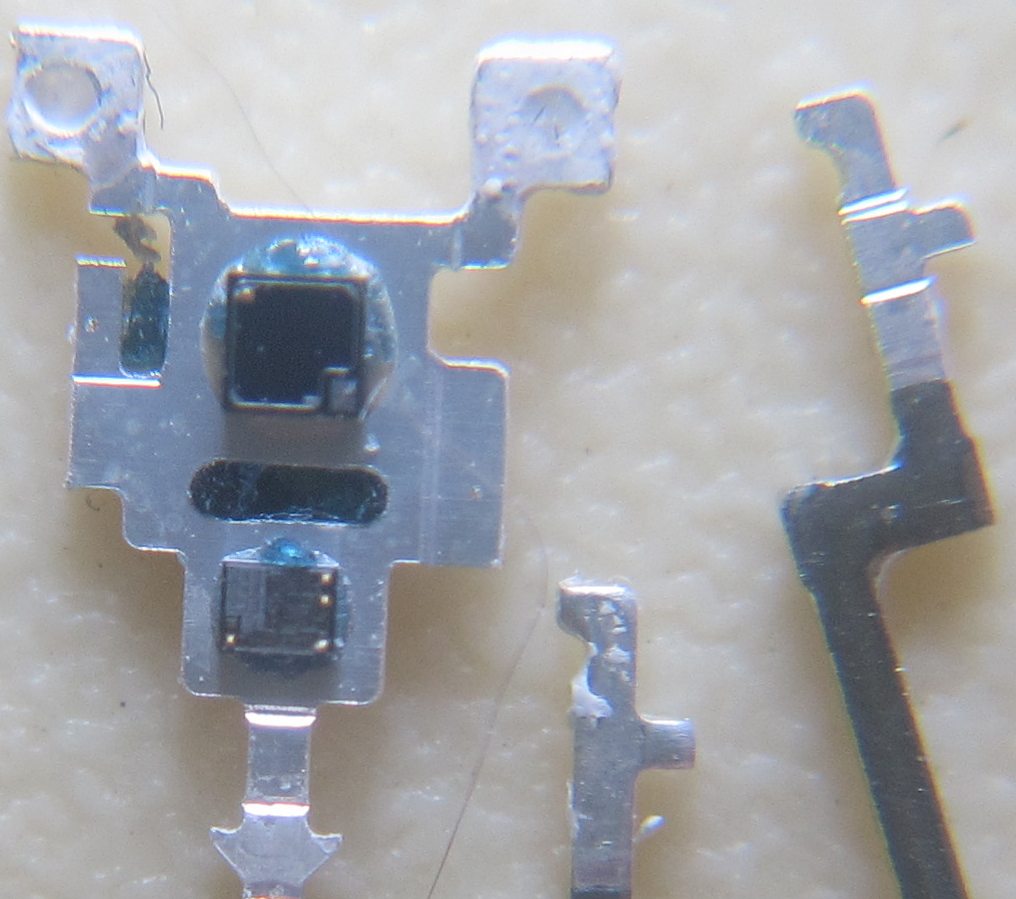 ��̍����̂��Z���T�[�ŁA�����`�b�v�ł��ˁB
���m�ɂ���ĈႤ�����m��Ȃ��ł����A
�z���͔��ɍׂ��悤�ŁA�Y�킳���ς薳���Ȃ��Ă܂����B
�����炯�Ă܂������A����͔��c�t���ł����ČŒ肵�Ă������Ƃłǂ��ɂ��o���邩���H
�Z���T�[�ƃ`�b�v����̉����Ă郂�m������Ώ����͊y�����m��Ȃ��ł��ˁB
--------------------------------------------------------
�A�T�q�y���ł͖����A
HOLTS�̋����^�C�v�������Č��܂����B
��ڂ̖ړI�́A�����\����m�邱�Ƃł��āA
�\�ɃV�[���h�������Ȃ����̂́A
�R�̎��ɋȂ����Ăē����ŃV�[���h���ꋏ�郂�m�������ł��B
�܂��A�����ȕ����̂�����܂����A����͐��i�ɂ�邩���ł����A
�V�[���h�͂���܂���ł����B
�������A���̉t�́A�n�����Ɩ�肪����ł܂����B
�`�b�v�̐ڒ��܂��������B
�������c������B���d�C�I�����������������
�ł��B
�Ȃ̂ŁA
�ア�^�C�v�ŁA�V�[���h���O���ɂ����āA�n�Y�����A
��قǂ̐��������̃^�C�v�ł���Ă݂邩�ł����A���Ԃ������肷����̂Ŏ��p�I�ł͂���܂���B
�����ŁA�L�p�ȕ��@�́A�V�[���h�^�C�v�̍��o���ł��B
�������A���̂ŁA�Z���T�[�⌋��������O�ɋC�����܂��B
�������A���ꂾ�ƁA�t�B���^��S�����̂̓����ł��B
�������A���_������܂��B
�t�B���^���ɓx�ɔ����Ȃ������Ƃɂ��A850nm�t�߂̊��x�͔���I�ɏオ��ł��傤�B
�܂��A�ʂŃ����Y��ݒu���邱�Ƃ��o���܂��B
�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
17/04/29
�g�����W�X�^���g�p�������m���A
������ƍl���悤�Ǝv���܂��āc�A
��̍����̂��Z���T�[�ŁA�����`�b�v�ł��ˁB
���m�ɂ���ĈႤ�����m��Ȃ��ł����A
�z���͔��ɍׂ��悤�ŁA�Y�킳���ς薳���Ȃ��Ă܂����B
�����炯�Ă܂������A����͔��c�t���ł����ČŒ肵�Ă������Ƃłǂ��ɂ��o���邩���H
�Z���T�[�ƃ`�b�v����̉����Ă郂�m������Ώ����͊y�����m��Ȃ��ł��ˁB
--------------------------------------------------------
�A�T�q�y���ł͖����A
HOLTS�̋����^�C�v�������Č��܂����B
��ڂ̖ړI�́A�����\����m�邱�Ƃł��āA
�\�ɃV�[���h�������Ȃ����̂́A
�R�̎��ɋȂ����Ăē����ŃV�[���h���ꋏ�郂�m�������ł��B
�܂��A�����ȕ����̂�����܂����A����͐��i�ɂ�邩���ł����A
�V�[���h�͂���܂���ł����B
�������A���̉t�́A�n�����Ɩ�肪����ł܂����B
�`�b�v�̐ڒ��܂��������B
�������c������B���d�C�I�����������������
�ł��B
�Ȃ̂ŁA
�ア�^�C�v�ŁA�V�[���h���O���ɂ����āA�n�Y�����A
��قǂ̐��������̃^�C�v�ł���Ă݂邩�ł����A���Ԃ������肷����̂Ŏ��p�I�ł͂���܂���B
�����ŁA�L�p�ȕ��@�́A�V�[���h�^�C�v�̍��o���ł��B
�������A���̂ŁA�Z���T�[�⌋��������O�ɋC�����܂��B
�������A���ꂾ�ƁA�t�B���^��S�����̂̓����ł��B
�������A���_������܂��B
�t�B���^���ɓx�ɔ����Ȃ������Ƃɂ��A850nm�t�߂̊��x�͔���I�ɏオ��ł��傤�B
�܂��A�ʂŃ����Y��ݒu���邱�Ƃ��o���܂��B
�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
17/04/29
�g�����W�X�^���g�p�������m���A
������ƍl���悤�Ǝv���܂��āc�A
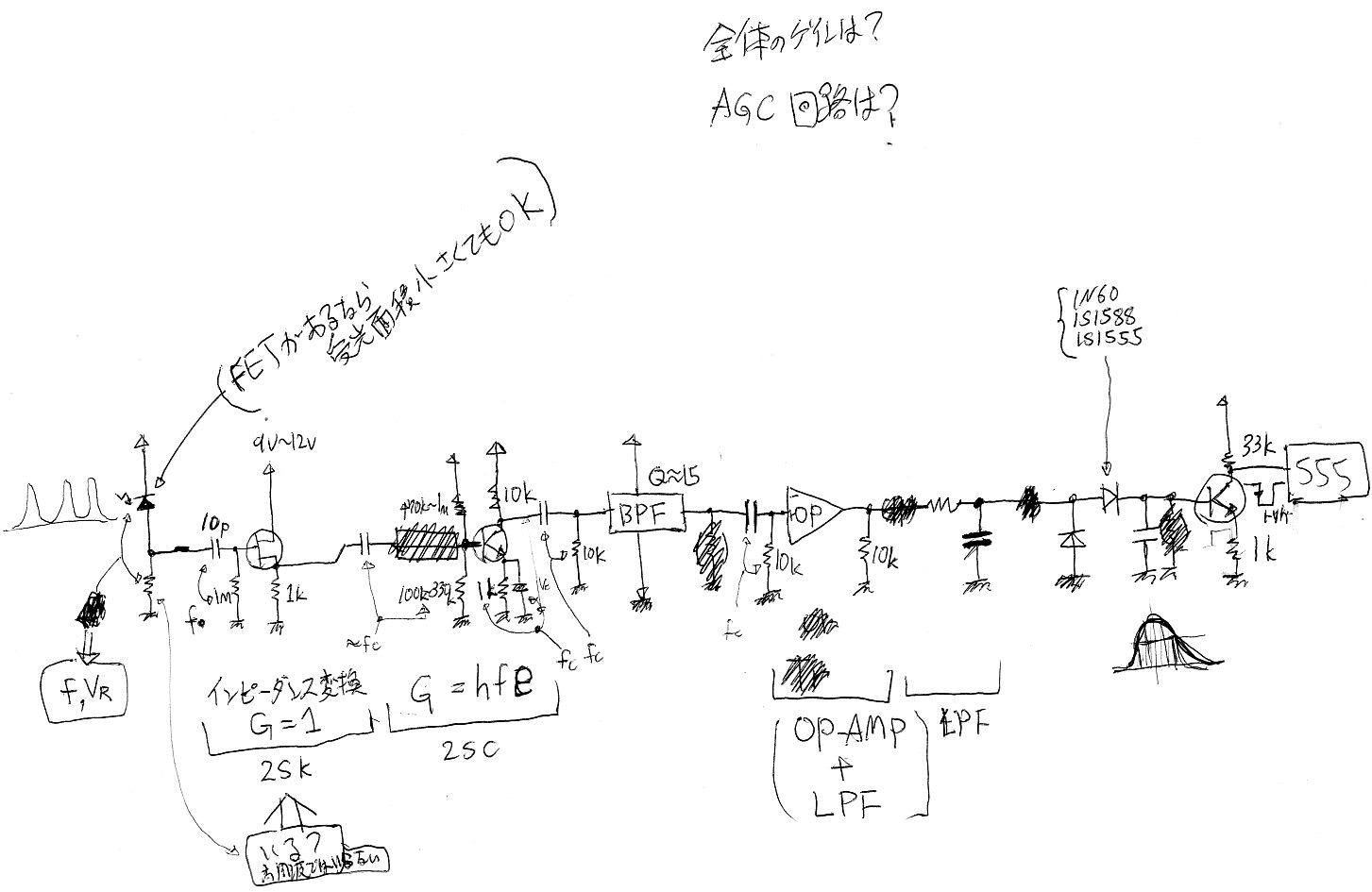 �\�z���Ƃ��������ł����A
Tr���ƁA��R�̒萔���A�d���d����Tr�̋K�i�ɂ���ĕς��̂��Y�݂ǂ���ł��ˁB
17/04/30
������Ƒg��ł�r���ł���
�����ƃQ�C�����K�v�Ȃ̂ŁA
���͂���BPF�܂ł̑�����1�i���₷�������ǂ��悤�ł��B
-------------------------
17/05/01
BPF�܂ł�Pre-Amp�I�������قڊm��B
�d���́ATr�̃o�C�A�X�̉�������12.5V���x���K���B
(9V�̏ꍇ�́A50K����74K����)
�\�z���Ƃ��������ł����A
Tr���ƁA��R�̒萔���A�d���d����Tr�̋K�i�ɂ���ĕς��̂��Y�݂ǂ���ł��ˁB
17/04/30
������Ƒg��ł�r���ł���
�����ƃQ�C�����K�v�Ȃ̂ŁA
���͂���BPF�܂ł̑�����1�i���₷�������ǂ��悤�ł��B
-------------------------
17/05/01
BPF�܂ł�Pre-Amp�I�������قڊm��B
�d���́ATr�̃o�C�A�X�̉�������12.5V���x���K���B
(9V�̏ꍇ�́A50K����74K����)
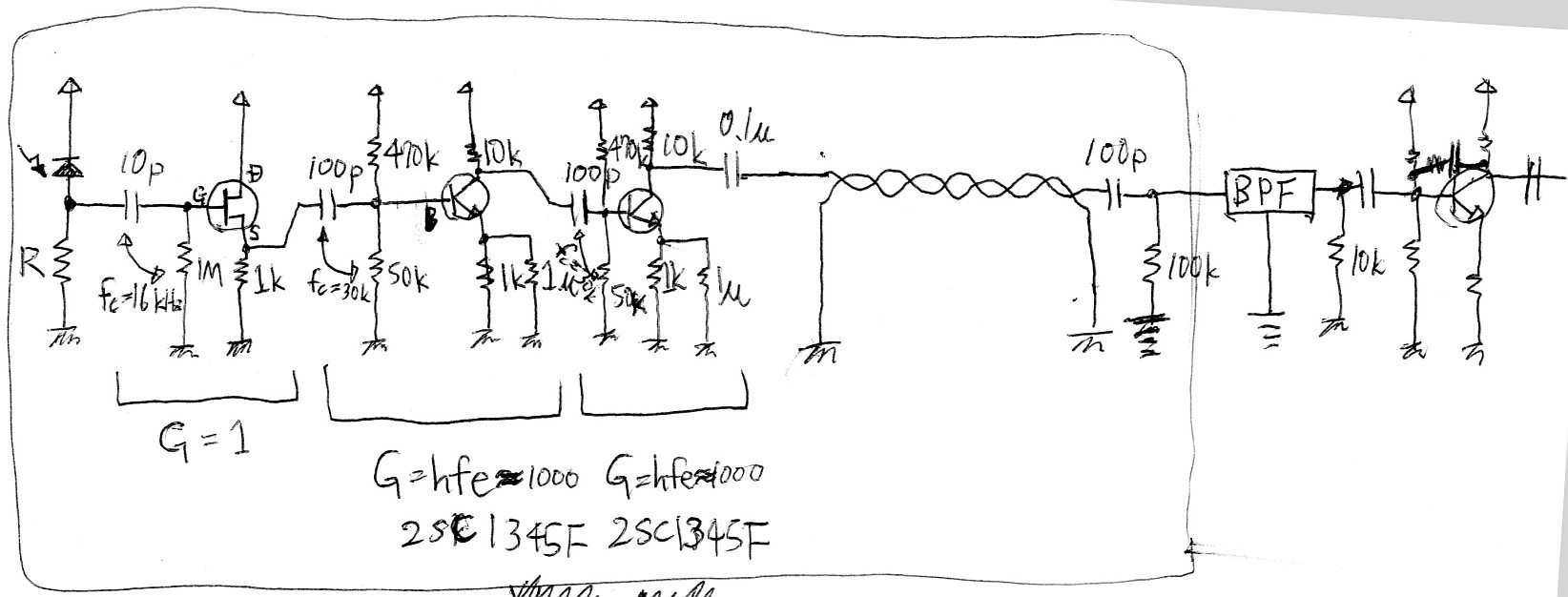
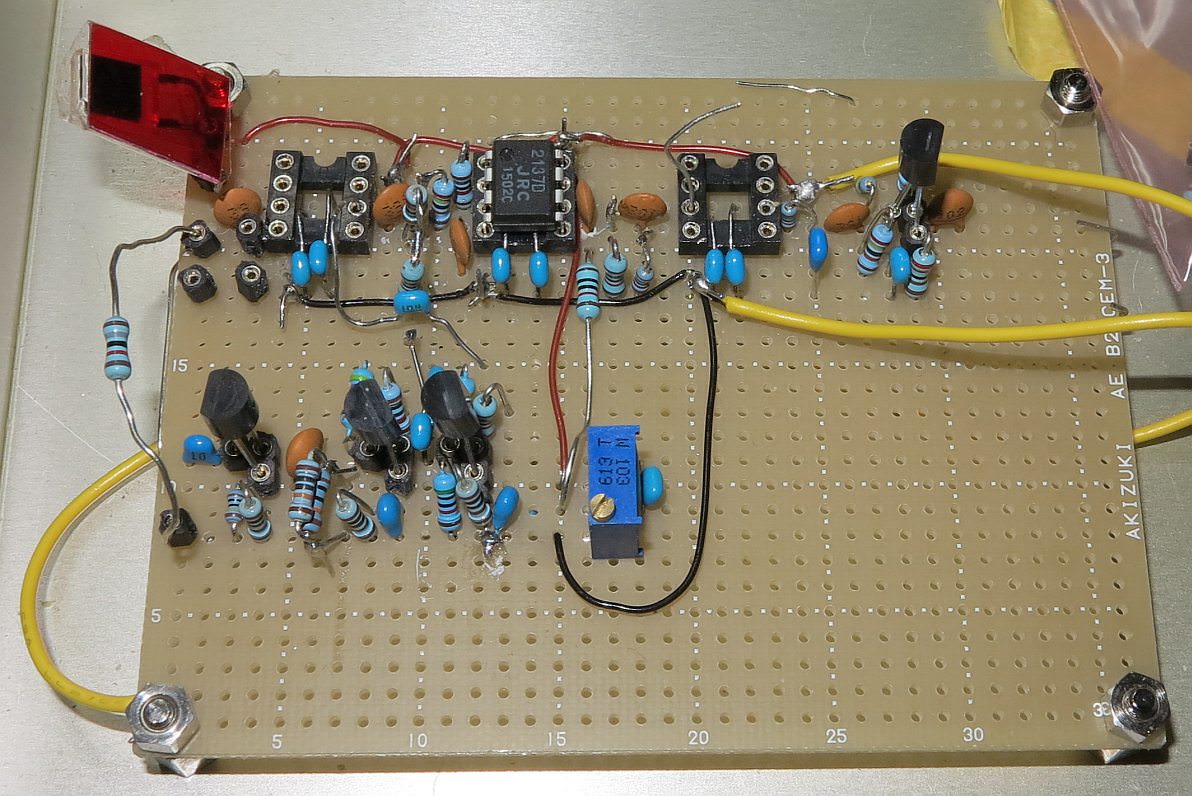 38KH����������悤�Ȑ��l�ɂ��Ă܂����A250KH���Ɍ����Ă��܂��A����g�͂����ƃJ�b�g�o���܂��ˁB
�Q�C�����傫���̂ŁABPF����̗U�������͂ɖ߂��Ă��āA���U�C���ł��B
(���͑��P�̂ł͔��U���Ȃ��B)
���̌���BPF��MHz�I�[�_�[�Ŕ��U���Ă�̂ŁA�R����}���邩�A���̃t�B���^�Ŏ�菜���K�v���B
���U�́A250MHz�A500MHz�A7MHz�t�߂ŋN���܂��B
7MHz��LPF�ŏ���
250Hz�����500Hz�͓��͂ւ̗U���ɂ�锭�U�ł��邱�Ƃ������B���P�[�X�̕߉����ŕς��܂��B
�Ȃ̂ŁA���͂���BPF����̗U���܂ł̉�H�̎�����A�V�[���h�ɋC���g���B
���Ƃ́A�V�[���h�̊O�ɏo���Ĉ����Ă��Ɨǂ����Ǝv���܂����B
�v�����̂ł����A250KHz�Ȃ�A
Q�l������������Ɖ�������A
�������ċ��U��H�ɂ��Ȃ��ŁA
LPF�AHPF�̑��i�ł�����قǖ��͖������ȁ[
�Ǝv���܂����B
�ǂ�����������čl����ƁA
Q�l��10�`12�ʂɁB
HPF�́A160Hz��
LPF�́A350Hz��
�łȂ�ׂ����i�ɂ���B
OP-AMP�̓d���d���������邱�Ƃɂ���Ĕ��U�����Ȃ��܂邱�Ƃ������B
------------------------------
17/05/07
RC�w����FCU�̂��߁A�t�H�[�}�b�g����OS��Win7�Ƀ_�E���O���[�h�������߁A
PSpice��OrCAD���V���ɓ���āA��H���ꏏ�ɏ����Ă��܂��Ă������߁A�V�����܂����B
����́A���i��Tr�Ȃ̂ŁA�����Ǝ��ۂ̎g�p�ƍ��v���郂�m�������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ������ł��B
���C�u�����́A�{�ɂ�����
TORAGI
�p�[�c�ƃ��C�u�����̈ꗗ�\��PDF����
JBIPOLAR
JJFET
���g�p�B
38KH����������悤�Ȑ��l�ɂ��Ă܂����A250KH���Ɍ����Ă��܂��A����g�͂����ƃJ�b�g�o���܂��ˁB
�Q�C�����傫���̂ŁABPF����̗U�������͂ɖ߂��Ă��āA���U�C���ł��B
(���͑��P�̂ł͔��U���Ȃ��B)
���̌���BPF��MHz�I�[�_�[�Ŕ��U���Ă�̂ŁA�R����}���邩�A���̃t�B���^�Ŏ�菜���K�v���B
���U�́A250MHz�A500MHz�A7MHz�t�߂ŋN���܂��B
7MHz��LPF�ŏ���
250Hz�����500Hz�͓��͂ւ̗U���ɂ�锭�U�ł��邱�Ƃ������B���P�[�X�̕߉����ŕς��܂��B
�Ȃ̂ŁA���͂���BPF����̗U���܂ł̉�H�̎�����A�V�[���h�ɋC���g���B
���Ƃ́A�V�[���h�̊O�ɏo���Ĉ����Ă��Ɨǂ����Ǝv���܂����B
�v�����̂ł����A250KHz�Ȃ�A
Q�l������������Ɖ�������A
�������ċ��U��H�ɂ��Ȃ��ŁA
LPF�AHPF�̑��i�ł�����قǖ��͖������ȁ[
�Ǝv���܂����B
�ǂ�����������čl����ƁA
Q�l��10�`12�ʂɁB
HPF�́A160Hz��
LPF�́A350Hz��
�łȂ�ׂ����i�ɂ���B
OP-AMP�̓d���d���������邱�Ƃɂ���Ĕ��U�����Ȃ��܂邱�Ƃ������B
------------------------------
17/05/07
RC�w����FCU�̂��߁A�t�H�[�}�b�g����OS��Win7�Ƀ_�E���O���[�h�������߁A
PSpice��OrCAD���V���ɓ���āA��H���ꏏ�ɏ����Ă��܂��Ă������߁A�V�����܂����B
����́A���i��Tr�Ȃ̂ŁA�����Ǝ��ۂ̎g�p�ƍ��v���郂�m�������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ������ł��B
���C�u�����́A�{�ɂ�����
TORAGI
�p�[�c�ƃ��C�u�����̈ꗗ�\��PDF����
JBIPOLAR
JJFET
���g�p�B
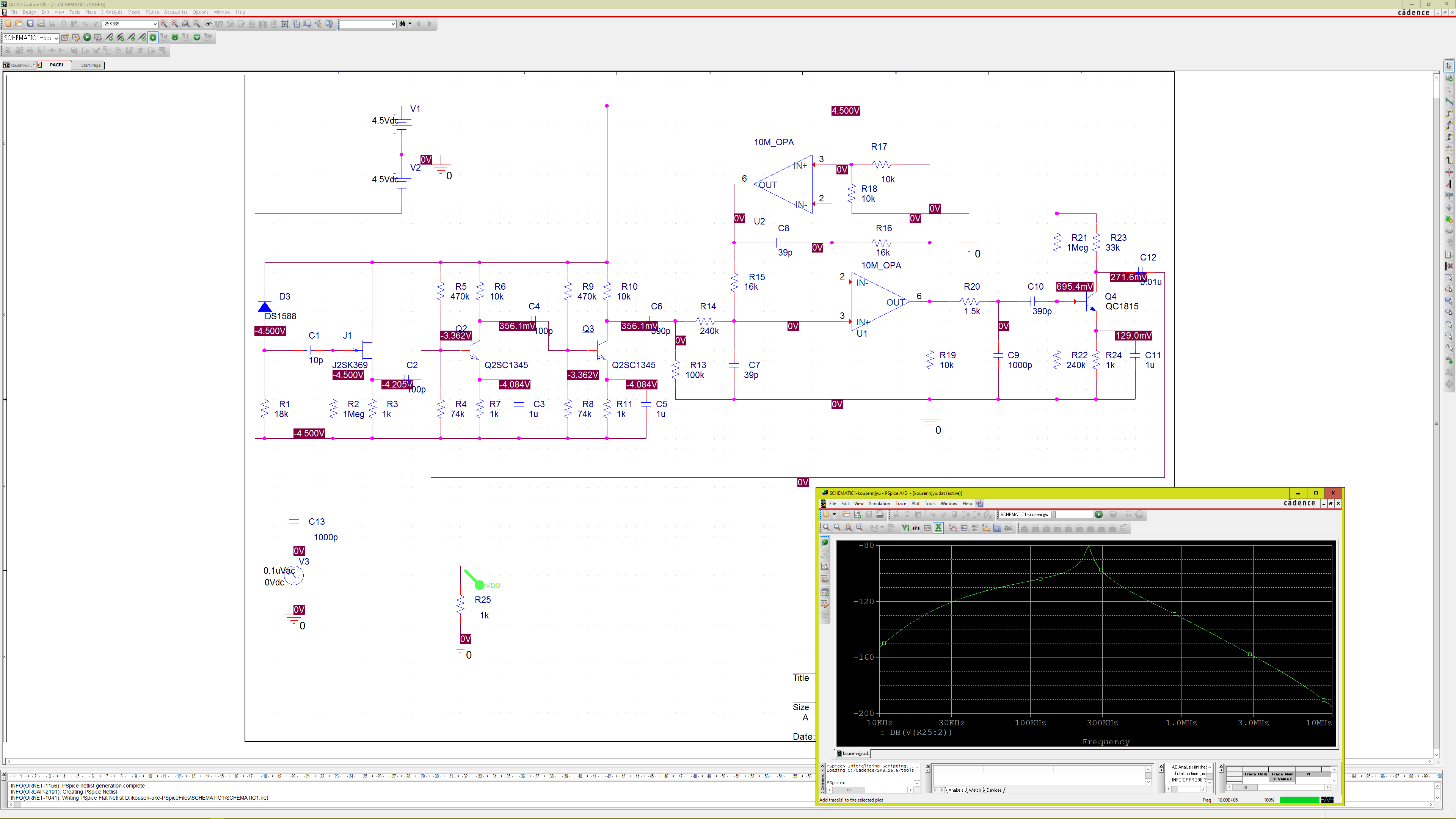 �Q�C�����Ⴗ����̂́A�����ƃo�C�A�X�L���͈͂��Y���Ă邩��H
�O�p�g���͂ŏo�͔g�`��������A���j�A���e�B�[������܂��B
���ƁA�O���̉�H�́A38KHz���l���ɓ���Đv���Ă邽�߁A
������ϕ���H������250KHz��p�ɘM��A�����ƃm�C�Y�����点�邩���A
���U��H�O�ɏ���LPF�v�f������Ă����ƃC�C�����H
�O��ŃV�[���h����B
17/05/08
���ATr�̓��͂ɐÓd�e�ʂ����邱�Ƃ��v�Z�ɓ���ĂȂ����ƂɋC�Â��܂����B
�C���s�[�_���X�܂��A�o�C�A�X��R���������ł��B
hfe�Ƃ́A�u�d���v�������Ȃ̂ŗL�����p�o������@���A���H
�Ƃ������Ƃ́A
�J�b�g�I�t���Â߂ɑ��i��CR�t�B���^�̃��X������
Tr�̃o�C�A�X��{���ƃC���s�[�_���X���l�����A�K���o�����X�ɑI�Ԃ��ƂƁA
Tr�͑������̍������m��I�Ԃ��ƁB
���ɏI�i�̑��������グ��B
�Ƃ肠����Tr����������250K��p�����Ă��A�O�{�����ł��B
�Q�C�����Ⴗ����̂́A�����ƃo�C�A�X�L���͈͂��Y���Ă邩��H
�O�p�g���͂ŏo�͔g�`��������A���j�A���e�B�[������܂��B
���ƁA�O���̉�H�́A38KHz���l���ɓ���Đv���Ă邽�߁A
������ϕ���H������250KHz��p�ɘM��A�����ƃm�C�Y�����点�邩���A
���U��H�O�ɏ���LPF�v�f������Ă����ƃC�C�����H
�O��ŃV�[���h����B
17/05/08
���ATr�̓��͂ɐÓd�e�ʂ����邱�Ƃ��v�Z�ɓ���ĂȂ����ƂɋC�Â��܂����B
�C���s�[�_���X�܂��A�o�C�A�X��R���������ł��B
hfe�Ƃ́A�u�d���v�������Ȃ̂ŗL�����p�o������@���A���H
�Ƃ������Ƃ́A
�J�b�g�I�t���Â߂ɑ��i��CR�t�B���^�̃��X������
Tr�̃o�C�A�X��{���ƃC���s�[�_���X���l�����A�K���o�����X�ɑI�Ԃ��ƂƁA
Tr�͑������̍������m��I�Ԃ��ƁB
���ɏI�i�̑��������グ��B
�Ƃ肠����Tr����������250K��p�����Ă��A�O�{�����ł��B
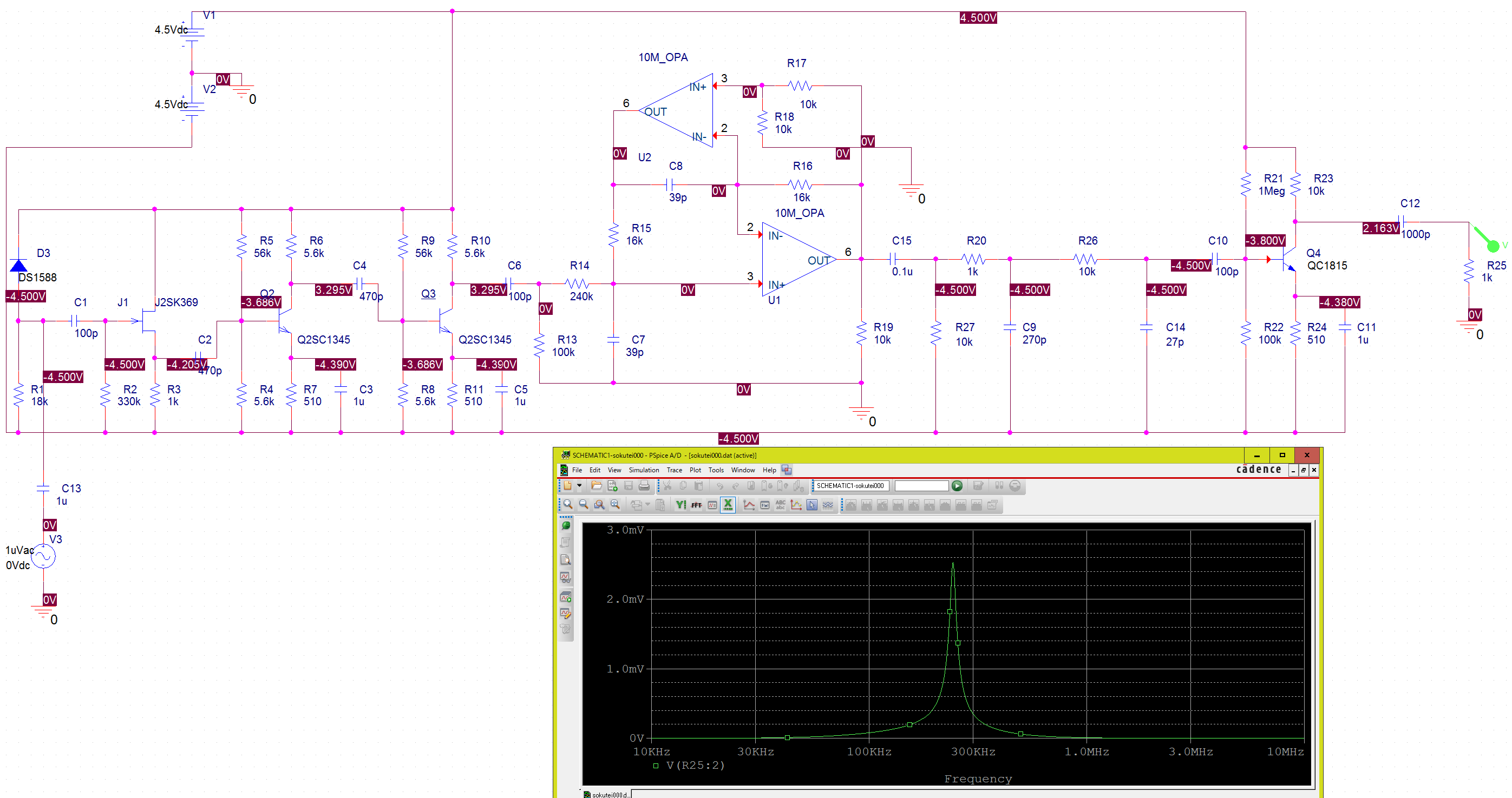 2�i�ڈȍ~���n�C�C���s�[�_���X�ɂ���K�v�͖����A
���͂ɐÓd�e�ʂ�����̂ŁA���͂̃C���s�[�_���X�������ē��͂̃f�J�b�v�����O�R���f���T�[���傫�߂ł��L���ɂ���B
����ɍ��킹�āA�o�̓C���s�[�_���X���Ⴍ�B
���͂̐Ód�e�ʂ��l����ƁA�����g������Tr���L���H
����FET�̓��͂�C������Vgd�ł��ς��B
�S�ʓI�Ƀg�����W�X�^�́A
���ۂ̉�H�̕����o�͔{���������B
�����N���Ⴄ����Ƃ������Ƃ�������x���邪�A
�I�i�́A�V�~���Ǝ��ۂ�10�{���鍷���o�Ă�B
�g�����W�X�^�̃o�C�A�X�͌��\�d���d���ɃV�r�A�Ȃ��Ƃ��A���B
���������l����ƁA���߂��C�C�ł����A
�ł�ł��l�������͈͂ɓ���Ȃ��ƁA�M�����O�a���āA�t�ɏ������Ȃ�B
17/05/10
�I�i�����őg��ł݂��g�R�B
2�i�ڈȍ~���n�C�C���s�[�_���X�ɂ���K�v�͖����A
���͂ɐÓd�e�ʂ�����̂ŁA���͂̃C���s�[�_���X�������ē��͂̃f�J�b�v�����O�R���f���T�[���傫�߂ł��L���ɂ���B
����ɍ��킹�āA�o�̓C���s�[�_���X���Ⴍ�B
���͂̐Ód�e�ʂ��l����ƁA�����g������Tr���L���H
����FET�̓��͂�C������Vgd�ł��ς��B
�S�ʓI�Ƀg�����W�X�^�́A
���ۂ̉�H�̕����o�͔{���������B
�����N���Ⴄ����Ƃ������Ƃ�������x���邪�A
�I�i�́A�V�~���Ǝ��ۂ�10�{���鍷���o�Ă�B
�g�����W�X�^�̃o�C�A�X�͌��\�d���d���ɃV�r�A�Ȃ��Ƃ��A���B
���������l����ƁA���߂��C�C�ł����A
�ł�ł��l�������͈͂ɓ���Ȃ��ƁA�M�����O�a���āA�t�ɏ������Ȃ�B
17/05/10
�I�i�����őg��ł݂��g�R�B
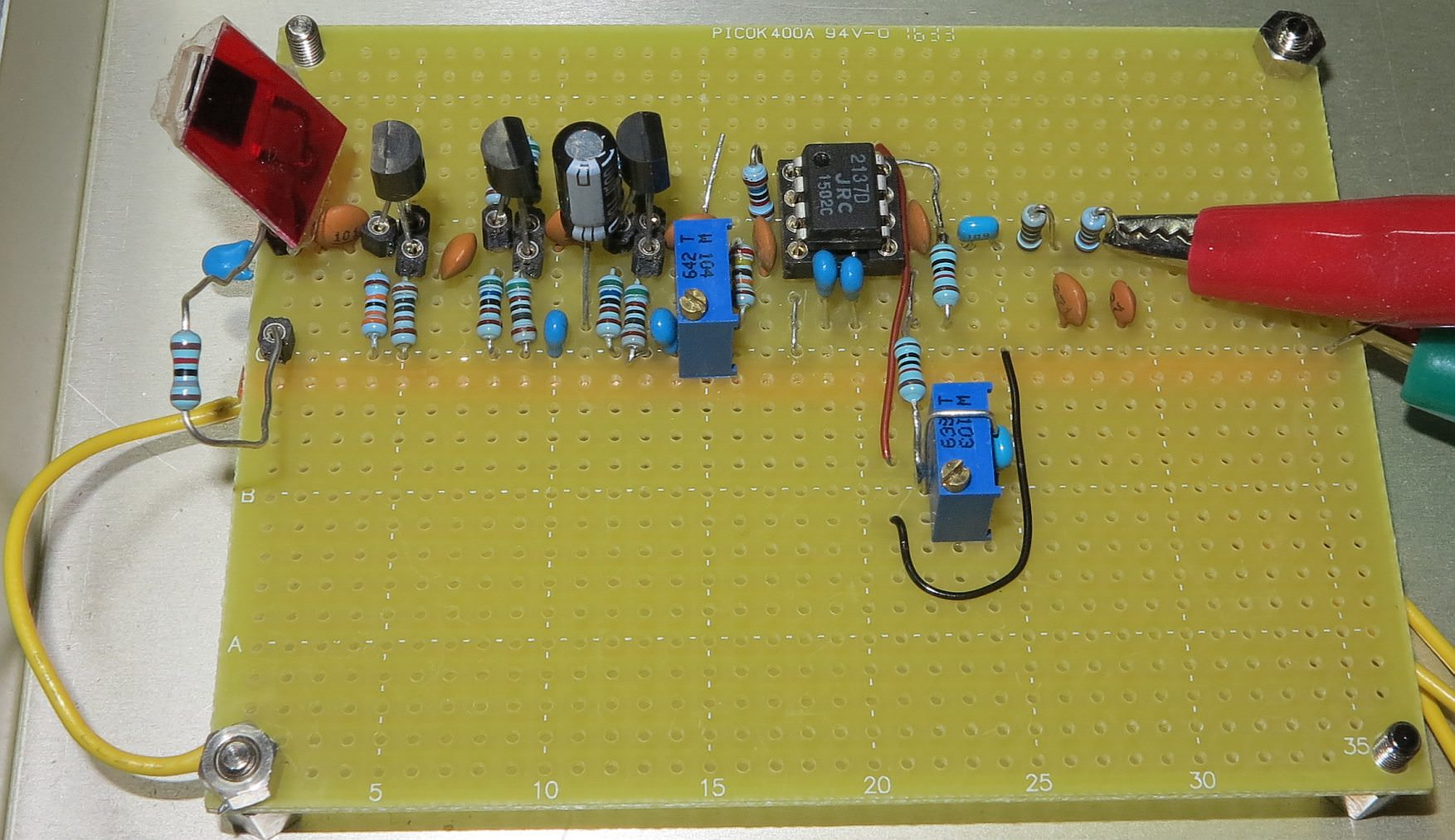
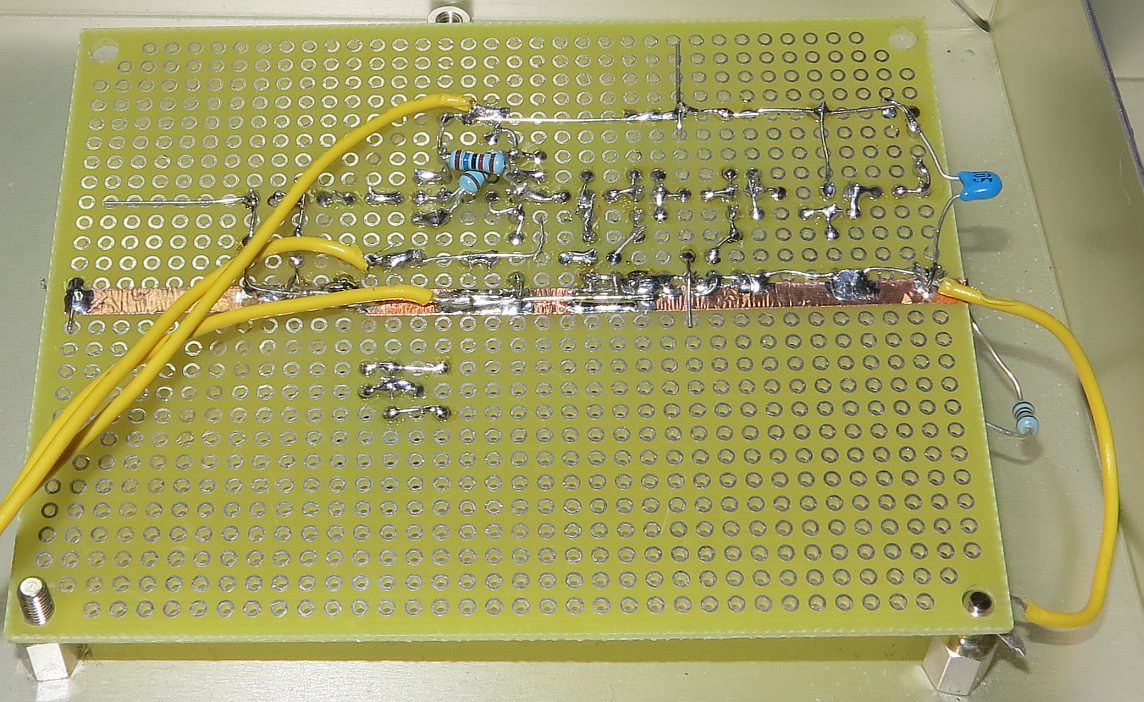 ���U�ɂ͔Y�܂��ꂽ���ǁA�d������ɃR���f���T�[��t�����炩�Ȃ�ጸ���܂����B
�R���f���T�[�́A�t����ʒu�ɂ���ẮA�t�ɁA���U���傫���Ȃ����肵�܂��B
������ɂ�鍷�����Ȃ�o�邱�Ƃ����������܂��B
���ƁALPF�͓�i�������܂������ABPF����8MHz�ʂ̂��܂���������ƘR��Ă܂��B
���U���̂����炷���Ƃ͉\�Ȃ̂��s���ł����A
�X�ɏI�i�Ƀt�B���^�ŗ}�����邩�Ǝv���܂��B
���̓��͂͂Ȃ��ŁA���̏�Ԃł��B
���U�ɂ͔Y�܂��ꂽ���ǁA�d������ɃR���f���T�[��t�����炩�Ȃ�ጸ���܂����B
�R���f���T�[�́A�t����ʒu�ɂ���ẮA�t�ɁA���U���傫���Ȃ����肵�܂��B
������ɂ�鍷�����Ȃ�o�邱�Ƃ����������܂��B
���ƁALPF�͓�i�������܂������ABPF����8MHz�ʂ̂��܂���������ƘR��Ă܂��B
���U���̂����炷���Ƃ͉\�Ȃ̂��s���ł����A
�X�ɏI�i�Ƀt�B���^�ŗ}�����邩�Ǝv���܂��B
���̓��͂͂Ȃ��ŁA���̏�Ԃł��B
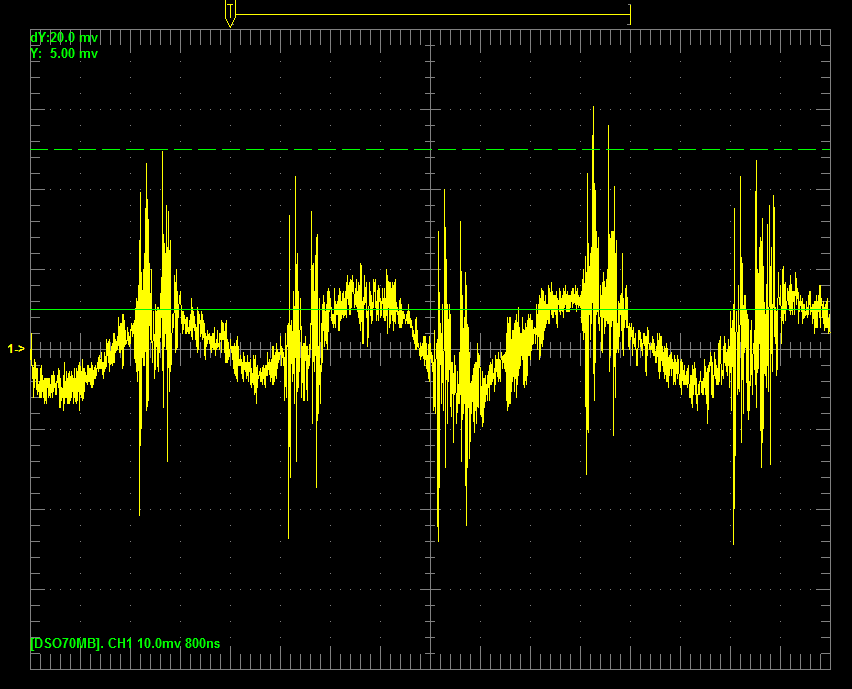 �c���́A10��V/Div�ł��̂ŁA�����͂Ȃ������ł��B
�����̃m�C�Y������������Ɨ��Ƃ���Ηǂ��ł��ˁB
���ƁA�����R�̕\�ʂ́A�����g��ʂ��悤�Ȃ̂ŁA�܂�d�Ȃ��Ă镔�i���m�ȂǕςɐG��Ȃ��悤�ɂ��������ǂ��H
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�I�[�o�[�h���C�u�Ȃ̂ł����A
������LED�ł��A���g���������A�f���[�e�B�[�䂪�Ⴏ��A
1A���x�͗����邱�Ƃ͐̂���DATA�\�ȂǂŒm���Ă܂������A
�ԊO��������W���[���p�̃����V���b�g�ł��A���̂��炢�͉\�̂悤�ł��ˁB
�Ȃ̂ŁA
�˂��l�߂�A���B�́A400m�ǂ���ł͖��������ł��B
�ł��A�܂��A�f���Ƀ��[�U�[�g���C�C�Ƃ����������c�B
1/2�f���[�e�B�[��̔��U�����APPM�Ƃ��čX��1/2�f���[�e�B�[�ő����邽�߁A
�I�[�o�[�h���C�u�́A��������6�`10�{���炢�ƌ��ς����Ă��܂������A
���̐��l���ƁA50�{�ʉ\�Ƃ��������ł��傤���c�H
�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{
��������j�o�[�T����ŁA�x�^GND�Ƃ͍s���Ȃ����A�M��Ȃ��甭�W������̂ŁA�N�V�^�ɋ߂��Ȃ�̂ł����A
�����e�[�v�Ƃ��A���܂���������o��������ȁA�Ƃ��v�����肵�Ă܂��B
���ʊ�ŕБ�GND�ʂȂ�Ă̂��ǂ��̂����ł��ˁB
�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{
��M��H��DABP������BPF�͐ݒ�o����Q�l��100�ȏ�ł�OK�Ƃ������̂ł����c�A
���܂蓾�����A����ɉ��i���Ȃ��ō��ꍇ�������悤�ȋC�����܂����B
DABP��H��Q��15�ɐݒ肵�Ă���܂����B
OP-AMP��I�ׂΗǂ��̂����m��Ȃ��ł����A�s����ȃC���[�W������܂����B
�̂̎�����W���[���̃O���t����Q=10�`13�ł����̂ŁA
�ŐV�̃��W���[������Q��15�`20�ʕK�v�Ɗ��������܂����A
Q�̍��������ݒ肾�ƁA���i�̌̍��Ŏ��g���̍����o���Ă��܂��Ƃ����ꍇ������悤�ł��B
�{�Ȃǂ�����ɓ������s������ɂ́AQ=10��1�i�Ȃ̂�2�`3�i��Q=10�ŁH�g���Ă�悤�Ȃ̂����܂����B
�E�B�[���u���b�W��BPF�ł���i�ł�Q=5���x�ł����B
n���̑��i�ɂ���ƁA���ꂪ�����قǁu��������g�������v�ɂȂ�A���߂ƎՒf���n�b�L���ƕ�����邱�ƂɂȂ�Ǝv���܂��B
Q�������Ȃ������ƂɁB�������A1�i�ŋ��������̂Ɠ����̂��Ƃ��B
�Ȃ̂ŁA
�܂��A���l������ɂ��炷���@������A��������ƁA���̕������u�p�������v�����ɁB
Q�͓����ł��A�Ւf�͉s���A���߂���Ƃ���͕������B�𗼗��B���U�����ƂȂ��������B
���̕��������₷�����������X����̂ŁA2�`3�i�d�˂Ă݂�ƃC�C�����Ƃ͎v���܂����B
�o�^�[���[�X�A�x�b�Z���A�`�F�r�V�F�t�ȂǂƂ����̂��c�A
�ŁAQ=10�̈�i��HPF���i�ł��̂��Ó����ȁH
���ƁA�{�ɏ����Ă������̂ł����ADABP������H�炵���A�i�X�U�����オ���āA�M�����ƒi�X�������Ă���A�u�x�������v�����邻���ł��B
�Ƃ����̂��AC�ɂ�����d���]����ƁAL�Ɠ����ɂȂ�킯�ŁA���U��H�Ɠ����ɂȂ�܂��B
�������A���U��H�͉����ɒx�ꂪ����܂��ˁB�Ƃ������Ƃ��ƁB
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���iBPF�̌X�̋��U���g�������炵�āA����Q�l�ł��A���߂͕��R�A�Ւf�͉s���A���U���Â炭�Ǝv�����̂ł����A
���i�W�߂ɖ�肪�o��̂ŁAQ=10�̈�i�{HPF���i�łǂ��ɂ��c�A
�ԊO�������R��������W���[���ɂ́A
�V�[���h���ꂽ�n�C�Q�C����AMP�ɁA�s��BPF
���ɂ́AAGC��H����������Ă�B
������f�B�X�N���[�g�ōČ��́A�R�X�g�����Ȃ�̃��m�ɂȂ�c�A
���̃X�N���v�g�Ōv�Z���\�ł��B
http://www.g-munu.t.u-tokyo.ac.jp/local_manual/bpf/bpf.html
�܂��A�����̕��i�̐��l�ƖړI���g���œ���
�c���́A10��V/Div�ł��̂ŁA�����͂Ȃ������ł��B
�����̃m�C�Y������������Ɨ��Ƃ���Ηǂ��ł��ˁB
���ƁA�����R�̕\�ʂ́A�����g��ʂ��悤�Ȃ̂ŁA�܂�d�Ȃ��Ă镔�i���m�ȂǕςɐG��Ȃ��悤�ɂ��������ǂ��H
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�I�[�o�[�h���C�u�Ȃ̂ł����A
������LED�ł��A���g���������A�f���[�e�B�[�䂪�Ⴏ��A
1A���x�͗����邱�Ƃ͐̂���DATA�\�ȂǂŒm���Ă܂������A
�ԊO��������W���[���p�̃����V���b�g�ł��A���̂��炢�͉\�̂悤�ł��ˁB
�Ȃ̂ŁA
�˂��l�߂�A���B�́A400m�ǂ���ł͖��������ł��B
�ł��A�܂��A�f���Ƀ��[�U�[�g���C�C�Ƃ����������c�B
1/2�f���[�e�B�[��̔��U�����APPM�Ƃ��čX��1/2�f���[�e�B�[�ő����邽�߁A
�I�[�o�[�h���C�u�́A��������6�`10�{���炢�ƌ��ς����Ă��܂������A
���̐��l���ƁA50�{�ʉ\�Ƃ��������ł��傤���c�H
�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{
��������j�o�[�T����ŁA�x�^GND�Ƃ͍s���Ȃ����A�M��Ȃ��甭�W������̂ŁA�N�V�^�ɋ߂��Ȃ�̂ł����A
�����e�[�v�Ƃ��A���܂���������o��������ȁA�Ƃ��v�����肵�Ă܂��B
���ʊ�ŕБ�GND�ʂȂ�Ă̂��ǂ��̂����ł��ˁB
�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{
��M��H��DABP������BPF�͐ݒ�o����Q�l��100�ȏ�ł�OK�Ƃ������̂ł����c�A
���܂蓾�����A����ɉ��i���Ȃ��ō��ꍇ�������悤�ȋC�����܂����B
DABP��H��Q��15�ɐݒ肵�Ă���܂����B
OP-AMP��I�ׂΗǂ��̂����m��Ȃ��ł����A�s����ȃC���[�W������܂����B
�̂̎�����W���[���̃O���t����Q=10�`13�ł����̂ŁA
�ŐV�̃��W���[������Q��15�`20�ʕK�v�Ɗ��������܂����A
Q�̍��������ݒ肾�ƁA���i�̌̍��Ŏ��g���̍����o���Ă��܂��Ƃ����ꍇ������悤�ł��B
�{�Ȃǂ�����ɓ������s������ɂ́AQ=10��1�i�Ȃ̂�2�`3�i��Q=10�ŁH�g���Ă�悤�Ȃ̂����܂����B
�E�B�[���u���b�W��BPF�ł���i�ł�Q=5���x�ł����B
n���̑��i�ɂ���ƁA���ꂪ�����قǁu��������g�������v�ɂȂ�A���߂ƎՒf���n�b�L���ƕ�����邱�ƂɂȂ�Ǝv���܂��B
Q�������Ȃ������ƂɁB�������A1�i�ŋ��������̂Ɠ����̂��Ƃ��B
�Ȃ̂ŁA
�܂��A���l������ɂ��炷���@������A��������ƁA���̕������u�p�������v�����ɁB
Q�͓����ł��A�Ւf�͉s���A���߂���Ƃ���͕������B�𗼗��B���U�����ƂȂ��������B
���̕��������₷�����������X����̂ŁA2�`3�i�d�˂Ă݂�ƃC�C�����Ƃ͎v���܂����B
�o�^�[���[�X�A�x�b�Z���A�`�F�r�V�F�t�ȂǂƂ����̂��c�A
�ŁAQ=10�̈�i��HPF���i�ł��̂��Ó����ȁH
���ƁA�{�ɏ����Ă������̂ł����ADABP������H�炵���A�i�X�U�����オ���āA�M�����ƒi�X�������Ă���A�u�x�������v�����邻���ł��B
�Ƃ����̂��AC�ɂ�����d���]����ƁAL�Ɠ����ɂȂ�킯�ŁA���U��H�Ɠ����ɂȂ�܂��B
�������A���U��H�͉����ɒx�ꂪ����܂��ˁB�Ƃ������Ƃ��ƁB
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���iBPF�̌X�̋��U���g�������炵�āA����Q�l�ł��A���߂͕��R�A�Ւf�͉s���A���U���Â炭�Ǝv�����̂ł����A
���i�W�߂ɖ�肪�o��̂ŁAQ=10�̈�i�{HPF���i�łǂ��ɂ��c�A
�ԊO�������R��������W���[���ɂ́A
�V�[���h���ꂽ�n�C�Q�C����AMP�ɁA�s��BPF
���ɂ́AAGC��H����������Ă�B
������f�B�X�N���[�g�ōČ��́A�R�X�g�����Ȃ�̃��m�ɂȂ�c�A
���̃X�N���v�g�Ōv�Z���\�ł��B
http://www.g-munu.t.u-tokyo.ac.jp/local_manual/bpf/bpf.html
�܂��A�����̕��i�̐��l�ƖړI���g���œ���
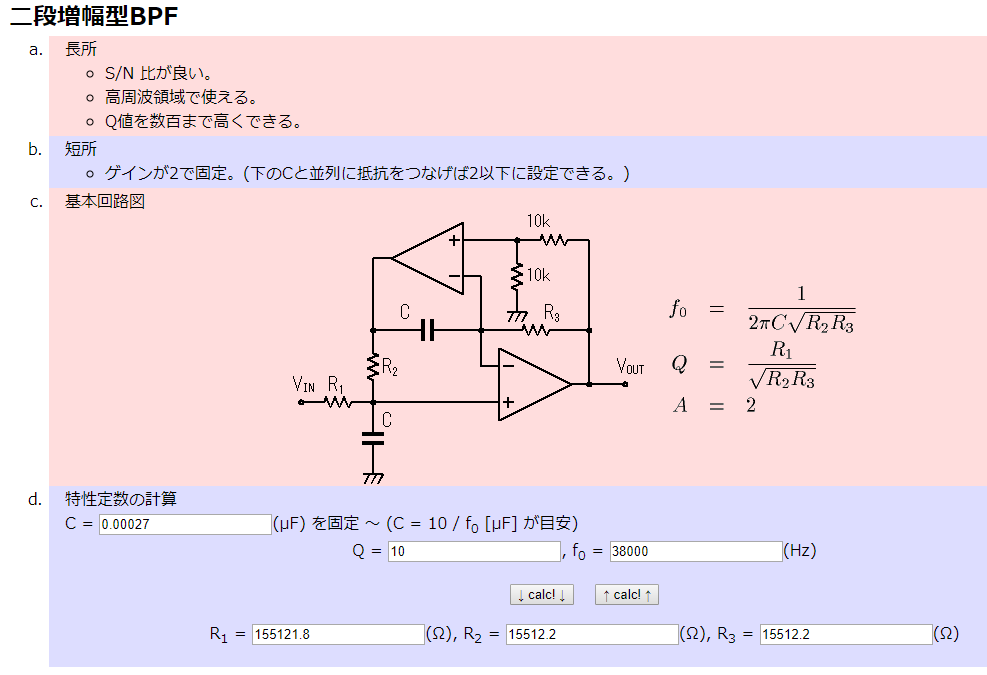 �����āA������R����͂��ċt�Z�B
�����āA������R����͂��ċt�Z�B
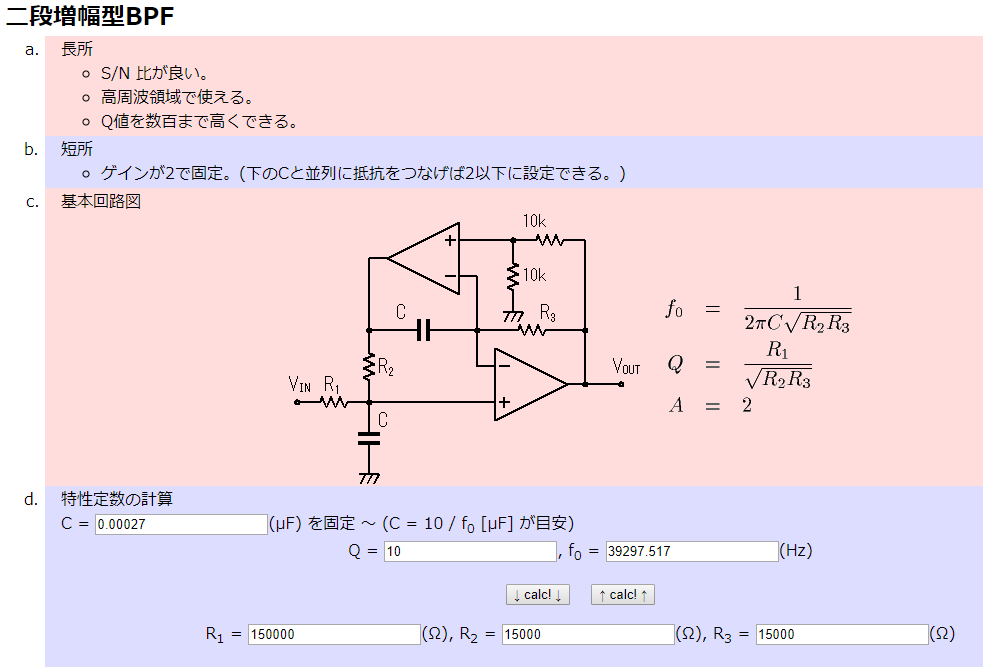 ���g������������邯�ǁA�����炪�ǍD�ȂƂ���BQ=10�Ȃ�s���銴���H
16k���Ƃ����Ǝ��g������߂ɏo�܂��B
���l��
���g������������邯�ǁA�����炪�ǍD�ȂƂ���BQ=10�Ȃ�s���銴���H
16k���Ƃ����Ǝ��g������߂ɏo�܂��B
���l��
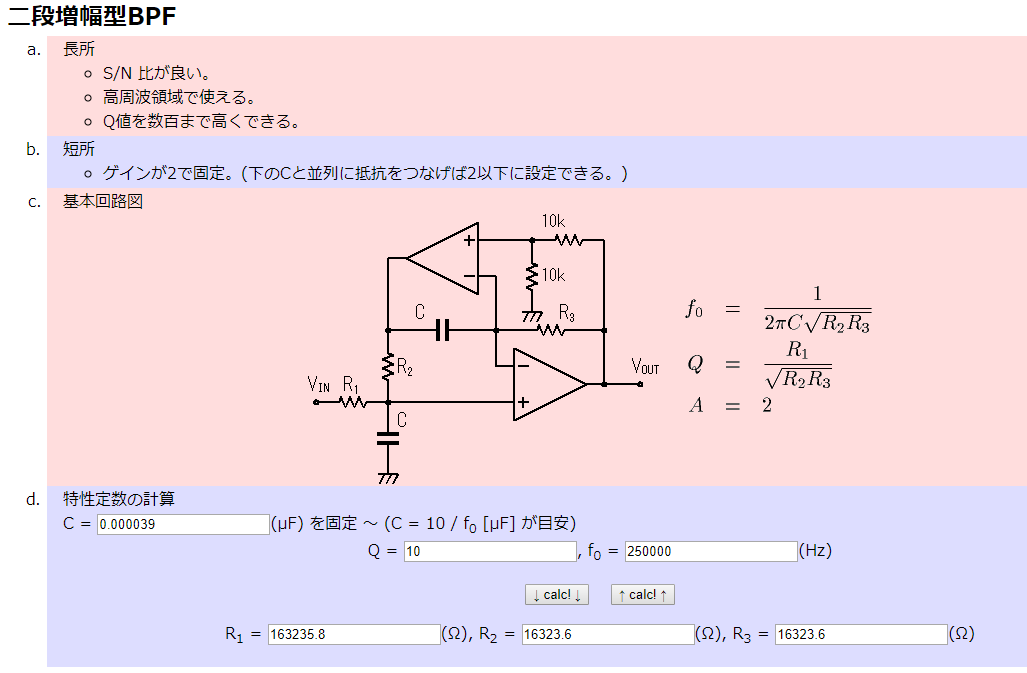
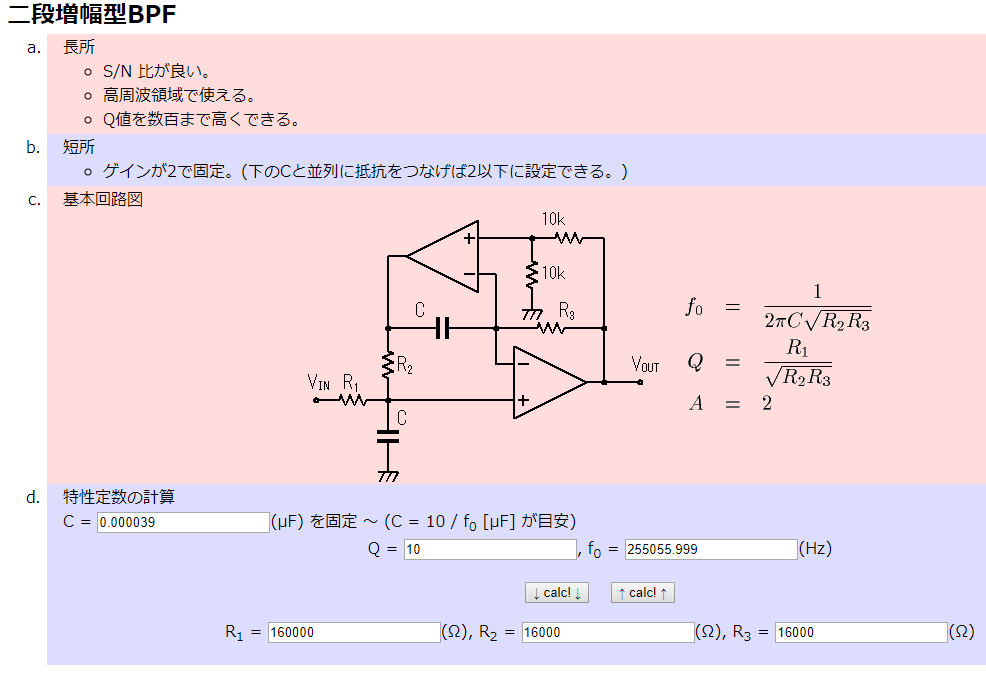 �Ƃ��������ŊȒP�ɋ��߂��܂����B
�o������̕��i�͋����������Ǝv���܂��B
���̌��ʂ��A���܂��܁A15K��16K�̊ԂɃs�[�N���~�����̂ŁA���̓��ɂ��邱�Ƃ��v�����܂����B
�Ƃ��������ŊȒP�ɋ��߂��܂����B
�o������̕��i�͋����������Ǝv���܂��B
���̌��ʂ��A���܂��܁A15K��16K�̊ԂɃs�[�N���~�����̂ŁA���̓��ɂ��邱�Ƃ��v�����܂����B
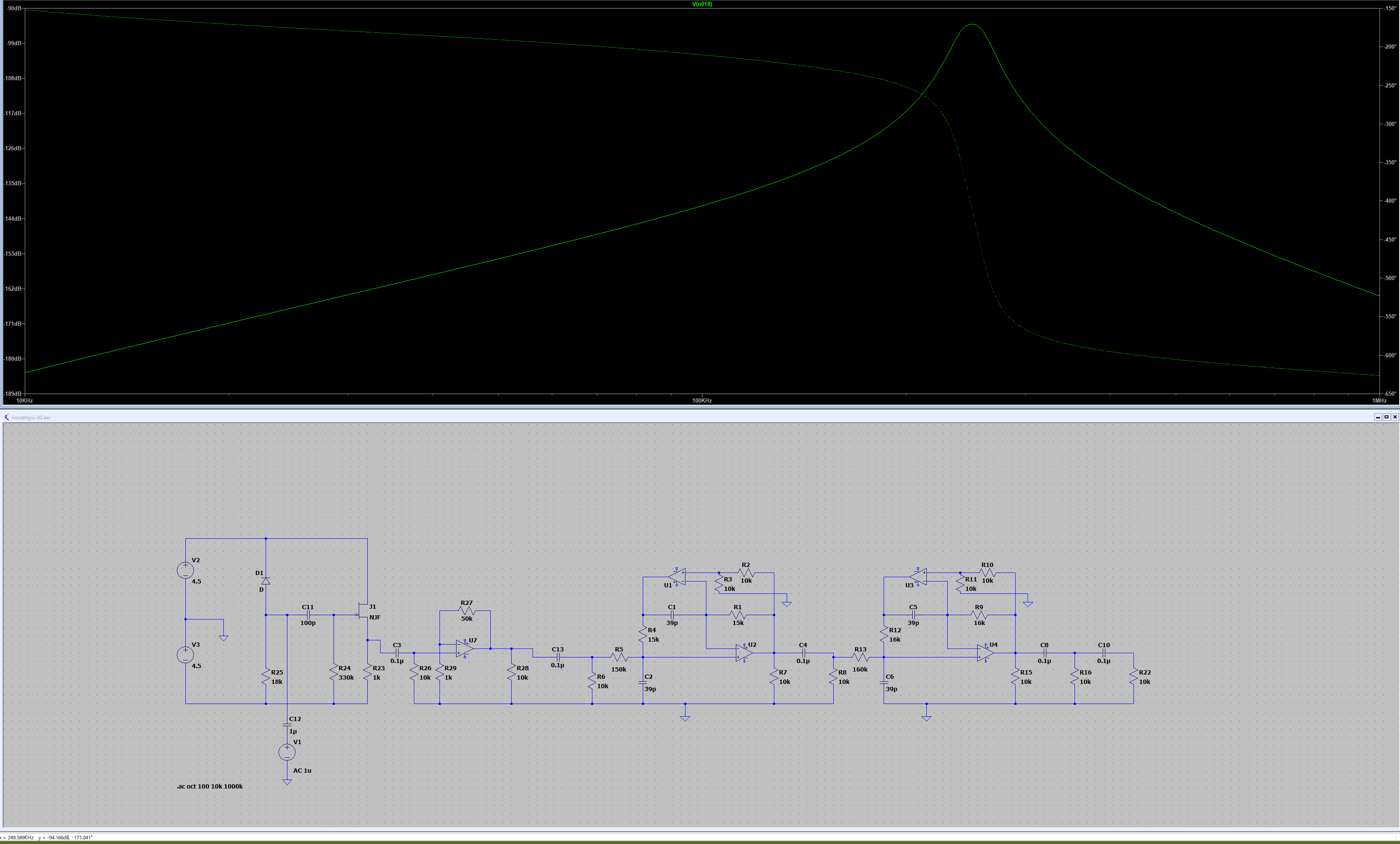 Q�ݒ��10�̏ꍇ���g���Ă�̂ŁA�ǁX�ݒ�o����B
�K����HPF��BPF��Q��ݒ肵�܂����B
Q�ݒ��10�̏ꍇ���g���Ă�̂ŁA�ǁX�ݒ�o����B
�K����HPF��BPF��Q��ݒ肵�܂����B
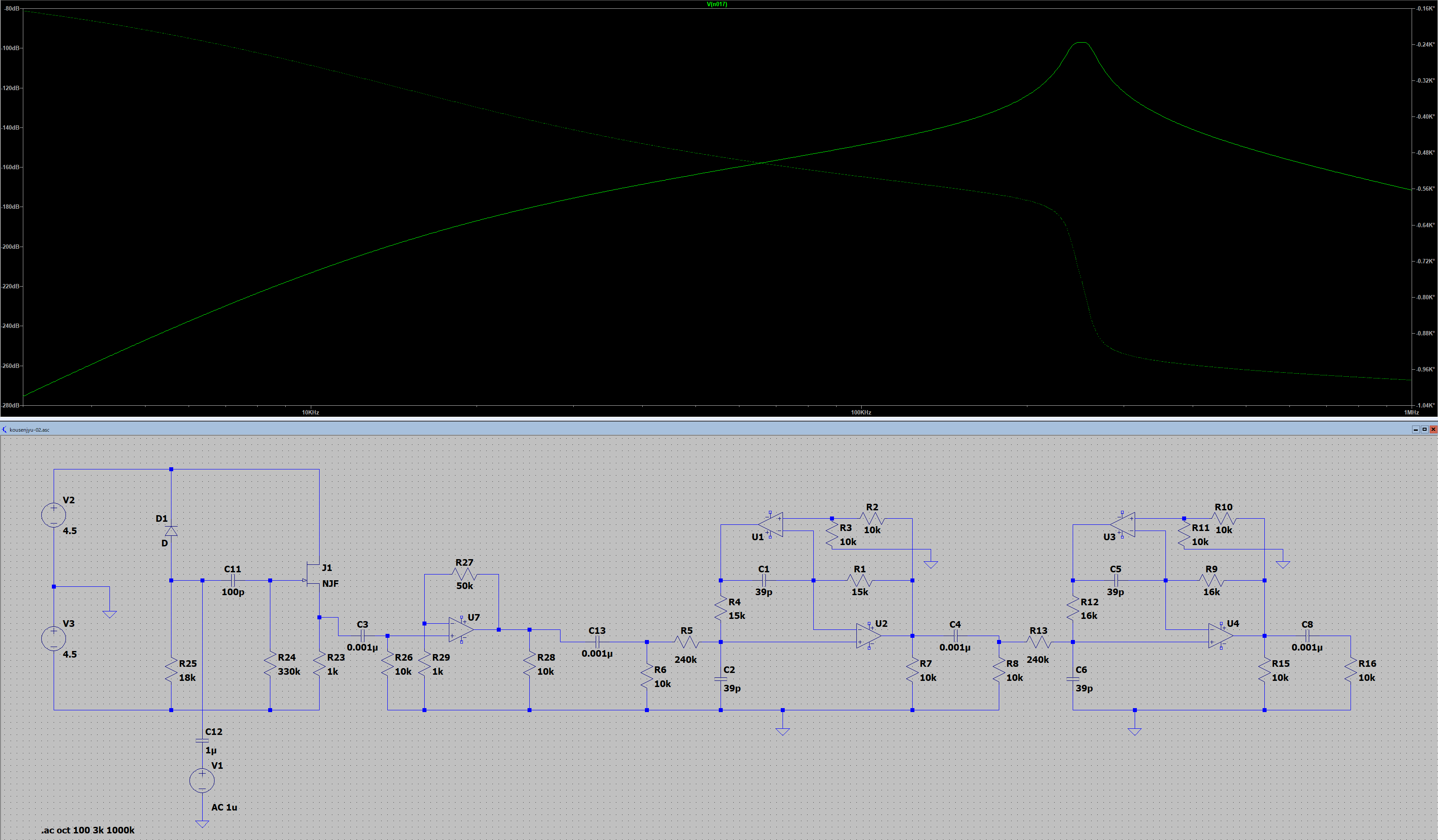 �̂̉�HQ=15���畔�i�����p���Ă�̂ŁA
���U�̂��₷����Q=15�ɋ߂������Ǝv���܂��B�������Y�݂ǂ���B
����������Ɗɂ��������ł��ˁB
HPF��Fc=15KHz���x�B
�l���͊ȑf������Ƃ��̐}�̊����B
�̂̉�HQ=15���畔�i�����p���Ă�̂ŁA
���U�̂��₷����Q=15�ɋ߂������Ǝv���܂��B�������Y�݂ǂ���B
����������Ɗɂ��������ł��ˁB
HPF��Fc=15KHz���x�B
�l���͊ȑf������Ƃ��̐}�̊����B
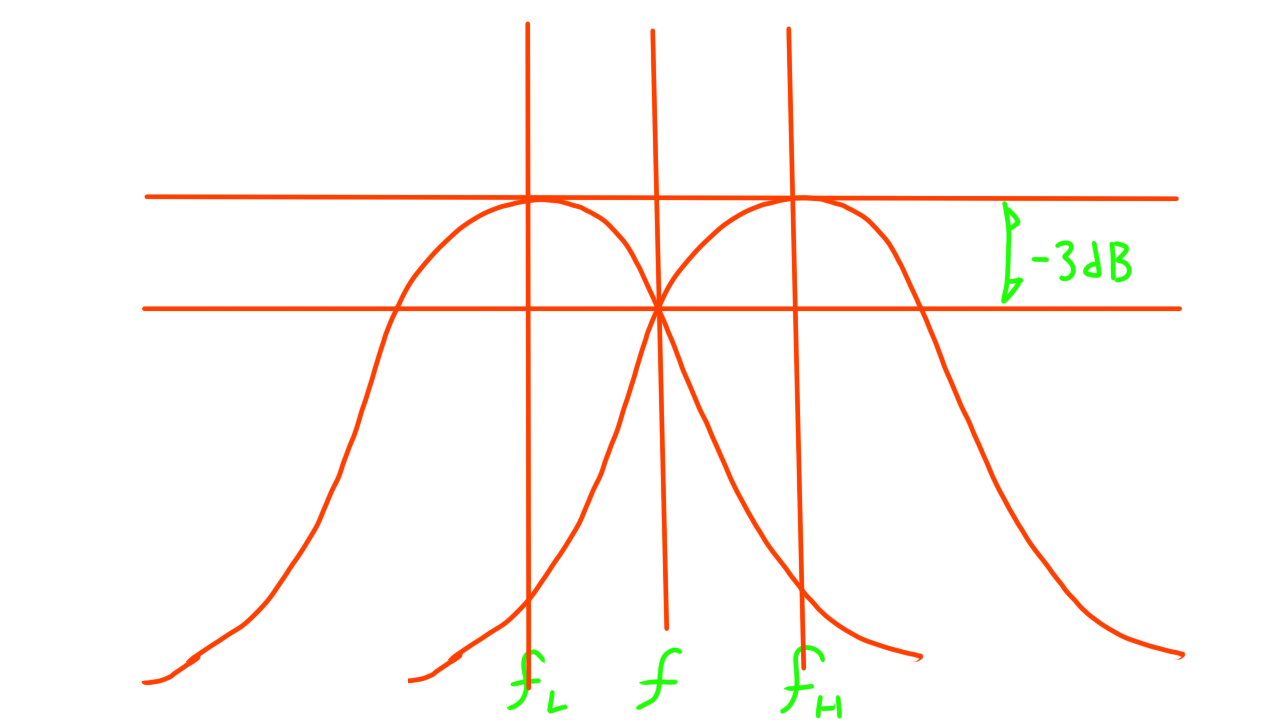 �O���C�R�Ƃ��͔����̃C���_�N�^�̏d�ˍ��킹�ł����Ȃ��Ă�B
�Ⴂ�͂����Z�Ƒ����Z�̈Ⴂ�����邪�c�A�N���X�I�[�o�[�̊����͎��Ă�Ǝv����B
�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{
���[�U�[Di�̔��U�ł����ATr�œd���𐧌�����͖̂����ɂ��āA
��R�ł�ACC��H�I�ɂ��Ă���Ȋ����ł��B
�O���C�R�Ƃ��͔����̃C���_�N�^�̏d�ˍ��킹�ł����Ȃ��Ă�B
�Ⴂ�͂����Z�Ƒ����Z�̈Ⴂ�����邪�c�A�N���X�I�[�o�[�̊����͎��Ă�Ǝv����B
�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{
���[�U�[Di�̔��U�ł����ATr�œd���𐧌�����͖̂����ɂ��āA
��R�ł�ACC��H�I�ɂ��Ă���Ȋ����ł��B
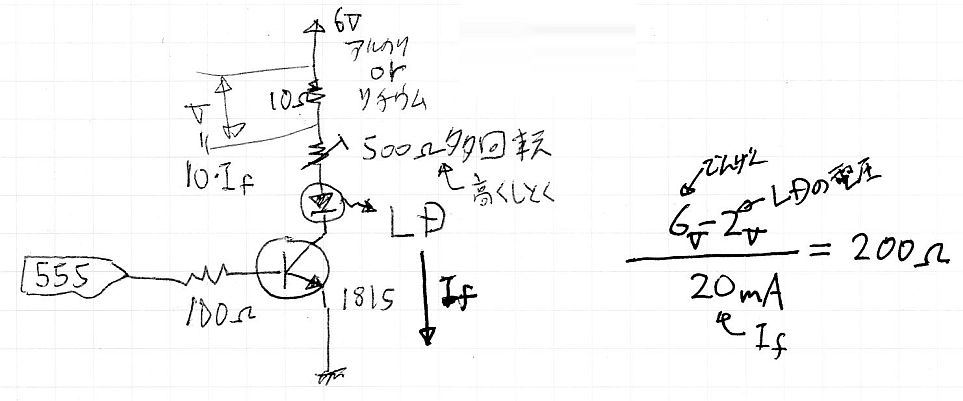 ����]���Œ�g���}�[�����ڂɐݒ肵�āALD�̉��x���C�����Ȃ���A10���ɂ�����d�������傤�Ǘǂ��ݒ肵�܂��B
�Ód�C��m�C�Y����6.5V���x�̃c�G�i�[�ŕی삵�Ă��ƃC�C�����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
500mW�ȏ��LD���ƁA���x�]�T�������ACC��H�쓮����{�ł����A
�N���X3���[�U�[�ȉ����ƁAACC��H�ł�40�x�ʍ����o��Ɩ��ɂȂ�܂��B
���闝�R�́A�o�͂�O�I���ɂ�鉷�x�㏸�ŏo�͂��㏸���A���G�l���M�[�ɂ���āA�~���[�ʂ��������邩�ň�u�ʼn��܂��B
�Ȃ̂ŁA�����ɂ͌��o�͂̎Q�Əo�͂��琧�䂷��APC��H�ɂȂ�܂��B
�ł����A���ۂ̃J�^���O�X�y�b�N���]�T�����邽�߁A
�́A�������̃��[�U�[�|�C���^�[�ɂ́A���������A���߂̓d���{��R��{�Œ�d���I�Ɉ����Ă܂����B
�����e�̏ꍇ�A��u�����������Ȃ��̂ŁA���M���̓N���A���Ă܂����A
�O�I���͂������ǂ������Ȃ��ł���ˁB
�d���͍Œ���A���J���A���z�͈�Ԉ��肵�Ă�A�R�C�����`�E���d�r�Ƃ��ɁB
�܂��A�c�G�i�[�Ńm�C�Y��Ód�C�Ȃǂ̕ی�����Ă����ƃC�C�ł��ˁB
�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{
�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{
�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{
����]���Œ�g���}�[�����ڂɐݒ肵�āALD�̉��x���C�����Ȃ���A10���ɂ�����d�������傤�Ǘǂ��ݒ肵�܂��B
�Ód�C��m�C�Y����6.5V���x�̃c�G�i�[�ŕی삵�Ă��ƃC�C�����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
500mW�ȏ��LD���ƁA���x�]�T�������ACC��H�쓮����{�ł����A
�N���X3���[�U�[�ȉ����ƁAACC��H�ł�40�x�ʍ����o��Ɩ��ɂȂ�܂��B
���闝�R�́A�o�͂�O�I���ɂ�鉷�x�㏸�ŏo�͂��㏸���A���G�l���M�[�ɂ���āA�~���[�ʂ��������邩�ň�u�ʼn��܂��B
�Ȃ̂ŁA�����ɂ͌��o�͂̎Q�Əo�͂��琧�䂷��APC��H�ɂȂ�܂��B
�ł����A���ۂ̃J�^���O�X�y�b�N���]�T�����邽�߁A
�́A�������̃��[�U�[�|�C���^�[�ɂ́A���������A���߂̓d���{��R��{�Œ�d���I�Ɉ����Ă܂����B
�����e�̏ꍇ�A��u�����������Ȃ��̂ŁA���M���̓N���A���Ă܂����A
�O�I���͂������ǂ������Ȃ��ł���ˁB
�d���͍Œ���A���J���A���z�͈�Ԉ��肵�Ă�A�R�C�����`�E���d�r�Ƃ��ɁB
�܂��A�c�G�i�[�Ńm�C�Y��Ód�C�Ȃǂ̕ی�����Ă����ƃC�C�ł��ˁB
�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{
�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{
�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{
LC���U�ɂōl���Ă݂�B �ŋ߁A�r�[�����C�t���Ȃ�ċ��Z�p�����邩��A�ǂ������j�b�`�Ȏ��v�ō�邩���l����K�v�����邩���H 220210 �� 400KHz��M�Ƃ��āAPD��2SK30(Z�ϊ�)��RF-AMP��IC��NJM5532DD 2SK30�FNch�^FET�F�����ƃ��[�m�C�Y�ō����̂��C�C�����B RF-AMP��IC�FDC����ŁANF���Ⴂ��B�FBGA420�ȂǁBSOT-23�ϊ���ɖ�����ڂ������B NJM5532�F�m�C�Y�A�I�t�Z�b�g�ȂǒႢ�B�⒮��ŏ�肭�s�����B 100KHz�ȉ����������J�b�g�B2MHz�ȏ���������J�b�g�B 220215 �X�ɋl�߂čl���Ă݂�B
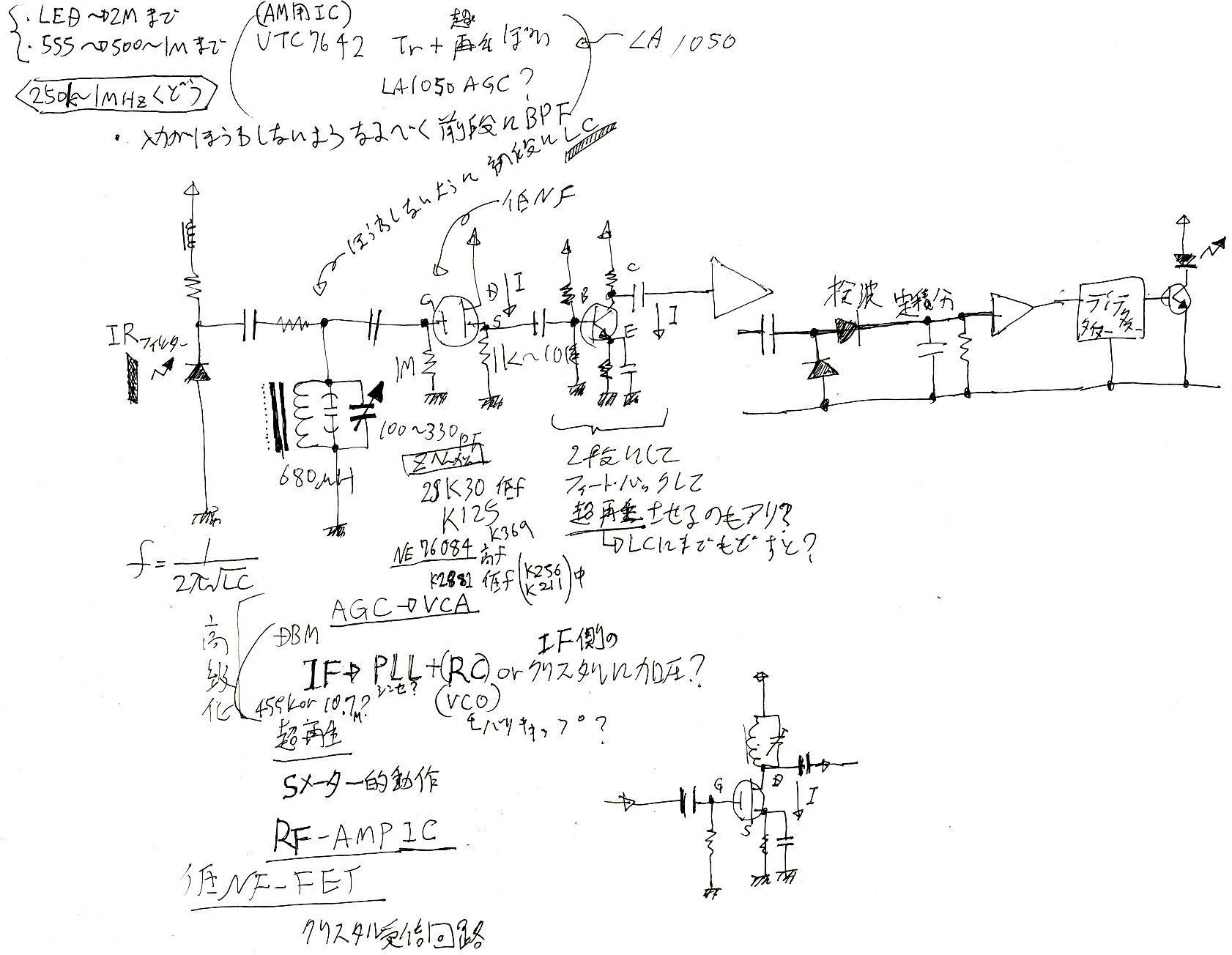 ���܂łƈႢ�A�v�����āA������M�@�̋Z�p�̕��ōl���Ă݂�B�ڍׂ͂悭����Ȃ��g�R�����ǁB
AM���W�I�Ȋ����ɁALC���U��H���g�����Ƃ��l���Ă݂��B
(AGC��~�L�T�[��H������ƁA���Ȃ�ǂ��Ȃ肻�������A�Ƃ肠�������������c�A
�ł��AIF�p455KHz��BPF�͎g���邩���H)
�S�c���ᖳ�����āA�t�F���C�g�R�A�͓_�������ǁA�{�[���y���ł͏����ɂ����B
�o���R���̕��́A��ʂ̍����x�ȃR���f���T�[�ƕ���ɂ��āA�����߂��₷������̂��C�C�����B
���̑����̌����͏��Ȃ�����������AQ�̍������m�͕K�v�Ȃ������ɂ��v�����ǁA
���d�ǂł̃C���o�[�^�[�̌��ɂ́A�����g�Ƃ��܂�ł���������c�A�A
�ŁA
����t�B���^���܂݁A(�ԊO�́H)LED��LD�Ŕ���������B
���̉�H�̏�Ԃł́AFET�̃Q�[�g-GND�Ԃ̒�R�͗v��Ȃ��Ǝv�����A���̎�O�̃Q�[�g�Ɍq����f�J�b�v�����O�R���f���T�[���v��Ȃ��n�Y�ŃA���B
���U��H�ƃA���e�i�ɓ�����PD�̊ԂɃf�J�b�v�����O�R���f���T�[�����邪�A������x�̒�R������ƃC�C�����B
�����̋��U�̃��C�A�E�g�́A����������ƒ��ׂČ��銴�������B
���̕��ɗL�鋤�U��H���܂�Tr�����n�p������A���A�҂ɂĒ��Đ��݂����Ȃ̂��o���邩���m��Ȃ��B
������x����������AOP-AMP�Ƃ����g���Č���Ɨǂ���������Ȃ��B
�����@�ł́A�L�ш�̂܂܃Q�C������������ƁA�傫�ȐM���ŖO�a���Ă���A���̍����g�ɂ��W�Q�A���ϒ����N��������ŁA�܂Ƃ��ɓ����Ȃ�������A�A
�Ȃ�ׂ��A���i�Ńt�B���^�[�������Ă��������B
���U���́A555���ƁACMOS�ŁA500KHz�܂œ�������N�^�C�v���A�����AICM7555IPAZ�́A1MHz�܂Ŕ��U�o����B
�d�����_�C���N�g�h���C�u���o�������ł���B�����łȂ����Ă��V���~�b�g�g���K�C���o�[�^�[�Ƃ��ł��C�P�邩�������B���ɂ����U�Ȃ�F�X�����āA�n�[�h���͒�߁B
�������A���K�͂�LD�̃p���[���䂵���܂܍����g�̃o�[�X�g�͓���g�R�����邩���B
�E���������m�B
RF-AMP��IC�A����ρA�������Ⴗ�����ȁH
NE76084�́AVHF�ё����p��5���炢�����Ă��̂����ǁA�s���z�u�������������B�g���Ȃ��B
AM���W�I�pIC�Ƃ����e�����邪�A�����܂Ń����`�b�v�W�ω�H�̋Z�p�ɗ����Ă��܂��̂��c�B
���ƁALC���̃t�B���^�[���ƁAC�̓��[�g�L���̒��Ȃ̂ŁA�傫���������Ă��A�ω����R�����̂ŁA�L�͈͂ɑΉ��������v�͏o���Ȃ��B
�}�C�N���C���_�N�^�ɂ́A�e�ʂ��炩�A���ȋ��U���g���Ƃ������̂�����̂ŁA�\���������m���g�p�������B
455KHz��IFT�R�C���Ƃ������m���A���B�R�C���̃R�A���̂ŁA���̂̃}�C�i�X�h���C�o�[���~�����g�R�B�I�[���C�������o�����������Ȃ̂łȂ��c�A
�w�������ň����Ă��ALC��H�́AL��C������ł��������A
�Q���}�j�E�����W�I�Ƃ��A�����@������ƕ���Ȃ̂��C�ɂȂ�B
�܂��A�U���G�l���M�[�����ߍ��ނɂ͗ǂ��̂����H�H
�����I�ɐU������荞�݁A�ǂ��U�������A��肭���o���B
�Ƃ����K�v��������̂ŁALC�̃��C�A�E�g�͋C���g�������ł���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220218
�����e�̎������LC���U�ōl���Ă݂�
�܂��A�E�`�ɌÂ��H���̃Q���}�j�E�����W�I�L�b�g������(���������Ă邯�ǁADi������Ă܂�)�A����ŃC���C�����ׂČ������ł��B
�o�[�A���e�i�I�ȃR�C��(����750��H���x@100KHz)���t���Ă���܂������A��c�R�C���ō��̂����ł����A�g���ɂ͋M�d�Ɏv���A
�ėp�̃A�L�V�������[�h�^�C�v��1mH���g���邩�H�Ǝv���A�\�����ł��B
���܂łƈႢ�A�v�����āA������M�@�̋Z�p�̕��ōl���Ă݂�B�ڍׂ͂悭����Ȃ��g�R�����ǁB
AM���W�I�Ȋ����ɁALC���U��H���g�����Ƃ��l���Ă݂��B
(AGC��~�L�T�[��H������ƁA���Ȃ�ǂ��Ȃ肻�������A�Ƃ肠�������������c�A
�ł��AIF�p455KHz��BPF�͎g���邩���H)
�S�c���ᖳ�����āA�t�F���C�g�R�A�͓_�������ǁA�{�[���y���ł͏����ɂ����B
�o���R���̕��́A��ʂ̍����x�ȃR���f���T�[�ƕ���ɂ��āA�����߂��₷������̂��C�C�����B
���̑����̌����͏��Ȃ�����������AQ�̍������m�͕K�v�Ȃ������ɂ��v�����ǁA
���d�ǂł̃C���o�[�^�[�̌��ɂ́A�����g�Ƃ��܂�ł���������c�A�A
�ŁA
����t�B���^���܂݁A(�ԊO�́H)LED��LD�Ŕ���������B
���̉�H�̏�Ԃł́AFET�̃Q�[�g-GND�Ԃ̒�R�͗v��Ȃ��Ǝv�����A���̎�O�̃Q�[�g�Ɍq����f�J�b�v�����O�R���f���T�[���v��Ȃ��n�Y�ŃA���B
���U��H�ƃA���e�i�ɓ�����PD�̊ԂɃf�J�b�v�����O�R���f���T�[�����邪�A������x�̒�R������ƃC�C�����B
�����̋��U�̃��C�A�E�g�́A����������ƒ��ׂČ��銴�������B
���̕��ɗL�鋤�U��H���܂�Tr�����n�p������A���A�҂ɂĒ��Đ��݂����Ȃ̂��o���邩���m��Ȃ��B
������x����������AOP-AMP�Ƃ����g���Č���Ɨǂ���������Ȃ��B
�����@�ł́A�L�ш�̂܂܃Q�C������������ƁA�傫�ȐM���ŖO�a���Ă���A���̍����g�ɂ��W�Q�A���ϒ����N��������ŁA�܂Ƃ��ɓ����Ȃ�������A�A
�Ȃ�ׂ��A���i�Ńt�B���^�[�������Ă��������B
���U���́A555���ƁACMOS�ŁA500KHz�܂œ�������N�^�C�v���A�����AICM7555IPAZ�́A1MHz�܂Ŕ��U�o����B
�d�����_�C���N�g�h���C�u���o�������ł���B�����łȂ����Ă��V���~�b�g�g���K�C���o�[�^�[�Ƃ��ł��C�P�邩�������B���ɂ����U�Ȃ�F�X�����āA�n�[�h���͒�߁B
�������A���K�͂�LD�̃p���[���䂵���܂܍����g�̃o�[�X�g�͓���g�R�����邩���B
�E���������m�B
RF-AMP��IC�A����ρA�������Ⴗ�����ȁH
NE76084�́AVHF�ё����p��5���炢�����Ă��̂����ǁA�s���z�u�������������B�g���Ȃ��B
AM���W�I�pIC�Ƃ����e�����邪�A�����܂Ń����`�b�v�W�ω�H�̋Z�p�ɗ����Ă��܂��̂��c�B
���ƁALC���̃t�B���^�[���ƁAC�̓��[�g�L���̒��Ȃ̂ŁA�傫���������Ă��A�ω����R�����̂ŁA�L�͈͂ɑΉ��������v�͏o���Ȃ��B
�}�C�N���C���_�N�^�ɂ́A�e�ʂ��炩�A���ȋ��U���g���Ƃ������̂�����̂ŁA�\���������m���g�p�������B
455KHz��IFT�R�C���Ƃ������m���A���B�R�C���̃R�A���̂ŁA���̂̃}�C�i�X�h���C�o�[���~�����g�R�B�I�[���C�������o�����������Ȃ̂łȂ��c�A
�w�������ň����Ă��ALC��H�́AL��C������ł��������A
�Q���}�j�E�����W�I�Ƃ��A�����@������ƕ���Ȃ̂��C�ɂȂ�B
�܂��A�U���G�l���M�[�����ߍ��ނɂ͗ǂ��̂����H�H
�����I�ɐU������荞�݁A�ǂ��U�������A��肭���o���B
�Ƃ����K�v��������̂ŁALC�̃��C�A�E�g�͋C���g�������ł���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220218
�����e�̎������LC���U�ōl���Ă݂�
�܂��A�E�`�ɌÂ��H���̃Q���}�j�E�����W�I�L�b�g������(���������Ă邯�ǁADi������Ă܂�)�A����ŃC���C�����ׂČ������ł��B
�o�[�A���e�i�I�ȃR�C��(����750��H���x@100KHz)���t���Ă���܂������A��c�R�C���ō��̂����ł����A�g���ɂ͋M�d�Ɏv���A
�ėp�̃A�L�V�������[�h�^�C�v��1mH���g���邩�H�Ǝv���A�\�����ł��B
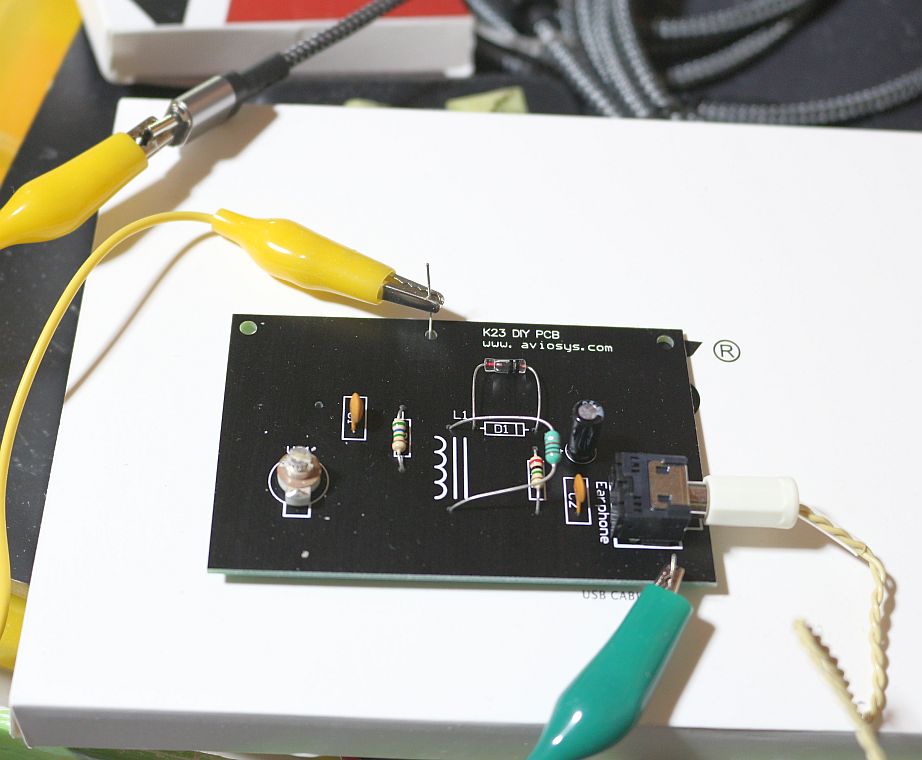 �Ƃ����悤�ȃe�X�g�Ȃ̂ŁA���ꂪ�t���Ă܂��B
�܂��A����������l�ł͖��������Ȃ̂ŁA���U������AQ�l���Ⴂ�����邩������܂���B
���t���̑��������͕̂t���O�����₷���悤�ɂƂ�Di�͔M����ł��B
�C���z���͎����炷���ɗ����Ă���̂ŃV���A�[�|���ɂ���ƁA��肭�s���̂ŁA�C�C�����ɂȂ�܂��B
�A���e�i�́A3m���x��USB�P�[�u���̊O�����̂ɐڑ��B
����ŁA���͏������Ȃ���A�������܂��B
���łɃA�[�X��������t���A�l�̂ɗ��Ƃ�����A�I�Ȃ��ς���Ă��܂��܂����B
���x���オ�邱�Ƃō��M���Ă邾�������m��Ȃ����c�A
�ǂ���ɂ���AQ��������Ηǂ��悤�Ȃ��Ƃ����H
��r�̂��߁A�o�[�A���e�i�Ɍ����B
�Ƃ����悤�ȃe�X�g�Ȃ̂ŁA���ꂪ�t���Ă܂��B
�܂��A����������l�ł͖��������Ȃ̂ŁA���U������AQ�l���Ⴂ�����邩������܂���B
���t���̑��������͕̂t���O�����₷���悤�ɂƂ�Di�͔M����ł��B
�C���z���͎����炷���ɗ����Ă���̂ŃV���A�[�|���ɂ���ƁA��肭�s���̂ŁA�C�C�����ɂȂ�܂��B
�A���e�i�́A3m���x��USB�P�[�u���̊O�����̂ɐڑ��B
����ŁA���͏������Ȃ���A�������܂��B
���łɃA�[�X��������t���A�l�̂ɗ��Ƃ�����A�I�Ȃ��ς���Ă��܂��܂����B
���x���オ�邱�Ƃō��M���Ă邾�������m��Ȃ����c�A
�ǂ���ɂ���AQ��������Ηǂ��悤�Ȃ��Ƃ����H
��r�̂��߁A�o�[�A���e�i�Ɍ����B
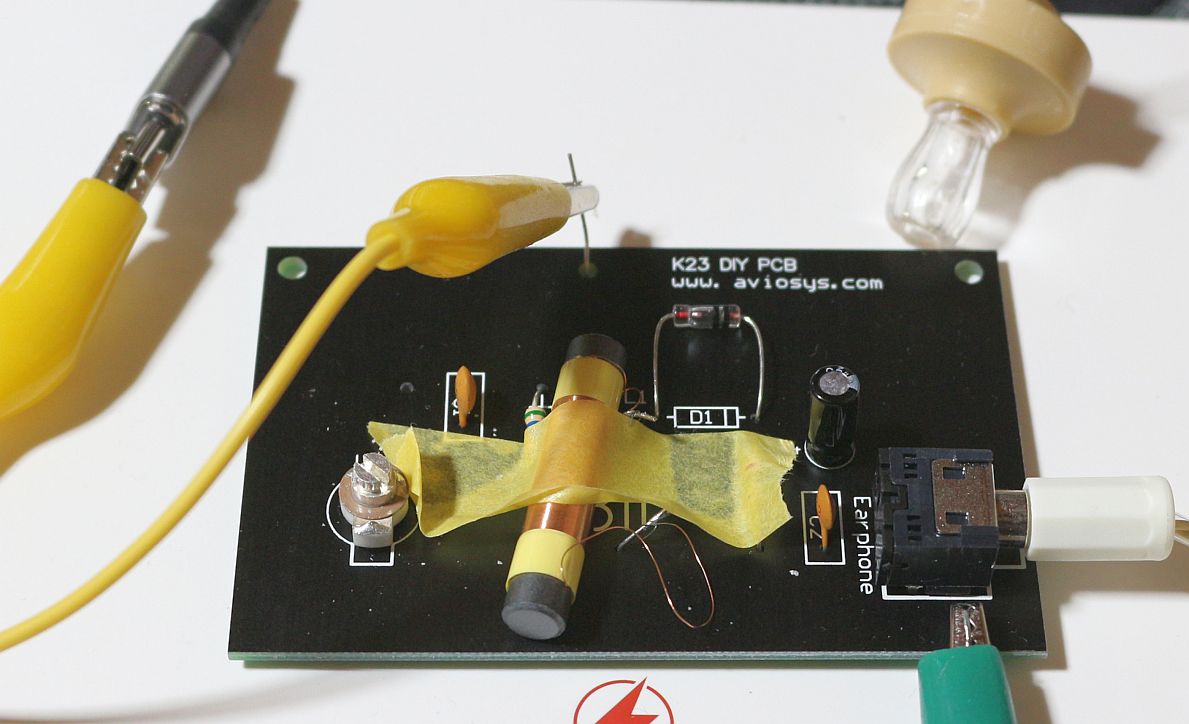 ��M���x�͕����������ς��܂���B
�A�[�X�ڑ��őI�Ȃ��ς��x�����͏��Ȃ��Ȃ��Ă�悤�ȋC������B
�Ƃ������A���M�̓x�����������Ă���B
�����A�I��x�������Ȃ��Ă���̂����B
�Â����m�ŁA�핢�̔�����א��Ȃ̂ŁA�t���b�N�X�g�����A
���āA�h�������܂Ŕ������A�����́A���C�^�[���t�邩���Ă��Ȃ��ƁA�����Ƃ������Ȃ������B�B
�N���X�^���C���z���́A��p���������̂ł����A���{���̂ɂ�����A���x���オ��A�g�[�����������������₷���Ȃ�܂����B
��M���x�͕����������ς��܂���B
�A�[�X�ڑ��őI�Ȃ��ς��x�����͏��Ȃ��Ȃ��Ă�悤�ȋC������B
�Ƃ������A���M�̓x�����������Ă���B
�����A�I��x�������Ȃ��Ă���̂����B
�Â����m�ŁA�핢�̔�����א��Ȃ̂ŁA�t���b�N�X�g�����A
���āA�h�������܂Ŕ������A�����́A���C�^�[���t�邩���Ă��Ȃ��ƁA�����Ƃ������Ȃ������B�B
�N���X�^���C���z���́A��p���������̂ł����A���{���̂ɂ�����A���x���オ��A�g�[�����������������₷���Ȃ�܂����B
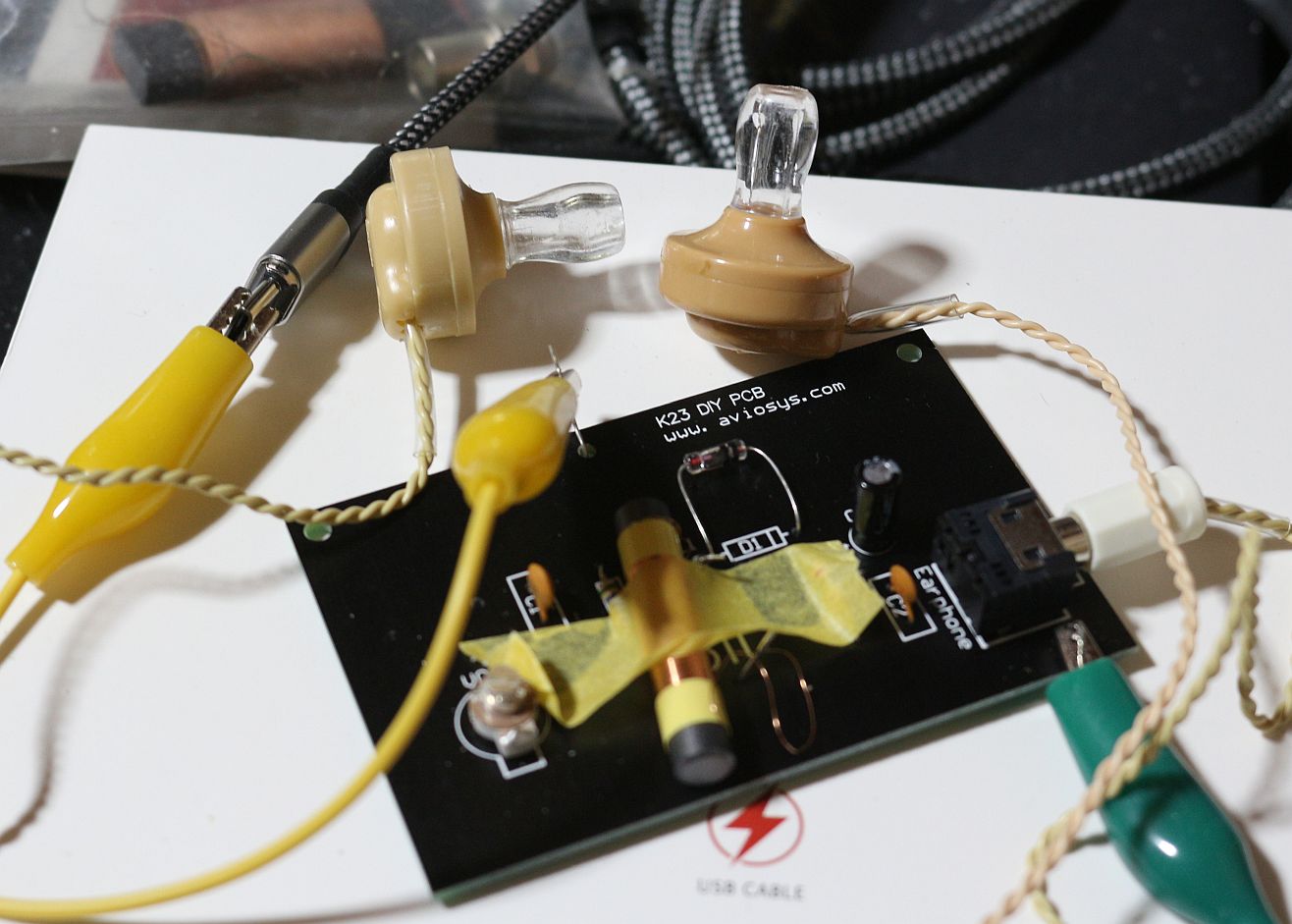 �ŁA�A�L�V�������[�h�^�C�v�ɖ߂��ƁA
�V�O�i���̋����͕ς��Ȃ����ǁA
��͂�A���M�������A3�Ȃ��炢��������̂����A������ǂ���ɔ���Ă�C���[�W������B
�A�[�X���O���ƁA2�`3�ǂɕ����o����B
�������ĕ��������ǖ���TBS�������̂ŁA954KHz�A�܂�A1MHz�߂��ł��ˁB
���_�Ƃ��ẮA
�V�O�i�����x�͌������Ⴄ�C���[�W�����������̂ŁA
�Ƃ肠�����A�\���m�C�h�̓A�L�V�������[�h�^�C�v�ōs���Ă݂悤���ȁ[�A�A�Ǝv���܂����B
�����́A�}�C�N���C���_�N�^�[�Ȃ��K�͂ŁA���́A�K�͂̑傫�߂̊������ψ�ȃC���_�N�^�[�łǂ����ȁH
1mH�Ȃ�A��ނ����肻���B���W�A���^�C�v�Ƃ��A�A
�������A����ŁA455KHz�����U������ƂȂ�ƁA�����Ă�g���}�[�R���f���T�[��120pF�ł̓M���M����F=459.44KHz�A
���i�̌�����t�F���C�g�̎��g���������ŖړI�̒Ⴓ�ɓ��B�o���Ȃ��B�܂��A�Œ��C�݂���c�A�A
�~�������Ȃ�A3.3mH�ʂ��~�����c�B
��ނƎ荠���ł́A�A�L�V�������[�h�^�C�v���ǂ����ǁA�o����̂́A�����̂�I�Ԃ��炢���B
��R������Q�l�ɋ����Ă��邱�Ƃ��l���āA�A
�Ƃ������ƂŁA���̒����́A�A�L�V�������[�h�^�C�v��1.5mH�A2.2mH��3.3mH�̑�����5mm�̃��c�B
����A�t�F���C�g�_��g���C�_���R�A�ɍא����Y��Ɋ����Ƃ���c�R�C���Ƃ��o����Ες���Ă���Ƃ͎v���B
���ƁA�Q���}�j�E�����W�I���l����ƁA
�Q���}�j�E��Di���g���Ă�ȏ�A��҂̕������Ȃ荂���d���������Ă�̂ŁA
���̏ꍇ�Ɠs�������Ȃ����Ă͂���B
�܂�A�m�C�Y�Ȃǂ̖����o�Ă���B
�N���X�^�����g����A�ʔ��������ł����AMHz�ȉ��ł́A60KHz������̂����E�ŁA����ȏ�̓C�L�i��MHz�s���Ă��܂������ł������B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�g�����W�X�^��������Ŗʓ|�L���̂��A�o�C�A�X�ƃA�C�h���d���̒����ŃA���B
��R�Őݒ肷��̂����A�J�[�{���ȉϒ�R�َ͈퓱�̊Ԃ̔M�G�����C�ɂȂ邩�Ǝv���Ă݂����A�����g�ł͂ǂ��Ȃ̂��낤�H
�M�G�������́A�N�d��En=��(4kTR)���Ƃ���A1/F�̕��z�̂悤�ł���B
�Ƃ���ƁA�����g�ł͗]����ɂȂ�Ȃ������m��Ȃ��̂ŁA
���Œ��R��IC�\�P�b�g�ɂ͂߂Ďg���Č��āA�����R�Ɍ��������肵�Ĕ�ׂĂ݂����g�R�ŃA���B
10K��VR�����肪�K�����낤���ȁH
����ƁA���i�̓��[�m�C�Y�A�n�C����Z���C�C���Ǝv���̂��A
FET�������̃C���s�[�_���X�ϊ��ɂ��邩�A���U�����i�Ƃ��Ďg�����H�������ǂ���B
���i��NPN�o�C�|�[���[�g�����W�X�^�ɂ��Ă��ǂ���ԂȂ�A�C���s�[�_���X�ϊ�����v��Ȃ������H
Tr���͂̃J�b�v�����O�R���f���T�[�́A33pF�ʂŁA�����o�b�T���Ƒ��i�Ő�̂��L�p�B
���Ƃ́A�t�H�gDi�̋t�o�C�A�X��R��]�荂���o���Ȃ��̂ŁA�ђʂ��鍂���g���R�C�����g���đj�~�������B
Z=��L�ł��邩��A1mH��1MHz����6.3K���ƂȂ�̂ŁA���܂���҂͏o���Ȃ����A
100mH�����肾�ƁA���\�Ɍ����Ă������B
PD�̌��̓�������ȂǃR���f�B�V�����ɂ����Ǝv���B
����ɁA100K�����x�̒�R���q������ǂ����낤���H
���W�I�pIC��LA1050�ƌ����O�[�q�̃��W�I�pIC�����������A���́AUTC7462�ƌ����̂��A���B
�����́AAGC(�I�[�g�Q�C���R���g���[��)�@�\�������Ă�̂ƁA
�����̓�����H������ƁA���Đ��ɋ߂��A���A�҂�����Ă���悤���B
���ƁA�o�C�A�X�����܂肩�����ĂȂ��Ǝv����Tr�����邯�ǁA���g�����˂Ă�̂��ȁH
�ŁA�A�L�V�������[�h�^�C�v�ɖ߂��ƁA
�V�O�i���̋����͕ς��Ȃ����ǁA
��͂�A���M�������A3�Ȃ��炢��������̂����A������ǂ���ɔ���Ă�C���[�W������B
�A�[�X���O���ƁA2�`3�ǂɕ����o����B
�������ĕ��������ǖ���TBS�������̂ŁA954KHz�A�܂�A1MHz�߂��ł��ˁB
���_�Ƃ��ẮA
�V�O�i�����x�͌������Ⴄ�C���[�W�����������̂ŁA
�Ƃ肠�����A�\���m�C�h�̓A�L�V�������[�h�^�C�v�ōs���Ă݂悤���ȁ[�A�A�Ǝv���܂����B
�����́A�}�C�N���C���_�N�^�[�Ȃ��K�͂ŁA���́A�K�͂̑傫�߂̊������ψ�ȃC���_�N�^�[�łǂ����ȁH
1mH�Ȃ�A��ނ����肻���B���W�A���^�C�v�Ƃ��A�A
�������A����ŁA455KHz�����U������ƂȂ�ƁA�����Ă�g���}�[�R���f���T�[��120pF�ł̓M���M����F=459.44KHz�A
���i�̌�����t�F���C�g�̎��g���������ŖړI�̒Ⴓ�ɓ��B�o���Ȃ��B�܂��A�Œ��C�݂���c�A�A
�~�������Ȃ�A3.3mH�ʂ��~�����c�B
��ނƎ荠���ł́A�A�L�V�������[�h�^�C�v���ǂ����ǁA�o����̂́A�����̂�I�Ԃ��炢���B
��R������Q�l�ɋ����Ă��邱�Ƃ��l���āA�A
�Ƃ������ƂŁA���̒����́A�A�L�V�������[�h�^�C�v��1.5mH�A2.2mH��3.3mH�̑�����5mm�̃��c�B
����A�t�F���C�g�_��g���C�_���R�A�ɍא����Y��Ɋ����Ƃ���c�R�C���Ƃ��o����Ες���Ă���Ƃ͎v���B
���ƁA�Q���}�j�E�����W�I���l����ƁA
�Q���}�j�E��Di���g���Ă�ȏ�A��҂̕������Ȃ荂���d���������Ă�̂ŁA
���̏ꍇ�Ɠs�������Ȃ����Ă͂���B
�܂�A�m�C�Y�Ȃǂ̖����o�Ă���B
�N���X�^�����g����A�ʔ��������ł����AMHz�ȉ��ł́A60KHz������̂����E�ŁA����ȏ�̓C�L�i��MHz�s���Ă��܂������ł������B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�g�����W�X�^��������Ŗʓ|�L���̂��A�o�C�A�X�ƃA�C�h���d���̒����ŃA���B
��R�Őݒ肷��̂����A�J�[�{���ȉϒ�R�َ͈퓱�̊Ԃ̔M�G�����C�ɂȂ邩�Ǝv���Ă݂����A�����g�ł͂ǂ��Ȃ̂��낤�H
�M�G�������́A�N�d��En=��(4kTR)���Ƃ���A1/F�̕��z�̂悤�ł���B
�Ƃ���ƁA�����g�ł͗]����ɂȂ�Ȃ������m��Ȃ��̂ŁA
���Œ��R��IC�\�P�b�g�ɂ͂߂Ďg���Č��āA�����R�Ɍ��������肵�Ĕ�ׂĂ݂����g�R�ŃA���B
10K��VR�����肪�K�����낤���ȁH
����ƁA���i�̓��[�m�C�Y�A�n�C����Z���C�C���Ǝv���̂��A
FET�������̃C���s�[�_���X�ϊ��ɂ��邩�A���U�����i�Ƃ��Ďg�����H�������ǂ���B
���i��NPN�o�C�|�[���[�g�����W�X�^�ɂ��Ă��ǂ���ԂȂ�A�C���s�[�_���X�ϊ�����v��Ȃ������H
Tr���͂̃J�b�v�����O�R���f���T�[�́A33pF�ʂŁA�����o�b�T���Ƒ��i�Ő�̂��L�p�B
���Ƃ́A�t�H�gDi�̋t�o�C�A�X��R��]�荂���o���Ȃ��̂ŁA�ђʂ��鍂���g���R�C�����g���đj�~�������B
Z=��L�ł��邩��A1mH��1MHz����6.3K���ƂȂ�̂ŁA���܂���҂͏o���Ȃ����A
100mH�����肾�ƁA���\�Ɍ����Ă������B
PD�̌��̓�������ȂǃR���f�B�V�����ɂ����Ǝv���B
����ɁA100K�����x�̒�R���q������ǂ����낤���H
���W�I�pIC��LA1050�ƌ����O�[�q�̃��W�I�pIC�����������A���́AUTC7462�ƌ����̂��A���B
�����́AAGC(�I�[�g�Q�C���R���g���[��)�@�\�������Ă�̂ƁA
�����̓�����H������ƁA���Đ��ɋ߂��A���A�҂�����Ă���悤���B
���ƁA�o�C�A�X�����܂肩�����ĂȂ��Ǝv����Tr�����邯�ǁA���g�����˂Ă�̂��ȁH
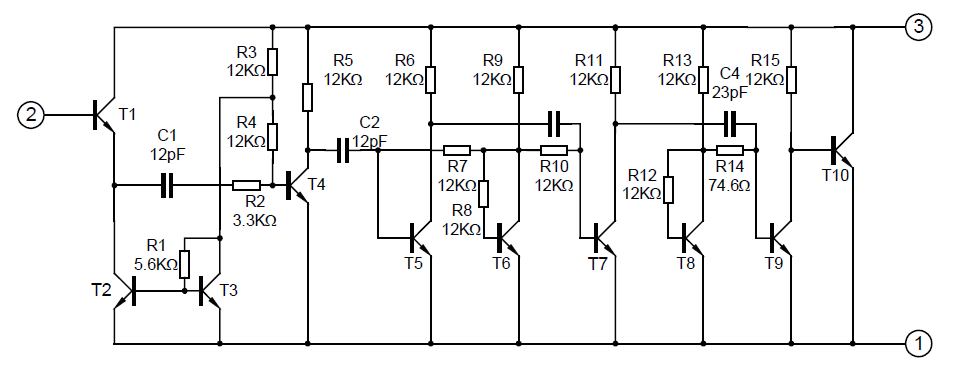 �p���X�̃o�[�X�g���Ԃ́A455KHz�̂����A50��Sec�ŁA1M�Ȃ�A10��Sec���x�ŁA�ǂ��̂ł͖������Ǝv���܂��B
�}�C�R�����ƁA���̃o�[�X�g�̒������������o�������ł��ˁB
�V�~�����[�^�[�ŁA������Ǝ����Č����B
�p���X�̃o�[�X�g���Ԃ́A455KHz�̂����A50��Sec�ŁA1M�Ȃ�A10��Sec���x�ŁA�ǂ��̂ł͖������Ǝv���܂��B
�}�C�R�����ƁA���̃o�[�X�g�̒������������o�������ł��ˁB
�V�~�����[�^�[�ŁA������Ǝ����Č����B
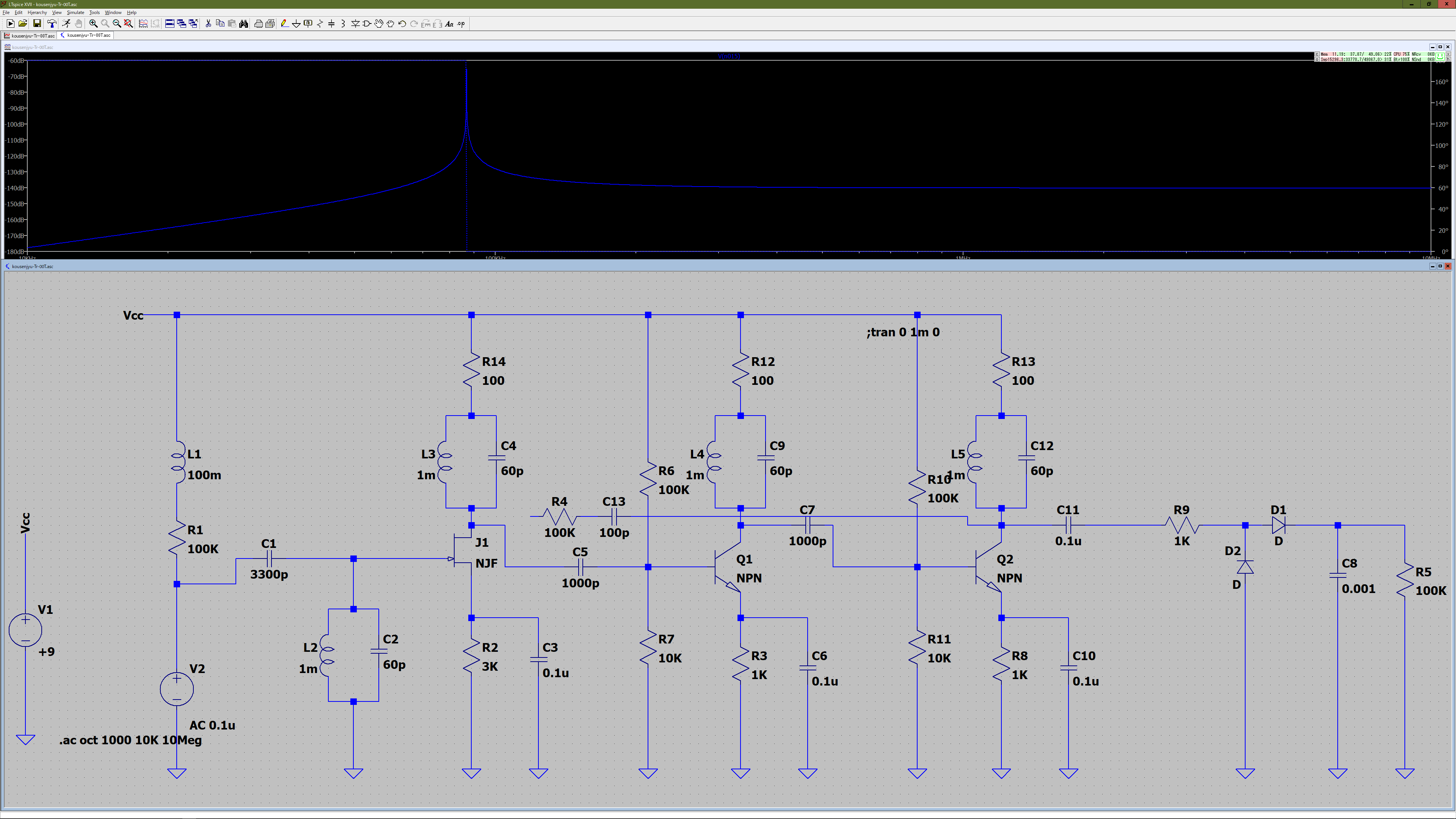 FET�ɋ��U�n���t���Ă�͖̂��ŁA���R�͌�q����B
�����@�́AL��C�����ŋ��U������͂��Ȃ��ǁA
�V�~�����[�^�[�ł́A���ꂪ���܂������Ȃ��݂����B
�f�J�b�v�����O�R���f���T�[��L�ŋ����Ă�Ƃ����c�A�A
���iFET��O�́A
�A���e�i�̂����Q���}�j�E�����W�I�Ɠ�������������A���̎��_��LC���U�̃X�y�N�g�����o�Ȃ��̂͊��ɂ��������B
�܂�A�V�~�����[�^�[�̌��E�H
���͂���f�J�b�v�����OC��100�����͂߂�ƁA
�����̋��U��Q�l�͉�����B
��������L��C�����z�����ꂷ���Ă邽�߂��ȁH
���U��H���ܑ̂Ȃ��̂ŁA���i�́A�����̋��U�̖����A���v�ɂ��Ă݂������ǂ������B
�Ƃ���ŁA455KHz��IF�ȃt�B���^�[�́AFCZ�R�C���̂悤�ȃR�A�����g�����X�\���ɂȂ��Ă����B���ɋ��U�p�̃R���f���T�[�������Ă���̂��Ⴄ�Ƃ����ȁH
6AKW-B3L3 IFT�R�C�� 10mm 455KHz(��)
-------------
�������B���͐M������R�����ɑ傫�������B
�܂���̓I�V���[�^�[�ɋ������ꂽ�M���ɂȂ��Ă��B
���Ƃ́A���Đ���H�����邩�Y�ݒ��B�B
Tr�̏o�͂Ɍq��������H�͋��U���g���̂����ɃY����B�ݒ��LC�l��3�`4�{�ς�邭�炢���ȁH
����́ATr�̎�ނ�o�C�A�X�ňړ�����̂ł�������ŃA���B�ǂ��������m���H
��������B
FET�ɋ��U�n���t���Ă�͖̂��ŁA���R�͌�q����B
�����@�́AL��C�����ŋ��U������͂��Ȃ��ǁA
�V�~�����[�^�[�ł́A���ꂪ���܂������Ȃ��݂����B
�f�J�b�v�����O�R���f���T�[��L�ŋ����Ă�Ƃ����c�A�A
���iFET��O�́A
�A���e�i�̂����Q���}�j�E�����W�I�Ɠ�������������A���̎��_��LC���U�̃X�y�N�g�����o�Ȃ��̂͊��ɂ��������B
�܂�A�V�~�����[�^�[�̌��E�H
���͂���f�J�b�v�����OC��100�����͂߂�ƁA
�����̋��U��Q�l�͉�����B
��������L��C�����z�����ꂷ���Ă邽�߂��ȁH
���U��H���ܑ̂Ȃ��̂ŁA���i�́A�����̋��U�̖����A���v�ɂ��Ă݂������ǂ������B
�Ƃ���ŁA455KHz��IF�ȃt�B���^�[�́AFCZ�R�C���̂悤�ȃR�A�����g�����X�\���ɂȂ��Ă����B���ɋ��U�p�̃R���f���T�[�������Ă���̂��Ⴄ�Ƃ����ȁH
6AKW-B3L3 IFT�R�C�� 10mm 455KHz(��)
-------------
�������B���͐M������R�����ɑ傫�������B
�܂���̓I�V���[�^�[�ɋ������ꂽ�M���ɂȂ��Ă��B
���Ƃ́A���Đ���H�����邩�Y�ݒ��B�B
Tr�̏o�͂Ɍq��������H�͋��U���g���̂����ɃY����B�ݒ��LC�l��3�`4�{�ς�邭�炢���ȁH
����́ATr�̎�ނ�o�C�A�X�ňړ�����̂ł�������ŃA���B�ǂ��������m���H
��������B
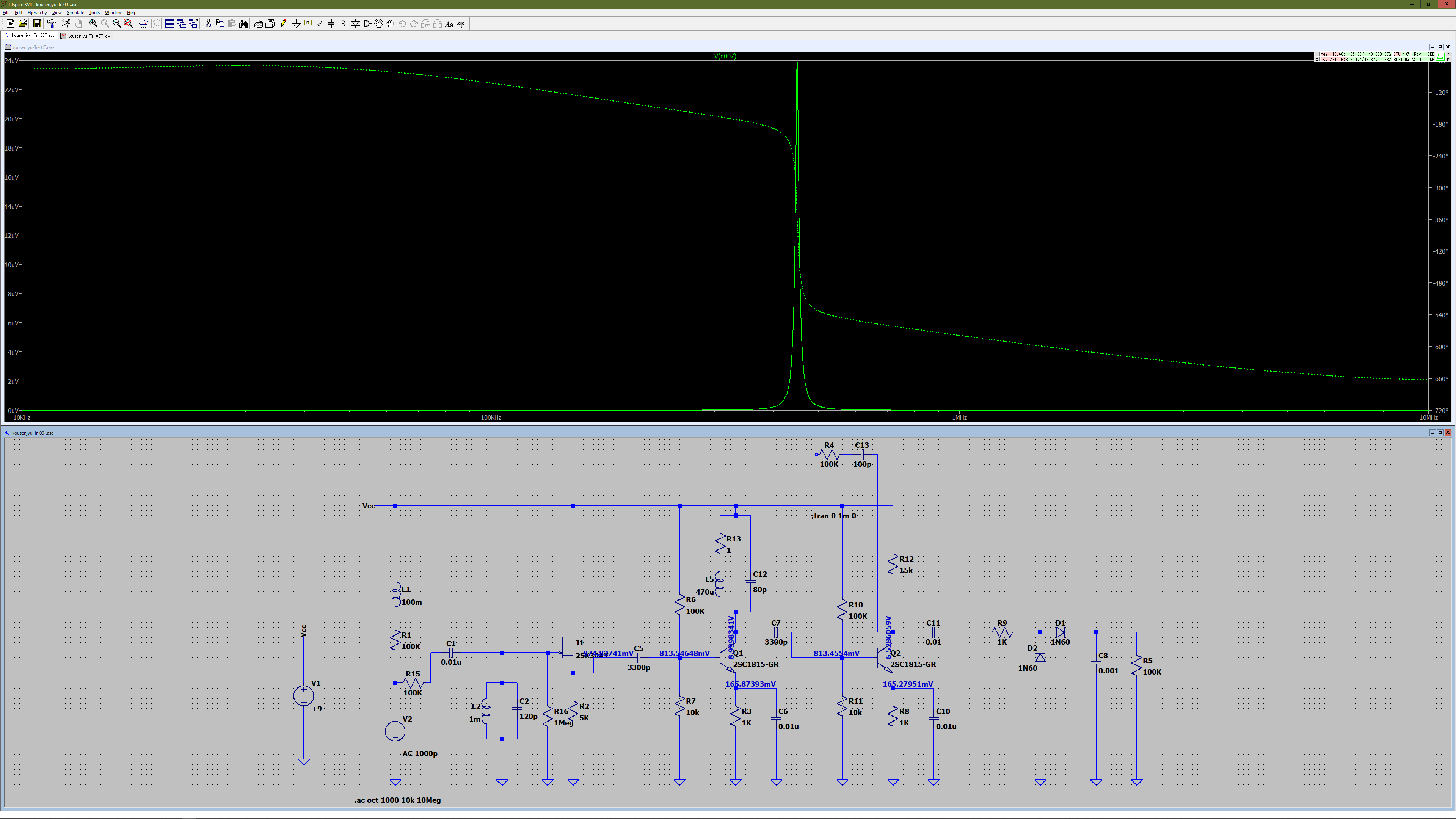 Tr�̋���H�͊�{�I��Q�l���オ��݂̂ŁA
�s�[�N�̑������́A���ʂ̑��������̂ƕς��Ȃ������B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���s��Ƃ���
FET�̕����ɋ��U��g��ł��l��������݂̂Ȃ̂ŁA�l�����B
�Ƃ������AFET�̓C���s�[�_���X�ϊ��ł����āA�����ł͂Ȃ��B�̂ŁA�����_�����Q�C����������B
����āA�����_�ł͂���Ȃ���������Ȃ����A�ł����i�����[�m�C�Y�ł������t�B���^��������̂͏d�v�ɂ��H�H
Tr�̋���H�͊�{�I��Q�l���オ��݂̂ŁA
�s�[�N�̑������́A���ʂ̑��������̂ƕς��Ȃ������B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���s��Ƃ���
FET�̕����ɋ��U��g��ł��l��������݂̂Ȃ̂ŁA�l�����B
�Ƃ������AFET�̓C���s�[�_���X�ϊ��ł����āA�����ł͂Ȃ��B�̂ŁA�����_�����Q�C����������B
����āA�����_�ł͂���Ȃ���������Ȃ����A�ł����i�����[�m�C�Y�ł������t�B���^��������̂͏d�v�ɂ��H�H
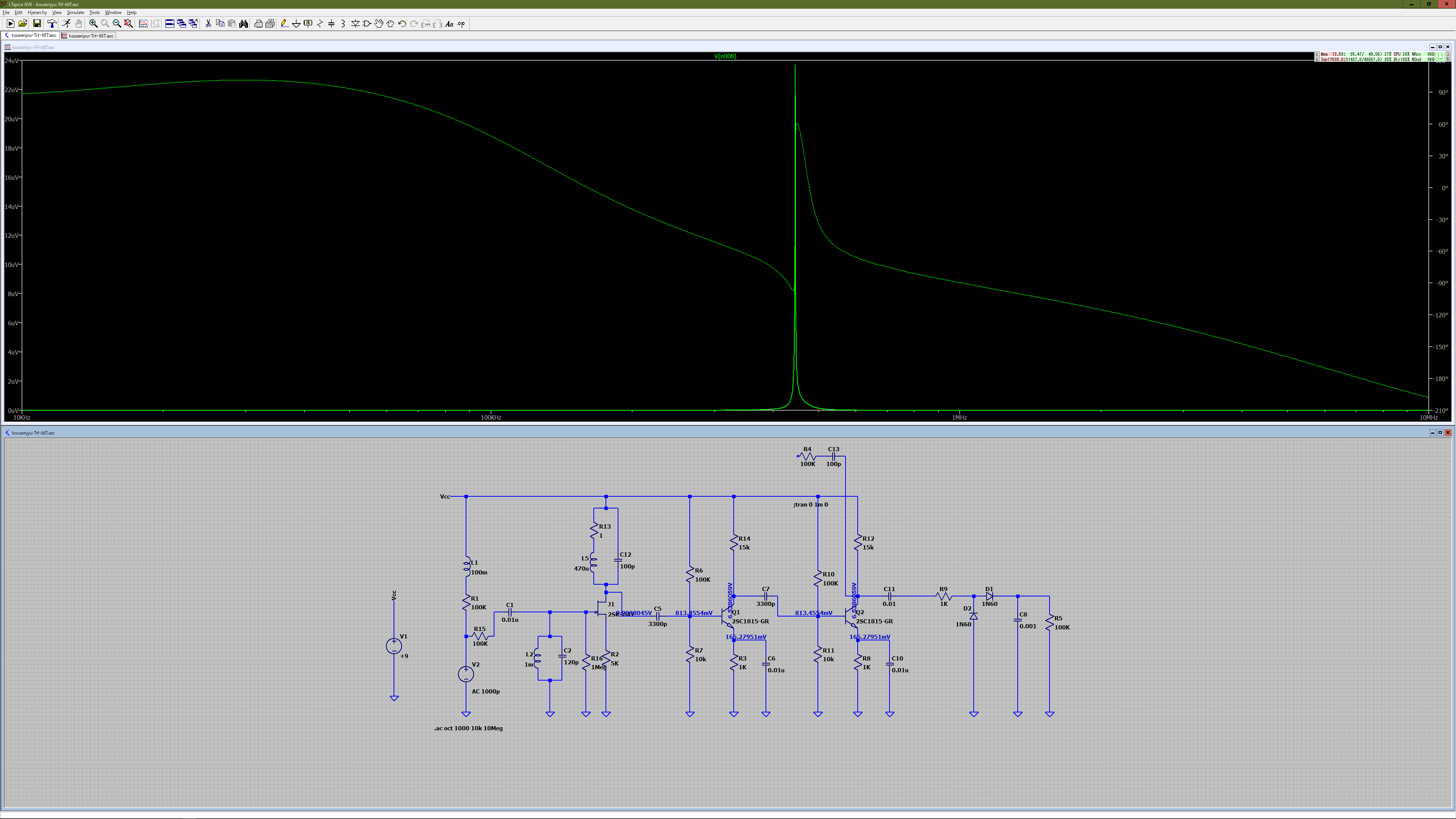 Q�͏オ�����悤�ɂ������邪�A�ʑ��̎��肪���������̂ŁA��͂�AFET��H�ɂ͋��U�n�͌����Ȃ��悤�ł���B���{�Ƃ��̖ړI�ȊO�B
JFET�́AB�Ɂ{�d�ʂ̃o�C�A�X��������o�C�|�[���[Tr�ƈႢ�A�\�[�X�ɓd��������邱�ƂŁAG���d�ʂ��オ��A����G�Ƀ}�C�i�X�̃o�C�A�X���������Ă��邱�ƂɂȂ�B
�Ԉ�����̂́A�o�C�|�[���[�Ɠ��������ŁA�o�C�A�X�������A�\�[�X�ɃR���f���T�[�Ńp�X���Ă�G���L��������������ŃA���B
����́A����킵�����A�ʂ̖ړI�Ȃ̂�������Ȃ��H
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220221
�Ƃ肠�����A�V���őg�����͂���ȃg�R
Q�͏オ�����悤�ɂ������邪�A�ʑ��̎��肪���������̂ŁA��͂�AFET��H�ɂ͋��U�n�͌����Ȃ��悤�ł���B���{�Ƃ��̖ړI�ȊO�B
JFET�́AB�Ɂ{�d�ʂ̃o�C�A�X��������o�C�|�[���[Tr�ƈႢ�A�\�[�X�ɓd��������邱�ƂŁAG���d�ʂ��オ��A����G�Ƀ}�C�i�X�̃o�C�A�X���������Ă��邱�ƂɂȂ�B
�Ԉ�����̂́A�o�C�|�[���[�Ɠ��������ŁA�o�C�A�X�������A�\�[�X�ɃR���f���T�[�Ńp�X���Ă�G���L��������������ŃA���B
����́A����킵�����A�ʂ̖ړI�Ȃ̂�������Ȃ��H
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220221
�Ƃ肠�����A�V���őg�����͂���ȃg�R
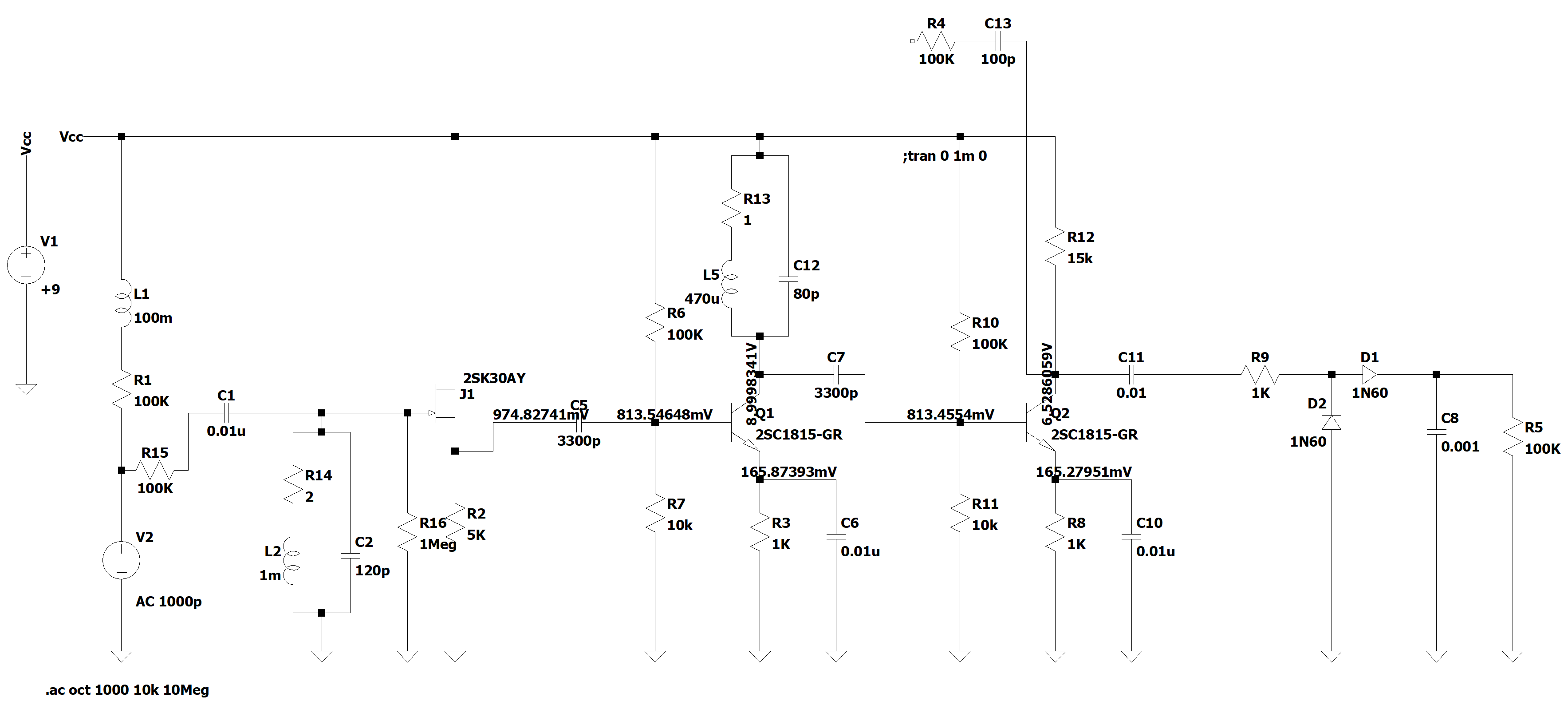 �f�J�b�v�����O�p�R���f���T�[�͂����Ɖ������邾�낤���A�o�C�A�X��Tr����ŁA�\���ɕt���Ă鋤�U��H�̐��l��Tr�̎�ނƂ��̐ݒ莟��B
FET�́A2SK303L-V3�F�h���C������f�d���F1.2�`3.0mA
�o�C�|�[���[�́A2SC1845�݊��i��KSC1845�Fhfe300�`600
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220222
(��)�����e�̎������LC���U�ōl���Ă݂�
K303-V3�FV3��IDSS=3mA�̃��f���B(y���Ƃ̐ؕ�)
�f�J�b�v�����O�p�R���f���T�[�͂����Ɖ������邾�낤���A�o�C�A�X��Tr����ŁA�\���ɕt���Ă鋤�U��H�̐��l��Tr�̎�ނƂ��̐ݒ莟��B
FET�́A2SK303L-V3�F�h���C������f�d���F1.2�`3.0mA
�o�C�|�[���[�́A2SC1845�݊��i��KSC1845�Fhfe300�`600
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220222
(��)�����e�̎������LC���U�ōl���Ă݂�
K303-V3�FV3��IDSS=3mA�̃��f���B(y���Ƃ̐ؕ�)
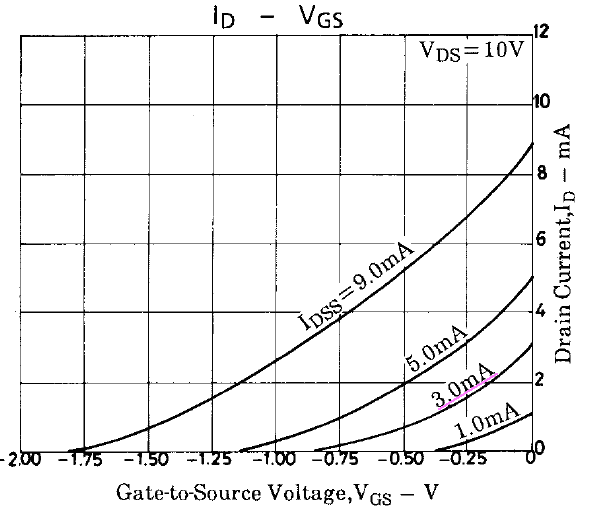 Rs=1�`2K���łǂ����H
1K����1mA����1V�������Ă邱�ƂɂȂ邯�ǁA�A�H
���������ɁA�o�����X�I�ɁA�����������ƁH �iVds��10V�ƌ����Ƃ��ɂ����ځB�j
Rs=1�`2K���łǂ����H
1K����1mA����1V�������Ă邱�ƂɂȂ邯�ǁA�A�H
���������ɁA�o�����X�I�ɁA�����������ƁH �iVds��10V�ƌ����Ƃ��ɂ����ځB�j
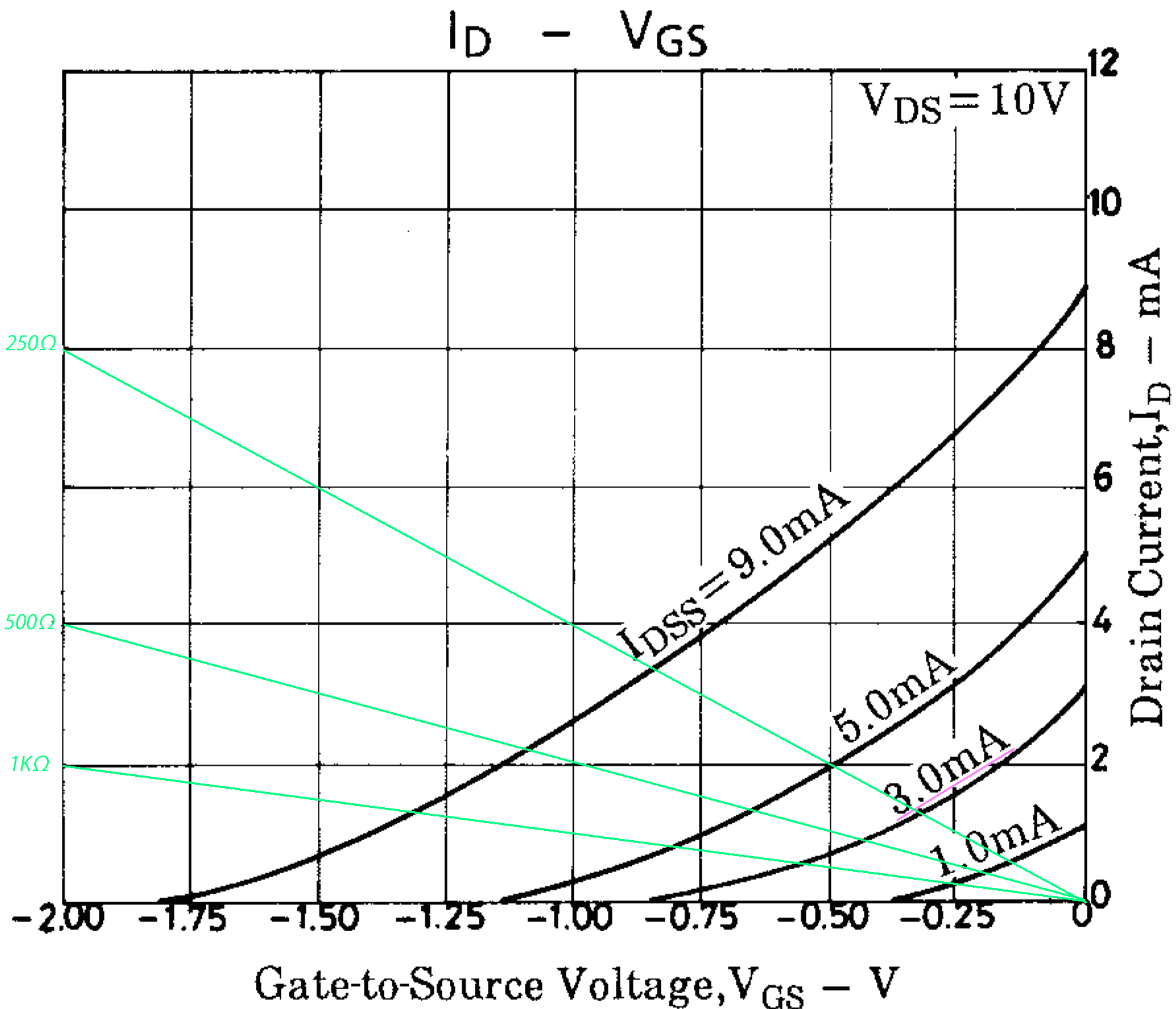 2SC1845
2SC1845
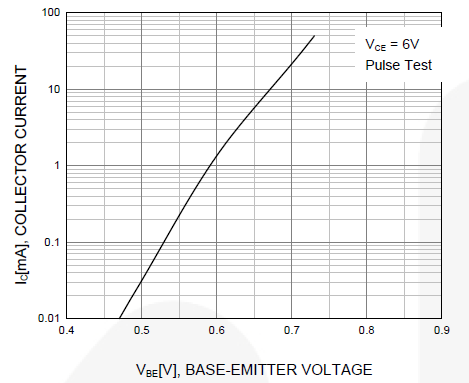 �o�C�A�X�p�̒�R�͍����ۂ��������ǁc�A100K����1M���͂ǂ����ȁH
Ice=1mA���x������ȓ���H
�ŁA���̑g�ݍ��킹�ł���Ă݂�ɁA�p�[�c�͈Ⴄ���ǁA�p�����^�̓R�����g�������B
�o�C�A�X�p�̒�R�͍����ۂ��������ǁc�A100K����1M���͂ǂ����ȁH
Ice=1mA���x������ȓ���H
�ŁA���̑g�ݍ��킹�ł���Ă݂�ɁA�p�[�c�͈Ⴄ���ǁA�p�����^�̓R�����g�������B
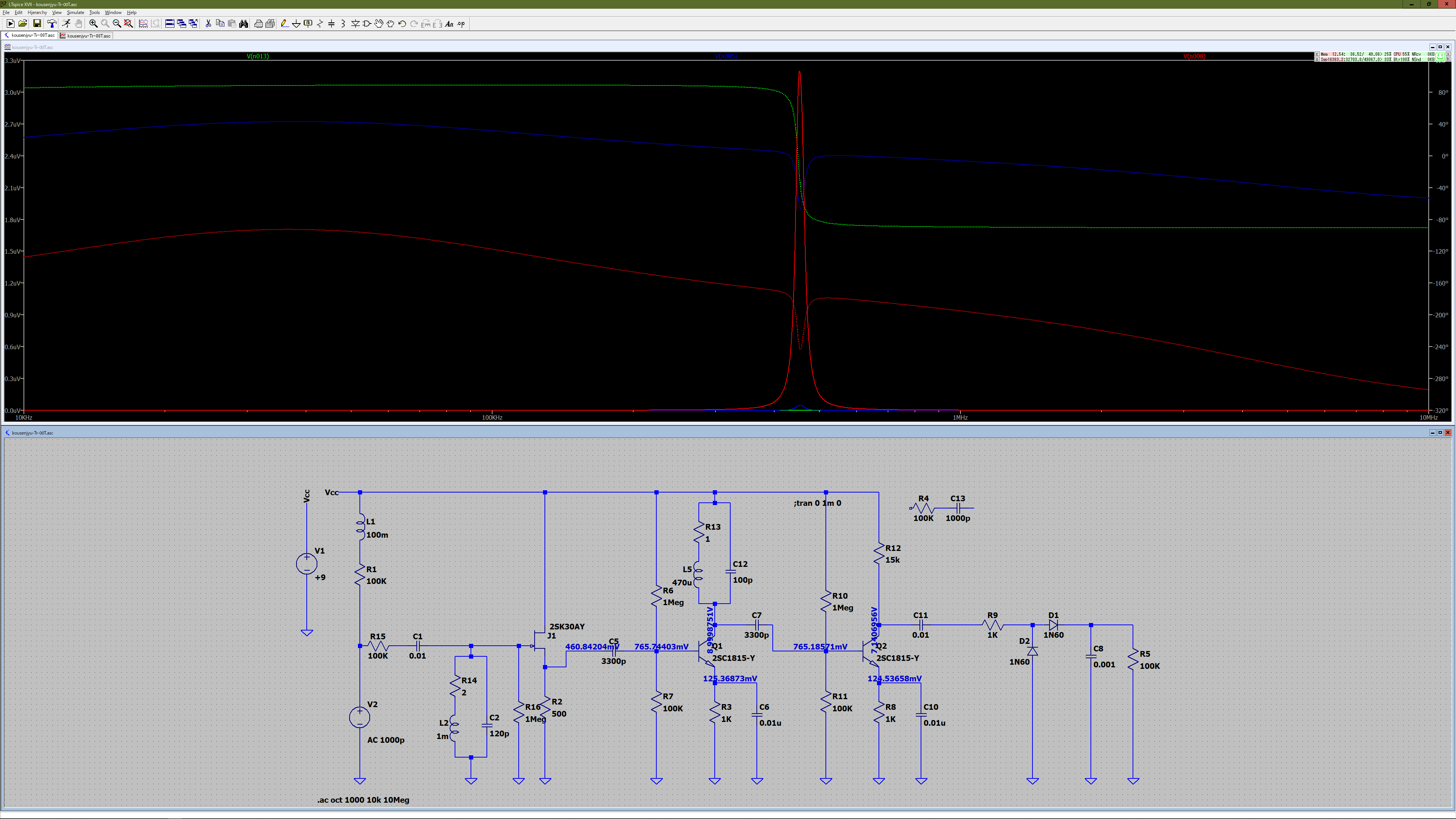 ���n��Tr�́A�o�C�A�X�𑽂߂ɗ����Q�C�����オ�邯�ǁA����ŗǂ��̂��ǂ������H�H
���ƁA�o�C�A�X��R���ꌅ�グ�����ǁA������C�C�̂��ȁH
�P�ɃQ�C�������҂��̂ł͖����ANF�Ƃ����l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂͂���B
�܂��A���n��Tr��H��LC�p�����^�́ATr�̎�ދy�уo�C�A�X�ɂ���Ă��Ȃ�ς��̂ŁAIC�\�P�b�g�d�l�ɂ������B����g�����B
�܂��AIC�\�P�b�g���炯�ɂȂ肻���c�B
�R�R�łڂ₫������B
OP-AMP�ƈ���āATr�f�B�X�N���[�g�̖��_�́A
�d���d���Ɍ����A�f�q�̕i�ԂȂǂɂ���ċ쓮�p�����^���������ς��Ƃ��B
��₱���������ŁA�w�p�I�ɍ����Ƃ����킯�ł��������������A�A
���\�͏��������ǁA�v������郂�m���ꍇ�ɂ���āu���ꂼ��v������A�uTr�f�B�X�N���[�g�őg��ł遁�̂��B�v�Ƃ����d�q�n�̔F���̓A�����ˁc�A�B
���s�I�I�i�k�[�ȍ�Ƃ��Ǝv�������ł��B
������u�Z�p���̃}�X�^�[�x�[�V�����v�Ƃ����銴���B
�����A�A�i���O��H�̋Z�p�͕K�v�ŁA�f�W�^�����Z�ɂ�������ƁA
�����@�B�Z�p�ł́A�@�B�I�ȋZ�p�̐��ނɌq�������ƊE������͎̂����B
�̂ĂĂ��܂����̂ł́A���߂��͍̂���B���ق��o�c�҂����ŁA1�N��̎�����l���āA10�N��̓c���͂炷�̂��W���d�l�ȉ�ЂƂ��ɂ���B
�����āA�v���Z�X�������Č����ڂ̌��ʎ����`���ƃh�c�{�ɍs���ˁB
�I�C�V�C�Ƃ����������Ă��āA���Ƃ͓��]�J���Ɏw�}���z��̂悤�Ɏg��CEO�Ƃ�CTO�֘A�H���Ƃ͕��������{�ƁH��͂��ȁB
�����E��l�Ԃ̓A�i���O�Ō`������Ă�B�Ȃ̂�����AI/F�O��͔����Ēʂ�Ȃ��Ƃ����̂�����B
�ǂ��炩����ΓI�ɖ��\�Ƃ͎v��Ȃ������ǂ��B�@���ɋ߂��������B
�����Z�p���A�g�ѓd�b�⍂���g���������āA�łт�ɋ߂���Ԃ����ǁA
�ʔ��������ł͂���B
�n�[�h�V���Z���o�Ă��āA�f�W�^���T���v���[��\�t�g�V���Z���o�Ă��Ėłт��������ǁA
�܂��A�ĔF������Ă��Ă�B���o�C�o���v�f���A���ɂ͂��邪�A���ꂾ���Ƃ͎v���Ȃ��B
�l�Ԃ����ɂ́A�D���Ŗ����A�ʔ������ǂ����H���d�v�B
�}�E���^�[�͗D���p�������B
�܂��A�Z�p�����o�c�҂��A���ӎ������n�͎��Ȏ咣(����̃A�s�[��)�Ŗ��s�����悭�N�����ƌ������ƁB
�I�i�j�X�g�ȋZ�p���̓A�������A����Ă�l�ԂɌ������ݎx�z��������㒷���A�A
�В��͌��Z�p�����A���Z�p��������Б��̐l�Ԃ��������ǁA���Ȃ��Ƌ�������邩��A�P���J���N����Ƃ����̂�ڂ̓�����ɂ��Ă��B������_���Ȃc�A�Ǝv����������ł���B
����������ӎ��̋������āA�A�F�ō�����Ƃ������o�͎������킹�Ȃ��̂��ȁH�Ƃ���ƊE�ɂ��Ďv���B���쌠�̎咣�ɂƂĂ��M�S�Ŏ蕨������̂ɃP���J����B
�Ƃ���ŁA
�����̂̌��ʂɂāA
2MHz���炢�܂ł͍��o�͂�LED���g����Ǝv����B
�ڍ��ʐς̏�����LD���ƁA�����Ə���\���������A�N���X1��2LD�K�͂��ƁA�ʑ��⏞����APC��H���K�v�ɂȂ�A��H�̋K�͂��傫���Ȃ�B
����́A���Ȃ�̂ɍ�����ALED��APC��H�ŁA�����͈ʑ��͘M���ĂȂ������͂��B
(�����_�A���̉摜������ƁA�����v�f������悤�ł���B)
����Ŕ��U������ƁA2MHz������܂ł͎��p�ł��銴���ł������B
���n��Tr�́A�o�C�A�X�𑽂߂ɗ����Q�C�����オ�邯�ǁA����ŗǂ��̂��ǂ������H�H
���ƁA�o�C�A�X��R���ꌅ�グ�����ǁA������C�C�̂��ȁH
�P�ɃQ�C�������҂��̂ł͖����ANF�Ƃ����l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂͂���B
�܂��A���n��Tr��H��LC�p�����^�́ATr�̎�ދy�уo�C�A�X�ɂ���Ă��Ȃ�ς��̂ŁAIC�\�P�b�g�d�l�ɂ������B����g�����B
�܂��AIC�\�P�b�g���炯�ɂȂ肻���c�B
�R�R�łڂ₫������B
OP-AMP�ƈ���āATr�f�B�X�N���[�g�̖��_�́A
�d���d���Ɍ����A�f�q�̕i�ԂȂǂɂ���ċ쓮�p�����^���������ς��Ƃ��B
��₱���������ŁA�w�p�I�ɍ����Ƃ����킯�ł��������������A�A
���\�͏��������ǁA�v������郂�m���ꍇ�ɂ���āu���ꂼ��v������A�uTr�f�B�X�N���[�g�őg��ł遁�̂��B�v�Ƃ����d�q�n�̔F���̓A�����ˁc�A�B
���s�I�I�i�k�[�ȍ�Ƃ��Ǝv�������ł��B
������u�Z�p���̃}�X�^�[�x�[�V�����v�Ƃ����銴���B
�����A�A�i���O��H�̋Z�p�͕K�v�ŁA�f�W�^�����Z�ɂ�������ƁA
�����@�B�Z�p�ł́A�@�B�I�ȋZ�p�̐��ނɌq�������ƊE������͎̂����B
�̂ĂĂ��܂����̂ł́A���߂��͍̂���B���ق��o�c�҂����ŁA1�N��̎�����l���āA10�N��̓c���͂炷�̂��W���d�l�ȉ�ЂƂ��ɂ���B
�����āA�v���Z�X�������Č����ڂ̌��ʎ����`���ƃh�c�{�ɍs���ˁB
�I�C�V�C�Ƃ����������Ă��āA���Ƃ͓��]�J���Ɏw�}���z��̂悤�Ɏg��CEO�Ƃ�CTO�֘A�H���Ƃ͕��������{�ƁH��͂��ȁB
�����E��l�Ԃ̓A�i���O�Ō`������Ă�B�Ȃ̂�����AI/F�O��͔����Ēʂ�Ȃ��Ƃ����̂�����B
�ǂ��炩����ΓI�ɖ��\�Ƃ͎v��Ȃ������ǂ��B�@���ɋ߂��������B
�����Z�p���A�g�ѓd�b�⍂���g���������āA�łт�ɋ߂���Ԃ����ǁA
�ʔ��������ł͂���B
�n�[�h�V���Z���o�Ă��āA�f�W�^���T���v���[��\�t�g�V���Z���o�Ă��Ėłт��������ǁA
�܂��A�ĔF������Ă��Ă�B���o�C�o���v�f���A���ɂ͂��邪�A���ꂾ���Ƃ͎v���Ȃ��B
�l�Ԃ����ɂ́A�D���Ŗ����A�ʔ������ǂ����H���d�v�B
�}�E���^�[�͗D���p�������B
�܂��A�Z�p�����o�c�҂��A���ӎ������n�͎��Ȏ咣(����̃A�s�[��)�Ŗ��s�����悭�N�����ƌ������ƁB
�I�i�j�X�g�ȋZ�p���̓A�������A����Ă�l�ԂɌ������ݎx�z��������㒷���A�A
�В��͌��Z�p�����A���Z�p��������Б��̐l�Ԃ��������ǁA���Ȃ��Ƌ�������邩��A�P���J���N����Ƃ����̂�ڂ̓�����ɂ��Ă��B������_���Ȃc�A�Ǝv����������ł���B
����������ӎ��̋������āA�A�F�ō�����Ƃ������o�͎������킹�Ȃ��̂��ȁH�Ƃ���ƊE�ɂ��Ďv���B���쌠�̎咣�ɂƂĂ��M�S�Ŏ蕨������̂ɃP���J����B
�Ƃ���ŁA
�����̂̌��ʂɂāA
2MHz���炢�܂ł͍��o�͂�LED���g����Ǝv����B
�ڍ��ʐς̏�����LD���ƁA�����Ə���\���������A�N���X1��2LD�K�͂��ƁA�ʑ��⏞����APC��H���K�v�ɂȂ�A��H�̋K�͂��傫���Ȃ�B
����́A���Ȃ�̂ɍ�����ALED��APC��H�ŁA�����͈ʑ��͘M���ĂȂ������͂��B
(�����_�A���̉摜������ƁA�����v�f������悤�ł���B)
����Ŕ��U������ƁA2MHz������܂ł͎��p�ł��銴���ł������B
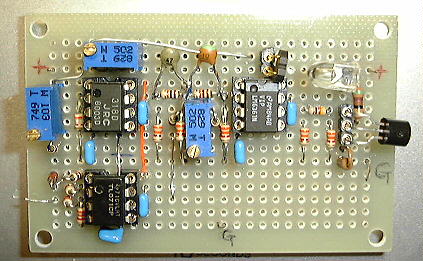 �����������̂ŁAAI�Ŋg�債�Ă݂��B
�����������̂ŁAAI�Ŋg�債�Ă݂��B
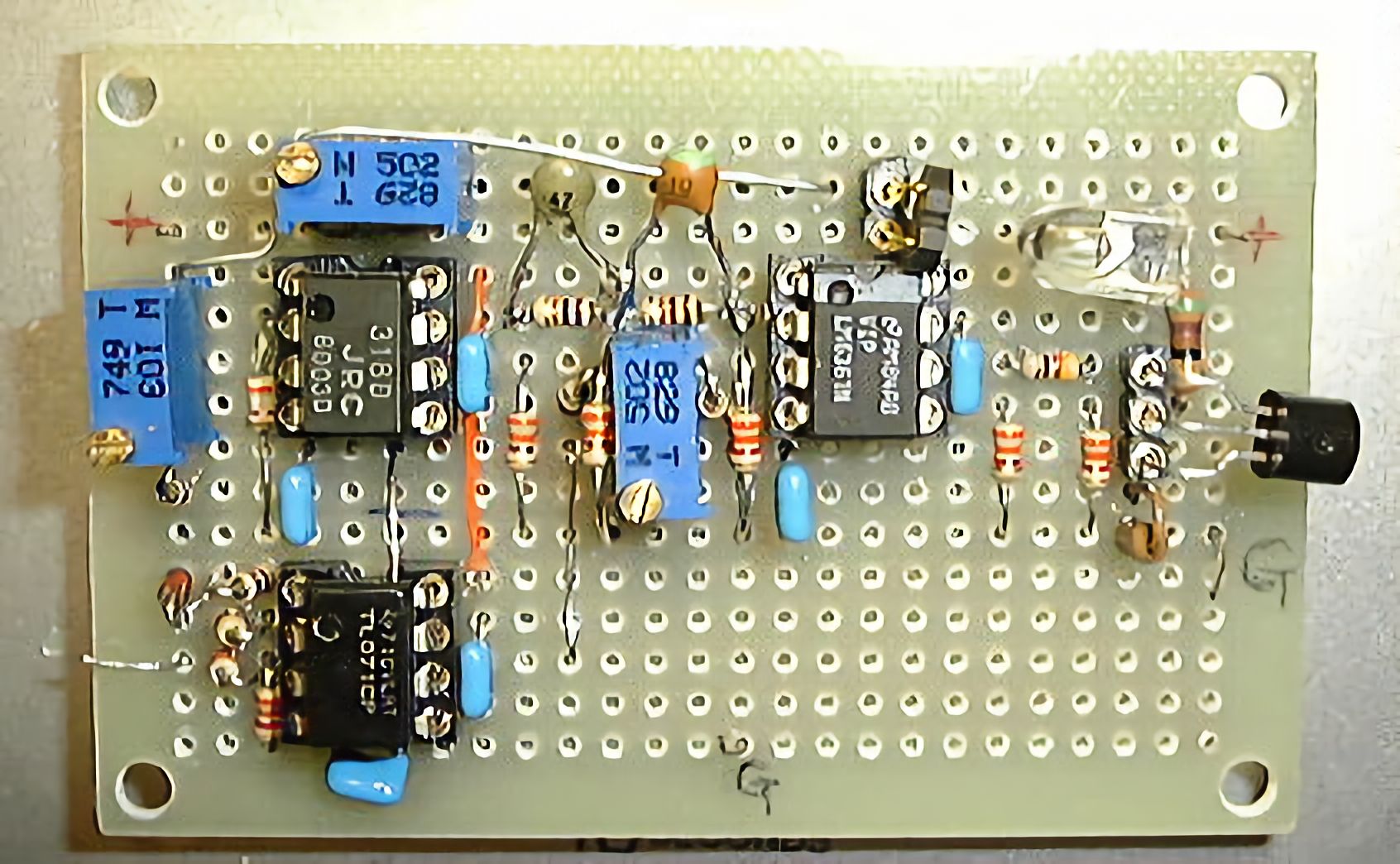 �E��̂͒�����OP-AMP���Ǝv����B�������ǂ݂ɂ������ANJM318D�H�������Ȃ̂Ń\�����Ǝv���B(316�Ƃ������ɂ��ǂ߂��������AJRC�ɂ͂��̔ԍ��͖��������B)
���v���ɁA����OP-AMP�̍����\����A��ʐς�PD�փo�C�A�X�ȂǂŁA�����Ɛ��䑤���������o���������m��Ȃ��Ǝv���Ă���B
�P�d�������\�����B
���i���͂�����A������Ƃ�������B�B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�����e�̎������LC���U��H�ʼn�����e�X�g�B
220223
�����ł悭�g����PLL�V���Z�T�C�U�[�����ɂ��āA���ׂ˂B
�\�z�́A�N���b�N�̃J�E���g�ɂ�镪�����ȁ[�A�ƁB
�ŁA���ׂČ��āA
PLL�V���Z�Ƃ́A�����̓V���Z�̕��ł����BPLL�͂��̔g��VFO�𐳊m�ɐ��䂷��Z�p�R�g�̂悤�ł��B�u�t�F�[�Y���b�N���[�v�iPLL�j�����Ƃ����̗̂��v
�ׂ����������̓o���L���b�v�ւ̈���x������RC���U�Ƃ�MIX��H�Ƀt�B�[�h�o�b�N���邱�Ƃŏo��̂��ȁH
�����MIX��H�͎��g�������炷�R�g���o����̂ł����A�ړI���g���̐M����IF���g���ŃA��10.7MHz�Ɉړ�������A����10.7MHz�Ƃ������g����p�̉s��BPF�őI��x���グ�邱�Ƃ��o���܂��ˁB
�܂�AIF���g���Ƃ����Œ���g���̉s�����g���ш��BPF��p����킯�ł��B
��2��IF��455KHz�H
IF�F����(���p�H)���g���Ƃ����B�Ƃ����ǔ����g���āA�A
�Ƃ����������ȁH�H���\�z���A���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���ƁA�R�C����Q�Ƃ́H
Q����L/R�@�@�F�N�I���e�B�[�t�@�N�^�[�B
������A�����̃t�B���^�̉s����Q�l�Ɗւ���Ă邱�Ƃ͊ւ���Ă��邪�c�A�B
�H���̃�5mm�̃A�L�V�������[�h�^�C�v�̂���Ă݂�B�u���[�J�[�FCore Master Enterprise�v
L�FQ�FR
100�ʁF15�F0.8��
150�ʁF30�F1.8��
220�ʁF30�F1.5��
330�ʁF40�F2.5��
470�ʁF20�F3.8��
680�ʁF30�F6.8��
1.0���F30�F8��
1.5���F30�F12��
2.2���F60�F14��
3.3���F30�F22��
�ǂ�����Ӑ��������Ƃ��낪���邪�A
�����́A������g����A�����̂ɂ��B�e�ʂ��H�����ȋ��U���g���B�B
�������o����A�f�[�^�V�[�g�Ƀ~�X�v��������ꍇ���傢�ɂ��蓾��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
FCZ�R�C���̂悤�ɁA
�g�����X��ɂȂ��Ă�σC���_�N�^�Ƃ����̂��������A�傫���̂�500��H
�g���}�[�R���f���T�[��1��]�����ǁA�R�C���͉��x����]�o����\���Ȃ̂ŁA���߂͂��₷������������B
�E��̂͒�����OP-AMP���Ǝv����B�������ǂ݂ɂ������ANJM318D�H�������Ȃ̂Ń\�����Ǝv���B(316�Ƃ������ɂ��ǂ߂��������AJRC�ɂ͂��̔ԍ��͖��������B)
���v���ɁA����OP-AMP�̍����\����A��ʐς�PD�փo�C�A�X�ȂǂŁA�����Ɛ��䑤���������o���������m��Ȃ��Ǝv���Ă���B
�P�d�������\�����B
���i���͂�����A������Ƃ�������B�B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�����e�̎������LC���U��H�ʼn�����e�X�g�B
220223
�����ł悭�g����PLL�V���Z�T�C�U�[�����ɂ��āA���ׂ˂B
�\�z�́A�N���b�N�̃J�E���g�ɂ�镪�����ȁ[�A�ƁB
�ŁA���ׂČ��āA
PLL�V���Z�Ƃ́A�����̓V���Z�̕��ł����BPLL�͂��̔g��VFO�𐳊m�ɐ��䂷��Z�p�R�g�̂悤�ł��B�u�t�F�[�Y���b�N���[�v�iPLL�j�����Ƃ����̗̂��v
�ׂ����������̓o���L���b�v�ւ̈���x������RC���U�Ƃ�MIX��H�Ƀt�B�[�h�o�b�N���邱�Ƃŏo��̂��ȁH
�����MIX��H�͎��g�������炷�R�g���o����̂ł����A�ړI���g���̐M����IF���g���ŃA��10.7MHz�Ɉړ�������A����10.7MHz�Ƃ������g����p�̉s��BPF�őI��x���グ�邱�Ƃ��o���܂��ˁB
�܂�AIF���g���Ƃ����Œ���g���̉s�����g���ш��BPF��p����킯�ł��B
��2��IF��455KHz�H
IF�F����(���p�H)���g���Ƃ����B�Ƃ����ǔ����g���āA�A
�Ƃ����������ȁH�H���\�z���A���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���ƁA�R�C����Q�Ƃ́H
Q����L/R�@�@�F�N�I���e�B�[�t�@�N�^�[�B
������A�����̃t�B���^�̉s����Q�l�Ɗւ���Ă邱�Ƃ͊ւ���Ă��邪�c�A�B
�H���̃�5mm�̃A�L�V�������[�h�^�C�v�̂���Ă݂�B�u���[�J�[�FCore Master Enterprise�v
L�FQ�FR
100�ʁF15�F0.8��
150�ʁF30�F1.8��
220�ʁF30�F1.5��
330�ʁF40�F2.5��
470�ʁF20�F3.8��
680�ʁF30�F6.8��
1.0���F30�F8��
1.5���F30�F12��
2.2���F60�F14��
3.3���F30�F22��
�ǂ�����Ӑ��������Ƃ��낪���邪�A
�����́A������g����A�����̂ɂ��B�e�ʂ��H�����ȋ��U���g���B�B
�������o����A�f�[�^�V�[�g�Ƀ~�X�v��������ꍇ���傢�ɂ��蓾��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
FCZ�R�C���̂悤�ɁA
�g�����X��ɂȂ��Ă�σC���_�N�^�Ƃ����̂��������A�傫���̂�500��H
�g���}�[�R���f���T�[��1��]�����ǁA�R�C���͉��x����]�o����\���Ȃ̂ŁA���߂͂��₷������������B
 �֗��ł͂��肻�������A���i�ɗ��肷���H������R�����߁B
��{�p�[�c�ŏ�肭�s���Ȃ��ꍇ�A���̎�Ƃ��Ă͎���Ă������B
(���f�[�^�V�[�g������A2�̒[�q�ȊO���ڑ��������ŁA�g�����X�ɂ��Ȃ��Ė������āA�Z���^�[�^�b�v�����������ł��B�^�_�̉σC���_�N�^�B�B)
�����������A���ӓ_�́A���̎�̃g�����X�́AFCZ�R�C���Ɠ��lDIP�ȃs�b�`�̊�ɂ̓n�}��Ȃ��\���������B
�Ȃ�A�O�ɏ�����455KHz��LC�ȃg�����X�\���̂�BPF����Ȃ��A
�������ȃZ���~�b�N�U���q���g�p�Ǝv�����p��BPF�ł��邱����g�������l�����B
�֗��ł͂��肻�������A���i�ɗ��肷���H������R�����߁B
��{�p�[�c�ŏ�肭�s���Ȃ��ꍇ�A���̎�Ƃ��Ă͎���Ă������B
(���f�[�^�V�[�g������A2�̒[�q�ȊO���ڑ��������ŁA�g�����X�ɂ��Ȃ��Ė������āA�Z���^�[�^�b�v�����������ł��B�^�_�̉σC���_�N�^�B�B)
�����������A���ӓ_�́A���̎�̃g�����X�́AFCZ�R�C���Ɠ��lDIP�ȃs�b�`�̊�ɂ̓n�}��Ȃ��\���������B
�Ȃ�A�O�ɏ�����455KHz��LC�ȃg�����X�\���̂�BPF����Ȃ��A
�������ȃZ���~�b�N�U���q���g�p�Ǝv�����p��BPF�ł��邱����g�������l�����B
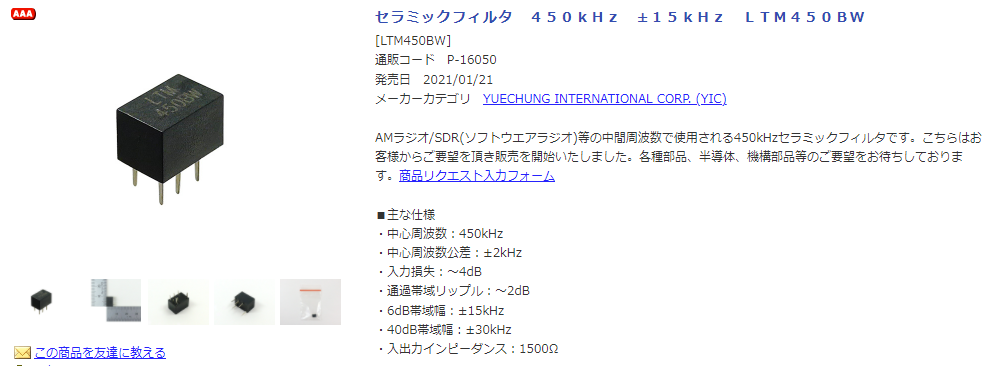
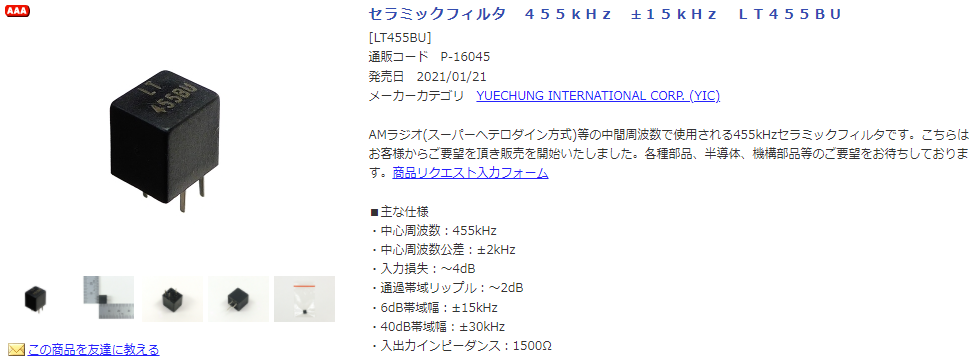 BU��BW�́A�ʉߑш�X�y�N�g�����Ⴂ�ABU�̕��������������B����āA���C�y�Ɏg����̂�BU�̕��ŁA�������R���p�N�g�Œl�i�����������B
���Ƃ́A�ߓn���������������̂��ǂ����A�Z���~�b�N�̐U�����ǂ�ȃ��x���Ȃ̂��H�Ƃ������������B
�Z���~�b�N�U���q��IF�t�B���^�[��10.7MHz�p������B
���J�j�J���ȐU���q������A���͂Ƀp���[���K�v�Ƃ�����̂��Ǝv�������ǁA�L�q�͖����B
���ꂪLC�ȃg�����X��455KHz�t�B���^�[�BIFT�Ƃ����B
BU��BW�́A�ʉߑш�X�y�N�g�����Ⴂ�ABU�̕��������������B����āA���C�y�Ɏg����̂�BU�̕��ŁA�������R���p�N�g�Œl�i�����������B
���Ƃ́A�ߓn���������������̂��ǂ����A�Z���~�b�N�̐U�����ǂ�ȃ��x���Ȃ̂��H�Ƃ������������B
�Z���~�b�N�U���q��IF�t�B���^�[��10.7MHz�p������B
���J�j�J���ȐU���q������A���͂Ƀp���[���K�v�Ƃ�����̂��Ǝv�������ǁA�L�q�͖����B
���ꂪLC�ȃg�����X��455KHz�t�B���^�[�BIFT�Ƃ����B
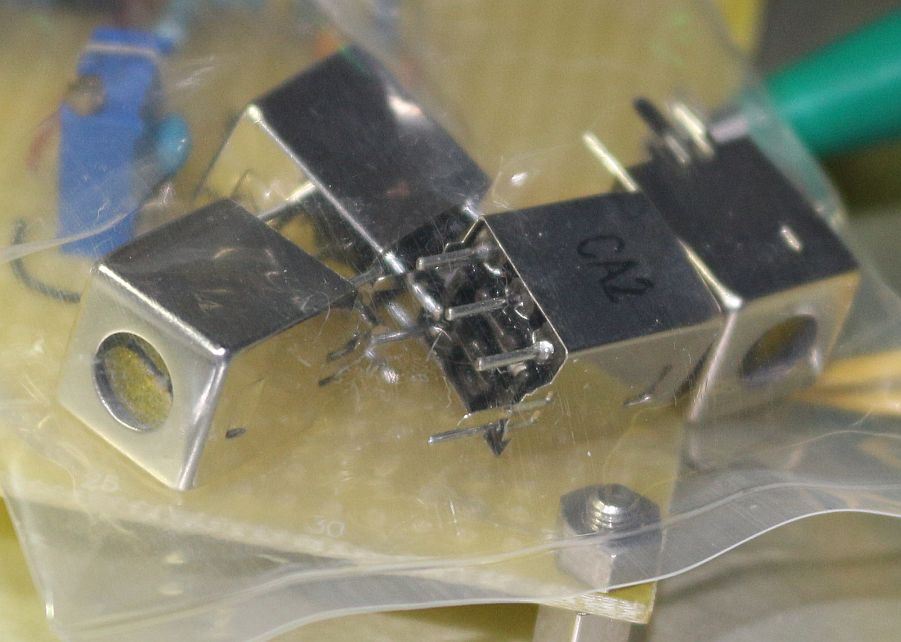 ���݂ɃZ���~�b�N�t�B���^�[��CF�Ƃ����B
�������A���g��AM�͖łт���������A�������Ȃ��ȁ[�A�Ƃ͎v�����ǁc�A�A�A
�܂��A455KHz�̓��Ԕg�Ƃ����K�i�͖łтȂ����ȁB
�ł��A455KHz�����g���Ȃ��̂͑������ł��A���B
�����R���p�ԊO��������j�b�g���A�����\��ڎw���Ă��邪�A�ėp�������邱�Ƃ��ڎw���Ă���B
�ėp���́A�Ȃ�ׂ���p�̓��ꕔ�i���g��Ȃ����Ƃł���B
�����R��������j�b�g�́A�܂��A�����Ȍ������킹�ɕK�v�ȉ����ɑΉ����ĂȂ����A�̂ɁA��������v�����A�������������[�U�[�_�C�I�[�h�ɂ��Ή����ĂȂ��B
�����J�b�g�͑��z�����������߁A�����Ȃ��Ă镔���͑����Ƃ͎v���A�����́A�܂��A���[�U�[�X�y�N�g��������ʂ��A����̗U�d�̑��w��BPF�ƍs���������A�ʎY�ł����Ȃ���ΒP�������ɍ�������B
�����I�ȉ����ŏ������Ƃ����Ƃ͏o���邩���H�H
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
2SK303-V5�̕����AVgs-Ids�Ȑ��������Ă�̂ŁA���x�����������Ǝv���̂ŁA����𒍕��BNF�Ƃ̌��ˍ������A���B
Rs��300�����x�ɉ�������o�͂͋t�ɉ��������̂ŁA1K���ɖ߂����B
OP-AMP�g���ƁA���U���₷�����A���͑��Ƀo�C�A�X���߂��Ă�����A�I�t�Z�b�g���ɂ���FET���͂Ɍ���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220224
�̂̉�H���������邱�ƂŃe�X�g���J�n�B
�g�`�̗���́A�m�C�Y�ŁA�W��߂�Ώ�����B(VR-HMD�̃x�[�X�X�e�[�V��������̃��[�U�[���ɔ������Ă����B�B)
���̑���AOP-AMP�����U���₷���Ȃ����������B
�C���C�������āA�n�C�Q�C����OP-AMP�͂���قǖ��ɗ����ĂȂ������B
���݂ɃZ���~�b�N�t�B���^�[��CF�Ƃ����B
�������A���g��AM�͖łт���������A�������Ȃ��ȁ[�A�Ƃ͎v�����ǁc�A�A�A
�܂��A455KHz�̓��Ԕg�Ƃ����K�i�͖łтȂ����ȁB
�ł��A455KHz�����g���Ȃ��̂͑������ł��A���B
�����R���p�ԊO��������j�b�g���A�����\��ڎw���Ă��邪�A�ėp�������邱�Ƃ��ڎw���Ă���B
�ėp���́A�Ȃ�ׂ���p�̓��ꕔ�i���g��Ȃ����Ƃł���B
�����R��������j�b�g�́A�܂��A�����Ȍ������킹�ɕK�v�ȉ����ɑΉ����ĂȂ����A�̂ɁA��������v�����A�������������[�U�[�_�C�I�[�h�ɂ��Ή����ĂȂ��B
�����J�b�g�͑��z�����������߁A�����Ȃ��Ă镔���͑����Ƃ͎v���A�����́A�܂��A���[�U�[�X�y�N�g��������ʂ��A����̗U�d�̑��w��BPF�ƍs���������A�ʎY�ł����Ȃ���ΒP�������ɍ�������B
�����I�ȉ����ŏ������Ƃ����Ƃ͏o���邩���H�H
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
2SK303-V5�̕����AVgs-Ids�Ȑ��������Ă�̂ŁA���x�����������Ǝv���̂ŁA����𒍕��BNF�Ƃ̌��ˍ������A���B
Rs��300�����x�ɉ�������o�͂͋t�ɉ��������̂ŁA1K���ɖ߂����B
OP-AMP�g���ƁA���U���₷�����A���͑��Ƀo�C�A�X���߂��Ă�����A�I�t�Z�b�g���ɂ���FET���͂Ɍ���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220224
�̂̉�H���������邱�ƂŃe�X�g���J�n�B
�g�`�̗���́A�m�C�Y�ŁA�W��߂�Ώ�����B(VR-HMD�̃x�[�X�X�e�[�V��������̃��[�U�[���ɔ������Ă����B�B)
���̑���AOP-AMP�����U���₷���Ȃ����������B
�C���C�������āA�n�C�Q�C����OP-AMP�͂���قǖ��ɗ����ĂȂ������B
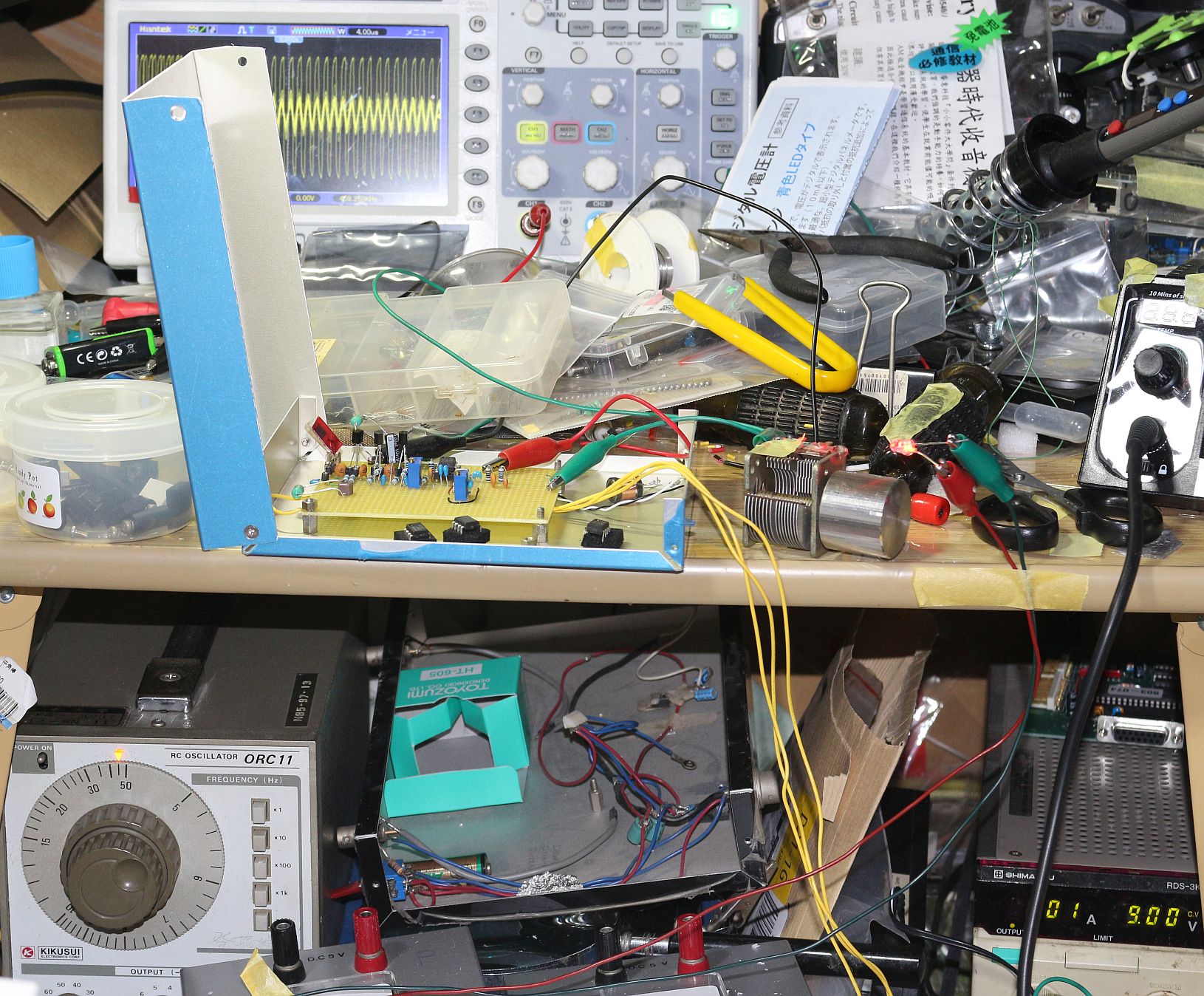 ���̎��_�ŁA�ŏ���3�i��Tr�����ł��A����Ȃ�̃Q�C�����o�Ă��Ă�̂Ɋւ�炸�AOP-AMP�����ɖ�肪�����āA�A�A
�����A���U���~�܂��Ă�ƁA����Ȍ��Ŕ�������ꍇ���B
OP-AMP�̎�ނɂ�镔��������ŁAFET���͂���Ȃ��ƁA���͂Ƀo�C�A�X�Ȃǂ���荞��ł�����A�C���s�[�_���X����߂�������Ŗ����N�����₷���B
�Ƃ肠�����A
NJM072�ł́A���U�C���Ȃ̂��C�ɂȂ�̂ŁA1��HOP-AMP1�i�Ŗ���ɂ������g�R
OP-AMP�̏o�͓͂d�͂��҂��A��C���s�[�_���X�h���C�u�p�ɐݒ�o����̂ŁA���g�O������Ɏg����B
���ƁA
�Q�C�������炸�����H�܂��A���W�I��8��AM���W�I�Ƃ����邵�c�A
�����A��Ԃ̓�_�́A2�i�ڂ�Tr��p����BPF�I���U����肭�s���Ȃ��B���Ɋɂ��s�[�N�͂���悤�����c�A�A�B
���̎��_�ŁA�ŏ���3�i��Tr�����ł��A����Ȃ�̃Q�C�����o�Ă��Ă�̂Ɋւ�炸�AOP-AMP�����ɖ�肪�����āA�A�A
�����A���U���~�܂��Ă�ƁA����Ȍ��Ŕ�������ꍇ���B
OP-AMP�̎�ނɂ�镔��������ŁAFET���͂���Ȃ��ƁA���͂Ƀo�C�A�X�Ȃǂ���荞��ł�����A�C���s�[�_���X����߂�������Ŗ����N�����₷���B
�Ƃ肠�����A
NJM072�ł́A���U�C���Ȃ̂��C�ɂȂ�̂ŁA1��HOP-AMP1�i�Ŗ���ɂ������g�R
OP-AMP�̏o�͓͂d�͂��҂��A��C���s�[�_���X�h���C�u�p�ɐݒ�o����̂ŁA���g�O������Ɏg����B
���ƁA
�Q�C�������炸�����H�܂��A���W�I��8��AM���W�I�Ƃ����邵�c�A
�����A��Ԃ̓�_�́A2�i�ڂ�Tr��p����BPF�I���U����肭�s���Ȃ��B���Ɋɂ��s�[�N�͂���悤�����c�A�A�B
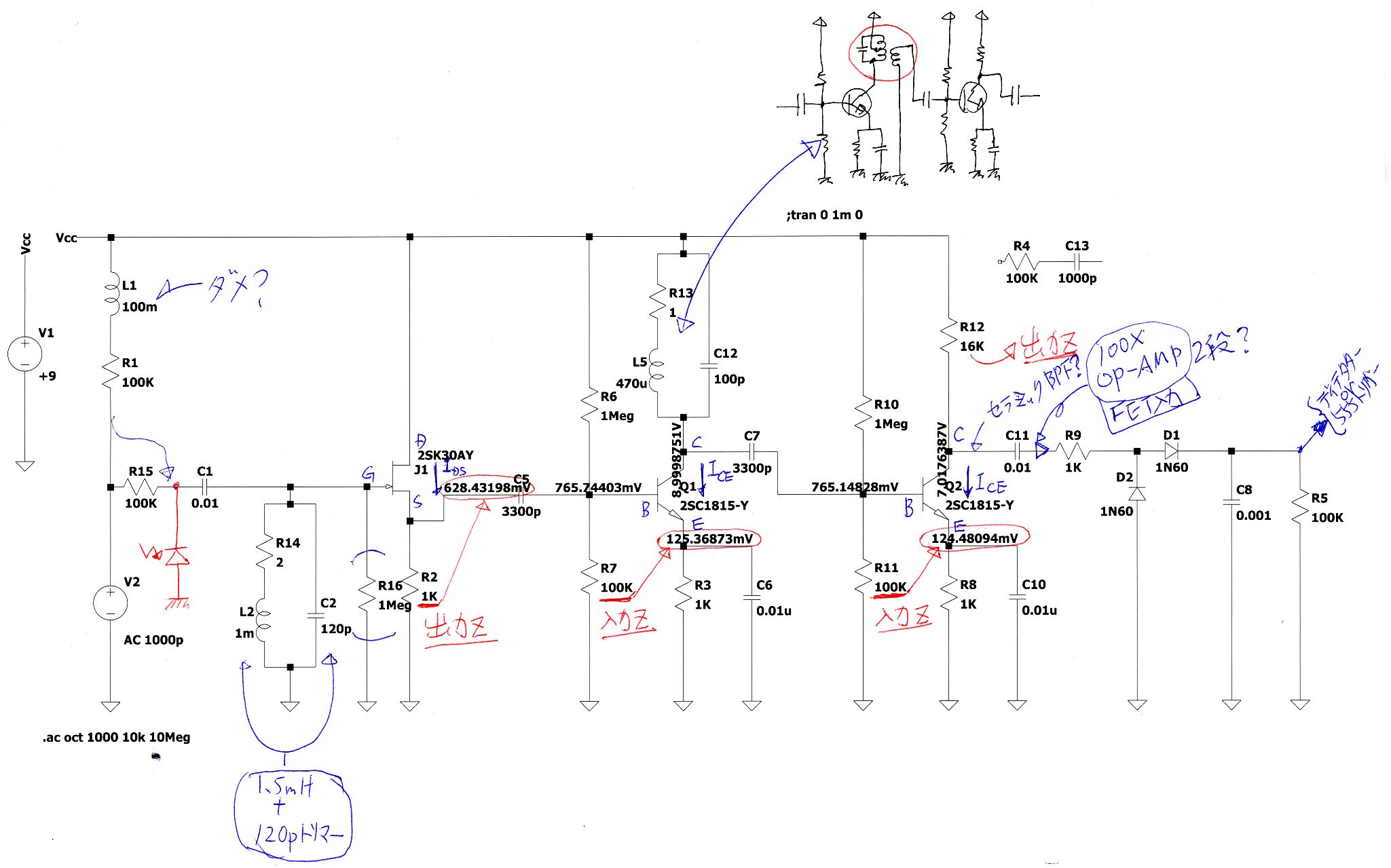 �ŁA��̕��ɏ������g�����X�\�����K�{�����m��Ȃ��H�B�ƂȂ�ƁA��p�p�[�c�ȊO�A�芪���R�C���ƂȂ�B
�g�����X�R�C����DIP�Ƀs�b�`������Ȃ����ۂ����A���̒ɂ����ł���B
���ƁA���M�����������ƍ���āA�ԊOLED�ŁA���ۋ�����ʂ��ăe�X�g�������B
���x�ŁA�s�̂̃����R��������W���[�����z�������Ƃ���ŃA���B
�����V���b�g�̃g���K�����O���ԕ���1/10������30�`��50Sec���炢���ȁH
�s�̂�TV�Ȃǂ̃����R��������W���[���́A�{���̐��\��肩�Ȃ芴�x�𗎂Ƃ��Ă���悤�ł���B
���ꂪ�Ȃ���A���ڌ��ɂ͎Օ����������āA�����������̂߂��Ⴍ����ł��A�قڊm���ɋ����قǔ�������B
���݂ɁA�s�̂̎�����W���[�����A�����V���b�g�p���X�Ȃ�A�J�����̃X�g���{�ł���N����Ĕ����A��쓮����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220225
���U��H�́A�ȑO��250KHz�̃��m�̉ϒ�R������������455KHz�d�l�ɂȂ����B
�^�C�}�[IC��LMC555�̂܂܂ŃL���̗ǂ���`�g���o�Ă���B
�ŁA��̕��ɏ������g�����X�\�����K�{�����m��Ȃ��H�B�ƂȂ�ƁA��p�p�[�c�ȊO�A�芪���R�C���ƂȂ�B
�g�����X�R�C����DIP�Ƀs�b�`������Ȃ����ۂ����A���̒ɂ����ł���B
���ƁA���M�����������ƍ���āA�ԊOLED�ŁA���ۋ�����ʂ��ăe�X�g�������B
���x�ŁA�s�̂̃����R��������W���[�����z�������Ƃ���ŃA���B
�����V���b�g�̃g���K�����O���ԕ���1/10������30�`��50Sec���炢���ȁH
�s�̂�TV�Ȃǂ̃����R��������W���[���́A�{���̐��\��肩�Ȃ芴�x�𗎂Ƃ��Ă���悤�ł���B
���ꂪ�Ȃ���A���ڌ��ɂ͎Օ����������āA�����������̂߂��Ⴍ����ł��A�قڊm���ɋ����قǔ�������B
���݂ɁA�s�̂̎�����W���[�����A�����V���b�g�p���X�Ȃ�A�J�����̃X�g���{�ł���N����Ĕ����A��쓮����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220225
���U��H�́A�ȑO��250KHz�̃��m�̉ϒ�R������������455KHz�d�l�ɂȂ����B
�^�C�}�[IC��LMC555�̂܂܂ŃL���̗ǂ���`�g���o�Ă���B
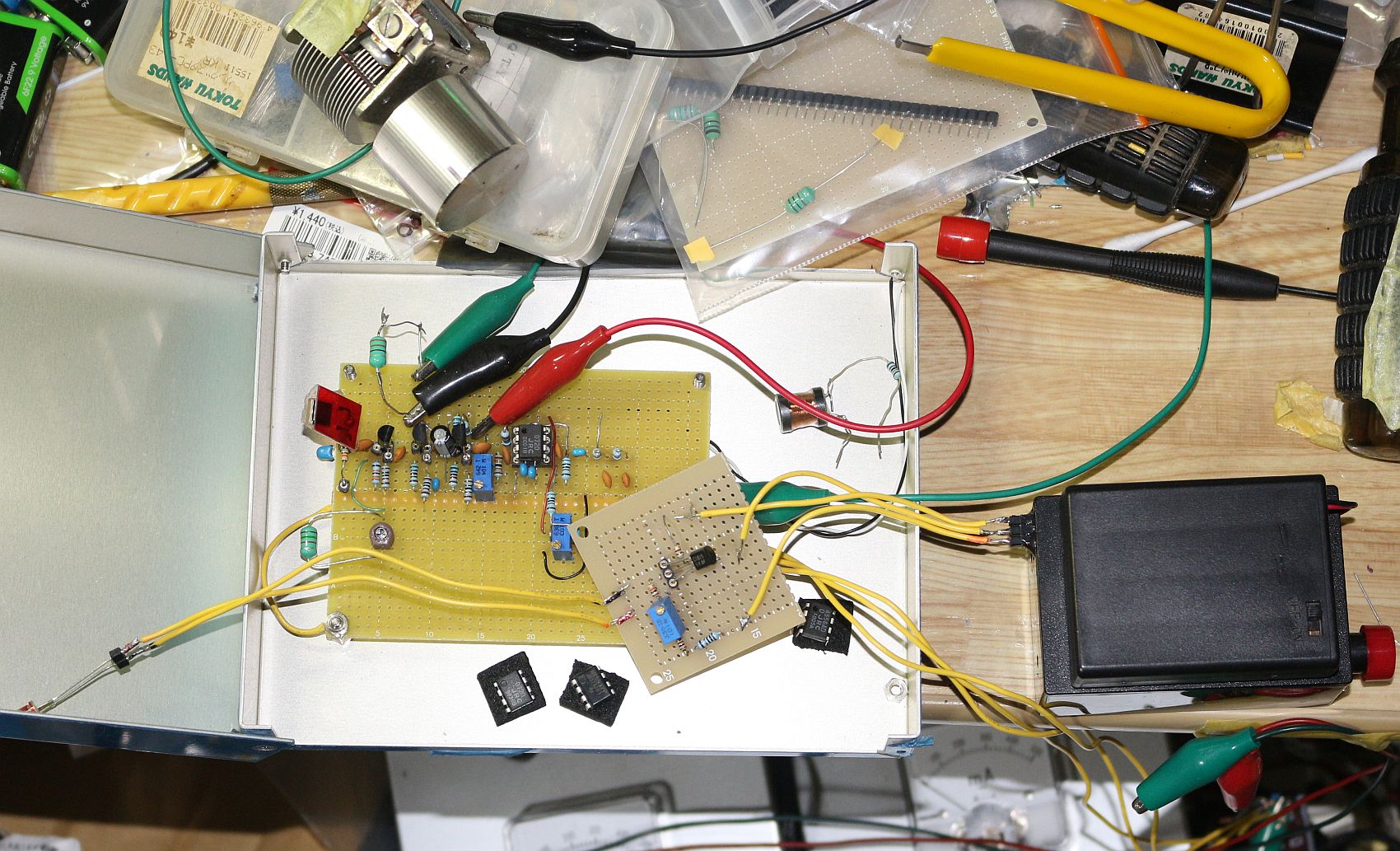 ����Di�{�������Tr�����ł����\�g�`�I�����͂���B
2�i�ڂ�Tr�̋��U�n�̉��ǂƁAOP-AMP��H�̉��ǂŁA���p�ɂȂ邩�H�ƌ����Ƃ���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�����e�̐���ɂ��ăC���C�����ς���B
220226�F����A���i�𒍕��������A�܂��͂��Ȃ��̂ŁA��������
�K�v�ȃQ�C���̌��ς�������Z���Ă݂悤�B
�ƂĂ��̂̃����R��������W���[���́A���B����10m���x�ŁAAv=80dB��ƌ������Ƃ炵���B
���̍����x�̂́A45m�Ƃ���B�������A���̊�LED�̕����i���͂��Ă�Ǝv�����ǁc�A�A
�ƂȂ�ƁA�ꉞ�A4�`5�{���炢�̋����A16�`25�{�̊��x�B+24�`30dB��悹�Ƃ��������ŁB
110dB�ʂƌ������ƂɂȂ邾�낤����A�R�����ɂ́A120dB�ʗ~�����B
����́A�t�B���^�[���g���Ă��A�����ȃ��m�ł͖����B
TTL���x��5V��-120dB�Ƃ�10E-6��1/1000000�ł��邩��A
5��V�ƂȂ邩�ȁH�����e�X�^�[�̕���\��100��V�̂����邩��A���I�ł͖����H�悤�Ɋ����邪�A�A
(�����N���X�̃e�X�^�[��mV�����W�ł�10��V�P�ʂɂȂ�B�����Ȃ�c�A�A)
�����A����͍�����H�ł��A���B
������M��H�̂悤�ɁA���i��LC�t�B���^�[��Tr���d�˂čs���N���X�^�����g���Ζ���ɃC�P�邩�������ǁc�A
�́A���菬�d�͓͂d�ꂪ100m�n�_��100��V/m�ȉ��̏ꍇ�Ɂ`�A�A�Ƃ������̂��o���Ă�̂ŁA�A�A�A
���ƁA�l�Ԃ̎��̃_�C�i�~�b�N�����W�����̃��x���B
������AGC��H��������H
������x��p�̃p�[�c�ŁA������܂���Ώo���邩�Ǝv���B
�ł��A���̈����Ă�������ȃ����R��������W���[���Ɣ�ׂĊ��ɍ���Ȃ������c�A�A
�Ƃɂ����A�m�C�Y�Ɣ��U�̖�肪��ԐF�Z���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���́AHF�H��10.7MHz�̔��U�Łc�A�Ƃ͌��킸�A�C���������ǁA�AVHF�̈�ցB�B�B
�́A�v���̂��߁A40MHz��60MHz�̔��U�A�����A�ϒ������A�������Ă����̂ŁA�ǂ��ɂ��g���Ȃ����ƍl�����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�̏��������ɌÂ����y�щ摜���o�Ă����̂ŁB�B�@�@�@(�}�͊ȈՉ������T�O�}�ł��B)
����Di�{�������Tr�����ł����\�g�`�I�����͂���B
2�i�ڂ�Tr�̋��U�n�̉��ǂƁAOP-AMP��H�̉��ǂŁA���p�ɂȂ邩�H�ƌ����Ƃ���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�����e�̐���ɂ��ăC���C�����ς���B
220226�F����A���i�𒍕��������A�܂��͂��Ȃ��̂ŁA��������
�K�v�ȃQ�C���̌��ς�������Z���Ă݂悤�B
�ƂĂ��̂̃����R��������W���[���́A���B����10m���x�ŁAAv=80dB��ƌ������Ƃ炵���B
���̍����x�̂́A45m�Ƃ���B�������A���̊�LED�̕����i���͂��Ă�Ǝv�����ǁc�A�A
�ƂȂ�ƁA�ꉞ�A4�`5�{���炢�̋����A16�`25�{�̊��x�B+24�`30dB��悹�Ƃ��������ŁB
110dB�ʂƌ������ƂɂȂ邾�낤����A�R�����ɂ́A120dB�ʗ~�����B
����́A�t�B���^�[���g���Ă��A�����ȃ��m�ł͖����B
TTL���x��5V��-120dB�Ƃ�10E-6��1/1000000�ł��邩��A
5��V�ƂȂ邩�ȁH�����e�X�^�[�̕���\��100��V�̂����邩��A���I�ł͖����H�悤�Ɋ����邪�A�A
(�����N���X�̃e�X�^�[��mV�����W�ł�10��V�P�ʂɂȂ�B�����Ȃ�c�A�A)
�����A����͍�����H�ł��A���B
������M��H�̂悤�ɁA���i��LC�t�B���^�[��Tr���d�˂čs���N���X�^�����g���Ζ���ɃC�P�邩�������ǁc�A
�́A���菬�d�͓͂d�ꂪ100m�n�_��100��V/m�ȉ��̏ꍇ�Ɂ`�A�A�Ƃ������̂��o���Ă�̂ŁA�A�A�A
���ƁA�l�Ԃ̎��̃_�C�i�~�b�N�����W�����̃��x���B
������AGC��H��������H
������x��p�̃p�[�c�ŁA������܂���Ώo���邩�Ǝv���B
�ł��A���̈����Ă�������ȃ����R��������W���[���Ɣ�ׂĊ��ɍ���Ȃ������c�A�A
�Ƃɂ����A�m�C�Y�Ɣ��U�̖�肪��ԐF�Z���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���́AHF�H��10.7MHz�̔��U�Łc�A�Ƃ͌��킸�A�C���������ǁA�AVHF�̈�ցB�B�B
�́A�v���̂��߁A40MHz��60MHz�̔��U�A�����A�ϒ������A�������Ă����̂ŁA�ǂ��ɂ��g���Ȃ����ƍl�����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�̏��������ɌÂ����y�щ摜���o�Ă����̂ŁB�B�@�@�@(�}�͊ȈՉ������T�O�}�ł��B)
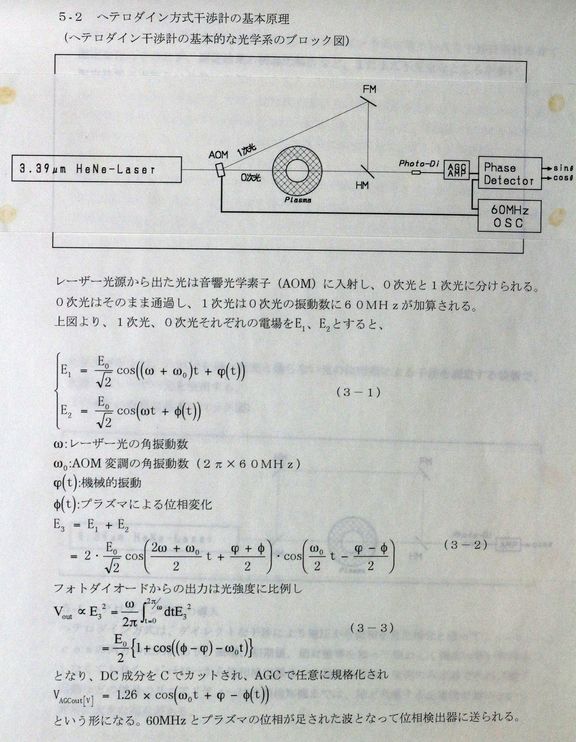 ���͋C�I�ɂ́A�A
���͋C�I�ɂ́A�A
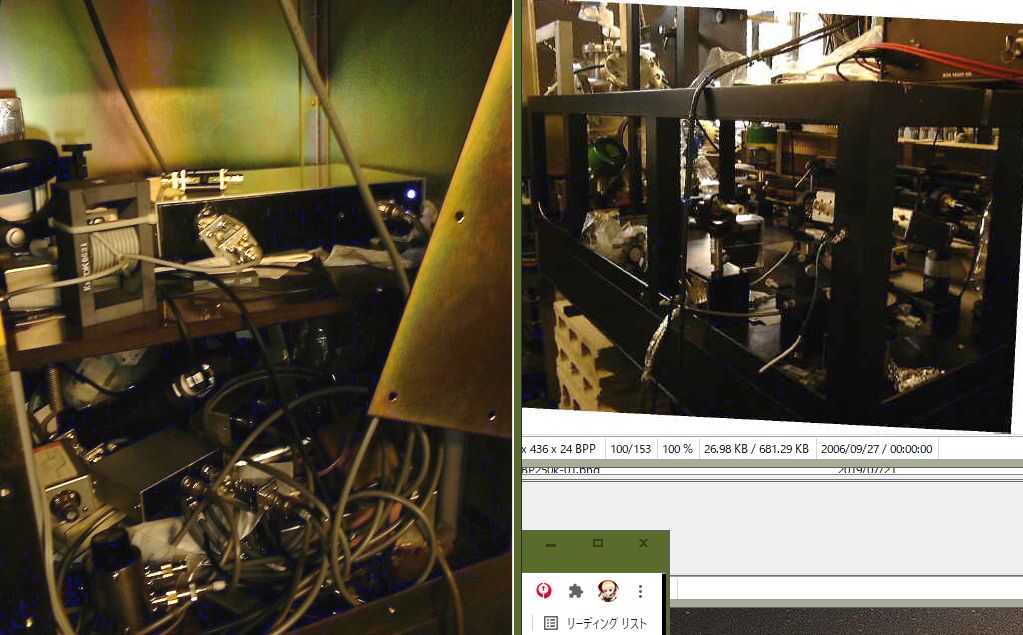 �@��̐��슮���ɂ�4�����ォ�������B
���A�l�ō��ɂ́A���ꑫ��Ȃ��\�Z�A�A
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�N���X�^���������Ă݂悤�B�B�B
�b�������e�ɖ߂��B
�����A��肭�s���̂Ȃ�ALD(���[�U�[�_�C�I�[�h)��p�ɂ��āA���g����60�`150MHz�Ɉ����グ�钧����ʔ��������B
���U���́A60MHz���̃N���b�N���W���[������ꍇ�ɂ���Ă͒��{�A�Ƃ肠�����AAPC�������W���[����ACC��H�ō����쓮�ɑΉ�����LD�쓮��OK���������A
������́A1�`2�i����(������������ƃm�C�Y�ŐU�����O�a����)����10.7MHz�̒��Ԏ��g���ɗ��Ƃ��B
���̌�455KHz�ɗ��Ƃ��āA���g���āA�V�O�i���̃f�B�e�N�^�[�ɓ����B
�Ƃ��������ɂȂ邩�ȁH
����́A������x�A�����p�r�Ȃǂ̃��W���[�����i���g�����ƂƊ�����Ă��B
VHF�ȗ̈�Ȃ̂ŁA�ɂ��Z���̈�́A��̗U�d���Ƃ��x�^GND�Ƃ��܂ŁA����Ȃ�̋C�������K�v�����ł���B
(�g�����Z���ƃX�P�[���k����������Ηǂ������A�A�A�Ƃ͍s���Ȃ��B�Ód�e�ʂȂǂ͋����قǑ傫���Ȃ邩��B)
�܂��́A�t�o�C�A�X���������t�H�gDi����M�@��RF���͂ɓ���Č��ăe�X�g�Ƃ��H
UHF�́A�}�C�N���X�g���b�v���C���Ƃ��g����悤�ɂ͂Ȃ�悤�ł����A
�t�H�gDi��LD���ʐM�p�ȂǓ���ɂȂ邵�A����͐ԊO�Ƃ��ɂȂ��Ă��܂��B��Փx�o���o���ȋC������B
�V���O�����[�h�t�@�C�o�[�p�̃��W���[�����Ƃ������������̕��i�B�o���Ȃ������A�A
�������̎��g���ɂȂ�ƁA���g�ǂ݂����ȁ`�c�A�A
120��150MHz���x���ǂ��Ǝv���Ă���ǁA���g���������̂Ń_�C���N�g�͖��������B
����āA���{�Z�p���K�v�B�܂�A���v�Ȃǂ̉ߒ��Řc�܂��č����g�����o�����ƂɂȂ�B
�ő�9���{���炢�������I���ȁH�S����ԗ�����ƂȂ��20MHz��30MHz�A50MHz�̃��W���[�����悳�����B
��܂��ȃt�B���^�[��144MHz�їp��FCZ�R�C���ɂȂ邩�Ǝv�����ǁA��������̂��ȁH
����455KHz��10.7MHz�ɂ��邽�߃~�L�T�[�Ŕ����߁{�|1MHz�̔�������RC�ł��ǂ����낤���ǁc�A
�������A�O�́A30MHz�܂Ŕ��U�o���郂�W���[�����������悤�ȁc�A
�V���~�b�g�g���K�[�C���o�[�^�[IC���ƌ��\�������U�����������ǁB
���肵�Ă���Ȃ���A10.7M�Ƃ��ŋ������邱�Ƃ��t���ʂƂȂ�B
�����ɂ��炵���N���X�^������{����̂����z�B�Ƃ����̂��A�~�L�T�[��10.7MHz�L�b�`����������������
���C�����U�̖W�Q����B���邢�́A�W�Q���Ȃ��悤�A�H�v����H
�����́A�V�[���h���ꂽ�ʋ��ŁA150�{10.7��160.7MHz�œ������Ă݂�Ƃ��A�A�A�A
(�����A150MHz�͎����d�g���g���Ȃ̂ŁA���C�y�ȃg�R������B)
������10.245MHz��������455KHz���o���āc�A�A�A
�~�L�T�[��IF�t�B���^�[�͎g���Ă݂����B
�ꕔ�Z�p�́A�ʐM�Z�p��A�i���O�V���Z�Ȋ��������B
������v���O���}�u�����g���W�F�l���[�^�[�Ƃ����̂����邯�ǁA�f�W�^���ȃ}�C�R���̕��ނɓ���B
�R�����g���͔̂Y�݃��m�ł͂���B
�ړI�̐�������ɓ���Ȃ��Ƃ��A���̑�p�i���x�H
�����@���V���Z�y����A�d�q�H��̉Ԍ`�������̂ł����A�f�W�^�����̔g�ŏ��������������B
�ł��A�V���Z�͏����c���Ă�B���Ƃ́A�^��ǃI�[�f�B�I�H
�������A�̂́A�d�q�H����������ׂ�≹�y��Ɋg������Ă����B�Ƃ����ٗl�Ȋ�������������B
�f�W�^���́A�قځA�����ɏ����鐔�w��[���l�����A�X���[�o����̂ŁA�Ȃ��\�R�������Ă�Ɩʔ����Ȃ��Ƃ����C������B
���ہA�����A�I���Ăɂ����āA�u���ʔ���v�ŋ@�\�����A�Ƃ����ƁA�e���I�t�߂ɕt�����J�����ނ���摜��͂��������ǂ��͂��B
(�܂��ɁA�f�W�J���Ō��ʂ͌��̎ˌ��ɋ߂��B�B�B)
���[�U�[�Ƃ��̃f�B�e�N�^�[�������ƁA2x2�Z���T�[�ŏ㉺���E�ǂ��炩�ɃY���Ă�Ƃ�������ɂ����o���Ȃ��B
�f�W�^���͖��\�ɋ߂��C������B���c�A�d�q��H���̂̊w��I�ȕ����������Ɗ�����B
�\�肪�ς��A���̌��w���v�̑���̌��w�f�q�̍ō����h���C�u���g���F200MH��������Ȃ̂ŁA200MHz�`500MHz���ǂ��Ǝv�����B
UHF�ԋ߂Ȏ��g���ŃA���B
���ۂ�RF�h���C�o�[��500MHz�܂ł��邵�A�f�q��350MHz�̂��m�F���Ă���A�A�A
���̎��g���́A���ԕ���\�≞�����x�ɊW����B
���x�œ`�����x���ς��̂ŁA�g�@�Ƃ��K�v�ł������B�Ό��A���w�I��������p���[�Ȃǂ̓�����K�v�������B
���Ƃ́A���ƌ����Ă��A�m�C�Y���G�B
���́ARF�p���[���W���[��IC�Ƃ��A���̂��ȁH
�����̓j�b�`�ȕ��ނ��������ǁA���͐F�X�ȂƂ�������Ă�݂����B�B
�������A���̔��U�͐��x�����܂�v��Ȃ��̂�LC���U�ł��\��Ȃ��Ƃ����B�B�B
�߂��悤�ŗ���Ă�Z�p�Ǝv���ƁA�ނ��Ă���悤�ȁH�H
�l���Ă݂��AUHF�t�߂Ŕ��U�o����LD�́A��͂�ʐM�p�ƂȂ邩���H
�{�c�����B
�܂��A430MHz�̑���M�@������455KHz�ȑ����ƍ����ĕς��Ȃ����Ƃ���Ă��H���A���݂����Ȃ̂ŁA����͉\�����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�Ȃ��A���̃u���O�́A�㏬�̂��߁AGoogle����e����Ă镔��������ABing�����𐄏��B
�܂��A������ł��A���[�J�[�i�̉����Ȃǂ͏Ȃ���Ă�g�R������B
�u���O�Љ�ɏ��������Ƃ��낾���A�ǂ��������\�R�ɏ�����̂��Y�ꂽ�B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���ꂩ��ǂ����邩�́A455KHz�̉�H����i�����Ă���A
��ʓILD�̊Ȉ�ACC��H�I�h���C�u���x���l�����āA
�h���C�u���g�����グ��郂�m�Ȃ�グ�čs�������Ǝv���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220227
���[�U�[�ō����g���U���o���邩���ς��邱�Ƃ��l��������ǁ{���A�A�A
���i�͑���������Ɂc�A�A
�܂��AFCZ�R�C�����ׂĂĕ����������ǁA�ڑ�����g�����W�X�^�̃R���N�^�e�ʂ̉e������Ə����Ă���܂����B
(�����e��:�ڑ����镉�חe��(�g�����W�X�^�̃R���N�^�e�ʓ�)���l�����Ă��g�p���������B)�ƁA�A�A
���[��A����g�p����������ATr�̃R���N�^�e�ʂ��傫�������̂ɂȂ̂��ȁH�o�C�A�X�ł��ς��Ƃ����c�A�A
�ł��A���ׂČ���ɁA2SC1845�̃Z�J���h�\�[�X�i��Cob=1.5pF�قǂ̏����ȃ��m�ł����B
����2SC945�������Ďg���悤�ɂ��悤�Ǝv�����ǁA�Z�J���h�\�[�X�i��NF���啪�Ⴄ�̂�����̂ŁA���ӂł��ˁB
���ƁA�G���ɂ������Ƃ���A���̑���������FET���g���邾�낤�ƌ������Ƃ��������Ă��܂����B�p�����^�͔����ł����c�A
����ρA�g�����X�\�����ᖳ���ƕs�����Ƃ��H�H
�܂��A�G�~�b�^�ɒ�R�͗v��Ȃ��悤�ł���B�ł�����͗]��W�Ȃ������B
���ƁAFCZ�̃Z���^�[�^�b�v�ł��狋�d���Ă�̂Ƃ����łȂ��̂����邯�ǁA�܂��A�������邩��ADC�����A���ɂ͊W�Ȃ��͂��B
�ł��A�Ƃɂ����A�R�R�̋�����肭�s���ĂȂ��͎̂����ł��ꂪ�~�\�B
�����A��Y��Ă����Ƃ��A�A
�S�d���̓d���������������B�������Ă��̖Y��Ă��B�B
��������A�o�C�A�X�������Ȃ��������c�H
���U�n�͑��ς�炸�_�������ǁA�l���͏����ς�����B
�ł���R�g�Ƃ�������g�����X�ɂ�����R�g�����ǁA�A�W����̂��ȁ[�H�H
455KHz��Ver�́A2�i�ڂ̃R�C���g�����X�̋��U��H�ƁAOP-AMP�����Ȃ̂����A
������������A3�i�ڂ����U�n����āA4�i�ڂ�����āAOP-AMP�͈�i�ɂ���A�ň�455KHz��BPF���g���R�g�ŁA�ڕW�͒B�������悤�ȋC�����Ă���B
�����A���̒i�K�́A����p�[�c���g��Ȃ����R�x�̃A����H�ł��̂��ڕW�B���̏����ł���B
�Ȃ̂ŁA�Z���~�b�N��BPF�͍ŏI��i���ȁB�g���Ƃ��Ă����̓Q�C���◧���オ�莞�Ԃ�������ƋC�ɂȂ邪�B
�����āA�s�̕i�̃����R�����W���[���������x���~�����c�A�A
�^��Ȃ̂́A�s�̕i�̓t�B���^�ɉ����g���Ă���̂��H�����āA���U���Ȃ��ł����ɑ������Ă�̂��H
���̈����ł������Ⴂ���i�̒��ɁA����قǑ��i�K�ȋ��U�Ƒ������J��Ԃ��v�f���l�ߍ��߂�Ƃ͎v���Ȃ��B������x�����Ȃ̂͗ʎY���Ă邩������邩�������A�A
�J���N���͒m���Ă��������ȁA�Ƃ͎v���B���ǁA�u���b�N�{�b�N�X�B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�f���[�e�B�[��������āA�X�g���{�̂悤�ɋ�������Z���Ԃɏo���ƁA
�f�B�e�N�^�̌�ɁA�m�C�Y�Q�[�g�݂�����臒l�̂�����̂ŁA�m�C�Y����|���邱�Ƃ͏o���Ȃ��̂��ȁH
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�ŁA�C���������A�����ƍ����g�ŁA����́u��ɖ����p�̐�p�p�[�c�v�����g�����ƂɊ�����āA
�o�����VHF�ш�ȏ�ŁA
��ɔ����̃��[�U�[�ɓ��������ɋ߂����m������Č������Ȃ����B
455MHz�ł̕��i�����Ȃ��̂ŁA�l���Ă���A���̋C�ɂȂ��Ă��������B
���g�����オ��A�芪���R�C�����Ƃ��Ă����삪���N�ł͂���B�X�ɋ�c�R�C���Ȃ�N�Z�����Ȃ��B
�ŁA�܂��́ALD(���[�U�[�_�C�I�[�h)�̎��ԉ��������ς��肽���B
�������Ă�LD�͊F�Â߂Ȃ̂����A�������[�U�[�|�C���^�[����w�f�B�X�N�h���C�u���Ɏg���Ă邿�傤�ǃN���X3B�ɓ��邩�H�Ƃ������x���ł���̂����c�A
�����A�ǂ��GaAs(GaAlAs?)�c�������U��ʔ������[�U�[�B(Vertical Cavity Surface Emitting Laser)�Ƃ����^�C�v�B
�ǂ�ɂ��A�f�[�^�V�[�g�Ɏ��ԉ��������Ɋւ��Ă͋L�q�������B�����A�Ǝ˂�������p�r�����炩���m��Ȃ��B
����́A�����Č��邵���������ȁH
�����I�Ȏ���������ɁA�h���[�v����(��P)�Ƃ����̂��A���A600Hz�̔��U�ŕω��͌��\���Ԃ�������悤�ł���B�ł��R���͔M�����̂悤���B
�x���ƂȂ�ƁA���U�̈�ɓ��ꂽ�܂܁A���̋��x��h���Ԃ�Ƃ����̂��o����Ηǂ����c�A�_���Ȃ�s�G�]�Ń~���[��h���Ԃ�Ƃ����ד��I�ɂ��v�����i���K�v�����B
�ŁA
���傤�������B�������Ă݂�B
����炵��DATA�͏��Ȃ����c�A
tr�Atf�́A�����A���C�W���O�^�C���A�t�H�[���^�C���B
�܂��A50nSec���x���̃��m�͌������B�܂��A1����100nSec���Ƃ��āA10MHz�ʂ��ȁH
�ϒ����������A���Ȃ�݂邾�낤���NJ��S�ɏ��������Ȃ����Ƃ��l���Ă��A����Ȃɍs���Ȃ��n�Y�B
�R���Ȋ����B
�I�[�o�[�V���[�g�̔g�`���������A20MHz�œ����������Ȃ̂̓A���B
�@��̐��슮���ɂ�4�����ォ�������B
���A�l�ō��ɂ́A���ꑫ��Ȃ��\�Z�A�A
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�N���X�^���������Ă݂悤�B�B�B
�b�������e�ɖ߂��B
�����A��肭�s���̂Ȃ�ALD(���[�U�[�_�C�I�[�h)��p�ɂ��āA���g����60�`150MHz�Ɉ����グ�钧����ʔ��������B
���U���́A60MHz���̃N���b�N���W���[������ꍇ�ɂ���Ă͒��{�A�Ƃ肠�����AAPC�������W���[����ACC��H�ō����쓮�ɑΉ�����LD�쓮��OK���������A
������́A1�`2�i����(������������ƃm�C�Y�ŐU�����O�a����)����10.7MHz�̒��Ԏ��g���ɗ��Ƃ��B
���̌�455KHz�ɗ��Ƃ��āA���g���āA�V�O�i���̃f�B�e�N�^�[�ɓ����B
�Ƃ��������ɂȂ邩�ȁH
����́A������x�A�����p�r�Ȃǂ̃��W���[�����i���g�����ƂƊ�����Ă��B
VHF�ȗ̈�Ȃ̂ŁA�ɂ��Z���̈�́A��̗U�d���Ƃ��x�^GND�Ƃ��܂ŁA����Ȃ�̋C�������K�v�����ł���B
(�g�����Z���ƃX�P�[���k����������Ηǂ������A�A�A�Ƃ͍s���Ȃ��B�Ód�e�ʂȂǂ͋����قǑ傫���Ȃ邩��B)
�܂��́A�t�o�C�A�X���������t�H�gDi����M�@��RF���͂ɓ���Č��ăe�X�g�Ƃ��H
UHF�́A�}�C�N���X�g���b�v���C���Ƃ��g����悤�ɂ͂Ȃ�悤�ł����A
�t�H�gDi��LD���ʐM�p�ȂǓ���ɂȂ邵�A����͐ԊO�Ƃ��ɂȂ��Ă��܂��B��Փx�o���o���ȋC������B
�V���O�����[�h�t�@�C�o�[�p�̃��W���[�����Ƃ������������̕��i�B�o���Ȃ������A�A
�������̎��g���ɂȂ�ƁA���g�ǂ݂����ȁ`�c�A�A
120��150MHz���x���ǂ��Ǝv���Ă���ǁA���g���������̂Ń_�C���N�g�͖��������B
����āA���{�Z�p���K�v�B�܂�A���v�Ȃǂ̉ߒ��Řc�܂��č����g�����o�����ƂɂȂ�B
�ő�9���{���炢�������I���ȁH�S����ԗ�����ƂȂ��20MHz��30MHz�A50MHz�̃��W���[�����悳�����B
��܂��ȃt�B���^�[��144MHz�їp��FCZ�R�C���ɂȂ邩�Ǝv�����ǁA��������̂��ȁH
����455KHz��10.7MHz�ɂ��邽�߃~�L�T�[�Ŕ����߁{�|1MHz�̔�������RC�ł��ǂ����낤���ǁc�A
�������A�O�́A30MHz�܂Ŕ��U�o���郂�W���[�����������悤�ȁc�A
�V���~�b�g�g���K�[�C���o�[�^�[IC���ƌ��\�������U�����������ǁB
���肵�Ă���Ȃ���A10.7M�Ƃ��ŋ������邱�Ƃ��t���ʂƂȂ�B
�����ɂ��炵���N���X�^������{����̂����z�B�Ƃ����̂��A�~�L�T�[��10.7MHz�L�b�`����������������
���C�����U�̖W�Q����B���邢�́A�W�Q���Ȃ��悤�A�H�v����H
�����́A�V�[���h���ꂽ�ʋ��ŁA150�{10.7��160.7MHz�œ������Ă݂�Ƃ��A�A�A�A
(�����A150MHz�͎����d�g���g���Ȃ̂ŁA���C�y�ȃg�R������B)
������10.245MHz��������455KHz���o���āc�A�A�A
�~�L�T�[��IF�t�B���^�[�͎g���Ă݂����B
�ꕔ�Z�p�́A�ʐM�Z�p��A�i���O�V���Z�Ȋ��������B
������v���O���}�u�����g���W�F�l���[�^�[�Ƃ����̂����邯�ǁA�f�W�^���ȃ}�C�R���̕��ނɓ���B
�R�����g���͔̂Y�݃��m�ł͂���B
�ړI�̐�������ɓ���Ȃ��Ƃ��A���̑�p�i���x�H
�����@���V���Z�y����A�d�q�H��̉Ԍ`�������̂ł����A�f�W�^�����̔g�ŏ��������������B
�ł��A�V���Z�͏����c���Ă�B���Ƃ́A�^��ǃI�[�f�B�I�H
�������A�̂́A�d�q�H����������ׂ�≹�y��Ɋg������Ă����B�Ƃ����ٗl�Ȋ�������������B
�f�W�^���́A�قځA�����ɏ����鐔�w��[���l�����A�X���[�o����̂ŁA�Ȃ��\�R�������Ă�Ɩʔ����Ȃ��Ƃ����C������B
���ہA�����A�I���Ăɂ����āA�u���ʔ���v�ŋ@�\�����A�Ƃ����ƁA�e���I�t�߂ɕt�����J�����ނ���摜��͂��������ǂ��͂��B
(�܂��ɁA�f�W�J���Ō��ʂ͌��̎ˌ��ɋ߂��B�B�B)
���[�U�[�Ƃ��̃f�B�e�N�^�[�������ƁA2x2�Z���T�[�ŏ㉺���E�ǂ��炩�ɃY���Ă�Ƃ�������ɂ����o���Ȃ��B
�f�W�^���͖��\�ɋ߂��C������B���c�A�d�q��H���̂̊w��I�ȕ����������Ɗ�����B
�\�肪�ς��A���̌��w���v�̑���̌��w�f�q�̍ō����h���C�u���g���F200MH��������Ȃ̂ŁA200MHz�`500MHz���ǂ��Ǝv�����B
UHF�ԋ߂Ȏ��g���ŃA���B
���ۂ�RF�h���C�o�[��500MHz�܂ł��邵�A�f�q��350MHz�̂��m�F���Ă���A�A�A
���̎��g���́A���ԕ���\�≞�����x�ɊW����B
���x�œ`�����x���ς��̂ŁA�g�@�Ƃ��K�v�ł������B�Ό��A���w�I��������p���[�Ȃǂ̓�����K�v�������B
���Ƃ́A���ƌ����Ă��A�m�C�Y���G�B
���́ARF�p���[���W���[��IC�Ƃ��A���̂��ȁH
�����̓j�b�`�ȕ��ނ��������ǁA���͐F�X�ȂƂ�������Ă�݂����B�B
�������A���̔��U�͐��x�����܂�v��Ȃ��̂�LC���U�ł��\��Ȃ��Ƃ����B�B�B
�߂��悤�ŗ���Ă�Z�p�Ǝv���ƁA�ނ��Ă���悤�ȁH�H
�l���Ă݂��AUHF�t�߂Ŕ��U�o����LD�́A��͂�ʐM�p�ƂȂ邩���H
�{�c�����B
�܂��A430MHz�̑���M�@������455KHz�ȑ����ƍ����ĕς��Ȃ����Ƃ���Ă��H���A���݂����Ȃ̂ŁA����͉\�����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�Ȃ��A���̃u���O�́A�㏬�̂��߁AGoogle����e����Ă镔��������ABing�����𐄏��B
�܂��A������ł��A���[�J�[�i�̉����Ȃǂ͏Ȃ���Ă�g�R������B
�u���O�Љ�ɏ��������Ƃ��낾���A�ǂ��������\�R�ɏ�����̂��Y�ꂽ�B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���ꂩ��ǂ����邩�́A455KHz�̉�H����i�����Ă���A
��ʓILD�̊Ȉ�ACC��H�I�h���C�u���x���l�����āA
�h���C�u���g�����グ��郂�m�Ȃ�グ�čs�������Ǝv���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220227
���[�U�[�ō����g���U���o���邩���ς��邱�Ƃ��l��������ǁ{���A�A�A
���i�͑���������Ɂc�A�A
�܂��AFCZ�R�C�����ׂĂĕ����������ǁA�ڑ�����g�����W�X�^�̃R���N�^�e�ʂ̉e������Ə����Ă���܂����B
(�����e��:�ڑ����镉�חe��(�g�����W�X�^�̃R���N�^�e�ʓ�)���l�����Ă��g�p���������B)�ƁA�A�A
���[��A����g�p����������ATr�̃R���N�^�e�ʂ��傫�������̂ɂȂ̂��ȁH�o�C�A�X�ł��ς��Ƃ����c�A�A
�ł��A���ׂČ���ɁA2SC1845�̃Z�J���h�\�[�X�i��Cob=1.5pF�قǂ̏����ȃ��m�ł����B
����2SC945�������Ďg���悤�ɂ��悤�Ǝv�����ǁA�Z�J���h�\�[�X�i��NF���啪�Ⴄ�̂�����̂ŁA���ӂł��ˁB
���ƁA�G���ɂ������Ƃ���A���̑���������FET���g���邾�낤�ƌ������Ƃ��������Ă��܂����B�p�����^�͔����ł����c�A
����ρA�g�����X�\�����ᖳ���ƕs�����Ƃ��H�H
�܂��A�G�~�b�^�ɒ�R�͗v��Ȃ��悤�ł���B�ł�����͗]��W�Ȃ������B
���ƁAFCZ�̃Z���^�[�^�b�v�ł��狋�d���Ă�̂Ƃ����łȂ��̂����邯�ǁA�܂��A�������邩��ADC�����A���ɂ͊W�Ȃ��͂��B
�ł��A�Ƃɂ����A�R�R�̋�����肭�s���ĂȂ��͎̂����ł��ꂪ�~�\�B
�����A��Y��Ă����Ƃ��A�A
�S�d���̓d���������������B�������Ă��̖Y��Ă��B�B
��������A�o�C�A�X�������Ȃ��������c�H
���U�n�͑��ς�炸�_�������ǁA�l���͏����ς�����B
�ł���R�g�Ƃ�������g�����X�ɂ�����R�g�����ǁA�A�W����̂��ȁ[�H�H
455KHz��Ver�́A2�i�ڂ̃R�C���g�����X�̋��U��H�ƁAOP-AMP�����Ȃ̂����A
������������A3�i�ڂ����U�n����āA4�i�ڂ�����āAOP-AMP�͈�i�ɂ���A�ň�455KHz��BPF���g���R�g�ŁA�ڕW�͒B�������悤�ȋC�����Ă���B
�����A���̒i�K�́A����p�[�c���g��Ȃ����R�x�̃A����H�ł��̂��ڕW�B���̏����ł���B
�Ȃ̂ŁA�Z���~�b�N��BPF�͍ŏI��i���ȁB�g���Ƃ��Ă����̓Q�C���◧���オ�莞�Ԃ�������ƋC�ɂȂ邪�B
�����āA�s�̕i�̃����R�����W���[���������x���~�����c�A�A
�^��Ȃ̂́A�s�̕i�̓t�B���^�ɉ����g���Ă���̂��H�����āA���U���Ȃ��ł����ɑ������Ă�̂��H
���̈����ł������Ⴂ���i�̒��ɁA����قǑ��i�K�ȋ��U�Ƒ������J��Ԃ��v�f���l�ߍ��߂�Ƃ͎v���Ȃ��B������x�����Ȃ̂͗ʎY���Ă邩������邩�������A�A
�J���N���͒m���Ă��������ȁA�Ƃ͎v���B���ǁA�u���b�N�{�b�N�X�B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�f���[�e�B�[��������āA�X�g���{�̂悤�ɋ�������Z���Ԃɏo���ƁA
�f�B�e�N�^�̌�ɁA�m�C�Y�Q�[�g�݂�����臒l�̂�����̂ŁA�m�C�Y����|���邱�Ƃ͏o���Ȃ��̂��ȁH
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�ŁA�C���������A�����ƍ����g�ŁA����́u��ɖ����p�̐�p�p�[�c�v�����g�����ƂɊ�����āA
�o�����VHF�ш�ȏ�ŁA
��ɔ����̃��[�U�[�ɓ��������ɋ߂����m������Č������Ȃ����B
455MHz�ł̕��i�����Ȃ��̂ŁA�l���Ă���A���̋C�ɂȂ��Ă��������B
���g�����オ��A�芪���R�C�����Ƃ��Ă����삪���N�ł͂���B�X�ɋ�c�R�C���Ȃ�N�Z�����Ȃ��B
�ŁA�܂��́ALD(���[�U�[�_�C�I�[�h)�̎��ԉ��������ς��肽���B
�������Ă�LD�͊F�Â߂Ȃ̂����A�������[�U�[�|�C���^�[����w�f�B�X�N�h���C�u���Ɏg���Ă邿�傤�ǃN���X3B�ɓ��邩�H�Ƃ������x���ł���̂����c�A
�����A�ǂ��GaAs(GaAlAs?)�c�������U��ʔ������[�U�[�B(Vertical Cavity Surface Emitting Laser)�Ƃ����^�C�v�B
�ǂ�ɂ��A�f�[�^�V�[�g�Ɏ��ԉ��������Ɋւ��Ă͋L�q�������B�����A�Ǝ˂�������p�r�����炩���m��Ȃ��B
����́A�����Č��邵���������ȁH
�����I�Ȏ���������ɁA�h���[�v����(��P)�Ƃ����̂��A���A600Hz�̔��U�ŕω��͌��\���Ԃ�������悤�ł���B�ł��R���͔M�����̂悤���B
�x���ƂȂ�ƁA���U�̈�ɓ��ꂽ�܂܁A���̋��x��h���Ԃ�Ƃ����̂��o����Ηǂ����c�A�_���Ȃ�s�G�]�Ń~���[��h���Ԃ�Ƃ����ד��I�ɂ��v�����i���K�v�����B
�ŁA
���傤�������B�������Ă݂�B
����炵��DATA�͏��Ȃ����c�A
tr�Atf�́A�����A���C�W���O�^�C���A�t�H�[���^�C���B
�܂��A50nSec���x���̃��m�͌������B�܂��A1����100nSec���Ƃ��āA10MHz�ʂ��ȁH
�ϒ����������A���Ȃ�݂邾�낤���NJ��S�ɏ��������Ȃ����Ƃ��l���Ă��A����Ȃɍs���Ȃ��n�Y�B
�R���Ȋ����B
�I�[�o�[�V���[�g�̔g�`���������A20MHz�œ����������Ȃ̂̓A���B
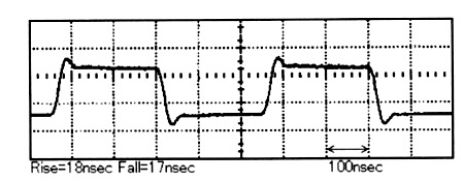 �܂��A���C�Y�ƃZ�g�����O�^�C����35nSec�Ƃ���ƁA���̓�{��ł���ρA20MHz���ȁH
�ϒ����������]���ɂ��āA30MHz�C�P����ǂ������B
(�u�t�@�C�o�o�̓i�m�b�p���XLD�v�Ƃ����̂ŁAtr=5nSec�A�J��Ԃ�����30MHz�쓮�炵���B�h���C�o�[��50MHz�쓮�܂ŏo����悤�ɏo���Ă�炵�����ǁA����ł��ĊO�x���B)
���̂ɒx���̂��͋C�ɂȂ�Ƃ���ł͂���BPN�ڍ��ʂȂ̂��A��N�ɂ�����Ƃ��H�H
���d�͂�LD�͂ƂĂ��_�o���ŐÓd�C�ɂ��ɂ߂Ďア���A���x�œ��������\�������ς��̂ŁA�I�[�o�[�ȓ��������Έ�u�ŋ��ʂ�����B
���������ł́A�d���p���X����u���������B����āA��d���ɂ���̂����A�p���X�Ȃ̂ŁA���x�Ǘ��͔�r�I���N�B�����ł́A�W�����x�������ŊǗ��o���邵�B
(APC��H�͂��̒ᑬ�Ԃ�Ɉނ������āc�A�A����Ӗ�APC���胂�W���[���̊����i�̉����ł��ǂ������B���M����Y���t���Ă邾�낤���A����Ŕg�`��`���̂ł͖����Ƃ������������H)
�ƂȂ�ƁA�s�{�ӂ����A10.7MHz�쓮�������I�Ɏv���B���߂Ȃ̂���h���C�u�����ď�肭�s����20�`30MHz�A�A�A
���t�@�C�o�[�̃l�b�g�����Gbps�Ƃ������ĂȂ����������H�H���̓��Ȃ͔̂[�������Ȃ����A�A�A���͓�l��ᖳ���̂����H
�����[���A�܂�Ȃ����m��m���Ă��܂����`�B�c�ƁA�ނ����݂����A
10.7MHz���g�������Ȃ͕̂s�K���̘N��B
�ϒ�������߂ł��A���[�U�[�Ȃ�A��������Ɍ��܂ō����x�ɂ�������K�v�����������B
�����ŁA�e�X�g��ACC��H�Ƃ������ǁA����͊�{�I�ɖ����ɂ���\��B3.3V�Ƃ�5V���͂ɒ�R��t���āA�d���𐧌�����̂݁B�d�����肾�����獂�߂̓d����v���B���ATTL���x���Ŗ���ƁB
LD�̓|�C���^�[�ňꎞ���Љ���ɂȂ������A�������̈����Ȃ̂́A���A���J���{�^���d�r4�ɒ�R�����������B���M�����������ł͂��邪�����Y�t�����W���[���ƂȂ��Ă����B
����ł��I�[�o�[�h���C�u�ȃ��x���œ����Ă������A�v�������͂��ԂƂ����Ǝv����B�܂�A�K�i�\�͂��Ȃ�]�T�������ăV�r�A�ɏ����Ă�g�R������̂��낤�B
�Â��̂ŁALD�̕i�Ԃ��A�s���ɐ��K�i�����J���Ȃ̂������A�T��̂ɗǂ����@��͍����B
�܂��́A�Ód�C�h�~�X�|���W�ɑ}�����܂܁A���ĂāAPD�̃s����T��B����CAN�����͋��ʁB�B
���́A�t�d��Vr�����d�����Ⴂ�̂������̂ŁA�t�d���̑ψ������̓d����������(1.9V�ʁH)�ALED�̈�Ō������̂��m�F���銴���H
�ԊO�������烏�J�������A1.5V�œ����e�X�^�[��Di�ɐ����o���[�h�͂ǂ����낤���H�H�H�����ȍ����o��c�A�A
����ɂ��Ă��A�t�ɂ͗��ꖳ����ɓd���ϐ����Ⴂ�̂́A�������v���ӂ��B���̂ɋK�i������Ȃɗ������Ă�̂��B�B�B
����͂����ƁA
�u�T�����ԊO�k�d�c�@�k�P�Q�P�V�O�@���o�́E���������F40MH���v�Ƃ����̂��������B
2200mW/sr�̒����o�͐ԊOLED�ŁA�ő勉�Ƀn�C�p���[�Ƃ̂��ƁB�B
�������A(IFP�F3A�A�p���X��10��S�A�f���[�e�B�[��1%)
�s�[�N�����g���F870nm�Ŕ����m�F�͗]�T�Ō����邾�낤�B
LED�̕��������Ƃ́A�A�Y�ނ��ǁB�B
�ŁA���Ȃ�A�����C�����āA�����d�g���g���I�ɂ��u30MHz�쓮�v�ł�肽���A
�ϒ����́A1/3�ȉ��ɂȂ邩�������ǁA�A���[�U�[�Ȃ�C�P��͂����Ǝv�����ALED�Ȃ�ǂ������B
�~�L�T�[�ŁAIF=10.7MHz�ɗ��Ƃ��A���̌�A455KHz�ɗ��Ƃ��Ƃ����V��������Ă݂邩�ȁH
���̎��g�����ƁA������2SC945�Ȃ�Ďg�������B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�t���[�ȃv���Z�X���l����B
���U���́A
�E30MHz�̓N���b�N���W���[��(PLL�ȃN���X�^���I�V���[�^�[���W���[��)��OK�H
�E�����́A���U��10mSec�Ƃ�������݂����Ȃ̂ŁA���U�������ςȂ��ɂ��āA555�̃����V���b�g�g���K�[��10��Sec���x��LD/LED�쓮��Tr�̓d���FVc������ON�ɂ�����B
(�C�ɂȂ�͎̂�M���̃Z���~�b�N��455KHz��BPF�̋��̗����オ�葬�x�ŃA���B��N�̐U��5��قǂŏ��Ȃ��B�_���Ȃ�ARC��455KHz�̃t�B���^�g�����X��p����܂ł����ǁA�A�A)
����ȊO�A��������Ƃ���͖����������B
�ŁA
��M����
�E30MHz����FCZ�g�����X�������M�i�K�œK�x�ɑ����B1�`2�i���x�H
�E30MHz��10.7MHz�ɗ��Ƃ��悤��19.3MHz��40.7MHz�̐����͖����B����āA�߂��̂�555�ŃV�t�g�������B�߂��̂�19.2MHz������19.6608MHz�̃��m���A���B
�@(19.2MHz�̓��W���[�ł͖������A�������Ⴂ���A���g�����߂����āA�{�|�̃V�t�g������IF��ʉ߂����˂Ȃ��H�B555�͋�`�g���������Ԋu�ŃX�y�N�g��������ł邱�ƂɂȂ�B�B
�@19.6608MHz�͗ǂ������B�������A�����x�R���f���T�[�A�Œ��R�Ƒ���]�g���}�[��v�����銴���B)
�EFCZ�R�C���Ƃ�LC���U�ł�����x�ш��I�тȂ��瑝���B
�E10.7MHz��IF��BPF�́A���\���������ɁA���S���g���ɂ��덷��������Ƃ���B
�@(�Ƃ����̂��A�ш敝�̑傫��WFM�Ƃ������蓾�邵�ADBM�ŃV�t�g�����]�v�ȃ��m��������肷��̂ƁA���͂̃X�y�N�g�������G�c�ɏ����̗p�r�Ȃ̂�����A
�@������O���Č����Γ�����O���H)
�E10.245MHz�̐����͊y�V�ň����������B
�E455KHz��IF��BPF�͌��\�V�r�A�ȑш�B�������s���I���̖{�ԁB
���ƁA�p�[�c�Ƃ��āA
������ł���A���g�������Z�V�t�g�p��DBM(�_�u���o�����X�h�~�L�T)��IC�́ASOP�̂�ϊ���Ńs���o���������m���A���̂ł��ꂪ�ǂ����ȁH
SOP-8����DIP-8�ɂ܂Ƃ߂�ϊ����ʍw�����āA�����őg�ݗ��āc�A�̓����h�C�B
DBM���������Ă��ATr�����`�ɏ�肭�M��ƁA���g���̉����Z(����)�͏o����炵���悤�����A���́A�L�����A�̘R�ꂩ�ȁH
�Ƃ������A�E�`�Ɍ������Ɏg�����Ƃ��čw�������]���R&K�̍����ȃp�b�V�uDBM����R����̂ŁA
���̓Q�C���ɋC���g���K�v�������邪�A���m�ɂ���ẮA������l���A�A
�p�b�V�u��DBM�Ƃ����ƁA�t�F���C�g�r�[�Y�̃g�����X��Di�Ńu���b�W������Ď��삷��Ƃ�����i���������B
������M�I�ȗp�r�Ƃ��Ă��A
�Z�N�V�����Ƃ������u���b�N�ɕ����A
IF��2��ʉ߈ȍ~�A���g�A�����A�Ƃ��A���ɗ��p�o����悤�ɏo������C�C�����B
�����R�����W���[����38KHz����455KHz��12�{�ł����āA455KHz����30MHz��66�{�ł���B�v800�{�̎��g�������ƂȂ�B
�����A455KHz����30MHz�ɏグ�Ă��A��IF��455KHz�Ȃ̂ŁA�Z���ԃp���X���ɂ͍v���x���Ⴍ�Ȃ�Ǝv���B
�����ǁA�p���X�̒Z�k��3�{���x�͂���Ȃ�ɉ\���Ƃ͎v���Ă���B
30MHz�̗��_�͉����낤�H
��H�������@�Ƃ��Ďd�オ���Ă銴���c�Ƃ��������H�H
���ԂƋ��Ƃ�����A���������̉�H��PD�����APC��H�ɂ���̂��c�A
(�ő�ɑË�����AAPC����ŗh���Ԃ�̂ł͖������āAAPC��H�ɂƂ��Ēǂ����Ȃ����x�Ɨʂŏ�悹���銴���H)
LD�̋��e���b�e�[�W���傫����A���t�@�����X�ɂ��R���g���[���ȂǕK�v�Ƃ����ɁAACC�ň��肵�Ĕ��U�o����Ƃ͎v���B
�d�����߂�́A��R���ᖳ�����āA��d��Di���Ƃǂ����ȁHLD���h���C�u���邾���Ȃ�ǂ����ǁA���W�����[�V�������o���Ȃ��c���A�A
�W�Ȃ����ǖ�����28MHz�т��āAVHF�ɓ���̂��ȁHE�X�|���o���DX�\�Ƃ������Ă���B
E�X�|�Ƃ́A���z�ɂ��d���w�B�܂葾�z�ŗ�N����d�q���d�������C��(�v���Y�})�̑w���Ǝv����B
�d�����Ă���̂ŋ����Ɠ��������R�d�q������킯�ŁA�d�g�˂�����ʂ��o��Ǝv����B
�����Œ��ׂČ����BVHF��30MHz�`�Ȃ̂ŁA28MHz��HF�����A��낤�Ƃ��Ă�����e�̓W���X�gVHF�̎n�܂�Ɉ���������Ƃ���ł���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�����e�̍����g�ʐM���̃C���C���c�A�A
220228
���ɓ������Ėʓ|�Ȃ��ƁB
FCZ�R�C���̊�ւ̐ڑ��B(���ꂪ��Ԃ̖��A�����ɂ�������Ƒ����������肷��B)
LD�̔g���Ƌɐ��̒T��B(�K�i�̓��ꂷ�邩�A�������L�����ė~�����g�R�����A������݂Ă��m�F�o���邩���B)
�����̃g�����W�X�^�ɂ��R���s�b�c���U��H�̋쓮�B(�p�����^�ݒ�B)
�����̂̋쓮�d���̈Ⴂ��x�������B
���[�U�[�͈���̂���6V�d�������d���ɂ��悤�Ǝv�����B
30MHz�쓮�́A��͂�V�r�A�ɂ͎v���B
���U��m�C�Y��}���Ȃ��獂���x�ɂ͂������B
����ȃ��j�o�[�T����ł́A�x�^GND������V�[���h������͍���Ȃ̂ŁA
�����P�[�X�������Ȃ����B�B
�ꉞ�A��������āB
�܂��A���C�Y�ƃZ�g�����O�^�C����35nSec�Ƃ���ƁA���̓�{��ł���ρA20MHz���ȁH
�ϒ����������]���ɂ��āA30MHz�C�P����ǂ������B
(�u�t�@�C�o�o�̓i�m�b�p���XLD�v�Ƃ����̂ŁAtr=5nSec�A�J��Ԃ�����30MHz�쓮�炵���B�h���C�o�[��50MHz�쓮�܂ŏo����悤�ɏo���Ă�炵�����ǁA����ł��ĊO�x���B)
���̂ɒx���̂��͋C�ɂȂ�Ƃ���ł͂���BPN�ڍ��ʂȂ̂��A��N�ɂ�����Ƃ��H�H
���d�͂�LD�͂ƂĂ��_�o���ŐÓd�C�ɂ��ɂ߂Ďア���A���x�œ��������\�������ς��̂ŁA�I�[�o�[�ȓ��������Έ�u�ŋ��ʂ�����B
���������ł́A�d���p���X����u���������B����āA��d���ɂ���̂����A�p���X�Ȃ̂ŁA���x�Ǘ��͔�r�I���N�B�����ł́A�W�����x�������ŊǗ��o���邵�B
(APC��H�͂��̒ᑬ�Ԃ�Ɉނ������āc�A�A����Ӗ�APC���胂�W���[���̊����i�̉����ł��ǂ������B���M����Y���t���Ă邾�낤���A����Ŕg�`��`���̂ł͖����Ƃ������������H)
�ƂȂ�ƁA�s�{�ӂ����A10.7MHz�쓮�������I�Ɏv���B���߂Ȃ̂���h���C�u�����ď�肭�s����20�`30MHz�A�A�A
���t�@�C�o�[�̃l�b�g�����Gbps�Ƃ������ĂȂ����������H�H���̓��Ȃ͔̂[�������Ȃ����A�A�A���͓�l��ᖳ���̂����H
�����[���A�܂�Ȃ����m��m���Ă��܂����`�B�c�ƁA�ނ����݂����A
10.7MHz���g�������Ȃ͕̂s�K���̘N��B
�ϒ�������߂ł��A���[�U�[�Ȃ�A��������Ɍ��܂ō����x�ɂ�������K�v�����������B
�����ŁA�e�X�g��ACC��H�Ƃ������ǁA����͊�{�I�ɖ����ɂ���\��B3.3V�Ƃ�5V���͂ɒ�R��t���āA�d���𐧌�����̂݁B�d�����肾�����獂�߂̓d����v���B���ATTL���x���Ŗ���ƁB
LD�̓|�C���^�[�ňꎞ���Љ���ɂȂ������A�������̈����Ȃ̂́A���A���J���{�^���d�r4�ɒ�R�����������B���M�����������ł͂��邪�����Y�t�����W���[���ƂȂ��Ă����B
����ł��I�[�o�[�h���C�u�ȃ��x���œ����Ă������A�v�������͂��ԂƂ����Ǝv����B�܂�A�K�i�\�͂��Ȃ�]�T�������ăV�r�A�ɏ����Ă�g�R������̂��낤�B
�Â��̂ŁALD�̕i�Ԃ��A�s���ɐ��K�i�����J���Ȃ̂������A�T��̂ɗǂ����@��͍����B
�܂��́A�Ód�C�h�~�X�|���W�ɑ}�����܂܁A���ĂāAPD�̃s����T��B����CAN�����͋��ʁB�B
���́A�t�d��Vr�����d�����Ⴂ�̂������̂ŁA�t�d���̑ψ������̓d����������(1.9V�ʁH)�ALED�̈�Ō������̂��m�F���銴���H
�ԊO�������烏�J�������A1.5V�œ����e�X�^�[��Di�ɐ����o���[�h�͂ǂ����낤���H�H�H�����ȍ����o��c�A�A
����ɂ��Ă��A�t�ɂ͗��ꖳ����ɓd���ϐ����Ⴂ�̂́A�������v���ӂ��B���̂ɋK�i������Ȃɗ������Ă�̂��B�B�B
����͂����ƁA
�u�T�����ԊO�k�d�c�@�k�P�Q�P�V�O�@���o�́E���������F40MH���v�Ƃ����̂��������B
2200mW/sr�̒����o�͐ԊOLED�ŁA�ő勉�Ƀn�C�p���[�Ƃ̂��ƁB�B
�������A(IFP�F3A�A�p���X��10��S�A�f���[�e�B�[��1%)
�s�[�N�����g���F870nm�Ŕ����m�F�͗]�T�Ō����邾�낤�B
LED�̕��������Ƃ́A�A�Y�ނ��ǁB�B
�ŁA���Ȃ�A�����C�����āA�����d�g���g���I�ɂ��u30MHz�쓮�v�ł�肽���A
�ϒ����́A1/3�ȉ��ɂȂ邩�������ǁA�A���[�U�[�Ȃ�C�P��͂����Ǝv�����ALED�Ȃ�ǂ������B
�~�L�T�[�ŁAIF=10.7MHz�ɗ��Ƃ��A���̌�A455KHz�ɗ��Ƃ��Ƃ����V��������Ă݂邩�ȁH
���̎��g�����ƁA������2SC945�Ȃ�Ďg�������B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�t���[�ȃv���Z�X���l����B
���U���́A
�E30MHz�̓N���b�N���W���[��(PLL�ȃN���X�^���I�V���[�^�[���W���[��)��OK�H
�E�����́A���U��10mSec�Ƃ�������݂����Ȃ̂ŁA���U�������ςȂ��ɂ��āA555�̃����V���b�g�g���K�[��10��Sec���x��LD/LED�쓮��Tr�̓d���FVc������ON�ɂ�����B
(�C�ɂȂ�͎̂�M���̃Z���~�b�N��455KHz��BPF�̋��̗����オ�葬�x�ŃA���B��N�̐U��5��قǂŏ��Ȃ��B�_���Ȃ�ARC��455KHz�̃t�B���^�g�����X��p����܂ł����ǁA�A�A)
����ȊO�A��������Ƃ���͖����������B
�ŁA
��M����
�E30MHz����FCZ�g�����X�������M�i�K�œK�x�ɑ����B1�`2�i���x�H
�E30MHz��10.7MHz�ɗ��Ƃ��悤��19.3MHz��40.7MHz�̐����͖����B����āA�߂��̂�555�ŃV�t�g�������B�߂��̂�19.2MHz������19.6608MHz�̃��m���A���B
�@(19.2MHz�̓��W���[�ł͖������A�������Ⴂ���A���g�����߂����āA�{�|�̃V�t�g������IF��ʉ߂����˂Ȃ��H�B555�͋�`�g���������Ԋu�ŃX�y�N�g��������ł邱�ƂɂȂ�B�B
�@19.6608MHz�͗ǂ������B�������A�����x�R���f���T�[�A�Œ��R�Ƒ���]�g���}�[��v�����銴���B)
�EFCZ�R�C���Ƃ�LC���U�ł�����x�ш��I�тȂ��瑝���B
�E10.7MHz��IF��BPF�́A���\���������ɁA���S���g���ɂ��덷��������Ƃ���B
�@(�Ƃ����̂��A�ш敝�̑傫��WFM�Ƃ������蓾�邵�ADBM�ŃV�t�g�����]�v�ȃ��m��������肷��̂ƁA���͂̃X�y�N�g�������G�c�ɏ����̗p�r�Ȃ̂�����A
�@������O���Č����Γ�����O���H)
�E10.245MHz�̐����͊y�V�ň����������B
�E455KHz��IF��BPF�͌��\�V�r�A�ȑш�B�������s���I���̖{�ԁB
���ƁA�p�[�c�Ƃ��āA
������ł���A���g�������Z�V�t�g�p��DBM(�_�u���o�����X�h�~�L�T)��IC�́ASOP�̂�ϊ���Ńs���o���������m���A���̂ł��ꂪ�ǂ����ȁH
SOP-8����DIP-8�ɂ܂Ƃ߂�ϊ����ʍw�����āA�����őg�ݗ��āc�A�̓����h�C�B
DBM���������Ă��ATr�����`�ɏ�肭�M��ƁA���g���̉����Z(����)�͏o����炵���悤�����A���́A�L�����A�̘R�ꂩ�ȁH
�Ƃ������A�E�`�Ɍ������Ɏg�����Ƃ��čw�������]���R&K�̍����ȃp�b�V�uDBM����R����̂ŁA
���̓Q�C���ɋC���g���K�v�������邪�A���m�ɂ���ẮA������l���A�A
�p�b�V�u��DBM�Ƃ����ƁA�t�F���C�g�r�[�Y�̃g�����X��Di�Ńu���b�W������Ď��삷��Ƃ�����i���������B
������M�I�ȗp�r�Ƃ��Ă��A
�Z�N�V�����Ƃ������u���b�N�ɕ����A
IF��2��ʉ߈ȍ~�A���g�A�����A�Ƃ��A���ɗ��p�o����悤�ɏo������C�C�����B
�����R�����W���[����38KHz����455KHz��12�{�ł����āA455KHz����30MHz��66�{�ł���B�v800�{�̎��g�������ƂȂ�B
�����A455KHz����30MHz�ɏグ�Ă��A��IF��455KHz�Ȃ̂ŁA�Z���ԃp���X���ɂ͍v���x���Ⴍ�Ȃ�Ǝv���B
�����ǁA�p���X�̒Z�k��3�{���x�͂���Ȃ�ɉ\���Ƃ͎v���Ă���B
30MHz�̗��_�͉����낤�H
��H�������@�Ƃ��Ďd�オ���Ă銴���c�Ƃ��������H�H
���ԂƋ��Ƃ�����A���������̉�H��PD�����APC��H�ɂ���̂��c�A
(�ő�ɑË�����AAPC����ŗh���Ԃ�̂ł͖������āAAPC��H�ɂƂ��Ēǂ����Ȃ����x�Ɨʂŏ�悹���銴���H)
LD�̋��e���b�e�[�W���傫����A���t�@�����X�ɂ��R���g���[���ȂǕK�v�Ƃ����ɁAACC�ň��肵�Ĕ��U�o����Ƃ͎v���B
�d�����߂�́A��R���ᖳ�����āA��d��Di���Ƃǂ����ȁHLD���h���C�u���邾���Ȃ�ǂ����ǁA���W�����[�V�������o���Ȃ��c���A�A
�W�Ȃ����ǖ�����28MHz�т��āAVHF�ɓ���̂��ȁHE�X�|���o���DX�\�Ƃ������Ă���B
E�X�|�Ƃ́A���z�ɂ��d���w�B�܂葾�z�ŗ�N����d�q���d�������C��(�v���Y�})�̑w���Ǝv����B
�d�����Ă���̂ŋ����Ɠ��������R�d�q������킯�ŁA�d�g�˂�����ʂ��o��Ǝv����B
�����Œ��ׂČ����BVHF��30MHz�`�Ȃ̂ŁA28MHz��HF�����A��낤�Ƃ��Ă�����e�̓W���X�gVHF�̎n�܂�Ɉ���������Ƃ���ł���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�����e�̍����g�ʐM���̃C���C���c�A�A
220228
���ɓ������Ėʓ|�Ȃ��ƁB
FCZ�R�C���̊�ւ̐ڑ��B(���ꂪ��Ԃ̖��A�����ɂ�������Ƒ����������肷��B)
LD�̔g���Ƌɐ��̒T��B(�K�i�̓��ꂷ�邩�A�������L�����ė~�����g�R�����A������݂Ă��m�F�o���邩���B)
�����̃g�����W�X�^�ɂ��R���s�b�c���U��H�̋쓮�B(�p�����^�ݒ�B)
�����̂̋쓮�d���̈Ⴂ��x�������B
���[�U�[�͈���̂���6V�d�������d���ɂ��悤�Ǝv�����B
30MHz�쓮�́A��͂�V�r�A�ɂ͎v���B
���U��m�C�Y��}���Ȃ��獂���x�ɂ͂������B
����ȃ��j�o�[�T����ł́A�x�^GND������V�[���h������͍���Ȃ̂ŁA
�����P�[�X�������Ȃ����B�B
�ꉞ�A��������āB
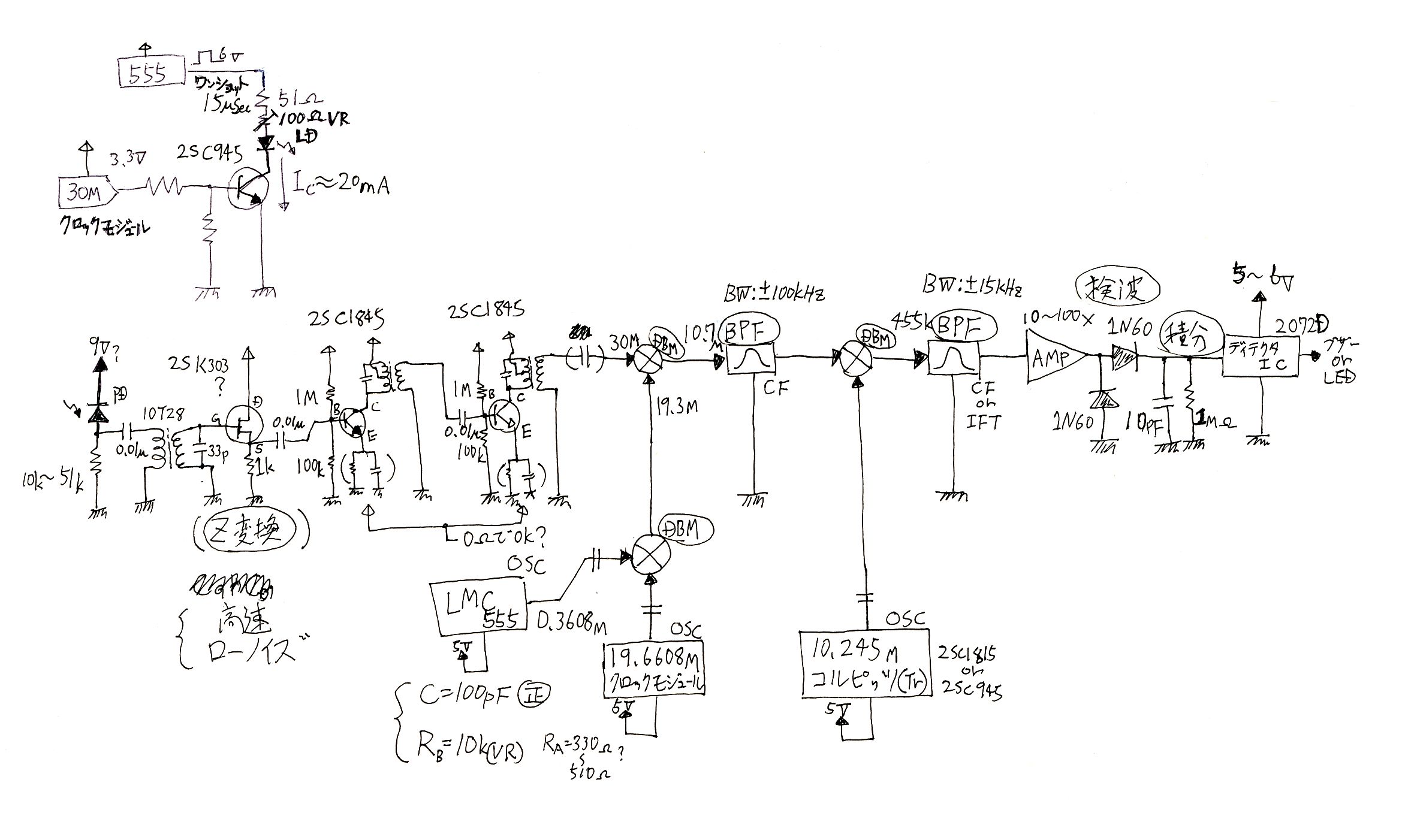 �|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
455KHz�^�C�v�ɖ߂��Ă݂�B
Tr�̋��U��H���g�����X�ɂ���B
�܂�AIFT(��)�����f���Ƃ��Ă�g�ݍ���ł݂��BC�̓J�^���O�l�BL�̒l�ɂ��Ă̓��[�^�[�Ŏ��������B
����ŁA�V�~�����[�V��������ƁA�M�����Ȃ��قNj��U���g���������ɂ���Ă���B
����ρATr(�}�ł�2SC1815�A���ۂɂ�2SC1845)�̃R���N�^�e�ʂ̂����Ȃ̂��ȁH
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
455KHz�^�C�v�ɖ߂��Ă݂�B
Tr�̋��U��H���g�����X�ɂ���B
�܂�AIFT(��)�����f���Ƃ��Ă�g�ݍ���ł݂��BC�̓J�^���O�l�BL�̒l�ɂ��Ă̓��[�^�[�Ŏ��������B
����ŁA�V�~�����[�V��������ƁA�M�����Ȃ��قNj��U���g���������ɂ���Ă���B
����ρATr(�}�ł�2SC1815�A���ۂɂ�2SC1845)�̃R���N�^�e�ʂ̂����Ȃ̂��ȁH
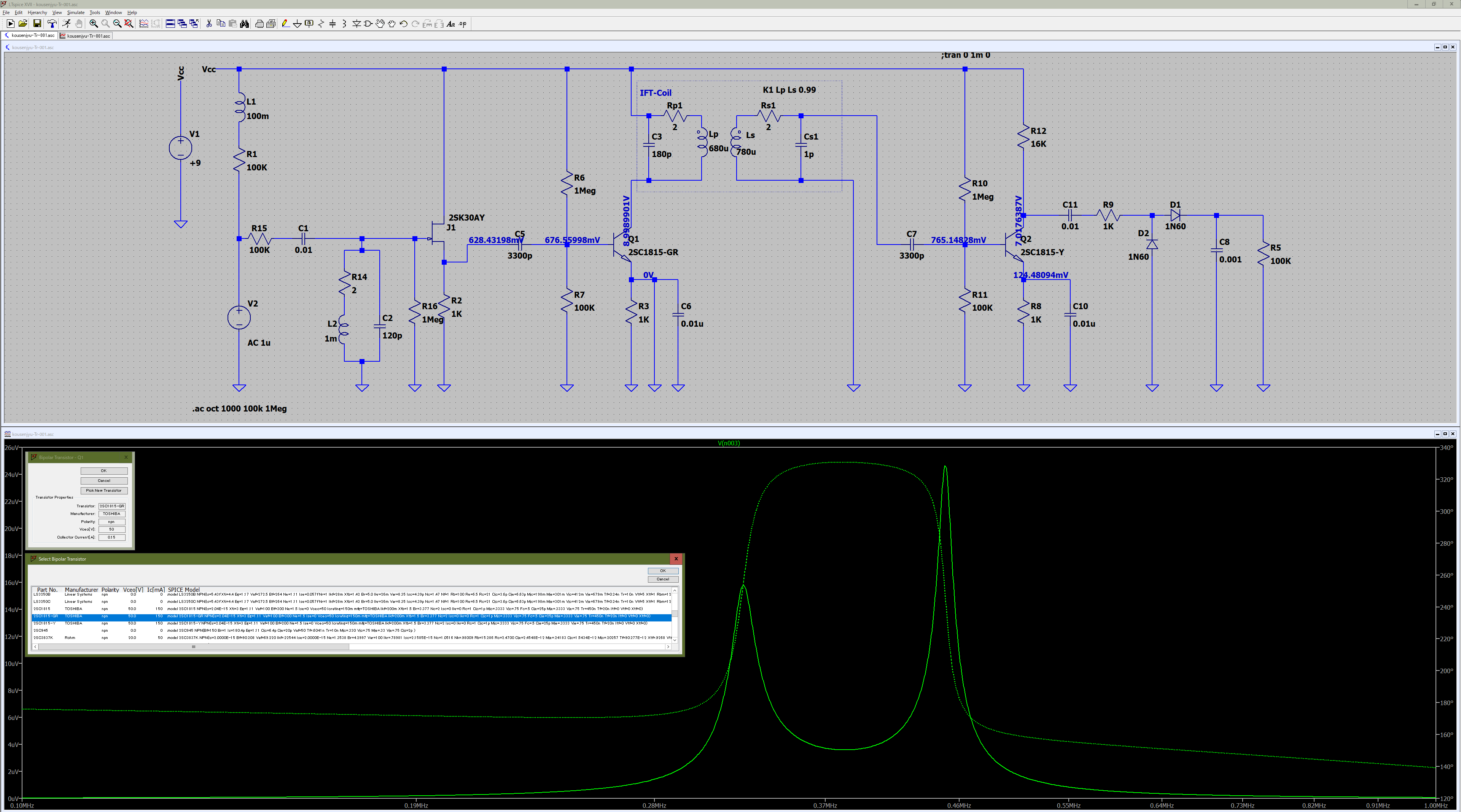 �G�~�b�^���Z�����Ă�̂́A�~�X�ł͖����B�ǂ���ł��������Ƃ��l���A��r�o����悤�ɂ��Ă���B
�����ł��A���P���J�Ȍ��ۂ������ĂāA
IFT�̗��_�v�l�ASpice�ɂ��V���A�����l�A�̂R�S�Ă���v���ĂȂ��C������B
���̂Ƃ���A470��H��10�`500pF�̃o���R�����q���ł������Ƃ����s�[�N��������Ȃ������B
�R���N�^�e�ʂ��āA���Tr�̂ǂ̒[�q�Ԃ̗e�ʂȂ̂��ȁH
�Ə����l���Ă݂�ɁA
�o�C�A�X�ŕς��̂�����ACob�c�BCob�͓��͗e�ʂƂ��̉\�����^���A�f�[�^�V�[�g�ׂČ�����R���N�^�̃L���p�V�^���X�������ł��B
�����G�~�b�^�ƃR���N�^�Ԃ̗e�ʂŁAE��GND�ƌq�����Ă邩�炻���Ă���́A�𗬓I�ɋ��d�d���Ɠ������A�A�����AFCZ�R�C���̃R�C���ƕ��s�ɃR���f���T�[���q�����Ă邱�ƂɂȂ�B
�܂��A�g�����X�\���ɂ��Ȃ��ƁA�㑱���鎟�̉�H�̓��͗e�ʂ̉e�����m���Ɏ邾�낤�B
���������Ƃ��Ă��A�Ώ��Ɏd���������C������BTr���R���N�^�e�ʂ̏��������ɕς���ʂ̂��ƂɂȂ�B
�G���ł́A2SC1906��2SK439�ň����Ă邪�A30MHz�̋L���ɂȂ��2SC945��FCZ�R�C���ň����Ă�B
2SK439�͂Ȃ��Ȃ��ǂ��݂��������ǁA�Â����邩���B
�����x���E���̎�M�@�ł��A���͒�����LC���U����A�R���N�^��FCZ�t��2SK439�ő������Ă���B
�����Ĉ�i����������A�����Ɏ���Tr��MIX����IF�t�B���^�[�ɒʂ��Ă���B
Mix�́A������A2SK439�ŁA���炭Tr�̔���`�����g���đ��������˂Ȃ������Ă���B
������̕����ǂ��ƌ������ƂȂ̂��H
���x��-10dB�͊y�X�N���A�Ƃ��邪�A0dB�����ɋK�i������Ă�̂����J���BdBm�Ƃ�dB�ʂƂ��Ȃ番����̂����c�A�A
�����{���ƑI��x�͑��ւ�����A���ꂪ���x�̗ǂ��ƊW���Ă�Ǝv����B
�܂�A��������ɃQ�C���̔{���グ�Ă��Ӗ��������B
�g�`�����̓d�g�ŖO�a���Ă���A�c�݂��獬�ϒ����N���Ă���A���U���Ă���V�O�i����MAX�ɕ\������ĂĂ��A��M�o���ĂȂ��B
��Ԃ�Ă���A�������������Ă��A���x�͋t�ɁA��œI�ɉ����闝�R�ŃA���B�B
���ƁA555�ł͂Ȃ�VCO(VFO)���g���Ă�P�[�X�����ʁB
���������A���Đ�����1�i���ƃG�~�b�^����R���f���T�[����x�[�X���A�҂����Ă�H
VHF�̈�̑����ɂ͂���FET���g���Ă��āA2SK439�A2SK241�A2SK192A�Ƃ����̂��|�s�����[�������悤�ł��B�ł��p�ՁB
��֕i�͂����Ȃ��悤�ȁH
�����A�����ŃJ�X�P�[�h�ڑ�����Ă��āA�A�җe�ʂ����Ȃ��Ƃ��B
�u������3SK�^�̍����g�p�f���A���Q�[�gMOS�^�d�E���ʃg�����W�X�^�́A���Q�[�g���\�[�X�ɐڑ����邱�ƂŁA���l�Ɏg����Ǝv����B�v
�Ə����Ă������B
���Ƃ́A��G���L�ш��M�pIC��FET�̓Q�[�g�ڒn��2SK125��NE76084�H
�܂��A439�͔����Ă邯�Ǎ��߂�������U��������Ƃ��H
FCZ��VHF�p�̎|���́A�łт��悤�ł��ˁB�B
�I�[�f�B�I�̍��ڂŃg�����W�X�^�̃f�B�X�N���[�g�������Ə��������R�ɁA
���̕��i�̔ėp���̖���������A���U�����Ď�ނ����Ȃ����āA���̑���Z���ŏI���Ȃ��Ƃ����Ė��Ȃ��Ɓc�A�A
�܂��A���v�Ȃnjv����p�r�ł͖łтĂȂ��ł����c�A�A
������OP-AMP�̎���������Ȃ��Ă��Ă�̂́A�A�i���O�r�f�I�△������ł��Ă銴���Ȃ̂ł��傤�ˁB
���R�[�h�̂悤�ɖ߂��Ă��邩���H
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�Ƃɂ����A�e�X�g�ł�FET��Z�ϊ��p���������A���p���������ǂ��B
�ŁA���̌�̂��AFET�̕����悳���Ȃ̂Ő�ւ��������ǁA�����B
�܂��A�����ȕ��@�Œ��B�͉\�ȃ��x���BFCZ���͈�������l���������ǂ������B
�ŁA������܂߂����i���B���o���āA����Ɏ�肩����ɂ́A�b�������肻���ł��ˁB
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
����܂łɁASpice�ɂ��V����̃e�X�g�i�K�Ńi�J�i�J���U�����Ȃ�
�������U��H���ǂ��ɂ����˂c�A�A
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�ŁA���v�ɂāA�A
�v�����̂����ǁA
�s�G�]�f�q�t�B�����H�ƃK���X�ŕϒ������ᐫ�\�ł��ǂ�����A�������w�f�q�����邩�����Č�����������B
���ʓx�A���ߐ��Ɖ������x���̂��ǂ����A�[�ʂ̃X���b�V���J�b�g�A�z���ނƂ��ґ�ȃ��m�͂Ȃ��A�s�G�]�̋����Y��ɂ͓�����Ă��A
�h�b�v���[�̂����܌��ۂ����͏o���邩���m��Ȃ��B
�����̉�͂��ȂŁA�t�̗̂e���4MHz���x��`�������Ă���Ă�̂�Ō������Ƃ�����B�N�I�[�c���g���邱�Ƃ͎g����炵���B
�����`�c�A�����Ȃ�ԊO�����AHM��FM���K���X�A�����ʓx�����B�R�����[�V���������Y�̐��x���B�g���͂���܂�v��Ȃ��B
�ґ�Ƀ}�C�N�����[�^�[�̕t�����I�v�g�}�C�N��X�e�[�W�A�}�O�l�b�g�x�[�X�A���U����w������Ɣ��ɍ��������A
�ꍞ��(�X���b�g)�����āA�l�W�Œ��߂邱�ƂŁA���ׂȊp�x�����̂�����Ă��g�R������B���������ǃ��[�U�[�v�����^�[�Ƃ��ō���Ă��g���Ȃ����ȁH
�����A�����́A�ƂĂ��V�r�A���B������͈͂łȂ�ׂ��ԕ��ɍs�����g�����ǂ��B
�{���A�����̃��[�U�[�͎G�����������x�������̂ŁA�K�X���[�U�[�Ȃǂ��g���̂����A
������LD�łǂ��܂ŃC�P��̂��������[�������B
�܂��A�K�X���[�U�[�Ȃ�A��{�g���āA��������A�i�s�g���o��Ǝv�����A�������肭�����o���Ȃ����Ƃ��B�B
��������g�R��10.5��m�̑�p���[��CO2�K�X���[�U�[���g���Ă����B��p�̌��w�p�i�ɂȂ�B�Z���T�[�͉t�̒��f�ŗ�₵�Ă���������ł������B
�ł��A�������Ċ������グ���3.39��m�ł��\���o���邵�A�F�X�y���Ȃ�̂ɁA�͋Ƃ��ȁ[�A�Ǝv���Đ������Ă����܂��ʂ��Ȃ��̂ŁA���Ă����B
�\�Z������Ίy�������Ƃ���R�o����̂��ȁ[�B�B
���ƂȂ��ẮA�����̘̂b�B
�������A���w�Ƃ����w���Đ�啪��̊w�Ȃ��ĕ��������Ƃ������B�d�q�Ƃ��A�����@�B������Ă�̂��ȁH
�t�@���f�[���[�e�[�V���������Ɏg���邩������Ȃ����A�ʔ��������m��Ȃ��B
����������B�B
�芪���R�C����DBM������Ă݂������ǁA���������܂�����ŁA�Y�ꂽ�B25�N�ȏ���O�ɂ���Ă����Ƃ�������ɂ́`�A�A
�������̂ĂĂȂ����������A�܂��A�A
�ɂ킩�ɖ����I������M��n�߂��̂����ǁB
�Ȃɂ�������Ď��s���Ă��A
������̂��[�����ăR�g�͖�������B
�Z�p�͊m���ɒ~�ς���Ă���B
���ʘ_�̐��ʂł��������Ȃ����ƂȂǖ����B
�G�~�b�^���Z�����Ă�̂́A�~�X�ł͖����B�ǂ���ł��������Ƃ��l���A��r�o����悤�ɂ��Ă���B
�����ł��A���P���J�Ȍ��ۂ������ĂāA
IFT�̗��_�v�l�ASpice�ɂ��V���A�����l�A�̂R�S�Ă���v���ĂȂ��C������B
���̂Ƃ���A470��H��10�`500pF�̃o���R�����q���ł������Ƃ����s�[�N��������Ȃ������B
�R���N�^�e�ʂ��āA���Tr�̂ǂ̒[�q�Ԃ̗e�ʂȂ̂��ȁH
�Ə����l���Ă݂�ɁA
�o�C�A�X�ŕς��̂�����ACob�c�BCob�͓��͗e�ʂƂ��̉\�����^���A�f�[�^�V�[�g�ׂČ�����R���N�^�̃L���p�V�^���X�������ł��B
�����G�~�b�^�ƃR���N�^�Ԃ̗e�ʂŁAE��GND�ƌq�����Ă邩�炻���Ă���́A�𗬓I�ɋ��d�d���Ɠ������A�A�����AFCZ�R�C���̃R�C���ƕ��s�ɃR���f���T�[���q�����Ă邱�ƂɂȂ�B
�܂��A�g�����X�\���ɂ��Ȃ��ƁA�㑱���鎟�̉�H�̓��͗e�ʂ̉e�����m���Ɏ邾�낤�B
���������Ƃ��Ă��A�Ώ��Ɏd���������C������BTr���R���N�^�e�ʂ̏��������ɕς���ʂ̂��ƂɂȂ�B
�G���ł́A2SC1906��2SK439�ň����Ă邪�A30MHz�̋L���ɂȂ��2SC945��FCZ�R�C���ň����Ă�B
2SK439�͂Ȃ��Ȃ��ǂ��݂��������ǁA�Â����邩���B
�����x���E���̎�M�@�ł��A���͒�����LC���U����A�R���N�^��FCZ�t��2SK439�ő������Ă���B
�����Ĉ�i����������A�����Ɏ���Tr��MIX����IF�t�B���^�[�ɒʂ��Ă���B
Mix�́A������A2SK439�ŁA���炭Tr�̔���`�����g���đ��������˂Ȃ������Ă���B
������̕����ǂ��ƌ������ƂȂ̂��H
���x��-10dB�͊y�X�N���A�Ƃ��邪�A0dB�����ɋK�i������Ă�̂����J���BdBm�Ƃ�dB�ʂƂ��Ȃ番����̂����c�A�A
�����{���ƑI��x�͑��ւ�����A���ꂪ���x�̗ǂ��ƊW���Ă�Ǝv����B
�܂�A��������ɃQ�C���̔{���グ�Ă��Ӗ��������B
�g�`�����̓d�g�ŖO�a���Ă���A�c�݂��獬�ϒ����N���Ă���A���U���Ă���V�O�i����MAX�ɕ\������ĂĂ��A��M�o���ĂȂ��B
��Ԃ�Ă���A�������������Ă��A���x�͋t�ɁA��œI�ɉ����闝�R�ŃA���B�B
���ƁA555�ł͂Ȃ�VCO(VFO)���g���Ă�P�[�X�����ʁB
���������A���Đ�����1�i���ƃG�~�b�^����R���f���T�[����x�[�X���A�҂����Ă�H
VHF�̈�̑����ɂ͂���FET���g���Ă��āA2SK439�A2SK241�A2SK192A�Ƃ����̂��|�s�����[�������悤�ł��B�ł��p�ՁB
��֕i�͂����Ȃ��悤�ȁH
�����A�����ŃJ�X�P�[�h�ڑ�����Ă��āA�A�җe�ʂ����Ȃ��Ƃ��B
�u������3SK�^�̍����g�p�f���A���Q�[�gMOS�^�d�E���ʃg�����W�X�^�́A���Q�[�g���\�[�X�ɐڑ����邱�ƂŁA���l�Ɏg����Ǝv����B�v
�Ə����Ă������B
���Ƃ́A��G���L�ш��M�pIC��FET�̓Q�[�g�ڒn��2SK125��NE76084�H
�܂��A439�͔����Ă邯�Ǎ��߂�������U��������Ƃ��H
FCZ��VHF�p�̎|���́A�łт��悤�ł��ˁB�B
�I�[�f�B�I�̍��ڂŃg�����W�X�^�̃f�B�X�N���[�g�������Ə��������R�ɁA
���̕��i�̔ėp���̖���������A���U�����Ď�ނ����Ȃ����āA���̑���Z���ŏI���Ȃ��Ƃ����Ė��Ȃ��Ɓc�A�A
�܂��A���v�Ȃnjv����p�r�ł͖łтĂȂ��ł����c�A�A
������OP-AMP�̎���������Ȃ��Ă��Ă�̂́A�A�i���O�r�f�I�△������ł��Ă銴���Ȃ̂ł��傤�ˁB
���R�[�h�̂悤�ɖ߂��Ă��邩���H
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�Ƃɂ����A�e�X�g�ł�FET��Z�ϊ��p���������A���p���������ǂ��B
�ŁA���̌�̂��AFET�̕����悳���Ȃ̂Ő�ւ��������ǁA�����B
�܂��A�����ȕ��@�Œ��B�͉\�ȃ��x���BFCZ���͈�������l���������ǂ������B
�ŁA������܂߂����i���B���o���āA����Ɏ�肩����ɂ́A�b�������肻���ł��ˁB
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
����܂łɁASpice�ɂ��V����̃e�X�g�i�K�Ńi�J�i�J���U�����Ȃ�
�������U��H���ǂ��ɂ����˂c�A�A
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�ŁA���v�ɂāA�A
�v�����̂����ǁA
�s�G�]�f�q�t�B�����H�ƃK���X�ŕϒ������ᐫ�\�ł��ǂ�����A�������w�f�q�����邩�����Č�����������B
���ʓx�A���ߐ��Ɖ������x���̂��ǂ����A�[�ʂ̃X���b�V���J�b�g�A�z���ނƂ��ґ�ȃ��m�͂Ȃ��A�s�G�]�̋����Y��ɂ͓�����Ă��A
�h�b�v���[�̂����܌��ۂ����͏o���邩���m��Ȃ��B
�����̉�͂��ȂŁA�t�̗̂e���4MHz���x��`�������Ă���Ă�̂�Ō������Ƃ�����B�N�I�[�c���g���邱�Ƃ͎g����炵���B
�����`�c�A�����Ȃ�ԊO�����AHM��FM���K���X�A�����ʓx�����B�R�����[�V���������Y�̐��x���B�g���͂���܂�v��Ȃ��B
�ґ�Ƀ}�C�N�����[�^�[�̕t�����I�v�g�}�C�N��X�e�[�W�A�}�O�l�b�g�x�[�X�A���U����w������Ɣ��ɍ��������A
�ꍞ��(�X���b�g)�����āA�l�W�Œ��߂邱�ƂŁA���ׂȊp�x�����̂�����Ă��g�R������B���������ǃ��[�U�[�v�����^�[�Ƃ��ō���Ă��g���Ȃ����ȁH
�����A�����́A�ƂĂ��V�r�A���B������͈͂łȂ�ׂ��ԕ��ɍs�����g�����ǂ��B
�{���A�����̃��[�U�[�͎G�����������x�������̂ŁA�K�X���[�U�[�Ȃǂ��g���̂����A
������LD�łǂ��܂ŃC�P��̂��������[�������B
�܂��A�K�X���[�U�[�Ȃ�A��{�g���āA��������A�i�s�g���o��Ǝv�����A�������肭�����o���Ȃ����Ƃ��B�B
��������g�R��10.5��m�̑�p���[��CO2�K�X���[�U�[���g���Ă����B��p�̌��w�p�i�ɂȂ�B�Z���T�[�͉t�̒��f�ŗ�₵�Ă���������ł������B
�ł��A�������Ċ������グ���3.39��m�ł��\���o���邵�A�F�X�y���Ȃ�̂ɁA�͋Ƃ��ȁ[�A�Ǝv���Đ������Ă����܂��ʂ��Ȃ��̂ŁA���Ă����B
�\�Z������Ίy�������Ƃ���R�o����̂��ȁ[�B�B
���ƂȂ��ẮA�����̘̂b�B
�������A���w�Ƃ����w���Đ�啪��̊w�Ȃ��ĕ��������Ƃ������B�d�q�Ƃ��A�����@�B������Ă�̂��ȁH
�t�@���f�[���[�e�[�V���������Ɏg���邩������Ȃ����A�ʔ��������m��Ȃ��B
����������B�B
�芪���R�C����DBM������Ă݂������ǁA���������܂�����ŁA�Y�ꂽ�B25�N�ȏ���O�ɂ���Ă����Ƃ�������ɂ́`�A�A
�������̂ĂĂȂ����������A�܂��A�A
�ɂ킩�ɖ����I������M��n�߂��̂����ǁB
�Ȃɂ�������Ď��s���Ă��A
������̂��[�����ăR�g�͖�������B
�Z�p�͊m���ɒ~�ς���Ă���B
���ʘ_�̐��ʂł��������Ȃ����ƂȂǖ����B
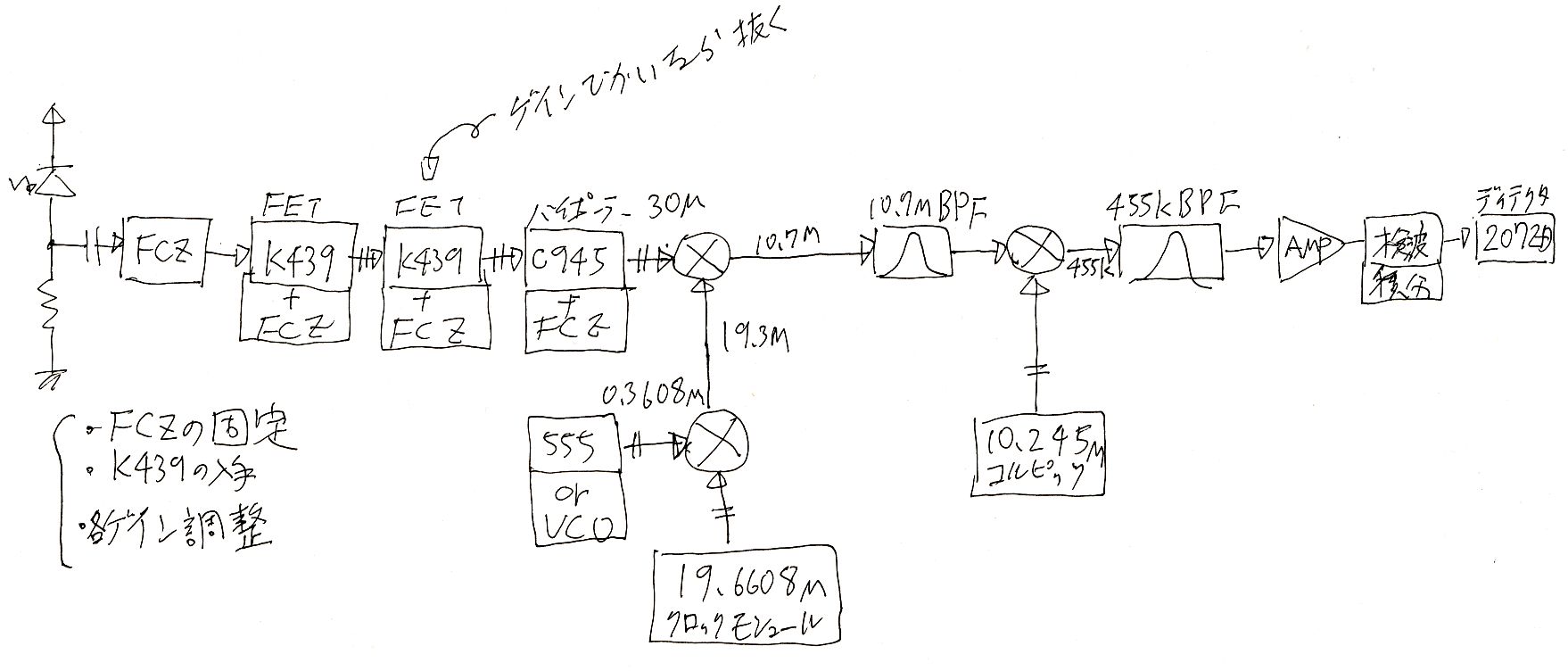 ����́A���i���l���A���\���Ԃ������邩�ȁH
���������Ƃ��̋@�\�������A�����o����]�T�A���s���Ă��A�C�������������B����Ȃ��Ƒ�ρB
Z�ϊ��Ƒ����𐮑R�ƃC���[�W�ł́A���������������A��������ɂ��������ǂ��݂����Ȃ̂ŁB
�����̃��C����FET�֕ύX�B��i�������āA10.7MHz����i�������ǂ������H�܂��AMIXer�̋K�i����B
�ꉞ�AFET�̃\�[�X��h�炷�����ł͖����A��������g���B
���ƁAIF�ʂ��O�̑��������\�������ǂ��o�邩�H
�܂��A��������Ƃ̃Q�C���̊W�����肻���B
�������ĉ����킯�ł͖����A���g���āA���̃p���X�ʼn����f�B�e�N�^��臂ȃ��b�`��ON�ɂ��銴���B
���ƁA�����̃R���s�b�c���U�̉�H�Ȃ̂����ǁA
����́A���i���l���A���\���Ԃ������邩�ȁH
���������Ƃ��̋@�\�������A�����o����]�T�A���s���Ă��A�C�������������B����Ȃ��Ƒ�ρB
Z�ϊ��Ƒ����𐮑R�ƃC���[�W�ł́A���������������A��������ɂ��������ǂ��݂����Ȃ̂ŁB
�����̃��C����FET�֕ύX�B��i�������āA10.7MHz����i�������ǂ������H�܂��AMIXer�̋K�i����B
�ꉞ�AFET�̃\�[�X��h�炷�����ł͖����A��������g���B
���ƁAIF�ʂ��O�̑��������\�������ǂ��o�邩�H
�܂��A��������Ƃ̃Q�C���̊W�����肻���B
�������ĉ����킯�ł͖����A���g���āA���̃p���X�ʼn����f�B�e�N�^��臂ȃ��b�`��ON�ɂ��銴���B
���ƁA�����̃R���s�b�c���U�̉�H�Ȃ̂����ǁA
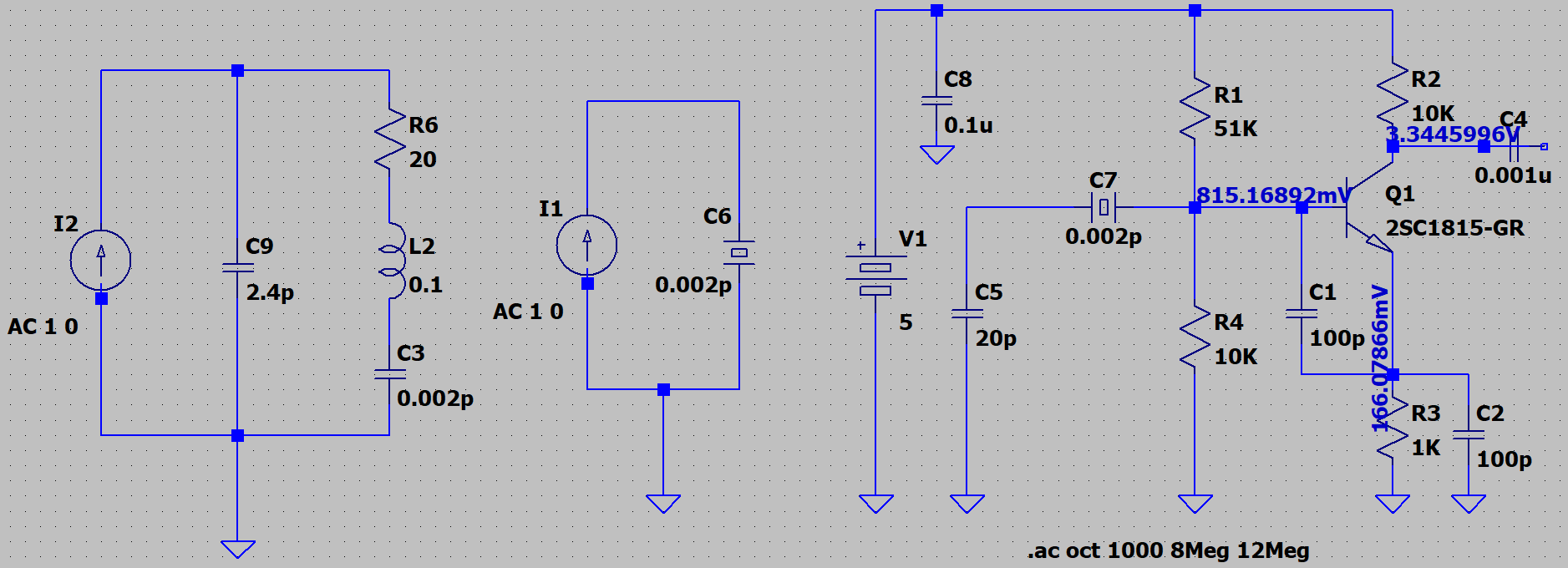 ��́A�����Ȃ�ɍl�����p�����^�B
�p�����^�Ŕ��U���ɂ����̂͏ꍇ�ɂ�邾�낤���ǁA
�����B
�F�X�M���Ă��A�S�����U���Ȃ��B
���ۂɓ����Ă�̂��Q�l�ɂ��Đݒ肵�Ă݂Ă��A�s�N���Ƃ����Ȃ��BTr�������Ȃ̂ɁA�����������Ȃ��B�~�X�Ŗ����\���������̂ŁA�����������ˁH
�d�r�ł���Ă�̂ŁA�ÓI�ł���A�ŏ��ɉ����h�����K�v�Ƃ��H�H
��́A�����Ȃ�ɍl�����p�����^�B
�p�����^�Ŕ��U���ɂ����̂͏ꍇ�ɂ�邾�낤���ǁA
�����B
�F�X�M���Ă��A�S�����U���Ȃ��B
���ۂɓ����Ă�̂��Q�l�ɂ��Đݒ肵�Ă݂Ă��A�s�N���Ƃ����Ȃ��BTr�������Ȃ̂ɁA�����������Ȃ��B�~�X�Ŗ����\���������̂ŁA�����������ˁH
�d�r�ł���Ă�̂ŁA�ÓI�ł���A�ŏ��ɉ����h�����K�v�Ƃ��H�H
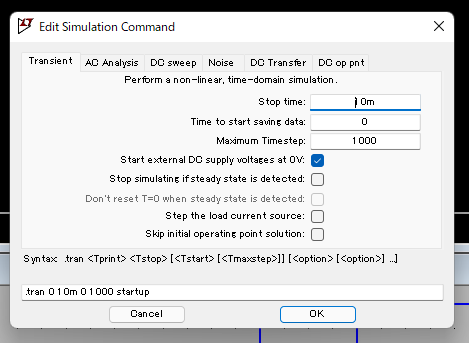 �_�����B�B
���ɃA���d���̓d�����R�s�[���ėh���Ԃ��Ă��AF���ł͂���܂�Ƌ��U����̂݁B����𗊂�ɁA�U�����傫��������悤�ɘM������E����B�B
����ȂɐU�����Ȃ��̂͂������ɂ��������B
�u���b�h�{�[�h�ł���������ǂ������B
�����A�قڗ��z�l�Ȃ̂ł́H�@������5V��2SC1815�Ɍ���B
�_�����B�B
���ɃA���d���̓d�����R�s�[���ėh���Ԃ��Ă��AF���ł͂���܂�Ƌ��U����̂݁B����𗊂�ɁA�U�����傫��������悤�ɘM������E����B�B
����ȂɐU�����Ȃ��̂͂������ɂ��������B
�u���b�h�{�[�h�ł���������ǂ������B
�����A�قڗ��z�l�Ȃ̂ł́H�@������5V��2SC1815�Ɍ���B
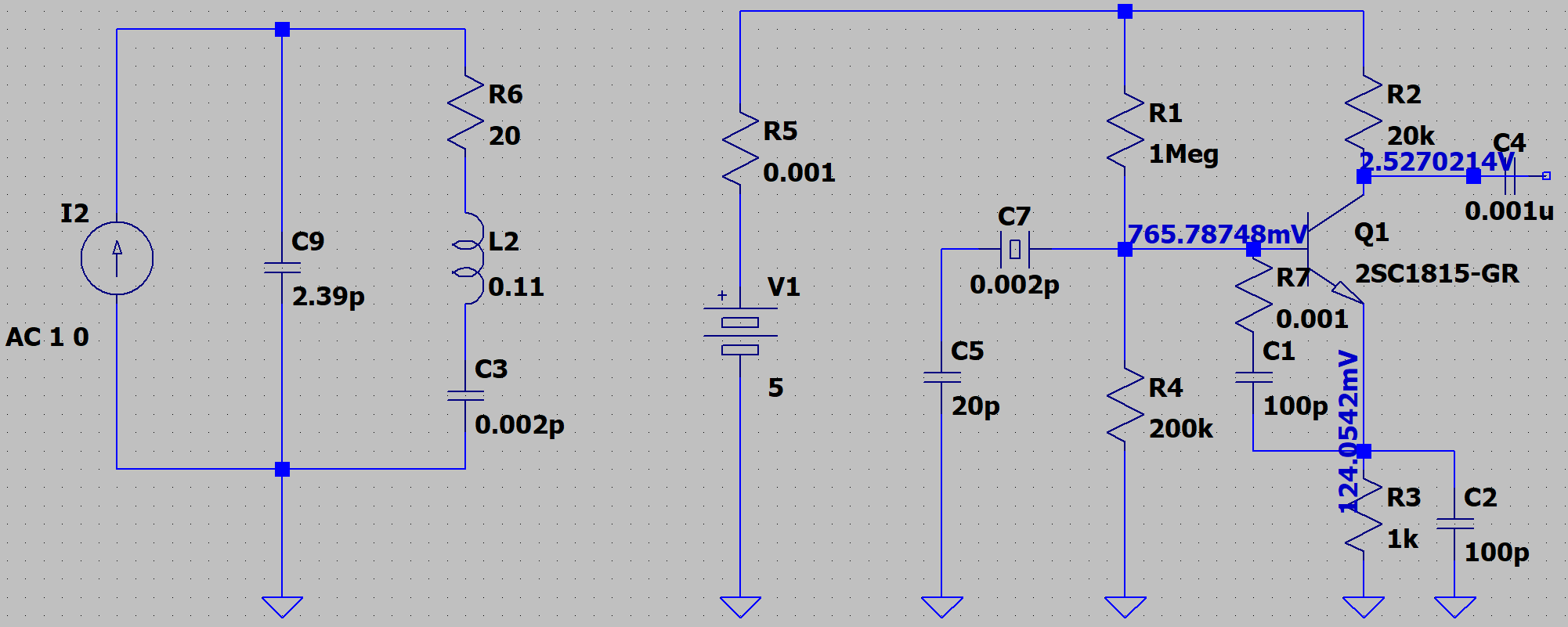 �ł��S���U�����Ȃ��B
1815�̉�H�́A2�������̂ŁA���̃p�����[�^���R�s�[���Ă���Ă݂����A�R�̂悤�ɓ����Ȃ��B
Spice�̐ݒ�Ȃ̂��H�H������l���ɂ����B�Ƃ����̂��A�C���o�[�^�[�ł͓����݂������B�ƂȂ�ƃg�����W�X�^���H�H1815���o����Ă�4��ނ��������B
���Ԃ̖��ʁI�I���������\�t�g��ňӖ��s���ɗ��s�s�Ȏ��Ԃ�H���̂́A�������܂Ȃ��̂ŕs���ȋC���B�B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�ŁA�l����B
���U������U�����₷�����ă`�F�b�N�BC3����菜���B
R1�ɑ�R4���������Ă݂��B
�ŁA�ٗ�̒������ԁA�܂�4mSec���āA�U�����n�܂����I�I���ʏ�600��Sec������Ύn�܂��Ă���B
�ł��S���U�����Ȃ��B
1815�̉�H�́A2�������̂ŁA���̃p�����[�^���R�s�[���Ă���Ă݂����A�R�̂悤�ɓ����Ȃ��B
Spice�̐ݒ�Ȃ̂��H�H������l���ɂ����B�Ƃ����̂��A�C���o�[�^�[�ł͓����݂������B�ƂȂ�ƃg�����W�X�^���H�H1815���o����Ă�4��ނ��������B
���Ԃ̖��ʁI�I���������\�t�g��ňӖ��s���ɗ��s�s�Ȏ��Ԃ�H���̂́A�������܂Ȃ��̂ŕs���ȋC���B�B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�ŁA�l����B
���U������U�����₷�����ă`�F�b�N�BC3����菜���B
R1�ɑ�R4���������Ă݂��B
�ŁA�ٗ�̒������ԁA�܂�4mSec���āA�U�����n�܂����I�I���ʏ�600��Sec������Ύn�܂��Ă���B
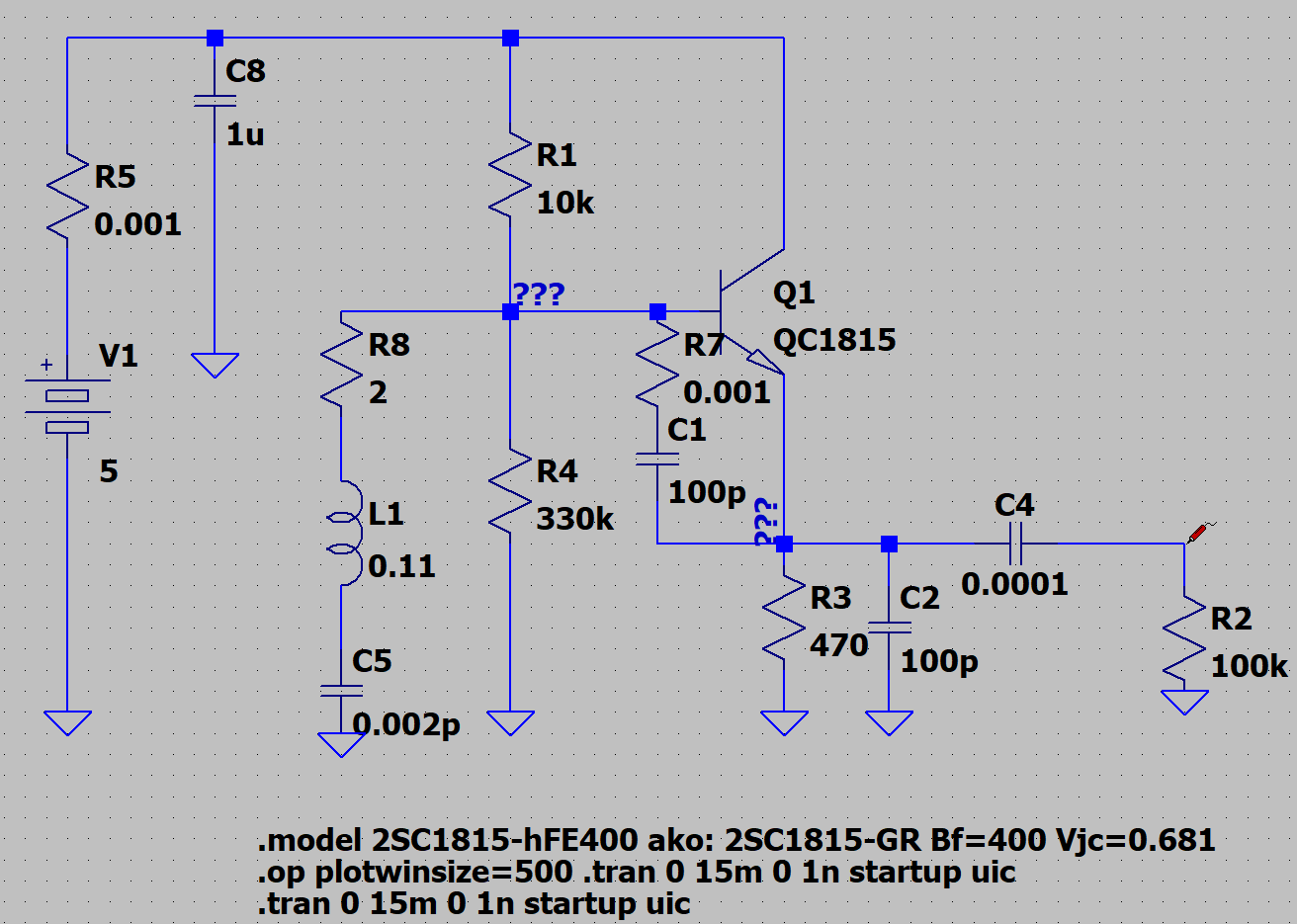 ��������A���U�n��߂��čX�ɍl����B
�Ȃ�ƁA�X��20mSec�ƁA�ƂĂ��x���Ȃ����B
�v���ɃO�O���Č��āA����ȂɌ��Ⴂ�ɒx���̂͋����Ȃ��ǁH
�������A�����Ȑݒ�Ɠ����ł͑S���ʖځB���Ăǂ��������Ƃ���H�H
�܂��A
R1�ɑ��AR4���������A������S�̓I�ɒႭ�����̂��������̂��H
�o�C�A�X��RR1��R4��������ƒ�߂Ƀo�����X���āA�o�͍͂��߂ɏo��悤�ɁB
�G�~�b�^���琳�A�҂���Ĕ��U����݂���������A
Z��1/(��C)������AR��C�̃o�����X���d�v�B���Ƃ́A�o�C�A�X�x�ǂ��B
R3��C2�̃o�����X�͗ǂ��悤�ȋC�����Ă�B
��������A���U�n��߂��čX�ɍl����B
�Ȃ�ƁA�X��20mSec�ƁA�ƂĂ��x���Ȃ����B
�v���ɃO�O���Č��āA����ȂɌ��Ⴂ�ɒx���̂͋����Ȃ��ǁH
�������A�����Ȑݒ�Ɠ����ł͑S���ʖځB���Ăǂ��������Ƃ���H�H
�܂��A
R1�ɑ��AR4���������A������S�̓I�ɒႭ�����̂��������̂��H
�o�C�A�X��RR1��R4��������ƒ�߂Ƀo�����X���āA�o�͍͂��߂ɏo��悤�ɁB
�G�~�b�^���琳�A�҂���Ĕ��U����݂���������A
Z��1/(��C)������AR��C�̃o�����X���d�v�B���Ƃ́A�o�C�A�X�x�ǂ��B
R3��C2�̃o�����X�͗ǂ��悤�ȋC�����Ă�B
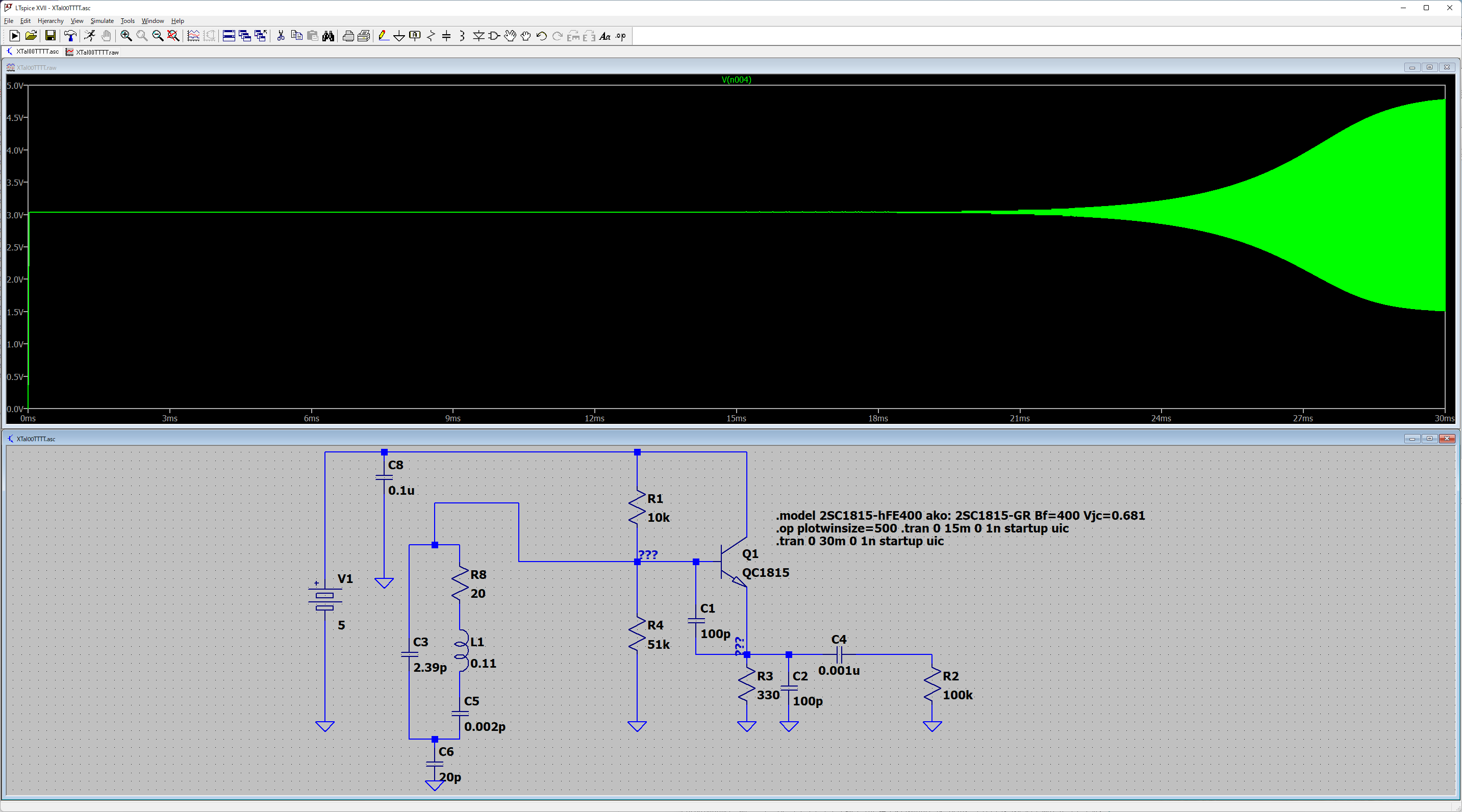 40�{�x���Ƃ��A�����̃��J���ȂƂ������邪�A
�ň��V�~�����[�V�������������Ȃ���A�V���ł͗ǂ����āA���ۂ̔z���Ŕ��U���Ȃ��\�����B
����������Ƌl�߂Ă͌��悤�Ǝv���B
��H�̖���2�B
�ETr��p���������̔��U�p�����^�̖��
�ETr�Ɍq����FCZ�R�C���̋����g���̑啝�Ȓቺ�Ƃ����Y���B
�E���U��NF��}�����Q�C���̔���B
�ELD�������[�U�[���U�܂ŏo���邩�B
�����ɂ́A
�EFCZ�R�C���̌Œ�B
�ELD�̋ɐ��Ȃǔ���������B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�Ƃ肠�����AX'tal�����Ŋ۔����͘M���Ă��̂ŁA��ꂽ�B
���U�����͕̂s�K���̍K���ł���A�������l����Ƌ^����c��B
���Ƃ́ATr�ɕt����FCZ�̋��U���g���̖�肪�傫���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�������肵�Ȃ��Ɛ���ɂ͎�肩����ɂ̓}�Y������������B
�����A
���ɍ��グ�邱�Ƃ����ւ̎��O�ł̓C�J���Ǝv���B
���O�͍Ō�̈ꉟ���ŁA�r���͂��C����肭���䂷��R�g�ŃA���B
���ɁA��C�ɂ�낤�Ƃ��āA���ʁA��蒼���͐S�Ɋ�����B
�Ŏ����Ȃ��Ŏn�߂āA���O�ŏI��点��݂����ȕ����͂��蓾��B
�����A�����v��Ȃ̂ŁA�I��点�Ȃ����Ă��ǂ����ȁH�ƍ���v�����Ƃɂ��Ă�B���C�̖��B
�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��ړI�́A�����������L�������Ƃ������x���Ƃ������ƁB���s���Ă��Z�p�Ƀv���X�ȕ��������蓾��B
���͓d�q�ł͖������c�A�֘A�͂���B
�L�^������Ă����A���ƂŁA�����o����B�����p�ŃA���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220302�F�����e�̐F�X�Ȗ�茴�������肵�đΏ��o���Ă����B
���A���K�I�ɁA�A���Ȃ̂ŁA�l���邾���ɗ��߂Ă�B
���X�N�����Ƃ��ɂ��Ȃ��A�����͑��l�ɉ�������悤�ȓ����Ƃ͋����~���������̑��݂����m��Ȃ��H
���U��x�点�錴���B
��ԂƎv����̂́A������H��C3�B�܂�ALCR�ɕ���ɂȂ�����C�ł���B
�x�[�X�ɗe�ʂ��������猋�\��肩������Ȃ��B
���U�����߂Ă�L��C�̃o�����X�Ȃ�Ă��̂��W���Ă�\�������邩���B
LRC���낤��LCR���낤�ƒ��ƕς��Ȃ��͂������A�ݒ�̂��₷�����C�ɂȂ����̂ŁA�N�I�[�c�̐ݒ�ɖ߂��āA�A
�x�[�X���͂ɒ�R�����B
40�{�x���Ƃ��A�����̃��J���ȂƂ������邪�A
�ň��V�~�����[�V�������������Ȃ���A�V���ł͗ǂ����āA���ۂ̔z���Ŕ��U���Ȃ��\�����B
����������Ƌl�߂Ă͌��悤�Ǝv���B
��H�̖���2�B
�ETr��p���������̔��U�p�����^�̖��
�ETr�Ɍq����FCZ�R�C���̋����g���̑啝�Ȓቺ�Ƃ����Y���B
�E���U��NF��}�����Q�C���̔���B
�ELD�������[�U�[���U�܂ŏo���邩�B
�����ɂ́A
�EFCZ�R�C���̌Œ�B
�ELD�̋ɐ��Ȃǔ���������B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�Ƃ肠�����AX'tal�����Ŋ۔����͘M���Ă��̂ŁA��ꂽ�B
���U�����͕̂s�K���̍K���ł���A�������l����Ƌ^����c��B
���Ƃ́ATr�ɕt����FCZ�̋��U���g���̖�肪�傫���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�������肵�Ȃ��Ɛ���ɂ͎�肩����ɂ̓}�Y������������B
�����A
���ɍ��グ�邱�Ƃ����ւ̎��O�ł̓C�J���Ǝv���B
���O�͍Ō�̈ꉟ���ŁA�r���͂��C����肭���䂷��R�g�ŃA���B
���ɁA��C�ɂ�낤�Ƃ��āA���ʁA��蒼���͐S�Ɋ�����B
�Ŏ����Ȃ��Ŏn�߂āA���O�ŏI��点��݂����ȕ����͂��蓾��B
�����A�����v��Ȃ̂ŁA�I��点�Ȃ����Ă��ǂ����ȁH�ƍ���v�����Ƃɂ��Ă�B���C�̖��B
�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��ړI�́A�����������L�������Ƃ������x���Ƃ������ƁB���s���Ă��Z�p�Ƀv���X�ȕ��������蓾��B
���͓d�q�ł͖������c�A�֘A�͂���B
�L�^������Ă����A���ƂŁA�����o����B�����p�ŃA���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220302�F�����e�̐F�X�Ȗ�茴�������肵�đΏ��o���Ă����B
���A���K�I�ɁA�A���Ȃ̂ŁA�l���邾���ɗ��߂Ă�B
���X�N�����Ƃ��ɂ��Ȃ��A�����͑��l�ɉ�������悤�ȓ����Ƃ͋����~���������̑��݂����m��Ȃ��H
���U��x�点�錴���B
��ԂƎv����̂́A������H��C3�B�܂�ALCR�ɕ���ɂȂ�����C�ł���B
�x�[�X�ɗe�ʂ��������猋�\��肩������Ȃ��B
���U�����߂Ă�L��C�̃o�����X�Ȃ�Ă��̂��W���Ă�\�������邩���B
LRC���낤��LCR���낤�ƒ��ƕς��Ȃ��͂������A�ݒ�̂��₷�����C�ɂȂ����̂ŁA�N�I�[�c�̐ݒ�ɖ߂��āA�A
�x�[�X���͂ɒ�R�����B
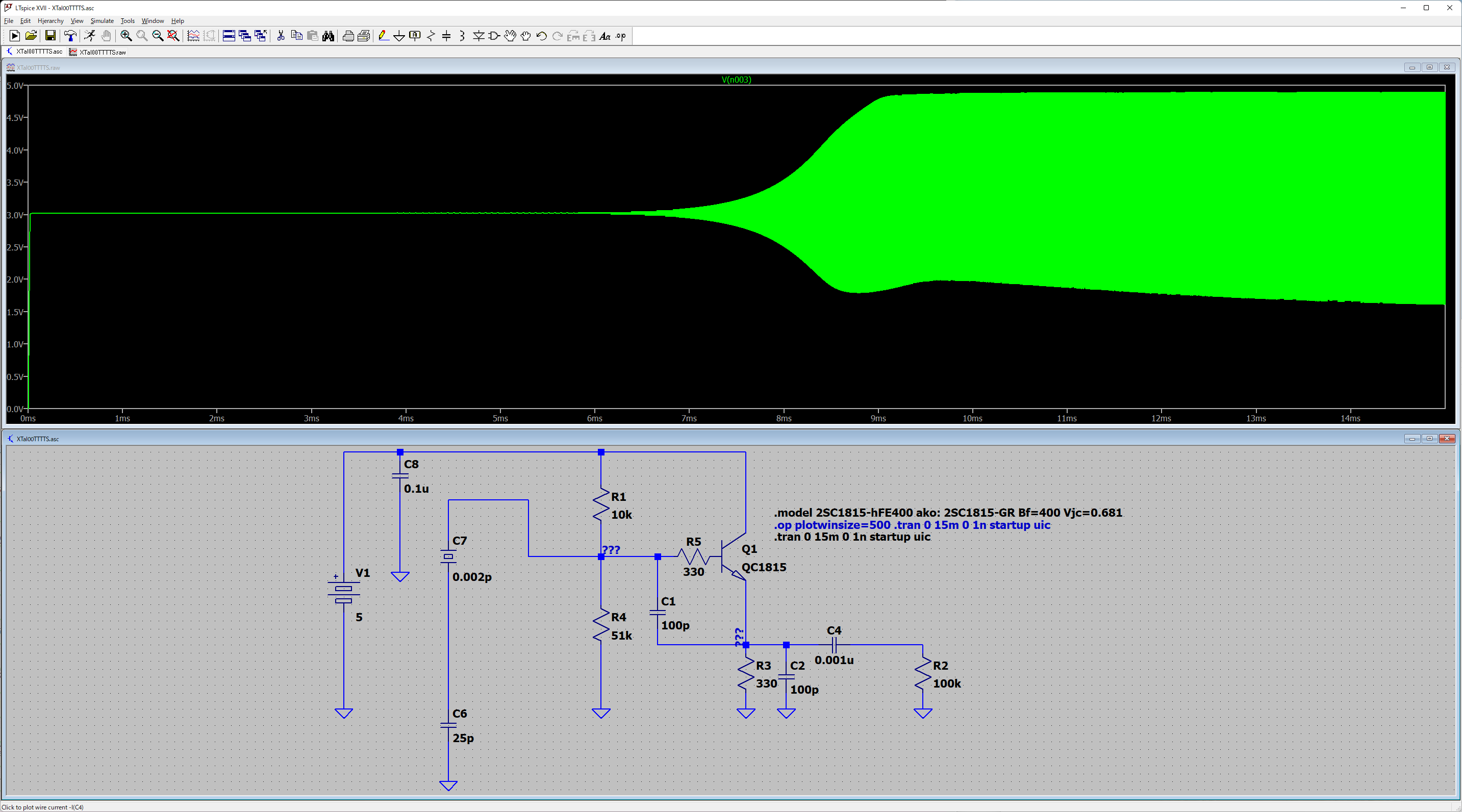 �\�z�����������̂��A�A���U�������Ɏn�܂�悤�ɂȂ����B
�g�`�͂�����Ƃ��тɂȂ��Ă����ŁA�c��ł鎖�ł��邪�A�܂���OK�B
���ɁA�N���X�^���̓�����H��L��1/10�AC��10�{���Ă݂�BL�͐U�����ʁAC�̓o�l�W���ɑ�������Ǝv����B
�\�z�����������̂��A�A���U�������Ɏn�܂�悤�ɂȂ����B
�g�`�͂�����Ƃ��тɂȂ��Ă����ŁA�c��ł鎖�ł��邪�A�܂���OK�B
���ɁA�N���X�^���̓�����H��L��1/10�AC��10�{���Ă݂�BL�͐U�����ʁAC�̓o�l�W���ɑ�������Ǝv����B
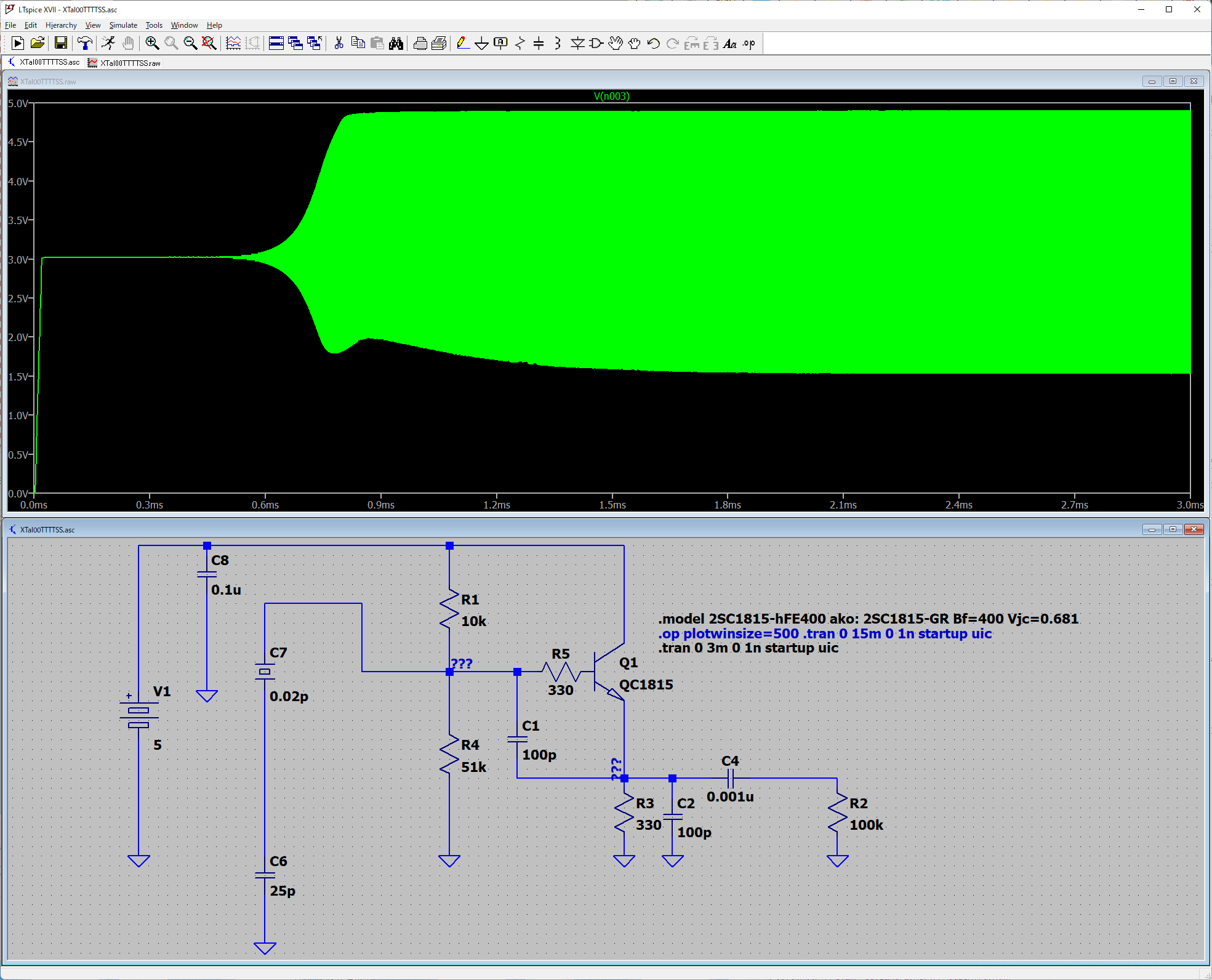 ����I�ɕς�����B���A���ۂ̃N���X�^���̒��g�̐��l�͕�����Ȃ��̂ŁA�܂��B�ł�L=0.11�͕��ʂ̕��i�ł́A�������ɋɒ[�ȕ��͋C������B���������番����Ȃ����B�B
�|�|�|�|�|
�ŁA
���ۂ̉�H�Ŕ��U���邩�Ƃ����e�X�g�B
�u���b�h�{�[�h��ɑg�ށB
����I�ɕς�����B���A���ۂ̃N���X�^���̒��g�̐��l�͕�����Ȃ��̂ŁA�܂��B�ł�L=0.11�͕��ʂ̕��i�ł́A�������ɋɒ[�ȕ��͋C������B���������番����Ȃ����B�B
�|�|�|�|�|
�ŁA
���ۂ̉�H�Ŕ��U���邩�Ƃ����e�X�g�B
�u���b�h�{�[�h��ɑg�ށB
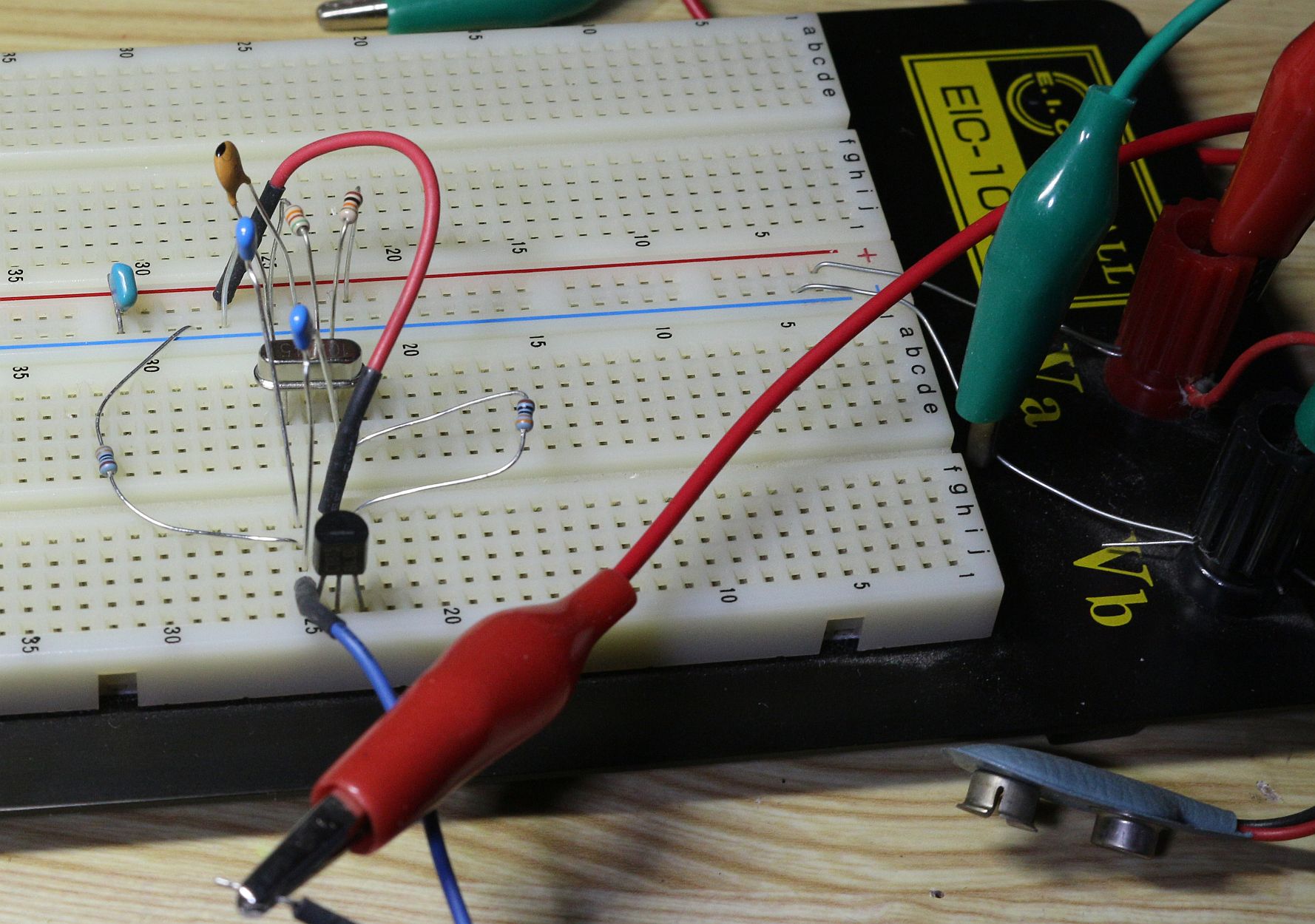 �����Ɣ��U�����B
�����Ɣ��U�����B
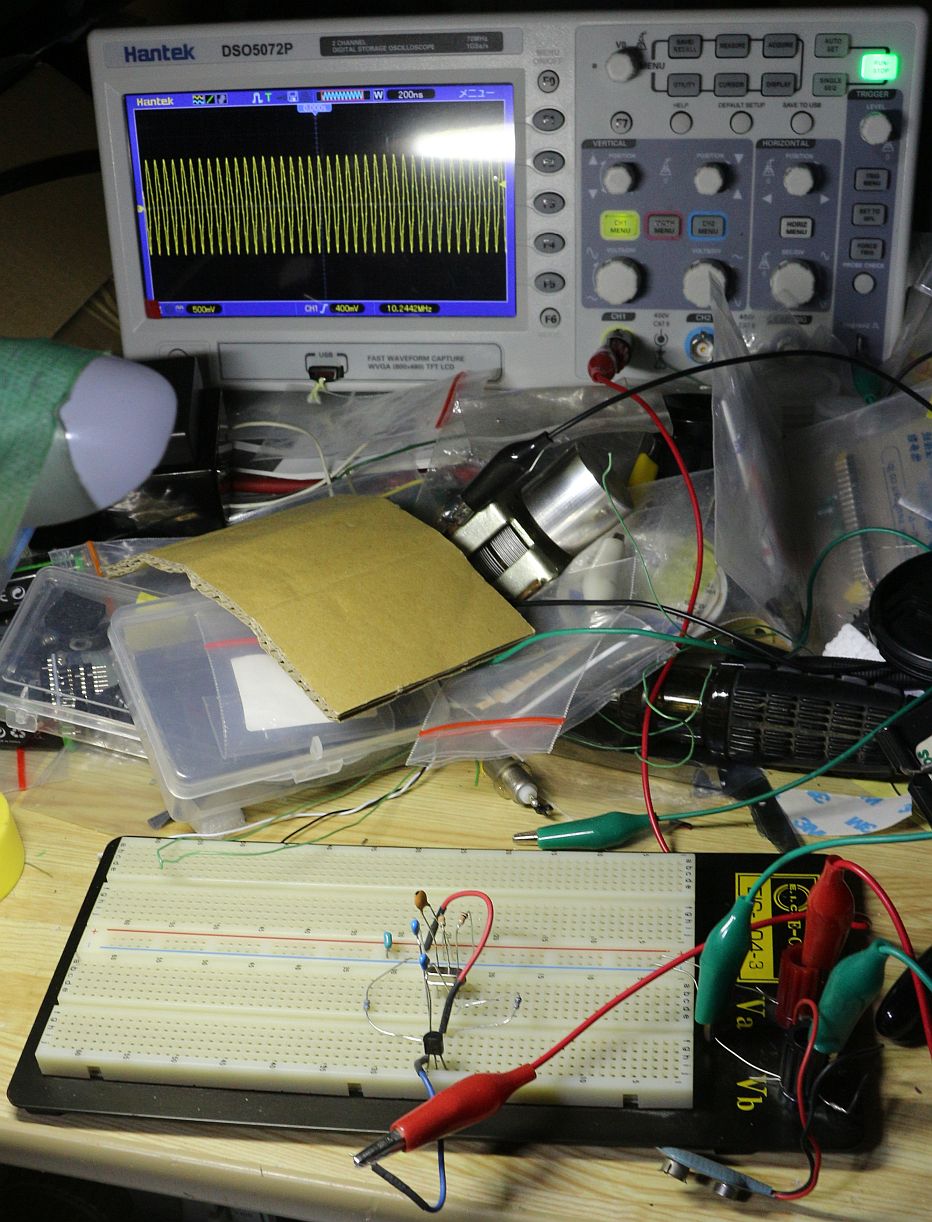 ���傢�Ώ̐��������O�p�g���ۂ��̂ŁA��̒��{�ɂ������Ă�̂����H
���傢�Ώ̐��������O�p�g���ۂ��̂ŁA��̒��{�ɂ������Ă�̂����H
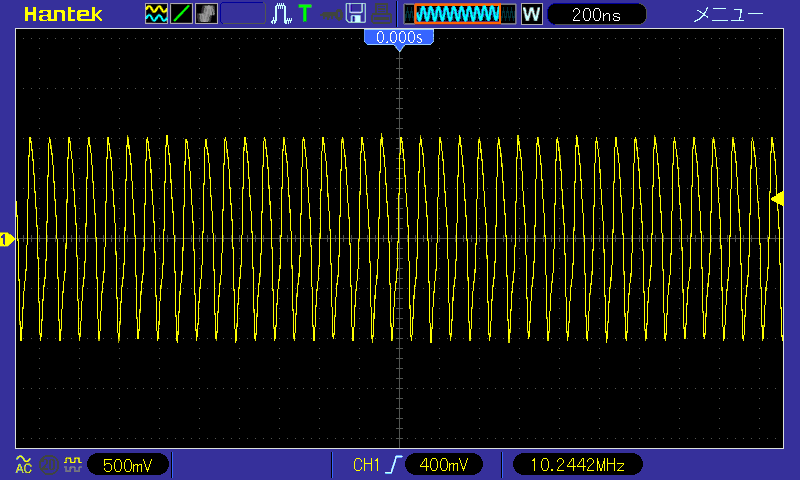 �|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���ɁA�g�����W�X�^�Ɍq����(FCZ)�R�C����LC�����g���̒ቺ���B
����́A����FCZ�R�C���̌�i�ɂ���g�����W�X�^�̃x�[�X�̗e�ʂ��e�����Ă����悤���B�B
FCZ�R�C�����g�����X�ɂ��Ă��A�������ĉe�����Ă���悤���B�B
�ȉ��̉��P�ŋ��U�̃Y�����������B���A��H�̕��i�������錋�ʂƂȂ����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���ɁA�g�����W�X�^�Ɍq����(FCZ)�R�C����LC�����g���̒ቺ���B
����́A����FCZ�R�C���̌�i�ɂ���g�����W�X�^�̃x�[�X�̗e�ʂ��e�����Ă����悤���B�B
FCZ�R�C�����g�����X�ɂ��Ă��A�������ĉe�����Ă���悤���B�B
�ȉ��̉��P�ŋ��U�̃Y�����������B���A��H�̕��i�������錋�ʂƂȂ����B
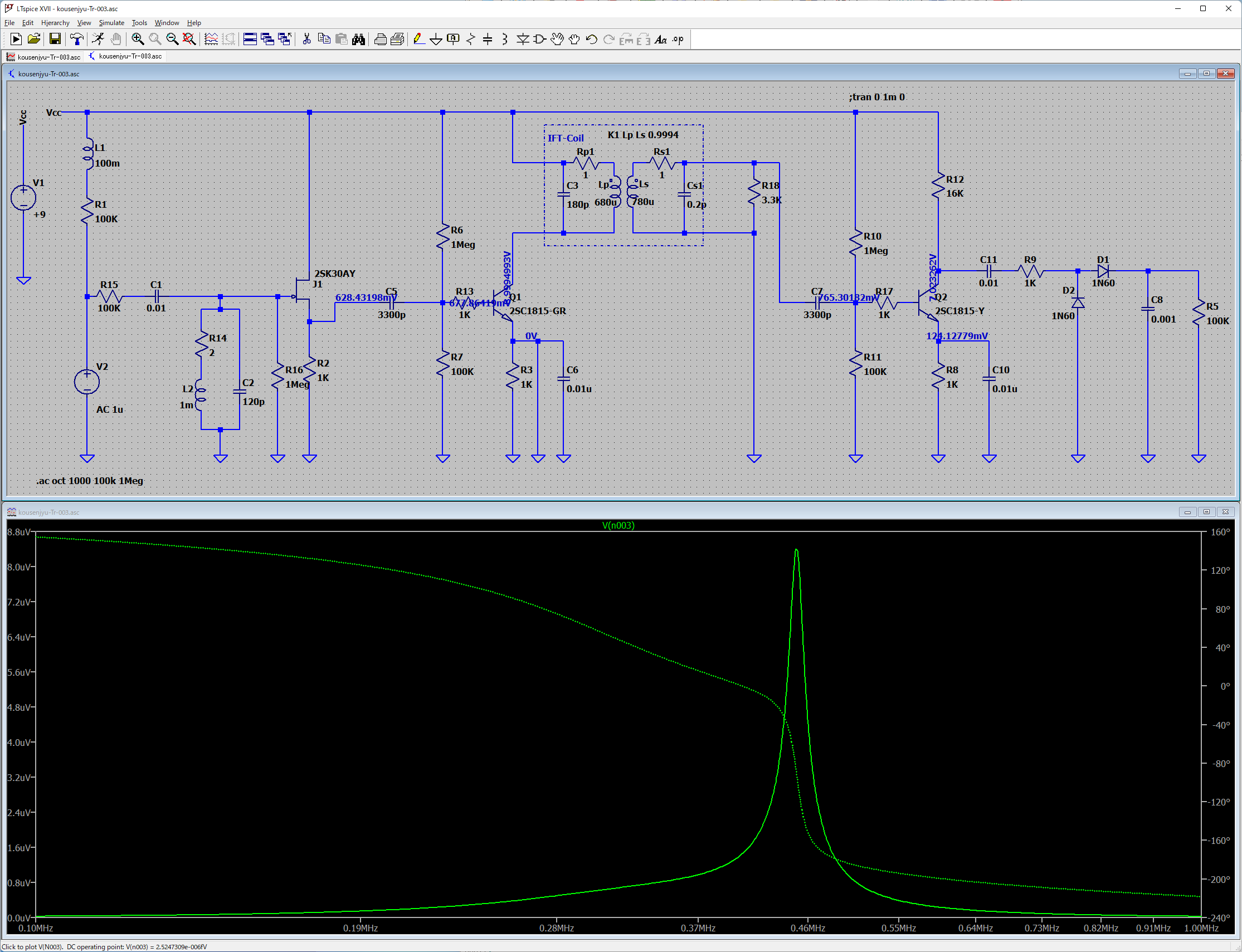 �������A�����g�ł́A�x�[�X�̒�R�ƃQ�[�g�̗e�ʂɂ���ĕ�������Q�C����������B
����āAFET�̉�H�ɂ��������ǂ��\���������B
���ۂ�455KHz����i��H�ł�FET�ɕς�����A���Ȃ���P�����B
(2SK303�ɂāA���܂�l�ĂȂ��������A��ŏ�������MOS-FET�Ɠ���̈悪�Ⴄ���낤�ɑ傫�����������B�s�v�c�B�\�[�X��GND�ɐڒn���Ă��邪�B���U�͂��₷���H)
�������A�����g�ł́A�x�[�X�̒�R�ƃQ�[�g�̗e�ʂɂ���ĕ�������Q�C����������B
����āAFET�̉�H�ɂ��������ǂ��\���������B
���ۂ�455KHz����i��H�ł�FET�ɕς�����A���Ȃ���P�����B
(2SK303�ɂāA���܂�l�ĂȂ��������A��ŏ�������MOS-FET�Ɠ���̈悪�Ⴄ���낤�ɑ傫�����������B�s�v�c�B�\�[�X��GND�ɐڒn���Ă��邪�B���U�͂��₷���H)
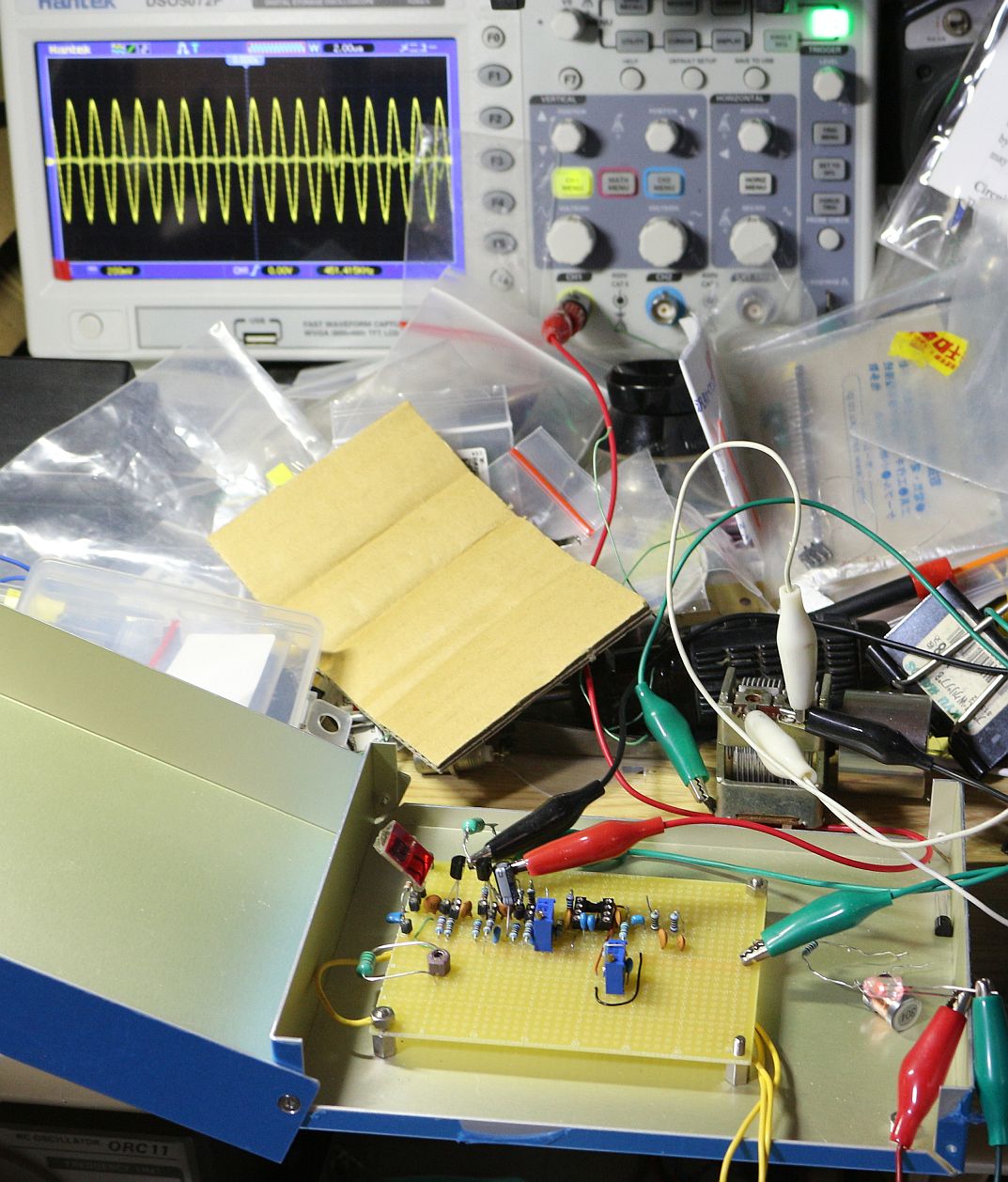 �Е�(1�i��)��Z�ϊ��Ȃ̂ŁA��i�����ł���Ȋ����B���Ȃ芴�x�A�b�v�����B
�o�C�|�[���[�g�����W�X�^�̓x�[�X�e�ʂ��o���Ȃ��B
�Ƃ����ꍇ�������̂�������Ȃ��̂�FET�D��̉\�����������B
30MHz���ƁA��͂�AVHF�p�J�X�P�[�h�ڑ���FET�A2SK439���~�����Ƃ��낾�Ǝv���Ă���B
LED�Ǝ˂��Č����Ƃ���A������2�i���x�ŁAIF�ɓ��ꂽ�����ǂ��Ƃ��������������B���̌�A10.7MHz�ȍ~�ő����Ƃ��������B455KHz�ł��ƃ��N�����m��Ȃ��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220303
���10mm�p��FCZ�R�C����IFT�̊�ւ̎��t���́A
��ƃR�C����M���ĂāA�h�����Ŋg��őΏ��͕s���������A
��45�x�ɌX�����DIP�K�i�̃��j�o�[�T����Ƀs�b�`�������R�g�������B
�ʕ����̎��t����������ƃY���Ă�̂łǂ��ɂ�����K�v�����邪�A�N��ƌ�����Ǝv���B
DBM�֓����L�����A�M���̓d���́A100mV�����肪�ǂ��݂����H
VR�œK�x�ɗ��Ƃ����Ǝv���B����g�Ȃ̂ŁA�C���s�[�_���X�͌��\�K�T�c�ł��ǂ��������B
455KHz����i��H�ŕ������ė������A�R�C����t����FET��2�i��������ƁA���Ȃ�̃Q�C���ɂȂ�́A�A
�P�[�X��߂Ȃ��Ƒ���ɔ��U����悤�Ȃ̂ŁA�g���}�[�R���f���T�[�Œ�������ۂ́A��ŃV�[���h���Ȃ������Ă���B�B
���̔��U�X���͔Y�܂�������ł���B�g�����X�\���ɂ�����AFET�̎�ނ�ς���Ή��P����̂��낤���H
���̌��̍��{����OP-AMP�́A�ǂ���ɂ��딭�U����̂Ŗ����ȗv�f�̂悤�ł���B
2�i��2.2mH��60pF�g���}�[�A3�i��3.3mH��60pF�g���}�[
60pF�͗e�ʂ������߂Ȃ̂�L���傫���Ȃ邵C�̕ω��ɃV�r�A�Ȃ̂ŁA���܂�I�X�X���ł͂Ȃ����c�A
(�O�ɁAL�͐U�����ʁAC�̓o�l�W���ɑ�������Ǝv����B�Ə������ʂ�ŁA�d���U���ɂȂ銴���H)
����i�ɂ͈����g���}�[�R���f���T�[�ƂȂ�Ƃ���Ȋ����B
�s�[�N�����Ȃ艸�₩�ȋC�����邪�A���݂���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�����e�̎�����Ȃǂɂ��ď����l�@�ŋl�߂�B
220304
FET�𒍕��AK439�~10�{K241�~2�A
�u�~�ؑ��Ɓv�Ƃ����g�R�B���݂Ɂu�~�ؑ��ƁA�U���v�Ƃ����������[�h���o�Ă���̂ŃA�����B�B
�����A
���Ŕ����ƕ]���͍����̂����邪�A������ɂ�͂肩�Ȃ�̃��X�N������B
�܂��A����ɓ����U���ł��ǂ����A�A�A
�s���z���K439�̏ꍇ������GSD�ŁAK241�̏ꍇDSG�A�ƂȂ�t�ł���̂ŁA���ӁB��������ꐫ�������ȁc�A
����2�͌݊���������ƐF�X�ȃg�R�ŏ�����Ă���BMOS-FET�Ȃ̂ŁA�ی삪�~�������AK241�̓c�G�i�[���������BK439�̕��͓�����H�������ĂȂ������B
���ӂ��ׂ��_�́A����FET�̓��ꐫ�B
Vgs-Ids�Ȑ��AMOS-FET�Ȃ̂����ACgs�Ƃ�Cds�Ƃ��ڍ��ԗe�ʂ������قǏ��Ȃ��悤���BCiss�Ƃ�Coss�Ƃ�������B
���ƁA�p���[�Q�C�����f�J���B
(2SK303��MOS-FET�Ɠ���̈悪�Ⴄ�̂ɑ傫�����������B�\�[�X��GND�ɐڒn���āB���U���₷�������B)
LTSpice�ŕ��ʂ�MOS-FET���f���̗e�ʂ��������ҏW������A�X�y�N�g���̖��͉����������A���������قږ����Ƃ�����肪�c���Ă���B
�����Ǝ��������Ηǂ��̂��������A���S�ɃV�~�����[�V������̉��P�ł����Ȃ����A����ȕ��i�������Ă邱�Ƃɂ͕ς��Ȃ��B
LTSpice�ł�����NPN�I�ԂƗǍD�Ȃ͖̂��ʂȓ����������悤�ŁA
945��1845���̃o�C�|�[���[��NPN�œ��o�͂̐Ód�e�ʂ�����������ꂾ���ŗǂ��̂��낤����ǁB�B
�x�[�X���̗͂e�ʂ̏��Ȃ����m���~�����B
�u���b�N�}���X�V�A006P��5V���M�����^���K�v�����A100mA�N���X����ʖڂ���������W���i�ɂȂ邾�낤�ȁB
�Е�(1�i��)��Z�ϊ��Ȃ̂ŁA��i�����ł���Ȋ����B���Ȃ芴�x�A�b�v�����B
�o�C�|�[���[�g�����W�X�^�̓x�[�X�e�ʂ��o���Ȃ��B
�Ƃ����ꍇ�������̂�������Ȃ��̂�FET�D��̉\�����������B
30MHz���ƁA��͂�AVHF�p�J�X�P�[�h�ڑ���FET�A2SK439���~�����Ƃ��낾�Ǝv���Ă���B
LED�Ǝ˂��Č����Ƃ���A������2�i���x�ŁAIF�ɓ��ꂽ�����ǂ��Ƃ��������������B���̌�A10.7MHz�ȍ~�ő����Ƃ��������B455KHz�ł��ƃ��N�����m��Ȃ��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220303
���10mm�p��FCZ�R�C����IFT�̊�ւ̎��t���́A
��ƃR�C����M���ĂāA�h�����Ŋg��őΏ��͕s���������A
��45�x�ɌX�����DIP�K�i�̃��j�o�[�T����Ƀs�b�`�������R�g�������B
�ʕ����̎��t����������ƃY���Ă�̂łǂ��ɂ�����K�v�����邪�A�N��ƌ�����Ǝv���B
DBM�֓����L�����A�M���̓d���́A100mV�����肪�ǂ��݂����H
VR�œK�x�ɗ��Ƃ����Ǝv���B����g�Ȃ̂ŁA�C���s�[�_���X�͌��\�K�T�c�ł��ǂ��������B
455KHz����i��H�ŕ������ė������A�R�C����t����FET��2�i��������ƁA���Ȃ�̃Q�C���ɂȂ�́A�A
�P�[�X��߂Ȃ��Ƒ���ɔ��U����悤�Ȃ̂ŁA�g���}�[�R���f���T�[�Œ�������ۂ́A��ŃV�[���h���Ȃ������Ă���B�B
���̔��U�X���͔Y�܂�������ł���B�g�����X�\���ɂ�����AFET�̎�ނ�ς���Ή��P����̂��낤���H
���̌��̍��{����OP-AMP�́A�ǂ���ɂ��딭�U����̂Ŗ����ȗv�f�̂悤�ł���B
2�i��2.2mH��60pF�g���}�[�A3�i��3.3mH��60pF�g���}�[
60pF�͗e�ʂ������߂Ȃ̂�L���傫���Ȃ邵C�̕ω��ɃV�r�A�Ȃ̂ŁA���܂�I�X�X���ł͂Ȃ����c�A
(�O�ɁAL�͐U�����ʁAC�̓o�l�W���ɑ�������Ǝv����B�Ə������ʂ�ŁA�d���U���ɂȂ銴���H)
����i�ɂ͈����g���}�[�R���f���T�[�ƂȂ�Ƃ���Ȋ����B
�s�[�N�����Ȃ艸�₩�ȋC�����邪�A���݂���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�����e�̎�����Ȃǂɂ��ď����l�@�ŋl�߂�B
220304
FET�𒍕��AK439�~10�{K241�~2�A
�u�~�ؑ��Ɓv�Ƃ����g�R�B���݂Ɂu�~�ؑ��ƁA�U���v�Ƃ����������[�h���o�Ă���̂ŃA�����B�B
�����A
���Ŕ����ƕ]���͍����̂����邪�A������ɂ�͂肩�Ȃ�̃��X�N������B
�܂��A����ɓ����U���ł��ǂ����A�A�A
�s���z���K439�̏ꍇ������GSD�ŁAK241�̏ꍇDSG�A�ƂȂ�t�ł���̂ŁA���ӁB��������ꐫ�������ȁc�A
����2�͌݊���������ƐF�X�ȃg�R�ŏ�����Ă���BMOS-FET�Ȃ̂ŁA�ی삪�~�������AK241�̓c�G�i�[���������BK439�̕��͓�����H�������ĂȂ������B
���ӂ��ׂ��_�́A����FET�̓��ꐫ�B
Vgs-Ids�Ȑ��AMOS-FET�Ȃ̂����ACgs�Ƃ�Cds�Ƃ��ڍ��ԗe�ʂ������قǏ��Ȃ��悤���BCiss�Ƃ�Coss�Ƃ�������B
���ƁA�p���[�Q�C�����f�J���B
(2SK303��MOS-FET�Ɠ���̈悪�Ⴄ�̂ɑ傫�����������B�\�[�X��GND�ɐڒn���āB���U���₷�������B)
LTSpice�ŕ��ʂ�MOS-FET���f���̗e�ʂ��������ҏW������A�X�y�N�g���̖��͉����������A���������قږ����Ƃ�����肪�c���Ă���B
�����Ǝ��������Ηǂ��̂��������A���S�ɃV�~�����[�V������̉��P�ł����Ȃ����A����ȕ��i�������Ă邱�Ƃɂ͕ς��Ȃ��B
LTSpice�ł�����NPN�I�ԂƗǍD�Ȃ͖̂��ʂȓ����������悤�ŁA
945��1845���̃o�C�|�[���[��NPN�œ��o�͂̐Ód�e�ʂ�����������ꂾ���ŗǂ��̂��낤����ǁB�B
�x�[�X���̗͂e�ʂ̏��Ȃ����m���~�����B
�u���b�N�}���X�V�A006P��5V���M�����^���K�v�����A100mA�N���X����ʖڂ���������W���i�ɂȂ邾�낤�ȁB
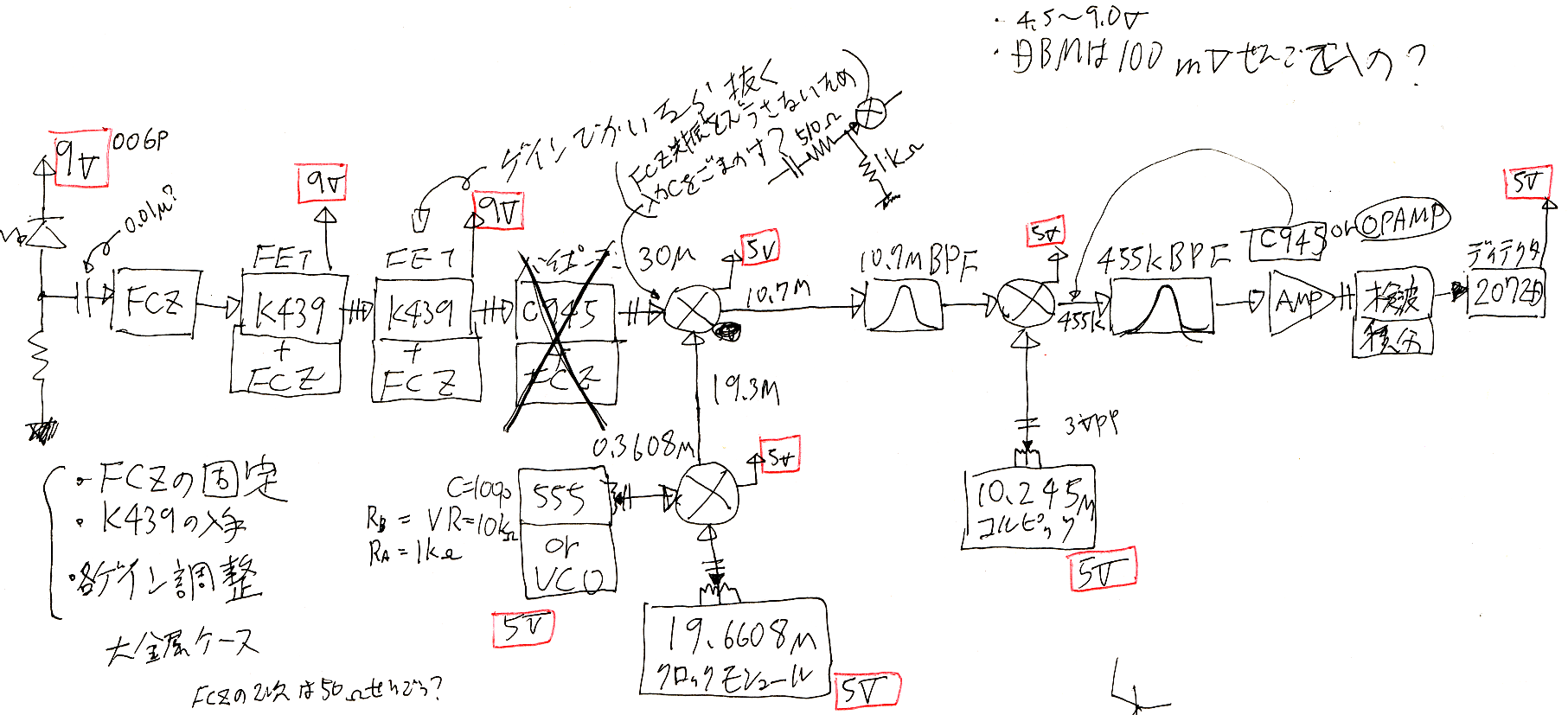 HF-VHF�ȗ̈�ŏ�������H�Ȃ̂ŁAZ�}�b�`���O�́A�قڗv��Ȃ����ȁH��H�����Ȃ�150MHz�܂ł͂���Ȋ����ōs���邩�ȁH
FET�̃\�[�X�Ɍq����Rs�́A���i100���A��i��220�����ǂ��݂����B
����́A�M�����x�ƃo�C�A�X����A�O�a��Ƒ������ƁA�m�C�Y�̉e�������邩�炩�ȁH�Ǝv���Ă���B
���Ƃ́ARF-AMP��IC��FCZ�R�C����g�ݍ��킹��Ƃ����邪�A���l�̖�肪�o�Ȃ��Ƃ͌���Ȃ��B
�P�[�X���傫���ƍ����t���̂ŁA�������������̂����P�[�X�ɂ����Ƃ��H
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�ȑO�A���[�U�[���ɂ��w�e���_�C�����v�́A�����g�͔��U���g���̐��x���v��Ȃ��̂�LC���U�ł��ǂ��Ə��������A
���ɁA��M�g�`�ɂ����܂肱�����͕K�v�Ȃ��B
����āAAGC-AMP�́A�P�ɒ���Ɍq���A�O�a�Řc�݂܂����ĂĂ��\��Ȃ��B����U�C���ł��ǂ��̂����B
�܂��A���܂����āA���U���Ȃ��f�q�͒������������A�܂��A�K�XLC�t�B���^�[�Ȃǂ�ʂ��Ζ���ł͂������݂����ł���B
�������A�ėp�������������߁A�t�B���^�[������VHF�̈��60dB��������̂ɂ͋�J�����L��������B
����͂���ȏ�ɑ啝�ȑ������K�v���B
�O��120dB�~�����Ə��������A���W�b�N��5V��TTL���x���ւ̊��Z�ŁA���g�Ȃǂ��猟�m���l�����0dBm���x���Ȃ�A100dB�I�[�_�[�Ȓ��x�ƂȂ�B
�M���������ł��邱�ƂƁA�t�B���^�[�����邱�ƂŁA������x���{���ɏo����Ƃ͎v���Ă��邯�ǁA�A
�܂��A���[�U�[�d�l�Ȃ̂ŃQ�C���̓\�R�܂ŗv��Ȃ��͎̂��������BLED�d�l���l���邩�ȁH
���[�U�[��ʂ��A�U�d�̑��w��BPF�͔��ɗL�������A����ΒP��30���A
�������Ⴍ���đ�ʂɍ��ΐ��S�~�����A�����������ō���ĒP���������āA3���Ƃ��ɂ͂Ȃ����B
���S�~�Ƃ́A�T�[���p�C���Ȃnj������Ȋ����B���ԊO�Ȃ̂ŁA�W���N�Z�����t�B�����Ȃ̂��낤���H
���w�n�̃t�H�gDi�͎���ʐς��L���ƁA�ڍ��e�ʂ��傫���āA�����g�Ɍ������A�m�C�Y���傫���Ȃ�B
�Ȃ̂ŁA�t�o�C�A�X�ŁA��R�w���L���A�e�ʂ������A�m�C�Y�����炷�B
�������A�ʐς��������Ǝ��̂́A������ʎ��̂������Ă��܂��B�����Ń����Y�ŏW������B
������ӂ̈Ĕz����肭�s���ĂȂ���w�͑��������B
���ɂ́A�Z���T�[�����Ɏ���̃v���A���v��݂��Ă����̂ŁA�O������m�C�Y�ɂ��m�C�X�ɋ��������B
�d�C(���d)�A�ꕔ�̕�������傪�����������߁A������A�d�q�H�w�͖�O�Ƃ�����ۂ������B
�������d�q���ł͂Ȃ��������A�ǂ��ɂ�����Ă����B
���^����ꂽ�ۑ�ɑ��ėD�G�ł��A���ӎ�������Ȃ��Ɣ��W�͓���B
�����A������ꂽ��A����͊��Ɋ������ł��邩��B�D�G���E���̃��m�B�ɂ��������čs�����̂Œ��ӁB
�ނ�ɂƂ��Ċ������́A�����ɓ��R�̃��m�ƂȂ�B�������������킯�ł������̂ɂȁB�B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220305
�܂��́AMOS-FET���g�������������B
HF-VHF�ȗ̈�ŏ�������H�Ȃ̂ŁAZ�}�b�`���O�́A�قڗv��Ȃ����ȁH��H�����Ȃ�150MHz�܂ł͂���Ȋ����ōs���邩�ȁH
FET�̃\�[�X�Ɍq����Rs�́A���i100���A��i��220�����ǂ��݂����B
����́A�M�����x�ƃo�C�A�X����A�O�a��Ƒ������ƁA�m�C�Y�̉e�������邩�炩�ȁH�Ǝv���Ă���B
���Ƃ́ARF-AMP��IC��FCZ�R�C����g�ݍ��킹��Ƃ����邪�A���l�̖�肪�o�Ȃ��Ƃ͌���Ȃ��B
�P�[�X���傫���ƍ����t���̂ŁA�������������̂����P�[�X�ɂ����Ƃ��H
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�ȑO�A���[�U�[���ɂ��w�e���_�C�����v�́A�����g�͔��U���g���̐��x���v��Ȃ��̂�LC���U�ł��ǂ��Ə��������A
���ɁA��M�g�`�ɂ����܂肱�����͕K�v�Ȃ��B
����āAAGC-AMP�́A�P�ɒ���Ɍq���A�O�a�Řc�݂܂����ĂĂ��\��Ȃ��B����U�C���ł��ǂ��̂����B
�܂��A���܂����āA���U���Ȃ��f�q�͒������������A�܂��A�K�XLC�t�B���^�[�Ȃǂ�ʂ��Ζ���ł͂������݂����ł���B
�������A�ėp�������������߁A�t�B���^�[������VHF�̈��60dB��������̂ɂ͋�J�����L��������B
����͂���ȏ�ɑ啝�ȑ������K�v���B
�O��120dB�~�����Ə��������A���W�b�N��5V��TTL���x���ւ̊��Z�ŁA���g�Ȃǂ��猟�m���l�����0dBm���x���Ȃ�A100dB�I�[�_�[�Ȓ��x�ƂȂ�B
�M���������ł��邱�ƂƁA�t�B���^�[�����邱�ƂŁA������x���{���ɏo����Ƃ͎v���Ă��邯�ǁA�A
�܂��A���[�U�[�d�l�Ȃ̂ŃQ�C���̓\�R�܂ŗv��Ȃ��͎̂��������BLED�d�l���l���邩�ȁH
���[�U�[��ʂ��A�U�d�̑��w��BPF�͔��ɗL�������A����ΒP��30���A
�������Ⴍ���đ�ʂɍ��ΐ��S�~�����A�����������ō���ĒP���������āA3���Ƃ��ɂ͂Ȃ����B
���S�~�Ƃ́A�T�[���p�C���Ȃnj������Ȋ����B���ԊO�Ȃ̂ŁA�W���N�Z�����t�B�����Ȃ̂��낤���H
���w�n�̃t�H�gDi�͎���ʐς��L���ƁA�ڍ��e�ʂ��傫���āA�����g�Ɍ������A�m�C�Y���傫���Ȃ�B
�Ȃ̂ŁA�t�o�C�A�X�ŁA��R�w���L���A�e�ʂ������A�m�C�Y�����炷�B
�������A�ʐς��������Ǝ��̂́A������ʎ��̂������Ă��܂��B�����Ń����Y�ŏW������B
������ӂ̈Ĕz����肭�s���ĂȂ���w�͑��������B
���ɂ́A�Z���T�[�����Ɏ���̃v���A���v��݂��Ă����̂ŁA�O������m�C�Y�ɂ��m�C�X�ɋ��������B
�d�C(���d)�A�ꕔ�̕�������傪�����������߁A������A�d�q�H�w�͖�O�Ƃ�����ۂ������B
�������d�q���ł͂Ȃ��������A�ǂ��ɂ�����Ă����B
���^����ꂽ�ۑ�ɑ��ėD�G�ł��A���ӎ�������Ȃ��Ɣ��W�͓���B
�����A������ꂽ��A����͊��Ɋ������ł��邩��B�D�G���E���̃��m�B�ɂ��������čs�����̂Œ��ӁB
�ނ�ɂƂ��Ċ������́A�����ɓ��R�̃��m�ƂȂ�B�������������킯�ł������̂ɂȁB�B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220305
�܂��́AMOS-FET���g�������������B
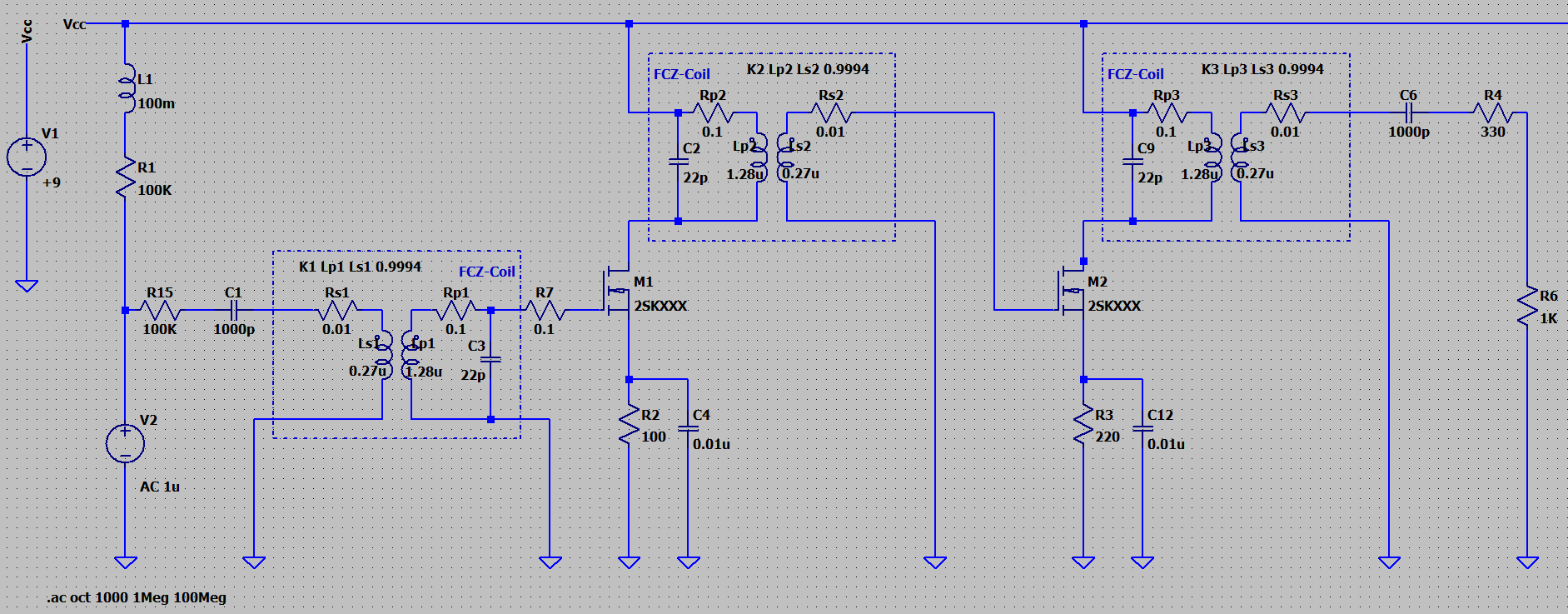 �����ŁA1�^�₪�o�����B
LTSpice�̃V�~�����[�V�����ł́AFCZ�R�C���̃g�����X�̌�i�ɗe�ʂ̂���o�C�|�[���[�g�����W�X�^�[�̃x�[�X���q���ƁA
�g�����X������A���ڌq���ł�̂Ɠ������A���U���g�����ቺ���āA�s�����݂�B
���A�G���Ō���ƁA
���ۂ̖����@�Ȃǂ̉�H�ł́A�o�C�|�[���[�g�����W�X�^���g�����X�̌�i�Ɍq���ŁA��肪�����悤�ł���B
�܂�A�g�����X�̐�͋��U�n�ɂ��܂�֗^�����A
�V�~�����[�^�[�̃g�����X���f�����ȑf������ƌ������Ƃ����m��Ȃ��B
(����Ȃ��ƁA�����@�Ȃ�āAANT��P�[�u���ŋ��U���g�����Y���Ă��܂����˂Ȃ��B)
�t�Ɍ����AMOS-FET���g���A�g�����X�ŕ����Ȃ��Ă��ǂ��̂����m��Ȃ��B
�R�C�����芪������ɂ͂��肪������������Ȃ��B
�Ȃ�A���i���ʂ�FET��Z�ϊ��˃o�C�|�[���[2�i�ł�OK�����m��Ȃ��B
�����ŁA1�^�₪�o�����B
LTSpice�̃V�~�����[�V�����ł́AFCZ�R�C���̃g�����X�̌�i�ɗe�ʂ̂���o�C�|�[���[�g�����W�X�^�[�̃x�[�X���q���ƁA
�g�����X������A���ڌq���ł�̂Ɠ������A���U���g�����ቺ���āA�s�����݂�B
���A�G���Ō���ƁA
���ۂ̖����@�Ȃǂ̉�H�ł́A�o�C�|�[���[�g�����W�X�^���g�����X�̌�i�Ɍq���ŁA��肪�����悤�ł���B
�܂�A�g�����X�̐�͋��U�n�ɂ��܂�֗^�����A
�V�~�����[�^�[�̃g�����X���f�����ȑf������ƌ������Ƃ����m��Ȃ��B
(����Ȃ��ƁA�����@�Ȃ�āAANT��P�[�u���ŋ��U���g�����Y���Ă��܂����˂Ȃ��B)
�t�Ɍ����AMOS-FET���g���A�g�����X�ŕ����Ȃ��Ă��ǂ��̂����m��Ȃ��B
�R�C�����芪������ɂ͂��肪������������Ȃ��B
�Ȃ�A���i���ʂ�FET��Z�ϊ��˃o�C�|�[���[2�i�ł�OK�����m��Ȃ��B
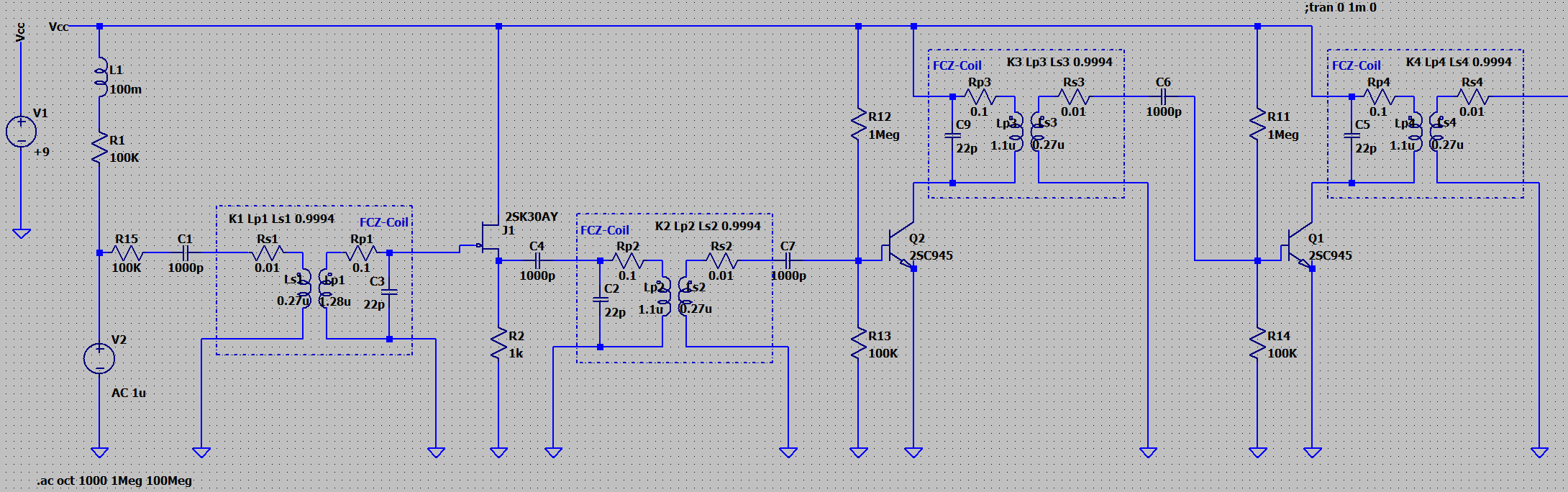 ���i����������B
�Ƃ���ŁAVHF�ō���ш�ƂȂ�ƁA150MHz��144MHz��FCZ�R�C�����g����̂ŁA���̒��x���܂�����B
�R�C���̎芪���ȂǂȂ�A200�`300MHz�܂ŃC�P�邩������Ȃ����A�A����ȏ��UHF�ŁA���Ȃ�l�����ς���Ă���Ǝv���B
���ƁA�N���b�N���W�����[�^�[�B�R���s�b�c��H���̐M�����x������DBM�p�̓K���l100mVrms���x�ɗ��Ƃ��ɂ́A
�Œ��R10K���Ȃ����ƒ���ɒP��]���Œ��R500���ōs����Ǝv���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
FET���͂����B
455KHz����i��H�ɂāA2SK439�������B
Tr�����ōl����ƃp���[�Q�C���́A��i��60dB�ƂȂ�悤�����A���X���A�����낤���ǁA���n�ł��A���B
�E��H���O�ɔ����o�����ƁA��͂�2�i�ڂŔ��U�͂���B
�E�������A�P�[�X���ŁA���p�ȉ�H�̔��U���ۂ͎~�߂₷���B�h���C���ɐڑ�����Ă�LC�̕���̓g�����X�\���ɂȂ��Ă��Ȃ����A���U�̃s�[�N�͂��Ȃ艸�₩�B
�E���̏�Ԃł́A�Q�C��������Ȃ��B
�Q�C�����~�������ǁA�m�C�Y�┭�U�͔��������B
���ɁA���U�͋C�ɂȂ�Ƃ���ł͂���B
��̐U�����z���C�g�m�C�Y���ł���A���ꂪ���U��H����N����Ă�Ƃ��A���̂��낤���H
IF�t�B���^�[��t������A�g�����X�\���ɂ���ǂ��Ȃ邩�H
���ϒ��̒P���p���X�ł͂Ȃ��A�M�����悹��A������x���U���Ă��Ă����ʂ��ēǂݎ���Ǝv�����A��H���܂����G�ɂȂ邵�A�p���X�̎��Ԃ������K�v�B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
455KHz����i��H�A
Z�ϊ���A2�i�ڂ�FET��IFT�R�C���������B��FCZ�R�C���Ɠ��������ŁB
�܂�A�g�����X�`���ɂȂ����B(���̎��̒i�͂��Ƃ̂܂�܁A�A)
���i����������B
�Ƃ���ŁAVHF�ō���ш�ƂȂ�ƁA150MHz��144MHz��FCZ�R�C�����g����̂ŁA���̒��x���܂�����B
�R�C���̎芪���ȂǂȂ�A200�`300MHz�܂ŃC�P�邩������Ȃ����A�A����ȏ��UHF�ŁA���Ȃ�l�����ς���Ă���Ǝv���B
���ƁA�N���b�N���W�����[�^�[�B�R���s�b�c��H���̐M�����x������DBM�p�̓K���l100mVrms���x�ɗ��Ƃ��ɂ́A
�Œ��R10K���Ȃ����ƒ���ɒP��]���Œ��R500���ōs����Ǝv���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
FET���͂����B
455KHz����i��H�ɂāA2SK439�������B
Tr�����ōl����ƃp���[�Q�C���́A��i��60dB�ƂȂ�悤�����A���X���A�����낤���ǁA���n�ł��A���B
�E��H���O�ɔ����o�����ƁA��͂�2�i�ڂŔ��U�͂���B
�E�������A�P�[�X���ŁA���p�ȉ�H�̔��U���ۂ͎~�߂₷���B�h���C���ɐڑ�����Ă�LC�̕���̓g�����X�\���ɂȂ��Ă��Ȃ����A���U�̃s�[�N�͂��Ȃ艸�₩�B
�E���̏�Ԃł́A�Q�C��������Ȃ��B
�Q�C�����~�������ǁA�m�C�Y�┭�U�͔��������B
���ɁA���U�͋C�ɂȂ�Ƃ���ł͂���B
��̐U�����z���C�g�m�C�Y���ł���A���ꂪ���U��H����N����Ă�Ƃ��A���̂��낤���H
IF�t�B���^�[��t������A�g�����X�\���ɂ���ǂ��Ȃ邩�H
���ϒ��̒P���p���X�ł͂Ȃ��A�M�����悹��A������x���U���Ă��Ă����ʂ��ēǂݎ���Ǝv�����A��H���܂����G�ɂȂ邵�A�p���X�̎��Ԃ������K�v�B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
455KHz����i��H�A
Z�ϊ���A2�i�ڂ�FET��IFT�R�C���������B��FCZ�R�C���Ɠ��������ŁB
�܂�A�g�����X�`���ɂȂ����B(���̎��̒i�͂��Ƃ̂܂�܁A�A)
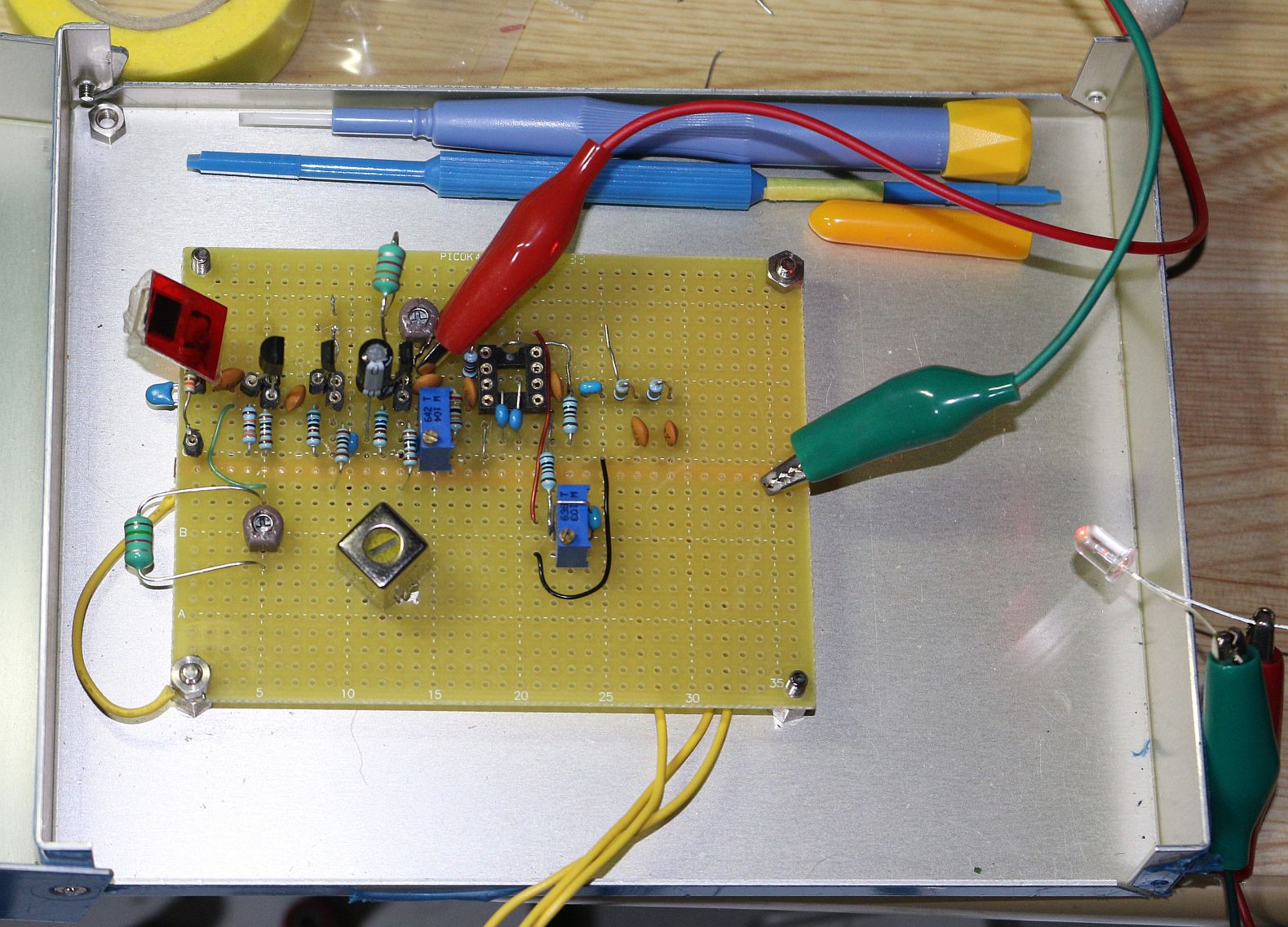 �z�������Ȃ�����Ă���薳���̂͒��g�̗ǂ��Ƃ���B
�t�^���J���Ă�Ɣ��U�͂��邪�B
�߂�Ƃ��Ȃ�̃X�g�b�v�o���h������悤�ŗ��Ƃ����B�܂�A�s�����U��(BPF)�ɂȂ�B
�����ALTSpice�ł̌��ʂƂ��Ȃ�Ⴄ�B�R�C���̓�����H�̃��f�����O�ɂ�鍷���Ǝv���B
������i�����A�c�o����̂��H
�����A����������ƃQ�C�����~�����B
��̒i���g�����X�`���ɂ���A��薳���o����̂����m��Ȃ����c�A
�Z���~�b�NIF�t�B���^�[�̌�ɂ��A���v���g���B�B
�����V���b�g�g���K�[�ŐM���̋��U�̗����オ������ׂ����B
�ŁA�I�V���[�^�[����A555�̔������j�b�g�ɐ�ւ��A�p���X���o���B
�z�������Ȃ�����Ă���薳���̂͒��g�̗ǂ��Ƃ���B
�t�^���J���Ă�Ɣ��U�͂��邪�B
�߂�Ƃ��Ȃ�̃X�g�b�v�o���h������悤�ŗ��Ƃ����B�܂�A�s�����U��(BPF)�ɂȂ�B
�����ALTSpice�ł̌��ʂƂ��Ȃ�Ⴄ�B�R�C���̓�����H�̃��f�����O�ɂ�鍷���Ǝv���B
������i�����A�c�o����̂��H
�����A����������ƃQ�C�����~�����B
��̒i���g�����X�`���ɂ���A��薳���o����̂����m��Ȃ����c�A
�Z���~�b�NIF�t�B���^�[�̌�ɂ��A���v���g���B�B
�����V���b�g�g���K�[�ŐM���̋��U�̗����オ������ׂ����B
�ŁA�I�V���[�^�[����A555�̔������j�b�g�ɐ�ւ��A�p���X���o���B
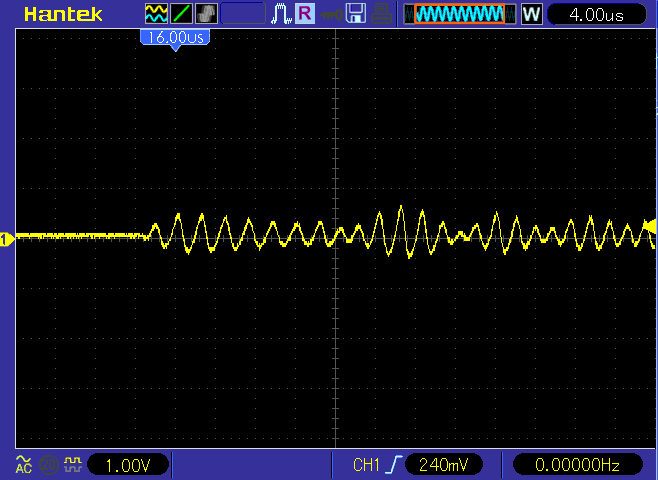 �U���J�n�̏����́A���傢�����Ă��Ȃ�݂����Ȃ̂��o��݂����B�A���ŏo���Ɩ�薳���B
������H��ς���ƁA�Z���p���X�ƂȂ�̂ŁALED�ł͓d���͌��\�҂����肵�܂����A
��������A������������LED���ꂵ���˂Ȃ��̂ŁA���͎g���Ă���܂���B
30MHz��FCZ�R�C�����ƁA���U�̏�Ԃ́A�܂��A���Ȃ�ς���Ă������ɂ��v���B
�Ƃ������ƂŁA455KHz����i��H�͂�����ł�����x�̓������o������������B
���Ƃ́A�����ƌ@�艺����邩�H�ǂ����邩�c�A�A
IFT�R�C���𑝂₵�āA�Q�C�����グ�āA����������ƘM���Č��������A�A�A
�����̎g�p�������A���Ȃ̂ŁA
���Ԃ�҂��āc�A���̉ۑ�����������B
���ƁA
Spice�ɂ�郌�[�U�[�_�C�I�[�h�̃V��������Ă݂����Ƃ͎v���Ă���B
LD�̃��f��������̂����A2�[�q�̃��m�ƁA3�[�q�ɂ܂Ƃ߂��Ă�̂ŁA�ǂ���ǂ����邩�������B
�G���Ƃ͎�ɁA1987�N�̏����̂������̋L�����Q�l�ɂ��Ă���B
(���Ƃ́A������g���Z�A�G�����C�H�Ƃ����邪�A�A)
�E�`�ɂ���{�͊F�Â����m�B�B
�㔼�̓����`�b�vIC�𑽗p���郂�m�������������A
1980�N�㏉���Ƃ��Ȃ��Ă���ƁA�^��ǂ������B�㔼��MSX�Ȃǃ}�C�R���A�����̏\�N�Ƃ��������ŃA���B�B
IBM5100�͂������ɃA�������A�AMZ-700�Ƃ��͌Â����ɓ��邾�낤�B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220306
�L�ш��M�@�́AAOR�́uAR-3000A�v�̊��x�ׂČ����B
�ō���0.25��V�ł�������1��V���x�A���B
�ȑO���Z�����̂��A5��V������A�I�[�_�[�͍����Ă���B
0.25��V�́A�M����������Ȃ��M���M�����낤����A��쓮�����������ɂ́A��͂�2�`3��V���v�������Ǝv���B
�����@�A�u�A�C�R����IC-R9500�v�ł́A�Ⴍ�ă}�C�i�X�\��dB�ʂƂ������ƂŁA0dB��=1��V�Ȃ̂ŁA���܂�卷�͖��������B
dBm�͓d�͂Ȃ̂ł����AdB�ʂ͓d���Ƃ�������킵��������܂��B
5V�ɏグ��Ƃ���ƁA�Q�C����120dB�A0dBm����100dB�Ȃ̂��K�v���ƌ����Ƃ���������
�ȑO���Z�����\�z�ƑS���ς��Ȃ��悤�ɂɂȂ��Ă����B
�ƂȂ�ƁA�����i3�i�ɁA���̌�A1�i���x���ȁH
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
IC-R9500�̂��̑��̎d�l�B
��M���� HF:�g���v���X�[�p�[�w�e���_�C������
V/UHF:�N���b�h�X�[�p�[�w�e���_�C������
���Ԏ��g�� HF��
��� 58.7MHz�A ��� 10.7MHz�A ��O 48kHz
V/UHF��
��� 278.7/778.7MHz�A ��� 58.7MHz�A��O 10.7MHz�A ��l 48kHz
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
455KHz�ł͂Ȃ��A48KHz�����āc�B
��܂��Ȍ��܂�͂��邪�A���[�J�[�ɂ���ėl�X�ɐݒ肵�Ă�悤�Ȃ̂ŁA
�����A
�s�̃p�[�c������A�m��I�Ȃ̂́A10.7MHz��455KHz��450KHz�����܂�B
�L�ш悶�ᖳ����A�������V���v���Ƀ^�[�Q�b�g���_����̂ŁA�����č����x�̂͂���Ǝv���B
�ŁA���̊��x�̑��ɁA�t�H�gDi�̏W���\�͂�����A
����ʐς��傫���ƁA�V�O�i���͏オ�邪�A����������������A�m�C�Y��������B
�Ȃ̂ŁA������x�̖ʐςŃ����Y���g���B���ɍ����g�͋t�o�C�A�X��������ɂ��e�ʒቺ�Ɍ��x���A���B
��͂�A���Ԏ��g���ɂ��Ă��瑝�����J��Ԃ���������悤���B
�i���[FM��M�@�́A�ш悪����455KHz��IF�͎g��Ȃ��H�ł�����L���ł͎g���Ă���B
AM�p�Ə����Ă��邱�Ƃ͂���B
�N���X�^���̃R���s�b�c���U��H�́A���O�̕������N���ƍl���đg��ł݂��B
���O�ւ̔��c�t���́A�M���g���₷�����߁A�N���X�^���ւ̔M������邽�߁A���߂ɂ��āA�q�[�g�N���b�v���g�����B
�U���J�n�̏����́A���傢�����Ă��Ȃ�݂����Ȃ̂��o��݂����B�A���ŏo���Ɩ�薳���B
������H��ς���ƁA�Z���p���X�ƂȂ�̂ŁALED�ł͓d���͌��\�҂����肵�܂����A
��������A������������LED���ꂵ���˂Ȃ��̂ŁA���͎g���Ă���܂���B
30MHz��FCZ�R�C�����ƁA���U�̏�Ԃ́A�܂��A���Ȃ�ς���Ă������ɂ��v���B
�Ƃ������ƂŁA455KHz����i��H�͂�����ł�����x�̓������o������������B
���Ƃ́A�����ƌ@�艺����邩�H�ǂ����邩�c�A�A
IFT�R�C���𑝂₵�āA�Q�C�����グ�āA����������ƘM���Č��������A�A�A
�����̎g�p�������A���Ȃ̂ŁA
���Ԃ�҂��āc�A���̉ۑ�����������B
���ƁA
Spice�ɂ�郌�[�U�[�_�C�I�[�h�̃V��������Ă݂����Ƃ͎v���Ă���B
LD�̃��f��������̂����A2�[�q�̃��m�ƁA3�[�q�ɂ܂Ƃ߂��Ă�̂ŁA�ǂ���ǂ����邩�������B
�G���Ƃ͎�ɁA1987�N�̏����̂������̋L�����Q�l�ɂ��Ă���B
(���Ƃ́A������g���Z�A�G�����C�H�Ƃ����邪�A�A)
�E�`�ɂ���{�͊F�Â����m�B�B
�㔼�̓����`�b�vIC�𑽗p���郂�m�������������A
1980�N�㏉���Ƃ��Ȃ��Ă���ƁA�^��ǂ������B�㔼��MSX�Ȃǃ}�C�R���A�����̏\�N�Ƃ��������ŃA���B�B
IBM5100�͂������ɃA�������A�AMZ-700�Ƃ��͌Â����ɓ��邾�낤�B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220306
�L�ш��M�@�́AAOR�́uAR-3000A�v�̊��x�ׂČ����B
�ō���0.25��V�ł�������1��V���x�A���B
�ȑO���Z�����̂��A5��V������A�I�[�_�[�͍����Ă���B
0.25��V�́A�M����������Ȃ��M���M�����낤����A��쓮�����������ɂ́A��͂�2�`3��V���v�������Ǝv���B
�����@�A�u�A�C�R����IC-R9500�v�ł́A�Ⴍ�ă}�C�i�X�\��dB�ʂƂ������ƂŁA0dB��=1��V�Ȃ̂ŁA���܂�卷�͖��������B
dBm�͓d�͂Ȃ̂ł����AdB�ʂ͓d���Ƃ�������킵��������܂��B
5V�ɏグ��Ƃ���ƁA�Q�C����120dB�A0dBm����100dB�Ȃ̂��K�v���ƌ����Ƃ���������
�ȑO���Z�����\�z�ƑS���ς��Ȃ��悤�ɂɂȂ��Ă����B
�ƂȂ�ƁA�����i3�i�ɁA���̌�A1�i���x���ȁH
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
IC-R9500�̂��̑��̎d�l�B
��M���� HF:�g���v���X�[�p�[�w�e���_�C������
V/UHF:�N���b�h�X�[�p�[�w�e���_�C������
���Ԏ��g�� HF��
��� 58.7MHz�A ��� 10.7MHz�A ��O 48kHz
V/UHF��
��� 278.7/778.7MHz�A ��� 58.7MHz�A��O 10.7MHz�A ��l 48kHz
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
455KHz�ł͂Ȃ��A48KHz�����āc�B
��܂��Ȍ��܂�͂��邪�A���[�J�[�ɂ���ėl�X�ɐݒ肵�Ă�悤�Ȃ̂ŁA
�����A
�s�̃p�[�c������A�m��I�Ȃ̂́A10.7MHz��455KHz��450KHz�����܂�B
�L�ш悶�ᖳ����A�������V���v���Ƀ^�[�Q�b�g���_����̂ŁA�����č����x�̂͂���Ǝv���B
�ŁA���̊��x�̑��ɁA�t�H�gDi�̏W���\�͂�����A
����ʐς��傫���ƁA�V�O�i���͏オ�邪�A����������������A�m�C�Y��������B
�Ȃ̂ŁA������x�̖ʐςŃ����Y���g���B���ɍ����g�͋t�o�C�A�X��������ɂ��e�ʒቺ�Ɍ��x���A���B
��͂�A���Ԏ��g���ɂ��Ă��瑝�����J��Ԃ���������悤���B
�i���[FM��M�@�́A�ш悪����455KHz��IF�͎g��Ȃ��H�ł�����L���ł͎g���Ă���B
AM�p�Ə����Ă��邱�Ƃ͂���B
�N���X�^���̃R���s�b�c���U��H�́A���O�̕������N���ƍl���đg��ł݂��B
���O�ւ̔��c�t���́A�M���g���₷�����߁A�N���X�^���ւ̔M������邽�߁A���߂ɂ��āA�q�[�g�N���b�v���g�����B
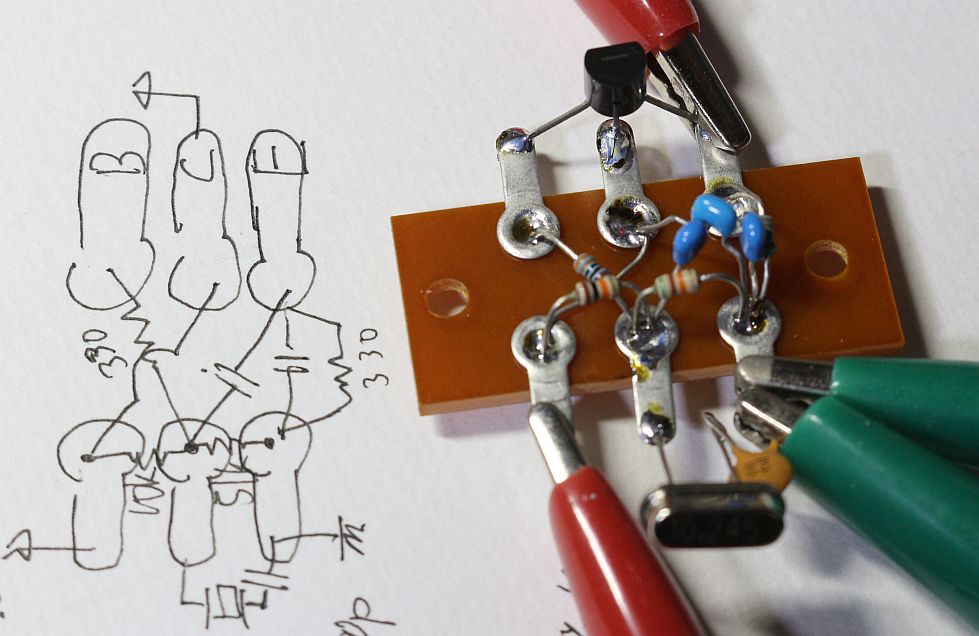 ���������̂��������B
�芪�����g���āADIP�\�P�b�g�Ƀn�}��B
���������̂��������B
�芪�����g���āADIP�\�P�b�g�Ƀn�}��B
 ��������߂Ȃ̂ŁA200MHz���x�̍����g�܂łȂ�Ή��o�������B
��0.1mm���C���[50m�Ƌ��ɒ������Ă݂��B
��������߂Ȃ̂ŁA200MHz���x�̍����g�܂łȂ�Ή��o�������B
��0.1mm���C���[50m�Ƌ��ɒ������Ă݂��B
 �o���R�������������A�A
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���Ƃ́A555����̂���������̂ł͍����g�������̂Ńt�B���^�[��K�v�Ƃ��邩�A�o���L���b�vDi�ɂ��VFO���ȁ[�Ɩ����Ă銴���B
555���ƁARC��LC�t�B���^�[���ȁH
���Ƃ́ALD���U���A�����gLED�Ń`�F�b�N�o���Ȃ����Ǝv���Ă���B
�����P�[�X���B�B�����������ށB
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�܂��A����́A����ɏ������Ƃɂ��悤�B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220307
�s���z�u�I�ɁAIFT�R�C����1�����̓d�������Ă����݂����B
2�����͊����������Ȃ�1/30�Ƃ��ɂȂ�̂Ŕ��ɒႢ�l�ɂȂ邱�ƂɂȂ�B�B
2:1���x�̊��������FCZ�R�C���̑�p�ɂ͂Ȃ�Ȃ��݂����B
�ƂȂ�ƁA1�����̃Z���^�[�^�b�v��p������肢�z�����K�v�ɂȂ邩���A�A
�����ǁA���̒[�q�̓Z���^�[���ᖳ�����A�d�l���̂����ꂷ����IFT�R�C���Ȃ̂ŁA�A�A�B
���Ƃ́A�o�C�A�X�Ƃ̌��ˍ����B�����邯�ǁA����i�ł́A�����܂łƂ����C�������B
�܂��A1MHz�p��FCZ�R�C�����g���邩�������B�B
455KHz����i��H�̌��ؒi�K�ŁA30MHz�̉�H�͏�����ɂ��A��U��Ƃ𒆒f����B
�\�z�͂���Ȋ����������B
�o���R�������������A�A
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���Ƃ́A555����̂���������̂ł͍����g�������̂Ńt�B���^�[��K�v�Ƃ��邩�A�o���L���b�vDi�ɂ��VFO���ȁ[�Ɩ����Ă銴���B
555���ƁARC��LC�t�B���^�[���ȁH
���Ƃ́ALD���U���A�����gLED�Ń`�F�b�N�o���Ȃ����Ǝv���Ă���B
�����P�[�X���B�B�����������ށB
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�܂��A����́A����ɏ������Ƃɂ��悤�B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220307
�s���z�u�I�ɁAIFT�R�C����1�����̓d�������Ă����݂����B
2�����͊����������Ȃ�1/30�Ƃ��ɂȂ�̂Ŕ��ɒႢ�l�ɂȂ邱�ƂɂȂ�B�B
2:1���x�̊��������FCZ�R�C���̑�p�ɂ͂Ȃ�Ȃ��݂����B
�ƂȂ�ƁA1�����̃Z���^�[�^�b�v��p������肢�z�����K�v�ɂȂ邩���A�A
�����ǁA���̒[�q�̓Z���^�[���ᖳ�����A�d�l���̂����ꂷ����IFT�R�C���Ȃ̂ŁA�A�A�B
���Ƃ́A�o�C�A�X�Ƃ̌��ˍ����B�����邯�ǁA����i�ł́A�����܂łƂ����C�������B
�܂��A1MHz�p��FCZ�R�C�����g���邩�������B�B
455KHz����i��H�̌��ؒi�K�ŁA30MHz�̉�H�͏�����ɂ��A��U��Ƃ𒆒f����B
�\�z�͂���Ȋ����������B
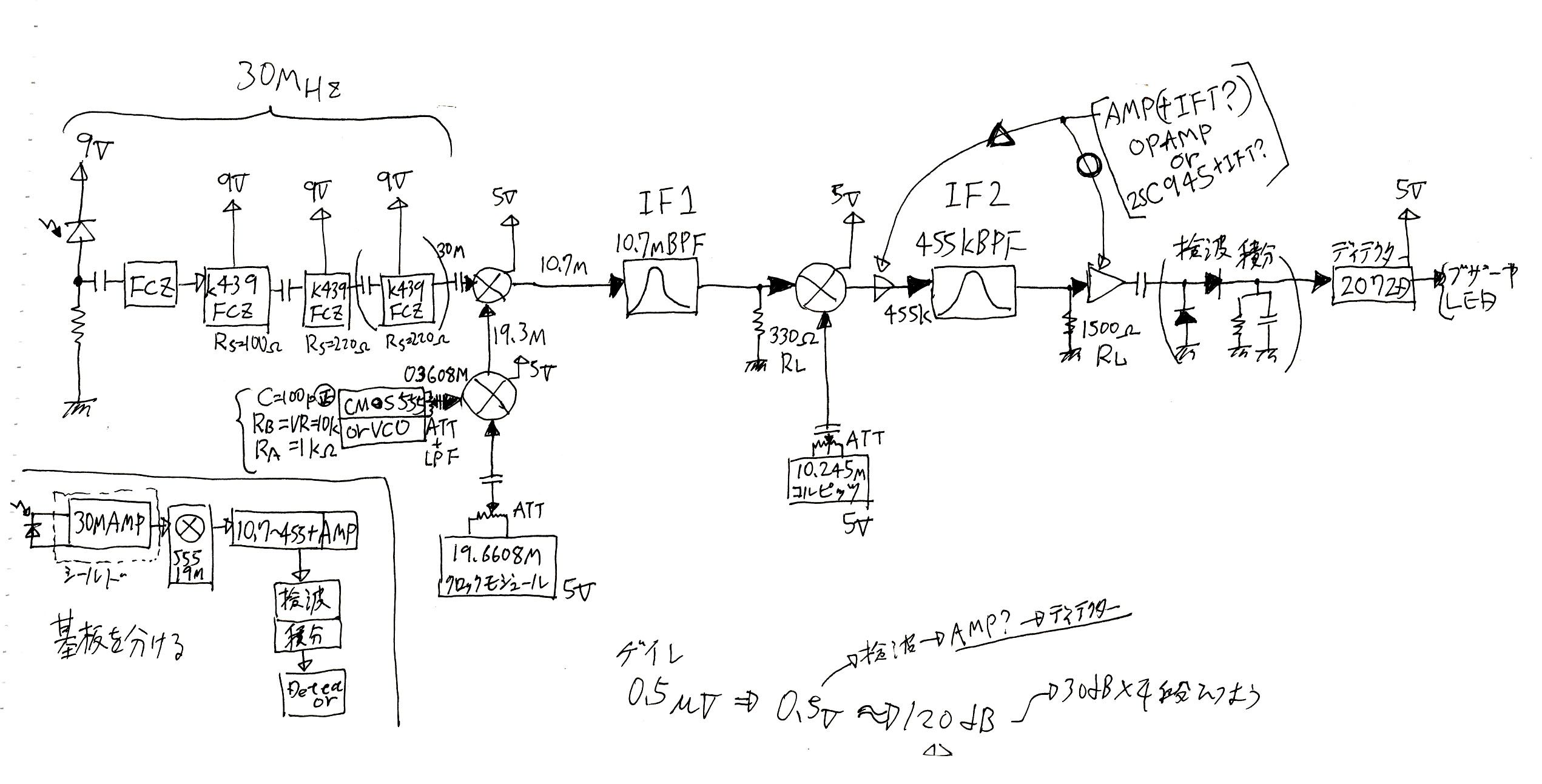 ��̓I�Ɏ����ŏd���̂́A�e��FCZ�R�C���̂悤��IFT�g�����X�����āA���U��A���x�ш���������ς��邱�Ƃł���B
30MHz�̏�Ԃő����O�i�̓C�P�邩�A����ȑO���H�A�܂��AIF�ɗ��Ƃ��Ă��瑝���͂ǂ̒��x�\���H�Ƃ��������B
�R�C����N���X�^���́A�u�T�g�[�d�C�v���L�x�ȃR�g�ɋC���t�����B
http://www.maroon.dti.ne.jp/satodenki/l.html
�̒��c�ɂ������g�R�������悤�ȁB
���݂̖��B
�E�Q�C���Ɣ��U�̊W���ǂ̒��x�����ς���Ȃ��B
�E���U�n�t�B���^�[�̑��p�Ɖߓn���������݂̓�̖��B������455KHz���Ⴂ�̂ŁB
�E���������肷���Ă�B
�ELD���Ȃ���30MHz�̃h���C�u�B
FCZ�R�C��/IFT�g�����X/�Z���~�b�N�t�B���^�[/�N���X�^���t�B���^�[�𑽐��g���Ƌ���������Ƃ����̂����邵�A��N�Ɏ��Ԃ�������A�������݂��Ȃ�B
�܂��A�����e�Ɋւ��č����\�ȉ�H���ƂȂ�ƁA�����ȕ����ł͂��邪�A
���v�⑼�Ɋւ���Z�p�ɂ͗L�p�ȕ���������B
�I�[�f�B�I�͒���g�ł��邪�A�����͖ʔ��������������Ƃ��v�������A����A�g���Ă�l�����Ȃ��B
�܂�A�f�W�^���̂�����ŁA�A�i���O�̃I�C�V�C�����������čs���ꂽ�����ł͂���B
����A�����͕����X���\���͖����Ƃ������Ȃ����c�A�A
HF-VHF-UHF������̓j�b�`�ł͂��邪�A�v���Z�p�ɂ͕s���ł���B���i���₷�͍̂l�����B
455KHz�̏ꍇ�A�R�C���g�����X���ʓ|�B
30MHz�̏ꍇ�ALD�h���C�u�̖��AIF�̎g�p�ȂǕ��G�ɂȂ�B�̂ɋ���������B
�ԊO�������R��������W���[���̓��쌴�����ǂ��Ȃ��Ă���̂��m�肽���Ƃ���ł͂��邪�A������ɂ͖����݂����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�����ĕs���������B
��ꂽ�̂Ŏ~�߂�ƌ������g�R���낤���B�B
�ЂƂ���J���č���Ă郂�m��
�̂�ɂ��āA�P�`�t���Ă���̃A�z������B
���ΖʂȂ̂Ɍh����g�킸��V�������B
����āA�ނ��Ă����B
�����̂��̔�펯�ł�����Ȃ����݂ɋC�Â��������ǂ��B
�ǂ����ŏK�������Ƃ������������������悤�Ɂu���R�v�Ƃ����āA�}�E���g����̂�������̂����A
����́A���̂悤�ȃ��x���ł������A�^�_�̃N�\���v�������B
�G�A���v��{�����Ɍx���I�Ȓ��ӂ����Ă����������ʂ͖��������B
�܂��A�q�g�̊��ׂ����Ǝv�����ƂŁA�����������낤�ɁB
�d�q�͐�傶�ᖳ�����ǁA
�d�q�W�̎Љ���āA���������̑����́H
�������}�E���^�[�̕�ɂȂ̂��H
��������������m�ʼnx�ɓ���̂͌��\�����A���l���������ނȁI�I�Ǝv�����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{
�ŁA���[�U�[�A�A�́A�ǂ̒��x�̏������������Ƃ����ƁA�A
���Ȃ�̂��珀���ŏW�߂Ă������m�ł���B(�H�����N���X3B���Ă��������炩�Ȃ�́B)
��̓I�Ɏ����ŏd���̂́A�e��FCZ�R�C���̂悤��IFT�g�����X�����āA���U��A���x�ш���������ς��邱�Ƃł���B
30MHz�̏�Ԃő����O�i�̓C�P�邩�A����ȑO���H�A�܂��AIF�ɗ��Ƃ��Ă��瑝���͂ǂ̒��x�\���H�Ƃ��������B
�R�C����N���X�^���́A�u�T�g�[�d�C�v���L�x�ȃR�g�ɋC���t�����B
http://www.maroon.dti.ne.jp/satodenki/l.html
�̒��c�ɂ������g�R�������悤�ȁB
���݂̖��B
�E�Q�C���Ɣ��U�̊W���ǂ̒��x�����ς���Ȃ��B
�E���U�n�t�B���^�[�̑��p�Ɖߓn���������݂̓�̖��B������455KHz���Ⴂ�̂ŁB
�E���������肷���Ă�B
�ELD���Ȃ���30MHz�̃h���C�u�B
FCZ�R�C��/IFT�g�����X/�Z���~�b�N�t�B���^�[/�N���X�^���t�B���^�[�𑽐��g���Ƌ���������Ƃ����̂����邵�A��N�Ɏ��Ԃ�������A�������݂��Ȃ�B
�܂��A�����e�Ɋւ��č����\�ȉ�H���ƂȂ�ƁA�����ȕ����ł͂��邪�A
���v�⑼�Ɋւ���Z�p�ɂ͗L�p�ȕ���������B
�I�[�f�B�I�͒���g�ł��邪�A�����͖ʔ��������������Ƃ��v�������A����A�g���Ă�l�����Ȃ��B
�܂�A�f�W�^���̂�����ŁA�A�i���O�̃I�C�V�C�����������čs���ꂽ�����ł͂���B
����A�����͕����X���\���͖����Ƃ������Ȃ����c�A�A
HF-VHF-UHF������̓j�b�`�ł͂��邪�A�v���Z�p�ɂ͕s���ł���B���i���₷�͍̂l�����B
455KHz�̏ꍇ�A�R�C���g�����X���ʓ|�B
30MHz�̏ꍇ�ALD�h���C�u�̖��AIF�̎g�p�ȂǕ��G�ɂȂ�B�̂ɋ���������B
�ԊO�������R��������W���[���̓��쌴�����ǂ��Ȃ��Ă���̂��m�肽���Ƃ���ł͂��邪�A������ɂ͖����݂����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�����ĕs���������B
��ꂽ�̂Ŏ~�߂�ƌ������g�R���낤���B�B
�ЂƂ���J���č���Ă郂�m��
�̂�ɂ��āA�P�`�t���Ă���̃A�z������B
���ΖʂȂ̂Ɍh����g�킸��V�������B
����āA�ނ��Ă����B
�����̂��̔�펯�ł�����Ȃ����݂ɋC�Â��������ǂ��B
�ǂ����ŏK�������Ƃ������������������悤�Ɂu���R�v�Ƃ����āA�}�E���g����̂�������̂����A
����́A���̂悤�ȃ��x���ł������A�^�_�̃N�\���v�������B
�G�A���v��{�����Ɍx���I�Ȓ��ӂ����Ă����������ʂ͖��������B
�܂��A�q�g�̊��ׂ����Ǝv�����ƂŁA�����������낤�ɁB
�d�q�͐�傶�ᖳ�����ǁA
�d�q�W�̎Љ���āA���������̑����́H
�������}�E���^�[�̕�ɂȂ̂��H
��������������m�ʼnx�ɓ���̂͌��\�����A���l���������ނȁI�I�Ǝv�����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{
�ŁA���[�U�[�A�A�́A�ǂ̒��x�̏������������Ƃ����ƁA�A
���Ȃ�̂��珀���ŏW�߂Ă������m�ł���B(�H�����N���X3B���Ă��������炩�Ȃ�́B)
 ���̑��ɁA2�N�O���炢�ɍw�������A�����Y�t�����W���[���������̂ŃN���X1�������Ǝv�����ǁA10�b�R���炢�������B
Amazon�Ŕ������̂����m��Ȃ��B
�ł����ꂪ������Ȃ������̂Œ������Ă����A
�o�͉͂��x�Ō��\�ς��͂�������A�܂��A�N���X3A�`3B���x���Ǝv����B
���̑��ɁA2�N�O���炢�ɍw�������A�����Y�t�����W���[���������̂ŃN���X1�������Ǝv�����ǁA10�b�R���炢�������B
Amazon�Ŕ������̂����m��Ȃ��B
�ł����ꂪ������Ȃ������̂Œ������Ă����A
�o�͉͂��x�Ō��\�ς��͂�������A�܂��A�N���X3A�`3B���x���Ǝv����B
 ��2�Z�b�g(20��)���������B
����͍̂��o�͋��x�̃G�l���M�[�Ŕ��˖ʂ��̂��낤����A��u�ŃA���B
����āA�Ód�C���_���Ȃ̂́A�R��������Ǝv����B
�܂��A���������t�����̕����ϐ����Ȃ��̂����邩��A�ڍ��ʂ̔j������肻���B
�����A�ŋ߁A�h���C�u�͈͂��L�����āA���G�ł����\���ɂ����͂Ȃ��Ă��Ă�悤�ł���B
���̎�̂��̂́A�d�C�I�ɂ́A�R���f���T�[�ƒ�R�̂݁B���Ƃ̓_�C�Ƃ������M���A�����o����R�����[�g�����Y���炢�c�A�ɂ߂ĒP���B
�������M�ɂ̓R���f���T�[���O���K�v�����邪�A��[�ɂ���̂ň��Ղ��Ǝv���B
�܂��A���|���s���O�ɂ���N���K�v�����玞�Ԃ�������̂�������Ȃ����A�d������̕ϒ��͎v�������������Ȃ��̂͑O�ɏ������ʂ�B
30MHz���ƁA�ϒ����͂��Ȃ艺�����Ă��܂��Ǝv���A2�`3���s���Ηǂ����ȁH�ƌ��������̗\�z�ł������A
�p���[������LD�́AAPC��H�̕K�v�������Ȃ��B�ڍ��ʐς��傫���Ɨ\�z���ꔽ���X�s�[�h�͗�����B
LD�́A�ʎY�ŋ��낵�������Ȃ����̂�����A����ɍ������wBPF���ʎY���Ĉ����Ȃ��ė~�����B
650nm��555nm�̂�����A���\�֗����ALD�̓X�y�N�g�������肵�Ă��Y��Ƃ����킯����Ȃ����ǁA�{�|20nm���x��BPF�͍����̂ł͂Ȃ����낤���B
���Ƃ́A���W�����[�^�[�A�P���ɓd���ŕϒ��o���Ȃ��Ȃ�A��r�I�����ł����w�I�ɏo���镔��������Ǝv���B
�������B�B
��2�Z�b�g(20��)���������B
����͍̂��o�͋��x�̃G�l���M�[�Ŕ��˖ʂ��̂��낤����A��u�ŃA���B
����āA�Ód�C���_���Ȃ̂́A�R��������Ǝv����B
�܂��A���������t�����̕����ϐ����Ȃ��̂����邩��A�ڍ��ʂ̔j������肻���B
�����A�ŋ߁A�h���C�u�͈͂��L�����āA���G�ł����\���ɂ����͂Ȃ��Ă��Ă�悤�ł���B
���̎�̂��̂́A�d�C�I�ɂ́A�R���f���T�[�ƒ�R�̂݁B���Ƃ̓_�C�Ƃ������M���A�����o����R�����[�g�����Y���炢�c�A�ɂ߂ĒP���B
�������M�ɂ̓R���f���T�[���O���K�v�����邪�A��[�ɂ���̂ň��Ղ��Ǝv���B
�܂��A���|���s���O�ɂ���N���K�v�����玞�Ԃ�������̂�������Ȃ����A�d������̕ϒ��͎v�������������Ȃ��̂͑O�ɏ������ʂ�B
30MHz���ƁA�ϒ����͂��Ȃ艺�����Ă��܂��Ǝv���A2�`3���s���Ηǂ����ȁH�ƌ��������̗\�z�ł������A
�p���[������LD�́AAPC��H�̕K�v�������Ȃ��B�ڍ��ʐς��傫���Ɨ\�z���ꔽ���X�s�[�h�͗�����B
LD�́A�ʎY�ŋ��낵�������Ȃ����̂�����A����ɍ������wBPF���ʎY���Ĉ����Ȃ��ė~�����B
650nm��555nm�̂�����A���\�֗����ALD�̓X�y�N�g�������肵�Ă��Y��Ƃ����킯����Ȃ����ǁA�{�|20nm���x��BPF�͍����̂ł͂Ȃ����낤���B
���Ƃ́A���W�����[�^�[�A�P���ɓd���ŕϒ��o���Ȃ��Ȃ�A��r�I�����ł����w�I�ɏo���镔��������Ǝv���B
�������B�B
 Amazon�̍w���������������4�N�O�������B�������A10��175�~�B
�ŁA�A��L�����̏��i�͗��ĂȂ��̂����A�悭����ƑS�������B91���Łc�A
���肩�������d�����猩��ɁA�N���X1��2�Ƃ͎v���Ȃ��c�A�A�B
�œ_�͒������ăO�ڒ��܂ŌŒ�ς݁B�R���f���T�[�͐����ɏ����Ă��邾���Ŗ����炵���B���Ă��A���̃^�C�v�̂ɂ����������c�A�A
���������A�`�b�vLD��p���Ă���悤�ł���B�������x���C�ɂȂ�g�R�ł�����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
30MHz�h���C�u��z�肵���h���C�u��H�B
Amazon�̍w���������������4�N�O�������B�������A10��175�~�B
�ŁA�A��L�����̏��i�͗��ĂȂ��̂����A�悭����ƑS�������B91���Łc�A
���肩�������d�����猩��ɁA�N���X1��2�Ƃ͎v���Ȃ��c�A�A�B
�œ_�͒������ăO�ڒ��܂ŌŒ�ς݁B�R���f���T�[�͐����ɏ����Ă��邾���Ŗ����炵���B���Ă��A���̃^�C�v�̂ɂ����������c�A�A
���������A�`�b�vLD��p���Ă���悤�ł���B�������x���C�ɂȂ�g�R�ł�����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
30MHz�h���C�u��z�肵���h���C�u��H�B
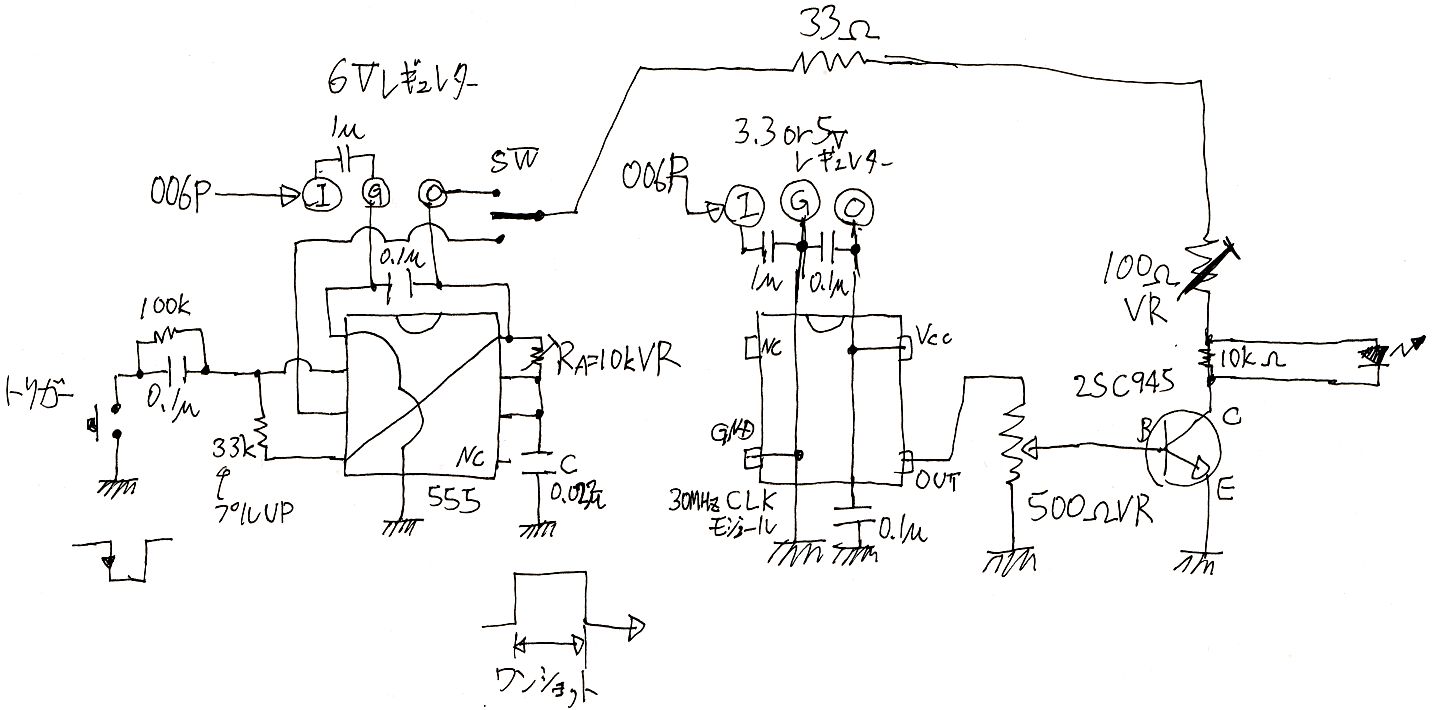 �������H�B
�������H�B
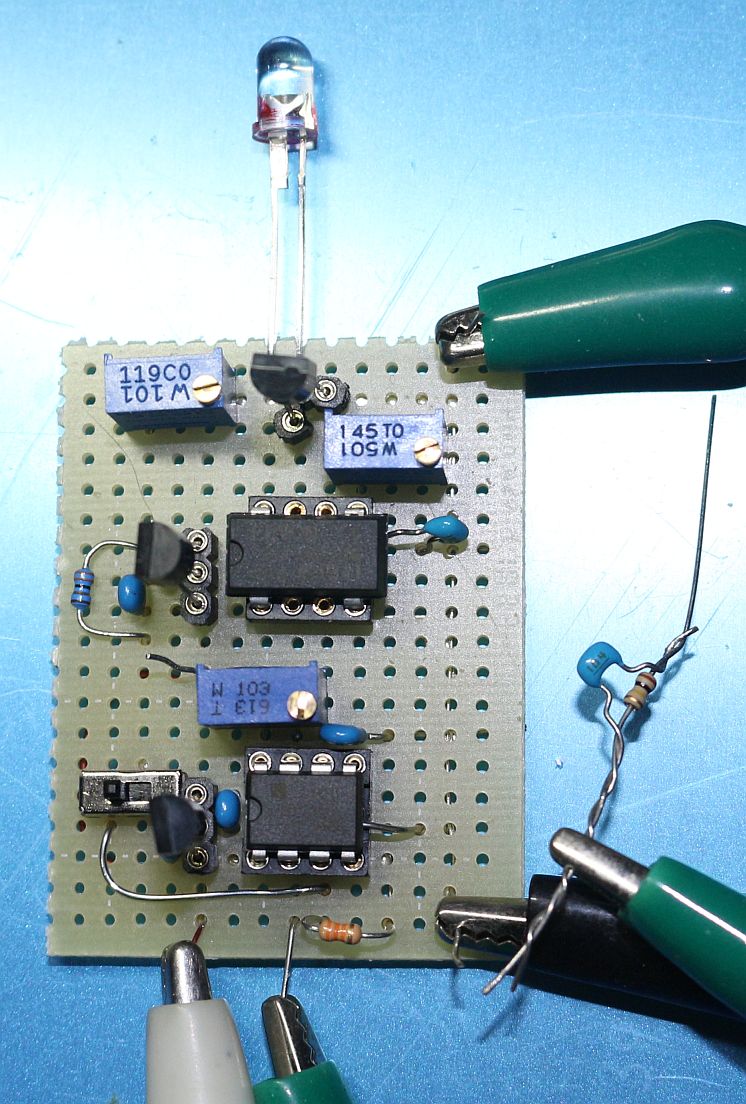 �����LED�APD���x�����ăe�X�g�o���ĂȂ��B
�e�X�g�p�ɁA����LD�ALED�A��ʐς�Si-PIN�t�H�gDi�Ƃ��A�����̑�����̃p�[�c���K�v�B
Tr��LED�ALD�̃h���C�u�̏�Ԃ́ALED�ւ̓d��(33���̓d��)��LED�ڑ��[�q�ԓd�����I�V���Ō���B
�ϒ��M������VR�̐ݒ肪����������ƁA����Ȃ��ă_�������A�傫�����Ă�������ςȂ��ŕϒ��������Ȃ�B
�t�o�C�A�X���������t�H�gDi�ő���̂��ŏI�I�Ȋ����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�c������v�̉ۑ�B
30MHz�ŔėpLD���쓮�o���邩�H�ˍ����ȃ��m�Ȃ�ϒ���2�`3���͍s�������B
FET�̃h���C����FCZ�R�C���̃g�����X�ő������Č��ʂ͂ǂ����H
�����̃Q�C����120dB�ɏo���邩�H
�ƌ����������ł���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220311�L�q
�g��: 638nm�̃I�����W���[�U�[1200mW�p���[���[�U�[���j�b�g��TTL�ϒ����t���Ă邯�ǁAPwm/ttl: 0-20kHz�Ƃ�0-30KHz���Ə����Ă������B
��͂�n�C���b�e�[�W�͒x���悤�ł��ˁB���[�U�[����ɂ悭�g���郂�W���[���̃^�C�v�̔h���i�炵���B
�ϒ��ɂ́A���w�f�q���K�v�����B
�����r�[�����t�@�b�g�r�[���Ƃ����炵���A(���b�r�[���Ɩ�Ă�B�B)
�ȑO���������A������x�����������S�ŁA���ꂽ�ꍇ�r�[�������₷������������B
���U�ƒ�~���J��Ԃ����A���U���ێ������x��ς���������������m��Ȃ��B
���̃^�C�v�́A��ōw�������������W���[���̓d�����͂�
10K�����M�����C���ɕ��݂���Ă邾���Ƃ������m�̂悤���A
�����LED�APD���x�����ăe�X�g�o���ĂȂ��B
�e�X�g�p�ɁA����LD�ALED�A��ʐς�Si-PIN�t�H�gDi�Ƃ��A�����̑�����̃p�[�c���K�v�B
Tr��LED�ALD�̃h���C�u�̏�Ԃ́ALED�ւ̓d��(33���̓d��)��LED�ڑ��[�q�ԓd�����I�V���Ō���B
�ϒ��M������VR�̐ݒ肪����������ƁA����Ȃ��ă_�������A�傫�����Ă�������ςȂ��ŕϒ��������Ȃ�B
�t�o�C�A�X���������t�H�gDi�ő���̂��ŏI�I�Ȋ����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�c������v�̉ۑ�B
30MHz�ŔėpLD���쓮�o���邩�H�ˍ����ȃ��m�Ȃ�ϒ���2�`3���͍s�������B
FET�̃h���C����FCZ�R�C���̃g�����X�ő������Č��ʂ͂ǂ����H
�����̃Q�C����120dB�ɏo���邩�H
�ƌ����������ł���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220311�L�q
�g��: 638nm�̃I�����W���[�U�[1200mW�p���[���[�U�[���j�b�g��TTL�ϒ����t���Ă邯�ǁAPwm/ttl: 0-20kHz�Ƃ�0-30KHz���Ə����Ă������B
��͂�n�C���b�e�[�W�͒x���悤�ł��ˁB���[�U�[����ɂ悭�g���郂�W���[���̃^�C�v�̔h���i�炵���B
�ϒ��ɂ́A���w�f�q���K�v�����B
�����r�[�����t�@�b�g�r�[���Ƃ����炵���A(���b�r�[���Ɩ�Ă�B�B)
�ȑO���������A������x�����������S�ŁA���ꂽ�ꍇ�r�[�������₷������������B
���U�ƒ�~���J��Ԃ����A���U���ێ������x��ς���������������m��Ȃ��B
���̃^�C�v�́A��ōw�������������W���[���̓d�����͂�
10K�����M�����C���ɕ��݂���Ă邾���Ƃ������m�̂悤���A
 10K���͌��\��������A����ȋ��x�ω��Ŕ��U���~�߂Ȃ��Ƃ����l���ł���Ǝv����B
������W���[���������ĂāA�t�H�g�g�����W�X�^�[�ł������B
���܂荂���ł͂Ȃ��B�㏸15��Sec���~15��Sec�Ƃ������x���B
�����Ȃ特�����w�f�q�ŏu�ԓI�Ƀt���[���A�E�g�����Ă��ʂ��ȁH
����@�p�̂�3�`6���ʂŔ����Ă�݂��������ǁH�ڍׂ͂܂����������ĕs���B
���[�U�[�͌����ɑ��Ă̌��ʕω����V�r�A�Ȃ̂ŁA�����R���p�̒���g�Ȏ�����j�b�g���ƁA
����������̑���M�̓u����Ƃ��ꂾ���ŁA�������Ă��܂��\��������B�X�g���{�ȂǍ����ω����郂�m�Ō��m���͔�������B
�Ԃ��UV���[�U�[�͗ʎY����Ă�̂ň������A�l�Ԃ����₷���͌��\�����悤�ł���B
�C���^�[�l�b�g�̌��ʐM�́A�V���O�����[�h�t�@�C�o�[�Ŏd�l����1�`1.5��m���x�̔g���Ȃ̂��낤����
���[�U�[�����Ǝv���Ă������A�A���ׂ�LED�����m��Ȃ��H
RC��H�ŃL���̗ǂ���`�g�Ƃ��A�����g�ƂȂ�ƁA�\�z���ꂽ�̂́A
�_����H�ŃA���A�V���~�b�g�g���K�[�C���o�[�^�[�̔��U��H�ł���l�ŁA
200MHz�N���X�̃I�V����tr�F���C�W���O�^�C��(�㏸����)����ABW�F�o���h���C�Y(�ш敝)������o���̂Ɏg���Ă܂����B
�������A���U��30�`60MHz�܂ł͏o�������ƁB
���U�����Ȃ�A������̕����A555�������N���Ǝv���܂��B�R���f���T�[�̃g�R��PWM�ł��g����O�p�g�����܂����B
������AP���t���Ă�̂����͂Ƀc�G�i�[�������ĂĐÓd�C�ɋ����̂ł����A���g���̌��E�ɂ͉e�����邩���H
�u74HC14AP�v�ƂׂČ����g�R�A�]��W�Ȃ������B�B�������E���̂����肻���H
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220212
�ꕔ���i�������̂ŁA�m�F��ƂŁB
�����Ƃ���B�����ǁA�ʐς��傫���ڍ��ԗe�ʁAtr�y��tf�́APIN�t�H�g�_�C�I�[�h�Ƃ��āA�����ݒ��x�ȋC������B
10K���͌��\��������A����ȋ��x�ω��Ŕ��U���~�߂Ȃ��Ƃ����l���ł���Ǝv����B
������W���[���������ĂāA�t�H�g�g�����W�X�^�[�ł������B
���܂荂���ł͂Ȃ��B�㏸15��Sec���~15��Sec�Ƃ������x���B
�����Ȃ特�����w�f�q�ŏu�ԓI�Ƀt���[���A�E�g�����Ă��ʂ��ȁH
����@�p�̂�3�`6���ʂŔ����Ă�݂��������ǁH�ڍׂ͂܂����������ĕs���B
���[�U�[�͌����ɑ��Ă̌��ʕω����V�r�A�Ȃ̂ŁA�����R���p�̒���g�Ȏ�����j�b�g���ƁA
����������̑���M�̓u����Ƃ��ꂾ���ŁA�������Ă��܂��\��������B�X�g���{�ȂǍ����ω����郂�m�Ō��m���͔�������B
�Ԃ��UV���[�U�[�͗ʎY����Ă�̂ň������A�l�Ԃ����₷���͌��\�����悤�ł���B
�C���^�[�l�b�g�̌��ʐM�́A�V���O�����[�h�t�@�C�o�[�Ŏd�l����1�`1.5��m���x�̔g���Ȃ̂��낤����
���[�U�[�����Ǝv���Ă������A�A���ׂ�LED�����m��Ȃ��H
RC��H�ŃL���̗ǂ���`�g�Ƃ��A�����g�ƂȂ�ƁA�\�z���ꂽ�̂́A
�_����H�ŃA���A�V���~�b�g�g���K�[�C���o�[�^�[�̔��U��H�ł���l�ŁA
200MHz�N���X�̃I�V����tr�F���C�W���O�^�C��(�㏸����)����ABW�F�o���h���C�Y(�ш敝)������o���̂Ɏg���Ă܂����B
�������A���U��30�`60MHz�܂ł͏o�������ƁB
���U�����Ȃ�A������̕����A555�������N���Ǝv���܂��B�R���f���T�[�̃g�R��PWM�ł��g����O�p�g�����܂����B
������AP���t���Ă�̂����͂Ƀc�G�i�[�������ĂĐÓd�C�ɋ����̂ł����A���g���̌��E�ɂ͉e�����邩���H
�u74HC14AP�v�ƂׂČ����g�R�A�]��W�Ȃ������B�B�������E���̂����肻���H
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220212
�ꕔ���i�������̂ŁA�m�F��ƂŁB
�����Ƃ���B�����ǁA�ʐς��傫���ڍ��ԗe�ʁAtr�y��tf�́APIN�t�H�g�_�C�I�[�h�Ƃ��āA�����ݒ��x�ȋC������B
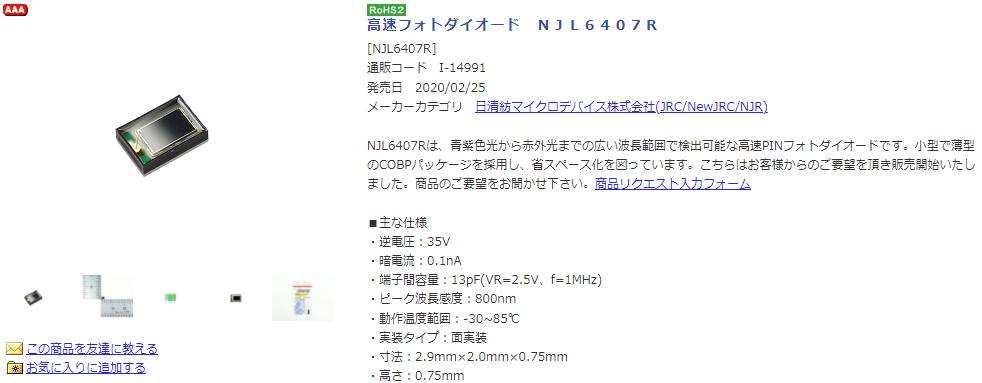 �A���G�N�ɗ��͖̂ʐς����傢�傫���̂�1/2�̑��x���炢�H
���Ƃ́A�t�o�C�A�X�̒�R�l�����������B
�A���G�N�ɗ��͖̂ʐς����傢�傫���̂�1/2�̑��x���炢�H
���Ƃ́A�t�o�C�A�X�̒�R�l�����������B
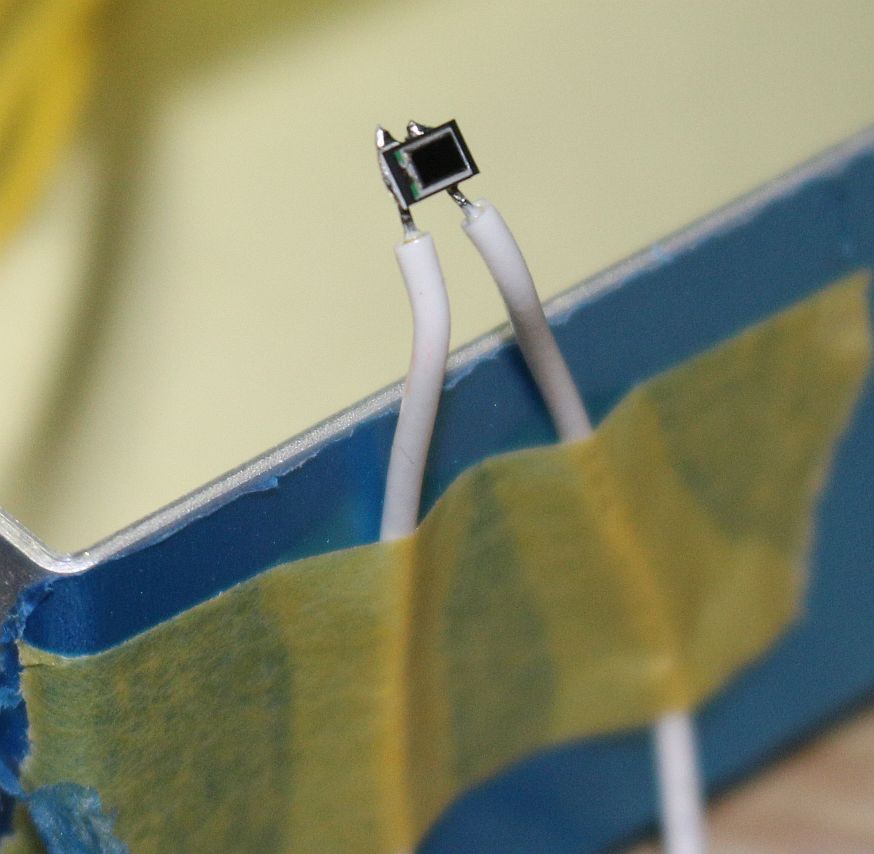 LED�́A�ш�40MHz�̃��m�ɂ����B870nm�ł��邪�A�����̂Ō�����B
����ŁA�ϒ���������B
LED�́A�ш�40MHz�̃��m�ɂ����B870nm�ł��邪�A�����̂Ō�����B
����ŁA�ϒ���������B
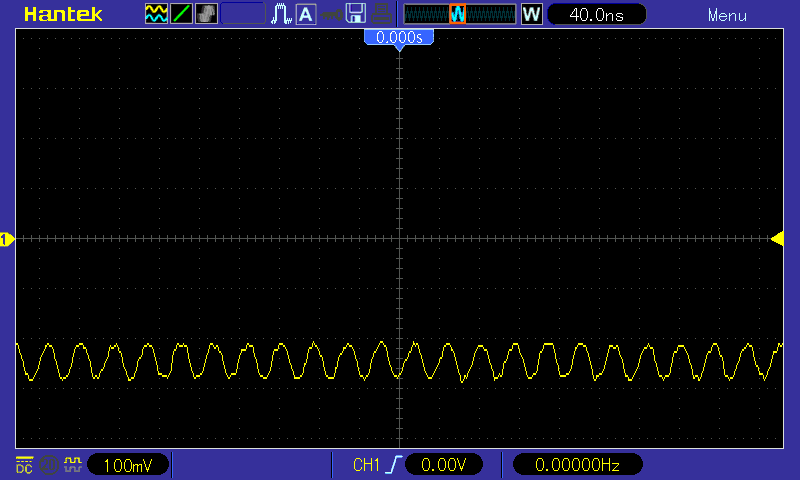 �N���b�N���W���[���́A3.3V�̃��m����5V�̂Ɍ����B
PD�̋t�o�C�A�X��R��2K���ƍ��߂Ȃ̂����邪�A1/2�ʂ̎��������āA�ϓ�������̂ŁA
������������A�d�g�Ƃ��Ă��E���Ă�\��������H
�I�[�_�[�I�ɂ́A�������P�x��455KHz�̕ϒ��Ɨ]��ς�炸�Ȃ̂ŁA�܂��܂��M�p�o���邩�ȁH
���ꂪ�N���A�o����ALD�̕ϒ��Ɏ�肩�����Ă݂邩���B
�g���K�[��AC�J�b�v�����O�A�V���O���V���b�g�ɂ��čēx���Č���ɂ���Ȋ����c�A
�N���b�N���W���[���́A3.3V�̃��m����5V�̂Ɍ����B
PD�̋t�o�C�A�X��R��2K���ƍ��߂Ȃ̂����邪�A1/2�ʂ̎��������āA�ϓ�������̂ŁA
������������A�d�g�Ƃ��Ă��E���Ă�\��������H
�I�[�_�[�I�ɂ́A�������P�x��455KHz�̕ϒ��Ɨ]��ς�炸�Ȃ̂ŁA�܂��܂��M�p�o���邩�ȁH
���ꂪ�N���A�o����ALD�̕ϒ��Ɏ�肩�����Ă݂邩���B
�g���K�[��AC�J�b�v�����O�A�V���O���V���b�g�ɂ��čēx���Č���ɂ���Ȋ����c�A
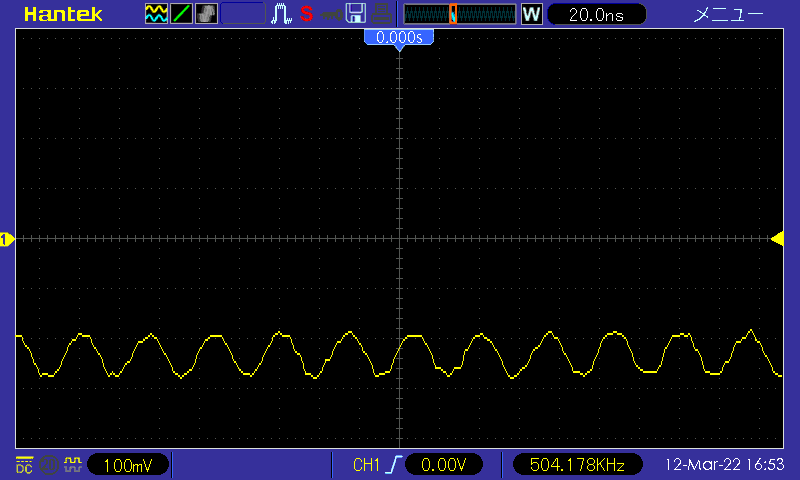 ���̂܂܌���ƁA�ϒ�����1/3���x�ƌ������ƂɂȂ�B
�������ł��邪�A�t�o�C�A�X��R�������̂ŁA����n�Őϕ�����Ă鐬�������邩������Ȃ��A�A
����30MHz���U��H�ŁA���[�U�[Di���W���[�����쓮���Ă݂�B�s�[�N�̓d���l�́A��i��1/2�ȉ��ɂȂ���x�ɍĒ��������B
���̂܂܌���ƁA�ϒ�����1/3���x�ƌ������ƂɂȂ�B
�������ł��邪�A�t�o�C�A�X��R�������̂ŁA����n�Őϕ�����Ă鐬�������邩������Ȃ��A�A
����30MHz���U��H�ŁA���[�U�[Di���W���[�����쓮���Ă݂�B�s�[�N�̓d���l�́A��i��1/2�ȉ��ɂȂ���x�ɍĒ��������B
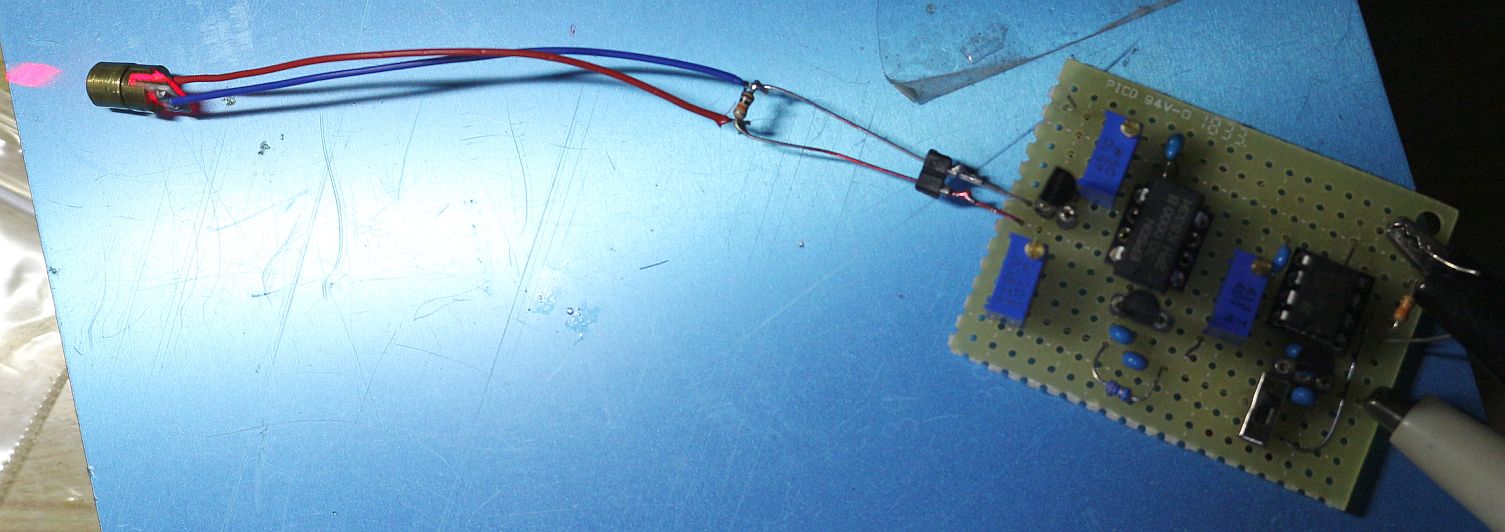
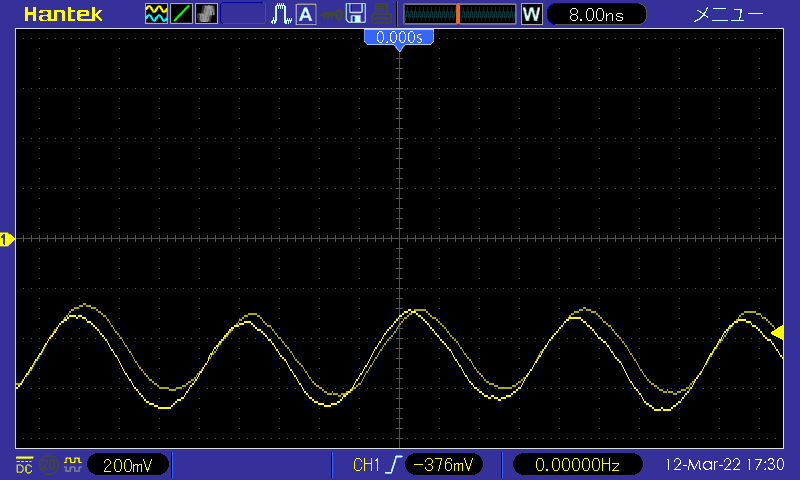 �g���K����肭�s���ĂȂ��̂�2�V���b�g���_�u���Ă͂��邪�A�ϒ����͗\�z��荂�������B
�܂�A���Ȃ�̐������ƌ����ėǂ��B
���v�ő��p���Ă���60MHz�ɂ��Ă��ǂ����������B
�����܂Ő�������Ƃ͎v���ĂȂ������B
�ƌ����킯�ŁA�A30MHz�p�̎�������쐬���邩�l�����ł͂���A�A
���߁�
�[���������[���̎��ŁA�g�ł��Ă�̂����̏�ԁB
�����x�F�ʐς�����̃p���[(�C���e���V�e�B�[)�ɊY���ł���B
�ڑ���A�}�C�i�X�����ɐU��ĂāA�I�V������INV���ĂȂ����ǁA�܂��c�A
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
30MHz�h���C�u�ȃ��[�U�[���̕ϒ��������₷�����邽�߁A�g���K�̒����A�\����INV���āA�L�^���������B
2/3�ʂ̕ϒ����ł���B�������A����n�̐ϕ���p�����邩������Ȃ��̂ŁA�ň��ł����ꂮ�炢�͕ϒ�����Ă�Ƃ����w�W�ɂȂ銴���B
�g���K����肭�s���ĂȂ��̂�2�V���b�g���_�u���Ă͂��邪�A�ϒ����͗\�z��荂�������B
�܂�A���Ȃ�̐������ƌ����ėǂ��B
���v�ő��p���Ă���60MHz�ɂ��Ă��ǂ����������B
�����܂Ő�������Ƃ͎v���ĂȂ������B
�ƌ����킯�ŁA�A30MHz�p�̎�������쐬���邩�l�����ł͂���A�A
���߁�
�[���������[���̎��ŁA�g�ł��Ă�̂����̏�ԁB
�����x�F�ʐς�����̃p���[(�C���e���V�e�B�[)�ɊY���ł���B
�ڑ���A�}�C�i�X�����ɐU��ĂāA�I�V������INV���ĂȂ����ǁA�܂��c�A
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
30MHz�h���C�u�ȃ��[�U�[���̕ϒ��������₷�����邽�߁A�g���K�̒����A�\����INV���āA�L�^���������B
2/3�ʂ̕ϒ����ł���B�������A����n�̐ϕ���p�����邩������Ȃ��̂ŁA�ň��ł����ꂮ�炢�͕ϒ�����Ă�Ƃ����w�W�ɂȂ銴���B
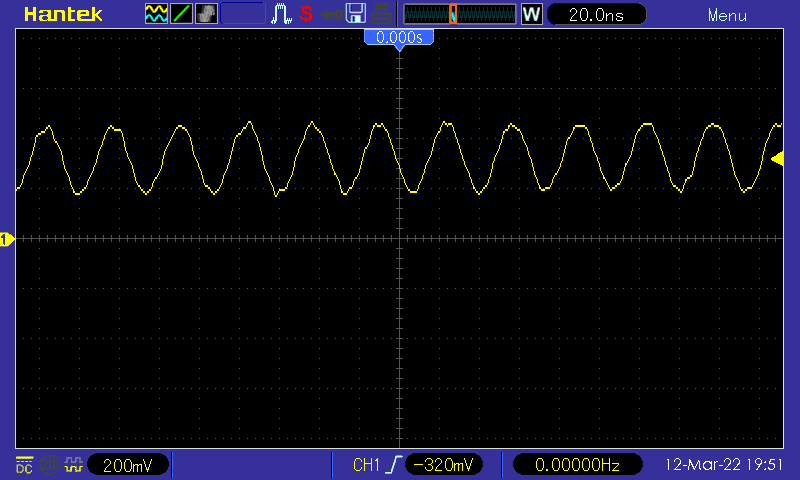 ���[�U�[�́A�������x�̓d���Ȃ̂ŁA�N���X2�ȉ��ł���B
�p���X�Ȃ̂ŁA�����l�͍X�ɂ��̔��������ł���B�����N���X1���x�ɂȂ�Ǝv���B
455KHz�̎�����j�b�g�͂��������r���ŗǂ��Ǝv���B
�p�[�c�𒍕����悤�Ƃ������A���[�����Ԃ��Ă��Ȃ��B
�߂��̂œd�Ԃōs���������������������A�A�A
�Ƃ肠�����A�����炩�̎����͗L�Ӌ`�ɏI������̂ŁA�~�߂Ă݂�B
�����āA���Ƃ̎����́A30MHz�̎�����j�b�g����肭�s���Ηǂ����ƂƎv�����B
�Ƃ肠�����A�p�[�c�́A�w�ǂ��邯�ǁA
IF�ɍ��킹�锭�U����������������ƃ��N�ɂ������͂����āA���̐���������o���ĂȂ��Ƃ��������ŃA���B
�t�H�g�_�C�I�[�h����FET��FCZ�R�C����t����BPF�A���v�����͏o����Ǝv���B
�܂��A���̂����ɍl���Ă݂悤���ȁ[�A�A�A�ƁB
���������A�H���ɂ̓v���O���}�u���ȃN���X�^�����W���[���A��MEMS���U�f�q�������āA�J�X�^�}�C�Y�o����̂����A��������400�~x10���Ɓc�A�A
�������݃��j�b�g��3�����傢����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
30MHz�Ȏ����H�𑱂��܂Łc�A�A�B
�`���^���Ə��߂Č��Ă�B
30MHz���x���ƁA���܂�p�^�[���͋C�ɂ��Ȃ����������ǁc�A�x�^GND�ŁA�܂��A�N�V�^����Ȃ��ق����ǂ��ƌ����Ηǂ����A�A���F���������˃~�X�Ɍq����˕��i�j���Ƃ����B�B
�����A�p�^�[���G�ɂł��A�ƂȂ�A���j�o�[�T����̃A�h���u�ŁA�ƌ������Ƃ͔����āAPC�Ńp�^�[�������āA������ł����������������ǂ��Ǝv���B
100MHz�z���邭�炢�Ȃ�A�p�[�c�̑��̒�����A��̗U�d���Ȃǂ��C�ɂ��������ǂ������B�B�B
�ŁA�܂��A
��Ƃ̗ǂ����l���āA�A
GND�͓����e�[�v�ɂ���BV+���������邩���B
���[�U�[�́A�������x�̓d���Ȃ̂ŁA�N���X2�ȉ��ł���B
�p���X�Ȃ̂ŁA�����l�͍X�ɂ��̔��������ł���B�����N���X1���x�ɂȂ�Ǝv���B
455KHz�̎�����j�b�g�͂��������r���ŗǂ��Ǝv���B
�p�[�c�𒍕����悤�Ƃ������A���[�����Ԃ��Ă��Ȃ��B
�߂��̂œd�Ԃōs���������������������A�A�A
�Ƃ肠�����A�����炩�̎����͗L�Ӌ`�ɏI������̂ŁA�~�߂Ă݂�B
�����āA���Ƃ̎����́A30MHz�̎�����j�b�g����肭�s���Ηǂ����ƂƎv�����B
�Ƃ肠�����A�p�[�c�́A�w�ǂ��邯�ǁA
IF�ɍ��킹�锭�U����������������ƃ��N�ɂ������͂����āA���̐���������o���ĂȂ��Ƃ��������ŃA���B
�t�H�g�_�C�I�[�h����FET��FCZ�R�C����t����BPF�A���v�����͏o����Ǝv���B
�܂��A���̂����ɍl���Ă݂悤���ȁ[�A�A�A�ƁB
���������A�H���ɂ̓v���O���}�u���ȃN���X�^�����W���[���A��MEMS���U�f�q�������āA�J�X�^�}�C�Y�o����̂����A��������400�~x10���Ɓc�A�A
�������݃��j�b�g��3�����傢����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
30MHz�Ȏ����H�𑱂��܂Łc�A�A�B
�`���^���Ə��߂Č��Ă�B
30MHz���x���ƁA���܂�p�^�[���͋C�ɂ��Ȃ����������ǁc�A�x�^GND�ŁA�܂��A�N�V�^����Ȃ��ق����ǂ��ƌ����Ηǂ����A�A���F���������˃~�X�Ɍq����˕��i�j���Ƃ����B�B
�����A�p�^�[���G�ɂł��A�ƂȂ�A���j�o�[�T����̃A�h���u�ŁA�ƌ������Ƃ͔����āAPC�Ńp�^�[�������āA������ł����������������ǂ��Ǝv���B
100MHz�z���邭�炢�Ȃ�A�p�[�c�̑��̒�����A��̗U�d���Ȃǂ��C�ɂ��������ǂ������B�B�B
�ŁA�܂��A
��Ƃ̗ǂ����l���āA�A
GND�͓����e�[�v�ɂ���BV+���������邩���B
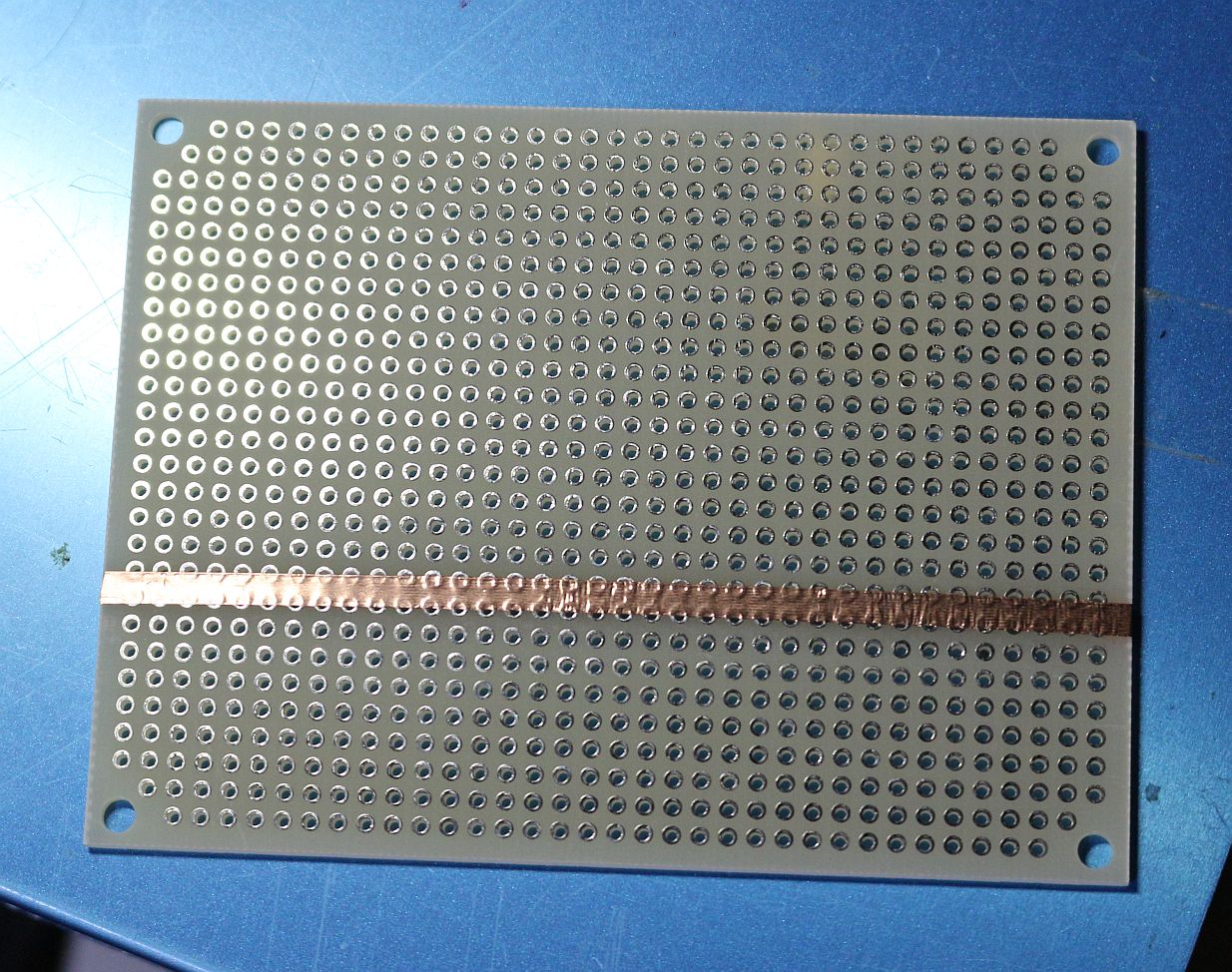 �����ɓ\��ɂ́A����������[����5mm�ʂ����āA�������Ă��Ȃ������Ő����ɒ����Ă݂Ă��甍�����Ă镔����\��B���Ƃ́A�S�������āA����Ȃ���Y��ɗǂ��\��t����B
(�v�́A�[���������������������e�[�v���A�������ĂĈʒu���߂��Č��܂�����A�[�����\��t���āA���̌�S�̂��A�ƌ������ƁB)
�����āA�ی�����˂āA�v�����g��p�̃t���b�N�X��h��B
FCZ�R�C���̌Œ�́A�ʕ����𗯂߂�c����ʂ�����0.8mm�h�����n�̃o�C�X�Ō����J���āA2mm�̃h�����n�̓d���h�����ōL�����ɂ���B
�܂��A�v��Ȃ����H���Ă����ƁA�����ɂ������x���o�鎖�͂��邩�ȁB�Ƃ��������B�ʂ������Ńn���_�t���̕K�v�Ȃقǂ͊����Ă��Ȃ��B
(�NjL�A���i�̂݁A�ʂ�GND�ɗ��Ƃ��Ɣ��U����܂�C���[�W�������̂ŁAGND�ɗ��Ƃ��܂����B)
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�ŁA2�i�܂ł���Ď����ƁA
30MHz�ł́A�R�A���O���قǔ�яo���ʒu�ɂȂ�B
1�i�ł͊��x�͒Ⴍ�A2�i�̎��͔��U���܂����Ă���B
�����ɓ\��ɂ́A����������[����5mm�ʂ����āA�������Ă��Ȃ������Ő����ɒ����Ă݂Ă��甍�����Ă镔����\��B���Ƃ́A�S�������āA����Ȃ���Y��ɗǂ��\��t����B
(�v�́A�[���������������������e�[�v���A�������ĂĈʒu���߂��Č��܂�����A�[�����\��t���āA���̌�S�̂��A�ƌ������ƁB)
�����āA�ی�����˂āA�v�����g��p�̃t���b�N�X��h��B
FCZ�R�C���̌Œ�́A�ʕ����𗯂߂�c����ʂ�����0.8mm�h�����n�̃o�C�X�Ō����J���āA2mm�̃h�����n�̓d���h�����ōL�����ɂ���B
�܂��A�v��Ȃ����H���Ă����ƁA�����ɂ������x���o�鎖�͂��邩�ȁB�Ƃ��������B�ʂ������Ńn���_�t���̕K�v�Ȃقǂ͊����Ă��Ȃ��B
(�NjL�A���i�̂݁A�ʂ�GND�ɗ��Ƃ��Ɣ��U����܂�C���[�W�������̂ŁAGND�ɗ��Ƃ��܂����B)
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�ŁA2�i�܂ł���Ď����ƁA
30MHz�ł́A�R�A���O���قǔ�яo���ʒu�ɂȂ�B
1�i�ł͊��x�͒Ⴍ�A2�i�̎��͔��U���܂����Ă���B
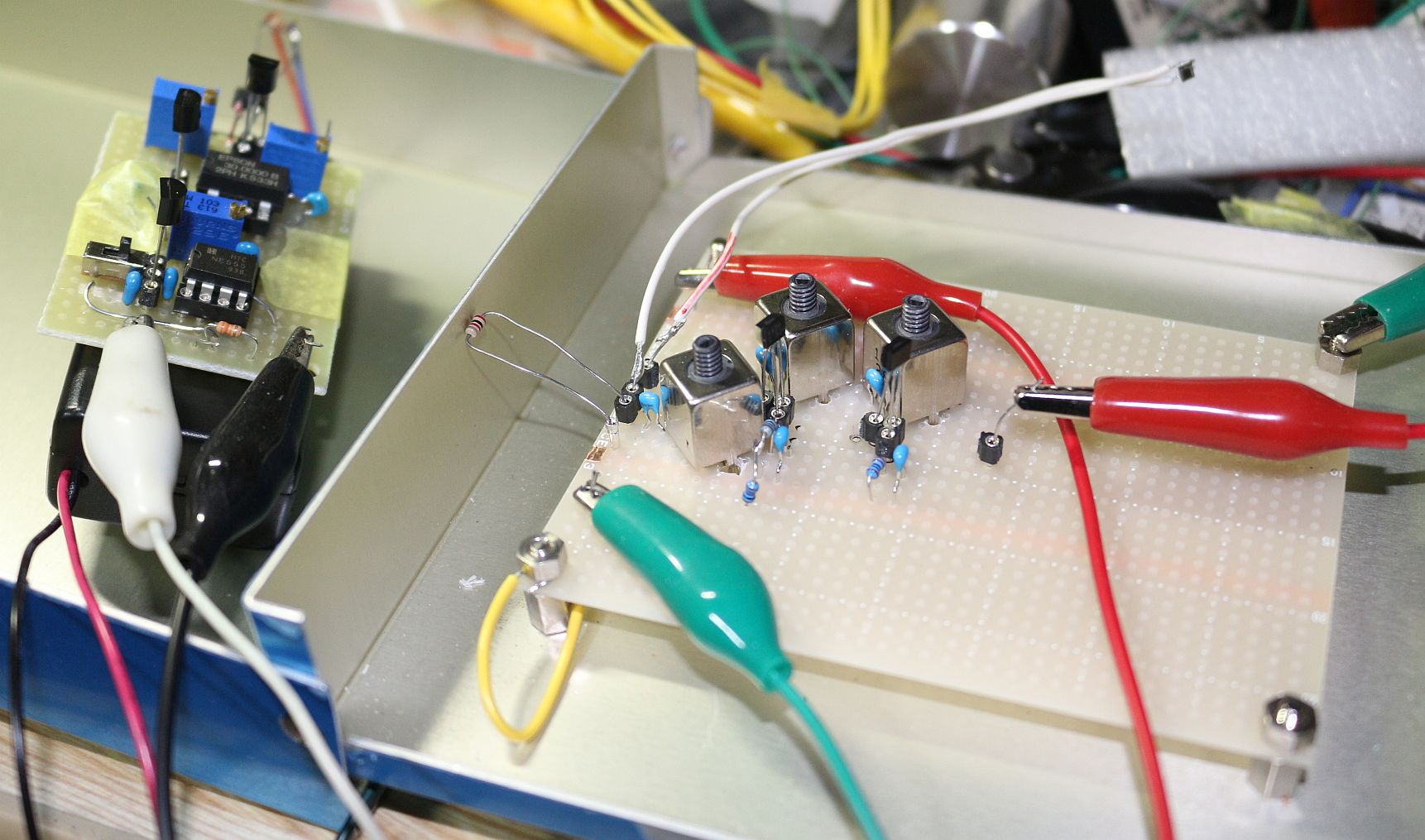 �R�A�̖��́AFCZ�R�C���ɕt���Ă�C��Ⴍ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�e�ʂ��������̂ŁA���l�ׂ͍������݂����������ǁA�A
���[�g�̒��Ȃ̂ŕω��ɓ݊��ŃA���B22pF���x�����z���낤���H
���U�̗��R���l����ɁA
�v�����g��̃p�^�[���B�ƁAFCZ�R�C�����m���߂�����H
�R�C���ƃR�C���̊ԂƂ��ɋ����̏����K�v�����B�Ƃ������A���i���V�[���h�{�b�N�X��ɂ���K�v������\�����B
���U���Ȃ��K�E�Z���~�����g�R�ł���B
���͂�Di��FCZ�R�C���̊Ԃ́A�R���f���T�[�݂̂����A��R����������ǂ������H�H
�Ƃ���ŁA���v�Ȃ̂����ǁA
�����A��ʉ����Ă������[�U�[�_�C�I�[�h����t�@�C�o�[���g���āA�Ǝv���Ă����̂����A���͎���������Ă�݂����B
���ƁA�t�@�C�o�[���Ńt�@���f�[���[�e�[�V�������A�Ƃ�����������炳��Ă��̂����A
������A�t�@�C�o�[�������āA�W���C���ɂȂ�Ȃ����ȁH�Ǝv�����Ă����B���Ō����ƁA���t�@�C�o�[�̃����O���[�U�[�W���C���Ŏ�������Ă���悤�ł���B
�������痣�ꂽ�̂ŁA�d���Ȃ��B
�����́A���m�ɗ̈�Ȃ̂ŁA�������邩�͖���Ń��X�N������B�A���l�������R�g������Ă�\��������A�A
���ʂ��������тƂ��Č���ꂽ��A�d���Ƃ��ĕs����ł����������藧���Ȃ��B
��т�����������A�������ċ��ɂȂ�Ƃ����̂�_���Ă̂ݐ��{�������o���̂��A���[���V���b�g�v��Ȃ�Č����炵�����ǁB
�ړI���疢�m�̌����ɂ͉��l�ς������Ȃ�����ɂȂ��Ă����悤�ɂ��v���B
�^����ꂽ�����Ƃ����̂̕��Y�����o���̂��e�ł���̂ł����F�X����Ă��������邪�A
�Z�������̐����Œ������𑖂�悤�Ȃ��ƂɂȂ��āA����Ȋ��o�ŁA�Z�������Ŕ��邱�Ƃ́A���Ȃ����B�B
���������A���v�̓}�C�N���g�̈�ł����āA�́A���������Ă�l�������悤�ȁB�B
���t�@�C�o�[�͓��g�ǂɑ�������悤���B
�ŁA�b��߂��ƁA�A
�d���ϓ��A���x�⏞�ȂǃA���A�����x��22pF�́A�����ĂȂ��B�ǂ��������m���B�B
�Ƃ肠�����A30pF�̃g���}�[�ȃo���R���ōς܂����ȁH
���U�̌����ɓd���������̃V���b�N������̂��m�F�����B
�������ƕϓ������āA���U����U�~�߂�ƁA���ꂪ�ێ������ꍇ���X���Ƃ��ċ����B
�ŁA
�g���}�[�t������w���������Ė��ɂȂ����̂ŁA
�Z���R���ȃf�B�X�N�^�C�v��20pF��4�������̂Ŏ��t���Ă݂��B
�R�A�̖��́AFCZ�R�C���ɕt���Ă�C��Ⴍ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�e�ʂ��������̂ŁA���l�ׂ͍������݂����������ǁA�A
���[�g�̒��Ȃ̂ŕω��ɓ݊��ŃA���B22pF���x�����z���낤���H
���U�̗��R���l����ɁA
�v�����g��̃p�^�[���B�ƁAFCZ�R�C�����m���߂�����H
�R�C���ƃR�C���̊ԂƂ��ɋ����̏����K�v�����B�Ƃ������A���i���V�[���h�{�b�N�X��ɂ���K�v������\�����B
���U���Ȃ��K�E�Z���~�����g�R�ł���B
���͂�Di��FCZ�R�C���̊Ԃ́A�R���f���T�[�݂̂����A��R����������ǂ������H�H
�Ƃ���ŁA���v�Ȃ̂����ǁA
�����A��ʉ����Ă������[�U�[�_�C�I�[�h����t�@�C�o�[���g���āA�Ǝv���Ă����̂����A���͎���������Ă�݂����B
���ƁA�t�@�C�o�[���Ńt�@���f�[���[�e�[�V�������A�Ƃ�����������炳��Ă��̂����A
������A�t�@�C�o�[�������āA�W���C���ɂȂ�Ȃ����ȁH�Ǝv�����Ă����B���Ō����ƁA���t�@�C�o�[�̃����O���[�U�[�W���C���Ŏ�������Ă���悤�ł���B
�������痣�ꂽ�̂ŁA�d���Ȃ��B
�����́A���m�ɗ̈�Ȃ̂ŁA�������邩�͖���Ń��X�N������B�A���l�������R�g������Ă�\��������A�A
���ʂ��������тƂ��Č���ꂽ��A�d���Ƃ��ĕs����ł����������藧���Ȃ��B
��т�����������A�������ċ��ɂȂ�Ƃ����̂�_���Ă̂ݐ��{�������o���̂��A���[���V���b�g�v��Ȃ�Č����炵�����ǁB
�ړI���疢�m�̌����ɂ͉��l�ς������Ȃ�����ɂȂ��Ă����悤�ɂ��v���B
�^����ꂽ�����Ƃ����̂̕��Y�����o���̂��e�ł���̂ł����F�X����Ă��������邪�A
�Z�������̐����Œ������𑖂�悤�Ȃ��ƂɂȂ��āA����Ȋ��o�ŁA�Z�������Ŕ��邱�Ƃ́A���Ȃ����B�B
���������A���v�̓}�C�N���g�̈�ł����āA�́A���������Ă�l�������悤�ȁB�B
���t�@�C�o�[�͓��g�ǂɑ�������悤���B
�ŁA�b��߂��ƁA�A
�d���ϓ��A���x�⏞�ȂǃA���A�����x��22pF�́A�����ĂȂ��B�ǂ��������m���B�B
�Ƃ肠�����A30pF�̃g���}�[�ȃo���R���ōς܂����ȁH
���U�̌����ɓd���������̃V���b�N������̂��m�F�����B
�������ƕϓ������āA���U����U�~�߂�ƁA���ꂪ�ێ������ꍇ���X���Ƃ��ċ����B
�ŁA
�g���}�[�t������w���������Ė��ɂȂ����̂ŁA
�Z���R���ȃf�B�X�N�^�C�v��20pF��4�������̂Ŏ��t���Ă݂��B
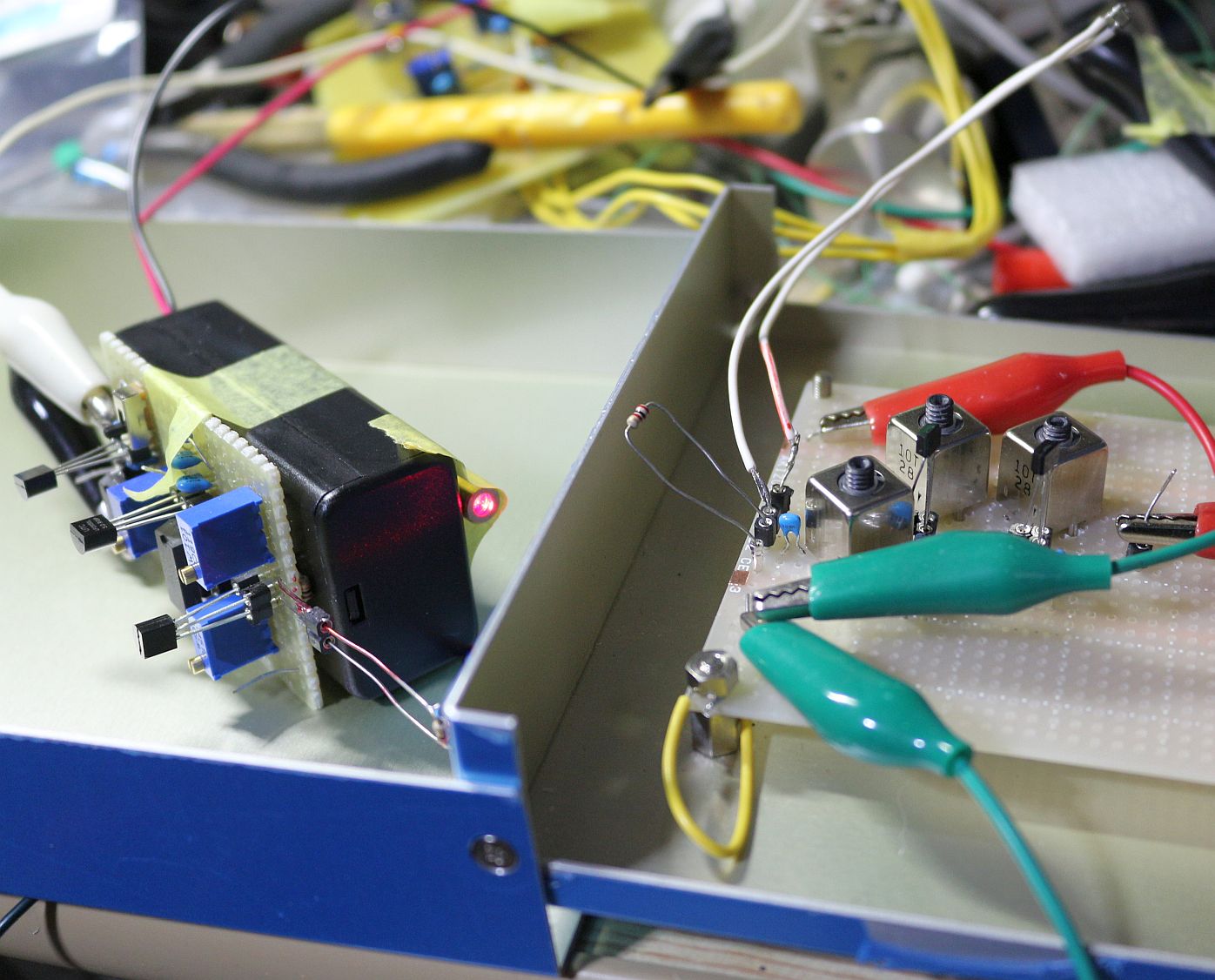 �R�A�̔�яo��������قǕς��Ȃ��B
����������ƁA��̊e�ʂ�Tr�̃R���N�^�e�ʂ݂����Ȃ̂��傫������̂����B������FCZ�R�C���̕ω��J�[�u�̉e�����BQ�t�@�N�^�[�ւ̉e�������O�͂��Ă���B
�����A2�i�łȂ�Ƃ����U���ɂ������x���܂ł͗����B�ł��A�M���M�����ۂ����珉�i���u���ی삷������̎d��݂����Ȃ͕̂K�v�����B
���܂ł�455KHz�̂悤�ɁA�����x�ȕ��͋C�ɂ͍s���ĂȂ������ł��邪�A�������������g���U�̎��_�̑������������ẴR�g�Ȃ̂ŁA���f���Â炢�B
�܂��A�b���l���悤�B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���U�́A�ꌩ�������Ă�悤�Ɏv���邪�A����ɕt�߂̎��g���Ŕ��M���Ă邽�߁A�����͂̃s�[�N�ƃY���Ă��ĕʕ��ł���B
�t�߂Ȃ̂ŁA�T��̂����Ȃ����B
���������킹��ɂ́A�ǂ��������炵����A�X���[�X�^�[�g�Ȃǂł܂����M���~�߂���ԂɎ����Ă����A
LD�ł͌������V�r�A������̂�LED���͂ł��B�����́A�I�V���[�^�[����̓d�C�M����10K��������͂ɑ���A���U�x����������B
���U���G�Ȃ̂ŁA�������Ȃ���A���i���珇���V�O�i���̃s�[�N��T��B
���̍ہA�I�V���̐M���͎���邱�Ƃ���A�������Ȃ��班���������Ă͎~�߂��K�v�B
(�R�A�̐U���Ȃǂł̉��~�߂ɂ��āA�̂̓p���t�B�����E�Ńl�W�~�߂��Ă����悤�����c�A)
���U�̌��ۂɂ́A��i�̑傫�ȐM���́A���i�ȂǍ����x�����ւ̃��[�v�o�b�N���l������B�܂�n�E�����O�̂悤�ȃ��m�B
���͂��V���[�g���Ă����U���~�܂�Ȃ��ꍇ�A��i���P�ƂŁH���U���Ă�B
��i���炢�͕W���I�ŁA�����Ƒ������ė~�����B
���Ƃ́AIF�t�B���^�[�Ȃǂ��g���邩��B���̌�ł�����x�������o����v�f�����邩���Ǝv���Ă���B
�Ō�́A���g���Ă���̑����Ƃ��A�����x�f�B�e�N�^�ŁB
���U�̌����������ɍl���Ă݂�ƁA��͂�A�o�͐M�������͂ɉ�荞��ł��܂��Ă���\�����^���B
FCZ�R�C���ɑ��ATr��D��S�̃��C�A�E�g���߂�����悤�ȁc�A�B
�������A�v��������Ȃ��B��̗U�d���������Ƃ�����A����Ŕ��U�̌����Ƃ��āA�M�����ǂ����֘R��Ă������Ƃ���l���Ă��܂��B�B
�����A�g��ł��܂����̂�����A�ł���R�g�́c�A�A�p�^�[���ʂ̑|�����炢���ȁB
FCZ�R�C����C�������Ɖ�����̂́A������ƋC�������Ă���B
33p��20p�ɂ��Ă������Ȃ̂�����A��ɂ��e�ʂ��ᖳ���ꍇ�A�o�����X�Ƃ��Ăǂ��Ȃ̂��H�Ƃ����B�B
���������������ӏ���o�����ƒ��ׂČ���ɁA���i��FCZ�R�C���ɂ��V�O�i���Ǝ��g�����Y�������U�̎�Ȃ錴���Ƃ����v�f���傫���B
�R�R�̃R�A�U�̉�]�ʒu�ł͖����A30MHz�V�O�i���ɍ��킹�āA���Ƃ͂���Ȃ�ɁA�Ƃ����g�R������B
�����A3��FCZ�R�C�����ꂼ��̊W�ɂāA�ǂ̎��g���ł����U�ł���v�f���A���B
�Ȃ̂ŁA�P�ɐU��������̂ł͖����A���������āA�^�[�Q�b�g�U����藣���悤�Ɉӎ����Ȃ��ƃV�O�i���̏o�͂邱�Ǝ��̂�����B
�ϒ������U������������ɂ́A�Ƃɂ������U���~�߁A
�X�C�[�v���������ɂ��āA�u���V���X�t�@���Ȃǂ��g�����A�`���b�p�[�ŕϒ��M���̗ʂ��������Č���Ɨǂ���������Ȃ��Ǝv�����B
���A���U�O�ɁA�V�O�i���Ɣ��U�̐M�����������Ĕg�`������n�߂�̂ł�����w�W�ɂ��Ă���B
���݂ɁA���ʂ̉����ԐFLED�ł��A���P�x�ŁA�ʐς������̂ł́A30MHz�͌��\�ȕϒ����o�����B�d����ʏ�ɍi���Ă���Ȃ�A�M���͂����ĕς�炸�A�������炢���ȁH
����σh���C�u�̏�Ԃ��l�����Ă��A455KHz��Z�ϊ���2�i�����̕������Ȃ芴�x�͍����C������B���[��c�A�A����ʐς��������āc�A�A
�g�����X�`���ɂȂ��āA�I�����n�b�L�����������͂���̂����ǁA�M���o�͂̑傫����S/N�A�\�R�͕����Ă�\�����傢�ɔZ���ŃA���B
�����ŁA���v�����郂�m�Ȃ�ƍl���Ă݂��B
�܂��A������ƊȈՂȂ̂�����Č��������v���̂����ǁB
�����ō���Ă����m�B
�EPre-AMP�{�o�C�A�X��H�B
�EAGC-AMP
�E�t�F�C�Y�f�B�e�N�^�[
�ELPF�AHPF�ABPF�́A�t�F�C�Y�f�B�e�N�^�[�̐���̃p�[�c�Ɠ��������B�B
�EAOM�̃h���C�o�[�͊����i���������̂ō���ĂȂ����A����\�B
�E1.5D-2V�̓������g�����X��̃t�F���C�g�Ɋ����t���ăR�������[�h�t�B���^�[�ɂ��Ă����B
�EATT�F�A�b�e�l�[�^�[�F���邪�A�_�C�������ς�T�^�̂��W�����N�������Ďg���Ă��B
�E���U��F�����i���������A�܂��A��낤�Ǝv���c�A�A
�E���ˌ��J�b�g�̃s���z�[������ʒ����̕Ό��ׁX�Ƃ������m�̓e�L�g�[�ɒ��B�o����B
���v�ō��R�g���܂�����ȕ��i�́A
�EFM(�t���~���[)�AHM(�n�[�t�~���[)�A�g���A�Ήp�����Y�F��/40�Ƃ��������x�Ȃ̂Łc�A�A�����Y�̓��m�R�[�g���x�B
�E�K�X���[�U�[���U��F�K���X�H�|�i�H�]�v�ȃX�y�N�g�������BPF������p�[�c�B�ł��A���͔����̃��[�U�[�ŗǂ��Ȃ�Ƃ肠�������荠�B
�EAOM(�������w�f�q=�u���b�O�Z���Ƃ��Ă��B)�F��_���e����(TeO2)���̂̒��B�ƕ��ʂ̐��x����肾���A�����r�[���ɕϒ��������ʂ̊���̂Ȃ�A�F�X�o�������B
�E�t�H�gDi�F���ԊO�̈悾�����̂œ���p�[�c���BHM�����ꂾ�����B
�E����Ȃ�ɍ����X�g���[�W�ȃf�W�^�C�U�[�{�}���`�v���N�T�{�g���K�[�p�^�C�}�[�Batan�Ŋp�x���o���ɁA���ω��A�@�B�I�m�C�Y�̊ɘa���̋@�\�̃\�t�g�͎����ō쐬�BA/D���͂̐ϕ�������͂��萻�B
�X�e�[�W�ɍڂ���~���|�z���_�[�Ƃ��Ă̓|�s�����[���Ǝv����A�R�����~�������ǁB�����B�c�~���[�ނ��������ǁB�B
�R�A�̔�яo��������قǕς��Ȃ��B
����������ƁA��̊e�ʂ�Tr�̃R���N�^�e�ʂ݂����Ȃ̂��傫������̂����B������FCZ�R�C���̕ω��J�[�u�̉e�����BQ�t�@�N�^�[�ւ̉e�������O�͂��Ă���B
�����A2�i�łȂ�Ƃ����U���ɂ������x���܂ł͗����B�ł��A�M���M�����ۂ����珉�i���u���ی삷������̎d��݂����Ȃ͕̂K�v�����B
���܂ł�455KHz�̂悤�ɁA�����x�ȕ��͋C�ɂ͍s���ĂȂ������ł��邪�A�������������g���U�̎��_�̑������������ẴR�g�Ȃ̂ŁA���f���Â炢�B
�܂��A�b���l���悤�B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���U�́A�ꌩ�������Ă�悤�Ɏv���邪�A����ɕt�߂̎��g���Ŕ��M���Ă邽�߁A�����͂̃s�[�N�ƃY���Ă��ĕʕ��ł���B
�t�߂Ȃ̂ŁA�T��̂����Ȃ����B
���������킹��ɂ́A�ǂ��������炵����A�X���[�X�^�[�g�Ȃǂł܂����M���~�߂���ԂɎ����Ă����A
LD�ł͌������V�r�A������̂�LED���͂ł��B�����́A�I�V���[�^�[����̓d�C�M����10K��������͂ɑ���A���U�x����������B
���U���G�Ȃ̂ŁA�������Ȃ���A���i���珇���V�O�i���̃s�[�N��T��B
���̍ہA�I�V���̐M���͎���邱�Ƃ���A�������Ȃ��班���������Ă͎~�߂��K�v�B
(�R�A�̐U���Ȃǂł̉��~�߂ɂ��āA�̂̓p���t�B�����E�Ńl�W�~�߂��Ă����悤�����c�A)
���U�̌��ۂɂ́A��i�̑傫�ȐM���́A���i�ȂǍ����x�����ւ̃��[�v�o�b�N���l������B�܂�n�E�����O�̂悤�ȃ��m�B
���͂��V���[�g���Ă����U���~�܂�Ȃ��ꍇ�A��i���P�ƂŁH���U���Ă�B
��i���炢�͕W���I�ŁA�����Ƒ������ė~�����B
���Ƃ́AIF�t�B���^�[�Ȃǂ��g���邩��B���̌�ł�����x�������o����v�f�����邩���Ǝv���Ă���B
�Ō�́A���g���Ă���̑����Ƃ��A�����x�f�B�e�N�^�ŁB
���U�̌����������ɍl���Ă݂�ƁA��͂�A�o�͐M�������͂ɉ�荞��ł��܂��Ă���\�����^���B
FCZ�R�C���ɑ��ATr��D��S�̃��C�A�E�g���߂�����悤�ȁc�A�B
�������A�v��������Ȃ��B��̗U�d���������Ƃ�����A����Ŕ��U�̌����Ƃ��āA�M�����ǂ����֘R��Ă������Ƃ���l���Ă��܂��B�B
�����A�g��ł��܂����̂�����A�ł���R�g�́c�A�A�p�^�[���ʂ̑|�����炢���ȁB
FCZ�R�C����C�������Ɖ�����̂́A������ƋC�������Ă���B
33p��20p�ɂ��Ă������Ȃ̂�����A��ɂ��e�ʂ��ᖳ���ꍇ�A�o�����X�Ƃ��Ăǂ��Ȃ̂��H�Ƃ����B�B
���������������ӏ���o�����ƒ��ׂČ���ɁA���i��FCZ�R�C���ɂ��V�O�i���Ǝ��g�����Y�������U�̎�Ȃ錴���Ƃ����v�f���傫���B
�R�R�̃R�A�U�̉�]�ʒu�ł͖����A30MHz�V�O�i���ɍ��킹�āA���Ƃ͂���Ȃ�ɁA�Ƃ����g�R������B
�����A3��FCZ�R�C�����ꂼ��̊W�ɂāA�ǂ̎��g���ł����U�ł���v�f���A���B
�Ȃ̂ŁA�P�ɐU��������̂ł͖����A���������āA�^�[�Q�b�g�U����藣���悤�Ɉӎ����Ȃ��ƃV�O�i���̏o�͂邱�Ǝ��̂�����B
�ϒ������U������������ɂ́A�Ƃɂ������U���~�߁A
�X�C�[�v���������ɂ��āA�u���V���X�t�@���Ȃǂ��g�����A�`���b�p�[�ŕϒ��M���̗ʂ��������Č���Ɨǂ���������Ȃ��Ǝv�����B
���A���U�O�ɁA�V�O�i���Ɣ��U�̐M�����������Ĕg�`������n�߂�̂ł�����w�W�ɂ��Ă���B
���݂ɁA���ʂ̉����ԐFLED�ł��A���P�x�ŁA�ʐς������̂ł́A30MHz�͌��\�ȕϒ����o�����B�d����ʏ�ɍi���Ă���Ȃ�A�M���͂����ĕς�炸�A�������炢���ȁH
����σh���C�u�̏�Ԃ��l�����Ă��A455KHz��Z�ϊ���2�i�����̕������Ȃ芴�x�͍����C������B���[��c�A�A����ʐς��������āc�A�A
�g�����X�`���ɂȂ��āA�I�����n�b�L�����������͂���̂����ǁA�M���o�͂̑傫����S/N�A�\�R�͕����Ă�\�����傢�ɔZ���ŃA���B
�����ŁA���v�����郂�m�Ȃ�ƍl���Ă݂��B
�܂��A������ƊȈՂȂ̂�����Č��������v���̂����ǁB
�����ō���Ă����m�B
�EPre-AMP�{�o�C�A�X��H�B
�EAGC-AMP
�E�t�F�C�Y�f�B�e�N�^�[
�ELPF�AHPF�ABPF�́A�t�F�C�Y�f�B�e�N�^�[�̐���̃p�[�c�Ɠ��������B�B
�EAOM�̃h���C�o�[�͊����i���������̂ō���ĂȂ����A����\�B
�E1.5D-2V�̓������g�����X��̃t�F���C�g�Ɋ����t���ăR�������[�h�t�B���^�[�ɂ��Ă����B
�EATT�F�A�b�e�l�[�^�[�F���邪�A�_�C�������ς�T�^�̂��W�����N�������Ďg���Ă��B
�E���U��F�����i���������A�܂��A��낤�Ǝv���c�A�A
�E���ˌ��J�b�g�̃s���z�[������ʒ����̕Ό��ׁX�Ƃ������m�̓e�L�g�[�ɒ��B�o����B
���v�ō��R�g���܂�����ȕ��i�́A
�EFM(�t���~���[)�AHM(�n�[�t�~���[)�A�g���A�Ήp�����Y�F��/40�Ƃ��������x�Ȃ̂Łc�A�A�����Y�̓��m�R�[�g���x�B
�E�K�X���[�U�[���U��F�K���X�H�|�i�H�]�v�ȃX�y�N�g�������BPF������p�[�c�B�ł��A���͔����̃��[�U�[�ŗǂ��Ȃ�Ƃ肠�������荠�B
�EAOM(�������w�f�q=�u���b�O�Z���Ƃ��Ă��B)�F��_���e����(TeO2)���̂̒��B�ƕ��ʂ̐��x����肾���A�����r�[���ɕϒ��������ʂ̊���̂Ȃ�A�F�X�o�������B
�E�t�H�gDi�F���ԊO�̈悾�����̂œ���p�[�c���BHM�����ꂾ�����B
�E����Ȃ�ɍ����X�g���[�W�ȃf�W�^�C�U�[�{�}���`�v���N�T�{�g���K�[�p�^�C�}�[�Batan�Ŋp�x���o���ɁA���ω��A�@�B�I�m�C�Y�̊ɘa���̋@�\�̃\�t�g�͎����ō쐬�BA/D���͂̐ϕ�������͂��萻�B
�X�e�[�W�ɍڂ���~���|�z���_�[�Ƃ��Ă̓|�s�����[���Ǝv����A�R�����~�������ǁB�����B�c�~���[�ނ��������ǁB�B
 �}�O�l�b�g�x�[�X�ނ��K�v��������B
�ł��A�����͕s�ւ����ǁA�������H���ɋ���(�A���~����)�̉�ɁA�X���b�g���āA�l�W�Œ��ߕt���Ĕ��ʂɓ������Ƃ����̂��ʔ�������ΒP���͂��Ȃ�����B
���Ƃ́APD�̏œ_�ʒu���킹��XYZ�X�e�[�W���g���Ă����ǁA�A���͂��Ȃ荂�����B�B
�}�O�l�b�g�x�[�X�ނ��K�v��������B
�ł��A�����͕s�ւ����ǁA�������H���ɋ���(�A���~����)�̉�ɁA�X���b�g���āA�l�W�Œ��ߕt���Ĕ��ʂɓ������Ƃ����̂��ʔ�������ΒP���͂��Ȃ�����B
���Ƃ́APD�̏œ_�ʒu���킹��XYZ�X�e�[�W���g���Ă����ǁA�A���͂��Ȃ荂�����B�B
 ���[��c�A����́A���炩�̍H�v���āA�A�Ƃ��������B���b�N&�s�j�I���̃}�E���g��3�g�������Ȃ肩���H�e���l�W�ł�������o���Ȃ����������ǁB
�����A���v�́A1�Z�b�g600�`1000��������ƌ���ꂽ�V�X�e���Ȃ̂ł���ȃ��m���B�t�ɋ��ɕ������킹��A�p�[�c�͈��Ղɑ��������m��Ȃ��B�����̘r�͕ʂ����ǁB
�����e�[�}��4�����ŏI���A���̌㍂���\��������A���̌������⑼��ɒ�����B�������͔�������B
�������ł݂������B���x�ω���K�^�A���l�̍Č����̓A���V�C���������邾�낤���ǁB�B�t���C�X���H�p�̃x�[�X�p�r�������݂����B
���[��c�A����́A���炩�̍H�v���āA�A�Ƃ��������B���b�N&�s�j�I���̃}�E���g��3�g�������Ȃ肩���H�e���l�W�ł�������o���Ȃ����������ǁB
�����A���v�́A1�Z�b�g600�`1000��������ƌ���ꂽ�V�X�e���Ȃ̂ł���ȃ��m���B�t�ɋ��ɕ������킹��A�p�[�c�͈��Ղɑ��������m��Ȃ��B�����̘r�͕ʂ����ǁB
�����e�[�}��4�����ŏI���A���̌㍂���\��������A���̌������⑼��ɒ�����B�������͔�������B
�������ł݂������B���x�ω���K�^�A���l�̍Č����̓A���V�C���������邾�낤���ǁB�B�t���C�X���H�p�̃x�[�X�p�r�������݂����B

 ���x�s���̃����Y�A�~���[��(���͍̂����p������)���ꉞ����悤�����A�z���_�[��BPF�͌�������Ȃ��B
���������A�����̃T�[�{�ɂ�鉓�u������l���Ă����B
���x�A����������ׂČ������B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220315
�ŁA�����Ȃ̂����A�����X�O���I�̃W���o�����~���[�z���_�[��1���ÂŔ����Ă��̂ōw���B���~���[�t���H5000�~�Ƃ����j�i�l�ł������B
�C�O��eBay�Œ��Â͂��������A�V�O�}���@�̂�$150������ł������̂ŁB
���x�s���̃����Y�A�~���[��(���͍̂����p������)���ꉞ����悤�����A�z���_�[��BPF�͌�������Ȃ��B
���������A�����̃T�[�{�ɂ�鉓�u������l���Ă����B
���x�A����������ׂČ������B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220315
�ŁA�����Ȃ̂����A�����X�O���I�̃W���o�����~���[�z���_�[��1���ÂŔ����Ă��̂ōw���B���~���[�t���H5000�~�Ƃ����j�i�l�ł������B
�C�O��eBay�Œ��Â͂��������A�V�O�}���@�̂�$150������ł������̂ŁB
 XYZR�X�e�[�W���Z�[���������̂ōw���B
�������܂ލ��v: �� 16,644
�W���o�����~���[�z���_�[�́A����3�`4�K�v�B
AOM�́A�܂��͊����i���B�Ǝv���Ă��邪�A����@�̒��Â�3�`4���ł��銴���B
�~���[�́A���[�U�[����@�̂́c�A������x�g�����ɂȂ�c�A�A
���ƁA�O���ɏ���ė���A�N���X�^���I�V���[�^�[�̃v���O���~���O�c�[�����w�����Ă��ǂ���������Ȃ��B
�ʐM�p��1�ʃI�[�_�[��LD�ƃV���O�����[�h�t�@�C�o�[�Ƃ����̂�����Ă݂������ǁA����͗\�Z�I�ɑ�ς����B���p�[�c�����Ȃ荂���B
�ŋ߂ɂȂ��āA���v���O�O���āA
�\�z�͂��Ă����ǁA���v�́A�d�͔g�̑���ɂ����Ȃ�L�]�Ȃ悤���B
�R�����������B�����^�C�v�Ȃ̂����V�O�}���@�̂́}3�������ǁA����́}4���ł���B
�l�i���荠������A�Z���^�[���Y���Ă��ǂ������Ɏg����Ηǂ��Ǝv���B
�������A�a���C���`�Ȃ̂ŁA30�~mm�^�C�v�̃~���[�͖����������B�܂��A�\��t����Εt���Ȃ����Ƃł��������ǁc�A
XYZR�X�e�[�W���Z�[���������̂ōw���B
�������܂ލ��v: �� 16,644
�W���o�����~���[�z���_�[�́A����3�`4�K�v�B
AOM�́A�܂��͊����i���B�Ǝv���Ă��邪�A����@�̒��Â�3�`4���ł��銴���B
�~���[�́A���[�U�[����@�̂́c�A������x�g�����ɂȂ�c�A�A
���ƁA�O���ɏ���ė���A�N���X�^���I�V���[�^�[�̃v���O���~���O�c�[�����w�����Ă��ǂ���������Ȃ��B
�ʐM�p��1�ʃI�[�_�[��LD�ƃV���O�����[�h�t�@�C�o�[�Ƃ����̂�����Ă݂������ǁA����͗\�Z�I�ɑ�ς����B���p�[�c�����Ȃ荂���B
�ŋ߂ɂȂ��āA���v���O�O���āA
�\�z�͂��Ă����ǁA���v�́A�d�͔g�̑���ɂ����Ȃ�L�]�Ȃ悤���B
�R�����������B�����^�C�v�Ȃ̂����V�O�}���@�̂́}3�������ǁA����́}4���ł���B
�l�i���荠������A�Z���^�[���Y���Ă��ǂ������Ɏg����Ηǂ��Ǝv���B
�������A�a���C���`�Ȃ̂ŁA30�~mm�^�C�v�̃~���[�͖����������B�܂��A�\��t����Εt���Ȃ����Ƃł��������ǁc�A
 �Ƃ肠�����A2�����B�B
HM����Ȃ����āA�L���[�u�^�C�v�̃r�[���X�v���b�^�[�����荠�����H
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�����e����ĂāA
�I�b�T���̂܂������ȋZ�p(�z�r�[)���x������̃}�E���g��������������ǁA
�Z�p�Ҋ������҂͂���Ȃ��ƌ���Ȃ��B���x���̈Ⴂ��������ˁB
���������y�̓o�b�T���ƒׂ������čs�������ˁB�g�̒����킫�܂���B�Ǝv������B
���ɁA3D�v�����^�[�Ƃ��g���Đ��䃂�[�^�[����Ă��l�ɂ��A�����悤�ȃ��c�����Ăď����̂ɂ��悤�Ƃ��Ă��B
����l���猩��A�X���N�\�c�C�l�����I�悵�Ă�킯�ŁB�l�i����x�������Č��ꂵ���ˁB
�킴�킴�q�g���o�J�ɂ��ɗ�����爫�����ȁ`�A�A
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���������A���[�������Ȃ������Ȃ̂����A�ʂ̃��[���A�h���X���瑗���Ă݂Ă���B
���A�����͒�x���Ȃ̂ŁA�܂��킩��Ȃ��B
2K���̃o�C�A�X��R�ŁA455KHz�̂̎����ɍ��܂Ŏg���Ă����A��ʐς�PD��30MHz�̉�H�Ɏg���Č�����A�M�������\�オ�����B
�o�C�A�X��R����肭�M��A��������ł����ƃQ�C�����҂���Ǝv���B
�P�œ_�̎�����K���X�����Y�́A���[�U�[�R�����[�g�p�����Ɉ����ɑ��݂��Ă���B�F�X���p���o�������B
�Ԃ�̔�����LD�Ɍ��������wBPF���A�T���Ώo�Ă��邩���m��Ȃ��̂ŁA����������ƒT���Ă݂悤�Ǝv���B
AOM�̃h���C�u���g�������āA80MHz�������悤�Ȃ̂ŁA������l���ɓ���悤�Ǝv���B
80MHz��FCZ�R�C�����A10mm�A7mm�����Ƃ����݂��邵�A���ꂭ�炢�̎��g���Ȃ�A�{�r���Ɏ芪�����\�����m��Ȃ��B
���̂����A���v�̘b�Ɉړ]���邩���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�Ȃ��A���v�쐬�̋C�����{�C�ɂȂ��Ă����B
�Ƃ͂����AAOM�������A�������̂�B�B
�r�[���X�v���b�^�[���w���������A�g�������ȃ��m�͗\�z�O�ɍ��������B�������݂�2383�~
���˖ʃ�/8�A�K���X�\�ʃ�/10�ƌ������x�B
�Ƃ肠�����A2�����B�B
HM����Ȃ����āA�L���[�u�^�C�v�̃r�[���X�v���b�^�[�����荠�����H
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�����e����ĂāA
�I�b�T���̂܂������ȋZ�p(�z�r�[)���x������̃}�E���g��������������ǁA
�Z�p�Ҋ������҂͂���Ȃ��ƌ���Ȃ��B���x���̈Ⴂ��������ˁB
���������y�̓o�b�T���ƒׂ������čs�������ˁB�g�̒����킫�܂���B�Ǝv������B
���ɁA3D�v�����^�[�Ƃ��g���Đ��䃂�[�^�[����Ă��l�ɂ��A�����悤�ȃ��c�����Ăď����̂ɂ��悤�Ƃ��Ă��B
����l���猩��A�X���N�\�c�C�l�����I�悵�Ă�킯�ŁB�l�i����x�������Č��ꂵ���ˁB
�킴�킴�q�g���o�J�ɂ��ɗ�����爫�����ȁ`�A�A
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���������A���[�������Ȃ������Ȃ̂����A�ʂ̃��[���A�h���X���瑗���Ă݂Ă���B
���A�����͒�x���Ȃ̂ŁA�܂��킩��Ȃ��B
2K���̃o�C�A�X��R�ŁA455KHz�̂̎����ɍ��܂Ŏg���Ă����A��ʐς�PD��30MHz�̉�H�Ɏg���Č�����A�M�������\�オ�����B
�o�C�A�X��R����肭�M��A��������ł����ƃQ�C�����҂���Ǝv���B
�P�œ_�̎�����K���X�����Y�́A���[�U�[�R�����[�g�p�����Ɉ����ɑ��݂��Ă���B�F�X���p���o�������B
�Ԃ�̔�����LD�Ɍ��������wBPF���A�T���Ώo�Ă��邩���m��Ȃ��̂ŁA����������ƒT���Ă݂悤�Ǝv���B
AOM�̃h���C�u���g�������āA80MHz�������悤�Ȃ̂ŁA������l���ɓ���悤�Ǝv���B
80MHz��FCZ�R�C�����A10mm�A7mm�����Ƃ����݂��邵�A���ꂭ�炢�̎��g���Ȃ�A�{�r���Ɏ芪�����\�����m��Ȃ��B
���̂����A���v�̘b�Ɉړ]���邩���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�Ȃ��A���v�쐬�̋C�����{�C�ɂȂ��Ă����B
�Ƃ͂����AAOM�������A�������̂�B�B
�r�[���X�v���b�^�[���w���������A�g�������ȃ��m�͗\�z�O�ɍ��������B�������݂�2383�~
���˖ʃ�/8�A�K���X�\�ʃ�/10�ƌ������x�B
 �l�I�ɂ́AAOM��BS��Z��]�ȊO�͓������Ȃ������ǂ��Ǝv���̂ŁA�������A��Ɍ��߂Ă��܂������B�Ȃ̂ŁA�e�L�g�[�ȃ}�E���g���@������A�A
���ƁA�}�E���g�x�[�X�A��(���b�h)�A�|�X�g�A�J���[�Ȃǂ͗����ɁB
���b�h�ƃ|�X�g�́A���킹�ău���P�b�g�Ƃ������ƂŁA�K�i���l���A�������[�J�[���ǂ����낤���A�R�R�̔�p���l���˂A���������������t���̂͒����Ȃ��B�B
�}�ʂł́A���b�h����12mm�A�|�X�g����12.7mm�Ƃ����̂������Ă��邯�ǁA�������ɂ���قǃK�^�͖������낤����A�K���ɏ����Ă���C������B
�ɂ��Ă��}�ʂ̋K���Ƃ��āA���E�Ώ̂��ᖳ���ƒ��S��(��_����)�͗v��Ȃ����A�ގ��̒��ɕ����������̂͒����Ȃ��Ƃ����R�g�ɂȂ��Ă�B�B�B�n�b�`���O�͖�������A-B�f�ʂƂ����������E�E
�������A����ɂ��Ă��A��������Ԃ̈�����������B�������i���܂Ƃ߂Ă����܂�����Ȃ�Ȃ��B
�R�R�ŁA�b���ς���āA
�L�ш��M�@��AR2002��AM��M���[�h�ɂāA30MHz���U��H��LED�ɂă`�F�b�N�B
1�`2m���x���ƁA��H����̓d�g�����Ŕ������Ă��܂��B
���̂܂܁A�t�o�C�A�X�������R���f���T�[�Ńf�J�b�v�����O�����t�H�g�_�C�I�[�h���炾�ƁA����ł͂Ȃ��悤�����A���\�ɋ��߂̃V�O�i��������B�����Y���悩�ȁH
�Œ������̓`�F�b�N�o���Ȃ��������A��������̎�M�@�̊��x���܂��܂��Ƃ��������ŃA���Ƃ������f���o�����B
���̎�M�@�́AAM���[�h��0.5��V(10dB S/N)�Ƃ���̂ŁA���Ȃ芴�x���ǂ��̂����m��Ȃ��B
���̋@��̉�H��MIX�͕�����Ȃ����ǁAFET�̃\�[�X��h���Ԃ邩�A�Q�[�g��2����FET���g���Ă����B
�����ɁA�i���[�o���h���Ƃ����̂�����Ǝv���̂ŁAIF����������A�A�A
�������U�{555�Ȃǂ̕Ώd�̌��ʂ̐��m�����K�v�Ƃ������ƂɂȂ�B
����BPF���L�������H�H
���Ƃ́A��p������A��ʐ�PD�{�R�����[�g�����Y���g���ȂǁA���v�ł͗ǂ����A�����e�ɂ͔��I�Ȋ����B
�ǂ����̍���̎��ƂƂ����������Łu���ʐM�v�Ƃ����̂�����Ă����̂ł����A7���Ԗڂ܂ŏI���Ȃ�����Ă��Ƃ��ɐ�グ�ċA�点�āA�ƌ����Ă��̂ł����A�A
���x�̃K�E�V�A�����z��A�_�u���X���b�g���Ȃ���������g�����t�Z�Ƃ��Ƃ����������ƋL���͂��Ă�̂ł����A
632.8nm�̃K�X���[�U�[�����͏����p�̃g�����X�������Ă�̂ŁA�\�R�̓r���ɒ[�q���A���M����t������Ƃ����P���ȕ��@�ł��āA�A
���ꂾ�Ƃ���܂�Ɏv���A������LD��APC��H(PD����)�ɕς��Ď����y�ѐ������Ă܂����B�ł������I����Ă��܂��ƌ����c�A�ꎞ�Ԕ����x�ŁA�A
�ŁA
���̂悤�ȍ\���ł�����A
�K�X���[�U�[�������ɋ߂��Ȃ�ƁA��́A�O�ɂǂ����̋L���ŏ������l�I���ǂ̎��������Ǝ����悤�Ȃ��Ƃł��āA
�P�ɃX���C�_�b�N�œd���d�����グ�Ă��A�܂����肵�Ďg����Ƃ������̂ł���܂��B
���������A�g�����X����200V�̌u�����͒������ł��ˁB�d�q�����臂ƒ�i�d���̊Ԃɗ]�T������̂ň��肵�ēd�q����Ԋ����ł��B
�V�O�}���@�̖ʐ��x�ۏ~���[�̃g�R���Č������ǃ�/10���ď����Ă���ȁ[�A�A�A
�R�[�g���ď����Ă��邩�炩�ȁH
�����C�A�A���~���C���g���Ă�����c�A�Ⴄ�̂��ȁH
�����ɗ��āA�V�O�}���@��~�j�T�[�L�b�g�AR&K�Ȃǂ̕������J�^���O���K�v�Ɋ������̂����ǁA�A�A�������ɁA�h�R�ɂ�����̂��B�B�B
���U��̓A�������ǁA���x�ɉe���̎ɂ����A�}�O�l�b�g�x�[�X�Ή��̏펥���̔�������䂪�~�������Ƃ͗~�����B
�l�W������R�Ă�����邯�ǁA���C�A�E�g���y�Ȋ����͂���B�d�݂ɂ�邽��݂Ɖ��x�����Ƃ��A�ǂ̒��x�̐��x�Ȃ̂��낤�B
���̊��x�Ɋւ��ẮA����LD�Ȃ�A�p���[�œ��ݓ|���R�g���o���郌�x�����Ǝv���B
�NjL��
�r�[���X�v���b�^�[�A�R���i�̃G�s�f�~�b�N�ɂ�莩��ҋ@�߂�1�`2�T�Ԍ���Ƃ��B�B
��������XYZR�X�e�[�W�́A�t���C�T�[�Ȃǂɕt����@�B���H�p�̂悤�����ǁA�ǂ��I���̉\���������B
�܂��APD���t�������Ȃ̂Ńl�W�̋K�i�̓e�L�g�[��OK�A���́AXYZ�X�e�[�W��OK�Ȃ̂ŁA�@�B�p���ƍX�Ɉ����Ȃ������ǁA�A
���w�p��XYZ�ł���͂�2���͉z����B
R�X�e�[�W�����O������ABS�p�Ɏg���邩���m��Ȃ��B
�啪�O�A���b�N&�s�j�I�������Ƃ͕����Ă����ǁA�����Ⴄ�悤�ȁc�A�A
�S�����ʼnƂ���������u�����u���삾�B�Ƃ������Ă��̂��B
���z�Ǝ��ԂƁA�ݒu�ꏊ�ŏ����ނ��Ă����B
���܂薧�ɂ��ƁA���邵�A�����H���̂ŁA�������ƁB�O���Ȃ��悤�ɁH
���ƁA
���i���������[���u���b�N�ŏ�肭�����ĂȂ������g�R�̂��ʃ��A�h�ŏ�肭�s�����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220316
30MHz�̂��̉�H�ł��A2SK439��2SK303�ƍ����ւ��ē������B�Ƃ������Ƃ́A���ҁA�}�C�i�X�ɉ�����o�C�A�X�̈�œ��삵�Ă�̂����A
����́A303�́A������ƃQ�C������߂ɏo���B���g���̖������肻�������A�����o�C�A�X�p�̒�RRs�ł�����x���P�o���邩�ȁ[�Ǝv���B
�܂��A303-V3����AVgs-Ids�̌��z�̍��߂����m��Ȃ��A303-V5�ɕς���Ƃ����Ɨǂ��Ȃ�\��������B
FCZ�R�C���̓����Z�b�e�B���O���قړ����Ȃ̂ŁA�����ւ��Ȃ��玎���Č���Ɩʔ��������m��Ȃ��B
���[�m�C�Y�Ȑ����A�������l������A303-V5�O�i�Ƃ����\�����m��Ȃ��H
�����A60MHz���x�܂Ŏg���邩�ȁ[�H�Ƃ������x�����Ǝv���B
220317
�l���Ă݂�ɁA������I�V����BW=70MHz�܂łȂ̂ŁA80MHz�̐v��������ƌ����������B
�Ƃ������ƂŁA�����60MHz���Ó��ȋC������B200MHz�����N�̃I�V������肷��̂͂�����ƃL�c�C�B
���̃Q�C����60�`70dB���x�Ǝv���A����50dB�قǂƍl����ƃ��N�ł͖����B
���U���傫�ȕǂł���A�R�A�̒����Ŕ����ɂ悯�Ă���̂����A����ȏ�͓���B
�e�i�̉�H���m��d���C�I�ɗ����K�v����������B
�m�F�ɂȂ邯�ǁA�����ł̔̔��̋K���́A
������p���i���S�@(PSC)�K�����i(���[�U�[�o�̓N���X2����)
�ł���A1mW�����Ǝv����B
���S���ōl����ƁA�r�[���̑�����A���s�x�Ȃǂɂ�邵�A�@��p�r�ɂ���Ă͋K���̑ΏۊO�B
�ŁA���ݎg�p���Ă�̂́A���ʂɒ������Ă���̂Ɠ������A5mW�����F�N���X3A�ł���BAPC����Ȃ��̂ő���3B���x���̏ꍇ�����邩���B
���ʊ�g���Ă�̂ŁA���̐Ód�e�ʂ͂���Ȃ�ɂ��邩������Ȃ��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220317
�������̃p�[�c�ނ��͂����B
FCZ�R�C����7mm�p�̃��m�́A���j�o�[�T����Ƀn�}��B���A������Ƌ����C���[�W�Ȃ̂ŁA�o�C�X�œ����֍��Ɨǂ��Ǝv���B�ʂ̌��͑傫�߂ɁB
�ŁA60MHz��FCZ�R�C���́A80MHz�ƌ��p���ǂ����ȁH50MHz���ƃL�c�C�����B
���Ƃ́AIF���g���ő������l����ƁA10.7MHz�́A14MHz�p���ȁH�����9MHz�̓L�c�C�����B
455KHz�̏ꍇ�A�O�ɏ��������Ǝv�����ǁA1.0MHz�p���g�����������B�Ⴂ���g��������Z���C�ɂ��Ȃ��悤�Ȃ̂ŁA�܂��ǂ����ƁB
�~���[�͋�F�ŁA���b�h�̎���20mm�Ƒ��߂̃��m�ŁA���̏�Ԃ͗ǂ��Ǝv���܂����B
�l�I�ɂ́AAOM��BS��Z��]�ȊO�͓������Ȃ������ǂ��Ǝv���̂ŁA�������A��Ɍ��߂Ă��܂������B�Ȃ̂ŁA�e�L�g�[�ȃ}�E���g���@������A�A
���ƁA�}�E���g�x�[�X�A��(���b�h)�A�|�X�g�A�J���[�Ȃǂ͗����ɁB
���b�h�ƃ|�X�g�́A���킹�ău���P�b�g�Ƃ������ƂŁA�K�i���l���A�������[�J�[���ǂ����낤���A�R�R�̔�p���l���˂A���������������t���̂͒����Ȃ��B�B
�}�ʂł́A���b�h����12mm�A�|�X�g����12.7mm�Ƃ����̂������Ă��邯�ǁA�������ɂ���قǃK�^�͖������낤����A�K���ɏ����Ă���C������B
�ɂ��Ă��}�ʂ̋K���Ƃ��āA���E�Ώ̂��ᖳ���ƒ��S��(��_����)�͗v��Ȃ����A�ގ��̒��ɕ����������̂͒����Ȃ��Ƃ����R�g�ɂȂ��Ă�B�B�B�n�b�`���O�͖�������A-B�f�ʂƂ����������E�E
�������A����ɂ��Ă��A��������Ԃ̈�����������B�������i���܂Ƃ߂Ă����܂�����Ȃ�Ȃ��B
�R�R�ŁA�b���ς���āA
�L�ш��M�@��AR2002��AM��M���[�h�ɂāA30MHz���U��H��LED�ɂă`�F�b�N�B
1�`2m���x���ƁA��H����̓d�g�����Ŕ������Ă��܂��B
���̂܂܁A�t�o�C�A�X�������R���f���T�[�Ńf�J�b�v�����O�����t�H�g�_�C�I�[�h���炾�ƁA����ł͂Ȃ��悤�����A���\�ɋ��߂̃V�O�i��������B�����Y���悩�ȁH
�Œ������̓`�F�b�N�o���Ȃ��������A��������̎�M�@�̊��x���܂��܂��Ƃ��������ŃA���Ƃ������f���o�����B
���̎�M�@�́AAM���[�h��0.5��V(10dB S/N)�Ƃ���̂ŁA���Ȃ芴�x���ǂ��̂����m��Ȃ��B
���̋@��̉�H��MIX�͕�����Ȃ����ǁAFET�̃\�[�X��h���Ԃ邩�A�Q�[�g��2����FET���g���Ă����B
�����ɁA�i���[�o���h���Ƃ����̂�����Ǝv���̂ŁAIF����������A�A�A
�������U�{555�Ȃǂ̕Ώd�̌��ʂ̐��m�����K�v�Ƃ������ƂɂȂ�B
����BPF���L�������H�H
���Ƃ́A��p������A��ʐ�PD�{�R�����[�g�����Y���g���ȂǁA���v�ł͗ǂ����A�����e�ɂ͔��I�Ȋ����B
�ǂ����̍���̎��ƂƂ����������Łu���ʐM�v�Ƃ����̂�����Ă����̂ł����A7���Ԗڂ܂ŏI���Ȃ�����Ă��Ƃ��ɐ�グ�ċA�点�āA�ƌ����Ă��̂ł����A�A
���x�̃K�E�V�A�����z��A�_�u���X���b�g���Ȃ���������g�����t�Z�Ƃ��Ƃ����������ƋL���͂��Ă�̂ł����A
632.8nm�̃K�X���[�U�[�����͏����p�̃g�����X�������Ă�̂ŁA�\�R�̓r���ɒ[�q���A���M����t������Ƃ����P���ȕ��@�ł��āA�A
���ꂾ�Ƃ���܂�Ɏv���A������LD��APC��H(PD����)�ɕς��Ď����y�ѐ������Ă܂����B�ł������I����Ă��܂��ƌ����c�A�ꎞ�Ԕ����x�ŁA�A
�ŁA
���̂悤�ȍ\���ł�����A
�K�X���[�U�[�������ɋ߂��Ȃ�ƁA��́A�O�ɂǂ����̋L���ŏ������l�I���ǂ̎��������Ǝ����悤�Ȃ��Ƃł��āA
�P�ɃX���C�_�b�N�œd���d�����グ�Ă��A�܂����肵�Ďg����Ƃ������̂ł���܂��B
���������A�g�����X����200V�̌u�����͒������ł��ˁB�d�q�����臂ƒ�i�d���̊Ԃɗ]�T������̂ň��肵�ēd�q����Ԋ����ł��B
�V�O�}���@�̖ʐ��x�ۏ~���[�̃g�R���Č������ǃ�/10���ď����Ă���ȁ[�A�A�A
�R�[�g���ď����Ă��邩�炩�ȁH
�����C�A�A���~���C���g���Ă�����c�A�Ⴄ�̂��ȁH
�����ɗ��āA�V�O�}���@��~�j�T�[�L�b�g�AR&K�Ȃǂ̕������J�^���O���K�v�Ɋ������̂����ǁA�A�A�������ɁA�h�R�ɂ�����̂��B�B�B
���U��̓A�������ǁA���x�ɉe���̎ɂ����A�}�O�l�b�g�x�[�X�Ή��̏펥���̔�������䂪�~�������Ƃ͗~�����B
�l�W������R�Ă�����邯�ǁA���C�A�E�g���y�Ȋ����͂���B�d�݂ɂ�邽��݂Ɖ��x�����Ƃ��A�ǂ̒��x�̐��x�Ȃ̂��낤�B
���̊��x�Ɋւ��ẮA����LD�Ȃ�A�p���[�œ��ݓ|���R�g���o���郌�x�����Ǝv���B
�NjL��
�r�[���X�v���b�^�[�A�R���i�̃G�s�f�~�b�N�ɂ�莩��ҋ@�߂�1�`2�T�Ԍ���Ƃ��B�B
��������XYZR�X�e�[�W�́A�t���C�T�[�Ȃǂɕt����@�B���H�p�̂悤�����ǁA�ǂ��I���̉\���������B
�܂��APD���t�������Ȃ̂Ńl�W�̋K�i�̓e�L�g�[��OK�A���́AXYZ�X�e�[�W��OK�Ȃ̂ŁA�@�B�p���ƍX�Ɉ����Ȃ������ǁA�A
���w�p��XYZ�ł���͂�2���͉z����B
R�X�e�[�W�����O������ABS�p�Ɏg���邩���m��Ȃ��B
�啪�O�A���b�N&�s�j�I�������Ƃ͕����Ă����ǁA�����Ⴄ�悤�ȁc�A�A
�S�����ʼnƂ���������u�����u���삾�B�Ƃ������Ă��̂��B
���z�Ǝ��ԂƁA�ݒu�ꏊ�ŏ����ނ��Ă����B
���܂薧�ɂ��ƁA���邵�A�����H���̂ŁA�������ƁB�O���Ȃ��悤�ɁH
���ƁA
���i���������[���u���b�N�ŏ�肭�����ĂȂ������g�R�̂��ʃ��A�h�ŏ�肭�s�����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220316
30MHz�̂��̉�H�ł��A2SK439��2SK303�ƍ����ւ��ē������B�Ƃ������Ƃ́A���ҁA�}�C�i�X�ɉ�����o�C�A�X�̈�œ��삵�Ă�̂����A
����́A303�́A������ƃQ�C������߂ɏo���B���g���̖������肻�������A�����o�C�A�X�p�̒�RRs�ł�����x���P�o���邩�ȁ[�Ǝv���B
�܂��A303-V3����AVgs-Ids�̌��z�̍��߂����m��Ȃ��A303-V5�ɕς���Ƃ����Ɨǂ��Ȃ�\��������B
FCZ�R�C���̓����Z�b�e�B���O���قړ����Ȃ̂ŁA�����ւ��Ȃ��玎���Č���Ɩʔ��������m��Ȃ��B
���[�m�C�Y�Ȑ����A�������l������A303-V5�O�i�Ƃ����\�����m��Ȃ��H
�����A60MHz���x�܂Ŏg���邩�ȁ[�H�Ƃ������x�����Ǝv���B
220317
�l���Ă݂�ɁA������I�V����BW=70MHz�܂łȂ̂ŁA80MHz�̐v��������ƌ����������B
�Ƃ������ƂŁA�����60MHz���Ó��ȋC������B200MHz�����N�̃I�V������肷��̂͂�����ƃL�c�C�B
���̃Q�C����60�`70dB���x�Ǝv���A����50dB�قǂƍl����ƃ��N�ł͖����B
���U���傫�ȕǂł���A�R�A�̒����Ŕ����ɂ悯�Ă���̂����A����ȏ�͓���B
�e�i�̉�H���m��d���C�I�ɗ����K�v����������B
�m�F�ɂȂ邯�ǁA�����ł̔̔��̋K���́A
������p���i���S�@(PSC)�K�����i(���[�U�[�o�̓N���X2����)
�ł���A1mW�����Ǝv����B
���S���ōl����ƁA�r�[���̑�����A���s�x�Ȃǂɂ�邵�A�@��p�r�ɂ���Ă͋K���̑ΏۊO�B
�ŁA���ݎg�p���Ă�̂́A���ʂɒ������Ă���̂Ɠ������A5mW�����F�N���X3A�ł���BAPC����Ȃ��̂ő���3B���x���̏ꍇ�����邩���B
���ʊ�g���Ă�̂ŁA���̐Ód�e�ʂ͂���Ȃ�ɂ��邩������Ȃ��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220317
�������̃p�[�c�ނ��͂����B
FCZ�R�C����7mm�p�̃��m�́A���j�o�[�T����Ƀn�}��B���A������Ƌ����C���[�W�Ȃ̂ŁA�o�C�X�œ����֍��Ɨǂ��Ǝv���B�ʂ̌��͑傫�߂ɁB
�ŁA60MHz��FCZ�R�C���́A80MHz�ƌ��p���ǂ����ȁH50MHz���ƃL�c�C�����B
���Ƃ́AIF���g���ő������l����ƁA10.7MHz�́A14MHz�p���ȁH�����9MHz�̓L�c�C�����B
455KHz�̏ꍇ�A�O�ɏ��������Ǝv�����ǁA1.0MHz�p���g�����������B�Ⴂ���g��������Z���C�ɂ��Ȃ��悤�Ȃ̂ŁA�܂��ǂ����ƁB
�~���[�͋�F�ŁA���b�h�̎���20mm�Ƒ��߂̃��m�ŁA���̏�Ԃ͗ǂ��Ǝv���܂����B
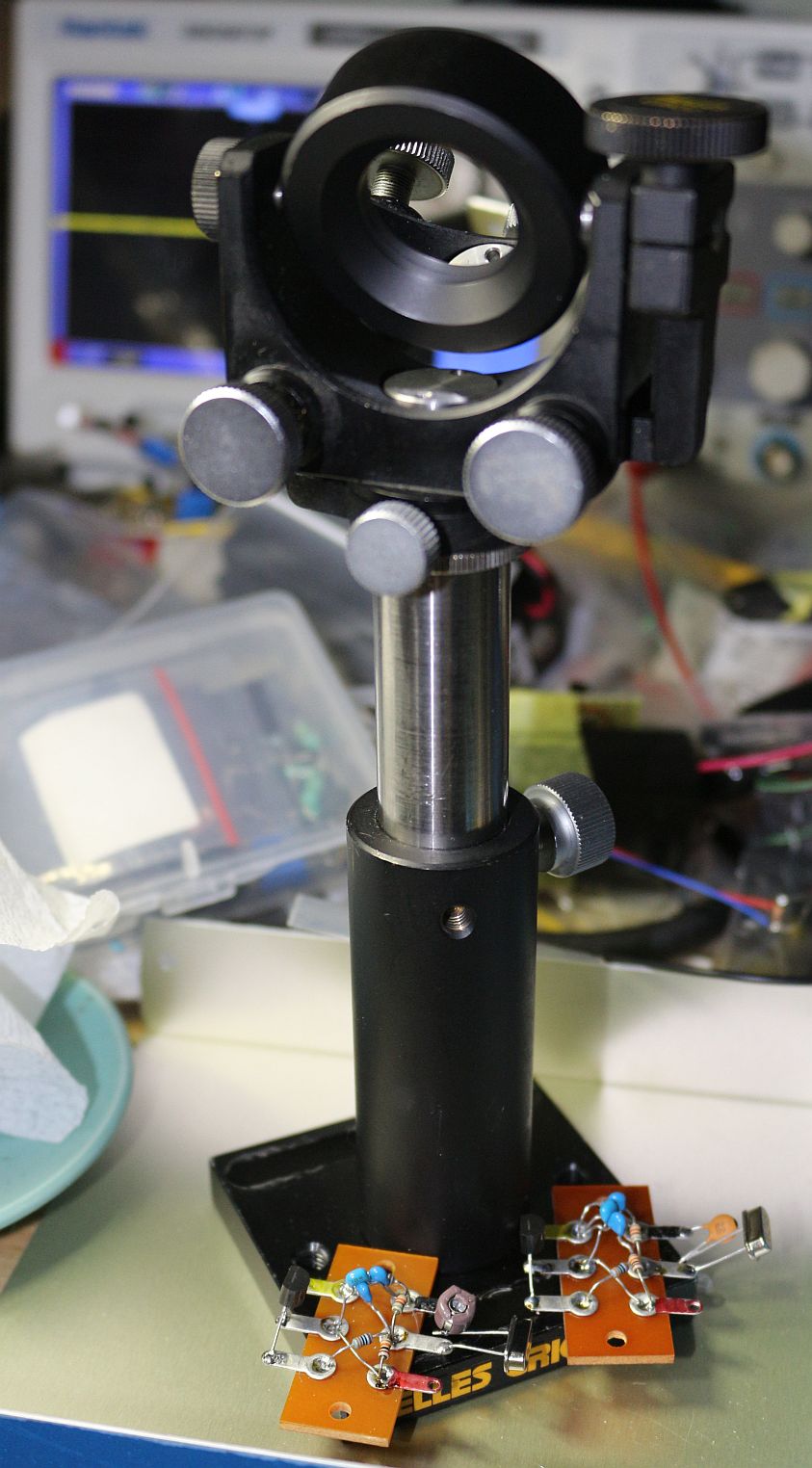 �����ŃC���`�K�i�Ƃ̓���̖�肪�o�Ă��邯�ǁA
���ɗ��~���[�z���_�[��mm�K�i�ō��킹�邱�Ƃɂ������Ǝv���܂��B
���ؐ��͌��ɂ˂����ĂȂ��݂����Ȃ̂�����A��J�͂����Ƃ�����Ȃ�ɂ������Ǝv���܂��B
�ł��A���{���̃u���P�b�g�͍����̂ŁA����mm������A���Ƃ́A���Â��A�u���b�N��̃��m�ɂ������Ă��ǂ���������Ȃ��Ǝv���Ă���܂��B
���{�̌������̏ꍇ�A�K�X���[�U�[�������X�O���I�ő��͊F�A�V�O�}���@�����������̂ł����A
�����A���̐��i�́A�݊���������悤�ȋC�����܂��B
���ɒu���Ă���̂́A�͂����p�[�c�őg�N���X�^��OSC�B
120pF�̃g���}�[(���F��)���t���Ă�����A����́A12.3125MHz�̃��m�ŁA��������ƁA12.3095�ʂ܂ł͍s���B
���̂܂܁A30MHz����IF��10.7MHz���o�����߂́A12.3MHz�Ƃ��Ďg���܂��B�Y���̓t�B���^�[�ł͈ꉞ�A�X���[����ш�ł��B
�Z���~�b�N�t�B���^�[��WFM�p���l�����Ă�̂ŁA�ʉߎ��g�����A�}30KHz�Ȃ̂ŁA
(�N���X�^���t�B���^�[��BW=15KHz�ł���A���傢�L�c�C�B12.6608MHz�{555���U�̍����̕��@�Ȃ�A���ł����A�A�A)
�܂��A10��H���x���R�C���ׂɒ���ɂ���X�ɓ�������悤�ł��B
�ŁA����Ă݂�B
���̃~�L�T�[�́A���o�͂��R���f���T�[�Ńf�J�b�v�����O���Ȃ��Ɠd������������I�t�Z�b�g�����肷��̂Ń_���B
AC�M��������ƌ����ďȗ��͏o���Ȃ��B�߂�ǂ������d�l���B
�����ŃC���`�K�i�Ƃ̓���̖�肪�o�Ă��邯�ǁA
���ɗ��~���[�z���_�[��mm�K�i�ō��킹�邱�Ƃɂ������Ǝv���܂��B
���ؐ��͌��ɂ˂����ĂȂ��݂����Ȃ̂�����A��J�͂����Ƃ�����Ȃ�ɂ������Ǝv���܂��B
�ł��A���{���̃u���P�b�g�͍����̂ŁA����mm������A���Ƃ́A���Â��A�u���b�N��̃��m�ɂ������Ă��ǂ���������Ȃ��Ǝv���Ă���܂��B
���{�̌������̏ꍇ�A�K�X���[�U�[�������X�O���I�ő��͊F�A�V�O�}���@�����������̂ł����A
�����A���̐��i�́A�݊���������悤�ȋC�����܂��B
���ɒu���Ă���̂́A�͂����p�[�c�őg�N���X�^��OSC�B
120pF�̃g���}�[(���F��)���t���Ă�����A����́A12.3125MHz�̃��m�ŁA��������ƁA12.3095�ʂ܂ł͍s���B
���̂܂܁A30MHz����IF��10.7MHz���o�����߂́A12.3MHz�Ƃ��Ďg���܂��B�Y���̓t�B���^�[�ł͈ꉞ�A�X���[����ш�ł��B
�Z���~�b�N�t�B���^�[��WFM�p���l�����Ă�̂ŁA�ʉߎ��g�����A�}30KHz�Ȃ̂ŁA
(�N���X�^���t�B���^�[��BW=15KHz�ł���A���傢�L�c�C�B12.6608MHz�{555���U�̍����̕��@�Ȃ�A���ł����A�A�A)
�܂��A10��H���x���R�C���ׂɒ���ɂ���X�ɓ�������悤�ł��B
�ŁA����Ă݂�B
���̃~�L�T�[�́A���o�͂��R���f���T�[�Ńf�J�b�v�����O���Ȃ��Ɠd������������I�t�Z�b�g�����肷��̂Ń_���B
AC�M��������ƌ����ďȗ��͏o���Ȃ��B�߂�ǂ������d�l���B
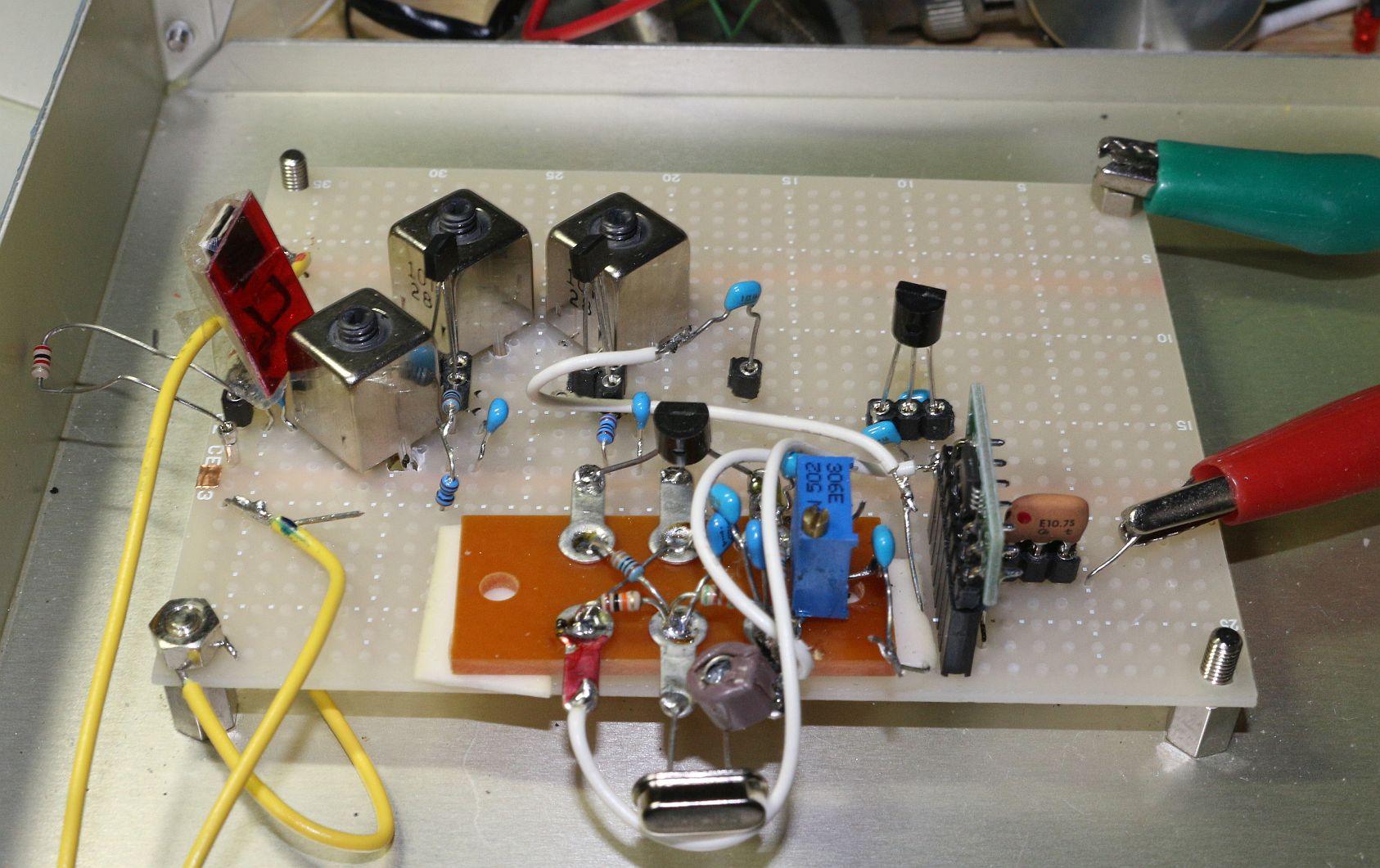 �����Ƃ���A10.6905�ł���B
������܂��A10.245MHz����߂ɃN���X�^�����������g���������āA455KHz�ɕϊ����Z���~�b�N�t�B���^�[��ʂ��B
���̊ԁA���x���������\���ȁH�Ǝv���Ă���B�܂��A30MHz�̒i�K�ł����������������o������c�A�Ƃ������Ă���B
�����Ƃ���A10.6905�ł���B
������܂��A10.245MHz����߂ɃN���X�^�����������g���������āA455KHz�ɕϊ����Z���~�b�N�t�B���^�[��ʂ��B
���̊ԁA���x���������\���ȁH�Ǝv���Ă���B�܂��A30MHz�̒i�K�ł����������������o������c�A�Ƃ������Ă���B
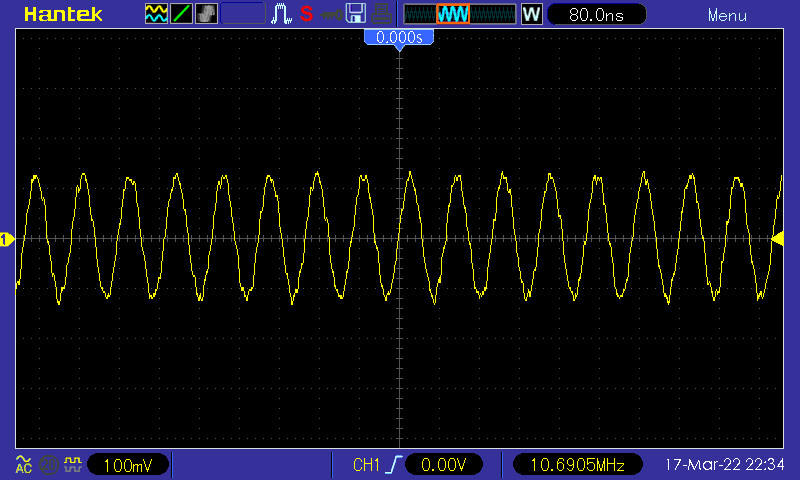 �ׂ����g�`�́A�L�����A�ƃV�O�i���𑫂������g�����R��Ă���̂ł́H�Ƃ�������B
LED�ł܂Ƃ��ɓ��삳����ɂ́A����80dB�ʗ~���������B
220318
�����܂ł��āA555��d���Ƃ��Č��炷�ƁA�d��������Ȃ��Ƃ������A�d���~�������Ă��邱�ƂɋC���t���B
�̂ɁATr�ő������ăX�C�b�`���Ă�邱�ƂɁB
��肢���@���v�����Ȃ������̂����A2SC1815��p���ď�肭�s�����B
�ׂ����g�`�́A�L�����A�ƃV�O�i���𑫂������g�����R��Ă���̂ł́H�Ƃ�������B
LED�ł܂Ƃ��ɓ��삳����ɂ́A����80dB�ʗ~���������B
220318
�����܂ł��āA555��d���Ƃ��Č��炷�ƁA�d��������Ȃ��Ƃ������A�d���~�������Ă��邱�ƂɋC���t���B
�̂ɁATr�ő������ăX�C�b�`���Ă�邱�ƂɁB
��肢���@���v�����Ȃ������̂����A2SC1815��p���ď�肭�s�����B
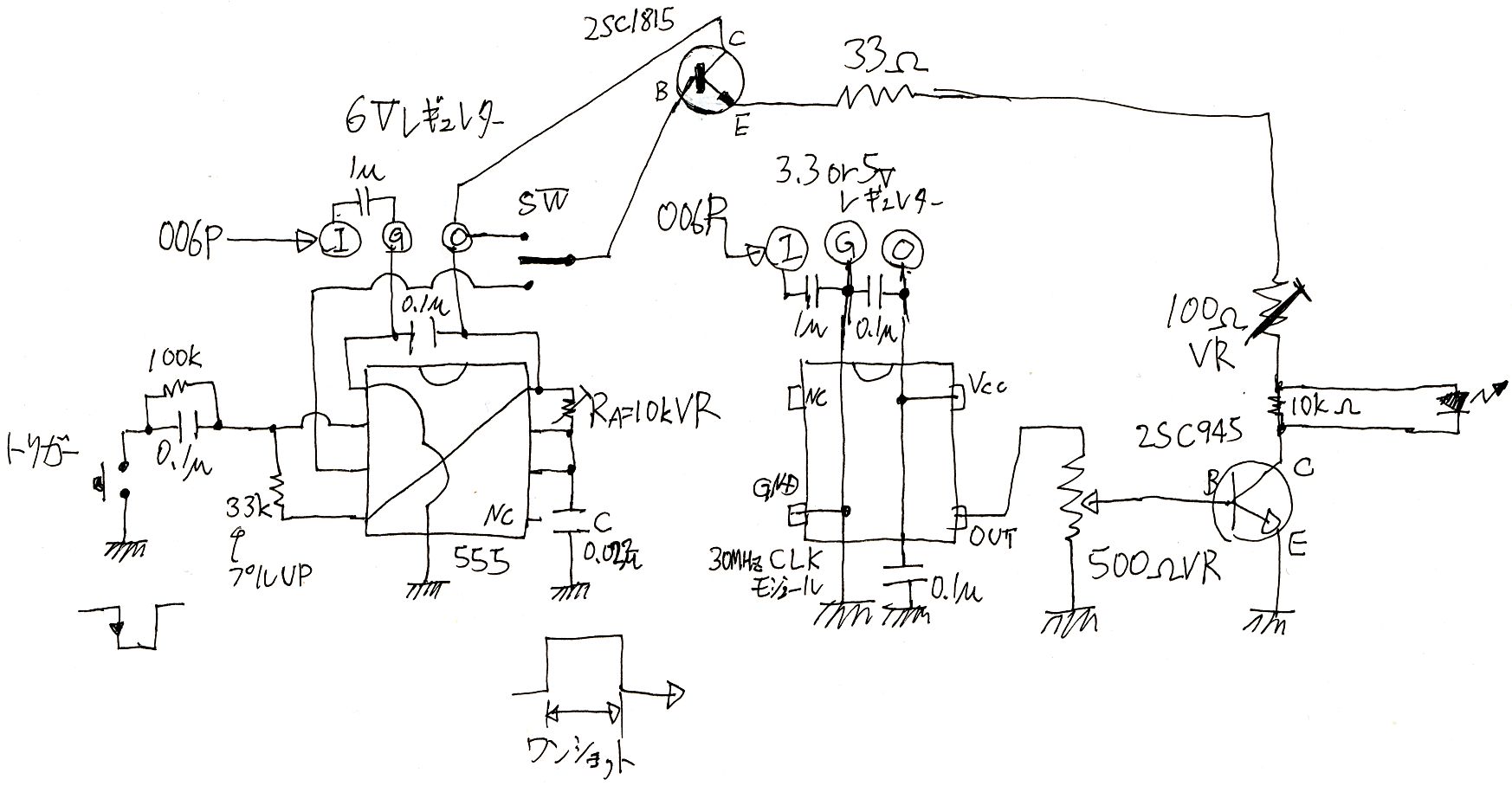 �g���K�[���̃R���f���T�[�́A0.001��F�ɂ����B��R�͕ς��ĂȂ����A1M���ȏオ�K���Ɏv���B
�����͂���Ȋ����B
�g���K�[���̃R���f���T�[�́A0.001��F�ɂ����B��R�͕ς��ĂȂ����A1M���ȏオ�K���Ɏv���B
�����͂���Ȋ����B
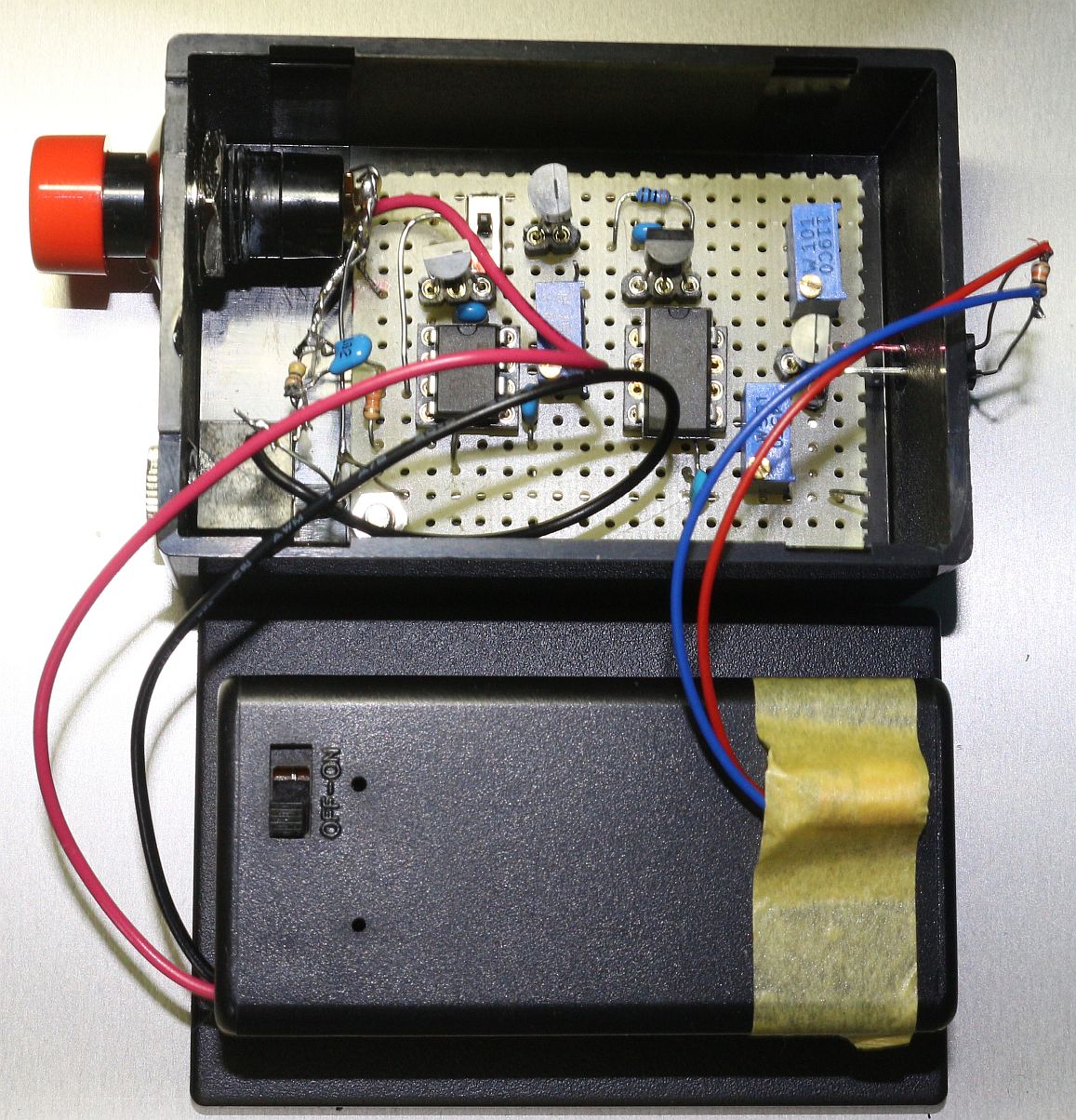 ��3.5mm�W���b�N�Ƀg���K�[�ƂȂ�X�C�b�`���q���B�Ԃ��{�^���̓e�X�g�p�ʼn����Ă�Ԃ͘A�������B
��3.5mm�W���b�N�Ƀg���K�[�ƂȂ�X�C�b�`���q���B�Ԃ��{�^���̓e�X�g�p�ʼn����Ă�Ԃ͘A�������B
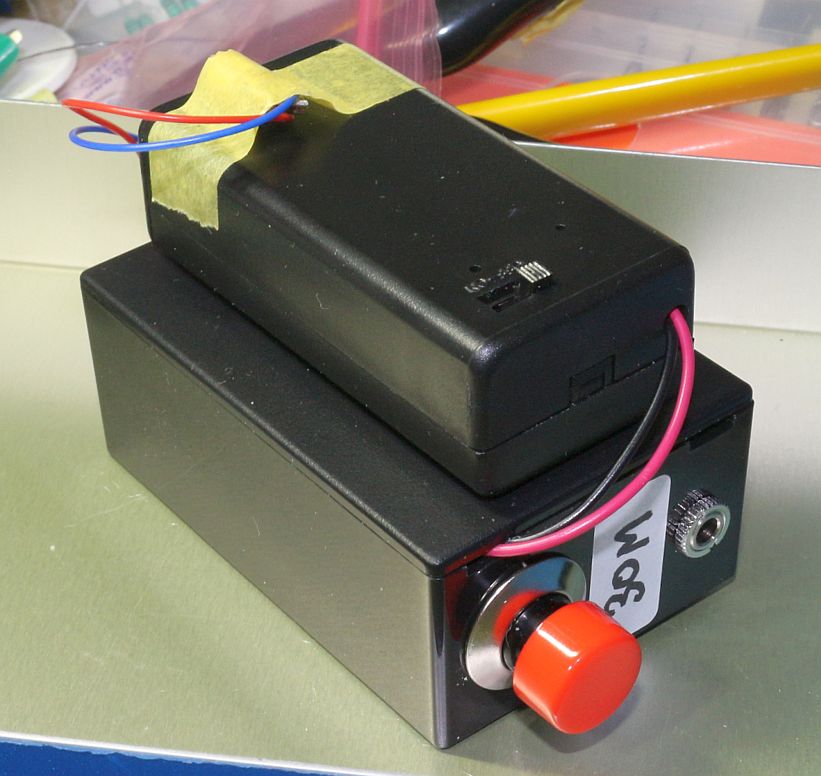 �����V���b�g�������Ă݂�B120��Sec���x�B��u���邭����̂�������B
��M���j�b�g��IF=10.7MHz��p������B
�����V���b�g�������Ă݂�B120��Sec���x�B��u���邭����̂�������B
��M���j�b�g��IF=10.7MHz��p������B
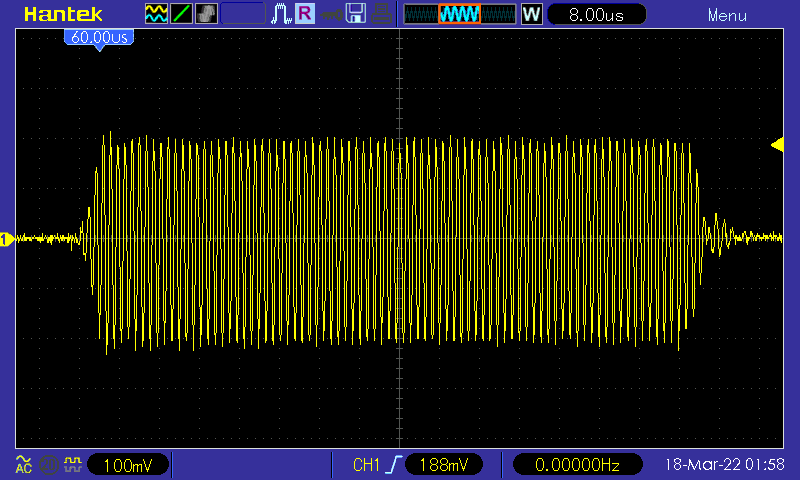 ���̂Ƃ���A�����ƒZ���p���X�ł��C�P�銴���ŃA���B
����455KHz�̃t�B���^�[�ŗ����オ�肪�݂邩�H�Ƃ����g�R�B�B
�NjL��
555��4��(���Z�b�g)�s����Vcc���q���Ă��邪�A����͂Ȃ��ق����ǂ���������Ȃ��ꍇ���H�`���^�����O�̌����H�B
2�ԃs�����グ�Ă����v���A�b�v��R�͗L���������ǂ��B�̂Ƀ��C�A�E�g�����X�ς��B
�����A����A555�̎�ނɂ����݂����ł���B�f�[�^�V�[�g���Ă��A�C���C���A�����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
������̑������A2SK439E��3�i�ɂ��Ă݂��B
���\�Ȕ��U�͂��Ă���ɂ�������炸�A�Q�C�����啝�ɉ��P����A���U��IF�̃t�B���^�[���Y��ɃJ�b�g����Ă���B
���U�͐M�����Ԃꂽ��A�s����ɂȂ�قǂł��Ȃ�����A�܂��ǂ���������Ȃ��B
�O�́A�r�[�g�A�b�v�Ǝv����4�{�قǂ̐U��������ꂽ���A�M�����傫���Ȃ������߂��A�g�`�̉��P������ꂽ�B
���̂Ƃ���A�����ƒZ���p���X�ł��C�P�銴���ŃA���B
����455KHz�̃t�B���^�[�ŗ����オ�肪�݂邩�H�Ƃ����g�R�B�B
�NjL��
555��4��(���Z�b�g)�s����Vcc���q���Ă��邪�A����͂Ȃ��ق����ǂ���������Ȃ��ꍇ���H�`���^�����O�̌����H�B
2�ԃs�����グ�Ă����v���A�b�v��R�͗L���������ǂ��B�̂Ƀ��C�A�E�g�����X�ς��B
�����A����A555�̎�ނɂ����݂����ł���B�f�[�^�V�[�g���Ă��A�C���C���A�����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
������̑������A2SK439E��3�i�ɂ��Ă݂��B
���\�Ȕ��U�͂��Ă���ɂ�������炸�A�Q�C�����啝�ɉ��P����A���U��IF�̃t�B���^�[���Y��ɃJ�b�g����Ă���B
���U�͐M�����Ԃꂽ��A�s����ɂȂ�قǂł��Ȃ�����A�܂��ǂ���������Ȃ��B
�O�́A�r�[�g�A�b�v�Ǝv����4�{�قǂ̐U��������ꂽ���A�M�����傫���Ȃ������߂��A�g�`�̉��P������ꂽ�B
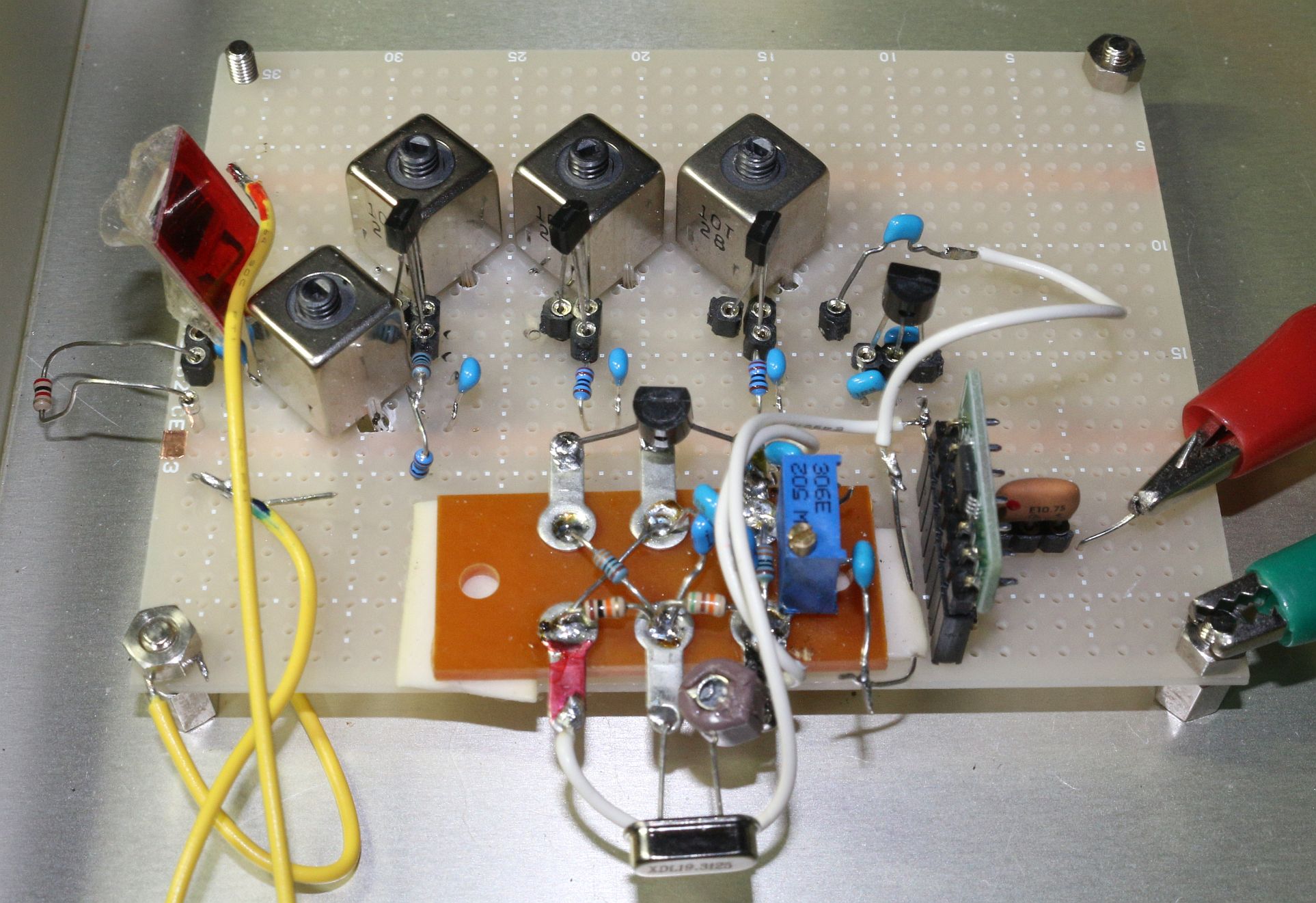 BNC�ŃX�}�[�g�ɂ����B����܂�W�Ȃ������B
�C���s�[�_���X���I�[�_�[���x�Ɋɂ߂ɍ��킹�Ă͂���B
���Ƃ��ƁA�ꍇ�Ɋ�肾���A�I�V����O��100���Ń^�[�~�l�C�g���Ă���B
�Ⴂ�Ƃ����獂���g�R�ɍs���ƌ��\���˂��N���邪�A10.7MHz�Ȃ̂ŁA����ܐ_�o���ɂȂ��Ă��W���Ȃ��B
���̃P�[�u���́A�����̂ŁA75�������m��Ȃ��B
BNC�ŃX�}�[�g�ɂ����B����܂�W�Ȃ������B
�C���s�[�_���X���I�[�_�[���x�Ɋɂ߂ɍ��킹�Ă͂���B
���Ƃ��ƁA�ꍇ�Ɋ�肾���A�I�V����O��100���Ń^�[�~�l�C�g���Ă���B
�Ⴂ�Ƃ����獂���g�R�ɍs���ƌ��\���˂��N���邪�A10.7MHz�Ȃ̂ŁA����ܐ_�o���ɂȂ��Ă��W���Ȃ��B
���̃P�[�u���́A�����̂ŁA75�������m��Ȃ��B
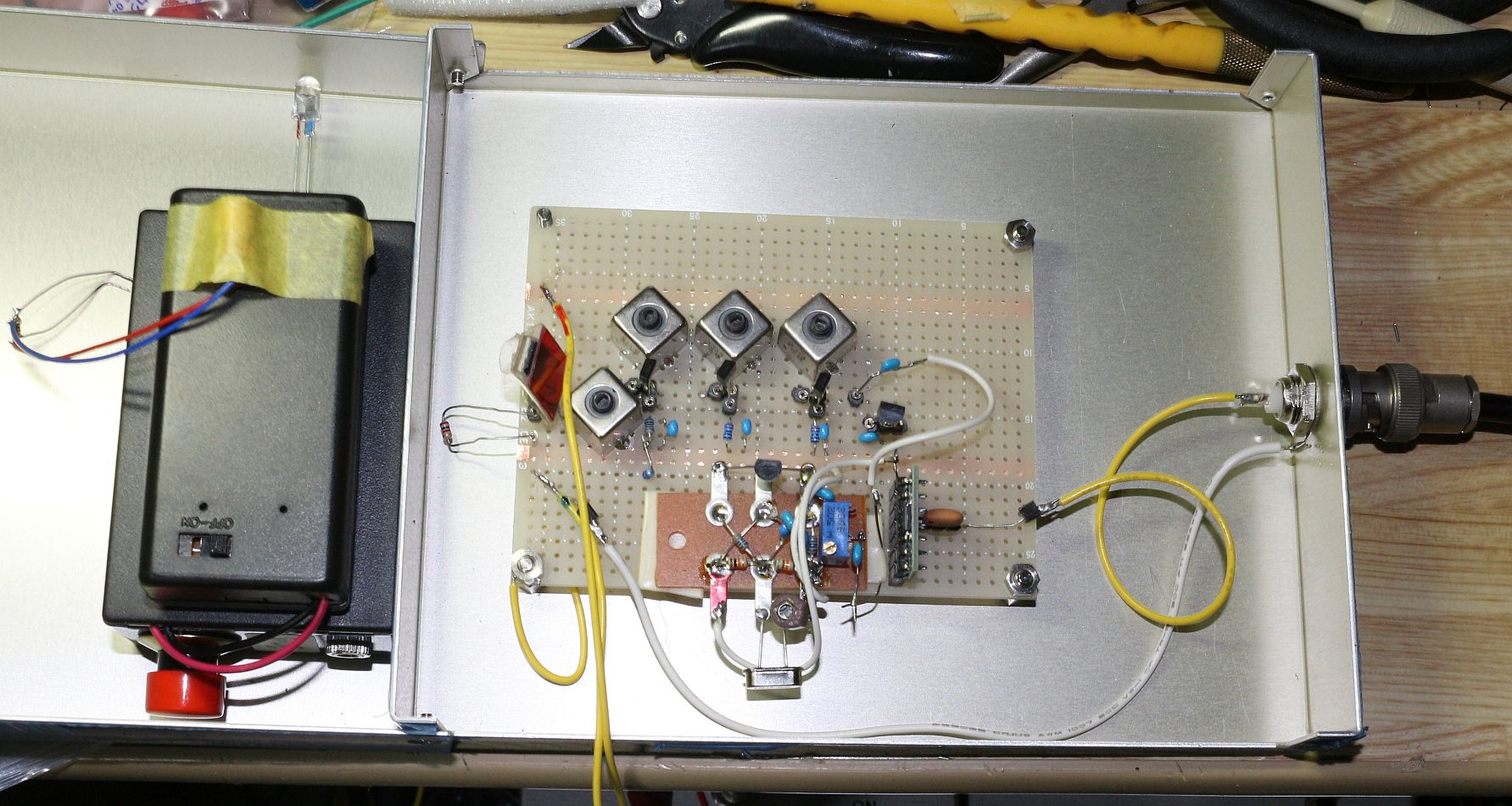 �ŁALED���ƁA�܂��A2�`3m���g�`�̑��݂��ǂ߂�g�R���Ǝv���B30MHz�̉�H�ł́A����ł��A���Ȃ�̐i���B
S/N�Ō����Ȃ�A����20dB�ȏ�~�����̂����A�A�V�O�i���̑傫���Ō����ƁA�ǂ����Ō�2�i�ʗ~�����Ƃ���B
�����A����Mixer�́A
�L�����A��100mV�ȏ�̑傫�ȃQ�C��������ƁA�Q�C���R���g���[�������邱�Ƃ��f�[�^�V�[�g�ɏ�����Ă�̂ŁA
�V�O�i�������̗v�f�����邩������Ȃ��B�Ƃ����̂��A���Ȃ�傫�ȐM�������Ă��A����قǔg�`�͑傫���Ȃ�Ȃ��B
���Ƃ���ƁA���U�̋����ȂǂŃQ�C�����ς���Ă邩���m��Ȃ��̂ŁA
�P�ɍŌ�̏o�͂̑傫���ŁA�P�����������߂��Ȃ��v�f�����邩������Ȃ��B�Ȃ̂ŁA��߂̐M���Œ������������ǂ��B
���v�̂��Ƃ�A�Z�p�I�ȋ����Ƃ̌��ˍ����ŁA30MHz�Ɉ����グ�Ă��邯�ǁA
���ۂ̃g�R�A�����̐M����10.7MHz�̐M���ł��A�\��������Ƃ͎v���Ă���B
�Ƃ���ŁAFCZ�R�C����7mm�p�̃��m��10mm�p�̃��m�B�������݂���ꍇ�A�ǂ����I�Ԃׂ����H
�l�i�͓��������A�R���p�N�g�ł��A���܂薧�ɒu���̂��D�܂����Ȃ��悤������A���\�őI�т����Ƃ��ł���B
�傫������10mm�p�̂��AQ���Ⴂ�B�����p��C�́A�ς��Ȃ��B���C�h�o���h�̎��A�傫���̂��g���ƌ������ƁH
80MHz�́A66MHz������ł��f�[�^�[���ڂ��Ă邵�A���g�����ς���Q�������ς�肻���ł���B
���Ƃ́A�d���e�ʂ̈Ⴂ���ȁH���M�Ɏg���̂ł͖����̂ŁA�A�A
220319
�C���t�����̂����ǁA
�Q�l�̎G�����Â����߂��A���Ȃ̂����A���݁A�E�̕����嗬�̂悤�ŁA������̕����Q�C�����o�����Ȋ����ł���B
�ŁALED���ƁA�܂��A2�`3m���g�`�̑��݂��ǂ߂�g�R���Ǝv���B30MHz�̉�H�ł́A����ł��A���Ȃ�̐i���B
S/N�Ō����Ȃ�A����20dB�ȏ�~�����̂����A�A�V�O�i���̑傫���Ō����ƁA�ǂ����Ō�2�i�ʗ~�����Ƃ���B
�����A����Mixer�́A
�L�����A��100mV�ȏ�̑傫�ȃQ�C��������ƁA�Q�C���R���g���[�������邱�Ƃ��f�[�^�V�[�g�ɏ�����Ă�̂ŁA
�V�O�i�������̗v�f�����邩������Ȃ��B�Ƃ����̂��A���Ȃ�傫�ȐM�������Ă��A����قǔg�`�͑傫���Ȃ�Ȃ��B
���Ƃ���ƁA���U�̋����ȂǂŃQ�C�����ς���Ă邩���m��Ȃ��̂ŁA
�P�ɍŌ�̏o�͂̑傫���ŁA�P�����������߂��Ȃ��v�f�����邩������Ȃ��B�Ȃ̂ŁA��߂̐M���Œ������������ǂ��B
���v�̂��Ƃ�A�Z�p�I�ȋ����Ƃ̌��ˍ����ŁA30MHz�Ɉ����グ�Ă��邯�ǁA
���ۂ̃g�R�A�����̐M����10.7MHz�̐M���ł��A�\��������Ƃ͎v���Ă���B
�Ƃ���ŁAFCZ�R�C����7mm�p�̃��m��10mm�p�̃��m�B�������݂���ꍇ�A�ǂ����I�Ԃׂ����H
�l�i�͓��������A�R���p�N�g�ł��A���܂薧�ɒu���̂��D�܂����Ȃ��悤������A���\�őI�т����Ƃ��ł���B
�傫������10mm�p�̂��AQ���Ⴂ�B�����p��C�́A�ς��Ȃ��B���C�h�o���h�̎��A�傫���̂��g���ƌ������ƁH
80MHz�́A66MHz������ł��f�[�^�[���ڂ��Ă邵�A���g�����ς���Q�������ς�肻���ł���B
���Ƃ́A�d���e�ʂ̈Ⴂ���ȁH���M�Ɏg���̂ł͖����̂ŁA�A�A
220319
�C���t�����̂����ǁA
�Q�l�̎G�����Â����߂��A���Ȃ̂����A���݁A�E�̕����嗬�̂悤�ŁA������̕����Q�C�����o�����Ȋ����ł���B
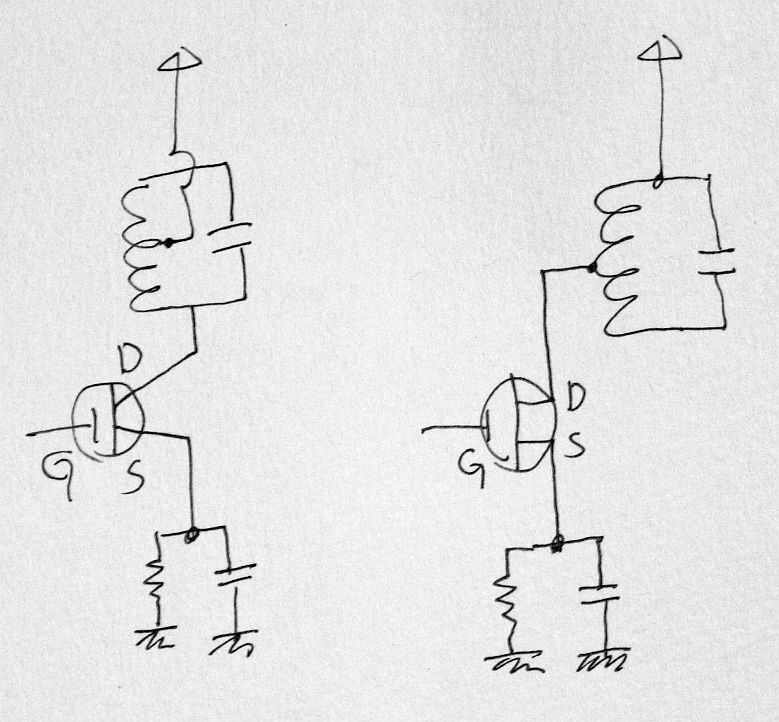 �g�ݑւ��邩�Y�ݒ��B
�g�ݑւ����B
�g�ݑւ��邩�Y�ݒ��B
�g�ݑւ����B
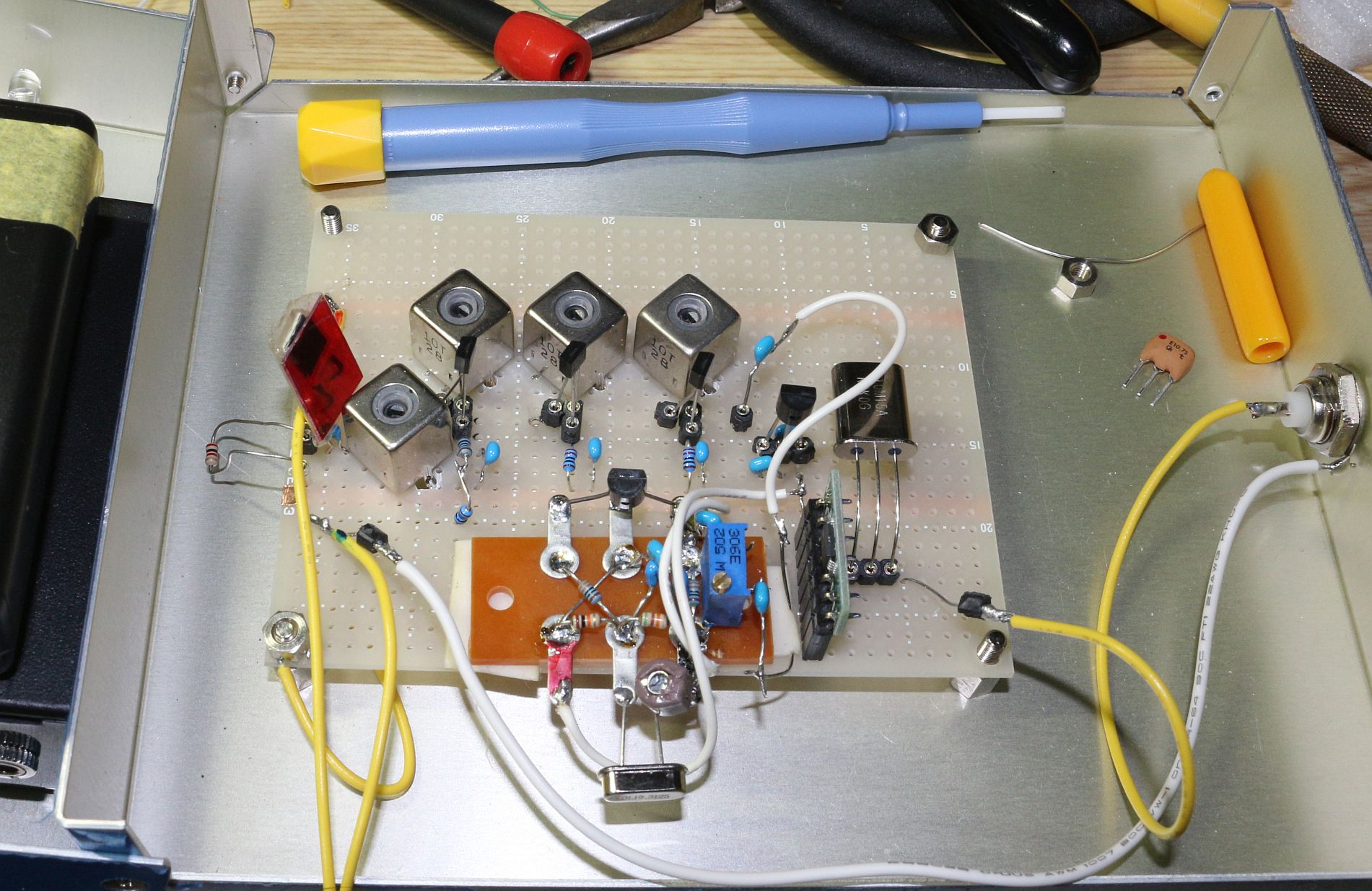 �p�^�[�����߂������̂ŏ\�����ŏI������B
�ŁA���ʁB
���U���~�܂����B����͋����B
�����ǁA���x�͏��X�����������B�܂��A�������f�J�������o�����f�J���Ȃ邩�̈Ⴂ���ȁH
�����āA���������������B�B�d����o�C�A�X��������Ώ����́H
FCZ�R�C���̃R�A���A�˂��������Œ���������悤�ɂȂ����B
���ۂ̃g�RIF�o�͂̔g�`��4�{���x�̎��g���������o�Ă��āA����Ă���B
10.7MHz��BW30KHz�̃Z���~�b�N�t�B���^�[����ш�̋���BW15KHz�̃N���X�^���t�B���^�[�ɂ���ƌ��\�Y��ɂ͂Ȃ邪�A�ш悪�����̂��B�B
�����A���U���~�߂₷���̂ŁA������i�������l���ɓ������B
�Ƃ������āA�Z���~�b�N�t�B���^�[�ɖ߂�����A���x�͉��P���ĂāA�O�Ƒ��F�������l�ɂȂ����悤���B
IF�p��19.3MHz�̋ǔ��̓g���}�[�ƒ����20��H���x���q���ƒ�������������̂ŁA�����ꂻ����s�������B
��������A����BW�̃t�B���^�ōs����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
IF�ȍ~��Mixer�ɂăQ�C�������������悤�Ȃ̂ŁA����Ȃ�ɑ����͕K�v�����A����ȑO�ɂ��܂��K�v���������āA
30MHz�i�K��4�i�ɂ���Ȃ�A���U���Ă�FET��I�Ԃ��ƂőΏ��Ƃ������@��A
���U���ĂĂ��܂��܂��A�ǂ��M�����o����̂ł́H�Ƃ����B
�������A20pF�̃R���f���T�[�����������̂ŁA�Ȃ�炩�̕��@�Łc�A
�ł����āA���ꂵ���̂��Ƃő҂��Ă�̂ɂ͒�������̂ŁA
39p��ɂ��āA18.5pF�Ƃ����B
�p�^�[�����߂������̂ŏ\�����ŏI������B
�ŁA���ʁB
���U���~�܂����B����͋����B
�����ǁA���x�͏��X�����������B�܂��A�������f�J�������o�����f�J���Ȃ邩�̈Ⴂ���ȁH
�����āA���������������B�B�d����o�C�A�X��������Ώ����́H
FCZ�R�C���̃R�A���A�˂��������Œ���������悤�ɂȂ����B
���ۂ̃g�RIF�o�͂̔g�`��4�{���x�̎��g���������o�Ă��āA����Ă���B
10.7MHz��BW30KHz�̃Z���~�b�N�t�B���^�[����ш�̋���BW15KHz�̃N���X�^���t�B���^�[�ɂ���ƌ��\�Y��ɂ͂Ȃ邪�A�ш悪�����̂��B�B
�����A���U���~�߂₷���̂ŁA������i�������l���ɓ������B
�Ƃ������āA�Z���~�b�N�t�B���^�[�ɖ߂�����A���x�͉��P���ĂāA�O�Ƒ��F�������l�ɂȂ����悤���B
IF�p��19.3MHz�̋ǔ��̓g���}�[�ƒ����20��H���x���q���ƒ�������������̂ŁA�����ꂻ����s�������B
��������A����BW�̃t�B���^�ōs����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
IF�ȍ~��Mixer�ɂăQ�C�������������悤�Ȃ̂ŁA����Ȃ�ɑ����͕K�v�����A����ȑO�ɂ��܂��K�v���������āA
30MHz�i�K��4�i�ɂ���Ȃ�A���U���Ă�FET��I�Ԃ��ƂőΏ��Ƃ������@��A
���U���ĂĂ��܂��܂��A�ǂ��M�����o����̂ł́H�Ƃ����B
�������A20pF�̃R���f���T�[�����������̂ŁA�Ȃ�炩�̕��@�Łc�A
�ł����āA���ꂵ���̂��Ƃő҂��Ă�̂ɂ͒�������̂ŁA
39p��ɂ��āA18.5pF�Ƃ����B
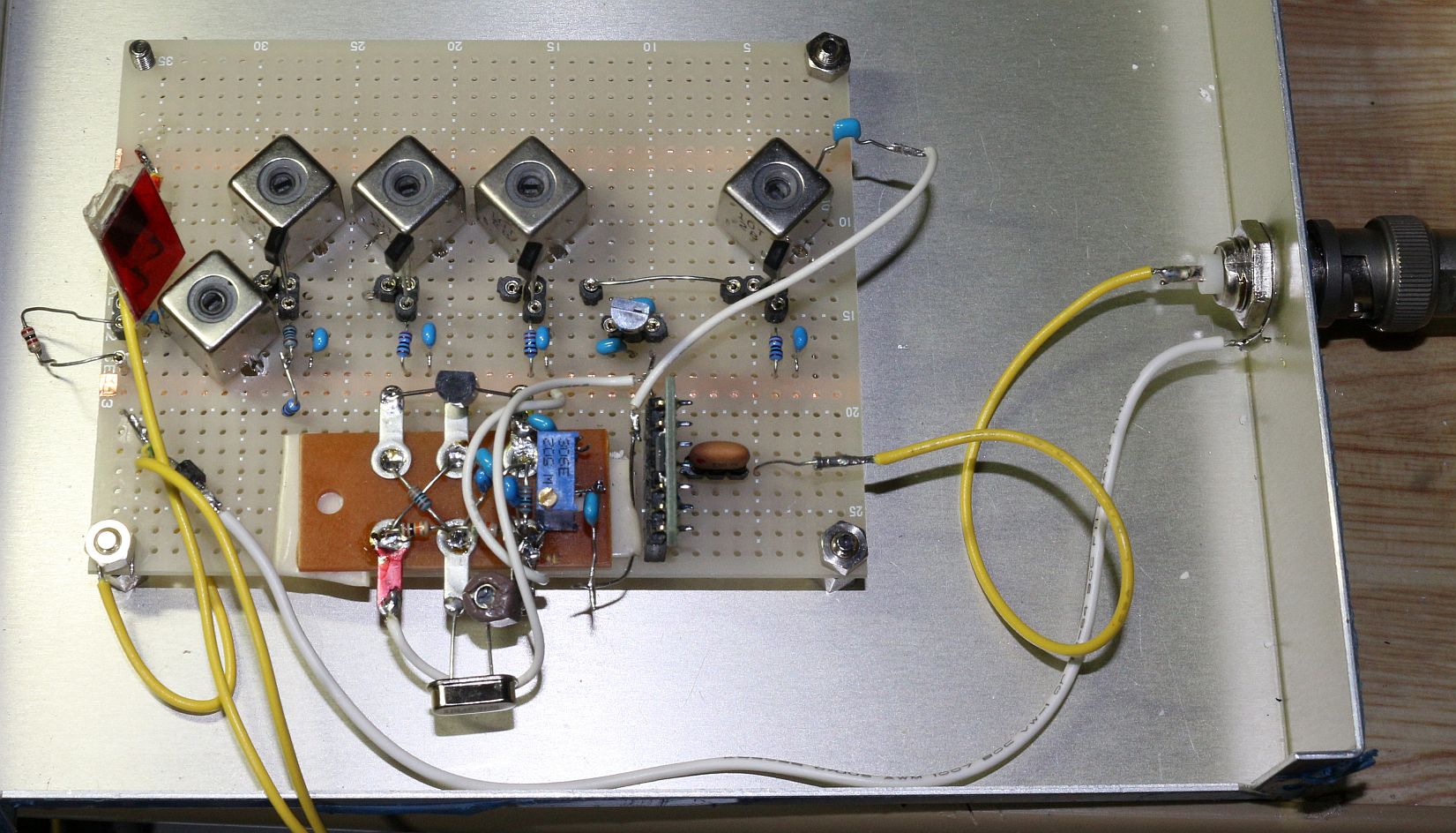 �����_�A���R�̂��Ƃ����U���Ă�̂����ǁA���ꂪ�������B
�ł��AIF�̃t�B���^�[�ŃJ�b�g�����B
�I�V���Ō���ɂ��A10.7MHz�̎��_�ł́A���Ȃ�̍����g�m�C�Y�������Ȃ��Ă���B
�Q�C���I�ɂ��t���ʂȊ��������Ă���B
�\���ɂ����ẮA�����g���J�b�g����Ă��Ă��~�����B���Ƃ�LPF���ȁH
�Ƃ������ƂŁA�I�V����20MHz�ȏ���J�b�g����@�\������̂łƂ肠����������g���ƁA���Ȃ�}�������B
�ł��A���x�͗ǂ��Ȃ��B��i�lj����^�_�̖��ʂƂ������x���ŃA���B�ł�3�i�ڂ������͂����ł������B
����ρA���U��Mixer�o�͂̐U����ጸ�����Ă�悤�ł���B�M�����Ԃ�Ă邩�AMixer�̃Q�C���R���g���[���B
�Ȃ̂ŁA���U���~�߂��Ȃ����Ă��A�ł�������߂����B
�߂Â���ƁA�C�L�i���g�`���傫���Ȃ�̂ŁAMixer���ɂ��Q�C���R���g���[�����A����ł́A�u�V�O�i�������U���v�Ƃ���������H��Ԃł���B
FET�̃h���C���Ƀt�F���C�g�r�[�Y�Ƃ��A���炩�̔��U�~�߂��~�����B
3�i�ڂ�4�i�ڂ̊Ԃ̐������߂Ȃ̂ł��邪�A�����Ɍy���G���ƁA���U���~�܂�A�M���͉�����Ȃ��C���[�W�B
��������Ȃ�Ƃ�����A��肭�s�������B
�Ƃ肠�����A4�i�ڂ̓��o�͂�1K�����q�����B���U�͎~�܂�Ȃ����ǁA���̒i�A��ɂ��邱�Ƃ͖����Ȃ����B
�����g�m�C�Y�͑��ς�炸�����A���̂Ȃ̂��s���B����������ƁA���̐U���ŗ�N����Ă镔�������邩������Ȃ��H
�Ƃɂ����A��M�Q�C�����v�����悤�ɂ͏オ��Ȃ��B
����̓N���X�^���t�B���^�[�̕����D���ʁB�Ƃ������Ƃ́A�R���s�b�c���U�̕����L���ăs�b�^�����킹��s���邩�ȁH
100��Sec�̃����V���b�g�̔�r�B
�オ�N���X�^���t�B���^�[�A�����A�Z���~�b�N�t�B���^�[�B
�����_�A���R�̂��Ƃ����U���Ă�̂����ǁA���ꂪ�������B
�ł��AIF�̃t�B���^�[�ŃJ�b�g�����B
�I�V���Ō���ɂ��A10.7MHz�̎��_�ł́A���Ȃ�̍����g�m�C�Y�������Ȃ��Ă���B
�Q�C���I�ɂ��t���ʂȊ��������Ă���B
�\���ɂ����ẮA�����g���J�b�g����Ă��Ă��~�����B���Ƃ�LPF���ȁH
�Ƃ������ƂŁA�I�V����20MHz�ȏ���J�b�g����@�\������̂łƂ肠����������g���ƁA���Ȃ�}�������B
�ł��A���x�͗ǂ��Ȃ��B��i�lj����^�_�̖��ʂƂ������x���ŃA���B�ł�3�i�ڂ������͂����ł������B
����ρA���U��Mixer�o�͂̐U����ጸ�����Ă�悤�ł���B�M�����Ԃ�Ă邩�AMixer�̃Q�C���R���g���[���B
�Ȃ̂ŁA���U���~�߂��Ȃ����Ă��A�ł�������߂����B
�߂Â���ƁA�C�L�i���g�`���傫���Ȃ�̂ŁAMixer���ɂ��Q�C���R���g���[�����A����ł́A�u�V�O�i�������U���v�Ƃ���������H��Ԃł���B
FET�̃h���C���Ƀt�F���C�g�r�[�Y�Ƃ��A���炩�̔��U�~�߂��~�����B
3�i�ڂ�4�i�ڂ̊Ԃ̐������߂Ȃ̂ł��邪�A�����Ɍy���G���ƁA���U���~�܂�A�M���͉�����Ȃ��C���[�W�B
��������Ȃ�Ƃ�����A��肭�s�������B
�Ƃ肠�����A4�i�ڂ̓��o�͂�1K�����q�����B���U�͎~�܂�Ȃ����ǁA���̒i�A��ɂ��邱�Ƃ͖����Ȃ����B
�����g�m�C�Y�͑��ς�炸�����A���̂Ȃ̂��s���B����������ƁA���̐U���ŗ�N����Ă镔�������邩������Ȃ��H
�Ƃɂ����A��M�Q�C�����v�����悤�ɂ͏オ��Ȃ��B
����̓N���X�^���t�B���^�[�̕����D���ʁB�Ƃ������Ƃ́A�R���s�b�c���U�̕����L���ăs�b�^�����킹��s���邩�ȁH
100��Sec�̃����V���b�g�̔�r�B
�オ�N���X�^���t�B���^�[�A�����A�Z���~�b�N�t�B���^�[�B
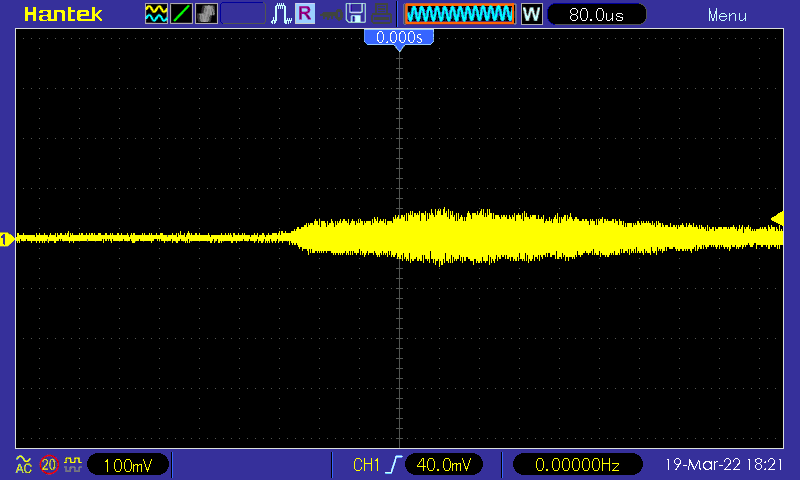
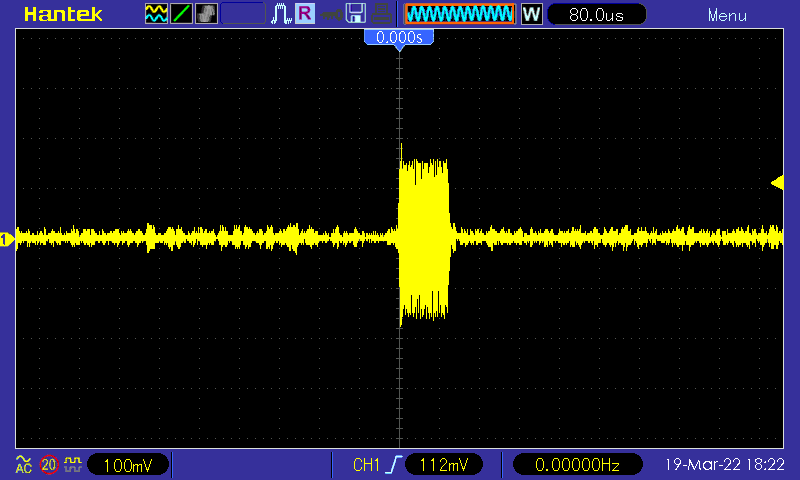 �N���X�^���t�B���^�[�͂ƂĂ��݂��B
�U�����������̂́A�����オ��̂��߂̗�N���Ԃ��Z���Ǝv����̂ƁA�����_�A�V�O�i�����ш敝�̂��傢�O�Ȃ̂ŁA�A�ł��AS/N�͗ǂ��B
�N���X�^���t�B���^�[�͂����Ƌ����ш�̂𒍕����Ă݂Ă���BBW=3.5KHz��
�ш敝���d�v�����A�X�g�b�v�o���h�̈�ł̃Q�C���͂ǂꂾ���ቺ�������邩�H�Ƃ����̂��d�v�����ł���B
�m�C�Y�́A���ɑ����U���Ȃ̂ŁALPF�ł����Ƃ��邯�lj�H�̕��i�_����������̂͌��Ȋ����B
�����̂�30MHz�ɋ߂��悤�Ȃ̂ŁA���U���Ă郂�m���R��Ă�̂����m��Ȃ��B
220320
�����g�́A���\�ȕ������A�I�V���ւ̓����P�[�u���ōڂ��Ă����B�Ȃ̂ŁA�t�F���C�g�R�A���g�����炩�Ȃ�ɘa�����B
�Ƃɂ���30MHz�̔��U�����Ă��Ă��A�����100mV����MAX��300mV�ȉ��ɗ��Ƃ��A�Q�C���R���g���[���ɂ�鐧���͐H�炢�Â炢�B
���Ƃ́A�s���āA���ԉ����̗ǂ��t�B���^�[�����������B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���[�U�[���������̃}�E���g���l����{���B
�N���X�^���t�B���^�[�͂ƂĂ��݂��B
�U�����������̂́A�����オ��̂��߂̗�N���Ԃ��Z���Ǝv����̂ƁA�����_�A�V�O�i�����ш敝�̂��傢�O�Ȃ̂ŁA�A�ł��AS/N�͗ǂ��B
�N���X�^���t�B���^�[�͂����Ƌ����ш�̂𒍕����Ă݂Ă���BBW=3.5KHz��
�ш敝���d�v�����A�X�g�b�v�o���h�̈�ł̃Q�C���͂ǂꂾ���ቺ�������邩�H�Ƃ����̂��d�v�����ł���B
�m�C�Y�́A���ɑ����U���Ȃ̂ŁALPF�ł����Ƃ��邯�lj�H�̕��i�_����������̂͌��Ȋ����B
�����̂�30MHz�ɋ߂��悤�Ȃ̂ŁA���U���Ă郂�m���R��Ă�̂����m��Ȃ��B
220320
�����g�́A���\�ȕ������A�I�V���ւ̓����P�[�u���ōڂ��Ă����B�Ȃ̂ŁA�t�F���C�g�R�A���g�����炩�Ȃ�ɘa�����B
�Ƃɂ���30MHz�̔��U�����Ă��Ă��A�����100mV����MAX��300mV�ȉ��ɗ��Ƃ��A�Q�C���R���g���[���ɂ�鐧���͐H�炢�Â炢�B
���Ƃ́A�s���āA���ԉ����̗ǂ��t�B���^�[�����������B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���[�U�[���������̃}�E���g���l����{���B
 ���\�͗ǂ����������ǁA
����o�Ă����NJF�����悤�Ȓl�i�ŁA�c�������B�B
�Ƃ肠�����A�����LD��p�Ƃ���B
���\�͗ǂ����������ǁA
����o�Ă����NJF�����悤�Ȓl�i�ŁA�c�������B�B
�Ƃ肠�����A�����LD��p�Ƃ���B
 LD�z���_�[�̂悤�ɁAL�A���O���ނ�V���ɗ��ĂĐݒu����B��������ȃR�̎��ނ̕����ǂ��Ǝv�������A�茳�ɖ����̂ŁA�A
(���[���J�o�[�̉����ł��ǂ��������A�ǂ��������ėǂ��̂������Ă��Ȃ������B�B)
LD���U���W���[�����������ɉA���E�̃Y�����Ȃ����㉺�̃Y���ɂ���B
�ł����āA
LD�z���_�[�̂悤�ɁAL�A���O���ނ�V���ɗ��ĂĐݒu����B��������ȃR�̎��ނ̕����ǂ��Ǝv�������A�茳�ɖ����̂ŁA�A
(���[���J�o�[�̉����ł��ǂ��������A�ǂ��������ėǂ��̂������Ă��Ȃ������B�B)
LD���U���W���[�����������ɉA���E�̃Y�����Ȃ����㉺�̃Y���ɂ���B
�ł����āA
 ����ŁA�㉺�̃Y�����ɘa���A�Ō�ɃX�R�[�v���Ŕ������B
���ƁA�o�����Ƀ��[����t����A�_�v�^��3��ޒ����B299�~��555�~��792�~���x�������̂ŁB�B
20mm�s�J�e�B�j�[�ȃ��[���}�E���g�V�X�e���́A���w�n�ɗL�p�Ɏv���A���v�ł��g���Ȃ����l���Ă���B
���v�p�̌����́A������Ƃ������肵��LD���W���[���ɂ������B�A���Ȃ�A�����X�O���I�̒��ẪK�X���[�U�[�Ƃ��B
�g���K�����O�Ȃ̂����A�~�m���V�N���b�v�ŐڐG������ƁA
�ڐG�̂�����Ƃ����m�C�Y�œ��p���X�����ł��܂������������B
�ŁA�}�C�N��SW�ɕς����炻�̂悤�Ȃ��Ƃ͑S�������Ȃ����B
�܂��A�g���K�𗣂����Ƃ��ɔ������鎖�Ԃ��N����Ȃ��B
�g���K�t�߂̔��ϕ��́A0.001��F��10M���ƂȂ��Ă���B�g���K�����������M���𑗂�A�ϕ����ăR���f���T�[�ɗ��܂����d�ׂ��������Ɩ߂������B
�`���^�����O�h�~�݂����Ȋ����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220322
�n�����Ō��������̕s���̃t�F���C�g�r�[�Y(�O�a��3.4mm�A�S��5.0mm)��
���i��4�i�ڂ�FET�̃h���C���ɂ͂߂�ƁB���U�����������B
����ŁA�㉺�̃Y�����ɘa���A�Ō�ɃX�R�[�v���Ŕ������B
���ƁA�o�����Ƀ��[����t����A�_�v�^��3��ޒ����B299�~��555�~��792�~���x�������̂ŁB�B
20mm�s�J�e�B�j�[�ȃ��[���}�E���g�V�X�e���́A���w�n�ɗL�p�Ɏv���A���v�ł��g���Ȃ����l���Ă���B
���v�p�̌����́A������Ƃ������肵��LD���W���[���ɂ������B�A���Ȃ�A�����X�O���I�̒��ẪK�X���[�U�[�Ƃ��B
�g���K�����O�Ȃ̂����A�~�m���V�N���b�v�ŐڐG������ƁA
�ڐG�̂�����Ƃ����m�C�Y�œ��p���X�����ł��܂������������B
�ŁA�}�C�N��SW�ɕς����炻�̂悤�Ȃ��Ƃ͑S�������Ȃ����B
�܂��A�g���K�𗣂����Ƃ��ɔ������鎖�Ԃ��N����Ȃ��B
�g���K�t�߂̔��ϕ��́A0.001��F��10M���ƂȂ��Ă���B�g���K�����������M���𑗂�A�ϕ����ăR���f���T�[�ɗ��܂����d�ׂ��������Ɩ߂������B
�`���^�����O�h�~�݂����Ȋ����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220322
�n�����Ō��������̕s���̃t�F���C�g�r�[�Y(�O�a��3.4mm�A�S��5.0mm)��
���i��4�i�ڂ�FET�̃h���C���ɂ͂߂�ƁB���U�����������B
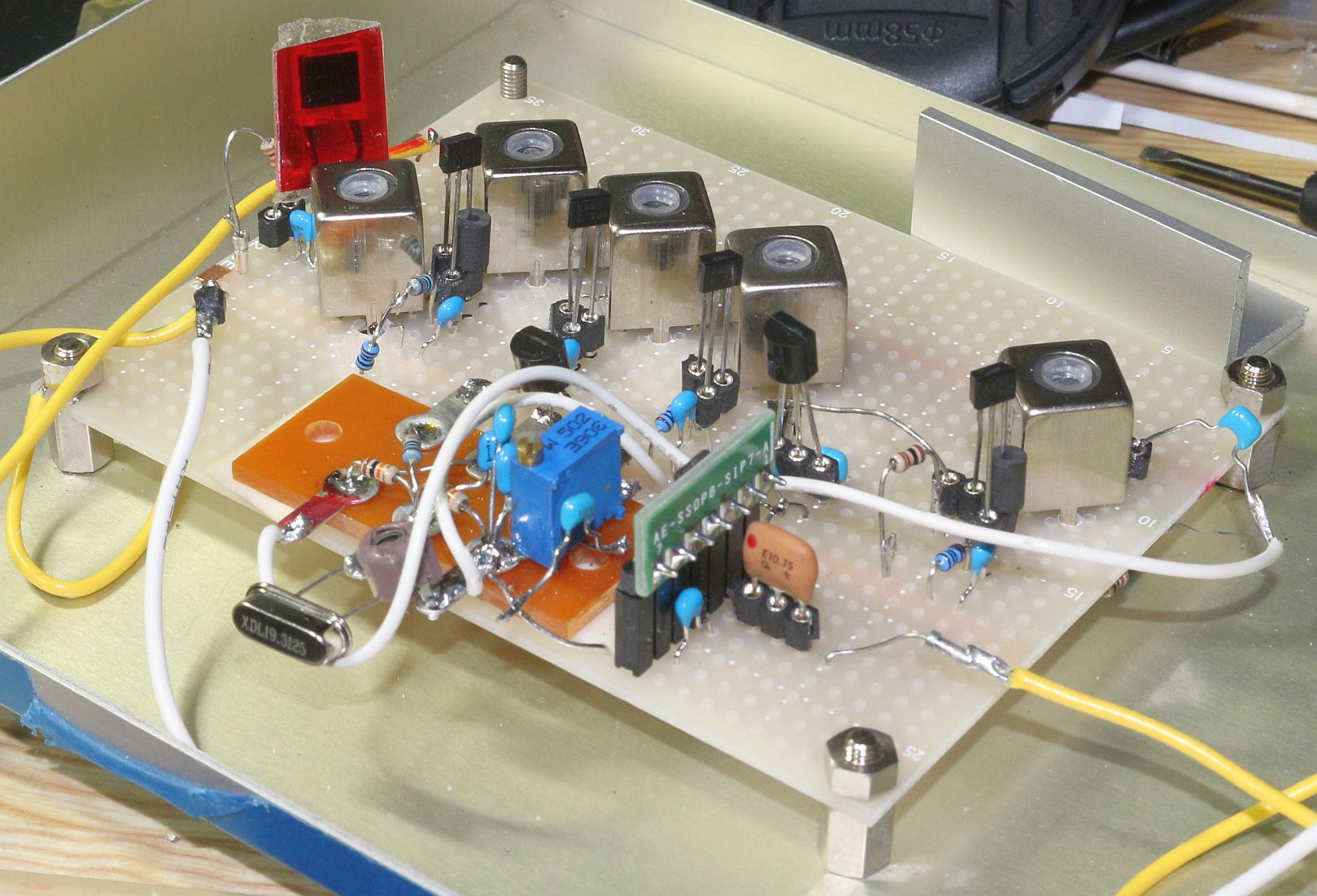 ���_�A�V�O�i�����������Ă�\�����A�������m��Ȃ����A
���\�D��ۂȂ̂ŁA��肭�g����c�A�A�Ǝv�����B
50MHz�̎�M�@�ł��A�p�[�c�̑��͋ɗ͒Z���Ƃ���̂ŁA����Ȃ�ɉe���̓A�����ȁ[�A�A�A�ƍ��v���Ă�g�R�B�B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�������ł܂�u���ʼn��Œ肵�A5���̃G�|�L�V�Ő���B
�ڒ��܂�A�A���O���͍������������ǂ����Y�ރg�R�B
���_�A�V�O�i�����������Ă�\�����A�������m��Ȃ����A
���\�D��ۂȂ̂ŁA��肭�g����c�A�A�Ǝv�����B
50MHz�̎�M�@�ł��A�p�[�c�̑��͋ɗ͒Z���Ƃ���̂ŁA����Ȃ�ɉe���̓A�����ȁ[�A�A�A�ƍ��v���Ă�g�R�B�B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�������ł܂�u���ʼn��Œ肵�A5���̃G�|�L�V�Ő���B
�ڒ��܂�A�A���O���͍������������ǂ����Y�ރg�R�B
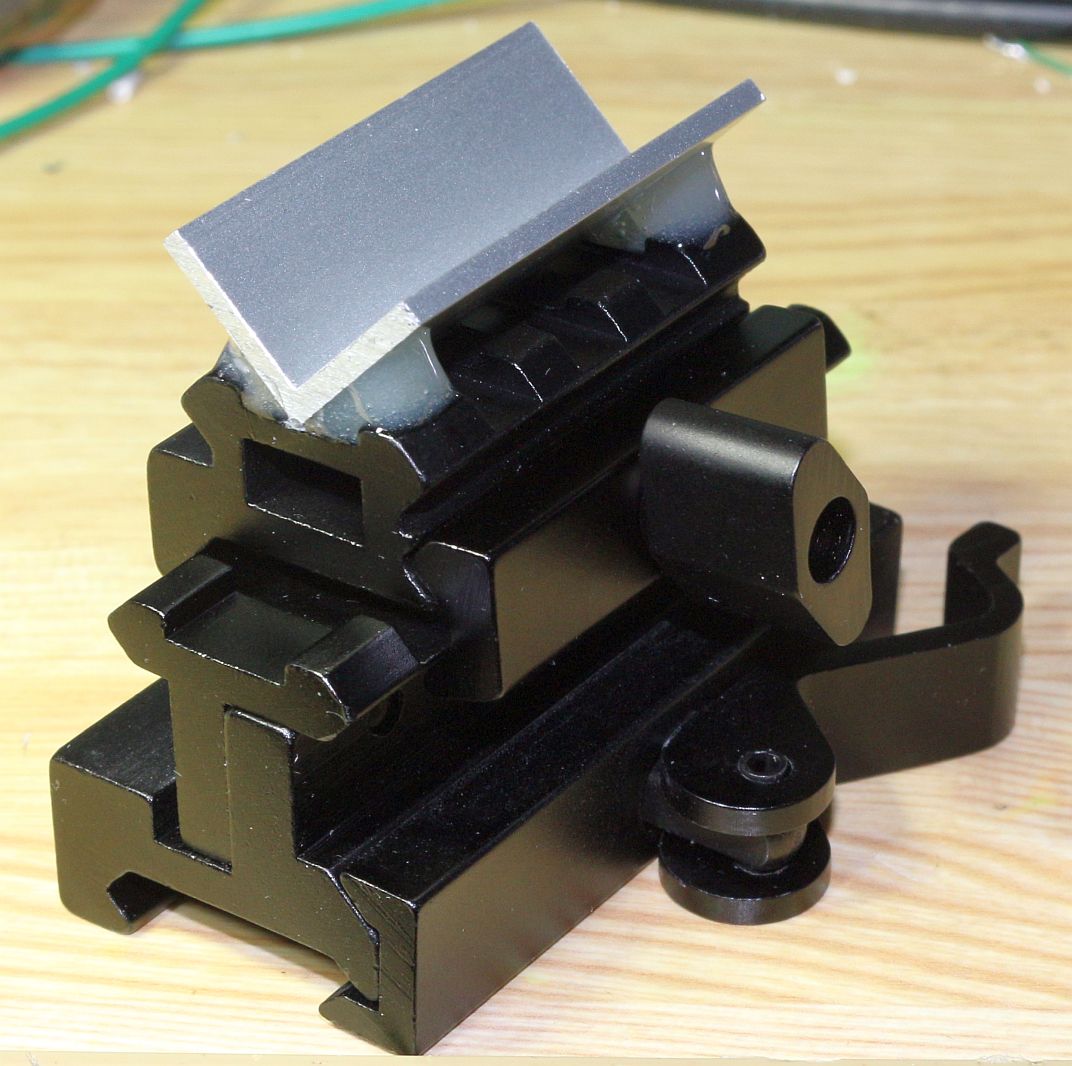 LD���W���[����ݒu���A�^�C���b�v���i�߂�B
����ނ���ă^�C���b�v�̉���LD���W���[���Ƃ̊Ԃɉ������ށB
LD���W���[����ݒu���A�^�C���b�v���i�߂�B
����ނ���ă^�C���b�v�̉���LD���W���[���Ƃ̊Ԃɉ������ށB
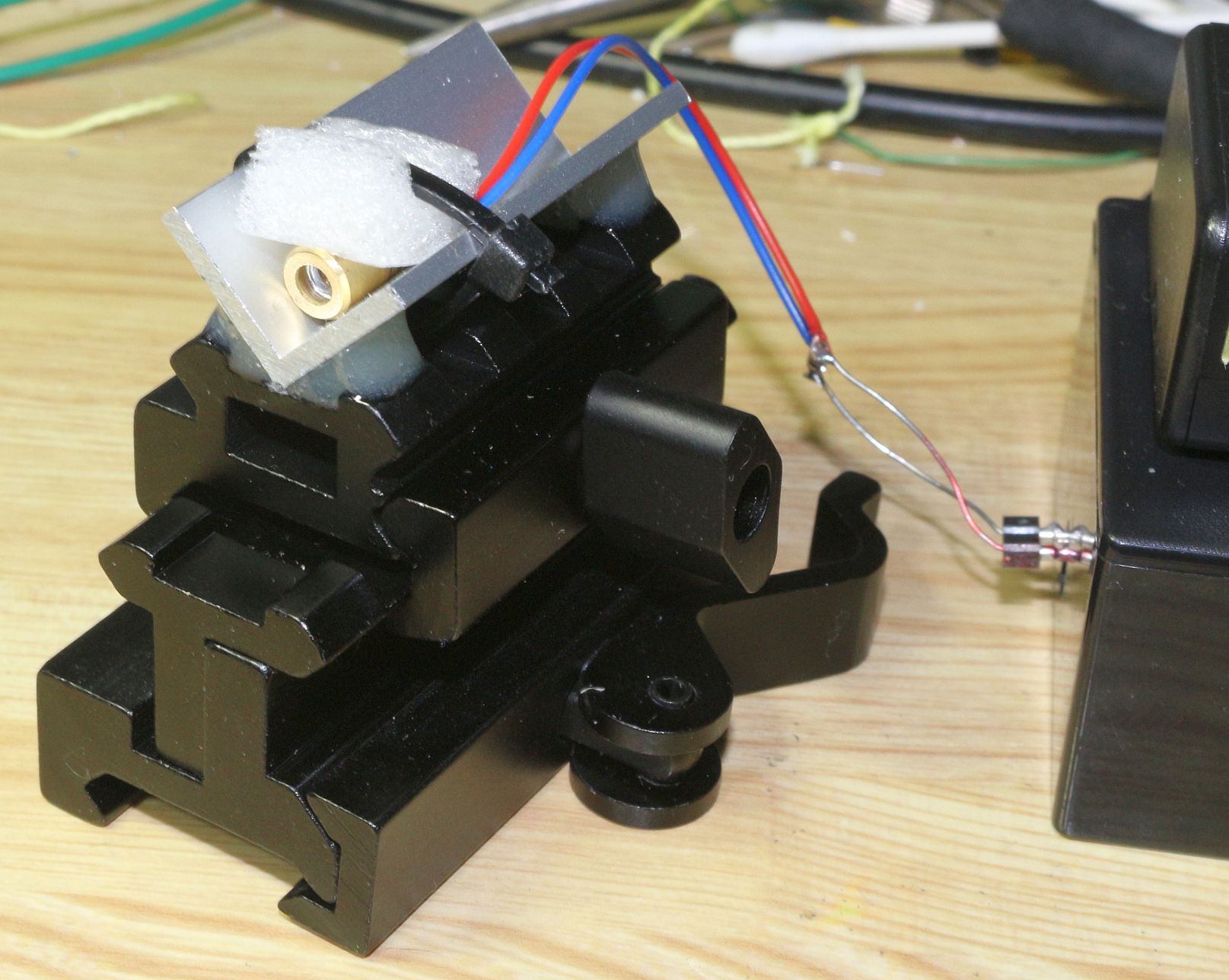 ����ł܂��܂��̌Œ�o�����B�P�[�u�����A���O���t�߂ɌŒ肵�Ȃ��ƈ���������̂ŁA�Ώ����l���Ă�g�R�B
���[���}�E���g�ɂ������Ă݂��B
����ł܂��܂��̌Œ�o�����B�P�[�u�����A���O���t�߂ɌŒ肵�Ȃ��ƈ���������̂ŁA�Ώ����l���Ă�g�R�B
���[���}�E���g�ɂ������Ă݂��B
 �P�[�u���́A����������ƒ����Ă��ǂ����ȁH�@
���ƁA�ŏI�I�ɂ́A����ނȂǂł͖����A�Œ���l�W�ƃX�v�����O�ȂǂŃX�}�[�g�ɗ}�����݂����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
L���ނ��傫���A�o�����X�I�ɃJ�b�R���t���Ȃ��C�����Ă邪�A
���h�肷��A����Ȃ肩���m��Ȃ��H
���������A���̃t���[�e�B���O�o�����ȃ��[���V�X�e���̃n���h�K�[�h�́AM4�p�Ȃ̂����ǁA
����M4-RIS�́A�]��M�肽���Ȃ��B�����o�������Ƃ����̂��A���B
�}���C��M4�d���K���ɂ��n�}�郂�m���Ǝv���̂ŁA�T�[�h�p�[�e�B�[�̃t���[���Ɍ��������ꍇ�̔p�i�ƂȂ����t���[�����������ȁ[�ƒT���Ă݂�ɁA
�A�b�p�[�{���A���V�[�o�[�݂̂ŁA5000�`6000�~�߂��B�\�z���ꌅ���������B�B�ǂ��������ƁH
������̊O�ρB��H�͂���������ƈႤ�Ƃ���ɕt����\��B
�P�[�u���́A����������ƒ����Ă��ǂ����ȁH�@
���ƁA�ŏI�I�ɂ́A����ނȂǂł͖����A�Œ���l�W�ƃX�v�����O�ȂǂŃX�}�[�g�ɗ}�����݂����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
L���ނ��傫���A�o�����X�I�ɃJ�b�R���t���Ȃ��C�����Ă邪�A
���h�肷��A����Ȃ肩���m��Ȃ��H
���������A���̃t���[�e�B���O�o�����ȃ��[���V�X�e���̃n���h�K�[�h�́AM4�p�Ȃ̂����ǁA
����M4-RIS�́A�]��M�肽���Ȃ��B�����o�������Ƃ����̂��A���B
�}���C��M4�d���K���ɂ��n�}�郂�m���Ǝv���̂ŁA�T�[�h�p�[�e�B�[�̃t���[���Ɍ��������ꍇ�̔p�i�ƂȂ����t���[�����������ȁ[�ƒT���Ă݂�ɁA
�A�b�p�[�{���A���V�[�o�[�݂̂ŁA5000�`6000�~�߂��B�\�z���ꌅ���������B�B�ǂ��������ƁH
������̊O�ρB��H�͂���������ƈႤ�Ƃ���ɕt����\��B
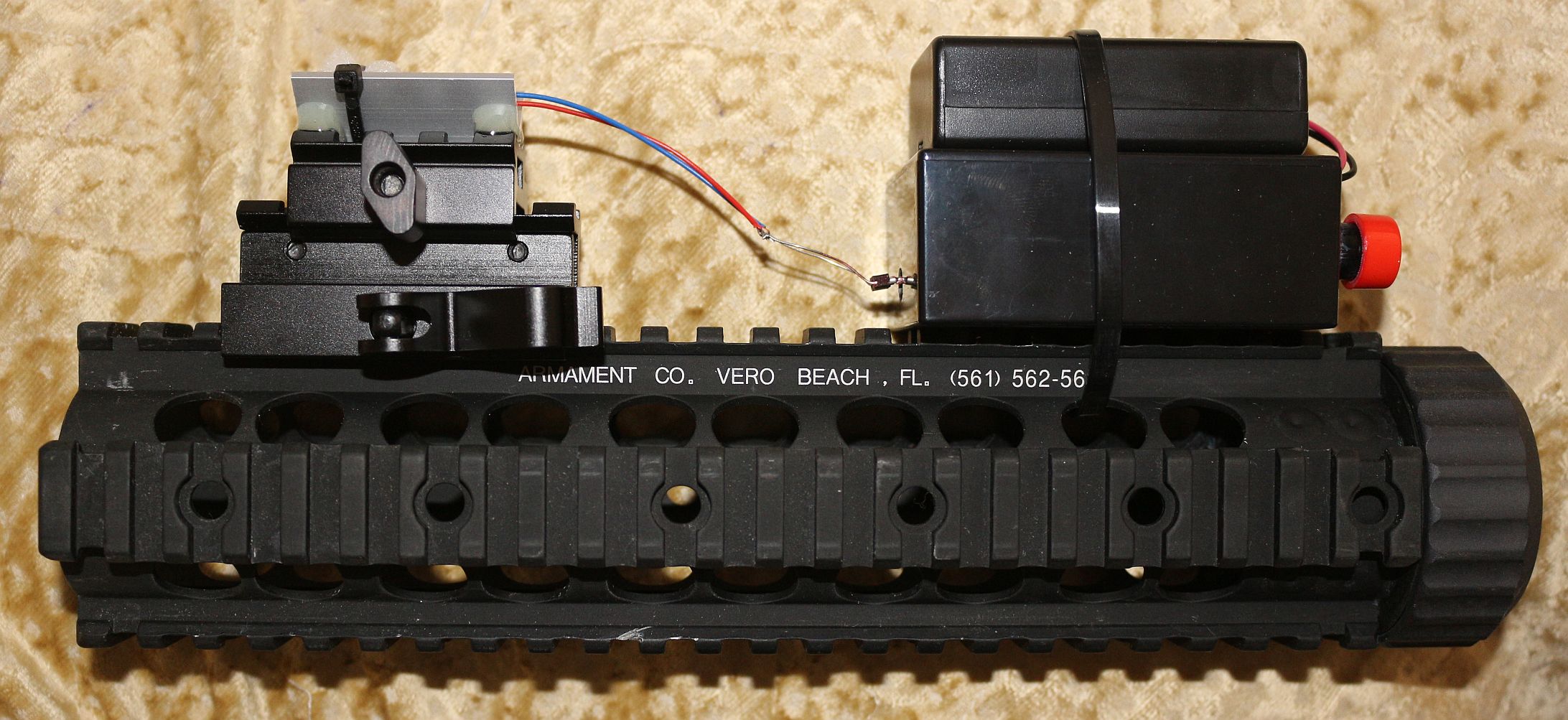 ���ƁAf=330mm�̓���̃R�����[�^�[���i�����������̂����A�h�R�ɂ�����̂��A������Ȃ��B
���w���i�̖ʐ��x=��/10�Ƃ������l�́A�g���ɉ�����ɂ��Ă��邩�Ƃ����ƁA
633nm�Ə����Ă��邱�Ƃ������C�����邪�A�����He-Ne�K�X���[�U�[��632.8nm�̎��ł���Ǝv����B
���b�h�A�|�[���́A�V�O�}���@�̂��ǂ��Ǝv�����B���\�����B���͑������ꂽ��t�ɍ����B
���b�h�X�^���h�͒��Ɠ������炢�����A���{����������A�܂Ƃ߂đ���Έꊇ�����z���������B
�X�^���h��t������K�v�B
Z�u���P�b�g�Ƃ����͍̂��߁BL�^�͈������A���ʂɋ���Ƃ��Ĕ����Ă�A���O���ł���p�o�������B
�L�l�e�B�b�N�~���[�z���_�[�́A�V�O�}���@����{�ʂ���B
�ł��A����͔j�i�l�������B
���ƁAf=330mm�̓���̃R�����[�^�[���i�����������̂����A�h�R�ɂ�����̂��A������Ȃ��B
���w���i�̖ʐ��x=��/10�Ƃ������l�́A�g���ɉ�����ɂ��Ă��邩�Ƃ����ƁA
633nm�Ə����Ă��邱�Ƃ������C�����邪�A�����He-Ne�K�X���[�U�[��632.8nm�̎��ł���Ǝv����B
���b�h�A�|�[���́A�V�O�}���@�̂��ǂ��Ǝv�����B���\�����B���͑������ꂽ��t�ɍ����B
���b�h�X�^���h�͒��Ɠ������炢�����A���{����������A�܂Ƃ߂đ���Έꊇ�����z���������B
�X�^���h��t������K�v�B
Z�u���P�b�g�Ƃ����͍̂��߁BL�^�͈������A���ʂɋ���Ƃ��Ĕ����Ă�A���O���ł���p�o�������B
�L�l�e�B�b�N�~���[�z���_�[�́A�V�O�}���@����{�ʂ���B
�ł��A����͔j�i�l�������B
 Si-PIN�t�H�g�_�C�I�[�h�A10�ŕS���\�~�Ȃ̂ŁA��ʍw���B
Si-PIN�t�H�g�_�C�I�[�h�A10�ŕS���\�~�Ȃ̂ŁA��ʍw���B
 �|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220323
LD�z���_�[�́A�}�X�L���O���ėv���������h�邩�c�A
���ꊴ���~�����Ȃ����̂ŁA�}�X�L���O�́A�r�����甍�������ƂɂȂ����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220323
LD�z���_�[�́A�}�X�L���O���ėv���������h�邩�c�A
���ꊴ���~�����Ȃ����̂ŁA�}�X�L���O�́A�r�����甍�������ƂɂȂ����B
 ����Ȋ����B
����Ȋ����B
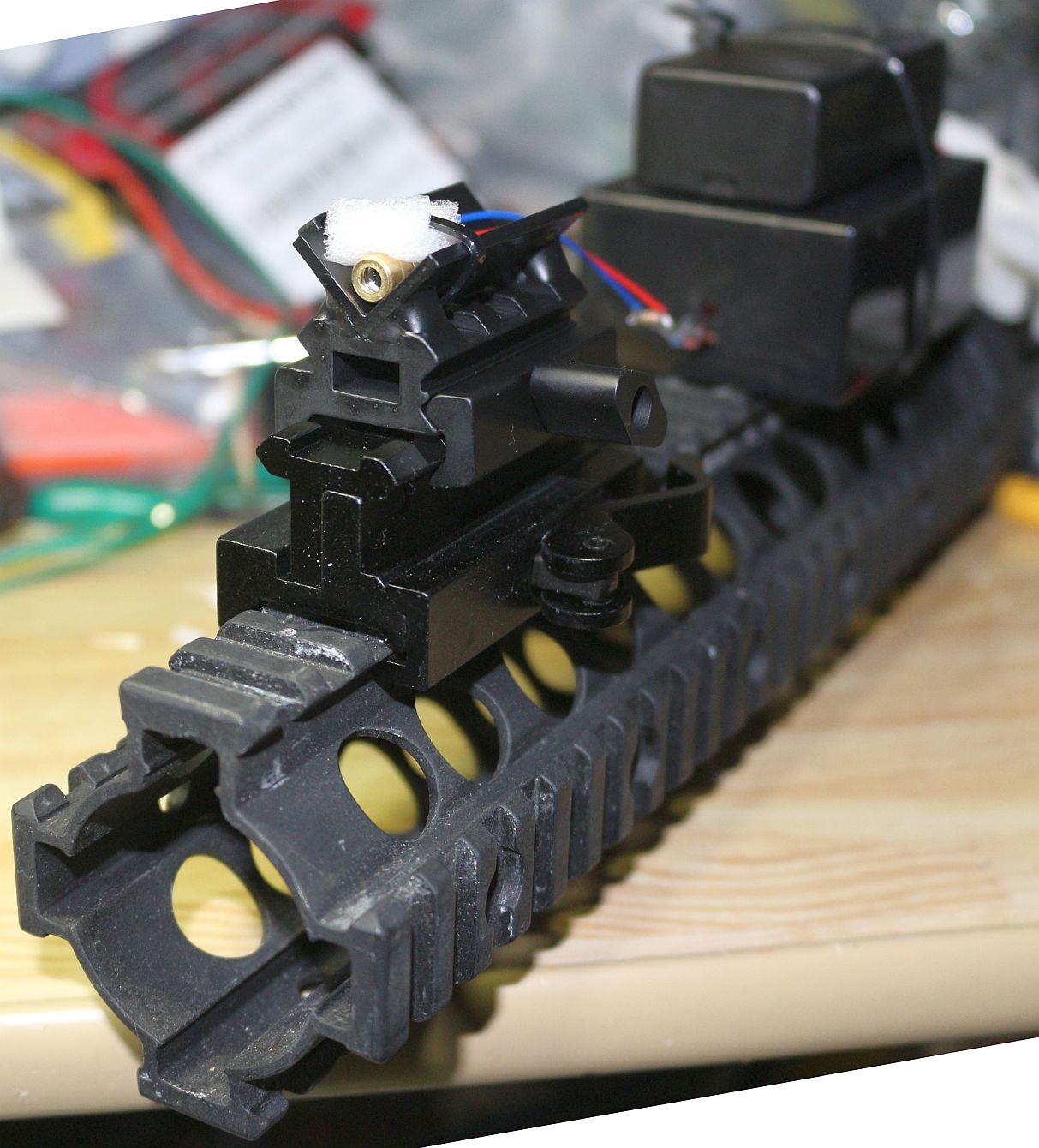 �|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�ŁA���́A
���U��̔��U���g���̕�B
20��H���q������19.3��12.3MHz�܂ō~���A�]��ɂ������肷���Ȃ̂ŁA�������x3��H�ʂ𒍕����悤�B
������2����ɂ���ƒ����o���镝��������炵�����ǁA�����Ă邯�ǁA�A�ܑ̂Ȃ��B�B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{
���60MHz�ȉ�H���n�����Ă݂�B
220324
������ŋ}�60MHz�̔��U�킪�K�v�ɂȂ����B��M�@���̂ɔ��U�o���Ȃ�������]���������o���Ȃ��̂ŁA�ŏd�v�B
�������A�ʂ��K�v�����B�B
�ŁA�������ݗp���B
�Ƃɂ����A��{�ŕK�v�ȃ��m�Ȃ̂ŁA
�~���������̂��������Ƃ�����C�L�i���i��ŁA3�����͓����ė��Ȃ��B
�Q�ĂĂ�����̕��𒍕��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�ŁA���́A
���U��̔��U���g���̕�B
20��H���q������19.3��12.3MHz�܂ō~���A�]��ɂ������肷���Ȃ̂ŁA�������x3��H�ʂ𒍕����悤�B
������2����ɂ���ƒ����o���镝��������炵�����ǁA�����Ă邯�ǁA�A�ܑ̂Ȃ��B�B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{
���60MHz�ȉ�H���n�����Ă݂�B
220324
������ŋ}�60MHz�̔��U�킪�K�v�ɂȂ����B��M�@���̂ɔ��U�o���Ȃ�������]���������o���Ȃ��̂ŁA�ŏd�v�B
�������A�ʂ��K�v�����B�B
�ŁA�������ݗp���B
�Ƃɂ����A��{�ŕK�v�ȃ��m�Ȃ̂ŁA
�~���������̂��������Ƃ�����C�L�i���i��ŁA3�����͓����ė��Ȃ��B
�Q�ĂĂ�����̕��𒍕��B
 �������A�������̕��������A�A
�������̃`�b�v���T�|�[�g���Ă邪�ASOT-23-5��SOT-23-6��DIP-6�ϊ��������̂ŁA�A
���̃`�b�v�̓v���O���~���O�̂��߂ɁA�s���Z�b�g�Ń\�P�b�g�Ƀ`�b�v���ڂ���̂����A���\��ρB
�܂��A�s���A�T�C���I�Ȕz��낵���Ȃ��B
�������A�������̕��������A�A
�������̃`�b�v���T�|�[�g���Ă邪�ASOT-23-5��SOT-23-6��DIP-6�ϊ��������̂ŁA�A
���̃`�b�v�̓v���O���~���O�̂��߂ɁA�s���Z�b�g�Ń\�P�b�g�Ƀ`�b�v���ڂ���̂����A���\��ρB
�܂��A�s���A�T�C���I�Ȕz��낵���Ȃ��B
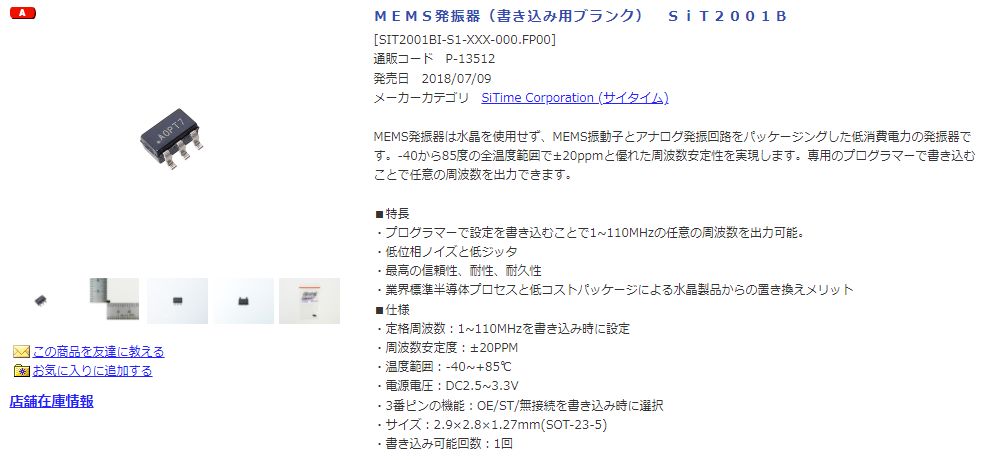 PC�ɂď����������ށB
�`�b�v�̃v���O���~���O�͏o�����悤���B
�����̔��c�t���́A
�M�A�Ód�C�ɒ��ӂ��Ȃ���ł���B
�}�X�L���O�e�[�v�Ń`�b�v������Ɗ��ɌŒ肵�āAI�^�̃R�e��ŁA���t���b�V����������n���_���Ăэ��܂��ĕt���Ă��������Ȃ̂����A
�[�����̑������{���c�t�����ẮA��₷�B(�^�̃s����NC�Ȃ̂͏��������g�R)
���ǁA�A�o�E�g�ŁA�M�ʼn��ĂȂ����Ƃ��C�ɂȂ�B
����ύׂ������ăX�g���X�������܂��ˁB
PC�ɂď����������ށB
�`�b�v�̃v���O���~���O�͏o�����悤���B
�����̔��c�t���́A
�M�A�Ód�C�ɒ��ӂ��Ȃ���ł���B
�}�X�L���O�e�[�v�Ń`�b�v������Ɗ��ɌŒ肵�āAI�^�̃R�e��ŁA���t���b�V����������n���_���Ăэ��܂��ĕt���Ă��������Ȃ̂����A
�[�����̑������{���c�t�����ẮA��₷�B(�^�̃s����NC�Ȃ̂͏��������g�R)
���ǁA�A�o�E�g�ŁA�M�ʼn��ĂȂ����Ƃ��C�ɂȂ�B
����ύׂ������ăX�g���X�������܂��ˁB
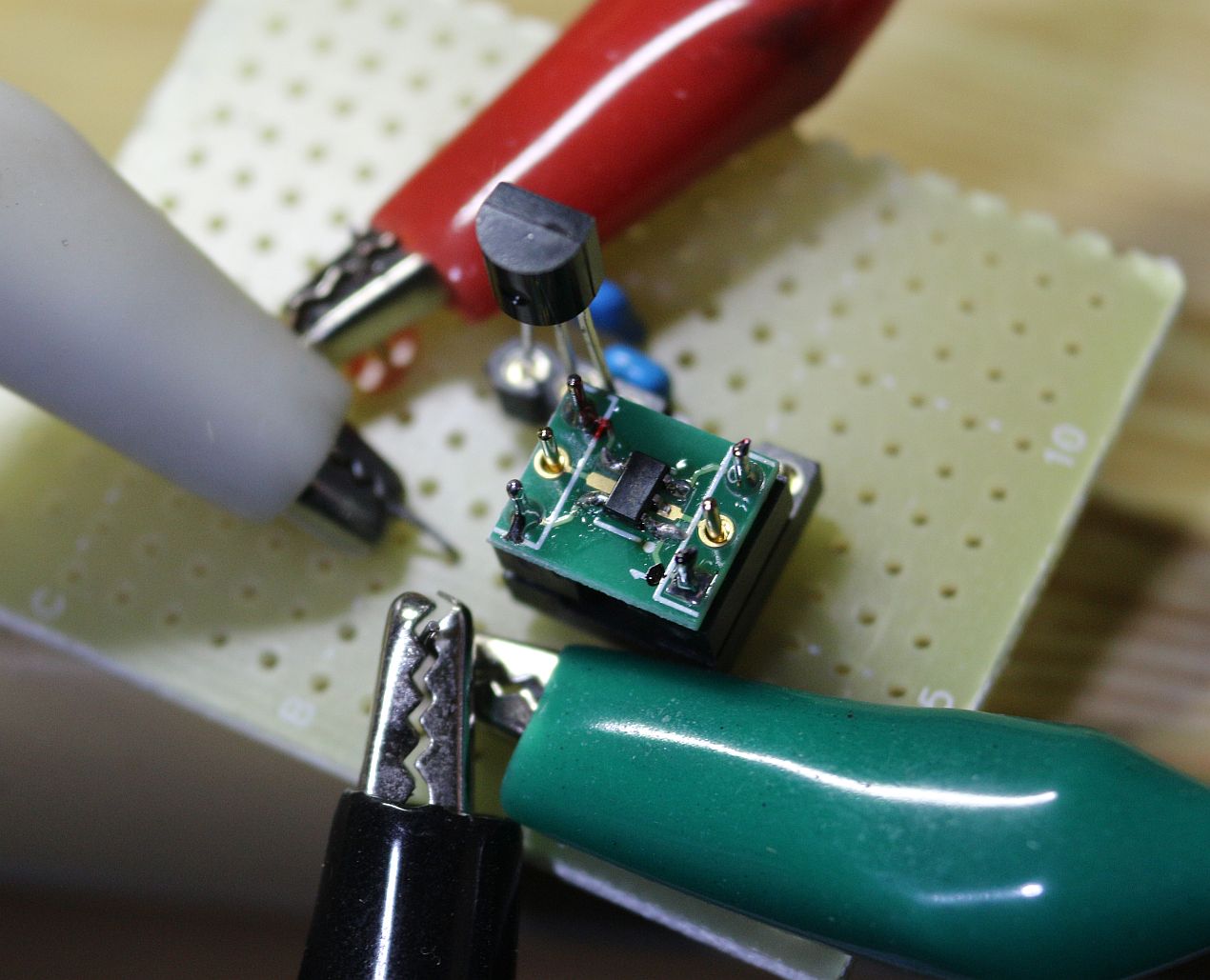 �����������B
�����������B
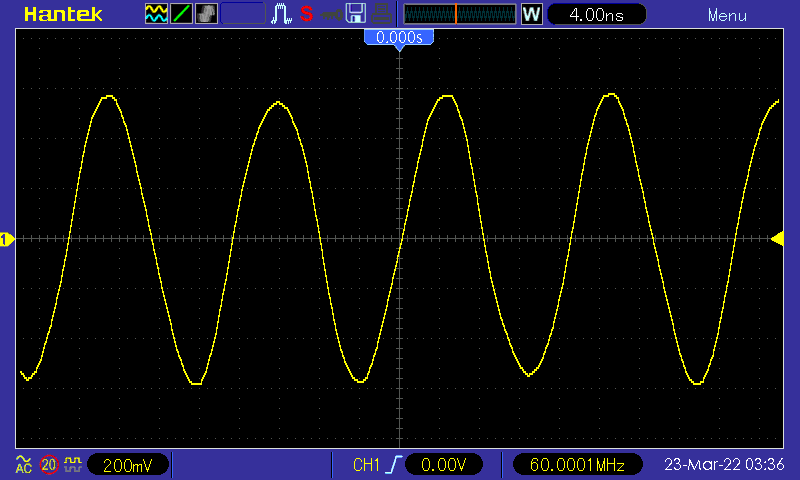 �o�͂�������Ə��������ȁH��20MHz�̃t�B���^�[���������Ă��̂ŊO������A�܂��܂��傫�����Ȃ����B
����ł��A�ш悪70MHz�܂ł̃I�V���Ƃ��ăM���M���Ȃ̂ł��������Ǝv���B
�o�C�|�[���[Tr�����ɂ́A�i�ꂾ����5V�̃N���X�^��OSC�̕�������ۂǃ��N�B
�ł��A�`�b�v�̎�ނ��L�x������A�g�����肪�ǂ��̂�����̂����H�H
�ŁB
����ł܂�������팟�̂�Pre-AMP�Ȃ郂�m���e�X�g�B
�\���́AFET��i�ŁA���o�͂�7mm�p��FCZ�R�C�����g���Ă���B
FCZ�R�C���́A80MHz�̃��m�ŁA����C��12pF�ł���Ă݂�B
�R���Ńe�X�g����ɁA���U�X��������̂����A
�P�[�X�ɓ����Ǝg���Ȃ��قǂɂȂ�B
�l�@����ɁA
60MHz�Ƃ��������g�A7mm�p��FCZ�R�C���Ƃ����B�R�g�ł���B
���炭�A���FCZ�R�C�����d����I�Ɋ����Ă�B���̓_10mm�p�̂ق����L�������m��Ȃ��B
7mm�p�̕����R�ꂪ�����̂��Ǝv���B�����������g�B�B
�ŁA���߂āA���͂̓Q�[�g��GND��1M���Ōq���A�o�͂̂�FCZ�R�C���ɂ����B
�o�͂�������Ə��������ȁH��20MHz�̃t�B���^�[���������Ă��̂ŊO������A�܂��܂��傫�����Ȃ����B
����ł��A�ш悪70MHz�܂ł̃I�V���Ƃ��ăM���M���Ȃ̂ł��������Ǝv���B
�o�C�|�[���[Tr�����ɂ́A�i�ꂾ����5V�̃N���X�^��OSC�̕�������ۂǃ��N�B
�ł��A�`�b�v�̎�ނ��L�x������A�g�����肪�ǂ��̂�����̂����H�H
�ŁB
����ł܂�������팟�̂�Pre-AMP�Ȃ郂�m���e�X�g�B
�\���́AFET��i�ŁA���o�͂�7mm�p��FCZ�R�C�����g���Ă���B
FCZ�R�C���́A80MHz�̃��m�ŁA����C��12pF�ł���Ă݂�B
�R���Ńe�X�g����ɁA���U�X��������̂����A
�P�[�X�ɓ����Ǝg���Ȃ��قǂɂȂ�B
�l�@����ɁA
60MHz�Ƃ��������g�A7mm�p��FCZ�R�C���Ƃ����B�R�g�ł���B
���炭�A���FCZ�R�C�����d����I�Ɋ����Ă�B���̓_10mm�p�̂ق����L�������m��Ȃ��B
7mm�p�̕����R�ꂪ�����̂��Ǝv���B�����������g�B�B
�ŁA���߂āA���͂̓Q�[�g��GND��1M���Ōq���A�o�͂̂�FCZ�R�C���ɂ����B
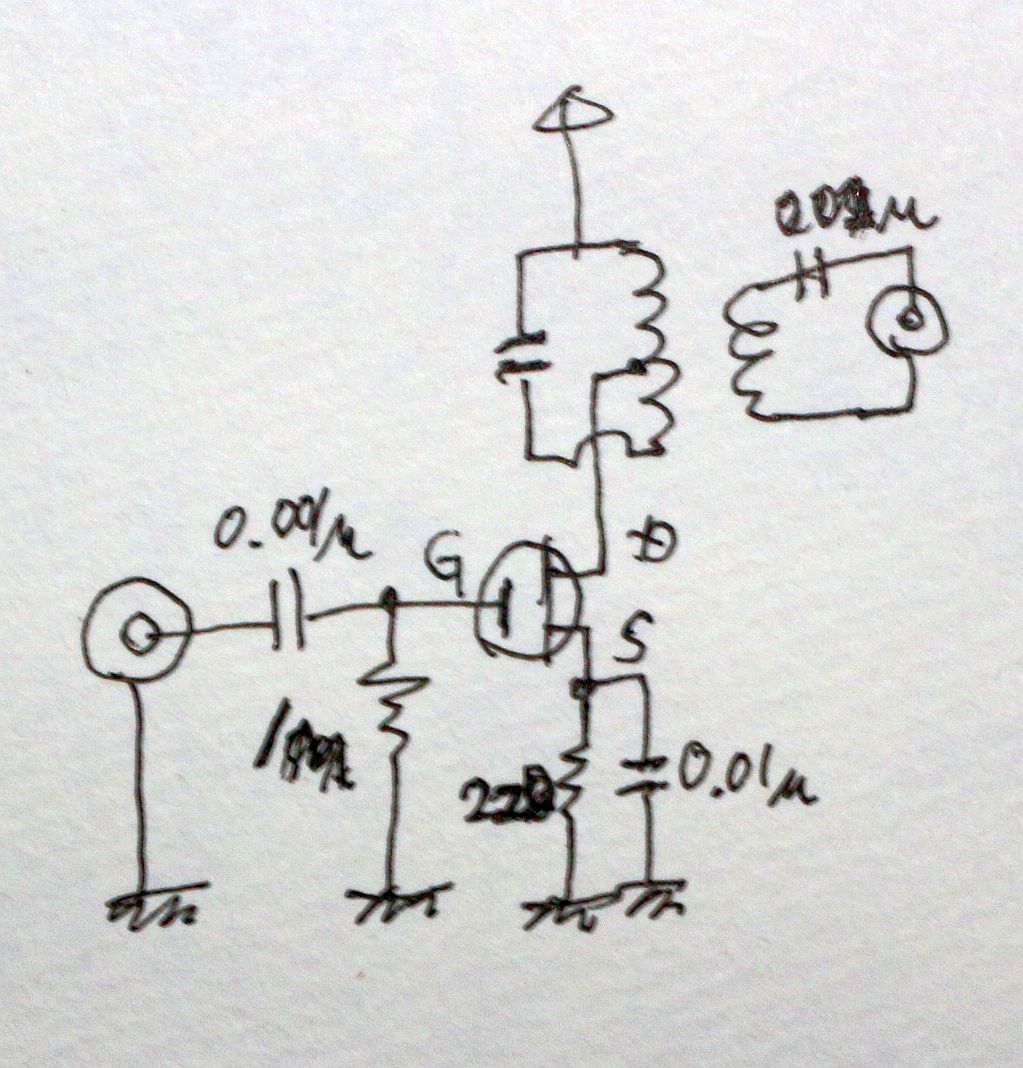 �}���A�������ǁA�h�R���ǂ��ς�������́A���f�͕t���Ǝv���B
�����i�K�p�̎���i�Ȃ̂ŁA
���o�͂̃f�J�b�v�����O�R���f���T�[�̓e�L�g�[��0.1��F�ɂ��Ă���A�\�[�X�̃p�X�R����0.01��F�ɂȂ��Ă�B
20dB���x�ł�����ƃQ�C�������Ȃ����ǁA���퓮�삷��B
�����A�P�[�X��߂�Ǝ�������g�����Y����悤�Ȃ̂ŃP�[�X�Ɍ����J���Ē����o����悤�ɂ������g�R�B
����Ȏ����̊����B
�}���A�������ǁA�h�R���ǂ��ς�������́A���f�͕t���Ǝv���B
�����i�K�p�̎���i�Ȃ̂ŁA
���o�͂̃f�J�b�v�����O�R���f���T�[�̓e�L�g�[��0.1��F�ɂ��Ă���A�\�[�X�̃p�X�R����0.01��F�ɂȂ��Ă�B
20dB���x�ł�����ƃQ�C�������Ȃ����ǁA���퓮�삷��B
�����A�P�[�X��߂�Ǝ�������g�����Y����悤�Ȃ̂ŃP�[�X�Ɍ����J���Ē����o����悤�ɂ������g�R�B
����Ȏ����̊����B
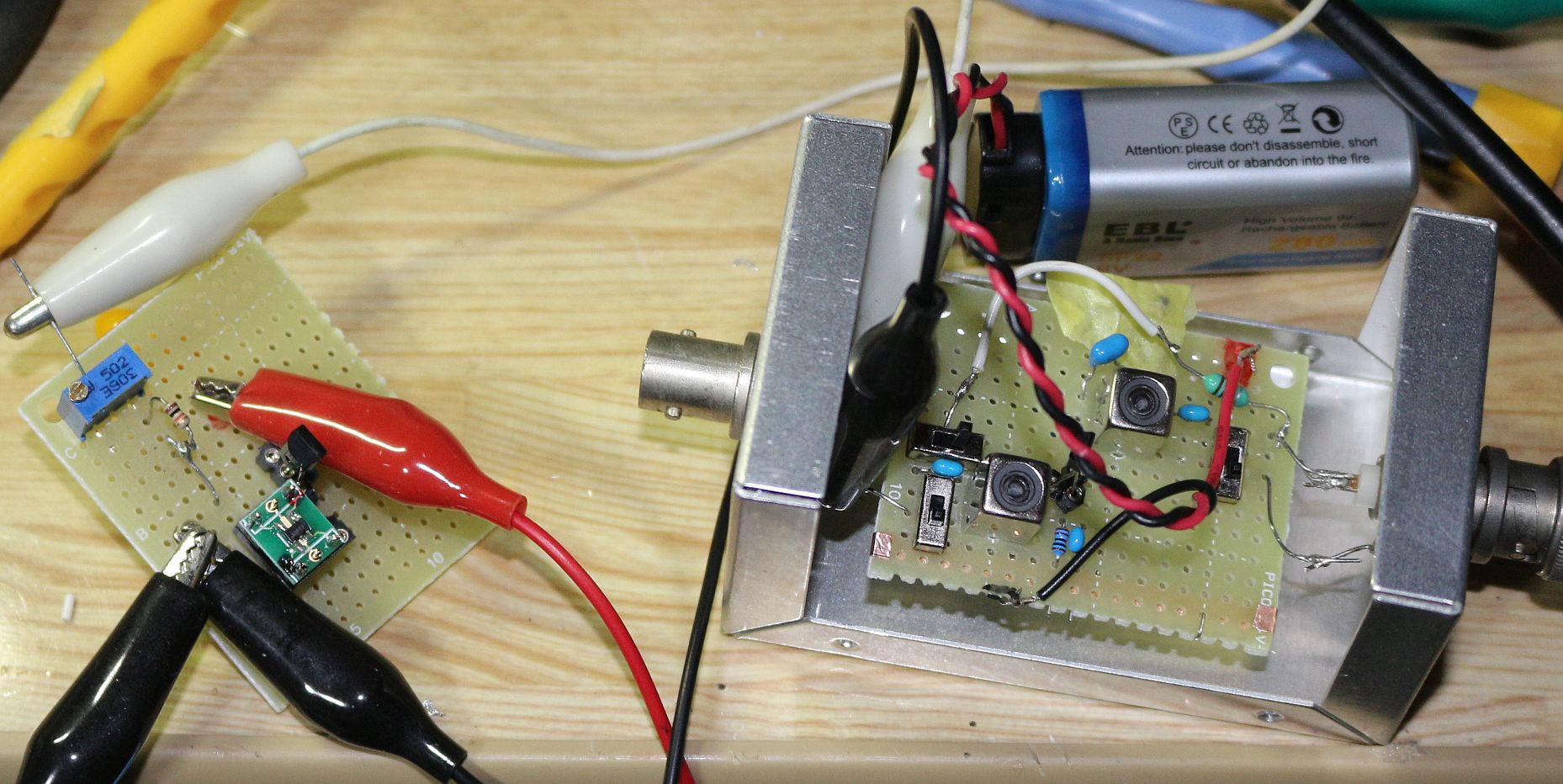 �I�V����O��51���Ń^�[�~�l�[�g���Ă�B
�܂��A10�{�̑����������A�t�H�gDi�łǂ��ł邩�H
BNC�͐≏�Ɛ�ւ����邵�B���o�͂̒����̃X���[SW�����Ă���B�������̃t�H�g�_�C�I�[�h�̋t�o�C�A�X��H�Ƃǂ����ˍ��킹�čs�����͕s���B
�z���g�̂Ƃ��A�t�o�C�A�X��H�������ɐ݂���A���ʂ��Ȃ��Ȃ�A�Q�C�����傫���o����Ƃ͎v�����c�A�A
�����J���čĒ����B�܂��܂��ǂ��Ȃ����B
�ł��A�A���~�̊O�Ƀf�J���������̃��m���߂Â��Ό��\�ς�肻���ɂ��v���B�B
�I�V����O��51���Ń^�[�~�l�[�g���Ă�B
�܂��A10�{�̑����������A�t�H�gDi�łǂ��ł邩�H
BNC�͐≏�Ɛ�ւ����邵�B���o�͂̒����̃X���[SW�����Ă���B�������̃t�H�g�_�C�I�[�h�̋t�o�C�A�X��H�Ƃǂ����ˍ��킹�čs�����͕s���B
�z���g�̂Ƃ��A�t�o�C�A�X��H�������ɐ݂���A���ʂ��Ȃ��Ȃ�A�Q�C�����傫���o����Ƃ͎v�����c�A�A
�����J���čĒ����B�܂��܂��ǂ��Ȃ����B
�ł��A�A���~�̊O�Ƀf�J���������̃��m���߂Â��Ό��\�ς�肻���ɂ��v���B�B
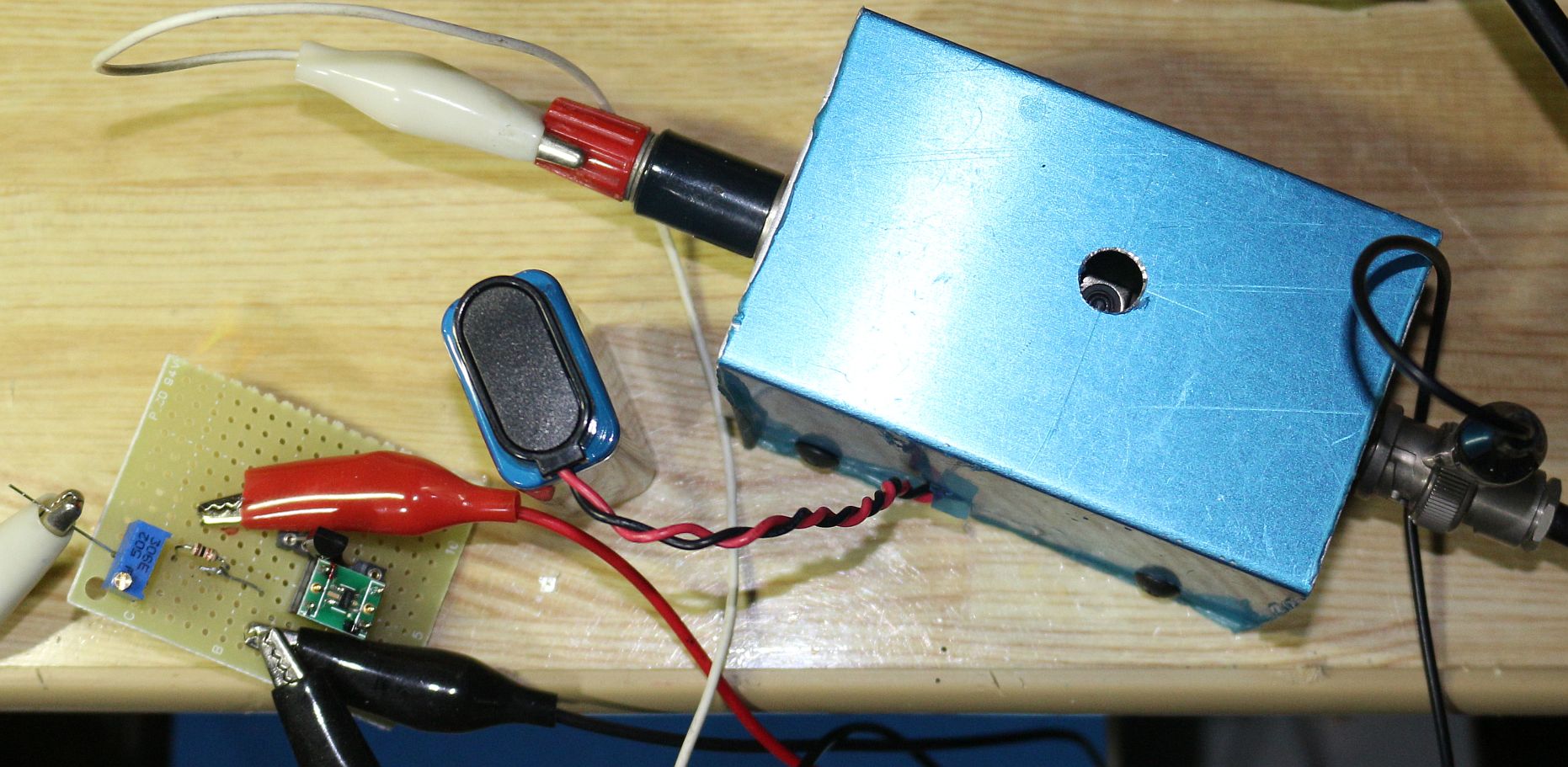 ���ɂ̓t�^��t����Ƃ���ɂ悢�����H�H
�d���m�C�Y���傫����A���o�͂�C������āA10mm�p��FCZ�R�C���A�d�r�܂œ���S���P�[�X�B�ƌ����������ȁH
�{�Ԃ̉�H�́A�����Ȃ�Ǝv����BSW�ƃp�C���b�g�����v���t����c�A
�����AFCZ�R�C������o�͂ɗ����t���āA��Ŏg���ꍇ�A10mm�p�ŁA��̋����𗣂��K�v���A���A�����A�R�C���Ȃ̂ŁA�d���m�C�Y�����₷���̂ŁA�����x�����ł͂��܂葽�p�������Ȃ��B
�M�������\�����Ă�Ƃ��A����d���́A2.2mA���x�B�p�C���b�g�����v�́A0.3mA���x���Ɩ���H
���d��LED���g���B
�e�X�^�[��Di���[�h�ł�����̂ŁA100K����I�������B�̂�0.07mA���x�Ǝv����B
���ɂ̓t�^��t����Ƃ���ɂ悢�����H�H
�d���m�C�Y���傫����A���o�͂�C������āA10mm�p��FCZ�R�C���A�d�r�܂œ���S���P�[�X�B�ƌ����������ȁH
�{�Ԃ̉�H�́A�����Ȃ�Ǝv����BSW�ƃp�C���b�g�����v���t����c�A
�����AFCZ�R�C������o�͂ɗ����t���āA��Ŏg���ꍇ�A10mm�p�ŁA��̋����𗣂��K�v���A���A�����A�R�C���Ȃ̂ŁA�d���m�C�Y�����₷���̂ŁA�����x�����ł͂��܂葽�p�������Ȃ��B
�M�������\�����Ă�Ƃ��A����d���́A2.2mA���x�B�p�C���b�g�����v�́A0.3mA���x���Ɩ���H
���d��LED���g���B
�e�X�^�[��Di���[�h�ł�����̂ŁA100K����I�������B�̂�0.07mA���x�Ǝv����B
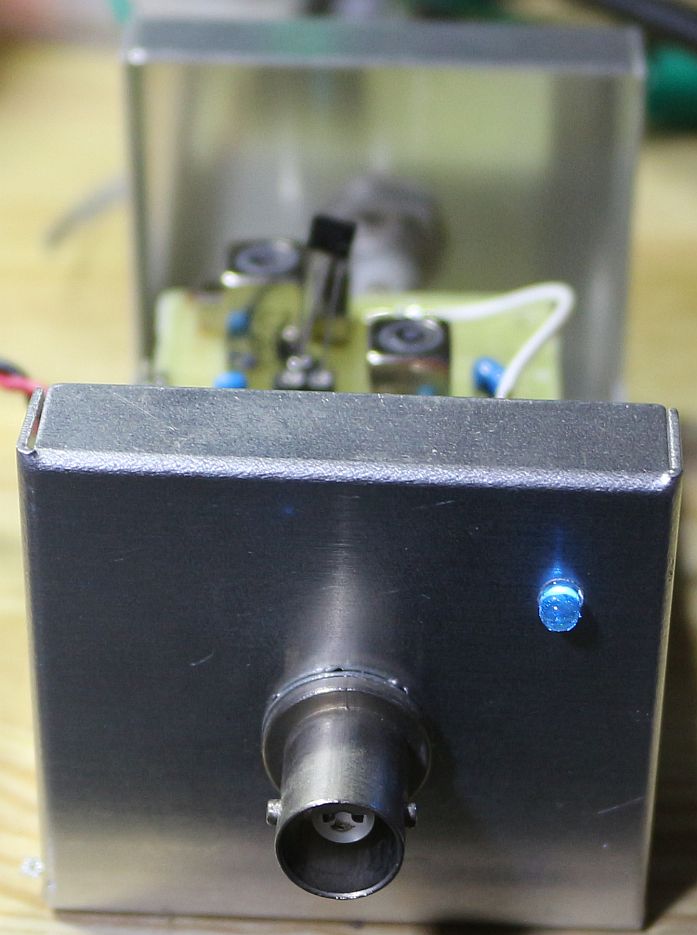
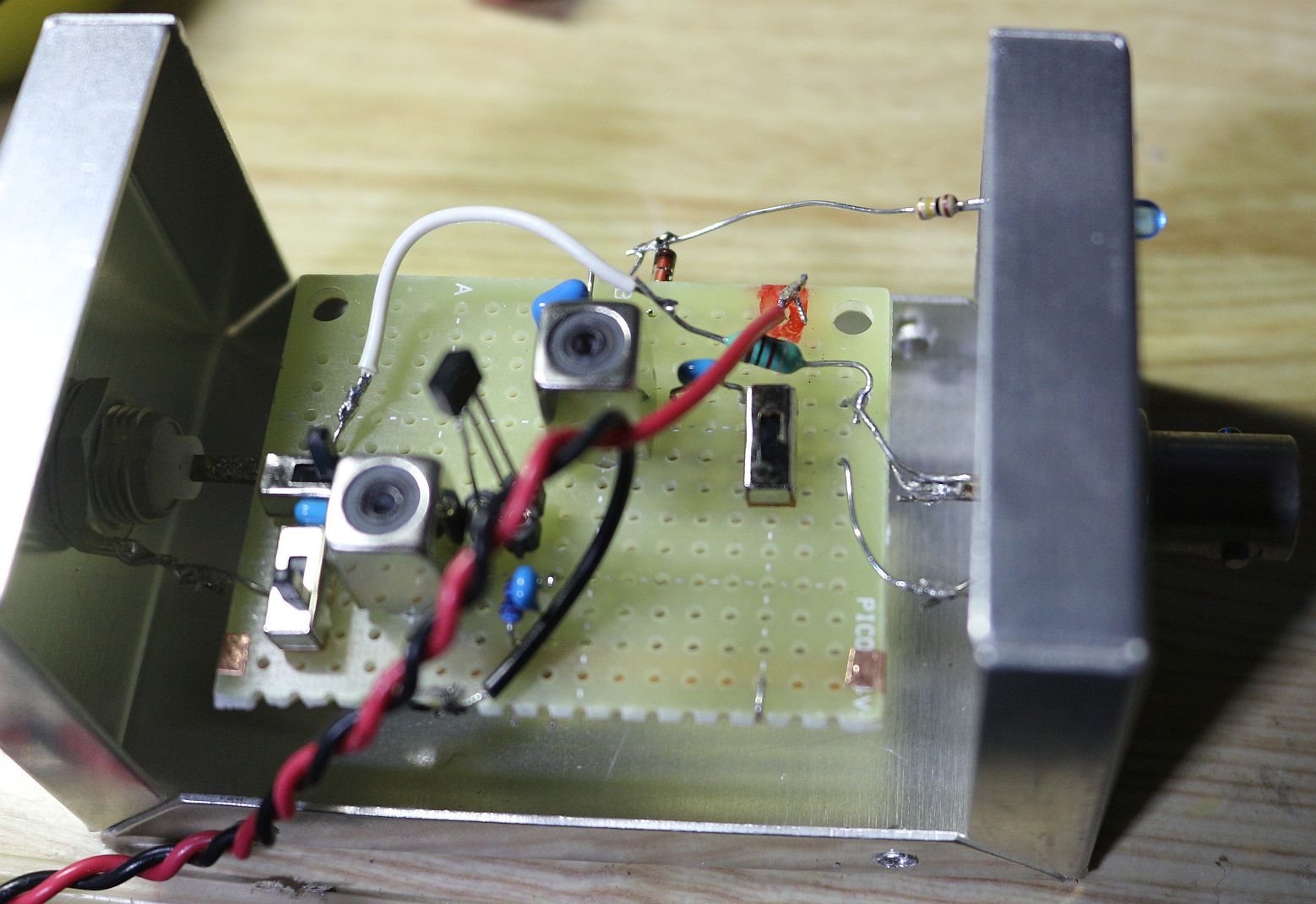 ����Ȃ̂ŁA�ܑ̂Ȃ��̂ŃX�C�b�`�͏ȗ����邱�ƂɌ��߂��B
���݂ɔ��U��̏���d����5.44mA�ł������B
220325
�Q�[�g��R��1M���Ƒ傫���A���o�͂�C���傫���̂ŁA������ƕs����ȋC������B�Q�[�g�͐Ód�e�ʂ�����̂ł�����ƃo�����X���K�v���Ǝv����B
�R�R�͒������K�v���ȁ[�B����̒i�K�Ńh�R�܂ł�邩�͕s���B
����Z��50���Ƃ��ɉ�����o�b�t�@AMP���x�ɂȂ邾�����ȁH
�F�X�ƘM���Ă݂āA�t�H�gDi���ɒu���A�t�o�C�A�X��R�Ƀ`���[�N�R�C������ꂽ�肵�āA�C���s�[�_���X�����߂ɂ��āA�i���{�̉�H�ɂȂ��Ă��邱�ƂɋC���t�����B�̂Ƀm�C�Y�̊W���オ�邩�ƁB
�܂��AFCZ�R�C��2���ƁA���i�̓��͂̃g�����X���C���s�[�_���X�ϊ��ƂȂ��Ă��郏�P�ŁB�V�[���h���Ă�̂Ȃ�A�����łȂ�Ƃ��������C������B
10mm�p��80MHz��FCZ�R�C�����K�v���ēx�l�������A�Ƃ肠�����A7mm�p��FCZ�R�C���ŁA�d�����肩���荞��ł�\�����A���̂ŁB�Ē������l���Ă݂悤�B
�R���f���T�[��20pF�̃g���}�[�ɕς��āAFCZ�R�C���̃l�W��1.5mm�ʉ��ő�̓��������A�R�C���̃l�W���Ŕ�������������ɂ����B
�U�������ŕ]�������A���U���������߁A������M�@��AM�ɂĒT���Ă�̂����ǁA�A�AS���[�^�[���e���̂Ƃ��ŋ�J�B���U�̏������h���ɂ��C�܂���Ŋ��S�ł͖����B
���U���~�߂ĂĂ��A�����_�A�U���͏������B
������������A��i�ڂ��g�����X�ŋ��U�ɂ��Ă��A�U���͉҂��Ȃ������B�B�Ȃ�A���i�̓X���[���ǂ������B�ł��A����������Ɨl�q������B
MEMS�͖����ŕ����ƃM���I�[�Ƃ��������̃m�C�Y�������݂����BAM�ő傫������A�U���̃m�C�Y�����A�A�AMEMSIC�̎�ނɂ���邩�������A�ŏI�I�ɂ̓N���X�^��OSC�̏o�Ԃ����H
�g�����̖��ł��̃m�C�Y��������ꂽ��ǂ��̂����ǁA�Ƃ����̂��A���̒l�i�Œv���I�Ɏv���̂Łc�B
�V���R���̐U���炵���̂ŁA���J�j�Y���I�ɂ́A�N�I�[�c�Ƌ߂��悤�ȋC�����邯�ǁB�B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�Ƃ���ŁA�L���[�u�ȃr�[���X�v���b�^�[�Ȃ̂����ǁA������������ɃL�����Z���̕ԋ������ɂ��Ă��܂����B�B�x��Ă��ǂ��Ə������̂����Ǔ`���Ȃ������悤���B�B
��������Ȃ��̂�����A�܂����������퉻������ŗ���ł������悤�Ȃ��Ƃ����A���ǂ̃g�R�\����啝�Ȓx��ɂȂ邩���c�B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�܂��A����1�i������AMP�A�S�R��肭�s���Ȃ��̂����ǁA���n�����Ƃ͎v�������Ȃ��B
�\�ʂ̐��ʂ����Ŗ����A���ʂ̃X�L���A�b�v�݂����Ȃ̂͐�ɂ��邩�炾�B
�\�R�̂Ƃ���͐h�������Ă���Ă��������Ȃ����A�A�A�X�g���X�ɂ����ӂ��B
MEMS�̔��U��ɂ́A�����Ɂu��ʑ��m�C�Y�ƒ�W�b�^�v��������Ă�̂ŁA�v���p�h���C�o�[��H�ɂ��g����Ηǂ��ȁ[�A�Ǝv���܂��B
10mm�p��FCZ�R�C����������肾���A���K�����i�Ƃ��ẮA�K�v�Ɏv���B
220326
���͑���FCZ�R�C����ݒu����ƃQ�C�����o�Ȃ���ɔg�`�������Ƃ������ƂŁA����ϖ����ɂ����B
����i�K�œ���e�X�g����Ɣ��U���₷�����R�ɁA�o�͂�50���Ń^�[�~�l�[�g���Ă��A�ڑ�����������Ȃ��Ɣ��U�X�������邱�Ƃ��m�F�����B
60MHz�Ƃ��������̂̎��ł��邪�A���͂ł͖����A�o�͂̃��[�h���ڑ������U�Ɍq����͖̂ӓ_�������B
�������A���̉�H�͐M�����̒����ɒu���n�C�C���s�[�_���X�Ŏ邱�Ƃ������ƂȂ�B�C���s�[�_���X�ϊ��p�ł���B
����ċt�o�C�A�X��H�ɉ��H���K�v�Ǝv����B�ł��Ȃ���^�_�̃o�b�t�@�[�ɂȂ邩���B
60MHz�͗\�z�O�ɃC���s�[�_���X��U���Ȃǂɒ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��悤���B�r�߂Ă͂����Ȃ��B
60MHz�ł́A���\�ȑ�����Ƃ������݂͂��Ȃ薳���Ȑݒ肪�A���B�܂�A������I�ԁB
���͂�C��0.01��F�A�Q�[�g��100K���ŁA�Ƃ肠�����܂Ƃ܂��������B���͂̃��[�h��R��C�̎�O�œK���ɍ��߂ɑI�ԁB
��r�̂��߂ɁA���͂�100���o�͂�50���ɂ��đ���Ƃ���ȍ�
��������(���͑�)
����Ȃ̂ŁA�ܑ̂Ȃ��̂ŃX�C�b�`�͏ȗ����邱�ƂɌ��߂��B
���݂ɔ��U��̏���d����5.44mA�ł������B
220325
�Q�[�g��R��1M���Ƒ傫���A���o�͂�C���傫���̂ŁA������ƕs����ȋC������B�Q�[�g�͐Ód�e�ʂ�����̂ł�����ƃo�����X���K�v���Ǝv����B
�R�R�͒������K�v���ȁ[�B����̒i�K�Ńh�R�܂ł�邩�͕s���B
����Z��50���Ƃ��ɉ�����o�b�t�@AMP���x�ɂȂ邾�����ȁH
�F�X�ƘM���Ă݂āA�t�H�gDi���ɒu���A�t�o�C�A�X��R�Ƀ`���[�N�R�C������ꂽ�肵�āA�C���s�[�_���X�����߂ɂ��āA�i���{�̉�H�ɂȂ��Ă��邱�ƂɋC���t�����B�̂Ƀm�C�Y�̊W���オ�邩�ƁB
�܂��AFCZ�R�C��2���ƁA���i�̓��͂̃g�����X���C���s�[�_���X�ϊ��ƂȂ��Ă��郏�P�ŁB�V�[���h���Ă�̂Ȃ�A�����łȂ�Ƃ��������C������B
10mm�p��80MHz��FCZ�R�C�����K�v���ēx�l�������A�Ƃ肠�����A7mm�p��FCZ�R�C���ŁA�d�����肩���荞��ł�\�����A���̂ŁB�Ē������l���Ă݂悤�B
�R���f���T�[��20pF�̃g���}�[�ɕς��āAFCZ�R�C���̃l�W��1.5mm�ʉ��ő�̓��������A�R�C���̃l�W���Ŕ�������������ɂ����B
�U�������ŕ]�������A���U���������߁A������M�@��AM�ɂĒT���Ă�̂����ǁA�A�AS���[�^�[���e���̂Ƃ��ŋ�J�B���U�̏������h���ɂ��C�܂���Ŋ��S�ł͖����B
���U���~�߂ĂĂ��A�����_�A�U���͏������B
������������A��i�ڂ��g�����X�ŋ��U�ɂ��Ă��A�U���͉҂��Ȃ������B�B�Ȃ�A���i�̓X���[���ǂ������B�ł��A����������Ɨl�q������B
MEMS�͖����ŕ����ƃM���I�[�Ƃ��������̃m�C�Y�������݂����BAM�ő傫������A�U���̃m�C�Y�����A�A�AMEMSIC�̎�ނɂ���邩�������A�ŏI�I�ɂ̓N���X�^��OSC�̏o�Ԃ����H
�g�����̖��ł��̃m�C�Y��������ꂽ��ǂ��̂����ǁA�Ƃ����̂��A���̒l�i�Œv���I�Ɏv���̂Łc�B
�V���R���̐U���炵���̂ŁA���J�j�Y���I�ɂ́A�N�I�[�c�Ƌ߂��悤�ȋC�����邯�ǁB�B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�Ƃ���ŁA�L���[�u�ȃr�[���X�v���b�^�[�Ȃ̂����ǁA������������ɃL�����Z���̕ԋ������ɂ��Ă��܂����B�B�x��Ă��ǂ��Ə������̂����Ǔ`���Ȃ������悤���B�B
��������Ȃ��̂�����A�܂����������퉻������ŗ���ł������悤�Ȃ��Ƃ����A���ǂ̃g�R�\����啝�Ȓx��ɂȂ邩���c�B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�܂��A����1�i������AMP�A�S�R��肭�s���Ȃ��̂����ǁA���n�����Ƃ͎v�������Ȃ��B
�\�ʂ̐��ʂ����Ŗ����A���ʂ̃X�L���A�b�v�݂����Ȃ̂͐�ɂ��邩�炾�B
�\�R�̂Ƃ���͐h�������Ă���Ă��������Ȃ����A�A�A�X�g���X�ɂ����ӂ��B
MEMS�̔��U��ɂ́A�����Ɂu��ʑ��m�C�Y�ƒ�W�b�^�v��������Ă�̂ŁA�v���p�h���C�o�[��H�ɂ��g����Ηǂ��ȁ[�A�Ǝv���܂��B
10mm�p��FCZ�R�C����������肾���A���K�����i�Ƃ��ẮA�K�v�Ɏv���B
220326
���͑���FCZ�R�C����ݒu����ƃQ�C�����o�Ȃ���ɔg�`�������Ƃ������ƂŁA����ϖ����ɂ����B
����i�K�œ���e�X�g����Ɣ��U���₷�����R�ɁA�o�͂�50���Ń^�[�~�l�[�g���Ă��A�ڑ�����������Ȃ��Ɣ��U�X�������邱�Ƃ��m�F�����B
60MHz�Ƃ��������̂̎��ł��邪�A���͂ł͖����A�o�͂̃��[�h���ڑ������U�Ɍq����͖̂ӓ_�������B
�������A���̉�H�͐M�����̒����ɒu���n�C�C���s�[�_���X�Ŏ邱�Ƃ������ƂȂ�B�C���s�[�_���X�ϊ��p�ł���B
����ċt�o�C�A�X��H�ɉ��H���K�v�Ǝv����B�ł��Ȃ���^�_�̃o�b�t�@�[�ɂȂ邩���B
60MHz�͗\�z�O�ɃC���s�[�_���X��U���Ȃǂɒ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��悤���B�r�߂Ă͂����Ȃ��B
60MHz�ł́A���\�ȑ�����Ƃ������݂͂��Ȃ薳���Ȑݒ肪�A���B�܂�A������I�ԁB
���͂�C��0.01��F�A�Q�[�g��100K���ŁA�Ƃ肠�����܂Ƃ܂��������B���͂̃��[�h��R��C�̎�O�œK���ɍ��߂ɑI�ԁB
��r�̂��߂ɁA���͂�100���o�͂�50���ɂ��đ���Ƃ���ȍ�
��������(���͑�)
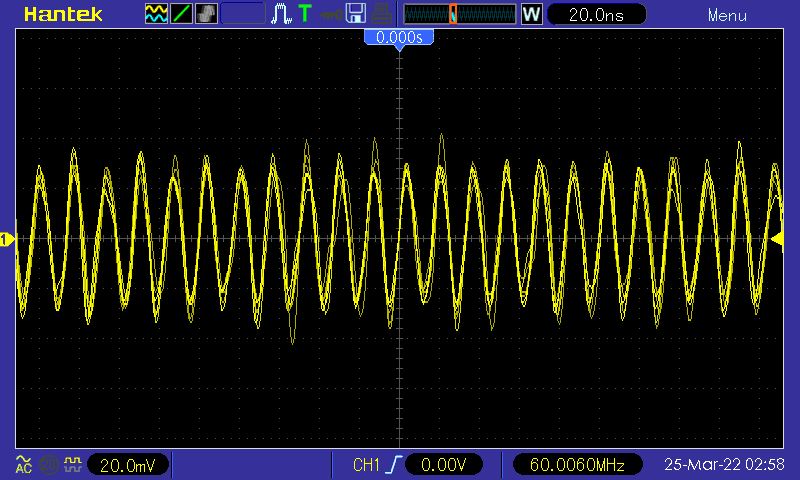 �����A��(�o�͑�)
�����A��(�o�͑�)
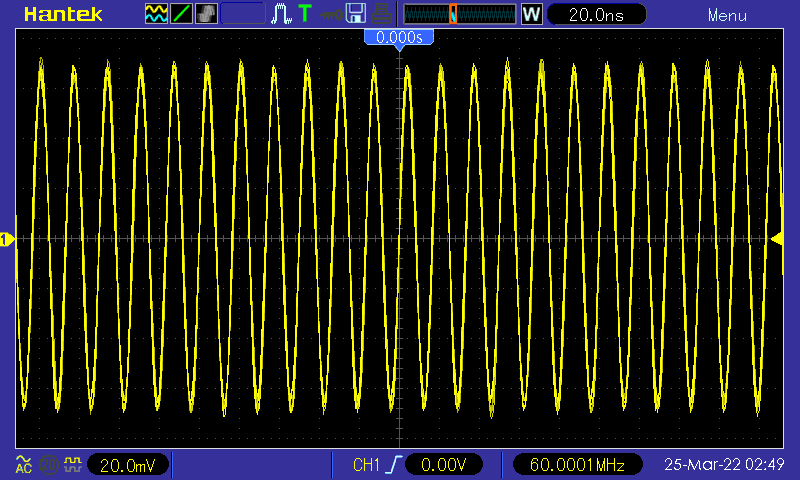 2�`3�{���炢�A�A�܂��܂��傫���Ƃ������x�B�g�`���Y��ɂȂ��Ă�̂�FCZ�R�C���ɂ��t�B���^�[�̂��������ȁH�B�M�����傫���Ȃ���S/N���オ�����ƌ������Ƃ��B
�����A����Z��傫���܂g�p���o����Ες���Ă��邩���m��Ȃ��B
�Ƃ���ŁA���v�Ȃ̂����A���g�����グ��ƁA���ԕ���\�͏オ�邪�A�p�x���s���m�ɂȂ肪�����Ǝv���B
�ʑ����o���PD��PDQ�̈ʑ������z���Ȃǂŏo�Ă��܂��A�������Ȃ���ԂɂȂ�ƌ������ƂɂȂ�X���͎�������Ƒz�������B�����i�͒����ς݂��Ǝv�����A�A���ɂ��F�X�Ɩ�肪�o�����B
�Ȃ̂ŁA��������Ɏ��g�����グ�܂���̂��l�����B
���ƁA���̎��g���т̏ꍇ�AIC�\�P�b�g�͎g��Ȃ����A��̂�����(�p�^�[��)�ʂɎ������邱�Ƃ������B
���̒������̗U�d���܂ŋC�ɂ���B
�I�V���̎��g���\����FFT�ł͂Ȃ��A�J�E���^�[�Ȃ̂ŁA�u����ƃY����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220327
����60MHz�̉�H�́A50MHz�̖����̋Z�p��������x�]�p�o����̂����ǁA
���ӂ��ׂ��́A�p�r�������̌v���Ȃ̂ŁA���������͍����Ŗ����Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ŁA�s�����n�����i�������킯�ɂ͍s���Ȃ��B
����āA�g�[�^���ŁA���ʂ�LC����2�`3�i���Ǝv���Ă���B
����āAPre-AMP�̏��i��FCZ�R�C����r�������͈̂Ӗ������邩���m��Ȃ��B
���m�ȃC���s�[�_���X�����܂��Ă��Ȃ��̂ŁB
���Ƃ́A�̍����AGC-AMP�Ȃ���̂����ǂ��č��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�����ł��ڂɂ���̂��A
�r�f�I�p����OP-AMP�₻�̑ш��VCA�Ȃǂ͖łтĂ�Ƃ��������̊���������B
�������A���R���u�łтĂ�v���肶�Ⴢ�m�����Ȃ��̂ŁA���̎���̃��m��T�����������邪�A
�R�C���Ȃǂ͎�����\�BAGC������IC�͒��B��������A3SK��FET�̑�2�Q�[�g�������̂��A�������c�B(�Q�[�g�M�����m�̊|���Z�I�v�f)
���̒��̌��ۂ͐F�X����̂ɁA�v���p�̃��m�͂��Ă�VHF�܂ŐL�тĂȂ��A����Ƌ��ɑމ����Ă�Ǝv���B
�ʐM�͑ш�̑����AGHz�͂܂�����悤�����A���̊Ԃ̕��������������Ă�̂͌v���p�r�Ƃ��Ă͉������ȁc�A
�ׂ���Ȃ���Z�p���̂Ă�̂͐l�Ԏ��߂悤�Ƃ��Ă�C���[�W���B
�Ƃ肠�������}�p�̑������o���Ă����B�Ǐ��\�z����ƌ������͕s���B(�ň��A���U�ɂ��Q�C���R���g���[�����\��Ă邾�Ɠ���B)
2�`3�{���炢�A�A�܂��܂��傫���Ƃ������x�B�g�`���Y��ɂȂ��Ă�̂�FCZ�R�C���ɂ��t�B���^�[�̂��������ȁH�B�M�����傫���Ȃ���S/N���オ�����ƌ������Ƃ��B
�����A����Z��傫���܂g�p���o����Ες���Ă��邩���m��Ȃ��B
�Ƃ���ŁA���v�Ȃ̂����A���g�����グ��ƁA���ԕ���\�͏オ�邪�A�p�x���s���m�ɂȂ肪�����Ǝv���B
�ʑ����o���PD��PDQ�̈ʑ������z���Ȃǂŏo�Ă��܂��A�������Ȃ���ԂɂȂ�ƌ������ƂɂȂ�X���͎�������Ƒz�������B�����i�͒����ς݂��Ǝv�����A�A���ɂ��F�X�Ɩ�肪�o�����B
�Ȃ̂ŁA��������Ɏ��g�����グ�܂���̂��l�����B
���ƁA���̎��g���т̏ꍇ�AIC�\�P�b�g�͎g��Ȃ����A��̂�����(�p�^�[��)�ʂɎ������邱�Ƃ������B
���̒������̗U�d���܂ŋC�ɂ���B
�I�V���̎��g���\����FFT�ł͂Ȃ��A�J�E���^�[�Ȃ̂ŁA�u����ƃY����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220327
����60MHz�̉�H�́A50MHz�̖����̋Z�p��������x�]�p�o����̂����ǁA
���ӂ��ׂ��́A�p�r�������̌v���Ȃ̂ŁA���������͍����Ŗ����Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ŁA�s�����n�����i�������킯�ɂ͍s���Ȃ��B
����āA�g�[�^���ŁA���ʂ�LC����2�`3�i���Ǝv���Ă���B
����āAPre-AMP�̏��i��FCZ�R�C����r�������͈̂Ӗ������邩���m��Ȃ��B
���m�ȃC���s�[�_���X�����܂��Ă��Ȃ��̂ŁB
���Ƃ́A�̍����AGC-AMP�Ȃ���̂����ǂ��č��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�����ł��ڂɂ���̂��A
�r�f�I�p����OP-AMP�₻�̑ш��VCA�Ȃǂ͖łтĂ�Ƃ��������̊���������B
�������A���R���u�łтĂ�v���肶�Ⴢ�m�����Ȃ��̂ŁA���̎���̃��m��T�����������邪�A
�R�C���Ȃǂ͎�����\�BAGC������IC�͒��B��������A3SK��FET�̑�2�Q�[�g�������̂��A�������c�B(�Q�[�g�M�����m�̊|���Z�I�v�f)
���̒��̌��ۂ͐F�X����̂ɁA�v���p�̃��m�͂��Ă�VHF�܂ŐL�тĂȂ��A����Ƌ��ɑމ����Ă�Ǝv���B
�ʐM�͑ш�̑����AGHz�͂܂�����悤�����A���̊Ԃ̕��������������Ă�̂͌v���p�r�Ƃ��Ă͉������ȁc�A
�ׂ���Ȃ���Z�p���̂Ă�̂͐l�Ԏ��߂悤�Ƃ��Ă�C���[�W���B
�Ƃ肠�������}�p�̑������o���Ă����B�Ǐ��\�z����ƌ������͕s���B(�ň��A���U�ɂ��Q�C���R���g���[�����\��Ă邾�Ɠ���B)
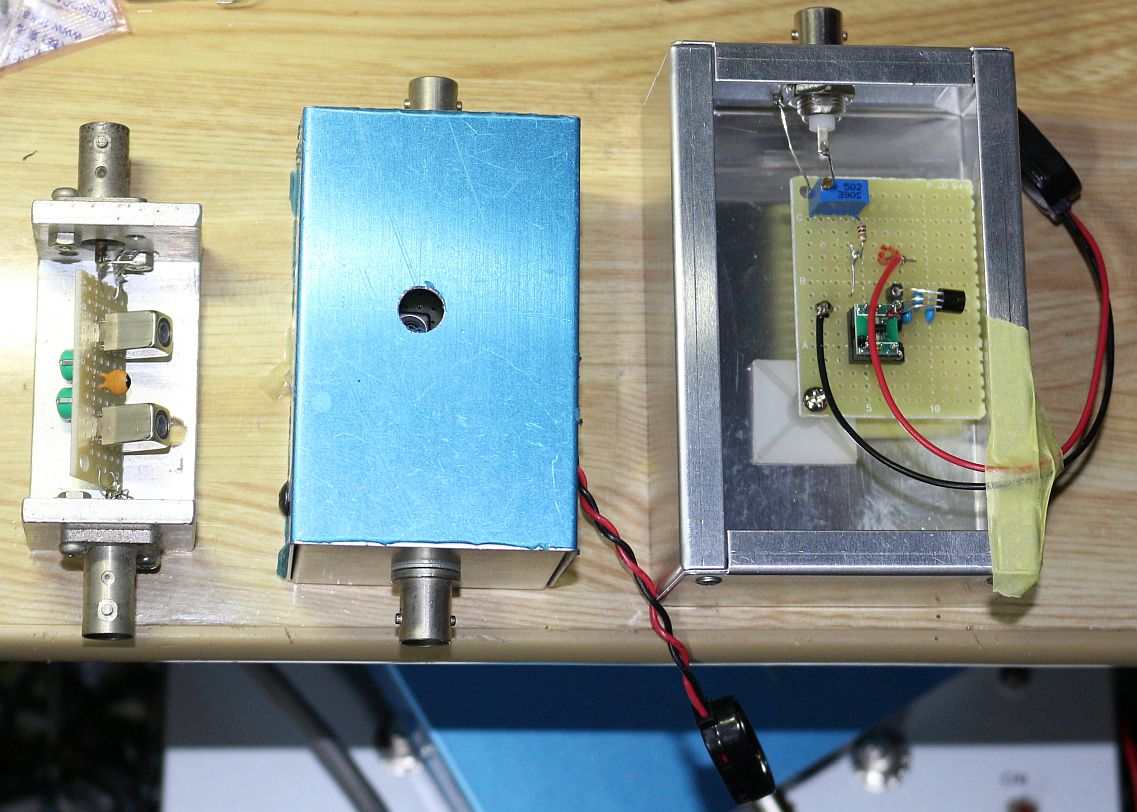 ���̂��V���ɍ����BPF�A
LC��H�͎�ŐG�ꂽ�肷��Ǝ��g���������Y�����肷��B
���Ƃ��̉�H�͔�r�I�s������������̂ŁA��͂�O�E�̉e������B
���o�͂��Ђ�����Ԃ��ƁA�Ē������K�v�ɂȂ�ʂŃA���B
�����A�M���̃��X�͗\�z���Ă�قǖ��������B
�����i�����́ATDK�⑾�z�U�d�ɓ������Ƃ��l���Ē��ׂČ���ɁA�A
���������l�i���B
���̂��V���ɍ����BPF�A
LC��H�͎�ŐG�ꂽ�肷��Ǝ��g���������Y�����肷��B
���Ƃ��̉�H�͔�r�I�s������������̂ŁA��͂�O�E�̉e������B
���o�͂��Ђ�����Ԃ��ƁA�Ē������K�v�ɂȂ�ʂŃA���B
�����A�M���̃��X�͗\�z���Ă�قǖ��������B
�����i�����́ATDK�⑾�z�U�d�ɓ������Ƃ��l���Ē��ׂČ���ɁA�A
���������l�i���B
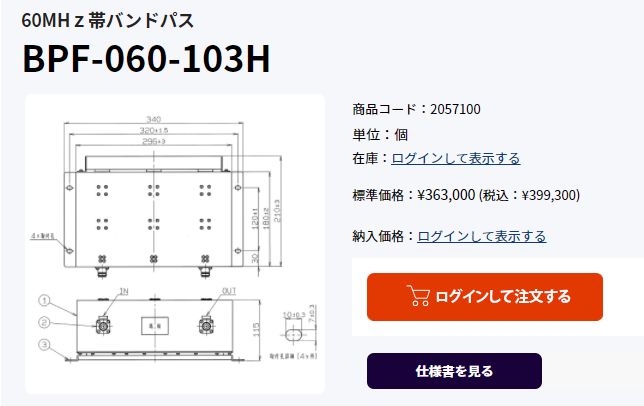 �~�j�T�[�L�b�g�̂��ƌ��\���߂��Ǝv���܂����B
�X�g�b�v�o���h�̌�������A�ш悪�}�`�}�`�Ȃ̂ŁA
���������ATr��ECB�̔z����ăG�N�{�Ƃ����̂��c�B
���ƁA�o�C�|�[���[Tr���p�������Ŏg���邩���l����ƁA�A
2SC945�̃f�[�^�V�[�g����́A
�����x�[�X�d���ŁA���x�������قǁAhfe�������A����₷���̂ŁA������Tr�̃o�����X���Ƃ�͖̂��������B
�����A�X�C�b�`�Ƃ��Ďg�p����Ȃ�ĊO���M�����Ȃ��̂ŁA�g���邩���H
�����āA���M�t�B����t�@���ŏ����͊ɘa���邩���B
���Ƃ̓v�b�V���v���ŁA���M������邩�H
2SC945�̓R���N�^����750mW�Ȃ̂ŁA�X�C�b�`���O�p���X�ŏo�����āA��ŋ��n�Řc�݂��Ƃ�B�Ƃ��o����B�B�ŁA2W�ʂ̏o�͂ɑς�����c�A�A
2�p���ŕ��M����肭����A�A���āA���钼�O�̒�i�쓮�ɂȂ��Ă��܂��悤�ȁB�B
���ɁA�|�s�����[��60MHz��2W���x�̋쓮���e�Ղȃp���[�̏o����Tr������c�A�A
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
30MHz�̌����e�̎����H�ɂ����āB
�O��22��H�ŁA12.3MHz�܂ʼn������Ă��܂������A
�N���X�^���̃R���s�b�c���U�́A�N���X�^���ɂ����镉�ׂ�L�ɂ��āA
�^����L�ɑ����ŕω����郂�m�ł͖����悤���B
2.2��H�~2�����60pF�̃g���}�[��19.3000MHz�֒������ł����B
�~�j�T�[�L�b�g�̂��ƌ��\���߂��Ǝv���܂����B
�X�g�b�v�o���h�̌�������A�ш悪�}�`�}�`�Ȃ̂ŁA
���������ATr��ECB�̔z����ăG�N�{�Ƃ����̂��c�B
���ƁA�o�C�|�[���[Tr���p�������Ŏg���邩���l����ƁA�A
2SC945�̃f�[�^�V�[�g����́A
�����x�[�X�d���ŁA���x�������قǁAhfe�������A����₷���̂ŁA������Tr�̃o�����X���Ƃ�͖̂��������B
�����A�X�C�b�`�Ƃ��Ďg�p����Ȃ�ĊO���M�����Ȃ��̂ŁA�g���邩���H
�����āA���M�t�B����t�@���ŏ����͊ɘa���邩���B
���Ƃ̓v�b�V���v���ŁA���M������邩�H
2SC945�̓R���N�^����750mW�Ȃ̂ŁA�X�C�b�`���O�p���X�ŏo�����āA��ŋ��n�Řc�݂��Ƃ�B�Ƃ��o����B�B�ŁA2W�ʂ̏o�͂ɑς�����c�A�A
2�p���ŕ��M����肭����A�A���āA���钼�O�̒�i�쓮�ɂȂ��Ă��܂��悤�ȁB�B
���ɁA�|�s�����[��60MHz��2W���x�̋쓮���e�Ղȃp���[�̏o����Tr������c�A�A
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
30MHz�̌����e�̎����H�ɂ����āB
�O��22��H�ŁA12.3MHz�܂ʼn������Ă��܂������A
�N���X�^���̃R���s�b�c���U�́A�N���X�^���ɂ����镉�ׂ�L�ɂ��āA
�^����L�ɑ����ŕω����郂�m�ł͖����悤���B
2.2��H�~2�����60pF�̃g���}�[��19.3000MHz�֒������ł����B
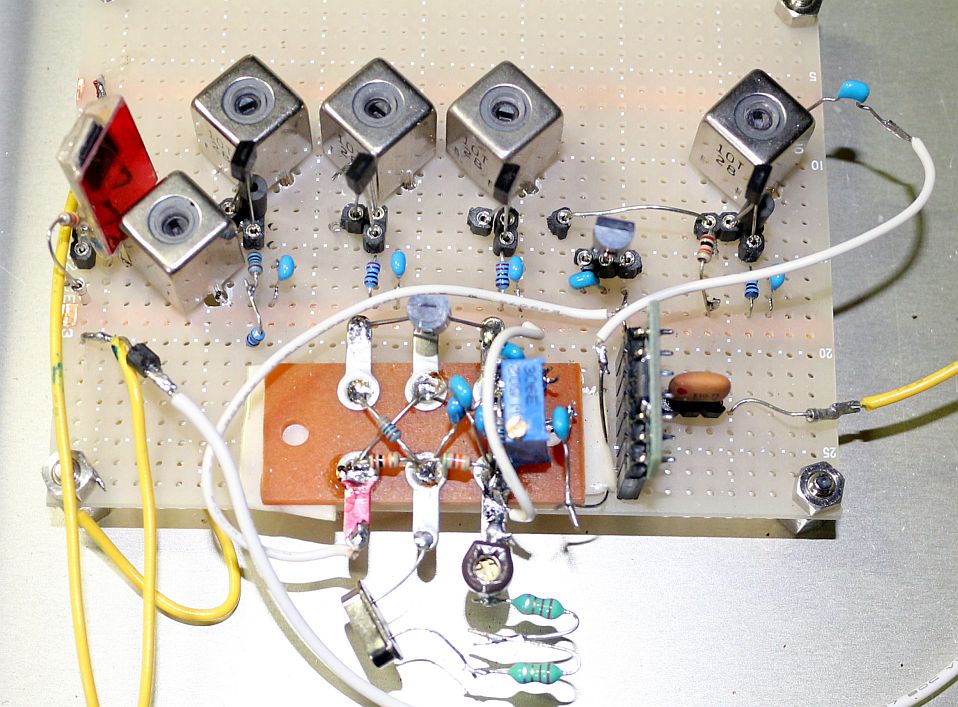
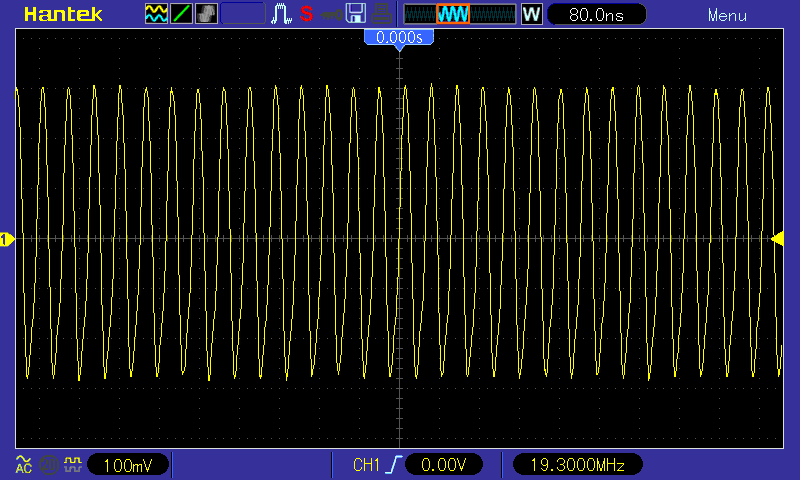 XYZR�X�e�[�W�́A���X��XY�AZ�AR��3�i�K�̕��i�̑g�ݗ��ĂɂȂ��Ă��̂ŁB
XYZ��R��ʂɎg���R�g���o����B�����Ȏd�l�������B
XYZR�X�e�[�W�́A���X��XY�AZ�AR��3�i�K�̕��i�̑g�ݗ��ĂɂȂ��Ă��̂ŁB
XYZ��R��ʂɎg���R�g���o����B�����Ȏd�l�������B
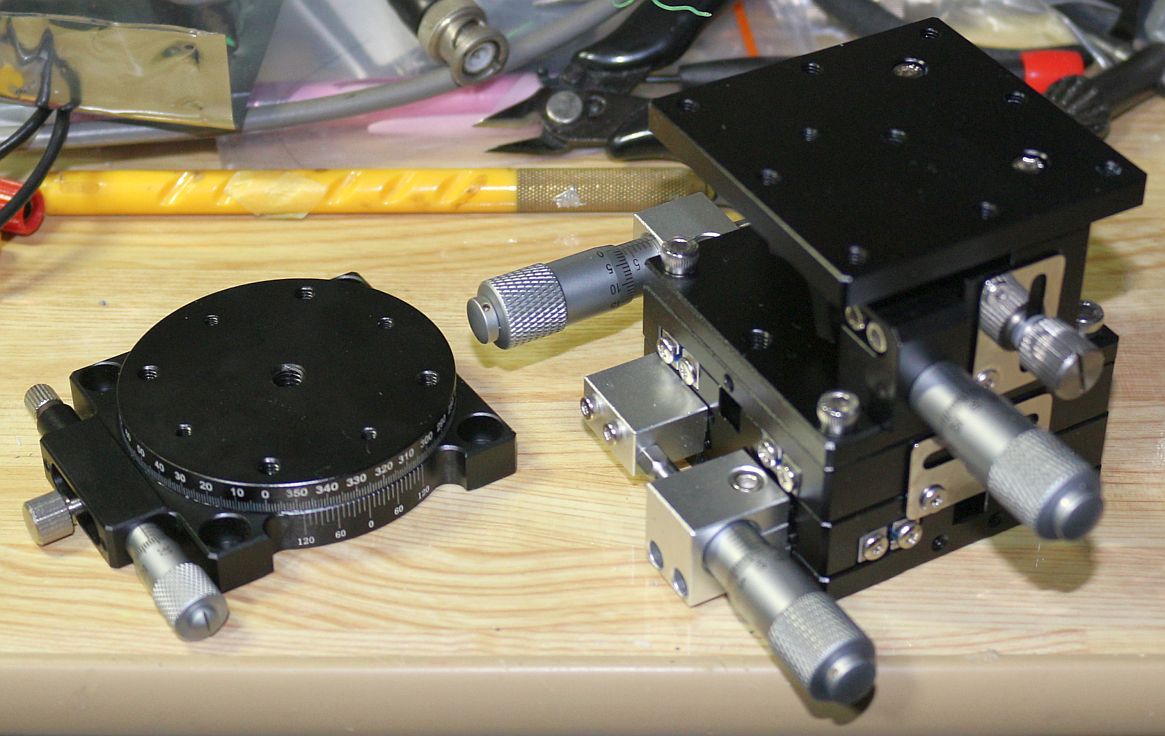 �L�l�N�e�B�b�N�ȃ~���[�z���_�[�́A
25.4��25mm�Ń|�[���ւ̃l�W�͐��ĂȂ��悤�����AM4�Ə����Ă���B
���̐��i��mm��inch�̍��p�Ȏd�l�ƌ������ƂɂȂ�B���[�|���@�͖łтė~�����Ƃ����͓̂��ӂŃA���B
�L�l�N�e�B�b�N�ȃ~���[�z���_�[�́A
25.4��25mm�Ń|�[���ւ̃l�W�͐��ĂȂ��悤�����AM4�Ə����Ă���B
���̐��i��mm��inch�̍��p�Ȏd�l�ƌ������ƂɂȂ�B���[�|���@�͖łтė~�����Ƃ����͓̂��ӂŃA���B
 �|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220404
10.7MHz��BW=�}3.75KHz�̃N���X�^���t�B���^�[�������A�ш�͌��\���������Ǝv���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220404
10.7MHz��BW=�}3.75KHz�̃N���X�^���t�B���^�[�������A�ш�͌��\���������Ǝv���B
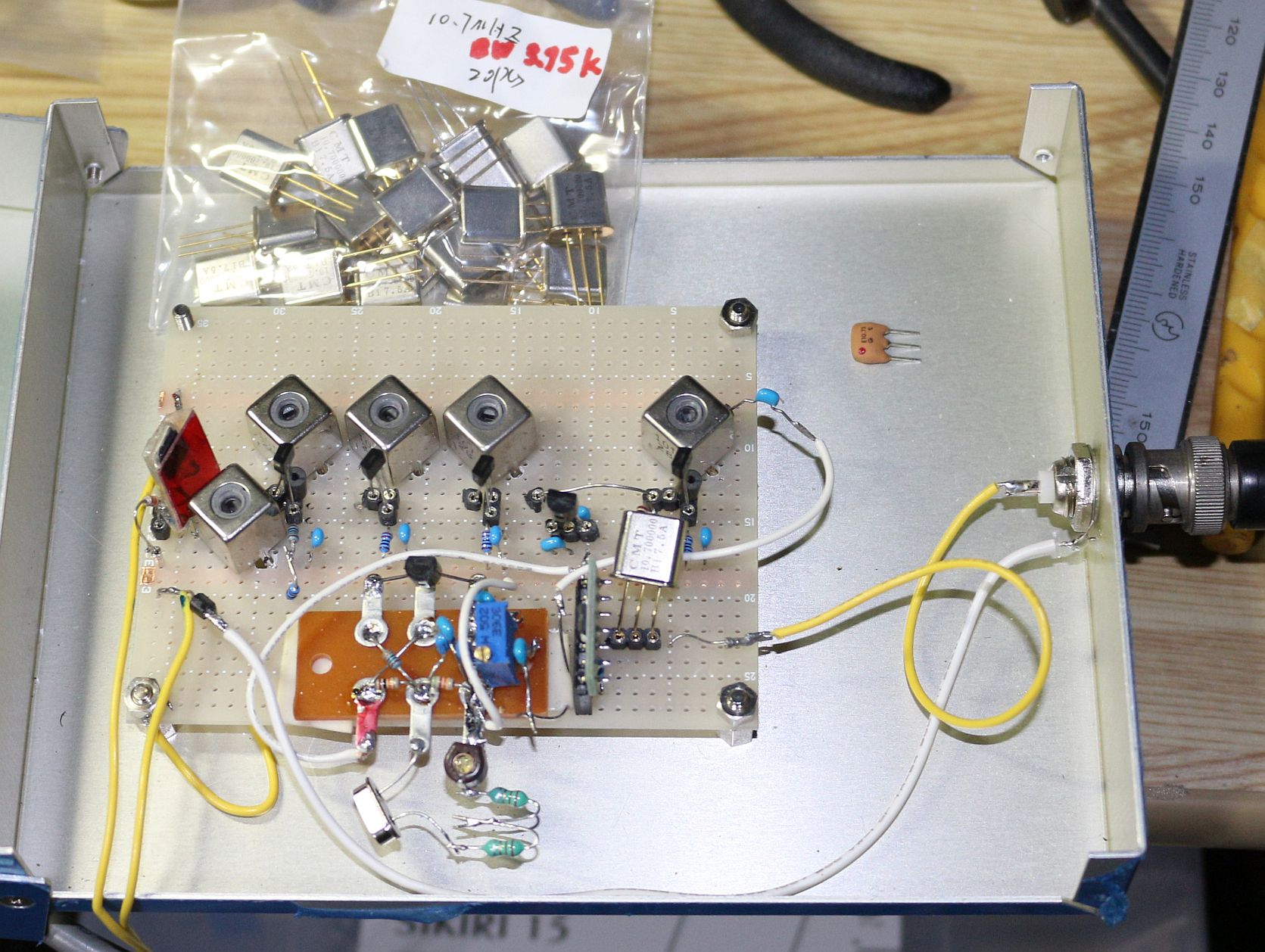 ���̃t�B���^�[�ł�100��Sec�̃o�[�X�g�ł̏o�͓����B
���̃t�B���^�[�ł�100��Sec�̃o�[�X�g�ł̏o�͓����B
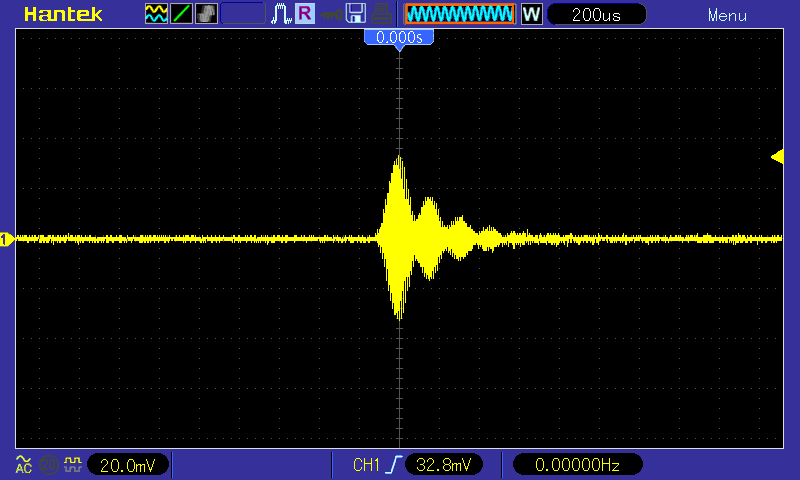 �^�C���X�P�[����L���ƁA
�^�C���X�P�[����L���ƁA
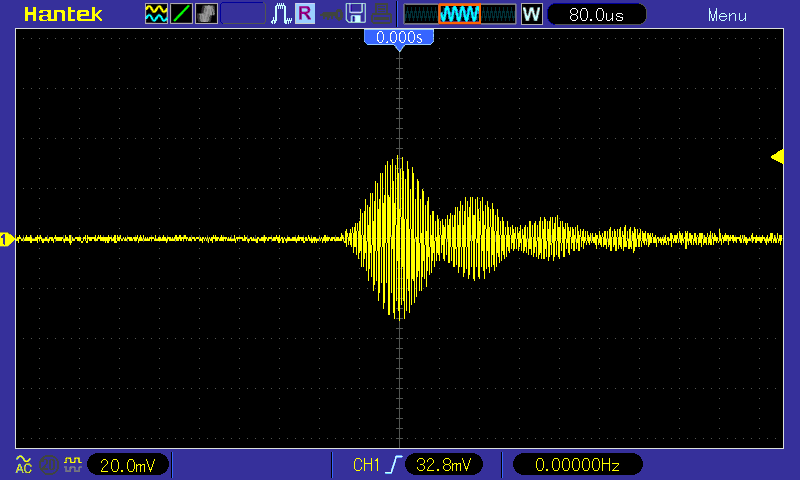 �g�ł��Ă邯�ǁA�����́A�܂��܂����ȁH
�A���g�̐U���́A
�g�ł��Ă邯�ǁA�����́A�܂��܂����ȁH
�A���g�̐U���́A
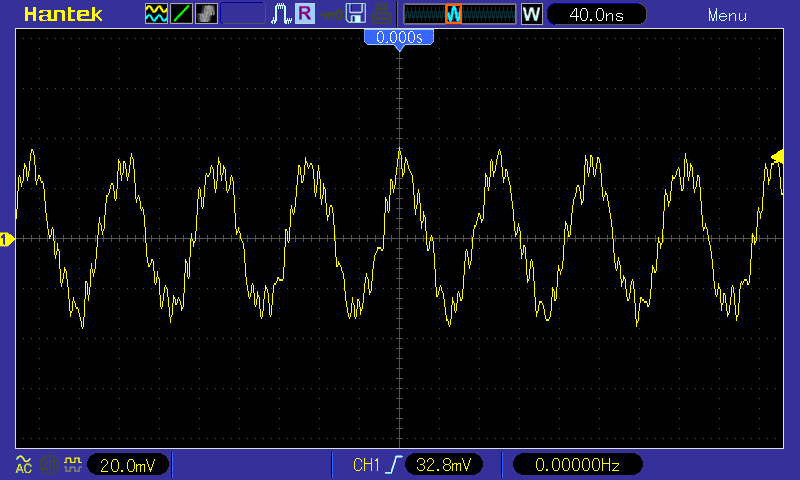 �Ȃ̂ŁA�܂��A�M���M���ł͂��邪��N�͍ő�܂ōs���Ă�ƌ�����B
���݂�
�Ȃ̂ŁA�܂��A�M���M���ł͂��邪��N�͍ő�܂ōs���Ă�ƌ�����B
���݂�
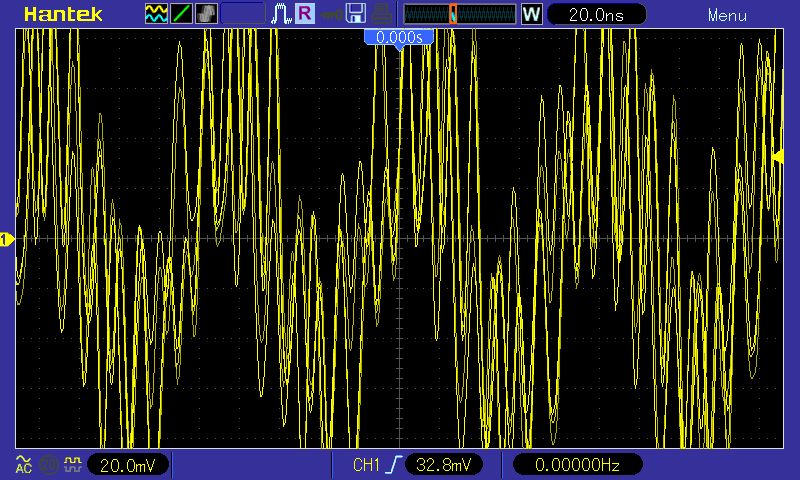 �Z���~�b�N�t�B���^�[�ł͑傫�Ȕg�`���o��B(���F�^�C���X�P�[���͈Ⴄ)
���u���Ă����A���g����������ƃY���Ă�̂��ȁH
�ǂ���ׂ����g�ł��Ă�̂́A���[�U�[���������č����g�������̂����m��Ȃ��B
LED�œ����Ηǂ������͕̂������Ă��邪�A���́A���Ԃ��ɂ����悤�ȏ�ԁB
�����I�ɂ́A5�{�ʂȂ̂ŁA�A�r�[�g�A�b�v�̘R�ꂩ���m��Ȃ��B
�ӊO�Ȃ̂́A�����t�B���^�[�̕����A�������������Ƃł��B
����������ƁA�}3.75K����Ȃ����ā}37.5�Ƃ����ᖳ�����낤���H�Ǝv���Ă��܂��B
�i�Ԃ݂�ƁA7.5�Ə����Ă���̂ŁA�{3.75K�|3.75K��BW=7.5K�ŁA�Ƃ������Ƃ̂悤�ł��ˁB
�}���āA�ꍇ�ɂ���āA�Е��̕���������A�S�̂̕��������肷��̂ŁA����킵���R�g���̏�Ȃ��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�����I�V���w���B
�Z���~�b�N�t�B���^�[�ł͑傫�Ȕg�`���o��B(���F�^�C���X�P�[���͈Ⴄ)
���u���Ă����A���g����������ƃY���Ă�̂��ȁH
�ǂ���ׂ����g�ł��Ă�̂́A���[�U�[���������č����g�������̂����m��Ȃ��B
LED�œ����Ηǂ������͕̂������Ă��邪�A���́A���Ԃ��ɂ����悤�ȏ�ԁB
�����I�ɂ́A5�{�ʂȂ̂ŁA�A�r�[�g�A�b�v�̘R�ꂩ���m��Ȃ��B
�ӊO�Ȃ̂́A�����t�B���^�[�̕����A�������������Ƃł��B
����������ƁA�}3.75K����Ȃ����ā}37.5�Ƃ����ᖳ�����낤���H�Ǝv���Ă��܂��B
�i�Ԃ݂�ƁA7.5�Ə����Ă���̂ŁA�{3.75K�|3.75K��BW=7.5K�ŁA�Ƃ������Ƃ̂悤�ł��ˁB
�}���āA�ꍇ�ɂ���āA�Е��̕���������A�S�̂̕��������肷��̂ŁA����킵���R�g���̏�Ȃ��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�����I�V���w���B
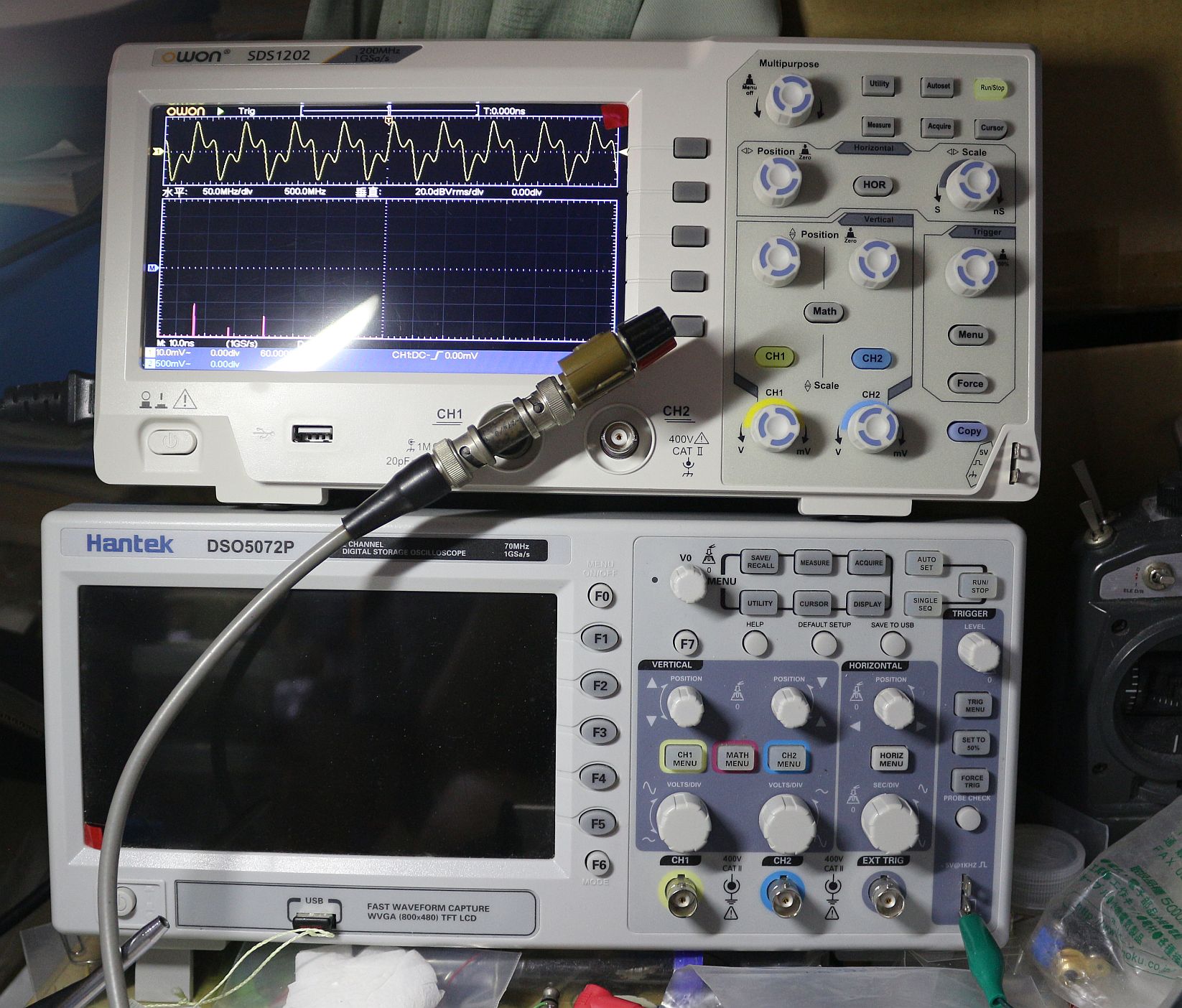 �����d���̃����W�������������ǁA
���X�|���X�͂��Ȃ�ǂ��B
1GS/Sec�ŁA�g�`��200MHz�AFFT��500MHz�܂ő����B
���̂�₤�`�Ŏg�������B
MEMS���U��̓V���R���̐U���炵���B
60MHz�̔��U��́A�����g���ƂĂ�����400MHz�ȏ�����邱�Ƃ����������B
�܂��A�̎�ނƂ��������ݐݒ肪�C���C���A���̂ŏo�Ȃ����₩�Ȃ̂�����c�A�A
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
��͊�����̂ɁA
���ߌ��e���K�v�Ȃ̂�
�����N���u�ŃN���A�V�[���ŁA
���G�����\�t�g�Ńp�^�[�����������B
�����d���̃����W�������������ǁA
���X�|���X�͂��Ȃ�ǂ��B
1GS/Sec�ŁA�g�`��200MHz�AFFT��500MHz�܂ő����B
���̂�₤�`�Ŏg�������B
MEMS���U��̓V���R���̐U���炵���B
60MHz�̔��U��́A�����g���ƂĂ�����400MHz�ȏ�����邱�Ƃ����������B
�܂��A�̎�ނƂ��������ݐݒ肪�C���C���A���̂ŏo�Ȃ����₩�Ȃ̂�����c�A�A
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
��͊�����̂ɁA
���ߌ��e���K�v�Ȃ̂�
�����N���u�ŃN���A�V�[���ŁA
���G�����\�t�g�Ńp�^�[�����������B
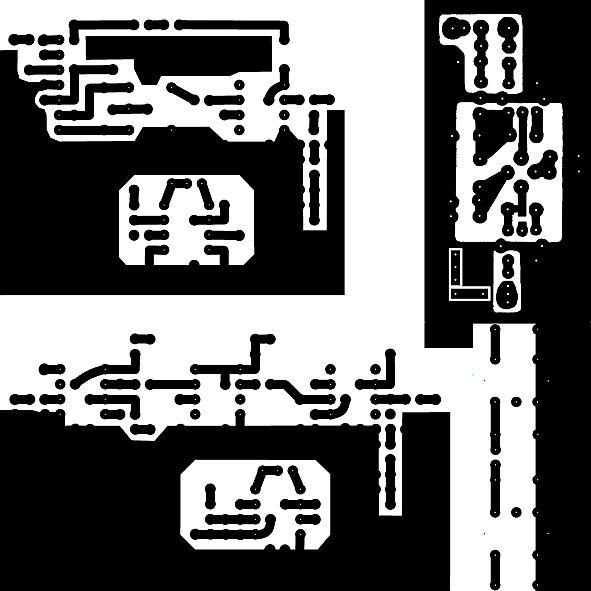 �����̌�Ǝ҂ɔ����̘b������A
CADLUS X
CADLUS PCB
����ꂽ�B
TA7124P�Ƃ�FCZ�R�C���̕��i�}�ʂ͍��Ȃ���Ȃ�Ȃ����A
�K���Ɋۈ�����������B
�����̌�Ǝ҂ɔ����̘b������A
CADLUS X
CADLUS PCB
����ꂽ�B
TA7124P�Ƃ�FCZ�R�C���̕��i�}�ʂ͍��Ȃ���Ȃ�Ȃ����A
�K���Ɋۈ�����������B
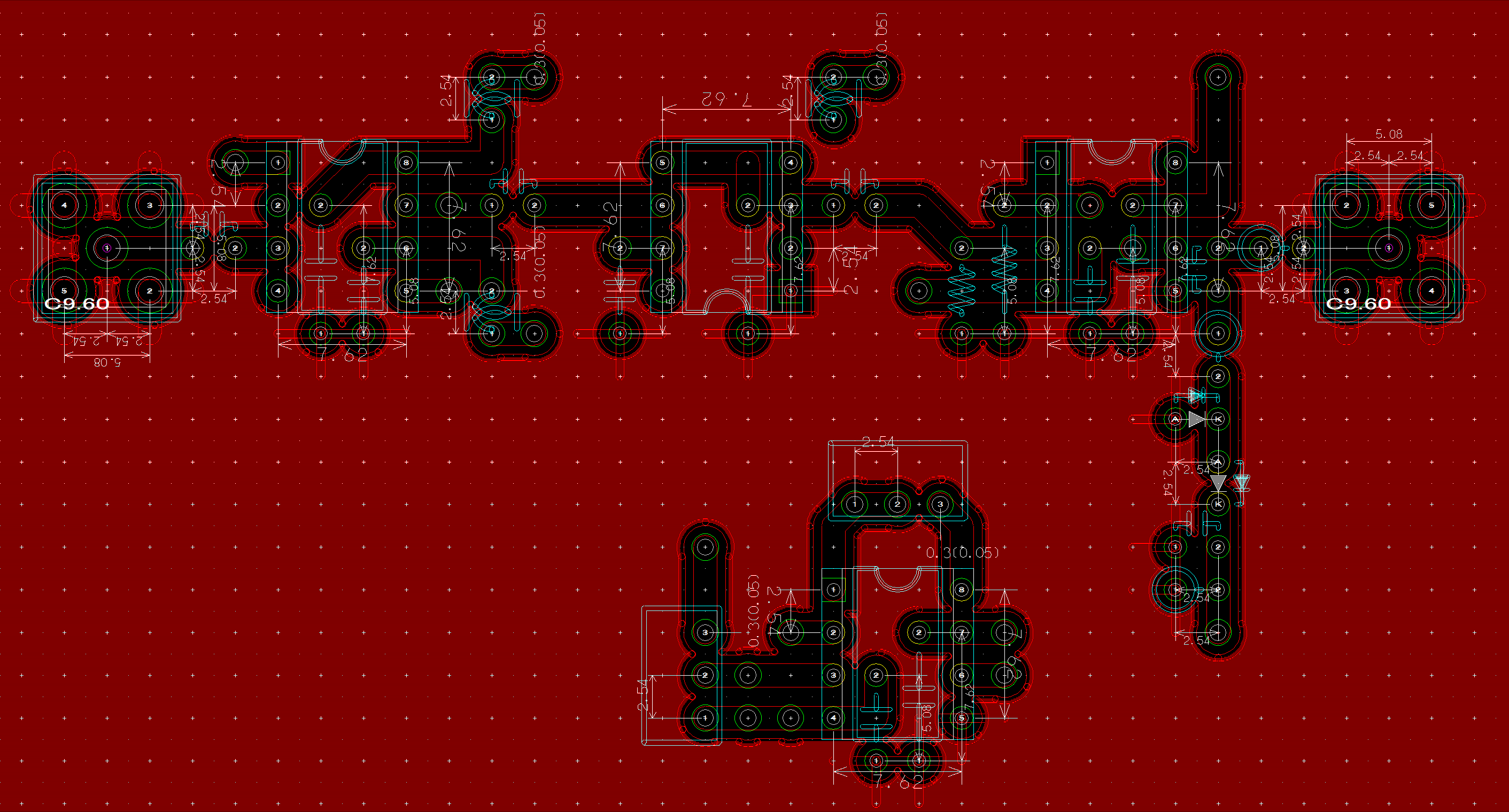 A��B�ʁA���i�ʁA�n���_�ʁA�\�ʁA���ʂ�����킵�������B
�V�~�����[�^�[�Ȃǂʼn�H�}�������ĂȂ��̂�
�l�b�g��\�z�o���Ȃ����߁A�ׂ�GND�͔������ŁA�[�q����h�Ƃ̐ڑ��̓T�[�}�����[�t�Ƃ��Ď蓮�ŁB
��p�t�H�[�}�b�g�Ȃ̂ŁA����̍�����PCB�Ǝ҂ƂȂ�B
�K�[�o�[�f�[�^���o���鐻�i�ł�50�����z����B
DesignSpark��KiCad���g���Č��悤�Ǝv�������A�ɂ킩�ɂ́A�A�A
�L���Ȃ�Autodesk��Eagle���ǂ������H
���z��Spice�n�̃\�t�g�ƘA�g���o����c�A�A
�ŏI�I�ɁA�T���n���g����C���N�W�F�b�g�ō��t�B�����������Ă����̂ŁA������g�����ƁB
�ŁACADLUS����ς��[��͂����Ȃ��̂�
B�ʃp�^�[����B�ʎ����x�^�̂ݕ\�������āA
��ʂ̂�����[����L���v�`�����āA���ۂ̃T�C�Y�։𑜓x����ύX���āA���G�����c�[�����Y��ɂ��Ă����܂����B
A��B�ʁA���i�ʁA�n���_�ʁA�\�ʁA���ʂ�����킵�������B
�V�~�����[�^�[�Ȃǂʼn�H�}�������ĂȂ��̂�
�l�b�g��\�z�o���Ȃ����߁A�ׂ�GND�͔������ŁA�[�q����h�Ƃ̐ڑ��̓T�[�}�����[�t�Ƃ��Ď蓮�ŁB
��p�t�H�[�}�b�g�Ȃ̂ŁA����̍�����PCB�Ǝ҂ƂȂ�B
�K�[�o�[�f�[�^���o���鐻�i�ł�50�����z����B
DesignSpark��KiCad���g���Č��悤�Ǝv�������A�ɂ킩�ɂ́A�A�A
�L���Ȃ�Autodesk��Eagle���ǂ������H
���z��Spice�n�̃\�t�g�ƘA�g���o����c�A�A
�ŏI�I�ɁA�T���n���g����C���N�W�F�b�g�ō��t�B�����������Ă����̂ŁA������g�����ƁB
�ŁACADLUS����ς��[��͂����Ȃ��̂�
B�ʃp�^�[����B�ʎ����x�^�̂ݕ\�������āA
��ʂ̂�����[����L���v�`�����āA���ۂ̃T�C�Y�։𑜓x����ύX���āA���G�����c�[�����Y��ɂ��Ă����܂����B
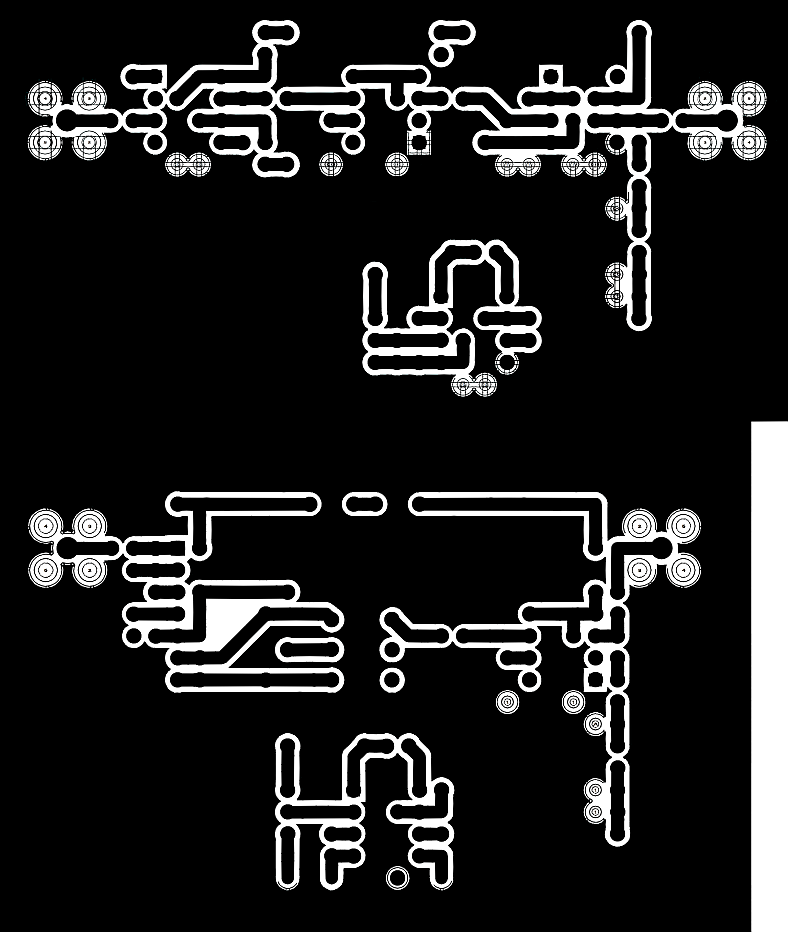 ���Ƃ́A�x�^GND�Ɣz����GND���q���̂ɗǂ����@�͖������ȁH
�t�H�g���W�X�g�Ŏ��F���̗ǂ�������
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���m�͂���Ȋ����ł��B
A4�T�C�Y�ł��B
���Ƃ́A�x�^GND�Ɣz����GND���q���̂ɗǂ����@�͖������ȁH
�t�H�g���W�X�g�Ŏ��F���̗ǂ�������
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���m�͂���Ȋ����ł��B
A4�T�C�Y�ł��B
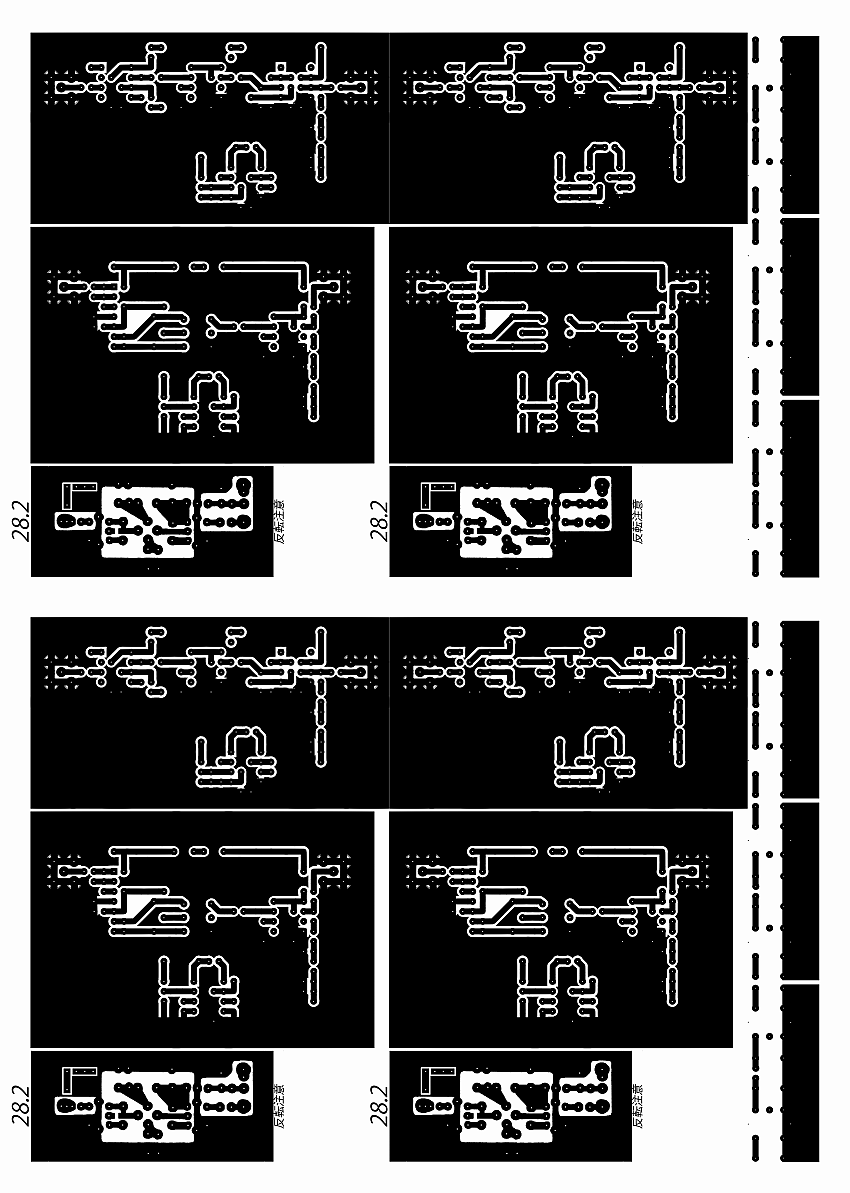 �����N���u�ɔ������悤���Ǝv���Ă܂��B
������̂̓��[�U�[�v�����^�Ȃ̂ł����A
���������A
�w�������OHP�ƃ��[�U�[�v�����^�ł���Đ��������̂ł����A��������Ȃȉ�H�Ń��X�N�����Ȃ������ł��B
�����Ƀ��[�U�[�v�����^�[�Ƀg���[�V���O�y�[�p�[�����Č�����ᰂ��o�邵�A���߂����\����̂Ń{�c�B
���[�U�[�p��OHP�����邯�ǁA����ρA���\���߂��邾�낤����A�A
����������I�o�����m�ɕ�����A�����A����ł��ǂ��̂����ǁc�A
Amazon�Œ��ׂ�ƁA
�T���n���g�̂ł͖����A������ɂ̓C���N�W�F�b�g�pOHP�V�[�g��OK�݂����Ȃ̂����邯�ǁA���[�U�[�p�͂Ȃ��B�B
���[�U�[�p���ƃR�N���̂��g�i�[�̒蒅���ǂ��Ă����݂����ł��ˁB
�Ƃ肠�����A�����̂ŁA�����N���u�̃N���A�V�[���̂����܂��s���Ȃ������Ƃ����l���āA�����͂��Ă݂܂����B
�V���[�v�ɏo���ɂ́A�G�b�`���O�t�̉��x���グ��Ɨǂ��炵���ł��ˁB
���������A�摜�����ŁA���߂ɂ���A�N�V�������g���܂����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220411
���[�U�[�v�����^�[��OHP�ɏo���Ă݂�����ǁA���Ȃ蓧�߂��ĂĂ��܂��낵���Ȃ��B
�▭�̘I�����s���Ζ��͖������낤���ǁA�Ȃ��Ȃ��ɓ���B
����āA�����N���u�ɃN���A�V�[���Ƃ��ē��e���Ă݂��B
����ȃt�H�g�_�C�I�[�h�ւ̋t�o�C�A�X��700�`1000mV�Ƃ������ƂŁA
�d���ƒ�R�l������Ȃ��̂ŁA�d��������Ȃ��B���ꂪ���݂���Ƃ��ɍs���̂���ςƌ������ƂŁA
Di�̏������d���ōs���R�g�ɁA
1.5V�d�r��Di3��22��H�ō����g���X�g�b�v�B
�����N���u�ɔ������悤���Ǝv���Ă܂��B
������̂̓��[�U�[�v�����^�Ȃ̂ł����A
���������A
�w�������OHP�ƃ��[�U�[�v�����^�ł���Đ��������̂ł����A��������Ȃȉ�H�Ń��X�N�����Ȃ������ł��B
�����Ƀ��[�U�[�v�����^�[�Ƀg���[�V���O�y�[�p�[�����Č�����ᰂ��o�邵�A���߂����\����̂Ń{�c�B
���[�U�[�p��OHP�����邯�ǁA����ρA���\���߂��邾�낤����A�A
����������I�o�����m�ɕ�����A�����A����ł��ǂ��̂����ǁc�A
Amazon�Œ��ׂ�ƁA
�T���n���g�̂ł͖����A������ɂ̓C���N�W�F�b�g�pOHP�V�[�g��OK�݂����Ȃ̂����邯�ǁA���[�U�[�p�͂Ȃ��B�B
���[�U�[�p���ƃR�N���̂��g�i�[�̒蒅���ǂ��Ă����݂����ł��ˁB
�Ƃ肠�����A�����̂ŁA�����N���u�̃N���A�V�[���̂����܂��s���Ȃ������Ƃ����l���āA�����͂��Ă݂܂����B
�V���[�v�ɏo���ɂ́A�G�b�`���O�t�̉��x���グ��Ɨǂ��炵���ł��ˁB
���������A�摜�����ŁA���߂ɂ���A�N�V�������g���܂����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220411
���[�U�[�v�����^�[��OHP�ɏo���Ă݂�����ǁA���Ȃ蓧�߂��ĂĂ��܂��낵���Ȃ��B
�▭�̘I�����s���Ζ��͖������낤���ǁA�Ȃ��Ȃ��ɓ���B
����āA�����N���u�ɃN���A�V�[���Ƃ��ē��e���Ă݂��B
����ȃt�H�g�_�C�I�[�h�ւ̋t�o�C�A�X��700�`1000mV�Ƃ������ƂŁA
�d���ƒ�R�l������Ȃ��̂ŁA�d��������Ȃ��B���ꂪ���݂���Ƃ��ɍs���̂���ςƌ������ƂŁA
Di�̏������d���ōs���R�g�ɁA
1.5V�d�r��Di3��22��H�ō����g���X�g�b�v�B
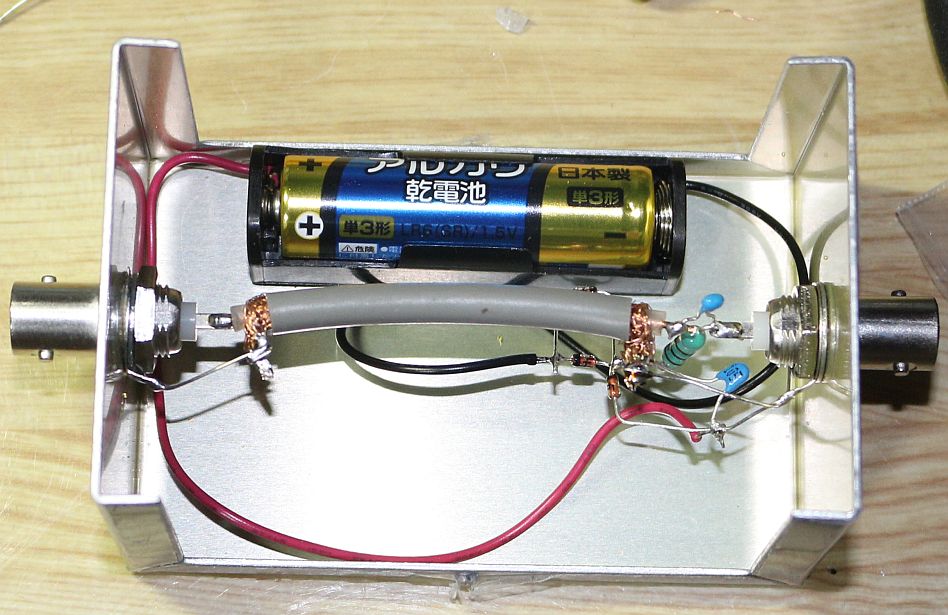 (����ʐς���30mA���x�͗���邩���m��Ȃ��Ɣ��f���Ă��邪�A
�t�H�g�_�C�I�[�h�̒�R���Ⴉ�����ꍇ���l���āA�Е���2�t���Ă���B�ꍇ�ɂ���ẮAGND�ɐڑ����Ă�Di���J�b�g���Ă�OK�������B)
�NjL��
�V���b�g�L�o���ADi�ƃX�C�b�`���ODi��g�ݍ��킹�邱�Ƃɂ��A��H���̂̏���d����25�`30mA��1.9mA�ɉ����邱�Ƃɐ����B
�����ׂ�1000mV�M���M���z���Ȃ��B50�����x��850mV�Ă��ǁB�]�T�������Ă�낵���Ǝv�����ʂƂȂ����B
�ŁAPre-AMP�̂����DC�X���[���s��Ȃ���Ȃ�Ȃ����ǁA����́A���o�͂��Ȃ��R�g�ɂȂ�̂ŁA22��H�ł͘R��ĉe������B
����āA22��H��C��GND�ɗ��Ƃ���22��H�Ƃ���T�^��LPF�̂悤�ɂȂ����B
(����ʐς���30mA���x�͗���邩���m��Ȃ��Ɣ��f���Ă��邪�A
�t�H�g�_�C�I�[�h�̒�R���Ⴉ�����ꍇ���l���āA�Е���2�t���Ă���B�ꍇ�ɂ���ẮAGND�ɐڑ����Ă�Di���J�b�g���Ă�OK�������B)
�NjL��
�V���b�g�L�o���ADi�ƃX�C�b�`���ODi��g�ݍ��킹�邱�Ƃɂ��A��H���̂̏���d����25�`30mA��1.9mA�ɉ����邱�Ƃɐ����B
�����ׂ�1000mV�M���M���z���Ȃ��B50�����x��850mV�Ă��ǁB�]�T�������Ă�낵���Ǝv�����ʂƂȂ����B
�ŁAPre-AMP�̂����DC�X���[���s��Ȃ���Ȃ�Ȃ����ǁA����́A���o�͂��Ȃ��R�g�ɂȂ�̂ŁA22��H�ł͘R��ĉe������B
����āA22��H��C��GND�ɗ��Ƃ���22��H�Ƃ���T�^��LPF�̂悤�ɂȂ����B
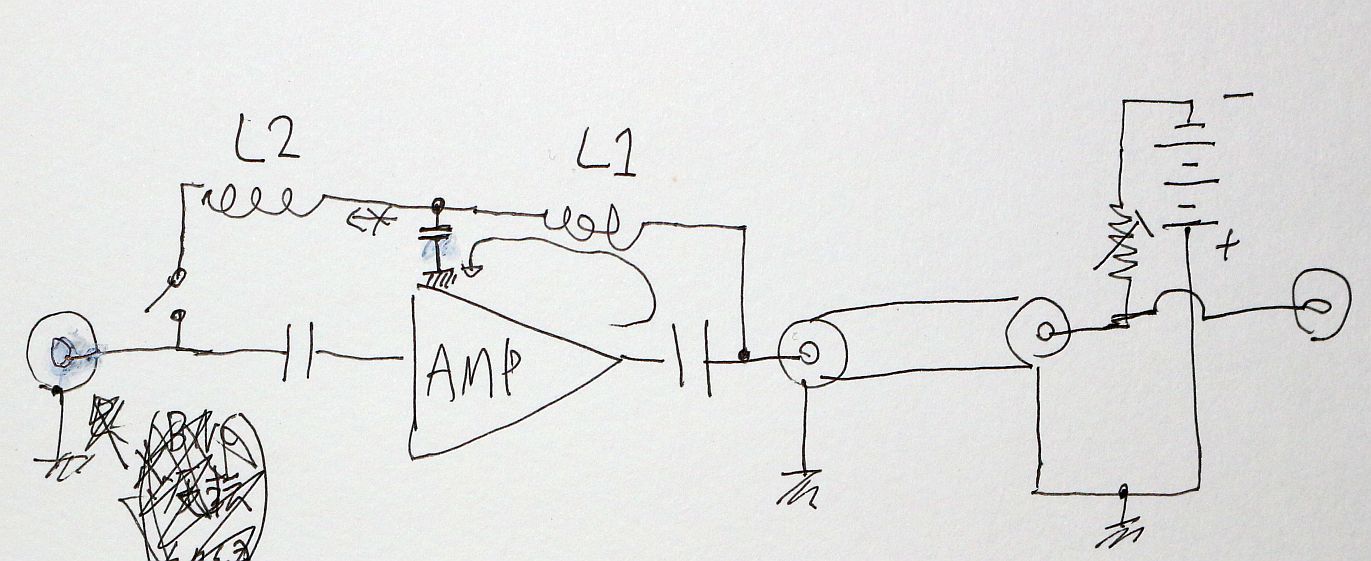 �܂��AL�͑傫���ƕ��V�e��(�e��)�ō����g��ʂ����A�ꍇ�ɂ���ẮA���ȋ��U���g���ɓ������Ă��܂��Ă��}�Y���B
��r�I�R���p�N�g�Ȃ̂����ȋ��U���g���͍����Ȃ��Ă�悤�Ȃ̂ŁA���������Ă��̒l�ł���B
Pre-AMP��80MHzFCZ�R�C����60MHz�����p�ɂ���R���f���T�[���Œ�l�Ɍ��߂܂���
�ȑO�A���_�l��12pF�ł�����g�p���Ă��̂ł����A
�O�����g���}�[�́A��͂�A�ق�12pF�ł����B
�����A�]�T���������邽�߁A����́A15pF�ɂ��Ă݂܂����B
�R�A�͌��\�˂����݂܂����A�������̕��R�C�����ɒ����̗]�T���c��A�ǂ����Ǝv���܂����B
�h���C����Q�[�g�ɗe�ʂ�����ꍇ�͂�������������������ǂ����Ƃ͗ǂ��ł��ˁB
��������20dB�s�����ǂ����Ƃ��������ŁA���X�オ���������ł��B
�����AGND���C�����V�r�A�ŁA���͂�GND����������A�P�[�X���Ɉ������������肷��Ƃ�����̌��ʂł��B
�܂��A���X�̎��������j�o�[�T����Ȃ̂ł����������ƂɂȂ�̂����m��܂���B
�t�^�̊J���߂��e�����܂��B�B
�G�b�`���O�t200cc�̓o�b�g�ɓ����ƗʓI�Ɍ������Ǝv���lj��B
Amazon�̉�ޗp�����Ȃ�����l�i�ł����̂ł�����g���R�g�ɁB
���������i���݂̒l�i�Ȃ̂ŁA2�{�܂Ƃ߂čw�����܂����B
�p�t�����͏��ΊD�B�����͊�߂��Ē��a���ȊO�͉��������ł��ǂ��Ƃ��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
������̖��B
����A���GND�ɓ���BNC��GND���q���Ƃ�낵���Ȃ��U�����o���B(�o�͂�BNC���U�����ቺ�����B)
���͂͌����Ȃ̂ŁA�����Ȃ��Ƃ��������B�����N�V�^�ɂȂ��Ă�̂����邯�ǁAFCZ�R�C����O�Ȃ̂ł�����e���������n�Y�B
FCZ�R�C���Ɠ����p�R���f���T�[�͂ł��邾���Z�����Œ�C���s�[�_���X�Ō��ԕK�v������B
���R�́A���x���Ԃœd�ׂ����Ƃ肷�邩�炾�B
����́A�Œ�R���f���T�[�̔w�ʒ��t���ŁA�R�A����������ފ����ɂȂ��ĂāA���U�����P���ꂽ�C������B
����ŁA�n�C�C���s�[�_���X�����m��Ȃ��A�t�H�g�_�C�I�[�h������ꍇ�A�ǂ��Ȃ�̂��͖��m���B
�܂��A
�uPre-AMP�̓��͂��P�[�XGND����Ĉ����ƌ��ʂ��ǂ��̂��s�v�c�B�v
�݂����Ȃ��Ƃ������Ă����̂ł����A
GND�ڑ�SW��ʂ��Ȃ�����A�P�[�X�Ɗ���q�����Ă͂��Ȃ������̂ŁA���͂�GND���≏����ĂāA
FCZ�R�C���̃g�����X����āA�M���݂̂��`�B����Ă��B
������̕����A�m�C�Y����炸�A�ǂ��Ƃ������ʂł������B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220418
�����N���u����̃N���A�V�[���������B
�𑜓x�͏\���B�����ǁA�\�z�������傢���߂���B
�܂��AL�͑傫���ƕ��V�e��(�e��)�ō����g��ʂ����A�ꍇ�ɂ���ẮA���ȋ��U���g���ɓ������Ă��܂��Ă��}�Y���B
��r�I�R���p�N�g�Ȃ̂����ȋ��U���g���͍����Ȃ��Ă�悤�Ȃ̂ŁA���������Ă��̒l�ł���B
Pre-AMP��80MHzFCZ�R�C����60MHz�����p�ɂ���R���f���T�[���Œ�l�Ɍ��߂܂���
�ȑO�A���_�l��12pF�ł�����g�p���Ă��̂ł����A
�O�����g���}�[�́A��͂�A�ق�12pF�ł����B
�����A�]�T���������邽�߁A����́A15pF�ɂ��Ă݂܂����B
�R�A�͌��\�˂����݂܂����A�������̕��R�C�����ɒ����̗]�T���c��A�ǂ����Ǝv���܂����B
�h���C����Q�[�g�ɗe�ʂ�����ꍇ�͂�������������������ǂ����Ƃ͗ǂ��ł��ˁB
��������20dB�s�����ǂ����Ƃ��������ŁA���X�オ���������ł��B
�����AGND���C�����V�r�A�ŁA���͂�GND����������A�P�[�X���Ɉ������������肷��Ƃ�����̌��ʂł��B
�܂��A���X�̎��������j�o�[�T����Ȃ̂ł����������ƂɂȂ�̂����m��܂���B
�t�^�̊J���߂��e�����܂��B�B
�G�b�`���O�t200cc�̓o�b�g�ɓ����ƗʓI�Ɍ������Ǝv���lj��B
Amazon�̉�ޗp�����Ȃ�����l�i�ł����̂ł�����g���R�g�ɁB
���������i���݂̒l�i�Ȃ̂ŁA2�{�܂Ƃ߂čw�����܂����B
�p�t�����͏��ΊD�B�����͊�߂��Ē��a���ȊO�͉��������ł��ǂ��Ƃ��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
������̖��B
����A���GND�ɓ���BNC��GND���q���Ƃ�낵���Ȃ��U�����o���B(�o�͂�BNC���U�����ቺ�����B)
���͂͌����Ȃ̂ŁA�����Ȃ��Ƃ��������B�����N�V�^�ɂȂ��Ă�̂����邯�ǁAFCZ�R�C����O�Ȃ̂ł�����e���������n�Y�B
FCZ�R�C���Ɠ����p�R���f���T�[�͂ł��邾���Z�����Œ�C���s�[�_���X�Ō��ԕK�v������B
���R�́A���x���Ԃœd�ׂ����Ƃ肷�邩�炾�B
����́A�Œ�R���f���T�[�̔w�ʒ��t���ŁA�R�A����������ފ����ɂȂ��ĂāA���U�����P���ꂽ�C������B
����ŁA�n�C�C���s�[�_���X�����m��Ȃ��A�t�H�g�_�C�I�[�h������ꍇ�A�ǂ��Ȃ�̂��͖��m���B
�܂��A
�uPre-AMP�̓��͂��P�[�XGND����Ĉ����ƌ��ʂ��ǂ��̂��s�v�c�B�v
�݂����Ȃ��Ƃ������Ă����̂ł����A
GND�ڑ�SW��ʂ��Ȃ�����A�P�[�X�Ɗ���q�����Ă͂��Ȃ������̂ŁA���͂�GND���≏����ĂāA
FCZ�R�C���̃g�����X����āA�M���݂̂��`�B����Ă��B
������̕����A�m�C�Y����炸�A�ǂ��Ƃ������ʂł������B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220418
�����N���u����̃N���A�V�[���������B
�𑜓x�͏\���B�����ǁA�\�z�������傢���߂���B
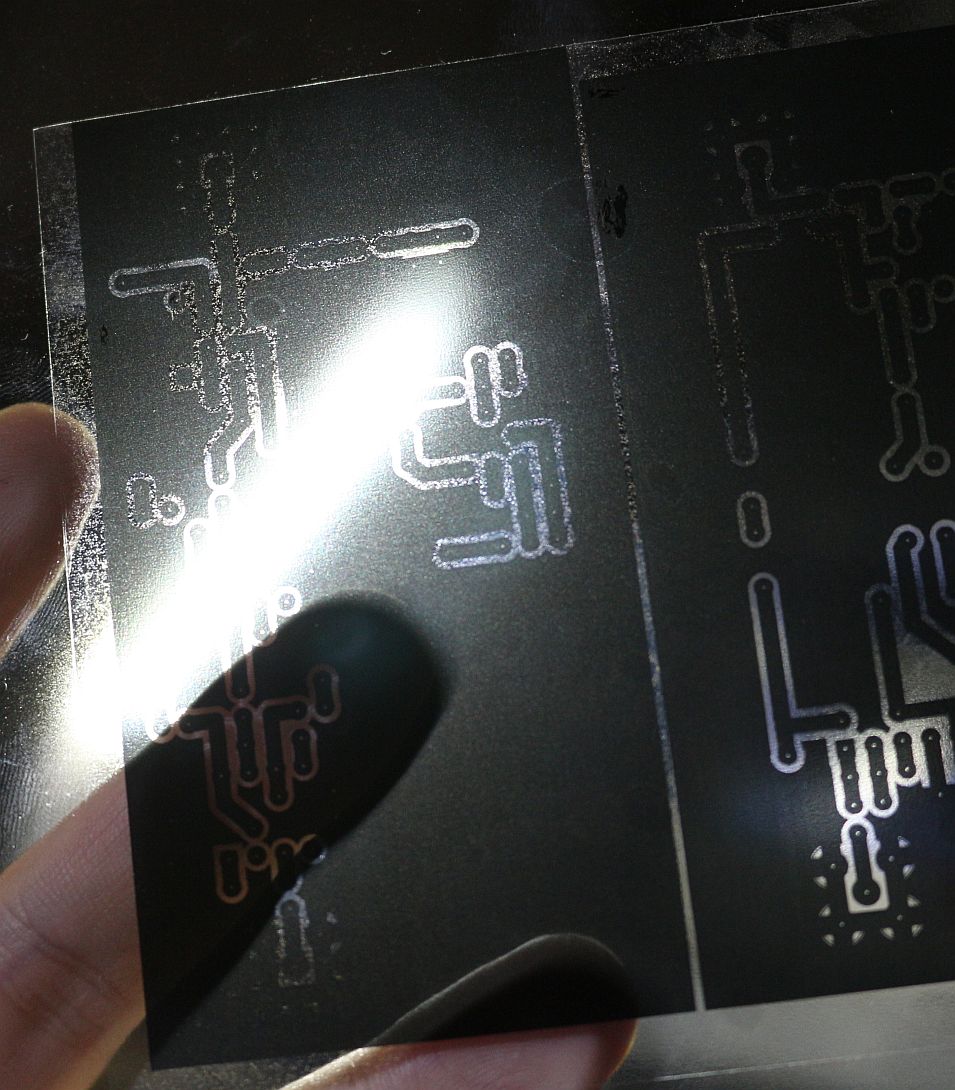 �����A�C���N�W�F�b�g�Ɠ������炢�����m��Ȃ��B
�����A�ׂ����h�b�g�̔Z�W������̂ŁA�g�U���Ă������ǂ�����������B
��H�́A���x�����ǂ���\��Ȃ̂ŁA
���́A�N���A�t�@�C�����ǂ������m��Ȃ��B
�V�[���̑䎆�����Ȃ̂ŁA�K���X�ɓ\��K�v�����邯�ǁA�������₷���悤�A�E�B���h�R�[�g�܂łǂ��ɂ��c�A
�ŁA�z���g�́A���n�ɃV�[���̃m���ɁA������ܐ��H�����������X�v���[�������āA�ʒu���߂�A�C�A���������₷������Ɨǂ��̂����ǁA
���̂܂܈�C�ɂ���Ă��܂����B�ʒu�͂��������A�C�A���������B������x����������ǂ��Ƃ��悤�B
6������ԓ������������Ƃ��v����̂ŁA4�����̓V�r�A�Ɏv���B
�̂̊�����́A�F���ς��̂ŁA���������ڈ����t�������ǁA
�ŋ߂͓̂��肪�ς��Ȃ��̂ŁA���m�ł��ˁB
1��15�b����1��30�b���x�ɂ��Ă݂悤�B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
60MHz��AMP�o�͂�BNC��GND��≏����ƁA��mV�̑����m�C�Y���o��̂ł����A
�����A�C���N�W�F�b�g�Ɠ������炢�����m��Ȃ��B
�����A�ׂ����h�b�g�̔Z�W������̂ŁA�g�U���Ă������ǂ�����������B
��H�́A���x�����ǂ���\��Ȃ̂ŁA
���́A�N���A�t�@�C�����ǂ������m��Ȃ��B
�V�[���̑䎆�����Ȃ̂ŁA�K���X�ɓ\��K�v�����邯�ǁA�������₷���悤�A�E�B���h�R�[�g�܂łǂ��ɂ��c�A
�ŁA�z���g�́A���n�ɃV�[���̃m���ɁA������ܐ��H�����������X�v���[�������āA�ʒu���߂�A�C�A���������₷������Ɨǂ��̂����ǁA
���̂܂܈�C�ɂ���Ă��܂����B�ʒu�͂��������A�C�A���������B������x����������ǂ��Ƃ��悤�B
6������ԓ������������Ƃ��v����̂ŁA4�����̓V�r�A�Ɏv���B
�̂̊�����́A�F���ς��̂ŁA���������ڈ����t�������ǁA
�ŋ߂͓̂��肪�ς��Ȃ��̂ŁA���m�ł��ˁB
1��15�b����1��30�b���x�ɂ��Ă݂悤�B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
60MHz��AMP�o�͂�BNC��GND��≏����ƁA��mV�̑����m�C�Y���o��̂ł����A
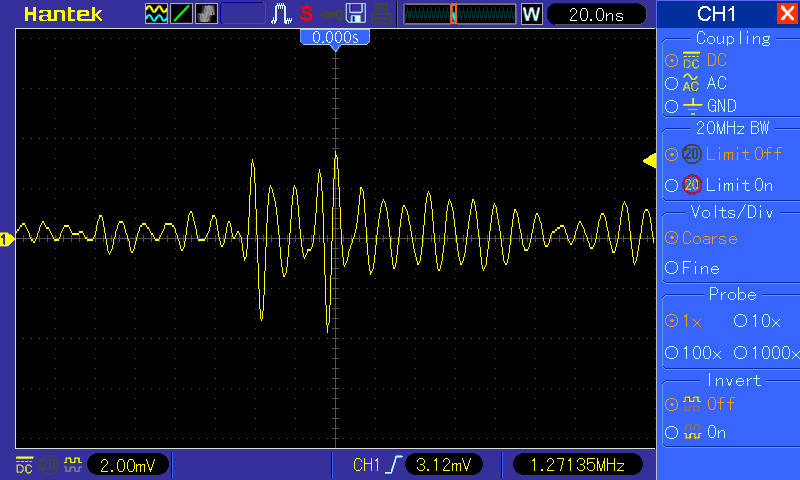 ���ꂪ�A�d�������Ȃ��Ă��o�邱�Ƃ������B
���̏H����120�~�̐≏�R�l�N�^�[��L���ɂ���Ə\��nSec�̃X�p�C�N�m�C�Y�̂悤�ȃ��m�������I�ɗ�N����Ă���B
�I�V����ς��Ă��o�邵�c�A
�����ɃR�l�N�^�����ɂ��āA����ɐڑ�������A����ł��o�Ă���c�B
�����A�R�l�N�^�̐≏��(�e�t�������ۂ�)�̗U�d���Ƃ��̌������̐��@�Ƃ������������m��Ȃ��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
AGC�Ȃ�AMP�ł����A
�f�[�^�V�[�g��LowNoise�Ə����Ă���Ȃ���ANF���ǂ������̂ŁA���i�Ɏg���R�g������邱�Ƃɂ��܂����B
���̂��߁A��H���C�A�E�g���啝�ɕς��̂ŁA�v�̂�蒼���ł��ˁB
�o�����CAD�́uEagle�v�ł���Ă݂܂��B
��������A�K�[�o�[�f�[�^�ƂȂ�A��͊C�O�Ɉ��������o���邩���m��܂���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220419
�ŁA�Ⴄ�^�C�v��AGC-AMP������ł��B
�v���̊���������������邱�Ƃɂ����B
�ŏ��ɈÈłŊ��P�J�b�^�[�Őؒf�B
�t�B�����J�����̐���Ɠ܂�y�ѓ��A��LUX�l���ׂ邩�A
�������ˌ����I�o�v�𒍕����Ă݂����A�ŋ߂̂�LUX���W���݂����B
�����́ALm/�u��
W/�u�̒P�ʂɔ�Ⴗ��Ǝv����B
�ƂȂ�ƁALUX��1/4�ɂȂ�A�I������(��)��4�{�ŗǂ��̂��ȁH
Lm�̎���������Ȃ����A�����̂́A�ǂ���A���x(W=J/Sec�̂悤���B)
�܂��A����������j�A�ɔ�������Ƃ����ꍇ�B
�����́A���C�g�{�b�N�X(�g���[�X��)�ł��ǂ������B
�O�O���Ă݂�ɁA
OHP�Ƃ��͐H�������������߁A�����ĕ��ʎ��ɂ��l�����܂������A
���ʎ��Ȃ�A���܂܂Ŏ����ɏo�����ꍇ�A���[�U�[�̕����ǂ������̂悤�ł��ˁB�B
���ƁA���1�N�ȏ�ۊǂ�����A10�����x�I�����Ԃ�����Ƃ��B
�ŁA���H�B
���z���͎��߂āA
3W��LED���C�g��4�`5cm���x�̋����ŁA�����������Ȃ���A8��45�b�ł���Ă݂܂����B
�����A���ʕs���́A�������Ԃ̉����ƁA�����Ē�߂̉��x�̃G�b�`���O�t�ŁA
17���ʂ����������ŁA
�p�^�[���́A�N���ɏo�������ł��B
�t���b�N�X�̓h�胀���Ղ��c���Ă܂���
���ꂪ�A�d�������Ȃ��Ă��o�邱�Ƃ������B
���̏H����120�~�̐≏�R�l�N�^�[��L���ɂ���Ə\��nSec�̃X�p�C�N�m�C�Y�̂悤�ȃ��m�������I�ɗ�N����Ă���B
�I�V����ς��Ă��o�邵�c�A
�����ɃR�l�N�^�����ɂ��āA����ɐڑ�������A����ł��o�Ă���c�B
�����A�R�l�N�^�̐≏��(�e�t�������ۂ�)�̗U�d���Ƃ��̌������̐��@�Ƃ������������m��Ȃ��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
AGC�Ȃ�AMP�ł����A
�f�[�^�V�[�g��LowNoise�Ə����Ă���Ȃ���ANF���ǂ������̂ŁA���i�Ɏg���R�g������邱�Ƃɂ��܂����B
���̂��߁A��H���C�A�E�g���啝�ɕς��̂ŁA�v�̂�蒼���ł��ˁB
�o�����CAD�́uEagle�v�ł���Ă݂܂��B
��������A�K�[�o�[�f�[�^�ƂȂ�A��͊C�O�Ɉ��������o���邩���m��܂���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220419
�ŁA�Ⴄ�^�C�v��AGC-AMP������ł��B
�v���̊���������������邱�Ƃɂ����B
�ŏ��ɈÈłŊ��P�J�b�^�[�Őؒf�B
�t�B�����J�����̐���Ɠ܂�y�ѓ��A��LUX�l���ׂ邩�A
�������ˌ����I�o�v�𒍕����Ă݂����A�ŋ߂̂�LUX���W���݂����B
�����́ALm/�u��
W/�u�̒P�ʂɔ�Ⴗ��Ǝv����B
�ƂȂ�ƁALUX��1/4�ɂȂ�A�I������(��)��4�{�ŗǂ��̂��ȁH
Lm�̎���������Ȃ����A�����̂́A�ǂ���A���x(W=J/Sec�̂悤���B)
�܂��A����������j�A�ɔ�������Ƃ����ꍇ�B
�����́A���C�g�{�b�N�X(�g���[�X��)�ł��ǂ������B
�O�O���Ă݂�ɁA
OHP�Ƃ��͐H�������������߁A�����ĕ��ʎ��ɂ��l�����܂������A
���ʎ��Ȃ�A���܂܂Ŏ����ɏo�����ꍇ�A���[�U�[�̕����ǂ������̂悤�ł��ˁB�B
���ƁA���1�N�ȏ�ۊǂ�����A10�����x�I�����Ԃ�����Ƃ��B
�ŁA���H�B
���z���͎��߂āA
3W��LED���C�g��4�`5cm���x�̋����ŁA�����������Ȃ���A8��45�b�ł���Ă݂܂����B
�����A���ʕs���́A�������Ԃ̉����ƁA�����Ē�߂̉��x�̃G�b�`���O�t�ŁA
17���ʂ����������ŁA
�p�^�[���́A�N���ɏo�������ł��B
�t���b�N�X�̓h�胀���Ղ��c���Ă܂���
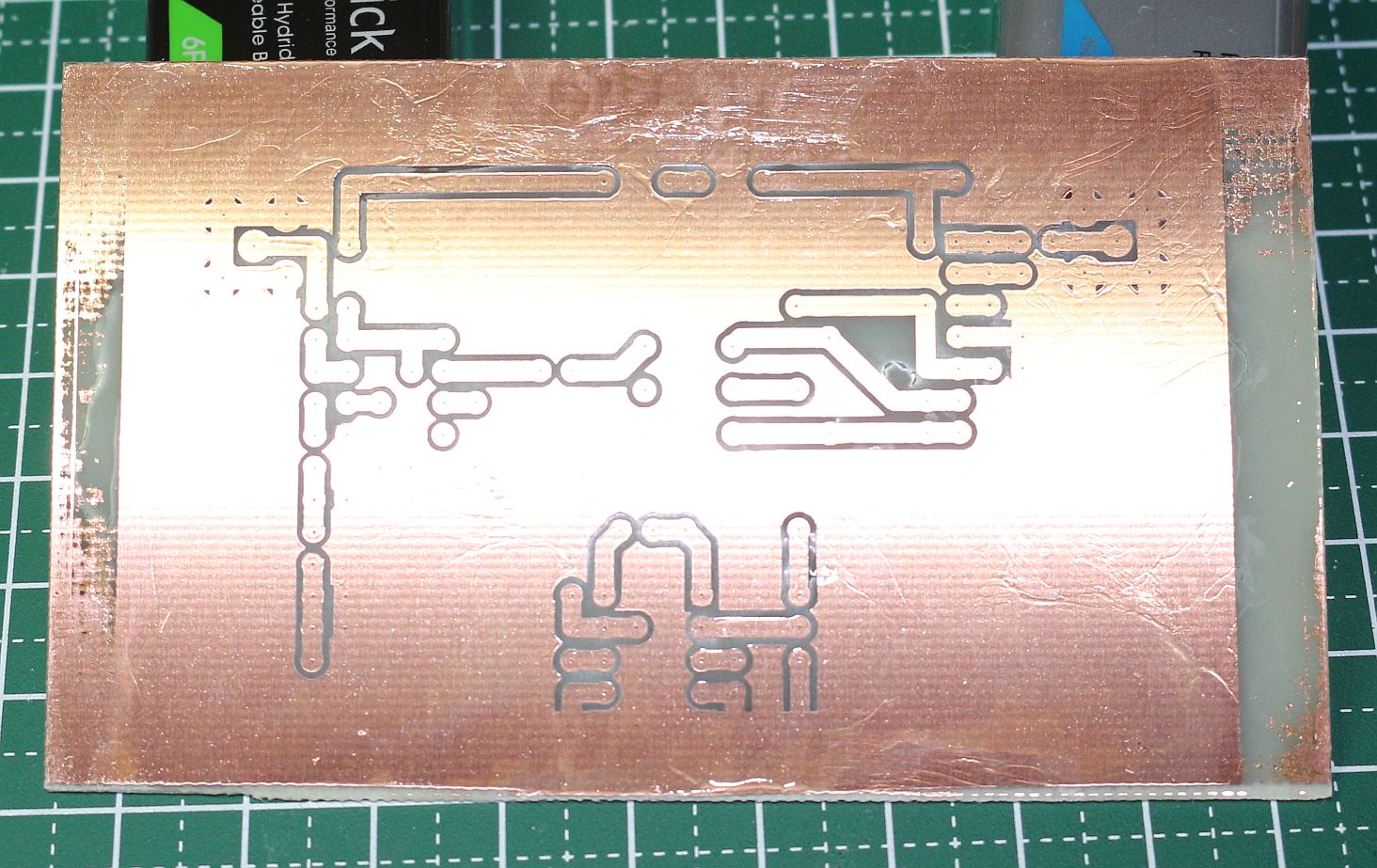 ���E�̌��ʕs���͊W�Ȃ��̂ł����A�܂��܂�����܂����B���M���M���B
�I���́A�I�[�o�[���́A�s�����ǂ��Ƃ����̂͑�̍����Ă�C������B
���Ƃ́A���J�����҂��Ă���B����ꂽ�̂ŁA����B
�V�^��A���ڂŐ������ėǂ������B
���x����肽����ƂƂ͎v���Ȃ����ǁA�A�A
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���G�����\�t�g�ŁA
�����h��70pt�A�z�[����8pt�̓�l�̃h�b�g��ł��Ă邽�߁A���ꂪ�Z���^���߂ɂƂĂ����������B
���߂����Ȃ���h�����n���Ă����ƁA�X�R���Ƃ��ڂ݂Ƀn�}�銴���ɂȂ�B
����ŁA��0.6mm�̃h�����ŊJ�������ɓ����a�Ǝv����IC�\�P�b�g��
��0.8mm�ŊJ�������́A�����Ǝv����10mm�p��FCZ�R�C�����L�b�`���ƃn�}��B
���E�̌��ʕs���͊W�Ȃ��̂ł����A�܂��܂�����܂����B���M���M���B
�I���́A�I�[�o�[���́A�s�����ǂ��Ƃ����̂͑�̍����Ă�C������B
���Ƃ́A���J�����҂��Ă���B����ꂽ�̂ŁA����B
�V�^��A���ڂŐ������ėǂ������B
���x����肽����ƂƂ͎v���Ȃ����ǁA�A�A
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���G�����\�t�g�ŁA
�����h��70pt�A�z�[����8pt�̓�l�̃h�b�g��ł��Ă邽�߁A���ꂪ�Z���^���߂ɂƂĂ����������B
���߂����Ȃ���h�����n���Ă����ƁA�X�R���Ƃ��ڂ݂Ƀn�}�銴���ɂȂ�B
����ŁA��0.6mm�̃h�����ŊJ�������ɓ����a�Ǝv����IC�\�P�b�g��
��0.8mm�ŊJ�������́A�����Ǝv����10mm�p��FCZ�R�C�����L�b�`���ƃn�}��B
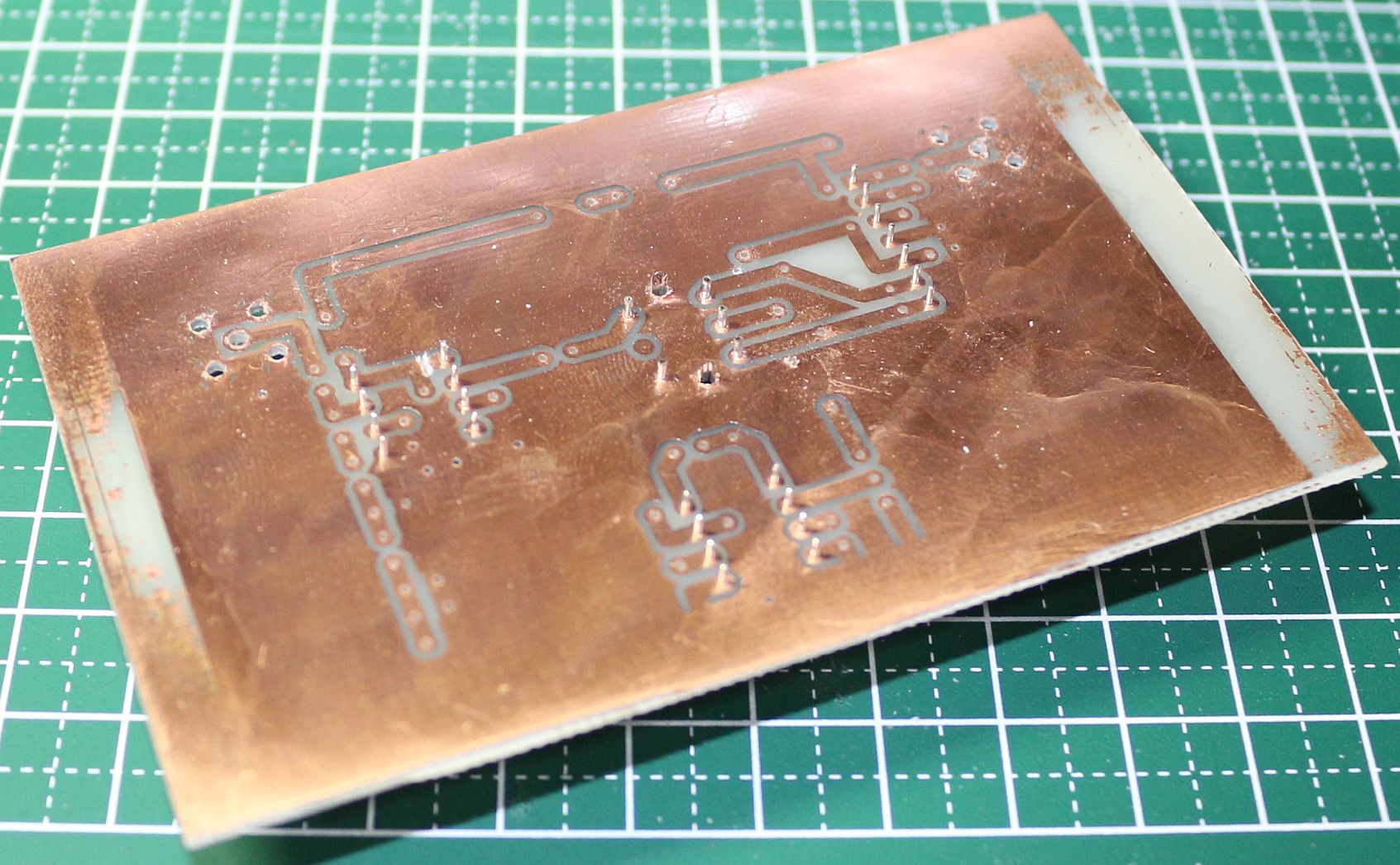 ���J����Ƃ́A��ς��������A�s�b�`�̐��x�ւ̕s���͞X�J�ɏI������B
������A�t���b�N�X�̓h��́A���M���Ȗ_�̕����ǂ������Ǝv���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�Ɠx�v�������̂ŁA�����Ă݂��B
�g����LED���C�g�X�^���h�́A4cm���炢�̋����ɂ���ƁA
�܂��A6500LUX���x�ŁA����ŁA10�������Ώ\�����낤�Ǝv���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���J����Ƃ́A��ς��������A�s�b�`�̐��x�ւ̕s���͞X�J�ɏI������B
������A�t���b�N�X�̓h��́A���M���Ȗ_�̕����ǂ������Ǝv���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�Ɠx�v�������̂ŁA�����Ă݂��B
�g����LED���C�g�X�^���h�́A4cm���炢�̋����ɂ���ƁA
�܂��A6500LUX���x�ŁA����ŁA10�������Ώ\�����낤�Ǝv���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
 �X�p�[�N���n���_�̕��������₷�������Ă���B���j�̈Ⴂ���ȁH
�����H�����̈Ⴂ��������B
�A���~�b�g�̂́A�S�肪�����炵���ł��B
�u�����h�ɒނ��Ĕ����Ă�l���������ǁA�p�r�ŕ����������ǂ��B
Goot�̂��ǂ��ƕ����B
�����n���_���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�V�^��2�^�C�v�̂�AGC-AMP���ł��������Ă����B
���R�ł͂��邯�ǁA�g���ĂȂ���H�Ƀ�PC1658C������������Ĕ���������B
�����͂��邯�ǏI�i�̃Q�C���Ƃ��Ă�����ƕ�����Ȃ��Ƃ���Řc�ނ̂ŁA
�X�C�b�`���ODi2����A�V���b�g�L�[�肠Di��֓d����������Əグ�āA
��PC1658C��2�ԃs���̃e�X�g���͂�180����GND�ƌq���A������H�̃G�~�b�^��R���������Ƃ���A1.8Vpp���x�̐U�����o��悤�ɂȂ����B
(���ƁA4�ԃs����5�ԃs�����q���ł������B�o�C�A�X��R���������Ĉ��肷��悤�ł���B)
�ŁA�����Ƒ����͏o����B�d�����͂ŃQ�C���R���g���[�����o���邱�Ƃ��m�F�����B
�܂�A����TA7124P�͌����̐V�i�������̂ŁA�U�������H
�Ǝv���Ă������{���̂悤�ł���B
FCZ�R�C���̓V�r�A�ł͖������A15pF���g������A���\���ɍs�����̂ŁA12pF�ŗǂ������B
�������AAGC��H�̕�����V���������ł������B
�\��̒P�d���̌v���A���vIC�́A�Ȃ��������͑��ɓd�ʂ��߂��Ă��ĂƂ������R��Ă��ă_���ł������B
�ƂȂ�ƁA
FET��CMOS���͂̒P�d��(12V�܂őς����郄�c)�Ƃ����̂������������߁A�Ƃ������Ђ����������B
�Ȃ����A���g���ȃm�[�}����OP-AMP�œ������B������A�P�d���Ŕ]������H�ɂ����B
�X�p�[�N���n���_�̕��������₷�������Ă���B���j�̈Ⴂ���ȁH
�����H�����̈Ⴂ��������B
�A���~�b�g�̂́A�S�肪�����炵���ł��B
�u�����h�ɒނ��Ĕ����Ă�l���������ǁA�p�r�ŕ����������ǂ��B
Goot�̂��ǂ��ƕ����B
�����n���_���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�V�^��2�^�C�v�̂�AGC-AMP���ł��������Ă����B
���R�ł͂��邯�ǁA�g���ĂȂ���H�Ƀ�PC1658C������������Ĕ���������B
�����͂��邯�ǏI�i�̃Q�C���Ƃ��Ă�����ƕ�����Ȃ��Ƃ���Řc�ނ̂ŁA
�X�C�b�`���ODi2����A�V���b�g�L�[�肠Di��֓d����������Əグ�āA
��PC1658C��2�ԃs���̃e�X�g���͂�180����GND�ƌq���A������H�̃G�~�b�^��R���������Ƃ���A1.8Vpp���x�̐U�����o��悤�ɂȂ����B
(���ƁA4�ԃs����5�ԃs�����q���ł������B�o�C�A�X��R���������Ĉ��肷��悤�ł���B)
�ŁA�����Ƒ����͏o����B�d�����͂ŃQ�C���R���g���[�����o���邱�Ƃ��m�F�����B
�܂�A����TA7124P�͌����̐V�i�������̂ŁA�U�������H
�Ǝv���Ă������{���̂悤�ł���B
FCZ�R�C���̓V�r�A�ł͖������A15pF���g������A���\���ɍs�����̂ŁA12pF�ŗǂ������B
�������AAGC��H�̕�����V���������ł������B
�\��̒P�d���̌v���A���vIC�́A�Ȃ��������͑��ɓd�ʂ��߂��Ă��ĂƂ������R��Ă��ă_���ł������B
�ƂȂ�ƁA
FET��CMOS���͂̒P�d��(12V�܂őς����郄�c)�Ƃ����̂������������߁A�Ƃ������Ђ����������B
�Ȃ����A���g���ȃm�[�}����OP-AMP�œ������B������A�P�d���Ŕ]������H�ɂ����B
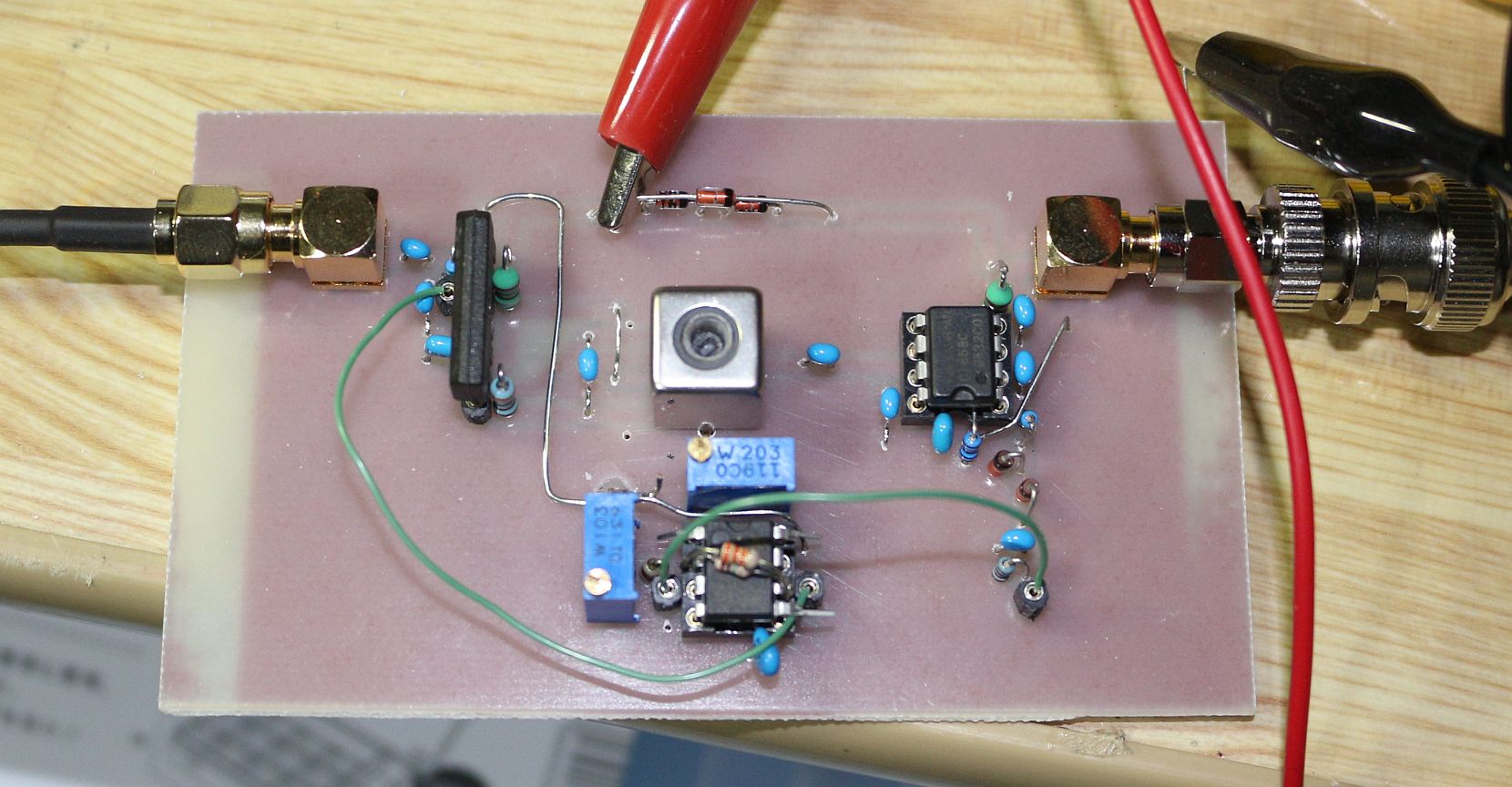 �I�[�g�Q�C���R���g���[�����o����悤�ɂȂ����B
���͉��}���u�����A�P�d����CMOS���ɕς���A�����Ɨǂ������m��Ȃ��B
�Ƃ������ƂŁA�v��AMP�̕����́A�p�^�[�����炵�ĕς��˂Ȃ�Ȃ��B
KiCAD�̏o�Ԃ��o�Ă��܂����Ă�B�B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���^�C�v��AGC-AMP�́A���͂̔��ˑ�̉��P�ƁA�d���Ƀ`���[�N�R�C���ƁA�r���Ƀt�F���C�g�r�[�Y�ŁA�͂��ɃQ�C���㏸�ƊO�A�������P�B
AD811�̓d���d�����グ��A�Q�C�����{�ʂ͏オ�邩���m��Ȃ��B
�����A���d���œ����A�d���A��OP-AMP�͏��Ȃ��̂ŁA��H��ς���͕̂K�v�ɔ����Ȃ�����A�I�X�X���o���Ȃ��ł��B
220421
����Ă�r���̐VAGC-AMP��2��H�̃I�[�g�Q�C���R���g���[�������܂��s���Ȃ��B�ۓ���M��Ȃ���l���Ă���B
�������A��H�Ɣz���͍����Ă���n�Y�B
�ŁA�˂��~�߂��̂��A
���g�o�͂͂��܂����삵�Ă���B
�܂��́A���g�M���������o��悤�Ɍ��������B
�ł��ُ�͎���Ȃ��������A
�܂�A���̓��x����ς��Ă��Q�C���R���g���[���d�����]��ω����Ȃ��B�{OP-AMP�̉��z�ڒn�_�̐������͒[�q�Ԃ̓d���̐H���Ⴂ(�C�}�W�i���[�V���[�g���Ă��Ȃ�)�B
�܂�OP-AMP���܂Ƃ��ɋ@�\���Ă��Ȃ����Ƃ����������B
����āAOP-AMP���̖̂��Ȃ̂����ǁA�P�d���Ń��[��to���[��(�t���X�C���O)���\�Ȃ̂��]�܂����B���A�d����12V�܂œ��삷��̂͏��Ȃ��B(�Ⴂ��TA7124P�̃Q�C���R���g���[���d���ɒB���Ȃ��B)
�Ȃ̂ŁA�E�`�ɂ��鐔�\��ނ�OP-AMP�̒���2��ޒ��x�������B
����ŁA�I�[�g�Q�C���R���g���[�������삷��悤�ɂȂ����B
�������Ȃ���A���o�͂̎��ԍ��ŁAAGC��H���������U���Ă���B
����āA�o�͂��ꌅ�݂������炠����x���肵���B�Ȃ̂ŁA���̉�H����͑��Ɉړ��B����Ɩ�肪�����Ȃ�܂łɉ��P�B
�I�[�g�Q�C���R���g���[�����o����悤�ɂȂ����B
���͉��}���u�����A�P�d����CMOS���ɕς���A�����Ɨǂ������m��Ȃ��B
�Ƃ������ƂŁA�v��AMP�̕����́A�p�^�[�����炵�ĕς��˂Ȃ�Ȃ��B
KiCAD�̏o�Ԃ��o�Ă��܂����Ă�B�B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���^�C�v��AGC-AMP�́A���͂̔��ˑ�̉��P�ƁA�d���Ƀ`���[�N�R�C���ƁA�r���Ƀt�F���C�g�r�[�Y�ŁA�͂��ɃQ�C���㏸�ƊO�A�������P�B
AD811�̓d���d�����グ��A�Q�C�����{�ʂ͏オ�邩���m��Ȃ��B
�����A���d���œ����A�d���A��OP-AMP�͏��Ȃ��̂ŁA��H��ς���͕̂K�v�ɔ����Ȃ�����A�I�X�X���o���Ȃ��ł��B
220421
����Ă�r���̐VAGC-AMP��2��H�̃I�[�g�Q�C���R���g���[�������܂��s���Ȃ��B�ۓ���M��Ȃ���l���Ă���B
�������A��H�Ɣz���͍����Ă���n�Y�B
�ŁA�˂��~�߂��̂��A
���g�o�͂͂��܂����삵�Ă���B
�܂��́A���g�M���������o��悤�Ɍ��������B
�ł��ُ�͎���Ȃ��������A
�܂�A���̓��x����ς��Ă��Q�C���R���g���[���d�����]��ω����Ȃ��B�{OP-AMP�̉��z�ڒn�_�̐������͒[�q�Ԃ̓d���̐H���Ⴂ(�C�}�W�i���[�V���[�g���Ă��Ȃ�)�B
�܂�OP-AMP���܂Ƃ��ɋ@�\���Ă��Ȃ����Ƃ����������B
����āAOP-AMP���̖̂��Ȃ̂����ǁA�P�d���Ń��[��to���[��(�t���X�C���O)���\�Ȃ̂��]�܂����B���A�d����12V�܂œ��삷��̂͏��Ȃ��B(�Ⴂ��TA7124P�̃Q�C���R���g���[���d���ɒB���Ȃ��B)
�Ȃ̂ŁA�E�`�ɂ��鐔�\��ނ�OP-AMP�̒���2��ޒ��x�������B
����ŁA�I�[�g�Q�C���R���g���[�������삷��悤�ɂȂ����B
�������Ȃ���A���o�͂̎��ԍ��ŁAAGC��H���������U���Ă���B
����āA�o�͂��ꌅ�݂������炠����x���肵���B�Ȃ̂ŁA���̉�H����͑��Ɉړ��B����Ɩ�肪�����Ȃ�܂łɉ��P�B
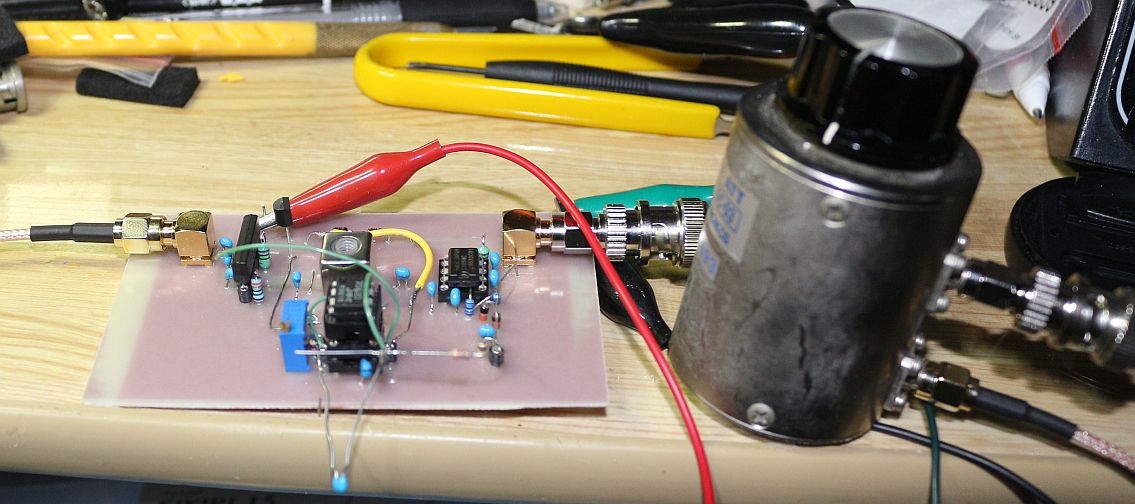 ���ۖ��A�ǂ̃��[�J�[��10��Sec�̏����\�ŃQ�C���R���g���[�����x��搂��Ă��邪�A���ۂ̉�H������ƁA2�`3���̃o���c�L������B
��́A����Ȃɑ����Q�C���R���g���[���͗v��Ȃ��Ƃ������A�������u����̗U���ŊܗL�����m�C�Y�̃Q�C���ɂ����킹�Ă��܂����߁A���܂�ǂ��Ȃ��Ǝv���B
�����A����2��H��OP-AMP��1��H�̃\�P�b�g�ɂ͂߂鎩��ϊ��A�_�v�^�[(�Q�^)���g���Ă���B
1��H�ł܂Ƃ���OP-AMP��T���˂Ȃ�Ȃ������B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220422
���̂��V���ɓ��肵�����m�A
10000�̂�1000�~�l�����ŁA1000�~�̃N�[�|����8000�~�ɂė��D�B
���ۖ��A�ǂ̃��[�J�[��10��Sec�̏����\�ŃQ�C���R���g���[�����x��搂��Ă��邪�A���ۂ̉�H������ƁA2�`3���̃o���c�L������B
��́A����Ȃɑ����Q�C���R���g���[���͗v��Ȃ��Ƃ������A�������u����̗U���ŊܗL�����m�C�Y�̃Q�C���ɂ����킹�Ă��܂����߁A���܂�ǂ��Ȃ��Ǝv���B
�����A����2��H��OP-AMP��1��H�̃\�P�b�g�ɂ͂߂鎩��ϊ��A�_�v�^�[(�Q�^)���g���Ă���B
1��H�ł܂Ƃ���OP-AMP��T���˂Ȃ�Ȃ������B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220422
���̂��V���ɓ��肵�����m�A
10000�̂�1000�~�l�����ŁA1000�~�̃N�[�|����8000�~�ɂė��D�B
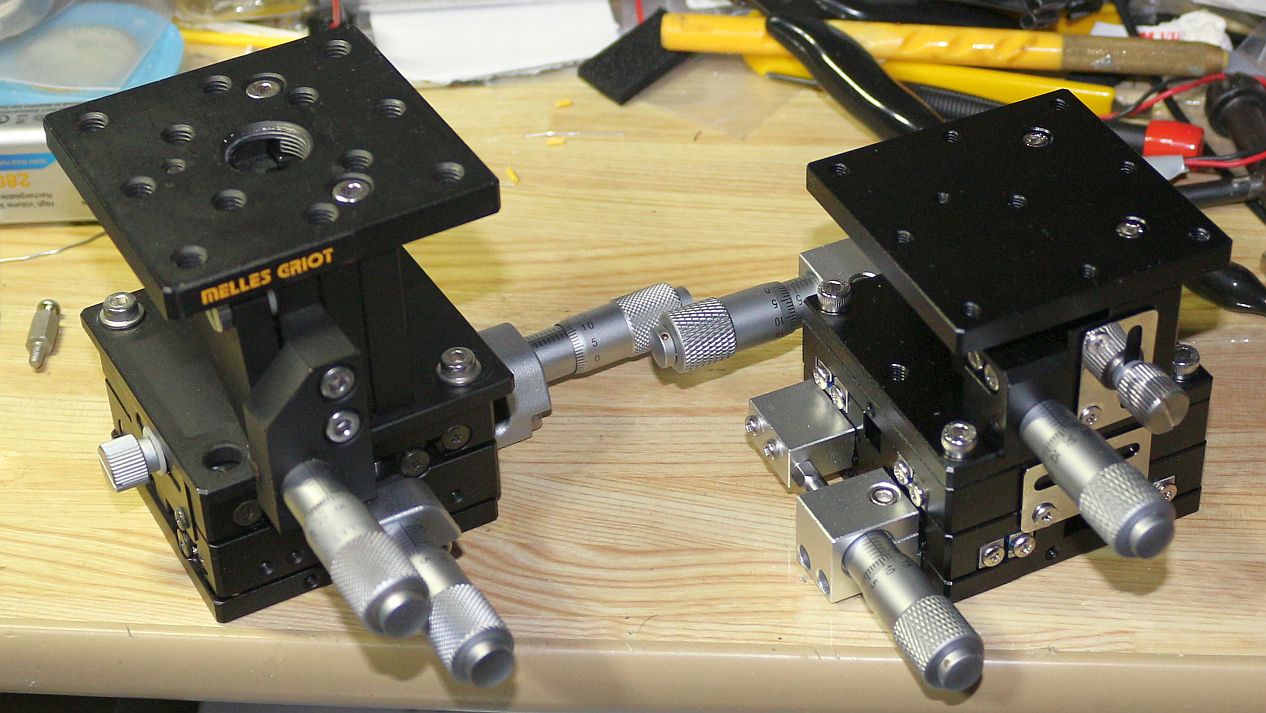 �V�O�}���@�Ə����Ă��������A�����X�O���I�������B
�܂��A�W�Ȃ������B
AGC-AMP�A��2��H���P�[�X�ɓ���܂����B
�V�O�}���@�Ə����Ă��������A�����X�O���I�������B
�܂��A�W�Ȃ������B
AGC-AMP�A��2��H���P�[�X�ɓ���܂����B
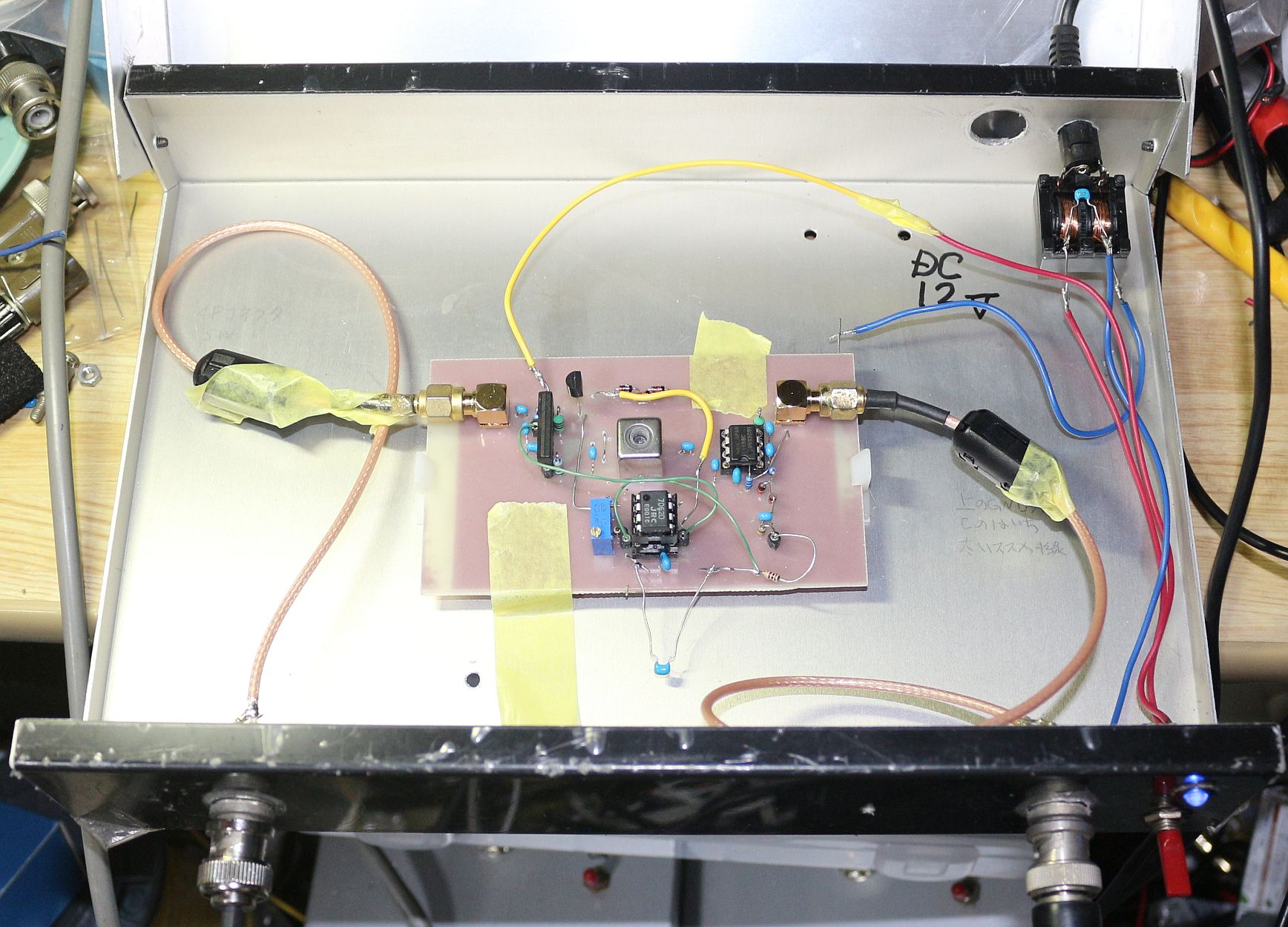 �ł��A�܂��A�P�[�X�ɓ����Ɩ��̊����ł����B
�ŁA�����P�[�u�����d���̂Œ��߂ɂ����̂��A���A�t�F���C�g�R�A���g���ăR�������[�h�̗U���炵�����m��}���Ă�̂ł����A
��������ŕی삵����A�r���Ƀr�[�Y����ꂽ�����ǂ������m��Ȃ��Ƃ��A�C���C���A�����Ǝv���܂��B
���ƁA50���ŏI�[���Ȃ��Œ��߂̃P�[�u�����o�͂Ɍq������A���͖����ŁA200MHz���x�̔��U������܂����B���P�[�u���ɂ��܂��B
�܂��́A�g���u���������Ƃ͎v���܂���B
���������ł����A
���ϒ��┭�U���C�ɂȂ�g�R�ł����A�A�A�A
�܂��A�Q�C���̖��́A�t���i��p���ăg�[�^�������ǂ����l���Ȃ��ƍs���Ȃ��Ǝv���Ă���܂��B
�����ƃP�[�XGND�̎����ȂǃC���C���ŕς�肤��̂œ���ł��ˁB
���U��ŏo����ŏ��ɂ���ƁA�U���������������Ȃ�B
���̌v���ɂ����ẮA�ő�Q�C���́A�O��AGC-AMP�Ƃ����ĕς��Ȃ��C������B
�ł��A�܂��A�P�[�X�ɓ����Ɩ��̊����ł����B
�ŁA�����P�[�u�����d���̂Œ��߂ɂ����̂��A���A�t�F���C�g�R�A���g���ăR�������[�h�̗U���炵�����m��}���Ă�̂ł����A
��������ŕی삵����A�r���Ƀr�[�Y����ꂽ�����ǂ������m��Ȃ��Ƃ��A�C���C���A�����Ǝv���܂��B
���ƁA50���ŏI�[���Ȃ��Œ��߂̃P�[�u�����o�͂Ɍq������A���͖����ŁA200MHz���x�̔��U������܂����B���P�[�u���ɂ��܂��B
�܂��́A�g���u���������Ƃ͎v���܂���B
���������ł����A
���ϒ��┭�U���C�ɂȂ�g�R�ł����A�A�A�A
�܂��A�Q�C���̖��́A�t���i��p���ăg�[�^�������ǂ����l���Ȃ��ƍs���Ȃ��Ǝv���Ă���܂��B
�����ƃP�[�XGND�̎����ȂǃC���C���ŕς�肤��̂œ���ł��ˁB
���U��ŏo����ŏ��ɂ���ƁA�U���������������Ȃ�B
���̌v���ɂ����ẮA�ő�Q�C���́A�O��AGC-AMP�Ƃ����ĕς��Ȃ��C������B
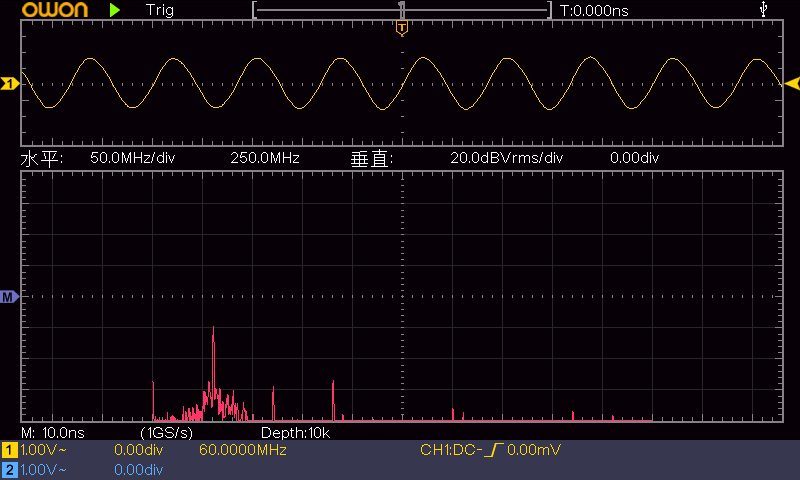 �m�C�Y�����ɂ��邱�Ƃ���A�Q�C���������グ�Ă��ǂ��͂Ȃ�Ȃ������B
TA7124P��NF=6dB�ƁA�D�G�ł͖����̂ŁA����ȏ�ɏグ��Ȃ�Pre-AMP���Ǝv���B
�������Ȃ���A�t�H�g�_�C�I�[�h��DATA��S/N���x�����A�t�o�C�A�X�ł����قǂɕς�邩���l�b�N�ł�����B
�m�C�Y�┭�U������āA�Q�C�����҂��̂ɂ͂��Ȃ��J�������ł���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
������AGC-AMP�A�R���f���T�[������������A��Q�C�����オ�����C�����܂��B
����ŁA�V�����AMP�͓������炢�̃Q�C�����Ǝv���܂��B
�����A�V�^��FCZ�R�C�������邽�߂��A�g�`�̘c�݂����܂�o�܂���B���ꂪ�v����e�����邩�́A�܂��s���ł����A�A�A
�����āAAD811�̓d���d���Ȃ̂ł����A
�f�[�^�V�[�g������ƁA�u�}5V�A�}15V�̓�i�d�l�v�ł����ē�������ւ��悤�ł��B
����āA�}9V�Ƃ��͐�ւ������܂��s���Ȃ�NG�Ȃ悤�ł��ˁc�A�A��V�Ȏd�l�ł��B
�܂��A�K�v�Ȃ���A���g���ш�̑啝�Ȋg���́A���U�Ȃǂ̊댯��������̂ŁA��̎����Ǝv���܂����B
���̓d�����ƁA���㈵�������h���C�o�[��OP-AMP�́A�ʂ̂��l���˂Ȃ�Ȃ������ł��ˁc�B
�Q�C���R���g���[���[�́A���͌��ɂ����������ǂ��C�����܂��B
�i���Ă��玝���グ����A�����グ�Ă���i���������A�m�C�Y�Ƃ��ɋ������ȃC���[�W�ł��B
���������Ӗ��ł��APre-AMP�����܂���A�A�A
���肪�t�H�gDi�Ȃ̂ŁA�C���s�[�_���X�̖�肪�o�₷���̂�Pre-AMP�����H
�����ɒu���C�ɂ��Ȃ��ėǂ����ȁ[�A�A�Ǝv���Ă���܂��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220423
�\�z���܂߂Ĕ�r�A�܂Ƃ߂Ă݂�ƁA
�E����H�F���U�X���ɂȂ�₷���B�˃h�R���ǂ����U���Ă�̂��H
�E�V��H�F�m�C�Y�������˂ǂ̐̒i�K�ŋN�����Ă���̂��H
�O�҂͓��͂ɃP�[�u���������q���������Ŕg���X���B�{���͂��傫���Ƙc�ށB
��҂͓��͂ɉ����q���Ȃ��Ă��g�����Ă���B
���͂��c�ނ̂́A�Q�C���R���g���[���͈͂��������ƂɋN�����Ă���B
AGC��H�̍������͂̑��������グ�Ăǂ��ɂ��c�A���ƁA�����h���C�o�[�̋A�Ғ�R�Ɣ{���ݒ���œK�����K�v�����B
�S�̓I�ɊeIC�̓d�����C���̎Օ���C�̋������K�v�����B
���Ɠ����P�[�u���͒Z�������ǂ����ƁB
���t�^�̐��i���g���闝�R�A�Q�C���������B�����Q�C����������̈�ɒB���Ă��Ȃ��B
���ǁA��H��AGC�Ƃ͌����Ȃ������Ȃ̂ŁA�����̈������͂ő傫���������Ă��Ԃ��ƁA�m�C�Y�������ߑ�ɑ�����\�����A���B
���m�Ȕ��f�ɂ́A�E�`�Ɋ��v������A�A�A�Ǝv�����ǁA�A
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���^�͏��i�̃�PC1658�����͊��ɂ��Ŗ\��C���ŁA�V�^��TA7124P�̃m�C�Y�Ń�PC1658����N���Ă�l�q������悤���B
��PC1658��NF���Ⴍ�Q�C�����傫�����A���̃Q�C���̂��߂��A�\��₷���C������B
�ŁA�����̃�PC1658��4-5��PIN����������Ă�̂����A2��PIN��GND��510���ōT���߂Ɍq���ł�����A�܂��܂��U�����傫���Ȃ����B
���̉�H�A��͂�AAGC�̕����������C������B
������Pre-AMP�ŁA���ϒ��������A�m�C�Y���葝������^�C�v�Ƃ����̂�����炵�����A���̂悤�ɂȂ�Ȃ��悤�ɒ��ӂ��K�v�ł���B
30MHz�̑�����H�ŁA�o����A���Ȃ苭�����U���ĂĂ��t�B���^�ŏ����Ă���AGC�ɓ����Ζ�薳�����Ƃ͊m�F���Ă���B
�������A�s��BPF�́A����H�Ȃ̂ŁA������������������X��������B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
AGC-AMP�ɂ��āA�Q�C�����m�C�Y���H�Ƃ����̂����邯��
(�c�݂₻��ɂ�鍬�ϒ��͗]��W�Ȃ��Ǝv���B)�A
�ǂ���ɂ��Ă����U���萫�v�f�͋]���ɏo���Ȃ��Ǝv���A
�܂��A���U��Z�����Ȃǂ��邯�ǃ�PC1658C�������̂ɓ���_�ł�����B
�����A�����g�܂ŐL�тĂĈʑ��]�T�I�ȗv�f���V�r�A�Ȃ̂��Ɨ\�z�B
�����ŁA�����̃��[�U�[CH���ɂ��M�����x�����邪�B
����ɑ��t�o�C�A�X��Pre-AMP�̑��݂��ǂ�قǗǍD���ɂ���āA
AGC-AMP�ɋ��߂���v�f���ς���Ă���悤�Ɏv�����B
�Ȃ̂ŁA�����́A�������ʂ̕���ł�����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�ł����āA
KiCAD��Ver6�ɂȂ��Ă���A���i���C�u�����̓ǂݍ��݂��܂Ƃ��ɏo���Ȃ��悤�ŁA
���ꂾ�ƁA�ǂ�PCB�pCAD���ǂ��̂�������ԂɎv����B
�{�����Ȃ荂���̂�����A�[���ł��A�A�A�������AKiCAD�̖{�͐��j���ɓ͂��Ƃ��B�B
�g���ZSp��KiCAD���W���AVer6�p�ŏo��Ɨ\�z�͂��Ă�̂ő҂���ԁB
KiCAD�{�̓����Ƃ������܂��������炵�Ė����Ă��x�����AVer6�͈ȑO�Ǝd�l�����Ȃ�Ⴂ�A
�����Ȃ�����A�O�O���Ċw�K�\���Ǝv���A�{�̓L�����Z���˗����܂����B�ǂ��Ȃ邱�Ƃ��A�A�A
�ꉞ�A�����܂ŏo���Ă��Ă���܂��B
�m�C�Y�����ɂ��邱�Ƃ���A�Q�C���������グ�Ă��ǂ��͂Ȃ�Ȃ������B
TA7124P��NF=6dB�ƁA�D�G�ł͖����̂ŁA����ȏ�ɏグ��Ȃ�Pre-AMP���Ǝv���B
�������Ȃ���A�t�H�g�_�C�I�[�h��DATA��S/N���x�����A�t�o�C�A�X�ł����قǂɕς�邩���l�b�N�ł�����B
�m�C�Y�┭�U������āA�Q�C�����҂��̂ɂ͂��Ȃ��J�������ł���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
������AGC-AMP�A�R���f���T�[������������A��Q�C�����オ�����C�����܂��B
����ŁA�V�����AMP�͓������炢�̃Q�C�����Ǝv���܂��B
�����A�V�^��FCZ�R�C�������邽�߂��A�g�`�̘c�݂����܂�o�܂���B���ꂪ�v����e�����邩�́A�܂��s���ł����A�A�A
�����āAAD811�̓d���d���Ȃ̂ł����A
�f�[�^�V�[�g������ƁA�u�}5V�A�}15V�̓�i�d�l�v�ł����ē�������ւ��悤�ł��B
����āA�}9V�Ƃ��͐�ւ������܂��s���Ȃ�NG�Ȃ悤�ł��ˁc�A�A��V�Ȏd�l�ł��B
�܂��A�K�v�Ȃ���A���g���ш�̑啝�Ȋg���́A���U�Ȃǂ̊댯��������̂ŁA��̎����Ǝv���܂����B
���̓d�����ƁA���㈵�������h���C�o�[��OP-AMP�́A�ʂ̂��l���˂Ȃ�Ȃ������ł��ˁc�B
�Q�C���R���g���[���[�́A���͌��ɂ����������ǂ��C�����܂��B
�i���Ă��玝���グ����A�����グ�Ă���i���������A�m�C�Y�Ƃ��ɋ������ȃC���[�W�ł��B
���������Ӗ��ł��APre-AMP�����܂���A�A�A
���肪�t�H�gDi�Ȃ̂ŁA�C���s�[�_���X�̖�肪�o�₷���̂�Pre-AMP�����H
�����ɒu���C�ɂ��Ȃ��ėǂ����ȁ[�A�A�Ǝv���Ă���܂��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220423
�\�z���܂߂Ĕ�r�A�܂Ƃ߂Ă݂�ƁA
�E����H�F���U�X���ɂȂ�₷���B�˃h�R���ǂ����U���Ă�̂��H
�E�V��H�F�m�C�Y�������˂ǂ̐̒i�K�ŋN�����Ă���̂��H
�O�҂͓��͂ɃP�[�u���������q���������Ŕg���X���B�{���͂��傫���Ƙc�ށB
��҂͓��͂ɉ����q���Ȃ��Ă��g�����Ă���B
���͂��c�ނ̂́A�Q�C���R���g���[���͈͂��������ƂɋN�����Ă���B
AGC��H�̍������͂̑��������グ�Ăǂ��ɂ��c�A���ƁA�����h���C�o�[�̋A�Ғ�R�Ɣ{���ݒ���œK�����K�v�����B
�S�̓I�ɊeIC�̓d�����C���̎Օ���C�̋������K�v�����B
���Ɠ����P�[�u���͒Z�������ǂ����ƁB
���t�^�̐��i���g���闝�R�A�Q�C���������B�����Q�C����������̈�ɒB���Ă��Ȃ��B
���ǁA��H��AGC�Ƃ͌����Ȃ������Ȃ̂ŁA�����̈������͂ő傫���������Ă��Ԃ��ƁA�m�C�Y�������ߑ�ɑ�����\�����A���B
���m�Ȕ��f�ɂ́A�E�`�Ɋ��v������A�A�A�Ǝv�����ǁA�A
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���^�͏��i�̃�PC1658�����͊��ɂ��Ŗ\��C���ŁA�V�^��TA7124P�̃m�C�Y�Ń�PC1658����N���Ă�l�q������悤���B
��PC1658��NF���Ⴍ�Q�C�����傫�����A���̃Q�C���̂��߂��A�\��₷���C������B
�ŁA�����̃�PC1658��4-5��PIN����������Ă�̂����A2��PIN��GND��510���ōT���߂Ɍq���ł�����A�܂��܂��U�����傫���Ȃ����B
���̉�H�A��͂�AAGC�̕����������C������B
������Pre-AMP�ŁA���ϒ��������A�m�C�Y���葝������^�C�v�Ƃ����̂�����炵�����A���̂悤�ɂȂ�Ȃ��悤�ɒ��ӂ��K�v�ł���B
30MHz�̑�����H�ŁA�o����A���Ȃ苭�����U���ĂĂ��t�B���^�ŏ����Ă���AGC�ɓ����Ζ�薳�����Ƃ͊m�F���Ă���B
�������A�s��BPF�́A����H�Ȃ̂ŁA������������������X��������B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
AGC-AMP�ɂ��āA�Q�C�����m�C�Y���H�Ƃ����̂����邯��
(�c�݂₻��ɂ�鍬�ϒ��͗]��W�Ȃ��Ǝv���B)�A
�ǂ���ɂ��Ă����U���萫�v�f�͋]���ɏo���Ȃ��Ǝv���A
�܂��A���U��Z�����Ȃǂ��邯�ǃ�PC1658C�������̂ɓ���_�ł�����B
�����A�����g�܂ŐL�тĂĈʑ��]�T�I�ȗv�f���V�r�A�Ȃ̂��Ɨ\�z�B
�����ŁA�����̃��[�U�[CH���ɂ��M�����x�����邪�B
����ɑ��t�o�C�A�X��Pre-AMP�̑��݂��ǂ�قǗǍD���ɂ���āA
AGC-AMP�ɋ��߂���v�f���ς���Ă���悤�Ɏv�����B
�Ȃ̂ŁA�����́A�������ʂ̕���ł�����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�ł����āA
KiCAD��Ver6�ɂȂ��Ă���A���i���C�u�����̓ǂݍ��݂��܂Ƃ��ɏo���Ȃ��悤�ŁA
���ꂾ�ƁA�ǂ�PCB�pCAD���ǂ��̂�������ԂɎv����B
�{�����Ȃ荂���̂�����A�[���ł��A�A�A�������AKiCAD�̖{�͐��j���ɓ͂��Ƃ��B�B
�g���ZSp��KiCAD���W���AVer6�p�ŏo��Ɨ\�z�͂��Ă�̂ő҂���ԁB
KiCAD�{�̓����Ƃ������܂��������炵�Ė����Ă��x�����AVer6�͈ȑO�Ǝd�l�����Ȃ�Ⴂ�A
�����Ȃ�����A�O�O���Ċw�K�\���Ǝv���A�{�̓L�����Z���˗����܂����B�ǂ��Ȃ邱�Ƃ��A�A�A
�ꉞ�A�����܂ŏo���Ă��Ă���܂��B
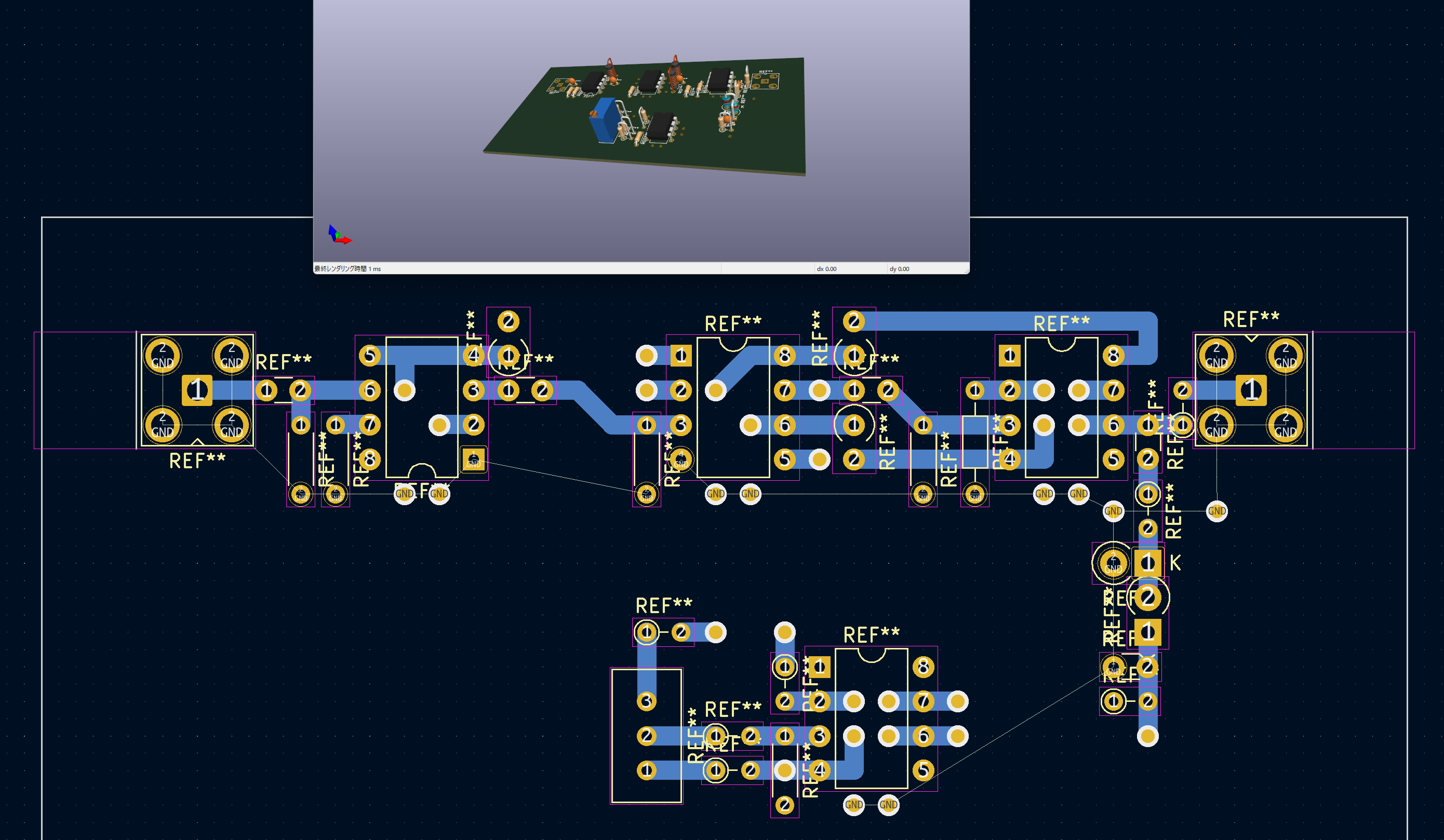 ���ʂɂ́A�p�^�[�����`����Ă��܂��B�x�^�͂܂��ł��B
���i�}�ʂ��t�b�g�v�����g�ƌ����܂����A
FCZ�R�C����TA7124P�Ȃǂ́A3D���f�������Ȃ���A����ʼn\�ł��̂ŁA�v�������ȒP�����ł��B
�����A�p�b�h(�r�A)�A�O�g�A�V���N�A�s���ԍ����x���Ǝv���܂��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���U��Ɍq���ł邯�ǁA���U�����ĂȂ���ԂŌv���B
�\�z�ʂ�Ƃ������A�z���C�g�I�ȃ��m��60MHz���S�̃m�C�Y�ł��ˁB������FCZ�R�C���ŃX�g�b�v����Ă�B
���ʂɂ́A�p�^�[�����`����Ă��܂��B�x�^�͂܂��ł��B
���i�}�ʂ��t�b�g�v�����g�ƌ����܂����A
FCZ�R�C����TA7124P�Ȃǂ́A3D���f�������Ȃ���A����ʼn\�ł��̂ŁA�v�������ȒP�����ł��B
�����A�p�b�h(�r�A)�A�O�g�A�V���N�A�s���ԍ����x���Ǝv���܂��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���U��Ɍq���ł邯�ǁA���U�����ĂȂ���ԂŌv���B
�\�z�ʂ�Ƃ������A�z���C�g�I�ȃ��m��60MHz���S�̃m�C�Y�ł��ˁB������FCZ�R�C���ŃX�g�b�v����Ă�B
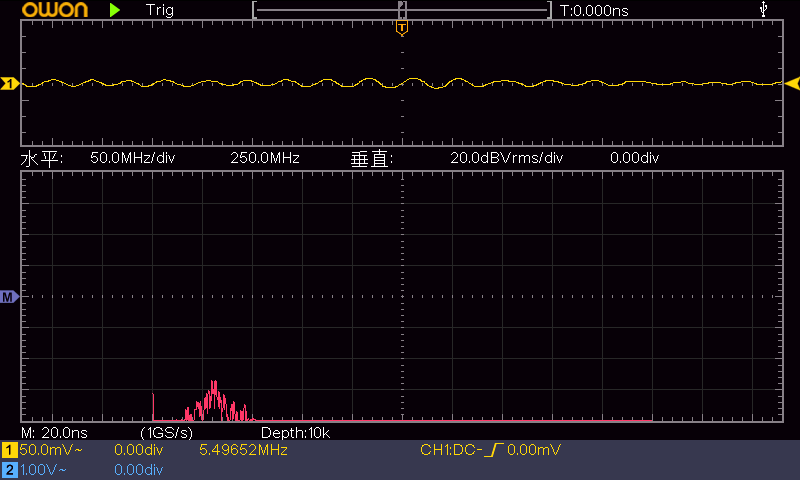 (�������j�A�A��ԉ��̂̓n���m�C�Y���Ǝv����B)
�����ASMA�ɉ����q���Ȃ��ł��R���͕ς��Ȃ��B�Ȃ̂�TA7124P�̃m�C�Y���ƁA
���͔̐���TV�p�ŁA�d�C���H���݂����łق�̂�g�����Ȃ�B
���ꂪ�P�ɓ��̓m�C�Y�Ȃ�A�Q�C�����グ��Ή������Ă������A
�̓����Ŕ������Ă�̂Ȃ炻���������Ȃ��B
�Ȃ̂ŁA�Q�C���R���g���[����H�͌��̕����ǂ��ƌ������ƂɂȂ�B
���A���̉�H�̏ꍇ�A2�̂����̃p���[�̖R�����n�C�Q�C��AMP�Ȃ̂ŁA�ړ����悤�������B
�܂��A���̉�H�\���̏ꍇ�ł́A���͐M���ɑ��A�m�C�Y���C�ɂȂ�ƌ������Ƃ͂��܂�Ȃ��悤�ȋC������B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220424
�C���s�[�_���X�s�����́A���U�ɂ����т��₷�������m��Ȃ��B
���̎�̉�H�̓��́A�ꍇ�ɂ���Ă͏o�͂ɂ��A�g�����X��BPF�AATT�Ȃnjq���ł�̂������̂́A���̂��߂��낤�B
BPF�́AFCZ�R�C��2�Ō��\�Ȃ̂����邯�ǁA
�~�j�T�[�L�b�g�́uBPF-A60+�v���C���s�[�_���X�����̂��߂Ȃ�g���邩�ȁH�Ǝv����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�v�Z�̃Q�C���͐V��H�̕�����̃n�Y�Ȃ̂ŁA���������Ǝv���A
����H���R���f���T�[�ŏo�͏オ�����̂����ǁA
TA7124P����PC1658C���Q�C�����傫���d�C��H���n���Ȃ̂ŁA
���������āc�A�ƁA�v���A���܂ł�0.1��F�ɑ��A1��F�݁B
����ƁA�U�����傫���Ȃ�A�t�]�B
�������g���̏ꍇ�A�����σZ���ł��A�e�ʂ��������Ȃ炻�ꂾ���v�������g�ł͒�ESR���ƍl�����̂ŁA
����Ƀf�[�^�V�[�g�̗�ɂ�0.1��F��OK�݂����ɏ����Ă��邯�ǁA���ۂ͂����ł��Ȃ��悤�Ȍ��ʂł���B�C���_�N�^�����邵�B
IC�����̃R���f���T�[�͂ƂĂ��d�v�ȃR�g���������B
����H�͗v����C�̂ݕt���������ǁA���������������������ƍs���邩���m��Ȃ����Ƃ͂��蓾��B
�����A�Q�C���̏グ�����́A�m�C�Y�Ɣ��U�̌����B���ɁA���U�͘_�O�ł���B
�V�^�́ABPF�����邯�ǁA���ꂪ�����}�V�ɂ��Ă邩���m��Ȃ��B
�Ƃ������ƂŁA�t�o�C�A�X��H��Pre-AMP���ǂ��Ȃ̂�����ł���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�����A�V��H�ȂǂŃm�C�Y�ŐM��DATA�̃��T�[�W���~�������Ȃ�A
��PC1658C���ɃQ�C�������p��R��t����ׂ����Ǝv���B�X�C�b�`�Ő�ւ���悤�Ȋ����ŁB
AGC�̃��[�v�̒����ᖳ���ƁA�A
���U���ᖳ���ꍇ�́AAGC���[�v�̑O��ɕt���Ă�����قLjӖ��͖����\���������B
�ŁA���^��IC�̓d�����͎����S��1.0��F�ɂ����B����������A�܂��オ���āA
�ǂ�����A�ŏ����͂ŃQ�C���R���g���[����������Ă����ԂɂȂ����B
�Ȃ̂ŁA��ʂ��t���ɂ������ǁA���^�̕����A��ォ���m��Ȃ��B�B�s�v�c�B
���Ƃ́A���萫�̗v�f���傫�����ȁB
��قǂ́A�g�����X�ABPF�AATT����o�͂ɓ����̂��A
�u�����N�b�V�����v�u���̂ŁA�u�ɏՁv�Ƃ�������悤�ł���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�ł����āA�����Ŕ�r�����Ȃ��ƃ_�����ۂ��̂ŁB�B
�Ƃ͂����A�Q�C���R���g���[���������Ă��ԁB
(�������j�A�A��ԉ��̂̓n���m�C�Y���Ǝv����B)
�����ASMA�ɉ����q���Ȃ��ł��R���͕ς��Ȃ��B�Ȃ̂�TA7124P�̃m�C�Y���ƁA
���͔̐���TV�p�ŁA�d�C���H���݂����łق�̂�g�����Ȃ�B
���ꂪ�P�ɓ��̓m�C�Y�Ȃ�A�Q�C�����グ��Ή������Ă������A
�̓����Ŕ������Ă�̂Ȃ炻���������Ȃ��B
�Ȃ̂ŁA�Q�C���R���g���[����H�͌��̕����ǂ��ƌ������ƂɂȂ�B
���A���̉�H�̏ꍇ�A2�̂����̃p���[�̖R�����n�C�Q�C��AMP�Ȃ̂ŁA�ړ����悤�������B
�܂��A���̉�H�\���̏ꍇ�ł́A���͐M���ɑ��A�m�C�Y���C�ɂȂ�ƌ������Ƃ͂��܂�Ȃ��悤�ȋC������B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220424
�C���s�[�_���X�s�����́A���U�ɂ����т��₷�������m��Ȃ��B
���̎�̉�H�̓��́A�ꍇ�ɂ���Ă͏o�͂ɂ��A�g�����X��BPF�AATT�Ȃnjq���ł�̂������̂́A���̂��߂��낤�B
BPF�́AFCZ�R�C��2�Ō��\�Ȃ̂����邯�ǁA
�~�j�T�[�L�b�g�́uBPF-A60+�v���C���s�[�_���X�����̂��߂Ȃ�g���邩�ȁH�Ǝv����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�v�Z�̃Q�C���͐V��H�̕�����̃n�Y�Ȃ̂ŁA���������Ǝv���A
����H���R���f���T�[�ŏo�͏オ�����̂����ǁA
TA7124P����PC1658C���Q�C�����傫���d�C��H���n���Ȃ̂ŁA
���������āc�A�ƁA�v���A���܂ł�0.1��F�ɑ��A1��F�݁B
����ƁA�U�����傫���Ȃ�A�t�]�B
�������g���̏ꍇ�A�����σZ���ł��A�e�ʂ��������Ȃ炻�ꂾ���v�������g�ł͒�ESR���ƍl�����̂ŁA
����Ƀf�[�^�V�[�g�̗�ɂ�0.1��F��OK�݂����ɏ����Ă��邯�ǁA���ۂ͂����ł��Ȃ��悤�Ȍ��ʂł���B�C���_�N�^�����邵�B
IC�����̃R���f���T�[�͂ƂĂ��d�v�ȃR�g���������B
����H�͗v����C�̂ݕt���������ǁA���������������������ƍs���邩���m��Ȃ����Ƃ͂��蓾��B
�����A�Q�C���̏グ�����́A�m�C�Y�Ɣ��U�̌����B���ɁA���U�͘_�O�ł���B
�V�^�́ABPF�����邯�ǁA���ꂪ�����}�V�ɂ��Ă邩���m��Ȃ��B
�Ƃ������ƂŁA�t�o�C�A�X��H��Pre-AMP���ǂ��Ȃ̂�����ł���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�����A�V��H�ȂǂŃm�C�Y�ŐM��DATA�̃��T�[�W���~�������Ȃ�A
��PC1658C���ɃQ�C�������p��R��t����ׂ����Ǝv���B�X�C�b�`�Ő�ւ���悤�Ȋ����ŁB
AGC�̃��[�v�̒����ᖳ���ƁA�A
���U���ᖳ���ꍇ�́AAGC���[�v�̑O��ɕt���Ă�����قLjӖ��͖����\���������B
�ŁA���^��IC�̓d�����͎����S��1.0��F�ɂ����B����������A�܂��オ���āA
�ǂ�����A�ŏ����͂ŃQ�C���R���g���[����������Ă����ԂɂȂ����B
�Ȃ̂ŁA��ʂ��t���ɂ������ǁA���^�̕����A��ォ���m��Ȃ��B�B�s�v�c�B
���Ƃ́A���萫�̗v�f���傫�����ȁB
��قǂ́A�g�����X�ABPF�AATT����o�͂ɓ����̂��A
�u�����N�b�V�����v�u���̂ŁA�u�ɏՁv�Ƃ�������悤�ł���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�ł����āA�����Ŕ�r�����Ȃ��ƃ_�����ۂ��̂ŁB�B
�Ƃ͂����A�Q�C���R���g���[���������Ă��ԁB
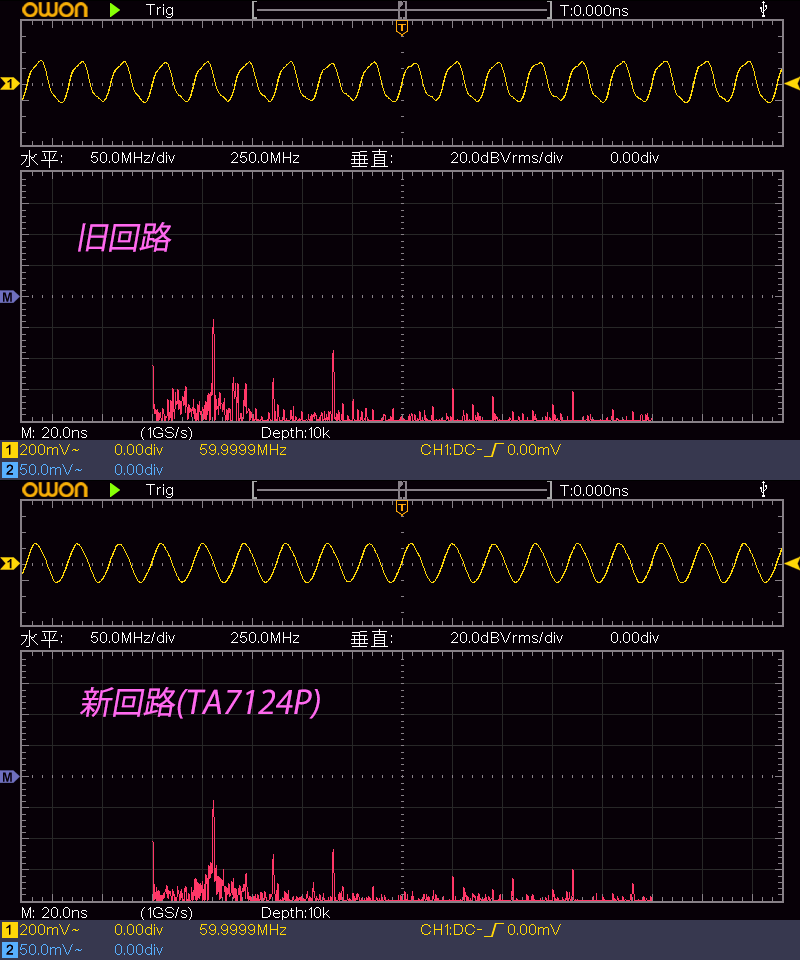 ���萫�͐V��H�A60MHz���ӂ̃m�C�Y�̒Ⴓ�͋���H���ȂƂ��������B
�g�`�́AFCZ�R�C���̗L���̉e������������A
�������j�A�ŏc���͑ΐ��\�L�ł͂��邪�A�S�ʂ�3�A5�A7�{�̃g�[�����ڗ��B����480MHz�܂ł���̂͋����B������̃��x���͗]��W�͖��������B
�Q�C�����R���g���[���̂�����Ȃ��Ⴂ�̈�ł͐U���̗h�炬�����邪�A���U��̐��������m��Ȃ��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���������قǁAGW�����܂��Ă�̂ɋC���t�����̂�����A�}���ŏH���ɂ�����ƒ������܂������A�������ق�1�i�����t���������ł��B
(�����͎؋��ŃM���M���Ƃ��������ōs�������ł��B�c�Ȃ̂ŏ������Ԃ̗]�T�o�Ă��������B)
���Ƃ́A
AGC-AMP�u��3��H�̊�v���ǂ����邩�ł��ˁB(��2��H�͊�~�X���Ȃ������ł����d�l�ύX�̉��H�����\���܂���)
��3��H���ŏ�����ϑ����邩�H�ŁA�K�[�o�[�f�[�^�o�͂��\�Ȃ̂ŁA
���������قǂ̒l�i�Ɣ[�����H�����ɂ߂Ȃ��Ắc�A
�Ƃ����̂�����܂����A��H�Ɏ藎��������Ƒ����ɒɂ��B
�������A�O������Ȃ�A���ʃx�^GND�̊�ɂ��悤�Ǝv���܂��B
�Ȃ̂ŁA���s�͏C�����Â炢�B
��̌�����U�d���Ƃ̊W�Ȃǂ��C�ɂȂ�͂��܂����A�A�A�A
�����͂���ƁA�L���p�V�^���X�̉e��������܂����AIC�\�P�b�g�d�l�ɂ͎����㑊�������Ȃ舫���ł��B
������͂Ђ���Ƃ����犄�������m��Ȃ��ł��ˁB
������A�����������ׂ˂B
�ŁA�O��ނ̉�H���o������A�ǂꂪ�ǂ����ŁA
�܂��A��H�A��̉��ǂƂȂ��Ă��������m��܂���B
���A����́A�O��Ȃǂɏ������ʂ�A�u�������Ƃ̓K���v�������m�ɂ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł��B
����ŁA���\��������Ηǂ��̂ł����A������Ȃ��̂Łc�A
�����ŁA�t�o�C�A�X��H�APre-AMP�A�t�B���^�[�̌��ʂ�m�肽���ł��ˁB
�m�C�Y�������ƁAAGC-AMP�̃Q�C���R���g���[��������Ɉ��������āA���T�[�W�����\���\�����뜜����܂��B
�܂��A�C���s�[�_���X�ω��̊ɏՍނƂ��Ă������邩���B
�Ȃ̂ŁA�t�B���^�[�́AAGC-AMP�̎�O�̐ݒu�������Č��čl���˂ł��B
�Ƃɂ������ɂ��A�F�����Ȃ��ꍇ�Ƃ����l����ɁA
�܂��A������́A
���炩���߁u�ۑ���܂Ƃ߁v�A�ғ��@�̂ق��֍s���āA�u�܂Ƃ߂āv�����W�ˑΏ����ȁ[�A�A�ƁB�M���Č��Ȃ��Ɣ���Ȃ����ʂ����邵�B
���ƁA���̑���Ȃǂ̋@�B�̏������W�͂������Ǝv���Ă܂��B
�Ƃ͂����A
���N�Ƀg�C�����R��������������20���A2���ɃV���A���̋쏜�������30���A����������N���邩����Ȃ��B�B(�n�k�ƕx�m�R������ԕ|���B)
�Q�C���A���U�A�e��m�C�Y�ǂ�ɏd����u�����H���̎������u�̊��̗v���ɍ��킹�Ȃ��ƁA�ǂ����ʂ͐��܂�Ȃ��\��������܂��B
���ۖ��Ƃ��āA
���s�ŏI���A������p������o���Ȃ��Ɛg�������o�����A
�V���Ȑ��슈�����o���Ȃ��Ƃ������z�Ƃ������A�z����o���Ȃ��S�z������܂��B
VHF�n�p�[�c�̓��荢�����������āA��Ԏ���Ă��܂��B
�Ƃɂ������ɂ��A�O�ɐi��ōs���ɂ́A�����W�̋@��𑝂₷�̂��d�v�Ɋ����Ă���܂��B
�Ȃ̂ŁA�����I�ɃV�r�A�Ȗ��ł�����悤�ł��B
��AGC-AMP��H�̉��ǂƐV����AGC-AMP��H�����܂��s���`�A
�����āA���Ƃ́APre-AMP��t�o�C�A�X��H�A�t�B���^�[���L�p�Ȋ����ɂ������ł��ˁB
���\�����̏����������ƁA���������ς�����Ƃ��ɑΏ����Â炢�ł����A�A�A
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220425
OWON�̃I�V���ASDS1202�͔M���Ȃ�B
USB�������[�����ƁA������Ȃ�M���B���ɓ\���Ă���V�[���������ꂩ�����Ă�悤�ɂȂ邵�A
���������ł�����ł͂��Ȃ胄�o���Ǝv���AFAN��t���܂����B
�\�ɂ̓t�B���^�[���t�@���K�[�h�A���ɂ̓T�[�N����̃t�@���K�[�h�𒅂��Ă܂��B
���ʂ͍����A����ŁA�������ł��g�������x�ɂȂ�܂����B
���萫�͐V��H�A60MHz���ӂ̃m�C�Y�̒Ⴓ�͋���H���ȂƂ��������B
�g�`�́AFCZ�R�C���̗L���̉e������������A
�������j�A�ŏc���͑ΐ��\�L�ł͂��邪�A�S�ʂ�3�A5�A7�{�̃g�[�����ڗ��B����480MHz�܂ł���̂͋����B������̃��x���͗]��W�͖��������B
�Q�C�����R���g���[���̂�����Ȃ��Ⴂ�̈�ł͐U���̗h�炬�����邪�A���U��̐��������m��Ȃ��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���������قǁAGW�����܂��Ă�̂ɋC���t�����̂�����A�}���ŏH���ɂ�����ƒ������܂������A�������ق�1�i�����t���������ł��B
(�����͎؋��ŃM���M���Ƃ��������ōs�������ł��B�c�Ȃ̂ŏ������Ԃ̗]�T�o�Ă��������B)
���Ƃ́A
AGC-AMP�u��3��H�̊�v���ǂ����邩�ł��ˁB(��2��H�͊�~�X���Ȃ������ł����d�l�ύX�̉��H�����\���܂���)
��3��H���ŏ�����ϑ����邩�H�ŁA�K�[�o�[�f�[�^�o�͂��\�Ȃ̂ŁA
���������قǂ̒l�i�Ɣ[�����H�����ɂ߂Ȃ��Ắc�A
�Ƃ����̂�����܂����A��H�Ɏ藎��������Ƒ����ɒɂ��B
�������A�O������Ȃ�A���ʃx�^GND�̊�ɂ��悤�Ǝv���܂��B
�Ȃ̂ŁA���s�͏C�����Â炢�B
��̌�����U�d���Ƃ̊W�Ȃǂ��C�ɂȂ�͂��܂����A�A�A�A
�����͂���ƁA�L���p�V�^���X�̉e��������܂����AIC�\�P�b�g�d�l�ɂ͎����㑊�������Ȃ舫���ł��B
������͂Ђ���Ƃ����犄�������m��Ȃ��ł��ˁB
������A�����������ׂ˂B
�ŁA�O��ނ̉�H���o������A�ǂꂪ�ǂ����ŁA
�܂��A��H�A��̉��ǂƂȂ��Ă��������m��܂���B
���A����́A�O��Ȃǂɏ������ʂ�A�u�������Ƃ̓K���v�������m�ɂ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł��B
����ŁA���\��������Ηǂ��̂ł����A������Ȃ��̂Łc�A
�����ŁA�t�o�C�A�X��H�APre-AMP�A�t�B���^�[�̌��ʂ�m�肽���ł��ˁB
�m�C�Y�������ƁAAGC-AMP�̃Q�C���R���g���[��������Ɉ��������āA���T�[�W�����\���\�����뜜����܂��B
�܂��A�C���s�[�_���X�ω��̊ɏՍނƂ��Ă������邩���B
�Ȃ̂ŁA�t�B���^�[�́AAGC-AMP�̎�O�̐ݒu�������Č��čl���˂ł��B
�Ƃɂ������ɂ��A�F�����Ȃ��ꍇ�Ƃ����l����ɁA
�܂��A������́A
���炩���߁u�ۑ���܂Ƃ߁v�A�ғ��@�̂ق��֍s���āA�u�܂Ƃ߂āv�����W�ˑΏ����ȁ[�A�A�ƁB�M���Č��Ȃ��Ɣ���Ȃ����ʂ����邵�B
���ƁA���̑���Ȃǂ̋@�B�̏������W�͂������Ǝv���Ă܂��B
�Ƃ͂����A
���N�Ƀg�C�����R��������������20���A2���ɃV���A���̋쏜�������30���A����������N���邩����Ȃ��B�B(�n�k�ƕx�m�R������ԕ|���B)
�Q�C���A���U�A�e��m�C�Y�ǂ�ɏd����u�����H���̎������u�̊��̗v���ɍ��킹�Ȃ��ƁA�ǂ����ʂ͐��܂�Ȃ��\��������܂��B
���ۖ��Ƃ��āA
���s�ŏI���A������p������o���Ȃ��Ɛg�������o�����A
�V���Ȑ��슈�����o���Ȃ��Ƃ������z�Ƃ������A�z����o���Ȃ��S�z������܂��B
VHF�n�p�[�c�̓��荢�����������āA��Ԏ���Ă��܂��B
�Ƃɂ������ɂ��A�O�ɐi��ōs���ɂ́A�����W�̋@��𑝂₷�̂��d�v�Ɋ����Ă���܂��B
�Ȃ̂ŁA�����I�ɃV�r�A�Ȗ��ł�����悤�ł��B
��AGC-AMP��H�̉��ǂƐV����AGC-AMP��H�����܂��s���`�A
�����āA���Ƃ́APre-AMP��t�o�C�A�X��H�A�t�B���^�[���L�p�Ȋ����ɂ������ł��ˁB
���\�����̏����������ƁA���������ς�����Ƃ��ɑΏ����Â炢�ł����A�A�A
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220425
OWON�̃I�V���ASDS1202�͔M���Ȃ�B
USB�������[�����ƁA������Ȃ�M���B���ɓ\���Ă���V�[���������ꂩ�����Ă�悤�ɂȂ邵�A
���������ł�����ł͂��Ȃ胄�o���Ǝv���AFAN��t���܂����B
�\�ɂ̓t�B���^�[���t�@���K�[�h�A���ɂ̓T�[�N����̃t�@���K�[�h�𒅂��Ă܂��B
���ʂ͍����A����ŁA�������ł��g�������x�ɂȂ�܂����B
 ���K�㗝�X��搂��Ƃ��͊������A
T&M Tech�����K�㗝�X�Ƃ����Ă�̂ł����A
�Ή��͂�������Ƃ��ĂāA���{��}�j���A��������܂��B
�\�R�������ɂ́A
�I�E�I���W���p���͋U���炵���ł��B����ȕ��͑����Ă������B
�z�z�f�[�^�������B
�O���猾���Ă邯�ǂڂ������萅���Ǝ҂Ȃǂ��g�b�v�ɏグ�Ă�Google���Ĕƍ߂��ˁB
�ł����āA�l�f�[�^�͌��{����I�I
�H���ł́A���{��T�C�g�̓R�R�����ƁB
http://ja.owontech.com/
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�v�����g�����ƎҁB
Twitter�ɂāA
JLCPCB���{�Ƃ����Ƃ��납��t�H���[���ꂽ�̂ŁA��������Č��悤�Ǝv���܂��B
����PCB�쐬�̊Ԃ���{�̃I�t�B�X����莝�������ȁH
���Ƃ́A�L���ȁuPCBWay�v�Ƃ��H
���ׂČ���ɁA�A
https://xn--p8jqu4215bemxd.com/archives/18938#i-4
10x10cm�̂�5���ł�10���ł�500�~�Ȃ�A�l�i���Ƃ�ł��Ȃ������ł��ˁB
�����̗�ׂĎ����Őؒf���邩���l�����Ȃ��炢�B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�R�C���̊��ȂǂŔ��U����̂��A�uM�����v�ɂ�锭�U���ۂƌ������Ƃ炵���ł��B
�Ȃ̂ŁAFCZ�R�C���ɂ̓V�[���h���{����Ă���ƁAFCZ������̋L���ɂ���܂����B
�A�i�f�o�̃g���C�_���R�C���L���ł������C������B
�ŁA�ŏ��͌o����������̂ŁA�A
�����炪�g�������o�14�����x�B������̂�5��������̂��������Ƃ��ĂƎv���̂ł����A
���̂Ƃ��A���o��20���Ƃ����炢���ȁH�ƔF���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���j�o�[�T�����o�[�W�����̉��ǂƓ��Y�̐V��H���݂ŁA
����ɂ�����Ƃ��̉�H�̉��ǂ͍�������������ł��B
�ŁA����b���́A���ǂ�A�v�����g����삪�l�b�N�ɂȂ肻���ł��ˁB
���ƁA��3��H�APre-AMP�A�t�o�C�A�X��H�A�A�t�B���^�[�AATT�A�A
���j�o�[�T��Ver�̗l�q�����āA���Ɏc��������H�̉��C��Ƃ��o���邩�H�H�Ƃ������ς�����B
���Ƃ́A��ƂȂǂ̔�p�ȂǁA����̂��߂ɂ�������������v�f�͂��̓��ɂ��A
�J���̌�������悤�ɂƁA
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�َ�ʕt���Ƃ����̂́A�lj��������������₷���̂ł����A
V�J�b�g����ꂽ�肵�Ȃ��ŁA�����A��̉�H���ڂ��āA�����Őؒf����Ȃ�Βlj��̗����͔������Ȃ������ł��B
�l�b�g���[�N��GND�A�T�C����������̂ŁA�R�s�y������O�Ƀx�^������K�v��������p�ł��B
�܂�A���̌�̉�H�ύX�͋C���t���Ă�����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�Q�C���̔�����o�������Ƃ��v���܂��āB
���ƁA��́A�َ�ʕt�����s���܂��B
��ؒf�̊��R�̎��ނ̐ؒf���o���邩���B
�ŁA������ƒT���Ă���܂��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220426
��H�����Ȃ�`�F�b�N�����Ƃ���ł��B
���̒i�K�Ń~�X���́A���������Ǝv���܂����c�A�A
���Ƃ́A�x�^GND�ƌ��Ԃ�VIA�ł�������A
��̉�H�������Ɩʕt�����܂��B
�ŁAPCB�Ǝ҂̃t�H�[�}�b�g�ŁA�K�[�o�[�t�@�C���������o���܂��B
���K�㗝�X��搂��Ƃ��͊������A
T&M Tech�����K�㗝�X�Ƃ����Ă�̂ł����A
�Ή��͂�������Ƃ��ĂāA���{��}�j���A��������܂��B
�\�R�������ɂ́A
�I�E�I���W���p���͋U���炵���ł��B����ȕ��͑����Ă������B
�z�z�f�[�^�������B
�O���猾���Ă邯�ǂڂ������萅���Ǝ҂Ȃǂ��g�b�v�ɏグ�Ă�Google���Ĕƍ߂��ˁB
�ł����āA�l�f�[�^�͌��{����I�I
�H���ł́A���{��T�C�g�̓R�R�����ƁB
http://ja.owontech.com/
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�v�����g�����ƎҁB
Twitter�ɂāA
JLCPCB���{�Ƃ����Ƃ��납��t�H���[���ꂽ�̂ŁA��������Č��悤�Ǝv���܂��B
����PCB�쐬�̊Ԃ���{�̃I�t�B�X����莝�������ȁH
���Ƃ́A�L���ȁuPCBWay�v�Ƃ��H
���ׂČ���ɁA�A
https://xn--p8jqu4215bemxd.com/archives/18938#i-4
10x10cm�̂�5���ł�10���ł�500�~�Ȃ�A�l�i���Ƃ�ł��Ȃ������ł��ˁB
�����̗�ׂĎ����Őؒf���邩���l�����Ȃ��炢�B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�R�C���̊��ȂǂŔ��U����̂��A�uM�����v�ɂ�锭�U���ۂƌ������Ƃ炵���ł��B
�Ȃ̂ŁAFCZ�R�C���ɂ̓V�[���h���{����Ă���ƁAFCZ������̋L���ɂ���܂����B
�A�i�f�o�̃g���C�_���R�C���L���ł������C������B
�ŁA�ŏ��͌o����������̂ŁA�A
�����炪�g�������o�14�����x�B������̂�5��������̂��������Ƃ��ĂƎv���̂ł����A
���̂Ƃ��A���o��20���Ƃ����炢���ȁH�ƔF���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���j�o�[�T�����o�[�W�����̉��ǂƓ��Y�̐V��H���݂ŁA
����ɂ�����Ƃ��̉�H�̉��ǂ͍�������������ł��B
�ŁA����b���́A���ǂ�A�v�����g����삪�l�b�N�ɂȂ肻���ł��ˁB
���ƁA��3��H�APre-AMP�A�t�o�C�A�X��H�A�A�t�B���^�[�AATT�A�A
���j�o�[�T��Ver�̗l�q�����āA���Ɏc��������H�̉��C��Ƃ��o���邩�H�H�Ƃ������ς�����B
���Ƃ́A��ƂȂǂ̔�p�ȂǁA����̂��߂ɂ�������������v�f�͂��̓��ɂ��A
�J���̌�������悤�ɂƁA
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�َ�ʕt���Ƃ����̂́A�lj��������������₷���̂ł����A
V�J�b�g����ꂽ�肵�Ȃ��ŁA�����A��̉�H���ڂ��āA�����Őؒf����Ȃ�Βlj��̗����͔������Ȃ������ł��B
�l�b�g���[�N��GND�A�T�C����������̂ŁA�R�s�y������O�Ƀx�^������K�v��������p�ł��B
�܂�A���̌�̉�H�ύX�͋C���t���Ă�����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�Q�C���̔�����o�������Ƃ��v���܂��āB
���ƁA��́A�َ�ʕt�����s���܂��B
��ؒf�̊��R�̎��ނ̐ؒf���o���邩���B
�ŁA������ƒT���Ă���܂��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220426
��H�����Ȃ�`�F�b�N�����Ƃ���ł��B
���̒i�K�Ń~�X���́A���������Ǝv���܂����c�A�A
���Ƃ́A�x�^GND�ƌ��Ԃ�VIA�ł�������A
��̉�H�������Ɩʕt�����܂��B
�ŁAPCB�Ǝ҂̃t�H�[�}�b�g�ŁA�K�[�o�[�t�@�C���������o���܂��B
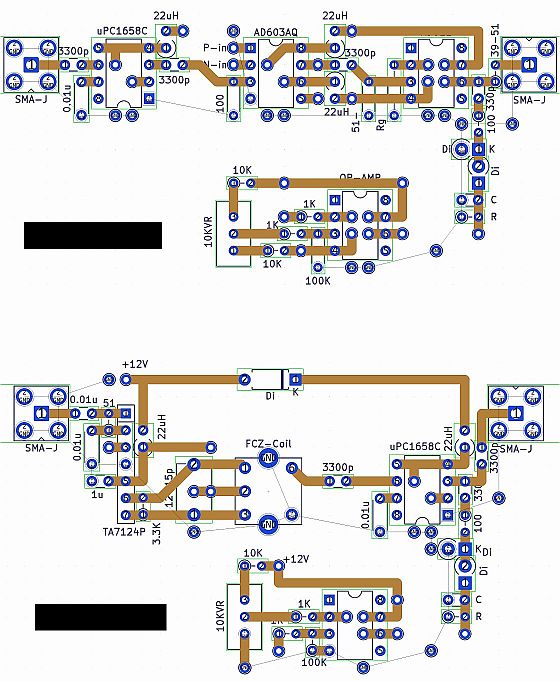 ����27���ɂ́A�����o���邩�ȁH�Ǝv���܂��B
�ŁA
PCBWay�ɏo���Ă݂���A�R���ɎO���ԁA12���ԑ҂��Ă��u�ԐM�҂��v��ԁB
�ǂ��Ȃ��Ă�̂��H�ƃ��b�Z�[�W�𑗂��Ă��������B
220427
�ŁA�L�����Z�����āAFusionPCB�ɂ��܂����B
�ŁA�x����ꎞ�Ԃ̓L�����Z���o����悤�ł����A
���̌�ɂځ[���ƍl���Ăĕs�������܂�A�m�F������~�X�����o�B
�َ�ʕt���̍ہA�x�^��GND���������Ă��B
����́A�܂��A�e�X�g�Ȃ̂Ń��W�X�g���Ηǂ��ł����A
3000�~��Ŏ��s��Ƃ����̂́A���[���������Ȃ��B
�����͖������I�ׂȂ������̂ŁA$22������܂����A�������Ƃ͑����Ǝv���܂��B
��͈���$4.90�Ȃ̂ŁA�u���������ʁv�Ȃ�A����ȂɃP�`��K�v���͂��܂薳�����ȁH�Ǝv���܂����B
��������Ȋ�����̓���ʕt���Ȃ�L�������ł����A��������10����$4.90�Ȃ̂�����A����ȂɕK�v�ȏ�ʂ����������ł��B
FusionPCB��KiCAD�̃K�[�o�[�r���[�A�ł́A�V���N���p�b�h��r�A�ɂ������ĂȂ��̂��ƃh�����f�[�^�̊m�F�݂̂ł����B
���ɁAFusionPCB�̃r���[�A�́A���Ȃ�d�������ł����A�z�F�I�ɂ�����Â炩�����悤�ȁc�A�B
�Ȃ̂ŁAGND��Via�̃`�F�b�N�Ȃ�KiCAD�̉�ʂ₻��3D�r���[�A�̕����ǂ����ȁH�ƁB
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220428
�ŁA�V�^��AGC-AMP��20�`30mV��TA7124P���o���z���C�g��FCZ�R�C����ʉ߂����Ǝv����m�C�Y���f�t�H���g�ł���̂ł����A
���͂ɒ��߂�BNC�������ƁA17��Sec�̃X�p�C�N�m�C�Y���ۂ��̂��o�܂��B�E�`�̊������Ȃ�ǂ��̂ł����A�A
����27���ɂ́A�����o���邩�ȁH�Ǝv���܂��B
�ŁA
PCBWay�ɏo���Ă݂���A�R���ɎO���ԁA12���ԑ҂��Ă��u�ԐM�҂��v��ԁB
�ǂ��Ȃ��Ă�̂��H�ƃ��b�Z�[�W�𑗂��Ă��������B
220427
�ŁA�L�����Z�����āAFusionPCB�ɂ��܂����B
�ŁA�x����ꎞ�Ԃ̓L�����Z���o����悤�ł����A
���̌�ɂځ[���ƍl���Ăĕs�������܂�A�m�F������~�X�����o�B
�َ�ʕt���̍ہA�x�^��GND���������Ă��B
����́A�܂��A�e�X�g�Ȃ̂Ń��W�X�g���Ηǂ��ł����A
3000�~��Ŏ��s��Ƃ����̂́A���[���������Ȃ��B
�����͖������I�ׂȂ������̂ŁA$22������܂����A�������Ƃ͑����Ǝv���܂��B
��͈���$4.90�Ȃ̂ŁA�u���������ʁv�Ȃ�A����ȂɃP�`��K�v���͂��܂薳�����ȁH�Ǝv���܂����B
��������Ȋ�����̓���ʕt���Ȃ�L�������ł����A��������10����$4.90�Ȃ̂�����A����ȂɕK�v�ȏ�ʂ����������ł��B
FusionPCB��KiCAD�̃K�[�o�[�r���[�A�ł́A�V���N���p�b�h��r�A�ɂ������ĂȂ��̂��ƃh�����f�[�^�̊m�F�݂̂ł����B
���ɁAFusionPCB�̃r���[�A�́A���Ȃ�d�������ł����A�z�F�I�ɂ�����Â炩�����悤�ȁc�A�B
�Ȃ̂ŁAGND��Via�̃`�F�b�N�Ȃ�KiCAD�̉�ʂ₻��3D�r���[�A�̕����ǂ����ȁH�ƁB
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220428
�ŁA�V�^��AGC-AMP��20�`30mV��TA7124P���o���z���C�g��FCZ�R�C����ʉ߂����Ǝv����m�C�Y���f�t�H���g�ł���̂ł����A
���͂ɒ��߂�BNC�������ƁA17��Sec�̃X�p�C�N�m�C�Y���ۂ��̂��o�܂��B�E�`�̊������Ȃ�ǂ��̂ł����A�A
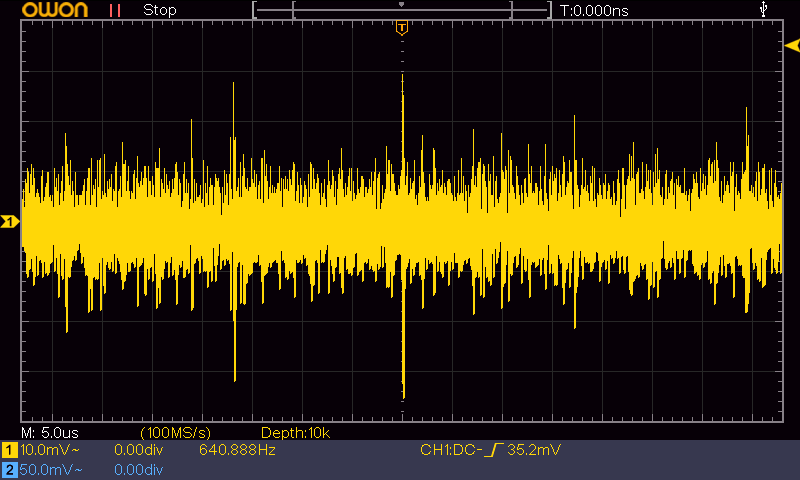 �܂��A700mVpp���x�̃V�O�i���Ȃ̂ł��ꂪ������A�m�C�Y�͓��ݒׂ��郌�x�������m��Ȃ��ł��B
���ƁA�I�i�̃�PC1658C�͌��\�g�����Ȃ�̂ŁA���M�t�B���݂����Ȃ̂�t���������ǂ������H�N�[���X�^�b�t�����C�y�����B
�����̕��́A�Q�C�������\�オ��܂������A���͊��ɂ��\�ꂪ�_�o���ɂ��v���܂��B
���͂ɁA�����A�ɏՍނƂȂ�t�B���^�[��Pre-AMP�AATT�Ȃǂ�t����ƈ��肷�邩���m��܂���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�ŋ߂̍L�ш�AMP�͈����̂ł����AIC�����Ȃ肿�����Ⴂ�̂ŁA���c�t�������Ȃ荢��Ȃ̂ł����A
�����Pre-AMP���Ɏg����A���ȃN�Z���������m���ł��邩���m��܂���B
�����A������A�������Ⴗ����̂ŁA�ǂ���������������Ηǂ��̂��ł��ˁB
���ƁA3GHz������܂ŃQ�C�����L�тĂ�̂ŁA�ւ��Ȉ����͋֕��̂悤�ł��B
SOT-343�́AMEMS���U���SOT-23�����������K�i�̂悤�ŁB�M�̖����܂߁A���c�t����������B
�ڂ���K�i���ASOT-23�ϊ���ɖ�������A��v���ċƎ҂ɍ���ĖႤ���ł��ˁB
����ł́A���̎�̃}�C�N���`�b�v�̐ڍ��́A�N���[�����c�ƃz�b�g�G�A�X�e�[�V�����Ƃ��ACCD�}�C�N���X�R�[�v��p���Ă���Ă�̂����܂����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
��쐬�Ɛؒf�p��ŁA����60MHz�Ȑ���Ɏg�������z���A151000�~���x�ɑ����܂����B(���z250000���炢�H)
�b���͒����͂��Ȃ������ł����A�R�R�ň�U�����̐ߖڂɂ������Ǝv���܂��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
Pre-AMP�ɍL�ш�A���vIC�������Č������v���A
���ƁAAD811�̑�֕i�ɂȂ鏬���߂̃`�b�v�ƕϊ�����B
4000�~�قǒ������܂����B
���������艡�Ɏ�������A���̃f�B�e�N�^�[�P�[�X�ɂ͂߂��邩���ł��B
�����A����͂��Ȃ莎���I�Ȏg�����Ȃ̂ŁA�\��ʂ�̐V�v�̃P�[�X���ǂ��Ǝv���܂��B
�܂��́AAGC-AMP�̑O�ɕt���Ă���`�F�b�N�����ł��ˁB
����͈ĊO���\�����ɍ��邩���ł��B
���ꂪ�ł�����������A�܂��AAGC-AMP���`�F�b�N�������̂ŁA�܂Ƃ߂Ď����Ă��������Ǝv���܂��B
�s���������AGW���ɂȂ邩���m��Ȃ��Ƃ������܂��B
Pre-AMP�����t�o�C�A�X��H��t���������U�����傫��������̂ł����A
�ƂȂ�ƁA�t�o�C�A�X��H�̌��ʂ͐��ŁA�U����10�{�߂��オ���Ă���\���͂���܂��ˁB
�����ŁA�����AGC�̃Q�C���R���g���[����������悤�ɂȂ��Ă����悤�Ȉ�ۂł��B
�E�`�ɂ���f�[�^�������Ƃ���A���T�[�W���~�͖̂��������̂ł����ASIN��COS�̂͂���܂����B
���̎����̃v���Y�}�����ł́A
1�t�����W�͂��Ȃ��̂ł����A�\�z����Ɉʑ����o��o�͂�100�`180mVpp���炢�o�Ă�悤�ł��B
�Ȃ̂ŁAAGC-AMP�o�͂�600�`700mV�Ɏv���܂��̂ŁA
AGC-AMP���͂���̏o�̓m�C�Y��50mV�������Ƃ��Ă��A�ʑ����o��o�͂ł�10�����s���Ȃ��\��������܂��B
�܂��A�m�C�Y�������Ă��A�����ł���A���a���ς�邾���Ȃ̂ŁA�p�x�̈ʑ��m�C�Y�͋ɏ������B
�ڂ�������ɁA�P�[�u���U���Ǝv����X�p�C�N�m�C�Y���A�傫���̂�100mVpp�ł����A�����܂ő傫���̂�0.5�b�Ɉ�炢�ŁA
�P�[�u�����O���ƁATA7124P�ŗL�̃z���C�g�m�C�Y�Ǝv����̂��A20�`30mV�A�܂��A�{���̃V�O�i����1/20�`1/30�ŁA
AGC���\�������Ȃ�A�o�͐U����������Ƒ傫�߂ɂ��āAS/N���グ��肪����܂��B
�ڂ�������ɁA�P�[�u���U���Ǝv����X�p�C�N�m�C�Y���A�傫�����̂�100mVpp�ł����A�����܂ő傫���̂�0.5�b�Ɉ�炢�ŁA
���̓P�[�u�����O���ƁATA7124P�ŗL�̃z���C�g�m�C�Y�Ǝv����̂��A20�`30mV�A�܂��A�{���̃V�O�i��700mV��1/20�`1/30�ŁA
�����āAAGC���\�������Ȃ�A�o�͐U����������Ƒ傫�߂ɂ��āAS/N���グ��肪����܂��B
�Ƃ������ƂŁATA7124P�̃m�C�Y�͒v�����ł͖����Ɗ��҂������ł��B
TA7124P��AGC-AMP�ł����A
�傫�߂̃Q�C��������ƁA�U����10��Sec���x�̗h�炬�������邱�Ƃ������܂����B
�����A�U���̌��g�ϕ���H�ɂ��ʑ��x��ɂ�鐧��̔��U���u�����Ɂv�N���Ă�悤�ł��B
���ۂɂ́A���a���h�炮�݂̂Ȃ̂ŁA�M����atan�����l�͋���Ȃ��ł����A�A
�����ʼn����s�s�����o��A���䑬�x�����X���Ƃ��Č��܂��B
���ہA���d���̃m�C�Y���l���Ă��A���ɑf�����Q�C�����������x�������ǂ��̂��Ǝv���܂��B
�Ƃ肠�����A�Q�C���R���g���[�����x���ꌅ�����āA�U���������Ă����܂����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�ł����āA�A
��̉�H�̓������܂Ƃ߂������Ȃ̂ł����A
����H�́A���͂̃R���f�B�V�����Ŗ\��₷���B�����U�C���ɂȂ�₷���B
TA7124P�̉�H�͂��̐���ł�m�C�Y���傫�߁B
��ԋC�ɂȂ�̂��A����炪�ǂ��o�邩�H�ł��ˁB
�O�҂́A���͂𐮍������邱�Ƃ��ŏd�v�ł����A�N�b�V�����i�K�ɂȂ郂�m���͂߂�̂������葁���悤�ł��B
��҂́A��H�̈ꕔ�̃Q�C����������̂��ǂ��̂ł����AAGC�ő傫�߂ɏo���āA���Ƃ�ATT�ōi��̂���肩���B
�Ƃɂ����A�g�����ɂȂ邱�Ƃ��F�����ł��ˁB�B
���o�͂Ƃ��Ƃ̑���������܂��̂ŁA�������́A���ۂɎg���Ă���Ă݂Ȃ��ƒ͂߂Ȃ����ȂƁB
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�����āA�V����AGC-AMP�̊�̉�H�ɂ́A
�uAD603AQ�v�Ɓu��PC1658C�v���K�v�Ȃ̂ŁA���j�܂łɑ����Ɨǂ��̂ł����A�A�A
��PC1658C�́A����H�̕ʂ̃��c����ꎞ�I�ɔ�������Ă��s���܂����A�O�҂����ł��B
���Ƃ́A�H���̃p�[�c�������Ă���Ȃ�A�ǂ��ɂ�����܂ŏo�������ł��B
����ŁA���܂������Ηǂ��̂ł����A
���i�́A�ꉞ�A����H�Ɠ����A��PC1658C�̃t���Q�C���ł��B
�Ȃ̂ŁA���̂܂܂Ȃ�A�X���͎��ē��͂ɐ_�o���ȕ������o��Ǝv���܂��B
�ł��A�ɏՍނ��g������A�A�Ғ�R�ŃQ�C��������������o���܂��B
�Ȃ��ǂ����ł̂��Ƃ�̓��e�������Ă�������
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
��������AGC-AMP�̃X�y�b�N������ƁA�ő��0.3��Vpp��0.7�`1Vpp�ɂ܂ŏグ��̂��W���I���ȁH�Ɗ����܂����B
�̂�70dB ���x���ȁ[�A�ƁB
�ŁA������ō�����̂��ǂ̒��x�Ȃ̂��Ƃ����ƁH���͂̐U��������Ȃ����߁A�f�[�^�V�[�g����̗\�z�����o���܂��A
OP-AMP�̐��\�ɂ����E����邽�ߔ���Ȃ������������ł��B
TA7124P�̂́A���Ȃ����ς����āA45+38dB��83dB�Əo�܂����A����Ȃɍ����̂��ȁH�Ƃ͎v���܂��B
�Ƃ����̂��A����H�̕����������炢�������ďo�ĂāA�A38�{18�{�H-6dB�ł��B
�u�H�v�́A�ݒ�l��15�{�ł���OP-AMP�̒�d���ȓ����h���C�u�̓L�c�����߂��Ȃ藎���Ă�Ǝv���܂��B
20dB���s���Ȃ������A�A�ƁA�v���Ă���܂��B-6��Z�����̂��߁A�Q�C���������܂��B
�Ȃ̂ŁA70dB�s���Ă邩�ȁ[�A�A�Ƃ������x�ɂ��v���܂��B
�܂��A�Q�C���͈��ȏ�͌����I�ł͖����A���߂Ă��A�Ȃ��Ȃ����܂��s���Ȃ��Ǝv���܂��̂ŁA���̒l���낤�Ǝv���Ă܂��B
�t�H�gDi�̗�p�ȂǓ��ʂȏꍇ�ɁAPre-AMP��v����̂����ʂȂ̂����m��܂���B�B
���Ƃ́A�����A�����̃��[�U�[���̃p���[��60MHz���C���̌v���@��̐������Ƃ������I�ȃ��m�ł��ˁB
�ł��A�������H����ԃn�C�Q�C���ŁA�Q�C���̒����͈͂��傫���̂������̗\��ł��B���U����Ԃ̓G�ł��B
�Ȃ̂ŁA�K�v�Ȃ��Ȃ�A���̕��͋A�Ғ�R�ŏ��i�̃Q�C���𗎂Ƃ������m��Ȃ��ł��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���ƁA�V�����ҋ��ɁA���݁A����YM-200�ȃP�[�X�ɓ���Ă�̂ł����A
������A�ۑ肪����A�傫�ȓS�P�[�X���ǂ��Ƃ����邩���H�Ƃ����l���ĂāB�B�܂��A����قlje���͖������ȁ[�A�Ƃ��B
����́A�V�[���h�����A���U�Ɋւ��Ă̑�̗v�f�������ł��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�ł����āA�R�������[�h�m�C�Y�̗}�~�ł����A
�O�ɁA�t�F���C�g�̃g�����X�̂悤�ȃR�A��1.5D2V�����邮�銪���Ƃ������C�����܂����A
�ʐ^�������܂����B�摜���������ł����A�ATDK���ł��B
�p������ĂȂ���A�����A�ǂ����Ŗ����Ă�u�c���Ǝv���܂��B
���ӂ��ׂ��Ƃ���́A�S�̂�≏���Ȃ��Ƌt�ɕςȂƂ��œd��������Ă��܂������m��܂���B
FCZ�R�C���ȃg�����X�̕t����Pre-AMP�Ŋ����ɂ�炻���Ǝv�����̂ł����A�A
������̕�������ȁ[�Ǝv���Ă����̂ł����A�Ȃɂ��̐U���X�y�N�g�����o�Ă܂��̂ŁA������ƍl�����ł��B
(FCZ�R�C���Ő�Ȃ����Ă��A�f�B�e�N�^���Ɛ≏�ŕ����Ă�Γ��������H�ł��ˁB)
FCZ�R�C���ō�����t�B���^�[���A�≏�������邱�Ƃ��\�ł����A�A����GND���q���č���Ă܂��ˁB
�≏�R�l�N�^���ςȌ��ۂ�����̂����m��Ȃ��̂ŁA����̉ۑ�Ƃ��čl���܂��B
�܂��A���d�m�C�Y���o�����Ƃɑ��肵�������̐M��������ꍇ�������悤�Ȃ̂ŁA���ۂ͂��܂�C�ɂȂ�Ȃ������H
����CH���̑����ɂ���Ď�܂������M�������܂�������̂��K�v�Ȋ����ł��傤���H
�NjL��
TA7124P�̃Q�C���̖��́AFCZ�R�C����3�F1���x�Ŋ�����Ă�g�����X�ł����āA10dB���x������Ƃ����̂������Ă܂����B
����ƁA����ρA70dB���傢�Ƃ��������ł��ˁB
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
[EOF]
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
PCBWay�ŋC�ɂȂ��Ă��̂ł����A
�����̕������~�܂��Ă�݂����ł��ˁB
�ƂȂ�ƁA��͑����Ă���̂������ɒx��邩���H�H
�ŁA
�L�ш�ȃ`�b�vIC��p����Pre-AMP�Ȃ̂ł����A
�v�����������́A�uBGA420�v�Ƃ������߂̃`�b�v���g�����Ǝv�����̂ł����A
�]��ɂ����������āA�A�A�Ȃ̂ŁA
�H���̃`�b�v�ƃR���f���T�[����������ꂽ�L�b�g�ȃ��m�ɂ��܂����B
������������āA�g�������ł��B
�O�҂̓Q�C����NF�̃X�y�b�N���ǂ��̂ł����A3GHz�܂ŐL�тĂ�̂͋t���ʂ����B
�ʑ��]�T�Ƃ��ǂ��Ȃ��Ă�̂�����Ȃ��̂ŁA�P�ɁA�X�y�b�N���Ă����̒ʂ�ɍs�����͕s���Ȃ̂ŁA
�Ƃ肠�����A���̊�����̃��m���s���邩�ȁ[�Ɗ����Ă܂��B
AMP�ł̃m�C�Y������������A3SK121�ȃK���q�f(GaAs)��FET���ǂ��̂����ł����A
����ȑO�̐U���X�y�N�g���̖�肪����ł��ˁB�����_�A�����s���Ȃ̂ŁB
�ɂ���5��Sec�̐U����0.5mSec�����ŚX���Ă�炵���̂ŁA
�{���I�ɂ́A5��Sec�̕��̐U�����ǂ����痈��̂��H�ł��ˁB
�C�ɂȂ�̂͋t�o�C�A�X�o�C�p�X�p��22��H�̃C���_�N�^�̑��p�����邯�ǁc�A�����0.1��F�Łc�A�A
�P����LC���U���l���Ă݂��0.11MHz�c�A2���݂��l���Ă��A0.15MHz�A�A
�܂��A�I�[�_�[�I�ɂ͋߂����ȁH
�c���ƃ}�Y�������B
���̍L�ш�Pre-AMP�ł����l�ɍ���Ď����悤�Ȍ��ۂ��o��悤�Ȃ�A�����ς��˂Ȃ�Ȃ��B
AGC-AMP�ł��o�����ςł��ˁB
�����AC���f�J�����邾�������ǁc�B�_����������L���H�A
���Ҕ������Njt�ɏ�����������đ�����g���O�ɒǂ��o���Ă݂�݂邱�ƂɁH�B�B
���ւ̔��Y�^�ɂȂ��Ă����`�c�A�A
�Ƃɂ����A���ΐ��O���t�ŃX�y�N�g��������ɁA�m�C�Y�̐U���͒Ⴍ�Ă��A���\�o�Ă�悤�Ȃ̂ŁA
�����ʑ����Ɍ��\�����y�Ԃ��낤�Ƃ������Ƃ��Z�����Ɣ��f���܂����B
�u���t�^�v��AGC-AMP�̌����ł����A
��H�}���c���Ă��̂Ō��܂����B
�܂��A���͂�-3dB�̃Ό^��ATT�A������LC��BPF���W���[��(����TA7124P�Ɠ���������TV�p)��ʂ��܂��B�����Ȃ�s���Ǝv���܂��B
15dB��RFAMP�pIC���6�ŁA90dB�������܂��B
���̔{�����ƁA�����A���U���Ă�ꍇ�����邩�Ǝv���܂��B
�����āA�o�͂��I�[�o�h���C�u��ԂŁA20dBm�œ��ł��Ȃ̂ŋ�`�g�̂悤�ȐU���Řc��ł���͂��ł��B
�������A�s��BPF������A����ŁA����X�y�N�g���ȊO���X�g�b�v���A�g�`�����`����܂��B
���̌�A�U�������p��VATT(�o���A�u��ATT)�_�C�I�[�h��ʂ�K��l�̐U���ɏo�͂�����B
�����āA-3dB�̃Ό^��ATT��ʂ��B
�Ƃ����d�g�݂ł��B
���U�Ɋւ��ẮA���o�͂�BPF������܂����A���o�͂Ɋɏp�Ɍy�x�́u�Ό^��ATT�v�����Ă�g�R�ł��ˁB
�܂�ɏՍ�2�N�b�V����x2��4����Ă銴���ł��B���͂ȓ��o�͂̕ی�ɂ͂Ȃ�Ǝv���܂��B
���ł��ɂ����āA�g�`�𐮌`������̂ŁA���̓��x�����傫���ƃm�C�Y���ڗ��Ǝv���܂��B
�������AAGC-AMP���āA�Q�C���R���g���[���͈͂����\�����̂ŁA���قǃg���u���ɂȂ�Ȃ��Ƃ��������ł��B
�܂��A�m�C�Y���o�Ă��A�ʑ��̃m�C�Y�ł͖�������قNjC�ɂ��Ȃ��Ƃ������m�ł��ˁB
�܂��A���䂵�ĂȂ��̂ŁAAGC�ƌĂԂ̂��s���ȑ��݂ł��ˁB
�����āA90dB��ATT-6dB�ł�����A�Q�C���͌��\���߂��Ǝv���܂��B
�������M���ɂ͌��\�L�������ł�������IC��NF=5.5�Ȃ̂ŁA�m�C�Y�͋����o�₷���ł��ˁB
NF�͑��������ۂ̃m�C�Y�̑����ł����A
TA7124P�̂悤�ɓ��͎G����IC�����Łu���ʔ������Ă���v�̂�����̂ŁA�����M�����ƁA�\�R���d�v�Ȋϓ_�ɂȂ�܂��B
TA7124P��p����AMP��6dbm�Ƒ傫�ȏo�͂̎�M��z�肵�Ă邽�߁A
�������A�Q�C���R���g���[������O�Ɍ����������Ă���̂Ȃ̂ŁA
����ɂ���ĎS/N��3�{���x�ǂ��Ȃ���ʂł͂��銴���B
����AGC-AMP�̌�i�ɂ���s��BPF�́A���g���Ă�R�̎��ނɓ��ꂽ�t�B���^�[�ƌ��\�����\���ł��B
�������A������́A�R�C���̈ꎟ���݂̂̎d�l�ł��B�܂�g�����X�\���ɂȂ��Ă��Ȃ��B
�O�i�ƌ�i�ɓ���BPF��p���Ȃ������̂́A�����A��i�ł̓p���[���傫�����邩�炾�Ǝv���܂��B
������AGC-AMP�̓��͂ɂ�锭�U���A���-1dB��T�^��ATT��t���邾���ŏ����܂��B
��̂�AGC-AMP�ɂ����āA�����핔���̃Q�C�����傫���o��Ȃ�A���̕�ATT��t���āA
���o�͊��̕ϓ��ɂ�锭�U�Ȃ�}����ׂ��ƍl���č���Ă�悤�ł��B
�������m�ł́A�\��dB�̌����������Ă�Ƃ��������ł��B
���������Ɋ����Ă���̂ŁA����̉�H�͑f�̏�ԂŃQ�C�����f�J���̂ŁA
�ɏՍނ̕ی������悤�ɂ������ł��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���ƁA�ʑ����o��̋K�i���o�Ă��܂����B
����͐��i�ɂ����͂����Ǝv���܂����A
�o�͂�150mVpp�Ƃ���̂ŁA�\�z�Ƒ�̕ς��Ȃ��ł��ˁB
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�ł����āA
�����x��AGC-AMP��p���āA�o�͂��������̂ŁA
�������グ��ȊO�ɁA��m�C�Y��Pre-AMP��H�͗L���ł͂���Ǝv���܂��B
Pre-AMP��H�̃o�C�p�X�p�X�p��L�ƕ����p�Ƃ�����GND�ւ̃p�X�R����C�ł����A
100��H��10��F�σZ����33�{���g���������g�ɑ���C���s�[�_���X�����Ƃ��܂��B
�����1000��F��OS�R���f���T�[����ESR�R���f���T�[��������ΐU���͖�薳�������邩�ȁH�Ǝv���܂��B
�Ƃ肠�����́A
�Y�킳���ς�C���_�N�^�[�̃`���[�N��H�����ă`�F�b�N���āA�������`���[�N�R�C���ƕ���C�̋��ł��邱�Ƃ̊m�F���K�v�ł��ˁB
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220430
�Ƃ���ŁAAGC-AMP��17��Sec�����ɏo��A�X�p�C�N�m�C�Y�����ǁA
�ǂ����A�X�C�b�`���O�d���A�_�v�^�̂悤�ł���B
�A�_�v�^��ς���Ǝ������傫�����ς��B
�����A�o�������͒x���Ă��A
�u�ԓI�ɑ����X�p�C�N�Ȃ̂ŁA�ǂ��������Ă��Ă�̂��A�A�A
�H���́A
AD-K120P100
�́A�����߂�����
AD-E120P150
�̕��́A���\�傫�ȃm�C�Y���o��B
�܂��A700mVpp���x�̃V�O�i���Ȃ̂ł��ꂪ������A�m�C�Y�͓��ݒׂ��郌�x�������m��Ȃ��ł��B
���ƁA�I�i�̃�PC1658C�͌��\�g�����Ȃ�̂ŁA���M�t�B���݂����Ȃ̂�t���������ǂ������H�N�[���X�^�b�t�����C�y�����B
�����̕��́A�Q�C�������\�オ��܂������A���͊��ɂ��\�ꂪ�_�o���ɂ��v���܂��B
���͂ɁA�����A�ɏՍނƂȂ�t�B���^�[��Pre-AMP�AATT�Ȃǂ�t����ƈ��肷�邩���m��܂���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�ŋ߂̍L�ш�AMP�͈����̂ł����AIC�����Ȃ肿�����Ⴂ�̂ŁA���c�t�������Ȃ荢��Ȃ̂ł����A
�����Pre-AMP���Ɏg����A���ȃN�Z���������m���ł��邩���m��܂���B
�����A������A�������Ⴗ����̂ŁA�ǂ���������������Ηǂ��̂��ł��ˁB
���ƁA3GHz������܂ŃQ�C�����L�тĂ�̂ŁA�ւ��Ȉ����͋֕��̂悤�ł��B
SOT-343�́AMEMS���U���SOT-23�����������K�i�̂悤�ŁB�M�̖����܂߁A���c�t����������B
�ڂ���K�i���ASOT-23�ϊ���ɖ�������A��v���ċƎ҂ɍ���ĖႤ���ł��ˁB
����ł́A���̎�̃}�C�N���`�b�v�̐ڍ��́A�N���[�����c�ƃz�b�g�G�A�X�e�[�V�����Ƃ��ACCD�}�C�N���X�R�[�v��p���Ă���Ă�̂����܂����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
��쐬�Ɛؒf�p��ŁA����60MHz�Ȑ���Ɏg�������z���A151000�~���x�ɑ����܂����B(���z250000���炢�H)
�b���͒����͂��Ȃ������ł����A�R�R�ň�U�����̐ߖڂɂ������Ǝv���܂��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
Pre-AMP�ɍL�ш�A���vIC�������Č������v���A
���ƁAAD811�̑�֕i�ɂȂ鏬���߂̃`�b�v�ƕϊ�����B
4000�~�قǒ������܂����B
���������艡�Ɏ�������A���̃f�B�e�N�^�[�P�[�X�ɂ͂߂��邩���ł��B
�����A����͂��Ȃ莎���I�Ȏg�����Ȃ̂ŁA�\��ʂ�̐V�v�̃P�[�X���ǂ��Ǝv���܂��B
�܂��́AAGC-AMP�̑O�ɕt���Ă���`�F�b�N�����ł��ˁB
����͈ĊO���\�����ɍ��邩���ł��B
���ꂪ�ł�����������A�܂��AAGC-AMP���`�F�b�N�������̂ŁA�܂Ƃ߂Ď����Ă��������Ǝv���܂��B
�s���������AGW���ɂȂ邩���m��Ȃ��Ƃ������܂��B
Pre-AMP�����t�o�C�A�X��H��t���������U�����傫��������̂ł����A
�ƂȂ�ƁA�t�o�C�A�X��H�̌��ʂ͐��ŁA�U����10�{�߂��オ���Ă���\���͂���܂��ˁB
�����ŁA�����AGC�̃Q�C���R���g���[����������悤�ɂȂ��Ă����悤�Ȉ�ۂł��B
�E�`�ɂ���f�[�^�������Ƃ���A���T�[�W���~�͖̂��������̂ł����ASIN��COS�̂͂���܂����B
���̎����̃v���Y�}�����ł́A
1�t�����W�͂��Ȃ��̂ł����A�\�z����Ɉʑ����o��o�͂�100�`180mVpp���炢�o�Ă�悤�ł��B
�Ȃ̂ŁAAGC-AMP�o�͂�600�`700mV�Ɏv���܂��̂ŁA
AGC-AMP���͂���̏o�̓m�C�Y��50mV�������Ƃ��Ă��A�ʑ����o��o�͂ł�10�����s���Ȃ��\��������܂��B
�܂��A�m�C�Y�������Ă��A�����ł���A���a���ς�邾���Ȃ̂ŁA�p�x�̈ʑ��m�C�Y�͋ɏ������B
�ڂ�������ɁA�P�[�u���U���Ǝv����X�p�C�N�m�C�Y���A�傫���̂�100mVpp�ł����A�����܂ő傫���̂�0.5�b�Ɉ�炢�ŁA
�P�[�u�����O���ƁATA7124P�ŗL�̃z���C�g�m�C�Y�Ǝv����̂��A20�`30mV�A�܂��A�{���̃V�O�i����1/20�`1/30�ŁA
AGC���\�������Ȃ�A�o�͐U����������Ƒ傫�߂ɂ��āAS/N���グ��肪����܂��B
�ڂ�������ɁA�P�[�u���U���Ǝv����X�p�C�N�m�C�Y���A�傫�����̂�100mVpp�ł����A�����܂ő傫���̂�0.5�b�Ɉ�炢�ŁA
���̓P�[�u�����O���ƁATA7124P�ŗL�̃z���C�g�m�C�Y�Ǝv����̂��A20�`30mV�A�܂��A�{���̃V�O�i��700mV��1/20�`1/30�ŁA
�����āAAGC���\�������Ȃ�A�o�͐U����������Ƒ傫�߂ɂ��āAS/N���グ��肪����܂��B
�Ƃ������ƂŁATA7124P�̃m�C�Y�͒v�����ł͖����Ɗ��҂������ł��B
TA7124P��AGC-AMP�ł����A
�傫�߂̃Q�C��������ƁA�U����10��Sec���x�̗h�炬�������邱�Ƃ������܂����B
�����A�U���̌��g�ϕ���H�ɂ��ʑ��x��ɂ�鐧��̔��U���u�����Ɂv�N���Ă�悤�ł��B
���ۂɂ́A���a���h�炮�݂̂Ȃ̂ŁA�M����atan�����l�͋���Ȃ��ł����A�A
�����ʼn����s�s�����o��A���䑬�x�����X���Ƃ��Č��܂��B
���ہA���d���̃m�C�Y���l���Ă��A���ɑf�����Q�C�����������x�������ǂ��̂��Ǝv���܂��B
�Ƃ肠�����A�Q�C���R���g���[�����x���ꌅ�����āA�U���������Ă����܂����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�ł����āA�A
��̉�H�̓������܂Ƃ߂������Ȃ̂ł����A
����H�́A���͂̃R���f�B�V�����Ŗ\��₷���B�����U�C���ɂȂ�₷���B
TA7124P�̉�H�͂��̐���ł�m�C�Y���傫�߁B
��ԋC�ɂȂ�̂��A����炪�ǂ��o�邩�H�ł��ˁB
�O�҂́A���͂𐮍������邱�Ƃ��ŏd�v�ł����A�N�b�V�����i�K�ɂȂ郂�m���͂߂�̂������葁���悤�ł��B
��҂́A��H�̈ꕔ�̃Q�C����������̂��ǂ��̂ł����AAGC�ő傫�߂ɏo���āA���Ƃ�ATT�ōi��̂���肩���B
�Ƃɂ����A�g�����ɂȂ邱�Ƃ��F�����ł��ˁB�B
���o�͂Ƃ��Ƃ̑���������܂��̂ŁA�������́A���ۂɎg���Ă���Ă݂Ȃ��ƒ͂߂Ȃ����ȂƁB
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�����āA�V����AGC-AMP�̊�̉�H�ɂ́A
�uAD603AQ�v�Ɓu��PC1658C�v���K�v�Ȃ̂ŁA���j�܂łɑ����Ɨǂ��̂ł����A�A�A
��PC1658C�́A����H�̕ʂ̃��c����ꎞ�I�ɔ�������Ă��s���܂����A�O�҂����ł��B
���Ƃ́A�H���̃p�[�c�������Ă���Ȃ�A�ǂ��ɂ�����܂ŏo�������ł��B
����ŁA���܂������Ηǂ��̂ł����A
���i�́A�ꉞ�A����H�Ɠ����A��PC1658C�̃t���Q�C���ł��B
�Ȃ̂ŁA���̂܂܂Ȃ�A�X���͎��ē��͂ɐ_�o���ȕ������o��Ǝv���܂��B
�ł��A�ɏՍނ��g������A�A�Ғ�R�ŃQ�C��������������o���܂��B
�Ȃ��ǂ����ł̂��Ƃ�̓��e�������Ă�������
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
��������AGC-AMP�̃X�y�b�N������ƁA�ő��0.3��Vpp��0.7�`1Vpp�ɂ܂ŏグ��̂��W���I���ȁH�Ɗ����܂����B
�̂�70dB ���x���ȁ[�A�ƁB
�ŁA������ō�����̂��ǂ̒��x�Ȃ̂��Ƃ����ƁH���͂̐U��������Ȃ����߁A�f�[�^�V�[�g����̗\�z�����o���܂��A
OP-AMP�̐��\�ɂ����E����邽�ߔ���Ȃ������������ł��B
TA7124P�̂́A���Ȃ����ς����āA45+38dB��83dB�Əo�܂����A����Ȃɍ����̂��ȁH�Ƃ͎v���܂��B
�Ƃ����̂��A����H�̕����������炢�������ďo�ĂāA�A38�{18�{�H-6dB�ł��B
�u�H�v�́A�ݒ�l��15�{�ł���OP-AMP�̒�d���ȓ����h���C�u�̓L�c�����߂��Ȃ藎���Ă�Ǝv���܂��B
20dB���s���Ȃ������A�A�ƁA�v���Ă���܂��B-6��Z�����̂��߁A�Q�C���������܂��B
�Ȃ̂ŁA70dB�s���Ă邩�ȁ[�A�A�Ƃ������x�ɂ��v���܂��B
�܂��A�Q�C���͈��ȏ�͌����I�ł͖����A���߂Ă��A�Ȃ��Ȃ����܂��s���Ȃ��Ǝv���܂��̂ŁA���̒l���낤�Ǝv���Ă܂��B
�t�H�gDi�̗�p�ȂǓ��ʂȏꍇ�ɁAPre-AMP��v����̂����ʂȂ̂����m��܂���B�B
���Ƃ́A�����A�����̃��[�U�[���̃p���[��60MHz���C���̌v���@��̐������Ƃ������I�ȃ��m�ł��ˁB
�ł��A�������H����ԃn�C�Q�C���ŁA�Q�C���̒����͈͂��傫���̂������̗\��ł��B���U����Ԃ̓G�ł��B
�Ȃ̂ŁA�K�v�Ȃ��Ȃ�A���̕��͋A�Ғ�R�ŏ��i�̃Q�C���𗎂Ƃ������m��Ȃ��ł��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���ƁA�V�����ҋ��ɁA���݁A����YM-200�ȃP�[�X�ɓ���Ă�̂ł����A
������A�ۑ肪����A�傫�ȓS�P�[�X���ǂ��Ƃ����邩���H�Ƃ����l���ĂāB�B�܂��A����قlje���͖������ȁ[�A�Ƃ��B
����́A�V�[���h�����A���U�Ɋւ��Ă̑�̗v�f�������ł��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�ł����āA�R�������[�h�m�C�Y�̗}�~�ł����A
�O�ɁA�t�F���C�g�̃g�����X�̂悤�ȃR�A��1.5D2V�����邮�銪���Ƃ������C�����܂����A
�ʐ^�������܂����B�摜���������ł����A�ATDK���ł��B
�p������ĂȂ���A�����A�ǂ����Ŗ����Ă�u�c���Ǝv���܂��B
���ӂ��ׂ��Ƃ���́A�S�̂�≏���Ȃ��Ƌt�ɕςȂƂ��œd��������Ă��܂������m��܂���B
FCZ�R�C���ȃg�����X�̕t����Pre-AMP�Ŋ����ɂ�炻���Ǝv�����̂ł����A�A
������̕�������ȁ[�Ǝv���Ă����̂ł����A�Ȃɂ��̐U���X�y�N�g�����o�Ă܂��̂ŁA������ƍl�����ł��B
(FCZ�R�C���Ő�Ȃ����Ă��A�f�B�e�N�^���Ɛ≏�ŕ����Ă�Γ��������H�ł��ˁB)
FCZ�R�C���ō�����t�B���^�[���A�≏�������邱�Ƃ��\�ł����A�A����GND���q���č���Ă܂��ˁB
�≏�R�l�N�^���ςȌ��ۂ�����̂����m��Ȃ��̂ŁA����̉ۑ�Ƃ��čl���܂��B
�܂��A���d�m�C�Y���o�����Ƃɑ��肵�������̐M��������ꍇ�������悤�Ȃ̂ŁA���ۂ͂��܂�C�ɂȂ�Ȃ������H
����CH���̑����ɂ���Ď�܂������M�������܂�������̂��K�v�Ȋ����ł��傤���H
�NjL��
TA7124P�̃Q�C���̖��́AFCZ�R�C����3�F1���x�Ŋ�����Ă�g�����X�ł����āA10dB���x������Ƃ����̂������Ă܂����B
����ƁA����ρA70dB���傢�Ƃ��������ł��ˁB
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
[EOF]
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
PCBWay�ŋC�ɂȂ��Ă��̂ł����A
�����̕������~�܂��Ă�݂����ł��ˁB
�ƂȂ�ƁA��͑����Ă���̂������ɒx��邩���H�H
�ŁA
�L�ш�ȃ`�b�vIC��p����Pre-AMP�Ȃ̂ł����A
�v�����������́A�uBGA420�v�Ƃ������߂̃`�b�v���g�����Ǝv�����̂ł����A
�]��ɂ����������āA�A�A�Ȃ̂ŁA
�H���̃`�b�v�ƃR���f���T�[����������ꂽ�L�b�g�ȃ��m�ɂ��܂����B
������������āA�g�������ł��B
�O�҂̓Q�C����NF�̃X�y�b�N���ǂ��̂ł����A3GHz�܂ŐL�тĂ�̂͋t���ʂ����B
�ʑ��]�T�Ƃ��ǂ��Ȃ��Ă�̂�����Ȃ��̂ŁA�P�ɁA�X�y�b�N���Ă����̒ʂ�ɍs�����͕s���Ȃ̂ŁA
�Ƃ肠�����A���̊�����̃��m���s���邩�ȁ[�Ɗ����Ă܂��B
AMP�ł̃m�C�Y������������A3SK121�ȃK���q�f(GaAs)��FET���ǂ��̂����ł����A
����ȑO�̐U���X�y�N�g���̖�肪����ł��ˁB�����_�A�����s���Ȃ̂ŁB
�ɂ���5��Sec�̐U����0.5mSec�����ŚX���Ă�炵���̂ŁA
�{���I�ɂ́A5��Sec�̕��̐U�����ǂ����痈��̂��H�ł��ˁB
�C�ɂȂ�̂͋t�o�C�A�X�o�C�p�X�p��22��H�̃C���_�N�^�̑��p�����邯�ǁc�A�����0.1��F�Łc�A�A
�P����LC���U���l���Ă݂��0.11MHz�c�A2���݂��l���Ă��A0.15MHz�A�A
�܂��A�I�[�_�[�I�ɂ͋߂����ȁH
�c���ƃ}�Y�������B
���̍L�ш�Pre-AMP�ł����l�ɍ���Ď����悤�Ȍ��ۂ��o��悤�Ȃ�A�����ς��˂Ȃ�Ȃ��B
AGC-AMP�ł��o�����ςł��ˁB
�����AC���f�J�����邾�������ǁc�B�_����������L���H�A
���Ҕ������Njt�ɏ�����������đ�����g���O�ɒǂ��o���Ă݂�݂邱�ƂɁH�B�B
���ւ̔��Y�^�ɂȂ��Ă����`�c�A�A
�Ƃɂ����A���ΐ��O���t�ŃX�y�N�g��������ɁA�m�C�Y�̐U���͒Ⴍ�Ă��A���\�o�Ă�悤�Ȃ̂ŁA
�����ʑ����Ɍ��\�����y�Ԃ��낤�Ƃ������Ƃ��Z�����Ɣ��f���܂����B
�u���t�^�v��AGC-AMP�̌����ł����A
��H�}���c���Ă��̂Ō��܂����B
�܂��A���͂�-3dB�̃Ό^��ATT�A������LC��BPF���W���[��(����TA7124P�Ɠ���������TV�p)��ʂ��܂��B�����Ȃ�s���Ǝv���܂��B
15dB��RFAMP�pIC���6�ŁA90dB�������܂��B
���̔{�����ƁA�����A���U���Ă�ꍇ�����邩�Ǝv���܂��B
�����āA�o�͂��I�[�o�h���C�u��ԂŁA20dBm�œ��ł��Ȃ̂ŋ�`�g�̂悤�ȐU���Řc��ł���͂��ł��B
�������A�s��BPF������A����ŁA����X�y�N�g���ȊO���X�g�b�v���A�g�`�����`����܂��B
���̌�A�U�������p��VATT(�o���A�u��ATT)�_�C�I�[�h��ʂ�K��l�̐U���ɏo�͂�����B
�����āA-3dB�̃Ό^��ATT��ʂ��B
�Ƃ����d�g�݂ł��B
���U�Ɋւ��ẮA���o�͂�BPF������܂����A���o�͂Ɋɏp�Ɍy�x�́u�Ό^��ATT�v�����Ă�g�R�ł��ˁB
�܂�ɏՍ�2�N�b�V����x2��4����Ă銴���ł��B���͂ȓ��o�͂̕ی�ɂ͂Ȃ�Ǝv���܂��B
���ł��ɂ����āA�g�`�𐮌`������̂ŁA���̓��x�����傫���ƃm�C�Y���ڗ��Ǝv���܂��B
�������AAGC-AMP���āA�Q�C���R���g���[���͈͂����\�����̂ŁA���قǃg���u���ɂȂ�Ȃ��Ƃ��������ł��B
�܂��A�m�C�Y���o�Ă��A�ʑ��̃m�C�Y�ł͖�������قNjC�ɂ��Ȃ��Ƃ������m�ł��ˁB
�܂��A���䂵�ĂȂ��̂ŁAAGC�ƌĂԂ̂��s���ȑ��݂ł��ˁB
�����āA90dB��ATT-6dB�ł�����A�Q�C���͌��\���߂��Ǝv���܂��B
�������M���ɂ͌��\�L�������ł�������IC��NF=5.5�Ȃ̂ŁA�m�C�Y�͋����o�₷���ł��ˁB
NF�͑��������ۂ̃m�C�Y�̑����ł����A
TA7124P�̂悤�ɓ��͎G����IC�����Łu���ʔ������Ă���v�̂�����̂ŁA�����M�����ƁA�\�R���d�v�Ȋϓ_�ɂȂ�܂��B
TA7124P��p����AMP��6dbm�Ƒ傫�ȏo�͂̎�M��z�肵�Ă邽�߁A
�������A�Q�C���R���g���[������O�Ɍ����������Ă���̂Ȃ̂ŁA
����ɂ���ĎS/N��3�{���x�ǂ��Ȃ���ʂł͂��銴���B
����AGC-AMP�̌�i�ɂ���s��BPF�́A���g���Ă�R�̎��ނɓ��ꂽ�t�B���^�[�ƌ��\�����\���ł��B
�������A������́A�R�C���̈ꎟ���݂̂̎d�l�ł��B�܂�g�����X�\���ɂȂ��Ă��Ȃ��B
�O�i�ƌ�i�ɓ���BPF��p���Ȃ������̂́A�����A��i�ł̓p���[���傫�����邩�炾�Ǝv���܂��B
������AGC-AMP�̓��͂ɂ�锭�U���A���-1dB��T�^��ATT��t���邾���ŏ����܂��B
��̂�AGC-AMP�ɂ����āA�����핔���̃Q�C�����傫���o��Ȃ�A���̕�ATT��t���āA
���o�͊��̕ϓ��ɂ�锭�U�Ȃ�}����ׂ��ƍl���č���Ă�悤�ł��B
�������m�ł́A�\��dB�̌����������Ă�Ƃ��������ł��B
���������Ɋ����Ă���̂ŁA����̉�H�͑f�̏�ԂŃQ�C�����f�J���̂ŁA
�ɏՍނ̕ی������悤�ɂ������ł��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���ƁA�ʑ����o��̋K�i���o�Ă��܂����B
����͐��i�ɂ����͂����Ǝv���܂����A
�o�͂�150mVpp�Ƃ���̂ŁA�\�z�Ƒ�̕ς��Ȃ��ł��ˁB
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�ł����āA
�����x��AGC-AMP��p���āA�o�͂��������̂ŁA
�������グ��ȊO�ɁA��m�C�Y��Pre-AMP��H�͗L���ł͂���Ǝv���܂��B
Pre-AMP��H�̃o�C�p�X�p�X�p��L�ƕ����p�Ƃ�����GND�ւ̃p�X�R����C�ł����A
100��H��10��F�σZ����33�{���g���������g�ɑ���C���s�[�_���X�����Ƃ��܂��B
�����1000��F��OS�R���f���T�[����ESR�R���f���T�[��������ΐU���͖�薳�������邩�ȁH�Ǝv���܂��B
�Ƃ肠�����́A
�Y�킳���ς�C���_�N�^�[�̃`���[�N��H�����ă`�F�b�N���āA�������`���[�N�R�C���ƕ���C�̋��ł��邱�Ƃ̊m�F���K�v�ł��ˁB
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220430
�Ƃ���ŁAAGC-AMP��17��Sec�����ɏo��A�X�p�C�N�m�C�Y�����ǁA
�ǂ����A�X�C�b�`���O�d���A�_�v�^�̂悤�ł���B
�A�_�v�^��ς���Ǝ������傫�����ς��B
�����A�o�������͒x���Ă��A
�u�ԓI�ɑ����X�p�C�N�Ȃ̂ŁA�ǂ��������Ă��Ă�̂��A�A�A
�H���́A
AD-K120P100
�́A�����߂�����
AD-E120P150
�̕��́A���\�傫�ȃm�C�Y���o��B
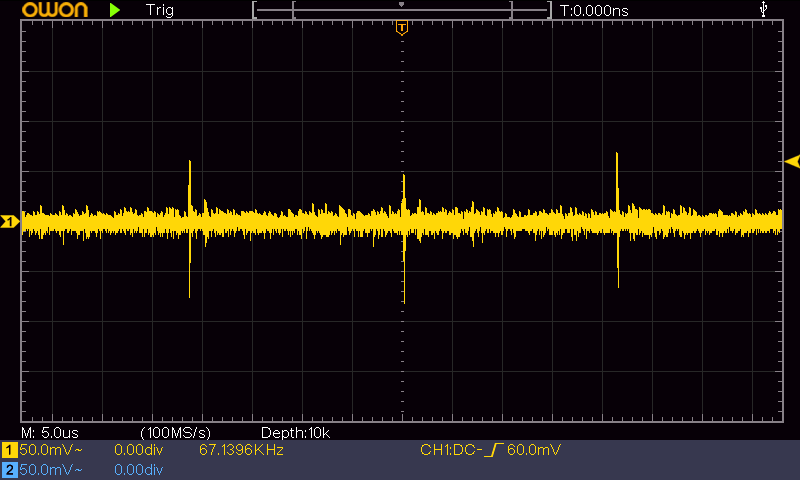 �R�������[�h���m�[�}�����[�h�����Ȃ苭���j�~���Ă�̂ɏ���Ă���̂́A
�R���Z���g����ăI�V������GND�����ʼn���Ă���Ƃ�����̂��ȁH
�܂��A
�R�������[�h�m�C�Y�Ɂu�����v������̂ŁA�t�B���^�[����������Ȃ��R�C���\�������H
�������ANFJ�̃I�[�f�B�IAMP�Ɏg���Ă���AC�A�_�v�^�[�Ȃ̂����ǁA
�R���Ɍq����ƁA�m�C�Y���قڏ�����B
�ł��A���܂�100V���痈��̂��X�p�C�N���o��B
���������āAAC���Ƀt�B���^�[��t����ƕς�����肷�邩���m��Ȃ��B
�V�[���h���[���̓d�������ǂ���A�ǂ���ς��Ȃ��\�����H
�g��AC�A�_�v�^�[�͍l���������ǂ��B
�ǂ��̂�����A�d�����ċ��p�Ŏg���̂��A����������Ȃ��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���ƁA�M������ꂽ�܂܁A�d��������ƁA�Q�C���R���g���[����H�����U���錻�ۂ��B
����́A�d���̃R���f���T�[���������邱�Ƃɂ���ĉ��P�B
�X�p�C�N�m�C�Y���������Ȃ��͂Ȃ����C������B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220501
�VAGC-AMP
�܂��A���̑��u�ւ̑����ȂǁA���\��]��������̍�Ƃ��c���Ă܂����A�ꉞ�[���o����`�ɂȂ�܂����B
�����d�l�y�сA���ɁA�P�[�X�́A�܂�����Ȃ��̂ł����A
���̃P�[�u���̎��Ȃǂ��܂߂ĕK�v�ɉ����Ċ����ł�����A�A�ƁA�v���܂��B
��AGC-AMP�͉��ǂ��ς݂܂������A���x���������߁A���U���₷�������ł��B
�̍w�������A����Ɠ������̂��A������̂ǂ����Ɏc���Ă���Ǝv���̂ł����A
�u10dB�̃o���A�u��ATT�v�ł��B
�R�������[�h���m�[�}�����[�h�����Ȃ苭���j�~���Ă�̂ɏ���Ă���̂́A
�R���Z���g����ăI�V������GND�����ʼn���Ă���Ƃ�����̂��ȁH
�܂��A
�R�������[�h�m�C�Y�Ɂu�����v������̂ŁA�t�B���^�[����������Ȃ��R�C���\�������H
�������ANFJ�̃I�[�f�B�IAMP�Ɏg���Ă���AC�A�_�v�^�[�Ȃ̂����ǁA
�R���Ɍq����ƁA�m�C�Y���قڏ�����B
�ł��A���܂�100V���痈��̂��X�p�C�N���o��B
���������āAAC���Ƀt�B���^�[��t����ƕς�����肷�邩���m��Ȃ��B
�V�[���h���[���̓d�������ǂ���A�ǂ���ς��Ȃ��\�����H
�g��AC�A�_�v�^�[�͍l���������ǂ��B
�ǂ��̂�����A�d�����ċ��p�Ŏg���̂��A����������Ȃ��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���ƁA�M������ꂽ�܂܁A�d��������ƁA�Q�C���R���g���[����H�����U���錻�ۂ��B
����́A�d���̃R���f���T�[���������邱�Ƃɂ���ĉ��P�B
�X�p�C�N�m�C�Y���������Ȃ��͂Ȃ����C������B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220501
�VAGC-AMP
�܂��A���̑��u�ւ̑����ȂǁA���\��]��������̍�Ƃ��c���Ă܂����A�ꉞ�[���o����`�ɂȂ�܂����B
�����d�l�y�сA���ɁA�P�[�X�́A�܂�����Ȃ��̂ł����A
���̃P�[�u���̎��Ȃǂ��܂߂ĕK�v�ɉ����Ċ����ł�����A�A�ƁA�v���܂��B
��AGC-AMP�͉��ǂ��ς݂܂������A���x���������߁A���U���₷�������ł��B
�̍w�������A����Ɠ������̂��A������̂ǂ����Ɏc���Ă���Ǝv���̂ł����A
�u10dB�̃o���A�u��ATT�v�ł��B
 T�^��ATT�̉ϔłŁA1�m�b�`1dB�ŕω����܂��B
���U�C���̎��ɂ������O�ɓ���A-2�`3dB����������Ɣ��U���~�܂�ꍇ�������Ǝv���܂��B
����ȊO�ɂ́A�t�B���^�[�����Č�����A�����g���Č�����o���܂��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�ł����āA���m�������Ă�������A�@�B�����ׂĂ�����ɍs���ďo�����̂ŁA
�E�`��60MHz�p�i���Ȃ��Ȃ�̂ŁA�b���́A�ł���R�g�͓��ōl���邱�Ƃ��炢�ł��B
���ƁA�������i�ō��郂�m������A�A
�������A
��̕��͔�����A4���o���܂������A�����Ȃ̂ŁA���ؗ̈�Ȃ̂ŁA�����o���Ȃ���ԂȂ̂����m��Ȃ��ł��B
���̏�Ԃ������ꍇ�A�Ƃ肠�����A������ŃG�b�`���O�A�Ǝv���̂ł����A
�O��A��������p�^�[���Ƃ��Ȃ�ς���Ă��܂����́A������Ȃ��Ƃ��܂��o���Ȃ���Ԃł��B
���ɁA��ؒf�̋@�B�������̏�ԂŎ~�܂��Ă���A
�t�F���C�g�R�A�Ɋւ��ẮA�����A���Ȃ�o���Ă�̂ɁA���������ĂȂ���Ԃł��B
�t�H�g���W�X�g�́A�܂�����������������݁A�Ȃ�Ȃ̂ŁA
�c���ʎ��ł���Ă݂�̂���肩�ȁH�Ƃ��v���Ă���܂��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�H���̃v���O���}�u���N���X�^���I�V���[�^�[���W���[���A
�������@�͔����Ȃ̂ŏo�������̃��W���[������������B
�`�b�v�ɂ́A60.0000�̍�����Ă����B
������M�@�ŕ����Ă݂�ƁAAM�ł͎�̃n�������邪�A�d���͓d�r�Ȃ̂Ŕ��U��̖��ł͖����B
���̃��[�h�ł́A�����ł������B
MEMS��OSC�̂悤�ɃM���I�[�Ƃ����̂͂Ȃ��āA�����ĉ��K�ł���B
�g�`�́A���g����`�g�Ȃ̂ŁA�����g���܂�ł���BMEMS������͏��Ȃ��C������B
T�^��ATT�̉ϔłŁA1�m�b�`1dB�ŕω����܂��B
���U�C���̎��ɂ������O�ɓ���A-2�`3dB����������Ɣ��U���~�܂�ꍇ�������Ǝv���܂��B
����ȊO�ɂ́A�t�B���^�[�����Č�����A�����g���Č�����o���܂��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�ł����āA���m�������Ă�������A�@�B�����ׂĂ�����ɍs���ďo�����̂ŁA
�E�`��60MHz�p�i���Ȃ��Ȃ�̂ŁA�b���́A�ł���R�g�͓��ōl���邱�Ƃ��炢�ł��B
���ƁA�������i�ō��郂�m������A�A
�������A
��̕��͔�����A4���o���܂������A�����Ȃ̂ŁA���ؗ̈�Ȃ̂ŁA�����o���Ȃ���ԂȂ̂����m��Ȃ��ł��B
���̏�Ԃ������ꍇ�A�Ƃ肠�����A������ŃG�b�`���O�A�Ǝv���̂ł����A
�O��A��������p�^�[���Ƃ��Ȃ�ς���Ă��܂����́A������Ȃ��Ƃ��܂��o���Ȃ���Ԃł��B
���ɁA��ؒf�̋@�B�������̏�ԂŎ~�܂��Ă���A
�t�F���C�g�R�A�Ɋւ��ẮA�����A���Ȃ�o���Ă�̂ɁA���������ĂȂ���Ԃł��B
�t�H�g���W�X�g�́A�܂�����������������݁A�Ȃ�Ȃ̂ŁA
�c���ʎ��ł���Ă݂�̂���肩�ȁH�Ƃ��v���Ă���܂��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�H���̃v���O���}�u���N���X�^���I�V���[�^�[���W���[���A
�������@�͔����Ȃ̂ŏo�������̃��W���[������������B
�`�b�v�ɂ́A60.0000�̍�����Ă����B
������M�@�ŕ����Ă݂�ƁAAM�ł͎�̃n�������邪�A�d���͓d�r�Ȃ̂Ŕ��U��̖��ł͖����B
���̃��[�h�ł́A�����ł������B
MEMS��OSC�̂悤�ɃM���I�[�Ƃ����̂͂Ȃ��āA�����ĉ��K�ł���B
�g�`�́A���g����`�g�Ȃ̂ŁA�����g���܂�ł���BMEMS������͏��Ȃ��C������B
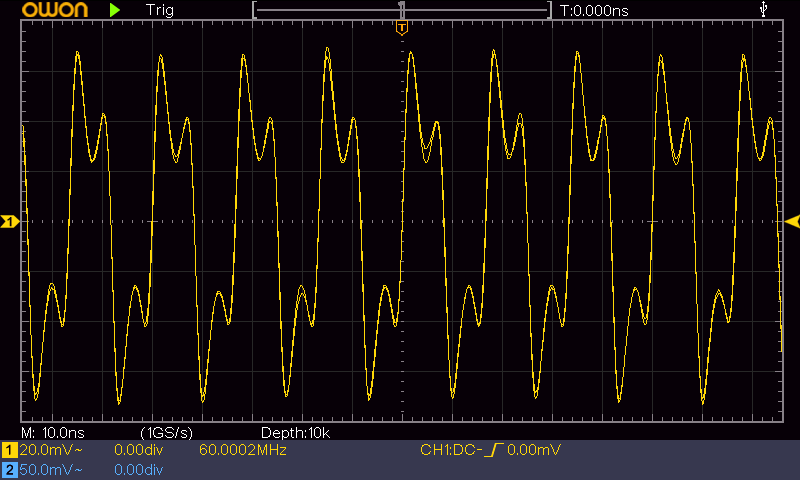 ����ŁA2W��AOM�h���C�o�[�����邩���m��Ȃ��B
�g���ӂ��������Ȃ��Ȃ��āA���肵�Ă��ہB
MEMS������̂́A���g�����x���ȁB60.00003�ɂȂ��Ă�Ƃ����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220503
KiCAD�ŁA����o�͂����z�v�����^�uCubePDF�v�ɂ��āAPDF�ŏo���āAAcrobat��PNG�o�́B
���̌�A���̉摜�t�@�C�����u�����v�ň���B
�u�Жʊ�v�ɂȂ�܂����A����Ȋ����ɂȂ�܂����B
���i�����Ă����Ă݂Ă��Y���͂Ȃ��悤�ł��ˁB
����ŁA2W��AOM�h���C�o�[�����邩���m��Ȃ��B
�g���ӂ��������Ȃ��Ȃ��āA���肵�Ă��ہB
MEMS������̂́A���g�����x���ȁB60.00003�ɂȂ��Ă�Ƃ����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220503
KiCAD�ŁA����o�͂����z�v�����^�uCubePDF�v�ɂ��āAPDF�ŏo���āAAcrobat��PNG�o�́B
���̌�A���̉摜�t�@�C�����u�����v�ň���B
�u�Жʊ�v�ɂȂ�܂����A����Ȋ����ɂȂ�܂����B
���i�����Ă����Ă݂Ă��Y���͂Ȃ��悤�ł��ˁB
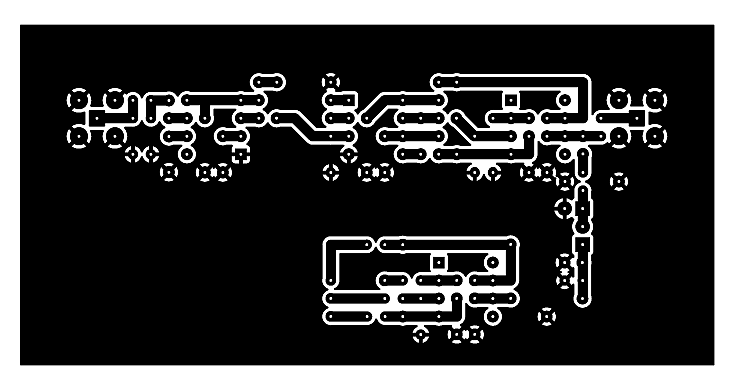 ���ʎ����ƁA�������o�����Ȃ̂ŁA�܂�����Ǝ҂ɗ��ނ��l�����ł��B
�����A�Ǝ҂ɗ��ނ̂Ȃ�APre-AMP��H���ꏏ�ɖʕt�����ďo�������Ƃ���ł��B
�܂��A��Ǝ҂ɗ��ނɂ��A�����������݂܂��̂ŁB
�ʕt�������ł��A��͂�A�����ɁA�ʂ̊������ł����������ǂ��Ǝv���܂����B
�܂��AAD603AQ�������Ă��Ȃ��ł����A�܂��C���C���������ʑ҂��ŁA
�ƎҔ����̏ꍇ�́A��������Ă���A���Ǔ_�Ȃǂ��܂`�Ŕ������������ǂ��ł��ˁB
���ʂ́A3�F00�ő��z�̕��Ɍ�����Ɩ�87000LUX�ł����ACOS�����ɂȂ��āA�����ʂł�65000LUX�Ƃ��������B
�ȑO��LED���C�g��6500LUX���x�ŁA10���Ƃ������Ƃ́A���̏�Ԃł�1���ƌ������Ƃł��ˁB
6���̓쒆���Ԃ�������A30�b�ł��ǂ��̂����m��܂���B
�́A�Ă�1���A�~��2���ł����āA�N�C�b�N�|�W�ɂȂ��Ă��班�������Ȃ����悤�Ȃ̂ŁA���̂悤�ȏ�Ԃ��ȁH�ƁB
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220504
�ȑO�����܂������A
SOT23�Ƃ�BGA420�Ƃ���������ȕ��i�Ɏg���n���_��Ƃɂ��āA
�ł���A�`�b�v��ATT���B���������Ⴗ���c�B
�`�b�v�̃n���U�t���ɁA
�u�A���~�b�g�v�́uKR-19-RMA�v�̃�0.5mm�ȃ��c���w���͂��Ă݂܂����A
�f�J���čׂ��̂ň����Ƀn���_���[���䂪�K�v�ɂȂ����̂Ńn�b�R�[�̓�i�̂��w���B
�ŁAKR-19�Ȃ̂ł����A
�u�����h�I�Ɉꗬ�ƌ������ƂŁA���̖�����I�ԃq�g�������̂ł����A
�u�X�p�[�N���n���_�v���S�肪�����̂ŁA�����Ă܂����B�H�����͂ǂ��Ȃ̂��ȁH
Twitter�ɂāA�u�����͂�63/37��������₷���v�Ƃ��A�ugoot�̂��荠�ŗǂ��v�Ƃ��B�����܂����B
�����͂ǂ��炩�Ƃ����ƁA���x�����肾�����悤�ȋC�����܂����A
�S�����Ⴍ�ċ��x������A����Ȃ�Ɋ��ҏo�������ł͂���܂��B
�ŁA
�u�N���[���n���_(�n���_�y�[�X�g)�v�ŁA63/37�����������̂Œ��ځB
�O����A�z�b�g�G�A�X�e�[�V�����̊ȈՂȂ͈̂����Ȃ��Ă܂����A���̕K�v���������ĂāA
���ʎ����ƁA�������o�����Ȃ̂ŁA�܂�����Ǝ҂ɗ��ނ��l�����ł��B
�����A�Ǝ҂ɗ��ނ̂Ȃ�APre-AMP��H���ꏏ�ɖʕt�����ďo�������Ƃ���ł��B
�܂��A��Ǝ҂ɗ��ނɂ��A�����������݂܂��̂ŁB
�ʕt�������ł��A��͂�A�����ɁA�ʂ̊������ł����������ǂ��Ǝv���܂����B
�܂��AAD603AQ�������Ă��Ȃ��ł����A�܂��C���C���������ʑ҂��ŁA
�ƎҔ����̏ꍇ�́A��������Ă���A���Ǔ_�Ȃǂ��܂`�Ŕ������������ǂ��ł��ˁB
���ʂ́A3�F00�ő��z�̕��Ɍ�����Ɩ�87000LUX�ł����ACOS�����ɂȂ��āA�����ʂł�65000LUX�Ƃ��������B
�ȑO��LED���C�g��6500LUX���x�ŁA10���Ƃ������Ƃ́A���̏�Ԃł�1���ƌ������Ƃł��ˁB
6���̓쒆���Ԃ�������A30�b�ł��ǂ��̂����m��܂���B
�́A�Ă�1���A�~��2���ł����āA�N�C�b�N�|�W�ɂȂ��Ă��班�������Ȃ����悤�Ȃ̂ŁA���̂悤�ȏ�Ԃ��ȁH�ƁB
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220504
�ȑO�����܂������A
SOT23�Ƃ�BGA420�Ƃ���������ȕ��i�Ɏg���n���_��Ƃɂ��āA
�ł���A�`�b�v��ATT���B���������Ⴗ���c�B
�`�b�v�̃n���U�t���ɁA
�u�A���~�b�g�v�́uKR-19-RMA�v�̃�0.5mm�ȃ��c���w���͂��Ă݂܂����A
�f�J���čׂ��̂ň����Ƀn���_���[���䂪�K�v�ɂȂ����̂Ńn�b�R�[�̓�i�̂��w���B
�ŁAKR-19�Ȃ̂ł����A
�u�����h�I�Ɉꗬ�ƌ������ƂŁA���̖�����I�ԃq�g�������̂ł����A
�u�X�p�[�N���n���_�v���S�肪�����̂ŁA�����Ă܂����B�H�����͂ǂ��Ȃ̂��ȁH
Twitter�ɂāA�u�����͂�63/37��������₷���v�Ƃ��A�ugoot�̂��荠�ŗǂ��v�Ƃ��B�����܂����B
�����͂ǂ��炩�Ƃ����ƁA���x�����肾�����悤�ȋC�����܂����A
�S�����Ⴍ�ċ��x������A����Ȃ�Ɋ��ҏo�������ł͂���܂��B
�ŁA
�u�N���[���n���_(�n���_�y�[�X�g)�v�ŁA63/37�����������̂Œ��ځB
�O����A�z�b�g�G�A�X�e�[�V�����̊ȈՂȂ͈̂����Ȃ��Ă܂����A���̕K�v���������ĂāA
 �ł��A�N���[���n���_���ĕۑ����������̂ŁA���܂��l���͂Ȃ����ȁ[�H�ƁB
�u�Ԑڒ��܂̂悤�ɁA�����܁A�W�b�v���b�N�A�①�łǂ����H�@���E�_�f�܂��L���H
���ׂČ���ɁA����ρA��������G�̂悤�ł��B
�Ȃ̂ŁA��₷�̂͗L�������ǁA�����܂͂ǂ������J���ł��B�E�_�f�܂͎_���h�~�ɗL�������H
�Ƃ肠�����A
����������A���������킯�ŁA�t�̃t���b�N�X�lj��ŏ_�炩���o����Ƃ��B�Ƃ������Ƃ炵���ł��ˁB
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�ŁA�]�������������̃}�C�N���X�R�[�v�Ƒ���w�����Ă��̂ł����A
�EJiusion 2K HD 2560x1440P USB�f�W�^����������
�ł��A�N���[���n���_���ĕۑ����������̂ŁA���܂��l���͂Ȃ����ȁ[�H�ƁB
�u�Ԑڒ��܂̂悤�ɁA�����܁A�W�b�v���b�N�A�①�łǂ����H�@���E�_�f�܂��L���H
���ׂČ���ɁA����ρA��������G�̂悤�ł��B
�Ȃ̂ŁA��₷�̂͗L�������ǁA�����܂͂ǂ������J���ł��B�E�_�f�܂͎_���h�~�ɗL�������H
�Ƃ肠�����A
����������A���������킯�ŁA�t�̃t���b�N�X�lj��ŏ_�炩���o����Ƃ��B�Ƃ������Ƃ炵���ł��ˁB
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�ŁA�]�������������̃}�C�N���X�R�[�v�Ƒ���w�����Ă��̂ł����A
�EJiusion 2K HD 2560x1440P USB�f�W�^����������
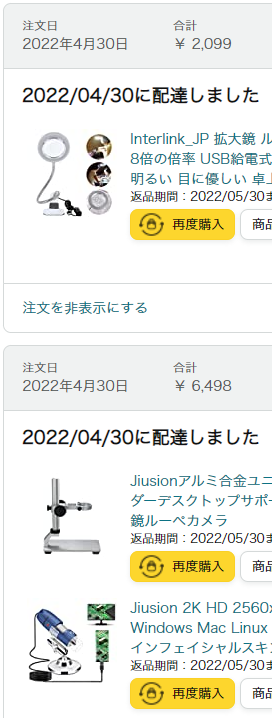 �����I�o��������ƈÂ��C������̂Œ������������ǂ������B
�����ɑ���{���Ƃ���ʊE�[�x�Ƃ��̐��\�͖������Ă�̂ł����A
������Ɣ{�����傫���̂ŁA�X�^���h�ň�ԗ����Ă��A�̈��USB�������[���炢�H���������B
���ƁA���{�I�ɉ��ߊ��Ƃ�����Ȃ��ł��ˁB
�܂��́A���ዾ�ł��L�c�C�悤�Ȋ�╔�i�̃`�F�b�N�p�ł��ˁB
���Ƃ́A�z�b�g�G�A�Ȃǂ̍�Ƃŗn����̂��m�F�Ȃ炩�Ȃ�L�������B
���ʂ̍�Ƃł́A�R���Ɠ����ɍw���������ዾ��LED�X�^���h�̕����L�������ł��B�������m�Ȃ̂ŁA�����Â炳�͂���܂����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
��������
���͍��A�o�[�Q���̂悤�ŁA���̂悤�Ȏ��ԂɁH�H
�����I�o��������ƈÂ��C������̂Œ������������ǂ������B
�����ɑ���{���Ƃ���ʊE�[�x�Ƃ��̐��\�͖������Ă�̂ł����A
������Ɣ{�����傫���̂ŁA�X�^���h�ň�ԗ����Ă��A�̈��USB�������[���炢�H���������B
���ƁA���{�I�ɉ��ߊ��Ƃ�����Ȃ��ł��ˁB
�܂��́A���ዾ�ł��L�c�C�悤�Ȋ�╔�i�̃`�F�b�N�p�ł��ˁB
���Ƃ́A�z�b�g�G�A�Ȃǂ̍�Ƃŗn����̂��m�F�Ȃ炩�Ȃ�L�������B
���ʂ̍�Ƃł́A�R���Ɠ����ɍw���������ዾ��LED�X�^���h�̕����L�������ł��B�������m�Ȃ̂ŁA�����Â炳�͂���܂����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
��������
���͍��A�o�[�Q���̂悤�ŁA���̂悤�Ȏ��ԂɁH�H
 �����镁�ʂ̈�Ԕ����63/37���ƂƂ��ɁA
138���Ƃ����̂�����ł݂��B
�����镁�ʂ̈�Ԕ����63/37���ƂƂ��ɁA
138���Ƃ����̂�����ł݂��B
 �ł��A���ʂ̃n���_�����ƍ����Ďg���ׂ�����Ȃ��C�����āA
�܂��A�`�b�v�Ɏg�������ꕔ���ł��ˁB
���Ȃ݂ɁA���O�C������O�͂����������B�B
�ł��A���ʂ̃n���_�����ƍ����Ďg���ׂ�����Ȃ��C�����āA
�܂��A�`�b�v�Ɏg�������ꕔ���ł��ˁB
���Ȃ݂ɁA���O�C������O�͂����������B�B
 ���ꂪ���O�C��������A���w�@��ɕς�����B
���������AD�^�̃R�e��1.6��1.2mm��lj��B
���A�~���{���̗��ʂ��ǂ��Ȃ̂�����Ȃ����ǁA�܂��A���ꂾ���͑��߂ɂ��Ă݂������ŁB�B
�܁A���ɑ��Ă͉~���͂Ȃ����`�A�A�ǂ��炩�Ƃ����Ɖ~�����߂��Ă�Ƃ����b���������B
���������APCB�̍쐬�˗����i��łȂ������c�A
�������������߂��Ă��Ȃ�����A����ȏ�͓����Ȃ��B�B
�Ód�C�A�d�����C���m�C�Y��{��Ƀ����[�N�ȃn���_�t���ɂ��āB
220506
�n�㕨�́{�ɑѓd���Ă邱�Ƃ������ł����A�u�d�ʍ��v�Łu�≏�j��v���N����f�q������v�f�������A
����āA�u���d�ʁv���m�Ȃ�A���قǖ��͖����Ƃ�������܂��āA����ɂ͋C���g���Ă����̂ł����A
��͂��̓d�ʂ���߂ɂ������ł��B
KR-19-RMA�̃�0.5mm�������ׂ��̂Ƀf�J���ďd���Ĉ����Â炭�A�Ԃ��Ēf��������̂ŁA
�n�b�R�[�̓�i�́u�n���_���[���v���w���B��ʂ�KR-19-RMA�͎��������ăn�}��Ȃ��̂ŁA��i�̂ق��͎��̒[��������ƍ��܂����B
�ŁA
���̃n���_���[���ɂ��A�[�X���[�q������܂��B
�n���_�S�e�ɂ�����܂��B�ŁA����σ`�b�v��M��ɂ͕K�v���ȁ[�A�A�A�Ɗ����A�Ώ����l����Ɏ���܂����B�B
�R���Z���g�̒[�q�̂͂�������Ă��̂ŁA�A�[�X�������o���āA�ēx�����n���_�t�����܂����B
�u���X�g�o���h�v�͂���̂ł����A�߂����Ɏg���ĂȂ��������B
�I�V�����A�[�X���t���Ă���A�����I�V���̃m�C�Y���A�[�X�q���Ȃ��Əo�₷���Ƃ����r���[�ɂ������̂ŁB
���ƁA����A�X�C�b�`���O�d�����d��������ăm�C�Y���o���Ă�悤�������̂ŁA
�I�V����X�C�b�`���O�d��AC�A�_�v�^�[�ɂ́A�uAC�d�����C���m�C�Y�t�B���^�[�v��������K�v���Ǝv���܂����B
�܂��A���������͎̂g���Č��Č��ʂ�����Ύg���āA�j�~�������ߕʂɗ���ċt���ʂ�������O�������ł��ˁB
�A�[�X���̓t�B���^�[➑̂ɐڑ������A�A�[�X�փX���[�����˂Ȃ�Ȃ��d�l�ł��B
�e�[�u���^�b�v�ŋ��p�Ƃ��ł͂Ȃ��A��{�A�@���ɂ���ł��ˁB
�܂��A�A�[�X�̎����Ȃ̂ł����A�q���łȂ������̂ŁA�n�ʂɃW�����N�ȃX�e�����X(SUS304)�̃A�[�X�_�ɃA�[�X����ڑ��B�Z���e�[�v�Ŋ����āA�����n�ʂɑ}���āA
����Ƀ_�C���N�g�ڑ�(��ɓd���֘A)�ƁA�l�̂ȂǃV���b�N����������藬���1�`2M�����q�������̂���낤�Ǝv���܂��B
��R�́A��̃��m�ɑ��A��t�����������݂̓˓��d���ɂ��V���b�N��������ėǂ����Ǝv���܂��B
���Ƃ́A�u�ѓd�h�~�}�b�g�v�B
�����[�N�p�u�ϔM�}�b�g�v���g�p�̕K�v������܂����A
���ؐ��i�͑ѓd�h�~�@�\��搂��Ă���悤�ł����A���ۂ́A����͑S���l������Ă��炸�A�t�ɁA�������ѓd���Ė��̂悤�ł��B
�����ŁA�u�ѓd�h�~�X�v���[�v�Ȃ̂ł����A���ʂ͉s���Ă��A�疌��������₷��������A���ʂ��������Ȃ����m�������A
��d�ȍ�Ƃ��l�����Ă�̂́A�G���W�j�A��ZC-26�Ƃ������m�ł����B������X�v���[���܂��BMonotaRO�̂͒�����������搂��Ă邯�nj��ʂ͎�߂Ƃ������܂����A�ǂ������H
�~��́A�C��₷���C�X�Ƃ��ɂ��X�v���[����ƌ��ʓI�Ɏv���܂��B��{�A���Ȃ��C���������������ǂ��ł��傤�ˁB
�܂��A�u�ѓd�h�~�}�b�g�v���z�[�U���Ƃ��G���W�j�A�̂Ƃ������������ł��B
�����A�ѓd�h�~�}�b�g�͑ϔM�����ア�̂ŁA�g���������ȁH�Ǝv���܂����B
�ł��A�����[�N�̃q�g�̑����́A���X�g�o���h�ŏ\���Ƃ̔��f�̂悤�Ȋ����ŁA����Ƃ��ł͎g���Ă܂���ˁB
���Ƃ́A�u�ѓd�h�~�s���Z�b�g�v�A�Ƃ��A�u�Ód�C�h�~��܁v�Ƃ����̂�����悤�ł����A�ƂĂ��Ǐ��Ȃ̂łǂ��Ȃ̂��H
�����A�Ód�C�Ɋւ��ẮA�c�G�i�[�ȂǂőΏ����đϐ��̂���i�������Ȃ��Ă��Ă�l�ł����A
GaAs��RF�pFET�Ȃǂ́A�ی삪�m�C�Y���郂�m�ɂȂ��Ă��܂����߁A�t���Ă��Ȃ������ǂ��Ƃ��A�A
SMD(�\�ʎ������i)�������āc�A
�ׂŃ����[�N�ȓ�������Č��܂����B
�o��Ȍ��������L�p�����ł����B
��ނ��g�߂˂Ǝv�����ʁA�v���p�b�P�[�W�̃��m�̓e�[�v�ŕی삵�Ȃ��Ɨn���Ă�����悤�ȁH
����⏤�i�̃R���Ƃ��Ńz�b�g�G�A�̓n���_�S�e���M�I�ɑf�q�ɗD�������@�ƌ����Ă�l���������ǁA�z���g�ɑf�q�ɗD�����̂��ȁH
�ǂ��炩�Ƃ����ƁA�A�ׂ����āA�������A���ʂ̑����ɒg�߂˂Ȃ�Ȃ��̂ł��̕��@�Ȃ����̂悤�ȁH
�W�Ȃ�������ی삹���ɃG�A�������Ă�͖̂��炩�ɊQ������Ǝv���B
���i���r���[�̃f�����X�g���[�V�����ł͉��x�ݒ�A���ʂ����_�o�ȓ�������������B�M�̋��Ɏ��肪���Ă�̂����Ĕ���B
�o����Ȃ�t���b�N�X��R�e�����܂��g���̂��d�v���Ǝv�����B
�����A��n���_�Ōo���ς݂����A
�Ⴂ���x�ł��炾��M���Ă�̂��M���z���Ⴍ�Ȃ��āA��M�`���Ō���Ă�f�q�����Ƀ_���[�W���o��̂Œ��ӂł���B
�������A�H���ɂ���`�b�vATT�͂������Ⴗ���ċ@�B�ň����ȊO�A�ǂ��g���̂��H���x���B
1005�T�C�Y���āA1mmx0.5mm���Ă��Ƃ��낤����c�A�A4�[�q��ڍ��͎���̋ƁB�B
�d�����K�v�ȏꍇ�ȂǁAR��d/S�ł��邩��A
�n���_�́A�\�ʐڍ��ʐ�S�Ɛڍ��ԋ���S�̖������v���ƂȂ�B
�ڍ��ʂ��L���Ĕ����ł���Ȃ�A
�U���U�������_�����s�������t���Ă��肷�镨���I(�@�B�I)�ڍ����}�V�ȕ����������ꍇ�����X�B
RC�Ɏg���R�l�N�^�ł��A�����I(�@�B�I)�ڍ��ʂ���ԉ��M���n�����肵�₷���B
�̂ɁA�n���_�ʂ̔M�����Ŋ�֕��M����^�C�v�̔����̂Ȃǂł́A�n���_�t�����ɉ������Ă�ƌ��ʓI���Ǝv���B
���A
�ǂ���ɂ��Ă��A�������łȂ���A�������P�[�u���ȂǂƔ�ׂ�Ό덷���̐��l�ł͂���\�����B
���Ⴀ�A�P�[�u���͉��M���Ȃ��̂��Ƃ����ƁA���Ă���̂����A���M�ʐς��傫���Ƃ�������������B
���Ƃ́A�v���̐��E�ł́A�َ퓱�̊Ԃ̐ڍ��ʐς��傫���ƃm�C�Y�̗ʂ�������B
�Ƃ����Ă��A�܂��͋C�ɂȂ�Ȃ��B
�ł����āA���܂Ŕ����̂�Ód�C�ʼn��Ǝv�������Ƃ́A
���W�b�NIC�����̊Ԃɂ����삵�Ȃ��Ȃ��Ă��Ƃ���2�炢�o�����Ă���B
�_���[�W��^�����u�Ԃ͐����ĂāA���̌㏙�X�ɉ���ƌ������ƂȂ̂��A�����Ǝ��ȊO�̐Ód�C�����m��Ȃ����A���̂��炢���Ȃ��p�x�ł͂���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220508
�u�ϔM�}�b�g�v�̐Ód�C�A�r�̖т����قǂ炵�����ǁA
��͂�A�l�̂ɒ~�ς����d�ׂ̕������ƌ������Ƃ̂悤�ł��B
�l�̂́A�P�ɂ̃R���f���T�[�ł����āA����ł��邽�ߑ債�ēd�ʂ��ς��Ȃ��Ă������̓d�ׂ߂��܂����c�A
�C�ɂȂ�Ȃ�\��ʂ�ѓd�h�~�X�v���[���x�ŗǂ����Ǝv���܂����B
�u�ѓd�h�~�}�b�g�v�́A���X�g�o���h����ɁA����g�R��A�����������Ƃ��̕��ɂ��L�������B�r�͔ς킵������������̂Łc�A
�Ód�C�Ȃǂ��L���炵���B
�G���W�j�A�̑ѓd�h�~�}�b�gZCM-06�͑ϔM���͂�����������悤�ł��B�Ȃ̂ŃR������{�A��p�Ƃ������ł��B
�܂��A����ŁA�A�[�X�̊��͐����������B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|+++
�V���Ȕ��U���AGC-AMP�ň�����0.3mVpp�ɍ��킹�悤�Ƃ���ƁA�U�����傫�����邵�A�s���肾�����B
�����ŁA�~�j�T�[�L�b�g��-20dB��ATT��t����ƁA
�C���s�[�_���X���Ⴂ�̈悩�獂���g�R�ɍs�����߂��A�O�{�U���̕��������Ȃ��Ă��܂��A
�X�Ɉ��肪�����A�d�r�ɐG�����肵�Ă��g�`���ς��n���B
�����ŁAFCZ�R�C�������ނ��Ƃɂ����B�����50MHz��FCZ�R�C��(�{��)���������̂ŁA
������͂߂��̂����A�m���ɉ��P�����̂����A�R�A���̂ɃZ���~�b�N�̂ł͑傫�����āA�S�̐����h���C�o�[�ō��킹��Ɏ������B
�����g��������Ƃ킩��ɂ����̂ŁA���x�̍���70MHz�܂ł�Hantek�̃I�V���ɂ���0.3mV�ɒ��߂����B�I���s�[�N�͉��₩�Ȃ悤�ł������B
�����ɓ��͂�u�����Ƃ͂����AFCZ�ɂ��K���ɐݒ肷�ׂ����̓C���s�[�_���X�����邩��B�K�s�K�͑��݂���B
���ꂪ���O�C��������A���w�@��ɕς�����B
���������AD�^�̃R�e��1.6��1.2mm��lj��B
���A�~���{���̗��ʂ��ǂ��Ȃ̂�����Ȃ����ǁA�܂��A���ꂾ���͑��߂ɂ��Ă݂������ŁB�B
�܁A���ɑ��Ă͉~���͂Ȃ����`�A�A�ǂ��炩�Ƃ����Ɖ~�����߂��Ă�Ƃ����b���������B
���������APCB�̍쐬�˗����i��łȂ������c�A
�������������߂��Ă��Ȃ�����A����ȏ�͓����Ȃ��B�B
�Ód�C�A�d�����C���m�C�Y��{��Ƀ����[�N�ȃn���_�t���ɂ��āB
220506
�n�㕨�́{�ɑѓd���Ă邱�Ƃ������ł����A�u�d�ʍ��v�Łu�≏�j��v���N����f�q������v�f�������A
����āA�u���d�ʁv���m�Ȃ�A���قǖ��͖����Ƃ�������܂��āA����ɂ͋C���g���Ă����̂ł����A
��͂��̓d�ʂ���߂ɂ������ł��B
KR-19-RMA�̃�0.5mm�������ׂ��̂Ƀf�J���ďd���Ĉ����Â炭�A�Ԃ��Ēf��������̂ŁA
�n�b�R�[�̓�i�́u�n���_���[���v���w���B��ʂ�KR-19-RMA�͎��������ăn�}��Ȃ��̂ŁA��i�̂ق��͎��̒[��������ƍ��܂����B
�ŁA
���̃n���_���[���ɂ��A�[�X���[�q������܂��B
�n���_�S�e�ɂ�����܂��B�ŁA����σ`�b�v��M��ɂ͕K�v���ȁ[�A�A�A�Ɗ����A�Ώ����l����Ɏ���܂����B�B
�R���Z���g�̒[�q�̂͂�������Ă��̂ŁA�A�[�X�������o���āA�ēx�����n���_�t�����܂����B
�u���X�g�o���h�v�͂���̂ł����A�߂����Ɏg���ĂȂ��������B
�I�V�����A�[�X���t���Ă���A�����I�V���̃m�C�Y���A�[�X�q���Ȃ��Əo�₷���Ƃ����r���[�ɂ������̂ŁB
���ƁA����A�X�C�b�`���O�d�����d��������ăm�C�Y���o���Ă�悤�������̂ŁA
�I�V����X�C�b�`���O�d��AC�A�_�v�^�[�ɂ́A�uAC�d�����C���m�C�Y�t�B���^�[�v��������K�v���Ǝv���܂����B
�܂��A���������͎̂g���Č��Č��ʂ�����Ύg���āA�j�~�������ߕʂɗ���ċt���ʂ�������O�������ł��ˁB
�A�[�X���̓t�B���^�[➑̂ɐڑ������A�A�[�X�փX���[�����˂Ȃ�Ȃ��d�l�ł��B
�e�[�u���^�b�v�ŋ��p�Ƃ��ł͂Ȃ��A��{�A�@���ɂ���ł��ˁB
�܂��A�A�[�X�̎����Ȃ̂ł����A�q���łȂ������̂ŁA�n�ʂɃW�����N�ȃX�e�����X(SUS304)�̃A�[�X�_�ɃA�[�X����ڑ��B�Z���e�[�v�Ŋ����āA�����n�ʂɑ}���āA
����Ƀ_�C���N�g�ڑ�(��ɓd���֘A)�ƁA�l�̂ȂǃV���b�N����������藬���1�`2M�����q�������̂���낤�Ǝv���܂��B
��R�́A��̃��m�ɑ��A��t�����������݂̓˓��d���ɂ��V���b�N��������ėǂ����Ǝv���܂��B
���Ƃ́A�u�ѓd�h�~�}�b�g�v�B
�����[�N�p�u�ϔM�}�b�g�v���g�p�̕K�v������܂����A
���ؐ��i�͑ѓd�h�~�@�\��搂��Ă���悤�ł����A���ۂ́A����͑S���l������Ă��炸�A�t�ɁA�������ѓd���Ė��̂悤�ł��B
�����ŁA�u�ѓd�h�~�X�v���[�v�Ȃ̂ł����A���ʂ͉s���Ă��A�疌��������₷��������A���ʂ��������Ȃ����m�������A
��d�ȍ�Ƃ��l�����Ă�̂́A�G���W�j�A��ZC-26�Ƃ������m�ł����B������X�v���[���܂��BMonotaRO�̂͒�����������搂��Ă邯�nj��ʂ͎�߂Ƃ������܂����A�ǂ������H
�~��́A�C��₷���C�X�Ƃ��ɂ��X�v���[����ƌ��ʓI�Ɏv���܂��B��{�A���Ȃ��C���������������ǂ��ł��傤�ˁB
�܂��A�u�ѓd�h�~�}�b�g�v���z�[�U���Ƃ��G���W�j�A�̂Ƃ������������ł��B
�����A�ѓd�h�~�}�b�g�͑ϔM�����ア�̂ŁA�g���������ȁH�Ǝv���܂����B
�ł��A�����[�N�̃q�g�̑����́A���X�g�o���h�ŏ\���Ƃ̔��f�̂悤�Ȋ����ŁA����Ƃ��ł͎g���Ă܂���ˁB
���Ƃ́A�u�ѓd�h�~�s���Z�b�g�v�A�Ƃ��A�u�Ód�C�h�~��܁v�Ƃ����̂�����悤�ł����A�ƂĂ��Ǐ��Ȃ̂łǂ��Ȃ̂��H
�����A�Ód�C�Ɋւ��ẮA�c�G�i�[�ȂǂőΏ����đϐ��̂���i�������Ȃ��Ă��Ă�l�ł����A
GaAs��RF�pFET�Ȃǂ́A�ی삪�m�C�Y���郂�m�ɂȂ��Ă��܂����߁A�t���Ă��Ȃ������ǂ��Ƃ��A�A
SMD(�\�ʎ������i)�������āc�A
�ׂŃ����[�N�ȓ�������Č��܂����B
�o��Ȍ��������L�p�����ł����B
��ނ��g�߂˂Ǝv�����ʁA�v���p�b�P�[�W�̃��m�̓e�[�v�ŕی삵�Ȃ��Ɨn���Ă�����悤�ȁH
����⏤�i�̃R���Ƃ��Ńz�b�g�G�A�̓n���_�S�e���M�I�ɑf�q�ɗD�������@�ƌ����Ă�l���������ǁA�z���g�ɑf�q�ɗD�����̂��ȁH
�ǂ��炩�Ƃ����ƁA�A�ׂ����āA�������A���ʂ̑����ɒg�߂˂Ȃ�Ȃ��̂ł��̕��@�Ȃ����̂悤�ȁH
�W�Ȃ�������ی삹���ɃG�A�������Ă�͖̂��炩�ɊQ������Ǝv���B
���i���r���[�̃f�����X�g���[�V�����ł͉��x�ݒ�A���ʂ����_�o�ȓ�������������B�M�̋��Ɏ��肪���Ă�̂����Ĕ���B
�o����Ȃ�t���b�N�X��R�e�����܂��g���̂��d�v���Ǝv�����B
�����A��n���_�Ōo���ς݂����A
�Ⴂ���x�ł��炾��M���Ă�̂��M���z���Ⴍ�Ȃ��āA��M�`���Ō���Ă�f�q�����Ƀ_���[�W���o��̂Œ��ӂł���B
�������A�H���ɂ���`�b�vATT�͂������Ⴗ���ċ@�B�ň����ȊO�A�ǂ��g���̂��H���x���B
1005�T�C�Y���āA1mmx0.5mm���Ă��Ƃ��낤����c�A�A4�[�q��ڍ��͎���̋ƁB�B
�d�����K�v�ȏꍇ�ȂǁAR��d/S�ł��邩��A
�n���_�́A�\�ʐڍ��ʐ�S�Ɛڍ��ԋ���S�̖������v���ƂȂ�B
�ڍ��ʂ��L���Ĕ����ł���Ȃ�A
�U���U�������_�����s�������t���Ă��肷�镨���I(�@�B�I)�ڍ����}�V�ȕ����������ꍇ�����X�B
RC�Ɏg���R�l�N�^�ł��A�����I(�@�B�I)�ڍ��ʂ���ԉ��M���n�����肵�₷���B
�̂ɁA�n���_�ʂ̔M�����Ŋ�֕��M����^�C�v�̔����̂Ȃǂł́A�n���_�t�����ɉ������Ă�ƌ��ʓI���Ǝv���B
���A
�ǂ���ɂ��Ă��A�������łȂ���A�������P�[�u���ȂǂƔ�ׂ�Ό덷���̐��l�ł͂���\�����B
���Ⴀ�A�P�[�u���͉��M���Ȃ��̂��Ƃ����ƁA���Ă���̂����A���M�ʐς��傫���Ƃ�������������B
���Ƃ́A�v���̐��E�ł́A�َ퓱�̊Ԃ̐ڍ��ʐς��傫���ƃm�C�Y�̗ʂ�������B
�Ƃ����Ă��A�܂��͋C�ɂȂ�Ȃ��B
�ł����āA���܂Ŕ����̂�Ód�C�ʼn��Ǝv�������Ƃ́A
���W�b�NIC�����̊Ԃɂ����삵�Ȃ��Ȃ��Ă��Ƃ���2�炢�o�����Ă���B
�_���[�W��^�����u�Ԃ͐����ĂāA���̌㏙�X�ɉ���ƌ������ƂȂ̂��A�����Ǝ��ȊO�̐Ód�C�����m��Ȃ����A���̂��炢���Ȃ��p�x�ł͂���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220508
�u�ϔM�}�b�g�v�̐Ód�C�A�r�̖т����قǂ炵�����ǁA
��͂�A�l�̂ɒ~�ς����d�ׂ̕������ƌ������Ƃ̂悤�ł��B
�l�̂́A�P�ɂ̃R���f���T�[�ł����āA����ł��邽�ߑ債�ēd�ʂ��ς��Ȃ��Ă������̓d�ׂ߂��܂����c�A
�C�ɂȂ�Ȃ�\��ʂ�ѓd�h�~�X�v���[���x�ŗǂ����Ǝv���܂����B
�u�ѓd�h�~�}�b�g�v�́A���X�g�o���h����ɁA����g�R��A�����������Ƃ��̕��ɂ��L�������B�r�͔ς킵������������̂Łc�A
�Ód�C�Ȃǂ��L���炵���B
�G���W�j�A�̑ѓd�h�~�}�b�gZCM-06�͑ϔM���͂�����������悤�ł��B�Ȃ̂ŃR������{�A��p�Ƃ������ł��B
�܂��A����ŁA�A�[�X�̊��͐����������B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|+++
�V���Ȕ��U���AGC-AMP�ň�����0.3mVpp�ɍ��킹�悤�Ƃ���ƁA�U�����傫�����邵�A�s���肾�����B
�����ŁA�~�j�T�[�L�b�g��-20dB��ATT��t����ƁA
�C���s�[�_���X���Ⴂ�̈悩�獂���g�R�ɍs�����߂��A�O�{�U���̕��������Ȃ��Ă��܂��A
�X�Ɉ��肪�����A�d�r�ɐG�����肵�Ă��g�`���ς��n���B
�����ŁAFCZ�R�C�������ނ��Ƃɂ����B�����50MHz��FCZ�R�C��(�{��)���������̂ŁA
������͂߂��̂����A�m���ɉ��P�����̂����A�R�A���̂ɃZ���~�b�N�̂ł͑傫�����āA�S�̐����h���C�o�[�ō��킹��Ɏ������B
�����g��������Ƃ킩��ɂ����̂ŁA���x�̍���70MHz�܂ł�Hantek�̃I�V���ɂ���0.3mV�ɒ��߂����B�I���s�[�N�͉��₩�Ȃ悤�ł������B
�����ɓ��͂�u�����Ƃ͂����AFCZ�ɂ��K���ɐݒ肷�ׂ����̓C���s�[�_���X�����邩��B�K�s�K�͑��݂���B
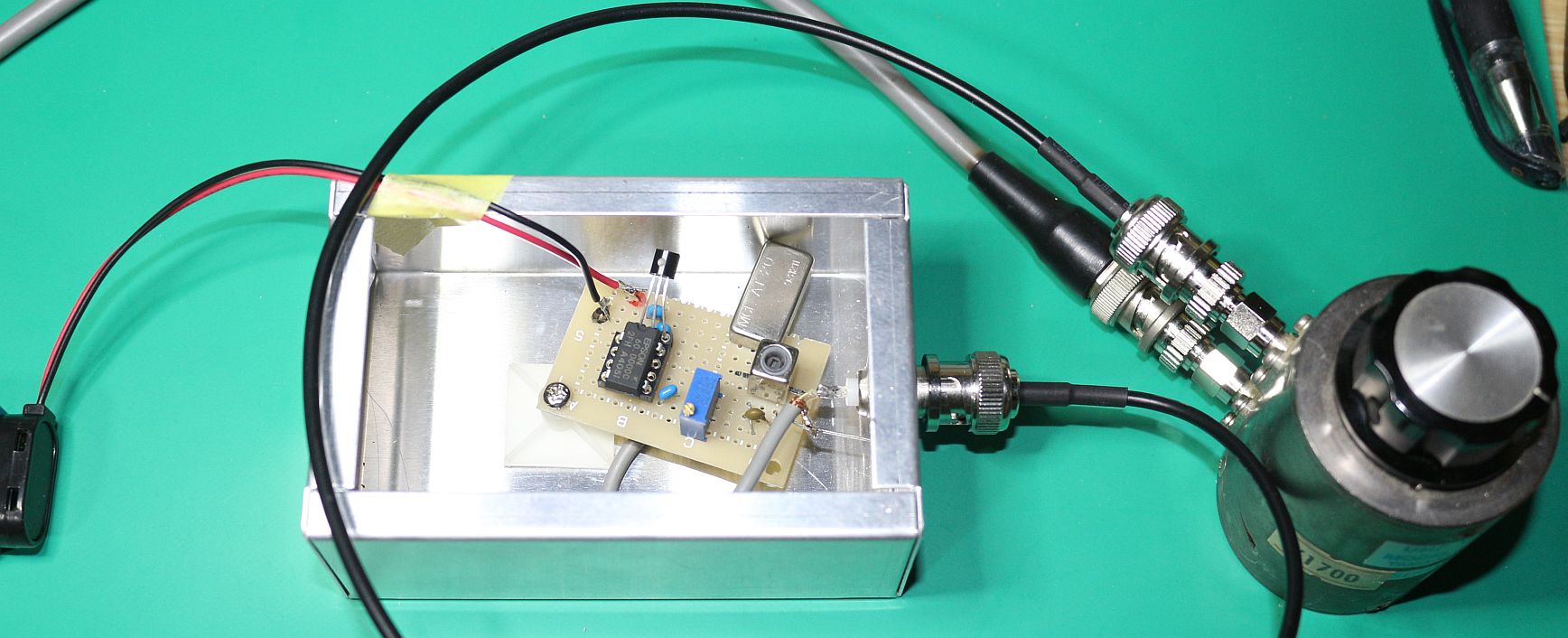 �Ƃ������ƂŁA60MHz�ɂ��Ȃ�ƁA���퓮��ɂ̓C���s�[�_���X�����͂ƂĂ��d�v�ƌ������Ƃ�������ꂽ�B
����Ŕ��������Ƃ́A�t�H�g�f�B�e�N�^��AMP���q���̂͂��Ȃ�_�o�����Ƃ������ƁB
�����ŎQ�l�ɂȂ�̂́A���t�@�C�o�[�ʐM�̎�����W���[�������m��Ȃ��B�ł��A���ʂ�o�C�A�X�����炩���ߓK������悤�ɍ���Ă��邩���m��Ȃ��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�t�H�g�_�C�I�[�h�̃C���s�[�_���X�́A�t�o�C�A�X�ɂ���Ă��Ȃ�ς�邵�A���炩�̎藧�Ă��K�v�Ɏv���B
����ɂ��Ă��A�d�r�ɐG��ƍ����g���ς��A�g�`���ς��B
�P�[�X�ɓd�r������ƁA�܂��ς��B
������ӂ́A�d���R���f���T�[�̋����Ŋɘa�͂������B�ˑR�N�����Ă���䌻�ۂł���B�B
����Ȕ��ח̈�ŐM���̓�����̂Ȃ������ȂƂ���ł��A�s��v�ɂ�锽�˂Ȃǂ̃g���u����������ƌ������Ƃ��B
������������A�c�^�{�[���Y�^�C�v�̔��Œ��R�������N�����\�����A�����A
�w���|�b�g�̂悤�ɒ��g���R�C����̃w���J���\���ł���Ƃ͎v���ĂȂ��̂ŁA���v���ȁ[�A�ƁB
�������o���ĂȂ��ꍇ�AAMP���f�B�e�N�^�����ɒu���Ƃ��Ă����͌��\����ƌ������Ƃ��B�������ȊO�͘_�O�ƂȂ�B
��ݔg�̖������邩���m��Ȃ��H
������ƌ���ł̎��ۂ̃}�b�`���O�̌v���Ƃ��āANanoVNA�ƌ������m���w���B
�Ƃ������ƂŁA60MHz�ɂ��Ȃ�ƁA���퓮��ɂ̓C���s�[�_���X�����͂ƂĂ��d�v�ƌ������Ƃ�������ꂽ�B
����Ŕ��������Ƃ́A�t�H�g�f�B�e�N�^��AMP���q���̂͂��Ȃ�_�o�����Ƃ������ƁB
�����ŎQ�l�ɂȂ�̂́A���t�@�C�o�[�ʐM�̎�����W���[�������m��Ȃ��B�ł��A���ʂ�o�C�A�X�����炩���ߓK������悤�ɍ���Ă��邩���m��Ȃ��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�t�H�g�_�C�I�[�h�̃C���s�[�_���X�́A�t�o�C�A�X�ɂ���Ă��Ȃ�ς�邵�A���炩�̎藧�Ă��K�v�Ɏv���B
����ɂ��Ă��A�d�r�ɐG��ƍ����g���ς��A�g�`���ς��B
�P�[�X�ɓd�r������ƁA�܂��ς��B
������ӂ́A�d���R���f���T�[�̋����Ŋɘa�͂������B�ˑR�N�����Ă���䌻�ۂł���B�B
����Ȕ��ח̈�ŐM���̓�����̂Ȃ������ȂƂ���ł��A�s��v�ɂ�锽�˂Ȃǂ̃g���u����������ƌ������Ƃ��B
������������A�c�^�{�[���Y�^�C�v�̔��Œ��R�������N�����\�����A�����A
�w���|�b�g�̂悤�ɒ��g���R�C����̃w���J���\���ł���Ƃ͎v���ĂȂ��̂ŁA���v���ȁ[�A�ƁB
�������o���ĂȂ��ꍇ�AAMP���f�B�e�N�^�����ɒu���Ƃ��Ă����͌��\����ƌ������Ƃ��B�������ȊO�͘_�O�ƂȂ�B
��ݔg�̖������邩���m��Ȃ��H
������ƌ���ł̎��ۂ̃}�b�`���O�̌v���Ƃ��āANanoVNA�ƌ������m���w���B
 SWR�������ƃ}�b�`���O�����Ă��Ȃ����ƂɂȂ�B
�A���e�i�`���[�i�[�Ƃ������m�łǂ��ɂ��o����̂��H���̓A���e�i�ƌ������t�H�gDi�Ȃ̂�
�M���𑗂��Ĕ���������̂ł͂Ȃ��\���̂Ȃ̂ŁA�v���͕s���ł���B
�����A�t�H�gDi���痈��V�O�i���ɑ��Ă̔��˔g�̗ʂ�ʑ�������o����A�����_�̃R���f�B�V�����͔���͂��ł���B
�܂�A���u������V�O�i����SWR�𑪒肹���ɁA�t�H�g�_�C�I�[�h��60MHz�̌��𑗂��āA���˔g�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�܂�A����60MHz���U����K�v�ɂȂ邩���m��Ȃ��A�M�����x���l���āA��͂葽���A������ƂɂȂ�B
VHF�Ȃǂ̃p�[�c�͖łтĂ邪�A
�K�v�������A�ł�ŗǂ����m�ł͖����A�Z�p���Ⴂ�̂̂ł��Ȃ��A�L�т�]�n������A���ɐL�тĂ���D
�ׂ��邾�����ړI�Ȃ玑�{��`�̍s�����������̊�Ƃ�����܂ł̂�����Ȃ����݂ɐ��艺����B
���ԎY�Ƃ�����Ȃ�A���̐�A�ɂ��ڂɑ������낤�B
�����Z�p�Ɍ���Ȃ�ƁA�H�ƋZ�p�I�Ȑ��l���Z�̋Z�p�ŕ����w�I�ȉ��߂ł͂Ȃ��Ȃ�B
�ςݏオ�����Z�p�����g���݂̂ł����A�������������w�I�l�͂���Ă��Ȃ��ƍs�����Ƃ���ł��낤�B
����ɂ��Ă�SMD�A�G�A�������Ă�Ƃ��`�b�v�������ĂȂ��Ɠ����Ă��܂����m���L��悤���B
�O���̂ɂ̓��N�ŗL�邩�������A���t���̓R�e���ǂ�����������ɂ��肻�����B
�X�C�b�`���O�d���̃m�C�Y�����A��͂�A���Ɋ���������L�̑傫���R�������[�h�p�R�C���ł́A�X�g���[�L���p�V�^���X�Ŋђʂ��Ă�\���������C�������B
�I�[�f�B�I�̌��ł��A���̗v�f���������C������B�C���_�N�^���X��~����ƁA�X�C�b�`���O�m�C�Y�͏����Ȃ��B
���ƍl������̂͑j�~�������ʁA�ʂ̃��[�gBNC�P�[�u�������GND���C���Ȃǂʼn�荞�ނ��ƁB����͉\���Ƃ��Ă̓v���Y�}�������̕��d�m�C�Y�Ƃ��Ȃ�ʂ����A���Ȃ��v�f�ł���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�}�C�R��������ۂ��ARF�V���Z�T�C�U�[IC���ڂ�ADF4351�̔��U��͏o�͂�50���炵���̂ŁA�ǂ����ȁ[�Ǝv������B
�܂��A�o�͒����͂��قǏo���Ȃ��Ǝv���̂ŁAATT��t����݂̂Ŗ��͖������ȁH
220510
�O��̑����I�B
AGC-AMP�����܂������Ȃ��ꍇ�A�����A���T�[�W��������ĉ~���`����Ė������R�͔��U�����Z���B
�����́A�قځA�C���s�[�_���X�s�����B������AGC-AMP�������킯�ł͂Ȃ��A�C���s�[�_���X�𐮍�������K�v�B
���ӏ��́A�t�H�g�_�C�I�[�h�|�����Ԃ̉\�����ɂ߂č����A�N�b�V������u�����A���������鉽�����K�v�B
��������͂����炪�o���ɔ��U�̍������Ă��Ȃ�����ȐU�����v�����Ă���̂ŁB
�܂��́A���T�[�W����������A60MHz�����������Ȃ������肵�Ċm�F���ė~�����B
���Ƃ́A�d���y�я��i�̃m�C�Y���炢�ł���B
�����œ����m�C�Y���X�g�b�v����\���ɂ͂��Ă���̂����A���ꂪ�A���d���̃m�C�Y��ʂ�GND���C���𗬂�āA�e�����g�傷�邱�Ƃ����O�����B
����́A�����̎����n�Ŏ����Č��邵���������Ǝv���B
��
�uNanoVNA�v���͂����B
���̋@�B���g���ɓ������āA�X�~�X�`���[�g�Ȃ̂����A�̃}�C�N���g�̎����Ō����C������̂����A�ڂ����͖Y��Ă��̂ŁA�O�O���Ă݂�ɁA�T�O�I�ȃ��m�͔��f���t�������A
����ŁA���ۂ̉�H���ǂ�����������肩�ȁH
�ߓn�����ł͕��f���ʂʼn����Z����x�N�g���}���������ȁA
��
�uNanoVNA�v���͂����B
STM32�ȃ}�C�R���ł��邪�AFW�̍X�V�ɂ�����Ǝ�Ԏ�����B
�ŁA���̑��u���g���Ă݂��B
�܂��A�g���n�߂Đ����Ԃ����ĂȂ��̂ŁA�C���C���ƃ��J�������A�m���邱�Ƃ͌����Ȃ��̂����ǁB�B
�ŁA�L�����u���[�g�����P�[�u���ɁA1m���傢�̃P�[�u����t�����A�^�[�~�l�[�^�[�ƃI�V�����q�������ʁB���g����60MHz�ɌŒ�B
�I�V�������̐��\����������L�����u���[�g�����t���̃P�[�u���݂̂��]�܂����Ǝv����B
�I�V���ɂ͗e�ʂ�����20pF�ȉ��Ə����Ă���B60MHz�ɂƂ��Ă͌��\�傫���l���Ǝv���B
SWR
SWR�������ƃ}�b�`���O�����Ă��Ȃ����ƂɂȂ�B
�A���e�i�`���[�i�[�Ƃ������m�łǂ��ɂ��o����̂��H���̓A���e�i�ƌ������t�H�gDi�Ȃ̂�
�M���𑗂��Ĕ���������̂ł͂Ȃ��\���̂Ȃ̂ŁA�v���͕s���ł���B
�����A�t�H�gDi���痈��V�O�i���ɑ��Ă̔��˔g�̗ʂ�ʑ�������o����A�����_�̃R���f�B�V�����͔���͂��ł���B
�܂�A���u������V�O�i����SWR�𑪒肹���ɁA�t�H�g�_�C�I�[�h��60MHz�̌��𑗂��āA���˔g�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�܂�A����60MHz���U����K�v�ɂȂ邩���m��Ȃ��A�M�����x���l���āA��͂葽���A������ƂɂȂ�B
VHF�Ȃǂ̃p�[�c�͖łтĂ邪�A
�K�v�������A�ł�ŗǂ����m�ł͖����A�Z�p���Ⴂ�̂̂ł��Ȃ��A�L�т�]�n������A���ɐL�тĂ���D
�ׂ��邾�����ړI�Ȃ玑�{��`�̍s�����������̊�Ƃ�����܂ł̂�����Ȃ����݂ɐ��艺����B
���ԎY�Ƃ�����Ȃ�A���̐�A�ɂ��ڂɑ������낤�B
�����Z�p�Ɍ���Ȃ�ƁA�H�ƋZ�p�I�Ȑ��l���Z�̋Z�p�ŕ����w�I�ȉ��߂ł͂Ȃ��Ȃ�B
�ςݏオ�����Z�p�����g���݂̂ł����A�������������w�I�l�͂���Ă��Ȃ��ƍs�����Ƃ���ł��낤�B
����ɂ��Ă�SMD�A�G�A�������Ă�Ƃ��`�b�v�������ĂȂ��Ɠ����Ă��܂����m���L��悤���B
�O���̂ɂ̓��N�ŗL�邩�������A���t���̓R�e���ǂ�����������ɂ��肻�����B
�X�C�b�`���O�d���̃m�C�Y�����A��͂�A���Ɋ���������L�̑傫���R�������[�h�p�R�C���ł́A�X�g���[�L���p�V�^���X�Ŋђʂ��Ă�\���������C�������B
�I�[�f�B�I�̌��ł��A���̗v�f���������C������B�C���_�N�^���X��~����ƁA�X�C�b�`���O�m�C�Y�͏����Ȃ��B
���ƍl������̂͑j�~�������ʁA�ʂ̃��[�gBNC�P�[�u�������GND���C���Ȃǂʼn�荞�ނ��ƁB����͉\���Ƃ��Ă̓v���Y�}�������̕��d�m�C�Y�Ƃ��Ȃ�ʂ����A���Ȃ��v�f�ł���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�}�C�R��������ۂ��ARF�V���Z�T�C�U�[IC���ڂ�ADF4351�̔��U��͏o�͂�50���炵���̂ŁA�ǂ����ȁ[�Ǝv������B
�܂��A�o�͒����͂��قǏo���Ȃ��Ǝv���̂ŁAATT��t����݂̂Ŗ��͖������ȁH
220510
�O��̑����I�B
AGC-AMP�����܂������Ȃ��ꍇ�A�����A���T�[�W��������ĉ~���`����Ė������R�͔��U�����Z���B
�����́A�قځA�C���s�[�_���X�s�����B������AGC-AMP�������킯�ł͂Ȃ��A�C���s�[�_���X�𐮍�������K�v�B
���ӏ��́A�t�H�g�_�C�I�[�h�|�����Ԃ̉\�����ɂ߂č����A�N�b�V������u�����A���������鉽�����K�v�B
��������͂����炪�o���ɔ��U�̍������Ă��Ȃ�����ȐU�����v�����Ă���̂ŁB
�܂��́A���T�[�W����������A60MHz�����������Ȃ������肵�Ċm�F���ė~�����B
���Ƃ́A�d���y�я��i�̃m�C�Y���炢�ł���B
�����œ����m�C�Y���X�g�b�v����\���ɂ͂��Ă���̂����A���ꂪ�A���d���̃m�C�Y��ʂ�GND���C���𗬂�āA�e�����g�傷�邱�Ƃ����O�����B
����́A�����̎����n�Ŏ����Č��邵���������Ǝv���B
��
�uNanoVNA�v���͂����B
���̋@�B���g���ɓ������āA�X�~�X�`���[�g�Ȃ̂����A�̃}�C�N���g�̎����Ō����C������̂����A�ڂ����͖Y��Ă��̂ŁA�O�O���Ă݂�ɁA�T�O�I�ȃ��m�͔��f���t�������A
����ŁA���ۂ̉�H���ǂ�����������肩�ȁH
�ߓn�����ł͕��f���ʂʼn����Z����x�N�g���}���������ȁA
��
�uNanoVNA�v���͂����B
STM32�ȃ}�C�R���ł��邪�AFW�̍X�V�ɂ�����Ǝ�Ԏ�����B
�ŁA���̑��u���g���Ă݂��B
�܂��A�g���n�߂Đ����Ԃ����ĂȂ��̂ŁA�C���C���ƃ��J�������A�m���邱�Ƃ͌����Ȃ��̂����ǁB�B
�ŁA�L�����u���[�g�����P�[�u���ɁA1m���傢�̃P�[�u����t�����A�^�[�~�l�[�^�[�ƃI�V�����q�������ʁB���g����60MHz�ɌŒ�B
�I�V�������̐��\����������L�����u���[�g�����t���̃P�[�u���݂̂��]�܂����Ǝv����B
�I�V���ɂ͗e�ʂ�����20pF�ȉ��Ə����Ă���B60MHz�ɂƂ��Ă͌��\�傫���l���Ǝv���B
SWR
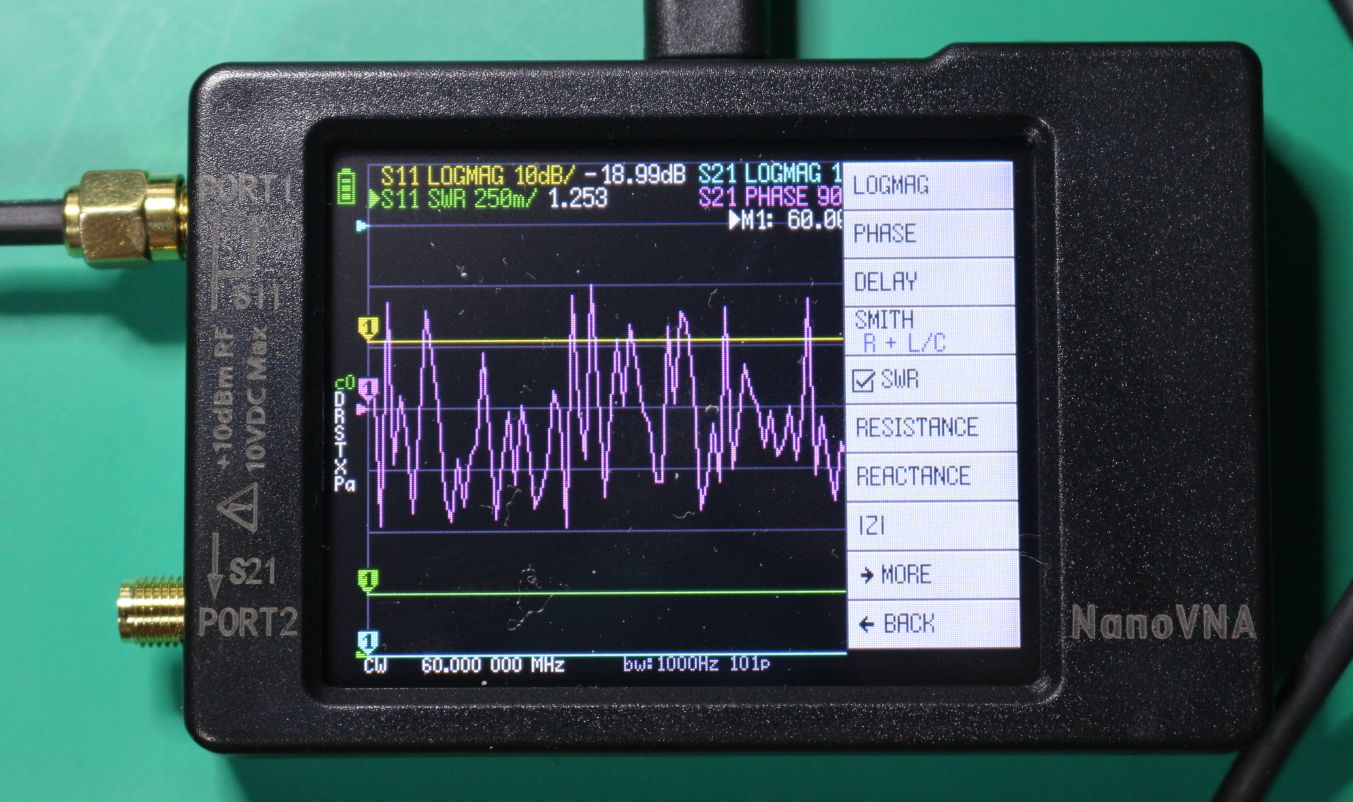 �܂��A���ۂ�1.253�ƌ������ƂȂ�A�C���C���A������ɂ͗ǂ���Ȃ��̂��ȁH
�C���s�[�_���X�̐�Βl�BRLC�����S�����킹���l�ƂȂ邪�A������̒����ł͖����H�H
�܂��A���ۂ�1.253�ƌ������ƂȂ�A�C���C���A������ɂ͗ǂ���Ȃ��̂��ȁH
�C���s�[�_���X�̐�Βl�BRLC�����S�����킹���l�ƂȂ邪�A������̒����ł͖����H�H
 �X�~�X�B��������̂��F�X�ȗv�f���܂Ƃ߂�20.9nH���Ƃ����l�����ȁB
�X�~�X�B��������̂��F�X�ȗv�f���܂Ƃ߂�20.9nH���Ƃ����l�����ȁB
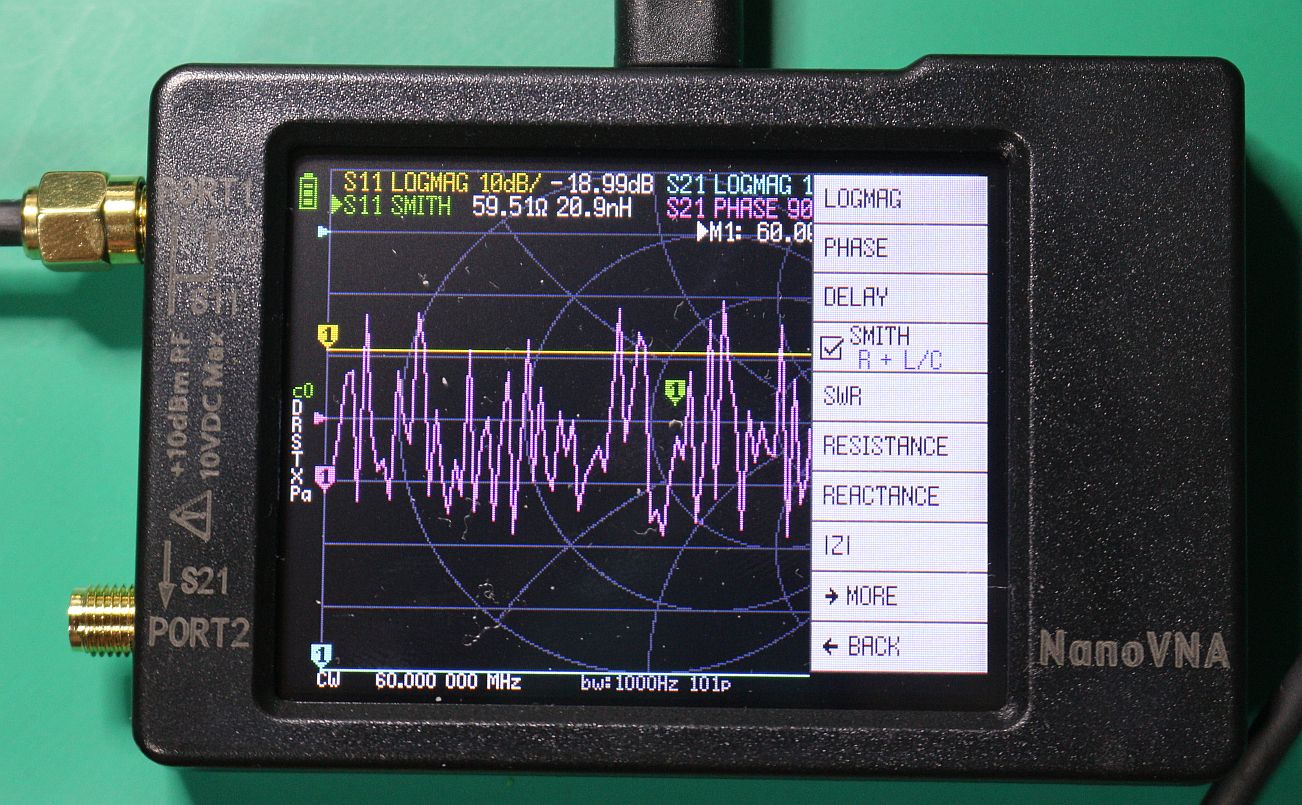 ���ɂ�LPF�̓����Ƃ��������̂ŃC���C���֗��ł���B
���蒆�A�I�V�����ɂ��A�|�����g���̔g�`�Ȃǂ��o�邪�A���g�̐�������`�g�őI��I�Ɋ��g���v�����Ă�C������B
���U��Ƃ��Ă͔g�`�������Ƃ����b�����������A
����́A���W�b�N�I�ɃV���Z�ŏo���Ă邩��̂Ȃ̂��ȁH�Ƃ��B
PC�ɐڑ����Č���\�t�g�����邪�A�g�s���銴���Ń��C���Ɏg���̂��I�V���Ɠ�������ړI���ȁH
�����ŃR���p�N�g�ȃm�[�gPC�ł�����Ώ͕ς�肻�������ǁB�B
�t�H�g�_�C�I�[�h���̔C�ӎ��g���̃C���s�[�_���X����͂ł��Ȃ����m���ȁH
�t�o�C�A�X�Ǝ��g���ŕς��̂ŊȒP�����ł͂Ȃ����ǁA�L���̕����ł͂���B
�t�H�g�f�B�e�N�^�����̉�H�Ɍq����Z�͑��邱�Ƃ��o���邩���m��Ȃ����A
���̋@�B�̑���M���̐U���͂�肩���傫���̂ŁA�o�C�A�X�����킹��ƌ����Ȃ��Ǝv����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220511
FusionPCB�������͂����B�^��p�b�N����Ă����B
���ɂ�LPF�̓����Ƃ��������̂ŃC���C���֗��ł���B
���蒆�A�I�V�����ɂ��A�|�����g���̔g�`�Ȃǂ��o�邪�A���g�̐�������`�g�őI��I�Ɋ��g���v�����Ă�C������B
���U��Ƃ��Ă͔g�`�������Ƃ����b�����������A
����́A���W�b�N�I�ɃV���Z�ŏo���Ă邩��̂Ȃ̂��ȁH�Ƃ��B
PC�ɐڑ����Č���\�t�g�����邪�A�g�s���銴���Ń��C���Ɏg���̂��I�V���Ɠ�������ړI���ȁH
�����ŃR���p�N�g�ȃm�[�gPC�ł�����Ώ͕ς�肻�������ǁB�B
�t�H�g�_�C�I�[�h���̔C�ӎ��g���̃C���s�[�_���X����͂ł��Ȃ����m���ȁH
�t�o�C�A�X�Ǝ��g���ŕς��̂ŊȒP�����ł͂Ȃ����ǁA�L���̕����ł͂���B
�t�H�g�f�B�e�N�^�����̉�H�Ɍq����Z�͑��邱�Ƃ��o���邩���m��Ȃ����A
���̋@�B�̑���M���̐U���͂�肩���傫���̂ŁA�o�C�A�X�����킹��ƌ����Ȃ��Ǝv����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220511
FusionPCB�������͂����B�^��p�b�N����Ă����B
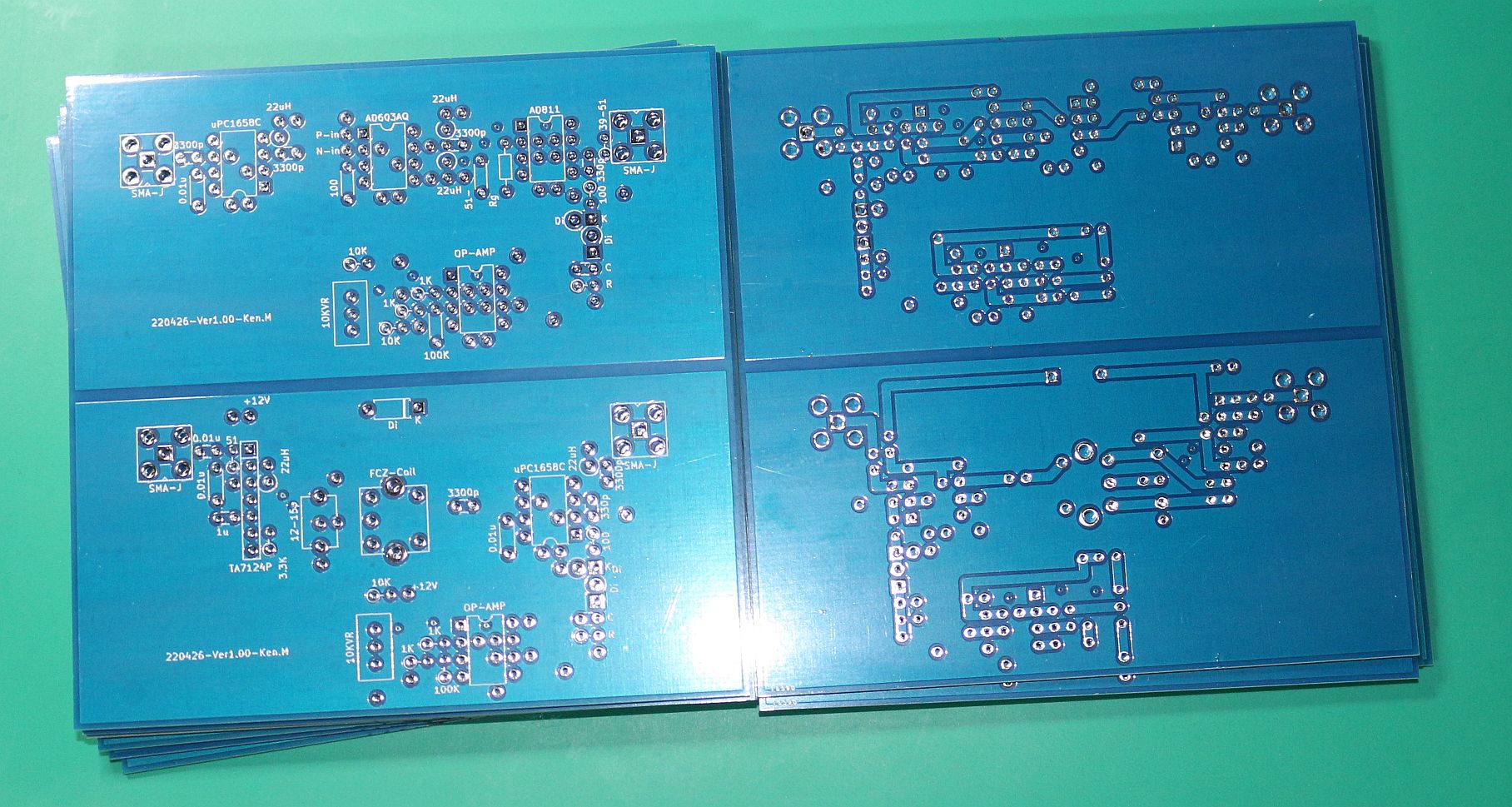 GND�̃X���[�z�[�����x�^�ƌq�����ĂȂ��ׂ̂͂}�ʘg�ɃR�s�y���ɐڑ��l�b�g���Ă��܂��ƌ����~�X�������B
������q���邽�߁A���W�X�g�������悭�Y��ɍ����@�͂Ȃ����ȁH
����Ɏ��Ԃ����������悤�����ǁA�z����$17�������̂ő��������B
�g�[�^������ƁA��������14���������B�R���i�Ŕz�����������������Ƃ���������PCBWay��肿����Ƒ����Ǝv���B
���x��PCBWay�⑼�ɂ�����ł݂邩�ȁH
���̎��́A�����GND�����Ȃǂ̖�������邽�߁A�َ�ʕt�����Ȃ��ŏo�����Ǝv���B
��H������ǂ���Ǝv�����B(�����_���͂�-1.85dB�̃Ό^ATT��t��)
�ǂ���ɂ���A���̉�H�ł̎������I���Ă���ɂȂ�͗l�B
����ō�ƂɎ�肩����邩�Ǝv������A�A�A
�܂��AAD603AQ�����������B
�܂��ATA7124P�̃��c�Ƌ���H�̌��ʂ����āA�X��Pre-AMP��H���̌��ʂ����āA
Pre-AMP��H���܂߂ĐV���Ȋ�����ȁH
����́A���1.2mm���������A1GHz�߂��Ă�1.6mm�ł��s����悤�Ȃ̂ŁA1mm������0.8mm�͂ǂ����ȁH�Ƃ��v���Ă���B
�M�����̃p�^�[���̑������A�e�ʁAZ�ɉe���������ȋC�����邪�A�]��ׂ��Ɖ�H�̌���H�ɋꗶ���邵�B�B
���ƁAGND�̋����B�M�����ɉ����āAGND�֏㉺�ɃX���[�z�[����ł��������ǂ��悤�Ȃ̂ŁA��������{�\��B
�NjL��
1.6mm���������B
���S�����ς����Ă��������̂��ȁH�Y��Ă��B
�ڂ�������ɁA
04/27�����ɔ����B05/6���ɔ����A05/11���ɓ����Ƃ����������������B
�����܂�1-3���A������7�����炢�Ƃ������Ƃ��ȁH
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�NjL02��
PCBWay�������z�����I�������疳���Ȃ��Ă����B
�����ł̐������Ԃ��啝�ɐL�тĂ����B
���̗��ʎ�����炩�H�H
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�NjL03��
���W�X�g�������̂ɁA��i�Ƃ����A�X�N���[�p�[���ǂ��炵�����A
�N���t�g�i�C�t���H�̋L�������������ǁA���݂̂ł̐����ʼn���Ȃ��c�B
����āA�}�C�i�X�h���C�o�[���\�t�g�ɂ����������悳���������A
Goot����u�\���_�[�A�V�X�g6�{�g SA-10�v�Ƃ����c�[�����������̂Œ����c�A�A
�ł͂��邯�ǁA�̂ɍ��������ǁA100MHz�쓮�\��LD
GND�̃X���[�z�[�����x�^�ƌq�����ĂȂ��ׂ̂͂}�ʘg�ɃR�s�y���ɐڑ��l�b�g���Ă��܂��ƌ����~�X�������B
������q���邽�߁A���W�X�g�������悭�Y��ɍ����@�͂Ȃ����ȁH
����Ɏ��Ԃ����������悤�����ǁA�z����$17�������̂ő��������B
�g�[�^������ƁA��������14���������B�R���i�Ŕz�����������������Ƃ���������PCBWay��肿����Ƒ����Ǝv���B
���x��PCBWay�⑼�ɂ�����ł݂邩�ȁH
���̎��́A�����GND�����Ȃǂ̖�������邽�߁A�َ�ʕt�����Ȃ��ŏo�����Ǝv���B
��H������ǂ���Ǝv�����B(�����_���͂�-1.85dB�̃Ό^ATT��t��)
�ǂ���ɂ���A���̉�H�ł̎������I���Ă���ɂȂ�͗l�B
����ō�ƂɎ�肩����邩�Ǝv������A�A�A
�܂��AAD603AQ�����������B
�܂��ATA7124P�̃��c�Ƌ���H�̌��ʂ����āA�X��Pre-AMP��H���̌��ʂ����āA
Pre-AMP��H���܂߂ĐV���Ȋ�����ȁH
����́A���1.2mm���������A1GHz�߂��Ă�1.6mm�ł��s����悤�Ȃ̂ŁA1mm������0.8mm�͂ǂ����ȁH�Ƃ��v���Ă���B
�M�����̃p�^�[���̑������A�e�ʁAZ�ɉe���������ȋC�����邪�A�]��ׂ��Ɖ�H�̌���H�ɋꗶ���邵�B�B
���ƁAGND�̋����B�M�����ɉ����āAGND�֏㉺�ɃX���[�z�[����ł��������ǂ��悤�Ȃ̂ŁA��������{�\��B
�NjL��
1.6mm���������B
���S�����ς����Ă��������̂��ȁH�Y��Ă��B
�ڂ�������ɁA
04/27�����ɔ����B05/6���ɔ����A05/11���ɓ����Ƃ����������������B
�����܂�1-3���A������7�����炢�Ƃ������Ƃ��ȁH
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�NjL02��
PCBWay�������z�����I�������疳���Ȃ��Ă����B
�����ł̐������Ԃ��啝�ɐL�тĂ����B
���̗��ʎ�����炩�H�H
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�NjL03��
���W�X�g�������̂ɁA��i�Ƃ����A�X�N���[�p�[���ǂ��炵�����A
�N���t�g�i�C�t���H�̋L�������������ǁA���݂̂ł̐����ʼn���Ȃ��c�B
����āA�}�C�i�X�h���C�o�[���\�t�g�ɂ����������悳���������A
Goot����u�\���_�[�A�V�X�g6�{�g SA-10�v�Ƃ����c�[�����������̂Œ����c�A�A
�ł͂��邯�ǁA�̂ɍ��������ǁA100MHz�쓮�\��LD
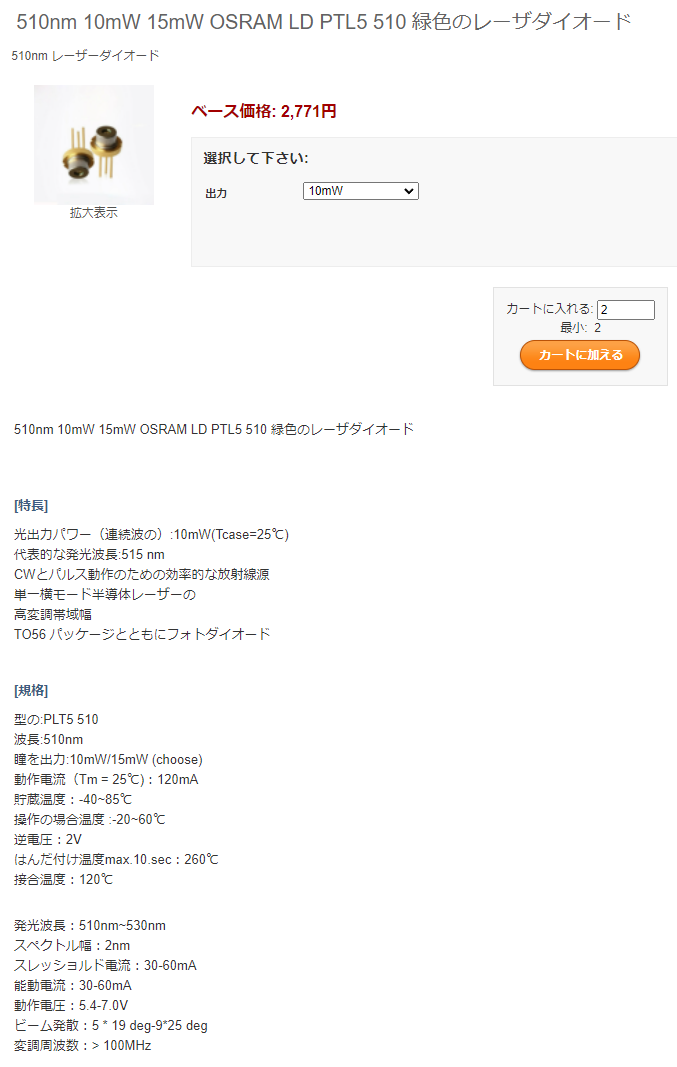 220513
���x�́AJLCPCB�ɔ��������B
220513
���x�́AJLCPCB�ɔ��������B
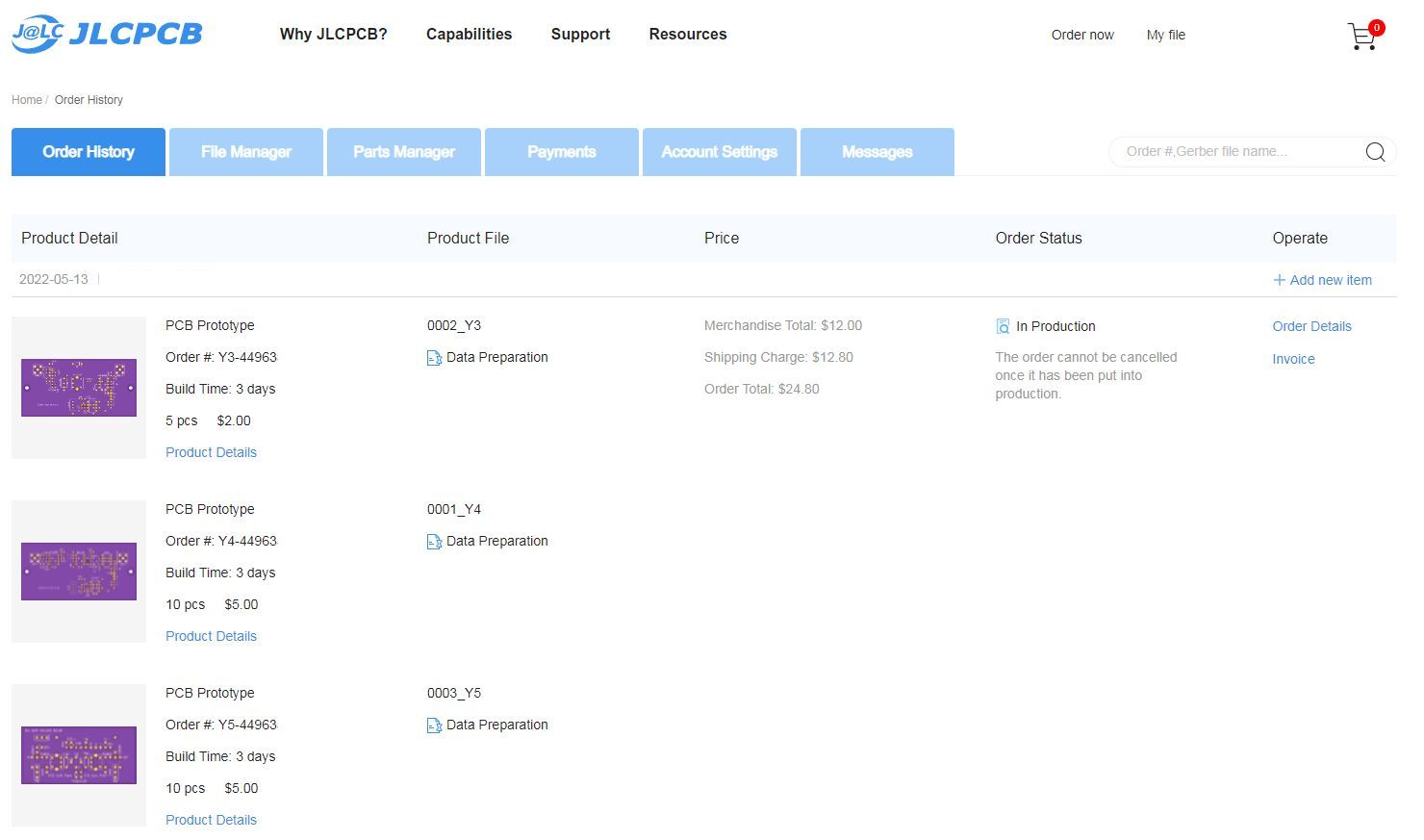 ���ӓ_�B
�E���{��Ή��ł͂Ȃ��˂�����x�@�B�|��𗊂�ɁB
�E�o�^�A���O�C���ŃG���[���N�������˗��R��������Ȃ��B����ǁAGoogle�A�J�E���g�Ń��O�C���o����̂ŁA���̕��@�œ������B���A���G�N�Ɠ����B
�E�i�������ł܂Ƃ߂đ���ݒ肾�ƁA��̎�ނ���������ˑ����^���ł�����x�̒l�i�̂Ƃ���Ȃ��ɂ܂Ƃ߂Ă����B
�E2�h���͍ŏ���5�̂݁B�ˎ��̊�����$4�������̂ł�����$5��10�ɂ����ق��������B
�E�c�C�b�^�[�A�J�E���g�ɓ��{���[�U�[�ւ̃N�[�|���Љ����B�lj��N�[�|����DM�ł��炦��炵�����A��������S�O���Ă�B
�ǂ�PCB�����Ǝ҂��A���F���Ⴄ���ǁA���ӂ��ׂ��_�͑����̌��ߕ����ȁH
�����̊�������܂Ƃ߂��邩�A�������ԂƗA�����Ԃ����ˍ��킹�l���đI�ڂ��B
���ʂ̃V���b�s���O�Ȓ�������Ⴂ���Ȃ����H�ƁA���Ȃ�ْ�����B�����A�������狰�낵���c�A�A�A
���x�́A���1mm�ɂ����B�����������������Ȃ�ꍇ���H�H
���̊�Ղɂ������ǁA
�Ԃ��Ɣ��邵�A���F���ƃ��W�X�g�̑��݂����o�I�ɔ��f���Â炢�B
�́A���ɑO�������̂ŁA�����Ȃ����ǁA�Ɠ������A���}�����H
�x�^�̂����̃~�X���A�K�[�o�[�r���[�A�[�Ō���ɁA�z�����̂̃~�X�܂ł͉���Ȃ��̂ŁA
�x�^������O�Ƀ\�t�g�Ŋm�F���ȁH
-----------�|�|�|�|�|
���̋@�̂́A�E�`�̊��ł̌v���ł́A���͖����ł����A
��������̕]���łł�����A�K�����������̌`�͖���ł���B�Ƃ����������ł��B�A
���x�������悤�ł����A���̃o�����X�͂��Ȃ�Ⴄ�ݒ�ŁA
�u���U�v�ƁuS/N�v�A�y�сA�X�C�b�`���O�d�������O�����Ƃ���ł͂���܂��B
�V�^�ł���TA7124�@�̏o�͒i�ł����PC1658C�̍ő�U�����l����ƁA
�o�͂͋C��25�����ŏI�iTr�̏���d����40mA�ƋL����Ă���B
�A�C�h���d����20mA�ł���Ƃ���ƁA20mArms������Ƃ݂āB
���̏�ň��S�����ς����āA25mApp�B�����50�����ׂɗ����Ƃ��āA1.25Vpp(3mW���x)�ƂȂ邩�Ǝv���܂��B
�ɃN�[���X�^�b�t�����t���čX�ɁA���₵�A�]�T���������悤�Ǝv���Ă���܂��B
�ʑ����o��̓��͂ɂ́A0dBm�`6dBm�̕������鐻�i������̂ŁB�傫�߂̓��͂Ȃ�AAGC-AMP���͂⏉�i�����S/N�ɂ͋����Ȃ�܂��B
�ǂ����Ă��m�C�Y�����������肵���ꍇ�A
��PC1658C�̗��_�Ƃ��āA�A�Ғ�R(NFB)�ɂ���ăQ�C�����o����Ƃ�������������܂��B
����ŁA�Q�C���������A���̑���Ƀv���A���v�̑����ɉƂ����l��������ł��B
-----------�|�|�|�|�|
�@�����̘A���ŁA�[���������i�͑S�Đ��퓮��͊m�F����܂����B
���̌�A���e�ؖ��X�֕����͂��Ǝv���܂��B�s�݂Ƃ������Ɨǂ��ł����c�A
-----------�|�|�|�|�|
220519
���삪�ł�������A�x�����A�[�����@�Ȃǎ葱�����Ă��A�u�����v���ꑱ����̂ŁA�������������Ă��āA
���e�ؖ��X�ւŁu�Í����v�𑗂�܂����B
�ŏ��́A���[���ŁA�㗝�X��ʂ��[���̈�_����ł������A���X�x���B
�u��������������ٔ������ǂ����Ǝv���܂��B�P�\�͈�T�Ԃ���܂��B�悭�l���ĉ������B�v�Ɠ`���܂����B
�ŁA���킹�邱�Ƃɂ��܂����B
�������o��ŁB�B�B�ǂ��܂Ńh�P�`�ȂH�H�@�������I�I
(�������͎����Ȃ̂����A�A����������ă��Ȏ��͐l�ɂ���Ȃ͐l�Ԃ̊�{�B���ꂪ����Ă�B)
���ƂŁA���[���ł̃C���~�����������̂ŁA�����A���֍ێȂ����Ƃɂ��悤�Ǝv���܂��B
�h�P�`�Ő��ӂ��������c���̂Ԃ邾�����ƍň����ȁE�E�A�A
�\�R�܂ł̐l�Ԃ��������B�݂����Ȍ��t��f���Ă����̂ł����A����͂������̃Z���t���ȁB
����҂̐�������낤�Ƃ����A�N�Q���Ă܂ŁA���āA����������Ǝ��ł��ĉ�������Ȃ��ŗǂ��Ȃ�Ƃ��l���Ă����̂����ł��ˁB
�Ƃɂ����A���m����ĕ����C�Ȃǖ����������Ƃ͎������B
�����i��[�������ǂ����������Ă������A���O�̃`�F�b�N�ł����Ɠ����Ă�̂ɂǂ��܂ōs�����犮���i�Ȃ̂��H����͂����炪���߂邱�Ƃ��B
���������A��������Ƃ��A���i�݂̂��Ǝv���Ă�̂��r�߂Ă�؋����B
���[�A�����ł����Ȃ������ȁ[�c�A�A�A
�o���A�Ќ��Ƌ��̖S�҂Ȃ�A�w�������̑����������Ă�n�Y�ŁA�C�̓ł��B
���ɁA���đւ�������Ȃ��̂Ȃ�A�����͂��Ȃ�X���[�y�[�X�ɂȂ�A�w���ւ̃��^�[�������邱�ƂɂȂ�B
220520
����͂������A�g���A�e�������ˁ`�A�A
���ӓ_�B
�E���{��Ή��ł͂Ȃ��˂�����x�@�B�|��𗊂�ɁB
�E�o�^�A���O�C���ŃG���[���N�������˗��R��������Ȃ��B����ǁAGoogle�A�J�E���g�Ń��O�C���o����̂ŁA���̕��@�œ������B���A���G�N�Ɠ����B
�E�i�������ł܂Ƃ߂đ���ݒ肾�ƁA��̎�ނ���������ˑ����^���ł�����x�̒l�i�̂Ƃ���Ȃ��ɂ܂Ƃ߂Ă����B
�E2�h���͍ŏ���5�̂݁B�ˎ��̊�����$4�������̂ł�����$5��10�ɂ����ق��������B
�E�c�C�b�^�[�A�J�E���g�ɓ��{���[�U�[�ւ̃N�[�|���Љ����B�lj��N�[�|����DM�ł��炦��炵�����A��������S�O���Ă�B
�ǂ�PCB�����Ǝ҂��A���F���Ⴄ���ǁA���ӂ��ׂ��_�͑����̌��ߕ����ȁH
�����̊�������܂Ƃ߂��邩�A�������ԂƗA�����Ԃ����ˍ��킹�l���đI�ڂ��B
���ʂ̃V���b�s���O�Ȓ�������Ⴂ���Ȃ����H�ƁA���Ȃ�ْ�����B�����A�������狰�낵���c�A�A�A
���x�́A���1mm�ɂ����B�����������������Ȃ�ꍇ���H�H
���̊�Ղɂ������ǁA
�Ԃ��Ɣ��邵�A���F���ƃ��W�X�g�̑��݂����o�I�ɔ��f���Â炢�B
�́A���ɑO�������̂ŁA�����Ȃ����ǁA�Ɠ������A���}�����H
�x�^�̂����̃~�X���A�K�[�o�[�r���[�A�[�Ō���ɁA�z�����̂̃~�X�܂ł͉���Ȃ��̂ŁA
�x�^������O�Ƀ\�t�g�Ŋm�F���ȁH
-----------�|�|�|�|�|
���̋@�̂́A�E�`�̊��ł̌v���ł́A���͖����ł����A
��������̕]���łł�����A�K�����������̌`�͖���ł���B�Ƃ����������ł��B�A
���x�������悤�ł����A���̃o�����X�͂��Ȃ�Ⴄ�ݒ�ŁA
�u���U�v�ƁuS/N�v�A�y�сA�X�C�b�`���O�d�������O�����Ƃ���ł͂���܂��B
�V�^�ł���TA7124�@�̏o�͒i�ł����PC1658C�̍ő�U�����l����ƁA
�o�͂͋C��25�����ŏI�iTr�̏���d����40mA�ƋL����Ă���B
�A�C�h���d����20mA�ł���Ƃ���ƁA20mArms������Ƃ݂āB
���̏�ň��S�����ς����āA25mApp�B�����50�����ׂɗ����Ƃ��āA1.25Vpp(3mW���x)�ƂȂ邩�Ǝv���܂��B
�ɃN�[���X�^�b�t�����t���čX�ɁA���₵�A�]�T���������悤�Ǝv���Ă���܂��B
�ʑ����o��̓��͂ɂ́A0dBm�`6dBm�̕������鐻�i������̂ŁB�傫�߂̓��͂Ȃ�AAGC-AMP���͂⏉�i�����S/N�ɂ͋����Ȃ�܂��B
�ǂ����Ă��m�C�Y�����������肵���ꍇ�A
��PC1658C�̗��_�Ƃ��āA�A�Ғ�R(NFB)�ɂ���ăQ�C�����o����Ƃ�������������܂��B
����ŁA�Q�C���������A���̑���Ƀv���A���v�̑����ɉƂ����l��������ł��B
-----------�|�|�|�|�|
�@�����̘A���ŁA�[���������i�͑S�Đ��퓮��͊m�F����܂����B
���̌�A���e�ؖ��X�֕����͂��Ǝv���܂��B�s�݂Ƃ������Ɨǂ��ł����c�A
-----------�|�|�|�|�|
220519
���삪�ł�������A�x�����A�[�����@�Ȃǎ葱�����Ă��A�u�����v���ꑱ����̂ŁA�������������Ă��āA
���e�ؖ��X�ւŁu�Í����v�𑗂�܂����B
�ŏ��́A���[���ŁA�㗝�X��ʂ��[���̈�_����ł������A���X�x���B
�u��������������ٔ������ǂ����Ǝv���܂��B�P�\�͈�T�Ԃ���܂��B�悭�l���ĉ������B�v�Ɠ`���܂����B
�ŁA���킹�邱�Ƃɂ��܂����B
�������o��ŁB�B�B�ǂ��܂Ńh�P�`�ȂH�H�@�������I�I
(�������͎����Ȃ̂����A�A����������ă��Ȏ��͐l�ɂ���Ȃ͐l�Ԃ̊�{�B���ꂪ����Ă�B)
���ƂŁA���[���ł̃C���~�����������̂ŁA�����A���֍ێȂ����Ƃɂ��悤�Ǝv���܂��B
�h�P�`�Ő��ӂ��������c���̂Ԃ邾�����ƍň����ȁE�E�A�A
�\�R�܂ł̐l�Ԃ��������B�݂����Ȍ��t��f���Ă����̂ł����A����͂������̃Z���t���ȁB
����҂̐�������낤�Ƃ����A�N�Q���Ă܂ŁA���āA����������Ǝ��ł��ĉ�������Ȃ��ŗǂ��Ȃ�Ƃ��l���Ă����̂����ł��ˁB
�Ƃɂ����A���m����ĕ����C�Ȃǖ����������Ƃ͎������B
�����i��[�������ǂ����������Ă������A���O�̃`�F�b�N�ł����Ɠ����Ă�̂ɂǂ��܂ōs�����犮���i�Ȃ̂��H����͂����炪���߂邱�Ƃ��B
���������A��������Ƃ��A���i�݂̂��Ǝv���Ă�̂��r�߂Ă�؋����B
���[�A�����ł����Ȃ������ȁ[�c�A�A�A
�o���A�Ќ��Ƌ��̖S�҂Ȃ�A�w�������̑����������Ă�n�Y�ŁA�C�̓ł��B
���ɁA���đւ�������Ȃ��̂Ȃ�A�����͂��Ȃ�X���[�y�[�X�ɂȂ�A�w���ւ̃��^�[�������邱�ƂɂȂ�B
220520
����͂������A�g���A�e�������ˁ`�A�A
 �l����ɁA�������͉���낤�Ƃ͂��Ȃ������m��Ȃ��B
�S�Ă̑��u���Ō�܂ł��ӔC������Ƃ������ė��āc�A�A
����́A�₾�ȁB�B
��炩���邩������Ȃ����炱���炪�Ǘ�����Ƃ������Ă����ǁA
���x�������Ԑ��������Ă邵�A�ǂ�ǂ�����Ȃ��čs�����Ɣ����Ă��ł��������R�g�����̂��C�����t�Ȃł��Ă��ȁH
��ŁA�C�ɐH��Ȃ���ǂ����悤���Ȃ��H
�ǂ����悤���Ȃ����Č��\���I�I
����ȂɃh�P�`�ň������������������m�Ȃ���Ă��ƂŁA�悭��������B
��������Ƃ������Ƃ��ǂ��������Ƃ��m��Ă�B
���ꂱ���A����ȕ��傠��Ȃ玩���ł��H�Ǝv�����B
�������������P����Ɗ��҂��Ă��̂����ǁA�S�R�ŋꂵ���B
��v�Ō��������m�ȊO�ɁAESD��A�����[�N�p�i���l����ƁA�قځA�o����ŁA
�����̎��v�́A1.7�����x�ł���B
1.5�`2���������Ƒ��̂��Ƃ������ɂ���Ă����J�������̒��x�Ƃ݂��Ă�̂��ȁA�A�A�A
------------------�|�|�|�|�|
�����e��60MHz�ȉ�H�ɓK�p���Ă݂�B
�ǂ��ɂ����i�𗬗p���l���āA
����ŁA60MHz�̉�H��������Ƃɂ������Ȃ��B
30MHz�̃��[�U�[�������j�b�g��60MHz�̃N���b�N���W���[����t���Č����B
�˂��l�܂��Ă͋��Ȃ���������Ȃ����A�ϒ�����10�`15%�ʂɂȂ��Ă��܂��B
2SC945�̃x�[�X�e�ʂ����邩������Ȃ����ATr�o�͂����Ă��A�U���͉������Ă͂���悤�����ǁA�h��ɉ������Ă�悤�Ȃ��Ƃ͖��������B
�ƂȂ�ƁA��͂�ALD���j�b�g���ȁH�@�܂��A40MHz���x�ɗ}���邱�Ƃɂ��Ă݂Ă��ǂ������H
���ꂩ��̗\�肾�����V�^�C�vAGC-AMP�Ȃ�A���̃^�C�v�͎��g�����肪�Ȃ�����A�ǂ��Ƃł��Ȃ邩���m��Ȃ��B
�ł��AAD603AQ�������B
������3000�~�ƍ����Ă�������2���������Ă̂ɓ͂��Ȃ��悤�Ȓx���͈̂Ӗ��������B
�����ŁA�A���G�N������B
���\�����ȂƂ��낪�o���Ă����B
�ŁA��Ԉ����Ƃ��ŁA�A�U���̉\�����A�����c�A
�l����ɁA�������͉���낤�Ƃ͂��Ȃ������m��Ȃ��B
�S�Ă̑��u���Ō�܂ł��ӔC������Ƃ������ė��āc�A�A
����́A�₾�ȁB�B
��炩���邩������Ȃ����炱���炪�Ǘ�����Ƃ������Ă����ǁA
���x�������Ԑ��������Ă邵�A�ǂ�ǂ�����Ȃ��čs�����Ɣ����Ă��ł��������R�g�����̂��C�����t�Ȃł��Ă��ȁH
��ŁA�C�ɐH��Ȃ���ǂ����悤���Ȃ��H
�ǂ����悤���Ȃ����Č��\���I�I
����ȂɃh�P�`�ň������������������m�Ȃ���Ă��ƂŁA�悭��������B
��������Ƃ������Ƃ��ǂ��������Ƃ��m��Ă�B
���ꂱ���A����ȕ��傠��Ȃ玩���ł��H�Ǝv�����B
�������������P����Ɗ��҂��Ă��̂����ǁA�S�R�ŋꂵ���B
��v�Ō��������m�ȊO�ɁAESD��A�����[�N�p�i���l����ƁA�قځA�o����ŁA
�����̎��v�́A1.7�����x�ł���B
1.5�`2���������Ƒ��̂��Ƃ������ɂ���Ă����J�������̒��x�Ƃ݂��Ă�̂��ȁA�A�A�A
------------------�|�|�|�|�|
�����e��60MHz�ȉ�H�ɓK�p���Ă݂�B
�ǂ��ɂ����i�𗬗p���l���āA
����ŁA60MHz�̉�H��������Ƃɂ������Ȃ��B
30MHz�̃��[�U�[�������j�b�g��60MHz�̃N���b�N���W���[����t���Č����B
�˂��l�܂��Ă͋��Ȃ���������Ȃ����A�ϒ�����10�`15%�ʂɂȂ��Ă��܂��B
2SC945�̃x�[�X�e�ʂ����邩������Ȃ����ATr�o�͂����Ă��A�U���͉������Ă͂���悤�����ǁA�h��ɉ������Ă�悤�Ȃ��Ƃ͖��������B
�ƂȂ�ƁA��͂�ALD���j�b�g���ȁH�@�܂��A40MHz���x�ɗ}���邱�Ƃɂ��Ă݂Ă��ǂ������H
���ꂩ��̗\�肾�����V�^�C�vAGC-AMP�Ȃ�A���̃^�C�v�͎��g�����肪�Ȃ�����A�ǂ��Ƃł��Ȃ邩���m��Ȃ��B
�ł��AAD603AQ�������B
������3000�~�ƍ����Ă�������2���������Ă̂ɓ͂��Ȃ��悤�Ȓx���͈̂Ӗ��������B
�����ŁA�A���G�N������B
���\�����ȂƂ��낪�o���Ă����B
�ŁA��Ԉ����Ƃ��ŁA�A�U���̉\�����A�����c�A
 ���Ȃ�̐��w�����Ă��A�����͕ς��Ȃ����ۂ��B
�v�������Ƃ����ǁATA7124P�͈����������ǁA�U���ł͂Ȃ������B
�ł��A�����C�Z���X���Y���R�s�[�i�ł���\���͂���B
�Ȃ�A�{���̓��Ő��͂���������ƃm�C�Y���Ⴂ�\�����A�������B
Pre-AMP���l���āA
��������60MHz�Ŏg���ׂ����A30MHz�ɂ��ׂ��������܂��ˁB
�ŁA����̎d�����ǂ��Ȃ�����g�`���o�Ȃ��̂ł́H
�Ǝv���A�t�o�C�A�X���������ɁA�^�[�~�l�[�^�[�����ăI�V���ɒ��ɓ���Č����Ƃ���A
���Ȃ�̐��w�����Ă��A�����͕ς��Ȃ����ۂ��B
�v�������Ƃ����ǁATA7124P�͈����������ǁA�U���ł͂Ȃ������B
�ł��A�����C�Z���X���Y���R�s�[�i�ł���\���͂���B
�Ȃ�A�{���̓��Ő��͂���������ƃm�C�Y���Ⴂ�\�����A�������B
Pre-AMP���l���āA
��������60MHz�Ŏg���ׂ����A30MHz�ɂ��ׂ��������܂��ˁB
�ŁA����̎d�����ǂ��Ȃ�����g�`���o�Ȃ��̂ł́H
�Ǝv���A�t�o�C�A�X���������ɁA�^�[�~�l�[�^�[�����ăI�V���ɒ��ɓ���Č����Ƃ���A
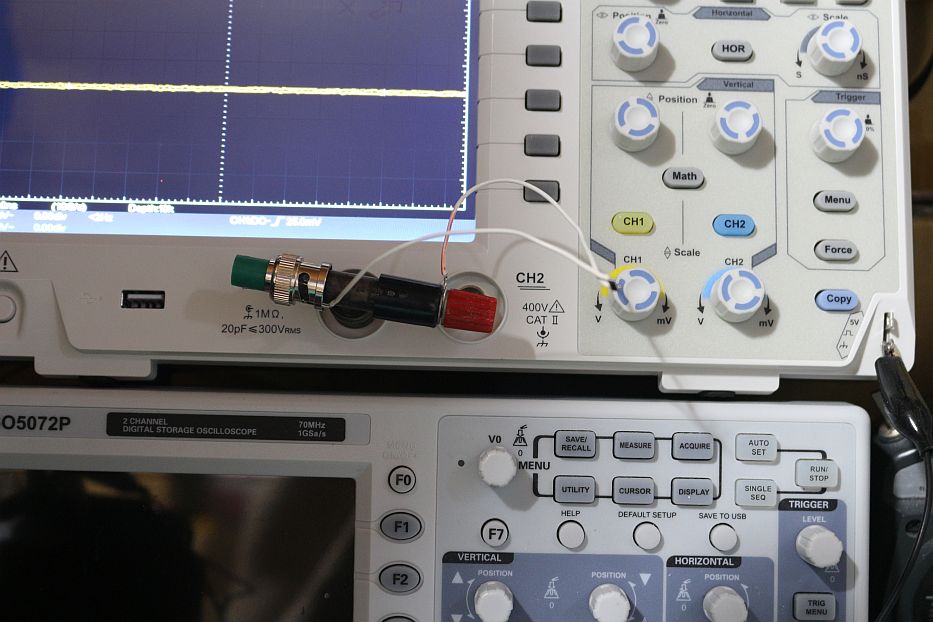 �ϒ�����100%�������������B(���̐ڑ��ł�0���牺�֍s���قnj��������B����������ƃh���C�u���Ă��ǂ������B)
�ϒ�����100%�������������B(���̐ڑ��ł�0���牺�֍s���قnj��������B����������ƃh���C�u���Ă��ǂ������B)
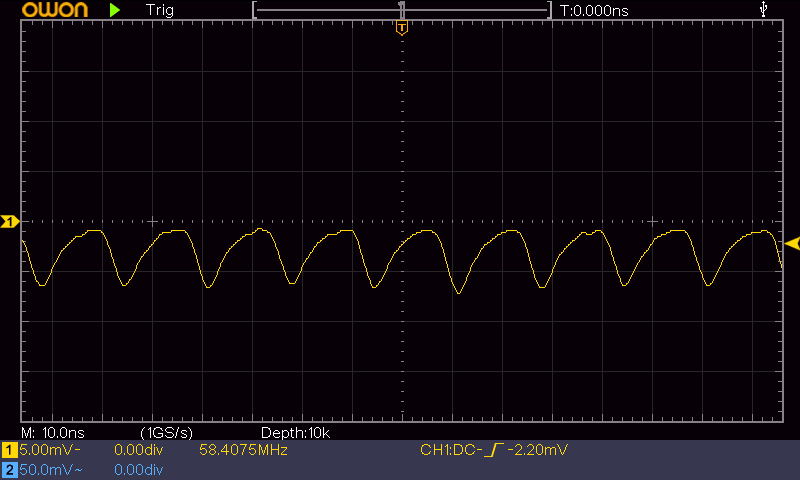 ���g�������r�Ȃ̂́A�g���K�����O�d���ɑ��A���������肹���A�J�E���g�l���������������ł���B
�܂荡�܂ł̑�����@���悭�Ȃ������悤�ł���B
�^�[�~�l�[�^�[�������ƕ�����?�͉�����Ƃ͎v���B���t�o�C�A�X�ł̉��P������B
����́A�p�r�������e�ŁA���v�ł͂Ȃ��B���p�Ƃ������Ƃł���B
------------------------------------------�|�|�|�|�|
220605
���ƁA�A���G�N��AD603AQ�������B
���[���h�������I�Ȃ̂ŁA�U���łȂ��Ǝv���B
�ł��A�����n���_���t���Ă���A�V�i�ł͂Ȃ��悤���B
�܂��A�g����Ε���͖������Ǝv���B
220620
�܂��A�T�Ȗ�肪�������̂����ǁA��̌����e�p�Ƃ��Ďg���ƍl���Ă���B
�ȑO�̊�̉�H�͑g��łȂ����ǁA
�܂��V���Ɏv���������B
���g�������r�Ȃ̂́A�g���K�����O�d���ɑ��A���������肹���A�J�E���g�l���������������ł���B
�܂荡�܂ł̑�����@���悭�Ȃ������悤�ł���B
�^�[�~�l�[�^�[�������ƕ�����?�͉�����Ƃ͎v���B���t�o�C�A�X�ł̉��P������B
����́A�p�r�������e�ŁA���v�ł͂Ȃ��B���p�Ƃ������Ƃł���B
------------------------------------------�|�|�|�|�|
220605
���ƁA�A���G�N��AD603AQ�������B
���[���h�������I�Ȃ̂ŁA�U���łȂ��Ǝv���B
�ł��A�����n���_���t���Ă���A�V�i�ł͂Ȃ��悤���B
�܂��A�g����Ε���͖������Ǝv���B
220620
�܂��A�T�Ȗ�肪�������̂����ǁA��̌����e�p�Ƃ��Ďg���ƍl���Ă���B
�ȑO�̊�̉�H�͑g��łȂ����ǁA
�܂��V���Ɏv���������B
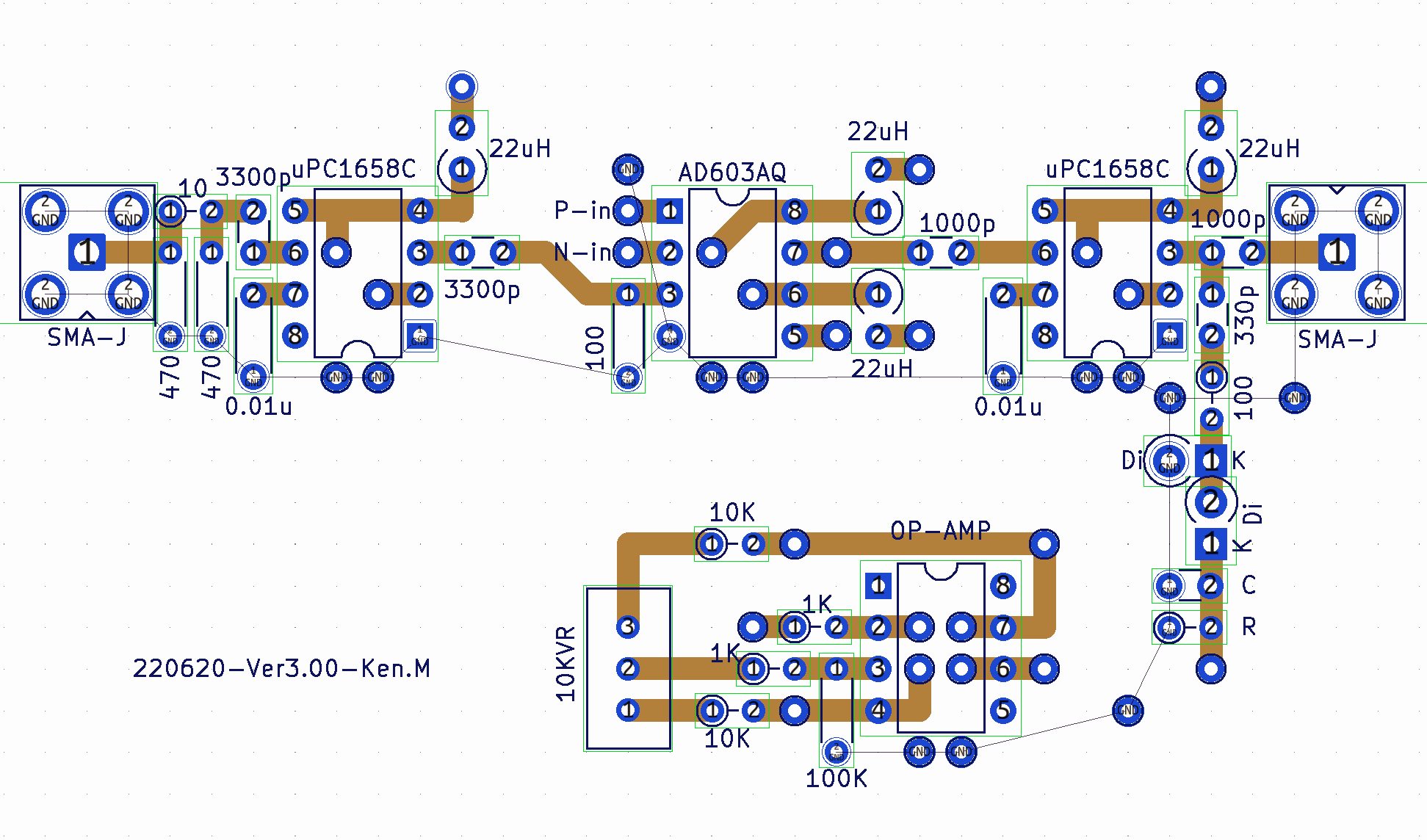 �I�i��OP-AMP�ł͂Ȃ��A��PC-1658C���g���Ƃ��������B
�ǂ��o�邩�͔���Ȃ����ǁA�Q�C���͏\�������A�o�͂��܂��܂��A�m�C�Y�͏��Ȃ��B
�����Č����Δ��U�̐S�z���ȁH
�A�Ғ�R��M���āA���x�ǂ��Q�C���ɏo�������ł͂���B
�Ƃ͂����A�܂��A�����Ǝ҂Ɉ˗����ȁH�H
���ʃx�^GND��1.6mm���A�łǂ��ɂ��B�Ƃ��v���Ă���B
�M�����ɉ����āAGND�ɃX���[�z�[����ł��˂B
���̓��ɂ��`
----------------------------------------------------�|�|�|�|�|
220622
��������B
�g�[�^���Ƃ��Ă�����JLCPCB�ɂ����B
$5�̃N�[�|�����������̂����邯�ǁA�����_�ł͑��������Ȃ�����̂��I�ׂ�B
-----------------------------------------------------�|�|�|�|�|
220705
���Ȃ�ȑO�A�����̃R�[�i�[�ŏ��������Ƃ����ǁA
�����̐��͓d�q�ł͖����̂�����A
Tr�̓����܂Œ��ׂĂ��o���͂��܂����A�f�B�X�N���[�g���x�X�g�ŗǂ��B�̂��B�Ƃ͗]��v���Ă��Ȃ��ł��B
�܂��A�����āA
�Ă��d���ɂ͔[���ɉ������X�s�[�h�ƗʎY�����v�������͂��ł������B
-�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�ł��A�d���������Ƃ��ɂ́A�Ƃ͍l���Ă��������Ƃ������B
FCZ�R�C���̑�p�B�܂��͑傫�ȃp���[����o�͂���ꍇ�B
�g���C�_���R�C�����g���A�����̓Z���~�b�N�g���}�[�ƂȂ�B
��������́A3�`4�F1���x�ŗǂ��Ǝv���B
�^�[������L�̃C���s�[�_���X�Ōv�Z�o����̂�50����肿����ƒႢ�ƃC�C���ȁH
�Z���^�[�^�b�v���~������A�o�C�t�@�C���[�������ǂ����Ǝv���B
60MHz�ƂȂ�ƁA
�R�A�́A�s�T�O�|�P�O��s�R�V�|�U���ǂ����B�ꎟ����10�`12T�ʂ��ȁH
���ӂ́A�������͓����悤�Ɍ����Ă��A���g���ɂ���ĕς��̂ŁA�L���Ȏ��g���Ŏg���R�g�B
���ɁAAGC��VCA�ȏW�ω�H�����őg�ނɂ́AVATT��Di��A3SK�Ȃǂ�FET�̑�2�Q�[�g�ւ�NFB���ǂ��Ǝv���B
���i�ɑg�ނ��Ƃɂ��A�Q�C���R���g���[���͈͂��L���Ȃ�B
�ʑ����o��̍�����DBM�́A�����ł́A�g�����X��Di�u���b�W��p���Ă����B�X�C�b�`���O�@�\�ŃA���B
��_�́A���̓Q�C�������\�K�v�ȃR�g�B�Ȃ̂ŁA�����3SK��FET�Ȃǂ��g���Ɨǂ��B���A��p��IC������̂ŃR���ŗǂ��Ƃ����������B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
����̂��Ƃɂ��āA
����̋��K����y���ǂ��ɂ��o���Ă��A�m�������Ƃł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��悭�������B
�ア�����̌��t�ɁA�Ԃ��ꂽ�B
�C�ɂ��đ�����������Ă�̂ɁA���炾��Ƃ���Čo��������Ă͍��邩�炱���炪�Ǘ�����Ƃ��A�����o�����̂��B
�ŁA���̒��x�̐l�ԂƂ������Ă����B�A
������A�ォ��ڐ��Ń}�E���g����Ȃ�A�m��Ă�ƌ����Ă�����B
��̎d�����x��闝�R�́A������ɂ͂Ȃ��B�����炪�̂낢���炾�B
�������Ⴂ���Ƃ��̏�Ȃ����A�ʎY��������Ɖ����邱�Ƃ������ς݂��B
�s���̈������Ƃ͖����������̂悤�Ƀ��V����̂����Ԃ��������������ʂ��B
�Í����̊����́A�J�[�h�̌��ϓ��ł����܂ŃM���M���ɂ��Ă���Ă��̂悤�Ȍ���@�������Ƃ͋����Ȃ��B
�̂̂悵�݂��Ƃ��Ă��A����A�����炱���l�Ԑ����^�����B
������ɉ��̎|�݂̂Ȃ��d����N����Ǝv���Ă�̂��H
����ĕt�������l�Ԃ��~�X�����B
�܂�ȂA������R����ƌ������Ƃ́A
�P�`�ŃA�R�M�ł������肾���珁��ɂ��郏�P���B
�������グ��Η�₷�K�v�Ȃ��ƌ������̂����A�A
�v���Y�}���x��10E+7������10.5��m�̃��[�U�[�ł��A�f�B�e�N�^���₳�Ȃ���A�Ƃ������Ă������A�������Ȃ������B
�R�R�͉��x���W���邪�A�ŏI�I�ɂ͈ʑ���]�p�x���B10.5��m�Ȃ�A���Ȃ���Ǝv���B
�ł���߂��������m�ł͖����B
���Ȃ玩���ł��ƌ��������g�R�����A
���X�A�܂Ƃ��Ɍh�ꂷ�炵��ׂꂸ�A�l�̈����̑����l�Ԃ������̂��A�\�ʂ�180�x�ς���Ă��̂ł��Ԃ������Ɏv�������A�{���͕ς���ĂȂ��̂��낤�B
���������A�w���̐����ŗǂ��|�W�V�������ێ����Ă�������낤�B
�l�Ԑ��ƉȊw���̂Ă��ƌ����C���[�W���ȁB
�܂��A�����~����A����͂����Ƃ������Ƃ��H
�O�`�͂��̕ӂŁA�Ƃ͎v�����ǁA
���̕s���Ɏv���A���������Ă�̂��H�Ƃ����̂�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����C���̓A���B
��Ԃɖ��Ɋ���ĖY��Ă��܂��Ȃǂ������Ȃ�����B
����ɁA���ꂾ�����Ȏ�������A
���A���������C�������̂��������B
�u�g�D�͓z�ꂩ���̂Ȃ��T���ăK�`���Ă邾���v���Ă̂������ǁA
�܂��A�����瑤�̐l�Ԃɖ]��łȂ����̂��낤����ˁB
�ł������͂����]��łȂ��ƌ������Ƃ����A���߂��Ă����킹��`���������B
230117�F���̐l�������Ă����ǁA�o����l�Ԃ�����Ǝז��Ȃ̂ŁA�킴�ƒǂ��o�����Ƃ��邱�Ƃ�����B�ƌ������Ƃ��l���������ǂ��B�ƁB
�l�����̃��J�j�Y�����Ⴄ�Ƃ������A�܂��A��Ԃɖڗ���������Ηǂ����A
���ɋ��߂Ă镪�삪�A�ڗ����Ƃ�o������~�Ȃ̂Ȃ�s�����@�ɂ܂�Ȃ��B�ł����������̂͑����Ǝv���B
���ꂱ���A���]�ݒʂ�}�X�R�~�ɍs�����Ďv�����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�Ȋw���Ă̂́A
�����ɍ��������ȗ��������ˉĂ��A
�ŏI�I�Ɏ��ۂƍ����Ă邩���̂ɂȂ�A�_���Ȃ璵�˂���B
�܂肻���܂ł́u���f�v���d�v�ł���B
���Ɏ���������Ȃ��B�ň��A�����Ȃ��B����ȃ}�E���g�^�C�v���悭���Ă����̂ŁA
�����͖��p���Ɠr���Œ��߂āA�����čs���悤�ɂ������Ƃ����x������B
���w����w�K���Ă��A�p����������A�������Ǝv���̂����c�A
���ɏ�ɗ��ƁA�N���w�E���ɂ������A�����ɂȂ邩��A�C�����o���Ȃ��Ȃ��Ă����B
�N���K���������������f���o����Ƃ͌���Ȃ��Ƃ������\�������肦�Ȃ����炾���A
���C�g�X�^�b�t�Ƃ͂ǂ��������Ƃ��H
�Ƃ����������ȁB
�܂�A�I���̓I�}�G����.�����琳����.
�݂����ȃ}�E���g���x�����I����l���́A���������Ȋw���x���Ƃ��Ăǂ��ȂH�Ƃ����l���B
�ł��A�悭����̂��A�A
���Ƃ́A�l�̎��s�����āA�������u�Ԉ���Ă�v��A�Ă��J��Ԃ����c�́A�A����σ_�����ˁB
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���������̂������܂����B
�I�i��OP-AMP�ł͂Ȃ��A��PC-1658C���g���Ƃ��������B
�ǂ��o�邩�͔���Ȃ����ǁA�Q�C���͏\�������A�o�͂��܂��܂��A�m�C�Y�͏��Ȃ��B
�����Č����Δ��U�̐S�z���ȁH
�A�Ғ�R��M���āA���x�ǂ��Q�C���ɏo�������ł͂���B
�Ƃ͂����A�܂��A�����Ǝ҂Ɉ˗����ȁH�H
���ʃx�^GND��1.6mm���A�łǂ��ɂ��B�Ƃ��v���Ă���B
�M�����ɉ����āAGND�ɃX���[�z�[����ł��˂B
���̓��ɂ��`
----------------------------------------------------�|�|�|�|�|
220622
��������B
�g�[�^���Ƃ��Ă�����JLCPCB�ɂ����B
$5�̃N�[�|�����������̂����邯�ǁA�����_�ł͑��������Ȃ�����̂��I�ׂ�B
-----------------------------------------------------�|�|�|�|�|
220705
���Ȃ�ȑO�A�����̃R�[�i�[�ŏ��������Ƃ����ǁA
�����̐��͓d�q�ł͖����̂�����A
Tr�̓����܂Œ��ׂĂ��o���͂��܂����A�f�B�X�N���[�g���x�X�g�ŗǂ��B�̂��B�Ƃ͗]��v���Ă��Ȃ��ł��B
�܂��A�����āA
�Ă��d���ɂ͔[���ɉ������X�s�[�h�ƗʎY�����v�������͂��ł������B
-�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�ł��A�d���������Ƃ��ɂ́A�Ƃ͍l���Ă��������Ƃ������B
FCZ�R�C���̑�p�B�܂��͑傫�ȃp���[����o�͂���ꍇ�B
�g���C�_���R�C�����g���A�����̓Z���~�b�N�g���}�[�ƂȂ�B
��������́A3�`4�F1���x�ŗǂ��Ǝv���B
�^�[������L�̃C���s�[�_���X�Ōv�Z�o����̂�50����肿����ƒႢ�ƃC�C���ȁH
�Z���^�[�^�b�v���~������A�o�C�t�@�C���[�������ǂ����Ǝv���B
60MHz�ƂȂ�ƁA
�R�A�́A�s�T�O�|�P�O��s�R�V�|�U���ǂ����B�ꎟ����10�`12T�ʂ��ȁH
���ӂ́A�������͓����悤�Ɍ����Ă��A���g���ɂ���ĕς��̂ŁA�L���Ȏ��g���Ŏg���R�g�B
���ɁAAGC��VCA�ȏW�ω�H�����őg�ނɂ́AVATT��Di��A3SK�Ȃǂ�FET�̑�2�Q�[�g�ւ�NFB���ǂ��Ǝv���B
���i�ɑg�ނ��Ƃɂ��A�Q�C���R���g���[���͈͂��L���Ȃ�B
�ʑ����o��̍�����DBM�́A�����ł́A�g�����X��Di�u���b�W��p���Ă����B�X�C�b�`���O�@�\�ŃA���B
��_�́A���̓Q�C�������\�K�v�ȃR�g�B�Ȃ̂ŁA�����3SK��FET�Ȃǂ��g���Ɨǂ��B���A��p��IC������̂ŃR���ŗǂ��Ƃ����������B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
����̂��Ƃɂ��āA
����̋��K����y���ǂ��ɂ��o���Ă��A�m�������Ƃł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��悭�������B
�ア�����̌��t�ɁA�Ԃ��ꂽ�B
�C�ɂ��đ�����������Ă�̂ɁA���炾��Ƃ���Čo��������Ă͍��邩�炱���炪�Ǘ�����Ƃ��A�����o�����̂��B
�ŁA���̒��x�̐l�ԂƂ������Ă����B�A
������A�ォ��ڐ��Ń}�E���g����Ȃ�A�m��Ă�ƌ����Ă�����B
��̎d�����x��闝�R�́A������ɂ͂Ȃ��B�����炪�̂낢���炾�B
�������Ⴂ���Ƃ��̏�Ȃ����A�ʎY��������Ɖ����邱�Ƃ������ς݂��B
�s���̈������Ƃ͖����������̂悤�Ƀ��V����̂����Ԃ��������������ʂ��B
�Í����̊����́A�J�[�h�̌��ϓ��ł����܂ŃM���M���ɂ��Ă���Ă��̂悤�Ȍ���@�������Ƃ͋����Ȃ��B
�̂̂悵�݂��Ƃ��Ă��A����A�����炱���l�Ԑ����^�����B
������ɉ��̎|�݂̂Ȃ��d����N����Ǝv���Ă�̂��H
����ĕt�������l�Ԃ��~�X�����B
�܂�ȂA������R����ƌ������Ƃ́A
�P�`�ŃA�R�M�ł������肾���珁��ɂ��郏�P���B
�������グ��Η�₷�K�v�Ȃ��ƌ������̂����A�A
�v���Y�}���x��10E+7������10.5��m�̃��[�U�[�ł��A�f�B�e�N�^���₳�Ȃ���A�Ƃ������Ă������A�������Ȃ������B
�R�R�͉��x���W���邪�A�ŏI�I�ɂ͈ʑ���]�p�x���B10.5��m�Ȃ�A���Ȃ���Ǝv���B
�ł���߂��������m�ł͖����B
���Ȃ玩���ł��ƌ��������g�R�����A
���X�A�܂Ƃ��Ɍh�ꂷ�炵��ׂꂸ�A�l�̈����̑����l�Ԃ������̂��A�\�ʂ�180�x�ς���Ă��̂ł��Ԃ������Ɏv�������A�{���͕ς���ĂȂ��̂��낤�B
���������A�w���̐����ŗǂ��|�W�V�������ێ����Ă�������낤�B
�l�Ԑ��ƉȊw���̂Ă��ƌ����C���[�W���ȁB
�܂��A�����~����A����͂����Ƃ������Ƃ��H
�O�`�͂��̕ӂŁA�Ƃ͎v�����ǁA
���̕s���Ɏv���A���������Ă�̂��H�Ƃ����̂�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����C���̓A���B
��Ԃɖ��Ɋ���ĖY��Ă��܂��Ȃǂ������Ȃ�����B
����ɁA���ꂾ�����Ȏ�������A
���A���������C�������̂��������B
�u�g�D�͓z�ꂩ���̂Ȃ��T���ăK�`���Ă邾���v���Ă̂������ǁA
�܂��A�����瑤�̐l�Ԃɖ]��łȂ����̂��낤����ˁB
�ł������͂����]��łȂ��ƌ������Ƃ����A���߂��Ă����킹��`���������B
230117�F���̐l�������Ă����ǁA�o����l�Ԃ�����Ǝז��Ȃ̂ŁA�킴�ƒǂ��o�����Ƃ��邱�Ƃ�����B�ƌ������Ƃ��l���������ǂ��B�ƁB
�l�����̃��J�j�Y�����Ⴄ�Ƃ������A�܂��A��Ԃɖڗ���������Ηǂ����A
���ɋ��߂Ă镪�삪�A�ڗ����Ƃ�o������~�Ȃ̂Ȃ�s�����@�ɂ܂�Ȃ��B�ł����������̂͑����Ǝv���B
���ꂱ���A���]�ݒʂ�}�X�R�~�ɍs�����Ďv�����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�Ȋw���Ă̂́A
�����ɍ��������ȗ��������ˉĂ��A
�ŏI�I�Ɏ��ۂƍ����Ă邩���̂ɂȂ�A�_���Ȃ璵�˂���B
�܂肻���܂ł́u���f�v���d�v�ł���B
���Ɏ���������Ȃ��B�ň��A�����Ȃ��B����ȃ}�E���g�^�C�v���悭���Ă����̂ŁA
�����͖��p���Ɠr���Œ��߂āA�����čs���悤�ɂ������Ƃ����x������B
���w����w�K���Ă��A�p����������A�������Ǝv���̂����c�A
���ɏ�ɗ��ƁA�N���w�E���ɂ������A�����ɂȂ邩��A�C�����o���Ȃ��Ȃ��Ă����B
�N���K���������������f���o����Ƃ͌���Ȃ��Ƃ������\�������肦�Ȃ����炾���A
���C�g�X�^�b�t�Ƃ͂ǂ��������Ƃ��H
�Ƃ����������ȁB
�܂�A�I���̓I�}�G����.�����琳����.
�݂����ȃ}�E���g���x�����I����l���́A���������Ȋw���x���Ƃ��Ăǂ��ȂH�Ƃ����l���B
�ł��A�悭����̂��A�A
���Ƃ́A�l�̎��s�����āA�������u�Ԉ���Ă�v��A�Ă��J��Ԃ����c�́A�A����σ_�����ˁB
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���������̂������܂����B
 �O�ɍ�����X�C�b�`���̂Ɏ��Ă邯�ǁA
�J�[�g���b�W�Ƃ��Ď��e�̖ɂ͂ߍ��ށB
���j�������ꂽ���u�Ԃ̂���B
������A�X�}�z�����m���ē����������ǂ����肷��悤�ł���B
������������̂́A2��ށA��u���[�U�[���_���̂�
��u������^�C�v�ł���B����������H�Ō��o����B
�X�}�z������Ȃ�A�X�R�[�v�Ƀf�W�J���g�ݍ���ŁA�����������肵�Ă��ǂ��Ǝv���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���D�����B
�O�ɍ�����X�C�b�`���̂Ɏ��Ă邯�ǁA
�J�[�g���b�W�Ƃ��Ď��e�̖ɂ͂ߍ��ށB
���j�������ꂽ���u�Ԃ̂���B
������A�X�}�z�����m���ē����������ǂ����肷��悤�ł���B
������������̂́A2��ށA��u���[�U�[���_���̂�
��u������^�C�v�ł���B����������H�Ō��o����B
�X�}�z������Ȃ�A�X�R�[�v�Ƀf�W�J���g�ݍ���ŁA�����������肵�Ă��ǂ��Ǝv���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���D�����B
 �x�[�X�����ȊO�͗ǍD���ȁ[�A�A�Ɨ\�����Ă���B
�z���_�[�̃}�C�N�����[�^�[���t��������������ƎK�тĂ���ɂ�ł��肵�܂������A���X�y�l�łǂ��ɂ��Ȃ�܂����B��薳���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220910
�V���Ȍ����e�������B
https://hobby.watch.impress.co.jp/docs/news/1438279.html
�e���ɃZ���T�[������A���[�U�[�����B���B��70m���Ƃ��B
���[�U�[��70m���Ă̂́A�Z�����ł��ˁB
�e��_���Ƃ����͖̂ʔ����ϓ_�����m��Ȃ��B
�V���v�������A�e�͌��Ƃ��K���I�o���邩��B
���B�����Ɛ��x�̋����Ƃ������V�r�A���̕ω��̊W�́A�^���ɍl����Ɠ�������ł��ˁB
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
DVD��LD�́A���[�U�[Di�̔��M��380MHz������Ă���Ƃ����L�����g���Z�œǂ݂܂����B
S/N���グ�邽�߂炵���ł����A�摜�ɉe�����o��Ə����Ă������̂͏ꍇ�ɂ��P�������ł��ˁB
�ł����āAUHF���ڂ���Z�p�ł����AAPC�̌���UHF�ȏd���H���ڑ�����Ă���Ƃ������m�ŁA
�܂��́AAPC��H�Ń��[�U�[���U����X���b�V�����h�M���M���̏�Ԃɒu���B
������380MHz�̎�߂̍����g�d�����d�˂銴���ł��B
����ŏo����炵���ł��B
APC�ւ̃t�B�[�h�o�b�N����͊ɂ₩�ȐM���݂̂̂悤�ł��B�����������ł����I�[�_�[���������Ⴄ�̂ňĊO���N�ɂ��܂��s���̂����f�X�ˁB
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�Ƃ���ŁA
��ʍw�������˂��̂����A
SONY�̐ԊO�������R������pIC�uCX20106A�v�Ƃ����̂�����B�����g��M�Ƃ��ė��p����邱�Ƃ�����悤�����A
�����A35KHz�Ƃ��[�����ǂ������Ƃ��������B
�Q�C���͍ő�80dB�炵���B������߂ł͂��邪�A������Q�l�ɂ��Ă݂�̂��ǂ���������Ȃ��B
����قnjÂ�IC�ł����������Ȃ̂ŁA�A
���ׂ���`���Ŏg���Ă����Â�������W���[��������IC�������B
�Ȃ̂ŁA40�N�߂��O�����m��Ȃ��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�����o�b�t�@�[�FBUF634
�����Ɏg���邩���H
230422
AGC-AMP������Ă�̂����A�Q�C���Əo�͂͒Ⴂ������Ȃ�̐��\�B
�Ȃ̂ŁA���W���������Ƃ���B
�ŁAPre-AMP�{�tBIAS��H������Ă݂��B
60MHzAGC-AMP�ɂ���APre-AMP��������
�t�H�g�f�B�e�N�^�ɋt�o�C�A�X���������H�t���B
�x�[�X�����ȊO�͗ǍD���ȁ[�A�A�Ɨ\�����Ă���B
�z���_�[�̃}�C�N�����[�^�[���t��������������ƎK�тĂ���ɂ�ł��肵�܂������A���X�y�l�łǂ��ɂ��Ȃ�܂����B��薳���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
220910
�V���Ȍ����e�������B
https://hobby.watch.impress.co.jp/docs/news/1438279.html
�e���ɃZ���T�[������A���[�U�[�����B���B��70m���Ƃ��B
���[�U�[��70m���Ă̂́A�Z�����ł��ˁB
�e��_���Ƃ����͖̂ʔ����ϓ_�����m��Ȃ��B
�V���v�������A�e�͌��Ƃ��K���I�o���邩��B
���B�����Ɛ��x�̋����Ƃ������V�r�A���̕ω��̊W�́A�^���ɍl����Ɠ�������ł��ˁB
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
DVD��LD�́A���[�U�[Di�̔��M��380MHz������Ă���Ƃ����L�����g���Z�œǂ݂܂����B
S/N���グ�邽�߂炵���ł����A�摜�ɉe�����o��Ə����Ă������̂͏ꍇ�ɂ��P�������ł��ˁB
�ł����āAUHF���ڂ���Z�p�ł����AAPC�̌���UHF�ȏd���H���ڑ�����Ă���Ƃ������m�ŁA
�܂��́AAPC��H�Ń��[�U�[���U����X���b�V�����h�M���M���̏�Ԃɒu���B
������380MHz�̎�߂̍����g�d�����d�˂銴���ł��B
����ŏo����炵���ł��B
APC�ւ̃t�B�[�h�o�b�N����͊ɂ₩�ȐM���݂̂̂悤�ł��B�����������ł����I�[�_�[���������Ⴄ�̂ňĊO���N�ɂ��܂��s���̂����f�X�ˁB
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�Ƃ���ŁA
��ʍw�������˂��̂����A
SONY�̐ԊO�������R������pIC�uCX20106A�v�Ƃ����̂�����B�����g��M�Ƃ��ė��p����邱�Ƃ�����悤�����A
�����A35KHz�Ƃ��[�����ǂ������Ƃ��������B
�Q�C���͍ő�80dB�炵���B������߂ł͂��邪�A������Q�l�ɂ��Ă݂�̂��ǂ���������Ȃ��B
����قnjÂ�IC�ł����������Ȃ̂ŁA�A
���ׂ���`���Ŏg���Ă����Â�������W���[��������IC�������B
�Ȃ̂ŁA40�N�߂��O�����m��Ȃ��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�����o�b�t�@�[�FBUF634
�����Ɏg���邩���H
230422
AGC-AMP������Ă�̂����A�Q�C���Əo�͂͒Ⴂ������Ȃ�̐��\�B
�Ȃ̂ŁA���W���������Ƃ���B
�ŁAPre-AMP�{�tBIAS��H������Ă݂��B
60MHzAGC-AMP�ɂ���APre-AMP��������
�t�H�g�f�B�e�N�^�ɋt�o�C�A�X���������H�t���B
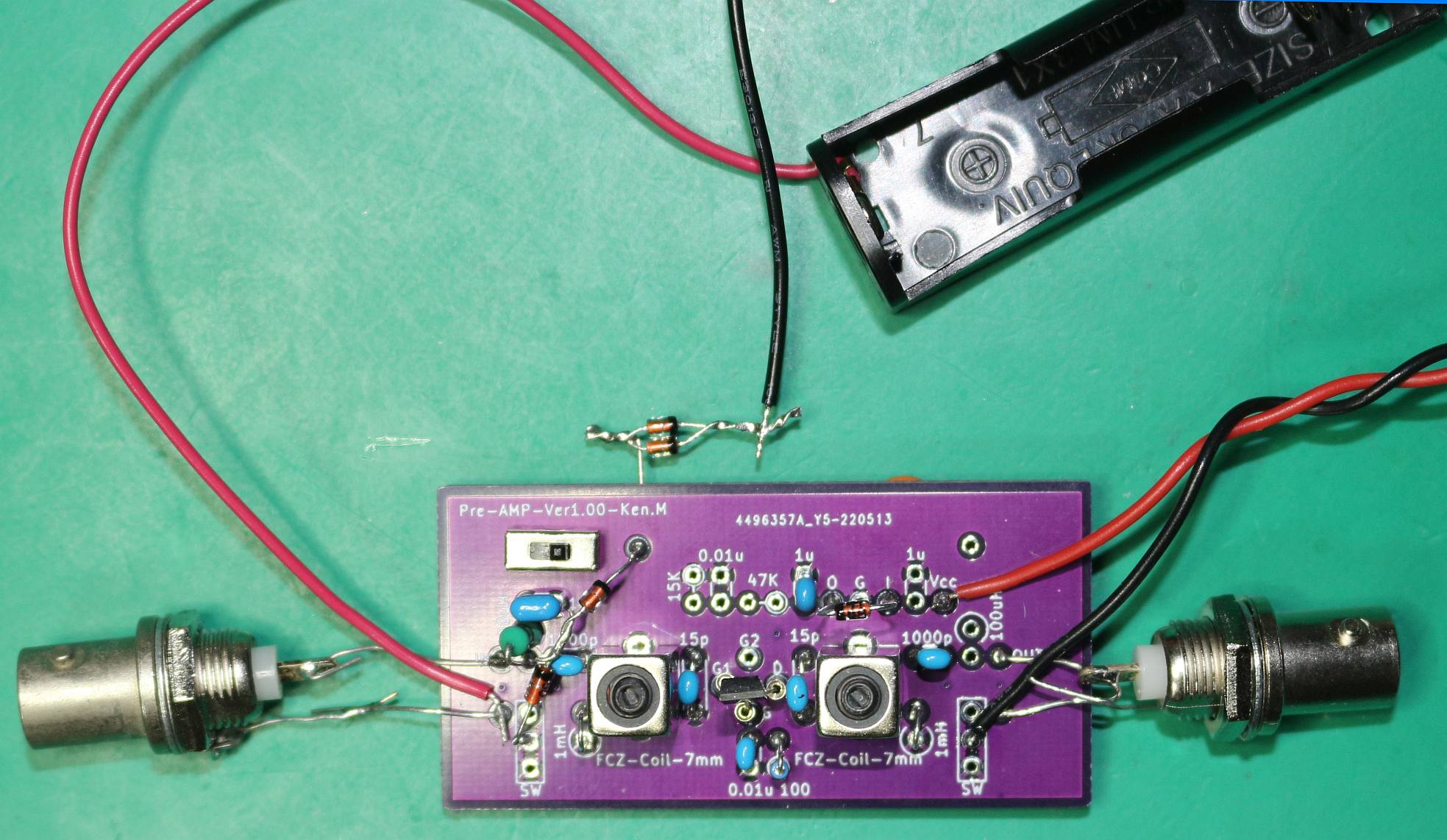 �ꉞ�A2SK439�Ƃ����Â�FET���g���Ă邯�ǁA
���ݔ̔�����Ă�2SK212�����X�Q�C�����Ⴂ���ǎg����̂ŁA��X�����S�ȉ�H�B
Rs�͕ς���K�v����B
�z���g�͏����̐v����m�C�Y�ȉq���ʐM�p��3SK��FET�̗\��̊�������̂ŁA�]���Ă�Ƃ��낪��������A�A
���[�U�[��60MHz��������PIN�t�H�gDi�Ŏ���ɂāA
�t�o�C�A�X�����Ȃ�L���ɓ������Ƃ��m�F�B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
230503
�ŋ߂�RF-AMP��IC��SMD�d�l�ł������Ⴂ�̂����邯�ǁA
�����g�����Ő_�o���g�������ł��A���ANF������g���Ƃ����������Ƃ������̂ŁA
���_�́A�ĊO�Q�C���������āA�o�͂��f�J�����m����������A
�ł����āA���w�����p�̃~���[�z���_�[��LD���j�b�g��t�������̂����ǁA
�s�J�e�B�j�[��20mm���[�����g���A�|�����������ƍl�����B
�ŏ����[�����A100�ψȉ����x���̎����ł����Ă��A���̈ꌅ��̈ٗl�ȍ������������̂ŁA
�^�����l�����B
�R���������ǂ��B
�ꉞ�A2SK439�Ƃ����Â�FET���g���Ă邯�ǁA
���ݔ̔�����Ă�2SK212�����X�Q�C�����Ⴂ���ǎg����̂ŁA��X�����S�ȉ�H�B
Rs�͕ς���K�v����B
�z���g�͏����̐v����m�C�Y�ȉq���ʐM�p��3SK��FET�̗\��̊�������̂ŁA�]���Ă�Ƃ��낪��������A�A
���[�U�[��60MHz��������PIN�t�H�gDi�Ŏ���ɂāA
�t�o�C�A�X�����Ȃ�L���ɓ������Ƃ��m�F�B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
230503
�ŋ߂�RF-AMP��IC��SMD�d�l�ł������Ⴂ�̂����邯�ǁA
�����g�����Ő_�o���g�������ł��A���ANF������g���Ƃ����������Ƃ������̂ŁA
���_�́A�ĊO�Q�C���������āA�o�͂��f�J�����m����������A
�ł����āA���w�����p�̃~���[�z���_�[��LD���j�b�g��t�������̂����ǁA
�s�J�e�B�j�[��20mm���[�����g���A�|�����������ƍl�����B
�ŏ����[�����A100�ψȉ����x���̎����ł����Ă��A���̈ꌅ��̈ٗl�ȍ������������̂ŁA
�^�����l�����B
�R���������ǂ��B
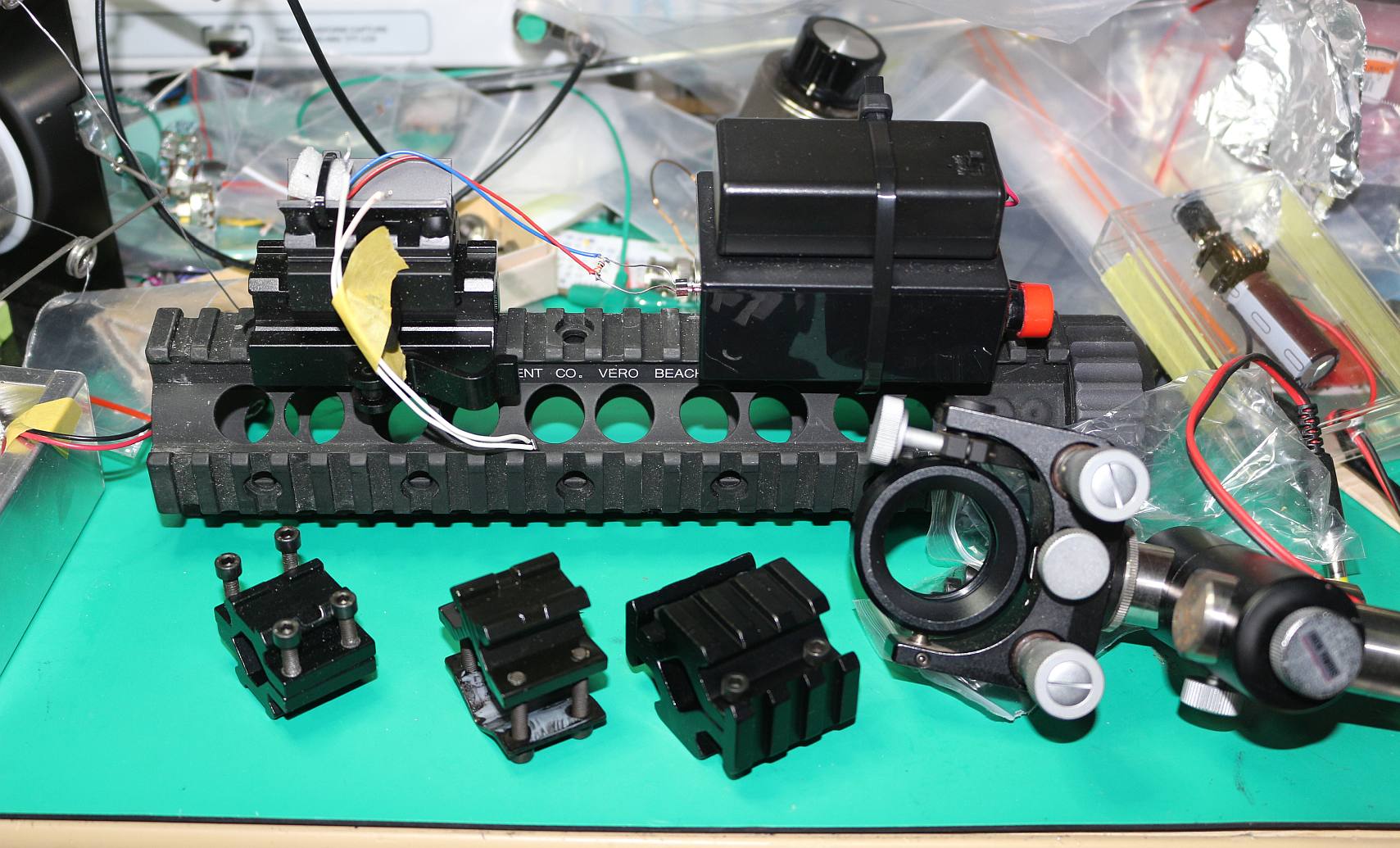 �^��肭��ƁA��т˂�v���X�`�b�N 150g��880�~�Ȃ̂ōw���B
���ʘ_���猾���ƁA���G�͈����Ȃ��������ǁA���ڂ̎��s�ō��܂����B�B
�O�҂͓����|�b�g�ōĕ��������āA�T�[���X�J�b�v�ɓ���āA
�����Č^��肵�悤�Ƃ������A�ǂ����A���̍a���|���s���Ȃ������B
�����ƒg�߂���A��҂��g�����肷��Ύ|���s�����������A�Ȃ��A�J��Ԃ��̂��Ȃ�Ƃ��B
�^��肭��ƁA��т˂�v���X�`�b�N 150g��880�~�Ȃ̂ōw���B
���ʘ_���猾���ƁA���G�͈����Ȃ��������ǁA���ڂ̎��s�ō��܂����B�B
�O�҂͓����|�b�g�ōĕ��������āA�T�[���X�J�b�v�ɓ���āA
�����Č^��肵�悤�Ƃ������A�ǂ����A���̍a���|���s���Ȃ������B
�����ƒg�߂���A��҂��g�����肷��Ύ|���s�����������A�Ȃ��A�J��Ԃ��̂��Ȃ�Ƃ��B
 �ŁA���ύX�B
�A���G�N��400�~�͂��Ȃ������A�l�W���o�����Ȃ��̃��[�����������̂ŃR�����g���B
�ڒ��́A1�N�O���炢����b��́A�u�d���Əu���ȁA�v�����y�A���ǂ��ł���B�Z���e�[�v�ł��ڂ�Ȃ��悤�ɂ��āA�������ϑw���銴���ł��B
�u���́A100�ς̃Z���_�C���ϏՌ��ȍ��̃��c�B�Ȃ��Ȃ��ł܂�Ȃ��̂ŁA�ŏ��̈ʒu���߂̎��̓X�[�p�[�t�ł������Ă���ł���A
�ŁA���ύX�B
�A���G�N��400�~�͂��Ȃ������A�l�W���o�����Ȃ��̃��[�����������̂ŃR�����g���B
�ڒ��́A1�N�O���炢����b��́A�u�d���Əu���ȁA�v�����y�A���ǂ��ł���B�Z���e�[�v�ł��ڂ�Ȃ��悤�ɂ��āA�������ϑw���銴���ł��B
�u���́A100�ς̃Z���_�C���ϏՌ��ȍ��̃��c�B�Ȃ��Ȃ��ł܂�Ȃ��̂ŁA�ŏ��̈ʒu���߂̎��̓X�[�p�[�t�ł������Ă���ł���A
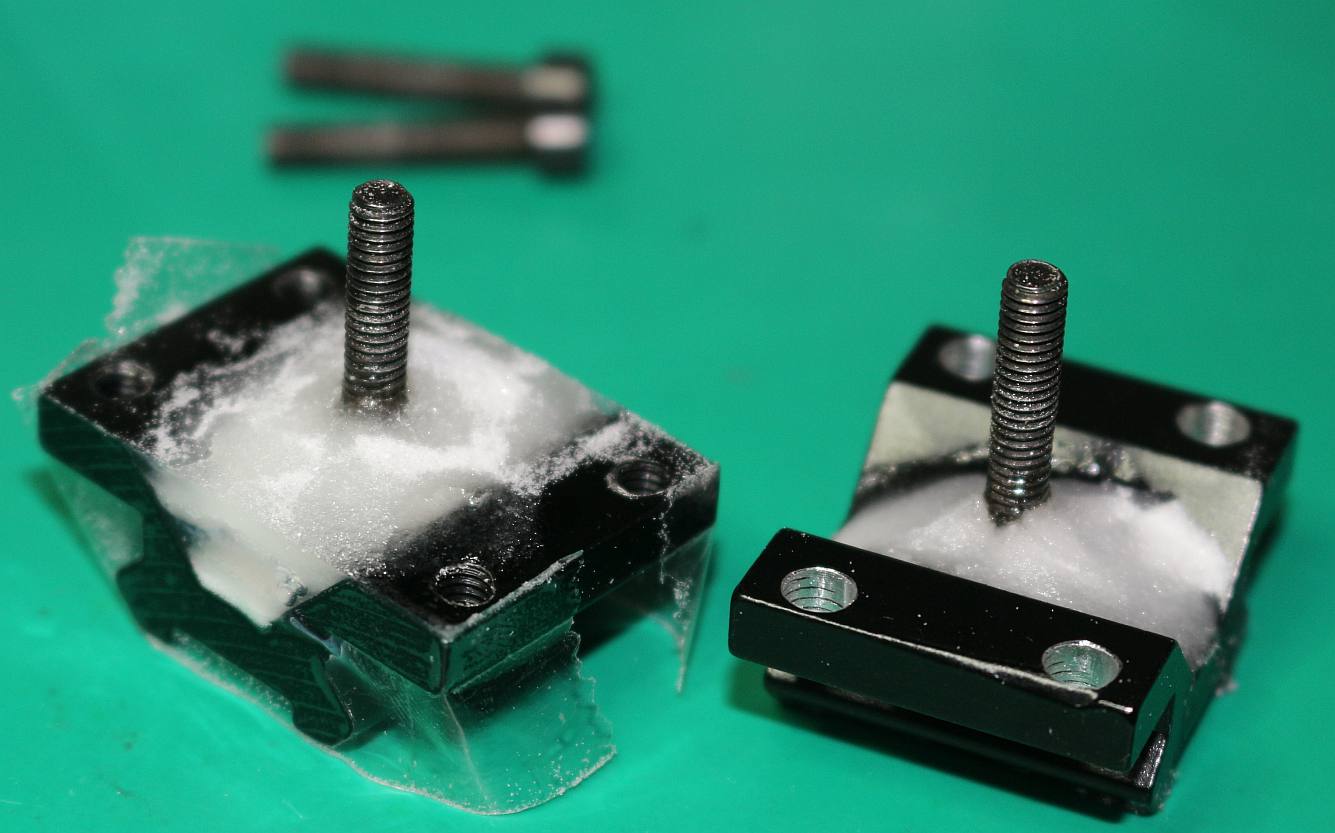
 �~���[�z���_�[�̓�30mm�̃��m�Ȃ̂ŁA��30mm�a�AT=5mm���̃A�N�����𒍕������̂����A
���ՂŐ^�Ƀl�W�����J���āA�͂߂悤�Ǝv������A�a��30.8mm���x�����Ă͂܂�Ȃ��B
�]���āA���S�̃l�W��͂�ŁA�܂����ՂŁA�Ǝv�������ǁA���Ղ̗͂̕����̓l�W���ɂ߂�����Ȃ̂ŁA
���Ղ��t��]�����A�˂���o�C�g�Ŗ����������B���A�܂��A����Ȃ�Ɏ|�����Ă͂܂����B
�~���[�z���_�[�̓�30mm�̃��m�Ȃ̂ŁA��30mm�a�AT=5mm���̃A�N�����𒍕������̂����A
���ՂŐ^�Ƀl�W�����J���āA�͂߂悤�Ǝv������A�a��30.8mm���x�����Ă͂܂�Ȃ��B
�]���āA���S�̃l�W��͂�ŁA�܂����ՂŁA�Ǝv�������ǁA���Ղ̗͂̕����̓l�W���ɂ߂�����Ȃ̂ŁA
���Ղ��t��]�����A�˂���o�C�g�Ŗ����������B���A�܂��A����Ȃ�Ɏ|�����Ă͂܂����B
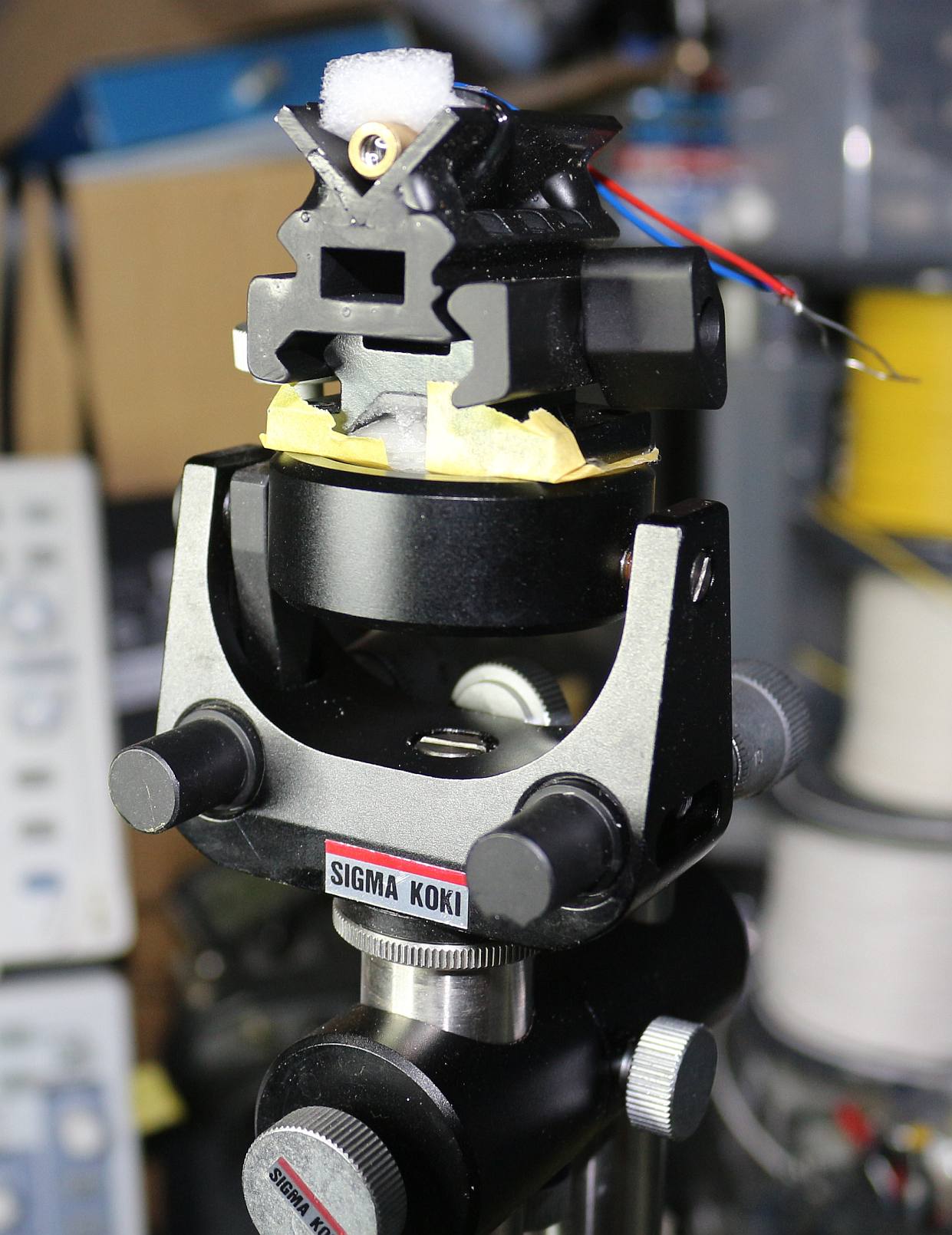 ���U��̌Œ�ɂ܂��ۑ肠��A
60MHz���ƃP�[�u���͂��܂蒷���͏o���Ȃ��̂��ǂ����邩�B�B
230505
�~���[�z���_�[�Ńe�X�g�B
��̏��Ńx�[�X���ӂ�ӂ�ł���B
�����łȂ��Ă��A�����l�W�́A1m���x�̋����ł́A���Ȃ�ׂ������邭�炢�ł���B
�t�o�C�A�X��-1.0V�ł���B�����X3.39He-Ne���[�U�[�p�̃f�B�e�N�^�̎d�l�B
����ł��A�V�O�i���͔{������B
�I�V���̓d�������W�́A50mV/Div�ł��Ȃ苭���V�O�i���ł��邪�A�������荇�킹��A�����Ƌ���1.5�{���x�͏o��B
���������A����������������ƁA�������ĖO�a����v�f�����邩���m��Ȃ�.
�����̃V���R��Pin�t�H�gDi�ɖ��������Ă���B
���U��̌Œ�ɂ܂��ۑ肠��A
60MHz���ƃP�[�u���͂��܂蒷���͏o���Ȃ��̂��ǂ����邩�B�B
230505
�~���[�z���_�[�Ńe�X�g�B
��̏��Ńx�[�X���ӂ�ӂ�ł���B
�����łȂ��Ă��A�����l�W�́A1m���x�̋����ł́A���Ȃ�ׂ������邭�炢�ł���B
�t�o�C�A�X��-1.0V�ł���B�����X3.39He-Ne���[�U�[�p�̃f�B�e�N�^�̎d�l�B
����ł��A�V�O�i���͔{������B
�I�V���̓d�������W�́A50mV/Div�ł��Ȃ苭���V�O�i���ł��邪�A�������荇�킹��A�����Ƌ���1.5�{���x�͏o��B
���������A����������������ƁA�������ĖO�a����v�f�����邩���m��Ȃ�.
�����̃V���R��Pin�t�H�gDi�ɖ��������Ă���B
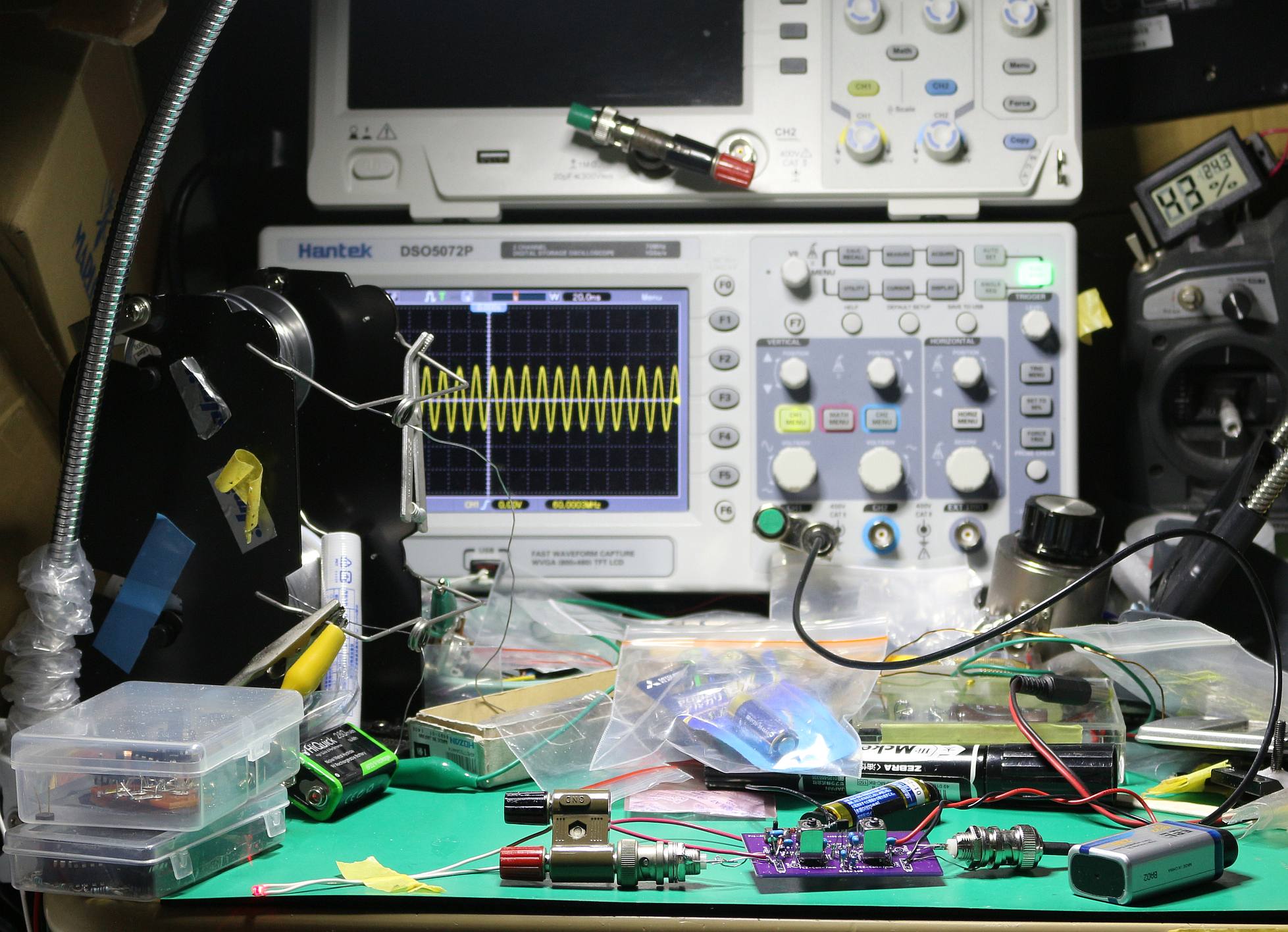 �E���ɔ������B
�E���ɔ������B
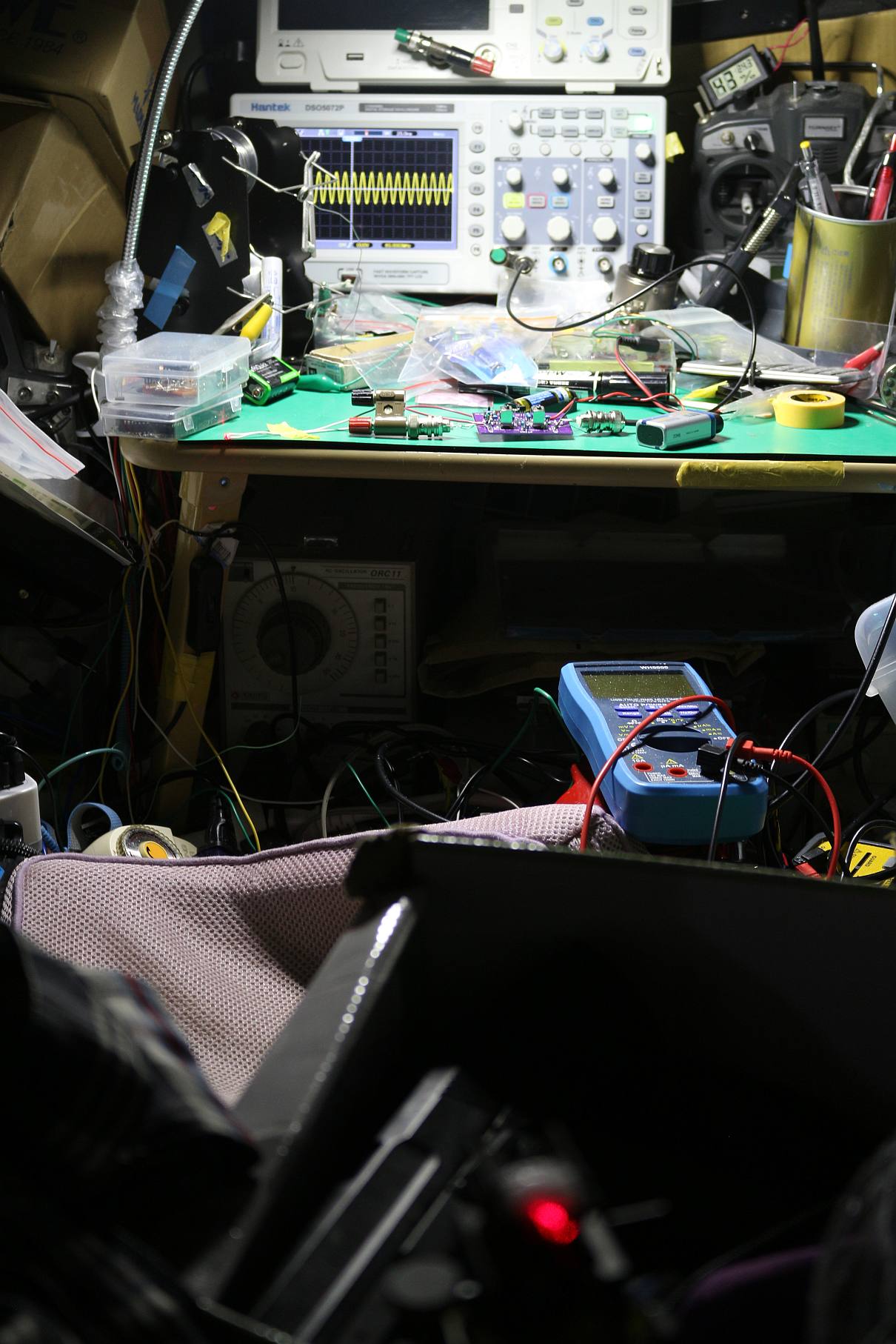 �������W���[�����t�����ɕt���邱�ƂŁA�P�[�u�����M���M������Ă���B
�������W���[�����t�����ɕt���邱�ƂŁA�P�[�u�����M���M������Ă���B
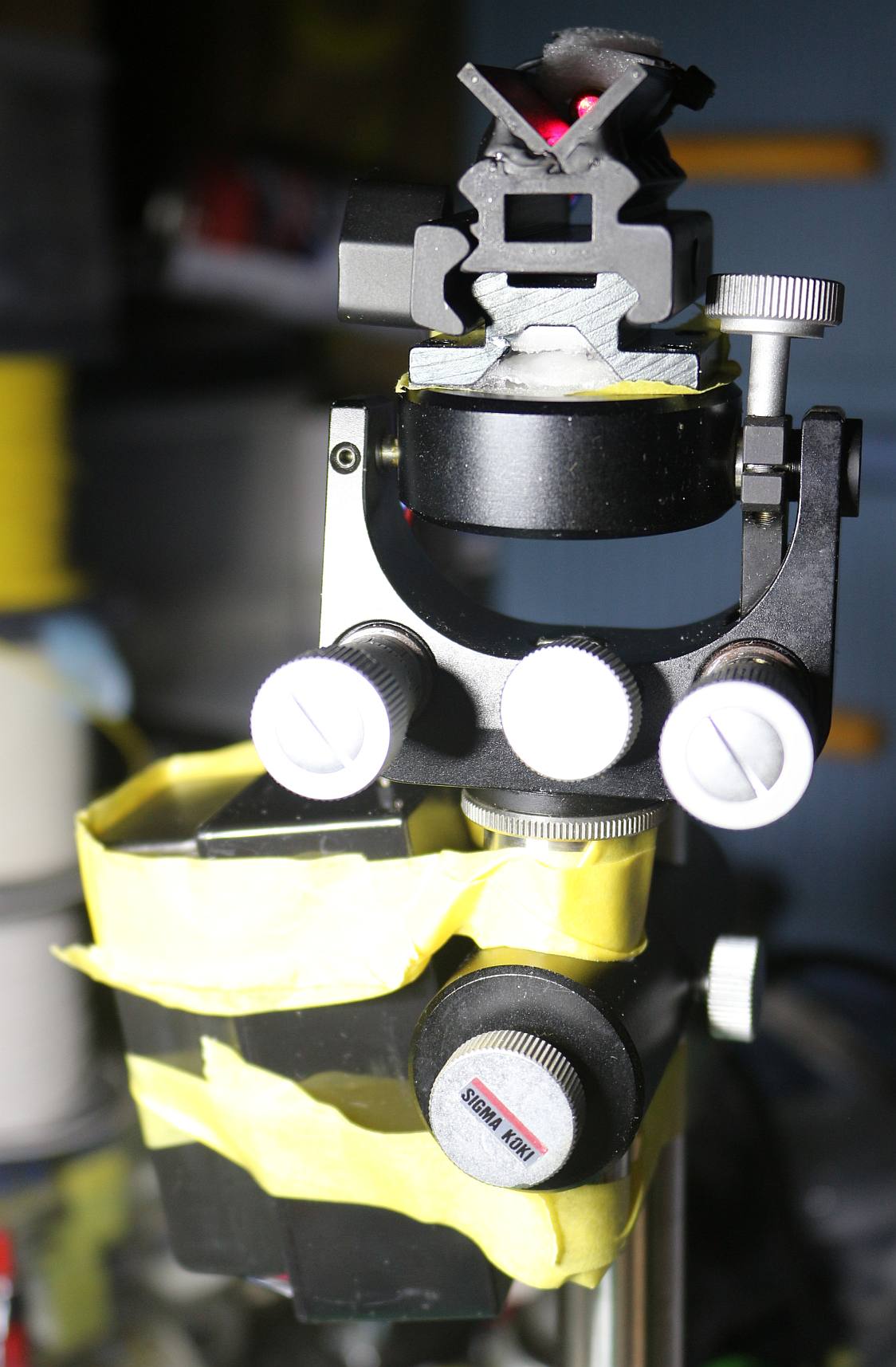 ���́A�����V���b�g�g���K�[��H���g������Ԃłǂ����H�����Ă݂����B
230505-2
�����V���b�g�ɂ��Ă���Ă݂��B
���́A�����V���b�g�g���K�[��H���g������Ԃłǂ����H�����Ă݂����B
230505-2
�����V���b�g�ɂ��Ă���Ă݂��B
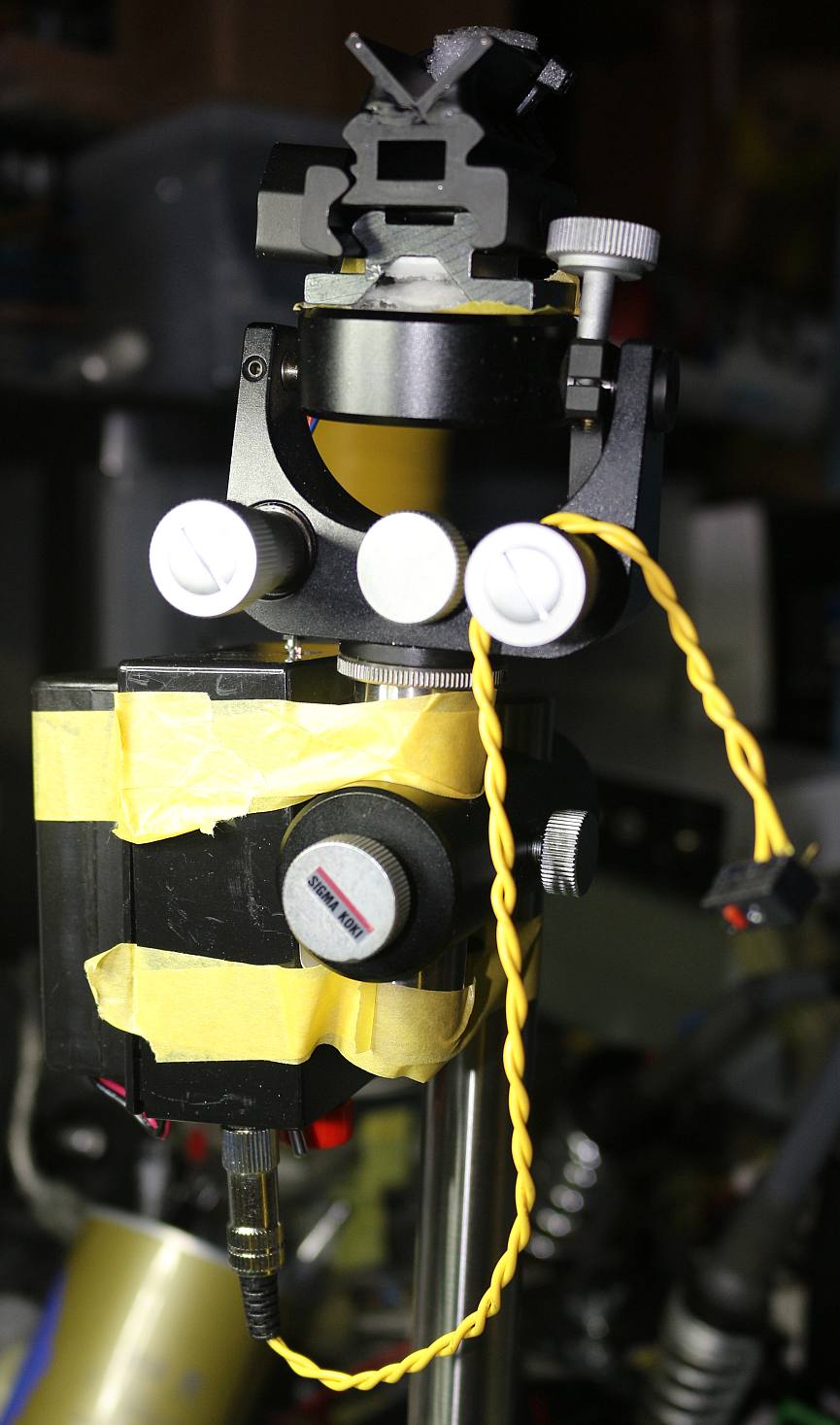 �v���O����c�C�X�g�P�[�u������āAD2F�n�̃}�C�N���X�C�b�`��t���Ă���B
����̔����M����555���g���K�����O����B
�ŁA���Č���ɁA�A
���U���Ԃ�100��Sec�s�b�^���ɃZ�b�g���Ă��Ă������B���������Ƃ̕��u�ŖY��Ă��B
�o�����̐M���̑傫���͂�����ƋC�ɂȂ邩���H
(������H��������Ɠ���Ă����炩���H�H�ł�60MHz�̓R���f���T�[���ђʂ��邩��A�����A�M���̕ϒ������グ���������̂����邩���B�Ǝv������C�͓d���Ɍq�����Ă����̂ŕʂ������B)
�v���O����c�C�X�g�P�[�u������āAD2F�n�̃}�C�N���X�C�b�`��t���Ă���B
����̔����M����555���g���K�����O����B
�ŁA���Č���ɁA�A
���U���Ԃ�100��Sec�s�b�^���ɃZ�b�g���Ă��Ă������B���������Ƃ̕��u�ŖY��Ă��B
�o�����̐M���̑傫���͂�����ƋC�ɂȂ邩���H
(������H��������Ɠ���Ă����炩���H�H�ł�60MHz�̓R���f���T�[���ђʂ��邩��A�����A�M���̕ϒ������グ���������̂����邩���B�Ǝv������C�͓d���Ɍq�����Ă����̂ŕʂ������B)
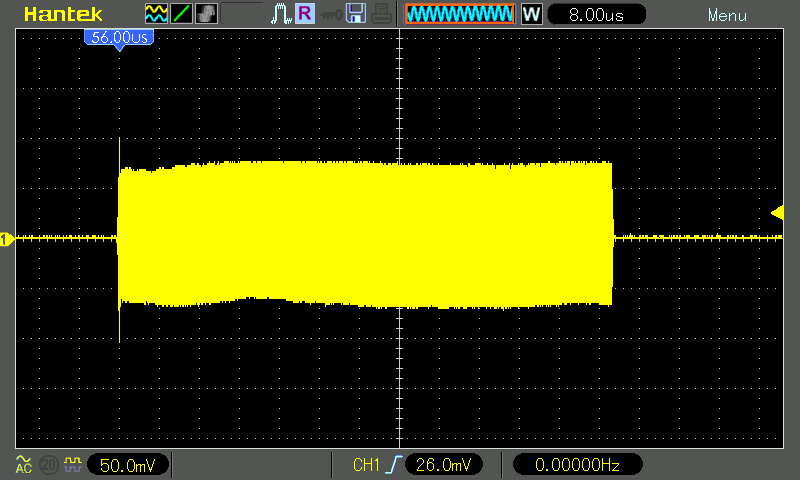 �g�傷��Ƃ���Ȋ����B555����C1815���h���C�u���Ă����炻�̉e�����A
��������Ԃ���n�܂��āA���ɃI�[�o�[�V���[�g���Ă�����肷��B�U���Ɏ��Ԃ�������̂�Pre-AMP�̋��n�̗�N���Ԃ����H�H�c�ɂ��Ă͒����Ƃ͎v���B
�g�傷��Ƃ���Ȋ����B555����C1815���h���C�u���Ă����炻�̉e�����A
��������Ԃ���n�܂��āA���ɃI�[�o�[�V���[�g���Ă�����肷��B�U���Ɏ��Ԃ�������̂�Pre-AMP�̋��n�̗�N���Ԃ����H�H�c�ɂ��Ă͒����Ƃ͎v���B
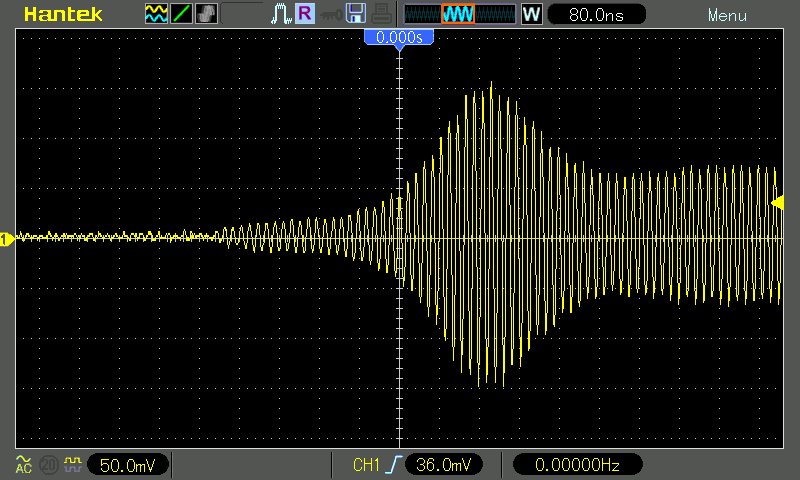 LD���n�Y���āA�����P�[�u�����q���A50���Ń^�[�~�l�[�g������Ԃœd���M��������
�R���Ō���ƈӊO�ɂ��A���܂�ϒ�����ĂȂ���Ԃő傫�Ȕ��������Ă��Ă�悤�ł���B300nSec�قǂ̊ԃI�[�o�[�V���[�g���Ă�����肷��B
LD���n�Y���āA�����P�[�u�����q���A50���Ń^�[�~�l�[�g������Ԃœd���M��������
�R���Ō���ƈӊO�ɂ��A���܂�ϒ�����ĂȂ���Ԃő傫�Ȕ��������Ă��Ă�悤�ł���B300nSec�قǂ̊ԃI�[�o�[�V���[�g���Ă�����肷��B
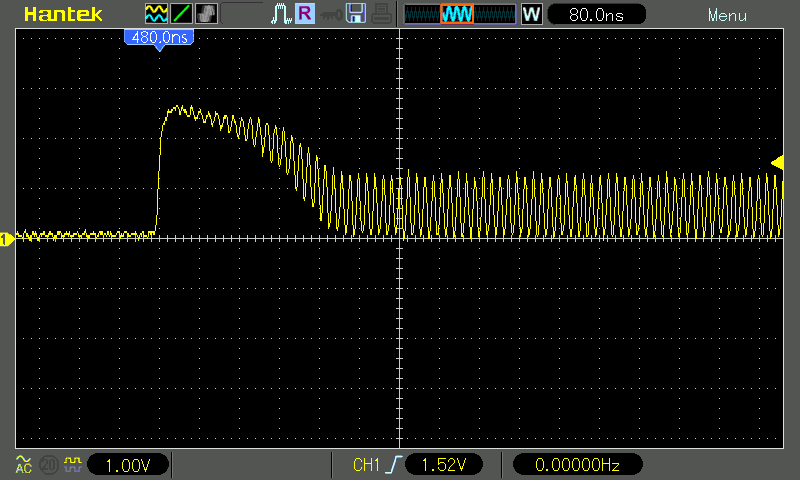 100��Sec�Œe����1000m/Sec�Ƃ��Ɖߒ��ł��u���͂��������e�����������ǁA
AGC-AMP�̔������l���ăM���M���͂���ȃ��m���ȁ[�Ƃ����l�ɃZ�b�g���Ă݂�B
���U���Ԃ̃p���X���A15��Sec�s�b�^���ɐݒ�B
100��Sec�Œe����1000m/Sec�Ƃ��Ɖߒ��ł��u���͂��������e�����������ǁA
AGC-AMP�̔������l���ăM���M���͂���ȃ��m���ȁ[�Ƃ����l�ɃZ�b�g���Ă݂�B
���U���Ԃ̃p���X���A15��Sec�s�b�^���ɐݒ�B
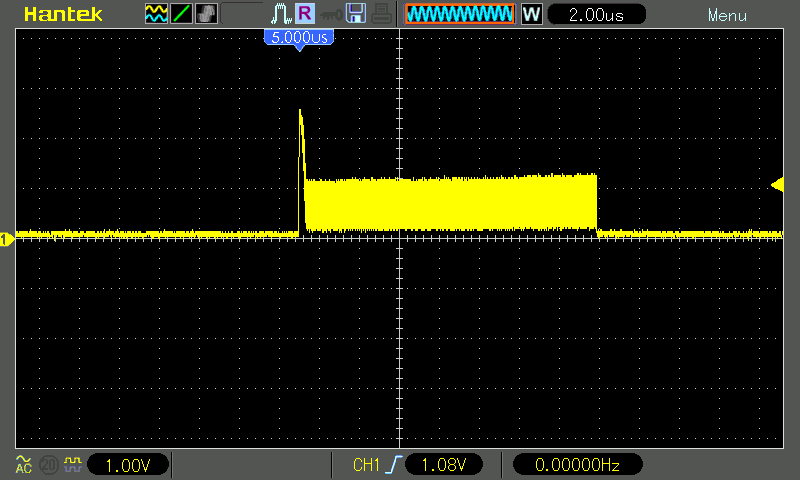 ���Ԏ������������Ă݂�ɁA�M���M���ł͂��邪�A����Ȋ����B
(����܂莞�Ԏ����k�߂�ƃT���v�����O���[�g����ς��A�\���ƍ����g�������ĕςȔg�`���o���肷��B�G�C���A�V���O�݂����Ȍ���)
���Ԏ������������Ă݂�ɁA�M���M���ł͂��邪�A����Ȋ����B
(����܂莞�Ԏ����k�߂�ƃT���v�����O���[�g����ς��A�\���ƍ����g�������ĕςȔg�`���o���肷��B�G�C���A�V���O�݂����Ȍ���)
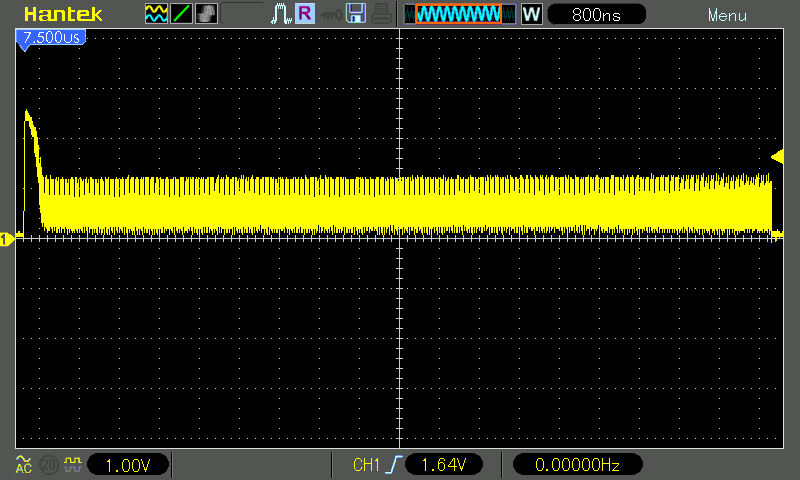 �쓮�d���M�����烌�[�U�[���̑���ɖ߂��Ă݂�Ƃ���Ȋ����B
�ǂ������ł͂���Ǝv�����A�I�[�o�[�V���[�g�����������ǂ��Ǝv���Ă͂���B���̓˓��d���݂����Ȃ͉̂��Ȃ̂��낤�H
���_�A�V���b�g�pTr��ʂ��Ȃ��Ńo�C�p�X��ԂŒ�R�ɂēd����ݒ肵�Ă邩��A��i�͉z���Ȃ��B���A�t�Ɍ����Ǝ������Ă����Ԃ̔����̃��X���傫���ƌ������ƂȂ̂��ȁH�H
�Ȃɂ��A��N���O���㉺������̂ł͖����A�d���[�����甭�������Ă�̂ŁA�A�܂��A���������̉��x�Ƃ������邩������Ȃ��H
�쓮�d���M�����烌�[�U�[���̑���ɖ߂��Ă݂�Ƃ���Ȋ����B
�ǂ������ł͂���Ǝv�����A�I�[�o�[�V���[�g�����������ǂ��Ǝv���Ă͂���B���̓˓��d���݂����Ȃ͉̂��Ȃ̂��낤�H
���_�A�V���b�g�pTr��ʂ��Ȃ��Ńo�C�p�X��ԂŒ�R�ɂēd����ݒ肵�Ă邩��A��i�͉z���Ȃ��B���A�t�Ɍ����Ǝ������Ă����Ԃ̔����̃��X���傫���ƌ������ƂȂ̂��ȁH�H
�Ȃɂ��A��N���O���㉺������̂ł͖����A�d���[�����甭�������Ă�̂ŁA�A�܂��A���������̉��x�Ƃ������邩������Ȃ��H
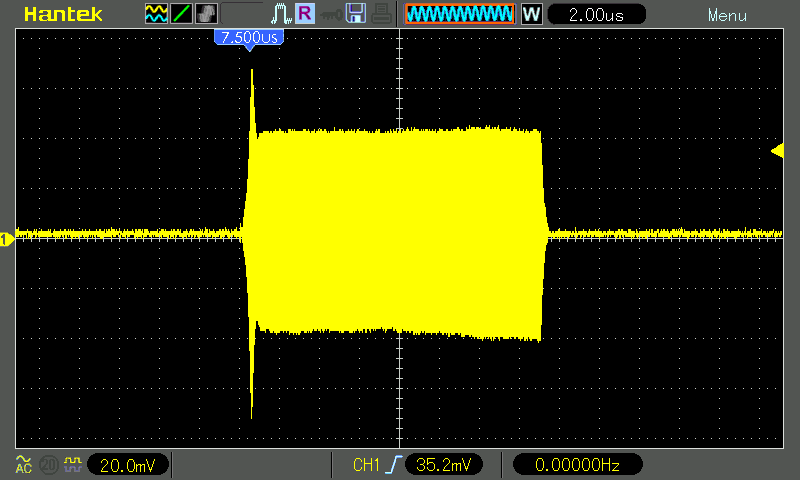 ����́A���i�ɂ�2���ۂœd���ƌ����x���Ɍ���Ζ��炩�����A
60MHz�̃I�[�o�[�V���[�g�́ADC�I�d���̃I�[�o�[�V���[�g�̌�ɋN�����Ă�Ǝv���B
����́ALD�����ł̃��[�U�[���U��Ԃ̕ω��Ȃ̂����m��Ȃ��B���������Ƃ���Ƃ��̌��G�l���M�[��LD������炵���̂łǂ��Ȃ̂��B
�����́A�I�[�o�[�V���[�g�����d����60MHz���|�������ƁA0����̔��U���ᖳ���̂ŁA���U��Ԃ̕ϓ��̐U�����ǂ��Ȃ��Ă���\�����A���B
�����ŁA
���炩���߁A������x�d�����X���[������LD�ɏ������̃o�C�A�X��������LED��ԋ߂��ňÂ����点�Ă����悤�Ȑݒ���v�������B�܂背�[�U�[�̈�̗�N�������ɂȂ邩�ƁB
�Ƃ������Ƃ́A���������ɂȂ��āA�������[�U�[���̕ϒ��������҂ł��邩���B
����́A���i�ɂ�2���ۂœd���ƌ����x���Ɍ���Ζ��炩�����A
60MHz�̃I�[�o�[�V���[�g�́ADC�I�d���̃I�[�o�[�V���[�g�̌�ɋN�����Ă�Ǝv���B
����́ALD�����ł̃��[�U�[���U��Ԃ̕ω��Ȃ̂����m��Ȃ��B���������Ƃ���Ƃ��̌��G�l���M�[��LD������炵���̂łǂ��Ȃ̂��B
�����́A�I�[�o�[�V���[�g�����d����60MHz���|�������ƁA0����̔��U���ᖳ���̂ŁA���U��Ԃ̕ϓ��̐U�����ǂ��Ȃ��Ă���\�����A���B
�����ŁA
���炩���߁A������x�d�����X���[������LD�ɏ������̃o�C�A�X��������LED��ԋ߂��ňÂ����点�Ă����悤�Ȑݒ���v�������B�܂背�[�U�[�̈�̗�N�������ɂȂ邩�ƁB
�Ƃ������Ƃ́A���������ɂȂ��āA�������[�U�[���̕ϒ��������҂ł��邩���B
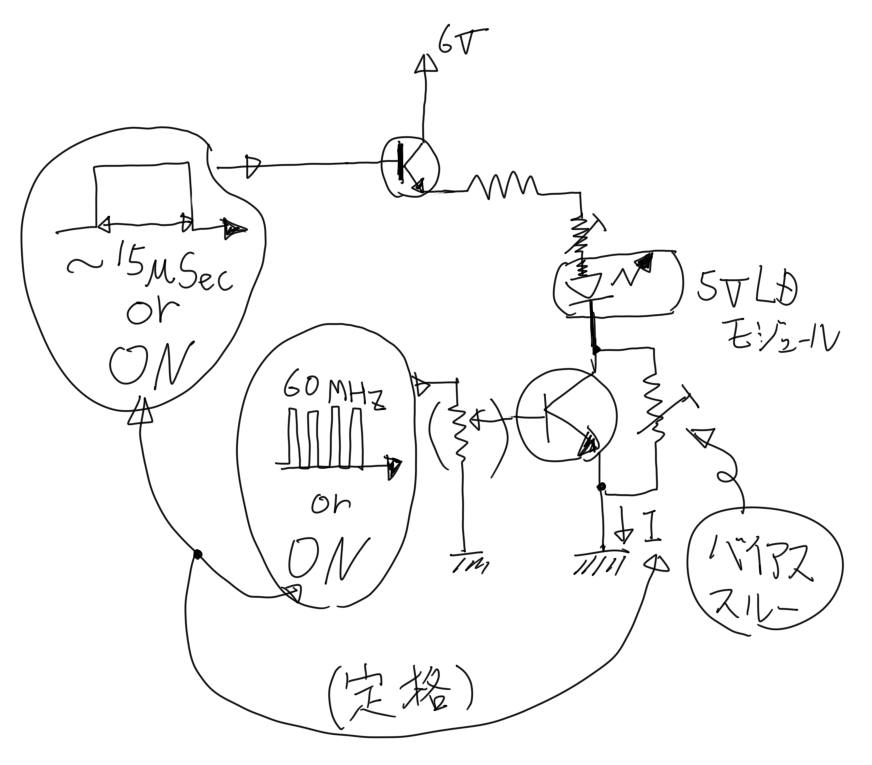 �������ςőg�ݍ��ނ͍̂�Ə㌋�\�ɓ�V���ȁA�A�A�H
5mA���xDC�����𗬂��悤�ɂ��Ă݂���A�C�P�邩���H500�`1K�����x���ȁH
1K���t������A�ꉞ�キ���U���Ă��ԁH���Ă������x�������̂ŁA�������傢�ア�����ǂ��݂��������ǁA�A
�ő�d����C1815������VR�Ō��߂āA(�Œ��R33���ɂ�����d������d����\�z)�B
C945�̎�O�ŁA�ϒ���������������Ƌl�߂�d�l���������Ǝv���̂ł����A33���ɂ�330mV���������Ă�B
�M���Č��āA�ϒ����͂���Ȋ�����MAX�ƂȂ����B
�������ςőg�ݍ��ނ͍̂�Ə㌋�\�ɓ�V���ȁA�A�A�H
5mA���xDC�����𗬂��悤�ɂ��Ă݂���A�C�P�邩���H500�`1K�����x���ȁH
1K���t������A�ꉞ�キ���U���Ă��ԁH���Ă������x�������̂ŁA�������傢�ア�����ǂ��݂��������ǁA�A
�ő�d����C1815������VR�Ō��߂āA(�Œ��R33���ɂ�����d������d����\�z)�B
C945�̎�O�ŁA�ϒ���������������Ƌl�߂�d�l���������Ǝv���̂ł����A33���ɂ�330mV���������Ă�B
�M���Č��āA�ϒ����͂���Ȋ�����MAX�ƂȂ����B
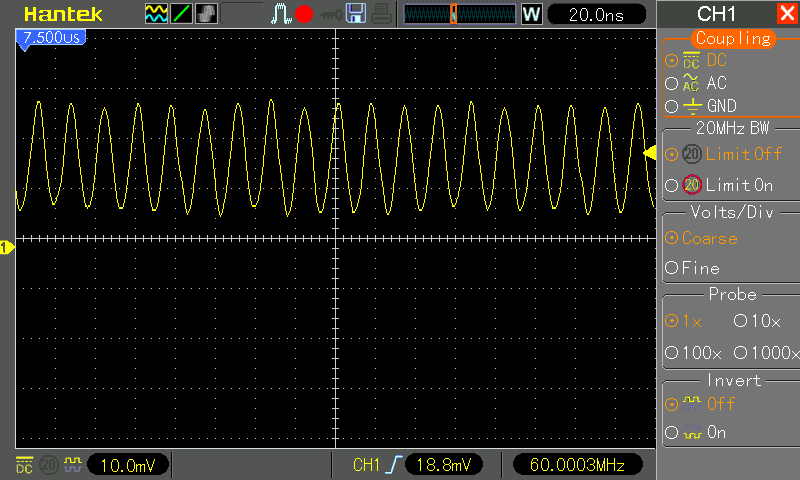 200MHz�I�V���ɕς����炱����̕����A����C���傫�߂Ȃ̂�����̂��A�U�����������H
�g�`�̒Ⴂ�Ƃ����c��ł܂�������������͖����A�A
200MHz�I�V���ɕς����炱����̕����A����C���傫�߂Ȃ̂�����̂��A�U�����������H
�g�`�̒Ⴂ�Ƃ����c��ł܂�������������͖����A�A
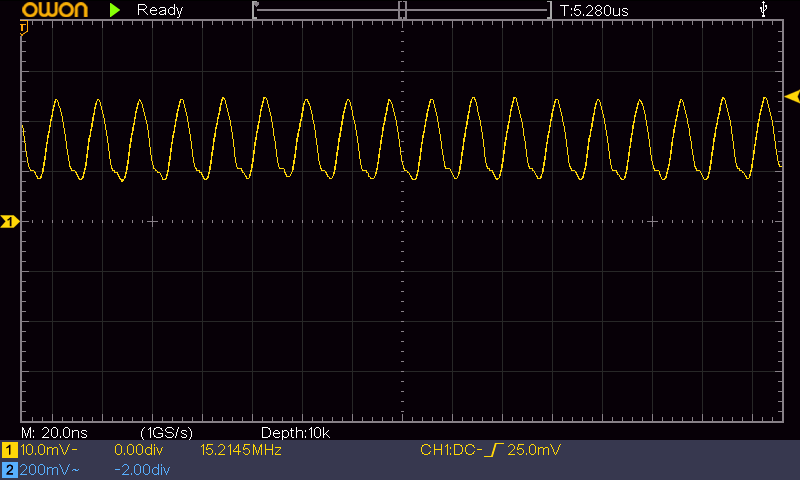 �Ƃɂ����AC945��O��VR�ݒ�ŁA
�������0����ɂ��Ȃ邵�A�グ���MAX�̂܂܁B�ł����B
C945�̎�O�́A�����Ă�d��������炵���B���x�[�X�ɓd�ׂ��������܂�̂����H
1K�����q���Ȃ����Ă��ǂ��݂������������A33���ɂ�520mV�������ĂāA�����グ��ƕϒ������Ɍ�����ςȂ���850mV���x�B
�̂ɁA�s�[�N��30mA����x����ĂĂ���́ALD�[�q���Ǝ�����4.5V���x�ɂȂ�A���S�Ȑv�ł���B
LD��2V���W���Ƃ�5V�������A���W���[��������91�����x���邩��A
(5V�|2V/91��)��33mA���W���Ǝv����B
6V�̃��M�����^���g���Ă��邩��A�܂��A�ʃT�C�h�Ōv�Z����ɁA
(6V�|2V)/(33���{91��)��32mA
MAX�����傢�Ⴂ�̂́AC1815��C945�Ȃǂ�������R���グ�Ă邩���m��Ȃ��B
�Ȃ̂ŁA������30mA��ł���B
�Ȃ��A�v�����͕ϒ��������邽�߁ADC�ő��肵�Ă邽�߁A�܂��A��������ʓ|���A�ȒP�ɂ͋t�o�C�A�X���������Ȃ��̂ł����ĂȂ��ł��B
�܂��A�ǂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�ŁA�I�[�o�[�V���[�g�́A���̌��ۂ���AC945�h���C�u�̕������m��Ȃ��H
�����A����̃L�����u���[�V������MAX�Ő�������܂ŐU���Ă�̂ł���قǏo�Ȃ��Ǝv���B
�܂��A�z���_�[�Ƀ}�E���g���˂B�B
�t�H�gDi��50���^�~�l�[�g�A�܂�����_�C���N�g�ő������l�q�B
�Ƃɂ����AC945��O��VR�ݒ�ŁA
�������0����ɂ��Ȃ邵�A�グ���MAX�̂܂܁B�ł����B
C945�̎�O�́A�����Ă�d��������炵���B���x�[�X�ɓd�ׂ��������܂�̂����H
1K�����q���Ȃ����Ă��ǂ��݂������������A33���ɂ�520mV�������ĂāA�����グ��ƕϒ������Ɍ�����ςȂ���850mV���x�B
�̂ɁA�s�[�N��30mA����x����ĂĂ���́ALD�[�q���Ǝ�����4.5V���x�ɂȂ�A���S�Ȑv�ł���B
LD��2V���W���Ƃ�5V�������A���W���[��������91�����x���邩��A
(5V�|2V/91��)��33mA���W���Ǝv����B
6V�̃��M�����^���g���Ă��邩��A�܂��A�ʃT�C�h�Ōv�Z����ɁA
(6V�|2V)/(33���{91��)��32mA
MAX�����傢�Ⴂ�̂́AC1815��C945�Ȃǂ�������R���グ�Ă邩���m��Ȃ��B
�Ȃ̂ŁA������30mA��ł���B
�Ȃ��A�v�����͕ϒ��������邽�߁ADC�ő��肵�Ă邽�߁A�܂��A��������ʓ|���A�ȒP�ɂ͋t�o�C�A�X���������Ȃ��̂ł����ĂȂ��ł��B
�܂��A�ǂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�ŁA�I�[�o�[�V���[�g�́A���̌��ۂ���AC945�h���C�u�̕������m��Ȃ��H
�����A����̃L�����u���[�V������MAX�Ő�������܂ŐU���Ă�̂ł���قǏo�Ȃ��Ǝv���B
�܂��A�z���_�[�Ƀ}�E���g���˂B�B
�t�H�gDi��50���^�~�l�[�g�A�܂�����_�C���N�g�ő������l�q�B
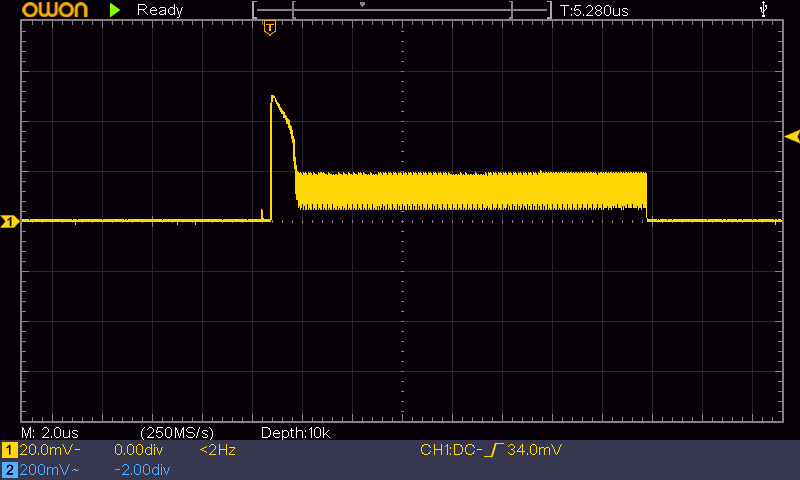
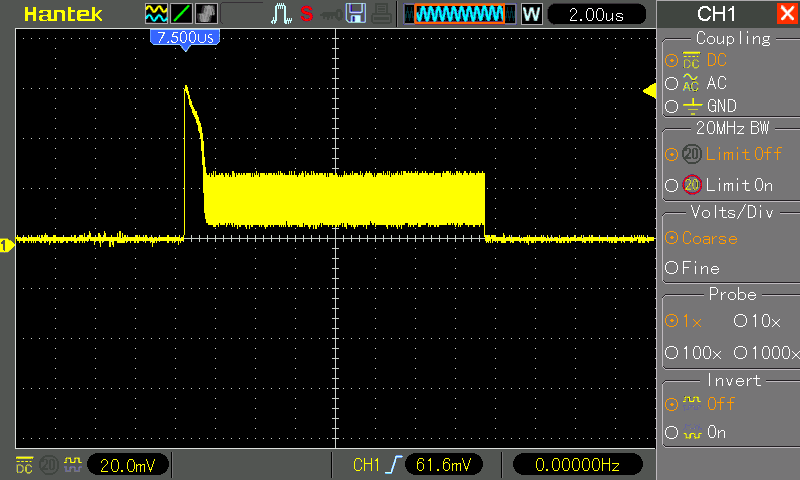 ��̃I�V���ŁA����������ɃI�[�o�[�V���[�g���Ă�B�B
����́A�O��ALD���n�Y���Ă݂ēd�����v�����Ă������������n�Y������ALD�̖�肶�ᖳ���̂��ȁH
����LD���M�Ō��E�������̂ł͖����A�����x�Ō��E�������̂Ȃ�A����͑��肾����A�ǂ����痈�Ă�̂��T���K�v��������B
Pre-AMP��p�����ꍇ�B�m�C�Y�Ȃ̂����Ȃ̂����Ȃ肪������Ƃ���B
��̃I�V���ŁA����������ɃI�[�o�[�V���[�g���Ă�B�B
����́A�O��ALD���n�Y���Ă݂ēd�����v�����Ă������������n�Y������ALD�̖�肶�ᖳ���̂��ȁH
����LD���M�Ō��E�������̂ł͖����A�����x�Ō��E�������̂Ȃ�A����͑��肾����A�ǂ����痈�Ă�̂��T���K�v��������B
Pre-AMP��p�����ꍇ�B�m�C�Y�Ȃ̂����Ȃ̂����Ȃ肪������Ƃ���B
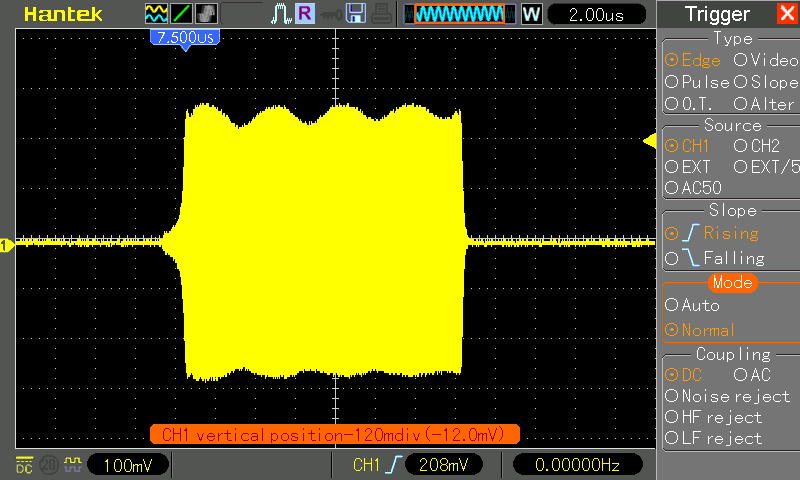 �L�����u���[�V�����Ō��̐U�����傫������̂ʼn�������̂����H
���j�b�g�̎�ł̎�������ς����肵�č����g�ւ̉e��������悤�Ƃ��Ă݂�A
���Č���ɁA�I�V���̃T���v�������Ƃ��h�b�g�Ƃ̊������肤�邯�ǁA����قNjC�ɂȂ�Ȃ������ł͂���B
�L�����u���[�V�����Ō��̐U�����傫������̂ʼn�������̂����H
���j�b�g�̎�ł̎�������ς����肵�č����g�ւ̉e��������悤�Ƃ��Ă݂�A
���Č���ɁA�I�V���̃T���v�������Ƃ��h�b�g�Ƃ̊������肤�邯�ǁA����قNjC�ɂȂ�Ȃ������ł͂���B
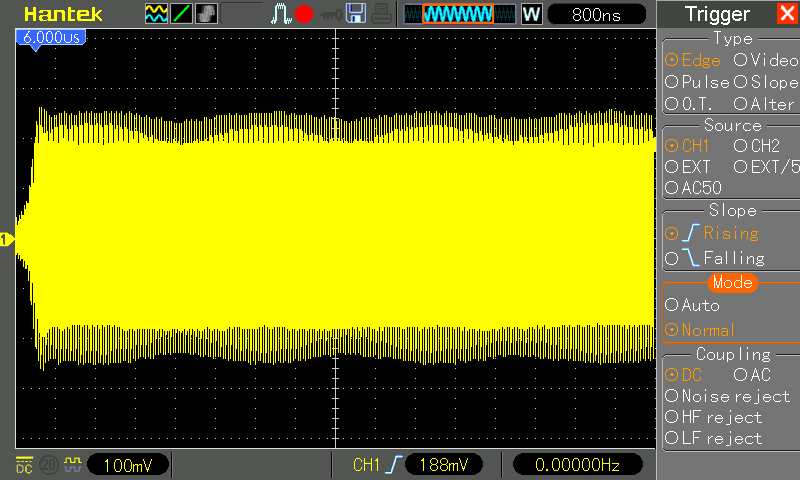 ���Ƃʼn��������A���͂̃p���X���C�L�i�������オ�����R�g�ɂ�郂�m�̂悤���A����Ԃł͂��˂�݂͂��Ȃ��B
�Ƃ肠�����A���̑���̐�[����������ɁA�����x�ɂ�����60MHz�ϒ������̃I�[�o�[�V���[�g�͏����������B
���Ƃʼn��������A���͂̃p���X���C�L�i�������オ�����R�g�ɂ�郂�m�̂悤���A����Ԃł͂��˂�݂͂��Ȃ��B
�Ƃ肠�����A���̑���̐�[����������ɁA�����x�ɂ�����60MHz�ϒ������̃I�[�o�[�V���[�g�͏����������B
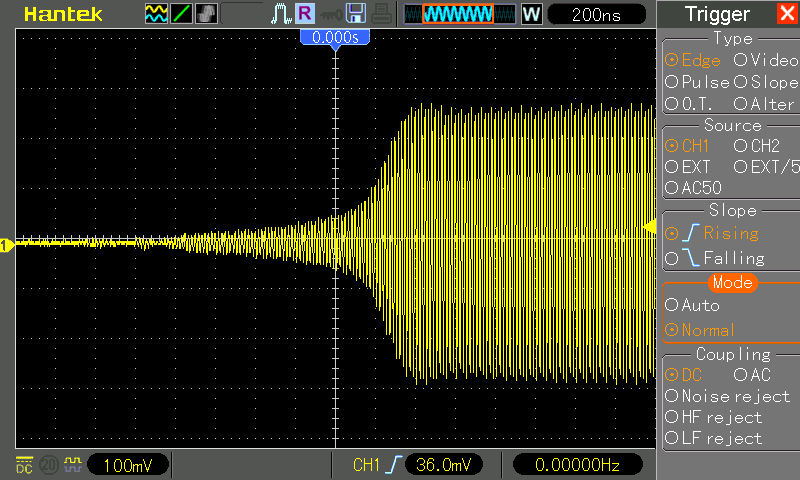 ��Ԃ̐�[��DC�����ɋ߂����瓖����O�̌��ʂł���B
���̌�ɂ���A�܂�ACal�ɂ�DC��AC����������(������H�̂��Ƃł͖����A�d�ˍ��킹�̂���)�x�X�g�̗̈悪�����I�ɑI��Ă銴�����ȁ[�A�ƁB
LD�̓d���̓m�C�Y�������Ă��ǂ��Ȃ��ƌ����Ă�̂ŁA���̃I�[�o�[�V���[�g�̓X���[�X�^�[�g�Ȃǂ̋@�\�ŗ��Ƃ������Ƃ���ł���B
�܂��A�M���Ȃ�A�����ŗǂ��Ǝv���B
�NjL��
��R�œd������������Ă�̂ɁA��������3�{�߂��o�͂��o�����Ƃ́A�����ダ�����ۂ��R�g���Ɗ������B
�����ŁA������̗e�ʂ��^���Ă݂��B50���̃^�[�~�l�[�^�[�ŗ��Ƃ��Ă���v���[�u��1/10�ɂăP�[�u����I�V���̓��͗e�ʂ����O����悤�ɂ��Ă݂��B
(���z�I�ɂ̓t�H�gDi�ɂ��t�o�C�A�X�ɂ������������A������Əd�������̂ł�߂��B)
���ꂾ���ŁA�����ԃI�[�o�[�V���[�g���������B�Ƃ������A��핔�����������Č����Ă��Ԃ������̂��ȁH
��Ԃ̐�[��DC�����ɋ߂����瓖����O�̌��ʂł���B
���̌�ɂ���A�܂�ACal�ɂ�DC��AC����������(������H�̂��Ƃł͖����A�d�ˍ��킹�̂���)�x�X�g�̗̈悪�����I�ɑI��Ă銴�����ȁ[�A�ƁB
LD�̓d���̓m�C�Y�������Ă��ǂ��Ȃ��ƌ����Ă�̂ŁA���̃I�[�o�[�V���[�g�̓X���[�X�^�[�g�Ȃǂ̋@�\�ŗ��Ƃ������Ƃ���ł���B
�܂��A�M���Ȃ�A�����ŗǂ��Ǝv���B
�NjL��
��R�œd������������Ă�̂ɁA��������3�{�߂��o�͂��o�����Ƃ́A�����ダ�����ۂ��R�g���Ɗ������B
�����ŁA������̗e�ʂ��^���Ă݂��B50���̃^�[�~�l�[�^�[�ŗ��Ƃ��Ă���v���[�u��1/10�ɂăP�[�u����I�V���̓��͗e�ʂ����O����悤�ɂ��Ă݂��B
(���z�I�ɂ̓t�H�gDi�ɂ��t�o�C�A�X�ɂ������������A������Əd�������̂ł�߂��B)
���ꂾ���ŁA�����ԃI�[�o�[�V���[�g���������B�Ƃ������A��핔�����������Č����Ă��Ԃ������̂��ȁH
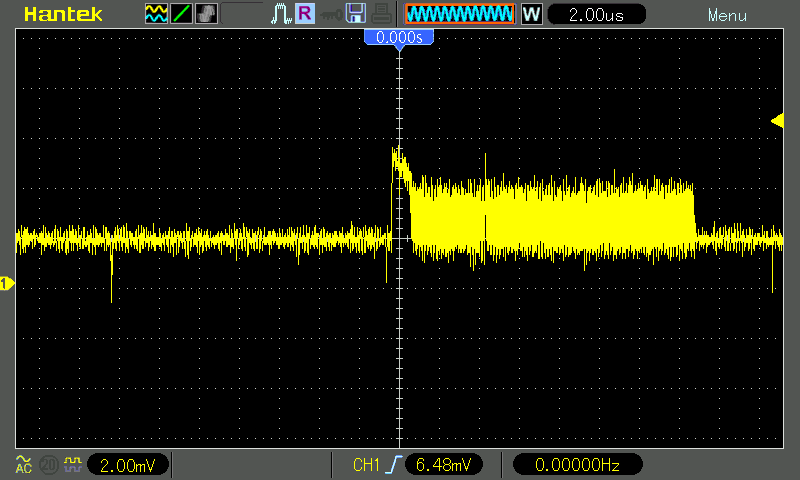 �܂��A�t�ɁA�P�[�u���Ȃǂ����ă^�[�~�l�[�^�[���Ȃ����A���Ȃ荂���I�[�o�[�V���[�g���o�邱�Ƃ������B
LD���ɃI�[�o�[�V���[�g������Ȃ�A������̗e�ʂ����点�t�ɉs���Ȃ�\���̕��������Ǝv���̂ŁA�v�����̖��Ɣ��f�Ɏ���B
�NjL02��
�X�Ȃ錟�؎���
�t�H�gDi�Ɏ���2.3V���x�̋t�o�C�A�X��������B�����̍����V���R��PIN�t�H�gDi�͒�d���ł�PN�ڍ��Ԃ̋�R�w���L����₷���Ȃ��Ă���B
�K�R�I��AC�ƂȂ邪10��F�̐σZ�����g���Ă���B�B
�����āA50���Ń^�[�~�l�[�g���āA1/10�v���[�u�ɓ���A�I�V���������50���Ń^�[�~�l�[�g���Ă���B
�܂��A�t�ɁA�P�[�u���Ȃǂ����ă^�[�~�l�[�^�[���Ȃ����A���Ȃ荂���I�[�o�[�V���[�g���o�邱�Ƃ������B
LD���ɃI�[�o�[�V���[�g������Ȃ�A������̗e�ʂ����点�t�ɉs���Ȃ�\���̕��������Ǝv���̂ŁA�v�����̖��Ɣ��f�Ɏ���B
�NjL02��
�X�Ȃ錟�؎���
�t�H�gDi�Ɏ���2.3V���x�̋t�o�C�A�X��������B�����̍����V���R��PIN�t�H�gDi�͒�d���ł�PN�ڍ��Ԃ̋�R�w���L����₷���Ȃ��Ă���B
�K�R�I��AC�ƂȂ邪10��F�̐σZ�����g���Ă���B�B
�����āA50���Ń^�[�~�l�[�g���āA1/10�v���[�u�ɓ���A�I�V���������50���Ń^�[�~�l�[�g���Ă���B
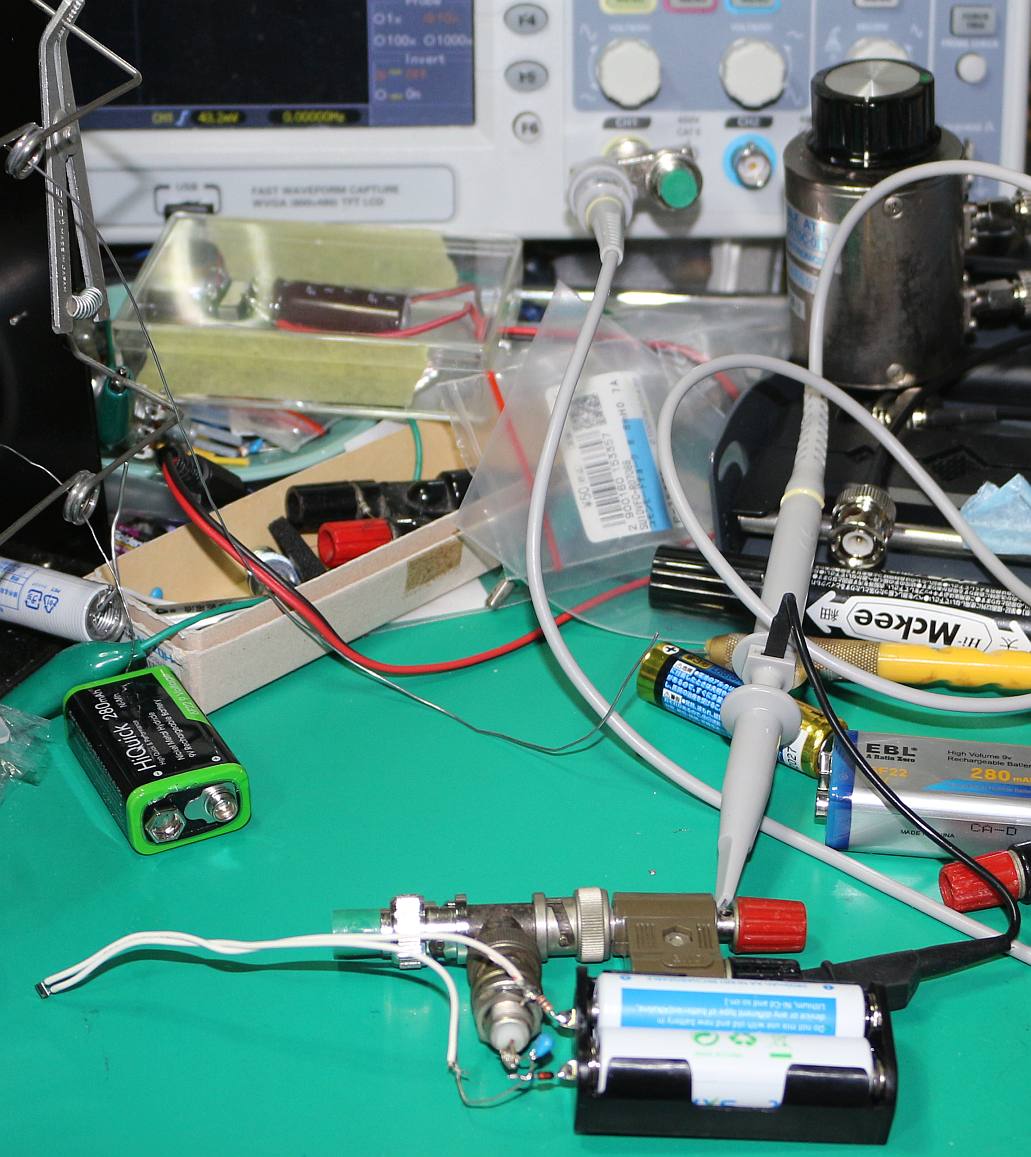 �I�[�o�[�V���[�g�����S�ɏ����������I�I
�I�[�o�[�V���[�g�����S�ɏ����������I�I
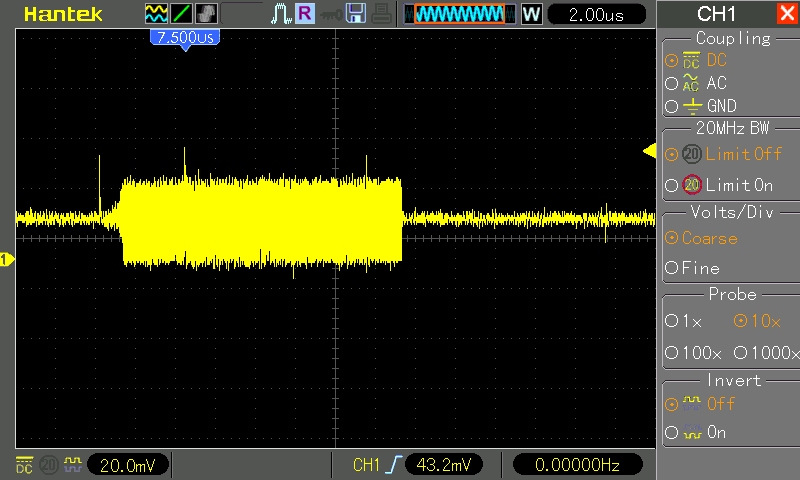 60MHz�̃V�O�i�����A�ƂĂ��傫���Ȃ�B
�Ód�e�ʒቺ�̌��ʂ͕�������悤�ŁA
�����\���ɂ���ăI�[�o�[�V���[�g�Ƃ݂�ꂽ�����͏������Ȃ��ď����Ă��܂��Ă���̂ł́H
230507
�NjL03��
���؎���2
�v���[�u�̌����^�[�~�l�[�g������Ԃ���AC���肪�L�c�C�̂ŁA
�Ë����āH�����͎��O�����B�������AC�̉e�����o�Ă��܂��Ǝv����B
(�v���[�u��Cal�łǂ��ɂ��Ȃ�\�����H)
����ƁA���Ȃ��߂̃I�[�o�[�V���[�g���o�����A���_�Ƃ��Ă̔��f��ς���Ɏ���قǂł͖��������B
60MHz�̃V�O�i�����A�ƂĂ��傫���Ȃ�B
�Ód�e�ʒቺ�̌��ʂ͕�������悤�ŁA
�����\���ɂ���ăI�[�o�[�V���[�g�Ƃ݂�ꂽ�����͏������Ȃ��ď����Ă��܂��Ă���̂ł́H
230507
�NjL03��
���؎���2
�v���[�u�̌����^�[�~�l�[�g������Ԃ���AC���肪�L�c�C�̂ŁA
�Ë����āH�����͎��O�����B�������AC�̉e�����o�Ă��܂��Ǝv����B
(�v���[�u��Cal�łǂ��ɂ��Ȃ�\�����H)
����ƁA���Ȃ��߂̃I�[�o�[�V���[�g���o�����A���_�Ƃ��Ă̔��f��ς���Ɏ���قǂł͖��������B
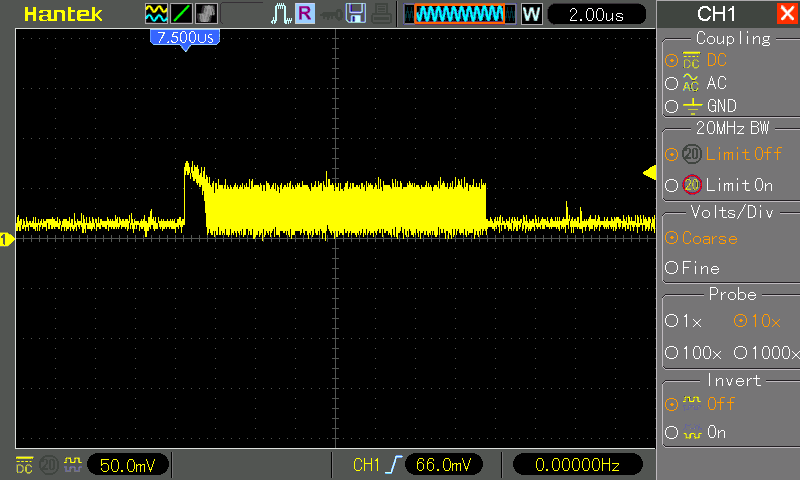 �v���[�u���L�����u���[�V���������B
�v���[�u���L�����u���[�V���������B
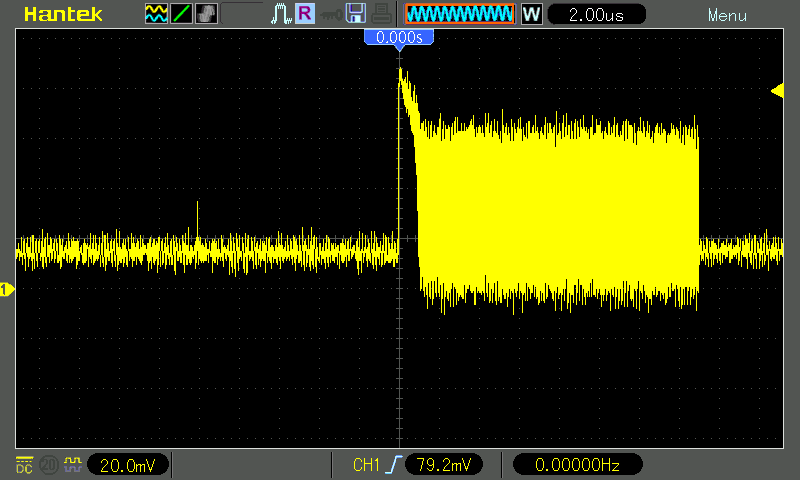 60MHz�ϒ������肵�����������ɂ���Ă�̂ŁA���ʓI�ɃI�[�o�V���[�g�͂��ĂȂ��n�Y�ł���B
�ŏ������葱���Ă��܂��̂�C945���肩�ƁB
�v���[�u�̊��x��1/10�{�ɂ��闝�R�́A1�{�ł́A���R���͗e�ʂ͕ς�炸�A�ǂ��Ă��\��������������̂Łc�A
230508
���i��FET�̃h���C����FB(�t�F���C�g�r�[�Y)�����Č������A�t�ɁA�M�������Ŕ��U����B
Tr�̒[�q�e�ʂƂŁA�G�������N���Ă�Ƃ����������B
���i���ᖳ����A���̒��x�̏��M���͗ǂ��̂����m��Ȃ����A���U�~�߂ɂ͋^��ȏꍇ������̂�F�m�����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|---------------------------------�|�|�|�|�|
230509
��O��AGC-AMP�̉�H�B
PCB�������̂ő�������Ă݂��B
60MHz�ϒ������肵�����������ɂ���Ă�̂ŁA���ʓI�ɃI�[�o�V���[�g�͂��ĂȂ��n�Y�ł���B
�ŏ������葱���Ă��܂��̂�C945���肩�ƁB
�v���[�u�̊��x��1/10�{�ɂ��闝�R�́A1�{�ł́A���R���͗e�ʂ͕ς�炸�A�ǂ��Ă��\��������������̂Łc�A
230508
���i��FET�̃h���C����FB(�t�F���C�g�r�[�Y)�����Č������A�t�ɁA�M�������Ŕ��U����B
Tr�̒[�q�e�ʂƂŁA�G�������N���Ă�Ƃ����������B
���i���ᖳ����A���̒��x�̏��M���͗ǂ��̂����m��Ȃ����A���U�~�߂ɂ͋^��ȏꍇ������̂�F�m�����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|---------------------------------�|�|�|�|�|
230509
��O��AGC-AMP�̉�H�B
PCB�������̂ő�������Ă݂��B
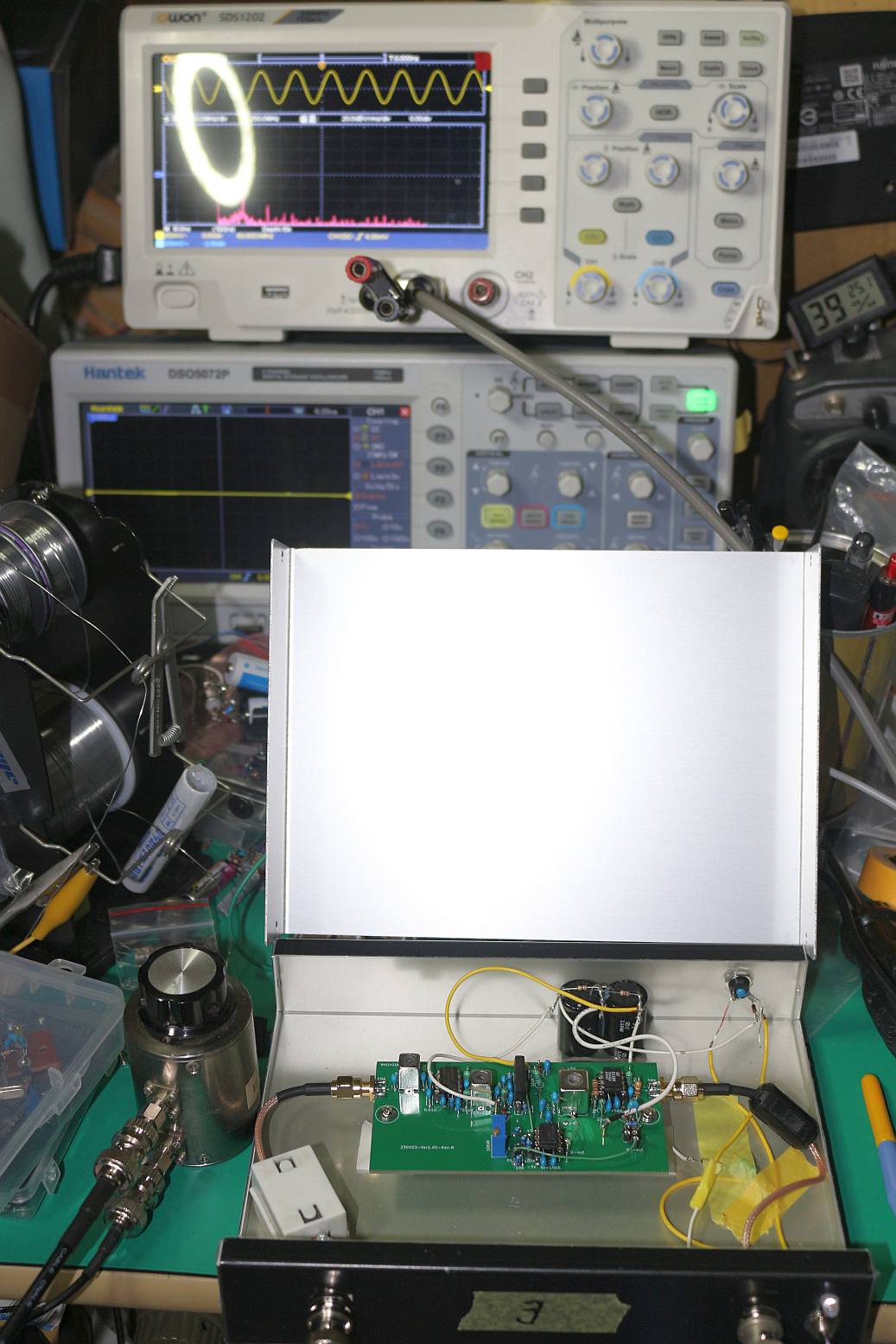 ���U���Ȃ��ňꔭ�ő�Q�C�����o���B
�����A�ŏ��̓��FCZ�p��C�͏��������邩���B�����1.6mm�ƌ����������炩�ȁH
���U���Ȃ��ňꔭ�ő�Q�C�����o���B
�����A�ŏ��̓��FCZ�p��C�͏��������邩���B�����1.6mm�ƌ����������炩�ȁH
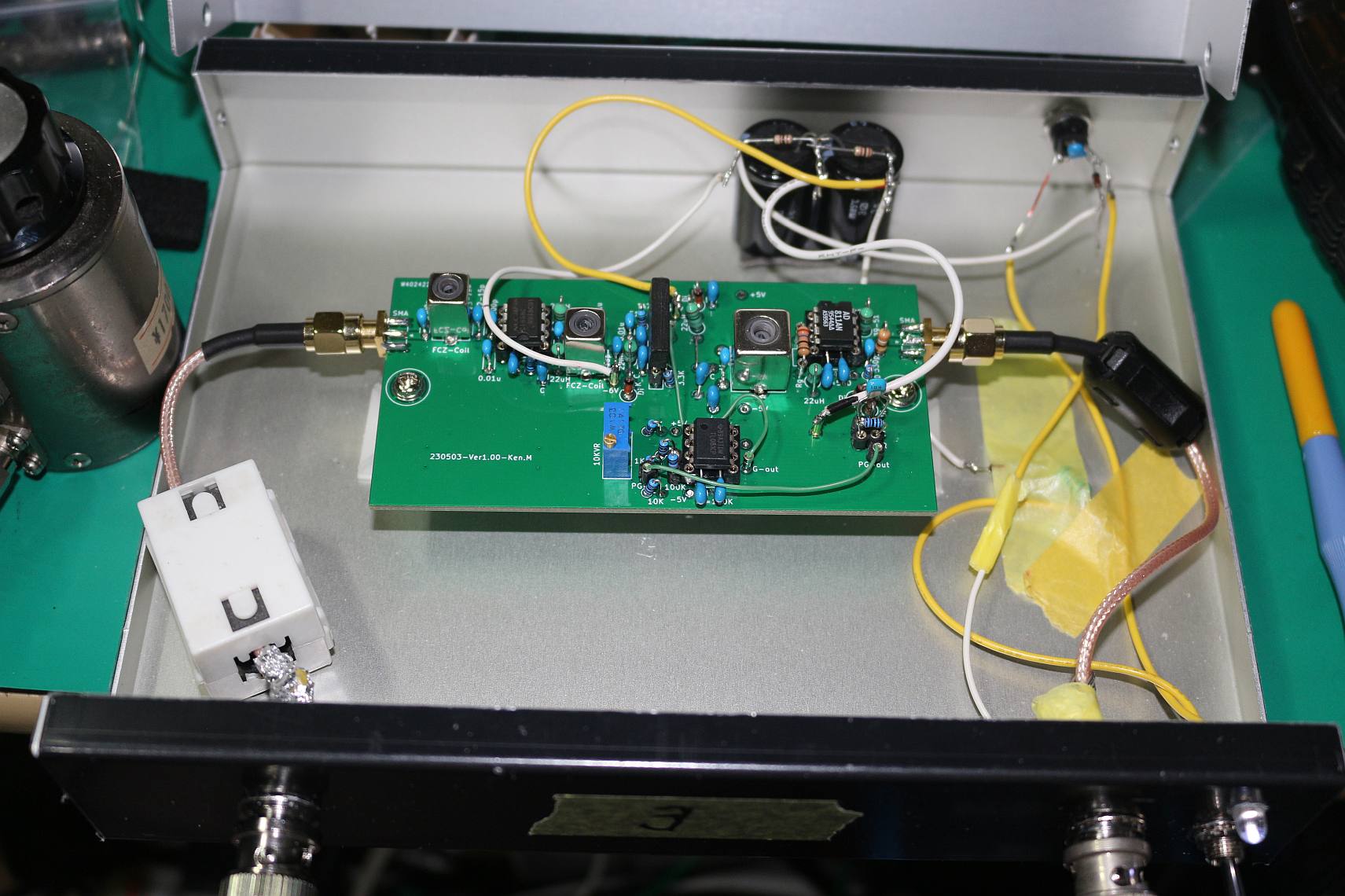 �P�[�X���ɕt���Ă�d���~�������邽�߂�Di��́A�K���d���ɂ��邽�߁A���ƂŃn�Y�����B
�{�|�d���́A��R�ɂ�镪���Ƃ����V���v�����B
�P�[�X���ɕt���Ă�d���~�������邽�߂�Di��́A�K���d���ɂ��邽�߁A���ƂŃn�Y�����B
�{�|�d���́A��R�ɂ�镪���Ƃ����V���v�����B
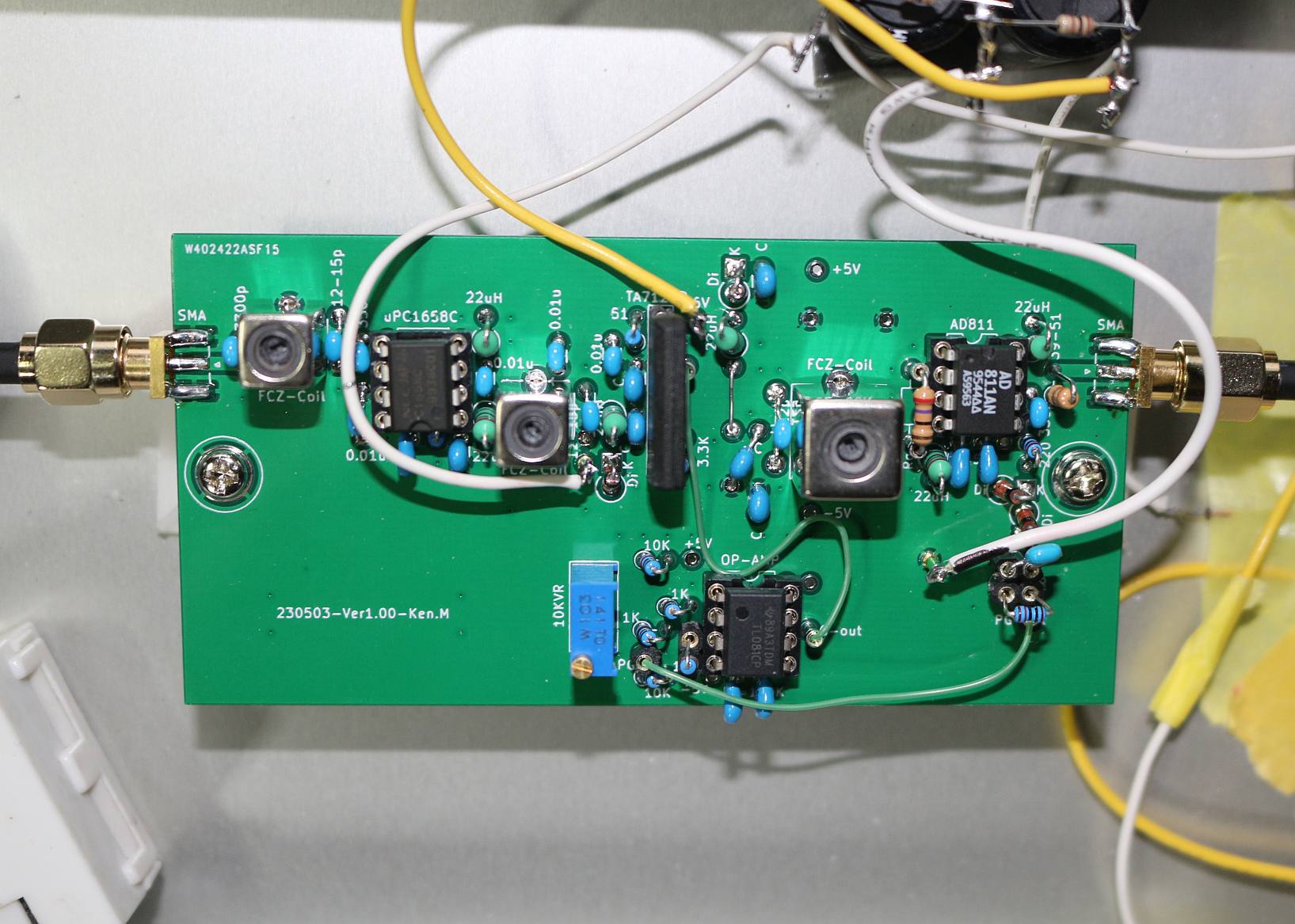 �g�`�ƃX�y�N�g���B��ԒႢ�̂̓n�����ƁB
���ƁA��{�����g���x�ł��邪�ʑ����o���LPF�ŃJ�b�g�����B
�g�`�ƃX�y�N�g���B��ԒႢ�̂̓n�����ƁB
���ƁA��{�����g���x�ł��邪�ʑ����o���LPF�ŃJ�b�g�����B
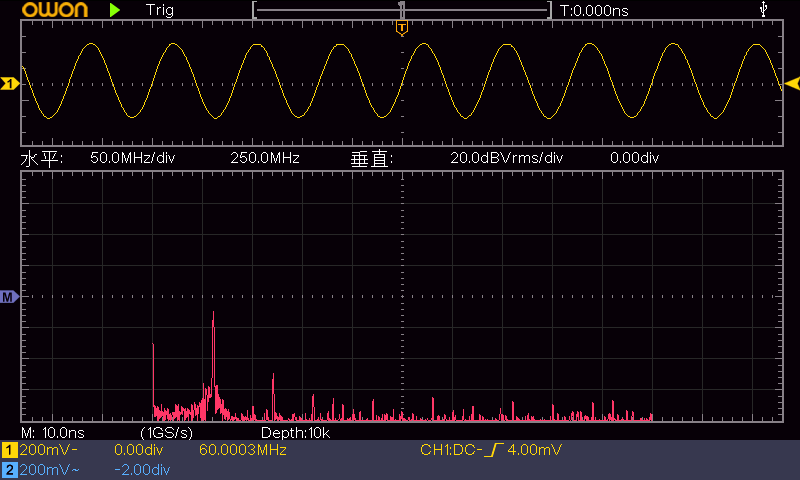 �����������̂ŁAPre-AMP�����Č����B
�����������̂ŁAPre-AMP�����Č����B
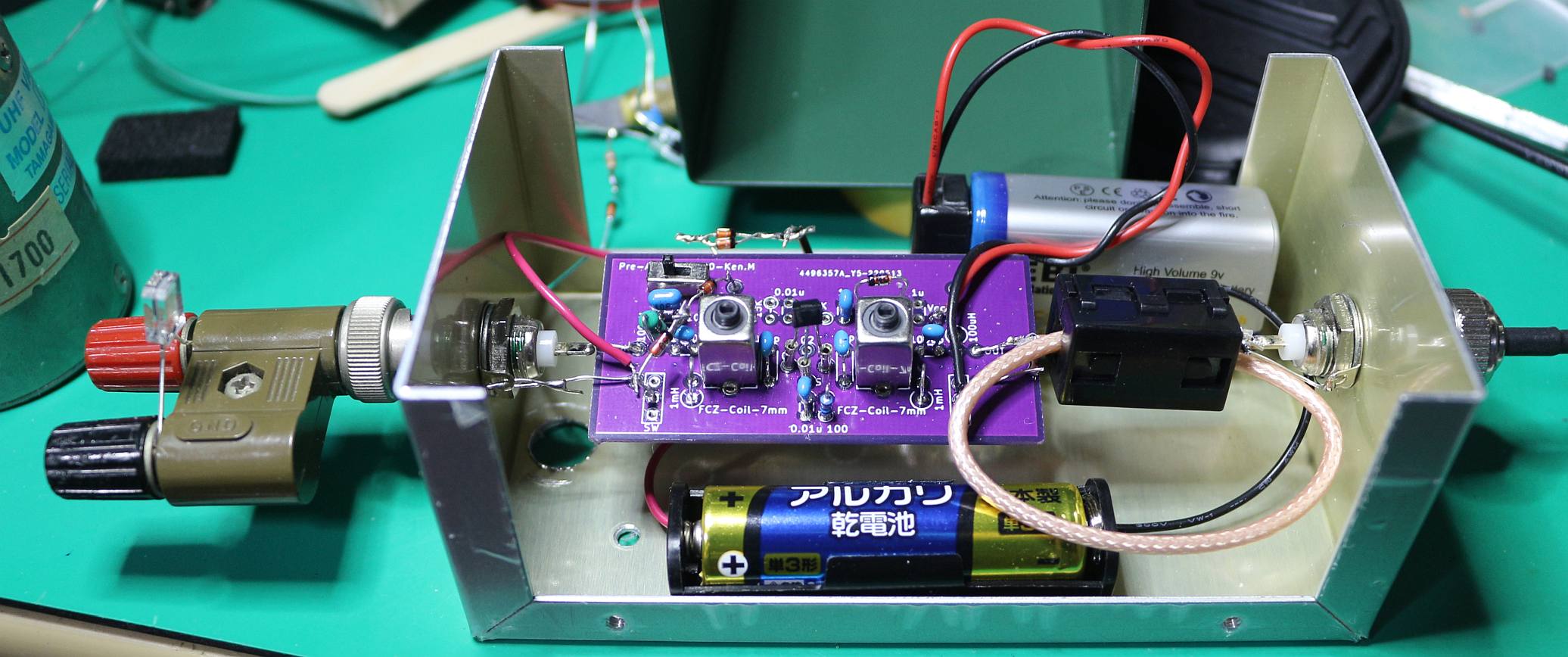 FCZ�R�C���͉������Ƃ����A�����o�����Ƃ��̕����s����������C������B
�R���̊���́A�����A1.0mm�ł���B����̂������p��C�ɑ���R�A�̏o���̊������Ⴄ�B
�t�H�g�_�C�I�[�h�ɁA60MHz�ϒ����[�U�[��15��Sec�ł�����ł݂��e�X�g�B
FCZ�R�C���͉������Ƃ����A�����o�����Ƃ��̕����s����������C������B
�R���̊���́A�����A1.0mm�ł���B����̂������p��C�ɑ���R�A�̏o���̊������Ⴄ�B
�t�H�g�_�C�I�[�h�ɁA60MHz�ϒ����[�U�[��15��Sec�ł�����ł݂��e�X�g�B
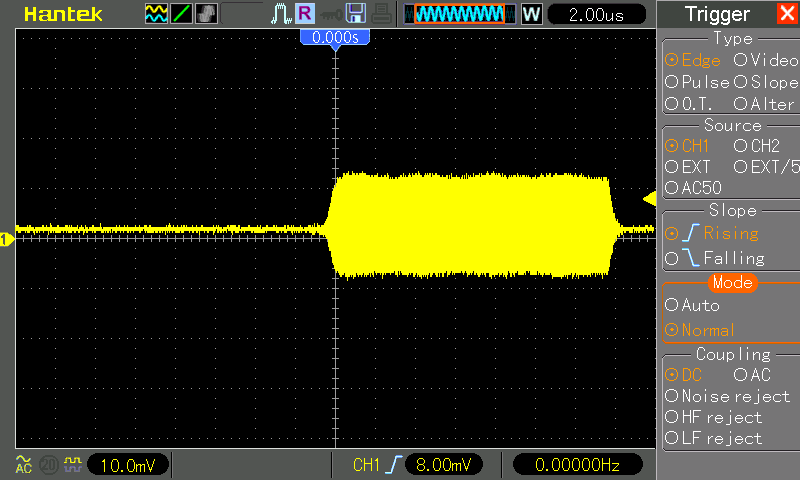 �t�o�C�A�X�������ƁA�S���ƌ����ėǂ��ق�60MHz�̔g�`���o�Ȃ��B
�t�H�gDi�́A�g�p�����ɂ���ẮA�t�o�C�A�X�������ăi���{�̃��m�ȏꍇ�������B
�ŁA���̓�̉�H��g�ݍ��킹��ƁA���U��������̂����A�Q�C���R���g���[����10��Sec�ʂ̎����ŐU�����Ă�悤�ł���B
�����𑬂����ē�i�ϕ��Ƃ�OP-AMP�̎�ނ�I�Ԃ��Ƃł��ł��邩�������A
���[�U�[�̎ア�U�����̐M���ł�����A�Q�C���R���g���[�����Ȃ���A�U���͎~�܂�悤���B
�܂��A���v�̏ꍇ�APre-AMP�ő������AAGC-AMP�ōi��C���ɓ��삳���邱�ƂŁA
Pre-AMP��AGC-AMP�̓`���n�ɋ�������̃m�C�Y������Ă���̂�h�~������ʂ�����B
�����A����́A���v���ᖳ���̂ŁA�A
++++�{�{�{�{�{
230528
��3��H�̋��݁B
���͂�FCZ���ɏՍ܂ɂȂ��Ă�B
���i���A��NF�����U���Â炢�B
�ǂ����ARF-AMP��IC�͔��]�o�͂̕������U�ɋ����C������B
�t�o�C�A�X�������ƁA�S���ƌ����ėǂ��ق�60MHz�̔g�`���o�Ȃ��B
�t�H�gDi�́A�g�p�����ɂ���ẮA�t�o�C�A�X�������ăi���{�̃��m�ȏꍇ�������B
�ŁA���̓�̉�H��g�ݍ��킹��ƁA���U��������̂����A�Q�C���R���g���[����10��Sec�ʂ̎����ŐU�����Ă�悤�ł���B
�����𑬂����ē�i�ϕ��Ƃ�OP-AMP�̎�ނ�I�Ԃ��Ƃł��ł��邩�������A
���[�U�[�̎ア�U�����̐M���ł�����A�Q�C���R���g���[�����Ȃ���A�U���͎~�܂�悤���B
�܂��A���v�̏ꍇ�APre-AMP�ő������AAGC-AMP�ōi��C���ɓ��삳���邱�ƂŁA
Pre-AMP��AGC-AMP�̓`���n�ɋ�������̃m�C�Y������Ă���̂�h�~������ʂ�����B
�����A����́A���v���ᖳ���̂ŁA�A
++++�{�{�{�{�{
230528
��3��H�̋��݁B
���͂�FCZ���ɏՍ܂ɂȂ��Ă�B
���i���A��NF�����U���Â炢�B
�ǂ����ARF-AMP��IC�͔��]�o�͂̕������U�ɋ����C������B
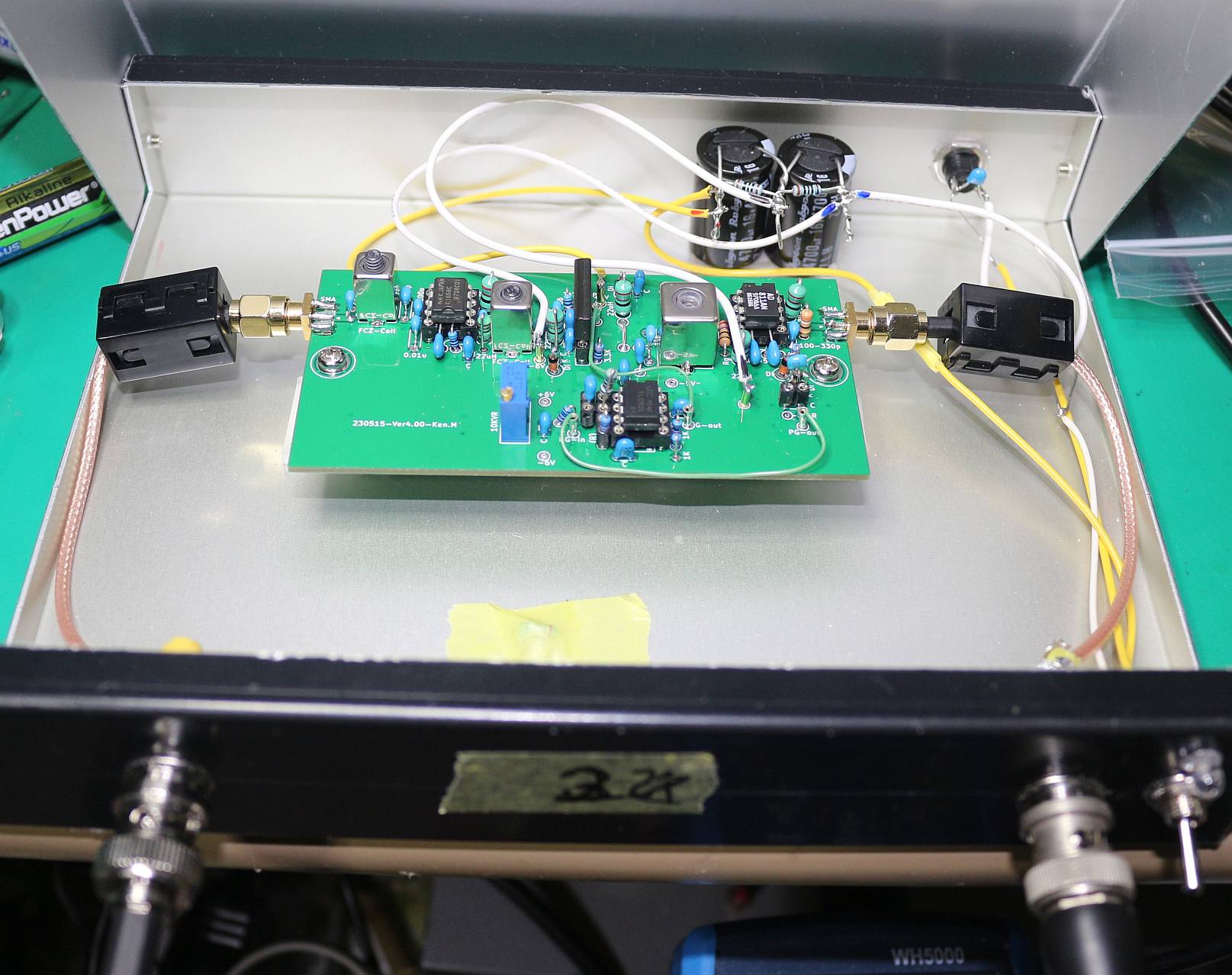 �X�ɉ��ǂ����Ƃ���̓Q�C���R���g���[���[���ȁH
�Ƃ肠�����A2��HOP-AMP�œ�K�̐ϕ������邱�ƂɂȂ����B
����ȏ�̐��\���~������A�����ňʑ��]�T�̍L��OP-AMP���~�����Ƃ��낾���A���ɍ���Ȃ��̂Ŋ����B
�����h���p�b�h�ɏo����s�b�`�Ȃ̂ŁA20XX�T�C�Y���x��SMD�ȃ`�b�v���������B
���ہA�M�����C���ɂ́A���W�A�����[�h��C�̗����ɁA�`�b�v�������ĕt���ăe�X�g���Ă݂��B
Pre-AMP�����x���グ��Ɣ��U���������B����āA���x��߂�2SK212�ɂ��Ă���B��Vgs��-0.2V���x�ɂȂ�悤Rs��ݒ�B
FET�̑����אڂ��ĂĒ����̂�Z�����������AIC�\�P�b�g���g���Ă�ȏ�A���E������B
�X�ɉ��ǂ����Ƃ���̓Q�C���R���g���[���[���ȁH
�Ƃ肠�����A2��HOP-AMP�œ�K�̐ϕ������邱�ƂɂȂ����B
����ȏ�̐��\���~������A�����ňʑ��]�T�̍L��OP-AMP���~�����Ƃ��낾���A���ɍ���Ȃ��̂Ŋ����B
�����h���p�b�h�ɏo����s�b�`�Ȃ̂ŁA20XX�T�C�Y���x��SMD�ȃ`�b�v���������B
���ہA�M�����C���ɂ́A���W�A�����[�h��C�̗����ɁA�`�b�v�������ĕt���ăe�X�g���Ă݂��B
Pre-AMP�����x���グ��Ɣ��U���������B����āA���x��߂�2SK212�ɂ��Ă���B��Vgs��-0.2V���x�ɂȂ�悤Rs��ݒ�B
FET�̑����אڂ��ĂĒ����̂�Z�����������AIC�\�P�b�g���g���Ă�ȏ�A���E������B
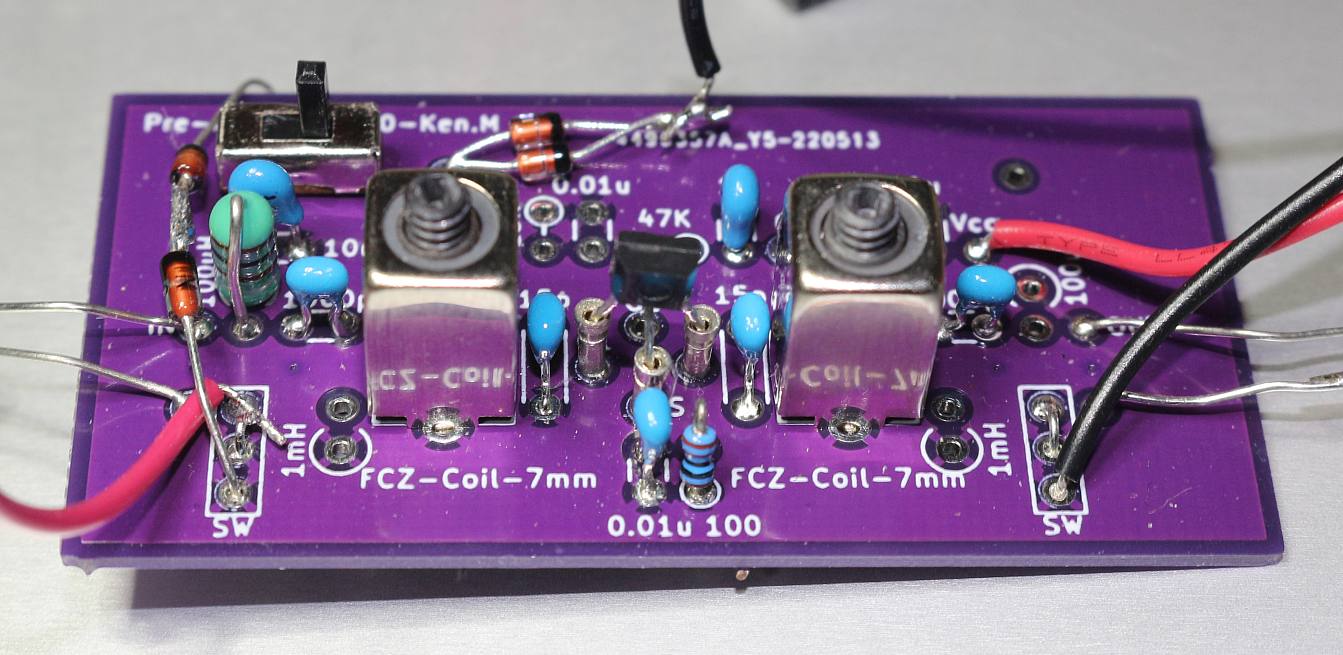 �v�������ǁA�t�H�g�f�B�e�N�^����P�[�u����t����ƁAZ�͐������Ă���Ƃ͎v���Ȃ�����������ɂ͂��邵�APre-AMP�͔��U���₷���B
�����ŁA�t�o�C�A�X��FCZ�Ńg�����X�ɂ��āc�A�Ƃ��l���Ă݂��B
�v�������ǁA�t�H�g�f�B�e�N�^����P�[�u����t����ƁAZ�͐������Ă���Ƃ͎v���Ȃ�����������ɂ͂��邵�APre-AMP�͔��U���₷���B
�����ŁA�t�o�C�A�X��FCZ�Ńg�����X�ɂ��āc�A�Ƃ��l���Ă݂��B
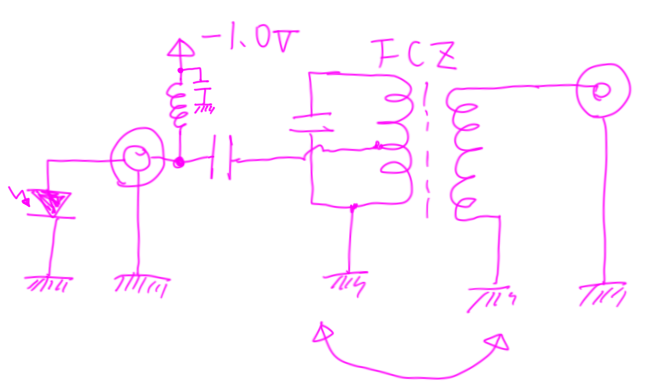 �܂��A����A�e�X�g�͂��Ă��Ȃ��B
�n�C�Q�C�����ƁA�C���C���V�[���h�ŋ�����肷��悤�ŁA
�����@�Ȃǂ͊��x�����Ȃ荂�������g���ϊ������Ă��瑝��������A�����ɂ���܂łɃP�[�X�����Ŋ������Ă镔���͂�����x����B
�Ȃɂ����A���x���グ�Ă��A�M�G���₻�̑��̃t�B�[���h�m�C�Y�Ōv���Ɏg������ɖ����B
���ϒ��p�̃h���C�u�M���̃W���~���O����肻���B
�Ƃ���ŁA���d�m�C�Y���l���A�X�p�C�N�I�ȃm�C�Y�ɑ���ϐ������Č����B
�܂��A����A�e�X�g�͂��Ă��Ȃ��B
�n�C�Q�C�����ƁA�C���C���V�[���h�ŋ�����肷��悤�ŁA
�����@�Ȃǂ͊��x�����Ȃ荂�������g���ϊ������Ă��瑝��������A�����ɂ���܂łɃP�[�X�����Ŋ������Ă镔���͂�����x����B
�Ȃɂ����A���x���グ�Ă��A�M�G���₻�̑��̃t�B�[���h�m�C�Y�Ōv���Ɏg������ɖ����B
���ϒ��p�̃h���C�u�M���̃W���~���O����肻���B
�Ƃ���ŁA���d�m�C�Y���l���A�X�p�C�N�I�ȃm�C�Y�ɑ���ϐ������Č����B
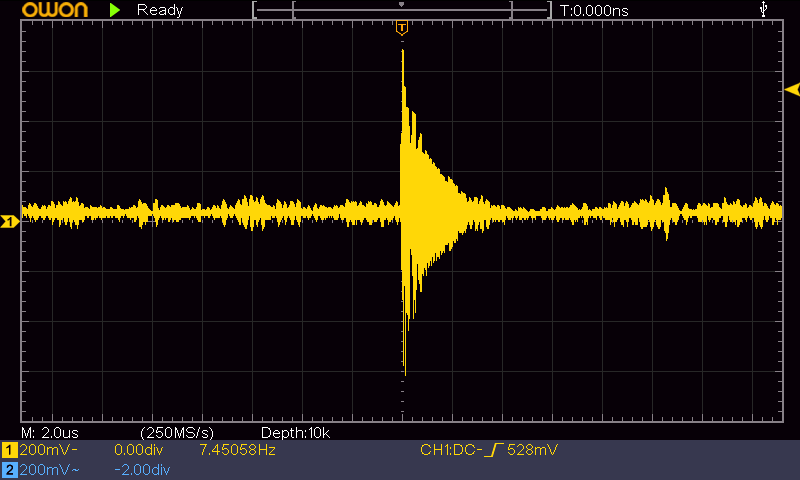 6��Sec���x�ŏ����邪�A�b�������̂́AFCZ�R�C���̋��n���U�����Ă邩�炾�낤�B
���͖����悤�����ǁA�ɓx�ɑ傫�ȃp���X�ɂُ͈퓮�삷��\�����B
Z�̐����A�o�͂̓��͑��ւ̃��[�v�o�b�N���C���g���Ƃ���ł͂���B
�����ŋC�ɂȂ��Ă��A�P�[�X�����ł�GND���[�v�B���͂̐≏���s�����B
6��Sec���x�ŏ����邪�A�b�������̂́AFCZ�R�C���̋��n���U�����Ă邩�炾�낤�B
���͖����悤�����ǁA�ɓx�ɑ傫�ȃp���X�ɂُ͈퓮�삷��\�����B
Z�̐����A�o�͂̓��͑��ւ̃��[�v�o�b�N���C���g���Ƃ���ł͂���B
�����ŋC�ɂȂ��Ă��A�P�[�X�����ł�GND���[�v�B���͂̐≏���s�����B
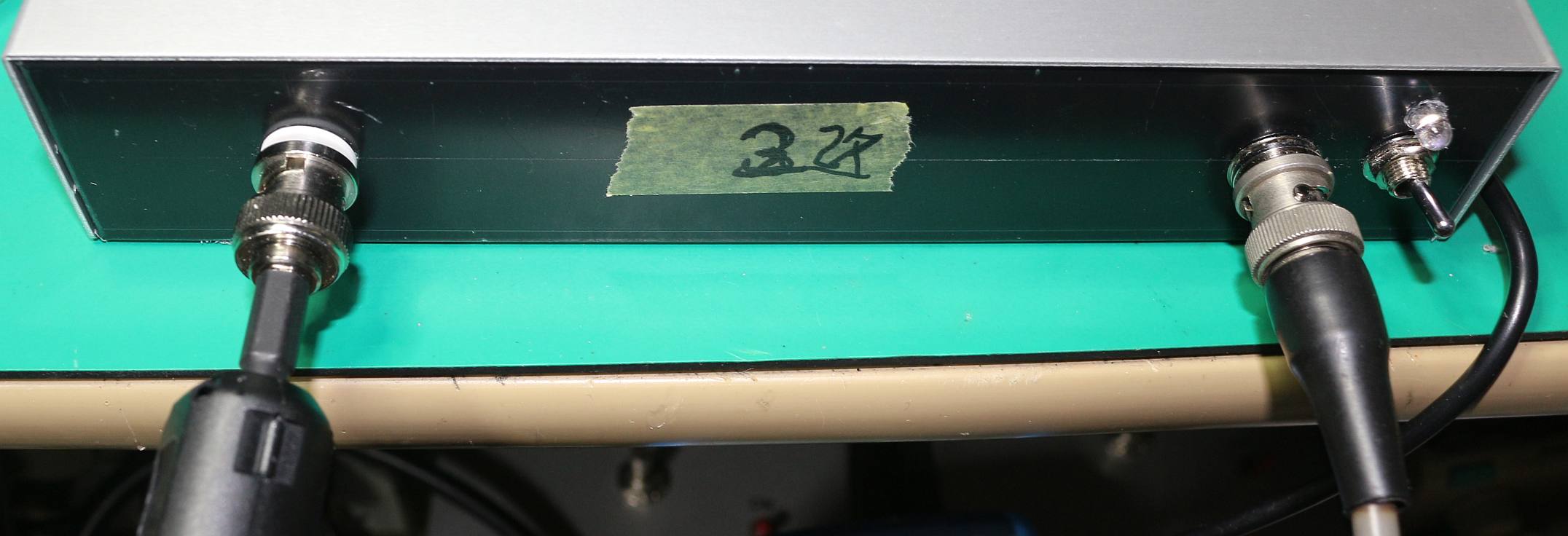 �����A�P�[�X�ɖ������Ă�̂ŁA�ђʂ������ȕ����������āA�܂��A�����̂��A���e�i�ɂȂ蓾��Ƃ��\�z���A�p�b�`���R�A�����p��ԁB�R�������[�h��}���Ă���B
�l�܂�Ƃ���A�d�q�͗���₷���g�R�𗬂�邩��AGND����Ă��A�܂��ʂ�GND���C���ȂǁA�ςȂƂ��ł܂�����ĂƂ������Ƃ��B
�X�y�N�g��������B
�����A�P�[�X�ɖ������Ă�̂ŁA�ђʂ������ȕ����������āA�܂��A�����̂��A���e�i�ɂȂ蓾��Ƃ��\�z���A�p�b�`���R�A�����p��ԁB�R�������[�h��}���Ă���B
�l�܂�Ƃ���A�d�q�͗���₷���g�R�𗬂�邩��AGND����Ă��A�܂��ʂ�GND���C���ȂǁA�ςȂƂ��ł܂�����ĂƂ������Ƃ��B
�X�y�N�g��������B
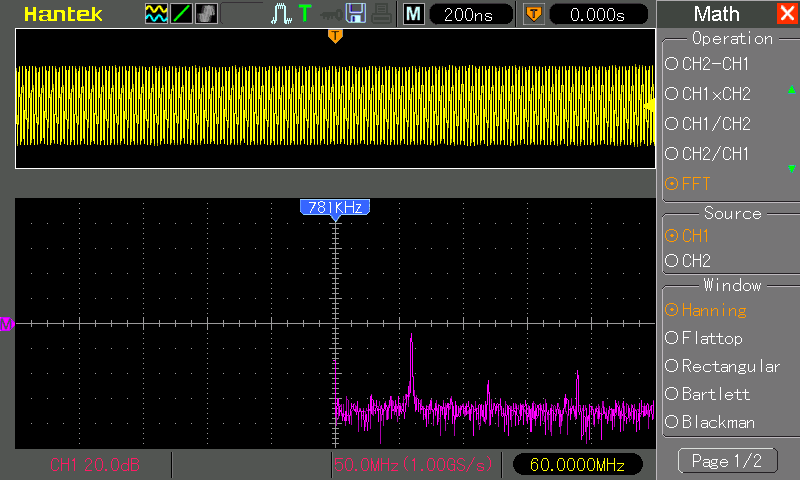 ����͎O�{�����g�c�����������H
���̓A�N���o�e�B�b�N�ȋz���ł͂Ȃ��AIC���t���ōs�����Ǝv���B
���NJ��T�Ԍキ�炢�ɗ���Ǝv����B
�NjL��
�Ƃ肠�����AAGC-AMP�ɂ��̂܂܃t�H�g�f�B�e�N�^���q����AGC-AMP�����U���邪�A2m���x�̒��߂̓����P�[�u�����q���Ɣ��U���Ȃ��B�����A���͂̃t�H�gDi�̎���C�Ȃǂ̈Ӗ��������`���P�[�u���ɂ���ĕς���Ă���̂��Ǝv���B
�Ȃ��A�P�[�u����3D2V�ł��邪�A���X���l�����Ȃ����x���Ǝv���B
�ƂȂ�ƁAPre-AMP������ꍇ�A����̏o�͑��ɂ������P�[�u����t���������A���ɕt������ǂ��̂����m��Ȃ��B
-------------�|�|�|�|�|
230605
�Ƃ肠�����AAGC-AMP�ɂ��̂܂܃t�H�g�f�B�e�N�^���q���Ɣ��U����
����͎O�{�����g�c�����������H
���̓A�N���o�e�B�b�N�ȋz���ł͂Ȃ��AIC���t���ōs�����Ǝv���B
���NJ��T�Ԍキ�炢�ɗ���Ǝv����B
�NjL��
�Ƃ肠�����AAGC-AMP�ɂ��̂܂܃t�H�g�f�B�e�N�^���q����AGC-AMP�����U���邪�A2m���x�̒��߂̓����P�[�u�����q���Ɣ��U���Ȃ��B�����A���͂̃t�H�gDi�̎���C�Ȃǂ̈Ӗ��������`���P�[�u���ɂ���ĕς���Ă���̂��Ǝv���B
�Ȃ��A�P�[�u����3D2V�ł��邪�A���X���l�����Ȃ����x���Ǝv���B
�ƂȂ�ƁAPre-AMP������ꍇ�A����̏o�͑��ɂ������P�[�u����t���������A���ɕt������ǂ��̂����m��Ȃ��B
-------------�|�|�|�|�|
230605
�Ƃ肠�����AAGC-AMP�ɂ��̂܂܃t�H�g�f�B�e�N�^���q���Ɣ��U����
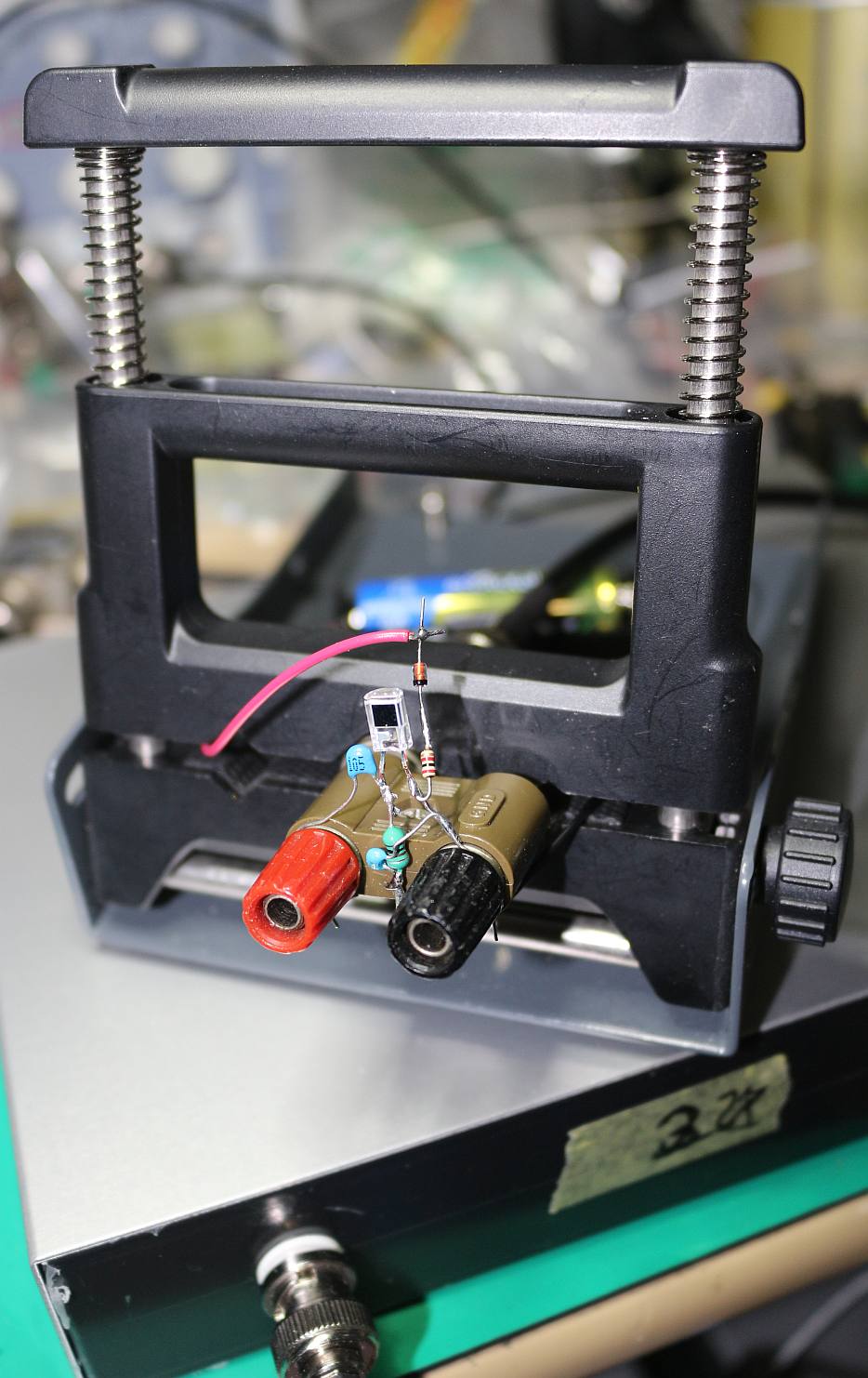 ���A2m���x�̒��߂̓����P�[�u�����q���Ɣ��U���Ȃ��X���B
���͂�Z�̑���BFCZ�R�C����K���o�����X�ɂ�����A49.96���ɂȂ����B
���̂͂��傢���������H
���A2m���x�̒��߂̓����P�[�u�����q���Ɣ��U���Ȃ��X���B
���͂�Z�̑���BFCZ�R�C����K���o�����X�ɂ�����A49.96���ɂȂ����B
���̂͂��傢���������H
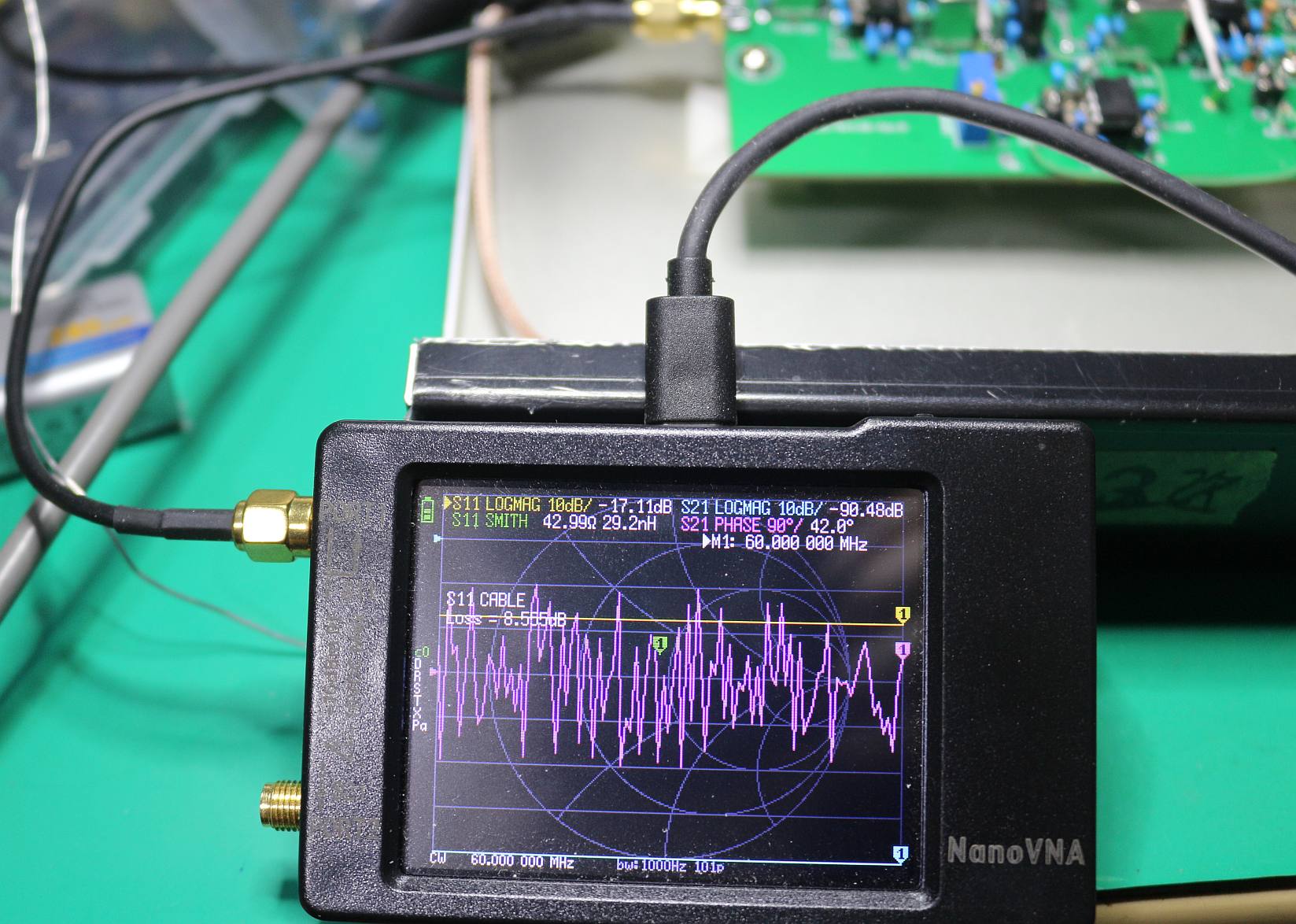 3D-2V�̃P�[�u���Ȃǂ��A�o�N�����邾�낤���ǁA65���Ƃ������̂܂ł������B�t�ɂ��Ȃ�Ⴂ�̂��B
3.5D-SFA�Ƃ����̂͗ǂ������B
3D-2V�̃P�[�u���Ȃǂ��A�o�N�����邾�낤���ǁA65���Ƃ������̂܂ł������B�t�ɂ��Ȃ�Ⴂ�̂��B
3.5D-SFA�Ƃ����̂͗ǂ������B
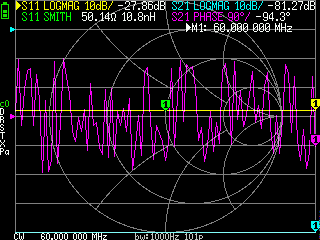 L���̒��pSMA�R�l�N�^�t���̃P�[�u���������B�ׂ��̂Ƒ����̂�3�{���B
�Ȃ̂ŁA�܂��́A�ׂ��������t���悤�Ƃ�����A������5mm���x����Ȃ��B
����́A�n���_�߂������Ōq���ŁA�p�b�`���R�A���͂߂āA�V�[���h�ɃA���~�����������B
L���̒��pSMA�R�l�N�^�t���̃P�[�u���������B�ׂ��̂Ƒ����̂�3�{���B
�Ȃ̂ŁA�܂��́A�ׂ��������t���悤�Ƃ�����A������5mm���x����Ȃ��B
����́A�n���_�߂������Ōq���ŁA�p�b�`���R�A���͂߂āA�V�[���h�ɃA���~�����������B
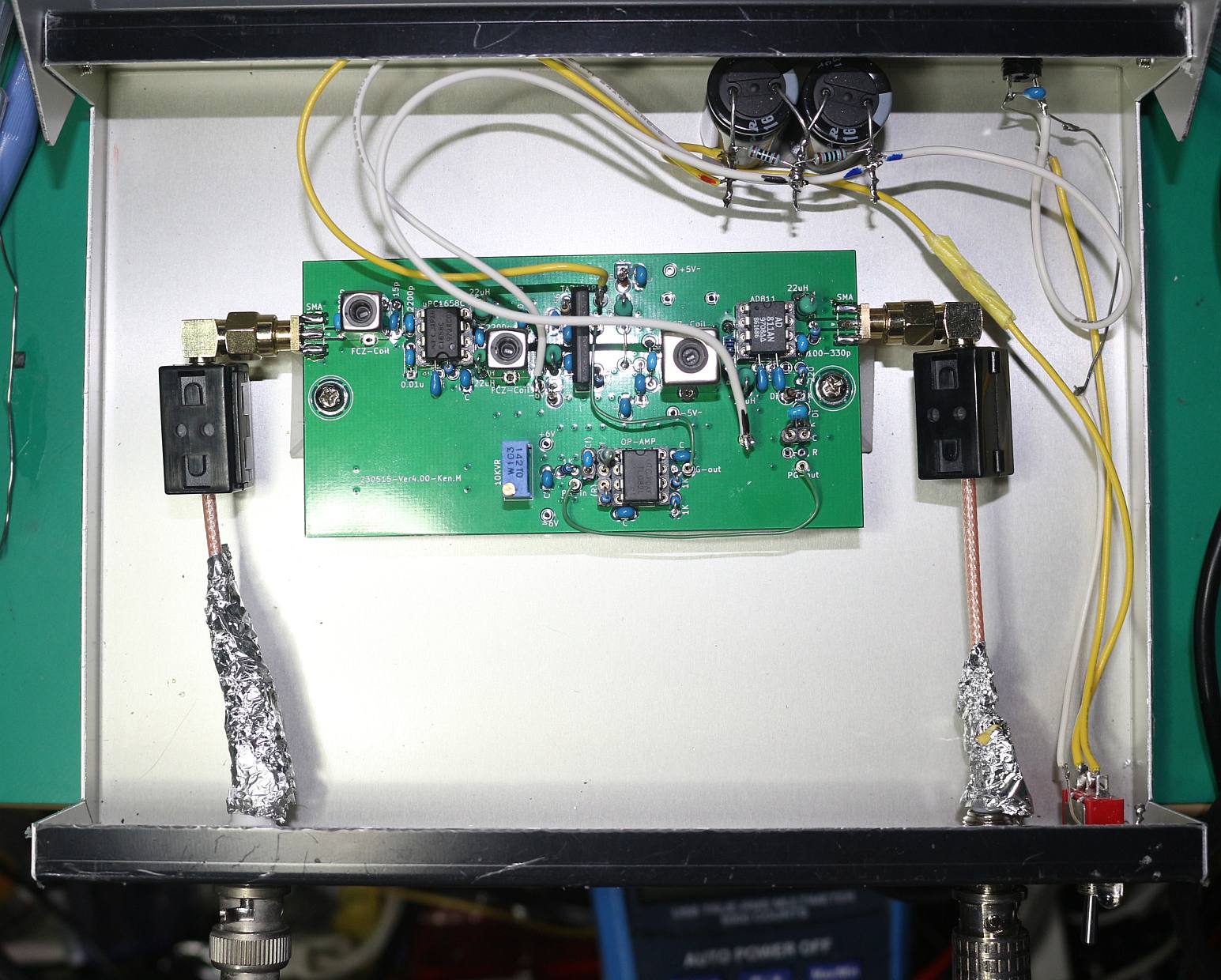 �����ǁA
���͊J�����Ɣ��U����X���������ʂƂȂ����B�܂�A���̑O�������������B
���̓��ɂ��A��ʒu�����炻���B
�V���Ȑv�̊�������̂ŁA���삵�Ď����Ă݂��B
(���Ĕ�Ȃ郂�m)
�����ǁA
���͊J�����Ɣ��U����X���������ʂƂȂ����B�܂�A���̑O�������������B
���̓��ɂ��A��ʒu�����炻���B
�V���Ȑv�̊�������̂ŁA���삵�Ď����Ă݂��B
(���Ĕ�Ȃ郂�m)
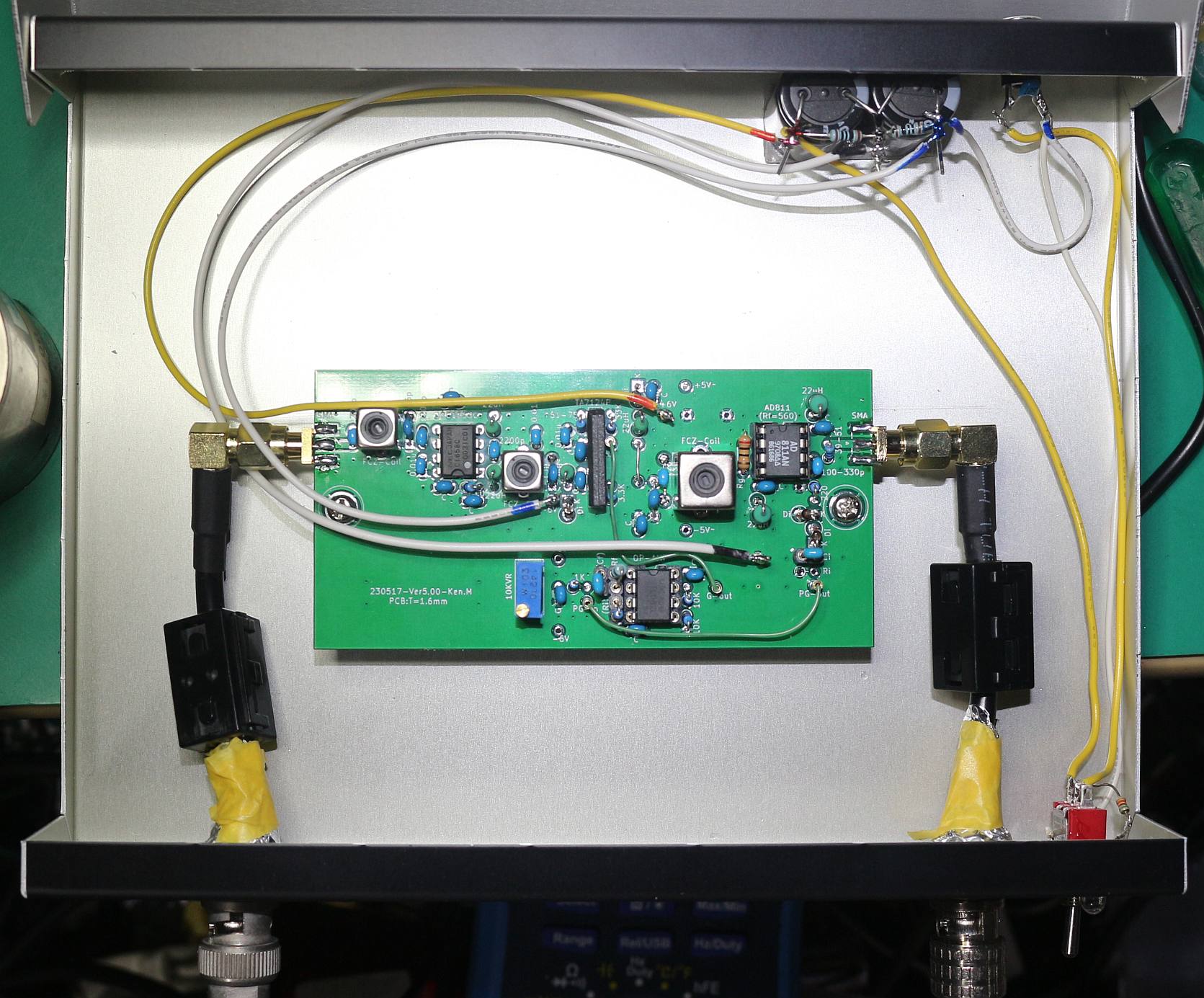 ��������L���Ȓ��p�R�l�N�^�P�[�u�����g�p�B
���o�͂�BNC�́A�≏�R�l�N�^�B
��̐͒��t���ƂȂ����B
�o�͂Ƀp�b�`���R�A�����Ȃ�ǂ������B�Ƃ������Ƃ̓R�������[�h�┽�˂�����݂����B
�Q�C���͂₽��傫�������ɂȂ����B
���łɁA�R��d�g�̃��[�v�o�b�N�����肻���B
FCZ50���80���g���Ӗ��́AC�̃o�����X�����肵�Ď��₷������ł��B
�܂��AZ�͒Ⴂ�Ƃ��납�獂���Ƃ��ɍs���Ƃ��ɋ������˂��܂��C���[�W�ł��B�B
�����ŁA
�M���R��̉e�������Ȃ��Ǝv������@�������A
�����_�C���N�g�ɓ��o�͂��Ă݂�B
��������L���Ȓ��p�R�l�N�^�P�[�u�����g�p�B
���o�͂�BNC�́A�≏�R�l�N�^�B
��̐͒��t���ƂȂ����B
�o�͂Ƀp�b�`���R�A�����Ȃ�ǂ������B�Ƃ������Ƃ̓R�������[�h�┽�˂�����݂����B
�Q�C���͂₽��傫�������ɂȂ����B
���łɁA�R��d�g�̃��[�v�o�b�N�����肻���B
FCZ50���80���g���Ӗ��́AC�̃o�����X�����肵�Ď��₷������ł��B
�܂��AZ�͒Ⴂ�Ƃ��납�獂���Ƃ��ɍs���Ƃ��ɋ������˂��܂��C���[�W�ł��B�B
�����ŁA
�M���R��̉e�������Ȃ��Ǝv������@�������A
�����_�C���N�g�ɓ��o�͂��Ă݂�B
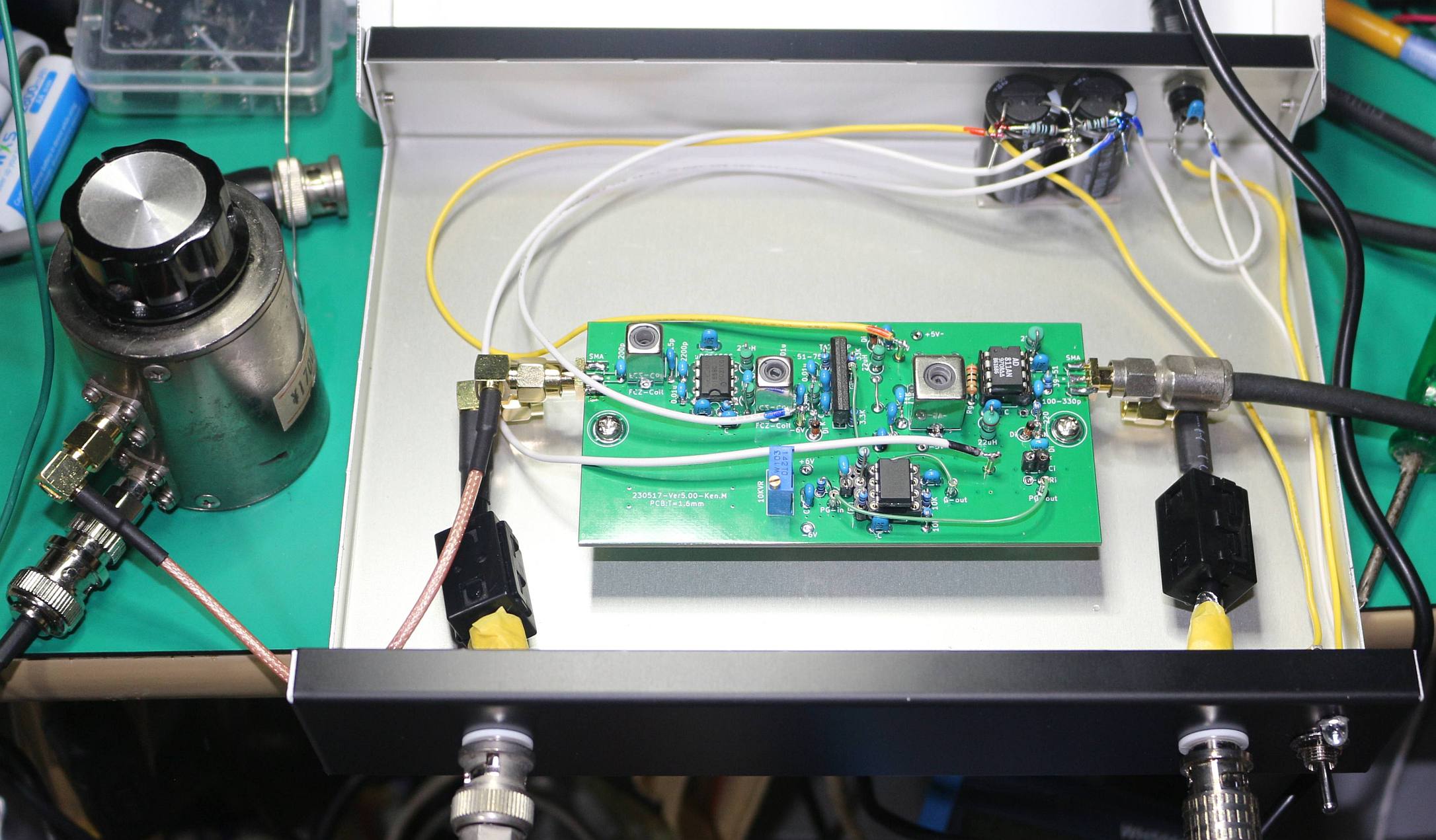 �p�b�`���R�A�͕t���Ă��Ȃ��B
�����A�ŏ��M���ł��A�Q�C���R���g���[����������A�ő�U���܂ŏo��B���Ȃ���肵�Ă���B
�̂ɁA���̌��ۂ́A�M���̘R��̉e���̏ؖ��ƂȂ邾�낤���A
�����R�l�N�^�𗼒[����Z���o���`�Ȃ�Έ��肷��\��������B
����ɉ�����3�Ԗڂ�FCZ�R�C���̐ڑ��̕ύX�ɂďo�͂]������A
�P�[�X�̃p�l���[�q����̏o�͂ł��A����x�͍X�ɏオ��\�������肦�邩���m��Ȃ�
�C���t�������A��͂�v���̂ق��u��{�̃Q�C������������v�悤�ɐ����Ă��܂����̂ŁA�ǂ����ł͐��킾���A
�p���[�f�o�C�_�[�Ɍq������A�O�ɕt����P�[�u���APre-AMP�A�f�B�e�N�^�Ȃǂ̃C���s�[�_���X�̐H���Ⴂ�����d�Ȃ�ƁA���\�Ȕ��U���鎖�����������B���ǁA�K�T�c�Ȉ������o���Ȃ��㕨�̏�Ԃ��B
Z�̐H���Ⴂ�́A���˂ɂ���Ē�ݔg�݁A�M���̘R��Ɍq�����Ă���̂����m��Ȃ����A�u���˂��_�C���N�g�ɐɖ߂��Ă���v�悤�Ȍ��ʂ͗ǂ��Ƃ͎v���Ȃ��B
��ʓI�ɁAZ�̒i���┽�˂ɂ�ATT�Ń����N�b�V�����u���̂��L���ł͂���B-3dB���x���L�������m��Ȃ��B
��͂�A�o�͂̃P�[�X������Z�̕s�A���v�f��M���̘R�ꂪ���Ȃ̂��Ɨ\�������B
�ŁA�o�͂Ɍq�����P�[�u����Z�߂ɂ��ăp�b�`���R�A�ŃR�������[�h��}��������啪���肷��B
�ǂ���������������̂��A�P�[�u�������˂Ŋ������Ă�̂��A�d�g�t�˓��ɂ����͂ւ̃��[�v�o�b�N�Ȃ̂����B
�����ŁA�蕪���ׁ̈A���͂��V���[�g���Ă݂�ƁA���וω��ɖ������ɂȂ����̂Ō�҂ł���ƒf�肷��Ɏ������B
-�|�|�|�|�|
230607
���̐���܂Ŏ��Ԃ�����̂ŁA�ł������̎����ɂ����͎��O�ɓ��Ă���
1����O�̑�3��H�ɂ����Ă̎����B
(���p�R�l�N�^�q���ŁA����������Ȃ��̂Ńn���_�߂������ʼn��������甭�U���܂��������c)
�p�^�[���J�b�g�ƃW�����p�ʼn������Ĕ��U�̂��₷���ȂǗl�q������B
�܂��A
���͂�FCZ�R�C���ɂĊ��S�ɐ≏�˔����Ɉ��������C������B
���ɁA
��3��FCZ�R�C���̋ɐ����]�ɂďo�͂̐M���̔��]���s���˂���ϔ����ɕs����Ɉ��������C������B
�܂�A���U�ɂ��ẮA�ǂ�����|���s�����B�B��ꂽ�B
�Ƃ͂����A��r�Ώۂ�IC�̒��t�����A�I�i�̓d���A�҂�OP-AMP��Rf���������A�P�[�X�ȂǂƂ�GND�̒���������\�Ⴄ�A�A
�ꉞ�A
�p�b�`���R�A�͕t���Ă��Ȃ��B
�����A�ŏ��M���ł��A�Q�C���R���g���[����������A�ő�U���܂ŏo��B���Ȃ���肵�Ă���B
�̂ɁA���̌��ۂ́A�M���̘R��̉e���̏ؖ��ƂȂ邾�낤���A
�����R�l�N�^�𗼒[����Z���o���`�Ȃ�Έ��肷��\��������B
����ɉ�����3�Ԗڂ�FCZ�R�C���̐ڑ��̕ύX�ɂďo�͂]������A
�P�[�X�̃p�l���[�q����̏o�͂ł��A����x�͍X�ɏオ��\�������肦�邩���m��Ȃ�
�C���t�������A��͂�v���̂ق��u��{�̃Q�C������������v�悤�ɐ����Ă��܂����̂ŁA�ǂ����ł͐��킾���A
�p���[�f�o�C�_�[�Ɍq������A�O�ɕt����P�[�u���APre-AMP�A�f�B�e�N�^�Ȃǂ̃C���s�[�_���X�̐H���Ⴂ�����d�Ȃ�ƁA���\�Ȕ��U���鎖�����������B���ǁA�K�T�c�Ȉ������o���Ȃ��㕨�̏�Ԃ��B
Z�̐H���Ⴂ�́A���˂ɂ���Ē�ݔg�݁A�M���̘R��Ɍq�����Ă���̂����m��Ȃ����A�u���˂��_�C���N�g�ɐɖ߂��Ă���v�悤�Ȍ��ʂ͗ǂ��Ƃ͎v���Ȃ��B
��ʓI�ɁAZ�̒i���┽�˂ɂ�ATT�Ń����N�b�V�����u���̂��L���ł͂���B-3dB���x���L�������m��Ȃ��B
��͂�A�o�͂̃P�[�X������Z�̕s�A���v�f��M���̘R�ꂪ���Ȃ̂��Ɨ\�������B
�ŁA�o�͂Ɍq�����P�[�u����Z�߂ɂ��ăp�b�`���R�A�ŃR�������[�h��}��������啪���肷��B
�ǂ���������������̂��A�P�[�u�������˂Ŋ������Ă�̂��A�d�g�t�˓��ɂ����͂ւ̃��[�v�o�b�N�Ȃ̂����B
�����ŁA�蕪���ׁ̈A���͂��V���[�g���Ă݂�ƁA���וω��ɖ������ɂȂ����̂Ō�҂ł���ƒf�肷��Ɏ������B
-�|�|�|�|�|
230607
���̐���܂Ŏ��Ԃ�����̂ŁA�ł������̎����ɂ����͎��O�ɓ��Ă���
1����O�̑�3��H�ɂ����Ă̎����B
(���p�R�l�N�^�q���ŁA����������Ȃ��̂Ńn���_�߂������ʼn��������甭�U���܂��������c)
�p�^�[���J�b�g�ƃW�����p�ʼn������Ĕ��U�̂��₷���ȂǗl�q������B
�܂��A
���͂�FCZ�R�C���ɂĊ��S�ɐ≏�˔����Ɉ��������C������B
���ɁA
��3��FCZ�R�C���̋ɐ����]�ɂďo�͂̐M���̔��]���s���˂���ϔ����ɕs����Ɉ��������C������B
�܂�A���U�ɂ��ẮA�ǂ�����|���s�����B�B��ꂽ�B
�Ƃ͂����A��r�Ώۂ�IC�̒��t�����A�I�i�̓d���A�҂�OP-AMP��Rf���������A�P�[�X�ȂǂƂ�GND�̒���������\�Ⴄ�A�A
�ꉞ�A
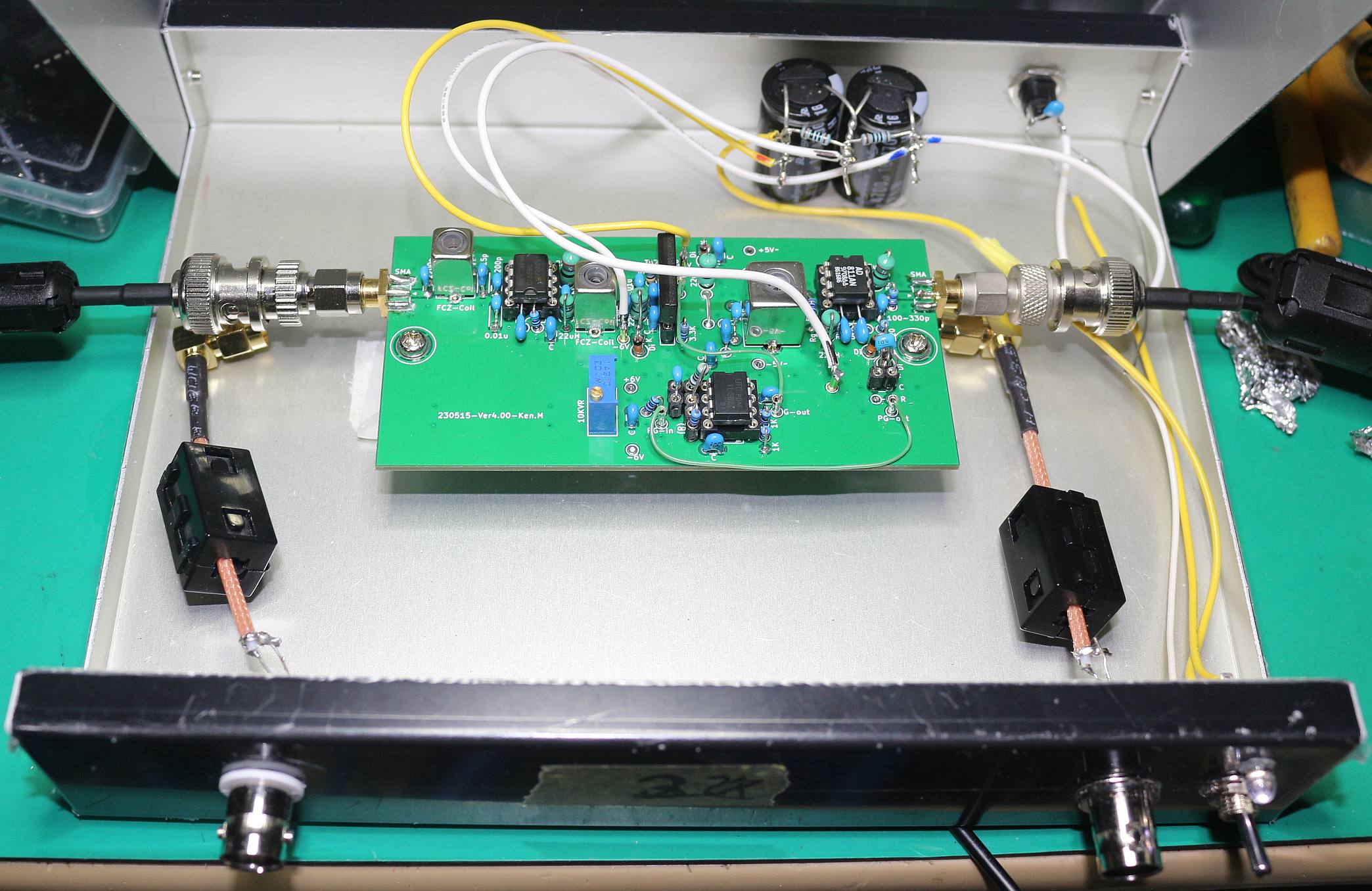 ��������Ă݂���A����Ȃ�ɗǍD�Ȋ����ʼn����ɂ�鍷�����Ȃ菬�����Ȃ�B�܂�M���̘R�ꂪ�L���B
�ŁA�X�}�[�g�ł͂Ȃ����A���̕��@�ɋ߂����@��͍��B
BNC�̃G�b�W�R�l�N�^�͂悭�킩��Ȃ�����̍Đv���K�v�B��ɕ��S�������肻���B
SMA�R�l�N�^��BNC�ւ̃A�_�v�^�ɕt����ƁA��������S���������A�R�l�N�^�[�A�_�v�^�͔��˂̌����ɂȂ�̂ŁA�Ȃ�ׂ������������A����Œ��Ɉ������ނɂ̓P�[�X�̒���������Ȃ������B
�ŁASMA�ȃP�[�u������������ŁA�X�}�[�g��BNC�֕ϊ��������Ǝv�����BSMA-J��BNC-J�A�_�v�^���H�����Z���ǂ������B�B
�H����SMA�R�l�N�^�P�[�u���B500�~�̂�VSWR��2.0�ȉ��ł�����ƐS�z�B�����݂����Ɍ�����1080�~�̂��AVSWR1.20�ȉ��B�傫�ȈႢ�̂悤�ȁc�A�A
�A���G�N�����Č��āA�v���p�̍����P�[�u����VSWR��1.15�ȉ��Ȃ̂ŁA�ǂ��������A���̂������͍������A�A�ł����ꂵ���I�����͖��������B
��������Ă݂���A����Ȃ�ɗǍD�Ȋ����ʼn����ɂ�鍷�����Ȃ菬�����Ȃ�B�܂�M���̘R�ꂪ�L���B
�ŁA�X�}�[�g�ł͂Ȃ����A���̕��@�ɋ߂����@��͍��B
BNC�̃G�b�W�R�l�N�^�͂悭�킩��Ȃ�����̍Đv���K�v�B��ɕ��S�������肻���B
SMA�R�l�N�^��BNC�ւ̃A�_�v�^�ɕt����ƁA��������S���������A�R�l�N�^�[�A�_�v�^�͔��˂̌����ɂȂ�̂ŁA�Ȃ�ׂ������������A����Œ��Ɉ������ނɂ̓P�[�X�̒���������Ȃ������B
�ŁASMA�ȃP�[�u������������ŁA�X�}�[�g��BNC�֕ϊ��������Ǝv�����BSMA-J��BNC-J�A�_�v�^���H�����Z���ǂ������B�B
�H����SMA�R�l�N�^�P�[�u���B500�~�̂�VSWR��2.0�ȉ��ł�����ƐS�z�B�����݂����Ɍ�����1080�~�̂��AVSWR1.20�ȉ��B�傫�ȈႢ�̂悤�ȁc�A�A
�A���G�N�����Č��āA�v���p�̍����P�[�u����VSWR��1.15�ȉ��Ȃ̂ŁA�ǂ��������A���̂������͍������A�A�ł����ꂵ���I�����͖��������B
 20cm�̂ɂ��Ă݂��B
�Ƃɂ����A�P�[�u���A�R�l�N�^���}�g���ɂ��Ă����A�i�������Ȃ��A���˂ȂNjN����ɂ����B
�ł����āAPre-AMP�̕��́A�q����Ɠd���̓���肵�Ă����ꎩ�̂̔��U�͂����B�ŁAAGC-AMP�̏�Ԃ̕ω������܂�Ȃ��B
����Ƃ���A�P�[�u���̏�ԂȂǂ�AGC-AMP�������U���邩���A�܂�Pre-AMP�o�͂�FCZ�R�C���ݒ�����ʂɂ͌����Ă�݂��������A���̓d���̓����̉e���͂قږ����B
���Ⴀ�A�Ƃ肠�����A�v�����āAFET�̒��t���܂ŗ\���i�߂Ă݂悤���A�A�B
�ŁA�V�^��3��ނ𑗂�A
�������Ԃ������Ă���ŐV�^�ɂ��ėl�q���ǂ���ŏI�ł��B
���́A�V���ȉ��NJ���v���Ă��܂��Ă��āA�܂��A�����ɐ��\�ƈ����₷���̉��P�Ƃ����`�A�A
�܂������͂��ĂȂ����ǁA����قlj��i��������Ȃ��̂ŁA���̓��ɔ������Ă��܂����Ƃ͎v���Ă���B
�܂��A�����e�ɂ��g���镔��������悤�����B
���8cm���x���ꂽ�Ƃ���10000�{�߂�VHF�M��������̂̓L�c�C�̂��ȁB
���̏�ԂŁA�����ŁA�Q�C���́A�ő�90�`100dB�͍s���Ă��邩���m��Ȃ��B
�p�^�[�����ׂ��������������ǁA�M��ۂɑ��������˂Ȃ��̂ő��߂ł��B
�ł����āAFET�̑������Z���o�����B
20cm�̂ɂ��Ă݂��B
�Ƃɂ����A�P�[�u���A�R�l�N�^���}�g���ɂ��Ă����A�i�������Ȃ��A���˂ȂNjN����ɂ����B
�ł����āAPre-AMP�̕��́A�q����Ɠd���̓���肵�Ă����ꎩ�̂̔��U�͂����B�ŁAAGC-AMP�̏�Ԃ̕ω������܂�Ȃ��B
����Ƃ���A�P�[�u���̏�ԂȂǂ�AGC-AMP�������U���邩���A�܂�Pre-AMP�o�͂�FCZ�R�C���ݒ�����ʂɂ͌����Ă�݂��������A���̓d���̓����̉e���͂قږ����B
���Ⴀ�A�Ƃ肠�����A�v�����āAFET�̒��t���܂ŗ\���i�߂Ă݂悤���A�A�B
�ŁA�V�^��3��ނ𑗂�A
�������Ԃ������Ă���ŐV�^�ɂ��ėl�q���ǂ���ŏI�ł��B
���́A�V���ȉ��NJ���v���Ă��܂��Ă��āA�܂��A�����ɐ��\�ƈ����₷���̉��P�Ƃ����`�A�A
�܂������͂��ĂȂ����ǁA����قlj��i��������Ȃ��̂ŁA���̓��ɔ������Ă��܂����Ƃ͎v���Ă���B
�܂��A�����e�ɂ��g���镔��������悤�����B
���8cm���x���ꂽ�Ƃ���10000�{�߂�VHF�M��������̂̓L�c�C�̂��ȁB
���̏�ԂŁA�����ŁA�Q�C���́A�ő�90�`100dB�͍s���Ă��邩���m��Ȃ��B
�p�^�[�����ׂ��������������ǁA�M��ۂɑ��������˂Ȃ��̂ő��߂ł��B
�ł����āAFET�̑������Z���o�����B
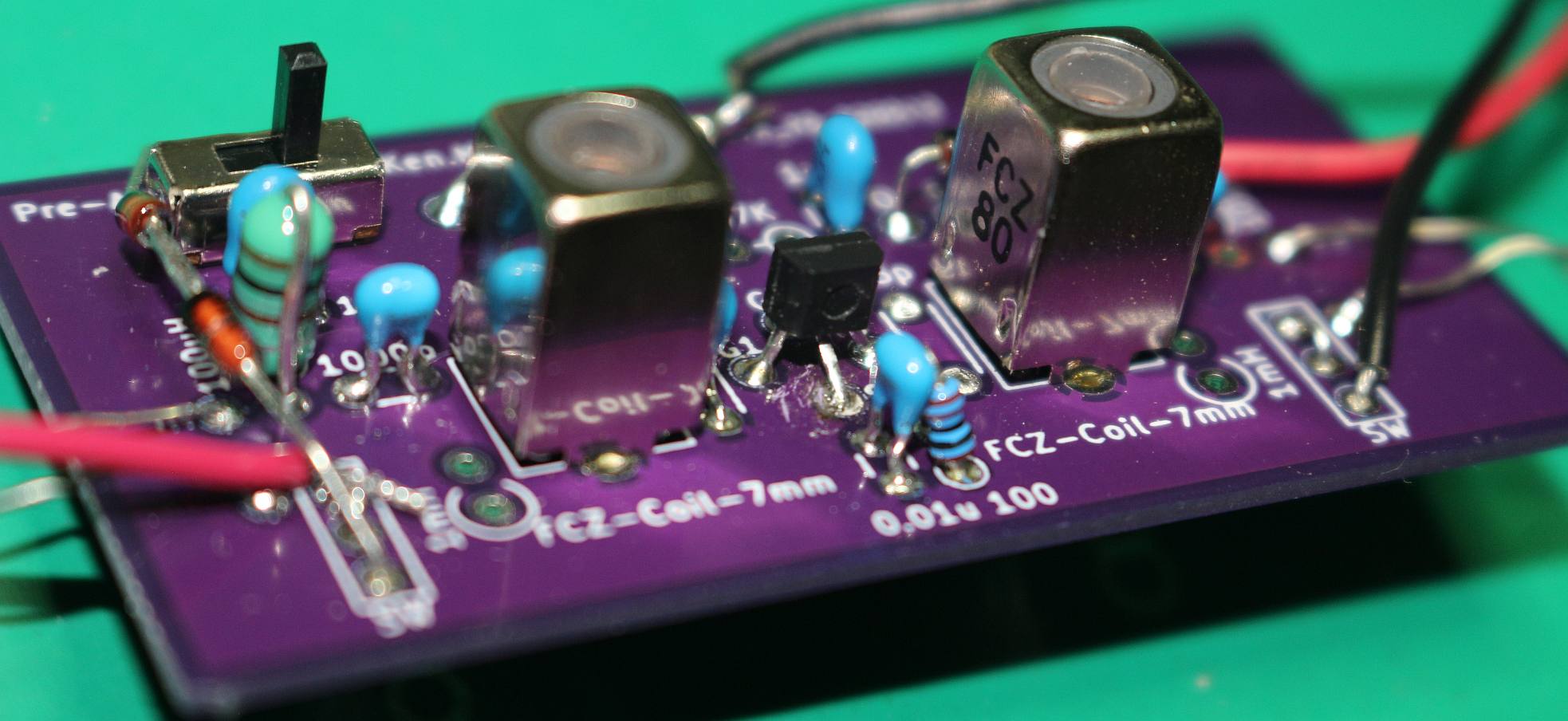 �܂��A2SK212�͔{�����Ⴂ�̂ŁA���X�A���U���Â炩�����̂ŁA���U�͂��Ȃ��悤�ł���B
�{���͂��傢������A�d���ɂ���4�`5�{���炢���ȁH
�M�������������āA�m�C�Y�܂݂�Ő��m�ɂ͔���Ȃ��B
�����P�[�X�ɓ���āABNC�ւ̃��C�������O��Z���������Ȃ�Ɍ����邩���B
����Ȃ�A2SK439�Ƃ��ł��ǂ����������B
�o�͂�FCZ�R�C���̐������́AVNA�ő��肵�Ȃ��獇�킹������AGC-AMP�ɂƂ��Ă��ǂ����낤�B
-----------------------------------------------------------------------
230612
�����_�A��̐����҂��ŁA�P�[�X���H����������x�ł���B
�����ڂ͗ǂ��Ȃ����������A�P�[�X�Ƃ��̓����̃P�[�u���̎����Ƃ��Ă͗ǂ��Ǝv���āA
�uMB11-8-25�v�ȃP�[�X���g�p�B
�d�������͂��Ȃ薧�W�����邱�ƂɂȂ����B
�܂��A2SK212�͔{�����Ⴂ�̂ŁA���X�A���U���Â炩�����̂ŁA���U�͂��Ȃ��悤�ł���B
�{���͂��傢������A�d���ɂ���4�`5�{���炢���ȁH
�M�������������āA�m�C�Y�܂݂�Ő��m�ɂ͔���Ȃ��B
�����P�[�X�ɓ���āABNC�ւ̃��C�������O��Z���������Ȃ�Ɍ����邩���B
����Ȃ�A2SK439�Ƃ��ł��ǂ����������B
�o�͂�FCZ�R�C���̐������́AVNA�ő��肵�Ȃ��獇�킹������AGC-AMP�ɂƂ��Ă��ǂ����낤�B
-----------------------------------------------------------------------
230612
�����_�A��̐����҂��ŁA�P�[�X���H����������x�ł���B
�����ڂ͗ǂ��Ȃ����������A�P�[�X�Ƃ��̓����̃P�[�u���̎����Ƃ��Ă͗ǂ��Ǝv���āA
�uMB11-8-25�v�ȃP�[�X���g�p�B
�d�������͂��Ȃ薧�W�����邱�ƂɂȂ����B
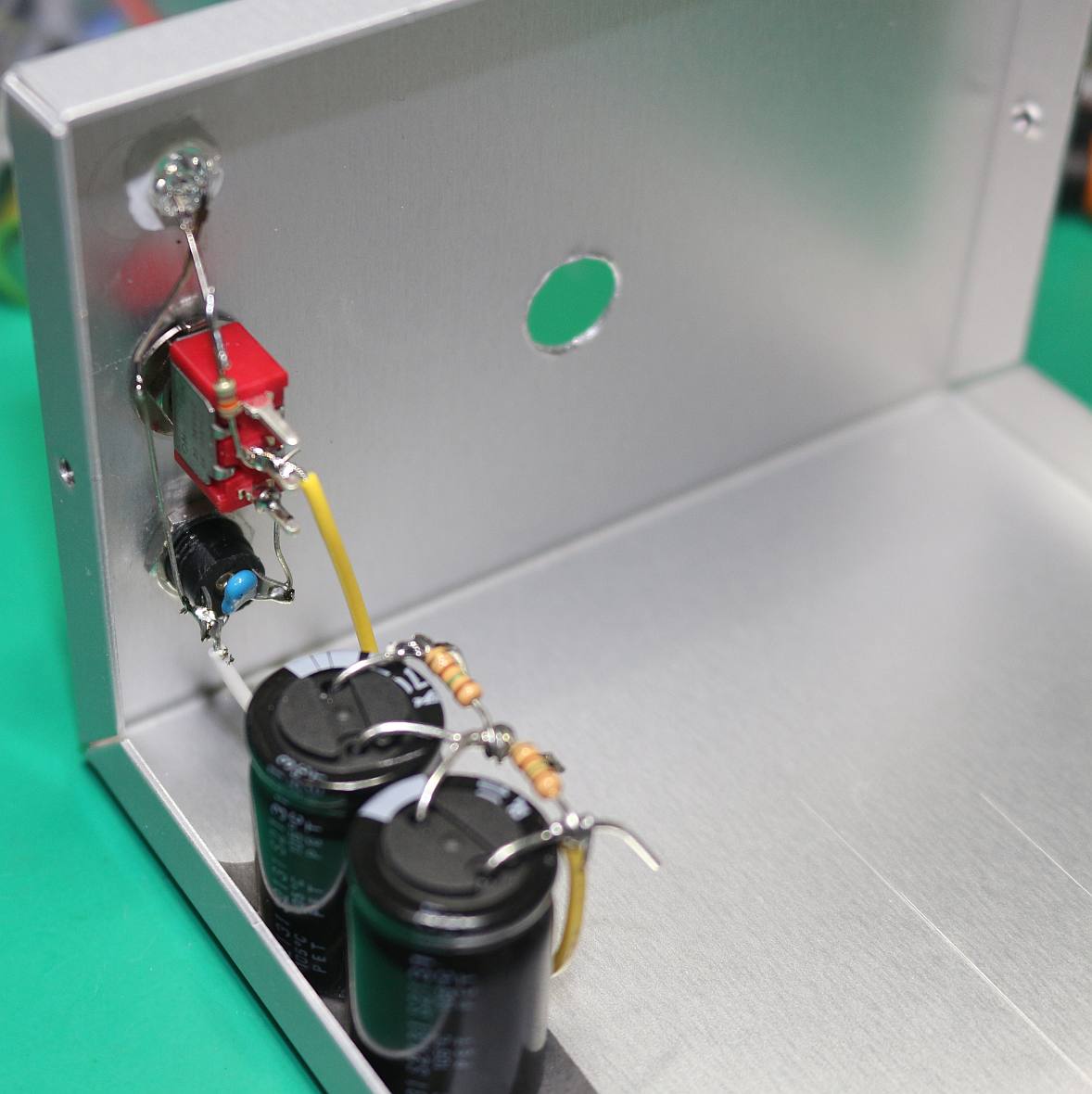 �����ŗ��[����P�[�u�����o�������ł���B
�����ŗ��[����P�[�u�����o�������ł���B
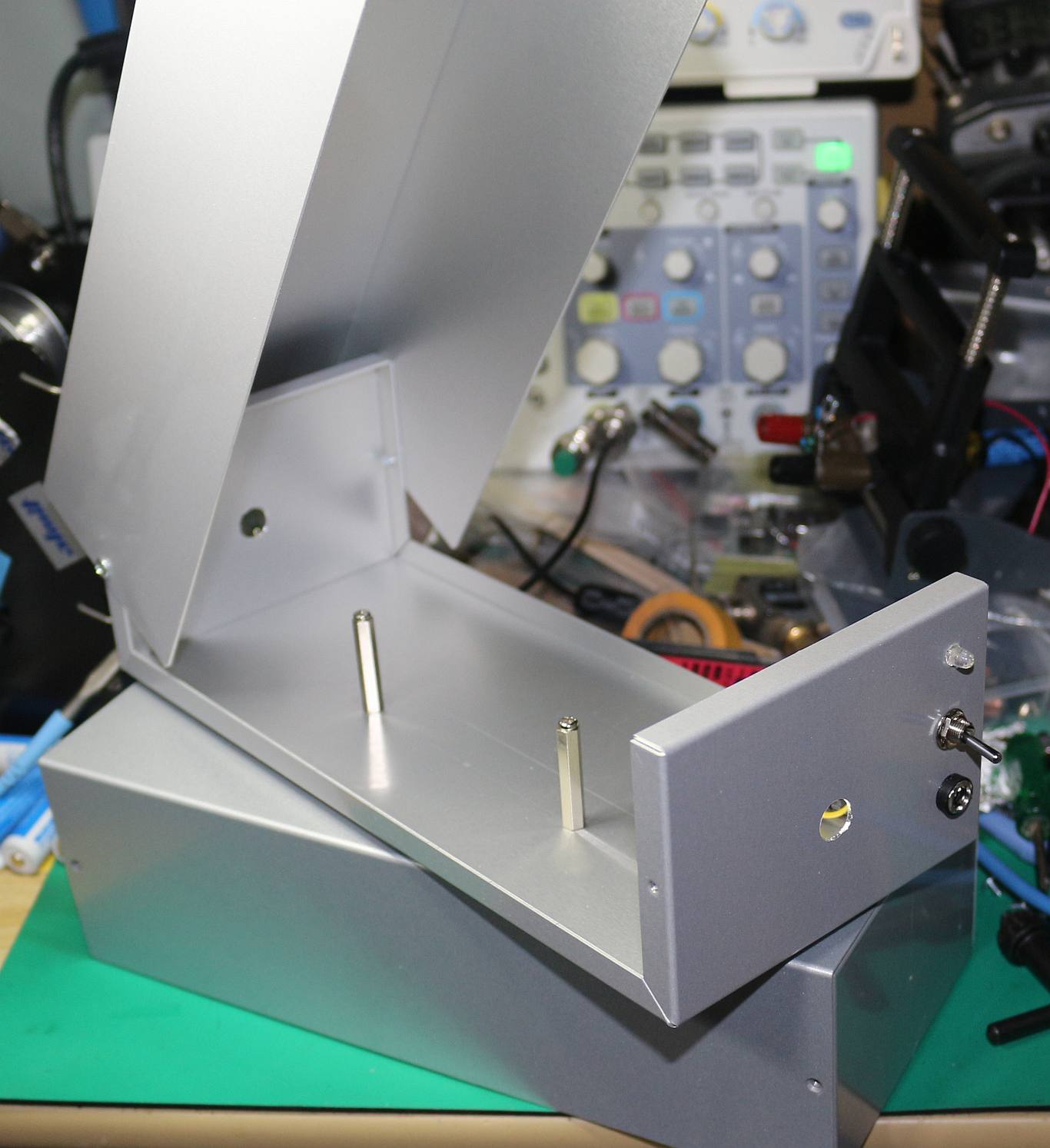 SMA-J��BNC-J�R�l�N�^�A�_�v�^�ȁA
�p�l�����t���ϊ��R�l�N�^���������̂ŁA�\�������炱�����������B
SMA-J��BNC-J�R�l�N�^�A�_�v�^�ȁA
�p�l�����t���ϊ��R�l�N�^���������̂ŁA�\�������炱�����������B
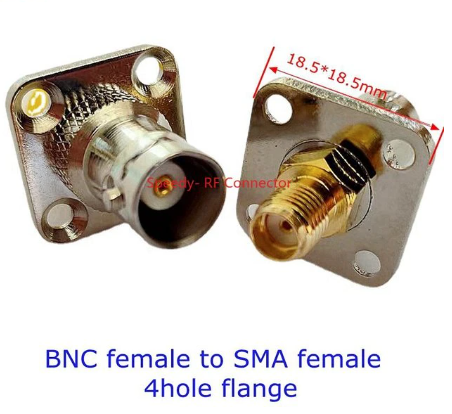 ----------------------�|�|�|�|�|
�ŁA�܂��A�o���邱�Ƃ���e�X�g�B
BNC�n���_�t���ڍ����̘R��\�h�ɁA
�A���~�����瓺���e�[�v�֕ύX�B
��ǂ����������ǁB������A�A���~���̂悤�Ƀy���y�����ĂȂ��̂ŁA�������ǂ��A�͂ݏo���Ă��ăV���[�g����Ȃǂ��h����B
GND�≏�n�̎����͕��d�Ȃǂ̎���U���m�C�Y�ɂ͗L���ł��A�d��I�U���̌��n����̓A���e�i�ɐ����Ă��܂������B�ŁA�꒷��Z�B
����ȂƂ����A�p�b�`���R�A�͗L�������B
�|�|�|�|�|
�����̋�������{�ł͂��邪�B
�t�o�C�A�X�APre-AMP�ɉ����āA�����Ă���P�[�u���̃��X�Ƃ����̂��o�J�ɂȂ疳���Ǝv�����B�����Ēᑹ�����ǂ����A���APE�Ȃǂ͌o�N�Ƃ��Ȃ��Ɏア�Ƃ����肻���B
�|�|�|�|�|
���U���͎�ɁA
�uZ�����v�A�u���o�͂̃��[�v�o�b�N�̃V�[���h�v�A�u�������Ȃ��Q�C���v
�ŗ}���ł���B
�V�O�i���ɑ��A�傫�����U���ĂȂ���A�Q�C���R���g���[���[���L���ɓ����B�̂ɃQ�C����������K�v�͖����B
�R��̃��[�v�o�b�N�͊��ɏo���邱�Ƃ�����Ă�̂ŁA
�Q�C���̒ጸ�����݂����A����قǕς��Ȃ������B��͂�A���{�Ƃ������x���ʼn����Ȃ��Ɓc�A
�|�|�|�|�|
�����ŁA��������������A�u���U�͎�ɂǂ����N�_�Ƃ��Ă��邩�H�v��T��B
���₩�ȂƂ��ł��I�i��AD811�ɐG���Ƒ傫�����U���錻�ۂ�����ꂽ�B
�m�F�̂��߁AAD811���W�����p�ɕς���Ɩw�ǔ��U���Ȃ��B
�܂��AIC�\�P�b�g�͎��߂����B
�|�|�|�|�|
�c��́A��͂�Z�����ł���(�t�H�gDi�����邪�A��ɏo�͑��̃R�l�N�^�A�P�[�u����ʑ����o��)�B�����AD811��IC�\�P�b�g��p���A��ւ̒��t���B
AD811�͒��ړI�ȋA�҂�p����OP-AMP�Ȃ̂ŁA���˔g�Ɏア���ȁH�Ǝv����B
����ɑ��ẮAFCZ�R�C����p����BPF�⓯���^�^�C�v��ATT���g���Č��悤�Ǝv���B
----------------------------------------------------------------------------
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�ǂ����ł̉�b�B
���o���~�ƕېg�ł����ˁB�B�B
���撣�艮����Ȃ�
���v���C�h�A���Ȍ����~�������ďo���~�������Ĉ����Ӗ��Ő��n����
�����̑f��������悤�Ȋ����ł��˂�
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�^�_�ł���Ă��Ƒ�����Ă݂ėl�q�����Ă���B
�܂��A���������Ƃ́A�����[���ʔ������ʂ��B�v�l�̒��g���m�肽���B
����̓f�J���Ă��A
�l�Ԑ��͓����ȉ������B�B
�����āA��2�̑��t�������B�����������ˁB
----------------------------------------------------------------------------
230615
���FCZ�R�C���̈��������߁A�T�g�[�d�C�ł͈����Ă��邪�A�������̂��ߌ��݃R�A�ނ̕i��������Ȃ����ɂ��Q���Ⴂ�Ƃ̂��ƁB�܂��AQ�����Ⴂ�̂Ȃ�ǂ����A�R�C���Ƃ��Ă̌����������Ƃ�����ƕs�����B
�ł��A�R�A�ނ̐��\������A���킸�����ȂƂ����\�����B
�����͂̐≏���čl��
FCZ�R�C�����g�����X�ɂ��邱�ƂŃR�������[�h�m�C�Y�����炷�Ă̐��m�Ȋm�F�B
���}�̒ʂ�AGND���������邩���ASW�ɂĐ�ւ��鎖�Ŕ�r����B
----------------------�|�|�|�|�|
�ŁA�܂��A�o���邱�Ƃ���e�X�g�B
BNC�n���_�t���ڍ����̘R��\�h�ɁA
�A���~�����瓺���e�[�v�֕ύX�B
��ǂ����������ǁB������A�A���~���̂悤�Ƀy���y�����ĂȂ��̂ŁA�������ǂ��A�͂ݏo���Ă��ăV���[�g����Ȃǂ��h����B
GND�≏�n�̎����͕��d�Ȃǂ̎���U���m�C�Y�ɂ͗L���ł��A�d��I�U���̌��n����̓A���e�i�ɐ����Ă��܂������B�ŁA�꒷��Z�B
����ȂƂ����A�p�b�`���R�A�͗L�������B
�|�|�|�|�|
�����̋�������{�ł͂��邪�B
�t�o�C�A�X�APre-AMP�ɉ����āA�����Ă���P�[�u���̃��X�Ƃ����̂��o�J�ɂȂ疳���Ǝv�����B�����Ēᑹ�����ǂ����A���APE�Ȃǂ͌o�N�Ƃ��Ȃ��Ɏア�Ƃ����肻���B
�|�|�|�|�|
���U���͎�ɁA
�uZ�����v�A�u���o�͂̃��[�v�o�b�N�̃V�[���h�v�A�u�������Ȃ��Q�C���v
�ŗ}���ł���B
�V�O�i���ɑ��A�傫�����U���ĂȂ���A�Q�C���R���g���[���[���L���ɓ����B�̂ɃQ�C����������K�v�͖����B
�R��̃��[�v�o�b�N�͊��ɏo���邱�Ƃ�����Ă�̂ŁA
�Q�C���̒ጸ�����݂����A����قǕς��Ȃ������B��͂�A���{�Ƃ������x���ʼn����Ȃ��Ɓc�A
�|�|�|�|�|
�����ŁA��������������A�u���U�͎�ɂǂ����N�_�Ƃ��Ă��邩�H�v��T��B
���₩�ȂƂ��ł��I�i��AD811�ɐG���Ƒ傫�����U���錻�ۂ�����ꂽ�B
�m�F�̂��߁AAD811���W�����p�ɕς���Ɩw�ǔ��U���Ȃ��B
�܂��AIC�\�P�b�g�͎��߂����B
�|�|�|�|�|
�c��́A��͂�Z�����ł���(�t�H�gDi�����邪�A��ɏo�͑��̃R�l�N�^�A�P�[�u����ʑ����o��)�B�����AD811��IC�\�P�b�g��p���A��ւ̒��t���B
AD811�͒��ړI�ȋA�҂�p����OP-AMP�Ȃ̂ŁA���˔g�Ɏア���ȁH�Ǝv����B
����ɑ��ẮAFCZ�R�C����p����BPF�⓯���^�^�C�v��ATT���g���Č��悤�Ǝv���B
----------------------------------------------------------------------------
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�ǂ����ł̉�b�B
���o���~�ƕېg�ł����ˁB�B�B
���撣�艮����Ȃ�
���v���C�h�A���Ȍ����~�������ďo���~�������Ĉ����Ӗ��Ő��n����
�����̑f��������悤�Ȋ����ł��˂�
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�^�_�ł���Ă��Ƒ�����Ă݂ėl�q�����Ă���B
�܂��A���������Ƃ́A�����[���ʔ������ʂ��B�v�l�̒��g���m�肽���B
����̓f�J���Ă��A
�l�Ԑ��͓����ȉ������B�B
�����āA��2�̑��t�������B�����������ˁB
----------------------------------------------------------------------------
230615
���FCZ�R�C���̈��������߁A�T�g�[�d�C�ł͈����Ă��邪�A�������̂��ߌ��݃R�A�ނ̕i��������Ȃ����ɂ��Q���Ⴂ�Ƃ̂��ƁB�܂��AQ�����Ⴂ�̂Ȃ�ǂ����A�R�C���Ƃ��Ă̌����������Ƃ�����ƕs�����B
�ł��A�R�A�ނ̐��\������A���킸�����ȂƂ����\�����B
�����͂̐≏���čl��
FCZ�R�C�����g�����X�ɂ��邱�ƂŃR�������[�h�m�C�Y�����炷�Ă̐��m�Ȋm�F�B
���}�̒ʂ�AGND���������邩���ASW�ɂĐ�ւ��鎖�Ŕ�r����B
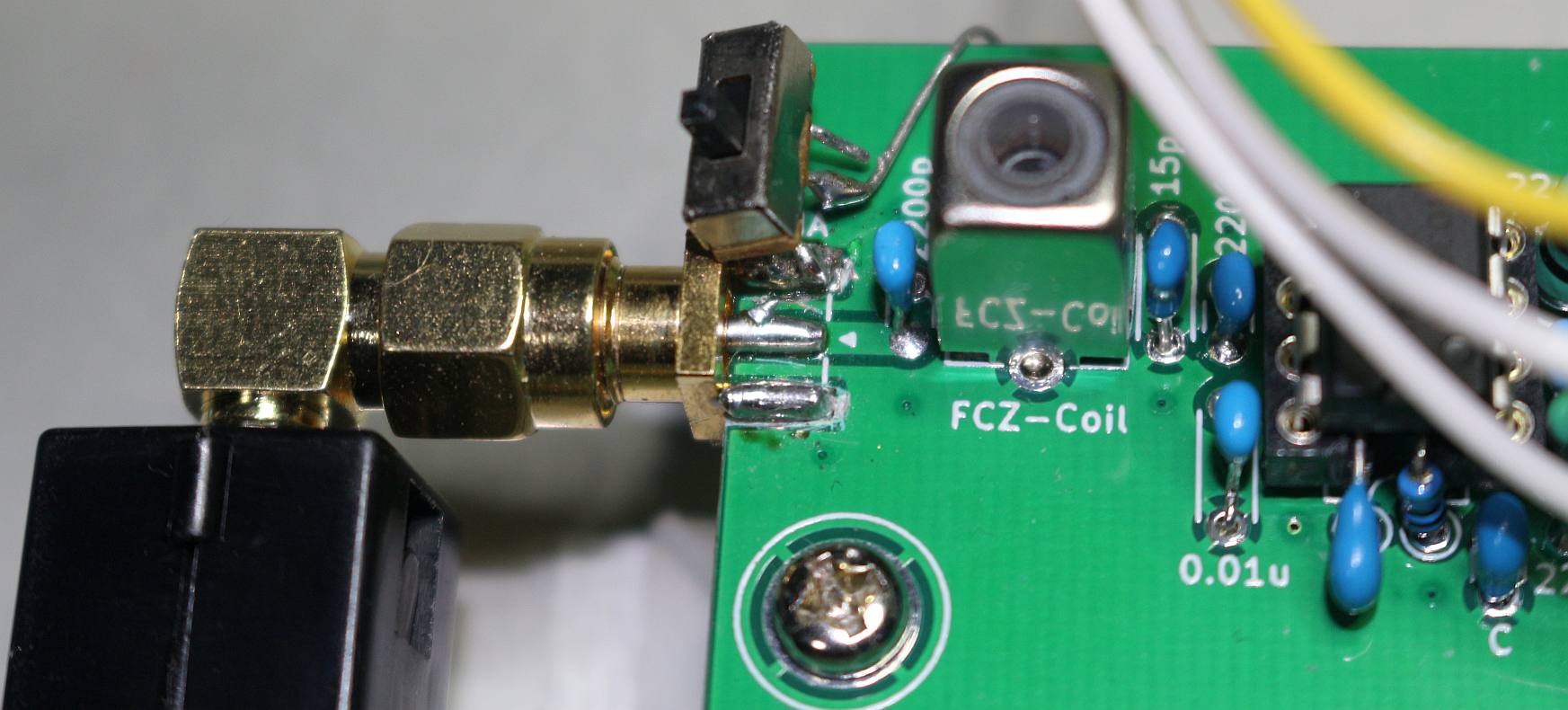 ���ʂƂ��ẮA��͂�AGND�����Ă���Ɣ��U����������X��������ꂽ�B
�P�[�u�����̂�GND���畂���Ă���̂ŃA���e�i�ɂȂ��Ă��܂��������o�����X���AGND���q���ƁA���ꂪ�A�X�g���[�L���p�V�^���X�����̂̑̐ς������ŁA���S���̕����ƊO�����̂̓d�ʍ��ފ����ŗU������Ă��邩�ƍl�����邪�s���ł͂���B
�v�͓d�ׂ̓����̗]�T�̍��ł��銴�����ƁB�܂��A�q���Ȃ��ꍇ�ȂǍl���Ȃ��Ă��ǂ����Ǝv�����B
���́A���ɁA�d���������̃V���b�N�ɂ���N�͈ĊO���Ȃ̂ʼn�H�S�ʂ�h���Ԃ�̂ł����āA
��펞�̓d������͋������A���������̃X���[�X�^�[�g�ȗv�f���~�����Ƃ���ł����邪�B
�܂��A���̔��U�́A���͂��V���[�g�����~���[�g���Ă��܂��Ύ~�܂邪�A�A
���̏ꍇ�̔��U�͏��i��IC���ۂ��̂Œ��t����Ԃł̓i���{���}�V�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��낤�B
(�I�i�����U�����ꍇ�́A���͂̃V���[�g�ł͎��܂�Ȃ��v�f�����肤��B
�ꍇ�ɂ���Ă͓d���܂ŗh���Ԃ��邱�Ƃ��B���ꂪVCA��AD603AQ�̏ꍇ�ł������B)
�����Ƀ`���[�N�R�C��1mH�Œ�ESR�d��8200��F���q���œ˓��d�����ɘa���Ă݂Ă����ʂ͂��܂�c�A�A
���d���̃X���[�X�^�[�g��������
���������Ă݂��B
���ʂƂ��ẮA��͂�AGND�����Ă���Ɣ��U����������X��������ꂽ�B
�P�[�u�����̂�GND���畂���Ă���̂ŃA���e�i�ɂȂ��Ă��܂��������o�����X���AGND���q���ƁA���ꂪ�A�X�g���[�L���p�V�^���X�����̂̑̐ς������ŁA���S���̕����ƊO�����̂̓d�ʍ��ފ����ŗU������Ă��邩�ƍl�����邪�s���ł͂���B
�v�͓d�ׂ̓����̗]�T�̍��ł��銴�����ƁB�܂��A�q���Ȃ��ꍇ�ȂǍl���Ȃ��Ă��ǂ����Ǝv�����B
���́A���ɁA�d���������̃V���b�N�ɂ���N�͈ĊO���Ȃ̂ʼn�H�S�ʂ�h���Ԃ�̂ł����āA
��펞�̓d������͋������A���������̃X���[�X�^�[�g�ȗv�f���~�����Ƃ���ł����邪�B
�܂��A���̔��U�́A���͂��V���[�g�����~���[�g���Ă��܂��Ύ~�܂邪�A�A
���̏ꍇ�̔��U�͏��i��IC���ۂ��̂Œ��t����Ԃł̓i���{���}�V�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��낤�B
(�I�i�����U�����ꍇ�́A���͂̃V���[�g�ł͎��܂�Ȃ��v�f�����肤��B
�ꍇ�ɂ���Ă͓d���܂ŗh���Ԃ��邱�Ƃ��B���ꂪVCA��AD603AQ�̏ꍇ�ł������B)
�����Ƀ`���[�N�R�C��1mH�Œ�ESR�d��8200��F���q���œ˓��d�����ɘa���Ă݂Ă����ʂ͂��܂�c�A�A
���d���̃X���[�X�^�[�g��������
���������Ă݂��B
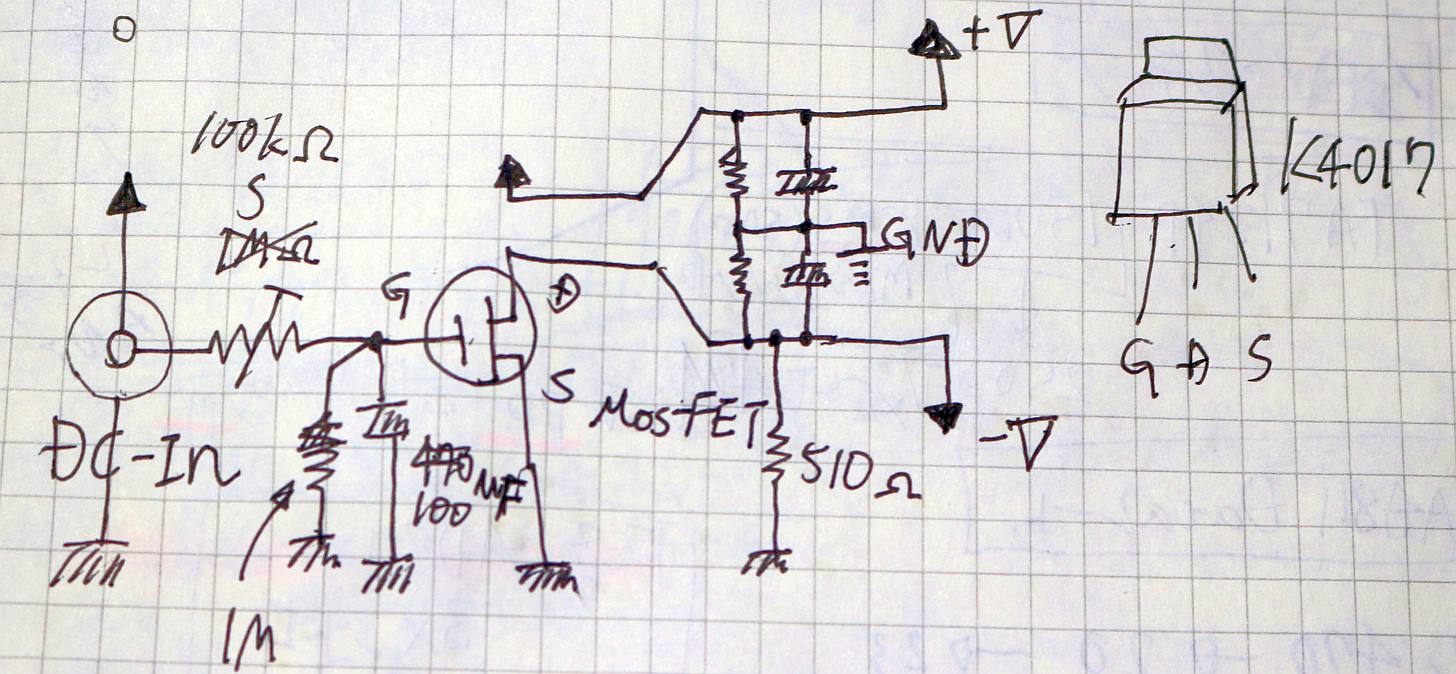 ���萔���e�L�g�[�ɑg���߁A�X�C�b�`�I��������ۂɓd��������̂�10�b���傢�قǂ�����B
���萔���e�L�g�[�ɑg���߁A�X�C�b�`�I��������ۂɓd��������̂�10�b���傢�قǂ�����B
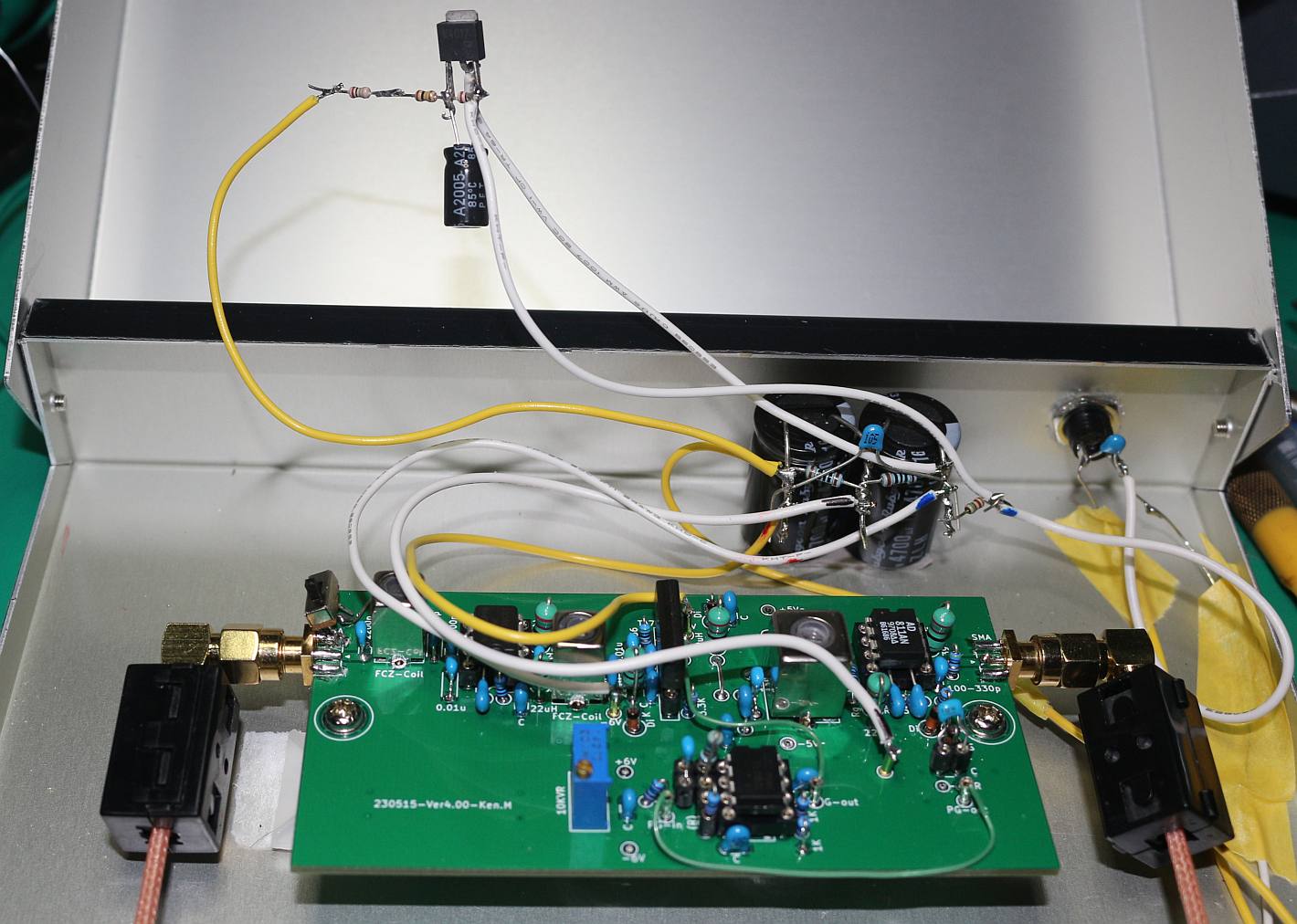 �ŁA�ǂ����Ƃ����ƁA
�V���b�N�Ŕ��U���邩���Ȃ����̔����ȃ��C���̏�Ԃɂ������ʂ������B
�܂�\�z�����قǍ������U�̏������ʂł����������B
���P�[�u�����ł̊O���������e�X�g��
VSWR=1.15�ȉ��̌v���p�ȍ����P�[�u�����͂����̂ŁA������P�[�X����o���悤�ɂ��Đڑ����ă`�F�b�N����B
���̃P�[�u���͂��Ȃ₩�ł͂Ȃ��A�ƂĂ��d���B
�H����1080�~�̕���1.5m��SMA�R�l�N�^�t���P�[�u���́AVSWR=1.20�ȉ��ŁA������ق�̋͂��ɗ�邪�A
���Ȃ�ǂ����x���Œ����ӂ�̉��i�͈��߂Ȃ̂ŁA�t�F�C�Y�f�B�e�N�^�ɒ��ړ����Ȃ��{�ōς݂��������A
�p�r�ɂ���ď\���I�ׂ�Ǝv���鑶�݂ł���B�U�d�̂�PTFE(�e�t����)�Ȃ̂ŁA�ϋv�����ǂ������ł���B
�ŁA�ǂ����Ƃ����ƁA
�V���b�N�Ŕ��U���邩���Ȃ����̔����ȃ��C���̏�Ԃɂ������ʂ������B
�܂�\�z�����قǍ������U�̏������ʂł����������B
���P�[�u�����ł̊O���������e�X�g��
VSWR=1.15�ȉ��̌v���p�ȍ����P�[�u�����͂����̂ŁA������P�[�X����o���悤�ɂ��Đڑ����ă`�F�b�N����B
���̃P�[�u���͂��Ȃ₩�ł͂Ȃ��A�ƂĂ��d���B
�H����1080�~�̕���1.5m��SMA�R�l�N�^�t���P�[�u���́AVSWR=1.20�ȉ��ŁA������ق�̋͂��ɗ�邪�A
���Ȃ�ǂ����x���Œ����ӂ�̉��i�͈��߂Ȃ̂ŁA�t�F�C�Y�f�B�e�N�^�ɒ��ړ����Ȃ��{�ōς݂��������A
�p�r�ɂ���ď\���I�ׂ�Ǝv���鑶�݂ł���B�U�d�̂�PTFE(�e�t����)�Ȃ̂ŁA�ϋv�����ǂ������ł���B
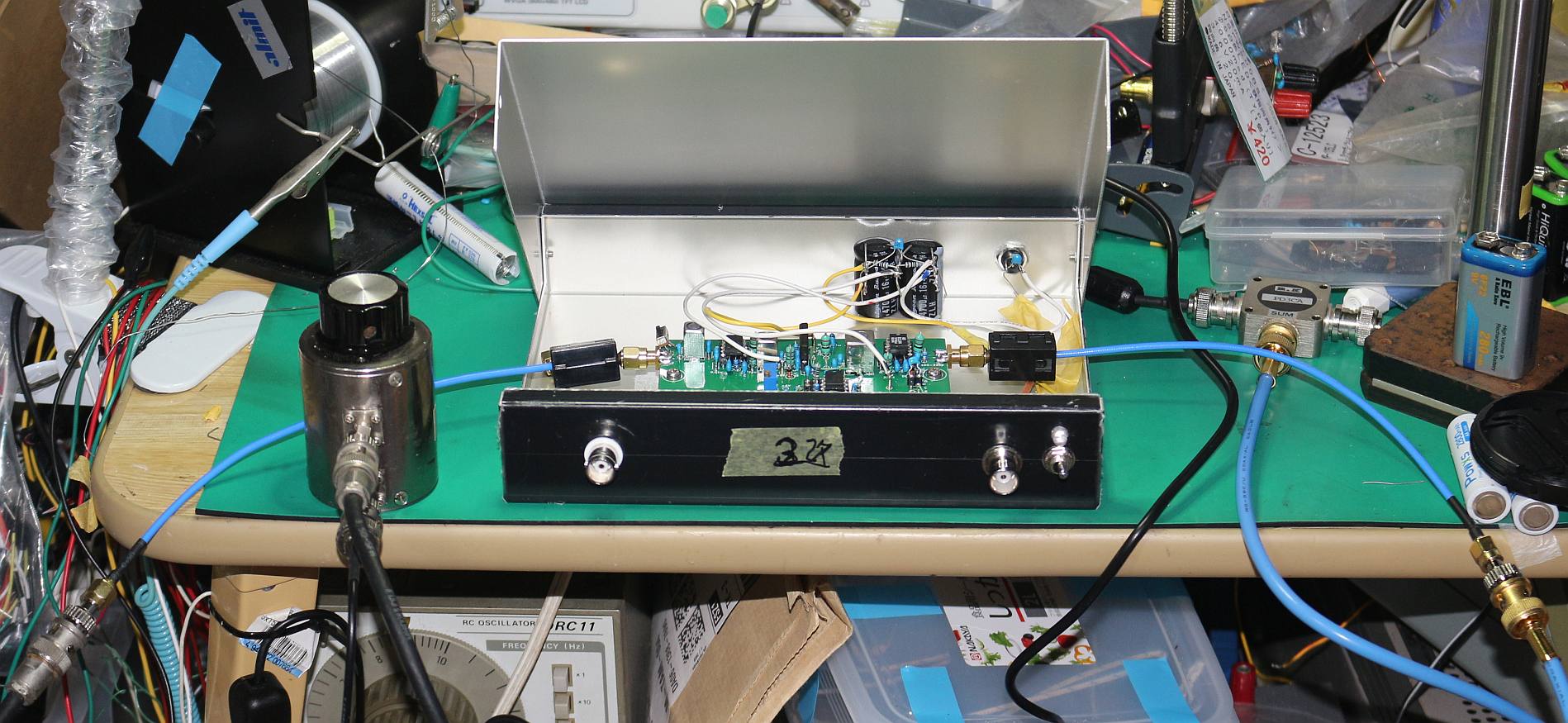 �P�[�u����20cm�ŁASMA-J��BNC-J�R�l�N�^�A�_�v�^�ł���Ȃ�ɍ����ȃP�[�u���Ɍq���ł���B
(�{���Ȃ�A�R�l�N�^�A�_�v�^���r�����āA������{�̍����P�[�u���Ōq���̂��x�X�g�ł��邪�A�A)
�_�����\�z�ʂ�A���Ȃ荂�����ʂŁA�U���̕s���肳�┭�U���}����ꂽ�B
(�p�b�`���R�A�͖����Ă�OK�̂悤�����ی��B)
�R���ɉ����A��̍ŐV����AIC�̒��t���A�����̃P�[�X�Ȃǂ̎g�p�ɂ��A�X�ɗǂ����ʂɌq����A�Ǝv���B
���̌��ʂ��炵�āA�Ƃɂ����`���n�̃P�[�u����R�l�N�^�́A
Z���s���m�ł�������A�s�A���ȃC���s�[�_���X�́A���˂��N�������U�X���Ȃǂ̖��Ɍq����̂ŁA�P�[�u���y�ѕϊ��R�l�N�^�͗ǂ����m���g���R�g�������ƂȂ�B
���ɁA�t�o�C�A�X��������Si-PIN�t�H�gDi���q���ł݂��BZ�}�b�`���O�͍s���Ă��Ȃ����A���Ȃ���肵�Ă����B
60MHz�̃��[�U�[�����Č���ƁA�U���͈ȑO���Q�ł����Ȃ���Ԃ��m�F�B
FCZ�R�C���̃g�����X�ŐM��Z�𐮍�����悤�ɕϊ�����A�X�ɍׂ����Q�ł��������āA�g�`�����肷��̂ł͖������Ƃ������҂����Ă�B
�]�k�����A�n���_�́A�A���~�b�g��KR-19�́A�H�������ǂ������ň�ʓI�ɂ͐l�C�����A������S���������B
�����X�Y60%�ł��A�X�p�[�N���n���_�̕������̕ӂ��i�i�ɗǂ����AKR-19�̂悤�Ɉ�u�e���悤�Ȋ��o�������B
���ɁA�X���[�z�[���̃n���_�t���ɂ́A�X�Y63%�́u�����n���_�v���ǂ��B���c�G��A���ꂪ�ǂ��̂����������A
����̗��_�́A�ނ��땔�i���O���Ƃ��ɁA��Z�_�ŁA���ꂪ�ǂ��̂ŁA�z�����₷���̂ŁA���i���O���₷���Ƃ������ŁA���i�⑼�̕����ɂ����S�����Ȃ��ςނƂ����ϓ_����ł���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
20230621
���ꂼ��ɐؒf�������A�^��BPF��̂ǂ�����g�����B
�P�[�u����20cm�ŁASMA-J��BNC-J�R�l�N�^�A�_�v�^�ł���Ȃ�ɍ����ȃP�[�u���Ɍq���ł���B
(�{���Ȃ�A�R�l�N�^�A�_�v�^���r�����āA������{�̍����P�[�u���Ōq���̂��x�X�g�ł��邪�A�A)
�_�����\�z�ʂ�A���Ȃ荂�����ʂŁA�U���̕s���肳�┭�U���}����ꂽ�B
(�p�b�`���R�A�͖����Ă�OK�̂悤�����ی��B)
�R���ɉ����A��̍ŐV����AIC�̒��t���A�����̃P�[�X�Ȃǂ̎g�p�ɂ��A�X�ɗǂ����ʂɌq����A�Ǝv���B
���̌��ʂ��炵�āA�Ƃɂ����`���n�̃P�[�u����R�l�N�^�́A
Z���s���m�ł�������A�s�A���ȃC���s�[�_���X�́A���˂��N�������U�X���Ȃǂ̖��Ɍq����̂ŁA�P�[�u���y�ѕϊ��R�l�N�^�͗ǂ����m���g���R�g�������ƂȂ�B
���ɁA�t�o�C�A�X��������Si-PIN�t�H�gDi���q���ł݂��BZ�}�b�`���O�͍s���Ă��Ȃ����A���Ȃ���肵�Ă����B
60MHz�̃��[�U�[�����Č���ƁA�U���͈ȑO���Q�ł����Ȃ���Ԃ��m�F�B
FCZ�R�C���̃g�����X�ŐM��Z�𐮍�����悤�ɕϊ�����A�X�ɍׂ����Q�ł��������āA�g�`�����肷��̂ł͖������Ƃ������҂����Ă�B
�]�k�����A�n���_�́A�A���~�b�g��KR-19�́A�H�������ǂ������ň�ʓI�ɂ͐l�C�����A������S���������B
�����X�Y60%�ł��A�X�p�[�N���n���_�̕������̕ӂ��i�i�ɗǂ����AKR-19�̂悤�Ɉ�u�e���悤�Ȋ��o�������B
���ɁA�X���[�z�[���̃n���_�t���ɂ́A�X�Y63%�́u�����n���_�v���ǂ��B���c�G��A���ꂪ�ǂ��̂����������A
����̗��_�́A�ނ��땔�i���O���Ƃ��ɁA��Z�_�ŁA���ꂪ�ǂ��̂ŁA�z�����₷���̂ŁA���i���O���₷���Ƃ������ŁA���i�⑼�̕����ɂ����S�����Ȃ��ςނƂ����ϓ_����ł���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
20230621
���ꂼ��ɐؒf�������A�^��BPF��̂ǂ�����g�����B
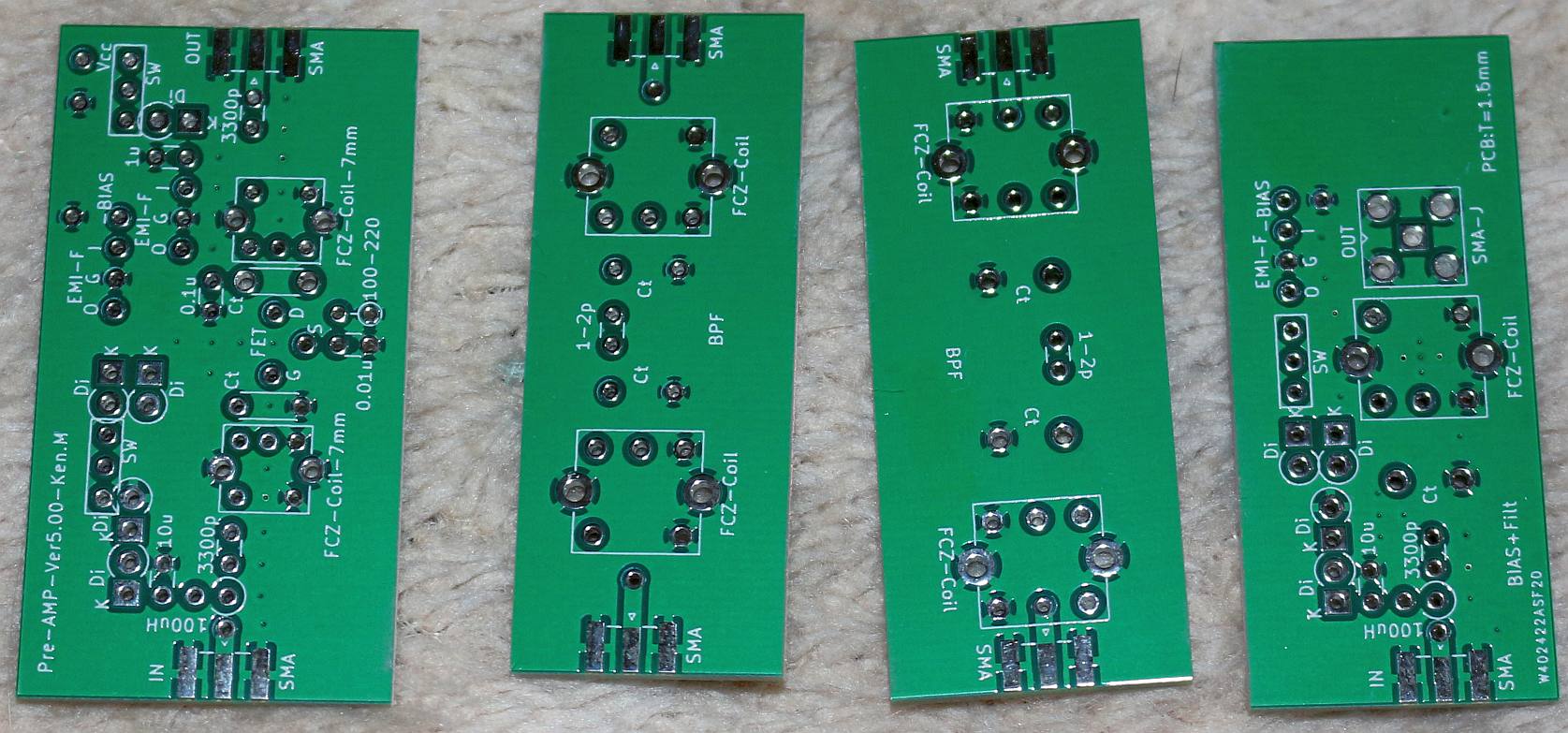 �Ⴂ�̓g���}�[�R���f���T�[���Œ�l�̃R���f���T�[���H�ł���B
��҂��Z�o���āA�g��ł݂��Ƃ���A�����A�s�[�N���o��B
(�^��C��3pF�����������킹�ĂȂ��̂ł��邪�A���e�͈͂ƔF�����A������g���B)
���ǁA�����U����������B�����A���ꂪ�A��ɏq�ׂ��R�A�ޗR����Q�̒Ⴓ���Ǝv����B
�����g�ł�ESR�����̗ǂ��P�^�f�B�X�N�R���f���T�[��t�����B
�Ⴂ�̓g���}�[�R���f���T�[���Œ�l�̃R���f���T�[���H�ł���B
��҂��Z�o���āA�g��ł݂��Ƃ���A�����A�s�[�N���o��B
(�^��C��3pF�����������킹�ĂȂ��̂ł��邪�A���e�͈͂ƔF�����A������g���B)
���ǁA�����U����������B�����A���ꂪ�A��ɏq�ׂ��R�A�ޗR����Q�̒Ⴓ���Ǝv����B
�����g�ł�ESR�����̗ǂ��P�^�f�B�X�N�R���f���T�[��t�����B
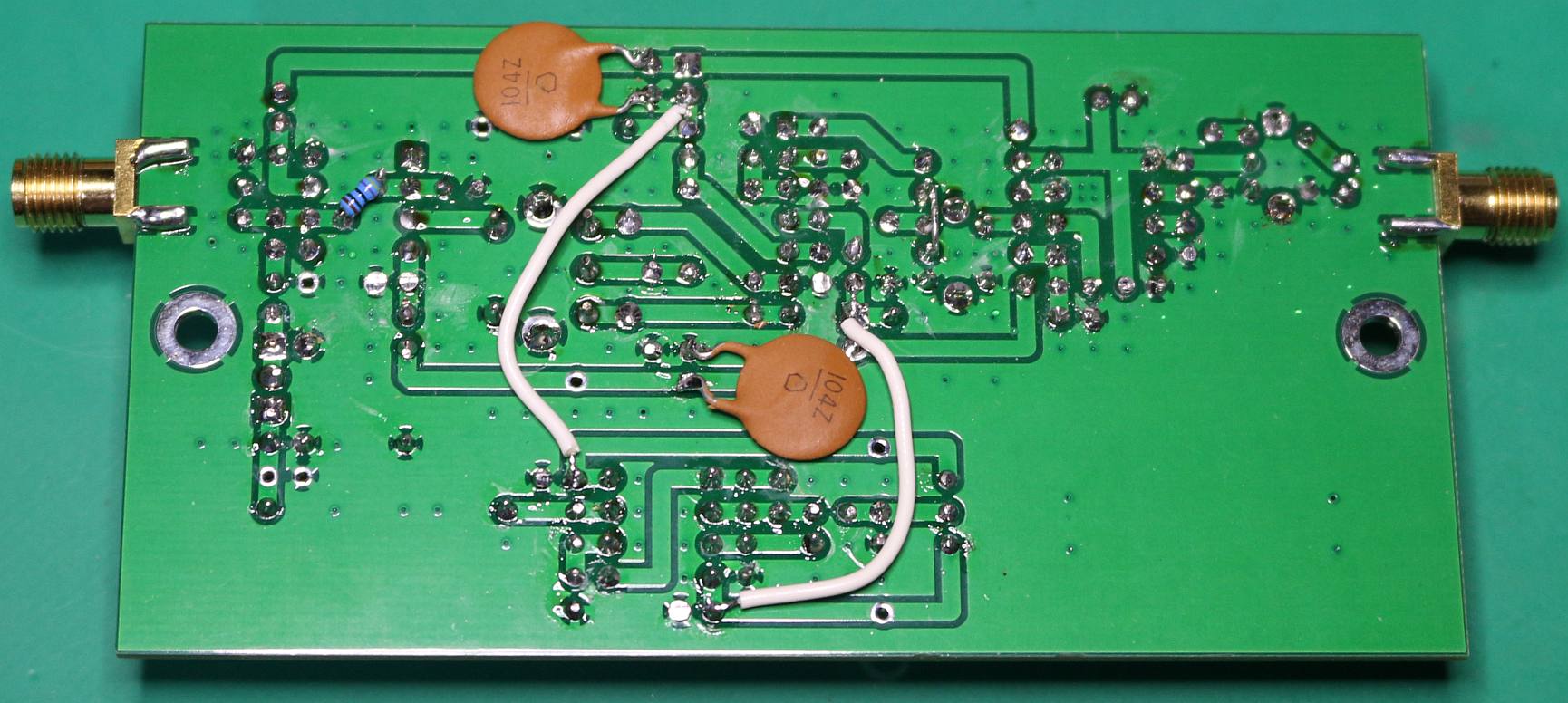 RF-AMP�̕�����IC�\�P�b�g��p���A���t���B
RF-AMP�̕�����IC�\�P�b�g��p���A���t���B
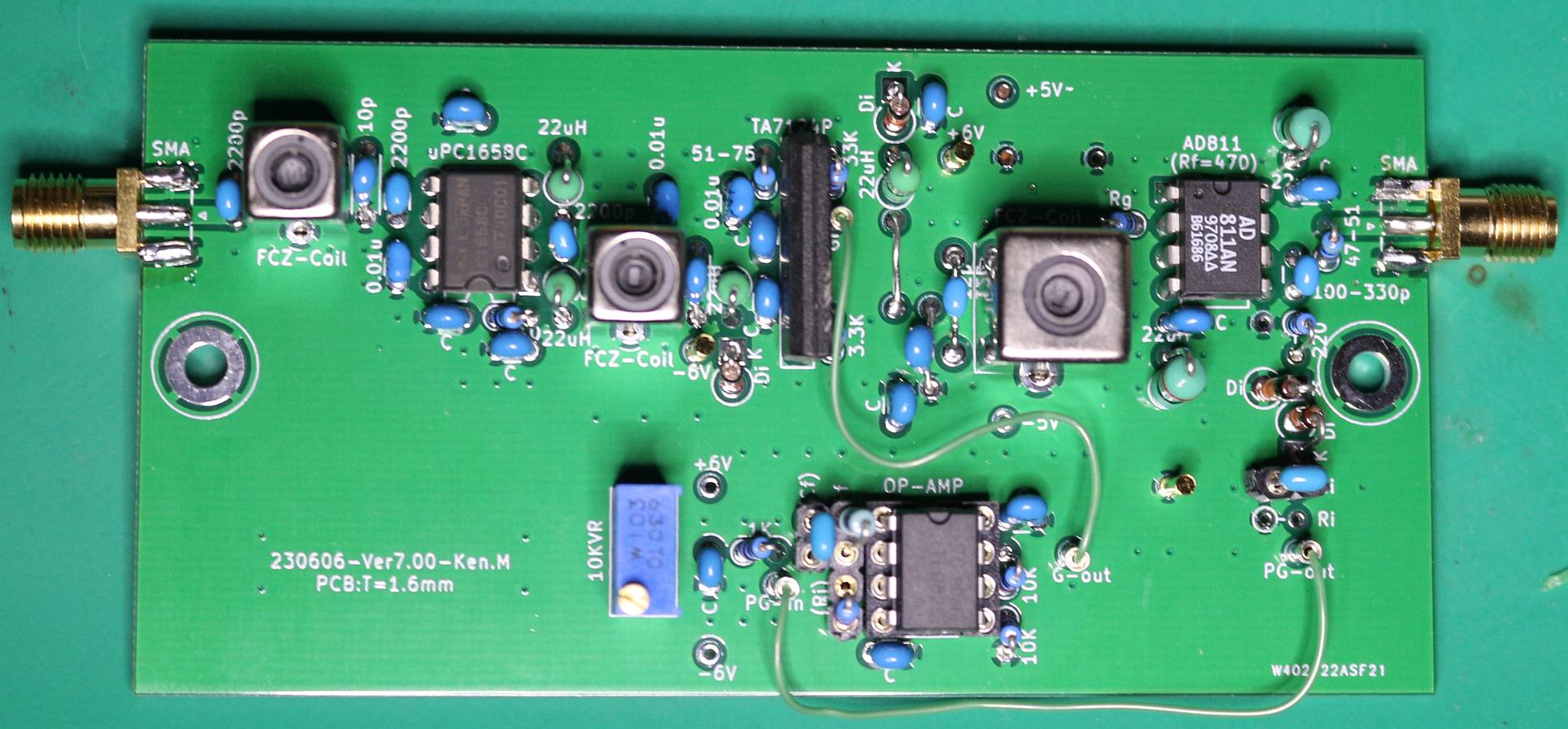
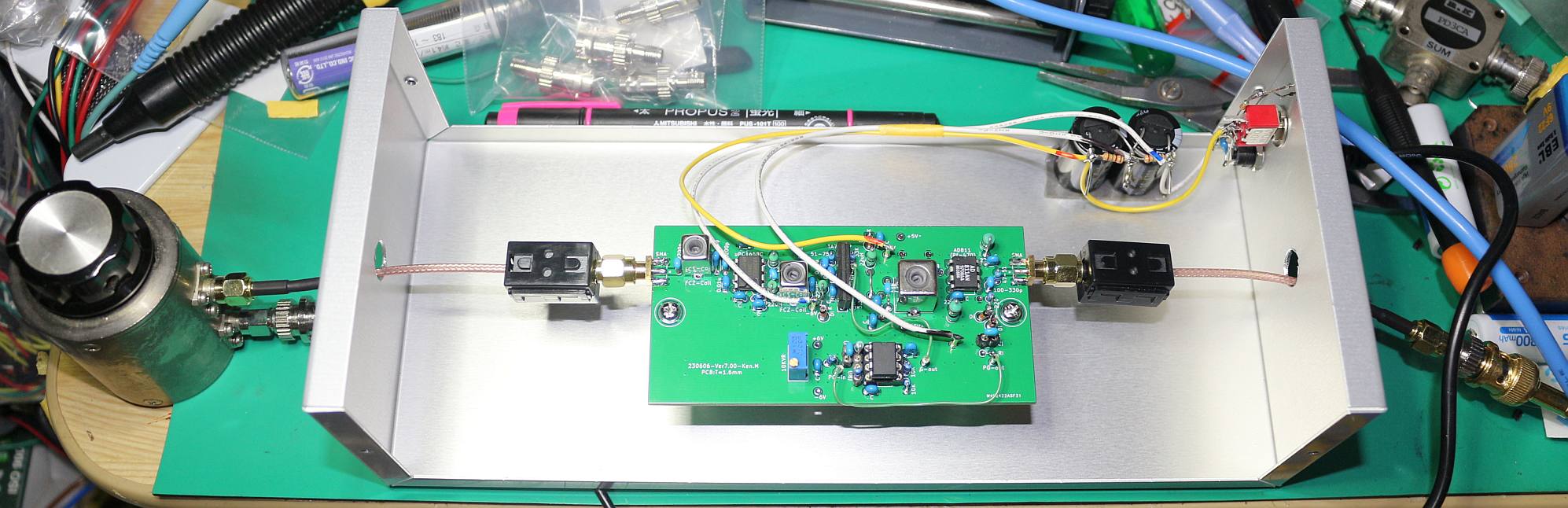 �}�̊���[�ɏo���Ă��铯���P�[�u���͎��������A���ʂ��ǂ��Ȃ��������AVSWR=1.15�ȉ��̃P�[�u���ɂ����B
������܂��ʂ��猾���ƁA�P�[�u���Ȃǂ̓`���n��Z�}�b�`���O���ǍD�ł���Ȃ�A
�u�z���Ȏ���̊�ł̎����I���ǒi�K�v�ƁA�قځA�ς��Ȃ����ʂƂȂ����B
���܂�ɂ��w�Ǖς��Ȃ��̂ŕs���ȋC���B
�����̍��Ƃ��ẮA
�E��3��FCZ�R�C���́A�]�B
�ERF-AMP�̕����͑S��IC�t���B
�E���ʂ́}5V�d�����C���Ƀf�B�X�N�R���f���T�[��ݒu�B
�E�����̃P�[�X�ŁA�����P�[�u���փ_�C���N�g�ڑ��B
�EGND���C���̃P�[�X�ւ̐ݒu�̈Ⴂ�B
�EGND�̃T�[�}���X�|�[�N�̑�����1.5�{��0.75mm�B
�ł���B
�C���t�����_�ł��邪�A
�P�[�u���ȂǓ`���n�̏�Ԃ������Ƃ��p�b�`���R�A�͂���Ȃ�ɗL���ł���B���ˁ˃R�������[�h�����Ȃ̂��H
�m�C�Y�ɂ��FCZ�R�C����N�Ǝv�����̔g�ł�����������B����͉ۑ肩���m��Ȃ��B
��2��FCZ�R�C�����݊��BTA7124P�̓��͂�C��5pF�Ƒ傫���̂ƁA51���͗v��Ȃ��͂��ł͂���̂��e�����B
�܂��A�����Q�C���̔䗦������������̕������肻���Ȃ̂ŁA�Nj����Ă܂ŁA�M��Ȃ��ėǂ��Ƃ��v���B
�}�̊���[�ɏo���Ă��铯���P�[�u���͎��������A���ʂ��ǂ��Ȃ��������AVSWR=1.15�ȉ��̃P�[�u���ɂ����B
������܂��ʂ��猾���ƁA�P�[�u���Ȃǂ̓`���n��Z�}�b�`���O���ǍD�ł���Ȃ�A
�u�z���Ȏ���̊�ł̎����I���ǒi�K�v�ƁA�قځA�ς��Ȃ����ʂƂȂ����B
���܂�ɂ��w�Ǖς��Ȃ��̂ŕs���ȋC���B
�����̍��Ƃ��ẮA
�E��3��FCZ�R�C���́A�]�B
�ERF-AMP�̕����͑S��IC�t���B
�E���ʂ́}5V�d�����C���Ƀf�B�X�N�R���f���T�[��ݒu�B
�E�����̃P�[�X�ŁA�����P�[�u���փ_�C���N�g�ڑ��B
�EGND���C���̃P�[�X�ւ̐ݒu�̈Ⴂ�B
�EGND�̃T�[�}���X�|�[�N�̑�����1.5�{��0.75mm�B
�ł���B
�C���t�����_�ł��邪�A
�P�[�u���ȂǓ`���n�̏�Ԃ������Ƃ��p�b�`���R�A�͂���Ȃ�ɗL���ł���B���ˁ˃R�������[�h�����Ȃ̂��H
�m�C�Y�ɂ��FCZ�R�C����N�Ǝv�����̔g�ł�����������B����͉ۑ肩���m��Ȃ��B
��2��FCZ�R�C�����݊��BTA7124P�̓��͂�C��5pF�Ƒ傫���̂ƁA51���͗v��Ȃ��͂��ł͂���̂��e�����B
�܂��A�����Q�C���̔䗦������������̕������肻���Ȃ̂ŁA�Nj����Ă܂ŁA�M��Ȃ��ėǂ��Ƃ��v���B
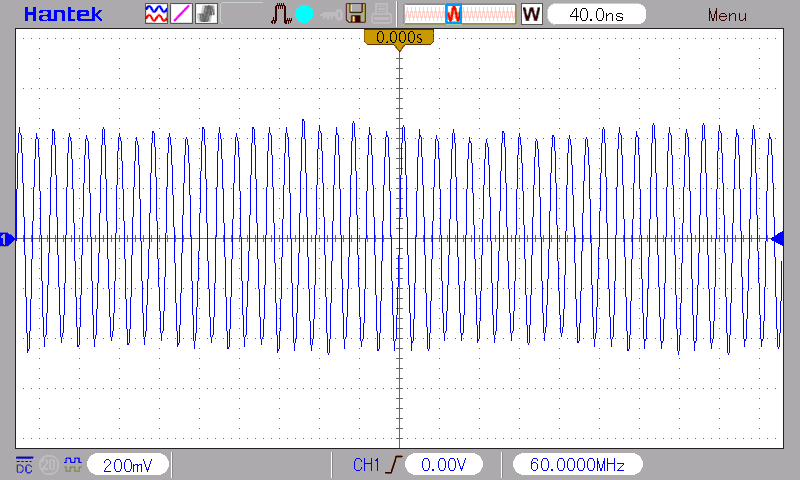 ������������Ȃ�ł���A�ʃX�y�N�g�����������Ă��邱�ƂɂȂ�B
�X�y�N�g���Ō���ƁA�Ă̒�50MHz�̃W���~���O��������x����B
������������Ȃ�ł���A�ʃX�y�N�g�����������Ă��邱�ƂɂȂ�B
�X�y�N�g���Ō���ƁA�Ă̒�50MHz�̃W���~���O��������x����B
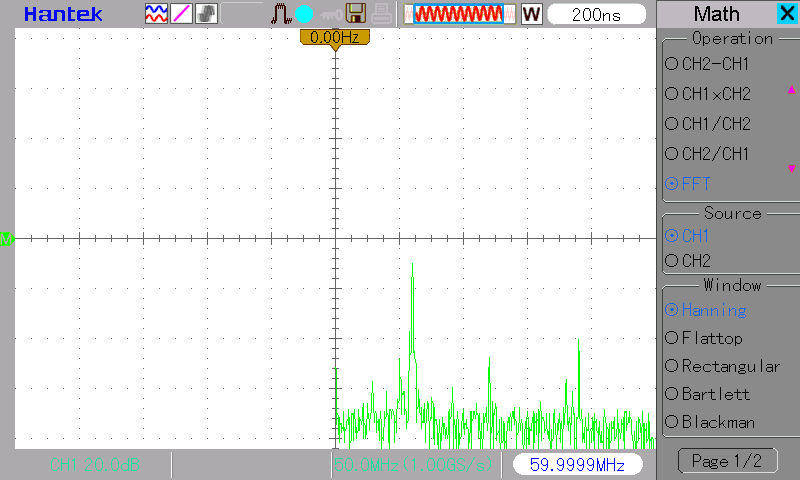 �K���A10MHz���Ⴄ�̂Ńt�B���^�[�ނŃJ�b�g�����ł��낤���Ǝv���B
�ǂ��R���̗h�炬�Ȃ̂��C�ɂȂ郂�m�ł͂��邪�A�A
���ۂɃ��T�[�W�����ǂ̒��x�̉~��`���̂��H�����āA�ŏI�I�Ɋp�x�ɂǂ̒��x�̉e����^���邩�H�ł���B
�f�J���M�������Ă����P���Ȃ��Ȃ�A���炭�I�i�̃Q�C����������悤�ȉ������K�v�ƂȂ�B
�o��������AL���̒��p�R�l�N�^�ʼn��}�̂悤��U���̔z�����o����X�}�[�g�����m��Ȃ��B
U���Ȃ̂ŁA�[�q�ԋ����̏_����o����B
�K���A10MHz���Ⴄ�̂Ńt�B���^�[�ނŃJ�b�g�����ł��낤���Ǝv���B
�ǂ��R���̗h�炬�Ȃ̂��C�ɂȂ郂�m�ł͂��邪�A�A
���ۂɃ��T�[�W�����ǂ̒��x�̉~��`���̂��H�����āA�ŏI�I�Ɋp�x�ɂǂ̒��x�̉e����^���邩�H�ł���B
�f�J���M�������Ă����P���Ȃ��Ȃ�A���炭�I�i�̃Q�C����������悤�ȉ������K�v�ƂȂ�B
�o��������AL���̒��p�R�l�N�^�ʼn��}�̂悤��U���̔z�����o����X�}�[�g�����m��Ȃ��B
U���Ȃ̂ŁA�[�q�ԋ����̏_����o����B
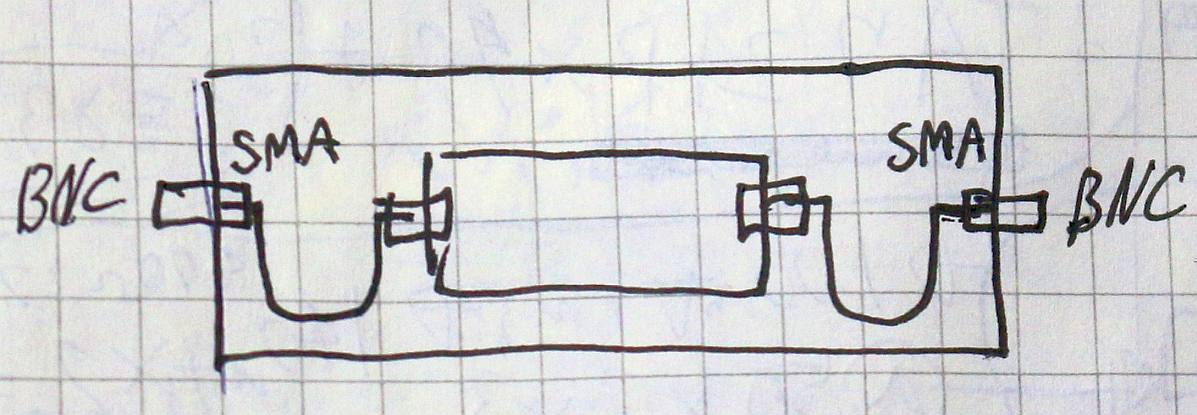 �E�P�[�XGND�ȂǂƃR�l�N�^GND�̐≏/�ڍ����ǂ��������邩�H
�EU���̋Ȃ��ɑς����鍂�i���P�[�u���ƁA�����ł̓��o�͐M���̃��[�v�o�b�N�ȗU�����������H
�E�p�b�`���R�A�͕t�����H
�ȂǁA����Ă݂Ȃ��Ƃ킩��Ȃ�����������B
�ŁA�����i�Ȃ���̍ŒZ��10cm���K�������ǁA15cm�̃P�[�u���Ŏ����B
�E�P�[�XGND�ȂǂƃR�l�N�^GND�̐≏/�ڍ����ǂ��������邩�H
�EU���̋Ȃ��ɑς����鍂�i���P�[�u���ƁA�����ł̓��o�͐M���̃��[�v�o�b�N�ȗU�����������H
�E�p�b�`���R�A�͕t�����H
�ȂǁA����Ă݂Ȃ��Ƃ킩��Ȃ�����������B
�ŁA�����i�Ȃ���̍ŒZ��10cm���K�������ǁA15cm�̃P�[�u���Ŏ����B
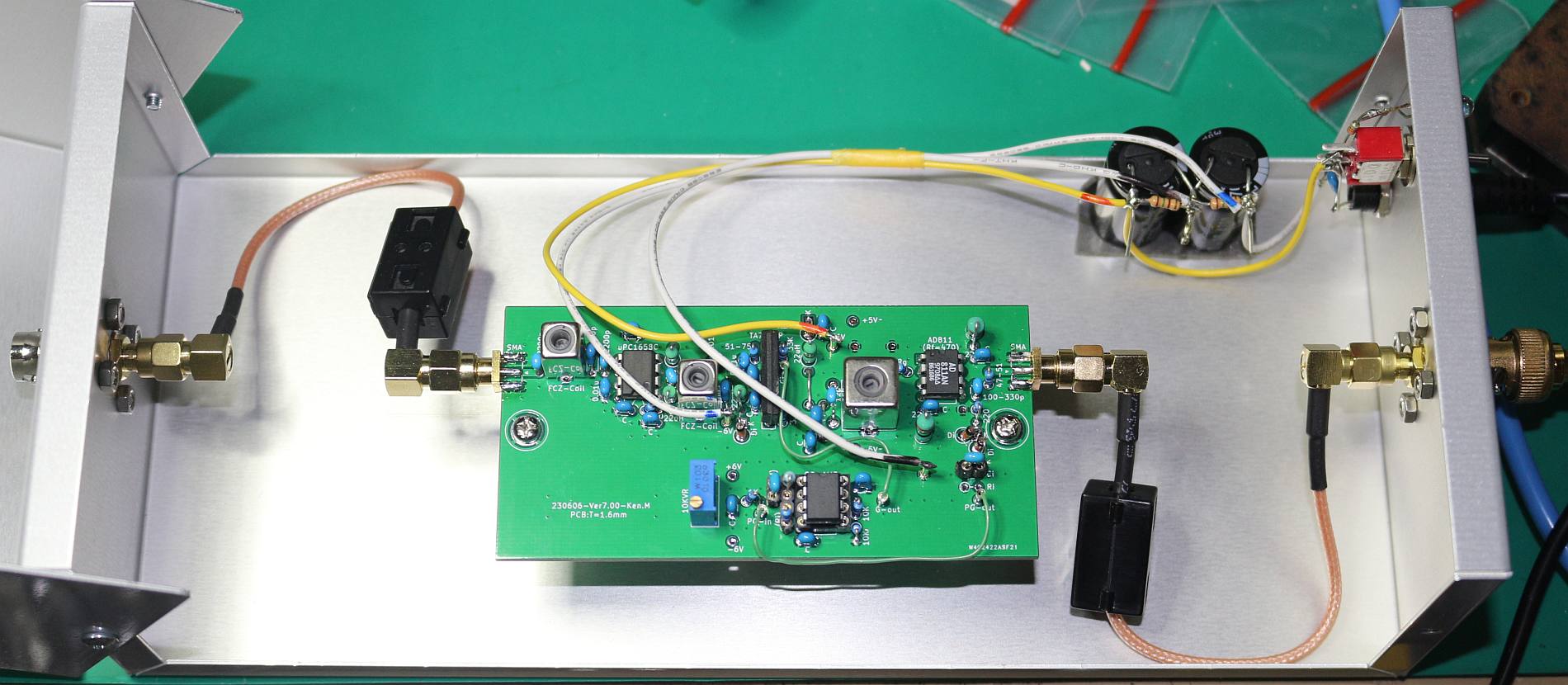
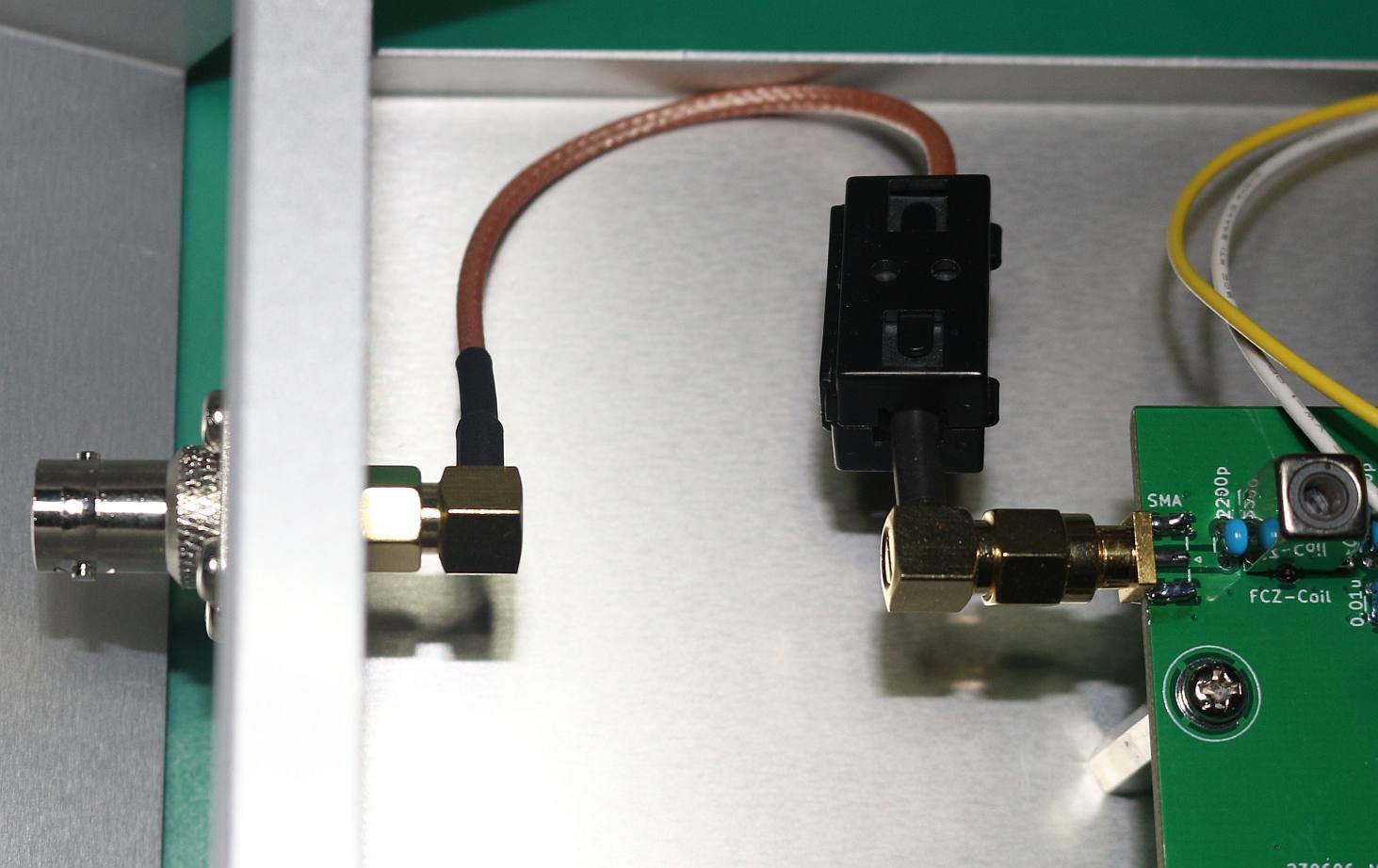 ���J�����V�r�A�Ȃ̂ŁA�R�l�N�^���u���ŕt���Ă���A�h�����Ō��J���Ƃ����`
�P�[�u���̎����]��ǂ��Ȃ��̂ł��邪�A�Ƃ肠�����A���͊������Ȃ������B
�����ŁA3.5D-SFA�P�[�u����m�̐�Ƀt�H�gDi��t���Č����B
�ŏ����������Ă������A�^�[�~�i���̊ɂ݂�����A���S���̕��ʂ̃t�H�gDi�̃A�m�[�h�ɐG�ꂽ�r�[�A�傫�����U���āA�ꎞ�~�܂�Ȃ��Ȃ����B
SFA�P�[�u���̗��[�Ƀp�b�`���R�A������Ɣ����͂���̂ŁA������̔��˂̐ςݏd�˂̑������ʁB�ƌ������Ƃ̂悤�ŁA�p�b�`���R�A�ł�����x���U���Ȃ��悤�ɂ͏o���邪�c�A�A
�����ŁA�O�̍d�������P�[�u���ڑ��łǂ�����������������A���S���̂ɐG�����Ƃ�����̒��x�͔�r�I���\�����߂ȐM�����������āA�ł����āA��𗣂��Ƃ����Ɏ~�܂����B
�Ƃ������ƂŁA�����BNC�ւ̕ϊ��R�l�N�^�̒��p�̃P�[�u���̎���ǂ�����Ζ�薳���������ƌ������Ƃ����������p�Ȋ����ł���B
�������A
�����p�l���Ɍq�������ϊ��R�l�N�^�ցA10cm�ȉ��Ŋ����i���A�I�[�_�[���C�h�̍����P�[�u�����K�v�ƂȂ����B
�������A�ׂ߂��ǂ��A���p�R�l�N�^�ȑ����B
�P�[�u���R�l�N�^���j�b�g��VSWR�l���āA�R�l�N�^�̗v�f�����\�傫���C������̂����B
(Voltage Standing Wave Ratio�FVSWR=1.15�Ƃ�1.20�ȉ��Ƃ����̂́A�ꉞ�P�[�u���݂̂̐��\�\�L���B)
�������AVSWR���������ƁA�t�˂�����A�p�b�`���R�A�������B�Ƃ����̂͒��ړI�ł͂Ȃ��悤���B
�����A�O�O���Ă݂āA��͂�A�u��ݔg�ɂ���ē`�����H���d�g����A���e�i�ɂȂ�v�ƋL�q����Ă����B
�Ƃ������ƂŁA�R�A�̎g�p�́A���X���������Ȃ��̂ŁA��a�̍�ł�����Ɛ��@�����B
���d�m�C�Y�ȂNJ��m�C�Y����̐M�����x�ɂ��S/N���l����
�E�t�o�C�A�X�F�J�b�g�I�t���Ⴍ�{���I�ɂ����Ďg���v�̗̈�Ȃ�傫�Ȍ��ʂ�������B
�EPre-AMP�F���������łȂ��A�P�[�u���ւ̏o��Z�̃}�b�`���O�̈Ӗ�������B
�EZ�����F�t�H�gDi��P�[�u���B
�E�P�[�u���������FPE���U�d�̂�RG58��20m�ł͌��\�ȃ��X�ƂȂ邾�낤�B
�EAOM�h���C�o�[�̏o�͘R��͐��Ȃ̂Œ��ӁB
�����ɂ͍l�����Ă����������f�R�ǂ��ł��낤�B
�����A�����̃P�[�u����U���ɂ��ďo���ƁA���̌`�̃P�[�X�̕����ɂ����Ӗ��͔�������B
�E�P�[�X���[����o�����Ƃɂ���āA�O���̃P�[�u�����ڋ߂��Ȃ��B
�E�P�[�X�����������d���������W���Ă��Đ��삪���N�B
�Ƃ������x���B
�ō����ȃZ�~�t���L�V�u���P�[�u�����g���Ȃ�A
�O�̃^�C�v�̃P�[�X���K�����ȁH
�����A���t���o���Ƃ̐�ւ������₷���Ƃ������Ƃ��Ⴂ���ȁH
���Ɛ����ɑ����Ē����łނ���Ō����B
���{�̂���O���Đڑ����Ȃ��Əo���Ȃ��B
���J�����V�r�A�Ȃ̂ŁA�R�l�N�^���u���ŕt���Ă���A�h�����Ō��J���Ƃ����`
�P�[�u���̎����]��ǂ��Ȃ��̂ł��邪�A�Ƃ肠�����A���͊������Ȃ������B
�����ŁA3.5D-SFA�P�[�u����m�̐�Ƀt�H�gDi��t���Č����B
�ŏ����������Ă������A�^�[�~�i���̊ɂ݂�����A���S���̕��ʂ̃t�H�gDi�̃A�m�[�h�ɐG�ꂽ�r�[�A�傫�����U���āA�ꎞ�~�܂�Ȃ��Ȃ����B
SFA�P�[�u���̗��[�Ƀp�b�`���R�A������Ɣ����͂���̂ŁA������̔��˂̐ςݏd�˂̑������ʁB�ƌ������Ƃ̂悤�ŁA�p�b�`���R�A�ł�����x���U���Ȃ��悤�ɂ͏o���邪�c�A�A
�����ŁA�O�̍d�������P�[�u���ڑ��łǂ�����������������A���S���̂ɐG�����Ƃ�����̒��x�͔�r�I���\�����߂ȐM�����������āA�ł����āA��𗣂��Ƃ����Ɏ~�܂����B
�Ƃ������ƂŁA�����BNC�ւ̕ϊ��R�l�N�^�̒��p�̃P�[�u���̎���ǂ�����Ζ�薳���������ƌ������Ƃ����������p�Ȋ����ł���B
�������A
�����p�l���Ɍq�������ϊ��R�l�N�^�ցA10cm�ȉ��Ŋ����i���A�I�[�_�[���C�h�̍����P�[�u�����K�v�ƂȂ����B
�������A�ׂ߂��ǂ��A���p�R�l�N�^�ȑ����B
�P�[�u���R�l�N�^���j�b�g��VSWR�l���āA�R�l�N�^�̗v�f�����\�傫���C������̂����B
(Voltage Standing Wave Ratio�FVSWR=1.15�Ƃ�1.20�ȉ��Ƃ����̂́A�ꉞ�P�[�u���݂̂̐��\�\�L���B)
�������AVSWR���������ƁA�t�˂�����A�p�b�`���R�A�������B�Ƃ����̂͒��ړI�ł͂Ȃ��悤���B
�����A�O�O���Ă݂āA��͂�A�u��ݔg�ɂ���ē`�����H���d�g����A���e�i�ɂȂ�v�ƋL�q����Ă����B
�Ƃ������ƂŁA�R�A�̎g�p�́A���X���������Ȃ��̂ŁA��a�̍�ł�����Ɛ��@�����B
���d�m�C�Y�ȂNJ��m�C�Y����̐M�����x�ɂ��S/N���l����
�E�t�o�C�A�X�F�J�b�g�I�t���Ⴍ�{���I�ɂ����Ďg���v�̗̈�Ȃ�傫�Ȍ��ʂ�������B
�EPre-AMP�F���������łȂ��A�P�[�u���ւ̏o��Z�̃}�b�`���O�̈Ӗ�������B
�EZ�����F�t�H�gDi��P�[�u���B
�E�P�[�u���������FPE���U�d�̂�RG58��20m�ł͌��\�ȃ��X�ƂȂ邾�낤�B
�EAOM�h���C�o�[�̏o�͘R��͐��Ȃ̂Œ��ӁB
�����ɂ͍l�����Ă����������f�R�ǂ��ł��낤�B
�����A�����̃P�[�u����U���ɂ��ďo���ƁA���̌`�̃P�[�X�̕����ɂ����Ӗ��͔�������B
�E�P�[�X���[����o�����Ƃɂ���āA�O���̃P�[�u�����ڋ߂��Ȃ��B
�E�P�[�X�����������d���������W���Ă��Đ��삪���N�B
�Ƃ������x���B
�ō����ȃZ�~�t���L�V�u���P�[�u�����g���Ȃ�A
�O�̃^�C�v�̃P�[�X���K�����ȁH
�����A���t���o���Ƃ̐�ւ������₷���Ƃ������Ƃ��Ⴂ���ȁH
���Ɛ����ɑ����Ē����łނ���Ō����B
���{�̂���O���Đڑ����Ȃ��Əo���Ȃ��B
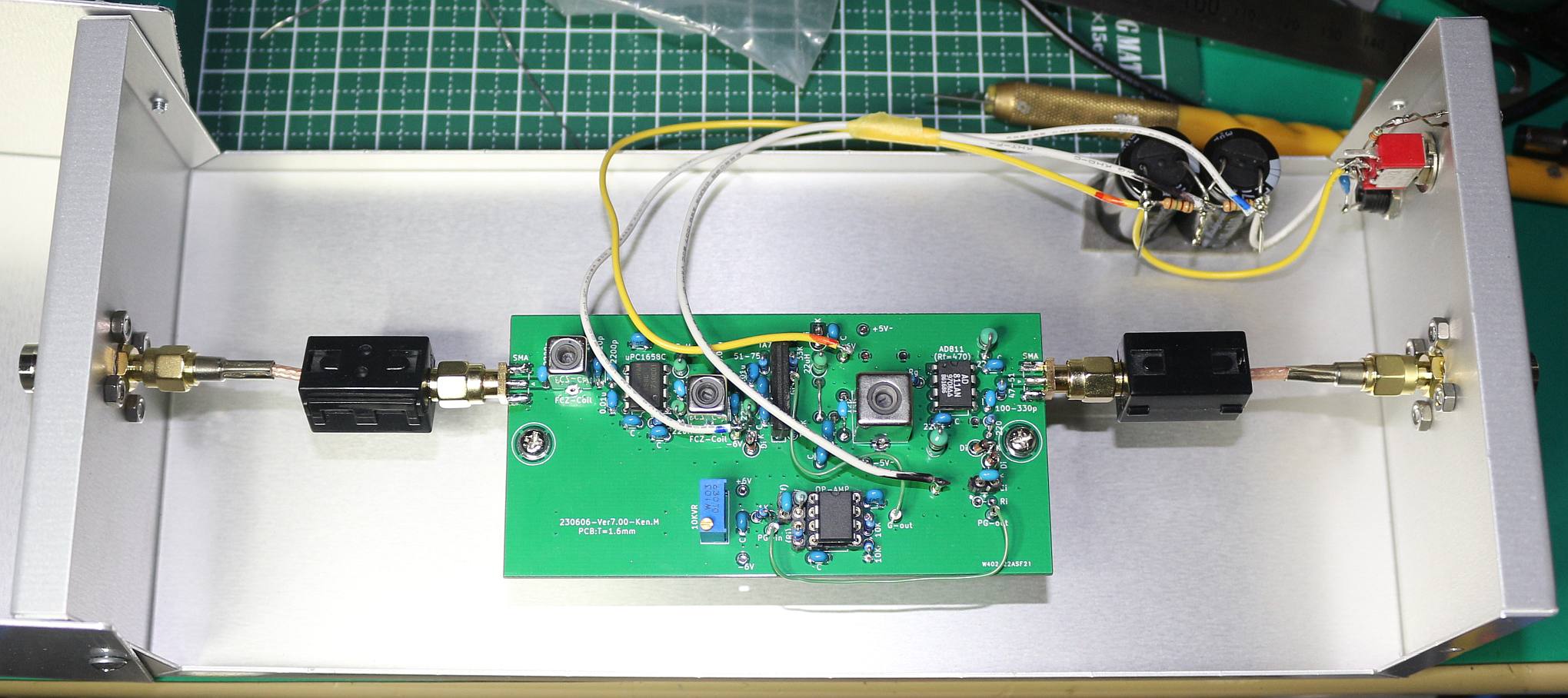 RG316�͗U�d�̂�PE�ŁA�R�l�N�^�͓���ʼn����璆�S���̂��n���_�t������B
����āA�ʏ�̂��U�d�̂̂Ȃ��s�A�������͑��߂ɂ���̂����A�܂��A���p�R�l�N�^�[���̓}�V�����ȁ[�Ǝv�������B
����ɂ��Ă��A�t�F���[�����A��������Ƃ��Ă���BRG316�Ή��R�l�N�^���F�X���肻��������A���@������Ȃ��ƌ������ƂȂ̂��ȁH
PTFE�^�C�v�̃P�[�u���ŁA�ʏ�̃X�g���[�g�R�l�N�^�ł����킵�Ă݂悤�Ƃ͎v�����ǁA�z���ɁA���Ԃ�������B
�����̌덷��1mm���x�ł����\�L�c�C�̂ŁA�z���g�͑g�݂Ȃ���l�q�����������ǂ������B
�ŁA�v�����ʂƂ��ẮA�A
�O��Ɠ����悤�ɁA3.5D-SFA�P�[�u����m�̐�Ƀt�H�gDi�����āA
�M�����C���ɐG��Ă݂�ƁA�ĊO���肵�Ă邵�A���U�͋N���������ɂȂ��B�����ɉ��P�����Ƃ����ėǂ����낤�B
���M��������Ȃ肾�Ǝv�����ǁA�������ǂ���ԂƂ͎v���Ȃ��̂ŁA�P�[�u���ƃR�l�N�^�̉��P�Ɋ��҂��ȁB
RG316�͗U�d�̂�PE�ŁA�R�l�N�^�͓���ʼn����璆�S���̂��n���_�t������B
����āA�ʏ�̂��U�d�̂̂Ȃ��s�A�������͑��߂ɂ���̂����A�܂��A���p�R�l�N�^�[���̓}�V�����ȁ[�Ǝv�������B
����ɂ��Ă��A�t�F���[�����A��������Ƃ��Ă���BRG316�Ή��R�l�N�^���F�X���肻��������A���@������Ȃ��ƌ������ƂȂ̂��ȁH
PTFE�^�C�v�̃P�[�u���ŁA�ʏ�̃X�g���[�g�R�l�N�^�ł����킵�Ă݂悤�Ƃ͎v�����ǁA�z���ɁA���Ԃ�������B
�����̌덷��1mm���x�ł����\�L�c�C�̂ŁA�z���g�͑g�݂Ȃ���l�q�����������ǂ������B
�ŁA�v�����ʂƂ��ẮA�A
�O��Ɠ����悤�ɁA3.5D-SFA�P�[�u����m�̐�Ƀt�H�gDi�����āA
�M�����C���ɐG��Ă݂�ƁA�ĊO���肵�Ă邵�A���U�͋N���������ɂȂ��B�����ɉ��P�����Ƃ����ėǂ����낤�B
���M��������Ȃ肾�Ǝv�����ǁA�������ǂ���ԂƂ͎v���Ȃ��̂ŁA�P�[�u���ƃR�l�N�^�̉��P�Ɋ��҂��ȁB
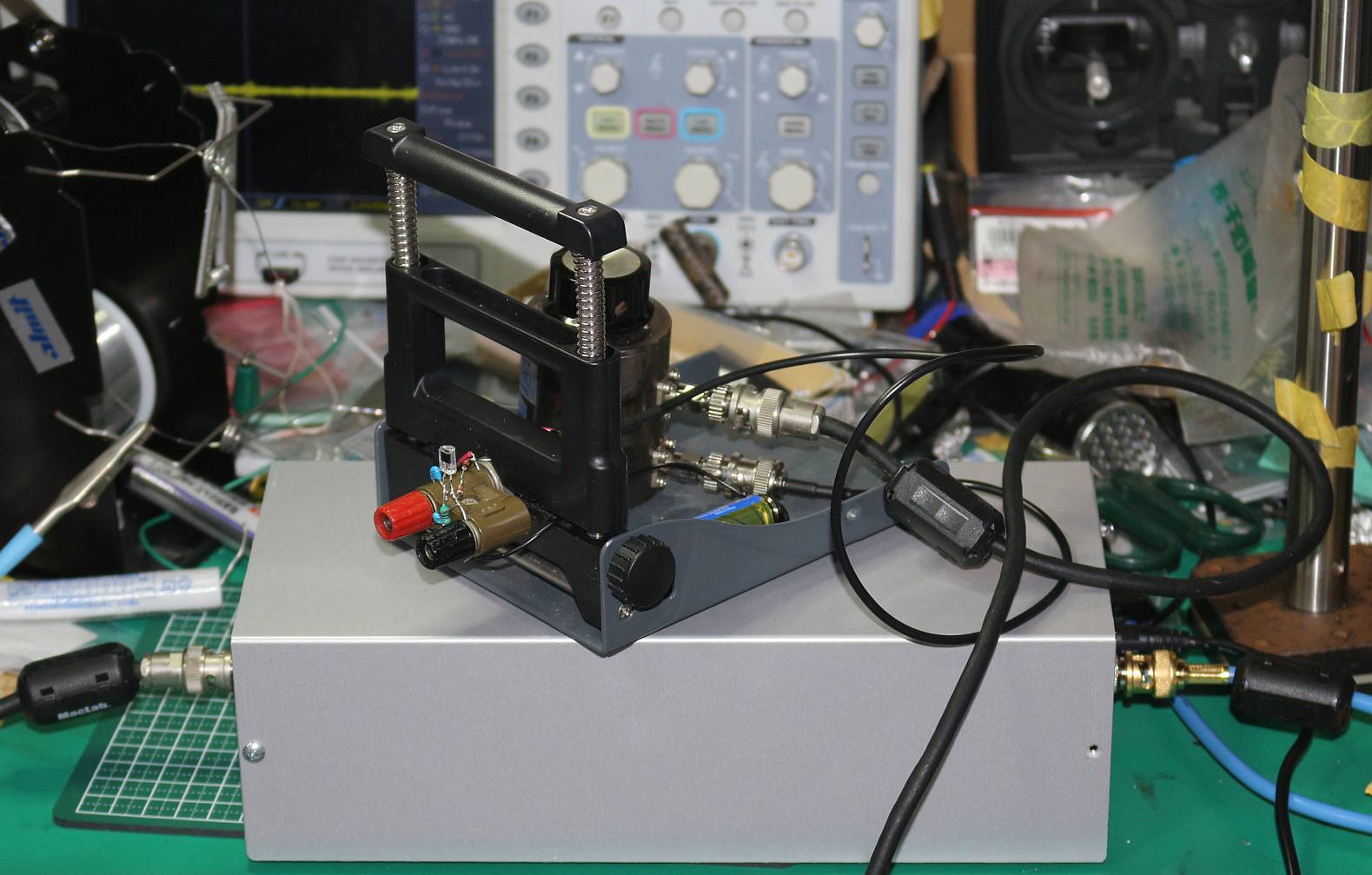 VNA�ɂāA���̉�H�̓��͂̃C���s�[�_���X�𑪂�����AZ=103���ƁA�ُ�ɍ����l���o���B
Z�̍������ւ̐M���͋������˂���̂Ŗ��B
Z�������Ƃ��납��Ⴂ�Ƃ���֍s���ꍇ�́A�U�����ɂ��J���[�ɋ߂��Ȃ�̂Ŕ��˂̖��͂��܂�N����Ȃ��B
���͂�Z�ɏd�v�ȕ����́AFCZ�R�C���̕s���a�ȃo�����X�ł���Ǝv���A�����M���Č���B
FCZ�R�C���́A�������Ɖ������Ƃ��œ�x�s�[�N���o���邪�A����́A�������̑Ώ����ǂ��悤�ŁA
������������A��������ŕω��ł�����E�ɋ߂������̂����m��Ȃ����A�ǂ���������Ă��瓚�����o���������ǂ��݂������BFCZ�R�C�����g������H��������ł̒��ӓ_�ł�����B
�����A�s�[�N�œ���Z��50�����x�Ɉ��肵���B(��2�A3��FCZ�R�C���́A�����������ǂ����ʂ������B)
������ւ�̖��̔�����VNA�͔��ɗL���������B
�ŁA�R�A�����\�o����������Ԃł̃o�����X�Ȃ̂ŁAC�����������������������A�K���Ǝv����7�`8pF����ɓ���Â炩�����̂ƁA�g���}�[�ł͑�����������Ƃ������f����A
�o���������܂܂̏�Ԃŗǂ��Ƃ��邪�A�U���Ȃǂœ����Ȃ��悤�A�u�p���t�B�����E�v�ŌŒ肷��B
�NjL��
�V���b�v�̃y�[�W�̃_�C�X�T�C�Y�̕\�L���Ԉ���Ă����B
RG316�̃_�C�X��3.25mm�̂悤�ŁA2.70mm�̂�����_�C�X���Ή��Ŏg����悤�Ȃ��Ƃ�������Ă����̂Łc�B�ʂ̃_�C�X�݂̂��Ǝv���Ă݂����A�P�̂ł͂Ȃ��̂ŁA�H��Ɣ��������ɁB
�A���ɁA�܂��A10���ʂ����邱�ƂɂȂ�B
0.55mm�����Ԃ������ƂɂȂ����B
������������A���ꂪ�A�����̕s�ǂɏ����e�����Ă��邩������Ȃ��B
���x�́A�P�[�u�����R�l�N�^���}�V�ȃ��m�ɂ��悤�Ǝv���B
----
���ȃ��m�ł��B
������ƒl���オ�����̂ƁA�M�����̂��肻���ȃV���b�v��10000�~�ōw���B
���^��M40�ł��B
�J�[�g���b�W�ɓ��ꂽ�X�|���W�e���������̔r䰃A�N�V�������y���߂܂��B
��C����������X�v�����O�̓{���g�̃v�b�V���R�b�N�ň��k���s���܂��B
VNA�ɂāA���̉�H�̓��͂̃C���s�[�_���X�𑪂�����AZ=103���ƁA�ُ�ɍ����l���o���B
Z�̍������ւ̐M���͋������˂���̂Ŗ��B
Z�������Ƃ��납��Ⴂ�Ƃ���֍s���ꍇ�́A�U�����ɂ��J���[�ɋ߂��Ȃ�̂Ŕ��˂̖��͂��܂�N����Ȃ��B
���͂�Z�ɏd�v�ȕ����́AFCZ�R�C���̕s���a�ȃo�����X�ł���Ǝv���A�����M���Č���B
FCZ�R�C���́A�������Ɖ������Ƃ��œ�x�s�[�N���o���邪�A����́A�������̑Ώ����ǂ��悤�ŁA
������������A��������ŕω��ł�����E�ɋ߂������̂����m��Ȃ����A�ǂ���������Ă��瓚�����o���������ǂ��݂������BFCZ�R�C�����g������H��������ł̒��ӓ_�ł�����B
�����A�s�[�N�œ���Z��50�����x�Ɉ��肵���B(��2�A3��FCZ�R�C���́A�����������ǂ����ʂ������B)
������ւ�̖��̔�����VNA�͔��ɗL���������B
�ŁA�R�A�����\�o����������Ԃł̃o�����X�Ȃ̂ŁAC�����������������������A�K���Ǝv����7�`8pF����ɓ���Â炩�����̂ƁA�g���}�[�ł͑�����������Ƃ������f����A
�o���������܂܂̏�Ԃŗǂ��Ƃ��邪�A�U���Ȃǂœ����Ȃ��悤�A�u�p���t�B�����E�v�ŌŒ肷��B
�NjL��
�V���b�v�̃y�[�W�̃_�C�X�T�C�Y�̕\�L���Ԉ���Ă����B
RG316�̃_�C�X��3.25mm�̂悤�ŁA2.70mm�̂�����_�C�X���Ή��Ŏg����悤�Ȃ��Ƃ�������Ă����̂Łc�B�ʂ̃_�C�X�݂̂��Ǝv���Ă݂����A�P�̂ł͂Ȃ��̂ŁA�H��Ɣ��������ɁB
�A���ɁA�܂��A10���ʂ����邱�ƂɂȂ�B
0.55mm�����Ԃ������ƂɂȂ����B
������������A���ꂪ�A�����̕s�ǂɏ����e�����Ă��邩������Ȃ��B
���x�́A�P�[�u�����R�l�N�^���}�V�ȃ��m�ɂ��悤�Ǝv���B
----
���ȃ��m�ł��B
������ƒl���オ�����̂ƁA�M�����̂��肻���ȃV���b�v��10000�~�ōw���B
���^��M40�ł��B
�J�[�g���b�W�ɓ��ꂽ�X�|���W�e���������̔r䰃A�N�V�������y���߂܂��B
��C����������X�v�����O�̓{���g�̃v�b�V���R�b�N�ň��k���s���܂��B

 20mm�s�J�e�B�j�[���[���}�E���g�𑽐��������Ă܂��́A
�X�R�[�v�ƃo�C�|�b�h�͏����ł͂Ȃ��ʂŎg���Ă������i��t���܂����ł��B
�t����ƌ��\�d���Ȃ�܂��B
�����͈����p�[�c�������悤�ł��B
��_��
�{���g�̃K�^�ƃX�g�b�p�[�̃��o�[�̖߂肪�ア�B���e�[�v�ŌŒ�B
�}�K�W�������Ȃ苭���������܂Ȃ��ƁA�}�K�W���X�g�b�p�[��������Ȃ��B����邩�H
�g���K�v�������X�d���B
�X�|���W�e�̉������݊����L�c�C���ȂǁB�V���R�[���X�v���[�𔖂��h��ƃC�C�����ɂȂ�܂����B
��ꂽ������e�f�ނ�ւ��܂��B
�����ŕt���Ă���X�R�[�v�̏o���͂��Ȃ�I�}�P���x���ł��B
���A���{����t�����`�A�A
----
���Ƃ́A�U���̔����ȗh�炬���C�ɂȂ�B�ʑ��̗h�炬������Ƃ���ƁA�t�B���^�[�ŃJ�b�g�ł��邩���l�b�N���B
�ʑ��̗h�炬����������Ƃ���ƁA�t�B���^�[�ŃJ�b�g�ł��邩���l�b�N���B
���̑��x��AGC�̃R���g���[�����ꡂ��ɑ������Ƃ͊m���ł���B
����āA���ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ͎v�����A���_�q����̖��ł͂���B
�܂��͍����g�`���[�N�p�C���_�N�^�ƕ����p��C�ł́A40�`100KHz�Ƃ������U���g���ƂȂ�̂ŁA����Q�͒�߂ɕۂ��������A���d�m�C�Y�̉e���ȊO�͓x�O���ł���B
�I�i�ȊO�͍ő��10�`20mA�������H��Ȃ��̂ŁA���܂ł̃R�C����OK���Ǝv����B
�����A�I�i��AD811�ւ̃`���[�N�́A���ׂɔ�ׂāA���ESR�����������m��Ȃ��̂ŁA��3�`4mm��4.7�`10��H���x�ɕύX�������Ǝv�����B
�����́A�I�i�̓m�C�Y����̂ł͂Ȃ��o�������������IC���h�삳��Ă�A�I�i��L�͖����Ă��ǂ������m��Ȃ��B
AD811��5V�쓮�Ł}2.9V�U���Ȃ̂ŏo�͂�47�����q���Ń}�b�`���O�����Ă��邱�Ƃ���A
�d����L���Ȃ����́A���Ȃ茵������Ԃł���B
�傫�����ȃt�@�N�^�[�̓d���p�̕����R���f���T�[�����A�ꗥ��50V��1��F���g�p���Ă���B
�σZ���͑傫�Ȓl���Ɛϑw�\����ESL���傫���Ȃ邵�A�ψ���������Ƙc�݂��o���肷��X�������B
�Ȃ̂ŁA50V��0.01��F�̃`�b�v�𗠕t�����邱�Ƃœ��������P����e�X�g���o����A�Ƃ͎v���B
�ӂ���͌��\�����̂ŁAL�̖��������Ă��邩���B
����ŁA�h�炬�������Ȃ���A
�t�B���^�[���A�Q�C���𗎂Ƃ����H�ł��邪�A���p��̖��͖��������ɂ͎v���B
�����ł�����ƒ�߂�|Z|�l�ɂ�FCZ�R�C���̃R�A���z�b�g�{���h�ŌŒ肷�邱�Ƃɂ����B�������ABNC������ł�63�����x���o�āA3.5D-SFA��m���q���ƍ��x��36���ƂȂ����B
20mm�s�J�e�B�j�[���[���}�E���g�𑽐��������Ă܂��́A
�X�R�[�v�ƃo�C�|�b�h�͏����ł͂Ȃ��ʂŎg���Ă������i��t���܂����ł��B
�t����ƌ��\�d���Ȃ�܂��B
�����͈����p�[�c�������悤�ł��B
��_��
�{���g�̃K�^�ƃX�g�b�p�[�̃��o�[�̖߂肪�ア�B���e�[�v�ŌŒ�B
�}�K�W�������Ȃ苭���������܂Ȃ��ƁA�}�K�W���X�g�b�p�[��������Ȃ��B����邩�H
�g���K�v�������X�d���B
�X�|���W�e�̉������݊����L�c�C���ȂǁB�V���R�[���X�v���[�𔖂��h��ƃC�C�����ɂȂ�܂����B
��ꂽ������e�f�ނ�ւ��܂��B
�����ŕt���Ă���X�R�[�v�̏o���͂��Ȃ�I�}�P���x���ł��B
���A���{����t�����`�A�A
----
���Ƃ́A�U���̔����ȗh�炬���C�ɂȂ�B�ʑ��̗h�炬������Ƃ���ƁA�t�B���^�[�ŃJ�b�g�ł��邩���l�b�N���B
�ʑ��̗h�炬����������Ƃ���ƁA�t�B���^�[�ŃJ�b�g�ł��邩���l�b�N���B
���̑��x��AGC�̃R���g���[�����ꡂ��ɑ������Ƃ͊m���ł���B
����āA���ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ͎v�����A���_�q����̖��ł͂���B
�܂��͍����g�`���[�N�p�C���_�N�^�ƕ����p��C�ł́A40�`100KHz�Ƃ������U���g���ƂȂ�̂ŁA����Q�͒�߂ɕۂ��������A���d�m�C�Y�̉e���ȊO�͓x�O���ł���B
�I�i�ȊO�͍ő��10�`20mA�������H��Ȃ��̂ŁA���܂ł̃R�C����OK���Ǝv����B
�����A�I�i��AD811�ւ̃`���[�N�́A���ׂɔ�ׂāA���ESR�����������m��Ȃ��̂ŁA��3�`4mm��4.7�`10��H���x�ɕύX�������Ǝv�����B
�����́A�I�i�̓m�C�Y����̂ł͂Ȃ��o�������������IC���h�삳��Ă�A�I�i��L�͖����Ă��ǂ������m��Ȃ��B
AD811��5V�쓮�Ł}2.9V�U���Ȃ̂ŏo�͂�47�����q���Ń}�b�`���O�����Ă��邱�Ƃ���A
�d����L���Ȃ����́A���Ȃ茵������Ԃł���B
�傫�����ȃt�@�N�^�[�̓d���p�̕����R���f���T�[�����A�ꗥ��50V��1��F���g�p���Ă���B
�σZ���͑傫�Ȓl���Ɛϑw�\����ESL���傫���Ȃ邵�A�ψ���������Ƙc�݂��o���肷��X�������B
�Ȃ̂ŁA50V��0.01��F�̃`�b�v�𗠕t�����邱�Ƃœ��������P����e�X�g���o����A�Ƃ͎v���B
�ӂ���͌��\�����̂ŁAL�̖��������Ă��邩���B
����ŁA�h�炬�������Ȃ���A
�t�B���^�[���A�Q�C���𗎂Ƃ����H�ł��邪�A���p��̖��͖��������ɂ͎v���B
�����ł�����ƒ�߂�|Z|�l�ɂ�FCZ�R�C���̃R�A���z�b�g�{���h�ŌŒ肷�邱�Ƃɂ����B�������ABNC������ł�63�����x���o�āA3.5D-SFA��m���q���ƍ��x��36���ƂȂ����B
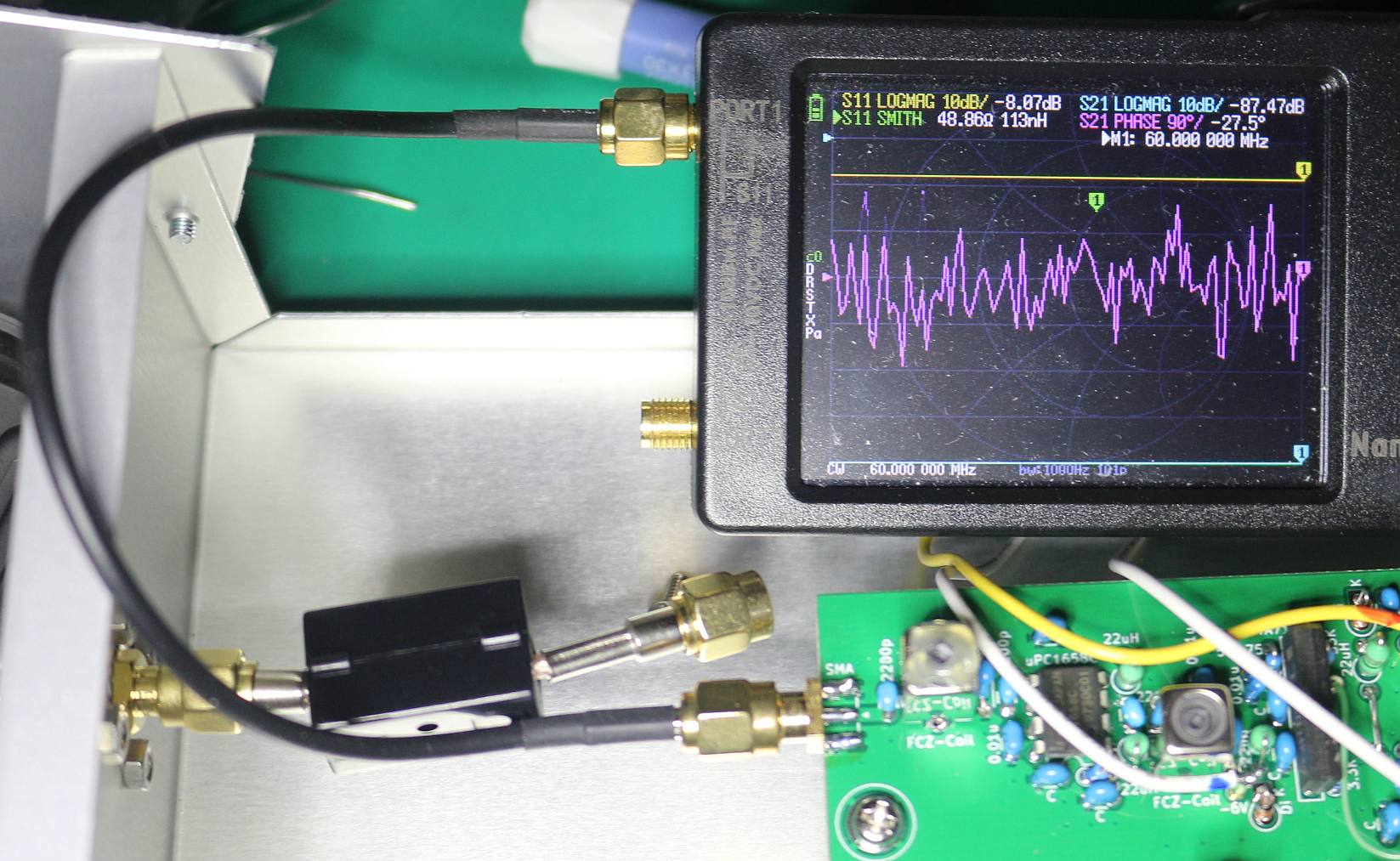 ����́A��ݔg�̃��x�����ʒu�ɂ���ĈႤ�Ƃ��������Ǝv���B
�܂�A�x�N�g��������Ă��邪|Z|�����킹�Ă���̂ŁA�A�����Ō��Ă�������L�l�����������B
���̌����́AFCZ�R�C�����U�n��L��C�̃o�����X�����m��Ȃ��B
�����A�����ł���ȂɃV�r�A�ɍ��킹�Ă��邱�Ƃ͌������Ƃ��Ȃ��悤�ȋC�����邩��A
FCZ�R�C���������ł���͈͂ŁA��̐U�����傫���Ȃ�Ƃ�����x�Ƃ��������ōς܂��Ă���̂ł͂Ȃ����H�Ƃ��B
�܂��A���̒����ł���������h�炬���������悤�Ȋ���������B
�I�i�̓d���ւ�L�̔r���A�����pC�̋����A�M���P�[�u���A�R�l�N�^�̍������ƃt�F���[���̒��ߕt���K���������l���Ă������A
�Ƃ肠�����A�����̓\�������邾�낤���ǁA���̂悤�Ȋ��̖��ɂ��ϓ_�ŕ]�����������ǂ���������Ȃ��B
�Ƃɂ����A���܂��������Ȃ��ƁA��ݔg�̖�肪����Ǝv���邱�Ƃ���A�p�b�`���R�A�Ȃǂ̑Ώ��ň��萫���ς�����肷�邩���m��Ȃ��B
20230701
|Z|��R(Real)�Ō��Ă���Im(���F���A�N�^���X)�������d�����Ă��Ȃ������̂����A���A�N�^���X��L���������ɑ��݂��Ă���B
�Ƃ������Ƃ́A���炭�A�Œ�[�Ŕ��ː������傫���Ȃ�������̐����ł��邩��A���Ȃ���ł���Ɣ��f�����B���A
SWR�Ƃ���������������邩�炱����Ȃ�ׂ�1�ɋ߂Â���Ƃ�͂�AR��Im�������傫���Ȃ�B
�����ŁA�Q�C���̃s�[�N�͑傫���ς��Ȃ��悤�����A���U�X���ɑ���Ⴂ���傫�������m��Ȃ��Ǝv���Ă���B
(��ݐU���A���U�X�����傫����A�g�`�͑傫���o��v�f�����邾�낤���猩�����̃s�[�N�����ł͕]���ł��Ȃ��B)
�����ŁA�܂��́A��������H�ŃP�[�u�����t����Ԃɂ�FCZ�R�C���̓����p��C�������邱�Ƃ��珉�߂Č���B
���ꂪ������x��肭�s���Ζ{��H�ɍ̗p����B
FCZ�R�C�������p�R���f���T�[��8pF�֕ύX�B
����́A��ݔg�̃��x�����ʒu�ɂ���ĈႤ�Ƃ��������Ǝv���B
�܂�A�x�N�g��������Ă��邪|Z|�����킹�Ă���̂ŁA�A�����Ō��Ă�������L�l�����������B
���̌����́AFCZ�R�C�����U�n��L��C�̃o�����X�����m��Ȃ��B
�����A�����ł���ȂɃV�r�A�ɍ��킹�Ă��邱�Ƃ͌������Ƃ��Ȃ��悤�ȋC�����邩��A
FCZ�R�C���������ł���͈͂ŁA��̐U�����傫���Ȃ�Ƃ�����x�Ƃ��������ōς܂��Ă���̂ł͂Ȃ����H�Ƃ��B
�܂��A���̒����ł���������h�炬���������悤�Ȋ���������B
�I�i�̓d���ւ�L�̔r���A�����pC�̋����A�M���P�[�u���A�R�l�N�^�̍������ƃt�F���[���̒��ߕt���K���������l���Ă������A
�Ƃ肠�����A�����̓\�������邾�낤���ǁA���̂悤�Ȋ��̖��ɂ��ϓ_�ŕ]�����������ǂ���������Ȃ��B
�Ƃɂ����A���܂��������Ȃ��ƁA��ݔg�̖�肪����Ǝv���邱�Ƃ���A�p�b�`���R�A�Ȃǂ̑Ώ��ň��萫���ς�����肷�邩���m��Ȃ��B
20230701
|Z|��R(Real)�Ō��Ă���Im(���F���A�N�^���X)�������d�����Ă��Ȃ������̂����A���A�N�^���X��L���������ɑ��݂��Ă���B
�Ƃ������Ƃ́A���炭�A�Œ�[�Ŕ��ː������傫���Ȃ�������̐����ł��邩��A���Ȃ���ł���Ɣ��f�����B���A
SWR�Ƃ���������������邩�炱����Ȃ�ׂ�1�ɋ߂Â���Ƃ�͂�AR��Im�������傫���Ȃ�B
�����ŁA�Q�C���̃s�[�N�͑傫���ς��Ȃ��悤�����A���U�X���ɑ���Ⴂ���傫�������m��Ȃ��Ǝv���Ă���B
(��ݐU���A���U�X�����傫����A�g�`�͑傫���o��v�f�����邾�낤���猩�����̃s�[�N�����ł͕]���ł��Ȃ��B)
�����ŁA�܂��́A��������H�ŃP�[�u�����t����Ԃɂ�FCZ�R�C���̓����p��C�������邱�Ƃ��珉�߂Č���B
���ꂪ������x��肭�s���Ζ{��H�ɍ̗p����B
FCZ�R�C�������p�R���f���T�[��8pF�֕ύX�B
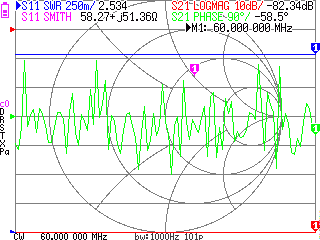 �s�[�N�U���ł��̏�ԁB�R�A�̏o������͔����������A
�܂�A���l�����܂��낵���Ȃ��B
������������悤�ɘM���Ă��A�Œ�SWR�����܂�Ⴍ�Ȃ炸�A������ƐU����������B
�s�[�N�U���ł��̏�ԁB�R�A�̏o������͔����������A
�܂�A���l�����܂��낵���Ȃ��B
������������悤�ɘM���Ă��A�Œ�SWR�����܂�Ⴍ�Ȃ炸�A������ƐU����������B
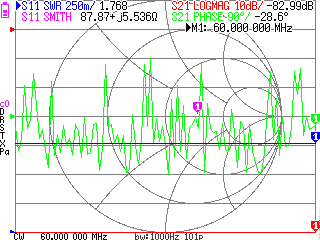 �����R���ł����̃s�[�N���o��\�����������悤���B��ݔg������R�����x�X�g�Ȃ̂����m��Ȃ����A
10pF�����R���傫���Ȃ�B
�ł����āA�R�A��˂����ނ��ƂŃR�A�̍�p�������Ȃ邪�A����������ƁA�������R�A�͐��\���^�₾����A�|���s���Ȃ��Ƃ�������邩������Ȃ��B
�R�A��˂�����Ńo�����X�������R=130���ʂƂȂ�A���Ȃ�q�h���B
10pF��8pF�����A���̍����x���ƁA������������C������B
���i�̕\�ł�60MHz��10pF�ƂȂ��Ă͂���B���IC�̗e�ʂȂǂ�C�v�f�������ꂽ���ʂ����Ȃ����̂����m��Ȃ���������Ƌɒ[�ȉe���Ɏv���Ă���B
�X�g���[�L���p�V�^���X�v�f�ł̋������́A���̌����������Ƃ͎v���̂ŁA����������pC��������Ƃ�͂�}�C�i�X�ʂ������Ȃ鎖�ɂȂ闝�R�ɂȂ蓾��B
C��10pF����ς����ASWR��Ⴍ�ނ荇�킹����@��T�銴�����ȁH�Ǝv���B
�������A����H�ɂ�SWR��������ƁA���U�Ɍq���邱�Ƃ����鎞������̂Ŏ�|�Ƌt�s���Ă��荬�����Ă���B
�����A�P�[�u����̐ڑ����ɂ�����P�[�X�o�C�P�[�X������悤������d�����Ȃ��A�[���͍l���Ă������͏o�Ȃ��悤�ȋC�����Ă���B
�o�����X������̂ɁA
C����������������ƁA�P����L�����������Ȃ���Ă̂��e������̂����B
20230707
���U���̂ӂ���ւ̑Ώ��ł��遄
�܂��́A�d���d���M���M���œd�����H���I�i��AD811�̃`���[�N22��H���W�����p���ŃV���[�g����B
���ɁA0.01��F�ɂ��Ă͑傫�߂̑ψ�50V��2012�T�C�Y�ȃ`�b�v�R���f���T�[�ɂāA����ȏ�ɂȂ������g�p�X�����ɂ���B
���ʂ�����ƁA���Ȃ蔭�U�X���ɂȂ�A�U�����s����ɁB
�����ŁA�I�i��22��H�̃W�����p�������������Ƃ�����肵���B
�܂�A�d���̃`���[�N�́A���Ȃ�K�v�ȗv�f�ł������B
�`���[�N��DC��R������ǂ����邽�ߏI�i�̂݃�3mm�ł͂Ȃ���4mm�ɂ������A������Ƒ���L���ă�5mm�ɂ��������ǂ��Ǝv�����ʂ��B
�����́A�ʏ�̓d���A��OP-AMP�ł̃M���M���́}6V���d�ɂ��邩�H�Ƃ��l�������A�p�^�[����ς��˂Ȃ�Ȃ����A�ϋv���ɖ�肪�o�邩���m��Ȃ��̂Łc�A
�X�ɁA��h���b�v�̉σ��M�����[�^���g��0.5V������11.5V���x����}�d���ɕ������Ă��ǂ����������A��������ɓd���G������̂��S�O����B
20230708
-------------------------------------------------------------------------------------------------------�|�|�|�|�|
��VNA��AGC-AMP�̓��͂��ŒZ�����Őڍ����Ĕ��˂̗l�q�Ɛ��������遄
�ŒZ�Őڍ��ł���ϊ��R�l�N�^���͂��āA���t���đ���ƌ������ƂɂȂ����B
�����R���ł����̃s�[�N���o��\�����������悤���B��ݔg������R�����x�X�g�Ȃ̂����m��Ȃ����A
10pF�����R���傫���Ȃ�B
�ł����āA�R�A��˂����ނ��ƂŃR�A�̍�p�������Ȃ邪�A����������ƁA�������R�A�͐��\���^�₾����A�|���s���Ȃ��Ƃ�������邩������Ȃ��B
�R�A��˂�����Ńo�����X�������R=130���ʂƂȂ�A���Ȃ�q�h���B
10pF��8pF�����A���̍����x���ƁA������������C������B
���i�̕\�ł�60MHz��10pF�ƂȂ��Ă͂���B���IC�̗e�ʂȂǂ�C�v�f�������ꂽ���ʂ����Ȃ����̂����m��Ȃ���������Ƌɒ[�ȉe���Ɏv���Ă���B
�X�g���[�L���p�V�^���X�v�f�ł̋������́A���̌����������Ƃ͎v���̂ŁA����������pC��������Ƃ�͂�}�C�i�X�ʂ������Ȃ鎖�ɂȂ闝�R�ɂȂ蓾��B
C��10pF����ς����ASWR��Ⴍ�ނ荇�킹����@��T�銴�����ȁH�Ǝv���B
�������A����H�ɂ�SWR��������ƁA���U�Ɍq���邱�Ƃ����鎞������̂Ŏ�|�Ƌt�s���Ă��荬�����Ă���B
�����A�P�[�u����̐ڑ����ɂ�����P�[�X�o�C�P�[�X������悤������d�����Ȃ��A�[���͍l���Ă������͏o�Ȃ��悤�ȋC�����Ă���B
�o�����X������̂ɁA
C����������������ƁA�P����L�����������Ȃ���Ă̂��e������̂����B
20230707
���U���̂ӂ���ւ̑Ώ��ł��遄
�܂��́A�d���d���M���M���œd�����H���I�i��AD811�̃`���[�N22��H���W�����p���ŃV���[�g����B
���ɁA0.01��F�ɂ��Ă͑傫�߂̑ψ�50V��2012�T�C�Y�ȃ`�b�v�R���f���T�[�ɂāA����ȏ�ɂȂ������g�p�X�����ɂ���B
���ʂ�����ƁA���Ȃ蔭�U�X���ɂȂ�A�U�����s����ɁB
�����ŁA�I�i��22��H�̃W�����p�������������Ƃ�����肵���B
�܂�A�d���̃`���[�N�́A���Ȃ�K�v�ȗv�f�ł������B
�`���[�N��DC��R������ǂ����邽�ߏI�i�̂݃�3mm�ł͂Ȃ���4mm�ɂ������A������Ƒ���L���ă�5mm�ɂ��������ǂ��Ǝv�����ʂ��B
�����́A�ʏ�̓d���A��OP-AMP�ł̃M���M���́}6V���d�ɂ��邩�H�Ƃ��l�������A�p�^�[����ς��˂Ȃ�Ȃ����A�ϋv���ɖ�肪�o�邩���m��Ȃ��̂Łc�A
�X�ɁA��h���b�v�̉σ��M�����[�^���g��0.5V������11.5V���x����}�d���ɕ������Ă��ǂ����������A��������ɓd���G������̂��S�O����B
20230708
-------------------------------------------------------------------------------------------------------�|�|�|�|�|
��VNA��AGC-AMP�̓��͂��ŒZ�����Őڍ����Ĕ��˂̗l�q�Ɛ��������遄
�ŒZ�Őڍ��ł���ϊ��R�l�N�^���͂��āA���t���đ���ƌ������ƂɂȂ����B
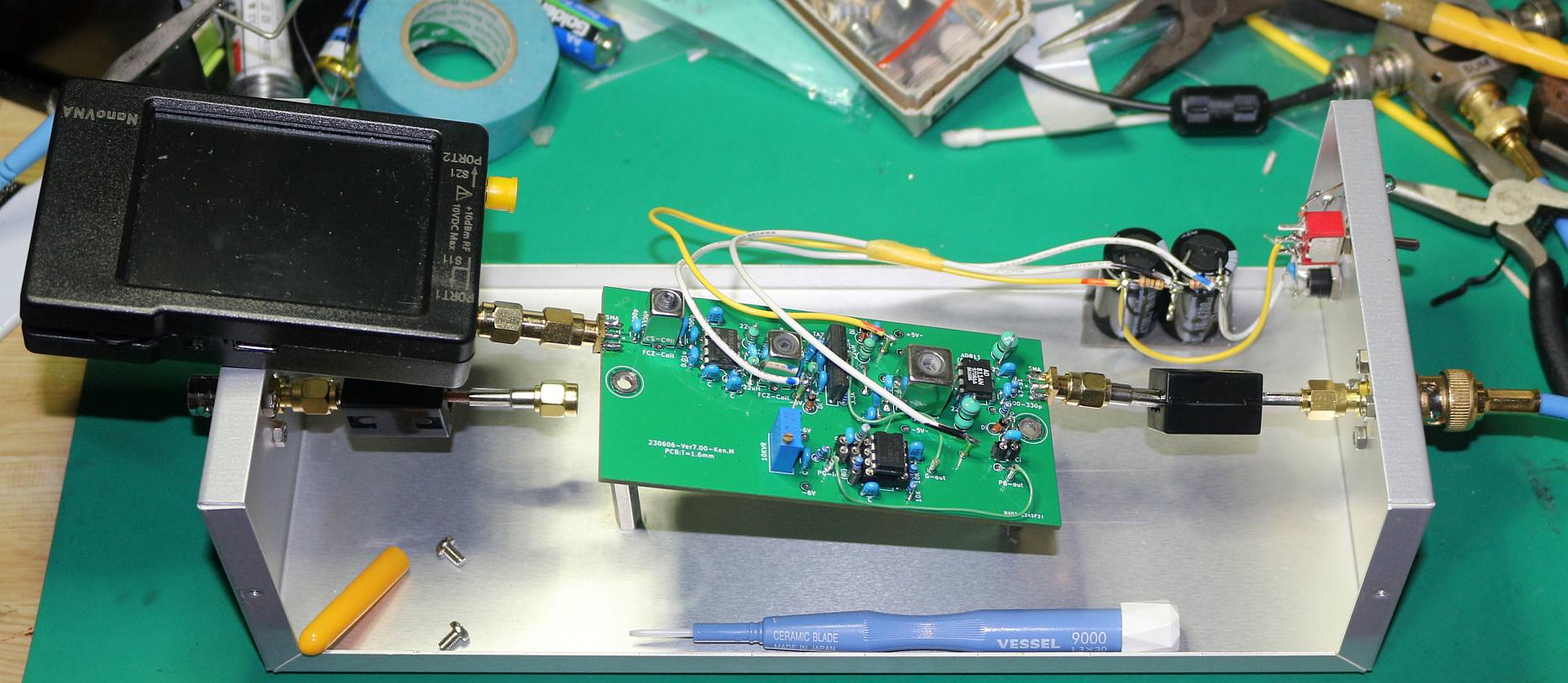 �Ƃ肠�����A���肵�Ă݂��Ƃ���A
�܂�����A�܂�L�����������Ɛ����āA����������邽�߁AFCZ�R�C���̃R�A����ߍ��ݕ����ɓ��������B
�R�A���O���قǁA�Ƃ�����Ԃ́A���������o�����X�Ƃ��ĕs���R�ȏ�ԂɎv���̂ŁA���ߍ��݂͑Ó����Ǝv���B
�������̊��G�ł́A
�E�C�}�W�i���[�̉�����̂قڃ{�g����ԂŁASWR���Œ�ƂȂ�A��v�����o���B
�E���������U���͎�������Ȃ����C���������A�P�[�u�����̕ω��ɂ���āA�o�͂̋����̌X�������܂�ω����Ȃ��Ȃ����C������B�܂�A�U�����P�[�u�����ɂ��Ȃ��Ȃ��������B
VNA�ł���Ȋ����B
�Ƃ肠�����A���肵�Ă݂��Ƃ���A
�܂�����A�܂�L�����������Ɛ����āA����������邽�߁AFCZ�R�C���̃R�A����ߍ��ݕ����ɓ��������B
�R�A���O���قǁA�Ƃ�����Ԃ́A���������o�����X�Ƃ��ĕs���R�ȏ�ԂɎv���̂ŁA���ߍ��݂͑Ó����Ǝv���B
�������̊��G�ł́A
�E�C�}�W�i���[�̉�����̂قڃ{�g����ԂŁASWR���Œ�ƂȂ�A��v�����o���B
�E���������U���͎�������Ȃ����C���������A�P�[�u�����̕ω��ɂ���āA�o�͂̋����̌X�������܂�ω����Ȃ��Ȃ����C������B�܂�A�U�����P�[�u�����ɂ��Ȃ��Ȃ��������B
VNA�ł���Ȋ����B
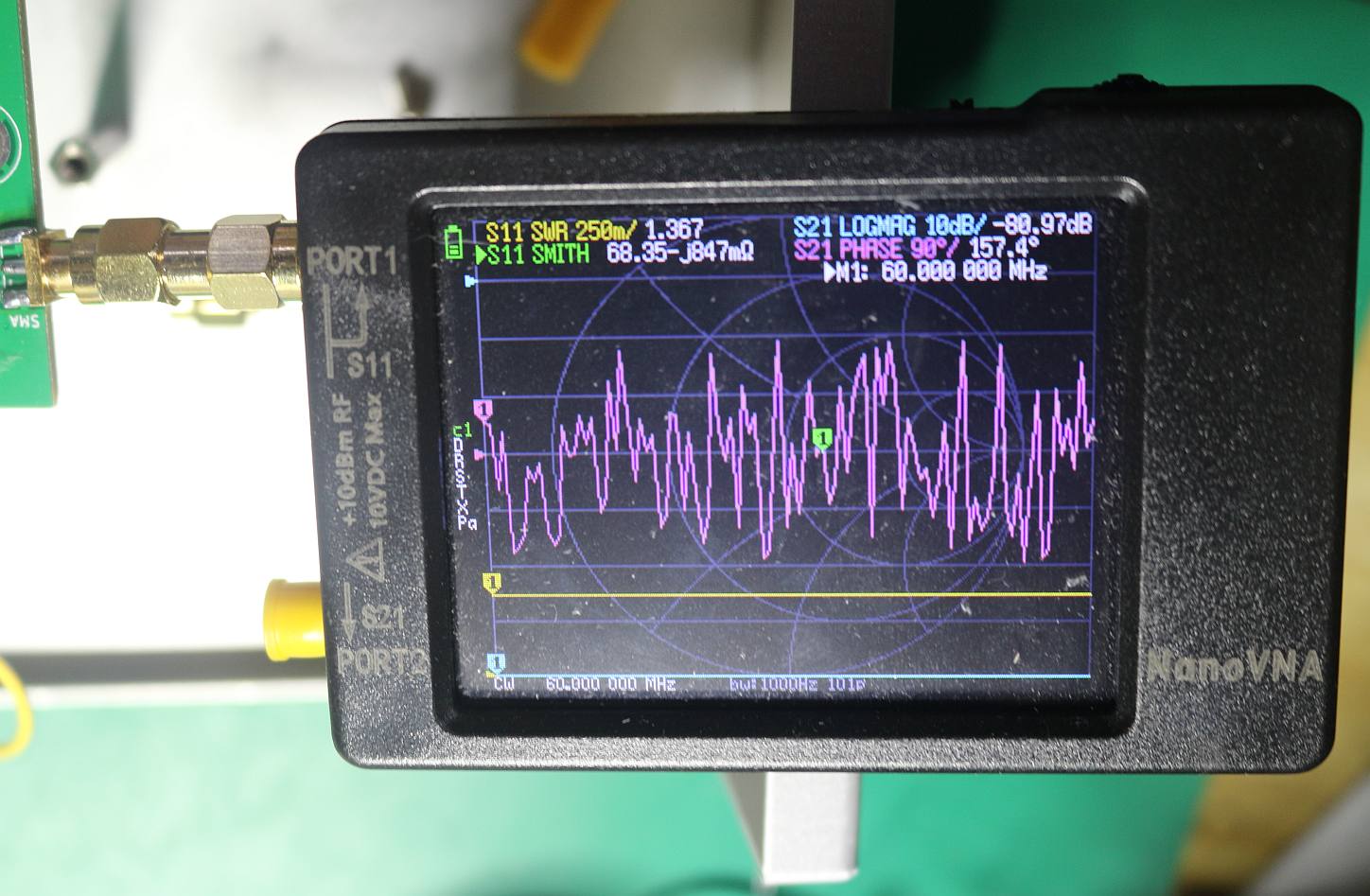 �C�}�W�i���[�������ɏ��ɏo����悤�ɂ�����B
����Z�̃��A�����FR=68.35���@��SWR=1.367
��i�ڂ�IC�̓���Z�����߂Ȃ̂ŁA�R�R�����E�����A�Ȃ��Ȃ��ǂ����ʂł���Ǝv����B
20230814
20240126
��Ƃ��I����āA�������O�ɖڂɂ������Ƃł��������ǁB
OP-AMP�Ȃǂ̏o�̓C���s�[�_���X�����ɂ��āA�ȑO���珑���Ă���Ǝv�����ǁA39�`43���Ƃ���߂ɐݒ肵�Ă�B
����́A�o�͂ɓ���Z���������邱�Ƃ�AZ�����������Ƃ��납��Ⴂ�Ƃ���͂���܂蔽�˂��Ȃ��Ƃ������ƂƓ���łł���B
�܂�A�����̉�H�ōs���Ă���o��Z��50������������50���̒�R�������ɐڑ�����̂́A���܂�ɂ����ȏ��̗��z���̂܂ܓI�ł��낤���ƁB
�ŁA�A�i�f�o���ǂ����̃T�C�g�ŁA�v�Z����ю����ɂāA33���Ƃ��Ń����M���O����є��U�X���\�h�ȂǁA�\���Ȗ������ʂ����Ə����Ă����L�����������̂ŃR�R�ɋL���Ă����B
������ȓ��Ō������郌�x���Ȃ炳�قǖ��Ȃ����낤���A�A
������������ŏ������L�������邯�ǁA
��R�̃m�C�Y�̓s���N�m�C�Y�I�ŁA�����g�̓[�[�x�b�N�I�ȃm�C�Y�����Ȃ��炵�����A�ꉞ�A�J�[�{�����ɗ͔����ċ���ɂ����B
���������t�B���K�[�A�N�V�����u���[�o�b�N��Glock17
���f���́AGen4�ł���B
�O���b�v�̌`�������I�����B
�O�ς͌��\�ǂ��B�n�[�h�Ȏ�����GLOCK��p�z���X�^�[�ɂ��������B
�C�}�W�i���[�������ɏ��ɏo����悤�ɂ�����B
����Z�̃��A�����FR=68.35���@��SWR=1.367
��i�ڂ�IC�̓���Z�����߂Ȃ̂ŁA�R�R�����E�����A�Ȃ��Ȃ��ǂ����ʂł���Ǝv����B
20230814
20240126
��Ƃ��I����āA�������O�ɖڂɂ������Ƃł��������ǁB
OP-AMP�Ȃǂ̏o�̓C���s�[�_���X�����ɂ��āA�ȑO���珑���Ă���Ǝv�����ǁA39�`43���Ƃ���߂ɐݒ肵�Ă�B
����́A�o�͂ɓ���Z���������邱�Ƃ�AZ�����������Ƃ��납��Ⴂ�Ƃ���͂���܂蔽�˂��Ȃ��Ƃ������ƂƓ���łł���B
�܂�A�����̉�H�ōs���Ă���o��Z��50������������50���̒�R�������ɐڑ�����̂́A���܂�ɂ����ȏ��̗��z���̂܂ܓI�ł��낤���ƁB
�ŁA�A�i�f�o���ǂ����̃T�C�g�ŁA�v�Z����ю����ɂāA33���Ƃ��Ń����M���O����є��U�X���\�h�ȂǁA�\���Ȗ������ʂ����Ə����Ă����L�����������̂ŃR�R�ɋL���Ă����B
������ȓ��Ō������郌�x���Ȃ炳�قǖ��Ȃ����낤���A�A
������������ŏ������L�������邯�ǁA
��R�̃m�C�Y�̓s���N�m�C�Y�I�ŁA�����g�̓[�[�x�b�N�I�ȃm�C�Y�����Ȃ��炵�����A�ꉞ�A�J�[�{�����ɗ͔����ċ���ɂ����B
���������t�B���K�[�A�N�V�����u���[�o�b�N��Glock17
���f���́AGen4�ł���B
�O���b�v�̌`�������I�����B
�O�ς͌��\�ǂ��B�n�[�h�Ȏ�����GLOCK��p�z���X�^�[�ɂ��������B

 �ׂ������Ƃ́AYoutube���ǂ��Ǝv���B
�Ƃ肠�����A�����̒@�����Ƃ��낪�l�b�N�ŁA�E�����������ǂ��Ƃ����������A�O���[�X���������Ă����̂ŁA�e�B�b�V���Ōy���@����������x�B
���[�U�[�����e�̋@�\�����B
���̕����̕���͐挩�̖��ɂĂ��łɎ��s�ς݁B
�̓���
https://www.nicovideo.jp/watch/sm25995979
�ŁA�u���[�o�b�N���J�̕��́A
�o�l�ɒ~�ς����̗͂ʂ̉���Łu�@���v���ɂ���āA�X���C�h����ނ���B���̒@���s���͂ƂĂ��Z���B
�g���K�[�v���͂ƂĂ��d���A���u�Ԃ͓��ɑ傫�ȗ͂��g���B
5Kg�ȏ�炵������A���{���o�[�����d���悤�Ȋ����B�g���K�[�Z�[�t�e�B�[�̍a���w�ɐH������Œɂ��Ƃ�������B
���R�ɁA�g���K�[�������A�g���K�[�g���x���������������Ƃ�����Ǝv���B
�Î~��Ԃ���R��̂�����
�G�l���M�[�ۑ��ł��͐ρˉ^���ʂł����藧�Ǝv�����ǁB
�P�Ɍ����ڂɑf�����X���C�h���������Ȃ�A�����s��������������Ɖ҂��ł������Ǝv���B
�����A���܂�x���ƃJ�[�g����Ȃ������B
�Ȃ̂ŁA������͍���i�����邱�Ƃɂ���ĕς�肻���B
(�d���Ȃ�A�V�����_�^�̃A�N�`���G�[�^�[���V���v���ŗǂ������B�܂��A�d�u���ł����f���K���ł��B���j�A���[�^�[�I�ł��H)
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
������Ɏ��g�������炵�����̂������Ă��������߁A�������𑪒�B
�P�ɁA�P���Ō��邾���B
�����A���[�U�[���Ȃ̂ŁA���w�I��BPF���g����B�����A���ʂɐԃt�B���^�[�Ƃ������Ă������B
��̂̓����B
�ׂ������Ƃ́AYoutube���ǂ��Ǝv���B
�Ƃ肠�����A�����̒@�����Ƃ��낪�l�b�N�ŁA�E�����������ǂ��Ƃ����������A�O���[�X���������Ă����̂ŁA�e�B�b�V���Ōy���@����������x�B
���[�U�[�����e�̋@�\�����B
���̕����̕���͐挩�̖��ɂĂ��łɎ��s�ς݁B
�̓���
https://www.nicovideo.jp/watch/sm25995979
�ŁA�u���[�o�b�N���J�̕��́A
�o�l�ɒ~�ς����̗͂ʂ̉���Łu�@���v���ɂ���āA�X���C�h����ނ���B���̒@���s���͂ƂĂ��Z���B
�g���K�[�v���͂ƂĂ��d���A���u�Ԃ͓��ɑ傫�ȗ͂��g���B
5Kg�ȏ�炵������A���{���o�[�����d���悤�Ȋ����B�g���K�[�Z�[�t�e�B�[�̍a���w�ɐH������Œɂ��Ƃ�������B
���R�ɁA�g���K�[�������A�g���K�[�g���x���������������Ƃ�����Ǝv���B
�Î~��Ԃ���R��̂�����
�G�l���M�[�ۑ��ł��͐ρˉ^���ʂł����藧�Ǝv�����ǁB
�P�Ɍ����ڂɑf�����X���C�h���������Ȃ�A�����s��������������Ɖ҂��ł������Ǝv���B
�����A���܂�x���ƃJ�[�g����Ȃ������B
�Ȃ̂ŁA������͍���i�����邱�Ƃɂ���ĕς�肻���B
(�d���Ȃ�A�V�����_�^�̃A�N�`���G�[�^�[���V���v���ŗǂ������B�܂��A�d�u���ł����f���K���ł��B���j�A���[�^�[�I�ł��H)
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
������Ɏ��g�������炵�����̂������Ă��������߁A�������𑪒�B
�P�ɁA�P���Ō��邾���B
�����A���[�U�[���Ȃ̂ŁA���w�I��BPF���g����B�����A���ʂɐԃt�B���^�[�Ƃ������Ă������B
��̂̓����B
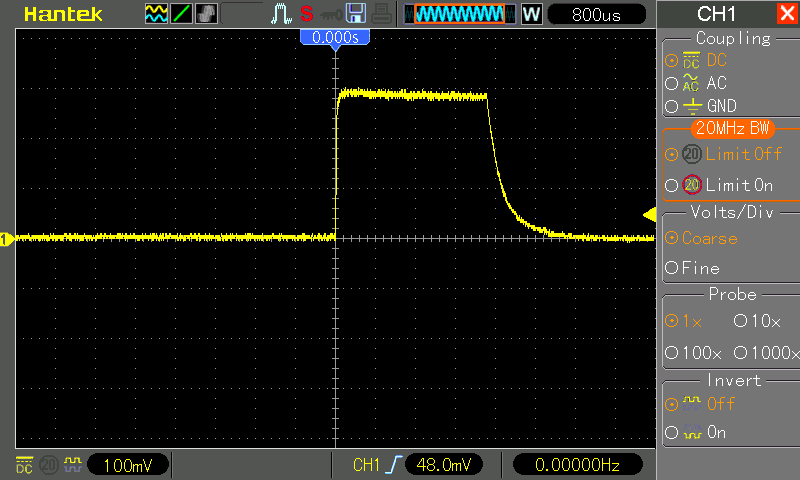
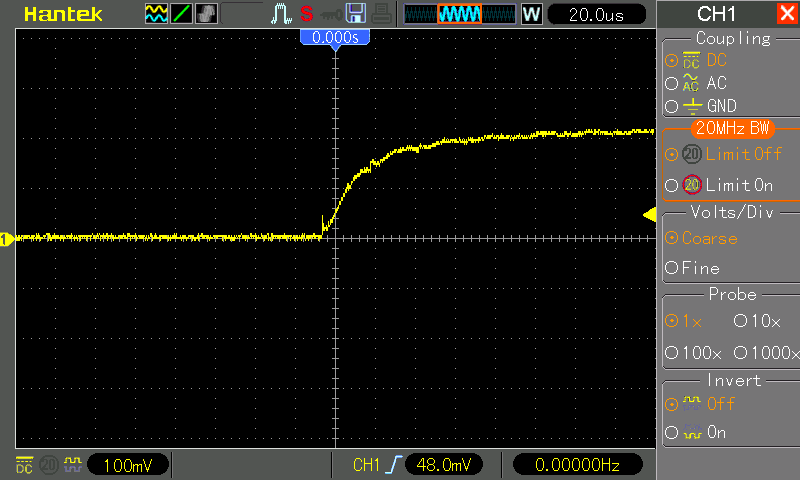 �E�����オ��(50%)�F5��Sec
�E�p���X���F3mSec
�����オ��̒x���́A�d���R���f���T�[���g���Ă�̂��炩���m��Ȃ��B
�����ƃp���X�̃G�b�W�������đ�����A������H�ł��Ȃ�J�b�g�ł���B(���Ȃ݂ɂ��̔����̎��萔�̓e�L�g�[�ł���B)
��������ɁA�����ł͂��邪�A��R�ƃR���f���T�[�̂悤�ŁA
��r�I�������R���f���T�[�ɏ[�d���Ĉ�C�ɕ��d���H
�t�ɔ�����H�ŃR���f���T�[�̓d�����r�I������蓦�������H
��2�ʂ肪�l������B
�E�����オ��(50%)�F5��Sec
�E�p���X���F3mSec
�����オ��̒x���́A�d���R���f���T�[���g���Ă�̂��炩���m��Ȃ��B
�����ƃp���X�̃G�b�W�������đ�����A������H�ł��Ȃ�J�b�g�ł���B(���Ȃ݂ɂ��̔����̎��萔�̓e�L�g�[�ł���B)
��������ɁA�����ł͂��邪�A��R�ƃR���f���T�[�̂悤�ŁA
��r�I�������R���f���T�[�ɏ[�d���Ĉ�C�ɕ��d���H
�t�ɔ�����H�ŃR���f���T�[�̓d�����r�I������蓦�������H
��2�ʂ肪�l������B
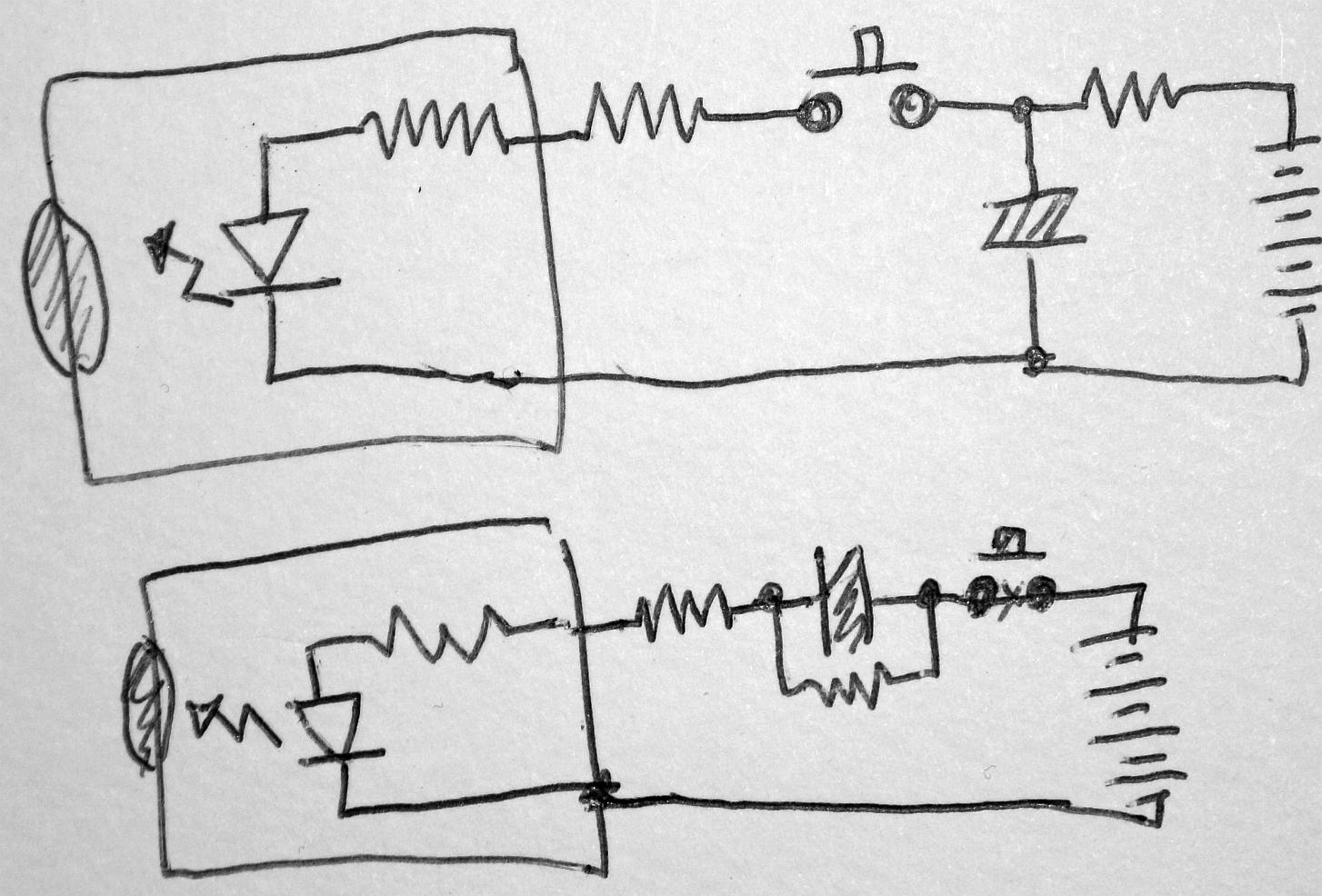 ����ɉ����āA�X�C�b�`���������m���f�����ʉ߂���̂Ń����N���u�ԓI�Ƃ����̂����邾�낤�B(�J���ĂȂ��̂ł��ׂė\�z�ŁA)
3P�}�C�N��SW�Ȃ�A���������m��Ȃ��B
����ɉ����āA�X�C�b�`���������m���f�����ʉ߂���̂Ń����N���u�ԓI�Ƃ����̂����邾�낤�B(�J���ĂȂ��̂ł��ׂė\�z�ŁA)
3P�}�C�N��SW�Ȃ�A���������m��Ȃ��B
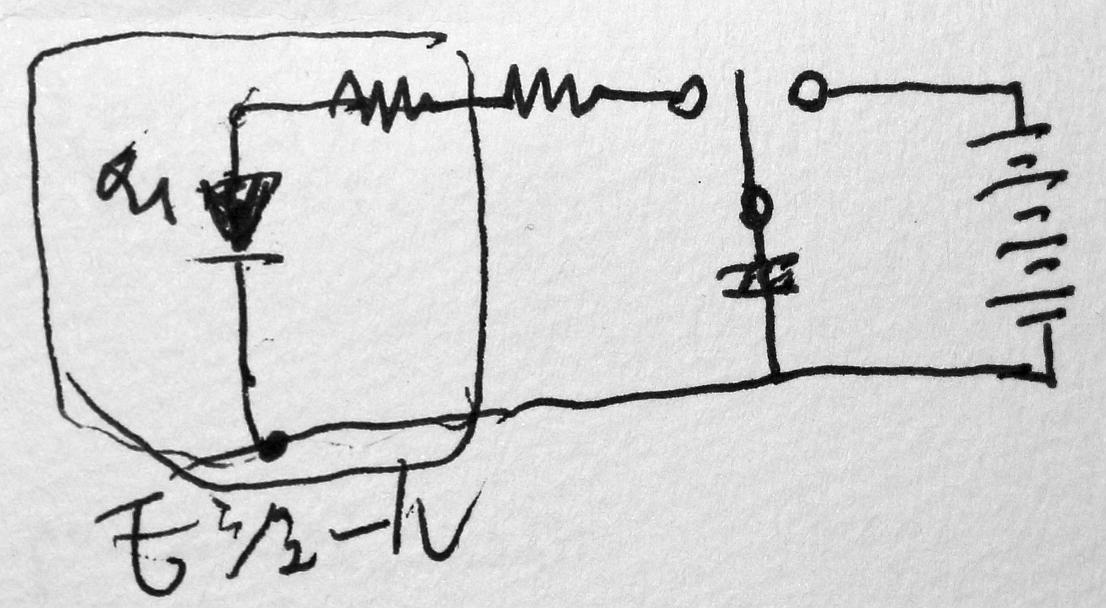 LD�͂�����̔ėp�i�ȃR�����[�^�[�t��LD���W���[�����g���Ă��������B3�_�x���Ȃ̂Œ����͂߂�ǂ������B
�Ƃɂ����ALD�����ɒ�R������A�������̃{�^���d�r����X�ɐ������Ă��܂��d���������邽�߂̒�R��t���Ă���n�Y�B
LD�͂�����̔ėp�i�ȃR�����[�^�[�t��LD���W���[�����g���Ă��������B3�_�x���Ȃ̂Œ����͂߂�ǂ������B
�Ƃɂ����ALD�����ɒ�R������A�������̃{�^���d�r����X�ɐ������Ă��܂��d���������邽�߂̒�R��t���Ă���n�Y�B
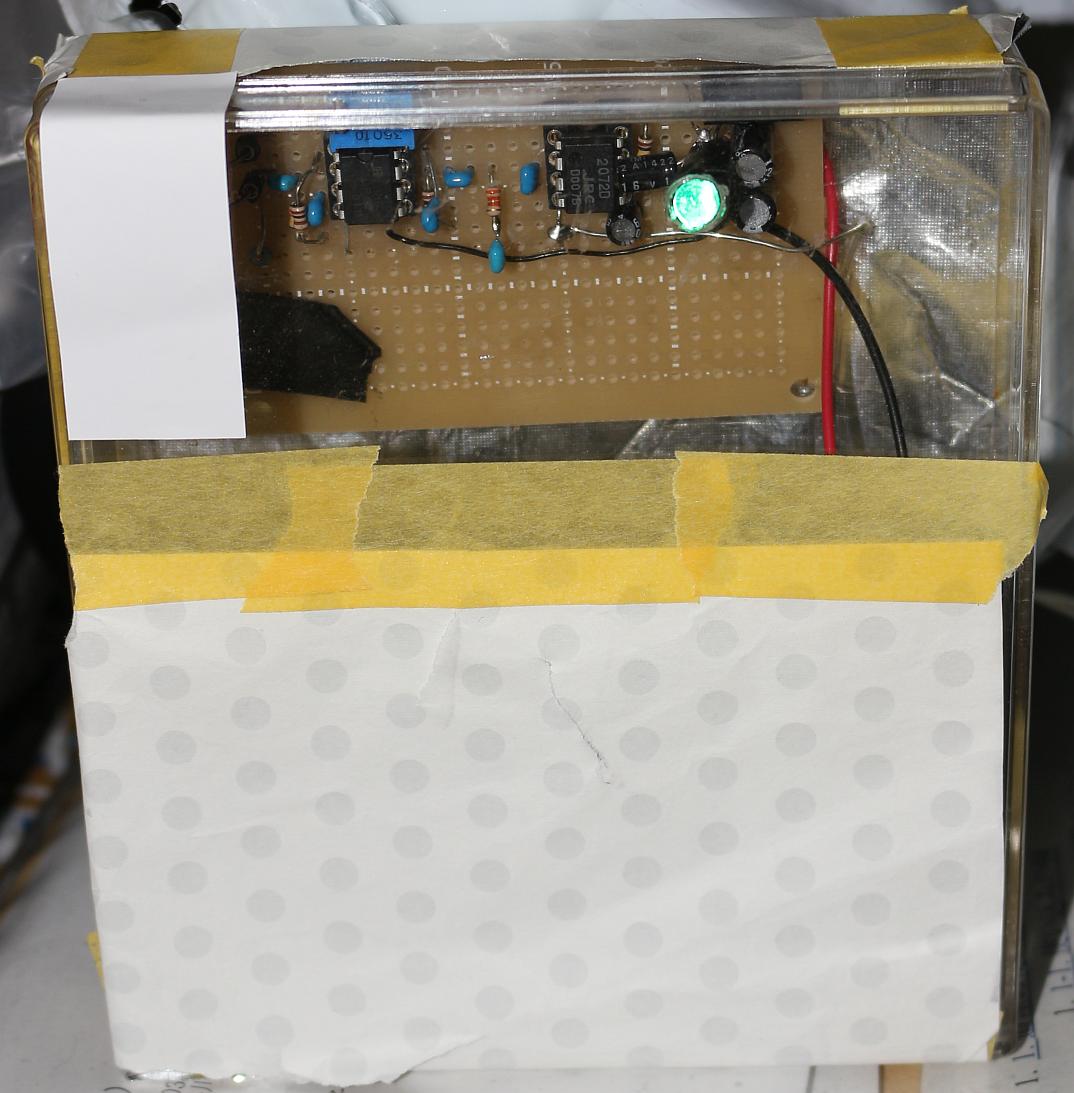
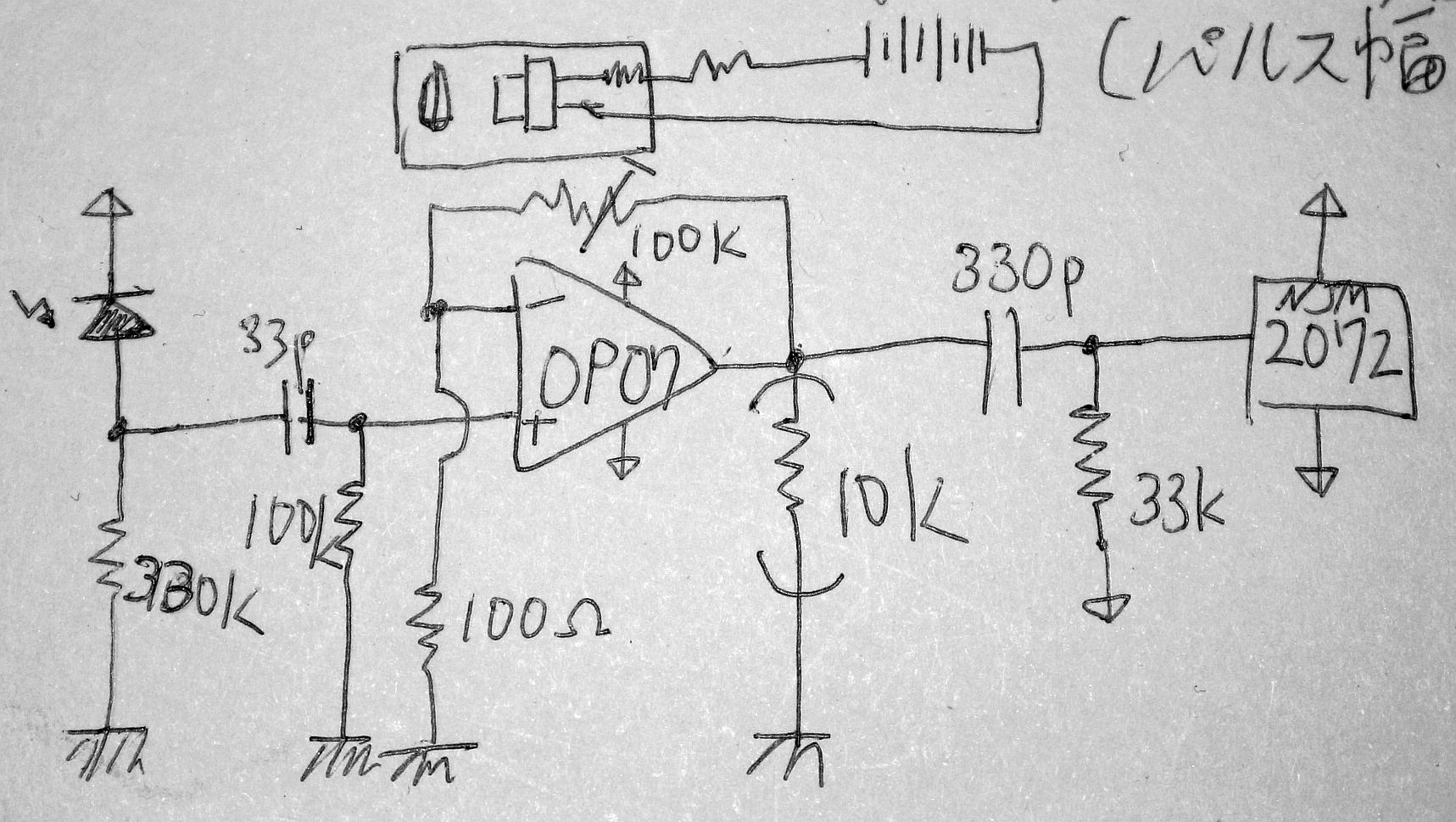 �}��330K��100K�ȏ�͋t�����ǁALD���W���[���Ȃ炱����̕����ǂ��Ɣ��f�B
�܂��A�|���J�{�P�[�X���������A�σm�C�Y�̂��߁A�A���~�V�[�g�V�[���h�����āAGND��1�_�A�[�X���s�����B
�z���g�́A�����P�[�X���ǂ����ǁA��{�͓d��ŁA�d���g�̏ꍇ�A�o����Ȃ�S���ǂ������B���ɓ��A�^�J�ȂǁH�B�A���~�͎Օ����g��������������ł��\�������H
���Ƃ́ALED�����邯�ǁA���ꂪ�O���ɂȂ肤��̂ŃX���[�X�^�[�g���Ռ��C���ɂ��Ă���BTr�Ń����[��H�œ��삳������A
�u�U�[�����������ǂ����ƁB
�ł���Ă݂�ƁA����Ȃ�ɃQ�C�����K�v�ł͂������B
�ĊO�Ɣ������݂��C������̂́APD�̔g�������������A960nm���x���s�[�N�����炩�ƁB
�܂��A���F�̎U���p�̃��m�ƁAPD�Ƀ����Y����Ƃ��A����ʐςƂ��B�B
�Ȃ��A�w����Amazon�ł͂Ȃ�VOISKY�Ƃ����g�R����w���B
���ƁA
�u�V���[�e�B���O�����W�I�����C���v�Ƃ����̂ŁA�X�}�z�̃J�������g���Ē��e�ʒu���m�F�ł���悤�ł��B
�ߋ��ɁB
���e�̃_�~�[�J�[�g�̃��[�U�[�������j�b�g�p�Ō������Ƃ�����܂����B
----------------------------------------------------------------------
�NjL��
������p��PD�ɋt�o�C�A�X�������Y��Ă����悤�Ȃ̂ŁA
�������݂������ŁA�����͂����Ƒ����Ǝv����B��10�{�ȏ㑬�������B
���肪�߂�ǂ��̂ŁA���̓��ɂ��B
�܂��A�P�ɃX�C�b�`����u����Ă�݂����Ȃ̂ŁB
��
���ʁA�����Ƃ���p���X���Ԃ͕��͕ς��Ȃ��B���A�X�C�b�`����ʼn����ƒ�������̂悤���B
�܂胁�J�j�J���Ȑڑ��ƎՒf���s���Ă���Ǝv����B
�ŁA�t�o�C�A�X��������ƁA����X�s�[�h�͍����������̂ɁA���̗����オ�肪�A�t�ɒx���Ȃ��Ă���B
����́A�t�o�C�A�X�ŁA���܂œ��ł��ł������\�����A�������x���܂ŕ\���ł���悤�ɂȂ������ƂɋN�����Ă��āA���ꂪ�����̖{���̎p�Ȃ̂����m��Ȃ��B
�����ƍ����t�o�C�A�X�d�����~�����قǂ��B
���[�U�[���U�Ɏ��Ԃ�������H���ǂ����͂܂��������s�������A�܂��A�A
�}��330K��100K�ȏ�͋t�����ǁALD���W���[���Ȃ炱����̕����ǂ��Ɣ��f�B
�܂��A�|���J�{�P�[�X���������A�σm�C�Y�̂��߁A�A���~�V�[�g�V�[���h�����āAGND��1�_�A�[�X���s�����B
�z���g�́A�����P�[�X���ǂ����ǁA��{�͓d��ŁA�d���g�̏ꍇ�A�o����Ȃ�S���ǂ������B���ɓ��A�^�J�ȂǁH�B�A���~�͎Օ����g��������������ł��\�������H
���Ƃ́ALED�����邯�ǁA���ꂪ�O���ɂȂ肤��̂ŃX���[�X�^�[�g���Ռ��C���ɂ��Ă���BTr�Ń����[��H�œ��삳������A
�u�U�[�����������ǂ����ƁB
�ł���Ă݂�ƁA����Ȃ�ɃQ�C�����K�v�ł͂������B
�ĊO�Ɣ������݂��C������̂́APD�̔g�������������A960nm���x���s�[�N�����炩�ƁB
�܂��A���F�̎U���p�̃��m�ƁAPD�Ƀ����Y����Ƃ��A����ʐςƂ��B�B
�Ȃ��A�w����Amazon�ł͂Ȃ�VOISKY�Ƃ����g�R����w���B
���ƁA
�u�V���[�e�B���O�����W�I�����C���v�Ƃ����̂ŁA�X�}�z�̃J�������g���Ē��e�ʒu���m�F�ł���悤�ł��B
�ߋ��ɁB
���e�̃_�~�[�J�[�g�̃��[�U�[�������j�b�g�p�Ō������Ƃ�����܂����B
----------------------------------------------------------------------
�NjL��
������p��PD�ɋt�o�C�A�X�������Y��Ă����悤�Ȃ̂ŁA
�������݂������ŁA�����͂����Ƒ����Ǝv����B��10�{�ȏ㑬�������B
���肪�߂�ǂ��̂ŁA���̓��ɂ��B
�܂��A�P�ɃX�C�b�`����u����Ă�݂����Ȃ̂ŁB
��
���ʁA�����Ƃ���p���X���Ԃ͕��͕ς��Ȃ��B���A�X�C�b�`����ʼn����ƒ�������̂悤���B
�܂胁�J�j�J���Ȑڑ��ƎՒf���s���Ă���Ǝv����B
�ŁA�t�o�C�A�X��������ƁA����X�s�[�h�͍����������̂ɁA���̗����オ�肪�A�t�ɒx���Ȃ��Ă���B
����́A�t�o�C�A�X�ŁA���܂œ��ł��ł������\�����A�������x���܂ŕ\���ł���悤�ɂȂ������ƂɋN�����Ă��āA���ꂪ�����̖{���̎p�Ȃ̂����m��Ȃ��B
�����ƍ����t�o�C�A�X�d�����~�����قǂ��B
���[�U�[���U�Ɏ��Ԃ�������H���ǂ����͂܂��������s�������A�܂��A�A
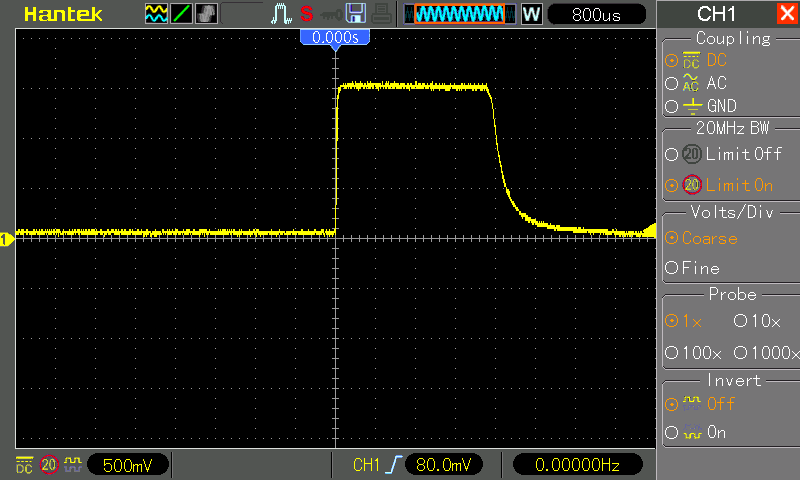
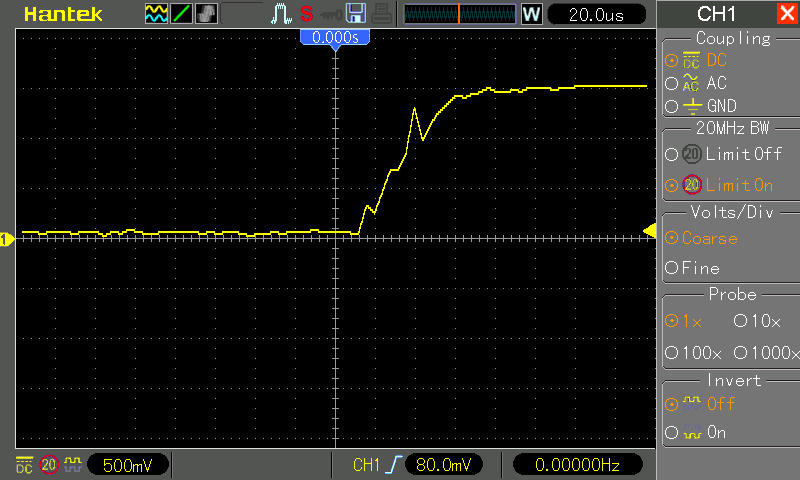 -----------------------------------------------------------------------
�NjL02��
�����𐰓V�̓����ȉ��O�Ȃǖ��邢�Ƃ���ɒu���ꍇ�A�Ȃ�ׂ��O�̑��z���Ȃǂ�����Ȃ��悤�ɂ��邱�ƂƁA
�o�C�A�X��R�������āA�Q�C���͂���������ŁB
���Ƃ́A�����Y����w�t�B���^�[��������x�Ӗ��������ǁA�U�d�̑��w��BPF�ʂ���Ȃ��Ƃ��܂������Ȃ��Ǝv���B
�o�C�A�X��R�ςɂāA3.3K�ŁA�����{��1000�{�ł���Ȃ�B
�����Ƌɒ[�ł����������B
100����10���ŁAPD�̃o�C�A�X�p�ϒ�R�ɒ���ɑ傫�߂̃}�C�N���C���_�N�^�����Ă݂��B����Ȃ�Ɋ��x�����邯�ǁA
���邢�Ƃ���ł͌��X�t�o�C�A�X�ȏ�̓d�����o�Ă��܂��Ă���Ƃ��낪���邩�Ǝv���B�ԊO�����R����������ɒ��˓��������������甽�����݂�܂���̂Ɠ����B
�t�o�C�A�X�ɂ����E�d�������邽�߁A���������̓��ˌ������x���I�[�o�[�Ƃ��������ł��邩�Ǝv����BBPF����Y�A�Ђ�����t����Ƃ��ȍH�v���K�v�B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�V���[�e�B���O�����W�E�I�����C��
����Ă݂��B
�ގ��\�t�g�͂��������邩�Ǝv���B
��������^�[�Q�b�g��F�����A���e�ł��郌�[�U�[�̋P�_�ʂ���B
-----------------------------------------------------------------------
�NjL02��
�����𐰓V�̓����ȉ��O�Ȃǖ��邢�Ƃ���ɒu���ꍇ�A�Ȃ�ׂ��O�̑��z���Ȃǂ�����Ȃ��悤�ɂ��邱�ƂƁA
�o�C�A�X��R�������āA�Q�C���͂���������ŁB
���Ƃ́A�����Y����w�t�B���^�[��������x�Ӗ��������ǁA�U�d�̑��w��BPF�ʂ���Ȃ��Ƃ��܂������Ȃ��Ǝv���B
�o�C�A�X��R�ςɂāA3.3K�ŁA�����{��1000�{�ł���Ȃ�B
�����Ƌɒ[�ł����������B
100����10���ŁAPD�̃o�C�A�X�p�ϒ�R�ɒ���ɑ傫�߂̃}�C�N���C���_�N�^�����Ă݂��B����Ȃ�Ɋ��x�����邯�ǁA
���邢�Ƃ���ł͌��X�t�o�C�A�X�ȏ�̓d�����o�Ă��܂��Ă���Ƃ��낪���邩�Ǝv���B�ԊO�����R����������ɒ��˓��������������甽�����݂�܂���̂Ɠ����B
�t�o�C�A�X�ɂ����E�d�������邽�߁A���������̓��ˌ������x���I�[�o�[�Ƃ��������ł��邩�Ǝv����BBPF����Y�A�Ђ�����t����Ƃ��ȍH�v���K�v�B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�V���[�e�B���O�����W�E�I�����C��
����Ă݂��B
�ގ��\�t�g�͂��������邩�Ǝv���B
��������^�[�Q�b�g��F�����A���e�ł��郌�[�U�[�̋P�_�ʂ���B
 ���������邢���߂��A�J�����̃L�����u���[�V�����Ȃǂ��V�r�A�������B
�J�����̋������|�C���g���Ƃ͎v���B
���ʁA���[�U�[���j�b�g���傫�������ɃY���Ă銴���������B
3�_�x�����A�݂傤�Ȕ������������܂��Ă��āA
�Ȃ̂ŁA�������悭�킩��Ȃ������B
�ʐ^�́A�ڕ��ʂ̒��e�C���Ő^�ɓ��ĂĂ���B
2�`3m���x�ł́A���\�ȒP�ɓ����邪�A�������Ƃ��āA�T�C�g���g��Ȃ��Ō��͖̂ʔ����Ȃ����낤�B
����������Ă�����������ȁH
�������Ă��������o�Ȃ��ꍇ�A
�r�f�I�J�����̃V���b�^�[�Ԋu�ŋP�_���B�e����Ȃ����ƂɋN������Ǝv����B
��������́A�X���[�V���b�^�[�̂ł���J��������Ȃ��Ɓc�A�A
���̃X���[�V���b�^�[��30Fps�Ƃ��ō̎悵��PC�ɓ]�����銴���̃��m�B
���[�����O�V���b�^�[�Ƃ������Ƃ��ȁH�H�H�H
�i���Q�C�������ŁA�V���b�^���Ԃ��ς�炸���ƁA
�R�}�ƃR�}�̊Ԃ��Ă�̂ŁA�A
����́A�J������I�Ԋ����B
�X�}�z�ł͂��܂��s���̂ŁB�B
Web�J��������i�J�i�J���������B
USB�J�����ŁA�X���[�V���b�^�[�̌������m��A���t�Ȃǂ�USB�łȂ���i�Ŏg���邩���m��Ȃ��B
����Ȃ̂́A�^�u���b�g�[���ƎO�r�X�^���h���ȁH�Y�[�����邩�H�H
���������邢���߂��A�J�����̃L�����u���[�V�����Ȃǂ��V�r�A�������B
�J�����̋������|�C���g���Ƃ͎v���B
���ʁA���[�U�[���j�b�g���傫�������ɃY���Ă銴���������B
3�_�x�����A�݂傤�Ȕ������������܂��Ă��āA
�Ȃ̂ŁA�������悭�킩��Ȃ������B
�ʐ^�́A�ڕ��ʂ̒��e�C���Ő^�ɓ��ĂĂ���B
2�`3m���x�ł́A���\�ȒP�ɓ����邪�A�������Ƃ��āA�T�C�g���g��Ȃ��Ō��͖̂ʔ����Ȃ����낤�B
����������Ă�����������ȁH
�������Ă��������o�Ȃ��ꍇ�A
�r�f�I�J�����̃V���b�^�[�Ԋu�ŋP�_���B�e����Ȃ����ƂɋN������Ǝv����B
��������́A�X���[�V���b�^�[�̂ł���J��������Ȃ��Ɓc�A�A
���̃X���[�V���b�^�[��30Fps�Ƃ��ō̎悵��PC�ɓ]�����銴���̃��m�B
���[�����O�V���b�^�[�Ƃ������Ƃ��ȁH�H�H�H
�i���Q�C�������ŁA�V���b�^���Ԃ��ς�炸���ƁA
�R�}�ƃR�}�̊Ԃ��Ă�̂ŁA�A
����́A�J������I�Ԋ����B
�X�}�z�ł͂��܂��s���̂ŁB�B
Web�J��������i�J�i�J���������B
USB�J�����ŁA�X���[�V���b�^�[�̌������m��A���t�Ȃǂ�USB�łȂ���i�Ŏg���邩���m��Ȃ��B
����Ȃ̂́A�^�u���b�g�[���ƎO�r�X�^���h���ȁH�Y�[�����邩�H�H
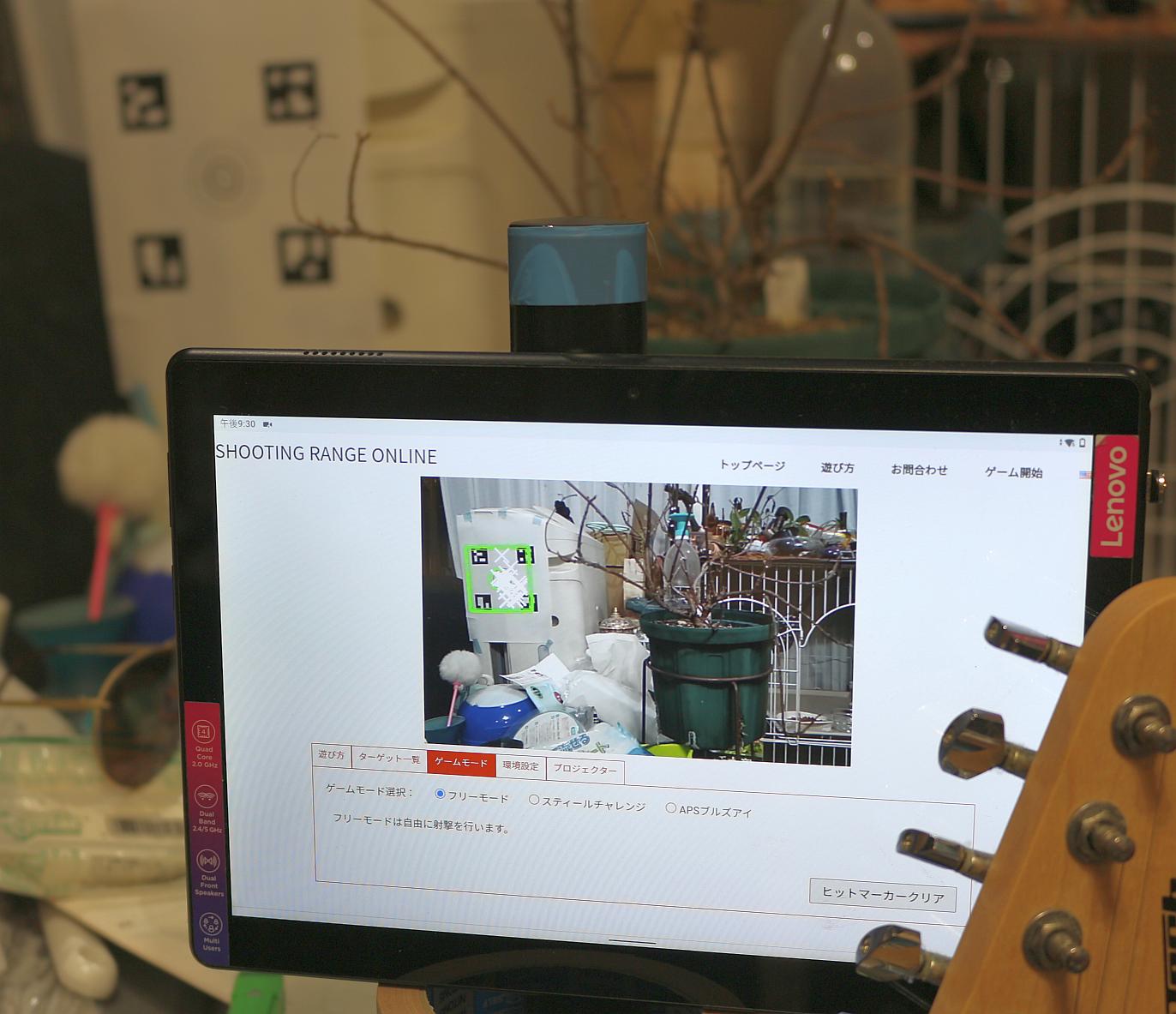
 �I�ɋ߂��Ƀ^�u�������āA
HDMI�A�_�v�^���A�A���h���C�hTV�APC�ɉ摜����āA�m�F���ǂ������H
�O�ɏ��������ǁALD���W���[�����W���[��������]�ł���̂Ȃ�A���E�̂��ꂪ�Ȃ��Ȃ�悤�ɉāA�㉺�̓T�C�g�łǂ��ɂ�����̂��]�܂��������m��Ȃ��B
�^�[�Q�b�g���Â��Ȃ��ƍ����V���b�^�[�ɂȂ�悤�Ȃ̂ŁA�\�R�����ӁB
�܂��t���Ȃǂɂ������[�����ǂ����ȁ[�H�ƁB
�܂��A���z�ȂǂŁA���邷����ƁA���[�U�[�ɂ��P�_��������ēǂ߂Ȃ��Ȃ�Ǝv���B
�NjL��
���̃V���[�e�B���O�Q�[���̉�ʂ��J�N�J�N�Ȃ̂ŁA�Q�[���ݒ��640x480�܂ʼn掿�𗎂Ƃ��ƁA
���܂��s���܂����B�u���E�U�̖�肩�AUSB�̔\�͂�PC�̔\�͂��ǂ��炩�ł��ˁB�B
OS�̐ݒ�ł�FullHD�ł������悤�Ȃ̂ł����A�A
CPU���d���Ȃ����A�A
�ǂ����A�v�APC��CPU�����ł������AUSB�[�q�̐ڐG�����ł����B�ړ_�����܂Ń}�V�ɂȂ�܂����B1024x768�ł�OK�Ȃ悤�ł��B
�W�I�̋߂��ɃJ������u���ׂ������肪�ł��܂��B���A��������ƁA�����̃^�[�Q�b�g�͓���Ȃ�܂��ł��ˁB�B
�オ�_�b�g�T�C�g�A�����I�[�v���ȃA�C�A���T�C�g�B
�I�ɋ߂��Ƀ^�u�������āA
HDMI�A�_�v�^���A�A���h���C�hTV�APC�ɉ摜����āA�m�F���ǂ������H
�O�ɏ��������ǁALD���W���[�����W���[��������]�ł���̂Ȃ�A���E�̂��ꂪ�Ȃ��Ȃ�悤�ɉāA�㉺�̓T�C�g�łǂ��ɂ�����̂��]�܂��������m��Ȃ��B
�^�[�Q�b�g���Â��Ȃ��ƍ����V���b�^�[�ɂȂ�悤�Ȃ̂ŁA�\�R�����ӁB
�܂��t���Ȃǂɂ������[�����ǂ����ȁ[�H�ƁB
�܂��A���z�ȂǂŁA���邷����ƁA���[�U�[�ɂ��P�_��������ēǂ߂Ȃ��Ȃ�Ǝv���B
�NjL��
���̃V���[�e�B���O�Q�[���̉�ʂ��J�N�J�N�Ȃ̂ŁA�Q�[���ݒ��640x480�܂ʼn掿�𗎂Ƃ��ƁA
���܂��s���܂����B�u���E�U�̖�肩�AUSB�̔\�͂�PC�̔\�͂��ǂ��炩�ł��ˁB�B
OS�̐ݒ�ł�FullHD�ł������悤�Ȃ̂ł����A�A
CPU���d���Ȃ����A�A
�ǂ����A�v�APC��CPU�����ł������AUSB�[�q�̐ڐG�����ł����B�ړ_�����܂Ń}�V�ɂȂ�܂����B1024x768�ł�OK�Ȃ悤�ł��B
�W�I�̋߂��ɃJ������u���ׂ������肪�ł��܂��B���A��������ƁA�����̃^�[�Q�b�g�͓���Ȃ�܂��ł��ˁB�B
�オ�_�b�g�T�C�g�A�����I�[�v���ȃA�C�A���T�C�g�B
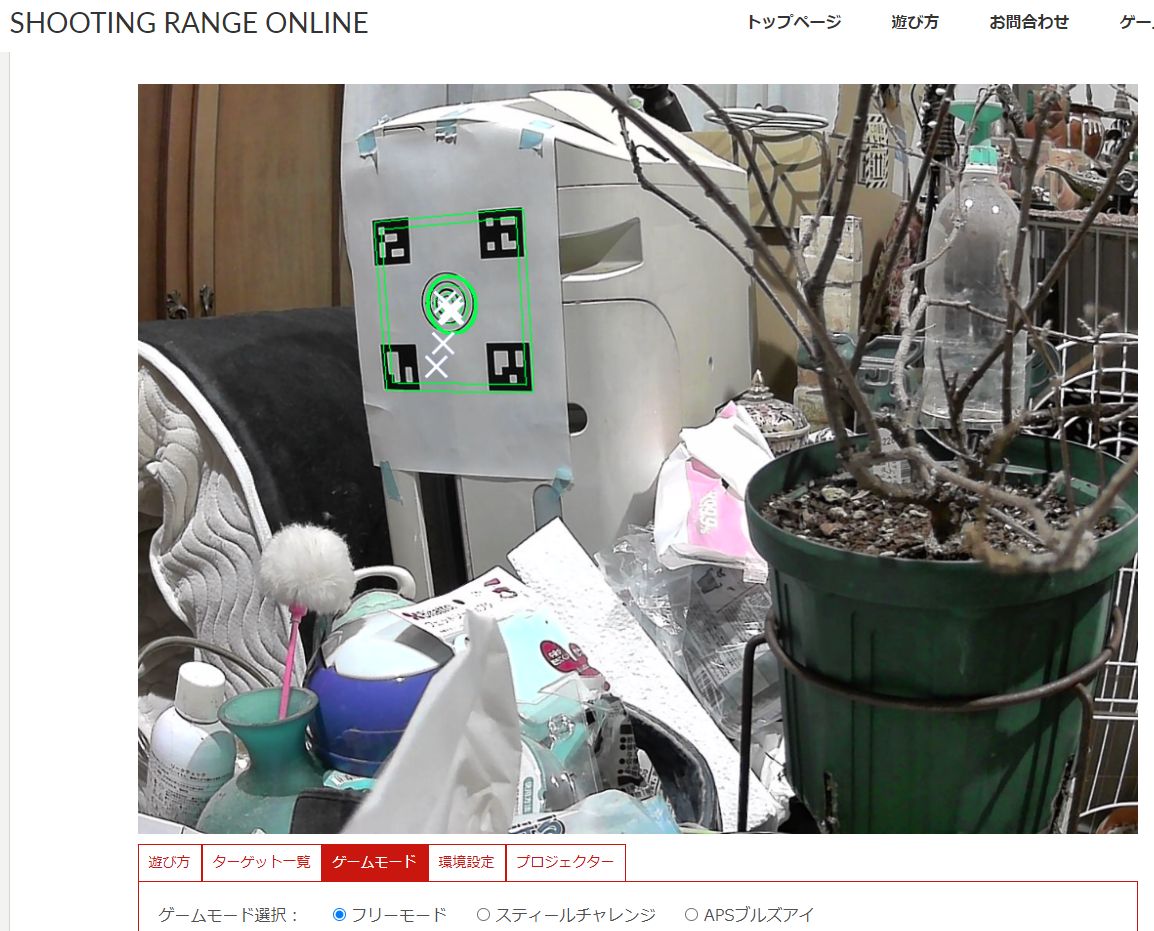 OS�̃J�����ݒ�ŘI�o��������x���Ƃ��Ȃ��ƁA���͔��Ȃ̂ŁA
����ł��Ȃ����Ƃ�����悤�ł��B
�܂��A���ł炵���̂ŁA���̂��������ōs�������B
���ƁA�������ԓ��̏e�̃u����V���b�^�[���Ԃ����\���G�ɂ��Ă܂��B
���܂�Ԃ�Ă�ƁA�������Ȃ��悤�ł��ˁB
�g���K�[���d���ƌ��\�Ԃ�܂�����B
240204
�掿�ŕ]�����ǂ����́A���W�N�[����C920n�Ƃ����̂ɂ����B�K���X�����Y�ŁA���������˂Ȃǂ̖��������Ȃ����B
�Â߂̏ꏊ�ƂȂ�̂ŁA�m�C�Y�Ȃǂ��e�����Ȃ��悤�A�Ȃ�ׂ����邢�����Y�̕����A�m�C�Y�ɋ������B
�V���[�e�B���O�����W�̉𑜓x��640x480�ɂ�
���W�̃\�t�g�E�F�A�Ń\�t�g�E�F�A�ōő�Y�[���A�s���g���Œ�B
���Ƃ́A�Â��Ƃ��̃t���[�����[�g�𗎂Ƃ�������OFF�A�����I�o��OFF�ɂ��A�Q�C���Ⴍ�����B
����ŁA������x�ǂ��Ȃ�������ǁA����ς薾�邷����̂��Â�����̂��_�����ۂ��B�p�����^�������̂œ���Ƃ��낪����B
�Ȃ�ׂ��A�O����̌����I�ɉe�����Ȃ������ǂ����Ǝv���B
����ꂽ���i���Ԉ���ĂăJ������C922�Ƃ���������ƌÂ߂������B��{�͎��Ă邪�A�K���X�����Y���ǂ����Ƃ��i���͂ǂ����H
�Ƃ������Ƃŕԕi�葱���B
�Ƃɂ����A���邭�Ė����̏��Ȃ��A�Ƃ�����Ƃ����B�����ĕ���(�^�[�Q�b�g)�͖��邷���Ȃ��悤�ɒ����B
�Ƃ͂����A���܂蕔���̏Ɩ����Â��ƃ��[�U�[�̐Ԃ��U�����A���肵�����e�_�̌덷���傫���Ȃ�B
�ŁA�ȑO�̃J�����ɖ߂�B�Â߂ō��`�F�b�J�[�ł͂��܂�ǂ��]���ł͖����ߋ��̃��m�ł��邪�A�v�����قLj����Ȃ��Ǝv���B
������A���j�^�[�A�[���ŋ߂��Ɋ��B
OS�̃J�����ݒ�ŘI�o��������x���Ƃ��Ȃ��ƁA���͔��Ȃ̂ŁA
����ł��Ȃ����Ƃ�����悤�ł��B
�܂��A���ł炵���̂ŁA���̂��������ōs�������B
���ƁA�������ԓ��̏e�̃u����V���b�^�[���Ԃ����\���G�ɂ��Ă܂��B
���܂�Ԃ�Ă�ƁA�������Ȃ��悤�ł��ˁB
�g���K�[���d���ƌ��\�Ԃ�܂�����B
240204
�掿�ŕ]�����ǂ����́A���W�N�[����C920n�Ƃ����̂ɂ����B�K���X�����Y�ŁA���������˂Ȃǂ̖��������Ȃ����B
�Â߂̏ꏊ�ƂȂ�̂ŁA�m�C�Y�Ȃǂ��e�����Ȃ��悤�A�Ȃ�ׂ����邢�����Y�̕����A�m�C�Y�ɋ������B
�V���[�e�B���O�����W�̉𑜓x��640x480�ɂ�
���W�̃\�t�g�E�F�A�Ń\�t�g�E�F�A�ōő�Y�[���A�s���g���Œ�B
���Ƃ́A�Â��Ƃ��̃t���[�����[�g�𗎂Ƃ�������OFF�A�����I�o��OFF�ɂ��A�Q�C���Ⴍ�����B
����ŁA������x�ǂ��Ȃ�������ǁA����ς薾�邷����̂��Â�����̂��_�����ۂ��B�p�����^�������̂œ���Ƃ��낪����B
�Ȃ�ׂ��A�O����̌����I�ɉe�����Ȃ������ǂ����Ǝv���B
����ꂽ���i���Ԉ���ĂăJ������C922�Ƃ���������ƌÂ߂������B��{�͎��Ă邪�A�K���X�����Y���ǂ����Ƃ��i���͂ǂ����H
�Ƃ������Ƃŕԕi�葱���B
�Ƃɂ����A���邭�Ė����̏��Ȃ��A�Ƃ�����Ƃ����B�����ĕ���(�^�[�Q�b�g)�͖��邷���Ȃ��悤�ɒ����B
�Ƃ͂����A���܂蕔���̏Ɩ����Â��ƃ��[�U�[�̐Ԃ��U�����A���肵�����e�_�̌덷���傫���Ȃ�B
�ŁA�ȑO�̃J�����ɖ߂�B�Â߂ō��`�F�b�J�[�ł͂��܂�ǂ��]���ł͖����ߋ��̃��m�ł��邪�A�v�����قLj����Ȃ��Ǝv���B
������A���j�^�[�A�[���ŋ߂��Ɋ��B
 �����܂Ŋ��A�t���Ȃǂɂ������Ǝv���B
����ł��A���Ԃ̖��邳�ł͔������Ȃ��H
�^�[�Q�b�g�̃J�����摜���悭���Ă���ƁA�قƂ�nj���Ȃ����A���Ƃ��A�����Ă�t���[���������Ă��������ĂȂ��B
����̓V���b�^�[�X�s�[�h�������āA�������Ȃ��̂��Ǝv���B
�����ŁA�J������ND�t�B���^�[(�j���[�g�����f���V�e�B�[�t�B���^�[)��ND100�����Ă݂��B�܂�A���ʂ�1/100�ɂȂ�B
�^�[�Q�b�g�S�ʂɓn���Ĕ�������悤�ɂȂ����B����������Ɩ��邩������AND500�Ƃ��K�v�����B�܂��A���������낦�ďd�˂Ďg���Ɨǂ������B
�J�����ɍi�肪��������̂����ǂˁB
�������A���邷�����烌�[�U�[���������̂ŁA�����̓^�[�Q�b�g�ɓ��悯���K�v���B
��ɒ��ɂ͉�ND�t�B���^�[������B�F�����͓�肩���ō��i�ʂ̎ʐ^�ɂ͌����Ȃ����ǁA���������g�����Ȃ�OK���ƁB
�����܂Ŋ��A�t���Ȃǂɂ������Ǝv���B
����ł��A���Ԃ̖��邳�ł͔������Ȃ��H
�^�[�Q�b�g�̃J�����摜���悭���Ă���ƁA�قƂ�nj���Ȃ����A���Ƃ��A�����Ă�t���[���������Ă��������ĂȂ��B
����̓V���b�^�[�X�s�[�h�������āA�������Ȃ��̂��Ǝv���B
�����ŁA�J������ND�t�B���^�[(�j���[�g�����f���V�e�B�[�t�B���^�[)��ND100�����Ă݂��B�܂�A���ʂ�1/100�ɂȂ�B
�^�[�Q�b�g�S�ʂɓn���Ĕ�������悤�ɂȂ����B����������Ɩ��邩������AND500�Ƃ��K�v�����B�܂��A���������낦�ďd�˂Ďg���Ɨǂ������B
�J�����ɍi�肪��������̂����ǂˁB
�������A���邷�����烌�[�U�[���������̂ŁA�����̓^�[�Q�b�g�ɓ��悯���K�v���B
��ɒ��ɂ͉�ND�t�B���^�[������B�F�����͓�肩���ō��i�ʂ̎ʐ^�ɂ͌����Ȃ����ǁA���������g�����Ȃ�OK���ƁB
 �ό^�́A�Ό��t�B���^�[�̏d�ˍ��킹�Ȃ̂ŁA�t����p�����V���b�^�[��Q�C�������Ȃǂ̋@�\������A�����Ȃ��J���������邩���B
����߂̌u�������ł��AND100���g���ƒ��e�\���̐��x���オ��悤�ŁA�L�p�ł���B
�Â߂̂Ƃ���ł́A���[�U�[�̋P�_�����邷���Ăɂ���ł��܂��̂��A�R���g���X�g��ʓx�𗎂Ƃ��Ă��Ȃ��Ȃ����x�������������m�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B
�t�H�gDi�̃o�C�A�X���Ă�^�[�Q�b�g�̃Z���T�[��ND�t�B���^�[�ŗ��Ƃ��Ă��ƍs�������ł���B
���̃^�C�v�́A����ȕω����ǂ߂�Ǝv���̂ŁA������������A���˓����ł����m�ł��邩���m��Ȃ��B
240213
�J�����p�Ό��t�B���^�[�͌a���������Ⴍ�Ă����\�Ȓl�i������B���⒆�Âł�����Ȃ�̒l�i���B
�������A�J�����ɂ���čœK�ȃ��m���Ⴄ���낤����A
�����ŁA100�ς̃T���O���X���ǂ���������Ȃ��B�x��������AND100�߂����邩�������A�d�ˈʂ͍s���邾�낤�B
�������������m�Ȃ�O���f�[�V�����̂��������T���O���X�̕����������₷�������B
�����AND�t�B���^�[�̕������|�I�ɋt���ɋ����B
�����A���˖h�~�R�[�g���̐��\�ł���Ǝv���B
���̕��@�́A���ɏ����Ă���悤�A�������̃R���f���T�[�̗e�ʂ�傫�����邱�ƂŁA�������Ԃ�����̂���ł͂���B
�Z���T�[���ɂ́A
�U�d�̑��w��BPF������Ɨǂ����ǁB
�ƁA�v������A���G�N�ł������I�I�A�������Ƒ҂��]��ł������m��ʐ��Y�����̂Ȃ���Z�B�|�s�����[�Ȕg���Ȃ̂ŁA�o�����̂��낤�B
�ό^�́A�Ό��t�B���^�[�̏d�ˍ��킹�Ȃ̂ŁA�t����p�����V���b�^�[��Q�C�������Ȃǂ̋@�\������A�����Ȃ��J���������邩���B
����߂̌u�������ł��AND100���g���ƒ��e�\���̐��x���オ��悤�ŁA�L�p�ł���B
�Â߂̂Ƃ���ł́A���[�U�[�̋P�_�����邷���Ăɂ���ł��܂��̂��A�R���g���X�g��ʓx�𗎂Ƃ��Ă��Ȃ��Ȃ����x�������������m�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B
�t�H�gDi�̃o�C�A�X���Ă�^�[�Q�b�g�̃Z���T�[��ND�t�B���^�[�ŗ��Ƃ��Ă��ƍs�������ł���B
���̃^�C�v�́A����ȕω����ǂ߂�Ǝv���̂ŁA������������A���˓����ł����m�ł��邩���m��Ȃ��B
240213
�J�����p�Ό��t�B���^�[�͌a���������Ⴍ�Ă����\�Ȓl�i������B���⒆�Âł�����Ȃ�̒l�i���B
�������A�J�����ɂ���čœK�ȃ��m���Ⴄ���낤����A
�����ŁA100�ς̃T���O���X���ǂ���������Ȃ��B�x��������AND100�߂����邩�������A�d�ˈʂ͍s���邾�낤�B
�������������m�Ȃ�O���f�[�V�����̂��������T���O���X�̕����������₷�������B
�����AND�t�B���^�[�̕������|�I�ɋt���ɋ����B
�����A���˖h�~�R�[�g���̐��\�ł���Ǝv���B
���̕��@�́A���ɏ����Ă���悤�A�������̃R���f���T�[�̗e�ʂ�傫�����邱�ƂŁA�������Ԃ�����̂���ł͂���B
�Z���T�[���ɂ́A
�U�d�̑��w��BPF������Ɨǂ����ǁB
�ƁA�v������A���G�N�ł������I�I�A�������Ƒ҂��]��ł������m��ʐ��Y�����̂Ȃ���Z�B�|�s�����[�Ȕg���Ȃ̂ŁA�o�����̂��낤�B
 �����Ƃ̃o�����X�ɂāA�L�����Z������8�ɑ��ʂ����B���̂̓J�[�g�ɓ��ꂽ���ǁA���S�g���������Y���Ă鐬�т������̂�����폜�����B
�����A���l����50nm�ƍL�߁B40nm�̂����������Ǒ債�ĕς��Ȃ���Ɋ����������BLD�g���ш�̕ω��Ȃǂ��l���A�i�K�I�Ɍ��Ă������Ǝv���B
�܂��A�V�O�}���@�Ƃ��ɂ͔��l���ꌅ�̂��I�[�_�[���C�h�ł������Ǝv�����A�A������LD�͒��S�g������s����Ȃ̂ŁA���̂��炢���������������ǂ����낤�B
�����}���C��G17Gen5MOS�ƃt�B���K�[�A�N�V�����u���[�o�b�N��G17�̉���
�����}���C��GLOCK17Gen5MOS�̃��R�C���̋����́A�����X���C�h��[�̋����̏d�肾�Ǝv���B
����́A�y���X���C�h�ɕt���Ă�Ƃ�������������B
�܂胍�A�C���i�[�t���[����(��q�̂��̂������)�Ԃ���̕����������̏d��Ȃ̂ŁA�X���C�h�ɕ��S��������Ȃ�����Ƃ��������B
�����ă��R�C��SP����ɃS�������܂��Ă����āA������x�V���[�v�ł��A�ߏ�ɉs���Ռ��͊ɘa����@�\���ƁB
�K�X�K���́A���R�C�����X���C�h�ōs���Ă邽�߁B���e�������������������Ă�\�������蓾�邩�ƁB
����āA�X���C�h�ɓ��ڂ���_�b�g�T�C�g�̑ϏՌ����͌��\�K�v���ȁH�Ƃ��v���B
�̔�����M4RIS�́ATN�o�����A�`�����o�[�ɂ͓d�C�Ȃ܂�������Ă������A�R�������鐸�x�݂����B�Ȃ܂�����ꂽL96AWS�����邯�ǂ���������邩���H
�Œ�e�g�̃G�A�\�t�g�K����������A�����ƒZ�e�ł͒Nj����Ă��A���قǕς��Ȃ��̂����B
�ł�G17�̓K�X�Ȃ̂ɍ����x���Ȃ̂͂ƂĂ������B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�����t�B���K�[�A�N�V�����u���[�o�b�N�ȓz
�����Ƃ̃o�����X�ɂāA�L�����Z������8�ɑ��ʂ����B���̂̓J�[�g�ɓ��ꂽ���ǁA���S�g���������Y���Ă鐬�т������̂�����폜�����B
�����A���l����50nm�ƍL�߁B40nm�̂����������Ǒ債�ĕς��Ȃ���Ɋ����������BLD�g���ш�̕ω��Ȃǂ��l���A�i�K�I�Ɍ��Ă������Ǝv���B
�܂��A�V�O�}���@�Ƃ��ɂ͔��l���ꌅ�̂��I�[�_�[���C�h�ł������Ǝv�����A�A������LD�͒��S�g������s����Ȃ̂ŁA���̂��炢���������������ǂ����낤�B
�����}���C��G17Gen5MOS�ƃt�B���K�[�A�N�V�����u���[�o�b�N��G17�̉���
�����}���C��GLOCK17Gen5MOS�̃��R�C���̋����́A�����X���C�h��[�̋����̏d�肾�Ǝv���B
����́A�y���X���C�h�ɕt���Ă�Ƃ�������������B
�܂胍�A�C���i�[�t���[����(��q�̂��̂������)�Ԃ���̕����������̏d��Ȃ̂ŁA�X���C�h�ɕ��S��������Ȃ�����Ƃ��������B
�����ă��R�C��SP����ɃS�������܂��Ă����āA������x�V���[�v�ł��A�ߏ�ɉs���Ռ��͊ɘa����@�\���ƁB
�K�X�K���́A���R�C�����X���C�h�ōs���Ă邽�߁B���e�������������������Ă�\�������蓾�邩�ƁB
����āA�X���C�h�ɓ��ڂ���_�b�g�T�C�g�̑ϏՌ����͌��\�K�v���ȁH�Ƃ��v���B
�̔�����M4RIS�́ATN�o�����A�`�����o�[�ɂ͓d�C�Ȃ܂�������Ă������A�R�������鐸�x�݂����B�Ȃ܂�����ꂽL96AWS�����邯�ǂ���������邩���H
�Œ�e�g�̃G�A�\�t�g�K����������A�����ƒZ�e�ł͒Nj����Ă��A���قǕς��Ȃ��̂����B
�ł�G17�̓K�X�Ȃ̂ɍ����x���Ȃ̂͂ƂĂ������B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�����t�B���K�[�A�N�V�����u���[�o�b�N�ȓz
 �Ƃɂ����g���K�[���d�����A�g���u���Ƃ��āA�g���K�[�X�v�����O���܂�₷���Ƃ̂��ƁB
�Ȃ̂ŁA��߂������ǂ����낤�Ɣ��f�B
�����ŁA�܂��A���R�C���X�v�����O�́A�����͎ア�����͂܂��Ă���B
������A53mm���x�ɐ�l�߂��B����55mm���x�̕����ǂ������̂ł��ƂŐL������SP�̊p�t�߂�܂�Ȃ��đS���������B�����̃o�l�͗]�T������̂łւ���Ȃ����g���K�[�X�v�����O�͔�J���郌�x���Ȃ̂ł��̒������ł��Ȃ��B
(���܂�Z�����ĐL���Ə������͒Ⴂ���A�o�l�̃��[�g���オ���Ă��܂��̂�����B)
���Ƀg���K�[�X�v�����O�A������O��ނ��邪�A�ŏ��ɂ͂܂��Ă�̂��g���B
(�s�b�`�ׂ̍����ア�̂͐�Ȃ����Ă��t���X�g���[�N�s���Ȃ��d�l�ł���̂ŏ��O�B)
�����31.5mm���x�ɂ��Ă݂��炤�܂����������B�������p���Ȃ��Ē�������33mm���x�ɉ��������B�����ɑ��Č��\�V�r�A�Ȃ̂ŁA���ӁB���ƈ��������ĐL���̂����܂�ǂ��Ȃ��Ǝv���B30mm�ɂ��Ă�OK����������1�o�ł��Ȃ�ς��̂Œ��ӁB
�����Ȃ̂ŁA�J�[�g����ĉ��������Č����Ă��A�����ƃt���X�g���[�N�s���悤�ɂ��Ă����Ɨǂ��Ƃ͎v���B�B
�܂��A�Œ��������Ɖ��������x�Ńt���X�g���[�N�s���悤�ɁB
���ƁABLK�̋�U��͗ǂ��Ȃ��炵���̂ŁA�|�[�g�����S������悤�X���C�h��V���[�g���R�C���@�\���ǂ��������Ă����B
�g���K�[�����������镔���̈�ԋɈ����d�������镔���́AGRP�^�b�N�O���X���g�������A�x���n���}�[�Ƃ����ǂ������B
�ȏ�Ńg���K�[�͌��\�y���͏o����B
�s���ɂȂ�����A��ꂽ�肷��O�ɍs���Ɨǂ��Ƃ����B
�d�l�͍���ς�邩���m��Ȃ��̂ŁA�T�d�ɁB
���ɁA�g���K�[�A�b�Z���u���̋Ɉ����������Ղ���ƁA
�O���̃t���b�v��SW�������グ�āA�g���K����u���[�o�b�N�̂Ƀ��O���N����悤�ł���B
�g���K�[�X�v�����O��肷���Ă��܂�����A��Ńw�^���Ă��Ď|�����삵�Ȃ��ꍇ�B
�g���K�[�X�v�����O�Ƀv���ȂǃX�y�[�T�[���͂߂�Ɨǂ������B
�����˂̒[�́A���������Ďg���Ă��������ɏ����Ȃ���悤�Ȃ̂ŁA�\�R���v�Z�ɓ��ꂽ�����ǂ��悤�ł���B
�g���K�[�X�v�����O��肷�����ꍇ�́A���������グ�邽�߃v���o���Ȃǂ̔����߂C�P�邩���B
�x���n���}�[�͂��Ȃ�g���K�[���y������B
�ގ��i��AZ�̒��Ɉ��Ȃǂ���悤���B
�����ǁA100���������Ȃ����炢�Ŗ��̏�������Ă���B
�O���X�^�C�v���ǂ����ǁB�B
AZ����CKM-002���t�̂ō����\�BCKG-002���O���X�^�C�v�B
���ƁA�g���K�[�Ƃ��̎��̊Ԃ̏������C�����Ȃ��ƁA
�g���K�[�ɂ�����ƃK�^������C������B
���ƁA�g���K�[�X�v�����O�A�[�����̊p�𗧂ĂĂ����Ԃ��o�ƐQ��悤�ł��B�Ȃ̂�1�o���傢�`2mm�]�T�������Đؒf���������ǂ��ł��B
�����̏ꍇ�́A3mm�˂��̃i�b�g�������ǁA
����őg�ݍ��ނ܂łɃo�l���ƊO��ĂԂ���т₷���̂Œ��ӁB
(�ڒ����邩�A�܂̒��ł���������ǂ��B)
�Ƃ���ŁA������Ă̓X���C�h�X�g�b�v���������Ă���A���������肪���āA�X�g�b�v���Ȃ��Ȃ����B
�}���C��G17�̂悤�ɁA�������Ȃɂ��ŗ��ł��Ƃ��H
------------------------------------
���[�U�[�̒��������ǁA
���W���[���̐�[���˂��ɃS��������ŃA���B
���ꂪ�킩������A�V���[�e�B���O�����W�I�����C���Œ��e�_�ƃA�C�A���T�C�g�ƍ��킷���Ƃ��ł����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
240228
���[�U�[���p��BPF���͂����̂ʼn����Ή��̑�ʐ�PIN�t�H�gDi(�s�[�N��960nm)��S6775�ɐݒu����
���l����50nm�A�U�d�̑��w���Ǝv����
�Ƃɂ����g���K�[���d�����A�g���u���Ƃ��āA�g���K�[�X�v�����O���܂�₷���Ƃ̂��ƁB
�Ȃ̂ŁA��߂������ǂ����낤�Ɣ��f�B
�����ŁA�܂��A���R�C���X�v�����O�́A�����͎ア�����͂܂��Ă���B
������A53mm���x�ɐ�l�߂��B����55mm���x�̕����ǂ������̂ł��ƂŐL������SP�̊p�t�߂�܂�Ȃ��đS���������B�����̃o�l�͗]�T������̂łւ���Ȃ����g���K�[�X�v�����O�͔�J���郌�x���Ȃ̂ł��̒������ł��Ȃ��B
(���܂�Z�����ĐL���Ə������͒Ⴂ���A�o�l�̃��[�g���オ���Ă��܂��̂�����B)
���Ƀg���K�[�X�v�����O�A������O��ނ��邪�A�ŏ��ɂ͂܂��Ă�̂��g���B
(�s�b�`�ׂ̍����ア�̂͐�Ȃ����Ă��t���X�g���[�N�s���Ȃ��d�l�ł���̂ŏ��O�B)
�����31.5mm���x�ɂ��Ă݂��炤�܂����������B�������p���Ȃ��Ē�������33mm���x�ɉ��������B�����ɑ��Č��\�V�r�A�Ȃ̂ŁA���ӁB���ƈ��������ĐL���̂����܂�ǂ��Ȃ��Ǝv���B30mm�ɂ��Ă�OK����������1�o�ł��Ȃ�ς��̂Œ��ӁB
�����Ȃ̂ŁA�J�[�g����ĉ��������Č����Ă��A�����ƃt���X�g���[�N�s���悤�ɂ��Ă����Ɨǂ��Ƃ͎v���B�B
�܂��A�Œ��������Ɖ��������x�Ńt���X�g���[�N�s���悤�ɁB
���ƁABLK�̋�U��͗ǂ��Ȃ��炵���̂ŁA�|�[�g�����S������悤�X���C�h��V���[�g���R�C���@�\���ǂ��������Ă����B
�g���K�[�����������镔���̈�ԋɈ����d�������镔���́AGRP�^�b�N�O���X���g�������A�x���n���}�[�Ƃ����ǂ������B
�ȏ�Ńg���K�[�͌��\�y���͏o����B
�s���ɂȂ�����A��ꂽ�肷��O�ɍs���Ɨǂ��Ƃ����B
�d�l�͍���ς�邩���m��Ȃ��̂ŁA�T�d�ɁB
���ɁA�g���K�[�A�b�Z���u���̋Ɉ����������Ղ���ƁA
�O���̃t���b�v��SW�������グ�āA�g���K����u���[�o�b�N�̂Ƀ��O���N����悤�ł���B
�g���K�[�X�v�����O��肷���Ă��܂�����A��Ńw�^���Ă��Ď|�����삵�Ȃ��ꍇ�B
�g���K�[�X�v�����O�Ƀv���ȂǃX�y�[�T�[���͂߂�Ɨǂ������B
�����˂̒[�́A���������Ďg���Ă��������ɏ����Ȃ���悤�Ȃ̂ŁA�\�R���v�Z�ɓ��ꂽ�����ǂ��悤�ł���B
�g���K�[�X�v�����O��肷�����ꍇ�́A���������グ�邽�߃v���o���Ȃǂ̔����߂C�P�邩���B
�x���n���}�[�͂��Ȃ�g���K�[���y������B
�ގ��i��AZ�̒��Ɉ��Ȃǂ���悤���B
�����ǁA100���������Ȃ����炢�Ŗ��̏�������Ă���B
�O���X�^�C�v���ǂ����ǁB�B
AZ����CKM-002���t�̂ō����\�BCKG-002���O���X�^�C�v�B
���ƁA�g���K�[�Ƃ��̎��̊Ԃ̏������C�����Ȃ��ƁA
�g���K�[�ɂ�����ƃK�^������C������B
���ƁA�g���K�[�X�v�����O�A�[�����̊p�𗧂ĂĂ����Ԃ��o�ƐQ��悤�ł��B�Ȃ̂�1�o���傢�`2mm�]�T�������Đؒf���������ǂ��ł��B
�����̏ꍇ�́A3mm�˂��̃i�b�g�������ǁA
����őg�ݍ��ނ܂łɃo�l���ƊO��ĂԂ���т₷���̂Œ��ӁB
(�ڒ����邩�A�܂̒��ł���������ǂ��B)
�Ƃ���ŁA������Ă̓X���C�h�X�g�b�v���������Ă���A���������肪���āA�X�g�b�v���Ȃ��Ȃ����B
�}���C��G17�̂悤�ɁA�������Ȃɂ��ŗ��ł��Ƃ��H
------------------------------------
���[�U�[�̒��������ǁA
���W���[���̐�[���˂��ɃS��������ŃA���B
���ꂪ�킩������A�V���[�e�B���O�����W�I�����C���Œ��e�_�ƃA�C�A���T�C�g�ƍ��킷���Ƃ��ł����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
240228
���[�U�[���p��BPF���͂����̂ʼn����Ή��̑�ʐ�PIN�t�H�gDi(�s�[�N��960nm)��S6775�ɐݒu����
���l����50nm�A�U�d�̑��w���Ǝv����
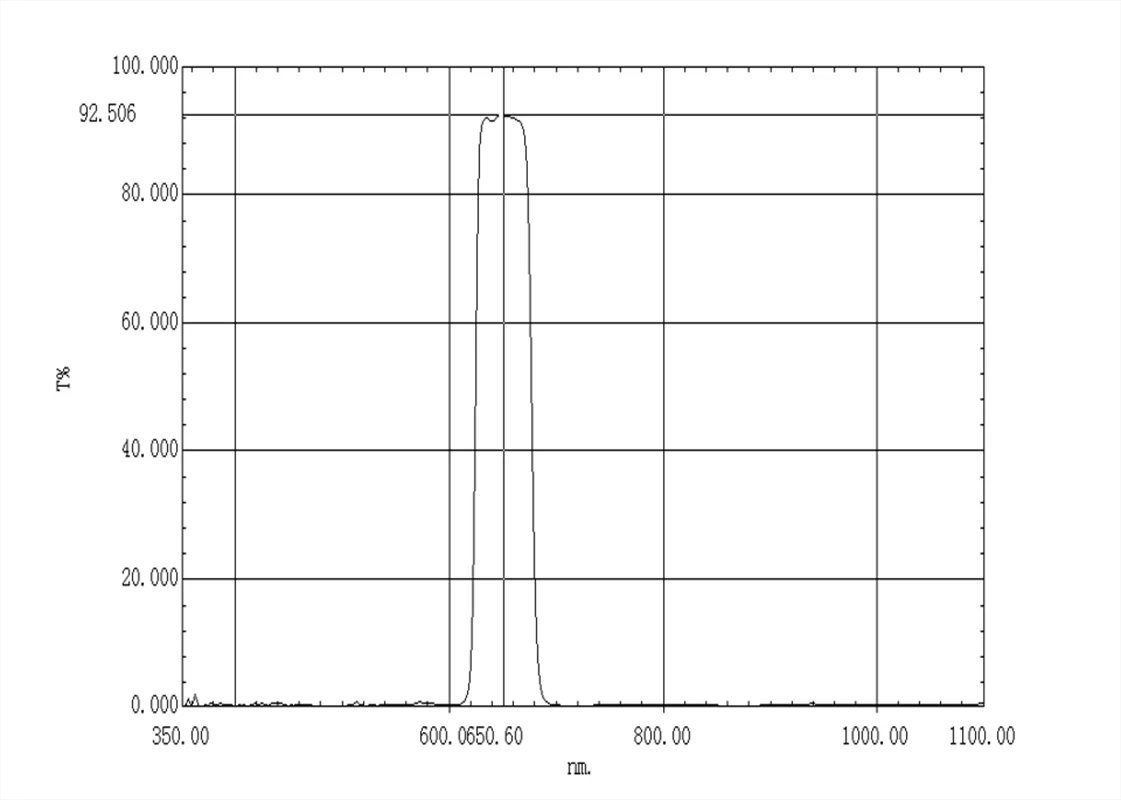 �K���X�͗��\������̂ŁA�R�[�g�ʂ�ڒ��ʂɂ���B�ڒ��܂�SU�\�t�g�̃N���A�[�B(�͂ݏo���������낤�ƈ�������Ɛڒ��ʂ܂Ŕ����ɋy�Ԏ�������B)
G�N���A�[���g���邩�������ǁB
�t�B���^�[��6mm�p�Ȃ̂ł҂�����ł���B
�K���X�͗��\������̂ŁA�R�[�g�ʂ�ڒ��ʂɂ���B�ڒ��܂�SU�\�t�g�̃N���A�[�B(�͂ݏo���������낤�ƈ�������Ɛڒ��ʂ܂Ŕ����ɋy�Ԏ�������B)
G�N���A�[���g���邩�������ǁB
�t�B���^�[��6mm�p�Ȃ̂ł҂�����ł���B
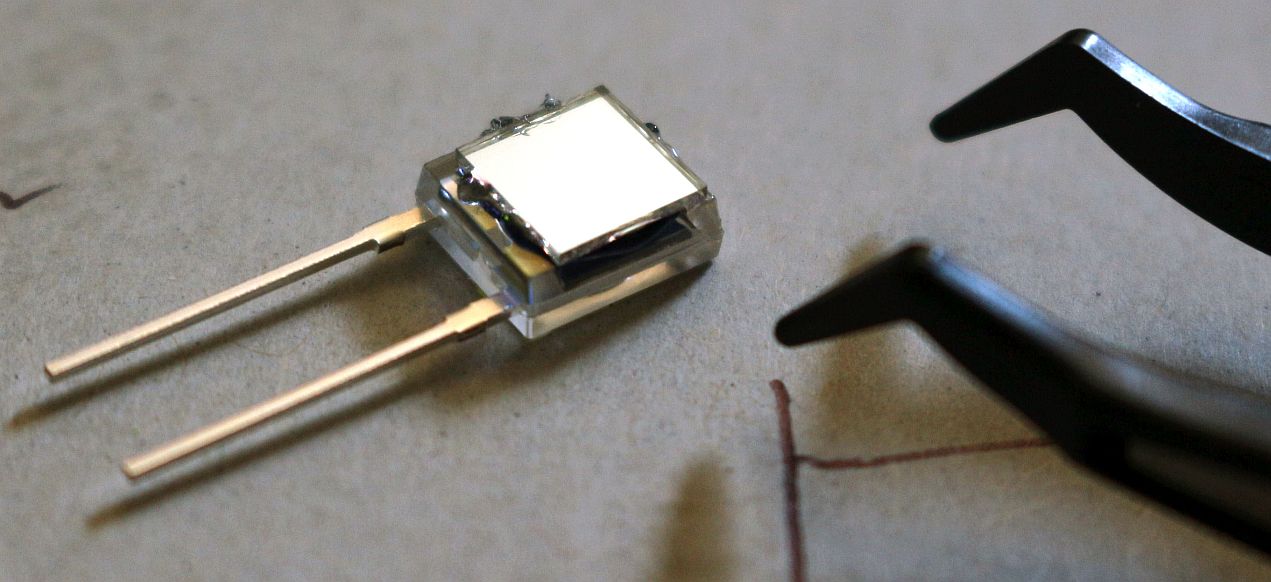 �t�H�gDi�̃Z���^�[�ɏ������炵�A�t�B���^�[���ڂ���������B
���܂苭�����ƁA�e�͂�䂪�݂���C�A������B�������Ă��ǂ����낤���ǁA��ɏq�ׂ�Ռ��h��������ƕs�����B
���Ƃ́A���S�d����A�N���t�g�i�C�t�Ȃǂł͂ݏo���ڒ��܂𗎂Ƃ��B
����ʂɃt�B���^�[�Ƃ̌��Ԃ���̌����R�ꍬ�܂Ȃ��悤�Ɏ���Ɂu�Ռ��h���v��h��B
�u���f���J�X�e�� �I���W�i���J���[�V���[�Y �d���p �Ռ��u���b�NPRO 50ml �͌^�p�h�� C-23�v
�t�H�gDi�̃Z���^�[�ɏ������炵�A�t�B���^�[���ڂ���������B
���܂苭�����ƁA�e�͂�䂪�݂���C�A������B�������Ă��ǂ����낤���ǁA��ɏq�ׂ�Ռ��h��������ƕs�����B
���Ƃ́A���S�d����A�N���t�g�i�C�t�Ȃǂł͂ݏo���ڒ��܂𗎂Ƃ��B
����ʂɃt�B���^�[�Ƃ̌��Ԃ���̌����R�ꍬ�܂Ȃ��悤�Ɏ���Ɂu�Ռ��h���v��h��B
�u���f���J�X�e�� �I���W�i���J���[�V���[�Y �d���p �Ռ��u���b�NPRO 50ml �͌^�p�h�� C-23�v
 (�v���C�}�[�������Ɣ�����₷���B)
���߂��Ȃ����m�͔��˂���悤�Ȃ̂ŁA
�摜��͂ɂ́A������n�[�t�~���[�I�Ɉ����āA���������_����o�������B
����ȈՁA�����p���X�������̕��́A�t�o�C�A�X��H��47mH���q�����B�܂�A�f�����M���͓������Ȃ��Ƃ����l���B
(�v���C�}�[�������Ɣ�����₷���B)
���߂��Ȃ����m�͔��˂���悤�Ȃ̂ŁA
�摜��͂ɂ́A������n�[�t�~���[�I�Ɉ����āA���������_����o�������B
����ȈՁA�����p���X�������̕��́A�t�o�C�A�X��H��47mH���q�����B�܂�A�f�����M���͓������Ȃ��Ƃ����l���B
 ���j�b�g�̌����̃Y�����C�������ꂸ�ł����̂Ń[���C���ł������ɂȂ��̂ŁA�_�b�g�T�C�g�ɐ�ւ����B
240301�|PM1�F20
�Z���T�[�˓������ɐݒu����悤�Ȕ�펯�ȉߍ����̏Ńe�X�g�A�������邪LED�����ɂ��������̂ŁA���Ƃ��A�ʂ̕\�����ǂ������B
�܂��A�A�̓�����Ō�쓮������݂����B
�r�j�e��K���X�I�Ȃ���������Ɠ��ߌ����̗ǂ��g�U�t�B���^�[�ɂ��āA�Z���T�[���̂ɂ͒��˓����ւ̓�����������t����B
�t�o�C�A�X�ȓd���̏㏸��A�����ƐM��������������g���t�B���^�[�ȂǂŎg���Ηǂ��Ǝv���B
���}�I�ɂ�ND�t�B���^�[���\�����ǁA���[�U�[����܂�̂ŁA���}�I��i�ƂȂ�B
650nmBPF�̓d�˂͂ǂ��Ȃ邩�ȁH
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
240308
���˓������ł̂���Ȃ鎎��
�V���v���Ȕ�����H�ł̎����B
�t�H�gDi�ւ̋t�o�C�A�X���R�������Ȃ��ƐG�����肵���Ƃ��̃m�C�Y�Ō�쓮�A���B
(�����ƃV�[���h�P�[�X�ɓ���Ă�Ζ��Ȃ������A����Ƀ��[�U�[�ɐM�����悹���OK����)
�t�o�C�A�X��R3K�����x�����Ƃ����ȁB
���j�b�g�̌����̃Y�����C�������ꂸ�ł����̂Ń[���C���ł������ɂȂ��̂ŁA�_�b�g�T�C�g�ɐ�ւ����B
240301�|PM1�F20
�Z���T�[�˓������ɐݒu����悤�Ȕ�펯�ȉߍ����̏Ńe�X�g�A�������邪LED�����ɂ��������̂ŁA���Ƃ��A�ʂ̕\�����ǂ������B
�܂��A�A�̓�����Ō�쓮������݂����B
�r�j�e��K���X�I�Ȃ���������Ɠ��ߌ����̗ǂ��g�U�t�B���^�[�ɂ��āA�Z���T�[���̂ɂ͒��˓����ւ̓�����������t����B
�t�o�C�A�X�ȓd���̏㏸��A�����ƐM��������������g���t�B���^�[�ȂǂŎg���Ηǂ��Ǝv���B
���}�I�ɂ�ND�t�B���^�[���\�����ǁA���[�U�[����܂�̂ŁA���}�I��i�ƂȂ�B
650nmBPF�̓d�˂͂ǂ��Ȃ邩�ȁH
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
240308
���˓������ł̂���Ȃ鎎��
�V���v���Ȕ�����H�ł̎����B
�t�H�gDi�ւ̋t�o�C�A�X���R�������Ȃ��ƐG�����肵���Ƃ��̃m�C�Y�Ō�쓮�A���B
(�����ƃV�[���h�P�[�X�ɓ���Ă�Ζ��Ȃ������A����Ƀ��[�U�[�ɐM�����悹���OK����)
�t�o�C�A�X��R3K�����x�����Ƃ����ȁB

 ���ׂĂ���������Ē��˂Ń`�F�b�N�B����ł����삷��B
���ׂĂ���������Ē��˂Ń`�F�b�N�B����ł����삷��B
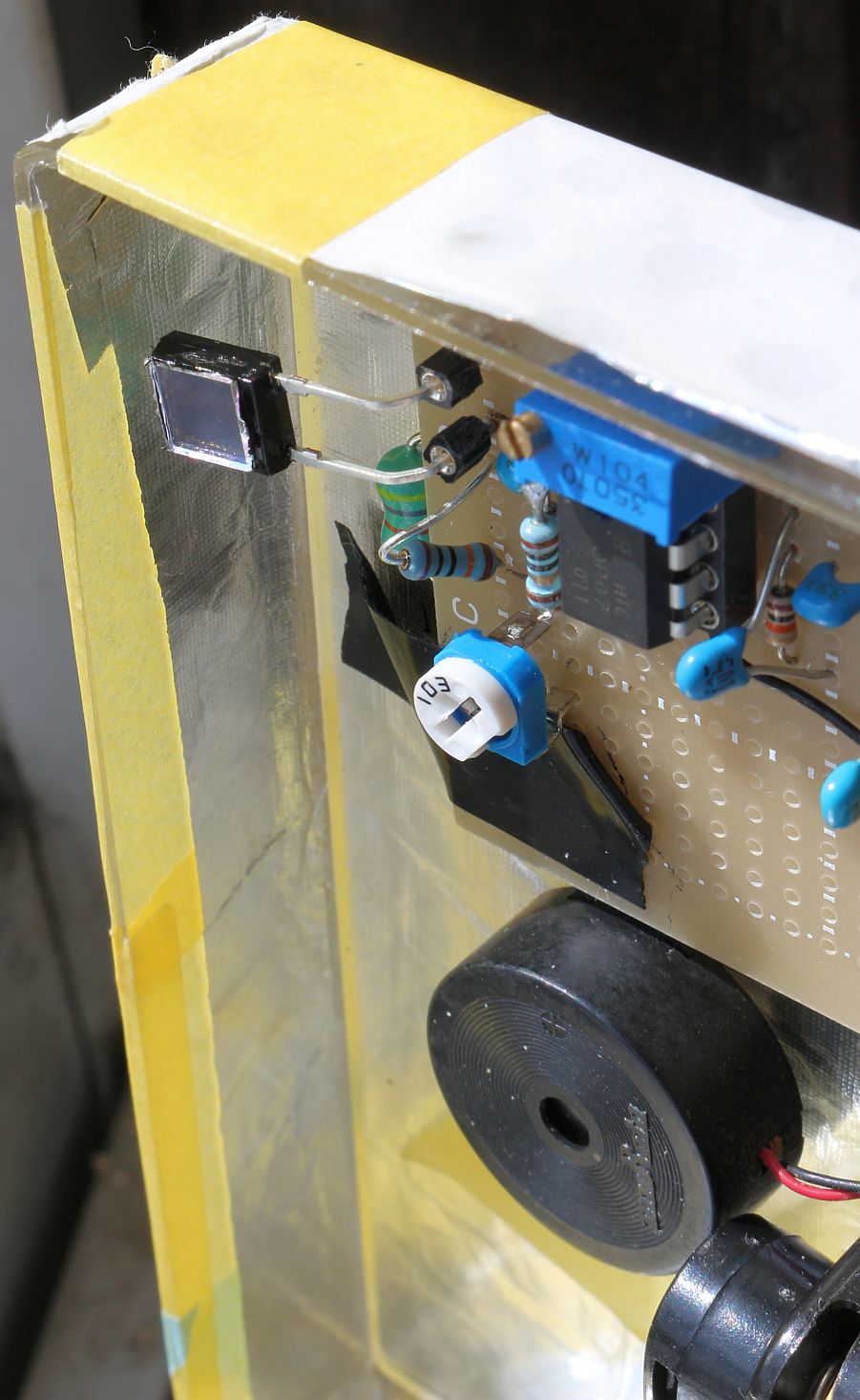 ����́A���[�U�[�ɐM�����̂���A���Ȃ���҂����܂�Ƃ��낾�B
�\�z�����̂́A�������̋���6�����{�H�̒��˂����ǂ����܂ʼnߍ��ɂ���K�v������̂��s���B�B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
240313
���[�U�[�����e�̎���e�X�g�Ƃ��̌�̗\��B
�����H��M�����B
3�i�����ƁA�������̊g�傾�B���荇�킹�ŁA�ݒ��20���{�܂ŏo���邪�A�I�[�v�����[�v�Q�C���������܂Ŗ����̂ŁB
�܂��AOP07��ł͌��x���A���B�ᑬ�����B�ł��A���[�U�[�����ȈՔ�����H���ɉ�H�̍���������K�v���Ȃ������B
����́A���[�U�[�ɐM�����̂���A���Ȃ���҂����܂�Ƃ��낾�B
�\�z�����̂́A�������̋���6�����{�H�̒��˂����ǂ����܂ʼnߍ��ɂ���K�v������̂��s���B�B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
240313
���[�U�[�����e�̎���e�X�g�Ƃ��̌�̗\��B
�����H��M�����B
3�i�����ƁA�������̊g�傾�B���荇�킹�ŁA�ݒ��20���{�܂ŏo���邪�A�I�[�v�����[�v�Q�C���������܂Ŗ����̂ŁB
�܂��AOP07��ł͌��x���A���B�ᑬ�����B�ł��A���[�U�[�����ȈՔ�����H���ɉ�H�̍���������K�v���Ȃ������B
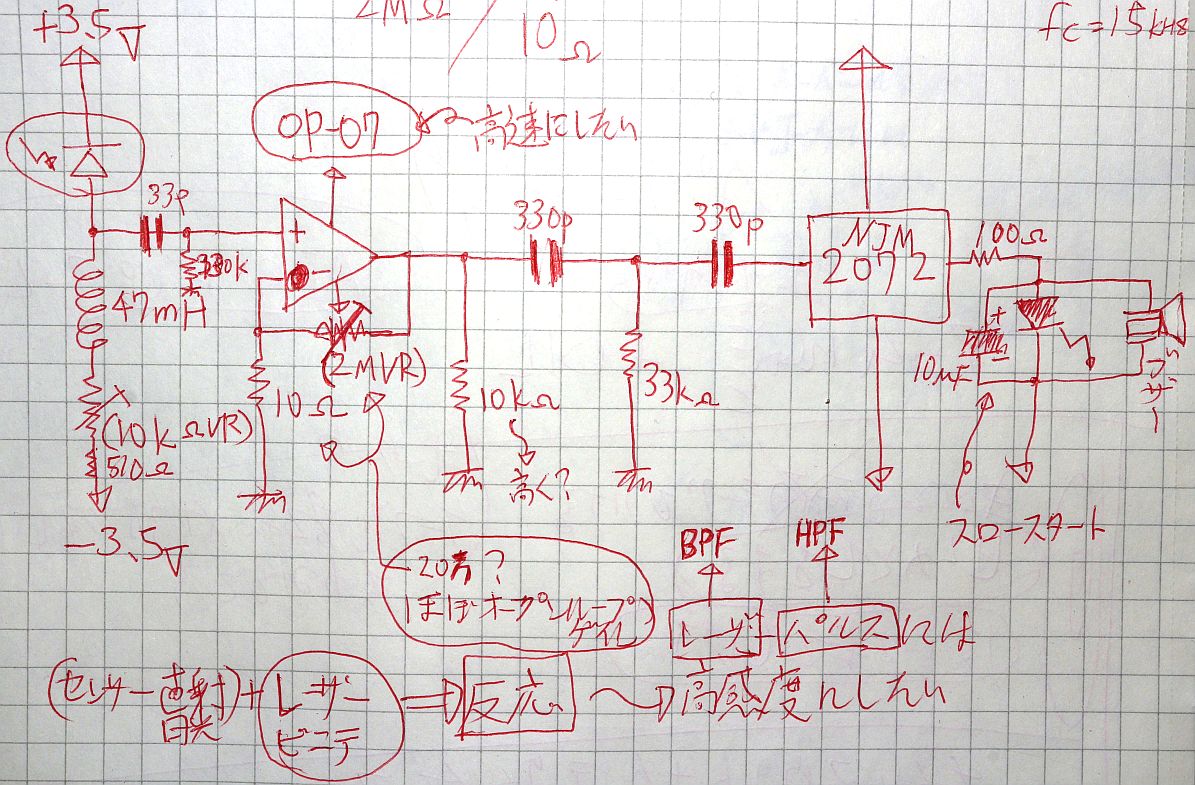 ���iOP07�̓��͎�O��330K����100K���֕ύX���Ă���B
24/03/10�FPM12�F15
�u�Z���T�[���́v�ɒ��˓����ĂȂ���A�ꉞ�A���߂ƕ��U�̃o�����X�̗ǂ������ȁu�g���[�V���O�y�[�p�[�v�Ƀ��[�U�[�Ă�B
���iOP07�̓��͎�O��330K����100K���֕ύX���Ă���B
24/03/10�FPM12�F15
�u�Z���T�[���́v�ɒ��˓����ĂȂ���A�ꉞ�A���߂ƕ��U�̃o�����X�̗ǂ������ȁu�g���[�V���O�y�[�p�[�v�Ƀ��[�U�[�Ă�B
 �g���y�����ł����쓮�͖������낤�ƌ������ƂŁA���蓾�Ȃ��قǂ̈������̃e�X�g�ŃA���B
�e��[����Z���T�[�܂Ŗ�11m���傢�B���ʂɔ�������B���\m�Ȃ�A�傫���L����Ȃ��̂ŁA��������Ǝv���B
��100m�`1Km�ȏ�Ȃ烌�[�U�[�r�[���́u�R�����[�^�[�v���悾�Ǝv���B
6V����̋t�o�C�A�X�d���͏\���̂悤���B��R�͖�1.5K���ł���B47mH������B
������3�i�K�������˂��A��őf�����`���b�s���O����Ɣ������銴���B
�����āAPWM����LED���C�g�́A���m�ɂ���Ă͋߂Â���Ɣ�������B
�����́A�A�����Ȃ̂�650nm���܂�ł�̂ŁA�A
�����Ɖs��HPF(������H)�ł�����x�����\���Ƃ͎v�����ǁB
���ƁA�ԊO�����R����1m�s���Ȃ��B����́A650nm���ア�̂ƁAOP07������ł̑������Ɍ��E���A���B
�R����ւ̑Ώ��ɂ́A���[�U�[�̍����g���U�Ɠd�C�M���n��BPF��K�v�Ƃ���B
�ȒP�ɂ́A�����R��������j�b�g�pIC��T���āA���̎��g����LD�U���Ă��B
�������������ł͖����Ȃ�ARF�A���v��455KHz��10.7MHz��IF���g���t�B���^�[�ŁA���̂܂܁B
�d�x���ƁA60MHz�ϒ��̃p���X���U���[�U�[������ŁAFCZ�R�C���Ȃǂ��g�������iAMP��MIX��H��t����IF���g���ɗ��Ƃ����g�B�V�O�i�����x����ǂފ����B
���[�U�[��60MHz������H�͊��ɏo���Ă邪�A������́AAGC��H�݂͐����A���g���āA���x�����m����Ηǂ����ȁH
Mix��H��IF�t�B���^�[���߂�ǂ����B�t��IF�t�B���^�[�̎��g���Ŕ��U��������@�����邯�nj|���������A�R�C�������ʓ|�B
�`�b�v�ȁAFET�AIC�̓A���Ȃ̂ŁA��قǂ̂��Ƃ�������ADIP�X�P�[���̊�ōs�����Ǝv���܂��B
���[�U�[�̓T�o�Q�I�d�l�ɂ͌������A�I���Ăɗǂ������ŃA���B
���[�U�[�̃R�����[�^�[�̃����Y���A���G�N�ɒ������Ă݂��B
300mm�A75mm�A50mm�����Y�ŃA���B
���������A�J��5V��LD���W���[���A��ʒ������i�ł́A�A���J���{�^���d�r4��6V�쓮�������悤�ŁB
�����A6V�œK���Ɏg����悤�ɁA��R�lj��Ƃ��͂Ȃ��̂ŁA����ɑς������v��������̂��ȁH
�|�|�|�|�|�|�|�|
�NjL����
10�����O���A������82����0.1��F�̃f�B�X�N�^�P�w�Z���R���̕���Ɍ����B
�̂ɁA4�i�̔����ɂ����B
����ŃQ�C�����ēx����������A
���˓�������ő����`���b�s���O���Ă��قڔ��������ɂȂ����B
�����R������[�U�[�����e�ł́A�t�Ɋ��x�������オ�����悤�ł���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
240314
�����Y�������B
�g���y�����ł����쓮�͖������낤�ƌ������ƂŁA���蓾�Ȃ��قǂ̈������̃e�X�g�ŃA���B
�e��[����Z���T�[�܂Ŗ�11m���傢�B���ʂɔ�������B���\m�Ȃ�A�傫���L����Ȃ��̂ŁA��������Ǝv���B
��100m�`1Km�ȏ�Ȃ烌�[�U�[�r�[���́u�R�����[�^�[�v���悾�Ǝv���B
6V����̋t�o�C�A�X�d���͏\���̂悤���B��R�͖�1.5K���ł���B47mH������B
������3�i�K�������˂��A��őf�����`���b�s���O����Ɣ������銴���B
�����āAPWM����LED���C�g�́A���m�ɂ���Ă͋߂Â���Ɣ�������B
�����́A�A�����Ȃ̂�650nm���܂�ł�̂ŁA�A
�����Ɖs��HPF(������H)�ł�����x�����\���Ƃ͎v�����ǁB
���ƁA�ԊO�����R����1m�s���Ȃ��B����́A650nm���ア�̂ƁAOP07������ł̑������Ɍ��E���A���B
�R����ւ̑Ώ��ɂ́A���[�U�[�̍����g���U�Ɠd�C�M���n��BPF��K�v�Ƃ���B
�ȒP�ɂ́A�����R��������j�b�g�pIC��T���āA���̎��g����LD�U���Ă��B
�������������ł͖����Ȃ�ARF�A���v��455KHz��10.7MHz��IF���g���t�B���^�[�ŁA���̂܂܁B
�d�x���ƁA60MHz�ϒ��̃p���X���U���[�U�[������ŁAFCZ�R�C���Ȃǂ��g�������iAMP��MIX��H��t����IF���g���ɗ��Ƃ����g�B�V�O�i�����x����ǂފ����B
���[�U�[��60MHz������H�͊��ɏo���Ă邪�A������́AAGC��H�݂͐����A���g���āA���x�����m����Ηǂ����ȁH
Mix��H��IF�t�B���^�[���߂�ǂ����B�t��IF�t�B���^�[�̎��g���Ŕ��U��������@�����邯�nj|���������A�R�C�������ʓ|�B
�`�b�v�ȁAFET�AIC�̓A���Ȃ̂ŁA��قǂ̂��Ƃ�������ADIP�X�P�[���̊�ōs�����Ǝv���܂��B
���[�U�[�̓T�o�Q�I�d�l�ɂ͌������A�I���Ăɗǂ������ŃA���B
���[�U�[�̃R�����[�^�[�̃����Y���A���G�N�ɒ������Ă݂��B
300mm�A75mm�A50mm�����Y�ŃA���B
���������A�J��5V��LD���W���[���A��ʒ������i�ł́A�A���J���{�^���d�r4��6V�쓮�������悤�ŁB
�����A6V�œK���Ɏg����悤�ɁA��R�lj��Ƃ��͂Ȃ��̂ŁA����ɑς������v��������̂��ȁH
�|�|�|�|�|�|�|�|
�NjL����
10�����O���A������82����0.1��F�̃f�B�X�N�^�P�w�Z���R���̕���Ɍ����B
�̂ɁA4�i�̔����ɂ����B
����ŃQ�C�����ēx����������A
���˓�������ő����`���b�s���O���Ă��قڔ��������ɂȂ����B
�����R������[�U�[�����e�ł́A�t�Ɋ��x�������オ�����悤�ł���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
240314
�����Y�������B
 75mm�́A�~�X�Łu-75mm�v�ʼn��ʂ������B
���A�l���Ă݂�A�R���̂ق����R���p�N�g�ɑg�߂邩���B
�ŁA�R���p�N�g�ɏo����̂��낤���ǂ��łɍ���Ă������͂ł����B�B
�Ε������Y�I�ȕ����̓��a40mm�̋����ɕt����ɂ́A�O�`50mm�̃����Y�͑傫���ȁ[�Ƃ��B
�T�C�Y�͗Z�ʌ����V���b�v�ł͂Ȃ������̂ŁA�A
�i�O�̓P���R�[��f=330mm�̂ł҂�����Ȃ̂��g���Ă����A���Œ��Ԃ������e�[�v���Ń����Y���O��Ăĕ�����ԁB
���m�R�[�g�Ƃ��`��A���x�͂��邯�ǒl�i�����\�{���Ⴄ�̂ŁA�A�j
���[�U�[�̍L������l����ƁA�Ε������Y�a��3�p�ʂł����������B
�`�F�b�N�p��H�B
�A�����ƃ����V���b�g�p���X���o���郂�m�B
5V�p���[�U�[���W���[���ɁA�A���J��4�{��6V��������ɁALD���̂�2V�Ƃ��āA���W���[�����̓�����91���Ɍp��������33�����K�v�Ƃ݂āA
75mm�́A�~�X�Łu-75mm�v�ʼn��ʂ������B
���A�l���Ă݂�A�R���̂ق����R���p�N�g�ɑg�߂邩���B
�ŁA�R���p�N�g�ɏo����̂��낤���ǂ��łɍ���Ă������͂ł����B�B
�Ε������Y�I�ȕ����̓��a40mm�̋����ɕt����ɂ́A�O�`50mm�̃����Y�͑傫���ȁ[�Ƃ��B
�T�C�Y�͗Z�ʌ����V���b�v�ł͂Ȃ������̂ŁA�A
�i�O�̓P���R�[��f=330mm�̂ł҂�����Ȃ̂��g���Ă����A���Œ��Ԃ������e�[�v���Ń����Y���O��Ăĕ�����ԁB
���m�R�[�g�Ƃ��`��A���x�͂��邯�ǒl�i�����\�{���Ⴄ�̂ŁA�A�j
���[�U�[�̍L������l����ƁA�Ε������Y�a��3�p�ʂł����������B
�`�F�b�N�p��H�B
�A�����ƃ����V���b�g�p���X���o���郂�m�B
5V�p���[�U�[���W���[���ɁA�A���J��4�{��6V��������ɁALD���̂�2V�Ƃ��āA���W���[�����̓�����91���Ɍp��������33�����K�v�Ƃ݂āA
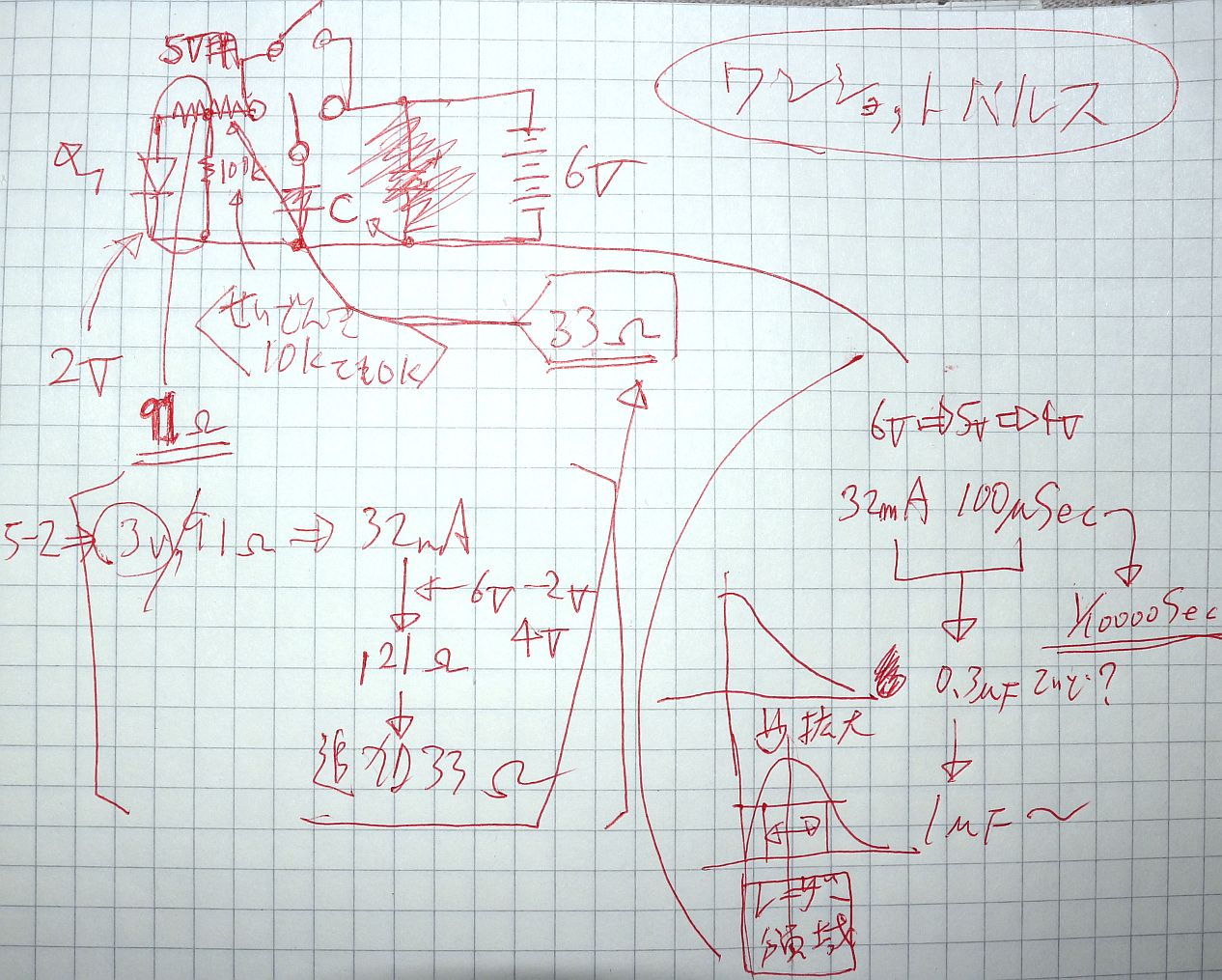 10K���͐Ód�C����̕ی�B
�����V���b�g�́A�^�C�}�[�ȂǕK�v�Ƃ��Ȃ��A1��F�ɓd�ׂ����߂āA�n���ȈՌ^�B
�����オ�蔻�肪���z�I�����A�ȈՎ����H�͔������Ă��̐M�����x�������Ă�B
10K���͐Ód�C����̕ی�B
�����V���b�g�́A�^�C�}�[�ȂǕK�v�Ƃ��Ȃ��A1��F�ɓd�ׂ����߂āA�n���ȈՌ^�B
�����オ�蔻�肪���z�I�����A�ȈՎ����H�͔������Ă��̐M�����x�������Ă�B
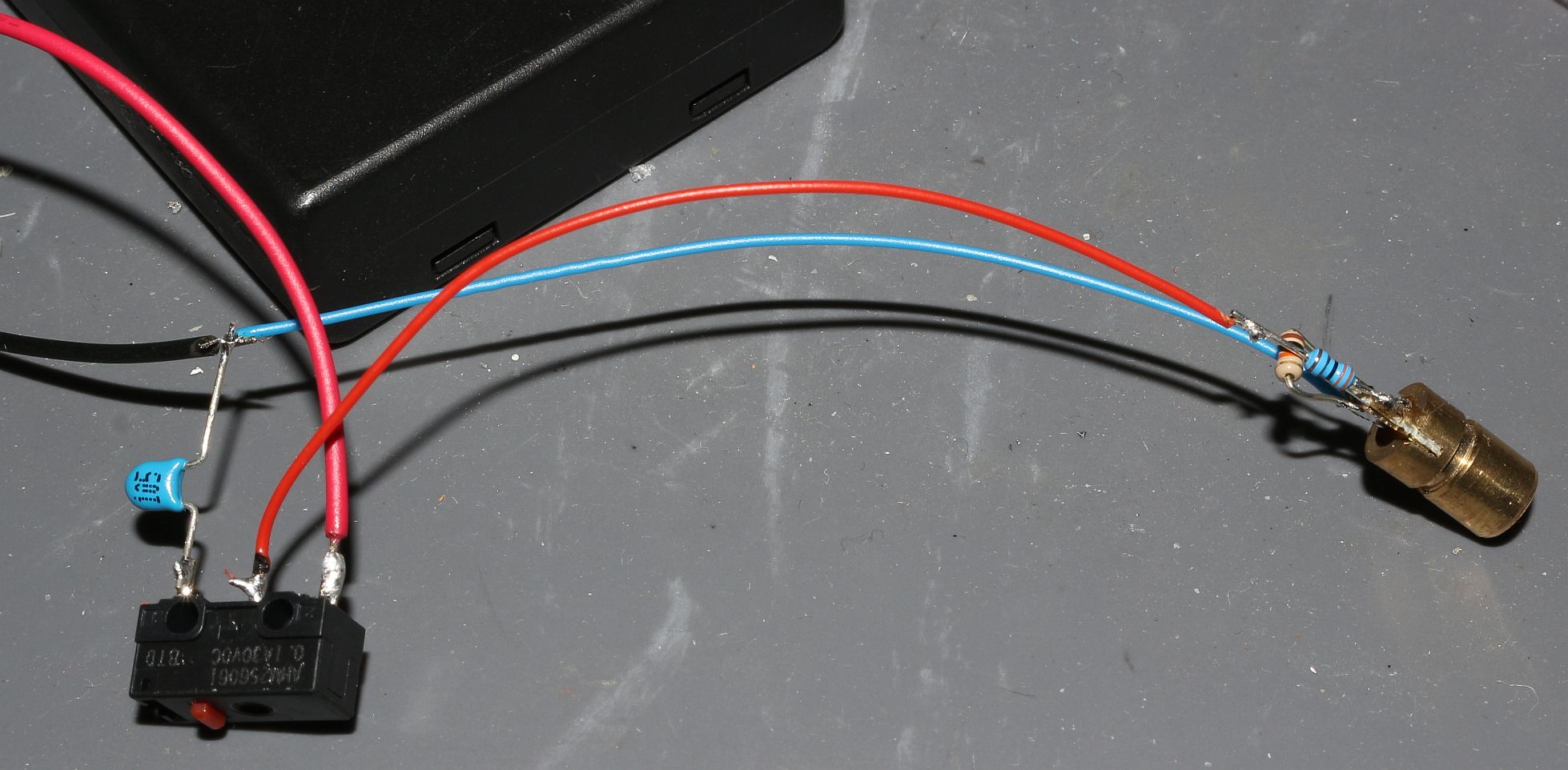 �e�X�g�������A����ɓ��삷��B
240315
���́AG17�ȃ��c��蔭�����Ԃ͒Z���̂ŁA�ڂɂ͌����キ������B
�����ŁA�Z���T�[�˓����ɓ��ĂĂ���Ă݂��Ƃ���A�t�Ɍ��\���߂ɏo��B
�R���f���T�[�̎�ނ�ALD�̃p���[���Ⴄ�̂������ĂȂ��B
�ǂ���ɂ���A�ǍD�Ȍ��ʂ������B
���Ȃ݂ɁA�d�r�Ȃ��ĘA������������A5mW�N���X�̋��������������B�܂��A5mW�̃��W���[�����낤����B
�u�N���[�Y�A�b�v�{3�v�Ƃ̓P���R�[���i��NO.3�ɓ�����n�Y�B
�������A33cm�����ō��킹��ݒ肾�����Ǝv���̂ŁA�AF=330mm�Ǝv����B��(1/f1)�{(1/f2)��1/f
����ŁA�����ɍ����Ǝv����A40.5mm�̂��}���~�ƌ������[�J�[�̂�836�~���x�Ō������B
�R����t����\��B
���ƁA�ꉞ�A�œ_�����̒����l�W���������̉\���A���̂��߁A800�~�̃�3mm�G���h�~���������B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
240316
�����̌����x�������B
C=1��F
������ƃM�U�M�U�������B�����ċt�o�C�A�X�͂����ĂȂ��B
�e�X�g�������A����ɓ��삷��B
240315
���́AG17�ȃ��c��蔭�����Ԃ͒Z���̂ŁA�ڂɂ͌����キ������B
�����ŁA�Z���T�[�˓����ɓ��ĂĂ���Ă݂��Ƃ���A�t�Ɍ��\���߂ɏo��B
�R���f���T�[�̎�ނ�ALD�̃p���[���Ⴄ�̂������ĂȂ��B
�ǂ���ɂ���A�ǍD�Ȍ��ʂ������B
���Ȃ݂ɁA�d�r�Ȃ��ĘA������������A5mW�N���X�̋��������������B�܂��A5mW�̃��W���[�����낤����B
�u�N���[�Y�A�b�v�{3�v�Ƃ̓P���R�[���i��NO.3�ɓ�����n�Y�B
�������A33cm�����ō��킹��ݒ肾�����Ǝv���̂ŁA�AF=330mm�Ǝv����B��(1/f1)�{(1/f2)��1/f
����ŁA�����ɍ����Ǝv����A40.5mm�̂��}���~�ƌ������[�J�[�̂�836�~���x�Ō������B
�R����t����\��B
���ƁA�ꉞ�A�œ_�����̒����l�W���������̉\���A���̂��߁A800�~�̃�3mm�G���h�~���������B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
240316
�����̌����x�������B
C=1��F
������ƃM�U�M�U�������B�����ċt�o�C�A�X�͂����ĂȂ��B
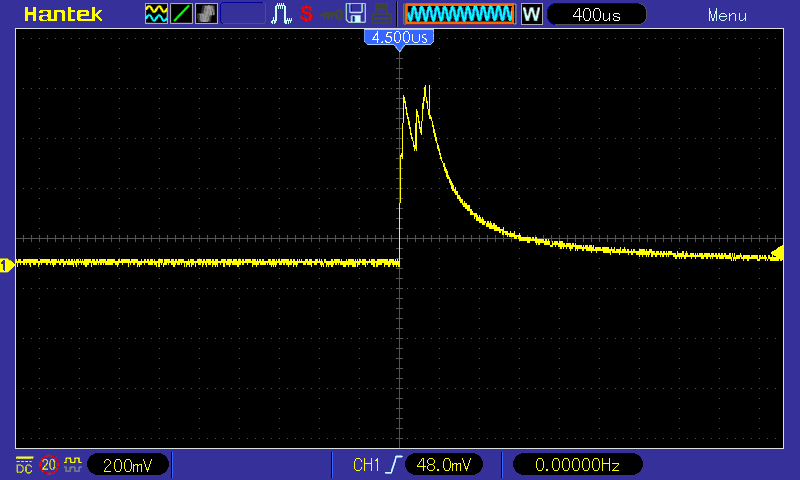 �}�C�N��SW�̖�肩���H�����J���Đړ_�����܂����āA
�}�C�N��SW�̖�肩���H�����J���Đړ_�����܂����āA
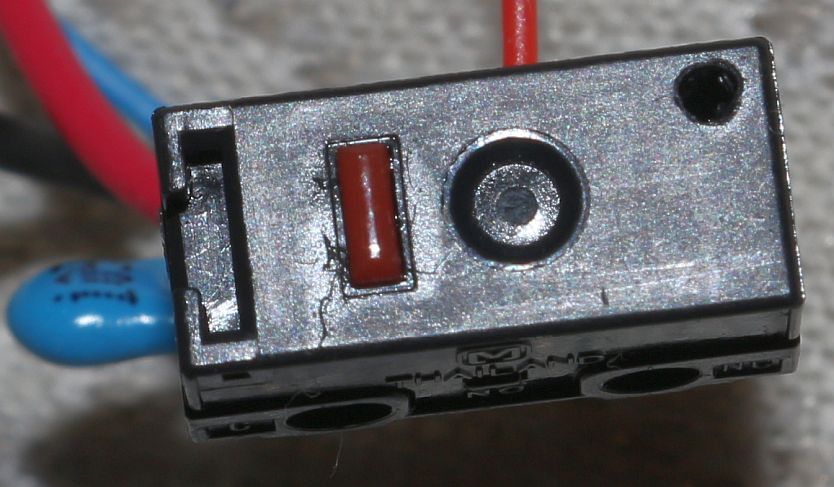 ���x��60MHz�Ɏg���Ă�����̃��c�Ŏ����B���t�o�C�A�X9V
�������㉺���́A����M���������Ȃ��悤�ɑg���̂�L�������Ǝv���̂Ŗ������ׂ����������A
�M�U�M�U�ȃC���[�W������B
���x��60MHz�Ɏg���Ă�����̃��c�Ŏ����B���t�o�C�A�X9V
�������㉺���́A����M���������Ȃ��悤�ɑg���̂�L�������Ǝv���̂Ŗ������ׂ����������A
�M�U�M�U�ȃC���[�W������B
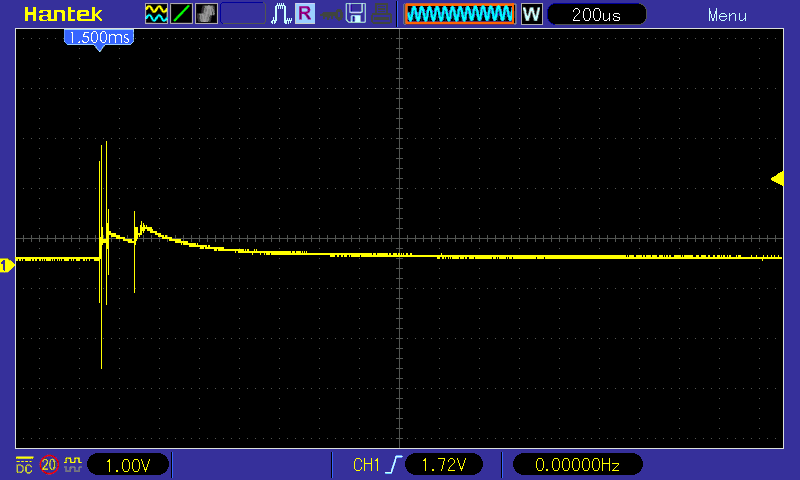 �R���f���T�[�ɂ��߂�LD���W���[���Ɏn�����A�̏������悤�Ɂu�ʂ��v�����̕������肷�邩�ȁH
����ƁA����������Ɣ������Ԃ͒����Ă��ǂ������B
����̉ۑ�ŃA���B
���������������B
C���ꌅ�グ10��F�ɂ����B��������������Ȃɗǂ��Ȃ��B
LED�����̈悪�����悤�ŁA
���[�U�[�̈�ň��肵�ďo���ɂ́A
�X�ɑ傫�����Ȃ��ƃC�J���Ƃ������Ƃ炵���B
�X��47�{��470��F�ɗe�ʂ��グ����A���邭�Ȃ��ďo�͂����������ǁA
�L�����ア�B
�������O���G17�̐M���́A�X�v�����O�ɂ�郁�J�j�J���Ȃ��������݂œ���肵�Ă镔�������邵�A
���͌����x�̃��x���I�[�o�[���Ă�悤���낤���B�Ȃɂ��6V�쓮���ۂ��B
�R���f���T�[�ɂ��߂�LD���W���[���Ɏn�����A�̏������悤�Ɂu�ʂ��v�����̕������肷�邩�ȁH
����ƁA����������Ɣ������Ԃ͒����Ă��ǂ������B
����̉ۑ�ŃA���B
���������������B
C���ꌅ�グ10��F�ɂ����B��������������Ȃɗǂ��Ȃ��B
LED�����̈悪�����悤�ŁA
���[�U�[�̈�ň��肵�ďo���ɂ́A
�X�ɑ傫�����Ȃ��ƃC�J���Ƃ������Ƃ炵���B
�X��47�{��470��F�ɗe�ʂ��グ����A���邭�Ȃ��ďo�͂����������ǁA
�L�����ア�B
�������O���G17�̐M���́A�X�v�����O�ɂ�郁�J�j�J���Ȃ��������݂œ���肵�Ă镔�������邵�A
���͌����x�̃��x���I�[�o�[���Ă�悤���낤���B�Ȃɂ��6V�쓮���ۂ��B
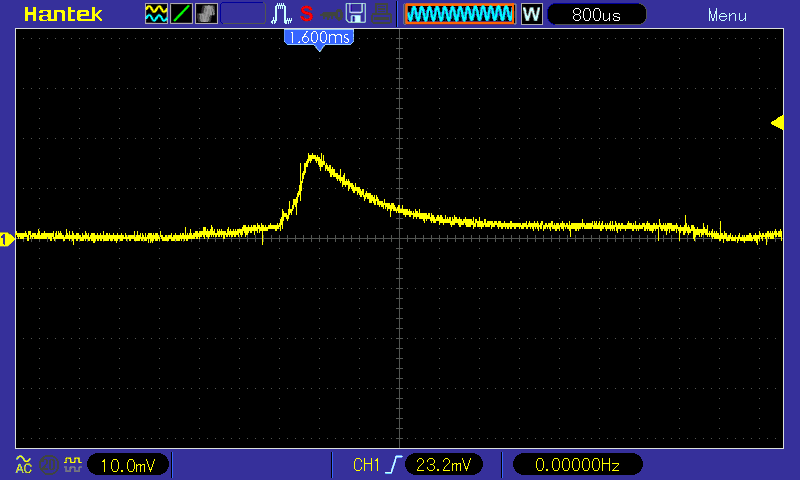 ����̂́A�������̂ɓ��ĂĔ��ˌ��𑪒肵�Ă���B
���̈Ⴂ���낤�B�܂��A�����M���ɂ́A�����オ�肪�s����Ηǂ��킯�����B�B���ʂ��オ��Ƃ������ǂ߂Ηǂ��B
���ɓ����ƁA�A
����̂́A�������̂ɓ��ĂĔ��ˌ��𑪒肵�Ă���B
���̈Ⴂ���낤�B�܂��A�����M���ɂ́A�����オ�肪�s����Ηǂ��킯�����B�B���ʂ��オ��Ƃ������ǂ߂Ηǂ��B
���ɓ����ƁA�A
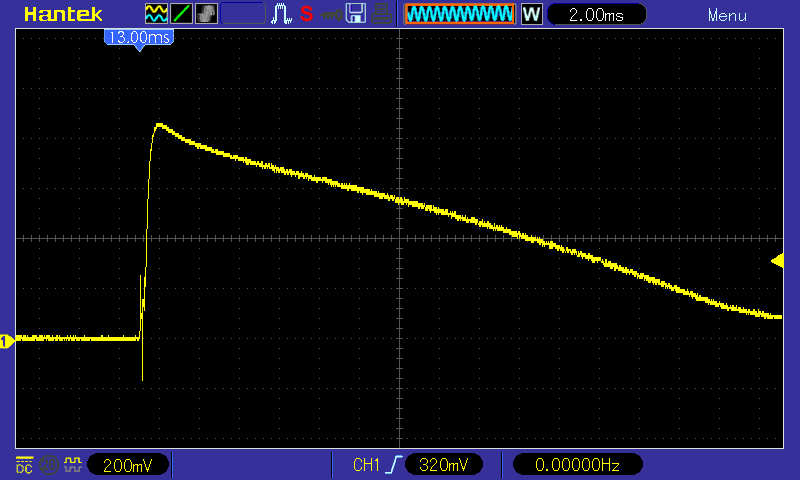 60MHz�͂��납�ADVD�̕ϒ��̂悤��380MHz�Ƃ��ł����U�ł��闧���オ�肪���邪
����́ALED���U�̈�Ń��[�U���U��O�őҋ@���Ă�̂ł���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�NjL����
GLOCK17�̃��[�U�[���𔒂����m�̔��ˌ��ɂđ��肵�����Ă݂��B���t�o�C�A�X9V
60MHz�͂��납�ADVD�̕ϒ��̂悤��380MHz�Ƃ��ł����U�ł��闧���オ�肪���邪
����́ALED���U�̈�Ń��[�U���U��O�őҋ@���Ă�̂ł���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�NjL����
GLOCK17�̃��[�U�[���𔒂����m�̔��ˌ��ɂđ��肵�����Ă݂��B���t�o�C�A�X9V
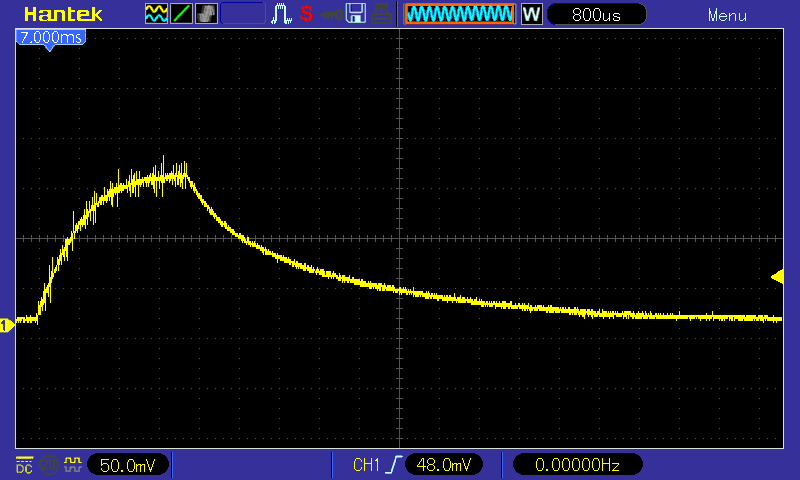 ����ψĂ̒肱�̒ʂ肾�����A�O�̑���̓��x���I�[�o�[�������̂��B
���łɃI�V�����͂�C�傫�������̂ŁA����łȂ܂��Ă�Ƃ����������悤���B�܂�A�^�[�~�l�[�^�[�Ȃǂ̕��ג�R�͂��Ă��Ȃ��B
����āA�I�V���̊e�ʂŐϕ�����Ă�͗l�ŁA���ۂ̎����H�ɑ��Ă͗����オ��͂����Ƒ����\���͏\���ɂ���B
�V���[�e�B���O�����W�I�����C���Ȃǂ̂悤�ȁA
�J�������g���Ĕ��肷��ꍇ�A���̃V���b�^�[�X�s�[�h���������Ĕ��肳��Ȃ��G���[���o��ꍇ�A
�R�R�̃R���f���T�[��傫������̂��肩���m��Ȃ��B
�t���[�����[�g��1/60�̃J������I��ŁA����ɍ��킹��̂��Ó��Ɏv���B
�ł����āA
�t�o�C�A�X�������A�^�[�~�l�[�^�[���q���A�����W�I�ɔ��˂����ďe�ɓ��ꂽ�܂܌����Ă݂��B���܂胁�J�j�J���œd�������B
����ψĂ̒肱�̒ʂ肾�����A�O�̑���̓��x���I�[�o�[�������̂��B
���łɃI�V�����͂�C�傫�������̂ŁA����łȂ܂��Ă�Ƃ����������悤���B�܂�A�^�[�~�l�[�^�[�Ȃǂ̕��ג�R�͂��Ă��Ȃ��B
����āA�I�V���̊e�ʂŐϕ�����Ă�͗l�ŁA���ۂ̎����H�ɑ��Ă͗����オ��͂����Ƒ����\���͏\���ɂ���B
�V���[�e�B���O�����W�I�����C���Ȃǂ̂悤�ȁA
�J�������g���Ĕ��肷��ꍇ�A���̃V���b�^�[�X�s�[�h���������Ĕ��肳��Ȃ��G���[���o��ꍇ�A
�R�R�̃R���f���T�[��傫������̂��肩���m��Ȃ��B
�t���[�����[�g��1/60�̃J������I��ŁA����ɍ��킹��̂��Ó��Ɏv���B
�ł����āA
�t�o�C�A�X�������A�^�[�~�l�[�^�[���q���A�����W�I�ɔ��˂����ďe�ɓ��ꂽ�܂܌����Ă݂��B���܂胁�J�j�J���œd�������B
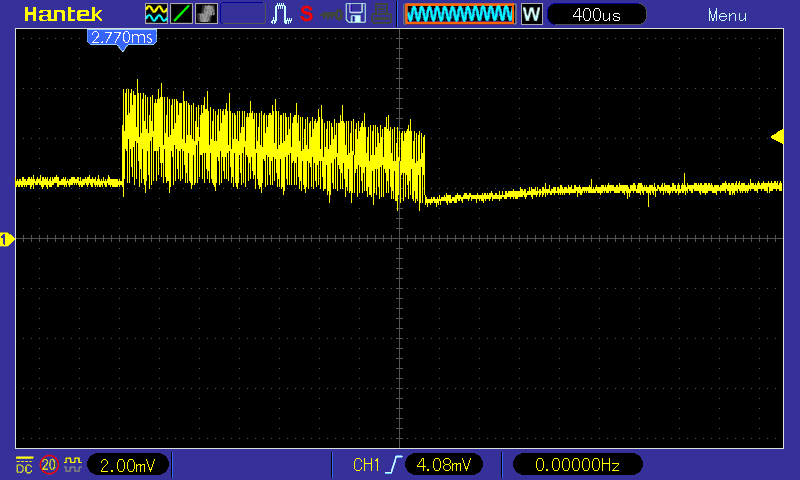 �����g�p���X���܂�ł����B
�g��
�����g�p���X���܂�ł����B
�g��
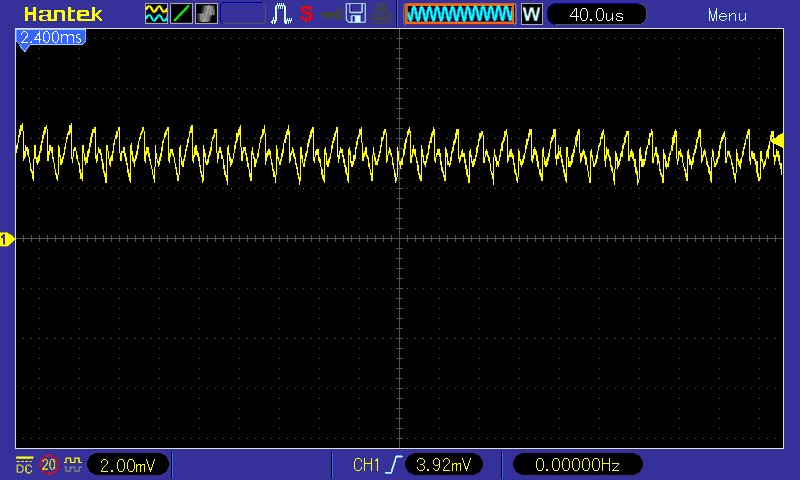 �Ƃ������Ƃł��邪�A
�d�r�����ĂĂ����d�́A���ȕ��d�ȊO�A��H�̕��d�̖��Ȃ��悤�Ȃ̂ŁA
�X�C�b�`�͎�d���ŃA���A������q�����u�u�ԁv���炭���U�������@�\�ɂȂ��Ă���悤���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���[�U�[�����e�W���p�R�����[�^�[�̐���B
�܂��́A�Z�k���ʂɏo����悤�ɂ��āA�g��ł́A�݂�B
�Ƃ������Ƃł��邪�A
�d�r�����ĂĂ����d�́A���ȕ��d�ȊO�A��H�̕��d�̖��Ȃ��悤�Ȃ̂ŁA
�X�C�b�`�͎�d���ŃA���A������q�����u�u�ԁv���炭���U�������@�\�ɂȂ��Ă���悤���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���[�U�[�����e�W���p�R�����[�^�[�̐���B
�܂��́A�Z�k���ʂɏo����悤�ɂ��āA�g��ł́A�݂�B
 ���傤�ǁA30m�Ŏ������鋗����T������A330mm-75mm��255mm���x�ɂȂ����̂ŁA��330��75�ł̋ߎ��I
�����p�̍a���A�t���C�X�Ղł��Ȃ艄���B
���傤�ǁA30m�Ŏ������鋗����T������A330mm-75mm��255mm���x�ɂȂ����̂ŁA��330��75�ł̋ߎ��I
�����p�̍a���A�t���C�X�Ղł��Ȃ艄���B
 �ŁA600m���x�̋����ɂĎ����߂���T��ƁA
�ŁA600m���x�̋����ɂĎ����߂���T��ƁA
 ����Ȉʒu�ɂȂ����B
�����������ƌ��_�ȋP�_�����������Č����Ȃ��B
�Ȃ̂ŁA�X�R�[�v���t���Ă���B
�A�o�E�g�Ɏ��������Ă�̂ŁA���_�̌a��10cm�ʂ��邩������Ȃ��B
�Ε������Y�ւ̌��͌a1.5cm���x�Ȃ̂ŁA�����ƌa�̏������Ε������Y���g���邪�A�Ȃ��Ȃ����������͖̂����B
�������ƂƂ�ł��Ȃ��l�i�ɂȂ�B
�ȑO�̂悤�ɁA1200m�ł̋P�_��15cm�ȉ��ɂ͂������B
���ʃ����Y��F=-5cm���x�ɂ�����A�����Ƃ������Ⴍ�Ȃ�̂��낤���H(2�d�˂���̒��x�s���Ǝv�����ǁB)
�t�ȍl������������̂ŁA
�I�y���O���X���t����k�����悤�Ȍ`���Ɏv���B
��r���m�Ɍv������A560m��ŁA�P�_��4�`6cm�̃R�����[�g�ɂȂ��Ă�悤�ł���B
����̓n�[�h�t�H�[�h�̌Â����[�U�[�T�C�g���g�������A
�����A5V���W���[����t���āA�ϒ��M���𑗂��ėl�q�����Ă݂����B
�������͎��3��ށB
�E�ԊO�������R���̋K�i38KHz�˕�600��Sec
�E�����V���b�g�p���X�̔����M��
�E60MHz�p���X��1��Sec�I�[�_�[�̕�
�����āA
�E455KHz��10.7MHz�Ȃǂ�IF���g���A�t�B���^�[�n�����̂܂g���B
38KHz�̔��U��H���ϒ������グ��ɂ́A������xLED��������������ŐM���𑗂�K�v�����肻���B
-------------------------------------------------
24/03/18
�\�j�[�́uCX20106A�v�́A�`���Ŏg���Ă����(35�N���炢�O)�g���Ă��ԊO�����R�����W���[����IC�ŁA
�Ȃ�ƁA���������O�����Ŕ����Ă邻���Ȃ̂ŁA�\�Z���o�����璍������R�g�ɂ����B
�Ƃ͂����A
�Â�IC�̈����ŁA�Q�C�������̍ō��̂Ɣ�ׂ���A�����Y�����ɂ��āA
�Q�C����80dB�ŁA�����炭15�`25dB�Ⴂ�l���Ǝv���BBPF��Q�l���Ⴂ�Ǝv����B
�����A���̎�̉�H�ł�PPM�M���Ɉ�����p���X���́A600��Sec�p���X�œ����Ƃ����K�i�����邪�A�ʂɒZ�߂ł��ǂ��݂������B
(�ɒ[��������A�X�g���{�Ō�쓮�N�����B)
�Ȃ�A������300��Sec���x�ɂ��Ă݂����Ǝv���B���e����1m�i�ނ��Ƃ����������H
�Ȃ̂ŁA���W���[�����g���A�o����o�C�A�X��006P�ȂǁA�ʓd���ō��߂ɐݒ肵�悤�Ǝv���B�o�C�A�X���ɂ�47mH�̃C���_�N�^��1K�����x�̒�R������B
1�ԃs�������͂����˂Ă�炵������AC�Ő��āA�ʂɉ�����Ηǂ��Ǝv���B
TTL���x����5V(4.5�`5.5V)��pIC�Ȃ̂ŁA������78L05�Ȃǃ��M�����[�^�[���g����555�ɑ����āA����p�̃u�U�[��LED�Ɍq���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�����̃Z���^�[�o���̕��@�����A
���[�U�[�T�C�g�����[���ɓ��ĂāA�����A���̒��S���A���[���̉����A�����o�����̉������ƂȂ�B�B
����ɁA�_�b�g�T�C�g�����킹��B
�G�A�K���Ȃǂ��ƁA�[���C���O�ɁA�e�̔�т����킩�H�Ƃ����w�W�ɂ��Ȃ�B
�Z���^�[�o�����o���Ȃ����^��̃��W���[���̏ꍇ�A�������ɉāA��ԉ��ɗ���悤�ɂ���Ǝ��R�����m��Ȃ��B
�e�͏�ɂ͔�Ȃ��̂ŁA�X�R�[�v�ނ���ɂ͂��炷���Ƃ����܂�o���Ȃ��悤�ɂȂ��Ă��邵�A�A
����Ȉʒu�ɂȂ����B
�����������ƌ��_�ȋP�_�����������Č����Ȃ��B
�Ȃ̂ŁA�X�R�[�v���t���Ă���B
�A�o�E�g�Ɏ��������Ă�̂ŁA���_�̌a��10cm�ʂ��邩������Ȃ��B
�Ε������Y�ւ̌��͌a1.5cm���x�Ȃ̂ŁA�����ƌa�̏������Ε������Y���g���邪�A�Ȃ��Ȃ����������͖̂����B
�������ƂƂ�ł��Ȃ��l�i�ɂȂ�B
�ȑO�̂悤�ɁA1200m�ł̋P�_��15cm�ȉ��ɂ͂������B
���ʃ����Y��F=-5cm���x�ɂ�����A�����Ƃ������Ⴍ�Ȃ�̂��낤���H(2�d�˂���̒��x�s���Ǝv�����ǁB)
�t�ȍl������������̂ŁA
�I�y���O���X���t����k�����悤�Ȍ`���Ɏv���B
��r���m�Ɍv������A560m��ŁA�P�_��4�`6cm�̃R�����[�g�ɂȂ��Ă�悤�ł���B
����̓n�[�h�t�H�[�h�̌Â����[�U�[�T�C�g���g�������A
�����A5V���W���[����t���āA�ϒ��M���𑗂��ėl�q�����Ă݂����B
�������͎��3��ށB
�E�ԊO�������R���̋K�i38KHz�˕�600��Sec
�E�����V���b�g�p���X�̔����M��
�E60MHz�p���X��1��Sec�I�[�_�[�̕�
�����āA
�E455KHz��10.7MHz�Ȃǂ�IF���g���A�t�B���^�[�n�����̂܂g���B
38KHz�̔��U��H���ϒ������グ��ɂ́A������xLED��������������ŐM���𑗂�K�v�����肻���B
-------------------------------------------------
24/03/18
�\�j�[�́uCX20106A�v�́A�`���Ŏg���Ă����(35�N���炢�O)�g���Ă��ԊO�����R�����W���[����IC�ŁA
�Ȃ�ƁA���������O�����Ŕ����Ă邻���Ȃ̂ŁA�\�Z���o�����璍������R�g�ɂ����B
�Ƃ͂����A
�Â�IC�̈����ŁA�Q�C�������̍ō��̂Ɣ�ׂ���A�����Y�����ɂ��āA
�Q�C����80dB�ŁA�����炭15�`25dB�Ⴂ�l���Ǝv���BBPF��Q�l���Ⴂ�Ǝv����B
�����A���̎�̉�H�ł�PPM�M���Ɉ�����p���X���́A600��Sec�p���X�œ����Ƃ����K�i�����邪�A�ʂɒZ�߂ł��ǂ��݂������B
(�ɒ[��������A�X�g���{�Ō�쓮�N�����B)
�Ȃ�A������300��Sec���x�ɂ��Ă݂����Ǝv���B���e����1m�i�ނ��Ƃ����������H
�Ȃ̂ŁA���W���[�����g���A�o����o�C�A�X��006P�ȂǁA�ʓd���ō��߂ɐݒ肵�悤�Ǝv���B�o�C�A�X���ɂ�47mH�̃C���_�N�^��1K�����x�̒�R������B
1�ԃs�������͂����˂Ă�炵������AC�Ő��āA�ʂɉ�����Ηǂ��Ǝv���B
TTL���x����5V(4.5�`5.5V)��pIC�Ȃ̂ŁA������78L05�Ȃǃ��M�����[�^�[���g����555�ɑ����āA����p�̃u�U�[��LED�Ɍq���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�����̃Z���^�[�o���̕��@�����A
���[�U�[�T�C�g�����[���ɓ��ĂāA�����A���̒��S���A���[���̉����A�����o�����̉������ƂȂ�B�B
����ɁA�_�b�g�T�C�g�����킹��B
�G�A�K���Ȃǂ��ƁA�[���C���O�ɁA�e�̔�т����킩�H�Ƃ����w�W�ɂ��Ȃ�B
�Z���^�[�o�����o���Ȃ����^��̃��W���[���̏ꍇ�A�������ɉāA��ԉ��ɗ���悤�ɂ���Ǝ��R�����m��Ȃ��B
�e�͏�ɂ͔�Ȃ��̂ŁA�X�R�[�v�ނ���ɂ͂��炷���Ƃ����܂�o���Ȃ��悤�ɂȂ��Ă��邵�A�A
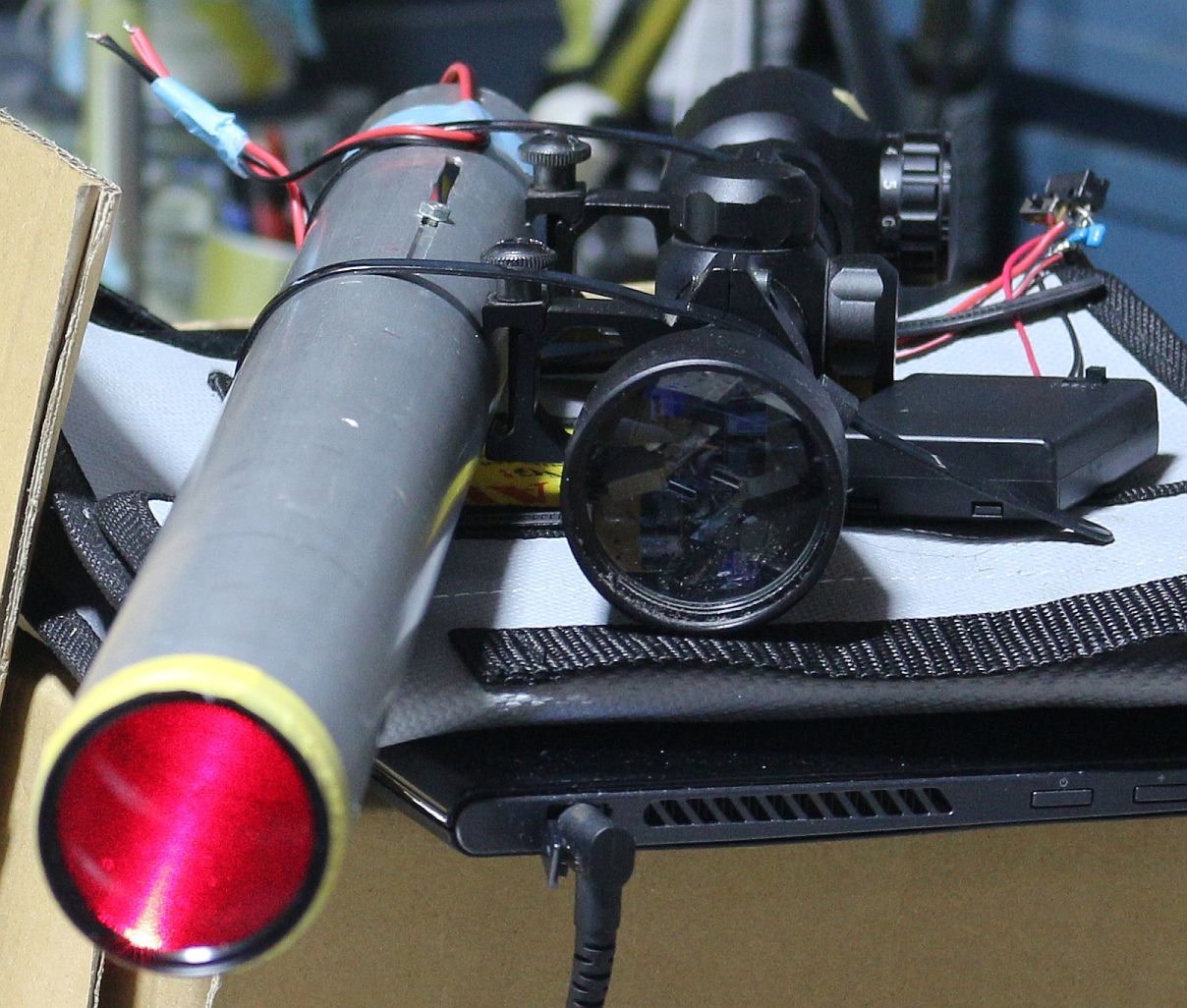 �|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
UV���W���ʼn��ʃ����Y�ɐڒ����悤��LD���W���[�����W���[�����������Ă��Ƃ��A➑̂ɃK�^������̂ŋC�������̂����ǁA
���̈���LD���W���[���A����➑̂̑O�������A�t�H�[�J�X�����O�ɂȂ��Ă����B���̃l�W�̃K�^�B
�܂�A
�t�H�[�J�X��傫�����点�A���ʋ������ɑΕ������Y���g���ăR�����[�g�����邱�Ƃ��\�����m��Ȃ��B
�����́A�œ_��Z������������]�܂������A�ǂ��܂ōs���邩�H
�����ǁA�������Ă��܂����̂ŁA���̂܂g�p���B�B
�Ƃ͂����A�K�^�������Ȃ̂ŁA�œ_�����߂���A�e�[�v���l�W�~�ߍ܂ŌŒ肵�������ǂ����Ǝv���B
���̒��ōL���肷������A���̒��ŕ��Č��������Ă��܂��ƁA���ʂɂȂ�̂ŁA�������킹�͏d�v�����ǁA���̏�Ԃł́A�����ȒP�ɂ������Ă��Ȃ��B
�Ƃ肠�����A�����Y�ł͖����A�^�_�̃K���X��(�����d����C�p�Ƃ��L��)���g���ƕ֗����ȁH�Ƃ͎v���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�ŁA��A560m��ɍ��킹�Ă݂����A�_�͂��Ȃ菬�����Ȃ�B���ǁA�n�[�h�t�H�[�h�̃��[�U�[�T�C�g���g�����Ƃ������A������ƈÂ��悤�ȋC������B
�Ε������Y�ւ̌��̌�����A�_�̑傫���ɂ����̂ň�T�ɂ͔��f�ł��Ȃ����A�A
400m���x���ƁA�u�����̕����̕ǂ��͌��\���邢���Ƃ�������B
700m�ł��`�F�b�N�����B�X�R�[�v�ł��P�_�́A�\���ɕ�����B
�̔�1/4�C���`�̃i�b�g��ł����݁A�O�r�ɌŒ�ł���悤�ɂ����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
UV���W���ʼn��ʃ����Y�ɐڒ����悤��LD���W���[�����W���[�����������Ă��Ƃ��A➑̂ɃK�^������̂ŋC�������̂����ǁA
���̈���LD���W���[���A����➑̂̑O�������A�t�H�[�J�X�����O�ɂȂ��Ă����B���̃l�W�̃K�^�B
�܂�A
�t�H�[�J�X��傫�����点�A���ʋ������ɑΕ������Y���g���ăR�����[�g�����邱�Ƃ��\�����m��Ȃ��B
�����́A�œ_��Z������������]�܂������A�ǂ��܂ōs���邩�H
�����ǁA�������Ă��܂����̂ŁA���̂܂g�p���B�B
�Ƃ͂����A�K�^�������Ȃ̂ŁA�œ_�����߂���A�e�[�v���l�W�~�ߍ܂ŌŒ肵�������ǂ����Ǝv���B
���̒��ōL���肷������A���̒��ŕ��Č��������Ă��܂��ƁA���ʂɂȂ�̂ŁA�������킹�͏d�v�����ǁA���̏�Ԃł́A�����ȒP�ɂ������Ă��Ȃ��B
�Ƃ肠�����A�����Y�ł͖����A�^�_�̃K���X��(�����d����C�p�Ƃ��L��)���g���ƕ֗����ȁH�Ƃ͎v���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�ŁA��A560m��ɍ��킹�Ă݂����A�_�͂��Ȃ菬�����Ȃ�B���ǁA�n�[�h�t�H�[�h�̃��[�U�[�T�C�g���g�����Ƃ������A������ƈÂ��悤�ȋC������B
�Ε������Y�ւ̌��̌�����A�_�̑傫���ɂ����̂ň�T�ɂ͔��f�ł��Ȃ����A�A
400m���x���ƁA�u�����̕����̕ǂ��͌��\���邢���Ƃ�������B
700m�ł��`�F�b�N�����B�X�R�[�v�ł��P�_�́A�\���ɕ�����B
�̔�1/4�C���`�̃i�b�g��ł����݁A�O�r�ɌŒ�ł���悤�ɂ����B
 �|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�NjL��
��Ń��[���ƃX�R�[�v��T�C�g�̌����̕��s�������������ǁA
�o���������[���̕��s���H�Ƃ�����肪����̂ŁA�A
�ڂ����́A����ɂ��邯�ǁA�o�����ƕ��s�ɂ������Ƃ���ł͂���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�����}���C�̓d���K��M4�n���̐��x�ւ̉e���ׂĂ݂�B
�O��ALD���W���[���ƃ}�E���g���Ă郌�[���̎������킹����@���l���A�ۑ肪���܂ꂽ�B
�o�����ƃ��[���̊W�̖�肾�B
240319
M4RIS���قږ����Ń`�F�b�N�B
�_�b�g�T�C�g����Ɍ��Ă݂�B
������18m
�T�C�g���n���h�K�[�h���ځˍ���10cm���炢���e�������B(�_�b�g�T�C�g�̃��e�B�N�����E�ɑ����Y���Ă邩�������B)
�A�b�p�[�t���[����[�ɓ��ځˎ������Ɋ�邪�A�E��15cm�قǃY����B
�ł����āA���������̂��A�K�^�ȊO�̂��Ƃł���B
�K�^�͖������A�o�����ƃn���h�K�[�h�̃��[�����Y���Ă邱�Ƃ������B�\���I�ɂ���v�͂Ȃ��Ȃ�����B
�o�������r���œr��ĂȂ���A�n���h�K�[�h�Ƃ���قǃY���Ȃ��\���ɂ��o���������Ǝv�����ǁA�A
�A�b�p�[�t���[���̃��[���́A�o�����ɌX���ɑ����Ǐ](�A��)�����悤�o���Ă��邪�A�Œ�͂�������ł͂Ȃ��̂ŁA����قǂ��Ɩ����̂悤���B
�ȒP�Ɍ����A
���e�̓A�b�p�[�t���[��(���V�[�o�[)�����o�����̕����ɋ߂����A�G�A�\�t�g�K���́A�n���h�K�[�h���ɂ��ꂪ����Ă�X��������B
�������A���^���t���[���ŁA�t���[�e�B���O�}�E���g�o�����Ȃ����Ă���B
���Ȃ݂ɒe�́A���\���x�ǂ��o�Ă�悤�ł���͂��܂芴�����Ȃ��B
�o�����ƃ��[���̓Y���Ă�Ȃ���s�ɋ������ׂ��Ȃ̂��낤���ǁA
�G�A�\�t�g�K���ł̓M�~�b�N��g�ݍ���ŁA���ꂪ���������m������悤���B
���Ƃ͑O�q�����悤�Ȗ��͎��e�ł�����ɂ͂���B
�ȈՓI�ɂ́A�n���h�K�[�h�̕��̓K�^�̉e���͂Ȃ��̂ŁA�����炭���t�������s�ł͖����Ƃ�����肾���ł���B
�P�ɕ��s�ɂ������Ȃ�A�n���h�K�[�h�ɍa�������āA�o�����ɂ͂߂�Ηǂ����ǁA
M4RIS�̏ꍇ�A�d���W�̃u�c���͂����Ă�̂ŁA���������Ă�B
�������A�n���h�K�[�h���t�����l�W���ɂ߂ĘM���Đ���ɂ�����̂͊ȒP����Ȃ��̂ŁA�T�C�g�̑��𒅒e�_�Ƀ[���C���������v��������@�ł�邵�������Ǝv���B
�����A�n���h�K�[�h���ƑO�߂���̂ŁA���n�C�}�E���g�Ō��ɉ����ł�����G�A�K���Ƃ��Ă������₷�������B
�t���[�e�B���O�}�E���g�ł������A�e�̍~�����������A�n�C�h���}�E���g�ƌ������c�̋t���z���g���₷���������ǁA�A�܂�n���h�K�[�h���ɕt����B
�n�C�}�E���g�́A���J�j�J���I�t�Z�b�g�Ƃ�����肪���邪�A�G�A�\�t�g�K���͂��̋ɂ݂ł͂��邯�ǁA�߂Ƀ}�E���g����A�e�̍~������t�Ɏ��F���͗ǂ��Ȃ邩���H�H
�u�p�g���I�b�g�{�v�ł����荬�ނƏ����E�ɃY����̂͗L��Ɗ����Ă�B�����A�u�p�g���I�b�gHC�v��肩�Ȃ萸�x���ǂ��炵���B
���������̂��l�����Ȃ���A�p�g���I�b�g�{�̓m�[�}����30m�w�b�h�V���b�g���\�ȃ��x���̃O���[�s���O�炵���B
�܂��A�L�b�`���g�܂ꂽ�G�A�\�t�g�K����������ƃv���̘c�݁A��ꂩ��K�^���ӂ���Ȃǂ�����B
����������āA���܂蒆���J�������Ȃ������ƌ������Ƃł���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���������́A�]�����Ɠ������o�ŁA
�������킹�āA�i��݂����ȃ��m��t���A�����h���������ǂ����낤�B���z�I�ɂ́B
������ɂ́A�����Y�������������ǂ���������Ȃ����A
�T�o�Q�n�Ƃ��ł͎w�����ȂǃC���C������s�����B
CX20106A�͑����A�����C�Z���X�i�����ʂɏo����Ă���悤�ł���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
HOP����Ȃ��Ă����e�Ŏ߂ɍ\���邱�ƁB
�Ȃ����s���Ă�̂ŁA�A�C�����m�����H�@
���e�ł��c�ɍ\����̂��ȑO�̓S���ł��邪�A
CQB�ȂNjߐڐ퓬�ł͐��x���v������Ȃ����ߋ��e����Ă���悤���B
CAR�V�X�e���B
�ł����āA�߂ɍ\����ƁA���i�̈ʒu�������ɂ���čČ�����������ƌ������ƂƂ������O�����B���ۖ��e�ɂ̓K�^�������B
�r��傫���Ȃ����܂܂ł́A���R�C�������������ނɂ͋Z�p�Ɨ͂��K�v�ɂȂ邩�Ǝv���\�z�B
�ō��̖��B
�����e�̃n���h�K�[�h�������͂Ńz�[���h����ƁA����肪�c�݁A
�Ə��ƒe�����Y����B
���e�ł����邱�ƁB
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
240322
�t�o�C�A�X�́A006P9V�ƍ������A���˓������ł͔����^��1K�����傢�̒Ⴓ���K�v�ɂȂ��Ă��̂ŁA1K���Ƃ����B
����ɒ����47mH��ڑ��B���R�C���͂��Ȃ�m�C�Y���E���₷�������̂ŁA�V�[���h�������ɁB
10K��VR�͏Ȃ����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�NjL��
��Ń��[���ƃX�R�[�v��T�C�g�̌����̕��s�������������ǁA
�o���������[���̕��s���H�Ƃ�����肪����̂ŁA�A
�ڂ����́A����ɂ��邯�ǁA�o�����ƕ��s�ɂ������Ƃ���ł͂���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�����}���C�̓d���K��M4�n���̐��x�ւ̉e���ׂĂ݂�B
�O��ALD���W���[���ƃ}�E���g���Ă郌�[���̎������킹����@���l���A�ۑ肪���܂ꂽ�B
�o�����ƃ��[���̊W�̖�肾�B
240319
M4RIS���قږ����Ń`�F�b�N�B
�_�b�g�T�C�g����Ɍ��Ă݂�B
������18m
�T�C�g���n���h�K�[�h���ځˍ���10cm���炢���e�������B(�_�b�g�T�C�g�̃��e�B�N�����E�ɑ����Y���Ă邩�������B)
�A�b�p�[�t���[����[�ɓ��ځˎ������Ɋ�邪�A�E��15cm�قǃY����B
�ł����āA���������̂��A�K�^�ȊO�̂��Ƃł���B
�K�^�͖������A�o�����ƃn���h�K�[�h�̃��[�����Y���Ă邱�Ƃ������B�\���I�ɂ���v�͂Ȃ��Ȃ�����B
�o�������r���œr��ĂȂ���A�n���h�K�[�h�Ƃ���قǃY���Ȃ��\���ɂ��o���������Ǝv�����ǁA�A
�A�b�p�[�t���[���̃��[���́A�o�����ɌX���ɑ����Ǐ](�A��)�����悤�o���Ă��邪�A�Œ�͂�������ł͂Ȃ��̂ŁA����قǂ��Ɩ����̂悤���B
�ȒP�Ɍ����A
���e�̓A�b�p�[�t���[��(���V�[�o�[)�����o�����̕����ɋ߂����A�G�A�\�t�g�K���́A�n���h�K�[�h���ɂ��ꂪ����Ă�X��������B
�������A���^���t���[���ŁA�t���[�e�B���O�}�E���g�o�����Ȃ����Ă���B
���Ȃ݂ɒe�́A���\���x�ǂ��o�Ă�悤�ł���͂��܂芴�����Ȃ��B
�o�����ƃ��[���̓Y���Ă�Ȃ���s�ɋ������ׂ��Ȃ̂��낤���ǁA
�G�A�\�t�g�K���ł̓M�~�b�N��g�ݍ���ŁA���ꂪ���������m������悤���B
���Ƃ͑O�q�����悤�Ȗ��͎��e�ł�����ɂ͂���B
�ȈՓI�ɂ́A�n���h�K�[�h�̕��̓K�^�̉e���͂Ȃ��̂ŁA�����炭���t�������s�ł͖����Ƃ�����肾���ł���B
�P�ɕ��s�ɂ������Ȃ�A�n���h�K�[�h�ɍa�������āA�o�����ɂ͂߂�Ηǂ����ǁA
M4RIS�̏ꍇ�A�d���W�̃u�c���͂����Ă�̂ŁA���������Ă�B
�������A�n���h�K�[�h���t�����l�W���ɂ߂ĘM���Đ���ɂ�����̂͊ȒP����Ȃ��̂ŁA�T�C�g�̑��𒅒e�_�Ƀ[���C���������v��������@�ł�邵�������Ǝv���B
�����A�n���h�K�[�h���ƑO�߂���̂ŁA���n�C�}�E���g�Ō��ɉ����ł�����G�A�K���Ƃ��Ă������₷�������B
�t���[�e�B���O�}�E���g�ł������A�e�̍~�����������A�n�C�h���}�E���g�ƌ������c�̋t���z���g���₷���������ǁA�A�܂�n���h�K�[�h���ɕt����B
�n�C�}�E���g�́A���J�j�J���I�t�Z�b�g�Ƃ�����肪���邪�A�G�A�\�t�g�K���͂��̋ɂ݂ł͂��邯�ǁA�߂Ƀ}�E���g����A�e�̍~������t�Ɏ��F���͗ǂ��Ȃ邩���H�H
�u�p�g���I�b�g�{�v�ł����荬�ނƏ����E�ɃY����̂͗L��Ɗ����Ă�B�����A�u�p�g���I�b�gHC�v��肩�Ȃ萸�x���ǂ��炵���B
���������̂��l�����Ȃ���A�p�g���I�b�g�{�̓m�[�}����30m�w�b�h�V���b�g���\�ȃ��x���̃O���[�s���O�炵���B
�܂��A�L�b�`���g�܂ꂽ�G�A�\�t�g�K����������ƃv���̘c�݁A��ꂩ��K�^���ӂ���Ȃǂ�����B
����������āA���܂蒆���J�������Ȃ������ƌ������Ƃł���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���������́A�]�����Ɠ������o�ŁA
�������킹�āA�i��݂����ȃ��m��t���A�����h���������ǂ����낤�B���z�I�ɂ́B
������ɂ́A�����Y�������������ǂ���������Ȃ����A
�T�o�Q�n�Ƃ��ł͎w�����ȂǃC���C������s�����B
CX20106A�͑����A�����C�Z���X�i�����ʂɏo����Ă���悤�ł���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
HOP����Ȃ��Ă����e�Ŏ߂ɍ\���邱�ƁB
�Ȃ����s���Ă�̂ŁA�A�C�����m�����H�@
���e�ł��c�ɍ\����̂��ȑO�̓S���ł��邪�A
CQB�ȂNjߐڐ퓬�ł͐��x���v������Ȃ����ߋ��e����Ă���悤���B
CAR�V�X�e���B
�ł����āA�߂ɍ\����ƁA���i�̈ʒu�������ɂ���čČ�����������ƌ������ƂƂ������O�����B���ۖ��e�ɂ̓K�^�������B
�r��傫���Ȃ����܂܂ł́A���R�C�������������ނɂ͋Z�p�Ɨ͂��K�v�ɂȂ邩�Ǝv���\�z�B
�ō��̖��B
�����e�̃n���h�K�[�h�������͂Ńz�[���h����ƁA����肪�c�݁A
�Ə��ƒe�����Y����B
���e�ł����邱�ƁB
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
240322
�t�o�C�A�X�́A006P9V�ƍ������A���˓������ł͔����^��1K�����傢�̒Ⴓ���K�v�ɂȂ��Ă��̂ŁA1K���Ƃ����B
����ɒ����47mH��ڑ��B���R�C���͂��Ȃ�m�C�Y���E���₷�������̂ŁA�V�[���h�������ɁB
10K��VR�͏Ȃ����B
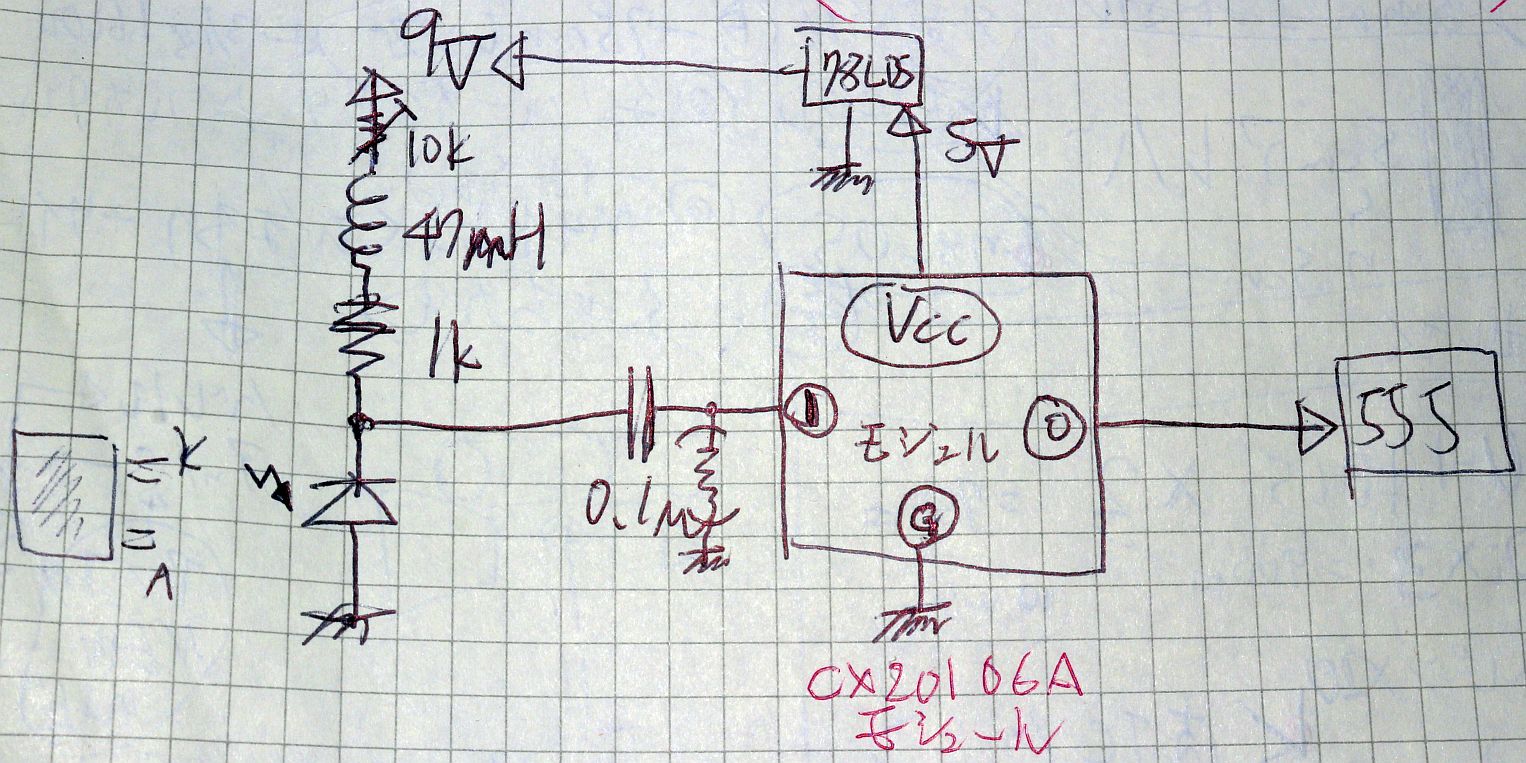 CX20106A���W���[���́AIC�K��̕��i���������ēS�̃V�[���h�P�[�X�ɓ����Ă��邾���ł���B
����ŁA555�����ALED�ƃu�U�[��炷�B
�t�B���^�[��t���Ȃ����^��Pin�t�H�g�_�C�I�[�h��t���āA�����R���삳����ƁA�����ȂNJW�Ȃ���������قǂ̊��x�ł������B
�ŁA650nm��BPF��t������ʐς�Pin�t�H�g�_�C�I�[�h��ݒu�B
����Ȋ����B
CX20106A���W���[���́AIC�K��̕��i���������ēS�̃V�[���h�P�[�X�ɓ����Ă��邾���ł���B
����ŁA555�����ALED�ƃu�U�[��炷�B
�t�B���^�[��t���Ȃ����^��Pin�t�H�g�_�C�I�[�h��t���āA�����R���삳����ƁA�����ȂNJW�Ȃ���������قǂ̊��x�ł������B
�ŁA650nm��BPF��t������ʐς�Pin�t�H�g�_�C�I�[�h��ݒu�B
����Ȋ����B
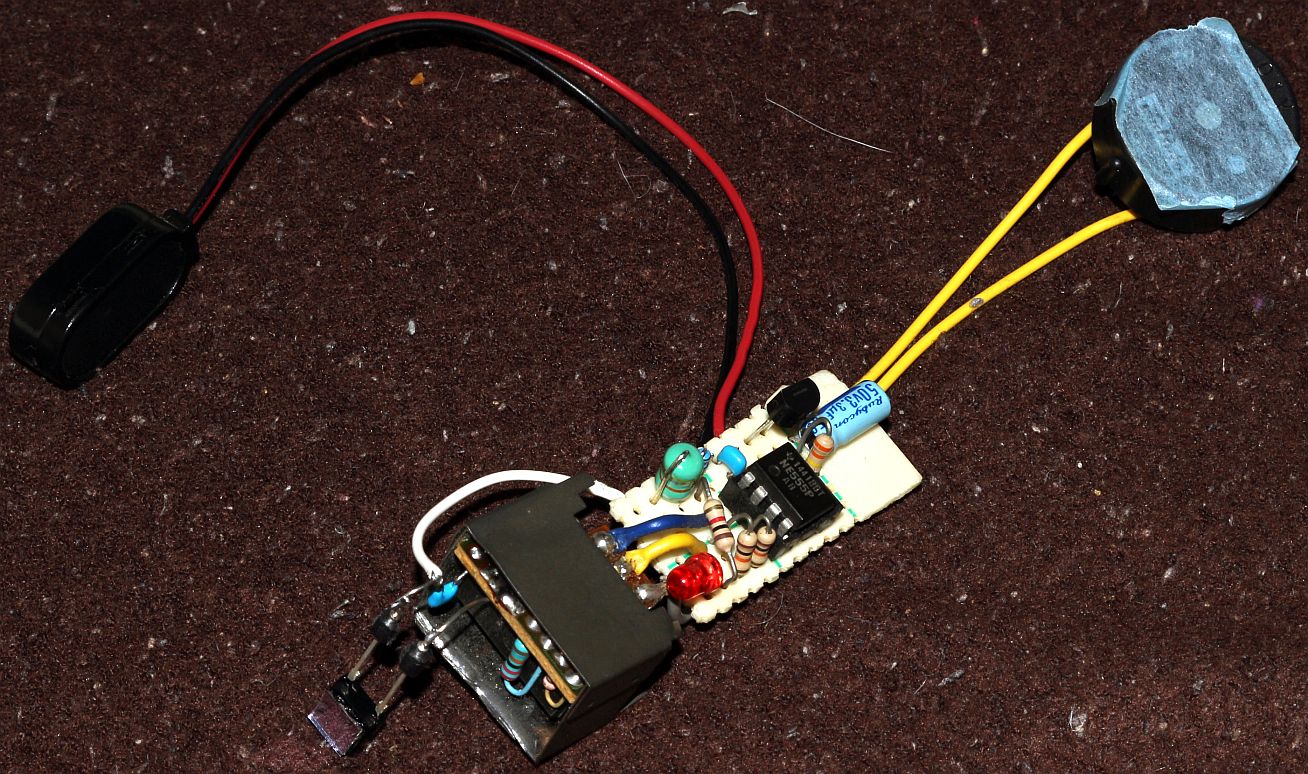 ����ŁA���S��650nm���x��LED��38KHz�̔��U��H���ƁA
������A�����������Ă���Ƃ͎v���Ȃ����邳�̕����ł�����������B
���U��H�͈ꉞ�A6V�쓮������(9V��OK)�A���[�U�[�́A�P���ɍ��̃��j�b�g��ڑ��ł���B
���[�U�[���ƁA���L���ł��A���˂��������X�R�[�v�Ŋϑ��ł���̂ŁA�܂萔Km�͔�Ԃ��ƂɂȂ�B
�����Ȃ�ƁA�����┽�ˌ�����̖��̕����C�����肩���m��Ȃ��B
���ᔽ�˂ȓh�����w�����Ă͂���B
------------------------------------------------------
�lj��̕������Ƃ��āA�Z���T�[�ł���t�H�g�_�C�I�[�h�ɒ��˓����Ă�ƌ�쓮�������̂����������B
��H�͂قڃV�[���h���ĂȂ��̂ŁA�m�C�Y�̑��������ł���쓮���N�����B
�܂��A����́A���g�͓S�̔��ɓ���Ă��������m�Ȃ̂�����B
��쓮���������̃��J�j�Y���́A�����炭�����ɂ���ăt�H�gDi�̃C���s�[�_���X�������邱�Ƃł���B
����ɂ���āA�R�C���Ȃǂւ̓d���U���̉e�����\�ʉ����₷���̂��Ǝv���B
�����ŁA�R�C���̃C���s�[�_���X�B
f=38KHz�ŁAL=47mH���ƁA
Z=2��fL=11.22K�����x�ƂȂ�B
�M���̘R��~�߂Ƃ��Ă͏\���ɍ�p���Ă���Ǝv���B
�����A�g���Ă���̂́A�����A�L�V�������[�h�̃}�C�N���C���_�N�^�[�Ȃ̂ŁA
�V�[���h���Ȃ����A�m�C�Y�͗U�����₷���悤�ɂ͎v���B
�^���N�^(���W�A��)�^�C�v�̃t�F���C�g�ŃV�[���h���ꂽ���m�ł͕ς�邩���m��Ȃ��B���A�����ɂ͎�ɓ���Ȃ��B
����Ō��ʂ����P����Ȃ��Ȃ�A��H���ƃV�[���h�{�b�N�X(�P�[�X)�ɓ����K�v��������B38KHz���Ƃ�͂�A�A���~���͓S���ǂ��B
���ƁA9V�Ȃ̂ŁA1K���͂�����ƃt�H�g�_�C�I�[�h�ɂƂ��ĒႷ�����S�ɂȂ邩���m��Ȃ��A1.5K�����x���ǂ������B�����C���_�N�^�̊�������R300�����x�L��B
�g���Ă��鉽�����̉�H����̎悷�邩�ȁH
100mH(104)���x�̂��~�����B�����H���ɂ��鑾�z�U�d��100mH������ƁA���ȋ��U���g����0.085MHz�Ƃ����ۂǂ��l�c�A�A
�Ƃ������ƂŁA�܂��͑Ë����ăA���~�P�[�X����`�F�b�N���ȁH
L�̒l��傫������Ȃ�500mH��1000mH�����A���܂葽���͂Ȃ����A�V�[���h����ĂĎ��ȋ��U�����Ȃ����m�������邩�H�ł���B
�傫�߂̓S�P�[�X�ƁA���͓S�̖Ԃ�����A����ȏ�͖������ǁA�P���������Ȃ��Č����I�ł͖����B
�o�����X�̗ǂ����Ƃ�����T���Ă銴���B
���x�I�ɂ͏\�������邪�A���Ƃ́A�ꉞ�A60MHz�̉�H���i�߂Ă������Ƃ͎v���Ă���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�ȈՓI�ɁA
��H���|���܂ŕ��ŁA�u�A���~�P�[�X�v�ɓ���A�W��➑̂̌��Ԃ���Z���T�[�ɑ��z���̒��˂����āA��쓮�������Ȃ邱�Ƃ��m�F�B
���Ԃ����Ȃ苷�߂Ȃ��Ƃ����Ȃ����Ƃ͗L��܂������A�A
���̒��˂̏�ԂŁA�ԊOLED�̃����R���ɔ������邱�Ƃ��m�F���܂����B
�V�[���h���ʓ|�����ǁAOK�Ƃ����ڐ��͕t���������B
240326
�A���~�P�[�X�ɓ���Ă݂��B
����ŁA���S��650nm���x��LED��38KHz�̔��U��H���ƁA
������A�����������Ă���Ƃ͎v���Ȃ����邳�̕����ł�����������B
���U��H�͈ꉞ�A6V�쓮������(9V��OK)�A���[�U�[�́A�P���ɍ��̃��j�b�g��ڑ��ł���B
���[�U�[���ƁA���L���ł��A���˂��������X�R�[�v�Ŋϑ��ł���̂ŁA�܂萔Km�͔�Ԃ��ƂɂȂ�B
�����Ȃ�ƁA�����┽�ˌ�����̖��̕����C�����肩���m��Ȃ��B
���ᔽ�˂ȓh�����w�����Ă͂���B
------------------------------------------------------
�lj��̕������Ƃ��āA�Z���T�[�ł���t�H�g�_�C�I�[�h�ɒ��˓����Ă�ƌ�쓮�������̂����������B
��H�͂قڃV�[���h���ĂȂ��̂ŁA�m�C�Y�̑��������ł���쓮���N�����B
�܂��A����́A���g�͓S�̔��ɓ���Ă��������m�Ȃ̂�����B
��쓮���������̃��J�j�Y���́A�����炭�����ɂ���ăt�H�gDi�̃C���s�[�_���X�������邱�Ƃł���B
����ɂ���āA�R�C���Ȃǂւ̓d���U���̉e�����\�ʉ����₷���̂��Ǝv���B
�����ŁA�R�C���̃C���s�[�_���X�B
f=38KHz�ŁAL=47mH���ƁA
Z=2��fL=11.22K�����x�ƂȂ�B
�M���̘R��~�߂Ƃ��Ă͏\���ɍ�p���Ă���Ǝv���B
�����A�g���Ă���̂́A�����A�L�V�������[�h�̃}�C�N���C���_�N�^�[�Ȃ̂ŁA
�V�[���h���Ȃ����A�m�C�Y�͗U�����₷���悤�ɂ͎v���B
�^���N�^(���W�A��)�^�C�v�̃t�F���C�g�ŃV�[���h���ꂽ���m�ł͕ς�邩���m��Ȃ��B���A�����ɂ͎�ɓ���Ȃ��B
����Ō��ʂ����P����Ȃ��Ȃ�A��H���ƃV�[���h�{�b�N�X(�P�[�X)�ɓ����K�v��������B38KHz���Ƃ�͂�A�A���~���͓S���ǂ��B
���ƁA9V�Ȃ̂ŁA1K���͂�����ƃt�H�g�_�C�I�[�h�ɂƂ��ĒႷ�����S�ɂȂ邩���m��Ȃ��A1.5K�����x���ǂ������B�����C���_�N�^�̊�������R300�����x�L��B
�g���Ă��鉽�����̉�H����̎悷�邩�ȁH
100mH(104)���x�̂��~�����B�����H���ɂ��鑾�z�U�d��100mH������ƁA���ȋ��U���g����0.085MHz�Ƃ����ۂǂ��l�c�A�A
�Ƃ������ƂŁA�܂��͑Ë����ăA���~�P�[�X����`�F�b�N���ȁH
L�̒l��傫������Ȃ�500mH��1000mH�����A���܂葽���͂Ȃ����A�V�[���h����ĂĎ��ȋ��U�����Ȃ����m�������邩�H�ł���B
�傫�߂̓S�P�[�X�ƁA���͓S�̖Ԃ�����A����ȏ�͖������ǁA�P���������Ȃ��Č����I�ł͖����B
�o�����X�̗ǂ����Ƃ�����T���Ă銴���B
���x�I�ɂ͏\�������邪�A���Ƃ́A�ꉞ�A60MHz�̉�H���i�߂Ă������Ƃ͎v���Ă���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�ȈՓI�ɁA
��H���|���܂ŕ��ŁA�u�A���~�P�[�X�v�ɓ���A�W��➑̂̌��Ԃ���Z���T�[�ɑ��z���̒��˂����āA��쓮�������Ȃ邱�Ƃ��m�F�B
���Ԃ����Ȃ苷�߂Ȃ��Ƃ����Ȃ����Ƃ͗L��܂������A�A
���̒��˂̏�ԂŁA�ԊOLED�̃����R���ɔ������邱�Ƃ��m�F���܂����B
�V�[���h���ʓ|�����ǁAOK�Ƃ����ڐ��͕t���������B
240326
�A���~�P�[�X�ɓ���Ă݂��B
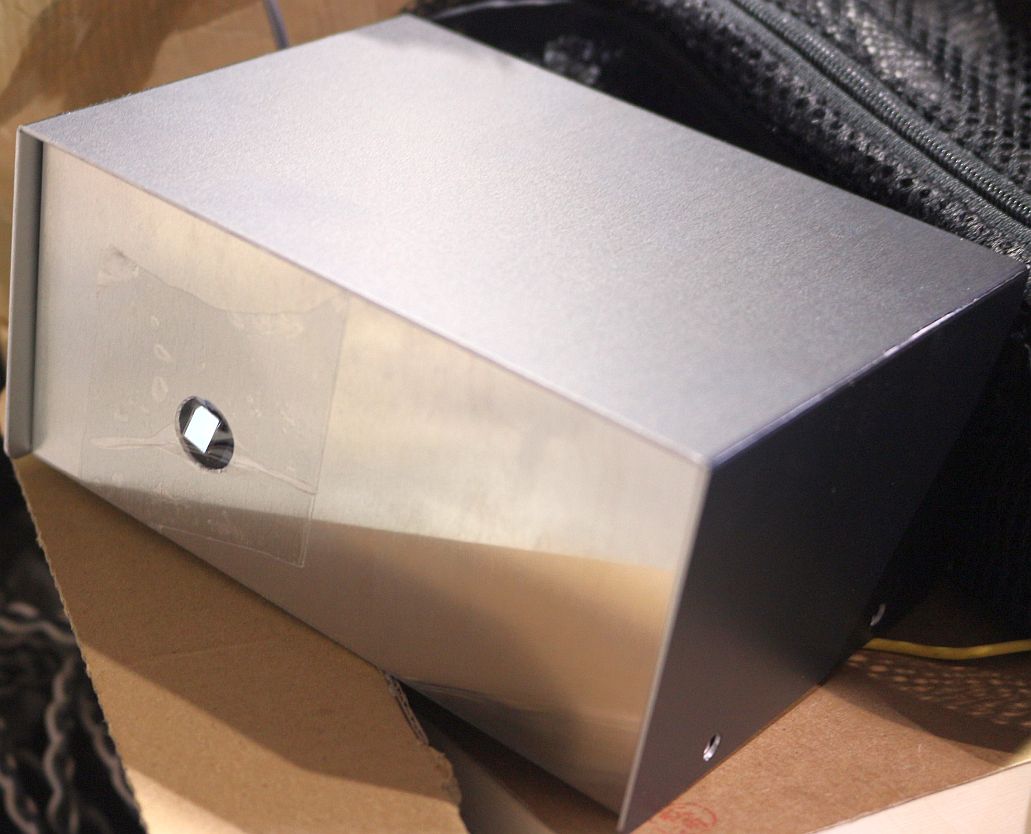 ��쓮�͂܂������Ƃ������������C������B
��H���ς̂��߁A�ꕔ�S�V�[���h�������B
���������A�A���~�P�[�X�ł̓V�[���h�����Ⴂ���Ƃ����邾�낤�B
�����̓R�C�����������B�R�����O�����B��R��1.5�`2.2KHz���ɂ�����ǂ������B
���Ɠd���̕������B�����ău�U�[���m�C�Y���ɂȂ��Ă����̂ŁA�u�U�[�̓d�����͂ɂ��R���f���T�[�����ꂽ�B
��쓮�����������A�܂��A�d���g�ȂǕʃ��[�g�����邩���m��Ȃ��B
555�Ɋւ��Ă��A�f����ON/OFF����̂ŁA�h���ɂ͂Ȃ邩���m��Ȃ��B
��쓮�͂܂������Ƃ������������C������B
��H���ς̂��߁A�ꕔ�S�V�[���h�������B
���������A�A���~�P�[�X�ł̓V�[���h�����Ⴂ���Ƃ����邾�낤�B
�����̓R�C�����������B�R�����O�����B��R��1.5�`2.2KHz���ɂ�����ǂ������B
���Ɠd���̕������B�����ău�U�[���m�C�Y���ɂȂ��Ă����̂ŁA�u�U�[�̓d�����͂ɂ��R���f���T�[�����ꂽ�B
��쓮�����������A�܂��A�d���g�ȂǕʃ��[�g�����邩���m��Ȃ��B
555�Ɋւ��Ă��A�f����ON/OFF����̂ŁA�h���ɂ͂Ȃ邩���m��Ȃ��B
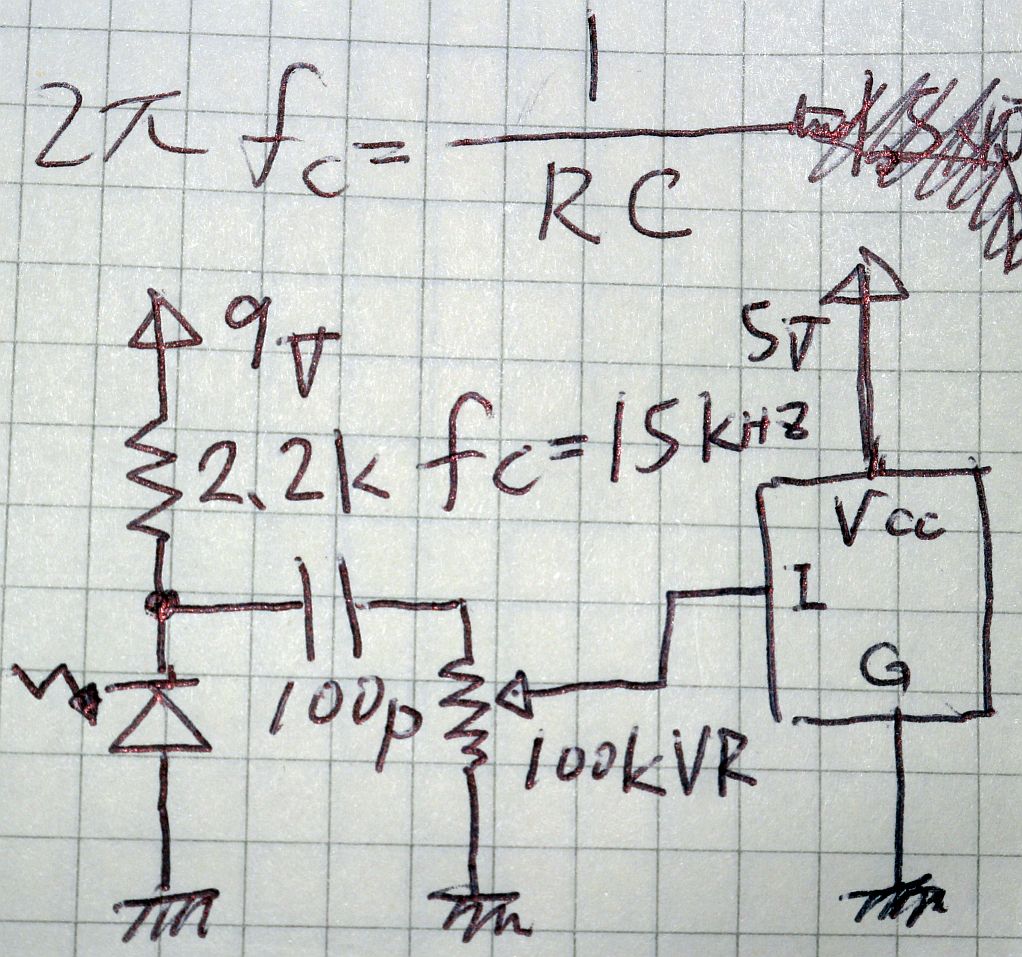
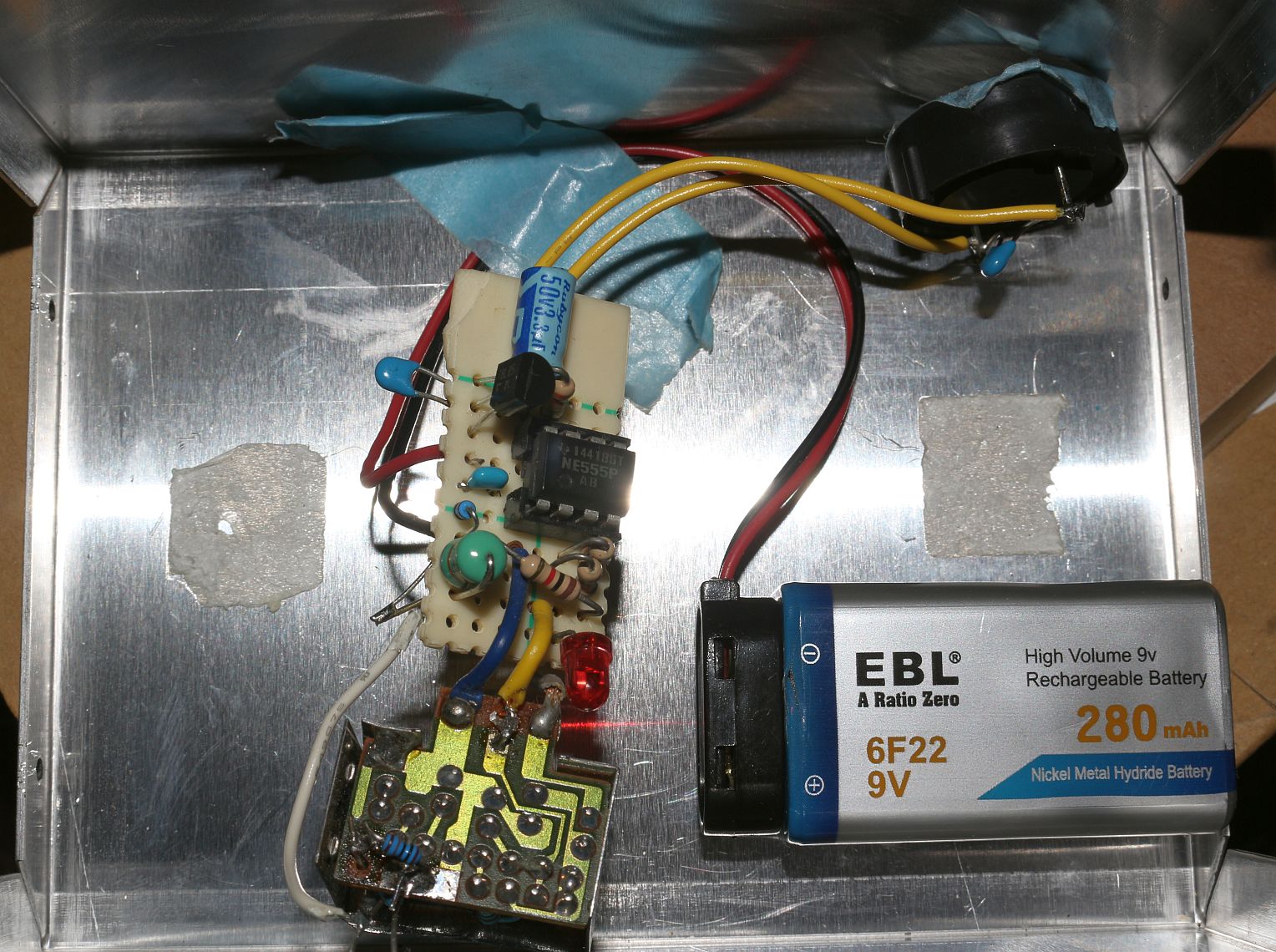 ���̖��Ɋւ��ẮA�Ռ��h�������\������₷���A�}�X�L���O�e�[�v��t���������ň�C�ɔ������̂ŁA�G�i�����h���Ƃ��A�v���C�}�[�������Ă݂�K�v��������B
�O�����ւ̔��f�ɑ��Ă͂��̔����挈���ȁ[�ƁA
�ڒ��ܕ����̓h���̔�������l���Ȃ��ƁB�B
�����_�A���x���������āA�����d���̓d��ON/OFF�ł�BPF���N����̂��쓮����B�������LD�ł��ł���B
�Ռ��Ō��炷�̂��K�v�B
���������A�t�H�g�_�C�I�[�h����ʐςȂ̂ŁA���ɂ��q�������ǁA����́AS/N��ɂ��ւ��̂ŁA���̂܂܂ɂ��邩�A�ʐς�������Ƃ��Ă������Ƃ��������B
���[�U�[�ł͐�Km��Ԃ̂͗]�T�ł���Ǝv���̂ŁA��쓮�����炷�̂��ۑ�ł���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�NjL��
�Ռ��́A�����ǂ����ȁ[�A�A�Ǝv�����B
�A���~����Ռ��e�[�v����t����ȂǁB
4�`5mm�p���x�̌���������̂��l�b�N���ȁH
�������͌��\�@�ׂ��Ƃ͎v���B
�h�������Ƃ����b�V���[�Ƃ��Ȃ�B
------------------------------------------------------
240327
�Ռ��͂Ƃ肠�����A���b�V���[�ɂāA
���̖��Ɋւ��ẮA�Ռ��h�������\������₷���A�}�X�L���O�e�[�v��t���������ň�C�ɔ������̂ŁA�G�i�����h���Ƃ��A�v���C�}�[�������Ă݂�K�v��������B
�O�����ւ̔��f�ɑ��Ă͂��̔����挈���ȁ[�ƁA
�ڒ��ܕ����̓h���̔�������l���Ȃ��ƁB�B
�����_�A���x���������āA�����d���̓d��ON/OFF�ł�BPF���N����̂��쓮����B�������LD�ł��ł���B
�Ռ��Ō��炷�̂��K�v�B
���������A�t�H�g�_�C�I�[�h����ʐςȂ̂ŁA���ɂ��q�������ǁA����́AS/N��ɂ��ւ��̂ŁA���̂܂܂ɂ��邩�A�ʐς�������Ƃ��Ă������Ƃ��������B
���[�U�[�ł͐�Km��Ԃ̂͗]�T�ł���Ǝv���̂ŁA��쓮�����炷�̂��ۑ�ł���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�NjL��
�Ռ��́A�����ǂ����ȁ[�A�A�Ǝv�����B
�A���~����Ռ��e�[�v����t����ȂǁB
4�`5mm�p���x�̌���������̂��l�b�N���ȁH
�������͌��\�@�ׂ��Ƃ͎v���B
�h�������Ƃ����b�V���[�Ƃ��Ȃ�B
------------------------------------------------------
240327
�Ռ��͂Ƃ肠�����A���b�V���[�ɂāA
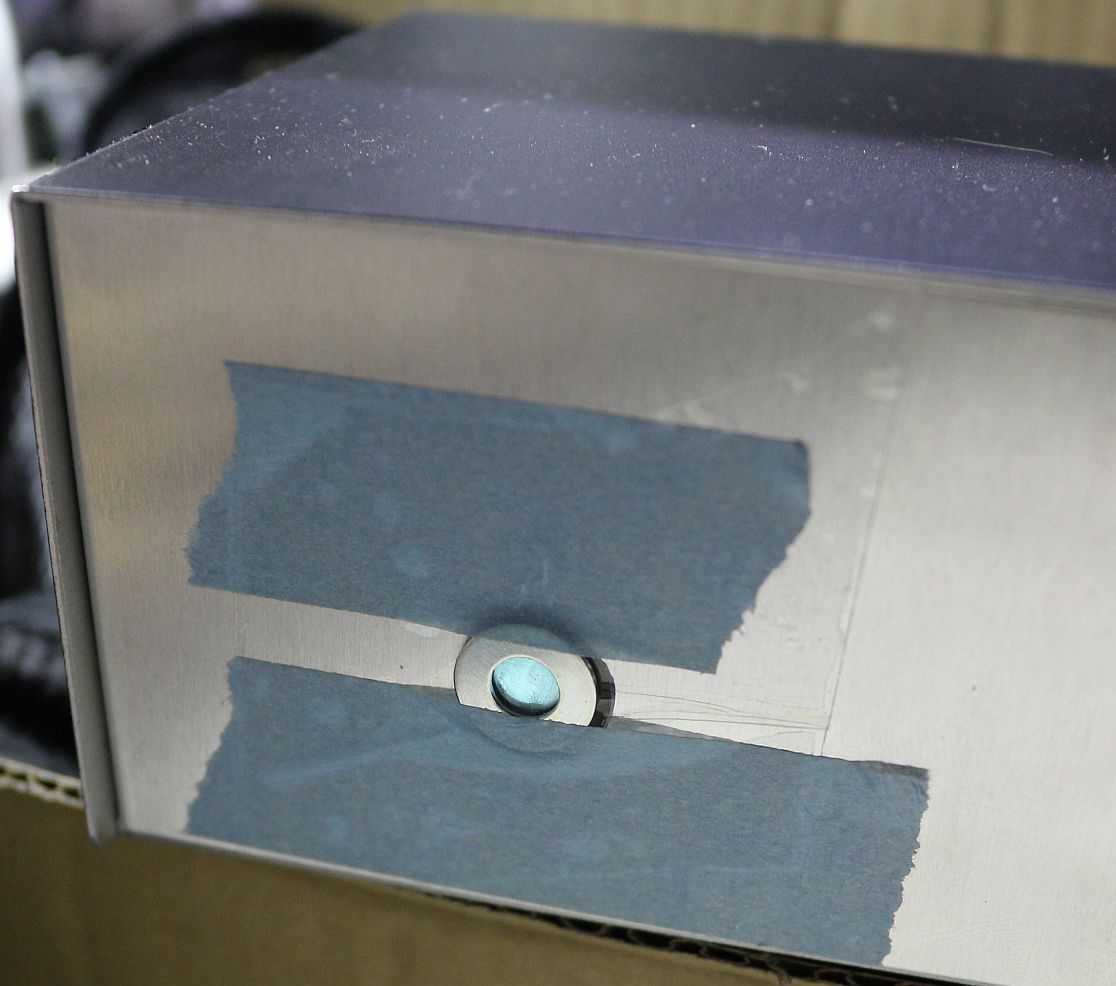 ���p��ɖ�肪���O����郌�x���Ŋ��x���Ⴗ���邱�ƂɋC�����B
�����A������H�̎��萔��Z���B
�ŁA�܂��A�lj���H�̐ݒ���������Ȃ��璼�˓����Ń`�F�b�N����B
�E���˓����Ƌt�o�C�A�X�̃R�C�����Ȃ��������������B�˓�˒P�Ɋ��x�㏸�ƃP�[�X�ւ̃m�C�Y�N���̊W���ȁH����Ƃ��A���̃m�C�Y���R�C�����U�������肷��H�A�R�C����C�����ŋ��U�Ƃ��H
�E���˓����́A��őf�����`���b�s���O���Ă��������Ă��܂��B��HPF��lj��������B�˔�����H��Fc=15KHz�ɐݒ肵�����肾�������AIC���̓���Z�������s���Ȃ̂�(����C�Ńf�J�b�v�����O����Ă���B)
LCR���[�^�[�ŁA10KHz�A100KHz�ł�IC���͂�Z�ʂ͌����邩���m��Ȃ��B
�E�u�U�[�̃m�C�Y���L��H�t�o�C�A�X�։�荞��ł�H
���Ƃ́A�������̃p���X���ƂĂ��Y��Ƃ͌����Ȃ��̂ŁA���ǂ�����������m�\�͂��オ�邩������Ȃ��B
���p��ɖ�肪���O����郌�x���Ŋ��x���Ⴗ���邱�ƂɋC�����B
�����A������H�̎��萔��Z���B
�ŁA�܂��A�lj���H�̐ݒ���������Ȃ��璼�˓����Ń`�F�b�N����B
�E���˓����Ƌt�o�C�A�X�̃R�C�����Ȃ��������������B�˓�˒P�Ɋ��x�㏸�ƃP�[�X�ւ̃m�C�Y�N���̊W���ȁH����Ƃ��A���̃m�C�Y���R�C�����U�������肷��H�A�R�C����C�����ŋ��U�Ƃ��H
�E���˓����́A��őf�����`���b�s���O���Ă��������Ă��܂��B��HPF��lj��������B�˔�����H��Fc=15KHz�ɐݒ肵�����肾�������AIC���̓���Z�������s���Ȃ̂�(����C�Ńf�J�b�v�����O����Ă���B)
LCR���[�^�[�ŁA10KHz�A100KHz�ł�IC���͂�Z�ʂ͌����邩���m��Ȃ��B
�E�u�U�[�̃m�C�Y���L��H�t�o�C�A�X�։�荞��ł�H
���Ƃ́A�������̃p���X���ƂĂ��Y��Ƃ͌����Ȃ��̂ŁA���ǂ�����������m�\�͂��オ�邩������Ȃ��B
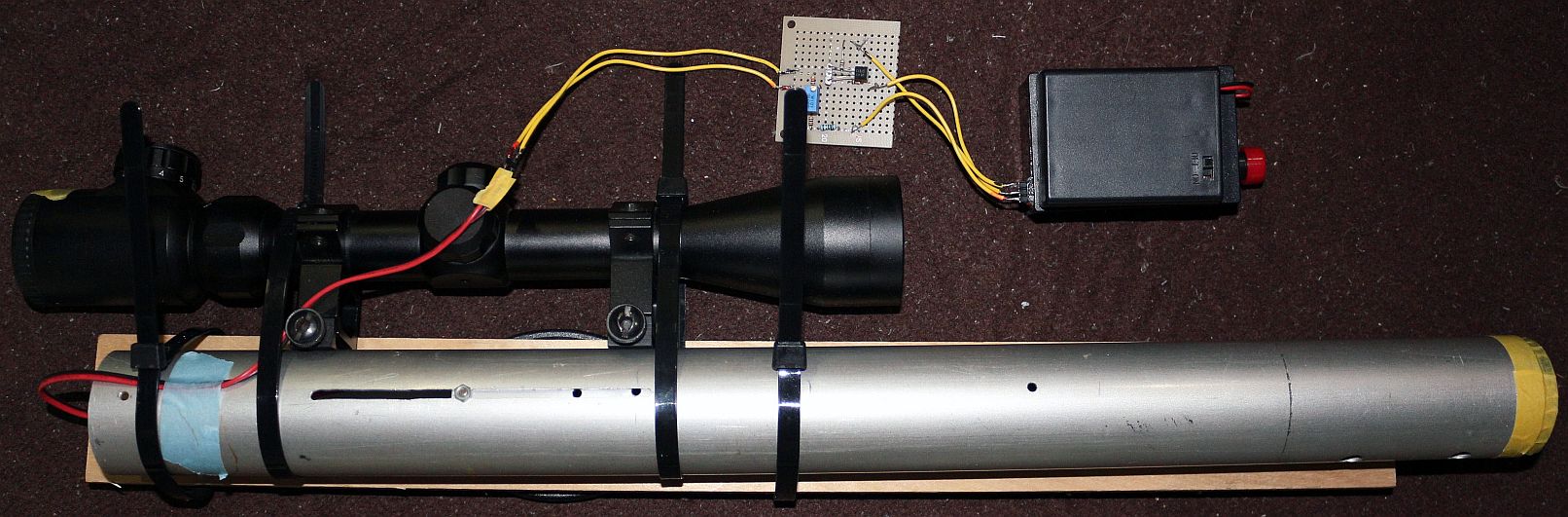 �Ȃ̂ŗL�]�Ȃ̂ł��邪�A�A
�������̂낭�����闝�R�ɁA���͂Ƀ��[�h��R(�^�[�~�l�[�^�[)�����Y��Ă����̂�����B�܂�A�I�V���̓��͂̊e�ʂȂǂ̉e�����Ă��B
���M���́A�ꉞ�A�R���N�^�G�~�b�^�Ԃ�1K�������Čy�����点�Ă���B
�Ƃ肠�����A100K�����O���āAC���Ƃ������Ђ��������āA0.001��F���x�ŁA���˓����̃`���b�s���O�ɔ������Â炭�A���x������قǗ����Ȃ��Ƃ���ɂȂ����B
���Ƃ́A���������ȁH���̏�Ԃł��A���Ȃ肢���邪�A�p���X���Y��ɂ�����A�L�т����ł͂���B
�ق��ɂ́ALD���W���[���o�͂̑傫�ȃ��m�ŁA
�u�d�l:��-100mw @ 650nm�A ��11.93x15.2mm�A����d��: 2.5v�A����d��: 130mA�v
�Ƃ����̂���r�I�����̂Ŏ����Ă��邪�A���S�K���̖��ŁA�u�ԓI�Ɍ��点��R�g�ƁA�r�[����������x�������邱�Ƃ��ȁB
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���[�U�[�����e�A������j�b�g�̃g���u���ˉ��
240327-02
���z�̋���Ȍ��𗁂т��Ȃ���`�F�b�N���Ă��̂����ǁA
�r������A�����Ȃ�A�u�U�[������ςȂ��ɂȂ����B
�ܔM�ȑ��z�̔M���A���̋����ɂ��ߓd���Ńt�H�g�_�C�I�[�h�̗����H�Ǝv���ĊO���Ă���~�܂Ȃ��B
�����ԃC���C������čŏI�I�Ɍ������̂́A�t�o�C�A�X����͂���O�����Ƃ������B
���Ⴀ��������m�C�Y������̂��H�Ǝv���ƁA���ɂ������d�����������Ă��邵�A�A
�Ƃ肠�����A555��ς��Ă݂�˕ς��Ȃ��B���M�����[�^�[�̓d�����I�V�����܂߂Č���B�ُ�Ȃ��B
���W���[����C���Â��Ǝv���A�S�������Ă��ω������B
CX20106A�̖��Ƃ��v�����A�A
���͂��V���[�g������ƍł��Â��ɂ͂Ȃ�B
C���L�邩��d�ׂ����������ǂ��Ǝv���A100K����߂��A���t����B
���A�ω������B
�S���A�ُ�Ȏ��ԂɎv����B
CX20106A��IC�\�P�b�g�ɂ��āA�ʂ̂��w���A�������ǂ����ȁH
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�t�o�C�A�X�Ƀm�C�Y�����́A
���M�����^�[IC���s����ɓd�C��H���Ă�Ɣ��f�B
��R��1K����2K���ɂ��āA
�d�r����̃��[�h���ƁA���M�����[�^�[�A�t�o�C�A�X�̕���_�ɁA�e�ʂ̑傫�ȃR���f���T�[�łȂ�Ƃ���������ɕω����ė������ǁA
�����A���͂͂��̂������@�ׂ����A�m�C�Y�͎���Ė����̂��ȁ[�A�A
�C���_�N�^���L���ɂ��āA�[���Ȃ̂ŁA���͉����d���Ŋm�F���B�c�����2K���͂��傢�����݂����B�ア���̊��x���ς��B
�Ƃ肠�����̖��͂Ȃ����������ǁA2K���ƃR�C�����������Ȃ����͓��ɓ��ĂĂ݂Ȃ��Ɓ`�B
�d�r����̃��[�h���͔n���ɂȂ�Ȃ���R�l�Ȃ̂��H
�����g�p��ESR��0.1��F���A100��F�ȑ�e�ʂ̓d���̕����������̂́A����d���̃J�b�g�I�t���g���̊W���낤�B
���Ƃ́A���Ɋ��x�����������ɋ������Ă�g�R�B
�������A�Ȃ��ɃC�L�i�������Ȃ����̂��s���A�A���M�����^�[��������ԂƂ��H�H
���M�����[�^�[�́ANFB���������Ă�̂ŁA�e�ʐ��̑傫�����ׂ͐������������肷��̂ł����A�����͑��߂ɐݒ肵����C���C���ς��Ă��ω������ŁA
���̎�O�Ŗ�肪�N���Ă����Ƃ́`�A�A
240329:�NjL��
���z�����˂ɂāA�t�o�C�A�X��H�ɃC���_�N�^��p���Ă����Ȃ������Ȍ��ʂ܂����B
�������A��őf�����`���b�s���O����Ɣ������Ă��܂��悤�Ȃ̂ŁA�f�J�b�v�����O�R���f���T�[�����������������ǂ������B
���Ƃ́A2K������⏬�����A1.5K���x�ɂ���Ɨǂ������B
L�͍X�ɑ傫���Ă��ǂ���������Ȃ����ǁA���[�U�[�ł͂��̕K�v���͂Ȃ������B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�O���[�����[�U�[�͂ǂ����H
�Ȃ̂ŗL�]�Ȃ̂ł��邪�A�A
�������̂낭�����闝�R�ɁA���͂Ƀ��[�h��R(�^�[�~�l�[�^�[)�����Y��Ă����̂�����B�܂�A�I�V���̓��͂̊e�ʂȂǂ̉e�����Ă��B
���M���́A�ꉞ�A�R���N�^�G�~�b�^�Ԃ�1K�������Čy�����点�Ă���B
�Ƃ肠�����A100K�����O���āAC���Ƃ������Ђ��������āA0.001��F���x�ŁA���˓����̃`���b�s���O�ɔ������Â炭�A���x������قǗ����Ȃ��Ƃ���ɂȂ����B
���Ƃ́A���������ȁH���̏�Ԃł��A���Ȃ肢���邪�A�p���X���Y��ɂ�����A�L�т����ł͂���B
�ق��ɂ́ALD���W���[���o�͂̑傫�ȃ��m�ŁA
�u�d�l:��-100mw @ 650nm�A ��11.93x15.2mm�A����d��: 2.5v�A����d��: 130mA�v
�Ƃ����̂���r�I�����̂Ŏ����Ă��邪�A���S�K���̖��ŁA�u�ԓI�Ɍ��点��R�g�ƁA�r�[����������x�������邱�Ƃ��ȁB
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���[�U�[�����e�A������j�b�g�̃g���u���ˉ��
240327-02
���z�̋���Ȍ��𗁂т��Ȃ���`�F�b�N���Ă��̂����ǁA
�r������A�����Ȃ�A�u�U�[������ςȂ��ɂȂ����B
�ܔM�ȑ��z�̔M���A���̋����ɂ��ߓd���Ńt�H�g�_�C�I�[�h�̗����H�Ǝv���ĊO���Ă���~�܂Ȃ��B
�����ԃC���C������čŏI�I�Ɍ������̂́A�t�o�C�A�X����͂���O�����Ƃ������B
���Ⴀ��������m�C�Y������̂��H�Ǝv���ƁA���ɂ������d�����������Ă��邵�A�A
�Ƃ肠�����A555��ς��Ă݂�˕ς��Ȃ��B���M�����[�^�[�̓d�����I�V�����܂߂Č���B�ُ�Ȃ��B
���W���[����C���Â��Ǝv���A�S�������Ă��ω������B
CX20106A�̖��Ƃ��v�����A�A
���͂��V���[�g������ƍł��Â��ɂ͂Ȃ�B
C���L�邩��d�ׂ����������ǂ��Ǝv���A100K����߂��A���t����B
���A�ω������B
�S���A�ُ�Ȏ��ԂɎv����B
CX20106A��IC�\�P�b�g�ɂ��āA�ʂ̂��w���A�������ǂ����ȁH
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�t�o�C�A�X�Ƀm�C�Y�����́A
���M�����^�[IC���s����ɓd�C��H���Ă�Ɣ��f�B
��R��1K����2K���ɂ��āA
�d�r����̃��[�h���ƁA���M�����[�^�[�A�t�o�C�A�X�̕���_�ɁA�e�ʂ̑傫�ȃR���f���T�[�łȂ�Ƃ���������ɕω����ė������ǁA
�����A���͂͂��̂������@�ׂ����A�m�C�Y�͎���Ė����̂��ȁ[�A�A
�C���_�N�^���L���ɂ��āA�[���Ȃ̂ŁA���͉����d���Ŋm�F���B�c�����2K���͂��傢�����݂����B�ア���̊��x���ς��B
�Ƃ肠�����̖��͂Ȃ����������ǁA2K���ƃR�C�����������Ȃ����͓��ɓ��ĂĂ݂Ȃ��Ɓ`�B
�d�r����̃��[�h���͔n���ɂȂ�Ȃ���R�l�Ȃ̂��H
�����g�p��ESR��0.1��F���A100��F�ȑ�e�ʂ̓d���̕����������̂́A����d���̃J�b�g�I�t���g���̊W���낤�B
���Ƃ́A���Ɋ��x�����������ɋ������Ă�g�R�B
�������A�Ȃ��ɃC�L�i�������Ȃ����̂��s���A�A���M�����^�[��������ԂƂ��H�H
���M�����[�^�[�́ANFB���������Ă�̂ŁA�e�ʐ��̑傫�����ׂ͐������������肷��̂ł����A�����͑��߂ɐݒ肵����C���C���ς��Ă��ω������ŁA
���̎�O�Ŗ�肪�N���Ă����Ƃ́`�A�A
240329:�NjL��
���z�����˂ɂāA�t�o�C�A�X��H�ɃC���_�N�^��p���Ă����Ȃ������Ȍ��ʂ܂����B
�������A��őf�����`���b�s���O����Ɣ������Ă��܂��悤�Ȃ̂ŁA�f�J�b�v�����O�R���f���T�[�����������������ǂ������B
���Ƃ́A2K������⏬�����A1.5K���x�ɂ���Ɨǂ������B
L�͍X�ɑ傫���Ă��ǂ���������Ȃ����ǁA���[�U�[�ł͂��̕K�v���͂Ȃ������B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�O���[�����[�U�[�͂ǂ����H
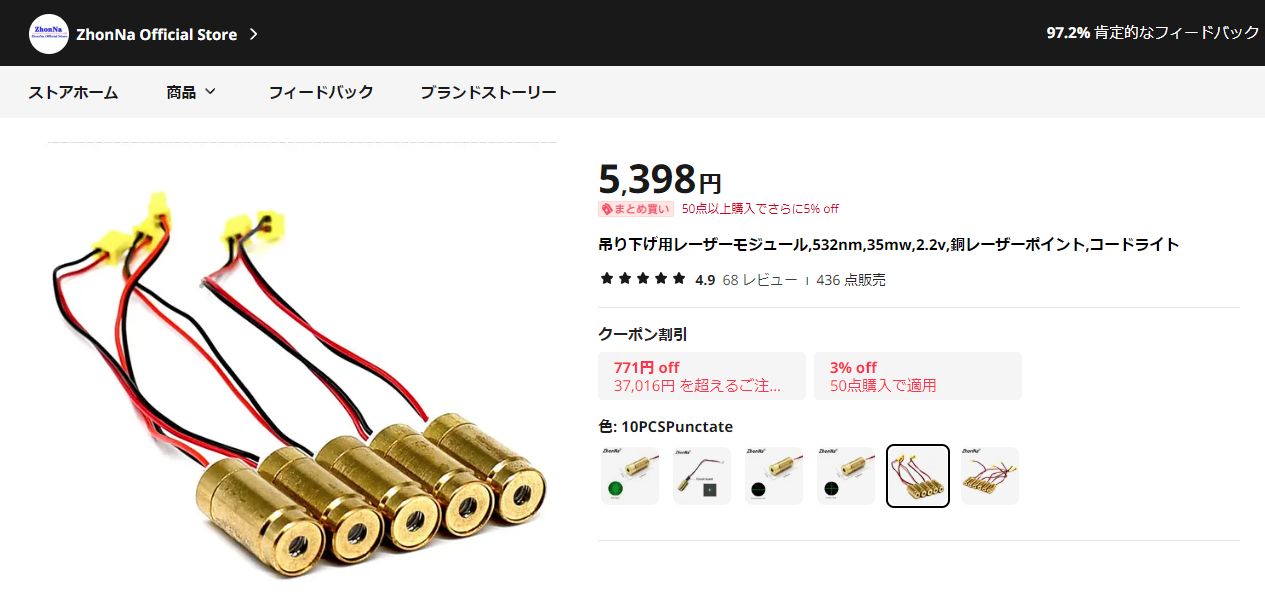
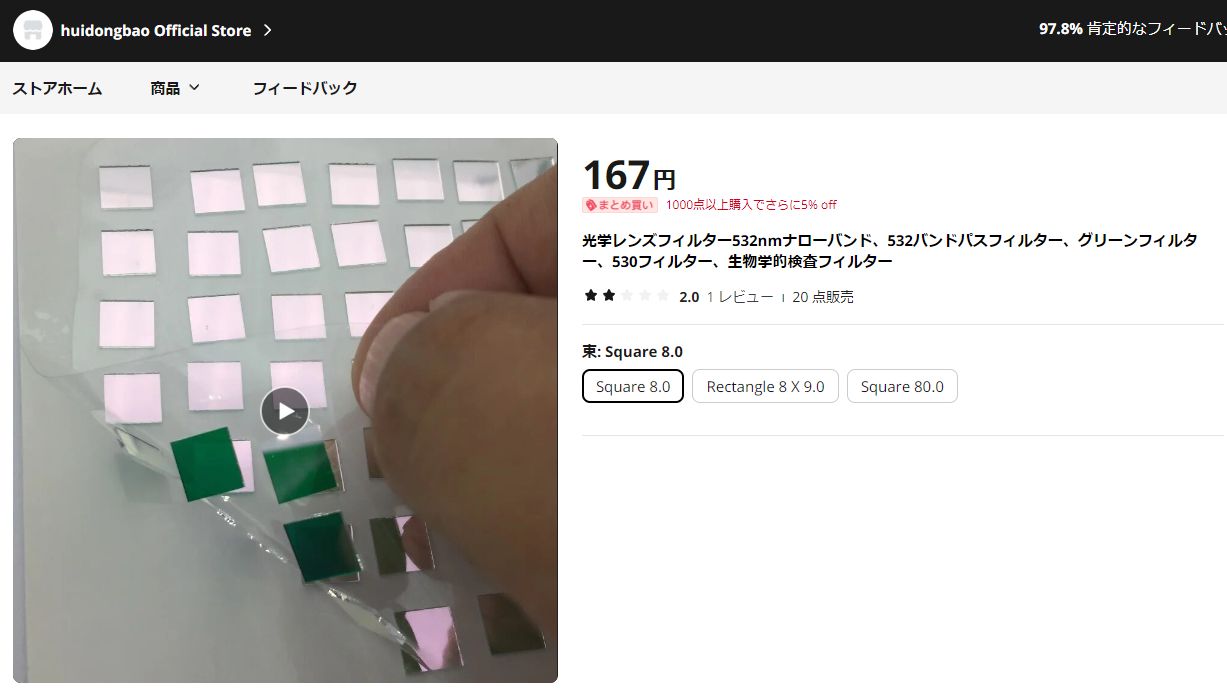 �܂��A�����B����������ABPF�̕���3�ȏゾ�Ƃ��Ȃ�̃��[�g�ŏオ���Ă����B
���_�́A�������b�e�[�W�ł��A���Ȃ薾�邭�����邱�ƁB
38KHz�ł͎g���邾�낤���ǁA60MHz�쓮�͖��m���B
�t�H�gDi�́A���������d�v������Ȃ�Pin�t�H�g�_�C�I�[�h�����ǁA
38KHz�Ȃ�A550nm�t�߂Ƀs�[�N�̉����d���̂ł��ǂ��Ǝv���B
BPF�̎d�l
���S�g��: 532 + - 5nm
�n�[�t�ш敝: 20nm
�s�[�N���ߗ�: �� 90%
�J�b�g�I�t�̐[��: �� 1%
LD��35mW�Ȃ̂ŁA���傢��߂ɔ���������̂��e���ȁH
���[�U�[����: 8000 - 30000����
���[�U�[�g��: 532nm
���[�U�[�p���[: 35mw
����d��: 2.1 - 2.2v
�ғ��d��: ��260ma-350ma
�����ƈ���50mW�̃h���C�u��H�������������A
�h���C�u��H�͐M���̎ז��ł��邵�A➑̂Ƀq�[�g�V���N���K�v�Ƃ̂��Ƃł�����l����Ɗ����ł���Ƃ��������B
�����Ă�Ԃ̃n�C�p���[�Ȃ̂�
��-100mw @ 650nm�A ��11.93x15.2mm�A����d��: 2.5v�A����d��: 130ma�B
�Ȃ̂ŁA�̓��b�e�[�W�̊��ɓd����H���B
�X�C�b�`���OTr��I�Ԃ��ƂɁB
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
240331
300mH�̑傫�ȃC���_�N�^���������̂ŁA�ڑ��B
���z�����˂ł̓d���O�a���R��1K���ɁB
�`���b�s���O��ɁA1000pF��330pF
�܂��A�����B����������ABPF�̕���3�ȏゾ�Ƃ��Ȃ�̃��[�g�ŏオ���Ă����B
���_�́A�������b�e�[�W�ł��A���Ȃ薾�邭�����邱�ƁB
38KHz�ł͎g���邾�낤���ǁA60MHz�쓮�͖��m���B
�t�H�gDi�́A���������d�v������Ȃ�Pin�t�H�g�_�C�I�[�h�����ǁA
38KHz�Ȃ�A550nm�t�߂Ƀs�[�N�̉����d���̂ł��ǂ��Ǝv���B
BPF�̎d�l
���S�g��: 532 + - 5nm
�n�[�t�ш敝: 20nm
�s�[�N���ߗ�: �� 90%
�J�b�g�I�t�̐[��: �� 1%
LD��35mW�Ȃ̂ŁA���傢��߂ɔ���������̂��e���ȁH
���[�U�[����: 8000 - 30000����
���[�U�[�g��: 532nm
���[�U�[�p���[: 35mw
����d��: 2.1 - 2.2v
�ғ��d��: ��260ma-350ma
�����ƈ���50mW�̃h���C�u��H�������������A
�h���C�u��H�͐M���̎ז��ł��邵�A➑̂Ƀq�[�g�V���N���K�v�Ƃ̂��Ƃł�����l����Ɗ����ł���Ƃ��������B
�����Ă�Ԃ̃n�C�p���[�Ȃ̂�
��-100mw @ 650nm�A ��11.93x15.2mm�A����d��: 2.5v�A����d��: 130ma�B
�Ȃ̂ŁA�̓��b�e�[�W�̊��ɓd����H���B
�X�C�b�`���OTr��I�Ԃ��ƂɁB
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
240331
300mH�̑傫�ȃC���_�N�^���������̂ŁA�ڑ��B
���z�����˂ł̓d���O�a���R��1K���ɁB
�`���b�s���O��ɁA1000pF��330pF
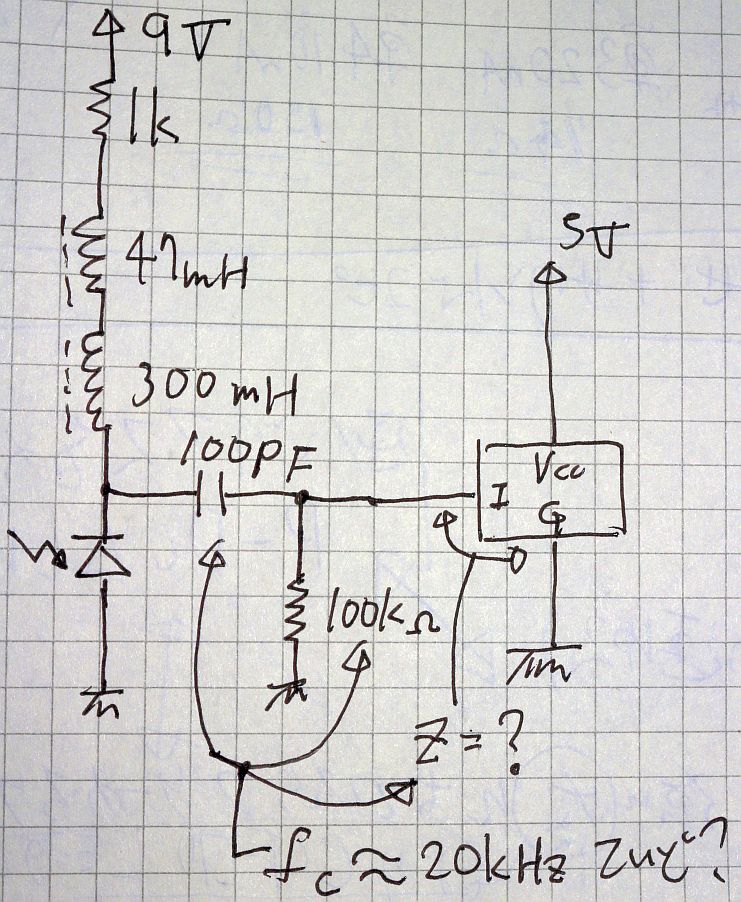
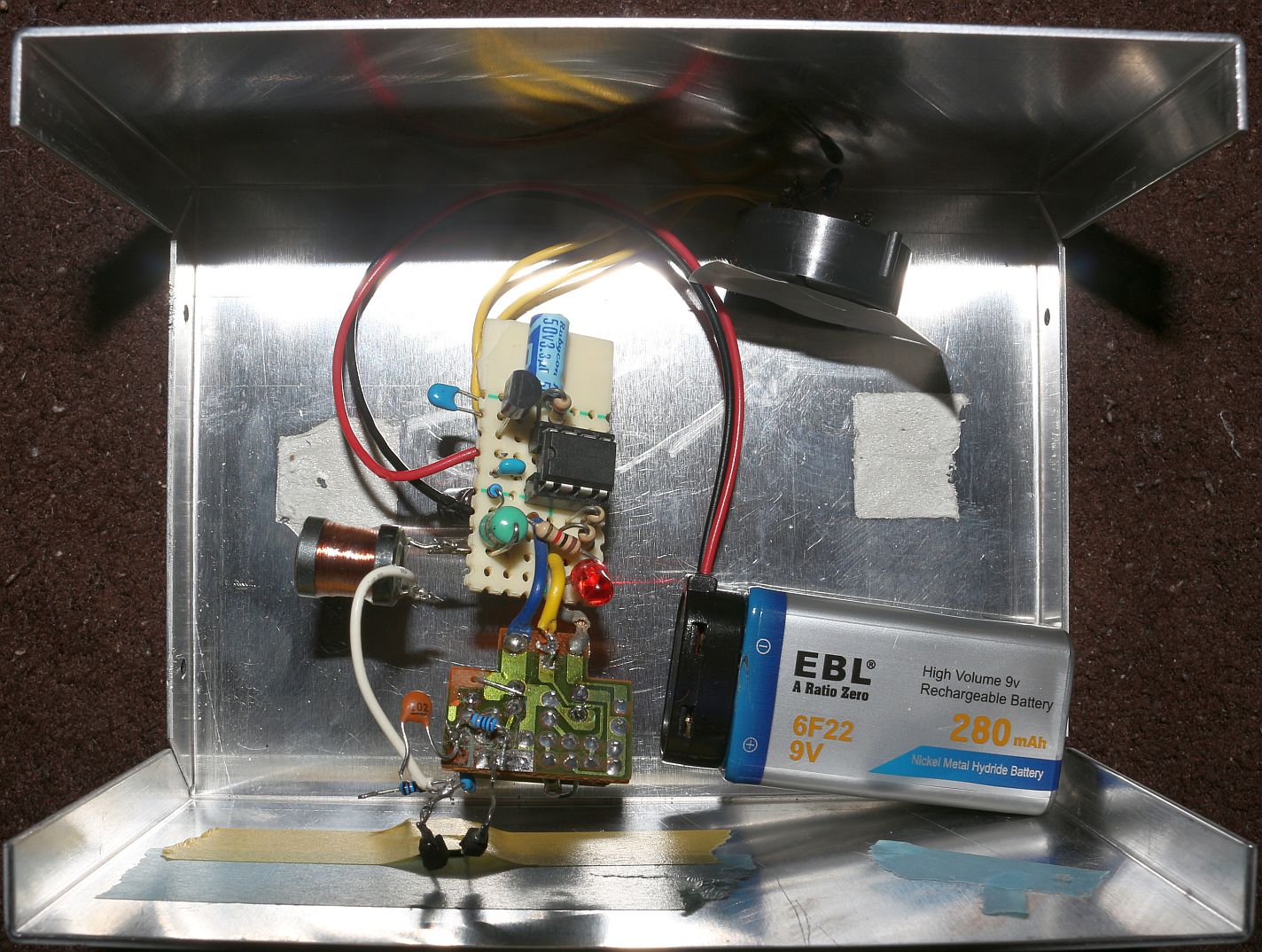 LCR���[�^�[�Ō����Ƃ���ACX20106A�̓���Z�́A38KHz�ł�5�`10K���ʂ��肻�����B�ꍇ�ɂ���Ă�100K���͕K�v�������B
����ĊO�����B
���̏�Ԃ�AM8:00�̒��˓����Ń`���b�s���O�ł̓G���[���o�Ȃ��B
�ۑ�Ƃ��ẮA�����m�C�Y��̗L��ꏊ�ł̓A���~�P�[�X�ł���쓮���N����B���S�P�[�X�Ȃǂ������B
�����p���X��������ALED���C�g��CCFL�����j�^�[�̋߂����ƌ�쓮����B�����߃��x���Ȃ̂ŊW�Ȃ��悤���B���A������LED�����d���̏Ǝ˂ɂ͋����e���ˊ��x�𗎂Ƃ��B�B
�NjL��
300mH�Ȃ��ǁA�^������12���Ƀ`�F�b�N���悤�Ƃ���O�ɒ����f�������B
�Ȃ̂ŁA���`�F�b�N�B
�O����47mH�݂̂Ń`���b�s���O���Ĕ��������Ȃ̂ŁA�܂��A����Ȃ肩�ȁH
�����500mH�������A�t���Ă݂�ƁA��쓮���~�܂�Ȃ��B�B�����A���ȋ��U�������A�m�C�Y���z���Ă���̂��̂ǂ��炩���낤�B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
240402
�u���[�U�[�����e�v����̌��w�n��ς��A�đ���B
�O�ɍ���Ďg���Ă������x�̑���n��MHz�ш�p�������Ŕ����v�f�������A�܂��A��͐ϕ��v�f�����������̂ŕϒ����Ȃǂ��킩��ɂ��������B
�����ŁA����������DC����v���悤�ɂ��A�^�[�~�l�[�^�[��50����2K���ɂ����B
GLOCK17���[�U�[�����e
LCR���[�^�[�Ō����Ƃ���ACX20106A�̓���Z�́A38KHz�ł�5�`10K���ʂ��肻�����B�ꍇ�ɂ���Ă�100K���͕K�v�������B
����ĊO�����B
���̏�Ԃ�AM8:00�̒��˓����Ń`���b�s���O�ł̓G���[���o�Ȃ��B
�ۑ�Ƃ��ẮA�����m�C�Y��̗L��ꏊ�ł̓A���~�P�[�X�ł���쓮���N����B���S�P�[�X�Ȃǂ������B
�����p���X��������ALED���C�g��CCFL�����j�^�[�̋߂����ƌ�쓮����B�����߃��x���Ȃ̂ŊW�Ȃ��悤���B���A������LED�����d���̏Ǝ˂ɂ͋����e���ˊ��x�𗎂Ƃ��B�B
�NjL��
300mH�Ȃ��ǁA�^������12���Ƀ`�F�b�N���悤�Ƃ���O�ɒ����f�������B
�Ȃ̂ŁA���`�F�b�N�B
�O����47mH�݂̂Ń`���b�s���O���Ĕ��������Ȃ̂ŁA�܂��A����Ȃ肩�ȁH
�����500mH�������A�t���Ă݂�ƁA��쓮���~�܂�Ȃ��B�B�����A���ȋ��U�������A�m�C�Y���z���Ă���̂��̂ǂ��炩���낤�B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
240402
�u���[�U�[�����e�v����̌��w�n��ς��A�đ���B
�O�ɍ���Ďg���Ă������x�̑���n��MHz�ш�p�������Ŕ����v�f�������A�܂��A��͐ϕ��v�f�����������̂ŕϒ����Ȃǂ��킩��ɂ��������B
�����ŁA����������DC����v���悤�ɂ��A�^�[�~�l�[�^�[��50����2K���ɂ����B
GLOCK17���[�U�[�����e
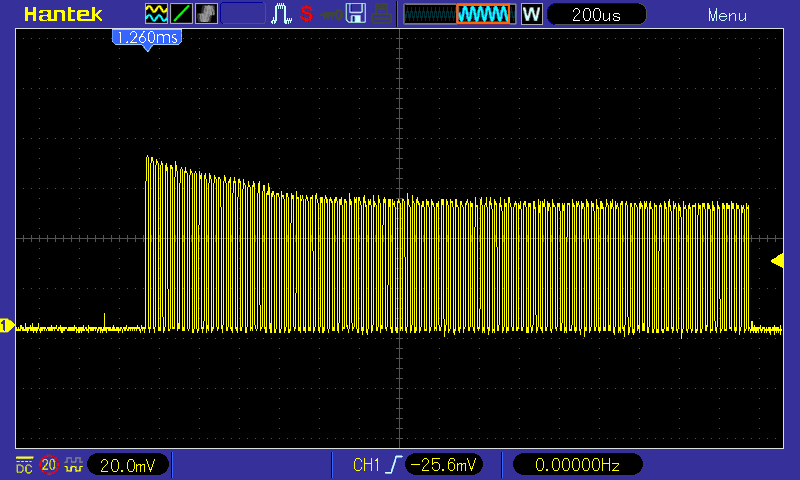
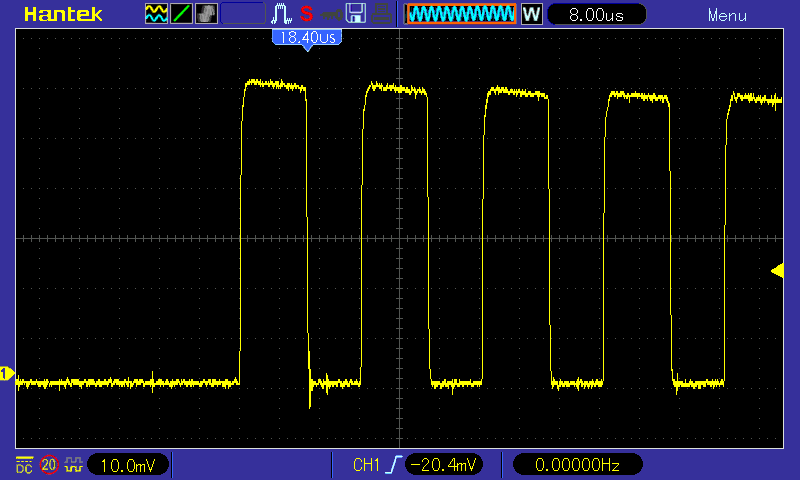 �d���ɃR���f���T�[�g�p�������̂��߂��A�ŏ��������B
���g���́A������H�������Ă�̂Ō��Â炢���A�A
4Div�~40��Sec��5�������x������AT=32��Sec
31KHz�ӂ肩�ȁH
����p���X��H
�d���ɃR���f���T�[�g�p�������̂��߂��A�ŏ��������B
���g���́A������H�������Ă�̂Ō��Â炢���A�A
4Div�~40��Sec��5�������x������AT=32��Sec
31KHz�ӂ肩�ȁH
����p���X��H
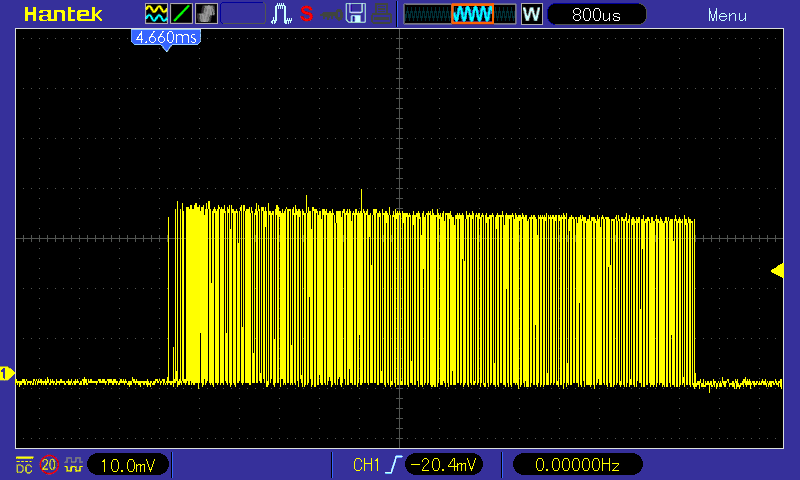
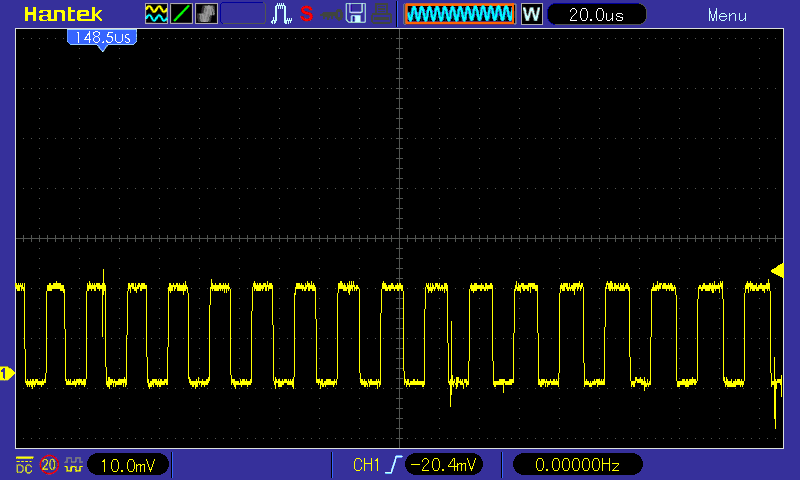 ����̂̓p���X���Ԃ������B�X�C�b�`�M���̔�����H�̎��萔����������ݒ肾�Ǝv���B�������́A�����ꎞ�I�Ɍ̈ӂɘM���Ă������悤���B
���ҕϒ�����100%�߂��悤�����A���[�U�[�͊Ԑڌ��A�����LED�Œ��ڌ��ɋ߂������̂ɁA���[�U�[�̕��������o���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���M���́A
�f���[�e�B�[��̋ψꐫ�A���M���g���̐��m���ƈ��萫�B
�p���X��Z�����邱�ƁB���K�v�Ȋ����B
���g���w��p��VR���T�[���b�g�ȑ���]�ɁB���o��������R��ɂ���B
�X�C�b�`�̔����pC���������B
��M���̃`�F�b�N�́A
�o�C�A�X�ɃC���_�N�^100mH���q���ł݂��B�������~�܂Ȃ��̂ŁA�m�C�Y���z���Ă邩�A���ȋ��U���g��85KHz�Ɉ����������Ă邩���m��Ȃ��B
�Ƃ肠�����A100mH�C���_�N�^2�������������݂��Ⴂ�ɒ���Ɍq���ł݂����ǁA�����͎~�܂Ȃ��̂ŁA�t�B�[���h�m�C�Y���z���Ă�\���͒Ⴂ���ȁH�Ɗ������B
���M���g���̌��ς���ɁA���g���J�E���^�[�͂��܂萄�����Ȃ��B�A�X�y�N�g����͂��s���Ă���킯�Ŗ����A�X���b�V�����h�����𐔂��Ă邾���Ȃ̂ŁA�s����A�s���m�ȂƂ�������B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�����e�p�̃O���[�����[�U�[�̃u�c���͂����B
�܂��́A���B
ACC��H�����[�U�[���W���[���Ƃ��������[�U�[�_�C�I�[�h�̌�[�ɒ��ɕt���Ă���B
(ACC��H�����ŕʔ�������Ă�̂ŁA�����Ɨ\�z�����Ă����B)
�܂��͔M���k�`���[�u����āA�z�b�g�{���h�����B
����̂̓p���X���Ԃ������B�X�C�b�`�M���̔�����H�̎��萔����������ݒ肾�Ǝv���B�������́A�����ꎞ�I�Ɍ̈ӂɘM���Ă������悤���B
���ҕϒ�����100%�߂��悤�����A���[�U�[�͊Ԑڌ��A�����LED�Œ��ڌ��ɋ߂������̂ɁA���[�U�[�̕��������o���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
���M���́A
�f���[�e�B�[��̋ψꐫ�A���M���g���̐��m���ƈ��萫�B
�p���X��Z�����邱�ƁB���K�v�Ȋ����B
���g���w��p��VR���T�[���b�g�ȑ���]�ɁB���o��������R��ɂ���B
�X�C�b�`�̔����pC���������B
��M���̃`�F�b�N�́A
�o�C�A�X�ɃC���_�N�^100mH���q���ł݂��B�������~�܂Ȃ��̂ŁA�m�C�Y���z���Ă邩�A���ȋ��U���g��85KHz�Ɉ����������Ă邩���m��Ȃ��B
�Ƃ肠�����A100mH�C���_�N�^2�������������݂��Ⴂ�ɒ���Ɍq���ł݂����ǁA�����͎~�܂Ȃ��̂ŁA�t�B�[���h�m�C�Y���z���Ă�\���͒Ⴂ���ȁH�Ɗ������B
���M���g���̌��ς���ɁA���g���J�E���^�[�͂��܂萄�����Ȃ��B�A�X�y�N�g����͂��s���Ă���킯�Ŗ����A�X���b�V�����h�����𐔂��Ă邾���Ȃ̂ŁA�s����A�s���m�ȂƂ�������B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�����e�p�̃O���[�����[�U�[�̃u�c���͂����B
�܂��́A���B
ACC��H�����[�U�[���W���[���Ƃ��������[�U�[�_�C�I�[�h�̌�[�ɒ��ɕt���Ă���B
(ACC��H�����ŕʔ�������Ă�̂ŁA�����Ɨ\�z�����Ă����B)
�܂��͔M���k�`���[�u����āA�z�b�g�{���h�����B
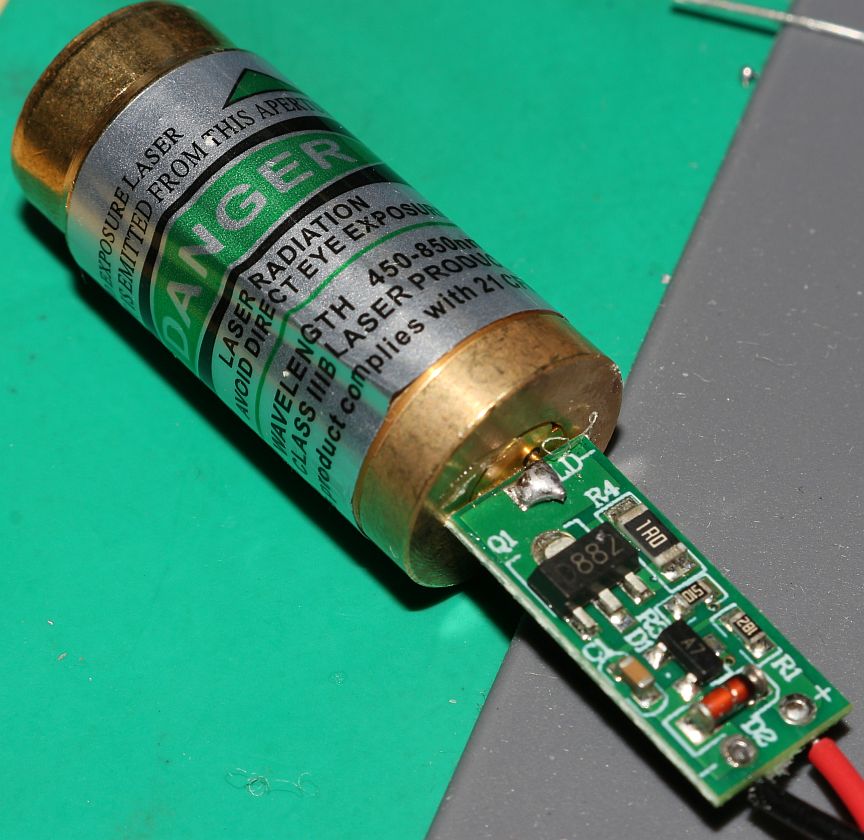
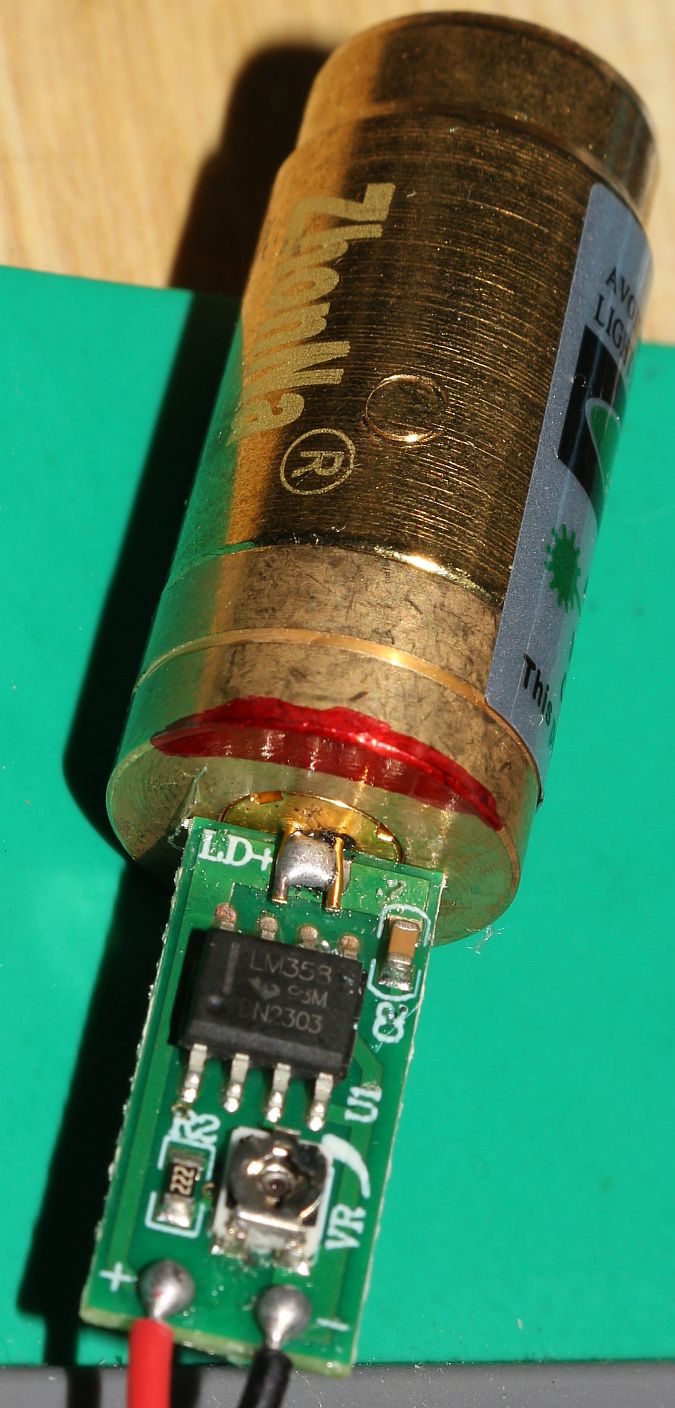 ACC�́AV���M�����^�[��OP-AMP�Ńg�����W�X�^���d���ɋ쓮����悤�ȉ�H���ȁH�Ǝv���܂��B
�����p��C�������g�h���C�u�̓G�ł��B
�ő�o�͂̎ア���[�U�[�͔��U�ƃ_���[�W����܂ł̏o�͗̈悪�����̂��A�p���[���Ď�����APC��H�������A(�o�͂̉��x���������\�傫��)
������x�o�͂̋����̂�ACC��H�������B�c�ƌ����C������B
���[�U�[�_�C�I�[�h�̒[�q�̃s���A�T�C�����L�^���āA�n���_�������A���M�ɒ��ӂȂ̂ŁA�����ɋz������Ŏ��B
�n���_�̎����ǂ��Ȃ��̂��A���܂��Y��ɂ͂Ƃ�Ȃ������̂ŁA�N���t�g�i�C�t�ł�����x�������Ƃ��A
��ɐ܋Ȃ��̗͂������Ȃ���M���Ĕ������B�c��̓N���t�g�i�C�t�����ݍ���Ő荞��Őؒf�B�����������B
���̌�A�s���̍����Ƀn���_���c���ăV���[�g���ĂȂ����m�F�B
�ŃP�[�u���ɕt����B
ACC�́AV���M�����^�[��OP-AMP�Ńg�����W�X�^���d���ɋ쓮����悤�ȉ�H���ȁH�Ǝv���܂��B
�����p��C�������g�h���C�u�̓G�ł��B
�ő�o�͂̎ア���[�U�[�͔��U�ƃ_���[�W����܂ł̏o�͗̈悪�����̂��A�p���[���Ď�����APC��H�������A(�o�͂̉��x���������\�傫��)
������x�o�͂̋����̂�ACC��H�������B�c�ƌ����C������B
���[�U�[�_�C�I�[�h�̒[�q�̃s���A�T�C�����L�^���āA�n���_�������A���M�ɒ��ӂȂ̂ŁA�����ɋz������Ŏ��B
�n���_�̎����ǂ��Ȃ��̂��A���܂��Y��ɂ͂Ƃ�Ȃ������̂ŁA�N���t�g�i�C�t�ł�����x�������Ƃ��A
��ɐ܋Ȃ��̗͂������Ȃ���M���Ĕ������B�c��̓N���t�g�i�C�t�����ݍ���Ő荞��Őؒf�B�����������B
���̌�A�s���̍����Ƀn���_���c���ăV���[�g���ĂȂ����m�F�B
�ŃP�[�u���ɕt����B
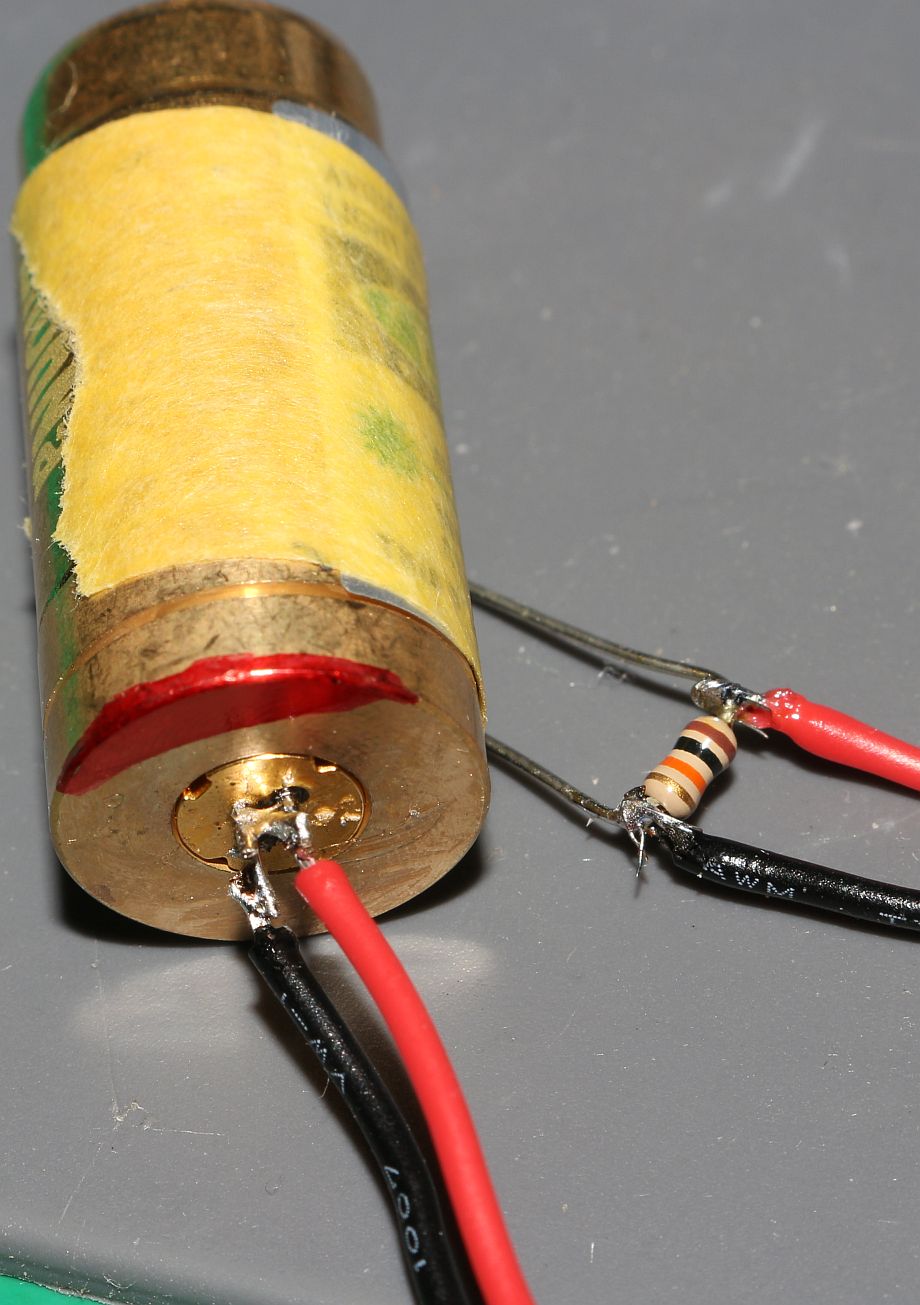 10K���͐Ód�C����̕ی�p�B
�ŁA3.4V�d����6.8�����q���ŊT�Z176mA�Ƃ������Ȃ��߂Ɍ��点�Ă݂�B�������d���d���̕����d���͈��肷�邯�ǁA�d���̋t�ڑ��ɒ��ӁB
���\���������Č�����B(�ʐ^�ł́A�X�g���{���g���Ă���B)
10K���͐Ód�C����̕ی�p�B
�ŁA3.4V�d����6.8�����q���ŊT�Z176mA�Ƃ������Ȃ��߂Ɍ��点�Ă݂�B�������d���d���̕����d���͈��肷�邯�ǁA�d���̋t�ڑ��ɒ��ӁB
���\���������Č�����B(�ʐ^�ł́A�X�g���{���g���Ă���B)
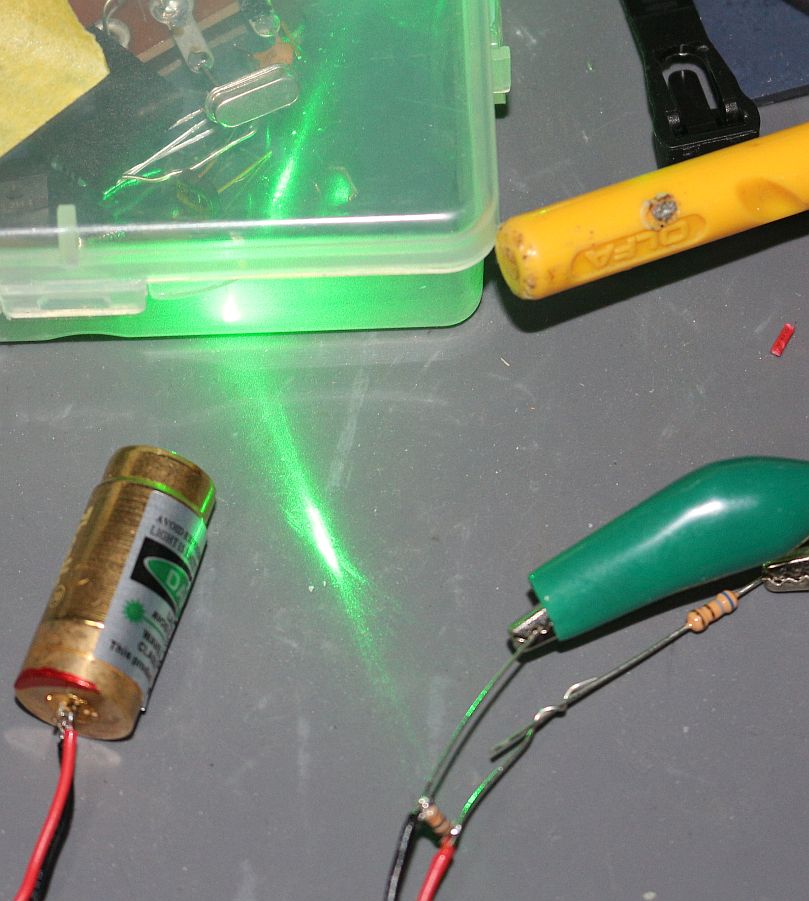 �����A38KHz�쓮���̂͗]�T�ŒǏ]���邾�낤�B
�������A�쓮�p�g�����W�X�^�͒�i�d�͂��傫�����m�ɂ��Ȃ��ƃ_�������ǁB
�o���h�p�X�t�B���^�[(BPF)�������ɓ͂����B
���������A�Ԃ̂����A�V�r�A�ȓ��ߑш�Ȃ̂ɁA���ߌ�������������Ƃ����������Ă銴���B����́A�l�ԂɎ��o�̔g���������e�����Ă�̂��낤�B
���ˌ��͕�F�I�����s���N�B
�����A38KHz�쓮���̂͗]�T�ŒǏ]���邾�낤�B
�������A�쓮�p�g�����W�X�^�͒�i�d�͂��傫�����m�ɂ��Ȃ��ƃ_�������ǁB
�o���h�p�X�t�B���^�[(BPF)�������ɓ͂����B
���������A�Ԃ̂����A�V�r�A�ȓ��ߑш�Ȃ̂ɁA���ߌ�������������Ƃ����������Ă銴���B����́A�l�ԂɎ��o�̔g���������e�����Ă�̂��낤�B
���ˌ��͕�F�I�����s���N�B
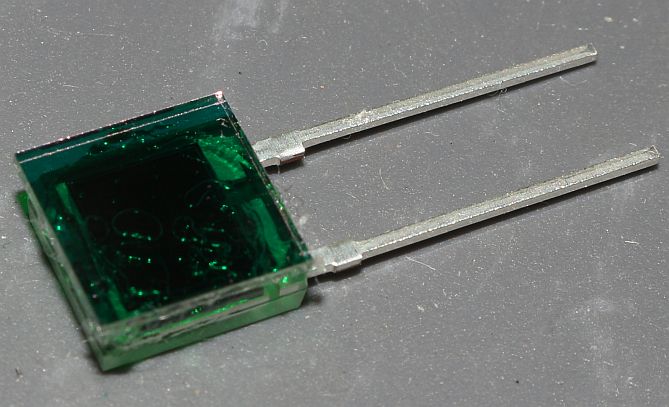
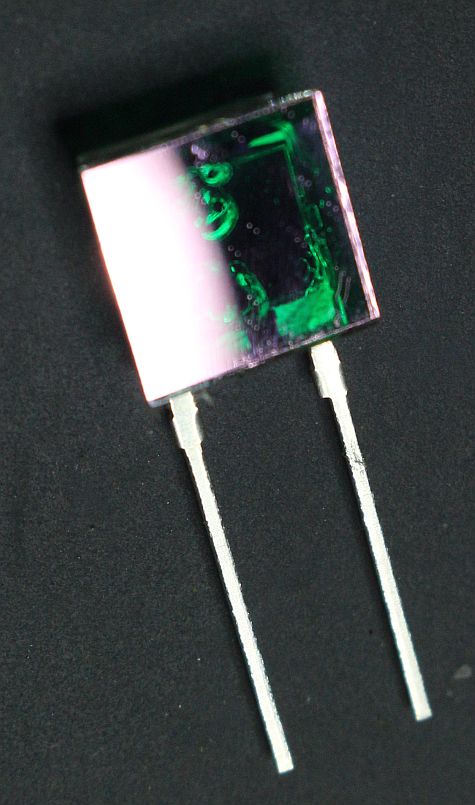 ��C�ɂȂ�̂̓X�g�b�v�o���h�̓��ߗ��ł���B�Ԃł������邱�Ƃ����ǁA���ɓ��߂��ĖO�a��G���[���ĂԂȂ�A�d�˂̕K�v�������肻���B�����̓z�b�g�~���[�̕������������B
650nm��532nm�̕ӂ�̑��z���̋��x�͂����ĕς��Ȃ��B
��H��̕��͐���������A����������ꂽ����Ȃ̂ŁA�b��������B
���̂𗬗p���o���邯�ǁA�������̍l��������̂ŁA
��C�ɂȂ�̂̓X�g�b�v�o���h�̓��ߗ��ł���B�Ԃł������邱�Ƃ����ǁA���ɓ��߂��ĖO�a��G���[���ĂԂȂ�A�d�˂̕K�v�������肻���B�����̓z�b�g�~���[�̕������������B
650nm��532nm�̕ӂ�̑��z���̋��x�͂����ĕς��Ȃ��B
��H��̕��͐���������A����������ꂽ����Ȃ̂ŁA�b��������B
���̂𗬗p���o���邯�ǁA�������̍l��������̂ŁA
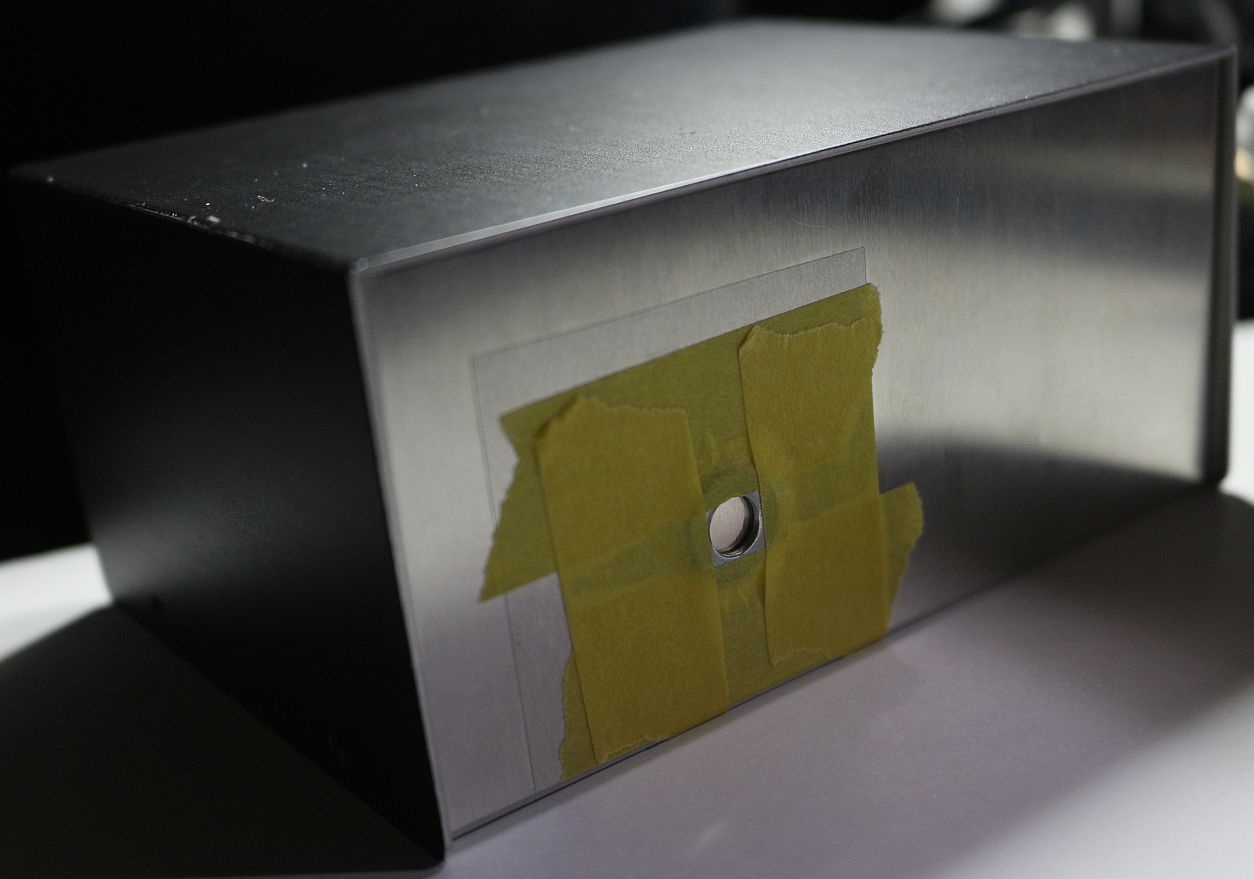 �|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
240414
�������͂����̂ŁA�܂��́A38KHz�̔��U��H����A�O���[�����[�U�[�_�C�I�[�h�̃h���C�u�����H��g�ݗ��ĂĂ݂��B
���A���ꂪ�ӊO�Ɏ肱�����Ă���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
240414
�������͂����̂ŁA�܂��́A38KHz�̔��U��H����A�O���[�����[�U�[�_�C�I�[�h�̃h���C�u�����H��g�ݗ��ĂĂ݂��B
���A���ꂪ�ӊO�Ɏ肱�����Ă���B
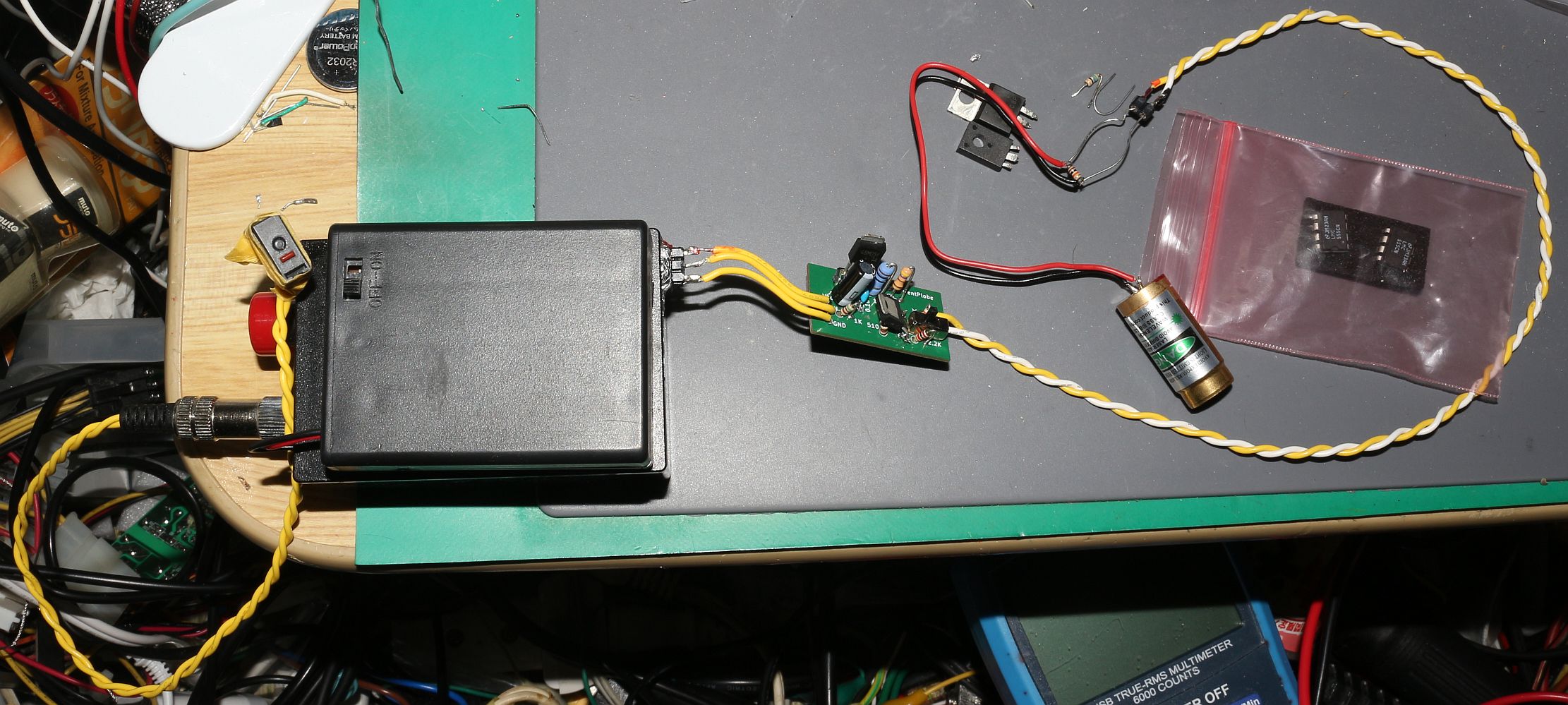 ��d�����������R��200�`250mA�����ݒ�ɂ��Ă���B
�p���[�g�����W�X�^�[�̕����́AIC�\�P�b�g�ɂ��Ēu���Ηǂ������̂����A�������ă_�����Ǝv���Ē��t���ɂ��Ă���B
���ƂŎv�����̂́ATr�̑����ׂ߂̐��ʼn������Ă��܂��Ηǂ��ƌ������ƁB
�܂��́A1.5A�N���X�̃o�C�|�[���[�g�����W�X�^�Ŏ����B
hfe��100���x�ƒႢ�̂����邪�B(���ꂪ�����ƍ��x�̓x�[�X�͓d��������ɂ����X��������悤�ŁA)
�����炭�A�^�C�}�[IC��555�̓�����R�Ńx�[�X�ɗ����d�������E�ňÂ�����悤���B
�p���X�Ō��炷���甼���͂��邯�ǁA���̔䂶�ᖳ�������B�B
���Ⴀ�A�p���[MOS-FET�Ɍ�������ƁAFET�̃Q�[�g�͂قڐ≏������ǂ����Ƃ����ƁA�X�ɈÂ��B
�ŏ��̓Q�[�g�̓d�ׂ������肷���H��t���Ă������A���ꂾ�ƃ��[�U�[�̔��U�Ɏ���Ȃ��B
�O���Ă��A�Q�[�g�e�ʂ�5000pF�قǗL��̂��������A��̐�����g�`�ɂȂ�A����ɕ����錴���́A��͂�555�̓�����R���Ǝv����B�B
���ꂪ�Q�[�g�̓d���B
��d�����������R��200�`250mA�����ݒ�ɂ��Ă���B
�p���[�g�����W�X�^�[�̕����́AIC�\�P�b�g�ɂ��Ēu���Ηǂ������̂����A�������ă_�����Ǝv���Ē��t���ɂ��Ă���B
���ƂŎv�����̂́ATr�̑����ׂ߂̐��ʼn������Ă��܂��Ηǂ��ƌ������ƁB
�܂��́A1.5A�N���X�̃o�C�|�[���[�g�����W�X�^�Ŏ����B
hfe��100���x�ƒႢ�̂����邪�B(���ꂪ�����ƍ��x�̓x�[�X�͓d��������ɂ����X��������悤�ŁA)
�����炭�A�^�C�}�[IC��555�̓�����R�Ńx�[�X�ɗ����d�������E�ňÂ�����悤���B
�p���X�Ō��炷���甼���͂��邯�ǁA���̔䂶�ᖳ�������B�B
���Ⴀ�A�p���[MOS-FET�Ɍ�������ƁAFET�̃Q�[�g�͂قڐ≏������ǂ����Ƃ����ƁA�X�ɈÂ��B
�ŏ��̓Q�[�g�̓d�ׂ������肷���H��t���Ă������A���ꂾ�ƃ��[�U�[�̔��U�Ɏ���Ȃ��B
�O���Ă��A�Q�[�g�e�ʂ�5000pF�قǗL��̂��������A��̐�����g�`�ɂȂ�A����ɕ����錴���́A��͂�555�̓�����R���Ǝv����B�B
���ꂪ�Q�[�g�̓d���B
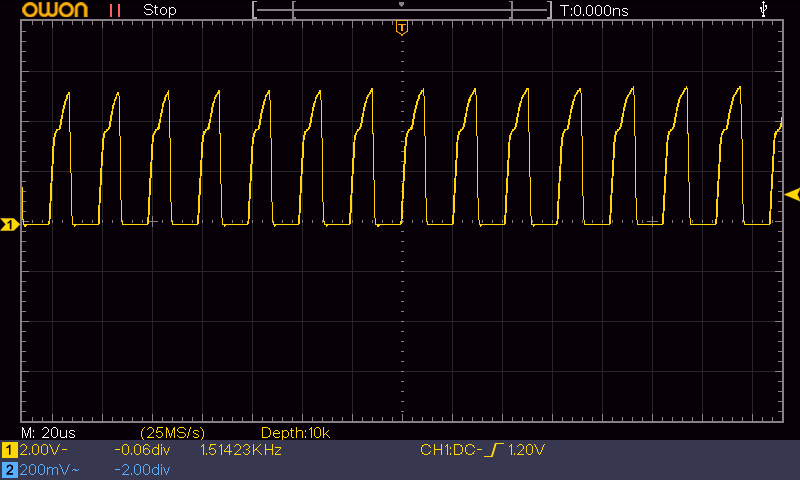 555��555���쓮���Ă�̂ŁA�Ȃ�����Z�������̂ŏo�͂��n��ƌ������ʂ��B
�����ALMC555�Ȃ̂ŁA�܂��}�V�Ƃ����������ƁB�B
�_���Ȃ�A������x�v���A�b�v��R�Ƃ��A���̃A���J��4�{��6V����A006P��9V�ɕς���K�v�����邩���B
�o�C�|�[���[�ōs���Ȃ�A�_�[�����g���ڑ����B
�h���C�u����2��555�������C���s�[�_���X�ȑ�d���^�ɕς���ׂ����ƌ��������B
�œd���e�ʂ̑���XD555�Ƃ����̂Ɍ������ȁH
�ŁAXD555�ɂ�����AFET�ł͍X�ɈÂ��Ȃ����C���B�B�X�ɓd�����ቺ���Ă�\�����B�o�C�|�[���[�ɖ߂��Ă݂悤�B
�c��́A�d���d���A�b�v���A�_�[�����g���ڑ������A�߂�ǂ��̂Ń_�[�����g���g�����W�X�^�[���C�C�����B�B
�Ǝv�������A��r�I�l�C�̂���2SK4017���L�����̂ŁA���ׂĂ݂�ɁA�e�ʂ����Ȃ��A�N���d������߂ŁA�M���M���s�����������B
����Ă݂�ɁA�c�ŏ��̃o�C�|�[���[���x���̊����B
�܂��A�t�H�g�����[�Ƃ��A�o�C�|�[���[�̃_�[�����g���ڑ����o���邯�ǁA
6V�ȓd���ł̓X�C�b�`�ɔ����̂��g���Ƃ����炪���E�Ȃ̂����H�Ƃ����̂��ATr��ʂ����X�C�b�`�łȂ���ƁA�ƂĂ����邭����B
�ŁA�Q�[�g�̔g�`���m�F����ƁA�f���[�e�B�[�䂪�Ⴍ�Ȃ��Ă��邱�Ƃ�������B
���̂Ƃ���A555�o�͂ƃQ�[�g�́A������ԂŁA�v���A�b�v�����ׂ������ł͂���B
555��555���쓮���Ă�̂ŁA�Ȃ�����Z�������̂ŏo�͂��n��ƌ������ʂ��B
�����ALMC555�Ȃ̂ŁA�܂��}�V�Ƃ����������ƁB�B
�_���Ȃ�A������x�v���A�b�v��R�Ƃ��A���̃A���J��4�{��6V����A006P��9V�ɕς���K�v�����邩���B
�o�C�|�[���[�ōs���Ȃ�A�_�[�����g���ڑ����B
�h���C�u����2��555�������C���s�[�_���X�ȑ�d���^�ɕς���ׂ����ƌ��������B
�œd���e�ʂ̑���XD555�Ƃ����̂Ɍ������ȁH
�ŁAXD555�ɂ�����AFET�ł͍X�ɈÂ��Ȃ����C���B�B�X�ɓd�����ቺ���Ă�\�����B�o�C�|�[���[�ɖ߂��Ă݂悤�B
�c��́A�d���d���A�b�v���A�_�[�����g���ڑ������A�߂�ǂ��̂Ń_�[�����g���g�����W�X�^�[���C�C�����B�B
�Ǝv�������A��r�I�l�C�̂���2SK4017���L�����̂ŁA���ׂĂ݂�ɁA�e�ʂ����Ȃ��A�N���d������߂ŁA�M���M���s�����������B
����Ă݂�ɁA�c�ŏ��̃o�C�|�[���[���x���̊����B
�܂��A�t�H�g�����[�Ƃ��A�o�C�|�[���[�̃_�[�����g���ڑ����o���邯�ǁA
6V�ȓd���ł̓X�C�b�`�ɔ����̂��g���Ƃ����炪���E�Ȃ̂����H�Ƃ����̂��ATr��ʂ����X�C�b�`�łȂ���ƁA�ƂĂ����邭����B
�ŁA�Q�[�g�̔g�`���m�F����ƁA�f���[�e�B�[�䂪�Ⴍ�Ȃ��Ă��邱�Ƃ�������B
���̂Ƃ���A555�o�͂ƃQ�[�g�́A������ԂŁA�v���A�b�v�����ׂ������ł͂���B
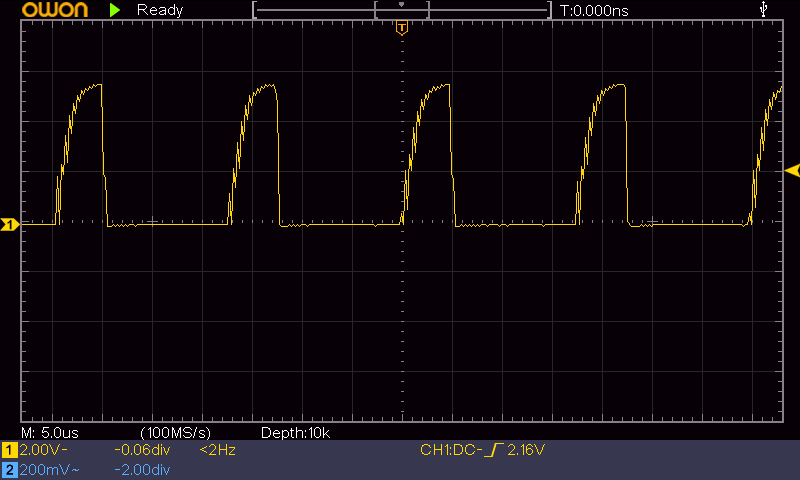 ���͗e�ʂɂ�闧���オ��̂Ȃ܂�ŁA7�`8�����x�ɗ����Ă��邪�A�쓮�p���X�̃f���[�e�B�[��1/3�ł���B�M�U�M�U���L��B
�Ԉ����VR���������H�Ɗm�F�����Ă݂����ǁA���i���Â�����M�������A�A
�Ƃ�����A�p���X������H�̕�����͏o���Ă���̂ō�蒼�������B
���̏�ŁA�_�[�����g���ȃo�C�|�[���[�A�K����MOS-FET�A�t�H�g�����[�Ȃǂ̑I�������画����l���čs�������B
�����ŁA��ʓI���_�́AVce�����߁B�ᑬ�ł��ˁB
�ŁA
������������B
�_�[�����g���g�����W�X�^ TTD1415B 100V7A
�_�[�����g���g�����W�X�^ ��R�� TTD1509B 80V2A�@����������Vce���ł����B
�ꉞ�A�ʏ��hfe�̍����̂������Ă݂邩�ȁH
�Ƃ肠�����A�v���A�b�v��R�œd�����X���b�V�����h�߂��ɏグ�Ƃ��̂��肩�ȁH
�Q�[�g�h���C�o�[�Ƃ��H
�P���ɂ͓d�������ǁc�A006P���ƁA�K���Ȓ�h���b�v�͖����A7806���x���g���R�g�ɂȂ�B
���ǁA
K4017�̎d�l���������A����قǑ傫�Ȗ��͂Ȃ������Ȃ̂ŁA
��Ԃ̖��́u�f���[�e�B�[��v�ł���B�܂��́A�p���X���U��H�쐬�̂ق����D�悩�ȁH
����́A���[�U�[���j�b�g��t���Ă��̂܂����I�Ɍ��点���Q�[�g�d���̔g�`�B
���͗e�ʂɂ�闧���オ��̂Ȃ܂�ŁA7�`8�����x�ɗ����Ă��邪�A�쓮�p���X�̃f���[�e�B�[��1/3�ł���B�M�U�M�U���L��B
�Ԉ����VR���������H�Ɗm�F�����Ă݂����ǁA���i���Â�����M�������A�A
�Ƃ�����A�p���X������H�̕�����͏o���Ă���̂ō�蒼�������B
���̏�ŁA�_�[�����g���ȃo�C�|�[���[�A�K����MOS-FET�A�t�H�g�����[�Ȃǂ̑I�������画����l���čs�������B
�����ŁA��ʓI���_�́AVce�����߁B�ᑬ�ł��ˁB
�ŁA
������������B
�_�[�����g���g�����W�X�^ TTD1415B 100V7A
�_�[�����g���g�����W�X�^ ��R�� TTD1509B 80V2A�@����������Vce���ł����B
�ꉞ�A�ʏ��hfe�̍����̂������Ă݂邩�ȁH
�Ƃ肠�����A�v���A�b�v��R�œd�����X���b�V�����h�߂��ɏグ�Ƃ��̂��肩�ȁH
�Q�[�g�h���C�o�[�Ƃ��H
�P���ɂ͓d�������ǁc�A006P���ƁA�K���Ȓ�h���b�v�͖����A7806���x���g���R�g�ɂȂ�B
���ǁA
K4017�̎d�l���������A����قǑ傫�Ȗ��͂Ȃ������Ȃ̂ŁA
��Ԃ̖��́u�f���[�e�B�[��v�ł���B�܂��́A�p���X���U��H�쐬�̂ق����D�悩�ȁH
����́A���[�U�[���j�b�g��t���Ă��̂܂����I�Ɍ��点���Q�[�g�d���̔g�`�B
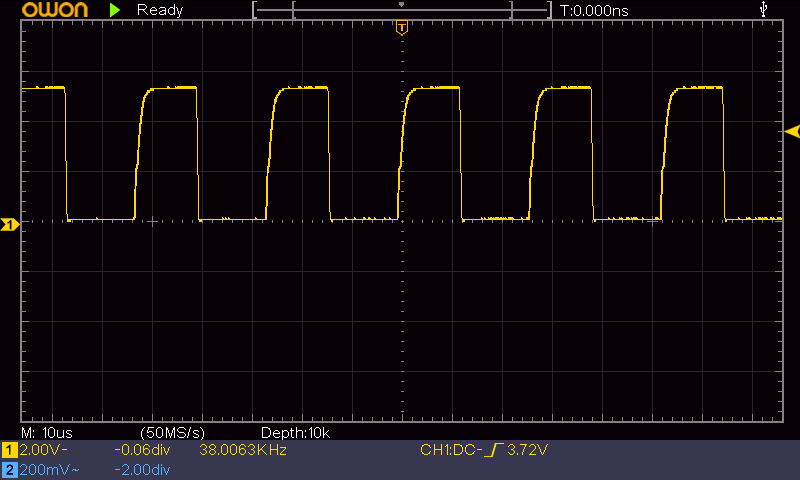 �f���[�e�B����グ�邽�߁ARA��300���ɉ����Ă����Ƃňُ퓮�삵�ĂĂ͂܂��Ă����B
RA�́A1000���ł����܂������ƍs���Ȃ�������B
���̏ꍇ1300���ł��܂��������B���M���g���̐��x�������B
�܂��A�f�[�^�V�[�g�ɂ��ԈႢ�Ǝv����L�q�������Ĉꎞ�A�������Ă����B
�ł����Č���ɁA��͂�A���[�U�[�͈Â��̂ŁAFET��Vds�ɋN������Ǝv���B
�d������p�̒�R�������邩�A�d���d�����グ�邩�H�ł���B
�ł����āA�����V���b�g�p���X�B
�f���[�e�B�[���Ⴂ�B���[�U�[�h���C�o�[���O���������肵����`�g�ɂ͂Ȃ邪�A�f���[�e�B�[��͒Ⴂ�܂܂ł���B
�������A�����������悤���B
�f���[�e�B����グ�邽�߁ARA��300���ɉ����Ă����Ƃňُ퓮�삵�ĂĂ͂܂��Ă����B
RA�́A1000���ł����܂������ƍs���Ȃ�������B
���̏ꍇ1300���ł��܂��������B���M���g���̐��x�������B
�܂��A�f�[�^�V�[�g�ɂ��ԈႢ�Ǝv����L�q�������Ĉꎞ�A�������Ă����B
�ł����Č���ɁA��͂�A���[�U�[�͈Â��̂ŁAFET��Vds�ɋN������Ǝv���B
�d������p�̒�R�������邩�A�d���d�����グ�邩�H�ł���B
�ł����āA�����V���b�g�p���X�B
�f���[�e�B�[���Ⴂ�B���[�U�[�h���C�o�[���O���������肵����`�g�ɂ͂Ȃ邪�A�f���[�e�B�[��͒Ⴂ�܂܂ł���B
�������A�����������悤���B
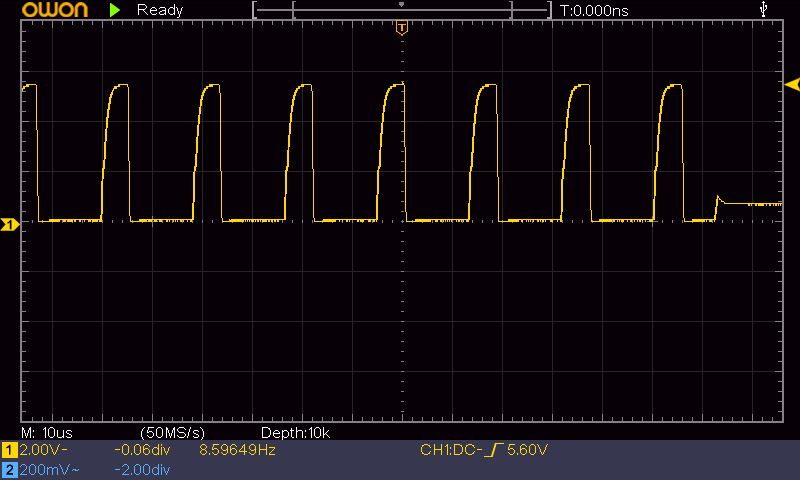 ����͓d�������p��555�̗����オ�肩�M�������p��555�̗����オ�肪�W���肻���B
�Ȃ̂ŁA�������Ԃ������L������A�ǂ������y���v���A�b�v���Ă݂�ƃC�C�����B
�����́A�p���X�������쓮�������Ȃ���A�����V���b�g�M���ŁuAND�Q�[�g�v���u���Z�v��ʂ��������ȁH
OP-AMP�ʼn��Z���L�������H
���̍ہA�Q�[�g�h���C�o��t�H�g�����[�Ȃǂ������ł���B
�ȒP�ɂ���Ȃ�A
PIC�Ȃǂ̃`�b�v�}�C�R���˃Q�[�g�h���C�o�[�˃p���[MOS-FET
�����\�ʎ�������Ηǂ��̂����A�A�d�q�H��Ƃ��Ă͋��C������B
�����ŁATr�ł̉��Z�������l���Ă݂��B
�o���G�[�V���������邯�ǁA���ꂼ��2K����ʂ��Ă܂Ƃ߁A510����ʂ��A1K����GND�ɗ��Ƃ��ATr�֑���B
�o�C�|�[���[Tr�͓d���œ��삷��̂ŗǂ��������AMOS-FET�͈Â��̂ł��傢�l���˂Ȃ�Ȃ������H
����͓d�������p��555�̗����オ�肩�M�������p��555�̗����オ�肪�W���肻���B
�Ȃ̂ŁA�������Ԃ������L������A�ǂ������y���v���A�b�v���Ă݂�ƃC�C�����B
�����́A�p���X�������쓮�������Ȃ���A�����V���b�g�M���ŁuAND�Q�[�g�v���u���Z�v��ʂ��������ȁH
OP-AMP�ʼn��Z���L�������H
���̍ہA�Q�[�g�h���C�o��t�H�g�����[�Ȃǂ������ł���B
�ȒP�ɂ���Ȃ�A
PIC�Ȃǂ̃`�b�v�}�C�R���˃Q�[�g�h���C�o�[�˃p���[MOS-FET
�����\�ʎ�������Ηǂ��̂����A�A�d�q�H��Ƃ��Ă͋��C������B
�����ŁATr�ł̉��Z�������l���Ă݂��B
�o���G�[�V���������邯�ǁA���ꂼ��2K����ʂ��Ă܂Ƃ߁A510����ʂ��A1K����GND�ɗ��Ƃ��ATr�֑���B
�o�C�|�[���[Tr�͓d���œ��삷��̂ŗǂ��������AMOS-FET�͈Â��̂ł��傢�l���˂Ȃ�Ȃ������H
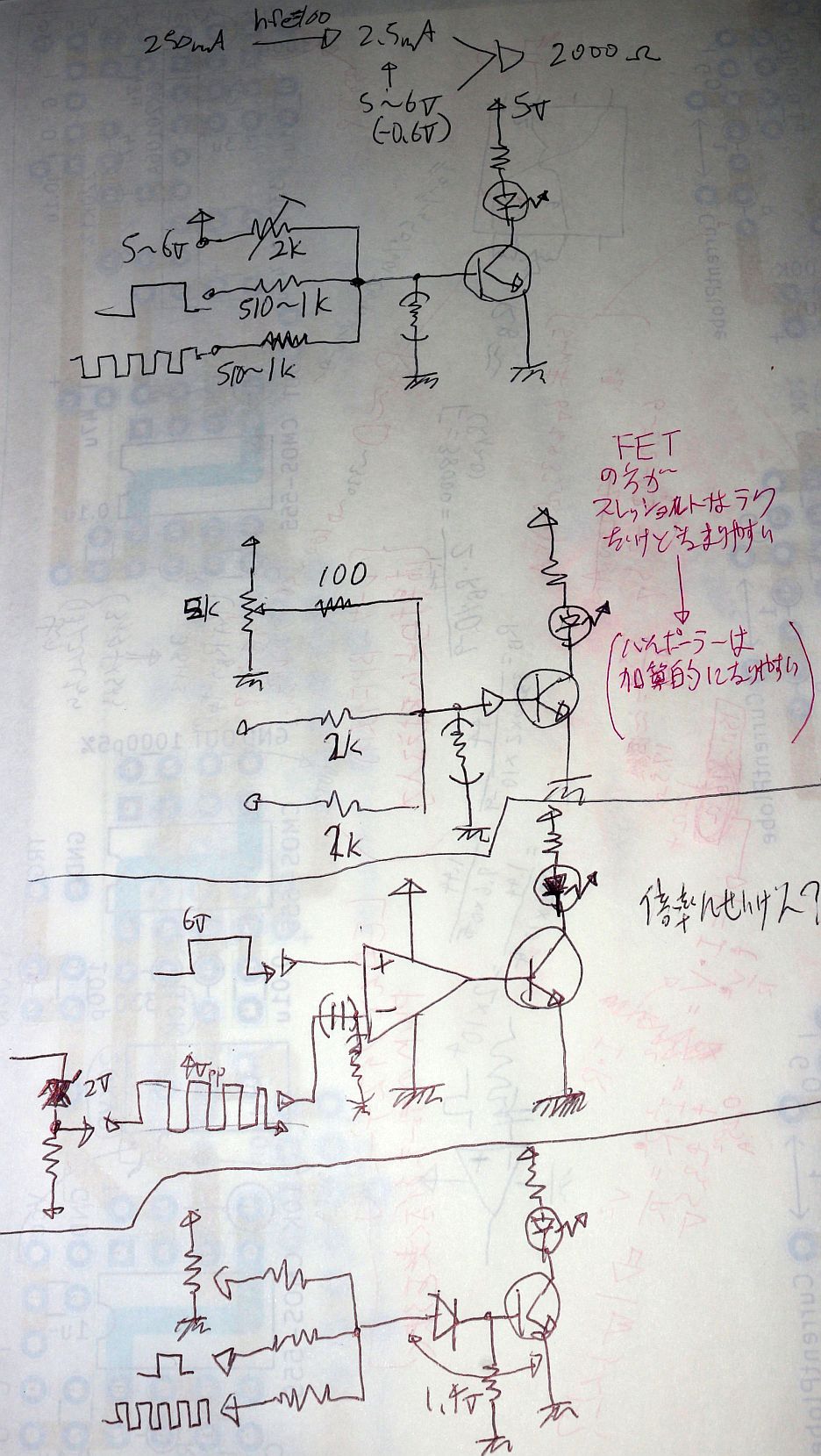 ���U��Ԃł������V���b�g�̃g���K�����O���Ă鎞�̏ꍇ�͔��ɖ��邢�B
�ł��A�L�����A�Ŕ����邭����B���̐M���́A38KHz�Ȃ̂ŁA��M�����������Ă��܂�����������B
�����ŁA��͂�AOP-AMP�Ŕ{���ɐ������������R���p���[�^�[���K�v�B
���̏ꍇ�A�{���ݒ�́A1�`3�{�Ȃ��������̒l�ɐݒ肷��ƃC�C���ȁH
���U��Ԃł������V���b�g�̃g���K�����O���Ă鎞�̏ꍇ�͔��ɖ��邢�B
�ł��A�L�����A�Ŕ����邭����B���̐M���́A38KHz�Ȃ̂ŁA��M�����������Ă��܂�����������B
�����ŁA��͂�AOP-AMP�Ŕ{���ɐ������������R���p���[�^�[���K�v�B
���̏ꍇ�A�{���ݒ�́A1�`3�{�Ȃ��������̒l�ɐݒ肷��ƃC�C���ȁH
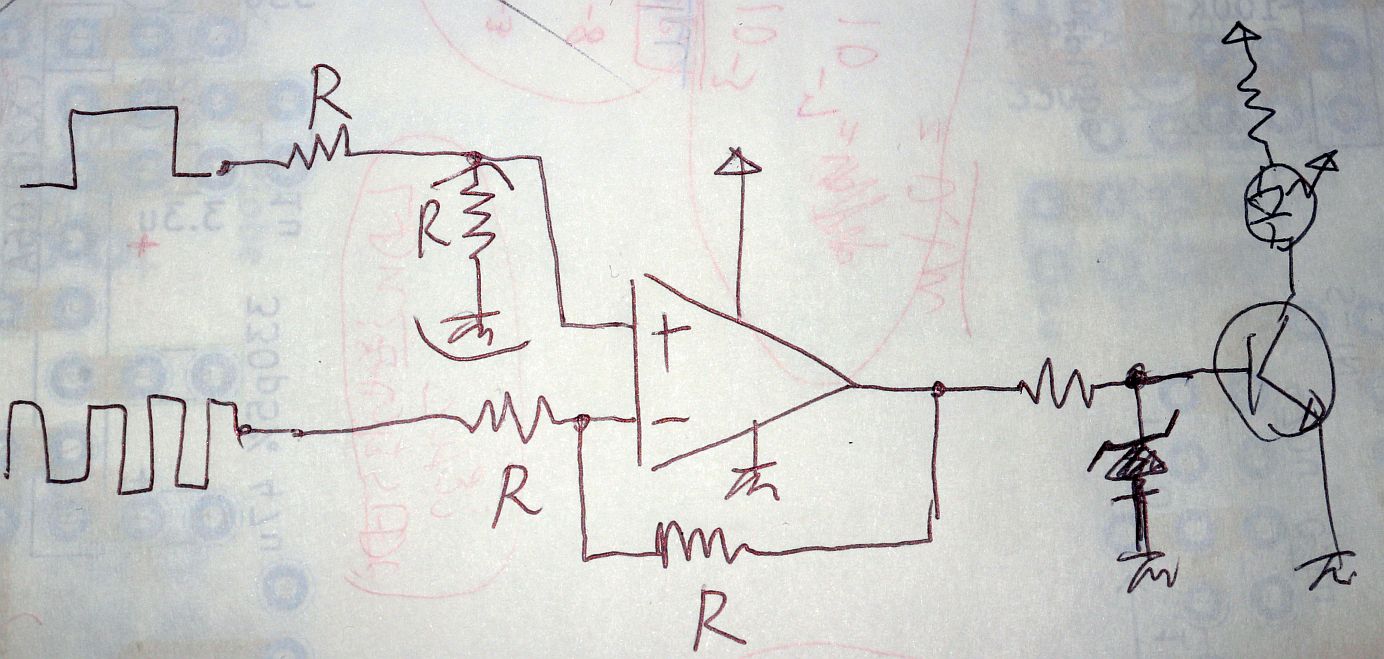 �����̃R���p���[�^�[IC�̎g�p�́A�s���A�T�C�����Ⴄ�̂ŁA���������Ă���B
���i���������Ȃ�A�R���p�N�g���ᖳ���͔̂Y�݂ǂ��B
��̍�蒼���ɔM��������A���̊�ŏo����`�F�b�N�͂��s�����������A�M��܂���ƁA����ӂ̑ϋv�����B�B
�����̎��s�͌��\�Ȏ��ԂƋ��̘Q��Ȃ̂ŁA�v�����ău���b�h�{�[�h�Ń`�F�b�N���邱�Ƃ����B
�����̃R���p���[�^�[IC�̎g�p�́A�s���A�T�C�����Ⴄ�̂ŁA���������Ă���B
���i���������Ȃ�A�R���p�N�g���ᖳ���͔̂Y�݂ǂ��B
��̍�蒼���ɔM��������A���̊�ŏo����`�F�b�N�͂��s�����������A�M��܂���ƁA����ӂ̑ϋv�����B�B
�����̎��s�͌��\�Ȏ��ԂƋ��̘Q��Ȃ̂ŁA�v�����ău���b�h�{�[�h�Ń`�F�b�N���邱�Ƃ����B
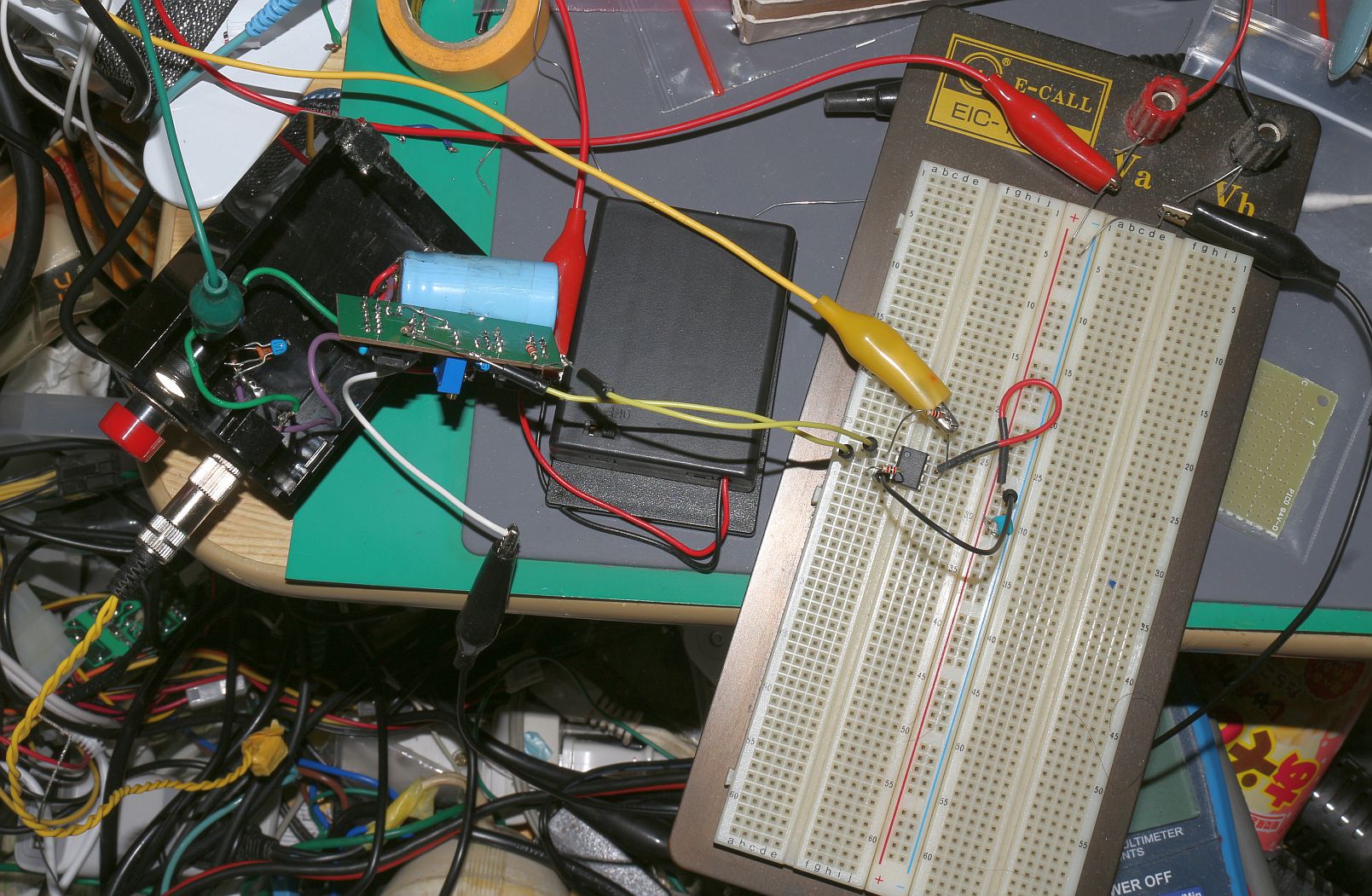 ���cOP-AMP�݂����ȌÂ��̂��L�����̂Ōq������A�X�s�[�h�����炸�A���U������ƌ����Ђǂ����ʂ��������A
�ėp��5534���q�������Ȃ��o���B
���cOP-AMP�݂����ȌÂ��̂��L�����̂Ōq������A�X�s�[�h�����炸�A���U������ƌ����Ђǂ����ʂ��������A
�ėp��5534���q�������Ȃ��o���B
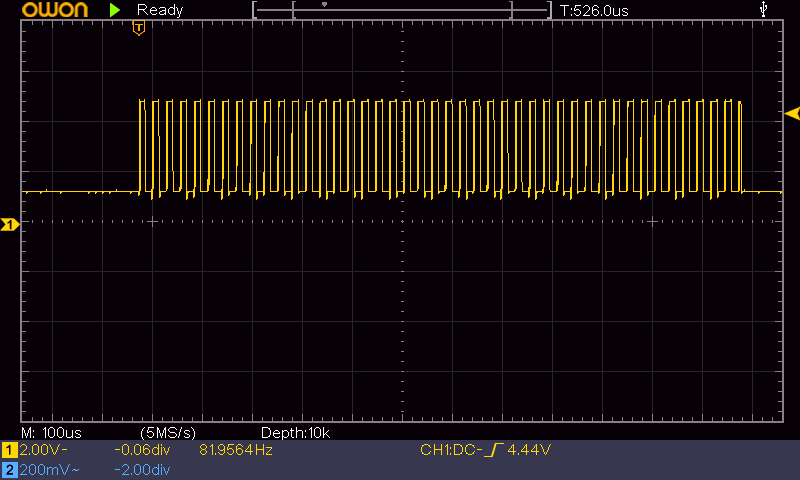 �Ƃ������ƂŁA�����͂��̂܂ܐi�s���ȁH
OP-AMP�́A�o�͂�������ƕ����Ă�̂ŁA���[��TO���[���Ƃ��A�t���X�C���O�A�P�d���p�ō����Ȃ̂�T���Ă݂銴�����ȁH
���ꂩ�ADi�����܂����B
330���̃v���A�b�v��R�����O���̂�Y��Ă����̂ŁA�O������OP-AMP�o�͂ɉ����t���Ȃ����Ă�OK�ɂȂ����B
�d�r��������Ƃւ����Ă��Ă�̂ŐV�i�ɕς����班���ς�邩���H
�Ƃ������ƂŁA�����͂��̂܂ܐi�s���ȁH
OP-AMP�́A�o�͂�������ƕ����Ă�̂ŁA���[��TO���[���Ƃ��A�t���X�C���O�A�P�d���p�ō����Ȃ̂�T���Ă݂銴�����ȁH
���ꂩ�ADi�����܂����B
330���̃v���A�b�v��R�����O���̂�Y��Ă����̂ŁA�O������OP-AMP�o�͂ɉ����t���Ȃ����Ă�OK�ɂȂ����B
�d�r��������Ƃւ����Ă��Ă�̂ŐV�i�ɕς����班���ς�邩���H
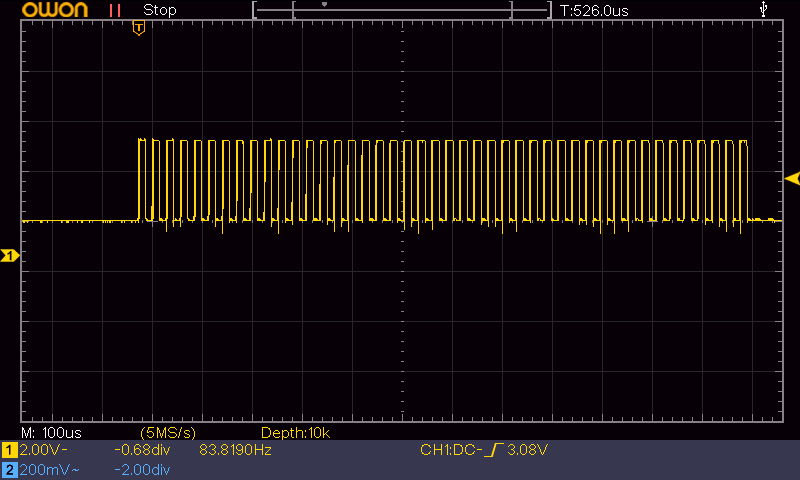 �ڐG�̖�肪����A���P����ƁA�R�ꂪ�m�F���ꂽ�̂ŁA
���ƁA�d�r�̓d����5.5V�ɉ�����A�V�O�i������߂ɂȂ��Ă�Ǝv���A
�����V�O�i���ƃL���̗ǂ����l����ƁA�����ȃV���b�g�L�o���ADi������������Ɨǂ��悤�������B
�܂��ADi�Ō��\�ς��̂����ǁA�����́AOP-AMP�̃X�C���O�̕���d���̋쓮�\�͂̕����d�v���ȁH
�V�O�i�������P���A���[�U�[�������o����ƁA38KHz�̔��U��Ԃɂĕǂւ̔��ˌ��ł���܂Ԃ������炢�ɂȂ蓾��R�g���m�F�B
�����t�H�gDi�Ŏ�Ƃ���Ȋ����B(�t�o�C�A�X����)
�ڐG�̖�肪����A���P����ƁA�R�ꂪ�m�F���ꂽ�̂ŁA
���ƁA�d�r�̓d����5.5V�ɉ�����A�V�O�i������߂ɂȂ��Ă�Ǝv���A
�����V�O�i���ƃL���̗ǂ����l����ƁA�����ȃV���b�g�L�o���ADi������������Ɨǂ��悤�������B
�܂��ADi�Ō��\�ς��̂����ǁA�����́AOP-AMP�̃X�C���O�̕���d���̋쓮�\�͂̕����d�v���ȁH
�V�O�i�������P���A���[�U�[�������o����ƁA38KHz�̔��U��Ԃɂĕǂւ̔��ˌ��ł���܂Ԃ������炢�ɂȂ蓾��R�g���m�F�B
�����t�H�gDi�Ŏ�Ƃ���Ȋ����B(�t�o�C�A�X����)
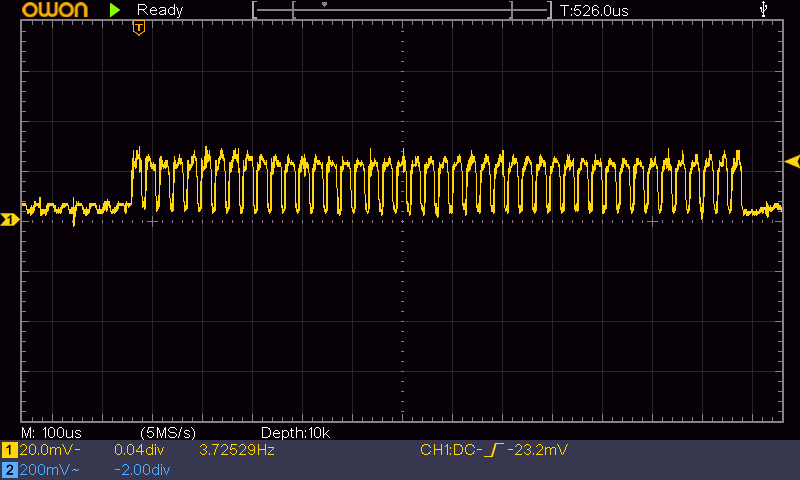 ���[�U�[�͋�������̂ŁA�_�C���N�g�ɎĂȂ���ԁB
�g���K�[�O�ł��A�M���������R��Ă�B�����OP-AMP��Di�łǂ��ɂ��Ȃ�\��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�o�͂̑傫�����[�U�[�_�C�I�[�h�́A�ڍ��ʐς��傫���A�̂ɐڍ��ԗe�ʂ��傫���A���������ɂ͌����Ȃ������m��Ȃ��B
�O���[�����[�U�[�͓��ɂ����Ȃ̂����m��Ȃ��B
�����ǁA38KHz���x�͑Ή����ė~�����A���c�A
NJM5534�͓��ʂŁA���̂́A�����Ă��܂��A���U�M��ON�̃{�^���������ƁA�t�ɏ����Ă��܂����肷��B������͓̂�ł���B
2��HOP-AMP���V���O���Ŏg���Ă݂Ă���B
�ς�����̂�NE5532��NJM13404�ʂ��B
NJM13404��Di������_�C���N�g�Ŏ�߂Ɍ����Ă�Ƃ������肩���B
�ア�̂�NJM13404�̍ő�d���h���C�u�\�͂����ア�݂����B
���[�U�[�͋�������̂ŁA�_�C���N�g�ɎĂȂ���ԁB
�g���K�[�O�ł��A�M���������R��Ă�B�����OP-AMP��Di�łǂ��ɂ��Ȃ�\��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�o�͂̑傫�����[�U�[�_�C�I�[�h�́A�ڍ��ʐς��傫���A�̂ɐڍ��ԗe�ʂ��傫���A���������ɂ͌����Ȃ������m��Ȃ��B
�O���[�����[�U�[�͓��ɂ����Ȃ̂����m��Ȃ��B
�����ǁA38KHz���x�͑Ή����ė~�����A���c�A
NJM5534�͓��ʂŁA���̂́A�����Ă��܂��A���U�M��ON�̃{�^���������ƁA�t�ɏ����Ă��܂����肷��B������͓̂�ł���B
2��HOP-AMP���V���O���Ŏg���Ă݂Ă���B
�ς�����̂�NE5532��NJM13404�ʂ��B
NJM13404��Di������_�C���N�g�Ŏ�߂Ɍ����Ă�Ƃ������肩���B
�ア�̂�NJM13404�̍ő�d���h���C�u�\�͂����ア�݂����B
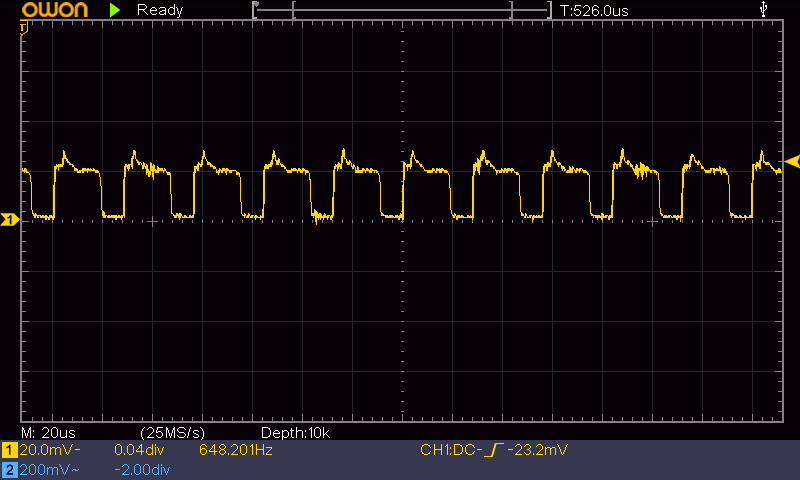
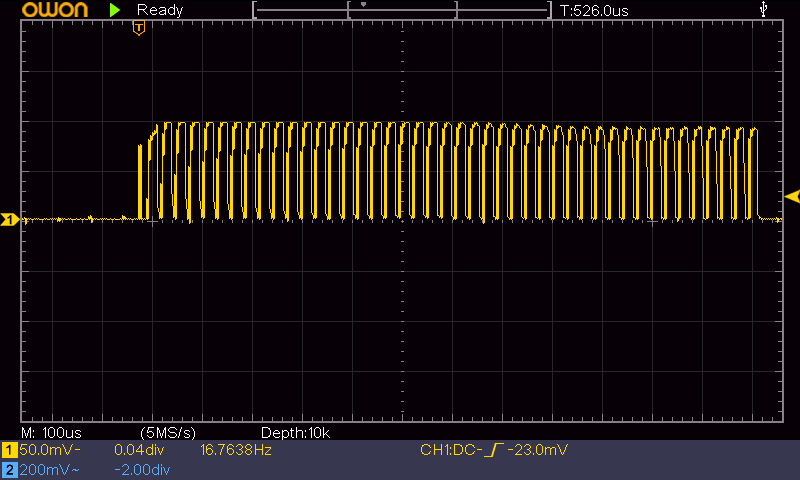 �ł��A���ꂾ�ƁA�O���[�����ᖳ�����ėǂ��̂ł́H�Ƃ��v���B
�܂��A�������킹�̓t���p���[�ŁA�p���X�͎�߂ł������֓͂��Ƃ����̂͂��邩���B
�V��ł�1��H���o�̓o�b�t�@AMP�ɂ��Ă݂��B
�ł��A���ꂾ�ƁA�O���[�����ᖳ�����ėǂ��̂ł́H�Ƃ��v���B
�܂��A�������킹�̓t���p���[�ŁA�p���X�͎�߂ł������֓͂��Ƃ����̂͂��邩���B
�V��ł�1��H���o�̓o�b�t�@AMP�ɂ��Ă݂��B
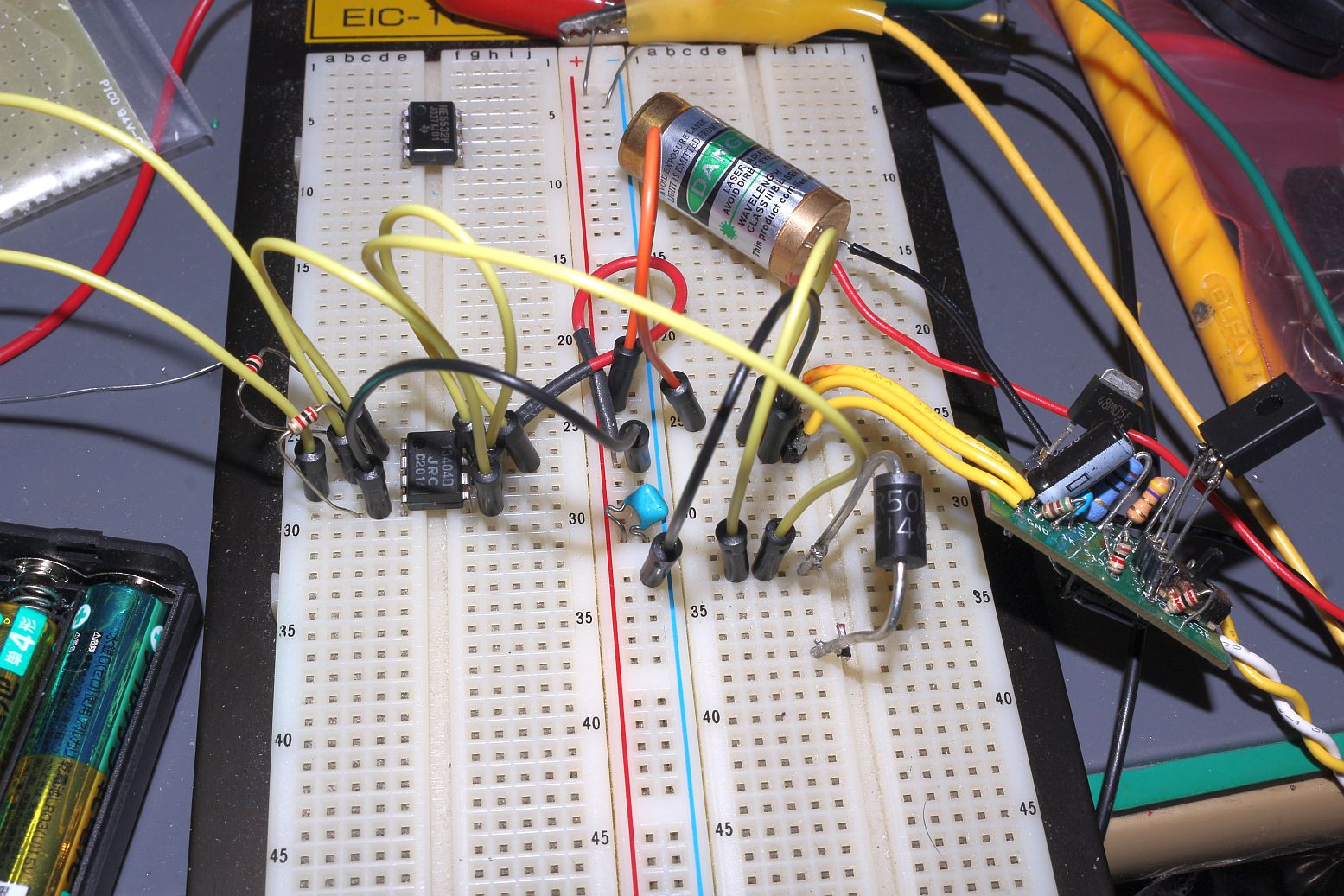 ����
����
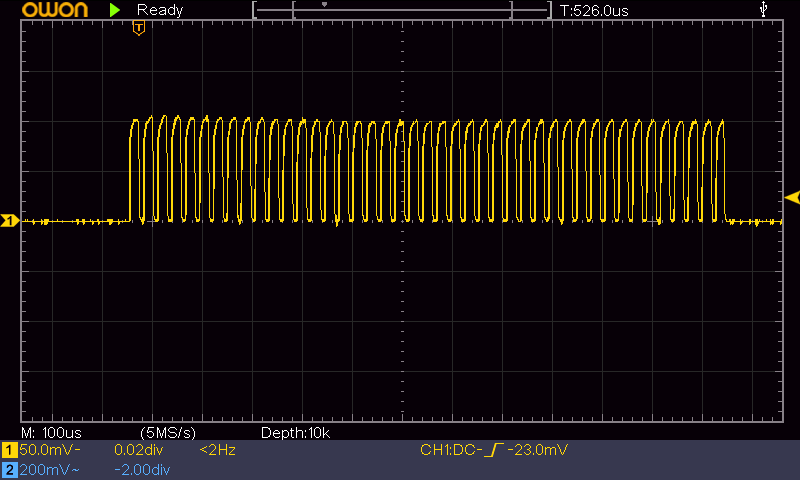 ���邳�͕ς��Ȃ����ǁA�g���K�[���b�`�_�E������̔g�`�X�^�[�g�̃G�b�W�����P���������B�B
�����AOP-AMP�̑��x�̖�肩�A��d�̑����ŁA�s�[�N�Ɋۂ݂��o���悤�ł���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
240417
Tr��hfe��2.5�{�ȏ㍂�����m�Ɍ����������A�s�v�c�ŋt�ɈÂ��Ȃ����B
OP-AMP�̏o�͓d�����Ⴂ�̂��ȁH�Ƃ������āA�g�`������ƁA���܂�ς��Ȃ����A
��͂�5534�������[��TO���[����13404�����Â��B�s�[�N�͎�����̂ɁA�A
�悭����ƁA�g�`����`�ɂȂ��Ă���̂ŁA�����X�s�[�h���x���āA�X���b�V�����h�ł̃f���[�e�B�[�䂪���\�������Ă���\�������邩�ȁH
���Ƃ́A���[�U�[��������Ԃ���_���̂ƁA�ŏ��A������Ă��Ԃ���A�Ƃ����X�^�[�g�n�_���Ⴄ�Ƃ����̂��L�邩���m��Ȃ��B
�Ƃ肠�����A�o�͓d�����Ⴂ�Ƃ��͖��������B
�����ADi������Ɠd���������邯�ǁA������d����������̂����̂悤�ŁADi�̃p���������̌��ʂ�������B
�ڂ���������LED������Ԃ��烌�[�U�[��N���Ĕ��U����܂łɁA������x�G�l���M�[���z�����Ԃ�������B�Ƃ������Ƃ͂��邩���A�Ǝv���B
���A�������A���́A�Ԃ̏��d�̓��[�U�[���A�O���[�����[�U�[�͂��ꂪ�傫�������H�ƌ������ƂȂ̂��ȁH
APC��H�{��߂̃p���X�Ȃ疳����h���C�u�ł���Ƃ��A�M���M���キ���[�U�[���U���Ă��Ԃɒu���āA�M���p���X��������u���ɍő�ɁA�ƂȂ�ƁA�c������B
���邳�͕ς��Ȃ����ǁA�g���K�[���b�`�_�E������̔g�`�X�^�[�g�̃G�b�W�����P���������B�B
�����AOP-AMP�̑��x�̖�肩�A��d�̑����ŁA�s�[�N�Ɋۂ݂��o���悤�ł���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
240417
Tr��hfe��2.5�{�ȏ㍂�����m�Ɍ����������A�s�v�c�ŋt�ɈÂ��Ȃ����B
OP-AMP�̏o�͓d�����Ⴂ�̂��ȁH�Ƃ������āA�g�`������ƁA���܂�ς��Ȃ����A
��͂�5534�������[��TO���[����13404�����Â��B�s�[�N�͎�����̂ɁA�A
�悭����ƁA�g�`����`�ɂȂ��Ă���̂ŁA�����X�s�[�h���x���āA�X���b�V�����h�ł̃f���[�e�B�[�䂪���\�������Ă���\�������邩�ȁH
���Ƃ́A���[�U�[��������Ԃ���_���̂ƁA�ŏ��A������Ă��Ԃ���A�Ƃ����X�^�[�g�n�_���Ⴄ�Ƃ����̂��L�邩���m��Ȃ��B
�Ƃ肠�����A�o�͓d�����Ⴂ�Ƃ��͖��������B
�����ADi������Ɠd���������邯�ǁA������d����������̂����̂悤�ŁADi�̃p���������̌��ʂ�������B
�ڂ���������LED������Ԃ��烌�[�U�[��N���Ĕ��U����܂łɁA������x�G�l���M�[���z�����Ԃ�������B�Ƃ������Ƃ͂��邩���A�Ǝv���B
���A�������A���́A�Ԃ̏��d�̓��[�U�[���A�O���[�����[�U�[�͂��ꂪ�傫�������H�ƌ������ƂȂ̂��ȁH
APC��H�{��߂̃p���X�Ȃ疳����h���C�u�ł���Ƃ��A�M���M���キ���[�U�[���U���Ă��Ԃɒu���āA�M���p���X��������u���ɍő�ɁA�ƂȂ�ƁA�c������B
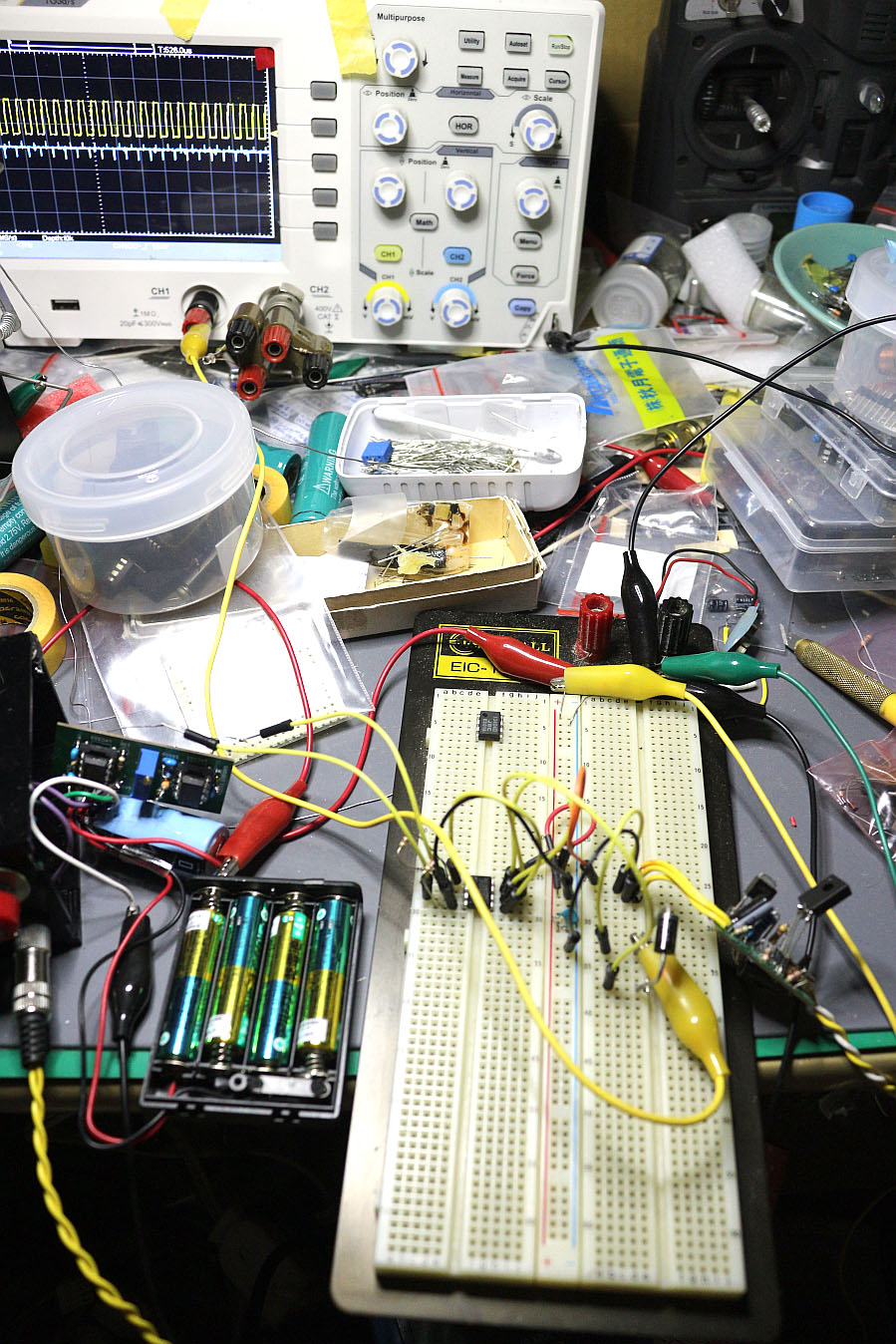 240418
���ǂ̂Ƃ���A5532�̏o�͂ɑ�d���p�����V���b�g�L�o���ADi��t�����̂����邩�����B
�g���K�������ĂȂ��Ƃ��͂�����Ƃ������[�U�[�����R���悤�����ǁA���ϒ��ŃA���B��R�̐ݒ�ł��R��̗ʂ͕ς���ꂻ�������A
�ŁAPCB������Ȋ����Ŕ��������傫�߂ɂȂ������ǁc�B
240418
���ǂ̂Ƃ���A5532�̏o�͂ɑ�d���p�����V���b�g�L�o���ADi��t�����̂����邩�����B
�g���K�������ĂȂ��Ƃ��͂�����Ƃ������[�U�[�����R���悤�����ǁA���ϒ��ŃA���B��R�̐ݒ�ł��R��̗ʂ͕ς���ꂻ�������A
�ŁAPCB������Ȋ����Ŕ��������傫�߂ɂȂ������ǁc�B
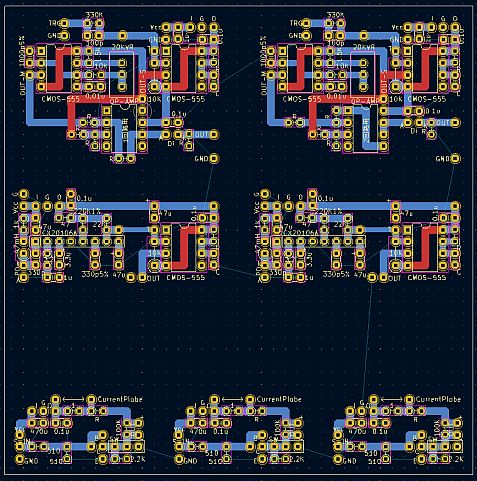 5mW���x�̐ԐFLD�Ȃ�OP-AMP�����ŋ�����H�ł��]�T�ōs����Ǝv���܂��B
�����͂܂��A���K����ŏo���Ȃ��ł��̂ŁA���̊�ƕ����Ē�������A�����̃E�F�C�g��������A�P���������ƈ����オ��̂Ł`�A
240421
������j�b�g�́A�t�o�C�A�X��H��t����ƒ��˓����ɂ͋����Ȃ邯�ǁA���x�͂��Ȃ艺����Ǝv����B
�t�H�g�_�C�I�[�h�����Ȃ�A�����炭���Ȃ荂�����x�ɂȂ邪�c�A
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
240430
4�̕��@����ׂ�ƁB
�E����OP-AMP�ˌ�쓮���Ȃ��P�d���̃��m�͂ǂꂩ�H
�E�_�[�����g���g�����W�X�^��Vce���������ǁc�A�A���ƁA��x���œ_������Ȃ������B
�E�Q�[�g�h���C�o�{�p���[MOS-FET�˃`�b�v�p�[�c�ɂȂ�\����Ȃ̂ŁA��v����ς��B�������s���A�T�C���̓��m�ɂ��Ⴄ�B
�E�t�H�g�����[�˔����ɒx�����B
�Ƃ��������ŁA�ŏ���OP-AMP������ȁH
�_�[�����g���Ȃ炤�܂������AOP-AMP���g��Ȃ��̂̕��@�ł����������H
240402
�_�[�����g���������B
��͂�R�ꂪ����B�����āAVce�������̂Ŗ��邭�Ȃ��B
�d���d����d�������p��R�Ŗ��邳�͂ǂ��ɂ��Ȃ邪�A�R��́A������555��2�i�\���̉�H�\���łǂ��Ȃ邩�H�Ƃ��������ɂȂ�B
�܂�A�ߋ��ւ̉�A�ȉ�H�Ɍ����B
����Ӗ��A�V���v���ŁA�m����������Ȃ��B
OP-AMP�`���ƂȂ�ƁA�����ŁA���[���t�߂܂Ńt���X�C���O���āA���U�Ȃnj듮����Ȃ��ƂȂ�ƁA����Ƃ��ł�����B
�x�^GND�Ƃ��ʼn��P����悢�̂����ǁB
240403
����H(555�̒���2�i)�Ƀ_�[�����g���g�����W�X�^�[�������Ă݂��B
�d�������p�̒�R�������̂Ō��͎�߂����A�R��ɂ���쓮���Ȃ��B
�����āA�g�`���A�����N����ďオ���Ă��������͂��Ȃ�ɘa���ꂽ�B
���̕������ǂ����낤�B
�܂��AOP-AMP���̉�H��𒍕��������ゾ���ǁB�o�����炻��������ǂ��ĘR��Ȃ����邭�������Ƃ���ł͂���B
�_�[�����g���g�����W�X�^��Vce��0.9V�Ȃ̂�5V���d�ŁA10����200mA�ƂȂ�B
����ł��ƁA���Ȃ薾�邭�Ȃ邵�A�R��ɂ���쓮�������B
�����A�����V���b�g�̃p���X�͖��邭�Ȃ��B555�̗����オ��Ɏ��Ԃ�������̂����邩�Ǝv�����A����قǎ��Ԃ͂������Ă��Ȃ��悤���B
����ɔ�ׂāA
�s�̂̌����e��G17�͂��Ȃ薾�邭������̂Ŕg�`������ƁA30mSec�̊Ԍ����Ă����B
����͑����A�J������1/30�̃V���b�^�[�X�s�[�h���l�����Ă�̂ł͖������ȁH
�ƂȂ�ƁA������́A1mSec�I�[�_�[������Â�������̂��d���������B
�����オ��̗�N���Ǝv�����A�A���p���X�Ɣ�ׂāA�Z���T�[�ւ̔�����^����\�͂͌��\�Ⴄ�B
����āA�p���X���Ԃ́A5mSec���x�ɏグ�Ă��ǂ���������Ȃ��B
5mW���x�̐ԐFLD�Ȃ�OP-AMP�����ŋ�����H�ł��]�T�ōs����Ǝv���܂��B
�����͂܂��A���K����ŏo���Ȃ��ł��̂ŁA���̊�ƕ����Ē�������A�����̃E�F�C�g��������A�P���������ƈ����オ��̂Ł`�A
240421
������j�b�g�́A�t�o�C�A�X��H��t����ƒ��˓����ɂ͋����Ȃ邯�ǁA���x�͂��Ȃ艺����Ǝv����B
�t�H�g�_�C�I�[�h�����Ȃ�A�����炭���Ȃ荂�����x�ɂȂ邪�c�A
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
240430
4�̕��@����ׂ�ƁB
�E����OP-AMP�ˌ�쓮���Ȃ��P�d���̃��m�͂ǂꂩ�H
�E�_�[�����g���g�����W�X�^��Vce���������ǁc�A�A���ƁA��x���œ_������Ȃ������B
�E�Q�[�g�h���C�o�{�p���[MOS-FET�˃`�b�v�p�[�c�ɂȂ�\����Ȃ̂ŁA��v����ς��B�������s���A�T�C���̓��m�ɂ��Ⴄ�B
�E�t�H�g�����[�˔����ɒx�����B
�Ƃ��������ŁA�ŏ���OP-AMP������ȁH
�_�[�����g���Ȃ炤�܂������AOP-AMP���g��Ȃ��̂̕��@�ł����������H
240402
�_�[�����g���������B
��͂�R�ꂪ����B�����āAVce�������̂Ŗ��邭�Ȃ��B
�d���d����d�������p��R�Ŗ��邳�͂ǂ��ɂ��Ȃ邪�A�R��́A������555��2�i�\���̉�H�\���łǂ��Ȃ邩�H�Ƃ��������ɂȂ�B
�܂�A�ߋ��ւ̉�A�ȉ�H�Ɍ����B
����Ӗ��A�V���v���ŁA�m����������Ȃ��B
OP-AMP�`���ƂȂ�ƁA�����ŁA���[���t�߂܂Ńt���X�C���O���āA���U�Ȃnj듮����Ȃ��ƂȂ�ƁA����Ƃ��ł�����B
�x�^GND�Ƃ��ʼn��P����悢�̂����ǁB
240403
����H(555�̒���2�i)�Ƀ_�[�����g���g�����W�X�^�[�������Ă݂��B
�d�������p�̒�R�������̂Ō��͎�߂����A�R��ɂ���쓮���Ȃ��B
�����āA�g�`���A�����N����ďオ���Ă��������͂��Ȃ�ɘa���ꂽ�B
���̕������ǂ����낤�B
�܂��AOP-AMP���̉�H��𒍕��������ゾ���ǁB�o�����炻��������ǂ��ĘR��Ȃ����邭�������Ƃ���ł͂���B
�_�[�����g���g�����W�X�^��Vce��0.9V�Ȃ̂�5V���d�ŁA10����200mA�ƂȂ�B
����ł��ƁA���Ȃ薾�邭�Ȃ邵�A�R��ɂ���쓮�������B
�����A�����V���b�g�̃p���X�͖��邭�Ȃ��B555�̗����オ��Ɏ��Ԃ�������̂����邩�Ǝv�����A����قǎ��Ԃ͂������Ă��Ȃ��悤���B
����ɔ�ׂāA
�s�̂̌����e��G17�͂��Ȃ薾�邭������̂Ŕg�`������ƁA30mSec�̊Ԍ����Ă����B
����͑����A�J������1/30�̃V���b�^�[�X�s�[�h���l�����Ă�̂ł͖������ȁH
�ƂȂ�ƁA������́A1mSec�I�[�_�[������Â�������̂��d���������B
�����オ��̗�N���Ǝv�����A�A���p���X�Ɣ�ׂāA�Z���T�[�ւ̔�����^����\�͂͌��\�Ⴄ�B
����āA�p���X���Ԃ́A5mSec���x�ɏグ�Ă��ǂ���������Ȃ��B
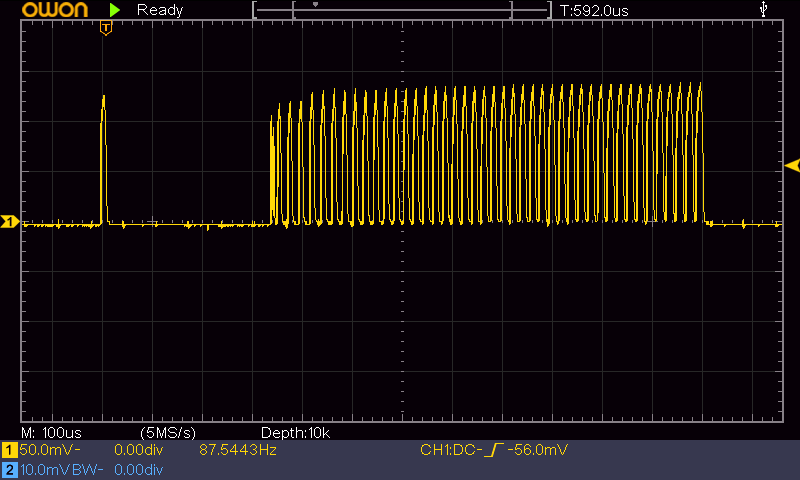 �g�`����`�g�̂悤�Ɋp�����ĂȂ��̂́A�Z���T�[���̖�肩�A���ʂ��ɂ₩�ɏ㉺���Ă�̂��H
���������A�������f���[�e�B�[�䂪�オ���Ă����悤���B
������ӁA�������͏\�����邢�̂ŁA���p�I�ɂ��A����ɋ߂Â��Ă����������K�v���ȁH
�����͂قړ�i�ڂ�555��H�̗����オ��̒x��̉\����ŁA���[�U�[�_�C�I�[�h�̃R���f�B�V�����ω��ł͖����Ǝv���B
�܂��A�h���C�u�����ɓd�ׂ����܂��Ă������Ƃ��l�����邪�A38KHz�ł͍l���Â炢���ȁA�A
�Ƃ肠�����A5�`7mSec�ň��肷��悤���B��H�̍H�v�łǂ��ɂ��Ȃ郂�m�Ȃ̂����C�ɂȂ�Ƃ��ł͂���B
240511
60MHzAGC-AMP�V��́A���V�O�i���̗L�������Œm�点�镔���̂݃`�F�b�N�B
���Ƃ͓����悤�ȕ����Ȃ̂ŁA��ɃR�R�����A����m�F�ɐ��������͂�ATT�̃X���[�z�[����������Ə������̂ŁA���P�������Ǝv���Ƃ����A���A�A���ƁA�R���f���T�[�������܂����B
���o�͂̈ʑ�����������A�Ō�̕ӂ��M���āA�o�͂̈ʑ��]�������������U�ɑ��ėǂ��Ɣ��f�B
�g�`����`�g�̂悤�Ɋp�����ĂȂ��̂́A�Z���T�[���̖�肩�A���ʂ��ɂ₩�ɏ㉺���Ă�̂��H
���������A�������f���[�e�B�[�䂪�オ���Ă����悤���B
������ӁA�������͏\�����邢�̂ŁA���p�I�ɂ��A����ɋ߂Â��Ă����������K�v���ȁH
�����͂قړ�i�ڂ�555��H�̗����オ��̒x��̉\����ŁA���[�U�[�_�C�I�[�h�̃R���f�B�V�����ω��ł͖����Ǝv���B
�܂��A�h���C�u�����ɓd�ׂ����܂��Ă������Ƃ��l�����邪�A38KHz�ł͍l���Â炢���ȁA�A
�Ƃ肠�����A5�`7mSec�ň��肷��悤���B��H�̍H�v�łǂ��ɂ��Ȃ郂�m�Ȃ̂����C�ɂȂ�Ƃ��ł͂���B
240511
60MHzAGC-AMP�V��́A���V�O�i���̗L�������Œm�点�镔���̂݃`�F�b�N�B
���Ƃ͓����悤�ȕ����Ȃ̂ŁA��ɃR�R�����A����m�F�ɐ��������͂�ATT�̃X���[�z�[����������Ə������̂ŁA���P�������Ǝv���Ƃ����A���A�A���ƁA�R���f���T�[�������܂����B
���o�͂̈ʑ�����������A�Ō�̕ӂ��M���āA�o�͂̈ʑ��]�������������U�ɑ��ėǂ��Ɣ��f�B
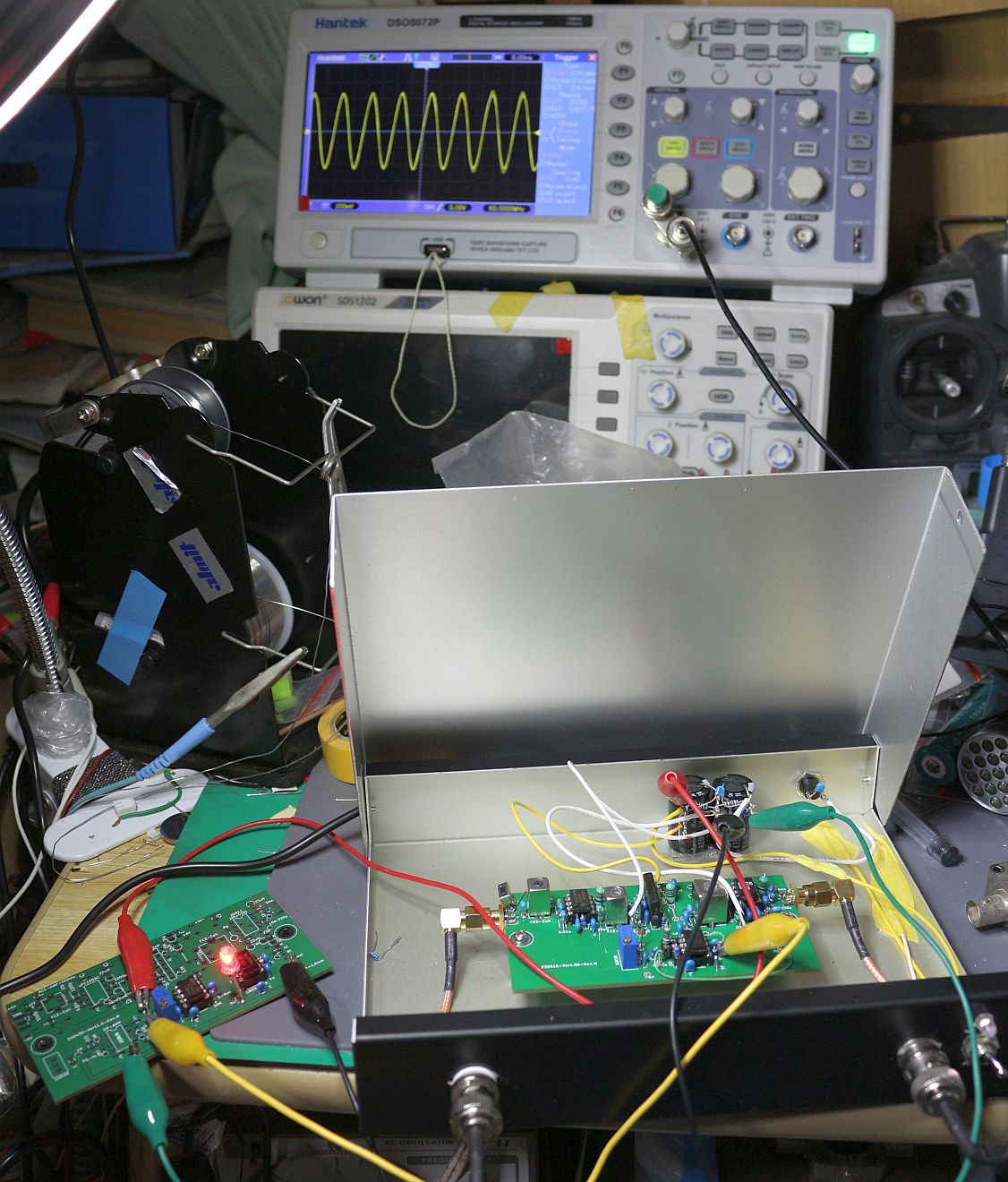 �����g�̕��͗e�ʂ������ߕ����p�X�������ǂ��Ƃ������܂����A1�ʂ�0.01��F�Ŕ�r ����������A�傫���Ă��قڕς��Ȃ������ł��B����āA���̗̈�ł́A��͏������˂镔�����傫���Ɣ��f���܂����B
���l�ɐM���̃p�^�[����R��t����̂��A���̗̈�ł́A����قǂ��܂���ʓI�ł͂Ȃ��悤�ł��ˁA�A
�g���Ă�p�[�c���������l����A����ᓖ�R���H�Ƃ��������ł��B
�����A�x�^GND��\�P�b�g��p��������Z������̂͌��\�����Ă��܂��ˁB
�ŁA�V���Ɋ�̔����ł��ˁB
240512
���O���ĐV��H��g�ݏグ�e�X�g���B
�傫���ς�����̂́AIC�\�P�b�g�������Ȃ������Ƃ���?
�����A����͂��܂肩������Ȃ��B�B
�܂��͔��U�X���B�����A�o�͂�����͂ւ̃��[�v�o�b�N�ɂ�郂�m�ŁA�ʑ��͊�{���]�ɂȂ��Ă�̂����ǁA�t�B���^�[��LC�����ŕς��悤�Ȃ̂ł���܂�g�����X�����Ŕ��]�͍D�܂����Ȃ������H
�����Ď����̃m�C�Y�������A����́A�ȑO����ő��̋@��ł��m�C�Y�g�`����̌�쓮�������B�����s���̓䂾���A��������o��Ύ��܂�B
���ƁA�p�^�[����A�d�����C�������͕t�߂�ʂ�悤�ɂ����̂ŁA���ꂪ�U�����N�����Ă�\��������B���͂��^�[�~�l�[�g���Ă����U����̂͂��ꂩ���B
���͕t�߂̓d���ɂȂ���R���f���T�[���O������A
���Ȃ藎���������`�B�R�R�ɗ�������d�ׂ̐U�����U�����Ă��B����U�d�̂Ȃ̂ŗ��z�I�ɂ̓p�^�[�������������ǂ����낤�B
�A�i���O�����g�̓�V�ȕ����ł���܂��ˁ`
�����ۑ�
�E�d������̉�荞�݂Ȃǂɂ�郋�[�v�o�b�N�ȃn�E�����O�I���ہB
�I�i���}6V�ɂ���H�����́ADi�œ�҂ɕ����邩�H
���Ƃ̓P�[�X��߂�Ƃ�����ƕς��v�f���B
�EFCZ�R�C����C�̒l�̖��ŁA�s�[�N���o�ĂȂ��\���B
�E�}�C�N���C���_�N�^�̓K���l�B
�����A���Ǝ��Ԃ�H�������Ă�B���Ă�B
240514
�I�i�����i�Ɠ����d�����C������蕪���A�}6V�쓮�ɂ����B
�Ȃ������A�m�C�Y�ɂ�锭�U�������������Ɏv�������A�I�i�̍����g���������Ȃ�オ���Ă����̂������̂悤���B
����͂����A�����@�̂悤�ȏ�ԂŁA�����ڑ������ł��A���M��̓d�������邾���ŁA�U�������Ȃ�o�Ă��Ă���B
���Ƃ́A��2��FCZ�̃s�[�N���͂�����o�Ȃ��̂����ǁA���pC�̔��e����E���Ă銴�����邪�A�A����������Ă݂����B���A�g���}�[���V�r�A�߂���̂ōl�����B�B
�Ƃɂ������ɂ��A�V��H��̕��j���ł��������Ă��������B
�NjL��
�v�����Ă݂āA���͂Əo�͂͂����Ɣ��]���Ă����B
�ł��ALC�̐ݒ�Ŕ����ɓ����̂������B
���U��C�̑I��́A���ɂ��U�d���������āA���ꂪ�傫���ƕ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂�����ǁA�Ƃ肠�����\�z������l���O�ɏo�Ă�\��������A�A�A
�g���}�[�ŒT�邵�������̂��ȁH
�z���������̂ŁA�g���}�[�ɐ�ւ���̂ɋ�J�����B
���A�s�[�N�͑傫���Ȃ������悭������Ȃ��B��𗠕Ԃ��������ŏ��ς��̂����邪�A
�ǂ����A���x�́A��i�ڂ̉�H�����傢���U���������Ă�悤�ł���B���ꂪ�A�����߂̔��U�B200mV���傢�̐U���Ȃ̂ŁA�ז��ŃA���B
���̌����́A�܂��s�������ǁA��͂�A�d���̉�荞�݂̉\��������B�}�C�i�X���̃}�C�N���C���_�N�^��r��������t�ɉ��P���邩���H
�\�P�b�g��C�������ւ�����@�̕�������ł͂��������A���H�I�ɍ�������B
�傫�߂Ə����߂Ń`�F�b�N�ł���A
�܂Ƃ߂�ƁA
�T��ƁA���U�|�C���g�����������A����͓�i�ڂ̑�����H�̔��U�̂悤�ŁA���͂��������Ă��U�����o��B
�����āA���̗U���I�Ȕ��U�͂Ȃ�ׂ��}�����݂����g�R�B
����Ƃ͈�����s�[�N���A���͂��őI�肪����킵���B
�������AGND�Ȃǂ̐ڑ����ŕω�����BZ�}�b�`���O���A���V�C�������H
���̒��ɂ͌��ʂ������Ȃ��l�ƁA���ʂɒB����v�Ă����悤�Ƃ���l������B
�M�o�[�ƃe�C�J�[�Ƃ����̂����āA
���[���V���b�g�Ȍv��ɂ̓e�C�J�[���_�̂����\�ɕ���Ă���Ƃ����B
��̌��������A���ɘb�������Ă��邪�A����ȂƂ��낾�낤�B
�Ɛт��グ�钆�ŁA�t�������Ă͂Ȃ�Ȃ��q�g�B����̓e�C�J�[�Ƃ��ďЉ��Ă����L������������B
�e�C�J�[�Ɗւ��Ƌz�����ꂽ�l�ɑ������o��̂ŁB
����ƂƂ��A�������Ƃ����邠��ł����ˁB�B
���ʂɈ��S���Đ����ł���Љ�A�E�ꂪ���������̂��A
���������������܂\���������ɂ��邩���B
���̐������B�B�B
���������A�c�C�b�^X�ł����������ǁA
�w��������Dr����Ȃ����灛���������Ȃ�Ė�������B
�Ƃ��f�J���Ȃ������ȁ[�ƌ����̂�����B��̋����ɂȂ�����y���B
�����͒n�ʂ�p�����V���[�r�W�l�X�ł����H�ƁA
240516
1�i�ڂƁA��i�ڂ̃R�C���̐ڑ����@���K�ł͖����A�P�`���Ă��̂����x�ቺ�▭�ȓ����U���̌����ɂȂ��Ă������B
�ł��R�����������ƁA���1.5�{�����Ȃ��āA�K�i�O�Ȃ̂ŁA������6�{�ɂȂ�B����Ȃ�A�Z�����āA��Őڍ�����̂��ǂ����ȁB
�������A�R�C����5�ɂȂ��Ă��������Up�ƂȂ�B
�����l�����A�Z���^�[�^�b�v���o�͂Ɍq���ł��̂���肾�����̂����ǁA���ꂪ�`���[�j���O��Q�l�������������Ă��B
FET���͂�������܂������A50����GND���Ƃ��Ă��郂�m���q���̂́A�A�Ƃ����̂��B���ƁA�����͓̂���Z���d���d���Ȃǂŕϓ������肷��B
�����ŁA���U��H��3pF�݂��ċ���ŏo���ɂ��Ă݂��炻�ꂾ���ł��傫�����P�B
��i�ڂ��������o���邩�������A�����e�X�g�̂���FCZ�R�C�������O���Ă��܂����B
�������ƁA�����Ƃ������肵���t�B���^�[�ɂȂ銴���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
38KHz�̔��U��H�̃O���[�����[�U�[�̊���ǁA
38KHz�̓d���������R���̂ŁA�Z���T�[����쓮���N�����B
�����ŁA2��H�^�̓�i�ڂɂ���A
�o�b�t�@�A���v������臒l��ݒ�ł���R���p���[�^�[�ɂ����B
����ŁA�M���̘R�ꂪ�Ȃ��Ȃ����B��쓮���Ȃ��Ȃ�B
�ł��A�₯�ɖ��邢�B
����M���������OP-AMP���x���̂Ńf���[�e�B�[��͍����Ȃ��B
�����g�̕��͗e�ʂ������ߕ����p�X�������ǂ��Ƃ������܂����A1�ʂ�0.01��F�Ŕ�r ����������A�傫���Ă��قڕς��Ȃ������ł��B����āA���̗̈�ł́A��͏������˂镔�����傫���Ɣ��f���܂����B
���l�ɐM���̃p�^�[����R��t����̂��A���̗̈�ł́A����قǂ��܂���ʓI�ł͂Ȃ��悤�ł��ˁA�A
�g���Ă�p�[�c���������l����A����ᓖ�R���H�Ƃ��������ł��B
�����A�x�^GND��\�P�b�g��p��������Z������̂͌��\�����Ă��܂��ˁB
�ŁA�V���Ɋ�̔����ł��ˁB
240512
���O���ĐV��H��g�ݏグ�e�X�g���B
�傫���ς�����̂́AIC�\�P�b�g�������Ȃ������Ƃ���?
�����A����͂��܂肩������Ȃ��B�B
�܂��͔��U�X���B�����A�o�͂�����͂ւ̃��[�v�o�b�N�ɂ�郂�m�ŁA�ʑ��͊�{���]�ɂȂ��Ă�̂����ǁA�t�B���^�[��LC�����ŕς��悤�Ȃ̂ł���܂�g�����X�����Ŕ��]�͍D�܂����Ȃ������H
�����Ď����̃m�C�Y�������A����́A�ȑO����ő��̋@��ł��m�C�Y�g�`����̌�쓮�������B�����s���̓䂾���A��������o��Ύ��܂�B
���ƁA�p�^�[����A�d�����C�������͕t�߂�ʂ�悤�ɂ����̂ŁA���ꂪ�U�����N�����Ă�\��������B���͂��^�[�~�l�[�g���Ă����U����̂͂��ꂩ���B
���͕t�߂̓d���ɂȂ���R���f���T�[���O������A
���Ȃ藎���������`�B�R�R�ɗ�������d�ׂ̐U�����U�����Ă��B����U�d�̂Ȃ̂ŗ��z�I�ɂ̓p�^�[�������������ǂ����낤�B
�A�i���O�����g�̓�V�ȕ����ł���܂��ˁ`
�����ۑ�
�E�d������̉�荞�݂Ȃǂɂ�郋�[�v�o�b�N�ȃn�E�����O�I���ہB
�I�i���}6V�ɂ���H�����́ADi�œ�҂ɕ����邩�H
���Ƃ̓P�[�X��߂�Ƃ�����ƕς��v�f���B
�EFCZ�R�C����C�̒l�̖��ŁA�s�[�N���o�ĂȂ��\���B
�E�}�C�N���C���_�N�^�̓K���l�B
�����A���Ǝ��Ԃ�H�������Ă�B���Ă�B
240514
�I�i�����i�Ɠ����d�����C������蕪���A�}6V�쓮�ɂ����B
�Ȃ������A�m�C�Y�ɂ�锭�U�������������Ɏv�������A�I�i�̍����g���������Ȃ�オ���Ă����̂������̂悤���B
����͂����A�����@�̂悤�ȏ�ԂŁA�����ڑ������ł��A���M��̓d�������邾���ŁA�U�������Ȃ�o�Ă��Ă���B
���Ƃ́A��2��FCZ�̃s�[�N���͂�����o�Ȃ��̂����ǁA���pC�̔��e����E���Ă銴�����邪�A�A����������Ă݂����B���A�g���}�[���V�r�A�߂���̂ōl�����B�B
�Ƃɂ������ɂ��A�V��H��̕��j���ł��������Ă��������B
�NjL��
�v�����Ă݂āA���͂Əo�͂͂����Ɣ��]���Ă����B
�ł��ALC�̐ݒ�Ŕ����ɓ����̂������B
���U��C�̑I��́A���ɂ��U�d���������āA���ꂪ�傫���ƕ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂�����ǁA�Ƃ肠�����\�z������l���O�ɏo�Ă�\��������A�A�A
�g���}�[�ŒT�邵�������̂��ȁH
�z���������̂ŁA�g���}�[�ɐ�ւ���̂ɋ�J�����B
���A�s�[�N�͑傫���Ȃ������悭������Ȃ��B��𗠕Ԃ��������ŏ��ς��̂����邪�A
�ǂ����A���x�́A��i�ڂ̉�H�����傢���U���������Ă�悤�ł���B���ꂪ�A�����߂̔��U�B200mV���傢�̐U���Ȃ̂ŁA�ז��ŃA���B
���̌����́A�܂��s�������ǁA��͂�A�d���̉�荞�݂̉\��������B�}�C�i�X���̃}�C�N���C���_�N�^��r��������t�ɉ��P���邩���H
�\�P�b�g��C�������ւ�����@�̕�������ł͂��������A���H�I�ɍ�������B
�傫�߂Ə����߂Ń`�F�b�N�ł���A
�܂Ƃ߂�ƁA
�T��ƁA���U�|�C���g�����������A����͓�i�ڂ̑�����H�̔��U�̂悤�ŁA���͂��������Ă��U�����o��B
�����āA���̗U���I�Ȕ��U�͂Ȃ�ׂ��}�����݂����g�R�B
����Ƃ͈�����s�[�N���A���͂��őI�肪����킵���B
�������AGND�Ȃǂ̐ڑ����ŕω�����BZ�}�b�`���O���A���V�C�������H
���̒��ɂ͌��ʂ������Ȃ��l�ƁA���ʂɒB����v�Ă����悤�Ƃ���l������B
�M�o�[�ƃe�C�J�[�Ƃ����̂����āA
���[���V���b�g�Ȍv��ɂ̓e�C�J�[���_�̂����\�ɕ���Ă���Ƃ����B
��̌��������A���ɘb�������Ă��邪�A����ȂƂ��낾�낤�B
�Ɛт��グ�钆�ŁA�t�������Ă͂Ȃ�Ȃ��q�g�B����̓e�C�J�[�Ƃ��ďЉ��Ă����L������������B
�e�C�J�[�Ɗւ��Ƌz�����ꂽ�l�ɑ������o��̂ŁB
����ƂƂ��A�������Ƃ����邠��ł����ˁB�B
���ʂɈ��S���Đ����ł���Љ�A�E�ꂪ���������̂��A
���������������܂\���������ɂ��邩���B
���̐������B�B�B
���������A�c�C�b�^X�ł����������ǁA
�w��������Dr����Ȃ����灛���������Ȃ�Ė�������B
�Ƃ��f�J���Ȃ������ȁ[�ƌ����̂�����B��̋����ɂȂ�����y���B
�����͒n�ʂ�p�����V���[�r�W�l�X�ł����H�ƁA
240516
1�i�ڂƁA��i�ڂ̃R�C���̐ڑ����@���K�ł͖����A�P�`���Ă��̂����x�ቺ�▭�ȓ����U���̌����ɂȂ��Ă������B
�ł��R�����������ƁA���1.5�{�����Ȃ��āA�K�i�O�Ȃ̂ŁA������6�{�ɂȂ�B����Ȃ�A�Z�����āA��Őڍ�����̂��ǂ����ȁB
�������A�R�C����5�ɂȂ��Ă��������Up�ƂȂ�B
�����l�����A�Z���^�[�^�b�v���o�͂Ɍq���ł��̂���肾�����̂����ǁA���ꂪ�`���[�j���O��Q�l�������������Ă��B
FET���͂�������܂������A50����GND���Ƃ��Ă��郂�m���q���̂́A�A�Ƃ����̂��B���ƁA�����͓̂���Z���d���d���Ȃǂŕϓ������肷��B
�����ŁA���U��H��3pF�݂��ċ���ŏo���ɂ��Ă݂��炻�ꂾ���ł��傫�����P�B
��i�ڂ��������o���邩�������A�����e�X�g�̂���FCZ�R�C�������O���Ă��܂����B
�������ƁA�����Ƃ������肵���t�B���^�[�ɂȂ銴���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
38KHz�̔��U��H�̃O���[�����[�U�[�̊���ǁA
38KHz�̓d���������R���̂ŁA�Z���T�[����쓮���N�����B
�����ŁA2��H�^�̓�i�ڂɂ���A
�o�b�t�@�A���v������臒l��ݒ�ł���R���p���[�^�[�ɂ����B
����ŁA�M���̘R�ꂪ�Ȃ��Ȃ����B��쓮���Ȃ��Ȃ�B
�ł��A�₯�ɖ��邢�B
����M���������OP-AMP���x���̂Ńf���[�e�B�[��͍����Ȃ��B
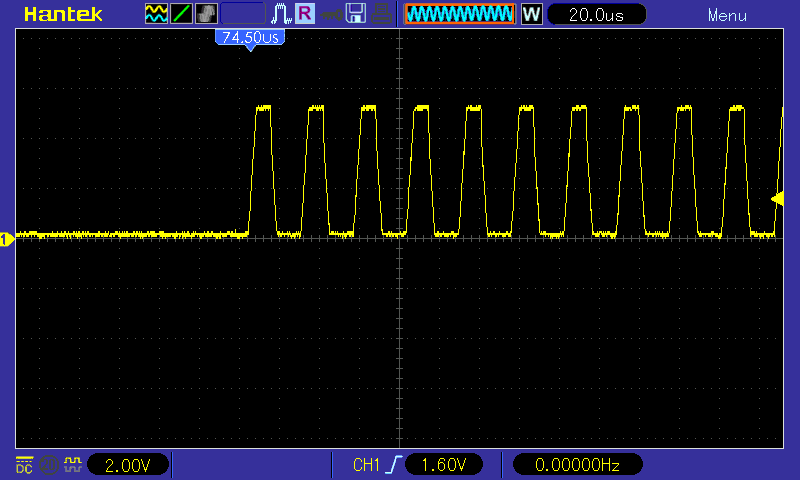 �������̐M��������Ƃ��Ȃ荂���B
�������̐M��������Ƃ��Ȃ荂���B
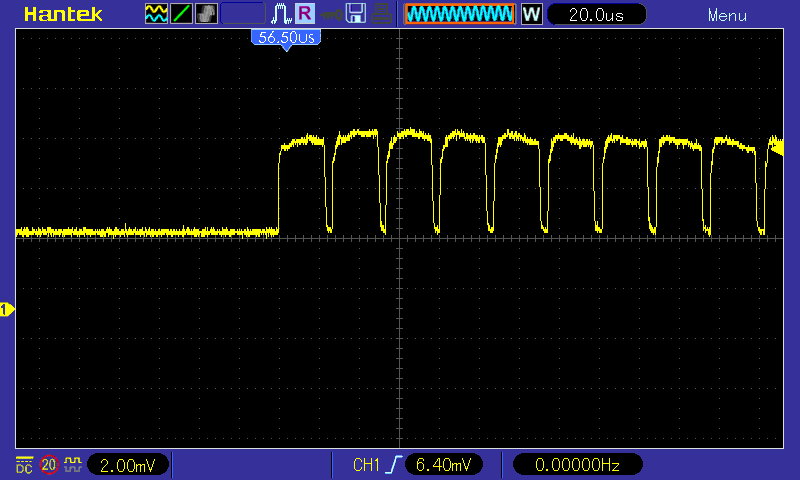 ��`�̃X���[�v��ԂȂ̂ŁA臒l��ς�����f��-�e�B�[��������ς�������A�����̈Ⴂ�ō��{�I�ȃ��m�ł͖����B
�ł����āA
�o�͂�Tr�Ɍq�����܂ܐ���M����������A��͂�Ƃ������A�f���[�e�B�������B
����́A���܂����d�ׂ�����Ǝv���A
���ꂪ�A�P�d���́A��������̐��䂪�ア����A�c���Ă��܂��Ă���̂����m��Ȃ��B
�����ŁA������ɘa���邽�߁A�o�͂�1K����GND�ɗ��Ƃ����B
�啪�ɘa�����B
��`�̃X���[�v��ԂȂ̂ŁA臒l��ς�����f��-�e�B�[��������ς�������A�����̈Ⴂ�ō��{�I�ȃ��m�ł͖����B
�ł����āA
�o�͂�Tr�Ɍq�����܂ܐ���M����������A��͂�Ƃ������A�f���[�e�B�������B
����́A���܂����d�ׂ�����Ǝv���A
���ꂪ�A�P�d���́A��������̐��䂪�ア����A�c���Ă��܂��Ă���̂����m��Ȃ��B
�����ŁA������ɘa���邽�߁A�o�͂�1K����GND�ɗ��Ƃ����B
�啪�ɘa�����B
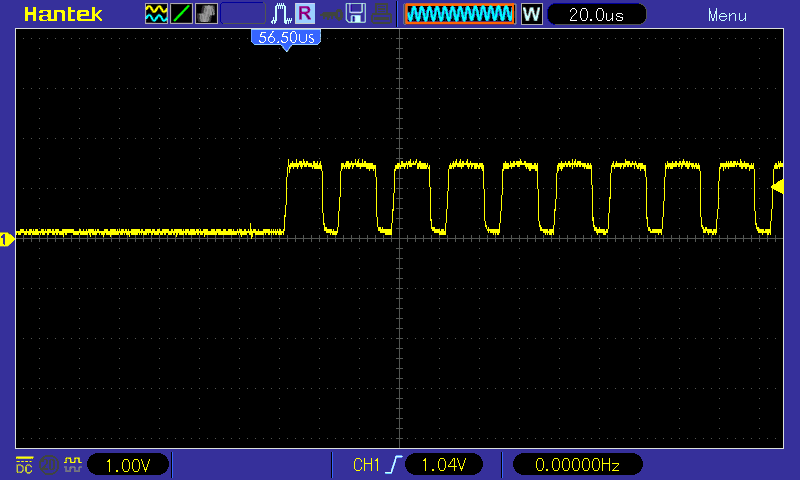 ���M���B
���M���B
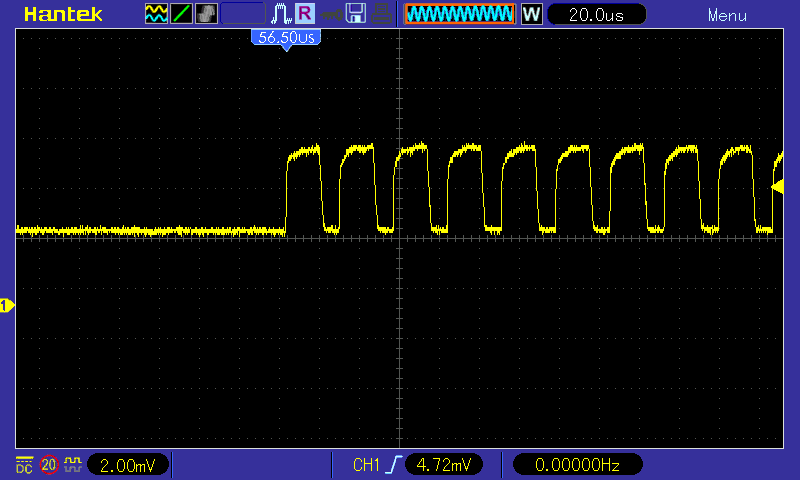 ���ƁA���x��ATr��Vce�Ȃǂɂ��d������̂��߁A�d�����グ�āA��R���グ�������ǂ����ȁ[�A�Ǝv���Ă���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
2025/02/17
�����R���p����pIC����ɓ���A���\���ʂɗL�邪�A
�O���[�����[�U�[��455KHz���U���ǂ���������Ȃ��B
�o����A10.7MHz�����肩���H
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�ŁA���ȁA���[�U�[�e�B
�d�r�������Ȃ����̂ŁA�������Ă݂܂����B�Z��������1.48V���x�ʂɂȂ����B
�d�r��5�ŁA
���ƁA���x��ATr��Vce�Ȃǂɂ��d������̂��߁A�d�����グ�āA��R���グ�������ǂ����ȁ[�A�Ǝv���Ă���B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
2025/02/17
�����R���p����pIC����ɓ���A���\���ʂɗL�邪�A
�O���[�����[�U�[��455KHz���U���ǂ���������Ȃ��B
�o����A10.7MHz�����肩���H
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�ŁA���ȁA���[�U�[�e�B
�d�r�������Ȃ����̂ŁA�������Ă݂܂����B�Z��������1.48V���x�ʂɂȂ����B
�d�r��5�ŁA

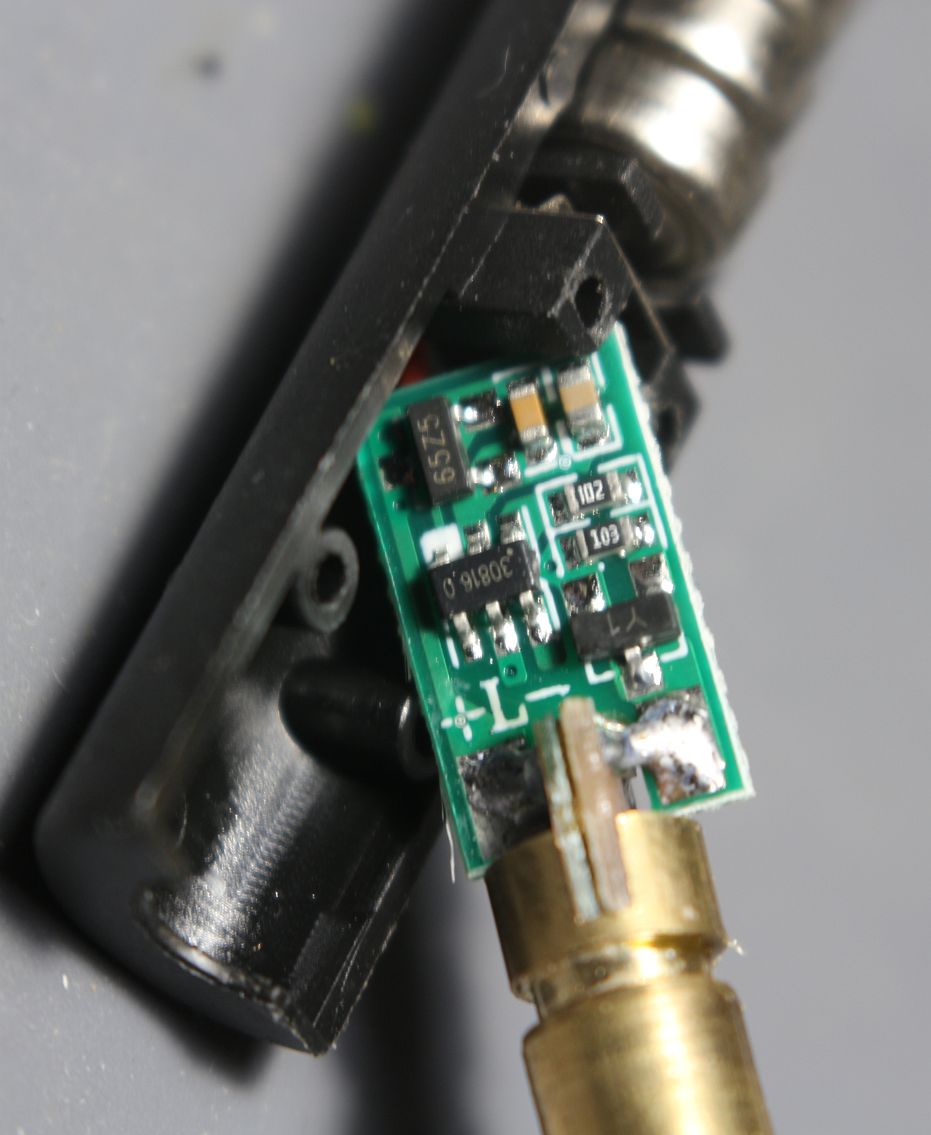 65Z5��30816-0��Y1�ƂȂ��Ă�悤���B
����́A
7.5�`8V�̓d�r�˃}�C�N��SW�˃{���e�[�W���M�����[�^�[�{C��IC�ɂ�锭�U�H�˃p���[Tr�˃��[�U�[���W���[���{R
�Ƃ������[�g�̂悤��
���ƃg���K�[����̃}�C�N��SW�ȊO�ɁA�J�[�g�m�F�p��SW������B
�������M������A�d�r�͊O�����d�ɂ��o���邩���m��Ȃ��B
65Z5��30816-0��Y1�ƂȂ��Ă�悤���B
����́A
7.5�`8V�̓d�r�˃}�C�N��SW�˃{���e�[�W���M�����[�^�[�{C��IC�ɂ�锭�U�H�˃p���[Tr�˃��[�U�[���W���[���{R
�Ƃ������[�g�̂悤��
���ƃg���K�[����̃}�C�N��SW�ȊO�ɁA�J�[�g�m�F�p��SW������B
�������M������A�d�r�͊O�����d�ɂ��o���邩���m��Ȃ��B
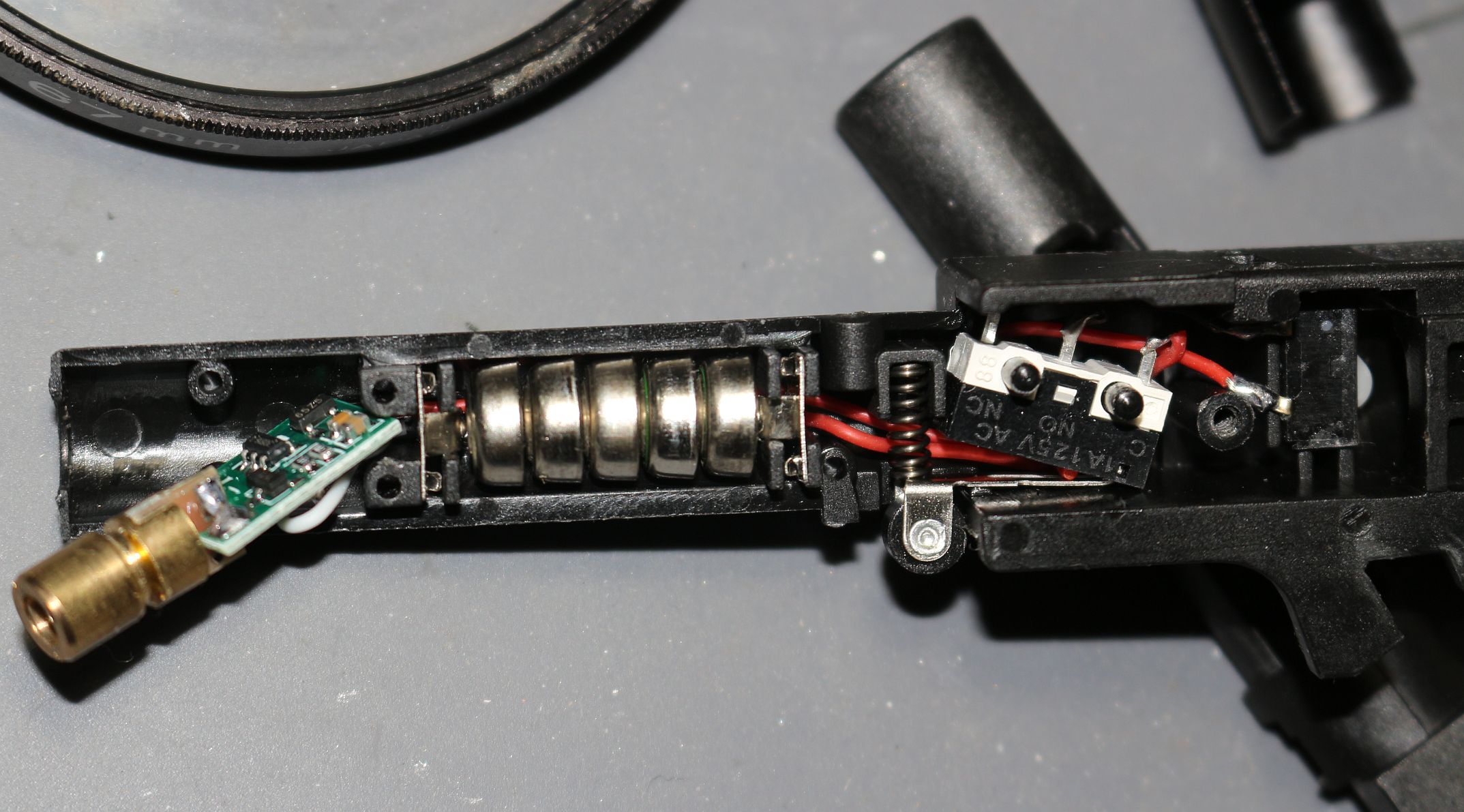 ���M�����[�^�[�ɂ�C������̂ŁA���U�͂��傢���Ԃ������邩���B
������A�������Ԃ������ݒ�̉\�����B
�������Ԃ̒����Ƃ��ƌ����ݒ�̂��������ȑ���͉ۑ肩�ȁB
�@�B�I�ɂ́A�g���K���d���̂ƃX���C�h�X�g�b�v�����邭�炢�H
���M�����[�^�[�ɂ�C������̂ŁA���U�͂��傢���Ԃ������邩���B
������A�������Ԃ������ݒ�̉\�����B
�������Ԃ̒����Ƃ��ƌ����ݒ�̂��������ȑ���͉ۑ肩�ȁB
�@�B�I�ɂ́A�g���K���d���̂ƃX���C�h�X�g�b�v�����邭�炢�H
 G17���ƃg���K�̃X�g���[�N���Z���̂ŏ��X�������̂��Ƃ������B
�܂��A�l����ƁA���M�����[�^�́A2V���x�̗]�T���K�v�Ǝv����B��h���b�v�^�C�v�ł͖����悤���B
5V�ŏo���̂ɁA7�`7.5V�ʕK�v�ƌ������Ƃ��Ǝv���B
�L���Ȃ�
�d�r�˃��[�h���ˑ傫�߂̃R���f���T�[�ƃ��j�b�g
�Ƃ����u���b�N�����B
�܂��́A�����ȃ��`�E���d�r���g���Ƃ��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
250510
[�����e�p]�傫�ȏo�̗͂��[�U�[�_�C�I�[�h�̍����g�쓮�B�B
G17���ƃg���K�̃X�g���[�N���Z���̂ŏ��X�������̂��Ƃ������B
�܂��A�l����ƁA���M�����[�^�́A2V���x�̗]�T���K�v�Ǝv����B��h���b�v�^�C�v�ł͖����悤���B
5V�ŏo���̂ɁA7�`7.5V�ʕK�v�ƌ������Ƃ��Ǝv���B
�L���Ȃ�
�d�r�˃��[�h���ˑ傫�߂̃R���f���T�[�ƃ��j�b�g
�Ƃ����u���b�N�����B
�܂��́A�����ȃ��`�E���d�r���g���Ƃ��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
250510
[�����e�p]�傫�ȏo�̗͂��[�U�[�_�C�I�[�h�̍����g�쓮�B�B
 SOT-23�̎��t���������B�u���b�W������`�ŗ������݁A���c�z�������Ŏ�菜���B
SOT-23�̎��t���������B�u���b�W������`�ŗ������݁A���c�z�������Ŏ�菜���B
 �ق����z���������ǂ������ȁ[�Ƃ��B
�p���[MOS-FET�̓Q�[�g�e�ʂ��傫���BK4017�A�Q�[�g�̗e�ʂ�750pF
�����ŁA�Q�[�g�h���C�o�[���g�p����B�摜�̓h���C�u�����B
�Q�[�g�h���C�o�[�FMCP1402T
�ق����z���������ǂ������ȁ[�Ƃ��B
�p���[MOS-FET�̓Q�[�g�e�ʂ��傫���BK4017�A�Q�[�g�̗e�ʂ�750pF
�����ŁA�Q�[�g�h���C�o�[���g�p����B�摜�̓h���C�u�����B
�Q�[�g�h���C�o�[�FMCP1402T
 �g��ł݂āA�Q�[�g�h���C�o�[�o�͂̃Q�[�g����d��
FET�����LD�̐���d���y�ѐ���d���͐���B
�����ǁA���̐M���͐ϕ�����Ă�̂ŁA���܂��o�Ȃ��B
�Ǝv������A
������̃o�C�A�X��H��60MHz�p�Ƃ���LC�������Ă��āA���ꂪ���ɂȂ��Ă����B
�g��ł݂āA�Q�[�g�h���C�o�[�o�͂̃Q�[�g����d��
FET�����LD�̐���d���y�ѐ���d���͐���B
�����ǁA���̐M���͐ϕ�����Ă�̂ŁA���܂��o�Ȃ��B
�Ǝv������A
������̃o�C�A�X��H��60MHz�p�Ƃ���LC�������Ă��āA���ꂪ���ɂȂ��Ă����B
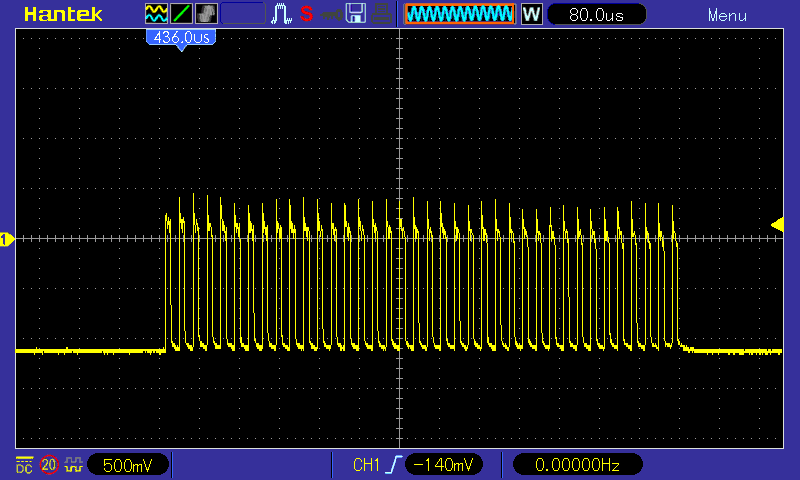 47����LD�����U���钼�O���x���̏�Ԃɂ�����A���X�͈��肷��悤���B���傫�ȍ��͂Ȃ��B
�܂��́A38KHz�Ő��������̂ŁA455KHz�ɃA�b�v�B
�܂��܂��A�쓮�ł������ǁA������ł��̃O���[�����[�U�[���W���[���̔������x�̌��E���߂��Ǝv�����B
47����LD�����U���钼�O���x���̏�Ԃɂ�����A���X�͈��肷��悤���B���傫�ȍ��͂Ȃ��B
�܂��́A38KHz�Ő��������̂ŁA455KHz�ɃA�b�v�B
�܂��܂��A�쓮�ł������ǁA������ł��̃O���[�����[�U�[���W���[���̔������x�̌��E���߂��Ǝv�����B
 �|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�t�@�X�K���H
�l�ł���ĂĂق��̂͒��ׂ���قƂ�ǂ��Ȃ�����A���������ǁA
���̎���̌����e�̃��m�炵���B
�悭�킩��Ȃ����ǁA�����������Ƃ炵���B
��{�����R���p�͐ԊO������W���[���̂悤�ʼn��\�N���ς���ĂȂ������B
�����p�p�[�c�Ƃ��Ă͔j�i�̐��\�̑f�q�����ǁB
�T�C�����T�[�^�ŃG�A���Ńg���K�����O����̂́A�Ƃ��̐̂Ɏv�����Ă����ǁB
���ω��𑁂��Ɏ@�m���Ȃ��ƐU���̉e������B
����́A��PFC�Ńu���[�o�b�N�łЂ��˂��͂�����G�A�ȃX�[�p�[�E�F�|���V�X�e���A�����CAT�̐U���A�����C���[�W���B
�V���[�^�[�����́A�Ζ��X�y�N�g�����m���낤������v���B�B
�������A�V���[�^�[�����̃^�[�Q�b�g�g���āA�}���V���̂Ђ��˂̃��c�����Ă��L�����������̂��ȁH�L�����������Ⴞ�����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�O���C�R�Ȃǂ�BPF�A
�ׂ̃o���h�Ƃ̃N���X�I�[�o�[�|�C���g�̓J�b�g�I�t���g��-3dB�̗l�Ȃ��ǁA
�܂�A�M���̔��l���͒P���ɓd����-6dB�ł͂Ȃ��āA�p���[�Ƃ���������-3dB��Q�l�����̓_�Ō���悤�ȋC�����邯�ǁA������o��
�ߓn�����̎����Ńx�N�g���}���獇�������肵���L�����B�B
����Z�̕��ׂɂ�����Ƃ��́A�d���𑫂�-6dB�̕����������Ƃ�������̂����A
�ʑ��̈Ⴂ�H��ш�̖ʐςƂ��ŏd�˂�Ɠs���������̂��ȁH
�܂��A�Ƃɂ����A�����R��������j�b�g��BPF��Q�l�̓O���t����10�`13���x�Ɠǂ߂�B
DABP���ł�Q��~���肷�����̂��Ǝv���B
���̒��x�Ȃ�ꎟ���A��BPF�ł��\�ł͂Ȃ����ȁH�Ǝv�����B�E�B�[���u���b�W�^�ł��B���Ƃ�OP-AMP�ɂƂ��ẮA���g���������̂��l�b�N���ȁH
�o�C�A�X�ݒ肪�߂�ǂ��������ǁA�g�����W�X�^�Ƃ�������H?
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�t�@�X�K���H
�l�ł���ĂĂق��̂͒��ׂ���قƂ�ǂ��Ȃ�����A���������ǁA
���̎���̌����e�̃��m�炵���B
�悭�킩��Ȃ����ǁA�����������Ƃ炵���B
��{�����R���p�͐ԊO������W���[���̂悤�ʼn��\�N���ς���ĂȂ������B
�����p�p�[�c�Ƃ��Ă͔j�i�̐��\�̑f�q�����ǁB
�T�C�����T�[�^�ŃG�A���Ńg���K�����O����̂́A�Ƃ��̐̂Ɏv�����Ă����ǁB
���ω��𑁂��Ɏ@�m���Ȃ��ƐU���̉e������B
����́A��PFC�Ńu���[�o�b�N�łЂ��˂��͂�����G�A�ȃX�[�p�[�E�F�|���V�X�e���A�����CAT�̐U���A�����C���[�W���B
�V���[�^�[�����́A�Ζ��X�y�N�g�����m���낤������v���B�B
�������A�V���[�^�[�����̃^�[�Q�b�g�g���āA�}���V���̂Ђ��˂̃��c�����Ă��L�����������̂��ȁH�L�����������Ⴞ�����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�O���C�R�Ȃǂ�BPF�A
�ׂ̃o���h�Ƃ̃N���X�I�[�o�[�|�C���g�̓J�b�g�I�t���g��-3dB�̗l�Ȃ��ǁA
�܂�A�M���̔��l���͒P���ɓd����-6dB�ł͂Ȃ��āA�p���[�Ƃ���������-3dB��Q�l�����̓_�Ō���悤�ȋC�����邯�ǁA������o��
�ߓn�����̎����Ńx�N�g���}���獇�������肵���L�����B�B
����Z�̕��ׂɂ�����Ƃ��́A�d���𑫂�-6dB�̕����������Ƃ�������̂����A
�ʑ��̈Ⴂ�H��ш�̖ʐςƂ��ŏd�˂�Ɠs���������̂��ȁH
�܂��A�Ƃɂ����A�����R��������j�b�g��BPF��Q�l�̓O���t����10�`13���x�Ɠǂ߂�B
DABP���ł�Q��~���肷�����̂��Ǝv���B
���̒��x�Ȃ�ꎟ���A��BPF�ł��\�ł͂Ȃ����ȁH�Ǝv�����B�E�B�[���u���b�W�^�ł��B���Ƃ�OP-AMP�ɂƂ��ẮA���g���������̂��l�b�N���ȁH
�o�C�A�X�ݒ肪�߂�ǂ��������ǁA�g�����W�X�^�Ƃ�������H?
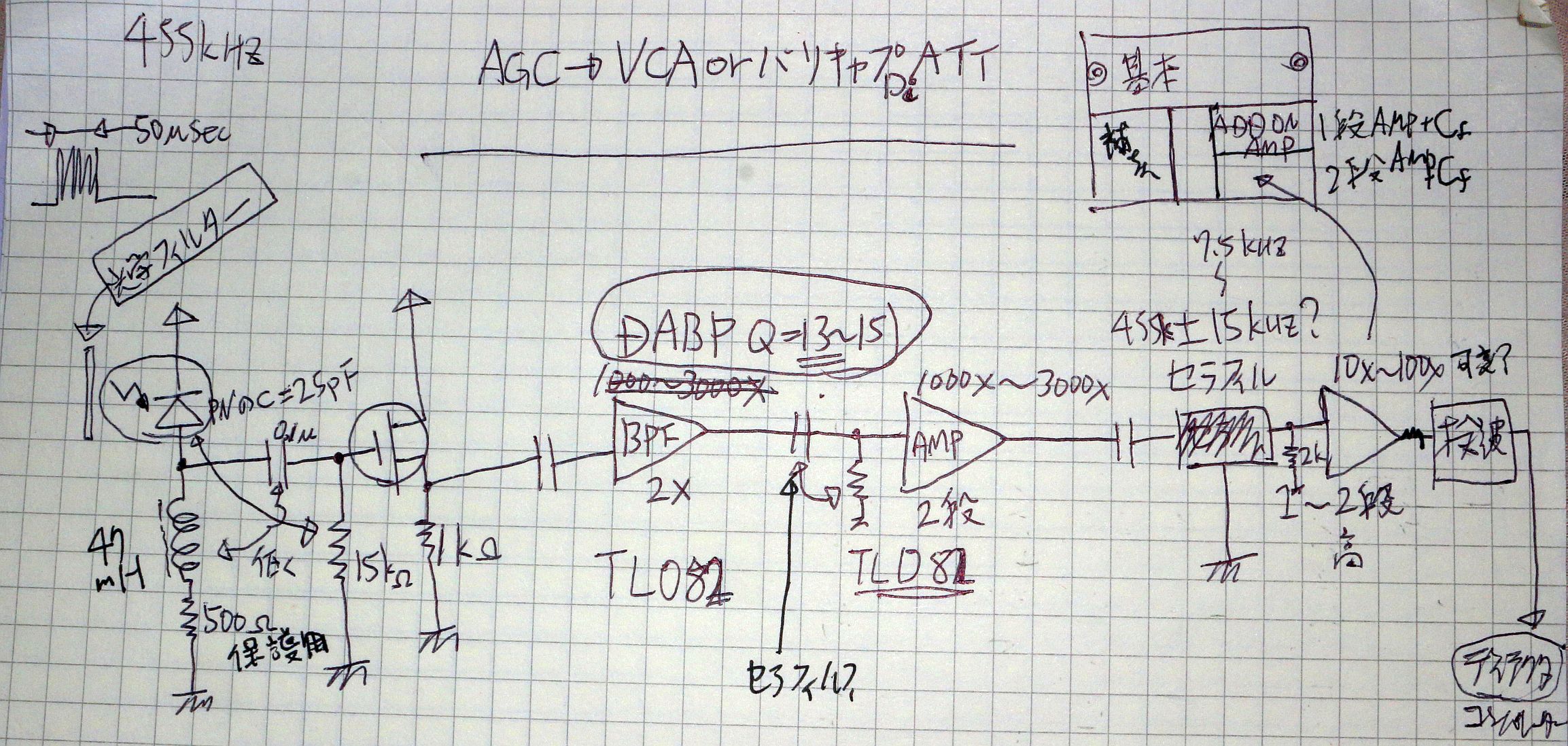 �����_�A�Z���t�B�������Ă��Ȃ����A�X�Ȃ鑝���́A����ŁA���Ȃ苭�������Ƃ��v���B
�܂��AAGC-AMP��H�������ĂȂ��̂ŁA�����Ƃ���ƁA�o���L���b�v�̂悤��ATT�p��Di�ȃ��m��ʂ��B�K�v������B
���̂Ƃ��́A��ʐς�����Ȃ����番�����Ďg�������B
���˔g�H�����V���b�g�B
�����_�A�Z���t�B�������Ă��Ȃ����A�X�Ȃ鑝���́A����ŁA���Ȃ苭�������Ƃ��v���B
�܂��AAGC-AMP��H�������ĂȂ��̂ŁA�����Ƃ���ƁA�o���L���b�v�̂悤��ATT�p��Di�ȃ��m��ʂ��B�K�v������B
���̂Ƃ��́A��ʐς�����Ȃ����番�����Ďg�������B
���˔g�H�����V���b�g�B
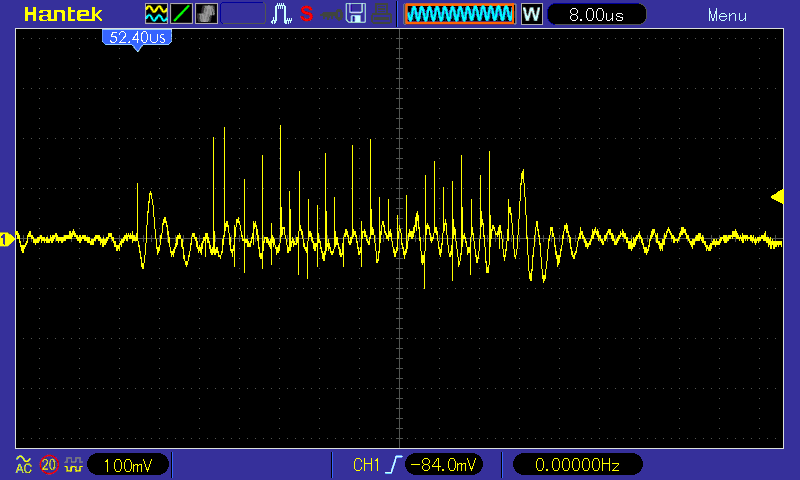 �A���o�͂ɂ�郂�m�BBPF�Ƃ̃`���[�j���O�̃Y���H�Ǝv���邤�Ȃ�݂����Ȃ̂��B
�A���o�͂ɂ�郂�m�BBPF�Ƃ̃`���[�j���O�̃Y���H�Ǝv���邤�Ȃ�݂����Ȃ̂��B
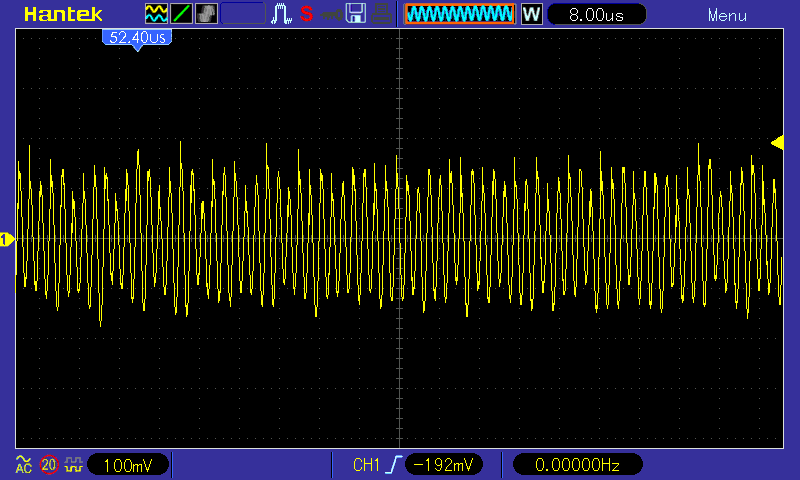 ���M�����B
���M�����B
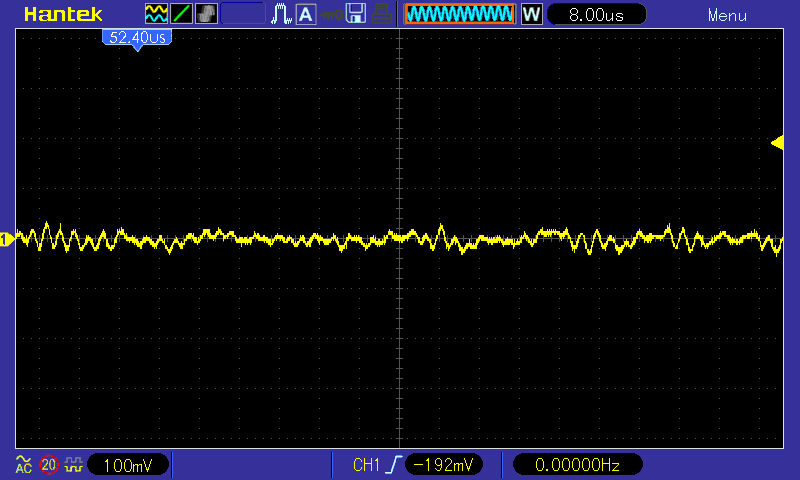 �|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
250718
AGC��H�ɂ��Ă݂����B
�I�[�g�Q�C���R���g���[���������l����B
��Z��H�Ȃǂ�VCA���_�C�I�[�h�̃A�b�e�l�[�^�[���K�v�B
Di��AGC�̓o���L���b�v���ł͂Ȃ��ADi�̒�d���ł̓��ʕω������Ă�����ۂ��B
�Ȃ̂ŁADi�����Ƃ��A���i���L���Ȃ̂����B
���̕������ƃt�B�[�h�o�b�N�͏o�͂Ƀl�K�e�B�u(���])�ȓd���l�ƂȂ邾�낤�B
�ėp��Di�ʼn\�Ȃ�B
�܂��A��ԍŏ��ɍ�����̂����̃^�C�v�����炳�قǓ���������A
���g��ϕ��A���]�����ATr�œd�����h���C�u��OK���낤�B
250719
�����g����455KHz�ł͂Ȃ�350KHz�ӂ�̂悤���B�������j�A�̏c��Log�B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
250718
AGC��H�ɂ��Ă݂����B
�I�[�g�Q�C���R���g���[���������l����B
��Z��H�Ȃǂ�VCA���_�C�I�[�h�̃A�b�e�l�[�^�[���K�v�B
Di��AGC�̓o���L���b�v���ł͂Ȃ��ADi�̒�d���ł̓��ʕω������Ă�����ۂ��B
�Ȃ̂ŁADi�����Ƃ��A���i���L���Ȃ̂����B
���̕������ƃt�B�[�h�o�b�N�͏o�͂Ƀl�K�e�B�u(���])�ȓd���l�ƂȂ邾�낤�B
�ėp��Di�ʼn\�Ȃ�B
�܂��A��ԍŏ��ɍ�����̂����̃^�C�v�����炳�قǓ���������A
���g��ϕ��A���]�����ATr�œd�����h���C�u��OK���낤�B
250719
�����g����455KHz�ł͂Ȃ�350KHz�ӂ�̂悤���B�������j�A�̏c��Log�B
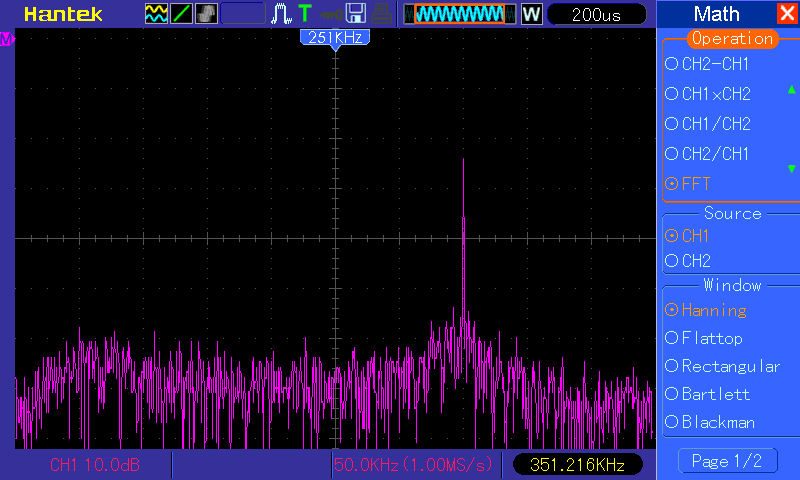 �v�Z��͂���ŁA
�v�Z��͂���ŁA
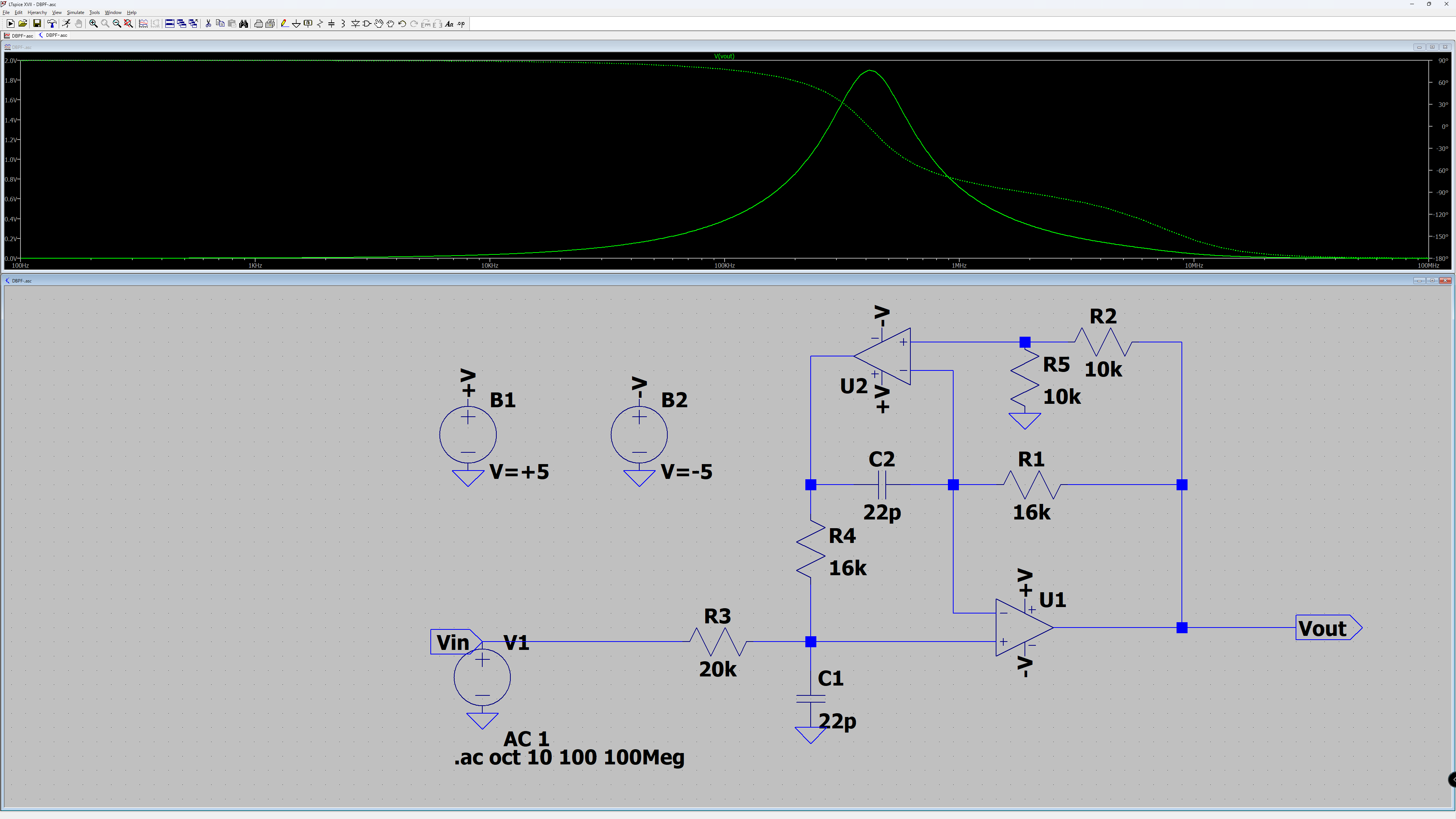 C�̃o�����X�l�̒��B������Ȃ��߁A
�v�Z�T�C�g�Ōv�Z���Ȃ����ς����̂����������m��Ȃ��B
�����āAOP-AMP�̑��x�̖������肻�����ȁH
C�̌������AQ�̊m�F�ƁAF0�����������ӏ��̊m�F�B
�����āA
AGC��H��g�ݍ��ނ��ƂɌ���B��}���B
C�̃o�����X�l�̒��B������Ȃ��߁A
�v�Z�T�C�g�Ōv�Z���Ȃ����ς����̂����������m��Ȃ��B
�����āAOP-AMP�̑��x�̖������肻�����ȁH
C�̌������AQ�̊m�F�ƁAF0�����������ӏ��̊m�F�B
�����āA
AGC��H��g�ݍ��ނ��ƂɌ���B��}���B
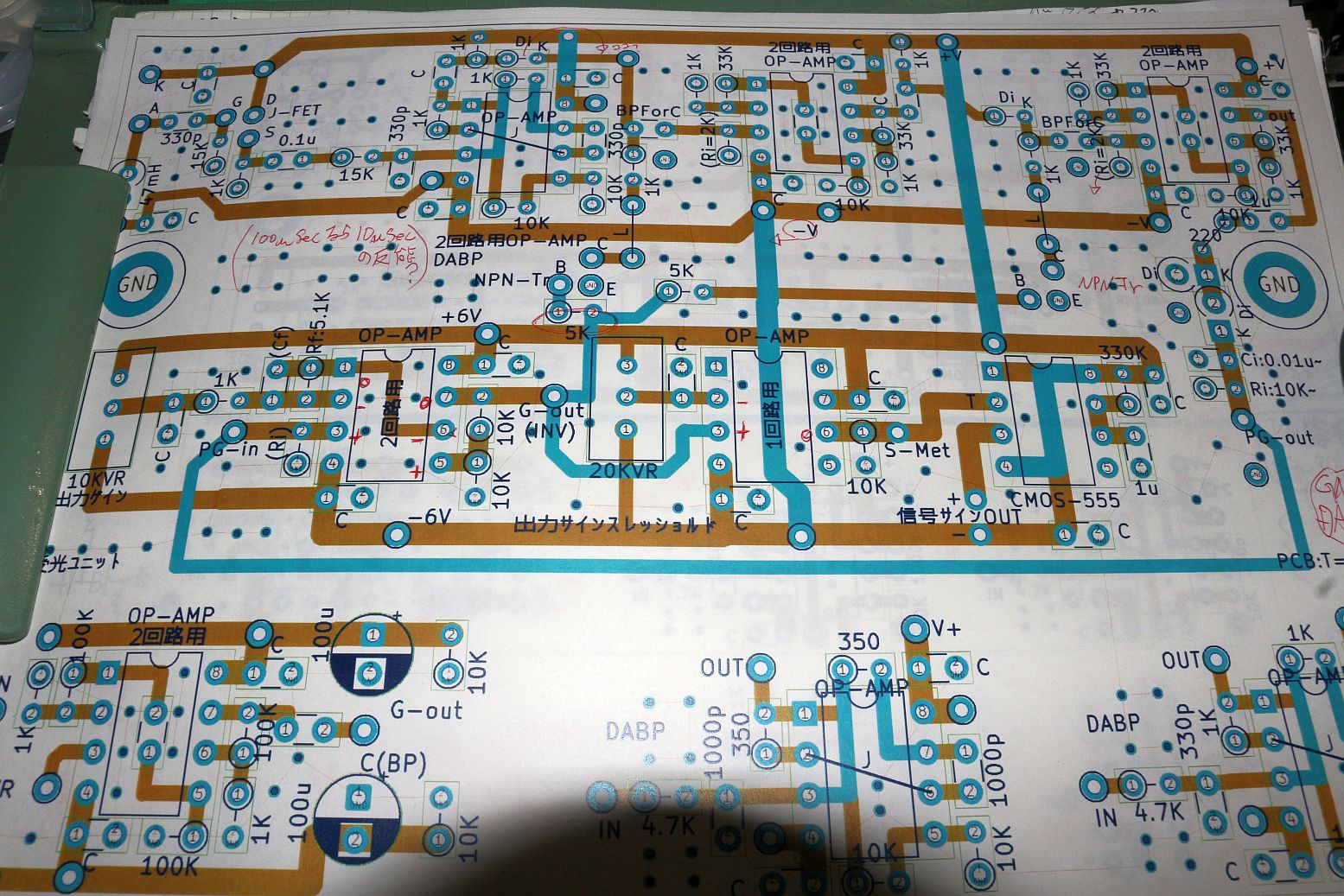
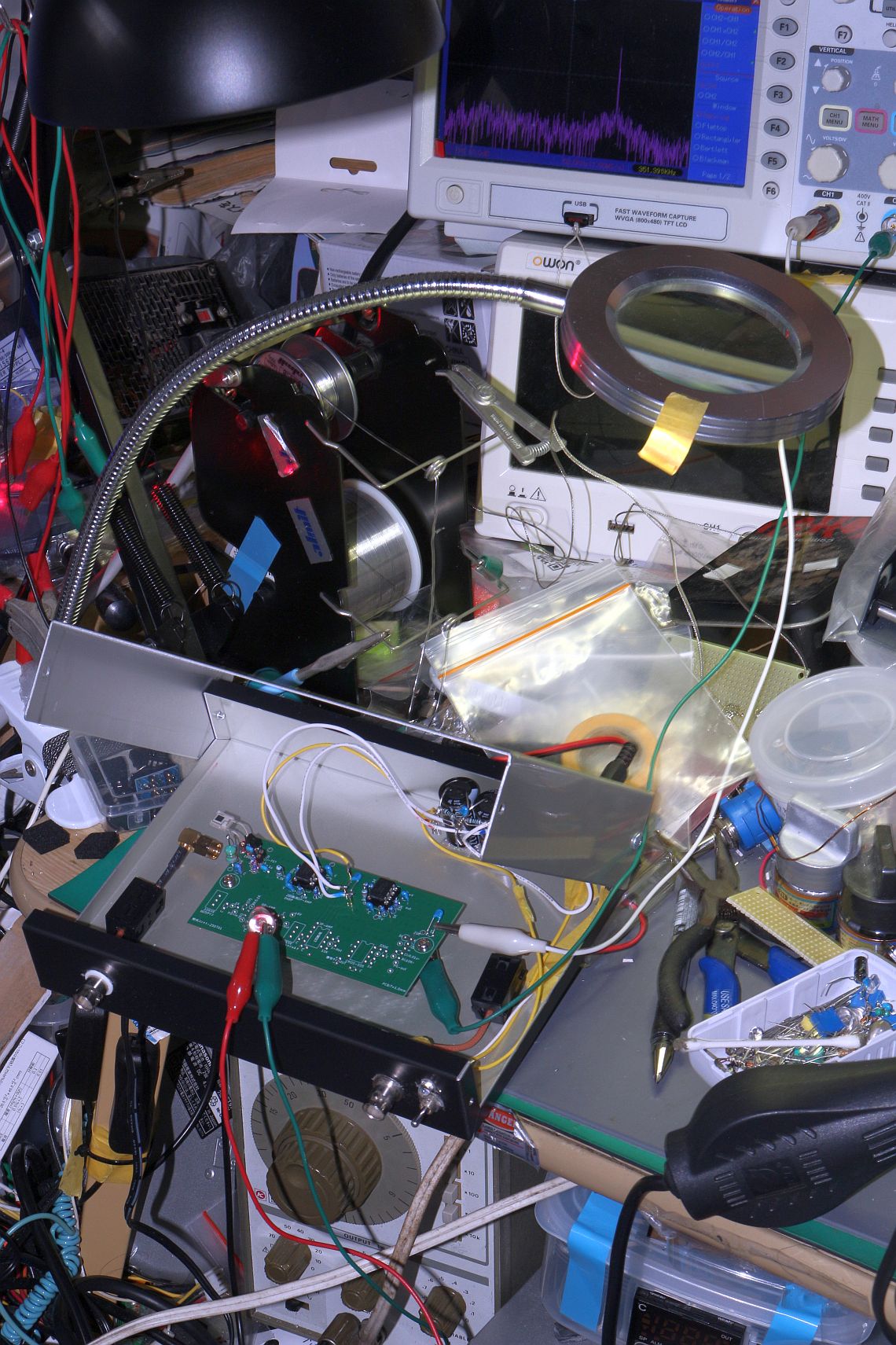 �d����SW�d������m�C�Y������̂Ńt�B���^����Ă���B
��̂���Ȋ�����PCB�����Ǝ҂ɔ��������B(AGC�F�I�[�g�Q�C���R���g���[�������ɂĉ����M���M��)
�d����SW�d������m�C�Y������̂Ńt�B���^����Ă���B
��̂���Ȋ�����PCB�����Ǝ҂ɔ��������B(AGC�F�I�[�g�Q�C���R���g���[�������ɂĉ����M���M��)
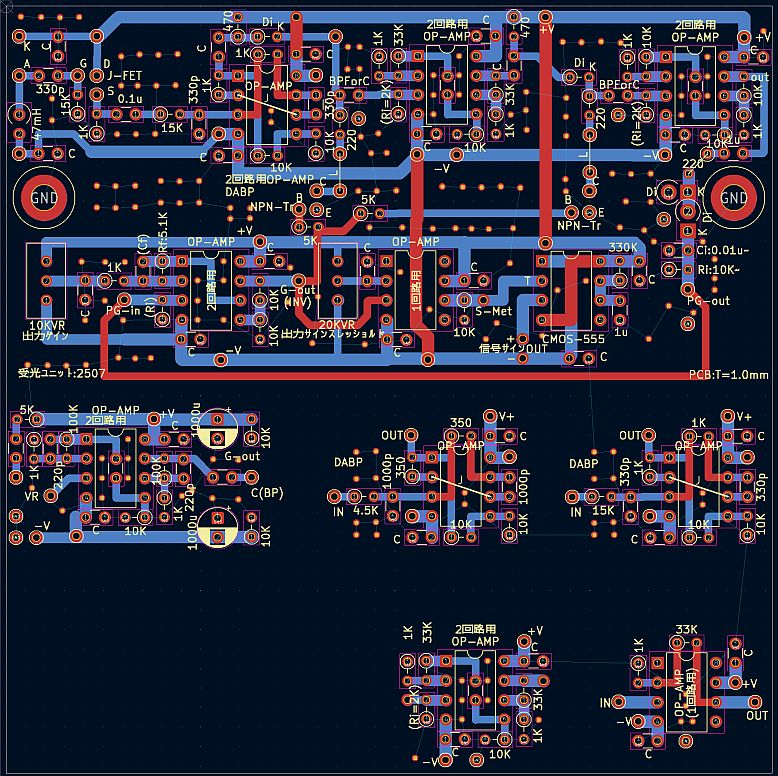 ��T�Ԃœ͂����ǁA����͂�����������B
���ɁA���������Đݒ肵�Ȃ���B�B
250720�NjL��
�Ƃ肠�����A
F0��C�ȊOR2R3�ɂ��R���̉e���ɗ��܂�B
(R2��R#�͓����l�̐ݒ肾����A(���萔��CR�Ƃ��������B)
C�̃o�����X�����e�ł��郌�x���AC=100pF�Ōv�Z���āA
Q��15�ɏグ�Ă݂�B
�ŁA����Ȋ����B
3.5K���Ȃ�Ē�R�͒��B���c�A�A������IC�\�P�b�g�ōs�������B
��T�Ԃœ͂����ǁA����͂�����������B
���ɁA���������Đݒ肵�Ȃ���B�B
250720�NjL��
�Ƃ肠�����A
F0��C�ȊOR2R3�ɂ��R���̉e���ɗ��܂�B
(R2��R#�͓����l�̐ݒ肾����A(���萔��CR�Ƃ��������B)
C�̃o�����X�����e�ł��郌�x���AC=100pF�Ōv�Z���āA
Q��15�ɏグ�Ă݂�B
�ŁA����Ȋ����B
3.5K���Ȃ�Ē�R�͒��B���c�A�A������IC�\�P�b�g�ōs�������B
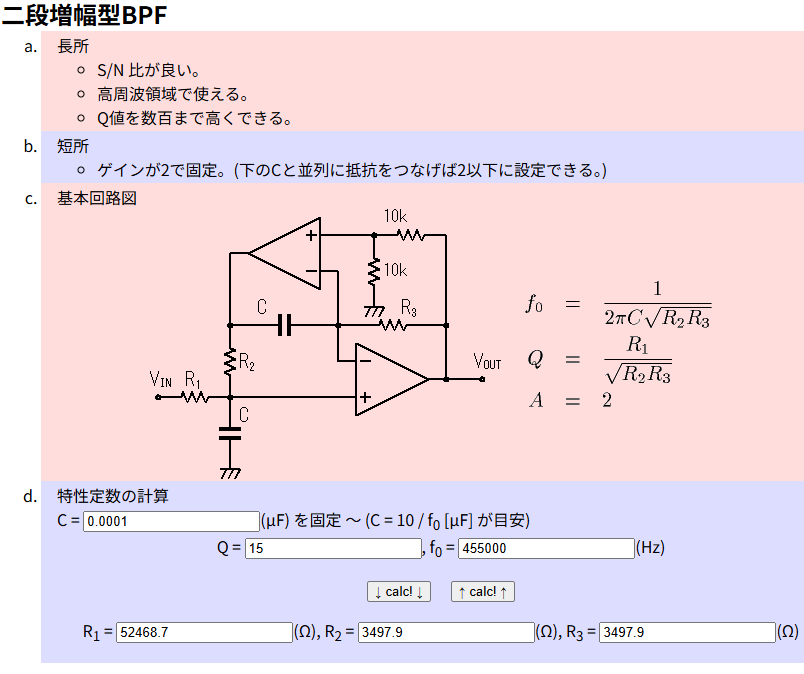 �NjL02��
�ǂ��ɂ������Ȃ��B
�v�������āAOP-AMP�̎�ނ�ς��Ă݂��B
GB�ς̍���4580�͔��U���Ă�悤���B
�Ō��\�I�[���}�C�e�B�[�ɂ��܂������₷��5532�ɂ�����A
����ȋ��ƂȂ����B
�NjL02��
�ǂ��ɂ������Ȃ��B
�v�������āAOP-AMP�̎�ނ�ς��Ă݂��B
GB�ς̍���4580�͔��U���Ă�悤���B
�Ō��\�I�[���}�C�e�B�[�ɂ��܂������₷��5532�ɂ�����A
����ȋ��ƂȂ����B
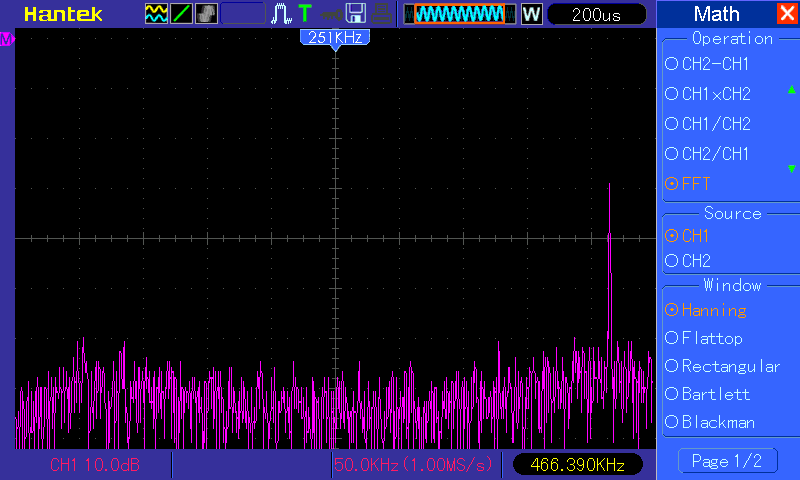 �}�ł́AOSC��LED���q���ŁA�s�[�N������o�����g�R�ł��B
��߂̃��[�U�[���ł�����B
�}�ł́AOSC��LED���q���ŁA�s�[�N������o�����g�R�ł��B
��߂̃��[�U�[���ł�����B
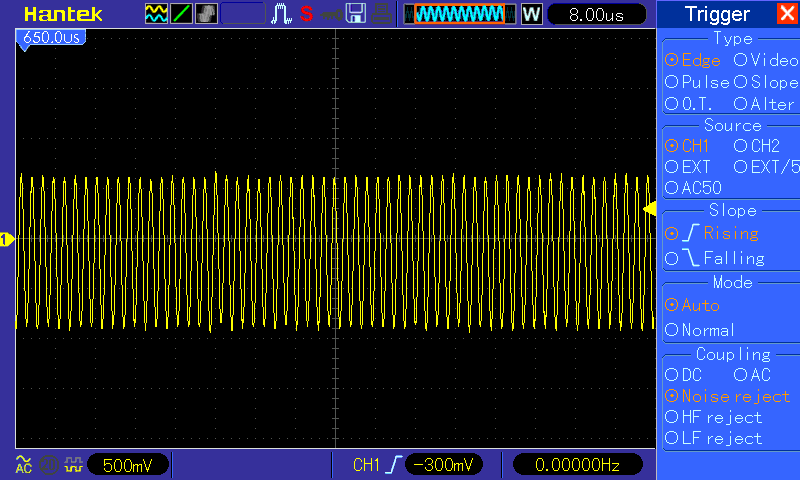 �������A�����V���b�g�͔��������Ȃ̂ł��A
���M�����キ�A���肵�Ȃ��B
�܂��A�ۑ�ł͂���B
-----------------------------
AGC��GC��H�����̏ꍇ�A
�ȑO�̂�ATT�p��Di�ł���1SV80���g���Ă����B
�������AATT�p��T���̂��A���Ȃ̂ŁA�A���G�N�ő����邩�H
�Ƃ��v�������ǁA
����Di�ׂ�ɁA���g�AATT�A�X�C�b�`���O�p�r�B
�ڍ��ԗe�ʂ�0.3pF�ƂƂĂ��������B�ł���i��50mA������B
���������ƁA���Ȃ��Ƃ�����g�ł́A1N4148�ł��\�ȋC������B
�����āADi��2����Ŏg���Ă������A�������Ă�����Ȋ����ł���B������i�A�v4���g���������ȁH
���̏ꍇ�A�d���̓�����o���̃��[�h��R��100�����A�܂�50���ɂȂ�悤�Ȕz�����邱�Ƃ��邪�A
�܂��A�����܂ō����g�ł��Ȃ��̂ŁA�ǂ����邩�ƁA�C���_�N�^��ʂ������g�̃��X�����Ȃ��Ƃ����v���ꉞ���Ă���B
�������A�����V���b�g�͔��������Ȃ̂ł��A
���M�����キ�A���肵�Ȃ��B
�܂��A�ۑ�ł͂���B
-----------------------------
AGC��GC��H�����̏ꍇ�A
�ȑO�̂�ATT�p��Di�ł���1SV80���g���Ă����B
�������AATT�p��T���̂��A���Ȃ̂ŁA�A���G�N�ő����邩�H
�Ƃ��v�������ǁA
����Di�ׂ�ɁA���g�AATT�A�X�C�b�`���O�p�r�B
�ڍ��ԗe�ʂ�0.3pF�ƂƂĂ��������B�ł���i��50mA������B
���������ƁA���Ȃ��Ƃ�����g�ł́A1N4148�ł��\�ȋC������B
�����āADi��2����Ŏg���Ă������A�������Ă�����Ȋ����ł���B������i�A�v4���g���������ȁH
���̏ꍇ�A�d���̓�����o���̃��[�h��R��100�����A�܂�50���ɂȂ�悤�Ȕz�����邱�Ƃ��邪�A
�܂��A�����܂ō����g�ł��Ȃ��̂ŁA�ǂ����邩�ƁA�C���_�N�^��ʂ������g�̃��X�����Ȃ��Ƃ����v���ꉞ���Ă���B
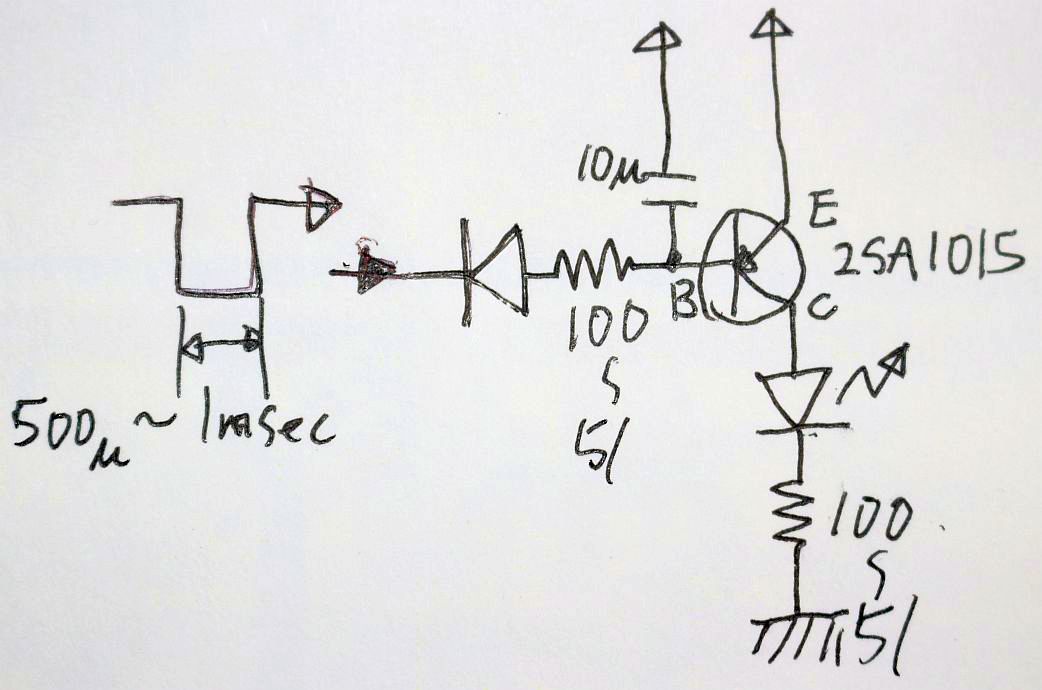 LED�ȊO�ɂ́A�u�U�[�Ƃ��A�����[�Ƃ����g����B
�ȑO�̓^�C�}�[��555�����b�`�_�E�������Ďg���Ă������A������̕����ʔ������B
�ŏI�I�ɂ́u�}�C�R���v���ȁH
�ԊO������W���[���Ń`�F�b�N�B
����m�F����
�E��̃z���_�[�ɂ͂߂�LD���W���[�����甭���B
532nm���[�U�[�����ǁA�����̂����邯�ǁA�ǂ����ԊO�X�y�N�g�����o���Ă�̂��Z���B
�������AFET�̃h���C�u�ɃQ�[�g�h���C�o�[��K�v�Ƃ���̂ŁA���̂悤�ȍ��o�͂ɂ����č����ł̉����͓���̂����m��Ȃ��B
�܂��A�ԐFLD�ŁA�̖����V�O�i���Ȃ�Δ䂪�ڗ������B
������̓���́A������Ɛ����o���ăL�����G�̕t�����A�N��������莞�ԓ|��邩�A�U��q���A�i�K�I�ɉ��悤�ȍ\�����C�C���ȁ[�H�ƁB
(�����ɏ�}�̍���ɂ���V�O�i��������Ɖ������ʼn����キ�Ă������������̔��肪���ĉ��闘�����B)
LED�ȊO�ɂ́A�u�U�[�Ƃ��A�����[�Ƃ����g����B
�ȑO�̓^�C�}�[��555�����b�`�_�E�������Ďg���Ă������A������̕����ʔ������B
�ŏI�I�ɂ́u�}�C�R���v���ȁH
�ԊO������W���[���Ń`�F�b�N�B
����m�F����
�E��̃z���_�[�ɂ͂߂�LD���W���[�����甭���B
532nm���[�U�[�����ǁA�����̂����邯�ǁA�ǂ����ԊO�X�y�N�g�����o���Ă�̂��Z���B
�������AFET�̃h���C�u�ɃQ�[�g�h���C�o�[��K�v�Ƃ���̂ŁA���̂悤�ȍ��o�͂ɂ����č����ł̉����͓���̂����m��Ȃ��B
�܂��A�ԐFLD�ŁA�̖����V�O�i���Ȃ�Δ䂪�ڗ������B
������̓���́A������Ɛ����o���ăL�����G�̕t�����A�N��������莞�ԓ|��邩�A�U��q���A�i�K�I�ɉ��悤�ȍ\�����C�C���ȁ[�H�ƁB
(�����ɏ�}�̍���ɂ���V�O�i��������Ɖ������ʼn����キ�Ă������������̔��肪���ĉ��闘�����B)
 ���ɏd���t���ăL�����̏㉺�͈ێ��������@�����邾�낤�Ǝv���B
�������ɂ����ˉ�(��)���~�����Ƃ������ǁA�ƂȂ�ƁA���������}�C�R����g�ݍ��ނ��ƂɂȂ�ˁB
�e�͏e�g�ȊO�R���p�N�g�ɂ��������A�������Z�߂ɂ������g�R�B�d�������肩����ƁA�A���ɖ�肪�o��B
��̔����͂��Ă���̂ł���ōX�Ƀ`�F�b�N�B�B
���ɏd���t���ăL�����̏㉺�͈ێ��������@�����邾�낤�Ǝv���B
�������ɂ����ˉ�(��)���~�����Ƃ������ǁA�ƂȂ�ƁA���������}�C�R����g�ݍ��ނ��ƂɂȂ�ˁB
�e�͏e�g�ȊO�R���p�N�g�ɂ��������A�������Z�߂ɂ������g�R�B�d�������肩����ƁA�A���ɖ�肪�o��B
��̔����͂��Ă���̂ł���ōX�Ƀ`�F�b�N�B�B
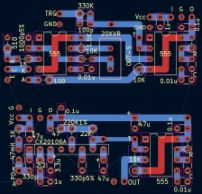 ���̉�H�ł̎�����́A�Â��uCX20106A�v��p���āA�����ɂ��g����d�l�����A�ԊO�p�ł����[�U�[�ɔ������邩��ǂ����������ǂ����ȁH�����̓f���ƃL�b�g�ňقȂ�B
���̏ꍇ�́A555�ȃ^�C�}�[���쓮���Ă��邯�ǁB�B
���Ɂu�}�C�R���v��t����K�v������B����ƁALD�d�l�Ȃ�A�U�d�̑��w������BPF���v�邩���B
���[�U�[�Ȃ�o�͂������Ŏ�ߏœ_��ς������650nm��LD���W���[�����C�C�Ǝv���Ă���B
�Ȃ�ɂ���A���[�U�[�̓V�r�A�Ȕ���ɂȂ�̂ŁA��X�̖ڕW�ɂƎv���Ă���B
���̉�H�ł̎�����́A�Â��uCX20106A�v��p���āA�����ɂ��g����d�l�����A�ԊO�p�ł����[�U�[�ɔ������邩��ǂ����������ǂ����ȁH�����̓f���ƃL�b�g�ňقȂ�B
���̏ꍇ�́A555�ȃ^�C�}�[���쓮���Ă��邯�ǁB�B
���Ɂu�}�C�R���v��t����K�v������B����ƁALD�d�l�Ȃ�A�U�d�̑��w������BPF���v�邩���B
���[�U�[�Ȃ�o�͂������Ŏ�ߏœ_��ς������650nm��LD���W���[�����C�C�Ǝv���Ă���B
�Ȃ�ɂ���A���[�U�[�̓V�r�A�Ȕ���ɂȂ�̂ŁA��X�̖ڕW�ɂƎv���Ă���B
 �|�|�|�|�|�|�|
�����H�ւ̓��́�
�ŏ���LED�����̂́A���̏o�����i��悤�ȊȈՌ^�ŗǂ��Ǝv���B
LD�����̏ꍇ�́A�R�����[�^�[���������炵��1.5�`2cm���x�ɍL���点�āA�����ʃ����Y�ŕ��s���ɂ���B
�u�}�C�R���v�����́A�v���O�����̕K�v�ȃf�W�^����H�Ȃ̂ŁA�C�x���g�ŃC���X�g�S���̂�������ɂȂ�\��B
���b�N�A�b�v�ȏe�̑���̓e�L�g�[�ʼn��F���s���N�������ɓh���āA�g���K�[�Ƀ}�C�N��SW�ŃC�C���ȁH
���S�C�̉����Ƃ��H�H
�e�g�����̗����˂�������u�i��v��A���ʂ́u��������h���v����ς�������Ȃ��B
������������A�u�G�A�K���p�̑�^�m�C�Y�T�v���b�T�[�̈����v���g���邩���B���͍��F�X�|���W�Ȃ�A���˂��ɏ��ɏo����\��������B
���ŋ������҂��Ȃ�A������͐Ȃ̔w��ɐݒu����K�v������H
���ł����āA
�E������̃f�W�^���̕����́A�������e�g�̍Đ���H�𗬗p�ł���ƃC�C�����BH��L�̂Ń����_���Đ��o����悤�ɂ���Ηǂ������B
�@����̃��W���[����CX20106A�Ȃǂ���A�o�͂��ʁX�ɋ쓮������Ηǂ��H (�V�O�i�����C�g�p�A�^�[�Q�b�g�p���[�^�[�쓮�p�A�����p)
�E���������́A������e�g�p��H���p�Ŕ��ˉ����o���A���S�Ƀg���K����}�C�R����38KHz�̔��U�������āA�p���[�h���C�u��Tr��H�ɂ���Ηǂ��B
�܂��A�i�K�I�Ɂ`�B
��Ր����10cmx10cm�܂Ŋi���ƌ������ƂŁA10�܂�5$�ł����A
�����������ނƃA���Ȃ̂�5���ɂ��āA
���T=0.8�`1.0mm�ɂ���A��~���傢���ȁ[�Ǝv���܂��B
�^�[�Q�b�g�̉�]�Ȃ�A
�M�����[�^�[
��I�Ԃ��ǁA130�n�Ńu���V���������肵�����m��I�Ԃ��Ƃ��d�v�B�����ł̃u���V�͂����Ƃ����Ԃɖ��ł���B
�f�W�b�g�ŁA�uLA7227�v�Ƃ����A�u����v���A���v�v�����������ǁA���g������炵�����牽���낤�ˁB
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
251101
������W���[����280�����B����284�ɂȂ�͂��B
�f�[�^�V�[�g�̈����������ĂČ����Ƃ��A
�NjLCX20106A��H�̓d�����q�����ĂȂ������̂Ŏ����B
�v���A�b�v��R���Е��ŃC�C���ȁH
�C�x���g�ł̍\�z�}�B�B
�|�|�|�|�|�|�|
�����H�ւ̓��́�
�ŏ���LED�����̂́A���̏o�����i��悤�ȊȈՌ^�ŗǂ��Ǝv���B
LD�����̏ꍇ�́A�R�����[�^�[���������炵��1.5�`2cm���x�ɍL���点�āA�����ʃ����Y�ŕ��s���ɂ���B
�u�}�C�R���v�����́A�v���O�����̕K�v�ȃf�W�^����H�Ȃ̂ŁA�C�x���g�ŃC���X�g�S���̂�������ɂȂ�\��B
���b�N�A�b�v�ȏe�̑���̓e�L�g�[�ʼn��F���s���N�������ɓh���āA�g���K�[�Ƀ}�C�N��SW�ŃC�C���ȁH
���S�C�̉����Ƃ��H�H
�e�g�����̗����˂�������u�i��v��A���ʂ́u��������h���v����ς�������Ȃ��B
������������A�u�G�A�K���p�̑�^�m�C�Y�T�v���b�T�[�̈����v���g���邩���B���͍��F�X�|���W�Ȃ�A���˂��ɏ��ɏo����\��������B
���ŋ������҂��Ȃ�A������͐Ȃ̔w��ɐݒu����K�v������H
���ł����āA
�E������̃f�W�^���̕����́A�������e�g�̍Đ���H�𗬗p�ł���ƃC�C�����BH��L�̂Ń����_���Đ��o����悤�ɂ���Ηǂ������B
�@����̃��W���[����CX20106A�Ȃǂ���A�o�͂��ʁX�ɋ쓮������Ηǂ��H (�V�O�i�����C�g�p�A�^�[�Q�b�g�p���[�^�[�쓮�p�A�����p)
�E���������́A������e�g�p��H���p�Ŕ��ˉ����o���A���S�Ƀg���K����}�C�R����38KHz�̔��U�������āA�p���[�h���C�u��Tr��H�ɂ���Ηǂ��B
�܂��A�i�K�I�Ɂ`�B
��Ր����10cmx10cm�܂Ŋi���ƌ������ƂŁA10�܂�5$�ł����A
�����������ނƃA���Ȃ̂�5���ɂ��āA
���T=0.8�`1.0mm�ɂ���A��~���傢���ȁ[�Ǝv���܂��B
�^�[�Q�b�g�̉�]�Ȃ�A
�M�����[�^�[
��I�Ԃ��ǁA130�n�Ńu���V���������肵�����m��I�Ԃ��Ƃ��d�v�B�����ł̃u���V�͂����Ƃ����Ԃɖ��ł���B
�f�W�b�g�ŁA�uLA7227�v�Ƃ����A�u����v���A���v�v�����������ǁA���g������炵�����牽���낤�ˁB
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
251101
������W���[����280�����B����284�ɂȂ�͂��B
�f�[�^�V�[�g�̈����������ĂČ����Ƃ��A
�NjLCX20106A��H�̓d�����q�����ĂȂ������̂Ŏ����B
�v���A�b�v��R���Е��ŃC�C���ȁH
�C�x���g�ł̍\�z�}�B�B
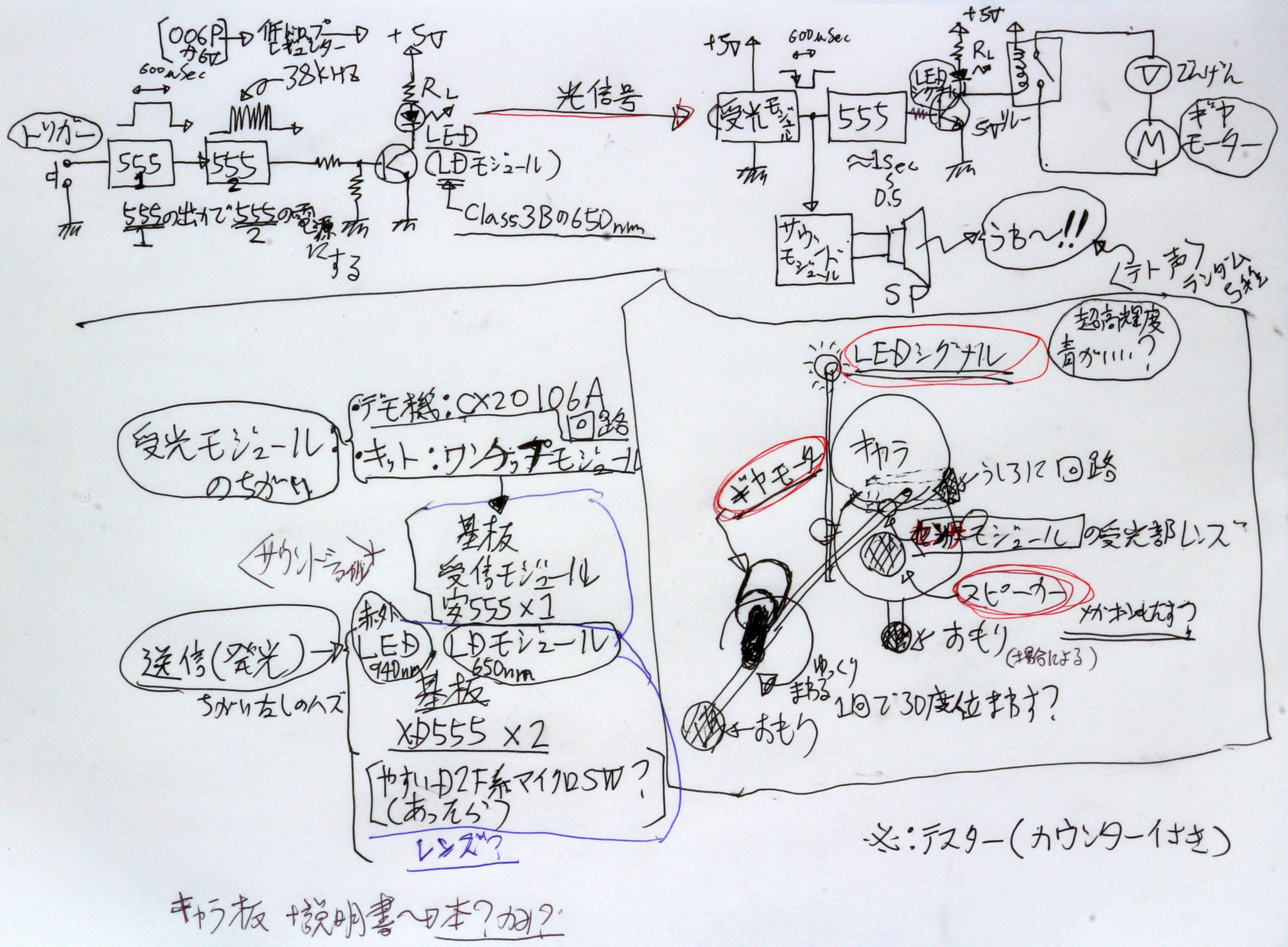 �E�����������̐��͎������������A�L�b�g�ɂ͊g���p�̐�����������ɓ���āA�������Ɖ����t�@�C����DL���ȁH�]�T������������������{�ɁH
�E�������[�U�[�͉����̓��ɂ��ł��C�C���ȁ[�ƁA
�E�ˌ��I�ɃL�����͓������ĉ������A�ꍇ�ɂ���ẮA�܂������Ă��̂ɂ�������̂ōl���˂B
(�^�[�Q�b�g��ǂ������Ȃ��猂�ƌl�I�ɂ��Ȃ萷��オ��Ǝv����B)
���o�C��BATT���d��Ȃǂɂ��ăL������������ɂ��Ă���肪���邱�ƂɋC�������B
�M�����[�^�[�����A�������ɌŒ肪�C�C�����B
����Ȃ��ƁA�ϗ��Ԃ̏�Ԃł́A�P�[�u�������܂�B
����ăL�����͓|�����Ă��܂��Ă��ǂ���������Ȃ��H�H
���Ɣ��������̋����I�ȓ��̓����A��������ɓ����̂��e���ȁB�����t�F���g���C�P�邩���B
CX20106A��H�̕��́A�m�C�Y�ɂ��\���B���삪���܂��s���Ă�̂ɉ����Ȃ��B
���Ȃ݂ɁA���͂�C��GND�ɗ��Ƃ��ƐÂ܂�B
���ƁA�t�H�gDi�̋t�o�C�A�X�t�߂ɁA�d��3�A470��F��OS�R���A��ʐσZ���~�b�N�A�ϑw�Z���~�b�N2�A�ƎO�d�ȏ�Ƀm�C�Y����������Ă��B�K�v�������Čp�������Ă�����̂�����A���ꂪ�Z�����ȁc�H
�܂�d���g�m�C�Y�Ɠd���̍��킹�Z�̍U�����ȁ`�A�A
����ł́A�\�肪�i�܂Ȃ��̂ŁA
CX20106A��H�͗l�q���ɂ��āA�L�b�g�i�Ɏg�����W���[���̕��ł���Ă݂邱�ƂɂƂ肠������ւ��悤�Ǝv�����B
��̐v�Ɉڂ肽���B
�C������̂̓��W���[���������[�ړ_��[�^�[�̐����痣�����ƁBSBD��m�C�Y�A�u�\�[�u�f�q�Ȃǎg���B
��͍Œ�10cm�����A5cm�ɂ������B
�܂��A���W���[���͊���烊�[�h���ŎO�҂ݏ�Ԃɉ������o����B
���ɂ́A�t�H�gMOS�����[�͂ǂ����ȁH�Ǝv�����B�������Ă݂��猋�\�����B���ۂ�������肾����f�q���̂i�őg�����C�C�����B
�Ƃ������ƂŁA�܂��́AN�^MOS-FET�̋쓮�ɂ��Ă݂悤���Ǝv���B
���[�^�[�͕ʓd�r�œ����������B1.5�`3.3V���x���Ŋ��d�r���C�C�����B
�M���͂�����x�x���n�C�g���N�ŊO�͂ɑ��ď�v�Ȃ̂��C�C���Ǝv���Ă���B
���[�^�[�g���ꍇ�́A�����V�[���h����Ă郂�W���[�����g�p����̂��e���ȁH
��̍\�z�́A�摜������ƃC�C�Ǝv���B��{�ACX20106A��H�̈ꕔ�������Ċg�����Ă����Ηǂ����낤�B
�����Đ}�B
�E�����������̐��͎������������A�L�b�g�ɂ͊g���p�̐�����������ɓ���āA�������Ɖ����t�@�C����DL���ȁH�]�T������������������{�ɁH
�E�������[�U�[�͉����̓��ɂ��ł��C�C���ȁ[�ƁA
�E�ˌ��I�ɃL�����͓������ĉ������A�ꍇ�ɂ���ẮA�܂������Ă��̂ɂ�������̂ōl���˂B
(�^�[�Q�b�g��ǂ������Ȃ��猂�ƌl�I�ɂ��Ȃ萷��オ��Ǝv����B)
���o�C��BATT���d��Ȃǂɂ��ăL������������ɂ��Ă���肪���邱�ƂɋC�������B
�M�����[�^�[�����A�������ɌŒ肪�C�C�����B
����Ȃ��ƁA�ϗ��Ԃ̏�Ԃł́A�P�[�u�������܂�B
����ăL�����͓|�����Ă��܂��Ă��ǂ���������Ȃ��H�H
���Ɣ��������̋����I�ȓ��̓����A��������ɓ����̂��e���ȁB�����t�F���g���C�P�邩���B
CX20106A��H�̕��́A�m�C�Y�ɂ��\���B���삪���܂��s���Ă�̂ɉ����Ȃ��B
���Ȃ݂ɁA���͂�C��GND�ɗ��Ƃ��ƐÂ܂�B
���ƁA�t�H�gDi�̋t�o�C�A�X�t�߂ɁA�d��3�A470��F��OS�R���A��ʐσZ���~�b�N�A�ϑw�Z���~�b�N2�A�ƎO�d�ȏ�Ƀm�C�Y����������Ă��B�K�v�������Čp�������Ă�����̂�����A���ꂪ�Z�����ȁc�H
�܂�d���g�m�C�Y�Ɠd���̍��킹�Z�̍U�����ȁ`�A�A
����ł́A�\�肪�i�܂Ȃ��̂ŁA
CX20106A��H�͗l�q���ɂ��āA�L�b�g�i�Ɏg�����W���[���̕��ł���Ă݂邱�ƂɂƂ肠������ւ��悤�Ǝv�����B
��̐v�Ɉڂ肽���B
�C������̂̓��W���[���������[�ړ_��[�^�[�̐����痣�����ƁBSBD��m�C�Y�A�u�\�[�u�f�q�Ȃǎg���B
��͍Œ�10cm�����A5cm�ɂ������B
�܂��A���W���[���͊���烊�[�h���ŎO�҂ݏ�Ԃɉ������o����B
���ɂ́A�t�H�gMOS�����[�͂ǂ����ȁH�Ǝv�����B�������Ă݂��猋�\�����B���ۂ�������肾����f�q���̂i�őg�����C�C�����B
�Ƃ������ƂŁA�܂��́AN�^MOS-FET�̋쓮�ɂ��Ă݂悤���Ǝv���B
���[�^�[�͕ʓd�r�œ����������B1.5�`3.3V���x���Ŋ��d�r���C�C�����B
�M���͂�����x�x���n�C�g���N�ŊO�͂ɑ��ď�v�Ȃ̂��C�C���Ǝv���Ă���B
���[�^�[�g���ꍇ�́A�����V�[���h����Ă郂�W���[�����g�p����̂��e���ȁH
��̍\�z�́A�摜������ƃC�C�Ǝv���B��{�ACX20106A��H�̈ꕔ�������Ċg�����Ă����Ηǂ����낤�B
�����Đ}�B
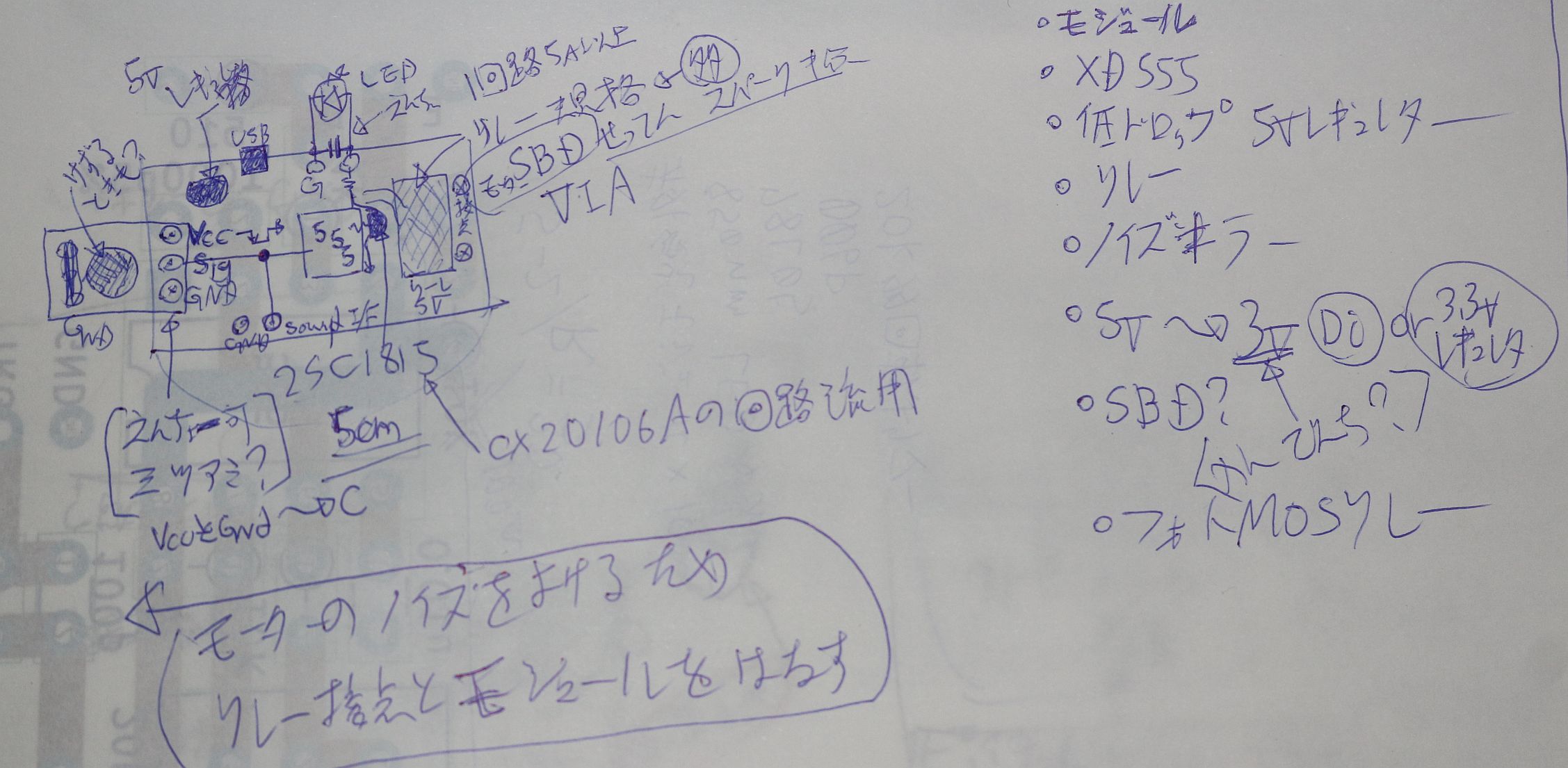 ��̍��[�ɔ�яo�Ă�̂�������W���[���B
������W���[����LED�ƂƂ��ɉ����\�B
2SC1815��N�^MOS-FET�ɕύX���邩�A�m�C�Y����B�B
�����A���͂����Ȑݔ�������A�d�g��ԊO���M������ь����Ă��邩���m��Ȃ��B
�Ȃ̂ŁA�V�[���h�ƃZ���T�[�ɂ͐M���@�̂悤�Ƀq�T�V�Ƃ��y���t�������B
�����ŁALD�ȉ����̓A�h�o���e�[�W�����B
IR�p�̎��������Y���͋Ɍ��܂ō��Ƃ��Ă��܂��X�ɗǂ������m��Ȃ��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
CX20106A��H�̕s��A��Ȍ����������I�I
�c�t�H�gDi�̋t�ڑ��B���ނ����̎���̕����A�A
�܂菇�o�C�A�X�ƂȂ�A���ʁA�����g�̊��x�������邱�ƂƂȂ�A
�t�B�[���h�m�C�Y�ɖ�������Ԃ������Ƃ����B
�����������ȃm�C�Y�Ȃ̂�C��t����c�t�o�C�A�X�̈Ӗ��������A�A�c���ˁB�ł��A�\����Ԃ��̓}�V������B�B
����Ȃō��g���Ă�CX20106A�Ȑ����Ă邩���H
�@�艺���܂Ƃ߂�ƁA
���ʊ��VIA�����Ȃ��A��������͖̂�肩�ȁH
�Ƃ��v�������A
���̓s�������đS�������ł��ʖڂŁA����́A�I���W��H�ł��������B
���M�����[�^�[��́AC���傫�߂Ȃ̂œd���̈�����H
�v���A�b�v��R���_�u���Ă�̂ŁA���l�������B
���͂�C�ŗ��Ƃ��Ζ\���͎~�܂�B
�S�P�[�X�ł͖������̖��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
251102
�m�C�Y��400KHz������̎����ŃX�p�C�N�I�Ȃ̂��r�V�r�V�ƁB
�����A�X�C�b�`���O�m�C�Y�����������痈�Ă�B
���Ƃ̓T�[�}���m�C�Y�Ƃ��n�������邩�ȁH
�Ƃ肠�����̊���ł��������āA�m�F���B
�����[�͎g�킸�AMOS-FET�ł̋쓮�ɂ��Ă݂��B
251104
�ύX
��̍��[�ɔ�яo�Ă�̂�������W���[���B
������W���[����LED�ƂƂ��ɉ����\�B
2SC1815��N�^MOS-FET�ɕύX���邩�A�m�C�Y����B�B
�����A���͂����Ȑݔ�������A�d�g��ԊO���M������ь����Ă��邩���m��Ȃ��B
�Ȃ̂ŁA�V�[���h�ƃZ���T�[�ɂ͐M���@�̂悤�Ƀq�T�V�Ƃ��y���t�������B
�����ŁALD�ȉ����̓A�h�o���e�[�W�����B
IR�p�̎��������Y���͋Ɍ��܂ō��Ƃ��Ă��܂��X�ɗǂ������m��Ȃ��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
CX20106A��H�̕s��A��Ȍ����������I�I
�c�t�H�gDi�̋t�ڑ��B���ނ����̎���̕����A�A
�܂菇�o�C�A�X�ƂȂ�A���ʁA�����g�̊��x�������邱�ƂƂȂ�A
�t�B�[���h�m�C�Y�ɖ�������Ԃ������Ƃ����B
�����������ȃm�C�Y�Ȃ̂�C��t����c�t�o�C�A�X�̈Ӗ��������A�A�c���ˁB�ł��A�\����Ԃ��̓}�V������B�B
����Ȃō��g���Ă�CX20106A�Ȑ����Ă邩���H
�@�艺���܂Ƃ߂�ƁA
���ʊ��VIA�����Ȃ��A��������͖̂�肩�ȁH
�Ƃ��v�������A
���̓s�������đS�������ł��ʖڂŁA����́A�I���W��H�ł��������B
���M�����[�^�[��́AC���傫�߂Ȃ̂œd���̈�����H
�v���A�b�v��R���_�u���Ă�̂ŁA���l�������B
���͂�C�ŗ��Ƃ��Ζ\���͎~�܂�B
�S�P�[�X�ł͖������̖��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
251102
�m�C�Y��400KHz������̎����ŃX�p�C�N�I�Ȃ̂��r�V�r�V�ƁB
�����A�X�C�b�`���O�m�C�Y�����������痈�Ă�B
���Ƃ̓T�[�}���m�C�Y�Ƃ��n�������邩�ȁH
�Ƃ肠�����̊���ł��������āA�m�F���B
�����[�͎g�킸�AMOS-FET�ł̋쓮�ɂ��Ă݂��B
251104
�ύX
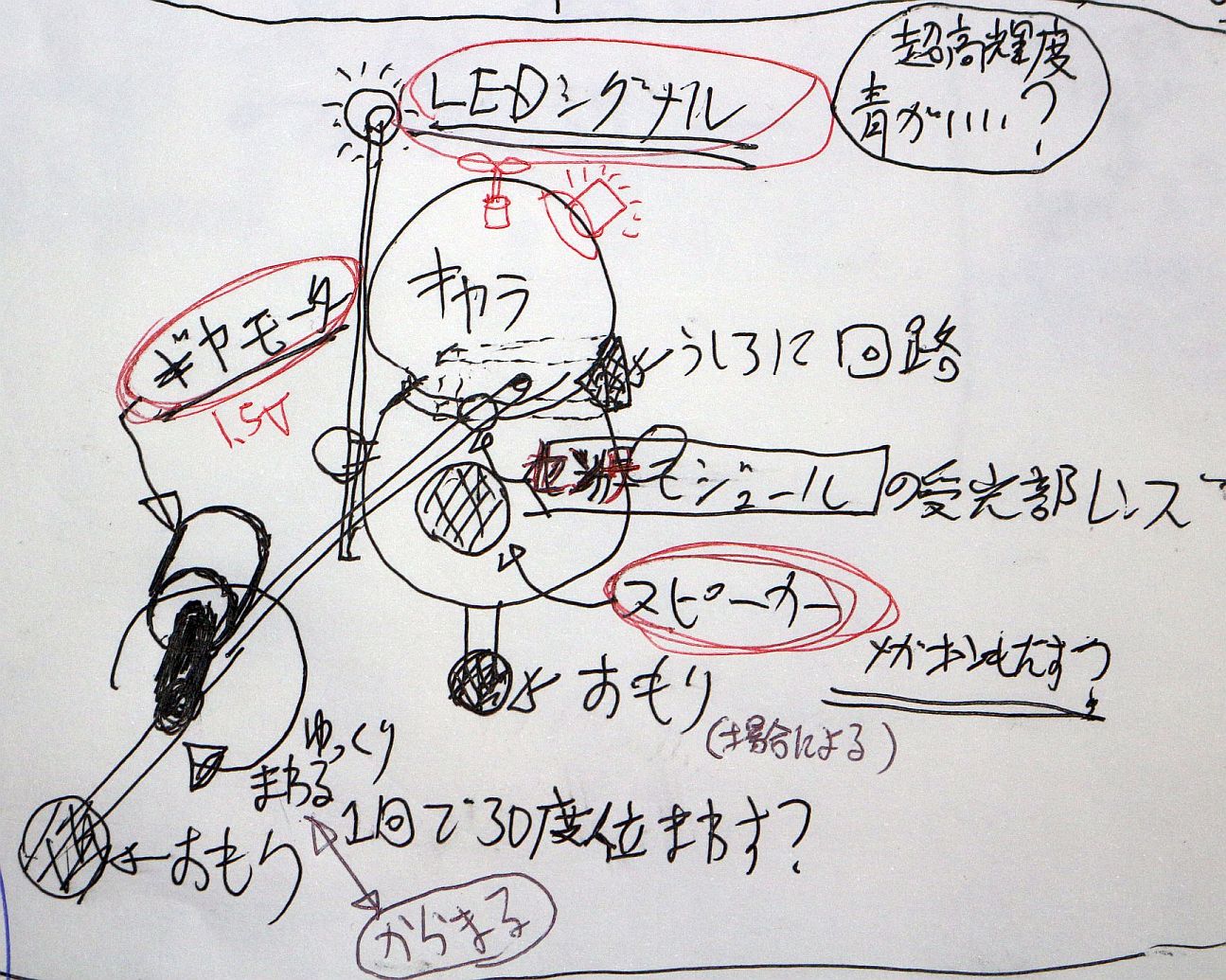 ���[�^�[�œ������������ǁ`�c�A�A
251105
555��̔�������������Ď������B
�g�`���Y��ȋ�`�ł͖������ǁA940nmLED�ł͏\�����ȁ[�ƁB
650nm���[�U�[�͂��Ȃ�V�r�A�����B
��{��H�����̂܂܂ŏo���邱�Ƃ́A
�ETr�̒�i�d�����������m�ɕύX(������R�̒ጸ)�A�x�[�X�d���p��R�̕ύX(�œK��)
�E�ԊO�̃����Y������啝�ɍ��Ƃ��āABPF+���������Y�ɕύX�B
�E���x�̍����Z���T�[���g���B
�E555�̎�ނ̕ύX�H
�E�d���d�����グ��H
251108
�����Y����藎�Ƃ����B���A����ܕω����Ȃ��B
�Œ���t�B���^�[�̌��݂�1/2�ɂȂ����̂�����A������1/4�ȉ��ɂȂ��Ă��ǂ��͂����Ƃ͎v���B�܂������Y�̏W���͑����e������Ƃ��āB
�ǂ����A�t�B���^�[�͖��������Ƃ��Ă�PIN�t�H�gDi�̊��x�t�H�gDi�͔g���ɂقڔ�Ⴕ�Ċ��x���オ��960nm���炢���s�[�N���ƌ������ƂƁA
�t�B���^�[�ŋɓx�ɕς�镔���Ƃ�����悤�����nj�҂͐��i�ɂ��B
���̓�ł��Ȃ�������[�U�[�͕s�����Ƃ��������B
�����ǁA���[�U�[�̓����Y�Ŕ�r�I�Y��Ɍ����W�߂��邩��A�r�[���̑�����������x�ێ������܂܋����͉҂��邾�낤�B
251109
������ƃ��[�U�[���������J�b�L���ƌŒ肵�ă����Y�̗L���Ŋm�F����Ɗ��x�͏オ���Ă����B
�����Y�̏W���̑��݂����邩��A4�{�Ƃ��͗v���ĂȂ��Ǝv�����ǁB
���@�Ƃ��ẮA���[�U�[�̓Y���ɑ��������ω�����̂ŁA�K�E�V�A���Ǝv���镪�z�̐���ɋ߂Â��Ă����A
�������Ȃ��Ȃ�����A������������B��r���������B
�����x�ɔ�Ⴗ����d���͓d��̓��ŗ�����ǁA�l�͂���Log�Ō��Ă邩��A���̕��@�����ł́A�Ȃ��Ȃ����̐��l���͏o���Ȃ������ʂ͏o�����B
���ƁA130�n���[�^�[�̎��������Ă݂āA�d����3V���Ƃ��Ȃ�R�~���e�[�^�[�����肩��̏Ă�������������̂ŁA1.5V���Ó����Ǝv�����B
�M���͂Ƃ肠�����A70�F1�t�߂�����Ă݂�\��Ő������������Ă�B
251111
���슮���B�m�C�Y����炸�A���Ȃ��������Ƃ��m�F����܂����B
251116
CX20106A��H�̈ꉞ�̐�����
�Z���T�[���͂�22K���݂����BJ-FET���͂Ȃ̂�������Ȃ��H
�ŁA
����ōő�Q�C���͏��������邩�������ǁA�������[�U�[�ɂ͗ǂ���������Ǝv���B
�Z���T�[�ɂ�650nm�̗U�d�̑��w����BPF��t���Ďg���Ă���B�d�˂�������Ɨ]�v�Ȍ����J�b�g�o����B
���Ƃ͓S�̃V�[���h���ȁH
���상�j���[���L�������B
LD�̃R�����[�^�[���������Y���g��Ȃ������ɕύX���B
�����d����C�p�̕������Y��LD���W���[����؍H�p�{���h�ł������Ďg���B
����̃��[�U�[�R�����[�^�[�́A�������Y���g�킸�A���v������d����C�p�̕��K���X�Ɍ������A
LD���W���[���̃t�H�[�J�X�����O����߂��ނ��ƂōL���点330mm�Ε������Y�ŕ��s���ɂ�������ɕς��܂����B
�������ŁA�X���[�Y�Ƀr�[���a��C�ӃT�C�Y�ɒ����ł��邱�ƂɂȂ�܂����B
251127
��H�͊��x���蒼���A�A���Ƀh���C�u��H������̕��̎���͑啝�ɉ��P���ꂽ�B
���0.8����0.6mm�ł��g�������C�y�Ɏ��݂ɐؒf�o����̂��ǂ����������Ɩ����Ă鎟��B
�����A���x���\�����Ǝv�����B�B
���F�̊�Ȃ獕�̕����������悤�ȋC�����Ă邪�@���ɁH
�O��A���ŏo���Ă��܂����̂ŁA�\�R�͂�����g���Ȃ���ǂ���̗p�Ƃ������g�R�B
LD�R�����[�^�[�����\��������悤�ŁA
���Ƃ́A��]�^�[�Q�b�g�Ƃ��A
���������A�قځA�o���Ă���B
���Ƃ́A�T�E���h�Ɖ�]���̎��삩�ȁB�Ƃ肠�����A�����ɂȂ����̂ŁA�����ɂȂ�܂��A�A
251128
����͂����B
���F���͗ǂ��������A���W�X�g�ɏ��������Ă��������ڗ����Ȃ��Ȃ�B
���[�^�[�œ������������ǁ`�c�A�A
251105
555��̔�������������Ď������B
�g�`���Y��ȋ�`�ł͖������ǁA940nmLED�ł͏\�����ȁ[�ƁB
650nm���[�U�[�͂��Ȃ�V�r�A�����B
��{��H�����̂܂܂ŏo���邱�Ƃ́A
�ETr�̒�i�d�����������m�ɕύX(������R�̒ጸ)�A�x�[�X�d���p��R�̕ύX(�œK��)
�E�ԊO�̃����Y������啝�ɍ��Ƃ��āABPF+���������Y�ɕύX�B
�E���x�̍����Z���T�[���g���B
�E555�̎�ނ̕ύX�H
�E�d���d�����グ��H
251108
�����Y����藎�Ƃ����B���A����ܕω����Ȃ��B
�Œ���t�B���^�[�̌��݂�1/2�ɂȂ����̂�����A������1/4�ȉ��ɂȂ��Ă��ǂ��͂����Ƃ͎v���B�܂������Y�̏W���͑����e������Ƃ��āB
�ǂ����A�t�B���^�[�͖��������Ƃ��Ă�PIN�t�H�gDi�̊��x�t�H�gDi�͔g���ɂقڔ�Ⴕ�Ċ��x���オ��960nm���炢���s�[�N���ƌ������ƂƁA
�t�B���^�[�ŋɓx�ɕς�镔���Ƃ�����悤�����nj�҂͐��i�ɂ��B
���̓�ł��Ȃ�������[�U�[�͕s�����Ƃ��������B
�����ǁA���[�U�[�̓����Y�Ŕ�r�I�Y��Ɍ����W�߂��邩��A�r�[���̑�����������x�ێ������܂܋����͉҂��邾�낤�B
251109
������ƃ��[�U�[���������J�b�L���ƌŒ肵�ă����Y�̗L���Ŋm�F����Ɗ��x�͏オ���Ă����B
�����Y�̏W���̑��݂����邩��A4�{�Ƃ��͗v���ĂȂ��Ǝv�����ǁB
���@�Ƃ��ẮA���[�U�[�̓Y���ɑ��������ω�����̂ŁA�K�E�V�A���Ǝv���镪�z�̐���ɋ߂Â��Ă����A
�������Ȃ��Ȃ�����A������������B��r���������B
�����x�ɔ�Ⴗ����d���͓d��̓��ŗ�����ǁA�l�͂���Log�Ō��Ă邩��A���̕��@�����ł́A�Ȃ��Ȃ����̐��l���͏o���Ȃ������ʂ͏o�����B
���ƁA130�n���[�^�[�̎��������Ă݂āA�d����3V���Ƃ��Ȃ�R�~���e�[�^�[�����肩��̏Ă�������������̂ŁA1.5V���Ó����Ǝv�����B
�M���͂Ƃ肠�����A70�F1�t�߂�����Ă݂�\��Ő������������Ă�B
251111
���슮���B�m�C�Y����炸�A���Ȃ��������Ƃ��m�F����܂����B
251116
CX20106A��H�̈ꉞ�̐�����
�Z���T�[���͂�22K���݂����BJ-FET���͂Ȃ̂�������Ȃ��H
�ŁA
����ōő�Q�C���͏��������邩�������ǁA�������[�U�[�ɂ͗ǂ���������Ǝv���B
�Z���T�[�ɂ�650nm�̗U�d�̑��w����BPF��t���Ďg���Ă���B�d�˂�������Ɨ]�v�Ȍ����J�b�g�o����B
���Ƃ͓S�̃V�[���h���ȁH
���상�j���[���L�������B
LD�̃R�����[�^�[���������Y���g��Ȃ������ɕύX���B
�����d����C�p�̕������Y��LD���W���[����؍H�p�{���h�ł������Ďg���B
����̃��[�U�[�R�����[�^�[�́A�������Y���g�킸�A���v������d����C�p�̕��K���X�Ɍ������A
LD���W���[���̃t�H�[�J�X�����O����߂��ނ��ƂōL���点330mm�Ε������Y�ŕ��s���ɂ�������ɕς��܂����B
�������ŁA�X���[�Y�Ƀr�[���a��C�ӃT�C�Y�ɒ����ł��邱�ƂɂȂ�܂����B
251127
��H�͊��x���蒼���A�A���Ƀh���C�u��H������̕��̎���͑啝�ɉ��P���ꂽ�B
���0.8����0.6mm�ł��g�������C�y�Ɏ��݂ɐؒf�o����̂��ǂ����������Ɩ����Ă鎟��B
�����A���x���\�����Ǝv�����B�B
���F�̊�Ȃ獕�̕����������悤�ȋC�����Ă邪�@���ɁH
�O��A���ŏo���Ă��܂����̂ŁA�\�R�͂�����g���Ȃ���ǂ���̗p�Ƃ������g�R�B
LD�R�����[�^�[�����\��������悤�ŁA
���Ƃ́A��]�^�[�Q�b�g�Ƃ��A
���������A�قځA�o���Ă���B
���Ƃ́A�T�E���h�Ɖ�]���̎��삩�ȁB�Ƃ肠�����A�����ɂȂ����̂ŁA�����ɂȂ�܂��A�A
251128
����͂����B
���F���͗ǂ��������A���W�X�g�ɏ��������Ă��������ڗ����Ȃ��Ȃ�B
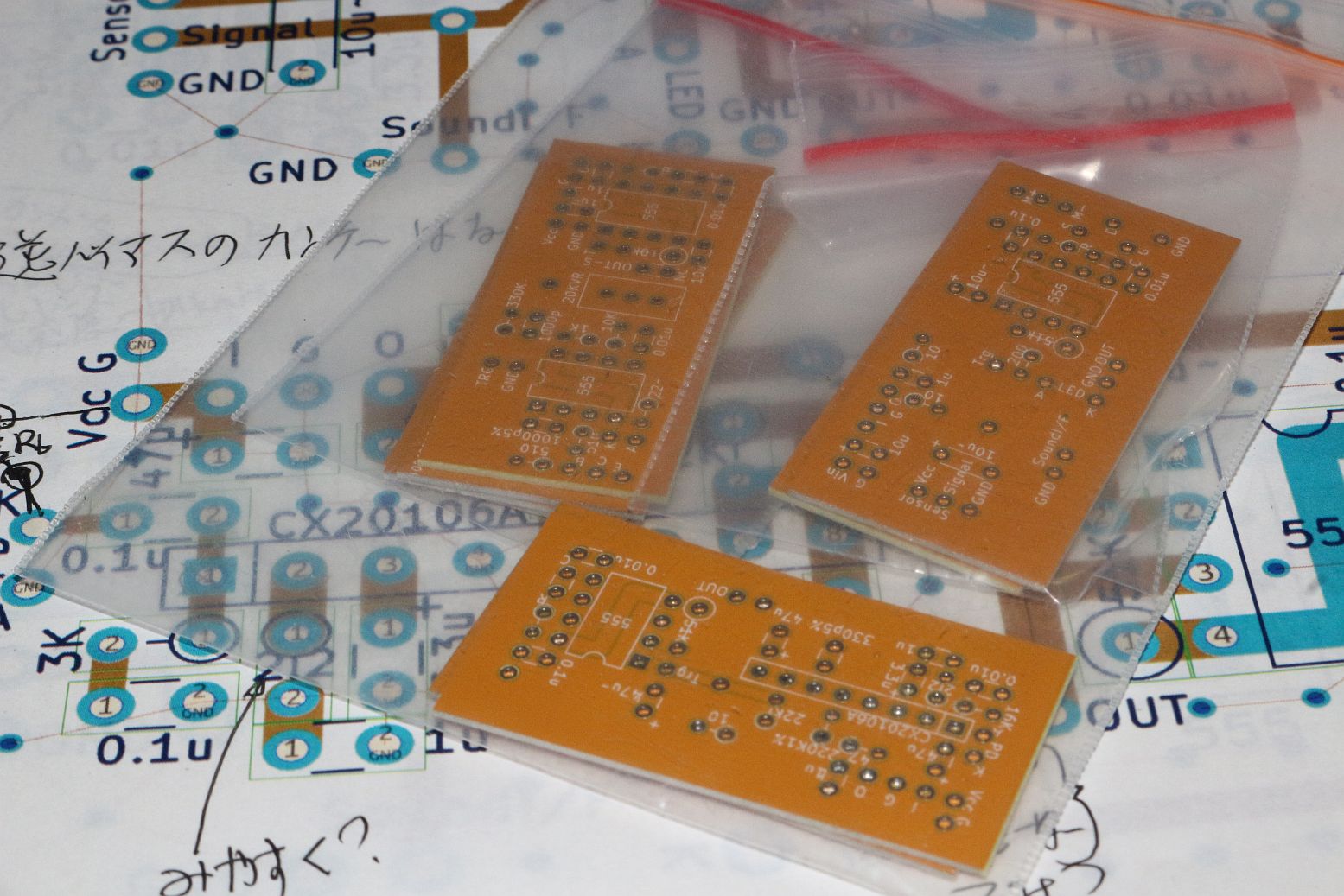 251130
���Â��Ȃ��Ă����g�R�Ń`�F�b�N�B
750m���傢��̊��������ǁA����ł�̂͂����瑤�̑��K���X�̉e��������݂����B
�܂��A�œ_�����S�ɂ͓˂��l�߂Ă��Ȃ����炱��Ȋ����ŁA�o�͂͐\�����Ȃ��Ǝv���B
251130
���Â��Ȃ��Ă����g�R�Ń`�F�b�N�B
750m���傢��̊��������ǁA����ł�̂͂����瑤�̑��K���X�̉e��������݂����B
�܂��A�œ_�����S�ɂ͓˂��l�߂Ă��Ȃ����炱��Ȋ����ŁA�o�͂͐\�����Ȃ��Ǝv���B
 �B�e�́A300mm�����Y�ŁAISO200�AF22�A10Sec�̂��g���~���O�B
251207
�ϗ��Ԏ�(���[���b�g��)�́A�ʔ����������ǁA�����_�A���x�⎿�ʁA�ėp�����ǂ��Ȃ��B
�C���C���ƕ����I�ɂ��쐬�I�ɂ��d�����A����̃f���ɂ͌����Ȃ��Ǝv���܂����B
�g�s�����ǂ��A�ꏊ�����Ȃ����āA�ȒP�ȃ��m���ǂ����ȁH
�e�̕��������ȃ^�C�v���v�������̂Ō��I���Ȃ��ƁB
���ɔ�r�I�Z��������Ȃ�A�Ε������Y�≚�ʃ����Y�������a�Z�œ_�������\�B
�܂��A�d������o�͂̓d�͂𑽏������A���ˌ����x���i�[�t�����A���S�ɂ��Ȃ���A�ׂ��r�[�����̂܂܂Ńn���h�K���ɑg�ݍ��ނȂǂ̒��V���v���ȈĂ��B
���̌�A
�������[�U�[���ɑ���t�B���^�[�̋����ȂǂɂāA38KHz�ɂāA�����R����C���o�[�^�[�Ɩ��ō쓮���Ă��܂�Ȃ��������l���Ă����B
�܂��A���w�t�B���^�[���g�p����Ή\���Ǝv���Ɏ���B��M���́A���W���[���ł�CX20106A��H�ł��C�P��͂��B
251219
��͂�ALD�𐔏\MHz�ɏグ�Ď�����������삷����@���l�����B
���M�����͏o���Ă���A���[�U�[�̋����ɂ���āA���x�͉����āAAGC��H�͔r���ALC����HPF�ɂ��\���ɂȂ�͂��B
251226
��y���ƁA���i���B�Ȃǂ̓s������12MHz��FCZ�R�C�����g�����m�Ƃ��܂����B
����́A38KHz�����܂��s���Ă���̗\��ł��B
���C�x���g�̏��T�C�g��
https://clamp-cc.sakura.ne.jp/event/Tact.html
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
#�����e#�����ˌ�#�ˌ�#���[�U�[#���f���K��#�r�[�����C�t��#���[�U�[����#�����̃��[�U�[#��#�}�C�N���X�C�b�`
#�d�q�H��
�����܂Ƃ߁���
RC�w���𑀏c���œ������B
http://clamp-cc.sakura.ne.jp/soujyuukan.html
RC�w���̎p������ɂ��āA
http://clamp-cc.sakura.ne.jp/Seigyo-R.html
�w���Ȃǂ̎�Ƀ��J�j�J������ɂ��āA
http://clamp-cc.sakura.ne.jp/heli-r001.html
���G�A�R���`���[���i�b�v�H
http://clamp-cc.sakura.ne.jp/Aircon-S.html
���z�d�r�ƁA���d�r�̍Đ��A����
http://clamp-cc.sakura.ne.jp/S-N-J.html
�w�b�h�t�H��AMP�Ȃ�
http://clamp-cc.sakura.ne.jp/tone-k-001.html
�����e�̐���
http://clamp-cc.sakura.ne.jp/kousenjyu.html
�����g��EMS�̐���
http://clamp-cc.sakura.ne.jp/M-EMS.html
http://clamp-cc.sakura.ne.jp/rc-gas001.html
(C)�F Presented by captor�������
http://clamp-cc.sakura.ne.jp/db-g-mokuji.html
����
�B�e�́A300mm�����Y�ŁAISO200�AF22�A10Sec�̂��g���~���O�B
251207
�ϗ��Ԏ�(���[���b�g��)�́A�ʔ����������ǁA�����_�A���x�⎿�ʁA�ėp�����ǂ��Ȃ��B
�C���C���ƕ����I�ɂ��쐬�I�ɂ��d�����A����̃f���ɂ͌����Ȃ��Ǝv���܂����B
�g�s�����ǂ��A�ꏊ�����Ȃ����āA�ȒP�ȃ��m���ǂ����ȁH
�e�̕��������ȃ^�C�v���v�������̂Ō��I���Ȃ��ƁB
���ɔ�r�I�Z��������Ȃ�A�Ε������Y�≚�ʃ����Y�������a�Z�œ_�������\�B
�܂��A�d������o�͂̓d�͂𑽏������A���ˌ����x���i�[�t�����A���S�ɂ��Ȃ���A�ׂ��r�[�����̂܂܂Ńn���h�K���ɑg�ݍ��ނȂǂ̒��V���v���ȈĂ��B
���̌�A
�������[�U�[���ɑ���t�B���^�[�̋����ȂǂɂāA38KHz�ɂāA�����R����C���o�[�^�[�Ɩ��ō쓮���Ă��܂�Ȃ��������l���Ă����B
�܂��A���w�t�B���^�[���g�p����Ή\���Ǝv���Ɏ���B��M���́A���W���[���ł�CX20106A��H�ł��C�P��͂��B
251219
��͂�ALD�𐔏\MHz�ɏグ�Ď�����������삷����@���l�����B
���M�����͏o���Ă���A���[�U�[�̋����ɂ���āA���x�͉����āAAGC��H�͔r���ALC����HPF�ɂ��\���ɂȂ�͂��B
251226
��y���ƁA���i���B�Ȃǂ̓s������12MHz��FCZ�R�C�����g�����m�Ƃ��܂����B
����́A38KHz�����܂��s���Ă���̗\��ł��B
���C�x���g�̏��T�C�g��
https://clamp-cc.sakura.ne.jp/event/Tact.html
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
#�����e#�����ˌ�#�ˌ�#���[�U�[#���f���K��#�r�[�����C�t��#���[�U�[����#�����̃��[�U�[#��#�}�C�N���X�C�b�`
#�d�q�H��
�����܂Ƃ߁���
RC�w���𑀏c���œ������B
http://clamp-cc.sakura.ne.jp/soujyuukan.html
RC�w���̎p������ɂ��āA
http://clamp-cc.sakura.ne.jp/Seigyo-R.html
�w���Ȃǂ̎�Ƀ��J�j�J������ɂ��āA
http://clamp-cc.sakura.ne.jp/heli-r001.html
���G�A�R���`���[���i�b�v�H
http://clamp-cc.sakura.ne.jp/Aircon-S.html
���z�d�r�ƁA���d�r�̍Đ��A����
http://clamp-cc.sakura.ne.jp/S-N-J.html
�w�b�h�t�H��AMP�Ȃ�
http://clamp-cc.sakura.ne.jp/tone-k-001.html
�����e�̐���
http://clamp-cc.sakura.ne.jp/kousenjyu.html
�����g��EMS�̐���
http://clamp-cc.sakura.ne.jp/M-EMS.html
http://clamp-cc.sakura.ne.jp/rc-gas001.html
(C)�F Presented by captor�������
http://clamp-cc.sakura.ne.jp/db-g-mokuji.html
����